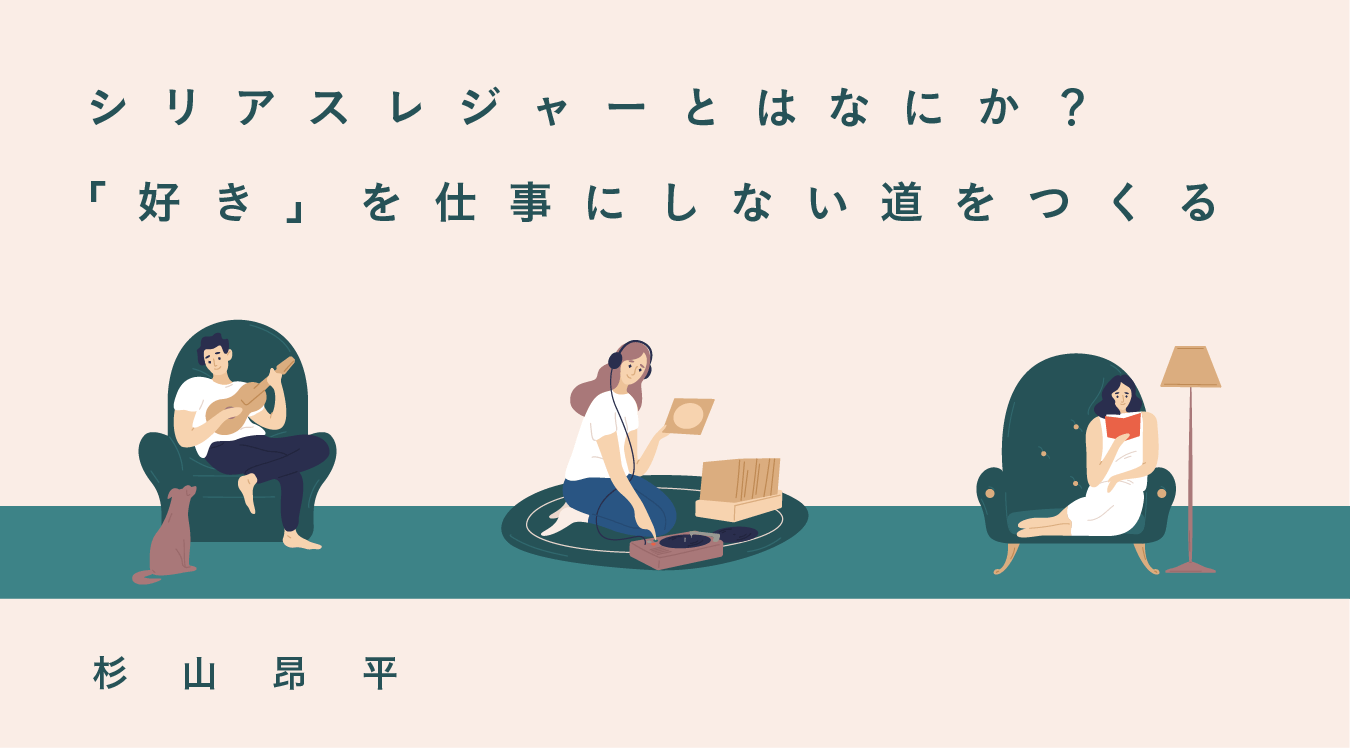「好きを仕事に」。こんな言葉を見かけることも、だいぶ増えましたよね。YouTubeやSNSなど、「好きなこと」を発信し、お金に変えていくためのプラットフォームもたくさんあります。
しかし、本当に「仕事に」するだけが正解なのでしょうか? あえて仕事にせず、「趣味」として真剣に取り組む道だってあるはずです。休息や気晴らしではなく、自分のやりたいことを実現するために行われる趣味である「シリアスレジャー」について、余暇研究と学習科学の学際的な立場から趣味を研究している杉山昂平さんに寄稿してもらいました。趣味としてやっていく選択肢の意味から、楽しみ方の学習や学習環境デザインの必要性まで、シリアスレジャーの現在地と可能性に迫ります。
端的に言うとね。
私は余暇研究と学習科学の学際的な立場から趣味を研究している。余暇研究と学習科学、どちらの分野も読者の方にはあまり馴染みがないかもしれない。まして両者を越境して「趣味」を研究するとなると、一見したところでは何をするのか想像がつかないだろう。
本稿では、そのような趣味研究とは何を考える試みであるのか、試論的に紹介したい。余暇研究と学習科学の考え方は、趣味のいかなる側面に光を当てるのか。それによって、趣味に関するいかなる問いが引き出されるのか。これらを論じることで、なぜ私は趣味研究が面白く、また必要だと考えているのか、その一端をお伝えできればと思う。
その際に鍵となるのが、余暇研究における「シリアスレジャー」という概念である。私が「趣味」と言うとき、それは「シリアスレジャーとしての趣味」を指している。今年の4月に宮入恭平氏と出版した書籍『「趣味に生きる」の文化論──シリアスレジャーから考える』(ナカニシヤ出版)でも、副題としてこの言葉を用いた。まずはシリアスレジャーの意味内容を紹介し、そこから論点を敷衍していこう。
シリアスレジャーとは何か
シリアスレジャーは、趣味の「趣味らしさ」が一体どこにあるのかを教えてくれる概念である。
もともと、カナダの余暇研究者ロバート・ステビンスが1982年の論文“Serious Leisure: A Conceptual Statement”において提唱した。アマチュアや趣味人(ホビイスト)、ボランティアといった人々の活動を表すための概念である。これらの活動は余暇に行われるが、労働のためのエネルギーを回復・再創造(re-creation = レクリエーション)するための休息や気晴らしではない。むしろ、自分のやりたいことを実現するために行われる活動である。そのような特徴を、ステビンスは「シリアス」(真剣な)という形容詞で表現し、休息や気晴らしとして行われる「カジュアル」な余暇活動と対比させた。
ステビンスは『Serious Leisure: A Perspective for Our Time』(2015年、Routledge)において、シリアスレジャーを次のように定義している。「アマチュア、趣味人、ボランティアの中核的な活動を体系的に追求すること。彼・彼女らにとって、その活動はたいへん重要で、面白く、充実したものだと感じられる。そのため、典型的な場合では、専門的なスキル、知識、経験の組み合わせを習得し、発揮することを中心としたレジャーキャリアを歩み始める」。ここから、シリアスレジャーとしての趣味は「余暇活動としての継続性」と「専門的な楽しみ方の実践」という2つの特徴によって、カジュアルレジャーから区別されることが分かる。ここに趣味らしさの源泉がある。
例えば、ぼーっとテレビを見ることと、趣味で漫画を描くことを比べてみよう。両者はともに余暇活動であるが、使われる知識やスキルの点では対照的である。ぼーっとテレビを見ることは、テレビの付け方さえ知っていれば誰にでもできる。後はその前に座っているだけでよい。それに対し、漫画を描くことは誰にでもできるものではない。私のように絵の描き方もストーリーのつくり方も知らない未経験者にとって、漫画は「描けない」ものである。未経験者に比べれば、趣味の漫画家はプロでなくとも「専門的」と言える。
そのような専門的な楽しみ方は、一朝一夕でできるものではない。活動を続け、経歴(レジャーキャリア)を積み、漫画を読み描きする経験を蓄積するなかで、趣味としての漫画活動は形づくられてく。趣味がこのような特徴をもつことは、日常的な直観にも合うのではないだろうか。
確かに、ぼーっとテレビを見ることも、私たちは人生の中で何度も行っている。だが、何度も見たからこそのテレビの見方をしているわけではない。ぼーっとテレビを見ることには、反復性はあっても継続性はないのである(逆に、何度も見たからこそ可能になるテレビの見方・楽しみ方をしていたとしたら、それは趣味になっている。ドラマの視聴などではそのようなケースもあるだろう)。
これらの特徴は、ある余暇活動が、あらかじめシリアスレジャーかカジュアルレジャーに区別されるのではないことも示している。確かに漫画を描くことのように、スキルがなければ実践しようがないため、シリアスレジャーとして行う他ない活動もある(そのような活動は参入障壁が高いと感じられるだろう)。その一方で、テレビや映画を観ることのように、カジュアルにもシリアスにも行いうる活動も存在する。その場合、趣味として映画を観る人もいれば、気晴らしとして映画を観る人もいることになる。シネフィルと呼ばれる映画通と普通の観客の違いである。シリアスレジャーとしての趣味は、活動のジャンルを表すのではなく、活動への「取り組み方」を表すのである。
なお、ステビンスは「プロが存在する分野」のシリアスレジャー実践者を「アマチュア」、「プロが存在しない分野」のシリアスレジャー実践者を「趣味人」(ホビイスト)と区別している。それに従うと、野球の世界にはプロがいるので、草野球を楽しむのはアマチュアとなる。一方で、切手収集の世界にはプロがいないので、切手収集を楽しむのは趣味人ということになる。私はこの区別の必要性を今のところ感じていないので、プロがいようがいなかろうが、シリアスレジャーの実践者を全て「趣味人」と呼んでいる。だが、eスポーツのようにプロが誕生しつつある分野の動態を捉えるには、アマチュアと趣味人の区別も役に立つかもしれない。
趣味としてやっていく選択肢
シリアスレジャーという概念を手にすると、「ある活動を趣味としてやっていくこと」を人生の一つの選択肢として積極的に位置づけられるようになる。
活動に趣味として取り組むのは、考えようによっては、何の変哲もないことのようにも思える。だが、これまで見てきたように、趣味は余暇活動のなかでも、継続性と専門性を帯びた独特な取り組み方なのであった。それゆえ、趣味の実践には、活動をカジュアルにではなく「趣味として」やっていく選択が常に含まれている。もちろん、その選択は暗黙のうちになされることもあるだろう。だが、少なくとも、活動を趣味としてやっていく時点で、その人は自らの興味関心に従って、一つのライフスタイルを選び取ったのだと考えられる。
また、趣味としてやっていくという選択は、活動をカジュアルなものに留めない選択であるのと同時に、仕事にしないという選択でもある。それは必ずしも消極的な選択とは限らない。もちろん、プロになれなかったから、稼げていないから、活動が「趣味にしかならない」場合もある(『「趣味に生きる」の文化論』第9章ではそのような事例として地下アイドルが論じられている)。だが、多くの趣味人は、プロとして稼ぐことをそもそも念頭に置いていないのではないだろうか。仕事にできないから趣味としてやっているというより、仕事にせず趣味としてやっているのである。
例えば、私の場合、大学のサークルに入ってから10年間フラメンコを踊ってきた。10年間続けてきたのはフラメンコで食べていくことを目指してではない。趣味としてフラメンコの面白さを味わい続けるためである。時には「プロを目指さないの?」と聞かれることもあった。だが、そのたびに「プロを目指さないといけないの?」と聞き返したくなった。フラメンコは好きだが、仕事は仕事で別のことをやりたいのである。
このような「ある活動を趣味としてやっていく」という選択肢の意味は、YouTuber全盛の現代社会だからこそ、改めて捉え直す価値があるだろう。ゲームからアウトドアまで、今や様々な分野にYouTuberがいる。彼・彼女らは動画を通して活動の魅力や面白さを伝える一方で、「好きなことで、生きていく」という価値観を体現している。ここでの「生きていく」とは、「好きなことを生涯にわたって楽しんでいく」という意味ではない。好きなことを収益化し、好きなことを仕事にする、という意味である。「プロを目指さないの?」という質問の派生形として、現代では「どうせならYouTubeもやらないの?」という問いかけがある。
そのように問われて、実際にYouTuberを目指すのか目指さないのかは本人次第である。だが、少なくとも、YouTuberを目指さないからと言って、その人が何かから逃げていると考えるのはお門違いだろう。あくまで、好きなことを趣味としてやっていく道を選んだのである。実際、収益化を目指すのは活動に対する大きな制約となる。自分の楽しさと視聴者の需要を天秤にかけることにもなるだろう。それに比べれば、仕事で稼いだお金を使って自分の好きなように趣味を楽しむ方が、好きなことで生きていると言えるかもしれないのだ。
楽しむことの難しさと、楽しみ方を学ぶ必要性
前項の議論は、乱暴に言ってしまえば「趣味としてやっていくことも一つの道として良いじゃないか」というものであった。それはシリアスレジャーとしての趣味の特徴のうち「余暇活動としての継続性」に注目したものと言える。他方、「専門的な楽しみ方の実践」という特徴にも目を向けると、事態はそう簡単なものではないことが見えてくる。
すでに漫画を描くことを例に述べたように、シリアスレジャーとしての趣味は、未経験者がすぐにできるようなものではなかった。専門的な知識や技能を身につけることで、初めて趣味らしい楽しみ方ができる。ふつう「趣味程度」と言えば稚拙さを意味するが、実際のところ趣味程度とは高度な水準である。
音楽やダンスをやっている知り合いの発表会を観覧し、「意外にすごい」と思った経験はないだろうか。仮に、あなたがその場でパフォーマンスに参加しろと言われても、できっこないと思うだろう。舞台上の演者たちは、それまでに何度も練習を重ね、どうにか披露するに耐えるパフォーマンスを完成させている。楽器を演奏する楽しみも、身体で踊る楽しみも、それを習得する過程抜きには成立しないのである。
ここから示唆されるのは、活動を趣味としてやっていくことは、実は結構難しい営みなのではないか、ということである。専門的な楽しみ方を学ぶことができないならば、趣味をやっていくことは人生の選択肢にあがらない。趣味は無条件にできるほど甘くはないのだ。
このことを、私は重要な問題として受けとめている。活動を趣味としてやっていく選択肢があることは、実際にやるかどうかは別として、価値のあることだと考えている。それによって、私たちは生涯にわたって自分の好きなことに関わり、カジュアルにやっていたのでは分からない奥深さを楽しむことができる。また、そのようにして熱心に取り組む活動があることによって、学校や職場での自己とは別の顔を持つことができ、ウェルビーイングがもたらされるだろう。だが、それが可能になるのは、楽しみ方を学べるという条件が満たされる場合に限られるのである。
しかも、楽しみ方は一度身につければ終わりというものではない。同じ楽しみ方をずっと続けられるのならば良いが、往々にして人は挫折したり、マンネリを感じたりする。楽しみ方を「学び続けられる」可能性があって、はじめて私たちは趣味をやっていけるのである。哲学者の國分功一郎氏も『暇と退屈の倫理学』(2015年、太田出版)において同様の結論に辿り着いている。退屈と気晴らしを繰り返す存在として人間を捉えたうえで、氏が導く結論は、日常における「楽しむための訓練」を通して、贅沢を取り戻すことであった。
文化資本による検討の隘路
活動を趣味としてやっていくことは、人生の積極的な選択肢の一つである。だが、それを選択肢として行使するためには、専門的な楽しみ方を学ぶ必要がある。そうでなければ、私たちは趣味をやっていくことすらできない。趣味がない、趣味が続かないと悩む人がいるのは、こうした趣味の難しさにも起因すると考えられる。
では、趣味の専門的な楽しみ方を、人はいかにして学ぶことができるのだろうか。
現実には、趣味を楽しめている人も世の中には数多く存在する。彼・彼女らは楽しむことの難しさを乗り越え、何らかの形で楽しみ方を身につけている。だとすれば、その趣味人生の中に、楽しみ方を学ぶための手がかりが隠されているかもしれない。
人によっては、このような問いを「文化資本」の観点から検討するだろう。文化資本は、もともと社会学者のピエール・ブルデューによって提案された概念である。個々人が家庭や学校で身につけた美的センスや教養、身のこなし方が、音楽ジャンルや芸術作品への嗜好となり、社会空間における地位をつくりだすことを意味している。文化資本の観点から見れば、楽しみ方を学べるのは社会階層やジェンダー規範が反映された家庭環境において、ということになる。
実際、そのようにして趣味の楽しみ方が学ばれるケースも存在している。例えば、マリケ・ヘクトらによる“Becoming a naturalist: Interest development across the learning ecology”という論文がある。自然に関わる活動をしている人々の生活史を聞き取り、いかにして自然へ興味を持つようになったのかを分析したものである。
この論文では園芸を趣味とするエリックという男性が登場する。66歳で、長らく自然趣味を楽しんできた彼の出発点は、幼少期にまで遡る。祖母の家に遊びに行き、庭で何時間も過ごしたり、祖母とキノコなどの野生食材を探しに行ったりしたことが、自然に興味を持つきっかけだったという。エリックは幼少期に身につけた楽しみを、生涯にわたって発展させている。
私も似たような話を聞いている。修士論文を書くためにアマチュアオーケストラ団員の方々にインタビューをしたとき、しばしば家庭環境の話題が出た。母親がピアノやヴァイオリンの先生だったとか、父親の集めた楽器が家に転がっていたというものである。こうした話を聞くと、「なんだ、結局生まれじゃないか」という気分に一瞬させられてしまう。
だが(だからこそと言うべきか)、私は楽しみ方の学習を、文化資本の問題としては扱わないようにしている。もちろん文化資本として楽しみ方が学ばれる場合もあるわけだが、そこに注目しても、これから趣味をやっていこうとする人間に何ができるのかは見えてこない。岸政彦氏は『100分de名著 ブルデュー ディスタンクシオン』(2020年、NHK出版)において、ブルデューの理論は社会構造に規定される私たちの「不自由を知る」ことを可能にすると述べている。そうであるならば、不自由を知ったうえで、それでも何をなし得るのかを知りたい。
何より、文化資本として楽しみ方を身につけた趣味人たちも、幼少期の家庭環境だけで学びを完結させているわけではない。園芸趣味のエリックは、長じて後、自然史博物館のプログラムやコミュニティ・ガーデン、趣味のクラブに参加することで、自然への興味をさらに深めていた。オーケストラ団員たちも、両親から楽器の手ほどきを受けた後に、中学や高校では吹奏楽部に入り、そして大学生や社会人になって管弦楽団に入ったことで、はじめてオーケストラの面白さに出会っている。こうした環境での学びならば、これから趣味をやっていこうとする人間も経験することができる。
家庭環境ではなく、実際の趣味の現場において楽しみ方がいかに学ばれるのか。こう問うことによって、楽しみ方の学習は私たち一人ひとりが取り組める実践的な問題となる。
学習環境から見出せる活路
ここで、ようやく学習科学の出番がやってくる。学習科学は認知心理学や人工知能研究に文化人類学が融合して形成された分野である。詳しい紹介は『主体的・対話的で深い学びに導く 学習科学ガイドブック』(2019年、北大路書房)や『学習科学ハンドブック 第二版』全3巻(2016-2018年、北大路書房)を参照されたい。
楽しみ方の学習を考えるうえで重要なのは、学習科学が学校教育を前提にしていないことである。教科をいかにして教えるかではなく、人間が有能に振る舞い、学ぶのはいかなる状況においてなのか、という問いから出発することで、学習科学は様々な社会生活の現場を「学習環境」として観察してきた。
一例を挙げよう。ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーによる『状況に埋め込まれた学習──正統的周辺参加』(1993年、産業図書)という研究がある。この研究では、現場での学びを可能にする条件が、徒弟制を事例に分析されている。その中に、西アフリカはリベリアにおける仕立屋の事例がある。
レイヴらによれば、仕立屋の現場には、見習いが学ぶための仕組みが備わっている。見習いはまず、アイロンがけやボタンづけといった責任の少ない簡単な作業をあてがわれる、というものである。このことは二つの意味で、見習いの学びを可能にしている。
一つ目の意味は、まだ技能が未熟であったとしても、その現場に参加する正統性を与えられるということである。現場の中で学ぶと言っても、何もせず、ただそこに存在しているのは不自然である。自分も居心地が悪いし、周りからも迷惑がられる。だが、「アイロンをかけておいて」と役割が与えられることで、そこに居る必然性が生まれる。
二つ目の意味は、「今はできないけれども、今後できるようになるべき仕事」が観察できるようになるということである。アイロンがけやボタンづけの作業では、見習いはほぼ完成品の衣服を手にすることができる。それによって衣服の構造や縫い方などを把握し、向こう側でミシンをかけている熟練者が何をやっているのかを、周辺的な立場から観察できるのである。
このような分析から、レイヴらは「できないなりに実践に参加しながら、できる人たちの実践に触れられる」状態こそが、現場での学びを可能にすると考えた。この状態を「正統的周辺参加」と呼んでいる。
趣味から離れた事例ではあるが、楽しみ方の学習環境を捉えるうえでも、このような知見は有効だろう。楽しみ方を学ぶには、まだその楽しみ方ができないときであっても、趣味の現場に参加できる必要がある。では、それはどのような身分として可能なのか? 学生のサークルであれば、「新入生」という立場が得られる。習い事教室に行けば「初心者」になれるだろう。しかし、そのような教育的制度化がなされていない活動の場合はどうなるのか。など、学習科学の知見を援用することで、楽しみ方の学習を可能にする環境を考察することができる。
また、既存の知見を援用するだけでなく、趣味の現場を学習環境として観察することで、新たな知見を得ることも期待される。決して多くないが、すでに趣味の現場をフィールドにした学習科学研究は登場している。ヘクトらの研究もそうであるし、アマチュアオーケストラ団員の楽団コミュニティやアマチュア写真家のSNSネットワークに注目した私の研究もそこに含まれる。このような研究から楽しみ方の学習環境のあり方が分かれば、私たちが趣味をやっていくためにどうすればよいのかも見えてくるだろう。運よく環境に恵まれれば趣味を楽しめるというのではなく、楽しむために学習環境にアクセスしたり、無ければ自分でつくる、という実践が可能になる。
ただ、正直なところ、現段階では、楽しみ方の学習環境とはこういうものだと結論づけることはできない。問いを提起したのは良いものの、それに答える研究の蓄積は乏しいのが現状である。だからこそ、様々な趣味の現場において、学習環境としての観察と分析がなされていってほしいと考えている。
その担い手は、何も学習科学者に限られる必要はない。趣味を楽しめるようになりたい人、趣味をもっと楽しみたい人が、やっていきたい趣味に応じて「楽しみ方の学習環境」を考えることができる。実際、私がこれまで書いてきた論文や『「趣味に生きる」の文化論』は、研究者だけでなく趣味人の方にも読まれているようだ。その中には、本文中では取りあげていない趣味(短歌、ジャグリング、ボードゲーム……)を実践されている方もいる。他の趣味の事例と比較することで、自分たちの趣味の場合はどうか、と考察されているようである。このような読まれ方は大変嬉しいものであるし、ぜひ「自分たちの趣味」を分析した結果も聞かせてほしい。ブログ記事や同人誌・ZINEにまとめられた方がいれば、ぜひ読んでみたい。
鯖主による学習環境デザインと社会批評を求めて
先ほど、知見の用い方として、楽しむための学習環境が無ければ自分でもつくれると述べた。実は、学習環境をつくることも、学習科学の特徴の一つである。学習環境をデザインし、その結果どのような学びが起きたのか/起きなかったのかを分析しながら、新たなデザインの原則を考える。観察するだけでなく「つくることを通して考える」ことで、現実的な変化をもたらしながら、効果的な学習環境のあり方を探究するのである。
趣味においても学習環境デザインが積極的に行われていくことを私は期待している。学校や職場では学びを促すための様々な努力がなされている割に、趣味の現場ではそのような話を聞かない。しかし、楽しんでいくための創意工夫だって、なされてもいいはずである。楽しみ方の学習には、既存の楽しみ方を身につけるだけでなく、これまで存在しなかった新たな楽しみ方を生み出し、身につけることも含まれる。私たちが趣味をより楽しめるようになるために、地域やインターネットを舞台に様々な現場=学習環境をデザインしていくとき、面白い文化が生まれるかもしれない。
楽しみ方の学習環境デザインを担う人々を、私は比喩的に「鯖主」と呼んでいる。箱庭ゲーム《Minecraft》の文化から借用した表現である。《Minecraft》ではプレイヤーは様々な種類の立方体ブロックからなる世界を自由に冒険したり、生活したりできる。さらに、他のプレイヤーとマルチプレイすることもでき、そのためのサーバーは誰でも自由に設置することができる。サーバー(=鯖)の管理者(=主)が、ネットスラング的に鯖主と呼ばれている。
鯖主は自分が趣味を楽しむだけでなく、他者が楽しむための環境をつくりだす存在である。『マインクラフトでマルチサーバーを立てよう!』(2017年、インプレス)という書籍では、サーバーで提供したいゲームプレイの方向性を考え、それに合わせたプラグラインを導入する方法が解説されている。鯖主の采配によって、それまでにない新たな遊び方が生み出されることもある。
現実の鯖主は学習環境デザインのためにサーバーを運営しているわけではない。だが、今ある趣味の現場に満足せず、自分で新しい環境をつくりあげる鯖主のふるまいは、楽しみ方の学習環境デザインの原型のように感じられる。
そのような「鯖主」は、趣味の世界には様々な立場で存在している。サークルやコミュニティの運営者、ハウツーやポータルサイトの執筆者、道具や用品の販売者……こうした人々が楽しみ方の学びを促す工夫を始めたとき、新たな趣味の世界が見えてこないだろうか。日々市場での競争にさらされている企業ならば変化せざるを得ない事情があるだろうが、趣味に対してはそこまでの外圧はない。だからこそ、鯖主たちのDIY精神は趣味の世界にとって貴重なものになると思う。
個々人も自分自身にとっての鯖主である。例えば、街中の習い事教室に通うにしても、どの先生につくかで、教え方や活動内容は異なってくる。いくつか教室を見学し、どこに通うかを比較検討している時点で、それは楽しみ方の学習環境デザインである。趣味としてやっていくのは難しいことだからこそ、楽しめるようになるための学習環境にもっと注意が向けられていい。与えられた環境でしか趣味をやってはいけない道理はないのである。
このようにして学習環境デザインに取り組もうとすると、趣味の世界や社会が抱える課題にも否応なしに直面することになるだろう。水野英莉氏による『ただ波に乗る Just Surf──サーフィンのエスノグラフィー』(2020年、晃洋書房)では、サーフショップを中心としたコミュニティが、ボードの選び方などを相談できる学習環境になっていると同時に、女性を排除する「男同士の絆」になっていることも描かれている。楽しみ方の学習環境では公平性が確保されているとは限らない。では、どうすれば公平性を生み出せるのか。こういったところまで考え始めると、学習環境のデザインは社会批評性も帯びていく。
おそらく、社会を「楽しみ方の学習環境」として眺めたらこそ見えてくる、公共的な課題が存在するだろう。趣味を研究することは、楽しむことを通して社会のあり方を考えるための、視点や道具立てにもなるのだ。コロナ禍は、趣味が社会的な問題であることを(珍しく)顕わにした出来事である。ライブハウスの営業自粛や、大学キャンパスにおける課外活動の制限など、趣味と公共性の問題だと思える事象はたくさんあった。指揮者の木許裕介さんによるブログ記事「大学オーケストラの危機」でも、学生オーケストラが楽しみ方の学習環境であるからこそ、活動制限が「危機」になることが述べられている。こうした事象について、趣味や統治の観点から整理できる必要性を改めて感じさせられる。余暇研究者はもっと仕事をしないといけない。
本稿では、趣味の趣味らしさを表す概念としてシリアスレジャーを取りあげ、それに注目することで「活動を趣味としてやっていくこと」を人生の選択肢として積極的に位置づけられること、その一方で、趣味としてやっていくことは専門性の高い楽しみ方であり、実は難しいものであることを示した。だからこそ、そのような楽しみ方を身につけられる学習環境が重要であり、趣味の現場、延いては社会を「楽しみ方の学習環境」として眺め、またデザインすることが、趣味をやっていくための鍵になるのではないかと提案した。私も引き続き趣味研究に取り組んでいく。このようなテーマや問題提起に興味を持たれた方がいたら、ぜひご自身でも趣味研究をやってみてほしい。「趣味研究」は趣味に関する研究であると同時に、趣味として行う研究であってもいいはずだ。
[了]
この記事は、PLANETSのメルマガで2021年7月22日に配信した同名記事をリニューアルしたものです。あらためて、2021年8月23日に公開しました。