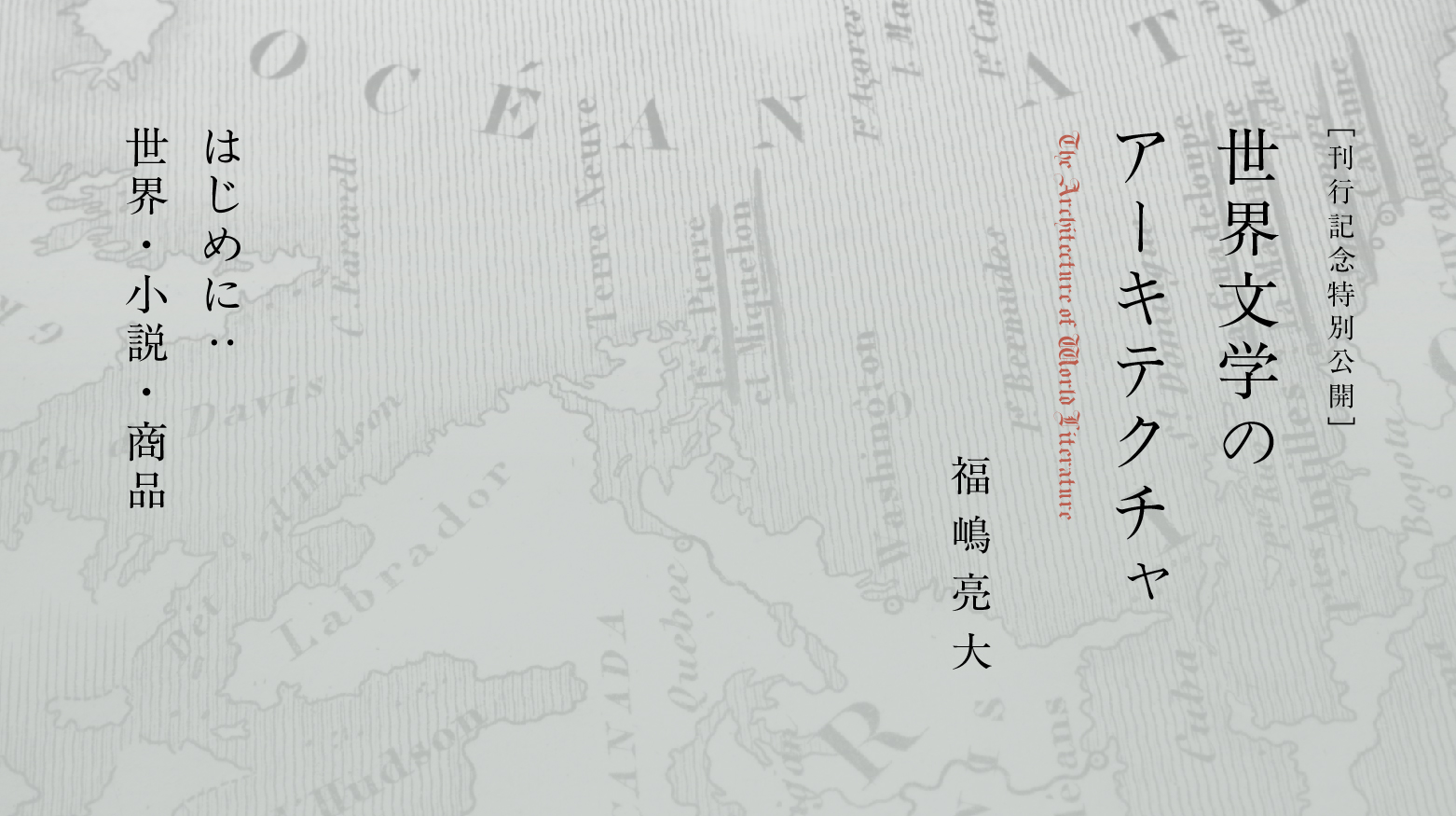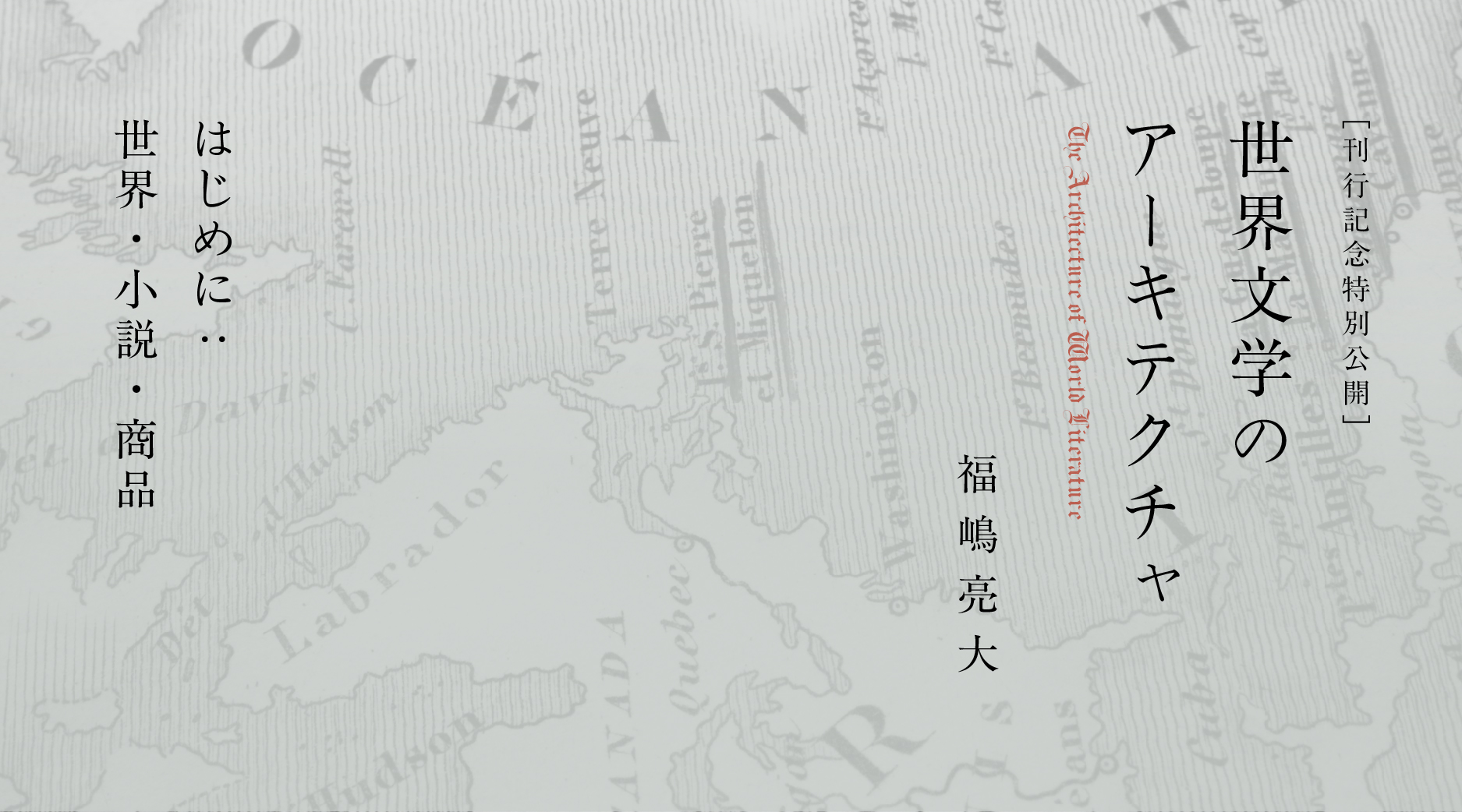批評家・福嶋亮大さんの新刊『世界文学のアーキテクチャ』の刊行を記念して、本書序章を特別公開します。
18世紀以降「小説」が「世界文学」の中核を占めるようになる過程で何が起きていたのか。心的/社会事象を言語に変換するプログラムは資本主義に連動しながらいかに進化してきたのか。「世界文学」の起源を探り、その設計思想の変遷をひとつの物語として大胆に描き出します。
端的に言うとね。
1、世界市場を旅する文学
二一世紀に入ってから、一八二〇年代のドイツでゲーテが語った「世界文学」(Weltliteratur)という概念が、しばしば文学研究の議論の俎上に載るようになった。各国の文学がしきりに他言語に翻訳され、自国の外にまでその流通の範囲を広げている今、西洋偏重の文学史観への反省を含んだ、より包括的な文学理解が要求されているのは確かである。「世界文学」はその要請に応えるために呼び出された一種のパスワードだと言えるだろう。
もっとも、世界文学がいささか捉えどころのない、漠然とした言葉であるのも確かである。われわれはこの概念から何を引き出せるだろうか。例えば、アメリカの比較文学者デイヴィッド・ダムロッシュは『世界文学とは何か?』と題した著作のなかで、世界文学を文学全体の「ある一つの部分集合」と見なす立場から、次のように記している。
私の考えでは、世界文学とは、翻訳であれ原語であれ(ヴェルギリウスはヨーロッパではずっとラテン語で読まれてきた)発祥文化を越えて流通した全作品を含む[1]。
ダムロッシュによれば、ある作品が原産地を越えて異郷で「アクティヴ」に存在するとき、その作品は「世界文学」としての資格をもつ。別の環境に移植されることによって、いっそう繁殖力を増した文学―それがダムロッシュの言う「世界文学」である。彼は翻訳によって文化の生育環境を変えることに、きわめて積極的な意味を与えている。「世界文学の領域へ入った作品は、真正さや本質を失うどころか、むしろより多くの点で豊かになりうる。このプロセスを追うためには、特定の状況において作品がどのような変容を遂げるのかをじっくりと見なければならない」[2]。
ダムロッシュは世界文学という概念を、さまざまな国家から移植された文学作品を集めた一種のプラットフォームとして捉えている。このプラットフォームの内部でさまざまな偶発的な「読み」の機会にさらされるとき、作品には思いがけない照明が当てられる。ダムロッシュにとって、世界文学とは各国文学のたんなる総和ではない。世界文学になることは、作品を既存の理解の文脈から抜き出して、新たな「実りある生」へと引き渡す契機なのである。
このような見解はある程度の説得力をもつ。現代の文学作品は、確かに世界市場を旅することによって自らを転生させる。この旅には内在的な終わりがないため、世界文学へのエントリーによって、個々の作品にはいわば長い余生の可能性が与えられる。各国の古代文学から現代文学までが「世界文学」というプラットフォームに登録されるとき、作品どうしの新たな関連性が生じ、文学の評価をめぐるコミュニケーションにもおのずと変動が生じる。第一章で詳述するように、そもそもゲーテの世界文学論こそが、まさに文学の翻訳者や伝達者の増大というコミュニケーション革命を前提としていたのである。
もっとも、ダムロッシュが世界文学を評価するとき、しばしば具体性を欠いた広告的な表現をしがちであることも否めない。例えば「アクティヴに存在する」とか「豊か」であるとか「実りある」というのが、どういう状況を指すのかは、はっきりしない。「世界文学」という観念を用いるにあたっては、本来は文学にとって世界とは何かという根本的な問いを立てねばならない。しかし、ダムロッシュは文学の流通する世界市場から「世界文学」の名称を導き出すだけで、当の「世界」の内実を歴史的に検証することがない。これは重大な欠陥ではないか。
2、世界文学というアーキテクチャ
私はここで、世界文学を各国文学の流通するプラットフォームというよりも、より概念的な「アーキテクチャ」の隠喩によって捉えたいと思う。architecture はもともと「建築」を意味するが、それが計算機科学では基本的な「設計思想」を指す言葉として転用され、その用法が今ではインターネットにまで波及している[3]。建築にせよコンピュータにせよ、さまざまなテクネー(技術)に先立つテクネー、つまりアルケー(始原)のテクネーが「アーキテクチャ」として総称されていることに変わりはない。
この概念を世界文学に当てはめてみよう。そうすると、世界文学というアーキテクチャは、たんにあれやこれやの文学作品のコレクションではなく、むしろ数世紀をかけて形作られてきた設計思想の集積として理解できる。コンピュータがデータを特定のアルゴリズムで処理するように、文学も心的事象や社会的事象を言語によって設計するのに、さまざまな手法を用いている。本書で論じるように、これらの設計思想の集まるアーキテクチャを飛躍させる「ビッグバン」となったのが、一六世紀以降のヨーロッパとその外部の世界との接近遭遇であった。文学を《世界文学》にしたのは、ゲーテ一人の功績ではない。むしろゲーテ以前からあったグローバリゼーション(世界化)の帰結こそが《世界文学》と呼ばれるべきである。
本書で輪郭づける《世界文学》には、二つの意味がある。一つは世界的に翻訳され流通する文学という意味であり、もう一つは《世界》を設計(プログラム)に組み込んだ文学という意味である。ダムロッシュはほぼ前者の問題しか考えていないが、本来は前者と後者のどちらも欠けてはならない。
ダムロッシュにとって、世界文学は文学全体の「部分集合」だが、私にはそれはいささか過小評価に思える。なぜなら、一六世紀以降の《世界》への傾斜こそが、文学史上の最も革新的な作家たち——一八世紀のデフォーやスウィフト、一九世紀のメルヴィルら——を出現させたのだから。
近代小説という特異なジャンルの発生は、特にこの後者の意味での世界文学と深く関わっている。ふつう近代小説は、共同体の解体および個人主義の発生と関連づけられる。しかし、共同体から離脱する「私」が中心化される以前に、《世界》との出会いが文学に質的な飛躍をもたらしていた。そのことは一九七〇年代以降の人文学で、すでに大きく取り上げられたことがある。特に、エドワード・サイードのような批評家は、「私」に先行する世界の権力構造を問い直し、ポストコロニアリズムの思潮がそれを受け継いだが、その理論的な発展はまもなく止まってしまった。私は本書で、そこに再び展望を与えることを試みたい。
もとより、文学の設計の「仕様書」が、あらかじめ作家たちに与えられたわけではない。しかし、事後的に観測すると、個々の文学者の仕事を導く設計思想=プログラムが、各時代である程度共有され、次の時代に変形的に継承されたように思える。では、個々の作家や作品を規定するアーキテクチャ、つまり設計思想の集積は、具体的にはいかなる進化史をたどって生み出され、成長し、また衰退したのだろうか。そして、この「世界文学の進化史」に対しては、どのような思想史的な意味づけがなされるべきだろうか。本書はこれらの問いに取り組んだ試論である。
3、精神の商品化
本論に入る前に、前提として二つの論点に言及しておきたい。第一の論点は、世界文学が商品経済と連動していたことである。第二の論点は、世界文学の中心が小説によって占められたことである。第一の論点から述べよう。ヨーロッパ統合を夢見たナポレオンが一八二一年に死去してからまもなく、ゲーテが世界文学のヴィジョンを示したとき、世界規模の交通の拡大がすでに彼の視界に入っていた。ゲーテに傾倒していた一八七五年生まれのトーマス・マンは、一九三二年の講演でそのことを的確に指摘していた。
ゲーテの世界文学の提唱のなかには、疑いもなく多くの先取りがありました。そして、彼の死後の百年間の発展、交通の発達、それがもたらした交易の迅速化、大戦によってさえも、停滞させられるよりもむしろ促進されたヨーロッパの、いや世界の緊密化、これらすべてが、ゲーテが今はその時代だと感じた時代を、いよいよ真に現実のものとするためには必須のものであったのでした[4]。
ゲーテの言う世界文学は「交易の迅速化」や「世界の緊密化」と密接につながっている。マンも注目するように、ゲーテは国境を超えた文化の相互浸透を「観念と感情の自由貿易」と言い表していた[5]。これらのメタファーは一九世紀のゲーテの段階で、経済的なモデルによって文化の流通が説明できるようになっていたこと、つまり精神の世界と商品の世界が多くの点で重なりつつあったことを示唆している。マンはゲーテ以降、精神と商品の結合がいっそう強固なものになったと認識していた。
さらに、マンと同世代のフランスの批評家ポール・ヴァレリーも、やはり大戦間期の一九三九年の論説で「精神の経済」に言及した。ヴァレリーの考えでは、あらゆる「精神的な事象」(科学、芸術、哲学)は経済的なものと似通っている。
私が株式取引所の用語を借りて話していることはお分かりだろう。精神的な事象に関して使うのは奇妙に思われるかもしれない。しかし、他によりよい言葉がないし、多分、この種の関係を表現するのに、捜しても他に適当な言葉はなさそうである。というのは、精神の経済も物質の経済も、人がそれを考えるとき、単純な価値評価のせめぎあいとして考えるのが最も分かり易いからである。
一つの文明とは一つの資本である。その増大のために数世紀にわたる努力が必要なのは、ある種の資本を増大させるのと同様で、複利法で増資していくのである[6]。
ヴァレリーにとって、精神の挙動を言い表すのに、経済以上に適格なメタファーはない。これは見かけ以上に大胆な考え方である。彼によれば、精神は宗教的にでも政治的にでも家族的にでも法的にでもなく、価値評価がたえず揺れ動く経済的な金融商品のように存在しており、だからこそ生産、消費、交換、増資、流通などのメタファーによって説明することができる。ヴァレリーの考察は、ゲーテの予告した世界文学の時代―観念や感情がグローバルな交易の対象になり、人類の知識が統合され増大してゆく段階―が、精神のあり方も深く規定し始めたことを示している(ちなみに、ヴァレリーにはゲーテの『ファウスト』を改作した『我がファウスト』という戯曲もある)。
むろん、このような精神の経済モデルには、いささか単純化のきらいもある。文学に経済的次元に還元できないもの、つまり市場化できないものがあるのは明らかである。この問題は小説(散文)以上に詩において、よりはっきりするだろう。というのも、詩は精神の商品化の傾向に対して、強い抵抗を示す文学ジャンルとしてしばしば評価されてきたからである。
例えば、一八八八年生まれのモダニズム詩人T・S・エリオットは「国民間の精神的な交わり」がなされるには、かえって翻訳困難な詩が必須だと見なした。詩というジャンルは安易な交換=翻訳を拒絶するからこそ、異なる言語どうしのコミュニケーションの深遠さを読者に自覚させることができる。「一言語で言えるだけで翻訳できないすべてのものに、詩はいつも気づかせてくれます」。エリオットの考えでは、ヨーロッパ文学はかたくななナショナリズムではなく、外国語の文学との「ギブ・アンド・テイク」の関係によって創造されてきた[7]。そして、この関係を持続するには、外国語を自由に翻訳できるという自惚れよりも、むしろなめらかな交換=翻訳を妨げる詩的な障害への鋭い感覚こそが有効なのである。
エリオットはここで、ゲーテ的な世界文学=世界市場の根底にある全面的な商品化に抗して、別のコミュニケーションの回路を描き出した。もっとも、このような抵抗の論理そのものが、いかに商品化の圧力が強いかを証明している。資本主義経済から完全に隔離された聖域は、もはやどこにもない。
だからこそ、モダニストのエリオットは詩を聖なる祭壇に祭り上げるのではなく、むしろなめらかな交換を限界に突き当たらせる文学的実験に差し向けた(彼が、詩という吹きさらしの実験場に与えた名称が「荒地」である)。それでも「世界文学の時代」はエリオット以降も加速し、精神はますます商品と見分けがたくなった。現代のわれわれもその条件から逃れることはできない。
4、資本主義のミメーシスとしての小説
この精神の商品化現象とも関わることだが、ここでもう一点確認したいのは、世界文学の中枢がもっぱら小説に占められたことである。むろん、世界文学には詩や演劇も含まれる。しかし、文学の「世界化」は小説の力なしにはあり得なかった。
本書では主に、小説の原産地をヨーロッパと中国に求めている。このうちヨーロッパに起源をもつタイプの小説の流行が、文学をグローバルに拡大させる契機となった。それはパンデミックを引き起こすウイルスに類比できる。ここで見逃せないのは、小説というウイルスの挙動が資本主義の挙動と近似していることである。例えば、世界システム論の提唱者であるイマニュエル・ウォーラーステインは、資本主義の本質に「万物の商品化」を見出している。
史的システムとしての資本主義は、それまでは「市場」を経由せずに展開されていた各過程——交換過程のみならず、生産過程、投資過程をも含めて——の広範な商品化を意味していたのである。いっそうの資本蓄積を追求しようとした資本家たちは、経済生活のあらゆる分野において、いっそう多くのこうした社会過程を商品化してしまうことになった[8]。
ウォーラーステインの考えでは、資本主義はその固有の歴史において「社会過程の広範な商品化」のプロセスを継続してきた。その結果、空気や水、人間関係はもとより、遺伝子や感情のような不可侵と思われる対象ですら、市場で流通する商品となる。資本主義の浸透によって、人類は世界のすべてに商品の形態を与えるようになった。例えば「愛は金で買えるか」という凡庸な問いは(それにイエスと答えるか否かにかかわらず)あらゆる人間関係がすでに商品世界のフィルターを通過していることを前提としている。
資本主義の「万物の商品化」に似たプロセスは、小説の歴史にも内包されている。そこにはいわば万物の小説化とでも呼べる衝動が見出される。興味深いことに、ウォーラーステインの挙げた社会生活上のプロセス——交換過程、生産過程、投資過程——はいずれも、小説というジャンルを成長させる推進力となった。
例えば、一八世紀には多くの書簡体小説が書かれたが、それはまさに手紙のやりとりという私的なコミュニケーション、つまり外部からは本来うかがい知れない秘密めいた交換過程を再現したものであった。例えば、一七六一年に刊行され、当時屈指のベストセラーとなったジャン=ジャック・ルソーの『新エロイーズ』では、令嬢ジュリとその家庭教師で平民のサン=プルー、およびその周囲のひとびとの手紙の交換が、感情のテレパシー的な共鳴現象として描き出されている。この『新エロイーズ』のおよそ半世紀前に、イギリスではデフォーの『ロビンソン・クルーソー』(一七一九年)が刊行された。その主人公の商人クルーソーはいわゆる「経済人」(ホモ・エコノミクス)のモデルとして、マルクスやマックス・ヴェーバーのような後世の理論家たちに注目された。
イギリスからブラジル、カリブ海までを横断するグローバリストであるクルーソーは、流れ着いた孤島を、十分な生産性を備えた場所に作り変える。生産者にして商人でもある彼にとって、大西洋を取り囲む大陸は、商品(黒人奴隷も含む)の循環する市場であり、カリブに浮かぶ島は原材料を資源に変える工場であった。クルーソーはベンチャーの欲望に巻き込まれながら、環大西洋世界の交換過程と孤島での生産過程をともに活気づけたのである。
さらに、『ロビンソン・クルーソー』のおよそ百年前の一六一五年に、スペインのミゲル・デ・セルバンテスは自作の『ドン・キホーテ』の後篇を刊行した。後篇はドン・キホーテとサンチョ・パンサの二人組が活躍する前篇が書物となって流通している状況を、物語の筋に組み入れた点で、巧妙なメタフィクションとなっている。
ドン・キホーテは学士を立ちあがらせると、こう言った―
「すると、わしのことを描いた物語があり、それを著わしたのがモーロの賢者であるというのは本当でござるか?」「本当なんてもんじゃありませんよ」と、サンソンが答えた、「わたくしの睨むところ、その本はこれまでに一万二千部のうえ印刷されているはずですからね。噓だと思うなら、本が出版されているポルトガル、バルセローナ、そしてバレンシアに訊いてみればすぐに分かることです。しかも現在、アントワープでも印刷中だという噂があります。ですからわたくしには、今後この本が翻訳されないような国も言葉もなかろうと思われるんですよ。」(後篇第三章/以下『ドン・キホーテ』の引用は牛島信明訳[岩波文庫]に拠る)
実際、一六〇五年に刊行された『ドン・キホーテ』はあまりに評判になったせいで海賊版が跋扈したばかりか、一六一〇年代には早くもロンドンやパリで翻訳が刊行されていた。セルバンテスはこの爆発的な流通の状況を逆手にとって、後篇を『ドン・キホーテ』という書物への自己言及を含んだメタフィクションに仕上げた。ここでは、セルバンテスの書いたテクストそのものが投資過程の一部に組み込まれている。つまり、資本が利潤を生み出し、自らをエンドレスに増殖させるように、『ドン・キホーテ』の後篇は『ドン・キホーテ』そのものの自乗として書かれた。しかも、そこには来たるべき全面的な翻訳の時代が、明らかに予告されていたのである。ウォーラーステインが言うように、「万物の商品化」と並ぶ資本主義のもう一つの特性は、資本の蓄積のプロセスそのものが目的化したことにある。自己拡張こそが資本主義を動かす力であり、その力を保つために万物を見境なく商品化することが必要となる。
ここで史的システムとしての資本主義と呼んでいる歴史的社会システムの特徴は、この史的システムにおいては、資本がきわめて特異な方法で用いられる——つまり、投資される——という点にある。すなわち、そこでは、資本は自己増殖を第一の目的ないし意図として使用される[9]。
セルバンテスは『ドン・キホーテ』そのものがまさに資本のように自己増殖してゆく倒錯的な状況に、自ら進んで介入した。それは『ドン・キホーテ』への「投資」をいっそう煽りながら、『ドン・キホーテ』のエンドレスな自己増殖そのものを笑いに変えるような仕掛けである。つまり、セルバンテスは資本主義のミメーシス(模倣)としての小説を書いたのであり、それが世界文学の原風景になった。彼が示したのは、資本主義の原理と小説の原理が相似形をなすということである。
5、感覚的にして超感覚的なモノ
ところで、私はここまで無造作に「商品」という言葉を使ってきた。しかし、商品という存在には、一筋縄ではいかない謎めいたところがある。例えば、マルクスは『資本論』の「商品の物神的性格とその秘密」を論じた名高い文章で、商品は一見して「平凡」でありながら、実際には神秘的なものだと主張した。
たとえば人間が木材から机を作れば、木材の形は変化する。それでも、机は木材であり、ありふれた感覚的なものであり続ける。しかし机がいったん商品として登場すると、それはとたんに感覚的にして超感覚的なものへと変身する。商品としての机は自分の足で床の上に立っているだけではない。他のすべての商品に対して逆立ちして、その木偶頭から妄想を繰りだす。それは机が自分で踊り始めるよりも、もっと不思議なことだ[10]。
モノは社会的に流通する商品になったとたん「感覚的にして超感覚的なもの」に変わる。例えば、机は感覚で捉えられるモノである。しかし、それが市場にエントリーし他の商品と関連づけられるとき、超感覚的な数値(価格)がそこに付加される。つまり、商品世界へのエントリーは、ありふれたモノを「感覚的にして超感覚的なもの」へと変身させる。
このマルクスの卓見は、小説における事物の分析にも応用できる。小説のなかの「机」も、商品と似ている。なぜなら、机は小説の内部にエントリーされることによって、通常とは異なる評価を受け得るからだ。それは主人公の思い出の机かもしれないし、由来のある骨董品かもしれない。小説の読者は、ありふれた机に深遠な意味を見出すかもしれない。そのとき、小説のモノは感覚的な次元に置かれるだけではなく、超感覚的な評価にも開かれることになる。小説を読むとは、感覚的なもの(事物)と超感覚的なもの(価値評価)が二重に重ねられた言葉を受け取ることと等しい。 商品と同じく、小説のなかの事物も、まさに「感覚的にして超感覚的なもの」である。『ドン・キホーテ』では、まさにこの二重性がさまざまなやり方で露出させられている。ドン・キホーテが風車を巨人と勘違いするとき、感覚を超えたもの(評価)が彼の感覚を狂わせている。さらに『ドン・キホーテ』の海賊版や翻訳の流通する出版界は、作中人物であるドン・キホーテやサンチョ・パンサの感覚では本来アクセスできない。にもかかわらず、その超感覚的なレベルの出来事を、ドン・キホーテ主従にとって感覚可能な世界まで降下させたところに、セルバンテスの卓抜なユーモアがあった。
この感覚的なものと超感覚的なものの交差については、第八章のモダニズム文学論で改めて取り上げたい。ここではひとまず、資本主義の論理や商品の特性が、いかに小説というジャンルと共鳴していたかを確認すれば十分である。
6、三つの視点
私は先ほど、アーキテクチャを「設計思想の集積」と見なしたが、それは硬直したものではなく、むしろ変化に富んだダイナミックなシステムである。かつて建築家の磯崎新は、アーキテクチャを「構築する力」と定義した[11]。一口に言えば、私が本書でやろうとするのも、文学を構築する力がどこからやってきたのかを探究することである。そのために、以下の三つの視角を用意した。
第一部は議論の前提として、ゲーテの世界文学論のコンテクストを再考するところから始める。ゲーテは一九世紀以前と以後の文化的世界をブリッジする思想家であり、彼の《世界文学》のヴィジョンにも過去と未来の双方につながってゆく要素がある。それを確認した後、私は思い切って古代までさかのぼり、小説の特性(他者志向性)を「ガリレイ的言語意識」をキーワードに示すことを試みる。世界文学のアーキテクチャ(建築)を支える地盤0 0 の特徴を、完全なものではないにせよ、簡略に描き出すことが第一部の目的となる。
第二部では世界文学を歴史的な建築物と見なす立場から、小説の進化史が考察される。私が試みたのは、ヨーロッパ、アジア、新世界という三つの地理的区分を設けて、世界文学の進化を再現することである。そこでは、ナショナリズムの文学よりもグローバリズムの文学が、あるいは自己の文学よりも他者の文学が、より基本的な形態と見なされるだろう。
第三部では世界文学のアーキテクチャのより詳しい解析のために、小説を構築するさまざまな思考のテーマがどのような脈絡で生じ、いかに機能してきたかを論じる。私はさしあたり七つのテーマを設定し、それぞれが文学の設計にどのような作用を及ぼしたかを示した。つまり、第三部はいわば一つ一つのテーマを主人公として、世界文学の軌跡をたどり直したものである。
[1]デイヴィッド・ダムロッシュ『世界文学とは何か?』(秋草俊一郎他訳、国書刊行会、二〇一一年)一五頁。
[2]同右、一八頁。
[3]アーキテクチャの概念をインターネットに本格的に応用したのは法学者のローレンス・レッシグであり、日本では情報社会学者の濱野智史の『アーキテクチャの生態系』(ちくま文庫、二〇一五年)などでそれが継承されている。
[4]トーマス・マン『ゲーテを語る』(山崎章甫訳、岩波文庫、一九九三年)六〇頁。
[5]同右、六一頁。
[6]ポール・ヴァレリー「精神の自由」『精神の危機』(恒川邦夫訳、岩波文庫、二〇一〇年)二二六、二二八頁。この論考についてはパスカル・カザノヴァ『世界文学空間』(岩切正一郎訳、藤原書店、二〇〇二年)でも言及される(三〇頁以下)。なお、ヴァレリーがこの精神=経済のモデルから、独自の抽象的人格を生み出したことも注目に値する。彼の思索的な小説『ムッシュー・テスト』(清水徹訳、岩波文庫、二〇〇四年)の主人公エドモン・テスト―ヴァレリーの知的分身でもある―は、ささやかな株取引で生計を立てながら、その純粋な精神の力によって「存在する一切をただ自分だけのために変形し、自分のまえに何が差し出されようと、それを手術してしまう」(二五頁)。このテストの「手術」によって、社会は数値の行列として再創造される。「八億一千七万五千五百五十……わたしは計算は追わず、ただこの未聞の音楽に耳を傾けていた。彼はわたしに株式市場の変動のありさまを伝えていたのだが、数詞の長い行列はまるで一篇の詩のようにわたしを捉えた」(三五‐六頁)。ヴァレリーの言う精神=経済は、物質的な商品というよりは、数値化された金融商品に近く、たえず評価の激しい変動にさらされている。しかも、この天文学的な数字の波動が夜の「音楽」となってテストを魅了するのである。
[7]「詩の社会的機能」(山田祥一訳)『エリオット全集3』(改訂版、中央公論社、一九七一年)二四九頁。
[8]イマニュエル・ウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』(川北稔訳、岩波文庫、二〇二二年)二三頁。
[9]同右、二〇頁。もとより、自己増殖そのものが目的になるというのは倒錯であり、利用可能な外部が枯渇すれば、このシステムはただちに行き詰まる。柄谷行人は『トランスクリティーク』(岩波現代文庫、二〇一〇年)で資本の自己増殖の欲動をマルクスのフェティシズム論から再考している。
[10]カール・マルクス『資本論 第一巻上』(今村仁司他訳、ちくま学芸文庫、二〇二四年)一四〇頁。
[11]磯崎新『日本の建築遺産選』(新潮社、二〇一一年)七頁。
この記事は2025年3月にPLANETSから刊行される、福嶋亮大さんの新刊「世界文学のアーキテクチャ」を期間限定で特別公開したものです。2025年3月17日に配信しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。