走ることは、苦しくてつらい──そんなイメージを持っていませんか? でも、それは過去のものとなりつつあります。気持ちよくて楽しい、日常生活の一部を彩るライフスタイルスポーツとしてのランニングが、ここ10年ほどで広まっています。
ランニングカルチャーの広がりに新たな動きをみる『走るひと』編集長・上田唯人さんと、自身も日常的に走っているPLANETS編集長・宇野常寛が対談。“走ること”の魅力やこれからの可能性、そして都市との結びつきについて、自由に意見を交わしました。
端的に言うとね。
走ることで街を捉えられる
宇野 2015年に上田さんにインタビューしていただいてから、もうめっちゃ走るようになって。時間が許すときは基本的に走るようにしているんです。僕みたいなアニメ評論とか書いている人間が走るようになるなんて、中学の同級生とかもびっくりしてますよ。インドアの権化みたいな男だったので(笑)。おかげさまで、すっかりランニングが趣味になりました。
上田 そうなんですね。2015年にインタビューさせていただいたとき、もともとウォーキングが好きだっておっしゃってましたよね。走るようになって、何か変わりましたか?
宇野 単純に、娯楽として走ることが楽しいなって思うようになりました。いざ走ってみると、意外と走れる自分とかを発見するわけです。それでいい気分になって、1日7キロとか走るようになって……ビギナーにありがちなことですが、案の定、足を痛め(笑)。その後は5キロくらいを無理なく走るようにしています。最近は、忙しくてなかなか走れなくなると、ちょっとフラストレーションを感じるほど。それくらい走ることが日常になっています。このごろ特に好きなのは、お出かけ先でのランニングですね。
上田 どのあたりを走られるんですか?
宇野 5〜6年前から三浦半島にハマっていて。浦賀あたりの海沿いを走って、スーパー銭湯に入る、という感じでよく走っていました。電車で1時間半くらいのところにパッと出かけて、ちょっと走って帰ってくる、みたいなことを早起きしてよくやっていたんですよ。それと、京都精華大学での講師もしているので、京都もよく走りますね。出張+ラン、みたいなことも面白い。
上田 お出かけや出張のとき以外で、日常的に走るのはどんなところなんですか?
宇野 普段は、事務所のある高田馬場あたりを走ることが多いですね。
上田 三浦半島や京都を走るときと、高田馬場周辺を走るときって、視点もぜんぜん違いそうですね。
宇野 違いますね。高田馬場を走っているときは朝起きてすぐに走ることが多いので、走りながら仕事の予定を考えたりしています。お風呂やトイレで事務的な用事のことを考えたり、アイディアを練ったりするのに近いですね。走る前って、「朝起きたばかりなのにわざわざ疲れることするのか」って思うんだけど、走ったあとは一度も後悔したことないです。一方で、三浦半島なんかを走るときは、ただただ「この休日を目一杯楽しもう!」っていう気持ちですね。
上田 僕もいろんな街を走るのが好きで、取材を兼ねて各地を走っているんです。3年前、キューバのハバナ市内を走ったとき、1960年代の旧車が走っている都市なので、どこに行っても排気ガスのせいであんまり呼吸が心地よくないことに気がついたり。走ることで、リアルな街の空気や情報も得られたりします。
宇野 走るようになってからわかったんですけど、走っている間ってスマホも見ないし、走ることと考えること以外が削ぎ落とされて、世界との向き合い方がすごくシンプルになりますよね。世界に対するアンテナをあえて絞ることで、見え方が変わるっていう快感が、僕はすごく好きです。
上田 あまり速いスピードで走ると、街自体から入ってくる情報量を咀嚼するのが間に合わなくなることがあるけれど、スピードを緩めると、心地よい速度で情報が入ってくる。だから、進んだり、止まったり、スピードを出したり、みたいなことを繰り返しながら、1時間ちょっとかけて10キロほどの距離を走るというのが面白い。走ることによって、街を捉えることの解像度がコントロールされるような感覚ってありますよね。
宇野 それはすごくわかります。時速10キロくらいのスピードで移動するからこそ見えてくるものっていうのはある。走ることによって、独特な角度から世界と接することができるのって、ある種の快楽だと思うんですよね。もちろん歩くことによって得られることも多いんだけど。走ることによって初めて見えることがあるというか。
上田 決して、歩くことで得られるベネフィットをかいつまんだものとは違うんですよね。あくまでも別のものであると。
宇野 歩くと街に包まれちゃうけれど、走ると街の流れを感じられる。たとえば高田馬場で言うと、諏訪通りあたりは比較的閑静な住宅街。それがちょっと北へ行って早稲田通り沿いに出ると、ブサイクなゾーンになる(笑)。その後目白のほうに行くとおしゃれなマダムの世界が広がって、最後にまたぐるっと回ってブサイク早稲田ゾーンに戻ってくる、みたいな。あの流れって、走って廻るからこそ感じられるものだと思います。短い距離のなかで、どんどん街の色が変わるんですよね。
上田 街を立体的に捉えられるような感覚がありますよね。その街に暮らすひとがどんな日常生活を送っているんだろう、と考えても、なかなかリアルにイメージすることはできない。それが外国だったらなおさらです。だけど、たとえば朝9時ごろにハバナを走ってみると、ここでは子どもたちが先生に連れられて、石碑の前で遊んでいる。一方で、1キロ離れた海岸では、釣りをしている30歳くらいの男のひとがめっちゃいる、みたいなことに出会うわけです。あと、交通量の多いバス通りと、住民がチラホラいるだけの路地のコントラストが極端だったり。そんな風に、その街で暮らすひとたちのリアルな日常を瞬間的に掴めるという面白さもありますね。「自転車でもできるんじゃないの」とか「クルマの窓を開ければできそう」みたいなことも頭をよぎったんですけど、それとは違う感覚というか。
宇野 時速10キロくらいだからこそのわかりやすさがありますよね。あれより速くても遅くても味わえない、街と街のつながりがある。
それと、ランニングは自由ですよね。僕はオタクなので、そんなにひと付き合いが得意じゃない。今でこそ、仕事がら初対面のひととも普通に話せるようになりましたけど、もともとは自分の世界に入りがちなんですよね。そんな僕でも、ランニング中にすれ違って爽やかに挨拶されたら、ついつい返しちゃいます。走っている間って、何者でもない〝ランナー〞になれるじゃないですか。ある種の心地よい匿名性があるんですよね。
上田 それわかりますね〜。
宇野 あれいいですよね。以前、仕事で1週間ほどアメリカにいて、宿がスタンフォード大のすぐ近くだったんです。それで、毎朝キャンパスを走っていたんですよ。西海岸は物価も高いし、僕は英語がしゃべれないし……居場所がないなあなんて思っていたけれど、ランニングしているときだけは溶け込んでいる感じがするわけですよね。近所の学生もおっちゃんも走っているし。
上田 それと同じような経験が僕にもあって。同じくハバナを走ったときにカメラを持って街の風景なんかを撮っていたんですけど、そのなかで、路地に座っていた老夫婦の写真を撮ったんです。どこぞの東洋人がいきなりカメラを向けて、怒るでもなく自然と微笑んで目線をくれるなんて、走っていなかったら撮れなかったと思います。そのとき僕がランナーだったから、街に溶け込むことができていたんじゃないかなと。スポーツという違う目的に興じているひとに対して警戒しない、みたいなことも、もしかしたらあるのかもしれませんね。
宇野 走っているひとが、自分に用があるとはまず思わないですもんね。あくまでも、通り過ぎるひととして捉えている。歩いているひとって、もしかしたら道を聞かれるかもとか、自分に用があるかもしれないという可能性を孕んでいるじゃないですか。でも、ランニングウェアを着て時速10キロくらいで走っているひとって、知り合いじゃない限りまず自分に話しかけてくることがない。究極的に言うと、風景の一部になるんだと思います。ランナーは、街の景色の一部としての、いわゆるモブキャラですよね。
上田 それは、街を走ることが当たり前になったからこそモブ化した、ということも言えますよね。
宇野 それは間違いないでしょうね。自動車があまり走っていなかった時代には、通るたびに子どもたちに「あー!」と指さされていたわけですからね(笑)。

走ることは〝つらいこと〞ではない
上田 『走るひと』をつくり始めた7〜8年前は、競技場的なものを飛び出して一般のひとが走るようになるっていうことがある種の新しいストリートカルチャーだと考えていたんですけど、最近はいろいろ変わってきていると感じています。日常生活の一部として走るひとが増えたことで、結果的に大会に出るひとの数も増えて、マラソン完走経験があるひとが多くなっている。すると、ある程度セミプロ化してくるんですよね。
宇野 いわゆるガチ勢のランナーたちもさらに増える。
上田 はい。それでどうなるかというと、たとえば代々木公園の織田フィールドを走るようになる。競技場のトラックを使って、トレーニングとして走るようになるんです。東京マラソンが始まってから10年以上経って、ストリートから始まった新しいランニングが、結局また競技場に戻ってきているっていうのは面白いというか。でも一方で、タイムなどは関係なしに、ただ走ることが好きだというひとたちも依然として増えています。
これまで『走るひと』を何冊もつくってきて、ちょっと偉そうな言い方をすると、途中までは啓蒙的なことが重要だと思っていたんです。「ランニングカルチャーはこうだ」みたいな。同時に、ミュージシャンやクリエイターだったり、アイドルの子たちだったり、「このひとたちも走っているんだよ」ということをとにかく見える化することで、「ランニングって広がっているんだな」と示す必要があると考えていました。だけど、だんだんセミプロ化するひとが増えてきたことで、そういったランニングの広がりについてはある程度前提が共有できたなというところがあって。みんな脚も強くなったし、たとえば女性がタイツとスポーツブラだけのスタイルで走ることが、2010年代前半だったらありえなかったかもしれないけれど、今の東京だったらありえる。
宇野 風景として定着してきている感じがしますよね。
上田 欧米化してきているというのもあるかもしれません。そういうスポーツライフが広がって定着してきたとき、走るひととしてできることが増えたなとも思っていて。それで、2018年に出した『走るひと5』では、僕たちもクリエイターとして新しい価値観を提示することが必要なんじゃないかとか考えるようになりました。これまでどおりリアルな良さを伝えることに加えて、クリエイトする観点が生まれたんです。それで『走るひと5』でやったのが、1月2日、3日の駅伝大会の傍らで撮影を行った「走るファッション」という企画です。日本の原風景のなかで外国人モデルを起用し、これまで誰も目にしたことがないようなファッションビジュアルを作りました。走ることを競技としてしか捉えてこなかったひとたちに対して、新しい文化が生まれていることを伝えていくためにも、『走るひと』としての見せ方は常に模索し続けているんです。
宇野 従来のマラソンに対するイメージって、「血反吐を吐きながら」という感じでしたもんね。
上田 そうなんですよ。そういう「つらいもの」としてのイメージがあるからこそ、1996年のアトランタ五輪で銅メダルを獲得した有森裕子さんの「自分で自分を褒めたい」という言葉が反響を呼んだわけです。高橋尚子さんがスターになったのも、もちろん2000年のシドニー五輪で金メダルを獲ったからということもあるけれど、彼女が見せた、弾けるような笑顔が人々を惹きつけた。苦しくてつらい〝マラソン〞のイメージと対照的だったからこそ、より輝いて印象的に映ったということなんですよね。しかし、メダリストたちのスター性や知名度に反して、一般のひとたちの間に走ることが広がることはほとんどありませんでした。このときはあくまでも、〝みるスポーツ〞としてマラソンが消化されていたんです。
宇野 走ることはつらいというのが大前提で、オリンピックでのアスリートの活躍も他人の物語の1つとしてしか捉えられなかった、ということですね。箱根駅伝ファンが走っているわけでないというのも似ているかもしれません。自分がそのスポーツをすることよりも、基本的には自分たちの国の代表や、思い入れのあるチームに感情移入することで、高揚感を得ると。だけど、誰もが発信力を持つ今の時代、人々の関心の中心は、他人の物語から自分の物語へと移ってきていると感じています。そういった背景は、ランニングをはじめとするライフスタイルスポーツの人口が増加していることにも関係している。僕自身がアニメやアイドルなどモニターの中のフィクション、つまりある種の他人の物語について批評してきた人間だからこそ、この変化を実感しています。だから、近代スポーツがさらに進化していくには、スポーツをとりまく物語をいかに自分ごとにしていくかということが必要なんじゃないかと考えています。
それにしても、ライフスタイルスポーツの存在感は年々大きくなっていますよね。一人でも気軽にできるという、敷居の低さも魅力の1つだと思います。
上田 敷居の議論で言うと、たとえばフットサルがサッカーにもたらした影響は大きい。趣味でサッカーをしたくても、11人集めるのってなかなか大変ですよね。昔は、団地だったり、部活だったり、あるいは企業のサークルだったりの共同体の規模感にフィットして、サッカーも草野球も今よりやりやすかったと思うんですけど。今では団地に子どもがいないとか働き方が多様化しているとか、いろいろな要因によって、共同体としてのスポーツがなくなってきています。こういった状況のなか、日韓ワールドカップの前後でフットサルのコートが激増しました。すると、少し余談にはなりますが、新しいカルチャーとして、サッカーとは全く違う文脈からさまざまなブランドが参入してきたんです。その証拠に、フットサルブランドのシェアトップはアスレタというブランドで、2位はスボルメという日本のドメスティックな、ストリートから出てきたようなブランド。つまり、アディダスやプーマではないんです。するとどういうことが起こるかというと、服も、ボールも、コートも、全てが新しいデザインのものになって、そこで生まれた新たな勢力が今度はサッカーに影響を与えるような状況が生まれました。話を戻すと、少なくとも今の日本国内において、ライフスタイルとしてのチームスポーツの最適な単位は、フットサルだったり、バスケットの3on3くらいであって、むしろそちらが主流になっているということです。でも、最近ではそれすらも仲間を集めるのが大変になってきている。
宇野 その流れのうえに、究極的に一人でできるランニングがあるわけですね。
上田 そうです。だから、日韓ワールドカップをきっかけにフットサル文化は急速に拡大・定着して、その後2008年ごろには頭打ちになったんですけど。ランニング人口は、今後もさらに拡大し続けるはず。ヨガやトレーニングも含めれば、もっと大きなマーケットになっていくのは確実だと思うんですよね。
宇野 ライフスタイルスポーツって、今までは本当に自分との戦いというか、自己満足の世界だったはずが、誰もがソーシャルな発信力を持つことによって、一人での体験も共有できるようになった。従来は、スポーツと言えばゲーム的に競って勝つことだったのが、自分の体験や感覚をシェアすることの快楽へと、比重が移ってきている。ある意味、わかりやすい刺激という点では、競技スポーツのほうがスリリングではあったと思うんですよね。一方で、ライフスタイルスポーツは自分の身体や内面と向き合う作業だったのが、その体験をシェアできるようになって、快楽の度合いが大きく増したのだろうと感じています。
上田 なるほど。ゲームを楽しむような感覚に取って代わったわけですね。
宇野 人間って、気持ちよくないことは支持しないので。人々は、この20年くらいで自分の体験をシェアするっていう快楽に目覚めたんだと思うんですよね。「こんなおいしいものを食べました」「こんな美しい景色を見ました」「イベントでこんなに盛り上がりました」とか。以前は、久しぶりに会った友達にしゃべるくらいしかこの快感を得る回路がなかったのが、毎日共有できるようになって、その喜びや楽しさに多くのひとが気づき始めた。その素材のひとつとして、ライフスタイルスポーツはすごくぴったりだったんでしょうね。誰でもすぐに真似できるという気軽さ、敷居の低さがフィットした。
上田 それに、走る場所を変えれば、発信する内容も簡単に変えられますからね。

宇野 そうそう。シチュエーションが変われば見せ方も変えられるし、毎日同じコースを走ったとしても、定点観測的な価値を帯びるじゃないですか。どちらも、自分の物語として非常に今の時代と相性がいい。
上田 習慣化させることに対して快楽を得ているひともいますよね。いわゆる、アプリ上に毎日のランニングの記録が溜まっていくことに喜びを感じるような。宇野さんは、そのあたりいかがですか?
宇野 僕も一応アプリで記録をつけています。単純に、数値化して可視化してくれることによって、達成感を得やすくなるというのはありますよね。競技スポーツって、たとえば野球で言うと防御率だったり打率だったり、数値化されがちじゃないですか。ランニングでは、自分の状態や習熟の度合いを、より手軽に細かくデータ化できるということに面白さを感じているひとも多いでしょうね。僕自身の習慣化の話をすると、上田さんに最初に取材してもらう前も、一時期ダイエット目的で走っていたことがあって。あのときは、自宅から新宿東口のヨドバシカメラまで3キロ弱走って行って、毎回必ずトミカを買って帰ってきていたんです(笑)。一個ずつミニカーが増えていくことに、すごく満足感を覚えていました。ヨドバシの店員さんにも顔覚えられましたもん。「ランニングですか?」って(笑)。
上田 それってある意味、ラジオ体操のスタンプと一緒ですよね。自分の努力や行動を可視化してくれることのうれしさがある。そうやって自分のなかで得られる達成感もあれば、今の時代で言うと、ひとに発表することで得られる快楽もあるわけですよね。
宇野 僕ももともとは野球だったり、競技スポーツを見るのが好きだったからよくわかるんですけど、みるスポーツはツイッター向きなんですよね。みんなで選手の行動や監督の采配にああだこうだ言うことでつながるのに向いている。一方で、ライフスタイルスポーツ、つまりするスポーツはインスタに向いている。体験のシェアだから、ビジュアルでわかりやすく伝わることが好まれます。それに、発信された情報を受け取る側としても、適度に身近なひとが走っているのを見ると、自分もやってみようかな、と思えたり。スターがテレビの向こうで走っていることよりも、ちょっと憧れる存在のモデルが朝走って楽しそうにしている、というシーンが、雑誌の4分の1ページでも紹介されているっていうことのほうが、単純に共感を呼ぶんじゃないでしょうか。
上田 それは、まさに『走るひと』創刊のときに抱いていた仮説そのものです。だから、走ることの良さを知ってもらって、走るひとが増えればいいなと考えたとき、アスリートではないひとの姿を切り取る雑誌にしようと考えました。創刊から5年以上が経って、この状況が変わらないかと言ったら、いくつかポジティブな変化もあって。ひとつは、走るひとが増えたことによって、アスリートに対して、身近な体験を通して尊敬の気持ちを抱く機会が増えてきていると感じています。たとえば、マラソン大会に向けた練習会で、コーチとして箱根駅伝に出場した経験を持つアスリートが来てくれたりすることがあって。一般のランナーにとって、箱根ランナーも身近な存在になりうるんです。すると、箱根駅伝の中継で伝えられる感動の物語とは違うことを、イベントなどを通して得ることができます。これはきっと、一般のランナーにもアスリートにも、双方にとって良いことのはずです。
走ることによるゆるやかなつながり
宇野 ちなみに、走ることが人々の間で一般的になってきたのはいつごろからなんですか?
上田 僕らは、2005年ごろだと考えています。ちょうどこのとき女性誌『FRaU』が〝走る女は美しい〞という企画を打ち出しました。同じころに「NIKE Beautiful Day In Odaiba」というヨガとランニングのイベントが開催されて、4000人の女性が集まりました。当時はみんなヨガパンツを履いて走っていて、今のようなスタイルはまだ確立されていないけれど、女性が走るということのリアルな場が生まれた瞬間だと言えます。現在のランニングカルチャーの文脈につながる、一歩目という感じですね。ただ、このときの〝女性とランニング〞には、「スポーティセレブ」のイメージがあって。要は、一部の恵まれた環境の女性が、「こんなヘルシーな生活いいでしょ?」と、雑誌やブログを通じてアピールするためのものでもありました。だから、多くのひとは憧れを抱きながらも、自分ごととしては咀嚼できなかったんですよね。
その後2007年の第1回東京マラソンが開催され、2010年以降はカラーランやバブルランのようなファンランブームも起こります。でも、ファンランはあくまでも一過性のブームだったことや、海外でのカラーパウダーの事故などもあって、2015年ごろにはほとんどのイベントがなくなってしまいました。それからは、スポーツブランドのマーケティングを含めて、ストイックなイメージへ回帰する時期なんかもありながら、最近では、セレブではなく共感、ブームではなくライフスタイル、それから、純粋に身体を動かすことの良さだったり、ポジティブで本質的な側面が支持されてきています。
宇野 なるほど〜。たとえば、今の40〜50代にはトレイルランに行って、フェイスブックに投稿して……みたいなひとが多い気がしているのですが、それはいつごろから走り始めたひとたちなんでしょう?
上田 いくつかあると思いますが、ひとつは2005年ごろに紹介されることが多かった、セレブの文脈に近いものは確実にあると思います。経営者がトライアスロンやトレイルランをやる、みたいな流れってあったじゃないですか。リーマンショックまでの間にJASDAQ上場したような経営者たちが、軒並み走り始めたという流れは、このときと符合するんですよね。経営者たちが、世間だったり社員だったりに向けて、自分の強さやライフスタイルを見せるためのひとつのツールにもなっていたと言うか。あとは、本当に修行僧や禅の教えのように、ただ黙々と自分と向き合って走るという方々もいて、時期的には同じタイミングで増えていった印象があります。
宇野 あれはあれで楽しそうだけど、ある世代の男性にとって、走ることってすごく自己修練的ですよね。ある意味マゾヒスティックな快楽とも言える。でもその感覚って、今の20〜30代の若い世代にはあんまり共有されていない気がします。僕もアプリを使って記録はとっているけれど、タイムとかはそんなに気にしない。坂道が多かったからちょっと遅かったな、くらいの情報を得て、それで終わり。ちょっと疲れたり、足が痛くなったら歩くこともあります。ガチで走っているひとたちは、ひたすら肉体を追い込むことで自己確認をしている部分もあると思う。極端に言うと、立ち止まることは悪、とさえ捉えていそうなひともいます。これって、ジムで身体を鍛えるときの思想に近いですよね。一時期僕もジムに通っていたことがあるのですが、続かなかったですね〜。雨の日とかも運動できていいなとは思いますけど。
上田 ジム通いが続くひと、なかなかいませんよね。たとえば一時期ズンバ(ダンスエクササイズの一種)が賑わっていたのは、おばさまがご近所さんと交流する場として機能していたからであって。結局ジムもコミュニティ化しないとなかなか続かない。楽しく続けているひとは、だいたいクラスに所属しています。
宇野 ランニングは一人でも続けやすい自由さがいいところでもあるけれど、ランニングクラブみたいなものがもっとあってもいいようにも思います。
上田 それで言うと、ランニングにもコミュニティができていて。とくに今の感覚にフィットするのは、走ることを目的としていないコミュニティだったりするんです。ランニングはあくまでもきっかけで、極端に言うとランニングの話をしなくても集まれるコミュニティ。たまに、一緒に参加したら楽しいから山中湖のレースに出て、そこらへんのペンションに泊まって帰ってくる、みたいなことはするんですよ。そういう、ある意味カフェだったり、サロンみたいな場に近いランニングのコミュニティがもっと増えてくると、ライフスタイルにさらにうまく走ることを取り入れられるひとが増えていく感じはありますね。
宇野 今の都市型のライフスタイルのひとつとして、ランニングというものを自分の生活に組み込みたいと思っているひとって、食べるものにも着るものにもそれなりに気を使うはず。さらに、習慣的に走るうえでは住む場所も結構重要になってくるじゃないですか。だから、ランニングって、すごく衣食住に直結していますよね。そして、ランニングをきっかけにしたコミュニティは、衣食住に対する価値観が似ているひとたちが集まるので、当然ライフスタイルサロンのようにもなっていく。むしろランニングよりも衣食住のほうに重点が置かれることがあるかもしれない。それに、ランニングでつながりあう関係性って、きっとちょうどいい距離感なんだと思うんですよね。24時間365日、ひとつの共同体に所属するっていうのとは違って、もっとさらさらしたつながりというか、心地よい距離感の関係性を築ける。
上田 コミュニティっていうと、どうしても町内会みたいなものを考えがちなんですけど、もうちょっとゆるやかなものなんですよね。ただ同じような習慣をもつひとたちが、半径5キロくらいの距離に住んでいるみたいな。そのひとたちが週末の夜に自然と集まって、健康的な食事を出してくれるちょっといい感じのレストランで食事をする、くらいの感覚で、一緒にランニングをする。
宇野 そうやってつながる関係性って、あるようでなかったと思います。純粋な友人の関係もあれば、同じ習慣をもっているひと同士、たとえば毎週1回、朝の1時間だけ顔を合わせる関係性もあり得るわけですよね。町内会のラジオ体操みたいなものとも違う、出入り自由で来なくなったとしても誰からも非難されることがないような。
上田 そういった関係性で言うと、湘南地域なんかにはあるみたいですね。湘南と言っても広いので、いろいろなところから海岸沿いを走ってくるじゃないですか。それでなんとなくいつもすれ違うひとと会釈したり。他人なんだけれど、習慣でつながっているんです。こういうのは、もしかしたらセントラルパークとかには昔からあったのかもしれないですけど。これが日本の都会で言うと、公園でも同じことが起こりうると思っています。たとえば代々木公園とひとくくりにしても、周りには渋谷もあって初台もあって松濤もあって、原宿もある。というときに、それぞれに住んでいるひとが走りにきて、公園を1周して帰る、みたいなことだって、ある意味習慣を共有していると言えます。これが少しずつ色濃くなって、たまに挨拶でもすれば、それはもうコミュニティなんですよね。
宇野 体験や習慣でつながると、結果的に、普段は関わることのないような層のひとにたちともゆるやかにつながれたりして、これが良い他者性をもたらしてくれるとも思います。

新しい価値を提示する
上田 東京マラソン以降、ランナー人口は1000万人になったといわれますが、中身を見ると、従来のいわゆる〝ガチランナー〞に近い500万人のランナーに、新しい500万人のランナーが加わった、きれいな二層構造になっています。その新しい500万人はこれまでの話にも出てきたように、ただ街を走ることや友達と走ることが好きだったり、タイムもあまり気にしないような若いひとたちのこと。その層にとってのランニングは、もともといる500万人のランナーたちとは全くと言っていいほど違うものでもあります。
宇野 それで言うと、マラソン大会だったりランニングのイベントも、もっと若い世代に向けて変わっていく余地がありますよね。もちろん、都市のインフラも、メディアも変わっていかなきゃいけない。
上田 毎年5月に開催されるアメリカのブルックリンハーフマラソンは、参加者の雰囲気だったり、エキスポのロケーションも含めて最高なんです。若いひとも多くて、男女のバランスもよくて。本当にランニング好きのひとたちが、友達同士で「行こうぜ」みたいな感じで参加していて。音楽バンドのライブがあったり、大会Tシャツがイケてたり。全部クールなんですよね。

宇野 フェスみたいなものっていうことですよね。日本でも、フェスとして設計すると良いと思う。〝マラソン〞っていう言葉を使わないのもありかもしれません。
上田 すでに染み付いたイメージと違った見せ方をするには、それもひとつの手段かもしれませんね。アメリカのランニングカルチャーには、見習いたいことがたくさんあると感じています。ただ、現時点ではまだ、アメリカと日本のランニングを取り巻く状況にはギャップがある。その要因のひとつには、人口の比重の違いがあると考えています。アメリカって、いわゆるミレニアル世代、つまり今で言う26〜39歳くらいのひとたちが人口分布の山になっているんです。それもあって、20代に向けて、ユースカルチャーとしてのランニングだったり、スポーツマインドをきちんと伝えていこうという気運があるんですよ。
一方で、日本だと団塊世代と団塊ジュニア世代が人口の山になっていて、どうしても40〜50代にマーケティングの照準を合わせざるを得ないみたいなことがあります。実際に、東京マラソンや大きな市民マラソンの参加者の平均年齢って、40代後半より上なんです。
宇野 まさに団塊ジュニアが中心なんですね。団塊世代も、70歳くらいだからまだ現役で走るひともいますよね。
上田 そこのギャップがあるからこそ、アメリカと日本では状況が違うということを前提に考えないと、かなりちぐはぐな議論になってしまう。
宇野 逆に考えると、若者が多いのなんてアメリカくらいのはずなので、どちらかと言うと「若い世代に深く刺す」みたいな形の提案が何かできるといいですね。
上田 確かにそうですね。あとはインバウンドにはまだまだ可能性があります。アジアを見ても、たとえば台湾は日本よりも平均年齢が6歳くらい若い。それでいて、ピラミッドの形は日本と似ているので。日本だけで見ると若い世代のボリュームが弱く見えても、台湾なり、アジア全体で捉えれば十分な市場になりえます。
以前、代官山蔦屋書店で「走るひとフェア」を開催したことがあるんです。そこでは、売り場のひとつの島で、走るひと編集部が選書した本だったり、グッズだったりを世界中から集めて紹介しました。そのときに感じたのが、海外のランニングやスポーツカルチャーを扱う雑誌や本って、僕らにとっての多くのヒントが詰まっているということ。そしてその多くが、インディペンデントマガジンなんですよね。海外ではそういう風に、草の根から新しいカルチャーが生まれていて、ランニングだけではなくいろいろなスポーツに対してフラットに愛を込めて編集している感じがすごく素敵で。美意識も高いですし。こういうものが日本にはまだほとんどないからこそ、紹介していくことに意義を感じました。

宇野 ランニングツーリズムみたいなことも、もっとあっていいと思うんですよね。最初に話したみたいに、走るためにどこかに行くっていうことがあってもいい。
上田 それがある意味一番楽しいですからね。それで言うと、マラソンの大会に泊まりがけで参加しにいくのもひとつだと思います。
宇野 東京でのカジュアルなイベントももっと増えたらいいですね。なんか、オタクが1回コミケ行ってみました、くらいのカジュアルさで参加できるような敷居の低いイベントを。だからやっぱり、フェス化ですね。イメージ的には、J-WAVEを聴いているひとたちくらいのカジュアルさ。J-WAVEを聴いているひとたちっていうのは、知的で文化的でホワイトカラーなんだけど、めちゃめちゃ専門知識があるわけではないじゃないですか。つまり、音楽は好きなんだけど、InterFMを聴くわけではない。自分から能動的に音楽を探りにいくほど好きっていうわけじゃないひとたち。
上田 そうですね。文化的なものに興味はあるけど、みずから掴みにいくよりはアンテナを張っている感じ。そういった層のひとたちって、サードウェーブコーヒーの主要顧客ともかぶっていそうですね。
宇野 かぶっていると思います。それくらいのひとたちでもハードルを感じずに参加できるような、間口の広いものが必要というか。東京マラソンはもちろん楽しそうで、ランニング初心者もたくさん応募するけれど、一方でガチで走るひとも多くて競技性があったり、そもそも倍率が高すぎるという敷居の高さもあるじゃないですか。走ることをライフスタイルに組み込んでいるひとのなかには、それで参加をためらうようなひともいると思うんです。だからこそ、ちょっとだけ生活を豊かにしたいとか、走ることの楽しさを再発見したい、っていうひとたちが中心になるイベントが欲しいですね。
上田 それに通ずる話で言うと、50年近くの歴史を持つ老舗スポーツショップの経営がうまくいかなくなった、ということがあって。今は再建しているところなんですけど。世間はランニングブームだと思っていたのに、割とガチで走っているひとたちがリスペクトしてきた店が立ちゆかなくなった。つまり、ランニングブームによって伸びていたのは、いわゆるガチ勢とは別の新しい層だったってことなんですよね。
宇野 さっきの話でたとえると、InterFMじゃなくてJ-WAVEが伸びてたわけですね。確かに、僕がウェアなどを見るときはオッシュマンズに行くことが多いです。きっとその違いと同じですよね。たぶん、それは関心領域の違いの問題で。僕みたいな〝ゆる層〞の関心は、スポーツというよりもライフスタイルのほうにアクセントがある。従来のランナーのみなさんは、スポーツにアクセントがあるように思います。
上田 昔から専門でやっているひとが、そのマインドの変化に対応するのがなかなか難しいっていう問題もあるんですけど、逆に言えば圧倒的チャンスなんですよね。
宇野 すそ野をガッと広げていくという意味でね。……本当、ランニングのフェスやりたいですよ。メディア主導でやるのがいいんじゃないですか? それこそ、走るひと冠でもいいし。絶対やるべきだと思います。「マラソン」とは銘打たないフェス。
上田 やりたいですね。それに近いことだと、僕たちは「フジロックラン」っていうのを毎年やっていて。フジロックの朝に、会場近くの苗場の自然のなかを走るというイベントです。これ、あくまでもメインはフジロックなんですよね。フジロックを精一杯楽しむための、ウォーミングアップとしてのランニング。これが、告知をほとんどしなくても各日100人くらいのひとが早起きして集まってくれるんです。



宇野 朝からそんなに集まるんだ。すごいですね。ある意味、夜更かしがエクストリームであるように、早起きもエクストリームですよね(笑)。
上田 確かにそうですね。今までは夜更かしのエクストリームな不良性に意識がいきがちだった。それで言うと、ロックミュージシャンに走っているひとが多いのも、じつはそっち側のエクストリームだったりしますよね。僕たちはこれまでいろんなひとにインタビューしてきましたけど、本当にロックミュージシャンがめっちゃ走ってるんですよ。表現したり、葛藤を抱えたり、ある種の極端な生き方をしているひとたちにとって、走ることがフィットしているというのは面白い。フジロックランのようなイベントを、都市部でも何かできたらいいなと考えているんですけどね。
宇野 ビールフェスみたいなのと組めたらいいですよね。走ったあとで、たっぷりカロリー摂ることになるという(笑)。それこそ、食品メーカーや飲料メーカーのブランディングとうまく結び付けられないかな。
上田 いいですね〜。たとえば、〝走る〞ことをテーマに、スポーツやアパレル、飲食などのさまざまなブランドが出店していたり、アーティストが何かつくっていたり、トークセッションが開かれていたり、ライブが行なわれていたり……たくさんのプログラムのなかのひとつに「みんなで走ろう」みたいなことがある、くらいの塩梅でもいいと思うんです。実際に走ることだけがメインじゃなくて、ランニングカルチャーに広く触れられるイベントというか。
宇野 そうですね。あるいは、とにかく歩いてもいいし、極端な話、ズルしてもいいんだけど、いくつかのチェックポイントをまわってゴールするっていうのもありかもしれない。僕、函館の高校で寮に入っていたんですけど、「速歩遠足」っていう謎の行事があって(笑)。朝5時くらいに叩き起こされて、山奥の小学校にポンと置いてこられるんですよ。それで、とにかく交通手段を使わないで帰ってこいって言われる(笑)。一応制限時間があって、早歩きくらいのスピードで行かないとだめなんですよね。運動部は走って、順位を競い合ったりする。ときどきチェックポイントがあって、先生がバナナとかくれるんです。
上田 エイドステーション的な感じですね(笑)。
宇野 それで、各チェックポイントでハンコをもらってゴールすると、PTAのおばちゃんがなぜかおしることキムチをくれる(笑)。なんかああいう感じで、走ってじゃないと行きづらいところにチェックポイントがいくつかあって、それを全部まわるとゴール後にライブを観られるとか。
上田 いいですね。ランニングの新しい価値提示につながると思います。
ランナーが根付く街へ
上田 やっぱり、メディアやスポーツブランド各社と話していても、「ランナーのいる景色をつくって盛り上げたい」ということはキーワードになっています。
宇野 だからこそ、街づくりを考えるうえでも、ランニングカルチャーは大事だな〜と思っているんですよね。走れる街ということは、要はちゃんとした道がある街というか。いろいろな街を走るようになると、走りやすい街と走りづらい街ってありますよね。たとえば、アジアの大都市はなかなか走りづらい。これは、最近急速に発展してきたことで、超ごちゃごちゃしたゾーンと、ものすごく大きな幹線道路があるようなゾーンに二分されているからじゃないでしょうか。この中間くらいのサイズ感が、走るには適していると思うんです。
上田 確かにそうですね。たとえば台北とかって、都市部の人口密度がめちゃくちゃ高いじゃないですか。縦に長くてバイクが多くて……みたいな。物理的に、ランナーが走るスペースがとりにくいんですよね。
宇野 逆に香港島とかで言うと、でっかい道路とかしかありませんよね。横断歩道があんまりなくて、曲がるところを間違えると目的地にたどり着けない、みたいな(笑)。ランナーが定着するためには、適度なすき間がないと。ごちゃごちゃしすぎていても、すき間がありすぎてもだめ。
上田 そうですね。2016年のリオ五輪を観に行ったとき感じたのが、ビーチ沿いだったり、要は観光客がいるような場所はランニングルートがあって、現地のひとじゃないひとたちが走っていたんです。でも、街のなかは走れるところがほぼないんですよ。あれはもう、都市計画的に観光地的な作り方をしているところと、旧市街地みたいなところの切り分けが明確。あそこまで明確だと、ある意味走りやすいんですけどね。
宇野 でもどうせだったら、完全に切り分けられたゾーンよりも、ある程度街の文脈を味わいながら走りたいですよね。それで言うと、川とかがあるとやっぱり走りやすいわけです。僕が京都を走るときは、ほとんど鴨川沿いを走っていますね。
上田 確かに、川好きっていうひとは結構います。
宇野 川は人間の都合に合わせて流れていないから、川沿いを走ると、整備された公園のようなゾーンもあれば、昔ながらの住宅地みたいなところもあるじゃないですか。だから、つくられた道路に沿って走ることはある意味通読で、川沿いを走ることは乱読なんです。ちなみに、神田川とかすごく走りづらいですけど、もし走ったら結構面白いと思います。東京がもうちょっと走りやすい街になってくれたらうれしいな〜。走りやすさで言うと、東京って人口の割にはランニングステーションが多くないイメージがあります。
上田 そうですね、ランステ少ないですね。ランニングステーションってコンセプトは素敵なんですけど、ビジネスモデルとしてもコンテンツの魅力としても、単体で存在できるものじゃなかったっていうのが最近の総括かなと思っていて。一時期いろんな事業者がランステをつくりましたけど、新しいランナーに対してそれほど響かなかったんですよね。それでまた徐々にランステが減ってきている。いわゆる従来のストイックなランナーが好むようなデザインで機能だけを提供しても、若いひとが来なかったという。
宇野 部活動の部室みたいにロッカーとシャワーが並んでいる感じですよね。だから僕は、おじいちゃんがやっていて跡継ぎに困っているような古い銭湯を買い取って、ランステの機能を備えた施設にするのとかいいと思うんです。あとは、銭湯って午後から営業するところが多いので、明け方から開けてランステにするとか。そこで、ちょっとした飲食なんかもできたりすればいい。
上田 ランニングだけが目的じゃない場所にするっていうことですよね。代々木八幡にある「&MOSH」は、ランニングステーションに、整骨院やカフェが併設されている。そんなイメージで。

宇野 僕もランニングのあとにスタバでパッションティーを飲んだり、寄り道してだらっとすることがあるんです。街を楽しむランニングのためには、東京で言えばランステがもっと必要だし、そこにカフェがあったりいろんなものと連動した場所になるといい。
それと今話していて思ったのが、走れる街とはつまり、朝から開いている店がいっぱいあることなんじゃないかと。銭湯もカフェも、もっと早朝から開いているところが増えたら、朝走るひとたちが集まる場になる。健康的な野菜がとれるような、朝ごはんを出してくれるお店とかもあるといいですね。朝活的なワーキングスペースと結びついていてもいい。全部の店が開いている必要はないけれど、なんとなく街全体が朝方になっていることって、結構大切だと思います。街が朝方になれば、時間の使い方もさらに多様化していくはず。今だと、たとえば早起きしてひとっ走りして、スタバでパッションティーでも買って帰ろうと思っても、スタバがまだ開いていないみたいな。
上田 少し営業時間が早まれば、ぐんと新しいカルチャーがつくられていきそうですよね。せっかく新しいランナーが増えているのだから、ランステのような場所も、たとえばいい感じのカフェをやっているひとたちが新しくつくってもいい。そういう空間が増えていけば、走ることがもっと自然にライフスタイル化していくと思います。
宇野 まずは、東京のどこかを走れるエリアにしていくところから考えてみてもいいかもしれませんね。たとえば、『PLANETS』のvol.9をつくったとき、千駄ヶ谷のほうへよく行ったわけです。それで感じたのが、あの辺はスポーツの大会やイベントを観に行くくらいしかやることがないんですよ。ご飯を食べるところもほとんどなければ、買い物スポットもない。新宿からも渋谷からもアクセスのいい、あんなにいい場所にありながら、本当に一目的のためだけにあって。そのあり方が、ある意味「するスポーツ」と「みるスポーツ」の隔絶を象徴しているとも言えるかもしれない。だから、スポーツっていうのはハレの日にイベントとして観に行くものじゃなくて、日常にあるものなんだと理解するところから、走れる街づくりが始まるんですよ。
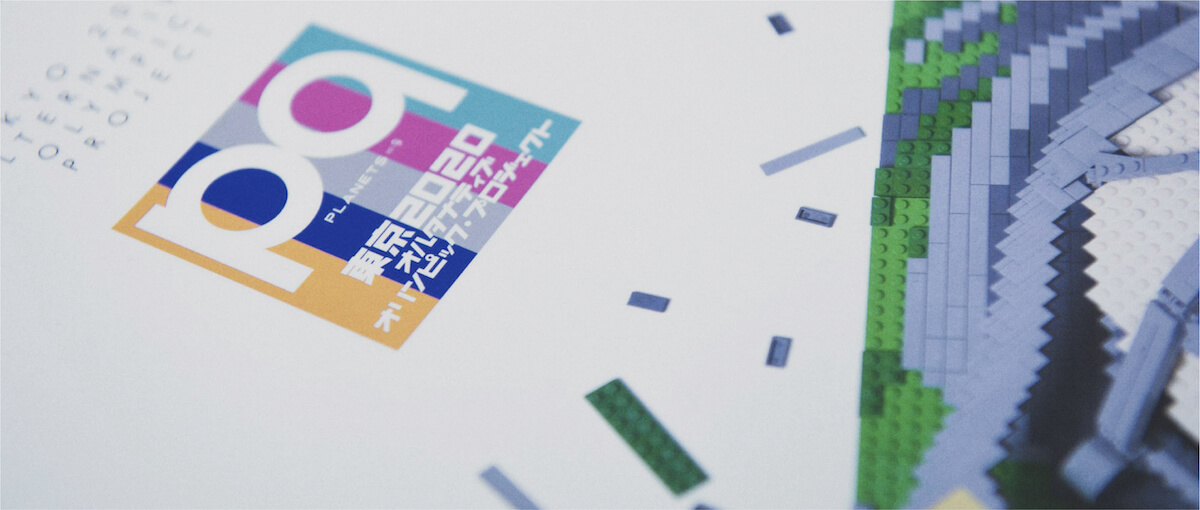
上田 そういう前提が共有できてくると、逆に、これからカフェを始めようと思っているひとが、ランナーが通るルートだったり、彼らの行動を考えながら出店する、みたいなことにもつながっていきそうです。今までになかった相乗効果が生まれそうですね。最近海外で台頭してきている雑誌とかを見ていると、彼らはほとんど〝ライフスタイルとしてのスポーツ〞を切り口にしているんですよね。登場人物が必ずしもアスリートではなくて、アーティストだったりクリエイターだったりが、この街でどうやって走っているか、みたいなことが描かれている。たぶん、それは僕たちが日本でやっていることにもすごく近くて。いわゆるアスリートじゃないひとがライフスタイルの一部として走っていることを、とにかく見える化しているんです。そして、ある程度見える化したら、場合によっては行政だったり、地域社会だったり、企業だったり、仕組みをつくる側にいるひとたちに向けて、働きかけを行っている。僕たちもそういう段階にきているようにも思います。
宇野 これは今パッと思いついたことですけど、1990年代の渋谷って、サブカルチャーの街だったわけですよね。要は、渋谷って団塊ジュニア世代の街なわけですよ。僕よりも5歳くらい上のひとたちが、渋谷の一番いい時代に青春を過ごした。だから、彼らが歳を重ねるごとに、サブカルチャーからライフスタイルの流れになっていくことは、当然出てくるはずなんです。そのことに、渋谷という街自体があまり気づいていなくて、ちょっと無理に若作りしている街になりかけているようにも感じます。もはや〝渋谷=若者の街〞ではないことを、いかにポジティブに捉えていくかっていうことだと思うんですね。
上田 渋谷をライフスタイルスポーツの街としてデザインするのはやってみたいですね。インバウンドの今後を考える視点も重要になってきそうです。
宇野 そうですね。インバウンドに今後も力を入れるならば、渋谷での新しいライフスタイルを見せることはかなり面白いはず。渋谷を走れる街にする方法、考えたいですね。


[了]
この記事は、2018年に刊行された『PLANETS vol.10』掲載の同名記事を再掲したものです。あらためて2021年5月6日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

