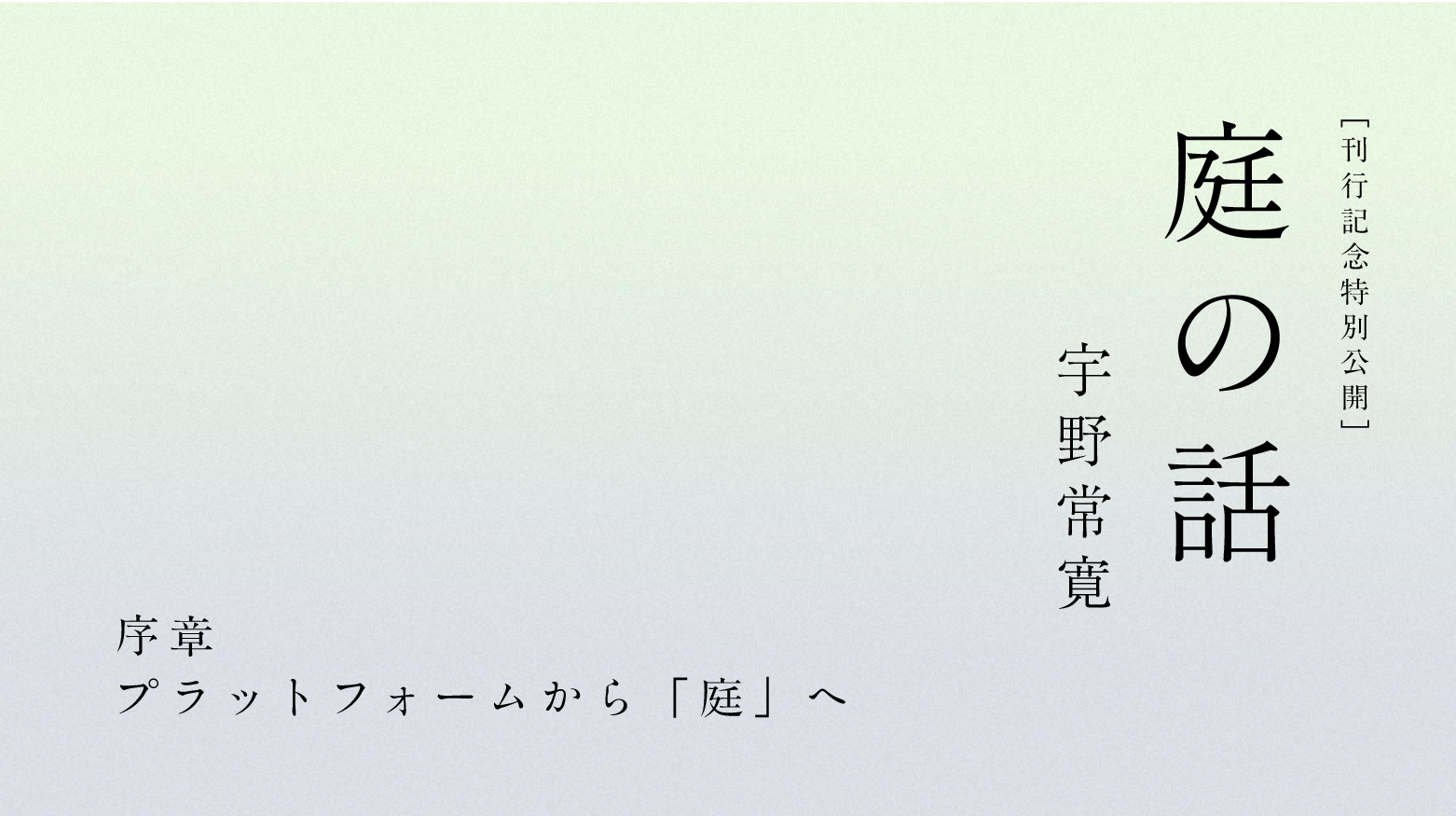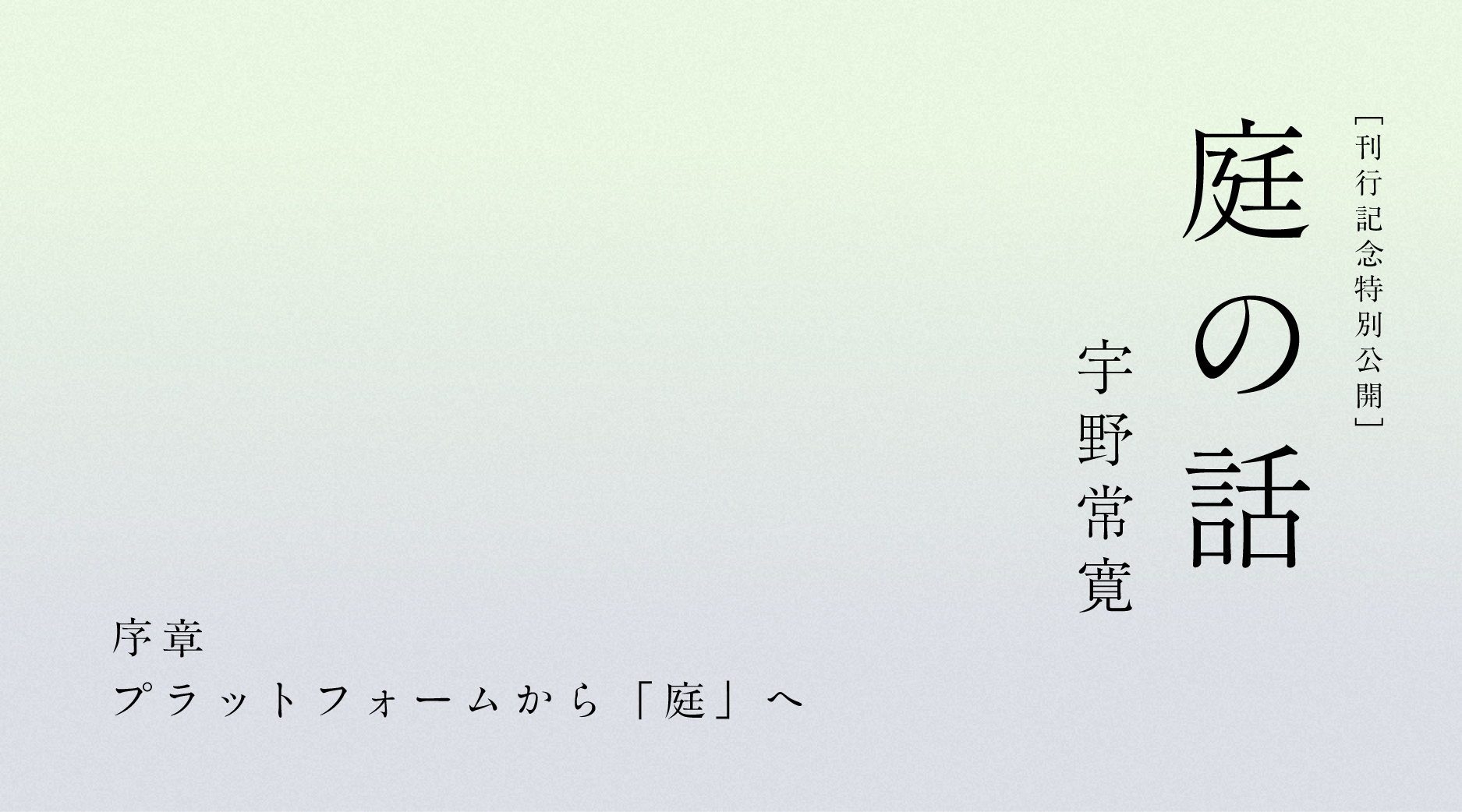編集長・宇野常寛の新刊『庭の話』が12月11日に刊行されます。「群像」で1年半連載したものを、丸1年かけてブラッシュアップしました。「たぶん、今までの僕の本の中で一番遠くまで行けた本だと思います」。『遅いインターネット』から4年、その続編であり(かなり変わったかたちでの)アップデート版です。
プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?
ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想します。
端的に言うとね。
1 キーウの幽霊
いまや懐かしい話だ。ロシアがウクライナに侵攻を開始した日、つまり開戦の翌日に当たる二〇二二年二月二十五日のことだった。ロシアの侵攻に抵抗するウクライナの人びと、そしてウクライナを支持する人びとのあいだで、ある噂がネットを通じて拡散していった。それは、ウクライナのMiG-29戦闘機を操縦するあるエースパイロットが、開戦から三十時間のあいだにロシアの戦闘機を六機撃墜したというものだった。
この「噂」には、約二十秒の短い動画が添えられていた。キーウの市街地のビルの隙間から見上げるように撮影されたそれは、上空を飛行する機影とその爆音を一瞬だけとらえていた。このエースパイロットは「キーウの幽霊」と呼ばれ、瞬く間にロシアの侵略に対する抵抗のシンボルの位置を獲得していった。ウクライナの前大統領ペトロ・ポロシェンコは、「キーウの幽霊」その人であるとするパイロットの画像をTwitter(当時はまだ「X」という名称ではなかった)に投稿し、欧州連合のウクライナ大使ミコラ・トチツキーは「一人のウクライナのMiG-29ジェット戦闘機パイロットが、ロシア人との空中戦で一日で六回の勝利を収めました。彼は「キーウの幽霊」と呼ばれています」とその存在を讃えた。
すでに広く知られているように、この噂は事実無根のデマにすぎない。そのようなエースパイロットは存在せず、投稿された動画はロシア製のコンピューターゲームの動画を再編集し合成したものであることがその日のうちに複数の、それも西側諸国のメディアの検証によって判明していた。
おそらくそれは開戦当初は圧倒的な優位を保持していると考えられていたロシアの侵攻を前にしたウクライナの市民が、あるいはウクライナを支援するどこかの国の誰かが自分たちを勇気づけるためにつくった他愛もない作り話にすぎなかった。しかしウクライナはこの小さな噂を最大限に利用した。「英雄」の物語によって自国の、そして西側諸国の市民の戦意高揚をおそるべき低コストで実現したのだ。
英雄の捏造のためにウクライナが「表立って」おこなったことはひとつだけだ。ウクライナ国防省がそのTwitterのアカウントで「キーウの幽霊」の噂について述べるさまざまな人びとの投稿を、とくにコメントも付けずただリツイートすること─それだけだった。しかし、その効果は絶大だった。国防省の担当者がこの「噂」を拡散する作業に費やした時間は、おそらく驚くほど短い。しかしこの「噂」の拡散が、西側諸国においてウクライナ支持の世論が開戦直後に急速に醸成されたことに少なからず貢献したことは疑いようがない。それが二十四時間足らずでデマであることが検証されたとしても、その費用対効果はきわめて高かったはずだ。
重要なのは、ほんの短い間だけエースパイロットの実在が信じられたことよりもむしろこの「噂」が広く、瞬く間に数多くの人びとにシェアされた事実のほうだった。たとえ捏造されたものであったとしてもそれを多くの人びとが求めていることが可視化されたことにこそ、意味があったのだ。この虚構の英雄の物語は大統領プーチンの専横と彼によって引き起こされた侵略戦争に抵抗するという西側諸国の市民たちの国境を越えた強い連帯が、それも急速に成立しうることを瞬く間に知らしめてしまったのだ。
「キーウの幽霊」の事例は今日における情報の操作が恐ろしいほど低コストでかつ高ベネフィットな戦術であることを、そして情報の発信はそれが事実を伝えることではなく、人びとの欲望に応えることにおいて威力を発揮することを私たちに教えてくれる。より正確には人びとが、一人の発信者としてその物語を語る快楽を利用することの有効性を証明している。この「噂」を広めたのは、国家による大規模なプロパガンダではなく市井の人びとの発信だった。だからこそ、それは国境を越えた民意の可視化として威力を発揮した。人びとはその実在が限りなく疑わしい「キーウの幽霊」について投稿することそのものに、情報を発信することそのものに強い高揚と快感を得ていたはずなのだ。
そしてこの虚構の英雄の存在は彼が実在しないことが瞬時に暴かれたとしても、危機を前にした「私たち」の連帯の高揚と快感を、そしてそれらが発信されることによって増幅することを人びとに十分すぎるほどに確認させたのだ。
この文章が書かれている二〇二四年現在、戦局は膠着して久しい。この膠着は大半の人びとにとって、予想外のものだったはずだ。開戦前「二週間保たない」と評されていたウクライナは、西側諸国の強力な支援を得て首都キーウを中心にもちこたえ、ロシアは戦線を大きく後退させた。そして開戦から最初の一年にあたる二〇二二年の戦局は大きくウクライナ側に傾くことになった。この戦況を生み出したのはウクライナ軍と国民の高い士気と、そしてそれを支える西側諸国の強力な支援であったことはすでに誰もが知っていることだ。そして後者を可能にしているのが西側諸国の親ウクライナ、反ロシアに傾いた国民世論であり、これがウクライナのプロパガンダの成功によって醸成されていたことはもはや疑いようがない。
ウクライナの大統領ゼレンスキーが、喜劇俳優出身であることは広く知られている。彼はテレビ番組の政治風刺ドラマで架空の大統領役を演じ、そのイメージを用いて現実の政治に進出して今日の地位を手に入れた。その選挙は彼が所属する劇団を母体とした政党によって、主演を務めた『国民の僕』の最新シーズンとして演出された。ゼレンスキーは、少なくとも二〇二二年当時において、情報社会下の民主主義におけるもっとも効果的なプロパガンダの方法を実践してみせた政治家であったはずだ。そのプロパガンダとはかつてのように、英雄の活躍を一方的に発信するものではなく、それを受け取った人びとにボールを預け、シュートをうながすパスであることによってしか成立しない新しいかたちのものだ。クレムリンにスーツで君臨し、陰謀論めいた国民の物語を語るプーチンの旧態依然とした独裁者のイメージをなぞる振る舞いに対し、カメラの前にTシャツ一枚で登場し、ロシアの非道への抵抗と、ウクライナへの人道的な支援を呼びかけるゼレンスキーの「役者の違い」は明白だ。そして両者の情報へのアプローチの差こそが、戦局に大きく反映されていたのだ。
そして現在における膠着状況が、西側諸国のウクライナへの関心低下によることもまた、疑いようがない。西側諸国の「ゼレンスキー疲れ」は開戦から半年足らずで指摘されていたが、今日ではそれに加えて二〇二三年十月のハマスのイスラエルに対する大規模テロ、そしてその後のイスラエルによるパレスチナに対する事実上の無差別攻撃が、西側諸国の市民の関心を集め相対的にウクライナへの関心を低下させている。
こうして考えたときウクライナの戦争は、断じて二十世紀への逆行ではない。そこで進行しているのはきわめて、二十一世紀的な現象だ。それは表面的には二十世紀型のナショナリズムの衝突のもたらした、かつての正規戦への回帰として現れている。それは残念ながら、この三十年に進行した時代の変化を不可逆なものだと認めたくない人びとの願望が見せている夢にすぎない。「キーウの幽霊」という現象と、ゼレンスキーのプロパガンダ戦略の成功が示すように、これは情報技術に基づいたグローバルなプロパガンダが、それもトップダウンではなくボトムアップに構成されるものがもっとも強い力で情況を決定するきわめて二十一世紀的な戦争なのだ。
戦線から遠のくと、楽観主義が現実にとって代わる。そして最高意思決定の段階では現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けているときは特にそうだ。
これは東京におけるテロをシミュレーションしたある映画のセリフの引用だが、今日においてこの「戦線」という概念は、少なくとも以前のようには存在しえなくなっている。二十世紀が後方の生産力が前線の戦力を支える総力戦の時代なら、二十一世紀はテロの時代だ。そこがもはやニューヨークやパリの中心街であったとしても、いや、そうであるからこそ戦場に選ばれることを、すでに人類は経験的に知っている。もはや誰にも「戦線から遠のく」ことはできない。なぜならばすでに戦線という概念が解体されつつあるからだ。
そもそもテロリズムとは、相対的に小規模な破壊と殺戮で最大限のプロパガンダをおこなうことを目的とした行為だ。そのために、敵国の中心部や重要な施設を象徴的に破壊し、その場所で市民を殺害し、恐怖を与える。これによって敵国の人心を刺激し、統治権力を脅かす。その敵国が民主的な制度にのっとっていればいるほど、その効果は高い。テロリストたちは敵国の人びとに破壊と殺戮を報道させることで、自分たちに注目を集め、メッセージを伝える。比喩的に述べれば、彼らは自分たちのYouTubeのチャンネルの登録者数を増やすために、テロをおこなっているのだ(実際に、現代のテロリストたちの多くが、自分たちの団体のプロパガンダとメンバーの勧誘の手段として、YouTubeなどのプラットフォームを用いている)。彼らの非合法な政治活動にとって情報発信は存在証明とほぼ同義であり、それによる新しいメンバーの獲得(動員)は活動の維持に直結している。そしてここではその情報発信の効果を最大化するものとしてテロが選ばれているのだ。
距離を無効化したアプローチ(攻撃)をおこなうテロとはインターネット的な戦争の形態だ。
二十世紀前半の総力戦、つまり二度の世界大戦のうち、とくに後者は放送(ラジオ)と映像(映画)というふたつの技術の産み出したものだと言われる。放送と映像、ふたつの技術は国家による大衆の動員力を飛躍的に増大させ(その先鋭化した形態が、全体主義運動だった)、総力戦を可能にした。続く冷戦下の東西両陣営の相対的な安定を支えたのは、このふたつの技術の融合したテレビだった。そしてその冷戦の終結の原因のひとつが、西側諸国の衛星放送の受信による東側諸国の市民の意識の変化であったことは記憶に新しい。人類にとって、戦争とは常に、情報技術によってその形態を決定されてきたのだ。
そして前線と後方の境界線を破壊したテロの時代を経て、今日の戦争をもっとも強い力で決定しているのがインターネット(SNSのプラットフォーム)上で展開されるプロパガンダとしての情報戦にほかならない。今日のテロリストたちの「攻撃」が、なかばサイバースペース上の彼らの発信の影響力の増大を目的におこなわれていることはすでに指摘したとおりだが、その延長に今日の国家間の「戦争」も存在する。これがウクライナで顕在化した、新しい戦争のかたちなのだ。
この新しい戦争のかたちが証明するように、今日の人類社会はインターネット上で、Facebookの、Instagramの、X(Twitter)のプラットフォーム上で展開されているユーザー間の情報発信による相互評価の連鎖と、その結果としての世論形成が支配的な力をもっている。それはいわば、すべてのプレイヤーが参加する相互評価のゲームにほかならない。今日の情報環境において、あらゆるユーザーは受信者であると同時に潜在的な発信者だ。そしてこのときユーザーには自己の発信に他のユーザーから反応を得るインセンティブが多かれ少なかれ発生する。つまり誰もが他のユーザーからのリアクションを潜在的に期待している。たとえそれが名もなき1アカウントであったとしても、いや、名もなき1アカウントだからこそ自分の投稿が不特定多数に評価されることは、一時的にでも強い快楽を与える。そして各プラットフォームは人間が情報発信によるインスタントな承認の中毒に陥っていることを経験的に知っている。そして「Like」や「Repost」というかたちでその承認を可視化することで、より人びとをその快楽の虜にした。そして今日では人類が覚えた新しい麻薬の効果を用いて政治的、経済的な「動員」をおこなうことこそをプロバガンダと、あるいは広報と呼ぶのだ。
とくに民主主義という制度は、この相互評価のゲームが世論に対して強い影響力をもつようになったことで迷走をはじめている。二〇一六年のブレグジットしかり、ドナルド・トランプの台頭しかり─。したがって、このプラットフォーム上の相互評価のゲームで優位に立つことが、西側の民主主義国に暮らす人びとの心を摑み、その世論を操作することが、これらの国家たちからの足並みをそろえた支援を獲得するためにもっとも有効であることをゼレンスキーは理解している。だからこそ彼はインターネットを通じて、戦場から国境を越えて「直接」世界中の市民に問いかけつづけているのだ。そしてその言葉がより新しい、次の戦争の出現によって人びとに届かなくなると同時に彼の戦略もまた破綻しつつあるのだ。
2 アフター・トランプの世界
ここで注意したいのは、そもそもロシアのウクライナへの侵攻はバイデン政権下のアメリカの非介入─たとえ侵攻があったとしても、ウクライナへは派兵はしないとなかば宣言したこと─を前提におこなわれたものだったことだ。アフガニスタンとイラクでの失敗から、今日のアメリカが二十一世紀初頭のように「世界の警察」を継続することは国民感情的に難しい。とくに人的損害に対する国民の忌避感は決定的だ。トランプから僅差で大統領の座を奪取したバイデンは常にトランプという稀代のポピュリストであり、世界でもっとも影響力のある政治的インフルエンサーの動向を警戒する必要があり、そのためトランプ以上に世論に配慮した政権運営を強いられてきた。この「配慮」のひとつが、結果として二〇二一年夏のアフガニスタンからの無残な撤退劇としてあらわれた。ここで西側諸国がタリバン政権の手綱を中国とロシアに渡さなければならなくなったことが、間接的にロシアのウクライナへの侵攻を可能にした。ウクライナの戦争はアメリカのポピュリズムの、具体的にはトランプという現象の落とし子なのだ。
二〇一六年に顕在化したトランプという固有名詞が、あるいはブレグジットと呼ばれた事件が象徴する現象は、この三十年の世界を牽引したグローバリゼーションと情報技術、世界をひとつにつなげる力へのアレルギー反応として位置づけられている。
この三十年のあいだに冷戦からパクス・アメリカーナへ、そしてその崩壊へと時代は移ろい、ローカルな国民国家からグローバルな市場に人類社会の最上位レイヤーは変化し、そして世界を変える究極の手段はそのローカルな国民国家の法を選挙や革命で変える政治から、グローバルな市場にイノベイティブな商品やサービスを投入する経済へと移行した。選挙や革命を通じた旧来の政治的なアプローチによる社会の変化はひとつのローカルな国民国家にとどまる。しかしこの新しい経済的なアプローチは、驚くほどの短い時間で世界中の人びとの社会と生活のかたちを変えることができる。そして、今日の現役世代の才能と情熱の大半がこの新しい(経済的な)アプローチに、とりわけ広義の情報技術を用いた産業に集中している。
ローカルな国家からグローバルな市場へ。これは前世紀末から世界中の経済学者や哲学者が口を揃えて述べていた常套句だった。たとえば、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートはそれを〈帝国〉という言葉で表現したのだが、彼らの予言が確実に現実化しつつあるその一方で、その進行の速度は彼らの予想よりも早く、彼らの予想外の事態を引き起こしている。その象徴が二〇一六年のふたつの事件─トランプとブレグジット─だった。
イギリスのジャーナリスト(デイヴィッド・グッドハート)は述べる。世界はいま「Anywhere」な人びとと「Somewhere」な人びとに二分されていると。Anywhereな人びと、つまり「どこでも」生きていくことができる人びととは今日のグローバルな情報産業や金融業のプレイヤー、クリエイティブ・クラスのことだ。彼らは東京でも、ロンドンでも、ニューヨークでも、シンガポールでも同じように働き、生きていくことができる。彼らに特定の国家に所属する国民であるという意識は相対的に希薄だ。彼らにとって国籍とは自己につけられた無数のタグ─所有しているクレジットカードや加入している動画配信のサブスクリプションサービスのようなもの─のひとつにすぎない。世界市民的な意識をもつ彼らの考える「社会」とは全人類が参加するグローバルな市場のことであり、そして自身の仕事(経済的なアプローチ)を通してその社会にコミットする。
これに対してSomewhereな、つまり「どこかで」しか生きられない人びととは二十世紀以前の、製造業を中心とした旧い産業に従事しローカルな国民国家の一員としての意識をもつ人びとだ。彼らの多くは旧先進国の中産階級であり二十世紀までその成長を支えていた製造業は、途上国との南北格差によって成立する加工貿易で富を得た産業だ。そのため、ナショナリスティックで排外主義的な傾向を帯びやすい。グッドハートによれば、ブレグジットとトランプの当選は後者の人びとの反乱であり、それはグローバル化、情報化といった世界から境界を消失させ、ひとつのゲームボードに統一する力に対するアレルギー反応なのだ。
このとき私たちが忘れてはならないのはこの構造が存在するかぎり(少なくとも既存の)民主主義に基づいた国家は、後者のSomewhereな人びとのアレルギー反応を抑制できないということだ。グローバリゼーションと情報化が実現した「境界のない」世界の成立は比喩的に述べればアメリカとベトナムの格差を縮めるその一方で、アメリカ国内の(シリコンバレーのアントレプレナーとラストベルトの自動車工の)格差を広げる。Anywhereな人びとが世界市民の視点から南北格差の是正を正義であり、国内格差の拡大は必要悪だと述べたときSomewhereな人びとは排外主義的なナショナリズムを選択せざるを得なくなる。Anywhereな人びとはこう述べるかもしれない。「境界のない世界」の実現はこの国の経済成長のために必要なのだ、と。その成長の成果を正しく再分配することで新しい格差を埋めることができる、と。しかしこの「正しい(とされる)」言葉はSomewhereな人びとに届かない。なぜならば、それは「あなたたちは世界に関与できない」と宣言しているに等しいからだ。自分たちの経済的なアプローチの成果の余剰を分配する代わりに、政治的なアプローチを濫用してその足を引っ張るべきではないと告げているに等しいからだ。この論理は、Somewhereな人びとの尊厳を根底から否定してしまう。そして、彼らの政治的なアプローチをより動機づける。なぜならば、彼らにはもはやローカルな国民国家を操縦して「境界のない世界」に歯止めをかけるほかないと告げられたに等しいのだから。これが、今日における民主主義の危機の本質だ。
この「境界のない世界」において、世界の大半を占めるSomewhereな人びとは世界に関与する手段をもたない。それはたしかに、錯覚にすぎない。実際には市場を介して(そして情報技術に支援されて)誰もが世界に関与「させられて」いるのが今日の新しい「境界のない世界」だからだ。しかし古い「境界のある世界」に生きるSomewhereな人びとはそれを実感することはできない。彼らの従事する古い産業では、個人はネジや歯車のような部品のひとつとして位置づけられるため、個人の仕事が社会の変化に関与していることを「実感」することが難しい。今日において彼らの「実感」できる社会へのコミットは主に民主主義に基づいた政治的なアプローチによって、ローカルな国民国家に代表を通じて間接的に関与することだ。だからこそ彼らは政治的なアプローチに夢中になる。それは彼らが世界に関与する実感を得る唯一の手段だからだ。
このときその一票は、ひとつの発言は、どんなに小さくても彼らにその実感を、世界に素手で触れる手触りを与える。それがどのようなものであれ、自己の声が他の誰かに承認されることは他の何ものにも代えられない快楽と安心を提供する。その対象が、家族でも友人でもない無関係な誰かであればとくにそうだ。
そして情報技術はこの承認の快楽を獲得するために必要なコストを飛躍的に下げた。とりわけ、民主主義において絶大な威力を発揮することになった。その結果として、今日の世界ではこの承認の快楽が民主主義を内側から破壊しつつある。
人間が求めているのは、正確には政治に関与することでの自己実現ではない。それはあくまで手段にすぎない。求めているのは世界に素手で触れているという手触りだ。そして、民主主義は個人が声を上げることを、無条件に肯定する。そしてすでに存在している声に賛否を示すことで驚くほど簡単に承認を獲得することができる。ある勢力に加担してその勢力と対立する勢力、つまり「敵」を批判することで、発言者が誰であろうと、発言の内容が事実に基づいていようといなかろうと、その発言は「味方」から一定の承認を獲得することができる。トランプが利用したのはこの現実なのだ。
Anywhereな人びとは、あるいはリベラルな立場に立つ人びとは述べる。トランプの述べる排外主義は倫理的に間違っている、と。「壁をつくれ」というアジテーションは政策的に無内容で、愚かだと。しかし彼らは何もわかっていない。トランプは間違っていることや、噓を述べている「からこそ」Somewhereな人びとを惹きつけているのだ。Somewhereな人びとが求めているのは、倫理的に正しいことでもなければ政策的に賢いことでもない。ただ、自分が世界に素手で触れているという実感なのだ。
ちなみにこのパンドラの箱を開けたのはむしろバラク・オバマだ。オバマをアメリカ大統領の座につけた二〇〇八年の選挙において、彼はインターネットを通じて国民一人ひとりに呼びかけた。アイデンティティの政治を全面的に展開したオバマは、インターネットを用いて個別の選挙民をターゲットに動員し、そして動員した人びとをゲーミフィケーション的に運動に没入させていった。その「草の根」の選挙戦略とは有権者一人ひとりがプレイヤーとして、自分自身が主役としてプレイできるゲームへの動員だった。彼を大統領の座に押し上げた二〇〇八年の選挙でオバマへの献金総額は約七・五億ドルに上ったが、これは敗れた共和党候補マケインの集めた三・六億ドルの二倍を超える。そして、オバマの集めた献金のうち五億ドルがインターネットを介した個人による小口献金だ。
そして二〇一六年のトランプは、この団体ではなく個人を情報技術を用いて動員する手法にFacebookなどのプラットフォームの活用と人工知能の分析を加えた。ここでは人間の存在が数字に置き換えられることになる。どのタイミングで、どの属性の人間にどのような単語を用いた広告を表示すれば何パーセントの割合でクリックされ、さらにそのうち何パーセントが商品を購入し、投票所に足を運ぶかが計算されている。この地域に住む、この職業の、このような映画を好み、この球団のサポーターであるこの人種の、この年齢の男性にこのような広告を提示するとこれだけの確率でリアクションする、という分析のもとに広報が展開された。そして一度動員された選挙民たちの多くはプラットフォームにみずから発信し、相互評価のゲームの中で承認を交換することに夢中になっていった。彼らのゲームへの没入が巨大な世論のうねりを形成し、トランプを大統領の座に押し上げたのだ。
3 ゲームの二層構造
いま、出現しつつあるのは言わば人びとが社会を物語としてではなくゲームとして把握する世界だ。古いたとえを用いれば、かつての近代人は世界と自己との関係を「政治と文学(物語)」としてとらえていた。しかし今日を生きる現代人はそれを「市場とゲーム」としてとらえている。
二十世紀まで、人間の多くは(多くの場合は国民の)歴史=物語によってその生を意味づけていた。歴史という物語のなかの登場人物として自己を位置づけることで、アイデンティティを確認していた。物語の主役は他にいる。それは国民を代表する政治家やアスリートであり、その時代を代表する俳優やポップスターだ。そして人びとは彼ら/彼女らに(映像や放送を通して)感情移入する。他人の物語にみずからを重ねあわせる。そして同じ物語の登場人物としての、国家を始めとする共同体の一員としての意識をもつ。価値のある共同体の一員であることに、アイデンティティを見出すのだ。しかし、二十一世紀の今日においてはゲームのプレイのもたらす世界に対する手触りがそれにとって代わっているのだ。
今日の世界は、巨大なひとつのゲームとしてとらえることができる。そして、このゲームは二層に分かれた構造をもつ。それはAnywhereな人びとのプレイするゲームと、Somewhereな人びとのプレイするゲームだ。
グローバリゼーションと情報化は、国家(ローカルな物語)よりも大きな市場(グローバルなゲーム)をもたらした。このあたらしい「境界のない世界」に対応したAnywhereな人びとは、個人の力(を用いた経済的なアプローチ)でグローバルな資本主義というゲームをプレイする(直接体験する)。対して対応できないSomewhereな人びとはローカルな相互評価のゲームをプレイする。それは他の誰かに認められること、つまり承認を獲得するためのゲームだ。そしてこの相互評価による承認の獲得のゲームのなかで、もっとも低コストで強い承認を得られる人気のプレイスタイルが「民主主義」なのだ。民主主義による政治への参加は画面のなかの誰かを「推す」ことで、擬似的に自己実現を果たす。集団の一部として代表を選ぶことで、他人の演じる国家の歴史という物語に感情移入する。そしてその実現には社会的な「正義」が保証されているために、人びとは迷うことなくそれにコミットすることができ、そして実現したときの快楽もきわめて大きいのだ。
前者のゲーム、つまり市場を通じた社会参加は自分の物語の体験であり、後者のゲーム、つまり民主主義を通じた政治参加は他人の物語への感情移入だ。
そして重要なのは後者、つまりSomewhereな人びとのプレイする小さなゲームが、より上位の前者、つまりAnywhereな人びとのプレイする大きなゲームの一部として提供されていることだ。
Somewhereにしか生きられない持たざる者にとって、特定の共同体に所属し、その内部からの承認を獲得することこそが唯一の世界に関与する実感を、世界に素手で触れる実感を得る方法だ。そして残酷な話だが今日においてAnywhereな人びとは、Somewhereな人びとのこうした欲望を可視化し、彼らのプレイする巨大な相互評価のゲームによって収益を上げる構造を作り上げている。その構造とはFacebook、X(Twitter)などのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)と呼ばれるインターネット上のプラットフォームだ。
このとき重要なのは、このSomewhereな人びとのプレイする相互評価のゲームが自己目的化すること、つまりゲームのプレイが手段ではなく「目的」になることだ。
自己の発信が、他の誰かになんらかのかたちで承認されること。それはその一瞬で忘れ去られる小さな承認だが、圧倒的に低コストで手に入るために人びとはまるで、口の寂しさをキャンディで慰めるようにそれを反復して求め、そして中毒に陥る。さらに中毒に陥った人びとは、やがて具体的に承認が得られなくてもゲームのプレイそのものを欲望するようになる。そこには、たとえ結果がともなわなくても世界に素手で触れる手触りがあるからだ。
こうして下位の相互評価のゲームのプレイヤー(Somewhereな人びと)はこのゲームそのものの快楽の虜になる。このときの「相互評価」の多くは、実質的にはインスタントな承認の交換にすぎないことは、すでにトランプが証明したとおりだ。つまりその内容が正確であることや、問題の解決に有効であることではなく、そのプレイヤーに承認を与えてくれる─同じ敵を憎み、同じ敵に石を投げるあなたは私の味方である─という承認の交換にすぎない。なぜならば、メッセージの内容を吟味して「評価」するよりも、敵か味方かを判断して「承認」を交換するほうが、時間的にも経済的にもコストパフォーマンスが高く知力も必要としないからだ。
そして、下位のゲーム(相互評価のゲーム、主に民主主義)の設計者を兼ねたメタプレイヤーたち(Anywhereな人びと)はこのゲームを中毒的に反復するゾンビのようなプレイヤーたち(Somewhereな人びと)を動員して収益を上げることで上位の市場のゲーム(金融資本主義)をプレイしているのだ。
このSomewhereな人びとの相互評価(承認の獲得)のゲームと、Anywhereな人びとの市場というゲーム、これが今日の情報社会におけるグローバルなゲームの二重構造だ。
そもそも貨幣とは、外部化された信用のことにほかならず、金融資本主義とはその人の社会的な信用に応じて市場から資金が調達されるメカニズムだ。そして今日の情報技術は、プレイヤー間の相互評価のゲームによってこの信用の一部を可視化している。ここで可視化された信用を広告などに結びつけることで換金すること、つまり共感資本として用いることで急激な成長を見せたのがGoogle、Facebookなどのプラットフォーマーたちだった。
彼らは、下位の相互評価のゲームを設計し、そこから収益を上げる。そしてその相互評価のゲームはプレイヤーの自己目的化により、無限に反復される。この構造を発明したことでプラットフォーマーたちは上位の金融資本主義のゲームで勝利を収め、かつゲームそのものも活性化させることに成功したのだ。リーマン・ブラザーズの破綻の寸前にその臨界点に達していた金融資本主義は、その後情報技術によって形成された相互評価のゲームと接続することによって─Google、Facebook、X(Twitter)などのプラットフォーマーを取りこむことによって─大きく拡張したのだ。
下位のゲームをプレイする人びとが、ゲームをプレイすることそのものを欲望することがプラットフォームの支配力を高め、上位のゲームを活性化させている。ここにはプレイヤーたちの自己目的化したゲームへの没入が、ゲームの構造をボトムアップに強化するという構造がある。プレイヤーによる下位のゲームの自己目的化が、上位のゲームの構造を再強化する─この現象は、一見、二十一世紀に出現した資本主義と情報技術の不幸な結婚の成果のように思える。ある意味ではそのとおりなのだが、ある意味では違う。この現象は古くて新しい問題なのだ。
4 二十一世紀の〈グレート・ゲーム〉
ハンナ・アーレントは一九五一年に出版した『全体主義の起原』で、十九世紀における英露の植民地争奪戦〈グレート・ゲーム〉について考察している。一般的には、ナショナリズムと植民地からの搾取を前提とした経済構造の結託が、帝国主義の拡大をもたらしたと考えられている。しかしアーレントはここで、むしろ帝国主義の拡大の原動力として、植民地に移住したヨーロッパ人たちの精神に注目する。このときアーレントがその精神を代表するものとして取り上げるのが、ラドヤード・キップリングの記した帝国主義の時代の植民地(インド)を舞台にした冒険活劇(『少年キム』)だ。
『少年キム』に登場するスパイたちはイギリス人もインド人もなく、ただ匿名の存在として活動にコミットし、敵国が己に懸けた賞金の額を誇りにするようになる。イギリス人のスパイとインド人のスパイが人種を超えた兄弟として共に戦うのだ。そこには、ナショナリズムもなければ人種差別もない。彼らの目的は金銭でも地位でも、ましてや国家の繁栄でもない。彼らの目的は、敵国によって自身に懸けられた賞金の金額というゲームのスコアだ。このスコアは何ものにも─金銭にも地位にも─代えることはできない。そして彼らは一様に「名を持たず、その代りに番号と記号だけを持つ」ことを幸福とする。それは、自分の物語を見つけて自己実現を果たすことによる解放ではなく、むしろ個人であることからの解放である。〈グレート・ゲーム〉に参加することで、彼らは匿名の存在となり純粋にスコアという報酬を目指してプレイすることになる。このとき〈グレート・ゲーム〉は、俗世間の価値から人間を解放し、生そのものを肯定してくれる装置として機能する。そして、このゲームのためのゲームには「終わり」がない。彼らの目的はゲームをプレイし、スコアを上げること、それ自体だからだ。キムの物語が体現する〈グレート・ゲーム〉は現実的な利害を超えた価値をもつ装置なのだ。
このゲームそれ自体への没入こそが、帝国主義の拡大の原動力であったとアーレントは考える。十九世紀後半にはすでに、帝国主義は拡大そのものが自己目的化したシステムとして完成されていたというのがアーレントの立場だ。アーレントは述べる。『少年キム』の冒険活劇で描かれた精神は、キップリングの独創ではなく、当時の帝国主義下の植民地を運営するヨーロッパ人たちのあいだで支配的だった精神を反映したものだと。植民地のヨーロッパ人たちの多くは(とくに、その運営を支える官僚機構において)まるでキップリングの冒険活劇に登場したスパイたちのように、ゲームのプレイそのものが自己目的化しており、このゲーム「への」欲望こそが、帝国主義の拡大することそのものの目的化をうながしたのだ。
その存在が世界に確実な影響を与える大規模なゲームに匿名のプレイヤーとして参加したとき、人間はゲームの攻略が、高いスコア(賞金)を上げることが手段ではなく、目的となる。そのために、そもそもこのゲームが何を目的に運営されているかには関心を払わなくなる。自分たちが依存する国家や、その背景にあるイデオロギー、加担しているシステムなどゲームの外部には関心を払わなくなる。アーレントの考えでは、人びとのゲームのプレイを通じた、生の実感への欲望の追求こそが、帝国主義の拡大の原動力にほかならないのだ。
アーレントはこのキム少年の冒険が読者を惹きつけたのは、彼が「ゲームのためにゲームを愛した」からだと述べる。近代社会において、人間はその人生に意味を求める。しかし、インターネット(とくにWeb2.0)の夢が、たとえ発信する手段が与えられても発信するに値する能力をもっている人間は一握りしかいないことを明らかにしてしまったように、人間一人ひとりの生に意味が求められることは、逆に人びとを追い詰める。今日の資本主義下において人間の大半はネジや歯車のような、匿名の部品にすぎないものとして扱われる。にもかかわらずその生に意味を求めてしまうからこそ、近代人は自己が入れ替え可能な存在であることに苦しむ。この皮肉な現実を理解し「醒めた意識」をもつ人間こそが、その生に意味ではなく「情熱的な生の充実感」を求めるようになる。そしてあえて匿名のプレイヤーとしてゲームに参加し、ゲームを攻略した報酬ではなく攻略する快楽そのものを求めるようになるのだ。
帝国主義の時代の末期から百年を経た今日において起きているのは、より矮小で、そしてより酷薄な現象だ。今日のプラットフォーム上の相互評価のゲームを、個人としてプレイする人びとの多くが、おそらくアーレントの指摘した〈グレート・ゲーム〉に埋没した植民地下のヨーロッパ人たちと同じ状態にある。ゲームに没入し、そのスコアを競った結果として、外部を見失っているのだ。
Somewhereな人びとの大半は、ネジや歯車のような生に耐えるため、承認を求めてプラットフォーム上の相互評価のゲームをプレイする。そしてその低コストな承認の獲得のもつ中毒性で考える意志と力を失い、やがてゲームプレイを自己目的化するようになる。その結果として彼らはAnywhereな人びとに動員され、換金されていく。
そしてここで留意したいのがこのようにSomewhereな人びとを中毒にして換金するプラットフォームの運営者たち=Anywhereな人びともまた、皮肉にも同じ構造の罠に陥っていることだ。
なぜならばSomewhereな人びとのプレイする二十一世紀の〈グレート・ゲーム〉とは、Anywhereな人びとのプレイする金融資本主義という上位のゲームのデッドコピーにほかならないからだ。
このゲームにおいては、株式会社という不死の生命をもつ存在─倒産することはあっても、自然死することのない、つまり永遠の時間を生きる存在─が設定される。そしてこの不死の存在がたどりうる未来の損益が、現在の価値(株価)に計算を経由して置き換えられる。当然のことだが、速く利益を生むシミュレーションが成立すると、その分だけ価値は高くなる。つまり予測される未来におけるプレイヤーの生み出しうる価値と、成長の速さ、そしてその事業が実現する成功率との掛け算で価値が決定される。
その結果として、株式会社というプレイヤーは、そしてこの不死の生命を操る人間たち─Anywhereな人びと─はその未来が予測可能、説明可能である「かのように」演じることになる。これが未来の価値を現在の値付けに反映する、ということだ。
この構造は多くの若いプレイヤーたちに挑戦のチャンスを与える一方で、ゲームの性格をある方向に決定づけている。Somewhereな人びとがこの瞬間の承認を求めてプレイするゲームと、同じ構造をもつゲームをAnywhereな人びとは未来に対する(予測可能性、説明可能性に対する)評価を求めてプレイしている。ふたつのゲームの差は、プレイヤーの不死性の有無とそれにともなう「時間」への態度だ。つまりSomewhereな人びとのプレイしているゲームとは、プレイヤーが存在する時間が有限であるために、この瞬間の値付けしか弾き出されない金融資本主義のゲームの簡易なバージョンであり、当然のことだがAnywhereな人びとがプレイするこのゲームは資本主義という拡張することを前提とした運動そのものだ。Anywhere な人びとが不死の身体の成長の可能性を演出するプレイの一部としていかに愚かなSomewhere な人びとを下位のゲームの中毒にするかが問われているのだ。しかし、プレイヤー間の相互評価の構造と、それを獲得する快楽が自己目的化する点において両者は共通している。つまり下位のゲームの外部はより投機的な性格の強くなった同じ構造のゲームなのだ。そして上位のゲームのプレイヤーは「不死」であり、そのプレイに「終わり」はない。
このようにアーレントの述べる〈グレート・ゲーム〉の構造は、今日の情報技術と金融資本主義との結びつきのなかで、二重化されている。Somewhereな人びとは、唯一世界に触れる実感を得る装置としての、相互評価のゲームに埋没する。他のプレイヤーから評価を受け、承認されること自体が目的化し、発信の内容はその手段でしかない。そしてSomewhereな人びとをゲームに埋没させることで政治的、経済的に動員し収益を上げるAnywhereな人びともまた、拡大することそのものを目的とした資本主義のゲームに取りこまれている(むしろ、彼らがSomewhereな人びとに与えたゲームは、自分たちのプレイするゲームの簡易版なのだ)。そしてアーレントが私たちに示したのは、このようなゲームの自己目的化が、人間とその社会を決定的に愚かにすることだった。たとえば二十世紀における全体主義という運動は、この二重化されたゲーム(〈グレート・ゲーム〉)の帰結として、この世界に生を受けたのだ。
5 速さと画一性
そして今日、閉じたネットワーク=プラットフォームにおける相互評価のゲームは、人間から世界を見る目と触れる手を、社会からは多様性を奪い去ろうとしている。
今日においてタイムラインに流れてくる情報の内容そのものが吟味されることはもはや難しく、ほとんどのプレイヤーは他のプレイヤーたちの反応を見て、より多くの評価が得られるリアクションを選択する。ここではもはや情報の内容ではなく、タイムラインの潮目だけが読まれている。こうして、人間は他の人間の顔色をうかがうだけしかしなくなり、問題そのもの、事物そのものについて考えることを放棄する。ある問題が生じたとき、その問題を解決する方法や問題設定そのものの妥当性は考えられなくなり、大喜利的にどう回答すると座布団を与えられるかのみを考えるようになる。シングルマザーがネグレクトで子供を死なせたとき彼女の人格への批判が集中し、貧困家庭への支援や地方自治体の児童へのケアといった制度の問題は置き去りにされる。ロシアのウクライナへの侵攻を外交的、経済的な圧力を用いて止める戦略ではなく、事実上ほぼ無関係な憲法九条の問題を取り上げて対立する他政党を攻撃する政治家が出現する。
なぜ、このようなことが起きるのか。前述したようにこの閉じたネットワーク上の相互評価のゲームにおいては、あらゆる人間が情報発信の手段をもち、そしてその大半の人間が多かれ少なかれ自分の発信に対する他のプレイヤーの評価を獲得することを目的としている。このときすでに多くのプレイヤーが話題にしている問題に対して発信することが効率的だ。そして、その発信の内容もその問題に対してすでに他のプレイヤーたちの多くが支持している意見に対し賛成するか、反対するかのどちらかを選択することがより効率的になる。いま、この国の議会制民主主義や言論において、第三極が機能せずに事実上の第一極の補完勢力になる理由もここにある。
つまりこのゲームにおいては、新しく問題を設定するインセンティブが、すでに広くシェアされた問題に(それも、すでに支配的な意見に賛成/反対することで)回答するインセンティブよりも圧倒的に低いのだ。そのためこうして、タイムラインの潮目を読みながら、他のプレイヤーからの評価を獲得するゲームをプレイしているうちに、誰もが同じタイミングで、同じ話題のことを考え、発信することになる。
このとき、人びとは情報の送受信になるべく時間的なコストを割かない。複雑な問題そのもの、事物そのものよりも、多くの場合二項対立に単純化された問題についてのコミュニケーションをするように、つまりタイムラインの潮目だけを読むようになる。他のプレイヤーと同じタイミングで、同じ話題に言及することが、このゲームで効率的に承認を獲得するためには有効だからだ。こうして「速さ」が求められていく。そしてその結果、閉じたネットワークの内部でシェアされる情報は多様性を失っていく。もちろん、多様性を社会に実装せよという声そのものは年々拡大している。ユーザー数の増加に比例して、発信される情報そのものも多様化している。しかしどれだけ多くの人びとが発信力をもち、発信される情報は多様化しても、この相互評価のゲームのなかでシェアされる話題は画一化していくのだ。
かつて「Web2.0」という理想が叫ばれていた時代があった。そう昔のことではない。提唱者の一人ティム・オライリーの論文が発表されたのが二〇〇五年のことだ。この言葉に明確な定義は与えられていない。しかしそのことが逆に、この言葉を当時のインターネットが手にしていた「夢」の象徴に押し上げていった。それまで、ある程度の専門的な知識を必要としていたインターネット(Web1.0)の情報発信が、ブログなどのサービスの普及によってコンピューターさえあればほぼ誰にでも可能になる。これによって、インターネットのすべてのユーザーが潜在的に受信者であると同時に発信者となる。これが「Web2.0」の骨子だ。当時、その推進者たちはこう主張していた。SNSなどの発展は、あらゆる人びとに情報発信の手段を与える。二十世紀のほぼすべての人類はメディアを介して情報を受信することしかできなかったが、二十一世紀のほぼすべての人類はプラットフォームを介して情報を発信することもできるようになる。みずから情報を発信することによって、人びとはより情報を深く考え、多角的に接するようになるだろうと。それが、世界に多様性をもたらすだろうと。しかしWeb2.0化の終着点、つまり「メディアからプラットフォームへ」の変化がもたらしたのは、まったく逆の効果だった。この変化がもたらしたのは、たとえ発信する手段を得てもほとんどの人間には発信に値する能力などなく、プラットフォームで展開するのはプレイヤー同士の低コストな承認の交換でしかないという現実の可視化だった。そして、いま人びとはプラットフォームの要求する相互評価のゲームの速度に追いつくために、拙速なコミュニケーションを無反省に重ね、問題の内容ではなく他人の顔色だけを読み、考えることを放棄してより愚かになっていこうとしている。そして、インターネットが実現したはずの多様性をみずから放棄しようとしているのだ。
政治から経済へ、国家から市場へ、メディアからプラットフォームへ、コミュニティから場へ、共同体から個人へ、物語からゲームへ。この変化はあるレベルでは確実に人間を檻から解放した。それまで声を上げる手段をもたなかった人びとが声を上げはじめ、それまで届かなかった遠く離れた場所にも声が届くようになった。しかし、あるレベルではこの変化は人間を別の檻に閉じこめたのだ。
物語と違ってゲームは人間を能動的にする。しかし能動的であること、自分の関与で世界が変わること/他のプレイヤーの承認を得ることの快楽は強力すぎて、人間をそれ以外の刺激から遠ざけてしまうのだ。
その結果として、人間は問題そのものに関与する動機を失い、そして世界のあるレベルから多様性は失われている。そこでここでは経済=場=プラットフォームから、そこで展開するゲームが与える快楽を相対化する方法を考えたい。それも家族とか、国家とか、そうしたつい最近まで、いや、こうしている今も多くの人びとを呪い、縛りつけているものに回帰することなく、プラットフォームの時代を内破することを考えたい。それが本書の主題だ。
6 「動員の革命」と複数化
現代の資本主義と情報技術の不幸な結婚としてのプラットフォームを内破すること─この主題を掲げたときにまず私たちが思い浮かべるのが、書を捨てて街に出ること、つまり実空間とそこに結びついた共同体に回帰することだ。しかし、事態はそう単純なものではない。なぜならば今日のサイバースペースを支配する相互評価のゲームは、実空間にも侵略を開始している、いや、すでに侵略は完遂されているからだ。
かつて「動員の革命」という言葉が囁かれたように、二〇一〇年代は情報技術を用いて人びとをサイバースペース経由で実空間に動員していった時代だった。アラブの春や香港の雨傘運動、日本の反原発デモといった社会運動、CDの販売からフェスの動員への音楽産業の収益構造の移行、「インスタ映え」を用いた商店や観光地の集客まで、FacebookやX(Twitter)などSNSのプラットフォームを経由した動員が政治からサブカルチャーまでこの時期に幅広く定着していった。それは参加者一人ひとりが発信することで、タイムライン上に潮流を形成し、それを目にした他のプレイヤーの参加をうながすボトムアップの動員だ。
人間は(それがどれほど洗練された希少なものであったとしても)紙や画面の上にある他人の物語に感情移入するよりも、(それがどれほど稚拙で凡庸なものであったとしても)プラットフォーム上に自分の物語を吐き出すほうを好む。二十世紀後半の中産階級たちは休日に自宅でカウチポテトのスタイルを取りながらオリンピックやサッカーのワールドカップなどの競技スポーツを見ていたが、現代のクリエイティブ・クラスは、みずから屋外に繰り出してランニングやヨガなどのライフスタイルスポーツをおこなうことを好む。
つい数十年前まで、この本質が覆い隠されていたのは、単に技術上の問題にすぎない。
二十世紀とは、放送と映像というふたつの技術の発展と組みあわせを用いて他人の物語に感情移入させることで、かつてない大規模な社会の形成に成功した時代だった。この間に人類は紙や画面、とくに後者のなかの他人の物語に感情移入することで、自己と社会との接続を確認していた。しかし、二十一世紀の今日において、人類は情報技術に支援され、その本来の習性を取り戻しつつある。自分の物語を語ること、その発信の内容が他の誰かに承認されること……。たとえほとんどの人間にできることが、すでに存在している支配的な意見のどれかに対して周囲の顔色をうかがいながら追従することだけだったとしても、その快楽は他人の物語に感情移入するそれを大きく上回る。
この習性を応用してプラットフォーマーは「自分の物語」を求めた人びとの欲望を刺激し、彼らを動員していった。人びとは自分の物語を求めて、ハッシュタグのついた実空間に動員されていった。もちろん、人間はそこで何ものにも出会うことはない。あらかじめ、ハッシュタグによって自覚された予定調和の事物にしか出会えない。街を歩いても、目当てのハッシュタグのついたもの以外目に入らなくなる。名所旧跡の前でセルフィーを撮る観光客が何ものにも出会えていないように。代わりに、彼らは相互評価のゲームに閉じこめられる。ハッシュタグとは、すでに多くの人びとが話題にしている事物を可視化する装置だ。彼らが触れているのは、事物ではなく人気のハッシュタグ=他のプレイヤーたちの発信の生んだタイムラインの潮流でしかないのだ。こうして実空間はサイバースペースに従属し、この閉じた相互評価のネットワークの内部に回収されたのだ。
プラットフォームの支配する今日のサイバースペースはもちろん、比喩的に述べれば「ハッシュタグに汚染された」実空間ももはやプラットフォームの一部でしかないのだ。
次に私たちが思い浮かべるのは、プラットフォームそのものを変質させること、具体的には今日の中央集権的なプラットフォームの寡占状態を、技術的に、経済構造的に自律分散的なものに変質させることだ。
プラットフォーム上では全員が同じゲーム(他のプレイヤーとの相互評価のゲーム)をプレイしている。このとき発信される情報の内容が多様であれば、ゲームそのものは画一化されていてもかまわない、むしろそうあるべきだと、この二十年の間に活躍したシリコンバレーのプラットフォーマーたちは考えた。Amazonの品揃えが豊かであれば、街の本屋はいらないというように。しかし前述したように、発信される情報が多様であったとしても、流通する情報の多様性が減じてしまっては意味がないのだ。
これに対し、支配的なプラットフォーマーに挑戦するスタートアップたちの一部はこの現象を克服するためにゲームの複数化を主張する。たとえば彼らはブロックチェーン技術を背景にしたWeb3の実現が、現在の巨大なプラットフォームにより事実上一元化され、本来自律分散的な構造をもつにもかかわらず擬似的に中央集権的な構造を獲得してしまった現代の(Web2.0以降の)インターネットを、本来の姿に引き戻すことに期待する。小さなプラットフォームが自律分散的に乱立し、小さなゲームが無数に展開されることによって今日の中央集権的なプラットフォームの支配のもたらす弊害(流通する情報の画一化)を取り除くことができると考えるのだ。
しかしおそらくWeb3の実現は、それ単体では解決にはならない。なぜならば、現在進行しているプラットフォームの支配によるゲームとそこで流通する情報の画一化は、むしろプレイヤーたちの欲望によってボトムアップに形成されていったものだからだ。たとえプレイできるゲームが複数あったとしても、かつてのインターネットがそうであったようにプレイヤーたちはみずからそれを手放し、インスタントな承認を求め単一のゲームをプレイするようになるだろう。
個人がウェブサイトをHTMLを用いて更新していた時代からブログの時代へ、そしてSNSの時代へ。この変化は個人の発信をより簡易にしただけではない。同時に相互評価のゲームがより大規模なものに変化し、他のプレイヤーからの評価が得られやすくなったこと、ある話題について発信することで、同じ話題に関心をもつ他のプレイヤーから反応されることが、この変化によって飛躍的に簡易になったことこそが重要だ。数十名の所属する集団のなかでは誰も相手にしなくなった陰謀論の類もX(Twitter)なら簡単に「共感」してくれる仲間を見つけることができる。こうして、人びとはみずから「ばらばらのものが、ばらばらのままつながる」インターネットの理想を手放したのだ。
インターネットという自律分散的なシステムを、プラットフォームが擬似的に中央集権に変化させたことを、多くの人びとが嘆く。そして、新技術で本来の姿を取り戻すべきだと主張する。しかし、問題の本質は技術にはない。むしろ、インターネットを擬似的な中央集権に変質させてしまったのは、それを用いる人間の欲望だからだ。プラットフォームのもたらしたボトムアップの中央集権を内破するために必要なのは、自律分散を支援する技術ではなく、自律分散を、多様性を、(問題についてのコミュニケーション=相互評価のゲームではなく)問題そのものにコミットする欲望を喚起することなのだ。
たとえ技術的にローカルなプラットフォームが乱立する世界が実現したとしても、そこで展開するゲームが変わらないかぎり、プレイヤーたちはより簡易な承認を求めてグローバルなプラットフォームへの接続を求める。より具体的には、自分たちのローカルなゲームで獲得した承認をより強化するために─たとえば、自分は隠された真実を知り、それをローカルなプラットフォームで説くことで得た承認をより強いものにするために─グローバルなプラットフォームでのより大きなゲームに参加していく。この皮肉な現実は、二〇二〇年のアメリカ大統領選挙における陰謀論(Qアノン)の流通によって、すでに証明されている。小さなプラットフォームで展開する相互評価のゲームは容易にフィルターバブルを形成し、デマと陰謀論の温床になる。そしてユーザーはより多くの承認を求めて、あるいはローカルなプラットフォームで形成された共同体を強化するためにその敵を求めて、グローバルなプラットフォームに接続していくのだ。ゲームの複数化は、問題を解決しない。必要なのは、相互評価のゲームによる承認の交換そのものを相対化することなのだ。
では、どうすれば、プラットフォームとそこで展開する相互評価のゲームを内破することができるのだろうか。ここで、少し変わった角度からプラットフォーム上の相互評価のゲームについて検討してみたい。
7 「関係の絶対性」とその外部
かつて吉本隆明は、人間が社会を認識する上で機能する三つの幻想を提唱した。それは自己幻想(自己に対する像)、対幻想(家族や恋人、友人などに対する一対一の関係に対する像)、共同幻想(集団に対する像)の三つで、これらは互いに独立して存在し、反発する(逆立する)とされる。そして、今日の情報社会を観察したときその中核に存在する代表的なSNS─Facebook、X(Twitter)、Instagramなど─は、この三幻想に対応した機能の組みあわせでできている。具体的にはプロフィールとは自己幻想であり、メッセンジャーとは対幻想であり、そしてタイムラインとは共同幻想である。自己幻想に拘泥するナルシストは不必要にFacebookのプロフィールの写真に凝り、少ない制限文字数に全力で抗ってたいして面白くもないジョークを盛りこもうとする。対幻想に依存する人は、家族や恋人からのLINEの返信や、既読マークの付くタイミングを相手との関係性の確認に用いて一喜一憂しながら暮らしている。そして共同幻想に取りこまれたゾンビたちは考える力を失い、X(Twitter)のタイムラインの潮目を読み、問題の解決でも新たな問題の設定でもなく、他のプレイヤーからのより多くの承認を獲得することだけを目的に投稿するようになる。
当然のことだがシリコンバレーの人びとが吉本を参照したなどということがあるはずもなく、彼らは人間のコミュニケーションの様式を実際のユーザーの行動から分析し、そしてそこから発見された欲望に工学的なアプローチで最適化していったにすぎない。その結果としていま私たちは情報技術によって吉本隆明の述べる三幻想に、より強くとらわれているのだ。
吉本の掲げたこの三幻想の源流にあるのが、「関係の絶対性」という概念だ。人間は他の人間との関係性から自由に思考することができない。したがって、ある関係(の絶対性)に対しては別の関係(の絶対性)を用いることでしか相対化することはできない。ある幻想からは、別の幻想を用いることでしか自立することはできないというのが吉本の主張だった。
半世紀前─かつての学生反乱の時代の終わりに、吉本は共産主義革命という二十世紀最大の共同幻想からの「自立」のために、対幻想に依拠するという処方箋を提示した。共同幻想から生じるイデオロギーの与える自己の存在に価値を与える歴史的な意味は、人間をどこまでも残酷にさせてしまう。アウシュビッツから南京、そして広島まで─二十世紀とは前半の半世紀でイデオロギーによる動員が未曽有の大量殺戮をもたらした時代だ。その生々しい記憶を父母から引き継いだはずの団塊世代たちが、既存のあらゆるものを否定した夢想的なイデオロギーを追求した結果として(つまり真正で無垢なイデオロギーが存在すると仮定し、具体的なビジョンもないままに既存のイデオロギーを批判して急進化した結果として)同じあやまちを、スケールこそ小さいがその残酷さでは引けを取らないかたちで引き起こしてしまったのが全共闘運動とその後の連合赤軍による「粛清」の代表する「内ゲバ」の連鎖だった。そしてこの「敗北」を背景に、全共闘運動のイデオローグとしての役割を担った吉本は彼らが「革命」という共同幻想から離脱するための処方箋を提示したのだ。それは対幻想──具体的には妻を得、子を儲け、家族を守ること──に足場を置きなおすことで共同幻想から「自立」するという方法だった。
その処方箋を提示された患者たち─全共闘の若き活動家たち─はたしかに、家庭という対幻想にアイデンティティの置き場を変えることで共同幻想からは自立した。彼らは髪を切り、ネクタイを締め、そして「妻と子供を守る」ために政治的なイデオロギーとそれを掲げる集団から離脱し、産業社会に身を投じていった。しかし彼らの新しい依存先となった家庭、つまり戦後的核家族という場の多くが、家長が専業主婦と子供を支配する搾取の装置であったこと、そしてまた彼らの多くが私的な領域において対幻想に依存するからこそ、公的な場では思考を停止して職場、つまり企業や団体のネジや歯車のような存在として共同幻想にとりこまれていったことは記憶に新しい。「夫」や「父」であることにアイデンティティを置くことで、彼らは安心して思考停止して「社畜」になったのだ。妻を殴ることで職場での鬱憤を晴らすことや、家族の生活を守るために会社の命令に従い不正に手を染めるといった「矮小な父」たちのありふれた卑しさに、吉本の唱導した「自立」は耐えられなかった。吉本が処方した薬物は乱用され、その結果生じた卑しさはこの国の戦後社会に今日も根強く残る封建的な価値観の延命に手を貸したのだ。
こうして吉本のある幻想を別の幻想で相対化するというプロジェクトは、あえなく失敗した。それどころか、むしろある幻想に支えられて「自立」することのもたらす安心が、別の幻想に埋没する卑しさを正当化し、うながすことを証明したのだ。かつて吉本は三幻想は「逆立」すると述べた。三幻想は独立して存在し、そして反発しあう。そのために、ある幻想に依拠することが別の幻想に依拠することに対しての抵抗になると考えた。しかし、ここで吉本は誤った。三幻想は「逆立」しているのではなく、単に独立して存在しているのだ。まるで、現代を生きる私たちが、プラットフォーム上の複数のアカウントを使いわけるように。そのため逆に、ある幻想に依拠することを用いて別の幻想への依拠をも強化することが可能になる。
そして今日の情報技術はこの三幻想を結託させ、とりわけ自己幻想の追求を大きく支援している。たとえば、現代を生きる人びとは、対幻想(他のユーザーとの関係)や共同幻想(所属する共同体)を誇示することでの自己幻想(アカウント)の強化を中毒的に欲望している。この構造がプラットフォーム上の相互評価のゲームを強化していることは論をまたない。二十一世紀の今日、吉本の三幻想はSNSというかたちで相互補完的に機能して、より強固に人類を関係の絶対性に縛り付け、相互評価のゲームのネットワークのなかに閉じこめているのだ。
言い換えれば、SNSのプラットフォームとは情報技術を用いて人間間の社会関係「のみ」を抽出する装置だと考えてよい。人間間の関係のみを肥大させた結果としてプラットフォーム上の人間の言動は「人とかかわること」に特化し、とくに承認の交換以外の欲望が喚起されなくなっているのだ。こうして、情報技術は人間を関係の絶対性の檻に閉じこめたのだ。
8 脱ゲーム的身体
ある幻想で、別の幻想を相対化することが原理的に不可能である以上、もはや関係の絶対性そのものを相対化するほかない。そして、インターネットのほんとうの夢はここにあったはずだ。それは不毛な、自己目的化した相互評価のゲームを通じて自己幻想を肥大させることではなく、一人の人間が家族や国家を経由せずに、世界とつながることそのものにあったはずだ。ばらばらの人間たちが、ばらばらの、家族や、国家といった共同体の一員としてではなく一人の人間のまま他の誰かとつながること。この新しい回路「も」世界に備えることで、相対的に自由になること。インターネットが実現してくれるかに見えたこの自由を、残念ながら私たちはいま、みずからの手で台なしにしようとしているのだ。
では、どうすれば私たちはこの情報技術に支援された関係の絶対性を相対化することができるのだろうか。
以前生まれつき手足の欠損している友人から、このような話を聞いたことがある。自分は別に「歩きたい」と思ったことはない、と。移動がより便利になればその手段は別にどのようなものでもよく、とくに二本の足で歩くことに憧れやこだわりはない、と。それでも新型義肢の開発プロジェクトに参加するのは、社会に対して多様性の価値を訴える効果が高いからだ。そう、彼は述べていた。
プラットフォームとは「社会的身体」を拡張する装置だ。好きな名前を選び、好きなアバターを用いて、東京の片隅からドナルド・トランプにもイーロン・マスクにもリプライを送ることができる。このとき、「五体満足」な私と「五体不満足」な彼との間にはまったく差はない。プラットフォームに接続したとき、彼の身体の「個性」は消失する。その結果、彼の「別に歩きたくない」(他の移動のほうがいい)という、あの身体だからこそ生まれたユニークな欲望も消去されてしまう。おそらく、ここに今日の人類が陥っている巨大な罠がある。
人間の創る世界を多様に、豊かにするためには、そこに吐き出される欲望が多様でないといけない。そして欲望は身体から「も」生まれる。歩いたことのない彼に歩きたいという欲望はなく、代わりにまったく別の移動への欲望が生まれているように。
しかし、FacebookやX(Twitter)に接続するとき、世界中のあらゆる人びとの社会的身体は同じものになっている。プラットフォームはユーザーの社会的身体を画一化する。それは社会的身体の五体満足主義にほかならない。プラットフォーム上のコミュニケーションが貧しいのは、そこでコミュニケーションの単位となるアカウント(≒社会的身体)が画一化されているからだ。FacebookやInstagramではLikeを与えるか、与えないか。共感するか、しないかで承認が交換される。X(Twitter)や匿名掲示板に散見される一言のコメントはもちろんのこと、そこに制限字数の限界まで文が書かれていたとしても、論理そのものはタイムラインに頻出する「定形」のものであることがほとんどだ(もちろん、ユーザーはそれで「考えた」気になっている)。
プラットフォームのもたらす画一的な社会的身体は相互評価のゲームで承認欲求を満たすこと以外の欲望をもちえない。つまり他のユーザーからの承認欲求を得ることしか考えられない身体を与えてしまう(プラットフォームの仕様上、それ以外の欲望が喚起されにくくなる)のだ。逆もまた然り、だ。目的は人間の身体を縛る。とくに人間間の関係性についての目的は決定的に人間の身体を縛りつける。ハッシュタグに動員されて街頭に出たとき、所属する共同体のメンバーシップを確認するための酒の席にいるとき、やはり私たちのおこなうコミュニケーションは画一化されている。承認を交換するだけの器官と化した結果として、ストリートを歩いているときに偶然目に入るものを気に留めなくなり、居酒屋で出された料理の味を気にしなくなる。
この悪しき循環によってこれらの場でもまた、人びとのコミュニケーションの主体は同じような社会的身体に画一化されてしまい、誰もが同じような行為しかしなくなるのだ。
こうして考えたとき、人間を人間同士の関係性の檻に閉じこめるプラットフォームは私たちが近代の社会のなかで育んできた身体の管理によって欲望を画一化する装置の完成形として位置づけることができる。
しかし今日のプラットフォーム上の画一的な身体はシリコンバレーのアントレプレナーたちの陰謀の結果生まれたものではなく、彼らが無数に提示したプランから私たちがきわめて民主的に選び取ったものだ。それは、私たちが望み、手に入れた貧しい身体なのだ。だからこそそれは市場から、それもインターネットというボトムアップで生成される場所から生まれてきたのだ。そして、その身体が特化する(「関係の絶対性」に縛られた)人間間のコミュニケーションは、残念ながら(少なくとも自分たちが思っているほどには)多様ではない。
では、どうすれば多様性を回復できるのか。プラットフォームの与える画一化された社会的身体を拒否し、脱ゲーム的な身体を回復することができるのだろうか。
9 虫と花
かつて真木悠介=見田宗介はこう述べた。「進化史上最もめざましい成功をおさめた種間関係は、昆虫と顕花植物の「共進化」である」と。「クローバーの芳香に引き寄せられるハナバチはその身体を「操作される」、他種の生殖のサイクルの内に組み込まれている。しかしハナバチはそのことによって自身もまた生存と生殖の機会を増大している」のであり、このとき「ハナバチは誘惑されてあることに歓びを感じ」ているはずだ、と(傍点原文)。
ある種の植物は、生殖のために昆虫などの自分たちとは異なる種の生物を誘惑する。その異種を誘惑するために発達した器官が「花」だ。花とは、同種の(私たちの場合は人間間の)コミュニケーションの外部に開かれた回路なのだ。
真木はリチャード・ドーキンスの利己的遺伝子論に、人間を含む動物の利他の根拠を求める。広く知られているように、ドーキンスは生物の個体を遺伝子の一時的な「乗り物」として考える。個体のために遺伝子があるのではなく、遺伝子のために個体があり、そのために、生物には自己遺伝子の存続と同じように、自己のものと近い遺伝子の存続に適した行動を選択するようにプログラムされている、と考える。アリやミツバチのワーカーたちがみずからの子孫を残すことなく姉妹の子孫を残すために行動するのは、個体にとっては利他的な行為だが遺伝子にとっては利己的な行為である、と。これによって、遺伝子の存続というゲームにおける合理的なプレイとしての利他という現象を説明することが可能になる。そのために生物は個体にとっての利他的な行為─それは実のところ遺伝子にとっての利己的な行為なのだが─に快楽を覚える本能をもつのだ。
このとき遺伝子はその一時的な乗り物である個体の同種だけではなく、異種にも利他的に働きかけて存続を試みることがある。真木によれば虫と花の共進化は、現時点におけるそのひとつの到達点だ。それは「個体にとっての利他」によってもたらされる「遺伝子にとっての利己」の快楽が、種を超えたアプローチによって最大化されたきわめて高度な進化なのだ。
そして、認知の能力を発達させた人間という動物はその高度な進化のもつ豊かさを理解することができる。人間がこの「花」という回路─同種に対するフェロモン的(性的)なアプローチに、異種に対する(季節的)アプローチが加えられた高度なもの─を、美という概念の根底に置いてきたのはそのためだ、と真木は考えるのだ。
利己的な遺伝子はときに個体に対して利他的な行為を要求し、個体はその利他的な行為に快楽を覚える。この快楽とは言い換えれば遺伝子の要求に従って自己という個体を解体することで得られる快楽だ。そして人間はみずからが個体であることを認知できる能力を保つために、みずからが淫している快楽が自己という個体の解体によって得られていることを理解することができる。ときに他者によって「される」ことが、つまり自己という領域が侵されることが強い快楽をもたらすことを理解することができる。人間とは自己の保存が快楽をもたらすように自己の解体もまた快楽をもたらすことを、そしてこのふたつの本能の組みあわせ(「花」的なアプローチ)がより強い快楽をもたらすことを覚えた動物にほかならないのだ。真木は、ここに文化とその多様化の根拠を見出す。芸術への、宗教への欲望は言い換えれば他者からの「花」的なコミュニケーションの産物なのだ。真木によれば人間は、特定の目的(遺伝子の一時的な乗り物となること)をプログラミングされた「エージェント的な主体」であると同時に、自我に目覚め、そのプログラムを相対化し、行動の目的を自己決定できる「テレオノミー的な主体」でもある。そのために自己解体と自己保存というふたつの矛盾する欲求を同時に抱いているのだ。
自己保存の欲求に駆動された、同種への性的なアプローチのみが存在するとき、その場に発生するコミュニケーションは単純な交配にとどまっていく。そこに自己解体の欲求に基づいた異種へのアプローチが加わったときはじめて、そこに多様な文化は「花」として咲くことになるのだ。
真木の詩的で、ロマンチックな語り口をいったん横に置いて一連の議論を眺めたとき、ここで述べられている「花」的なコミュニケーションに、プラットフォームを内破していくための大きな手がかりがあることに気づく。そう、今日の人類は、「花」的なコミュニケーションのことを忘れている。いま、人類は情報技術に支援されて人間間の相互評価のゲームに中毒的に埋没し、人間外の事物とコミュニケーションすることを忘れてしまっているのではないか。これまでとは比較にならないほど速く、低廉にアクセスできるようになった同種とのコミュニケーションに埋没し、人間外の事物とのコミュニケーションのことを、置き去りにしはじめているのではないか。自己が何かを「する」、承認を獲得し自分が何者「である」かを確認「する」、ことでの自己保存の快楽の中毒になり、事物に心身を侵「される」快楽を、自己解体の快楽を、そして自己解体を経由することで初めて実現する自己保存の快楽を忘れてはいないか。
たとえば二〇二〇年以降多くの人類が、ウイルスという人間「ではない」ものの脅威にさらされたとき、それを直視することから逃げた。多くの人びとが、新型コロナウイルスが未知であることを受け入れられなかった。世界にはまだ、わからないことがあることを受け入れることができなかった。ある人たちはそれはただの風邪と変わらない、「大したことのない」感染症だと述べた。こうした言葉は、それが未知のものであることに怯える人びとの不安を埋めてくれた(ドナルド・トランプはこの効果を利用し、意図的にデマを拡散し、この種の人びとの支持を集めた)。また、ある人たちは急造された新型コロナウイルスのワクチンは、ビル・ゲイツが密かに指揮した人口削減を目的とした毒物であると主張した。このような陰謀論は、そもそも今日の情報の錯綜そのものに耐えられない人たちの精神を安定させる役割を果たした。そして、人びとのこうした未知の事物に対するアレルギー反応が、情報を、社会を大きく混乱させ、パンデミックそのものを長期化させていった。あのパンデミックは、人間間の相互評価のゲームに逃避し、人間外の事物から目を背けた人びとの生んだ情報の混乱と誤情報の拡散(インフォデミック)によって強く下支えされていたのだ。
あのころ人間たちは新型コロナウイルスという未知の存在に怯え、既知の存在とのコミュニケーションに埋没していた。ウイルスという人間外の存在との、長い時間をかけたコミュニケーションのもたらす不安に耐えられず、それから逃れるために情報技術によって支援された人間同士の拙速なコミュニケーションに閉じこもった。この疫病から暮らしを守るために必要な、ウイルスとの感染抑制のゲームではなく、人間間の相互評価のゲームをプレイしていた。そしてその結果として多くの人が、コロナ・ショックを前にしたとき、それを口実にそれ以前から遂げようとしていた野心を追求し、それ以前から疎ましく思っていた対象にツバを吐いたのだ。
しかし私たちはウイルスによって絶たれた人間同士のつながりを回復すること(相互評価のゲームで承認を交換すること)ではなく、人間以外のもの(ウイルス)と正面から対峙することで危機に耐えられる社会を獲得するべきだったのではないか。この知恵を得たときに、人間同士のつながりもまたより強固で、建設的なものとして蘇るはずだ。
そしていま、ほんとうに必要なことは人間間の閉じたネットワークのなかで、相互評価のゲームをプレイすることではない。むしろ人間「ではない」事物とコミュニケーションすること、つまり「虫」を誘惑するための「花」のようなアプローチなのだ。
10 プラットフォームから「庭」へ
人間の眼は誰かと眼を合わせるためだけのものではない。人間の手は、誰かの手を取るためだけのものではない。その眼は空を見て、星を見て、宇宙を観ることもできるし、その手はスプーンを持ち、ハサミを用い、弓を引くことができる。人間の身体と精神には人間外の事物とのコミュニケーションを経ることではじめて発動する能力があり、芽生える欲望がある。人間は人間外の事物とのコミュニケーションの可能性に開かれた存在だ。しかし、二十一世紀の人類はその可能性を、なかば無自覚に手放そうとしている。
したがって、私たちは(人間間の相互評価のゲームによる承認の交換を相対化するために)人間外の事物とのコミュニケーションを回復しなければならない。実空間が情報技術に汚染されたいま、プラットフォームの外部に逃れることはすでに難しく、そしてプラットフォームを複数化することでは問題の本質にアプローチできない。だからここでは、このプラットフォーム化した世界を内破して、変質させる方法を考えてみたい。国家から市場へ、メディアからプラットフォームへ、では次はなにか?
ここではその次のものを「庭」の比喩で考えたい。
なぜ「庭」なのか。プラットフォームには人間しかいない。それも画一化された身体をもつ人間しかいない。そして人間間のコミュニケーションしか存在しない。しかし「庭」は異なる。「庭」は人間外の事物にあふれている場所だ。草木が茂り、花が咲き、そしてその間を虫たちが飛び交う。「庭」にはさまざまな事物が存在し、その事物同士のコミュニケーションが生態系を形成している。人間が介在しなくとも、そこには濃密なコミュニケーションと生成変化が絶えず発生している。「庭」を得て、そこを訪れることで人間は人間外の事物に接し、それらにかかわることで人間間の相互評価のゲームから相対的に離脱する。プラットフォームの与える画一化された身体ではコミュニケーションできないものに触れることで、本来の多様な身体を取り戻す。その眼は他の人間と眼を合わせることから解放され、その手は他の人間と手をつなぐことから解放される。
しかし、同時にそこはあくまで人間の手によって切り出された場だ。完全な人工物であるプラットフォームに対して、「庭」という自然の一部を人間が囲いこみ、そして手を加えたものは人工物と自然物の中間にある。だからこそ、人間はその生態系に介入し、ある程度までコントロールできる。岩が置かれ、砂利が敷かれ、砂が撒かれている。しかし、完全にコントロールすることはできない。そこは常に天候の、季節の移り変わりの影響を受け、草花の、虫たちの、鳥の、獣の侵入を受け変化しつづける。人間はそこに関与し、変化を与えることができるがその結果をコントロールすることができない。「庭」とは、その意味において不完全な場所だ。しかし、だからこそそこはプラットフォームを内破する可能性を秘めているのではないか。
「家」族から国「家」まで、ここしばらく、人類は「家」のことばかりを考えすぎてきたのではないか。しかし人間は「家」だけで暮らしていくのではない。「家庭」という言葉が示すように、そこには「庭」があるのだ。家という関係の絶対性の外部がその暮らしの場に設けられていることが、人間には必要なのではないか。
そして「庭」とは(私企業のサービスにすぎないSNSプラットフォームのように)、私的な場である。しかしその場は半分だけ、公的なものに開かれている。それぞれの「家」の内部と外部の接点としての外庭があり、そして家事や農作業、あるいは集団礼拝や沐浴の場としての中庭がある。
「家」の内部で承認の交換を反復するだけでは見えないもの、触れられないものが「庭」という事物と事物の自律的なコミュニケーションが生態系をなす場には渦巻いている。事物そのものへの、問題そのものへのコミュニケーションを取り戻すために、いま、私たちは「庭」を再構築しなければいけないのだ。プラットフォームを「庭」に変えていくことが必要なのだ。
そしてサイバースペースはもちろんのこと、今日においては実空間すらも「庭」としての機能はあらゆる場所から後退している。だからこそ、このプラットフォーム化した社会をどう「庭」に変えていくのか。それが本書の主題だ。
この世界に「庭」を、多様な人間外の事物との豊かなコミュニケーションが可能であり、その生態系に(支配することなく)関与する場を、どう手にするのか。それを、サイバースペースと実空間、両方の面から考えていきたいと思う。
「庭(ニハ)」という言葉は、かつては現代とはやや異なる用いられかたをしていた。いくつかの辞書を引いて古語におけるその意味を調べると、それは現代語の「場」と同じような意味であったことが記されている。
たとえば当時は狩をする「狩場」を「狩庭」と書いていた。漁労をするのは「網庭」、稲作をするのは「稲庭」、草刈りをするのは「草庭」、製塩をおこなう場所は「塩庭」と呼び、さらに戦闘、交易、芸能、仏神事のおこなわれる場所をそれぞれ、軍庭、市庭、売庭、乞庭、舞庭、祭りの庭、講の庭などと呼んだという。
共通しているのは、そこが人間が何かの事物とコミュニケーションを取るための場所であった、ということだ。その対象は、人間というよりはむしろ人間外の事物であった。農作物や獲物であり、それらを用いて製作される道具たちであり、そしてときにこれらの事物に宿る仏神たちであった。この性質は今日の主に観賞を目的に造られる庭にも、引き継がれている。
そして「庭」という言葉は、単に「場」を示すものから、徐々に家屋の内部または隣接した場所のなかで、とくになんらかの事物を対象に作業をする空間のことをさすものに変化していった。そこは、人間の私的な領域と公的な領域とを接続する蝶番のような場所だった。だからこそ、やがて社会的な分業が進行し、その場所が観賞用の、つまり「観る」ためのものに変化したとき、「庭」はそこに暮らす人びとの世界観を象徴的に表現するものとして機能するようになったのだ。
一、地形により、池のすがたにしたがひて、よりくる所々に、風情をめぐらして、生得の山水をおもはへて、その所々はさこそありしかと、おもひよせ〳〵たつべきなり
一、むかしの上手のたてをきたるありさまをあととして、家主の意趣を心にかけて、我風情をめぐらして、してたつべき也
一、国々の名所をおもひめぐらして、おもしろき所々を、わがものになして、おほすがたを、そのところになずらへて、やハらげたつべき也
この三ヵ条は、世界最古(平安時代末期に成立)の造園の指南書とも言われる『作庭記』に記された、造園の基礎となる心得だ。ここで主張されている心得を本書の文脈で現代的に言い換えると、おおむね以下のようになる。
まず、「庭」とはその家屋の置かれた地形に基づいて造られた実際の自然のミニチュアであるということ、次にその造型に造園家や家主の世界観が反映された作品であるということ、そして最大の参照先はさまざまな土地に実在する景勝地であるということだ。つまり『作庭記』における「庭」とはまずその土地の個性を引き出し、そこに人間のメッセージを、他の場所に存在する自然の生みだした美をかけあわせることで表現するものなのだ。
かつてのバロック式庭園が人間が理性を用いその人間の秩序に自然の秩序を従わせることへの欲望を、園林が現世には存在しえない桃源郷への欲望をそれぞれ体現したように、人類の歴史のなかで、「庭」とはその時代の人間が考える理想の世界像を体現する場として造られてきた。では、いまこの時代にあるべき「庭」とはなにか。ここではそんな、「庭の話」をしたい。
この記事は、2024年12月に講談社から刊行される、宇野常寛の「庭の話」序章を期間限定で特別公開したものです。2024年12月11日に配信しました。これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。