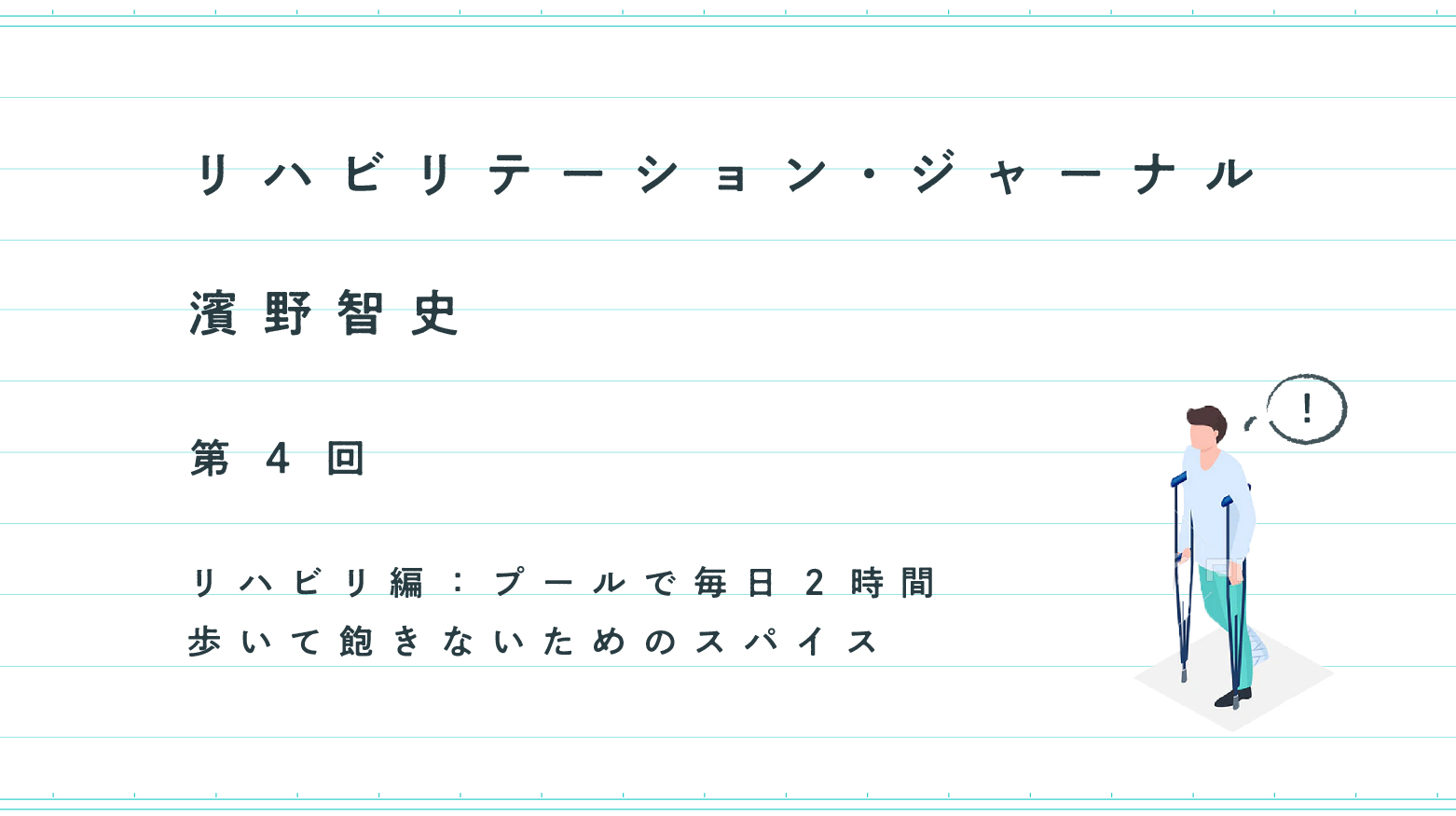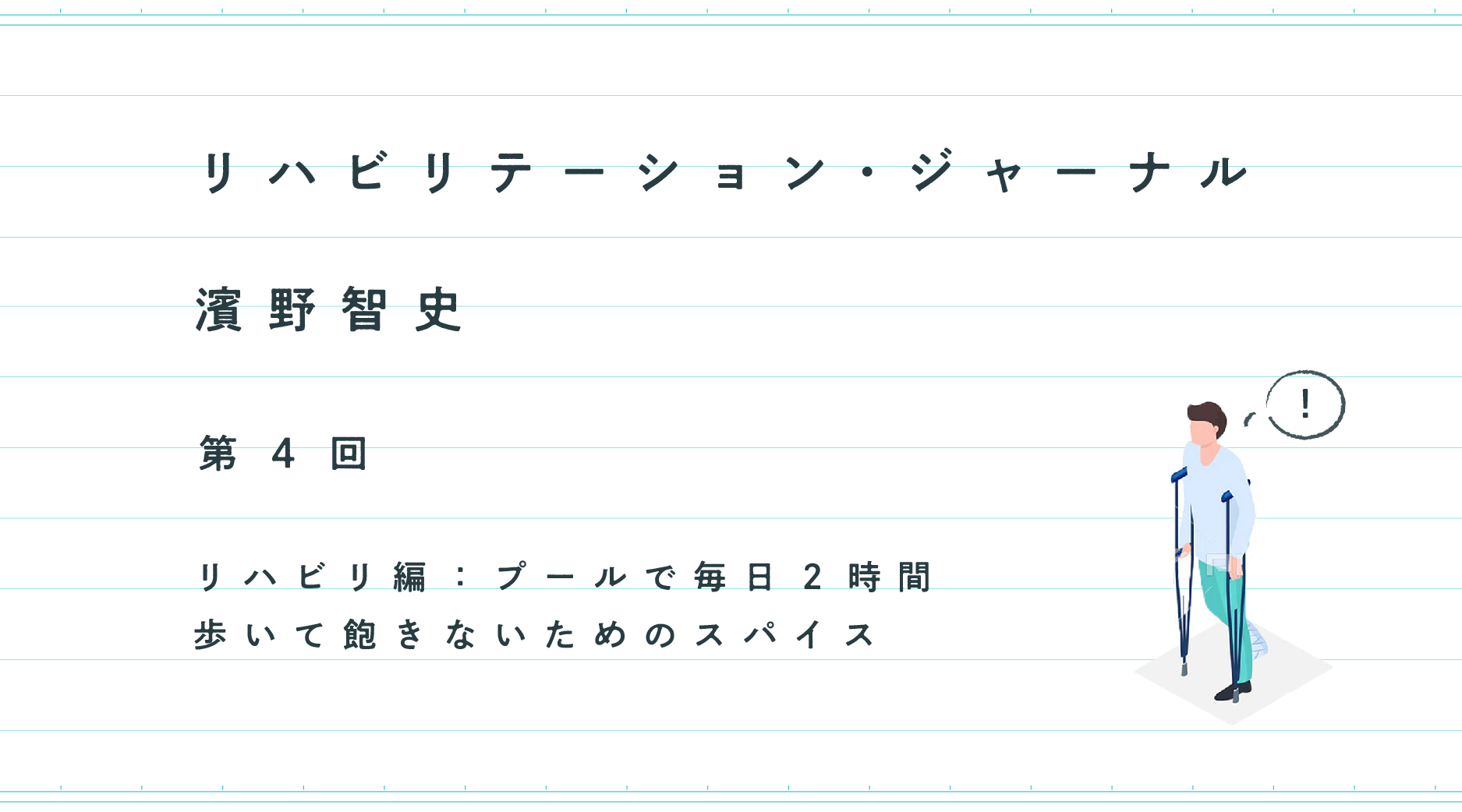批評家の濱野智史さんによる連載「リハビリテーション・ジャーナル」です。指定難病「特発性大腿骨頭壊死症」にかかり、人工股関節を入れる手術を受けるため、約1ヶ月間の入院生活を送ることとなった濱野さん。人生初の経験となる長期にわたる入院生活、そしてその後のリハビリ生活の中で見えてきたノウハウやメソッドを紹介しながら、「健康」と「身体」を見つめ直していきます。
第4回では、前回の記事で濱野さんが熱く魅力を語ったプールを「飽きない」ためのデバイスやメソッドについて紹介します。
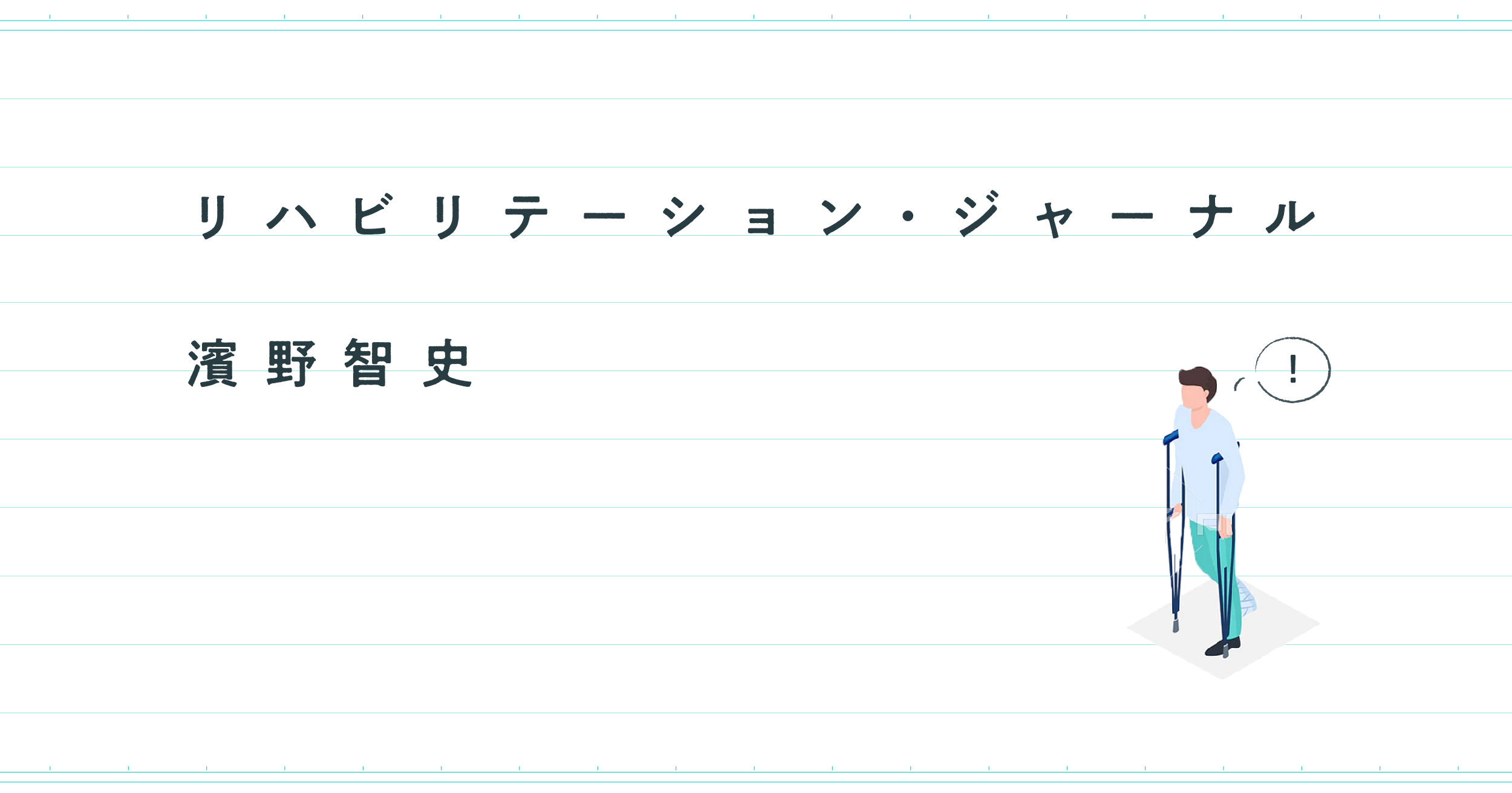
「リハビリテーション・ジャーナル」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
スポーツにおける最大の課題にして敵、それは「飽きる」問題
私はここまで、「プール・ウォーキングは毎日2時間、無理なく続けられるのでダイエット効果も高い」と連呼してきたが、「そもそも2時間もスマホも触らずにただ歩くなんて退屈なはずだし、飽きてしまって続かないのではないか」という疑問を抱く方もいるだろう。
実はかくいう私も、この「飽きる」問題はスポーツや運動を日常的に継続していく上で非常に重要なポイントだと考えている。実際、私のこれまでのスポーツ半生は「飽き」との闘いだったといっても過言ではない。
たとえばかつてジムに通っていた30代前半の頃は、最初こそ目新しくて飽きることはないのだが、すぐに筋トレマシンやエアロバイクの無味乾燥感に耐えられず、数回も行くころには飽きて行かなくなってしまった。えんえんと景色が変わらない単調さのなかで運動し続けることが、自分の場合どうしてもできないのである。
同時期にジョギングも半年ほどやっていた。これも最初こそ楽しいのだが、5km・10km・15kmと距離を伸ばし、自宅の周りのルートをあらかた走り尽くしてしまうと、その光景の変わらなさにやはり飽きが来てしまう。移動手段を変えても結局は同じで、サイクリングも同じ結果になってしまった。私の場合、荒川沿いをロードバイクで10回程度は走ったことがあるが、これも最初の数回はきわめて楽しいのだが、結局は毎度変わらぬ光景にうんざりしていつしか乗らなくなってしまったのである。
そこで私は最終的に「登山」に行き着くことになる。自分がまだ登ったことのない山というのは日本中に無数とあるし、山道というのはその光景・路面といい常刻々と変化を絶やすことがない。その意味で登山は自分にとって最高の「飽きない」アクティビティである。しかし、残念ながら登山は(都市部に住んでいる限り)毎日のようにやるわけにはいかないスポーツだ。よって私は、何か自宅のそばで毎日飽きずに続けられるスポーツやアクティビティがないか、常に探し求めてきた。
結論から言うと、プール・ウォーキングはおそらく私にとって、現時点で最もこの「飽き」問題を高いレベルでクリアしているアクティビティである。実際、この半年で私なりにいろいろな対策(飽きないためのデジタル・アイテムの導入やオリジナル・メソッドの開発)を試して習慣として定着させることにも成功している。ここでは、ぜひそのノウハウを余すことなく紹介したい。
飽きずに長時間プール・ウォーキングを続けるコツ:デジタル・アイテム編
・スマート・ウォッチ:まず紹介したいのがApple Watchに代表されるスマート・ウォッチである。プールで使用するため、防水規格IP68相当の性能を備えている必要はあるが、最近のものであればたいていこれはクリアしているはずだ。
ただし、結論から言うとこれは必須ではない。スマート・ウォッチはご存知のとおり、運動中の身体情報(特に心拍数)の可視化・モニタリング・記録を可能にするウェアラブル・デバイスである。ただし、こと水中歩行に限っていえば、それほど運動強度が激しく変化するようなものではないため、心拍数を常に計測してカロリー消費量を見ても(最初のうちこそ楽しいが)しばらくするとさほど変化がないことに気づく。ある程度プールに通う回数も増えて運動内容もパターン化してくると、スマート・ウォッチを装着することの煩わしさのほうが勝ってしまい(毎回の充電が必要なほか、後述する保護バンドの装着が必要なのも地味に面倒)、結果的に私はスマート・ウォッチはしなくなった。
ただし一点補足しておくと、(私営のフィットネスジムではとうに使えたのだが)「公営プール」となると最近まで利用禁止のところが多かった。少なくとも私が通う江東区の公営プールでは、2022年4月までスマート・ウォッチは「安全面」から利用が禁止されていたという。その理由はどうやら「金属製のスマート・ウォッチを他人にぶつけたり、床や壁にぶつけて破損したり、その破片が他人を傷つける可能性があるから」ということのようだ。そのため現在でも、素の状態でのスマート・ウォッチ利用は許されておらず、必ずスマート・ウォッチ全体を覆うことができる半透明なシリコン製かゴム製の保護バンドを着用する必要がある(これはAmazonなどで購入できるほか、公営プールの窓口でも販売していることもある)。
経緯はともあれ、公営プールでもせっかくスマート・ウォッチが使用可能となっており、もしあなたがたまたま防水性能つきのスマート・ウォッチを所有しているのであれば、最初のうちは利用してみるのをおすすめしたい。自分がどれくらいの動きで水中歩行・水泳をすると心拍数・カロリー消費数が変わるのかを細かく見るだけでも、いわゆる小さなPDCAサイクルを回してプラン・目標を立てやすくなり、結果モチベーションも維持しやすくなるので、特に運動初心者にはおすすめのデバイスである(ちなみに心拍数さえ測れればなんでもよく、Apple Watchである必要は全くない。その意味でいうと、おすすめなのはXiaomi Smart Bandシリーズで、5000円強で購入できる)。
ちなみにApple Watchの「ワークアウト」(運動種別を選ぶと、その運動に特化したKPIを測定・表示してくれるApple Watch専用のアプリ)では「水泳」が用意されており、何mプールかを設定すると、自動でラップ数(何回周回したか)を自動で計測し、平均タイムなども計測してくれる。水泳ガチ勢であれば、これはだいぶ便利な機能だろうとは思うが、私の場合は水中歩行のほうがメインなので、基本的に使用していない(むしろ「水泳」はカロリー消費量を常に表示してくれないのが不満なので、私は「ウォーターフィットネス」を選択している)。ただし、おそらくApple Watchでのカロリー消費量も結局は先述したMETs値と心拍数をもとに大まかな値を算出しているだけなので、そこまで神経質になる必要はなく、ただの目安として参照する程度にしておこう。
・水泳専用の骨伝導イヤホン:スポーツシーン(ランニング)に特化した骨伝導イヤホンとしてはShokzのプロダクトが知られているが、水泳に特化したラインナップ(OpenSwim Pro)も存在している。これはもちろん防水性能を備えているのは当然として、もう1つ「デバイス内のローカルストレージにmp3などの音楽ファイルを保管して再生できる」というのがその特徴(というか必須要件)となっている。
というのも、Bluetoothの電波は水中では遮断されてしまうからである。つまり、(普通はプールでの利用が禁止されているが)もしBluetooth接続の防水ワイヤレスイヤホンを水中で装着したとしても、Apple Watchなどの再生元デバイスを水中に入れただけで、音楽の再生は途絶えてしまうのだ。そのため水中歩行・水泳いずれの場合にしても、普通のワイヤレスイヤホン・骨伝導イヤホンは用をなさない。
そこで出番となるのがこの水泳専用の骨伝導イヤホンである。これもまた、最近の公営プールでは使用が認められてきているようだ。私の通っている江東区のプールでは、耳をふさがない防水性能つきの骨伝導イヤホンのみ利用が許可されている。
ただし、これはスマート・ウォッチよりもはるかに購入のハードルは高い。というのも水泳専用の骨伝導イヤホンとなると、利用シーンがそれこそ水中に限られてしまうからだ。ローカルストレージのmp3を再生するモードと、Bluetoothで接続してワイヤレスイヤホンとして使用できるモードを切り替えることはできるが、連続使用時間の問題もあり、充電も途中で必要になるので、あまり水泳以外のときに使おうとは思わないだろう。
そこで私の場合は、例によってAmazonで格安の中華製水泳用骨伝導イヤホンを購入した(セールで6000円程度だった)。それにしても、PCからmp3をUSBケーブル経由で転送するだなんて、いつぶりだろうか。それこそかつてのmp3プレイヤー「iPod」シリーズを所有していた時代以来で、おそらく10年、いや15年ぶりくらいかもしれない。私はこうして、長らく自分のストレージの奥にひっそり眠っていた音源を引っ張り出し、プールで聞く日々を始めた。
最初こそ楽しかった。運動時の音楽は、もちろん暇つぶしや気分転換として有効ではある。だが、結局「PCからmp3を転送する」という点があまりにも面倒だったのと、やはり安価な製品で水中で毎日のように使ったからだろうか、利用して2ヶ月ほどでPCとの接続ができなくなってしまった(充電はできるのでまだ使用はできるが、コンテンツが入れ替えられないので事実上無用の長物と化した)。そのため、こちらも現在は使用していない(そのかわりに自分独自のメソッドで、2時間飽きずにプール・ウォーキングを継続するコツを編み出した。このあとで紹介する)。
・補足:プールの必須アイテムについて(水着、キャップ、ゴーグル、タオル)
ここでアイテム・グッズ解説の補足として、プールを利用する際に必須となる水泳グッズについても簡単に触れておこう。そもそも普段プールに行く習慣がない人は、水着もキャップもゴーグルも持っておらず、その費用感も分からないだろうし、どういったものを選べばいいのか全くわからないだろうからだ(私もそうだった)。
結論から言うと、これも例によってAmazonなどのEC通販サイトで安価なものを適当に探して買えば大丈夫だ。水泳グッズはどれも非常に安価である(おそらく、水泳というスポーツがそれだけ世界的にも広く普及してマーケットも大きいからなのだろう)。
まずフィットネスプール用の水着は、男性用/女性用ともに、ノーブランドでよければ2000円台から購入できる。フィットネス用の水着は肌の露出も少なく、誰でも安心して着られるデザインが主流なので、ほとんどの人が安心して選べるはずだ。ネットで購入する場合、サイズが合うかどうか不安に思う人もいるかもしれないが、最近の水着はよく伸びてフィットする伸縮素材で作られているため、そこまでサイズ・フィッティングはシビアに考えなくても大丈夫である。またサイズもかなり幅広く展開されているため(これも世界中で水泳が普及しているからだろう)、見つからないということはないはずだ。
次にスイミングキャップは1000円程度から、ゴーグルも1500円程度から購入できる。ちなみにキャップとゴーグルは100円ショップでも売っているが、ゴーグルだけはおすすめしない。私の場合、すぐに壊れて全く使い物にならなかったので、ここだけはケチらないほうがいいだろう。ただしプールで水泳はせず水中歩行しかしないのであれば、ゴーグルは不要である。
最後のタオルは誰でも自宅に持っているだろうから、新規に購入する必要はないだろう(ちなみに私はむかし登山用に購入した速乾素材のタオルを使っている。コンパクトサイズで吸水力・乾燥性が高いのでおすすめである)。
つまり、これら全部を新規で揃えても、安く抑えれば5000円程度で済むのである(さらにAmazonでは、男性用水着水着・キャップ・ゴーグル・タオルなどがすべてセットになった商品が3000円程度で売っている)。
とはいえ、普段着のままでも始められる散歩・ウォーキングに比べると、「新規購入」のハードルが高いのは事実である。実際続けるかもわからないスポーツに、いきなり始める前に3〜5000円の出費がかかるというのは、たしかに躊躇しても仕方がない。おそらくこれが原因で、プール・水泳はやっていないという人が大半なのかもしれない。
ちなみに水着・キャップ・ゴーグルの三種の神器は、公営プール施設によってはレンタル・その場で購入できる場合もあるので、事前にネットで調べてみるのもよい。それでも水着だけは普通レンタルできないので、これだけは購入が必須である。水着を買うのはどうしても嫌ということであれば、ユニクロやワークマンなどで売っている水陸両用のショーツを購入するのもよい。これなら家から着用していけば更衣室での着替えすら不要である(かくいう私も一番最初はこれで行った。プールの魅力に気づいてからはすぐに水着を買ったが)。
また特に女性の場合、髪がプールで濡れるのは避けたいという方もいるだろう(濡れた髪を乾かすのが面倒だったり、塩素などで髪にダメージを受けたくなかったりなどの理由がありうる)。その場合は、完全防水のシリコン製スイミングキャップがおすすめである。ほぼ完全な防水を実現してくれるが、汗でキャップ内が少々蒸れやすいというデメリットはある。
飽きずに長時間プール・ウォーキングを続けるコツ:メソッド編
次に紹介するのは、デジタル・デバイスの力を借りることなく、水中歩行のやり方自体に工夫を加えた私独自のメソッドである。これらは私の場合実際に良い効果も出ているので、簡単に紹介したい(といっても、あくまで私にはこれが合っていたというだけの話なので、軽く参考程度にしてもらえればと思う)。
・脳内で音楽を再生する・鼻歌をうたう・メロディにあわせて即席で替え歌を作る:
わざわざ「メソッド」として言語化するほどのものでもない気もするが、これが実に水中歩行との相性が良いのであえて紹介したい。
まず前提として、何度も書いてきたように、水中歩行は(同じプールで行う水泳とは異なり)「息継ぎ」が存在せず、運動負荷も軽い。そのため、水中歩行という運動行為に集中した状態(いわゆる「ゾーン」)に入るのは少し難しい。つまり、慣れてくると要はただ水中を歩いているだけなので、わりと暇になってしまうし、25mプールをぐるぐる周回しているだけなので飽きやすい。
そこで音楽の出番になるわけだが、実は骨伝導イヤホンがなくても、脳内で音楽を再生したり、人が周りにいなければ小さな音量で鼻歌をうたったりするだけでも、十分2時間は楽しめる。ちなみに私以外にも、わりと鼻歌をうたいながら水中歩行をしている人は多い。プールはわりと雑然としたノイズに満ちた環境なので、鼻歌程度はほとんど気にならないのである。
ちなみに私は、子どものときにプレイした懐かしのRPGの戦闘BGM(特にロマサガシリーズ)をYouTubeなどで聞いたあと、プールに行って脳内でエンドレスプレイするのに一時期だいぶハマっていた。戦闘BGMはそもそもゲーム中、エンドレスに何十時間もプレイ中に聞くことを前提に作曲されているので、この脳内エンドレス再生に特に適していると私は思う。とはいえこれはあくまで私の場合なので、個々人の好みや嗜好性にあわせて適したものを探してみるのもまた一興だろう。
さらにこれはおまけレベルの話だが、このBGMに勝手に歌詞をつけて「替え歌」のようなものを即席でつくるのもなにげにおすすめである。これは後述するが、水中歩行は散歩などと全く同じで、歩きながら雑多な思考をするのに向いている。別に特に意識しなくても、2時間も歩いていれば、自然とアイデアやプランが湧いてくるのである。
ただし問題は、その湧き出してくるアイデアを紙なりスマホなりにメモすることが水中歩行中は難しいということだ。そこでテクニックとして使えるのが替え歌である。脳内で再生している音楽にあわせて、思いついた言葉を即席で鼻歌に乗せて、何度も繰り返しうたっていると、そのとき思いついたアイデアなどが脳内に定着しやすいのだ。別に替え歌の形にしなくてもよいのだが、かつて文字や書籍といったメディア(記録媒体)のない時代、吟遊詩人が歌にのせて歴史を物語っていたのは、「歌う」という行為自体が人々の間で記憶しやすく、流通しやすかったからだとメディア論ではいわれている。要はそれと同じメディア効果を、現代でも自分ひとりのなかで簡潔に完結させられるのがプールというアーキテクチャなのである。
ちなみに私はほぼ毎日のようにこのメソッドを使って、プール・ウォーキング中に思いついた内容を記憶し、プールから上がったらすぐに「ジャーナル」アプリにメモするのが日課になっている。
余談ではあるが、そもそも私がここまでプール・ウォーキングを推す理由も、まさにここにある。それは当初は歩行という身体運動のリハビリテーションのために始めたプール・ウォーキングだったが、途中からは精神活動(発想・記憶といった脳内認知活動)のリハビリテーションという観点でもポジティブな効果をもたらしていることに気づいたのである(まさにその効果のおかげで、私はこの原稿を執筆することもできている)。健全な身体にこそ健全な精神が宿るのは当然で自明のことだが、これを自分ごととして体感・発見できたのは非常に大きかった。しかもそのための環境は、公共プールという形で、まさに私達の社会がコモンズ/共有インフラとして運営しているのだ。だとすれば、その場所/行為に関する知見もまたナレッジとして言語化しておきたいというのが、本原稿を執筆する私のモチベーションとなっている。
・瞑想水中ウォーキング(マインドフルネス瞑想の取り入れ):
いま書いたように、プール・ウォーキングはアイデアの着想・整理といった知的活動に適している。水泳やランニングなどに比べれば運動強度は低く心拍数もそこまで上がらないので、運動しながらでも思考という脳内言語活動をするための「余裕」が確保されやすいからだ。
その上で私がさらにプール・ウォーキング中に編み出したメソッドは、いわゆるマインドフルネス瞑想の要素を取り入れるというものだ。
そのやり方は実にシンプルで、「目を瞑って水中歩行する」というだけである。目を瞑るとまっすぐ歩けずレーンからはみ出してしまう可能性もあるので、プールの壁を水中で片手で軽くなぞるように触れながら、それをガイド(手がかり)にしてゆっくりと深呼吸しながら歩くのがおすすめだ。ちなみにプールの水中歩行レーンは、スロープや階段などからアクセスしやすい一番端のレーンにほぼ必ず設置されているので、レーン内の左右どちらかは必ず壁沿いを歩くことになるので、この「壁を触れながら目をつむる」というのがやりやすい。
もちろん最初は怖くてほんの数mで目を開けてしまうが、別にそれでよい。ただし水中歩行レーンは皆ゆっくり歩行しているので、それでも特に危険性はない。すぐにその環境に慣れて、あっというまに25m連続でも目を瞑って歩けるようになる。そうすると、マインドフルネス(感覚への集中力)もより一層研ぎ澄まされて高まっていく。
本稿はマインドフルネス瞑想のメソッドやメリットを紹介することが目的ではないので、その内容じたいは詳説しないが、簡単にいうとそのポイントは「”心を無にする”というよりも、”いまここにある状況・感覚にひたすら集中する”」ところにある。これによって、まさに心が無に、つまり雑念や煩悩、不安や迷いのようなネガティブな感情が消えていき、リラックスしつつも集中力の高まった状態になっていくと言われている。私はマインドフルネス瞑想が流行り始めた頃から、たまたまとあるきっかけで日常生活にも積極的にこれを実践するようになっていたのだが、これが実にプール・ウォーキングとうまく噛み合ってくれる。
要はこの瞑想水中ウォーキングは、視覚情報を遮断することによって、その分だけ他の感覚が鋭敏に研ぎ澄まされるので、マインドフルネス効果が高いのである。たとえば聴覚であれば、水だけでも実に多彩な音が聞こえてくる。ありとあらゆる泳いでいる音(水を手でかく音、足で蹴る音、クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ特有の音など)や、遠くで聞こえるシャワーの音、プールのスタッフがホースを使って床を清掃している音などが、実にクリアに四方八方から聞こえてくる。触覚も同様で、普段は気にならないちょっとしたプール内の水流の動き(水のうねりや、壁の排出口から噴出されている水の勢い)、わずかな水温・気温の違いや変化にも敏感になる。また、もちろん水中歩行レーンには他の人もいるので、ぶつかったりしないよう周囲の情報をキャッチしようとするのも、感覚を研ぎ澄まし集中力を高めるバフ効果をもたらしてくれるのだろう。
ちなみに私は何度か経験したことがあるのだが、実はこの感覚は「滝行」にも少しだけ近いところがある。滝行はその水流のあまりの衝撃の強さと水温の冷たさとで、雑念という雑念はあっという間に吹き飛び、極めて意識もシャッキリかつスッキリするのである。もちろん滝行とまではいかないが、水の流れや清涼感を感じることで、マインドフルネスを高めるという共通点はある気がしている(むしろプールは沐浴と並べたほうが適切かもしれない)。ちなみに私はプール・ウォーキングのこうした効果を「心の洗濯」と勝手に呼んでおり、すでに述べたとおり、もはや私にとって身体(フィジカル)のリハビリテーションだけでなく、精神(メンタル)の健康という観点からも重要なルーティンとなっている。
ということで、いささかスピリチュアル成分多めの記述になってしまったが、この手のマインドフルネス関連のアクティビティ(瞑想・ヨガなど)に興味がある人は、ぜひプールでの瞑想歩行も一度試してみてほしい。実際、「プールの中で目を瞑って歩く」というのはほぼ全く危険性もなく簡単にできる行為なのだが、これほど簡単に同じようなことが安全にできるスポーツやアクティビティは他にはあまりないと思われる。実際、公道上でこれをやるのは危なすぎるし、ジムのマシン運動では目を瞑っても前進移動まではできないので、「一寸先は闇」的な緊張感が足りず、おそらく集中力や感覚がそこまで研ぎ澄まされないはずだ。
ちなみに蛇足だが、長野の善光寺の本尊の下には、「お戒壇巡り」というものがある。これは完全に真っ暗闇な空間を手探りで歩いていき、「極楽の錠前」という金属に触れて、地上に戻るというものである。あくまでこれは私見だが、要するにマインドフルネスを高めるための体験的装置なのであり、瞑想水中ウォーキングの体験は私がこれまで体感したもののなかだとこれが一番近いといえる。
・歩き方の強度やペースを適度に変えて、運動強度にメリハリをつける:
これはスポーツをする人であれば誰もが無意識のうちにやっていることだと思うが、適度に運動強度にメリハリをつけてほどよいリズムをつくるのも、そのスポーツを飽きずに続けるためのコツの1つだ。
この点、地上でのウォーキングやランニングは非常に簡単である。疲れたら歩いたりペースを落とし、運動強度を上げたければ走るペースを上げればいいだけだ。しかし水中歩行となると、この点はいささか事情が異なる。何度も書いているようにプールでは水中抵抗が大きく働くので、歩く速度を変えようと思ってもその可変幅には限界がある(というより、そんなに速くは歩けない)。
むしろプール・ウォーキングの場合は、ゆっくり歩いているときのほうが運動強度を上げやすい。ポイントは、普段よりも手や足を大きく動かして、水中抵抗を多めに作りながら動かすことだ。かなり大げさで大振りな手足の動きで歩くのもよいし、片足・両足でジャンプする動きを入れるのもよいし、HIIT(高強度インターバルトレーニング)のように手足を小刻みに素早く動かす動きを水中で行うのものよい(地上ではとても連続してはできないような激しい動きも、浮力が働く水中ではそこまで心拍数が上がらず無理なく行える)。
特にこれらの動きは、歩行レーンを歩いている人が多くて混雑していたり、水中で歩くペースがかなり遅い方が前にいたりするときなどに積極的に挟むのがよい。さきほど紹介した水中瞑想ウォーキングに切り替え、歩く速度を遅めに調整するのもおすすめのやり方である。
これがなぜおすすめかというと、こういうメソッドを取り入れてメリハリをつける選択肢を用意しておくことで、「遅い人が前にいるせいで、自分の歩くペースが邪魔されている」などとネガティブな感情を抱くのを避け、「むしろ運動強度やマインドフルネスを上げるチャンスタイムがやってきた」とポジティブに捉えなおすことができ、無駄にイライラしたりすることがなくなるからだ。小さいことのようだが、プール・ウォーキングを楽しく平静なマインドセットで長く続ける上では、大事なメソッドだと私は考えている。
またこれは「水泳編」の項目で後述するが、水中歩行と水泳を織り交ぜるのもよい(というか、泳げる人であれば自然とそうなるだろう)。たとえばクロール(自由形)や平泳ぎをこなして心拍数が上がったら、水中歩行レーンに移って休憩とクールダウンをかねたウォーキングを行い、また水泳レーンに戻る……といった運動強度の変化をつけることで、それこそ先述したようにサウナでの「ととのう」にほんの少し近い感覚を得ることもできる(あくまで私見だが、思いっきりクロールで泳いだあとに水中をふらふらと歩いてクールダウンするときの感覚は、たしかに「ととのう」に近いものがあるなと感じている)。