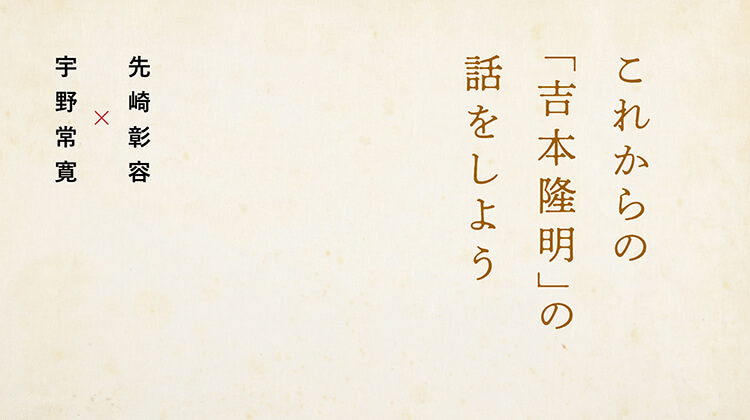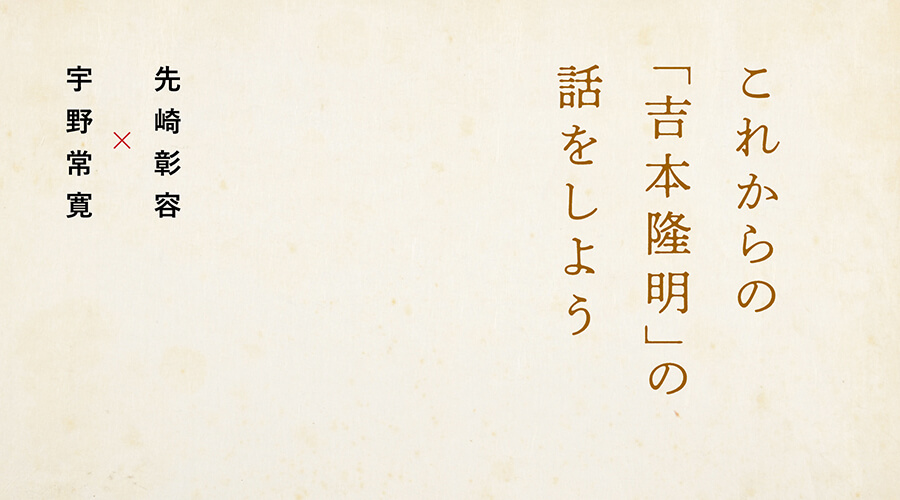「戦後最大の思想家」と呼ばれながらも、今日においてはほとんど読み返されることのない吉本隆明──。しかし、その仕事は今日の情報社会でこそ参照されるべきである。
日本思想史が専門の先崎彰容さんと宇野常寛が、吉本隆明の再読を通して現代の個人と資本主義の問題、国家と民主主義の問題、そして土地と身体の問題まで話しました。
端的に言うとね。
『共同幻想論』の可能性の中心
宇野 2020年7月、先崎さんがNHKの「100分de名著」で吉本隆明の『共同幻想論』(1968年)を解説されていたわけですが、ちょうど僕もその数ヶ月前に刊行された『遅いインターネット』でも吉本を取り上げていたので、とても勉強になりました。先崎さんは番組の中で、今日の情報社会における個のあり方と、当時の吉本隆明の問題意識にリンクするものを感じて、その観点から吉本隆明の再読を試みたと述べられていましたが、その視点は僕の『遅いインターネット』での試みと、とても近いものを感じました。なので、今日はそこを入り口に、いま吉本隆明を読み返すことの意義というか、そこから先にどんな地平が見えてくるのかということについて、お話を伺えたらと思います。
先崎 はい、よろしくお願いします。僕が『共同幻想論』を取り上げることをNHKに提案したのは1年ぐらい前のことでした。『共同幻想論』は非常に読みにくい本で難解だと言われていて、あまりちゃんと読み解かれていない。それを一般の人の手に届ける必要性があるだろうと思ったので。
この本はすごく基本的に言うと、「国家の成り立ちは何か」ということの根源を、「共同幻想」をキーワードに問うたものです。学生運動が激化していた1968年に刊行されて、当時は団塊の世代の左翼学生に、国家を批判的に乗り越える試みとして読まれていました。僕にとって国家の成り立ちを問うことは大事な問題として興味があるけど、それだけには留まらない奥行きと深みがこの著作にはあると思います。
たとえば2020年現在、僕らはネット社会で情報というものに取り囲まれて、その意見に一喜一憂して生きるようになっている。SNSで炎上したり、それが原因で自殺する人まで出てきてしまっています。生身の手触りのある空間じゃなくて、画面の向こう側の世界を現実の中に取り込んで死に至る可能性がある。これは「共同幻想」と言えるわけです。そこまで射程を広げて読んだら面白いんじゃないか、と考えたんですね。
あと、もう一つ僕が興味あるのは、吉本は時代状況に関係なく、原理的な思考をしている点です。吉本は1960年代に、谷川雁、村上一郎と3人で「試行」という雑誌を創刊して、当時の政治の動きから超然としたことを書いている。若いころの鹿島茂さんは『共同幻想論』を読んだ際、「これが時代をどう解き明かしてくれるのか、わからなかった」という印象を持ったという。
宇野さんの『遅いインターネット』は、「オリンピックを前にして、この国はビジョンを持っていなくて、否定と批判しか言葉を持てていない」という話から書き始められてましたよね。そういう、小さな正義を信じ込んだり、独善に陥って何か決め込んでいる人には、特有の世界の見え方があるわけです。それが吉本の説いていた「個人幻想って何だろう?」と考えることにつながるような気がした。ネット上でつながって、みんなで誰かを叩いている人たちが、共通で持ってしまっている「幻想」というものは何だろう? そういうことを考えると、吉本ぐらい深い思索をした人のものを参照軸にしないと、逆に時代は見えにくいんじゃないかと思ったわけです。
吉本は1960年に、日米安保改定の反対運動が激化していたとき、「戦後世代の政治思想」という短い文章で、「現在ラジオ、テレビ、雑誌、週刊誌、映画などのメディアの発達で、きわめて容易に社会の動きに参加できる状況がありながら、その思想を生み出すはずの主体意識が希薄になって、不安定である」「この不安定さを、ヒステリックに駆り立てているのが文学者や思想家たちだ」と述べてるんです。まさに、2015年のネット上での安保法制の議論とか、現代のネット社会にそのまま当てはまる話ですね。
さらに吉本は、「知識人や文学者は、安保改定問題をアメリカの軍事力に日本民族が従属するか、独立するかという民族問題にしている」と指摘している。2015年の安保法制も、沖縄の基地問題もそうですよね。
結局、思想的には左右の両極にいるように見えて、大江健三郎も石原慎太郎も、民族感情を煽っている民族主義者であるという点では同じだと吉本は言っている。では何が一番大事なのかを考えるときに、彼は情報のコミュニケーションで錯綜している人間たちに「お前らちょっと冷静になれ」と言ったんです。それで、マルクス主義の用語で「国家独占資本主義」という言葉がありますが、国家と官僚による資本の主導と独占、つまり巨大資本の存在が、日米関係に深いかかわりを持っていると主張しています。民族という共同幻想に取り込まれることを暗に警戒している。言われてみれば当たり前のことですが、今日でもかなり有効な言説でしょう。
ともあれ、いま僕たちの社会は、自分らしさとかアイデンティティをどこに求めればいいのかという問題に非常に悩んでいる。これも宇野さんが本で書かれていることですが、かつてはテレビの時代で受動型だったのが、ネットの時代になって参加型になったのはいい。けれど、一人ひとりが小さな論客になってあふれかえるようになる中で、ほんとうに人々は確信をもってアイデンティティを発揮できているのだろうか、と。
そもそも、個人が自分らしい意見を立てるというのは非常に難しいことで、誰にでもできることではありません。そうなると、多くの人は罵詈雑言とか否定形のコミュニケーションによってしかアイデンティティを確保できないという非常に不健全な状態になっている。情報化社会は、個人の発信を促すと同時に、自己同一性を解体してもいる。これが宇野さんの本から感じた感想なのです。この問題を考え直すために、吉本の原理的な思想を応用したいと考えたわけです。
戦後思想史の脈絡と「関係」という問題設定をめぐって
宇野 それは実存の問題系ですね。吉本の著作は、1970年前後の学生運動の最盛期から今日まで、実際に書かれたものから半分離れてもっぱら実存の問題として読まれてきたことは否めない。そして吉本自身もそうした自分の読まれ方を引き受けることで、影響力を最大化してきたところがあると思います。ただ、先崎さんがおっしゃるように吉本自身は、実存に還元される以前の「関係」にこだわってきた側面もあるわけです。たとえば『共同幻想論』は端的に言うと、当時絶大な影響力を持っていたマルクス主義とは違う方法での国家批判が可能かを考えたものだったわけです。マルクスが社会の下部構造(経済)に着目したのに対し、吉本はむしろ上部構造(文化や宗教)、もっといえば幻想の領域から議論を展開した。ここでのポイントは幻想領域を扱っているにもかかわらず、それが少なくとも書かれたものの段階では必ずしも実存の問題に閉じていない。いや、閉じまいとする意思のもとに幻想を生み出す「関係」の問題に手を伸ばしたところだったと僕は思います。だから吉本隆明を実存の問題として読むという態度から離脱して、「関係」の思想家として読み直すことが、吉本の再評価の第一歩なのではないかと僕も考えます。
先崎 「関係」という概念は、非常に重要ですね。以前、吉本隆明と直接面識のあった京都大学の先生が、「僕は吉本自身から、個人幻想によって共同幻想を全否定しようとは思ってないと直接聞いたことがある。むしろ、共同幻想という言葉を関係と言い換えた場合、その関係のあり方を問いなおし、可能性と危うさをきちんと見出そうとしてたんだ」と聞きました。
それで思い出したのですが、今年は三島由紀夫没後50年なので、映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』が公開されましたね。あの映画の最大のセールスポイントは、三島と全共闘側が何をしゃべっていたのかを、けっこうちゃんと再現してるところです。その中で、全共闘側の芥正彦らは「関係からの絶対的な自由を求めたい」としきりに言う。一方の三島由紀夫は、彼の強調する「文化概念としての天皇」とともに、理想の日本を取り戻したいと言った。つまりもう一度、「関係」の中に没入したいと言ったのです。
「関係」という言葉をさらに平易に「つながり方」に変えるとしたら、僕たちは今、ネット上への書き込みという行為によって社会と容易につながってしまう。それは実はアリジゴクに足を引き込まれることに近いんだけど、無防備なままネット社会に身をさらしてしまっている。三島や東大全共闘、吉本らの1960年代の発言は、こうしたネット社会における個人と社会の関係性を問うためにも面白いんじゃないかしら。
宇野 そして、なぜいま「吉本隆明」だったのかというと、今日の世界では、経済と情報の発信を通して──この二つは、本質的なところで重なり合っているわけですが──世界に素手で触れることができる。少なくとも、素手で触れられるという幻想が共有されてしまっている。しかし、そのためにむしろ自分が触れられる範囲や、影響を与えられる力の弱さに多くの人々は耐えられなくなっている。だからこそ、人間はグローバルな市場ではなくローカルな政治にアイデンティティを託すようになる、というのが、僕があの本で提示した世界観です。その人の作り上げた商品やサービスの成果、またはポテンシャルが多角的に評価されて影響力が決定される経済とは異なり、民主主義を用いた政治の世界では一人一票の原則が貫かれているわけですし、それ以上に自分の考えを社会に発信することで、ほんの少しかもしれないけれど、確実に世界を変えられたと信じることができる。もちろん、たとえ自分ではなくてもできる、ネジや歯車のように感じてしまう仕事でも、一人ひとりの行動は確実に世界を変えているのだけれど、自分の意思を言葉にして発信し、それが他の誰かを少しでも動かすことには圧倒的な手触りがある。この情報技術が与える圧倒的な手触りは諸刃の剣で、人々を生き生きとさせる一方で、その強すぎる快楽のために自分と社会との距離感を見失ってしまう人も多いし、この快楽を悪用すればいくらでも人を騙すような動員をかけることができる。
そしてユニークな存在であることが要求されるニューエコノミーの世界とは異なって、今日のアイデンティティ・ポリティクスが全面化した民主主義は手っ取り早く「自分と同じような誰かがいること」を確認する装置になっている。
僕は、一部の恵まれた人以外は経済ではなく政治を、それも他の誰かを否定するかたちで、「自分たち」を確認する装置として選ぶだろうし、既にそうなっているという前提で書いているわけです。
要するに、吉本が半世紀前に主張した「自立」の問題が一周回って再燃してきている。こうした時代だからこそ、吉本が展開した「関係」をめぐる思考をもう一度、ただし少し変わった角度から読み直してみようと考えたわけです。
つまり、誰もがその影響力はともかく世界に素手で触れられてしまう情報環境が整ってしまった時代において、人間はどう世界と関係したらいいのか、という視点から吉本隆明を読み直してみたいんです。
先崎 ちょっとその議論の前提を戦後思想史的に復習しておくと、実は「世界に素手で触れる」ような「実感」の希薄さの問題は、1960年代当時にもキーワードになっていました。この焦燥感を埋めようとするために、当時30代だった大江健三郎は『沖縄ノート』(1970年)などを書き、左派的な視点で沖縄や広島の問題にコミットした。逆に石原慎太郎の作品は、性の快楽に没入し自己を蕩尽させる一他方では個人の対極にある政治、ファシズムがもつ合一性の魅力に傾倒する。女性ではなく、今度は国家に自己を解消してしまうわけです。大江も石原も、性的なものにこだわることで、生の実感を得ようとした点では同じです。この点を指摘して、「もうちょっと冷静になれ」と言い続けたのが、おそらく江藤淳だった。
特に石原慎太郎については、セックスにせよ政治にせよ、大人がする行為にも関わらず、本来の意味での「大人さ」が決定的に欠けているんですよね。男女の営みにおいても、政治においても、ままならない他者との関係を構築していく駆け引きが必要なものですが、石原の場合、性的な合一化にこだわったり、国家と自分を密着させたがったりする。
要するに、アメリカという巨大な「父」から政治的に自立できないというコンプレックスが、そうした左右の性急さを生んでいた。そこに対して江藤淳は、性と民族的情念に絡めとられるべきではないと言い続けた。この鍵括弧つきの「政治」が1970年代半ばに終わりを迎えます。その後の日本は、資本主義の「欲望」つまり消費によってアイデンティティを確保する時代へと移ってゆくことになります。この構造に自覚的だったのが、吉本隆明だったという流れですね。
宇野 はい。そこで吉本は、1980年代の消費社会の進行に対して、いま読み直すとびっくりするくらい楽観的な態度を示している。それは、消費という行為が、大衆が初めて手にした自己幻想の表現方法だったからで、もちろん留保はつけながらも吉本はここに何らかの「自立」の契機を見ていたことは間違いない。
しかし、これは今となっては当たり前のことなのだろうけれど、消費による「自立」など成立するわけがない。当時は、モノの消費による自己表現というパフォーマンスが前の時代に対するカウンターとして意味があったからそう見えただけで、それが当たり前のことになった時代には化けの皮が剥がれてしまう。結局みんな同じマクドナルドのハンバーガーを食べていることに安心するのでは、それは「自立」とは真逆の態度だし、ならば自分はスローフードを食べることで消費社会に抵抗しているつもりになったとしても、それはスローフードという商品を消費しているだけで、資本主義下の差異化のゲームをプレイしているにすぎない。それはさんざん批判されてきたように自己を記号化することにしかならない。
今日の情報社会下における「モノからコトへ」の変化は、自己表現の回路の変化だと位置づけることができます。他人の作った「モノ」の消費から自分が体験する「コト」の発信へ。しかし、ここで明らかになったのはほとんどの人間に語るに値する「コト」などなく、むしろその空虚さを埋めるために、「発信すること」で共同幻想に接続し、貧しい自己幻想を底上げするようになるということです。自分の言葉で民主主義にコミットすることで自立を試みた結果、逆に共同幻想に依存してしまうという皮肉な状況が定着してしまっているわけです。
「言葉によって言葉を取り戻す」という戦略はいかに可能か
先崎 伺いながら思い出していたんですが、実は明治時代末期、日露戦争後の1910年に、石川啄木が『時代閉塞の現状』で、今の話と似たようなことを書いてるんですね。明治維新から日本は富国強兵で走ってきた、でも日露戦争で勝ったあとの若者には閉塞感が漂っている。戦争に勝って、富国強兵の「強兵」は若者の興味から消えたし、国家目標を達成してしまったから「国」も意識から消えて、残ったのが「富」だけ。
当時は学校を出ても就職もまともにないような時代で、優秀な若者は富を追求するけど、そこに関われない奴らは都会の中で悶々としてる。自分もその一人だからこそ、三行詩の歌を描いて憂さを晴らしているのであって、近代という時代が、こうした内向的で閉塞に満ちており、憂さを晴らすように自分が詩を書いているとしたら、ほんとうに不幸な日々を送っている。だから、詩を書かない日がいい日なんだ、と。
こういう感性って、SNSで何かに対してネガティブなツイートをしたり、何か大きなものとつながることで卑小な自分から目を背けたいと感じてしまう今の社会の情報発信にも通じているような気がしました。
宇野 まさに通じていますね。政治は一人ひとりを尊重するのだけれど、経済は成功者しかしてくれない。今、「アイデンティティの政治」が各国で常態化しているように、政治と経済のパワーバランスが後者に傾くとどうしても政治の承認の再分配装置としての側面が強くなりすぎてしまう。このとき、現代のSNSを中心とした情報環境、つまり「発信する快楽」を用いた「速すぎる」インターネットは民主主義を半ば機能停止させてしまうことになる。
では、その格差を生み出したグローバル資本主義を批判すればよいのか。もちろん、批判は必要なのだけれど、それを単に国内格差を増大させるとか、文化を画一化させるとかいう紋切り型の批判で済ませてしまうわけにもいかない。比喩的に述べれば、ラストベルトの自動車工とシリコンバレーのアントレプレナーの格差は広がっている一方で、アメリカとベトナムの経済格差については、かつてでは考えられないくらい縮まっている事実がある。もちろん、この自ら生み出した怪物を人類はどうにかしないといけないのだけれど、SNSに溢れている紋切り型の批判は、それこそ承認の問題を解決するためのサプリメントみたいなもので決して有効打にはならないのではないか、ならどのような建設的な批判があり得るのか、ということを考えないと意味がない。吉本隆明が生きていたらたぶん、そう言ったと思うんです。
先崎 そう、その構造は、マーク・ザッカーバーグ主宰のブッククラブで取り上げられて話題になったモイセス・ナイムの『権力の終焉』(2015年)という本でも書かれていたことです。日本では格差社会と言えば、単なる所得の二極化というイメージなんだけど、それは二つの意味で間違っています。一つは、アメリカ国内における二極化とは白人中間層の没落が起きているという意味であって、その反面、世界各地からラティーノやアジア系、中東系などの非白人の移民が急速に増えていて、非正規の時給制の仕事で充分に生活できるようになった。もう一つは、世界的に見ても、いま宇野さんがおっしゃったベトナムの例のように、新興国の30億ぐらいの単位の人間が経済的に上昇し、生きていけるようなっている。
そういう世界全体の構造を見ないで、自分たちの主観的な肌感覚や実存の問題ばかり喋ることには意味がない、といったことが、まさにナイムの本にも書かれているんですね。
宇野 1980年代以降の吉本隆明は、普通に考えれば時代の空気に流されて安易な消費社会肯定論に陥ってしまったことは間違いない。もちろん、それはマルクス主義が輝いていた時代を引きずっていた人々を解放する力はあったのかもしれないけれど、いま読み返すと今日ここで話されているような問題にあまりに無警戒だったと言わざるを得ない。さらにこの時期の吉本は理論的、体系的な著作は少なく、かなりの部分がアイデアスケッチ的なメモのようなものだと思うし、中にはほんとうに思いつきを書き殴ったものもある。しかし、その一方でこの時期の未整理の吉本の予感のようなものが今日の情報社会を予見したことは間違いなくて、要するに吉本は、これから20世紀を席巻した共同幻想は経済構造的にも情報環境的にも衰退していって、人間は高度に発達した資本主義と情報技術に支えられて生きていけるというビジョンをおぼろげに示している。
これは事実上、今日の情報社会を決定づけている、ときにカリフォリニアン・イデオロギーと揶揄されるアメリカ西海岸の情報産業のイデオロギーとも、親和性が高い考え方です。そして吉本はこの高度資本主義と情報技術によって支援された人間が世界を把握する視線を、臨死体験の視線に例えている。古今東西の臨死体験の記憶はどれも似通っていて、自分が少し高い位置から死にかけている自分の身体を眺めている、というもので、要するにそれは自分自身の位置を自分が客観的に見ることの出来る視座を獲得しているということです。
先崎 そうですね、言ってましたね(笑)。
宇野 これは、今で言うところのGoogle Mapsのようなもので、つまり吉本は人間が世界を観る方法が情報技術で切り替わるように、人間の抱く社会像も切り替わるだろうと考えた。ここまではよいのだけれど、そこから吉本はかなり安易で、楽観的なユートピアを提示していく。この臨死体験的、Google Maps的な視線は要するに胎児の視線の全能感で、そこに吉本は救済のビジョンを見出してしまう。高度資本主義と情報技術という「母胎」に包まれた胎児たちに溢れた社会はいままさに実現しているわけですが、これはどう考えてもフィルターバブルに安住し、ときにフェイク・ニュースを拡散して精神の安定を図る「胎児」たちに溢れたディストピアでしかない。だから、僕はこの時期の吉本がどこで間違えたかが重要なのだと思うわけです。
先崎 そういった現代社会の構造に対する見立ての上に、宇野さんの本では、世界との「つながり方」への一つの処方箋として、「書く」という行為を取り戻すということを掲げられているわけですよね。それが「遅いインターネット」の実践であり、僕の言葉で言い直すと「手ざわり」ということになるんだと思うんですが。
宇野さんとしては、そういう手ざわり感というか物づくり感を言葉に対して取り戻すことが、いま挙げられていたような人々なり、母型論的な主体なりに対して、一つの処方箋になるという感覚がおありなんでしょうか?
宇野 僕はそう思っています。なぜならば、人間はこの「書く」ことの快楽という欲望をもう手放さないだろうと思うからです。人々は今、世界に素手で触れるためSNSに言葉を書いて、そして実は書かされていることに気づかないでいる。そしてそれは麻薬的な快楽を伴っていて、なかなか抜け出せない。こうした快楽に溺れている人に対して、書く欲望を禁欲しろと言ってもそれは難しくて、やはりどこかに世界に素手で触れる感触を求めてしまうのが人間という生き物だと思います。そこで、どうせなら「書く」という行為を通じて、むしろ牢獄から脱出するべきだと考えました。
先崎 その結論って、ある意味においてはすごく陳腐なことじゃないですか。これは吉本隆明の思想についても同様で、「個人幻想」とか「大衆の原像」とは何なのだろうとか考えたときに、吉本の言っていることって、よく言われるように実に陳腐なことなんですよ。
ただ、陳腐なことほどつまずいて考え直す必要があって、吉本の場合、キーワードになるのが「裂け目」という言葉なんです。この言葉遣いの意味が、長いことわからずにいたんですが、最近「柳田國男論」を読み直していて、そこでも「裂け目」という言葉を使っていることに気がついたんです。
「柳田國男論」の骨子を簡単に言えば、柳田國男の文体というものが、一方では『遠野物語』で見たような古きなつかしき日本の原風景、いわゆる常民の情緒に内在した文体で書いていながら、他方で、民俗学とか文化人類学などの制度的な学問の枠組みを意識して書いている部分もある。つまり視線が二重化してるということを指摘した。こうした柳田の言葉遣いの二重性を、吉本は「裂け目」と呼んでいたわけです。
そして、言葉によっておかしくなったものを、言葉で取り戻すとおっしゃった宇野さんのテーマは、ある一つの言葉遣いに没入して自己を記号化して、言葉と意味の関係を固定化してしまうのではなくて、もう一度そこに裂け目を見出し、世界との「関係」であったり「幻想」であったりの作り方を、不断に再設定し、更新し続けていくということだと思います。
宇野 はい、まさにそういうことだと思います。
先崎 ただ、当然ながらそれは誰にでもできるわけではない。そもそも言葉によって自己のアイデンティティを満たすために、みんなTwitterなり何なりを始めたはずなんですよね。自己の意見を言うために。にもかかわらず、その言葉はもちろん洗練されてないし、逆に個性を求めれば求めるほど、実はものすごい凡庸な言葉しか言えなくなって、記号化の中へと入り込んでいくわけですよ。自己を求めれば求めるほど、それが拡散して消えてしまったり、ある否定語に集合した個性なき者同士がうなずきあうことによって束の間の安堵を得たりといった悪循環に陥ってしまう。「自立」はほんとうに難しい。
これに関連して、吉本隆明全集の月報を書くために『ハイ・イメージ論』を読み返していて気づいたことがある。「ファッション論」の中の話なんですが、吉本は「高度消費社会の問題は反復と循環だ」ということを強調している。ファッションは飽食の時代の象徴で、その究極がファッションモデルのはずです。ところが、ファッションモデルの体型は、消費社会が求める美を徹底的に追求した結果、拒食症だったり、北朝鮮とかで飢餓に苦しんでる人々と同じ状態になっているじゃないかと。最も豊かな時代が一周回って貧困社会を生きる人と同じになっている。循環している。
宇野 ああ、ありましたね。
先崎 つまり、真や善や美を徹底して追求しても、それが気づかないうちに悪に転落していくぞという、吉本にとって敗戦体験以来の一貫した問題関心なんですよ。
だから、今の言葉の話にしても、個性というのを徹底的に追求しようとしたなれの果てが、まったくの記号化された個人になってしまう。そのことに、僕らはおそらく耐えられないんじゃないか。徹底的に自由に個性を追求する状態に、人は耐えられないんじゃないか、というのが僕の立場です。ここが、僕が保守主義者であると言われる所以なんだけれど。
個性を市場や情報環境の流れの中で無理やり求めようとした結果、自己主張は消費の一部に回収されて無害な記号化に陥ってしまう。そうした人間たちの発する言葉は、否定形のコミュニケーションによって島宇宙を作り、互いにうなずき合うような共同性しか生み出せない。アイデンティティが非常に痩せ枯れて陳腐化してしまっている。それが僕には、見るに堪えない。
宇野 その点についての僕の考えは、内実を陳腐にしないためには、方法はベタで陳腐なコミットメントを恐れるべきではない、ということだと思っています。吉本隆明から糸井重里に至る1980年代的な消費社会肯定論が陥った罠は、ひとつにはここにあったはずで、誰かと異なった言動を選ぶことが自己目的化すると、どんどん表現がやせ細っていく。この問題を回避しないとまずはいけない。そして次にこれも糸井重里が象徴する問題なのだけれど、彼は80年代からずっと、戦略的に「語り口」だけで価値を生もうとしているわけです。それは最初は、「それが正しければどのような語り口であっても構わない」というそれまでの左翼的な言葉に対するアンチテーゼだったのだと思うのだけれど、その「何を」語るかではなく「どう」語るかという点だけで、すべてを表現しようとする姿勢は、結局語り口は巧みだけれど内実は無内容なこの国のテレビや広告文化のようなものしか産まなかったし、糸井さん自身もいまそのツケを払わされているように思うわけです。
だから僕は方法や語り口はときにベタで「も」いいのではないか。結果として先崎さんのいう「裂け目」のようなものをよりたくさん生み出すことが大事で、そのためには陳腐なアプローチを恐れてはいけない、と思い直した時期があったんです。僕もこの本を出して、さんざんベタに「啓蒙主義者に回帰している」と批判されたのだけど、それでいいと思っている。むしろ、そこをサボってしまうと、タイムラインを四六時中眺めながら自分が動員したいと考えている層に「共感」される立ち位置はどこかを考えながら生きる人生が待っている。こうした閉じた相互評価のネットワークの中で行われる動員のゲームから、何も生まれないことは自明です。
今のSNSが中心になった情報社会の一番まずいところの一つが、閉じた相互評価のネットワークの中で共感の獲得競争と動員のゲームをやっていると、問題そのものは議論されなくなることです。
こうした評価経済のゲームでは、ある問題が起きたときに「この問題はどう解決できるか」でもなければ「この問題設定は正しいのか?」でもなく、この問題に対してどう回答すると他の人からの好感度や市場価値が上がるか、に最適化していくことが勝利に近づいていく。結局、主流派と、反主流派、そしてこの二項対立をバカにしながら結局状況にコミットせずに主流派を利するという三つくらいの紋切り型に集約されていく。でも大事なのは、その問いそのものを解決することと、問いの妥当性を問い直すことです。しかしこうした本来の議論はこのゲームからはじき出されてしまう構造になっている。
柳田から吉本に受け継がれた「裂け目」はこの構造からの脱出口として、いま考え直されてもいいのかもしれません。要するに、ある言葉が吐き出されたときに、今は情報環境がマイナスに作用して人間を本来複数に開かれているはずの言葉の意味を一つに限定してしまう。だからこの罠の存在を踏まえた上で、インターネットに発信するという、いつの間にか当たり前になってしまった行為に相応しい書き方を開発するところからはじめよう、と今の僕は考えています。
先崎 その宇野さんが回帰する表面的な陳腐さを恐れない啓蒙主義というのは、僕においては手ざわりに重きを置く保守主義であって、究極的には「政治的なるもの」への抗いなんですよね。ここで言う政治とは、他者を他者としてでなくマスとして扱い、自分の支配力をどれだけ拡大するかの道具としてしか見ない技術主義のことです。そういう人々が、まさに今、臆面もなく前面に出てくる時代になっている。その最たるものがトランプのがさつな発言であって、アメリカや中国のように国際政治のメインストリームにさえなりつつある。
こうなると、やはり石川啄木が言ったような「赤裸々な自然主義が席巻する。所詮人間なんてのは性欲の存在だ。所詮人間なんてのは支配欲の存在である」みたいな言葉が主流になって、暴力性・政治性だけが臆面もなく出てくる。
これは個人的な体験ですが、知識人というのは、とにかく他人の評価に終始しがちで、Twitterに張り付きっぱなしで人格的におかしくなっちゃう学者もいる。これに抗うということが、僕にとっては人間がリズムを取り戻し、生き方を取り戻すということなんだと思うんです。
宇野 たとえば僕は「人」について書かない、というのはどうだろうと、いま考えているんです。僕らが「関係」というとき、つい家族関係とか男女の性愛とか、要するに人間同士の社会関係のことを想定してしまう。しかし、吉本の議論はもうちょっと広い射程をもっていたはずで、人間同士の関係だけではなくて、たとえば人間と人間の作り出した構造との関係でもあったはずなんですね。
消費社会を批判するとき、僕たちは要するに物事ではなくて人間と向き合えと述べてきた。西海岸の人たちを眺めてみても、情報社会の台頭の背景には明らかに消費社会への反省があったことは間違いないと思います。しかし、今度はその反動で、情報社会下に生きる人間は人間の顔しか見なくなった。ここには厄介な問題があって、いま先崎さんがおっしゃったように常にネットワーク上に吐き出された人間の言葉にばかり向き合っていると、逆に人間が人間ではなく、どういう投稿をしたら「いいね!」や「リツイート」を高い確率でくれるかを考えるようになる。そうするとだんだん他のユーザーが人間ではなく、機械のように見えてきてしまう。だから、僕はネットワーク上の言葉を介して直接その人に言及するのではなくて、あくまで人間以外の物事について書く、というのが一つの有効な方法だと思っています。誰それがいい、とか悪いということは直接書かないで、その人がかかわる物事のほうに焦点を当てて論じていく。そのほうがかえって、人間を数字や機械のように見てしまう罠から逃れられると僕は思っているんです。
先崎 ネットという新しい社会空間から離脱し、ベタな意味での他者への関心が必要なんでしょうね。現在の評価経済社会における勝ち筋が、あからさまに暴力化する政治システムしかなかったとしても、それがほんとうにアリストテレスの言う「善き生」なのだろうかという問い。こうした問いかけを続ける必要があるという気がします。古典という時間軸を利用して、現実に埋没してしまった私たち自身から離脱と俯瞰を試みるわけです。
そのためにも必要なのが、やはり吉本の『共同幻想論』なのではないか。幻想に取り込まれている自分をほんとうの意味で爆破する過激さ。野蛮さと過激さが、実は徹底した原理的思索においてのみ可能だということを、身振り=文体をもって示す姿勢。こうした精神の佇まいが、結果的に、凡百の書籍の瓦礫の中から、光を放って残ってくる。古典になる。
「フロンティアなきフロンティア」を、どこに/どのように求めるのか
宇野 今となっては、人間同士の狭義の「関係」に閉じてしまったネットワークの外側にこそ、空間的にも時間的にも、目を向けるべき世界の広がりがあるんじゃないか。そういう可能性に価値を見出そうとする人たちが、一人また一人と離脱していくことでしか、現状を相対化できないと思います。そういうポジティブな離脱可能を信じることができる、相互評価の閉じたネットワークの原理が働かない場所が「あなたがあるプラットフォームで何十万フォロワーいたとしても、ここでは無価値だ」と胸を張って言える裂け目を、こうなってしまった社会にどれだけたくさん作っていけるのかの勝負じゃないでしょうか。
2016年のブレグジットとトランプのショックで逆説的に明らかになったことの一つに、かつて西海岸の起業家たちによってコンピュータ技術とインターネットによる社会変革が成功した理由は、そこが解放された場であったからだということがあります。これまでとは違うルールで動くゲームを彼らはそこに新しく、次々と作ることができた。それは言い換えれば地球上にはすでになくなっていたフロンティアをサイバースペースの中に擬似的に作り上げることだと言えると思います。世界中の人間を超国家的に結ぶことができる場を、新たに作り上げたということだったわけです。
しかし、それから四半世紀が経って、ほんとうに世界中の人々を一つのネットワークで結んでしまうと、それ自体が世界を包み込む繭になってしまった。もはやインターネットはフロンティアでもなんでもなく、時代の閉塞感を象徴する場所になってしまっています。たとえばこの状況を利用して大統領の座を手に入れたのがトランプだったわけで、西海岸の理想は四半世紀足らずで敗北してしまった。かつて、サイバースペースがフロンティアとして機能することでかろうじて維持されていたものが、今は失われてしまっているのは間違いない。
先崎 そのフロンティアという問題設定に関しては、僕が20代くらいの時に佐伯啓思氏の『貨幣・欲望・資本主義』(2000年:2013年に『貨幣と欲望:資本主義の精神解剖学』として増補改訂)などの本を読み始めて、この保守思想家を面白いなと思ったときの気分を思い出しました。我々の資本主義が工業型から消費型になったことによって、たえず欲望を喚起し続ける社会、つまり無限のフロンティアを自動的に求めていくことが宿命化されて、微細な差異を作り続けることになった現代社会を、佐伯さんは批判的に捉えていた。
彼の見方に立脚して言えば、資本主義を駆動してきた欲望というものが、さらにインターネットの世界においてもう一段階広がって、ある意味でスピリチュアルなものというか、我々の心の中のフロンティアまで開拓するということになってきた。これが今の宇野さんのお話なのかなと思いました。
そうなったときに、我々はさらに情報空間なり、心の中なりに新しいフロンティアを開拓するということに取り憑かれ続けなければならないのか。それともその運動自体を回避するという態度を身につけるべきなのか。そのあたり、どういうイメージで考えていらっしゃるのか、もう少し伺えますか?
宇野 まず、佐伯啓思さんは90年代の後半から、これからの保守のあり方を考えたとき、何から何を保守すべきかを論じていたと思うんですね。それは要するに、これからの保守はグローバル資本主義に対する保守でしかあり得ないという趣旨のことを、佐伯さんは当時から述べていた。人間から世界の手触りを奪うグローバル資本主義に抗うための根拠としてパトリオティズムを重視したのだと思います。ナショナリズムと違って、愛郷を根拠にするパトリオティズムは、言ってみれば爪や髪の毛のように、切っても切れない身についたものとして否応なく存在してしまう。それを空位の玉座を守るように、ナショナリズムに便宜的に格上げする、というのが当時の佐伯啓思さんの戦略だったはずです。まるで、今のアンチグローバリズムの左翼が表面的に述べるようなことを、20年前に、しかもかなり理論的に、政治的なリアリズムを踏まえながら述べていた。こうして考えてみると、きわめて正確な状況理解に基づいた戦略だったなと思います。
20年前の佐伯啓思さんが、2016年のトランプをどう見るのだろうかというのは気になりますね。トランプは結果的に佐伯的な戦略を悪用するかたちで、愛郷をフックに世界の手触りを求める人々を釣り上げ、そして佐伯啓思が理想としたものは真逆の、即時的な高揚感に立脚した排他的なイデオロギーに回収していった。そういう怪物が現実に生まれてしまっているわけですからね。
先崎 なるほど。ただ、やはりフロンティアという言葉が喚起する空間の無限性を志向するイメージについては、非常に複雑な感想があります。保守的立場の人間にとって空間性は、「関係」によって出てくる時間性の積み重なりの範囲内なんですよ。たとえば、我々がものを買うことで人とつながったりするとき、営業マンなら「この顧客は自分からいくらで買ってくれるのだろう」と他者を数字に還元して評価したりするわけだけど、そういう「食っていくための功利的なコミュニケーション」だけでは、人間の精神は耐えられないと思う。そういう領域外に、友達と他愛のないことで駄弁るとか、無為でプライスレスな時間を担保することで、はじめて精神のバランスは保たれているわけです。だから、佐伯氏の場合は、そういう時間の積み重なりとして、歴史とか伝統を重視していたはずです。グローバル経済が世界を画一化、つまり無色透明な空間にするのに対し、保守の空間性はたっぷりと時間を含んでいる。
でも一方で、僕たちの社会はフロンティアを過剰に求めすぎた結果、地球上にもネット空間にも尽きてしまった反動で、原理主義化もしているんです。トランプ現象がある種の地域主義に基づいていたり、イスラム原理主義の過激派が、最先端のネット技術を駆使して文化復興を目指してもいる。つまり歴史と文化をめぐって、原理主義と保守主義を区別しなければならない。そのポイントは「過激化」にあると思います。僕らの世界は不可避的にグローバル化、近代化の波に呑み込まれている。それに対して反動的に対応すると、暴力やテロルを含んだ過激な原理主義になる。一方で、先ほどの友人との会話の例にあるように、保守主義とは本来、過激さとは最も無縁なはずなのです。その歴史と文化への興味関心は、心に養分を取り戻すためのものなのですから。
宇野 はい。だから、さっき先崎さんがおっしゃったフロンティアに取り憑かれることの罠はとても重要な問題だと思います。僕は大事なのは、無限の成長と万人の成功の可能性が信じられるユートピアという幻想が機能していることではなくて、いまこのとき、この場所を支配しているものから離脱して、別のルールで動いている場所に移動できることや、新しいルールを別の場所に作ることができること、そして今、ここのルールを書き換えられると信じられること。このどれか一つでも信じられないと、置かれた場所に祝福されなかった人間は世界の手触りを失ってしまう。
むしろ、フロンティア、もしくはそれに類するものがどこにあるのかという議論から抜け落ちてしまうのは人間の側の問題で、それはより正確には吉本が取り上げた「関係」の問題です。吉本が述べていたのは、「自立」することで「関係の絶対性」をしっかり受け止める主体がない限り、人間はフロンティアに旅立っても収容所のように生きるしかないということなのだと思います。
先崎 実のところは私自身も、口先では保守を掲げながら、宇野さんと同じく、どこかの土地に縛られずに移動したり、組織にアイデンティティを預けたりしない生き方をしてきた人間です。だから保守のくせして、吉本隆明なんかも読んできたわけです。
ただ、移動や離脱の自由について考えるときに、キーワードだと思っているのが「宿命」ということです。移動することや留まることそれ自体が問題なのではなく、重要なのは、その選択を自分自身が宿命として引き受けられるかどうかだと思います。
そのことを決定的に思い知らされたのが、東日本大震災での体験でした。あのときは私自身、自主避難でいろいろな場所を転々としていた。たまたまテレビで、帝国ホテルに宿泊を許可された避難民の方たちを見たんですね。取材でその被災者が言っていたのは、「こんなとこに泊まったって疲れるだけだ」というものでした。これがもし、自分たちが自由意志で選んだ家族旅行だったり、あるいは特別にお金を払って体験する宿泊だったら、帝国ホテルに泊まるのは楽しい体験だったはずです。でも、そうは思えなかった。なぜなら彼らにとって、それが「宿命」としては引き受けがたい体験だったからです。
それとは逆に、もし福島なりどこかの地域なりに、一生生きていくということを「宿命」と感じられるなら、彼らはどこにも行かなくても自由なのです。こうした思考回路を持たずに、国家や共同体からの離脱や解放を唱える進歩派、あるいはただ離脱せずに留まるだけを愛郷だと断ずる保守派、いずれも思想の強度として弱いんですね。
宇野 僕は子供のころ、父親の仕事の都合で引っ越しを繰り返していたのですけれど、そのせいで、ちょっと人間には根っこになる共同体が必要だという考え方にはなんというか、実感のレベルで抵抗があるんですよね。言ってみればこれは移住者の、どこに行っても「よそ者」の視点からの考えですね。
僕はいろいろな土地に住んできたけれど、たしかにその土地の風土は当然ものの見方や感じかたをかなり方向づけてしまう。けれど、個人のアイデンティティを決定的に縛ったりするとはどうしても思えない。そういう物語を信じたい人がたくさんいるだけだと感じることのほうが、それこそナマの体験として圧倒的に多かったわけです。むしろ、人間には根っこなんてないのだからこそ、根拠を捏造したがる生き物なのだと僕は考えているんですね。人間はどこでも生きていける生き物だからこそ、その適応の一環としてときに自分と土地との関係や、共同体との関係をあとから捏造するわけです。
その一方で、自分は好きなところに移動しながら「どんな土地でも変わらずに生けていける」と言う人たちにも違和感が大きくて、やっぱり転勤族の子弟の実感からするとそれも嘘なんですよ。自分自身の経験として、もう単純に合う土地と合わない土地がある。これはほとんど生理的なレベルで、たとえば僕はとにかく北海道が肌に合わなくて、逆に関西はすごく居心地が良かった。自分はノマドなのだと言っている人たちも、実際はすごく狭い起業家やコンサルタントのコミュニティに依存していて、四六時中Facebookを眺めていたりする。だから僕は彼らがあんまり自由な人たちだとは思っていないんです。このタイプの人たちが「自立」しているように僕にはまったく思えないですね。インタビューに答える内容から、Facebookに書く自慢話まで全部ソックリですから。彼らを観ていると人間はどんな土地でもそりゃあ生きていけるのだけど、むしろ精神的には拠って立つ場所がないといけないのだなと痛感するわけです。
先崎 私の父親の場合も、非常に職業が不安定な人で、数年おきくらいに狂ったように引っ越しを繰り返す人でした。常に転々とさせられていたので、まったく宇野さんと同じ感覚がある。
いま「根拠」という言葉を使われましたが、われわれ近代的な人間は、出自の瞬間からあらかじめ故郷不在の状態にあって、根拠というものが空虚というか、多重化されている状態にあると、ラカンあたりが言っていましたね。これは日本の近代思想における大きな問題でもありました。たとえば萩原朔太郎がエッセイ「日本への回帰」で書いていたように、明治以来の近代化というのは、簡単にいえば故郷を喪失し続けた時代だった。ヨーロッパの場合はまだヨーロッパのものがあるけれど、日本の場合はヨーロッパの猿真似をした偽物のビルしかなく、かつて蓄積したものを全部否定して、故郷を喪失して空虚になっている。そういうことは、戦前の時点で言われていた。そういうロマン主義的な問題を引きずっているというか、何度目かの変奏をされているのが我々の世代なのでしょう。
今回の議論に沿って言えば、無根拠な存在として我々が、吉本隆明における「大衆の原像」という概念をどこまで使えるのかという問題も出てくると思います。
宇野 『遅いインターネット』で引用したデイビッド・グッドハートの議論に「どこか」じゃないと生きていけないSomewhereな人々と、「どこでも」生きていけるAnywhereな人々の対比があるじゃないですか? 今の話は実はどちらも嘘っぱちで、ほんとうの問題は実は「どこにも」根拠なんてないのだということと、それがアイデンティティの政治やインターネットが与えた発信能力のせいで隠蔽されてしまっているということじゃないかと思うんです。実際にすべての人間はほんとうは転勤族で、移住者のようなもののはずです。結果的にたどり着いた土地や出会ってしまった人に対して多かれ少なかれ発生する責任を直視したくない人が、こうした擬似問題に回収されてしまっているのだと思います。
先崎 つまり、最後は「批評とは何か」という話に帰着する気がします。結局のところ、共同体の側であろうがノマドの側であろうが、自分が生きている社会状況を自明の前提にしてしまった人間は、いざ状況に流されれば簡単に自己を見失ってしまう。
けれども、たとえば日本で最初期の批評家に北村透谷という人がいますが、この人物について「精神が脱臼している人」と評した人がいた。萩原朔太郎も似たような批評を書きますが、彼らは古典的な調和、伝統的な共同体に所属した状態から、宿命的に離脱している。そこからどうやってもう一度、共同体と関わるのか、あるいはノマドのような生き方を選び直すのか。この痛切な問い自体が、批評を生みだすんですよ。
今日の話で言えば、それこそが「書く」ことを取り戻す営みだし、つながりに呑み込まれずに「自立」するということではないか。吉本の言葉でまとめるなら、つながりの関係の中にある「亀裂」とか「裂け目」に身を置くということ。そういう状態を探し出すための言葉が、まさに批評なんですよね。
宇野 はい。いま吉本から持ち帰るものがあるとするのなら、一番大きいものはそうした「裂け目」を作りだす批評の言葉なのだと思います。今日はほんとうに勉強になりました。
[了]
この記事は佐藤賢二と中川大地が構成し、2020年11月19日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。