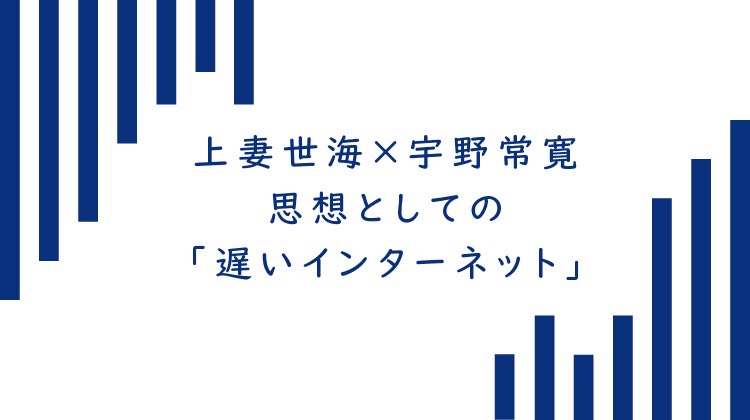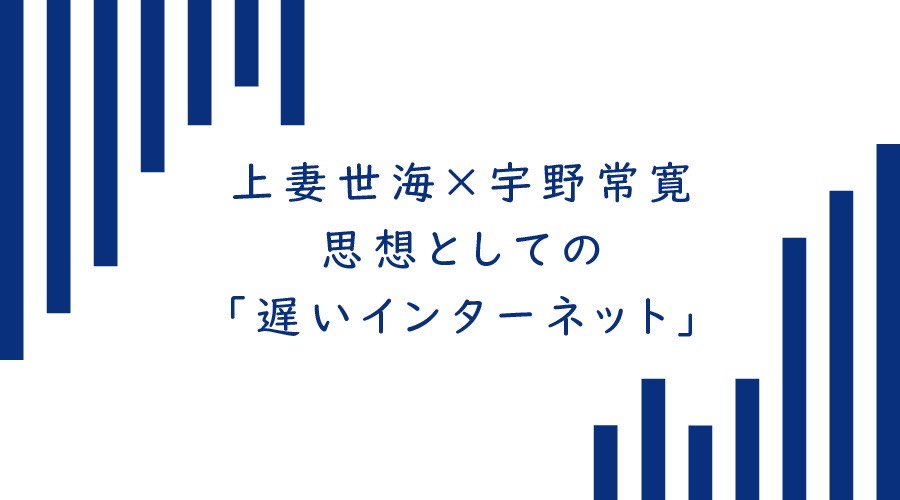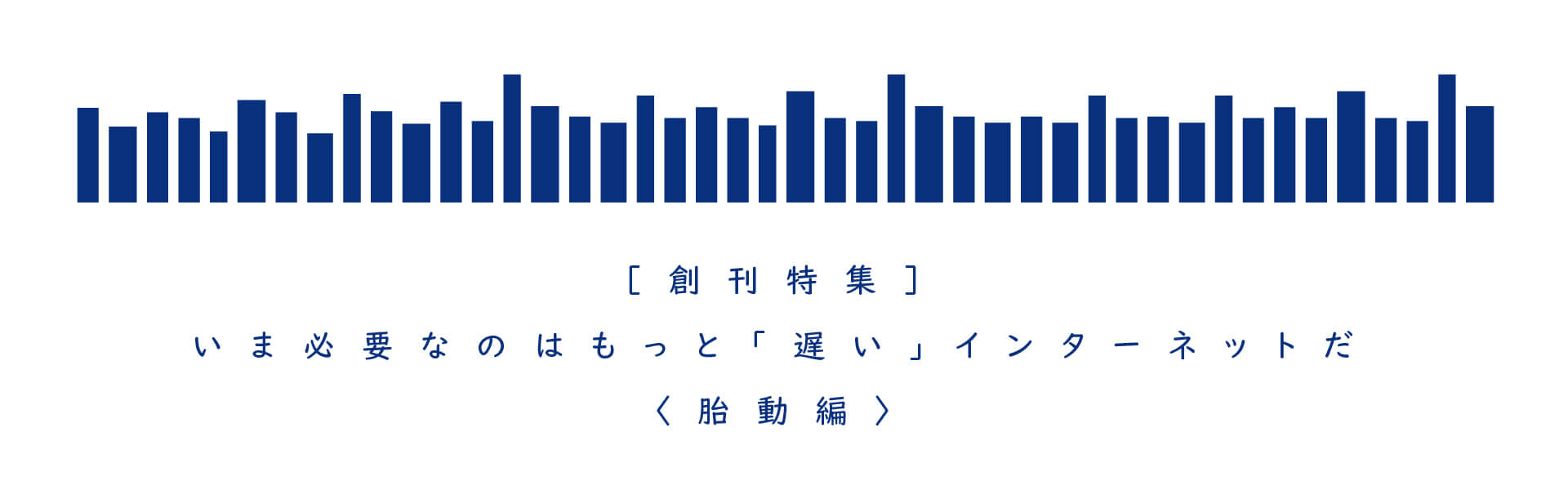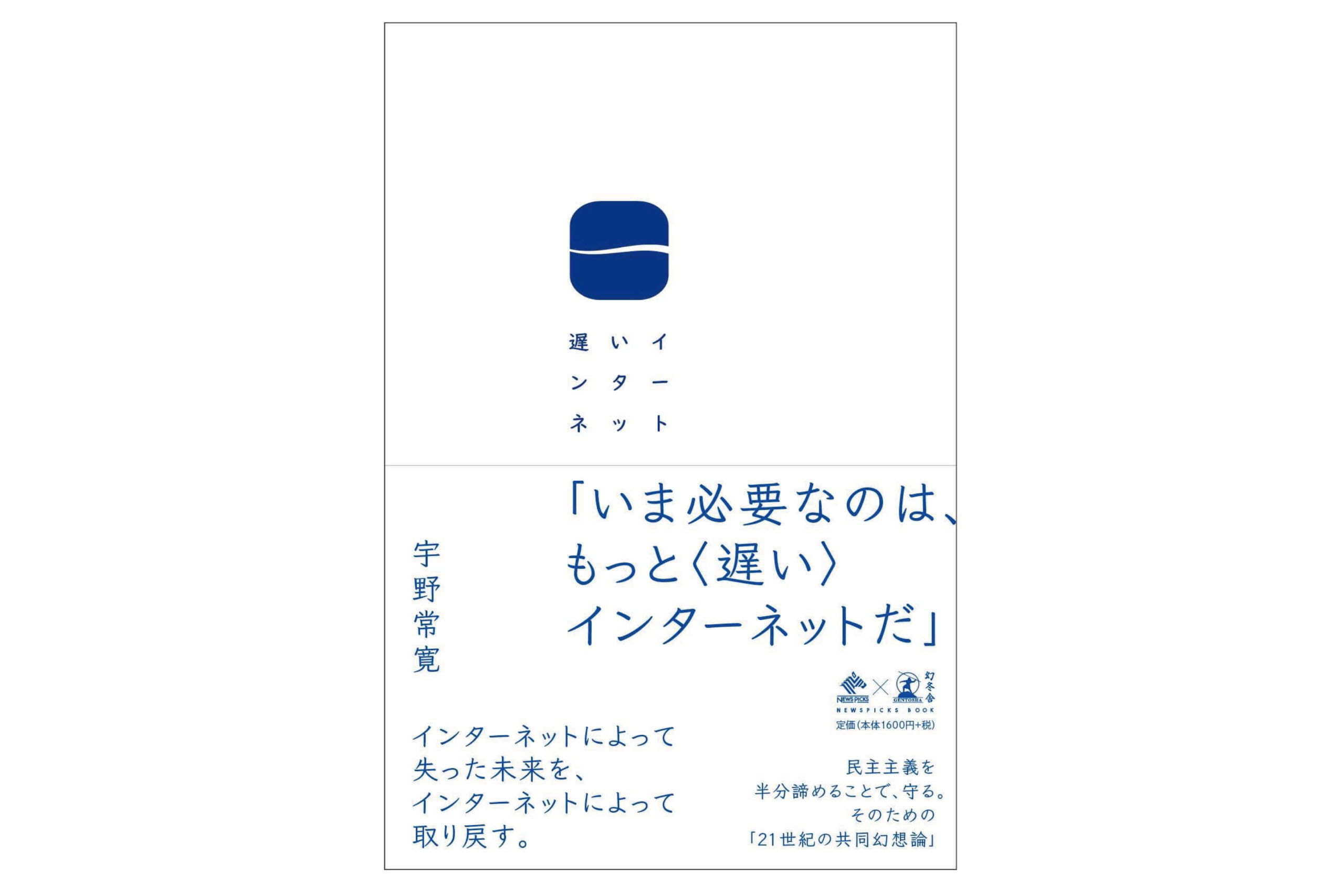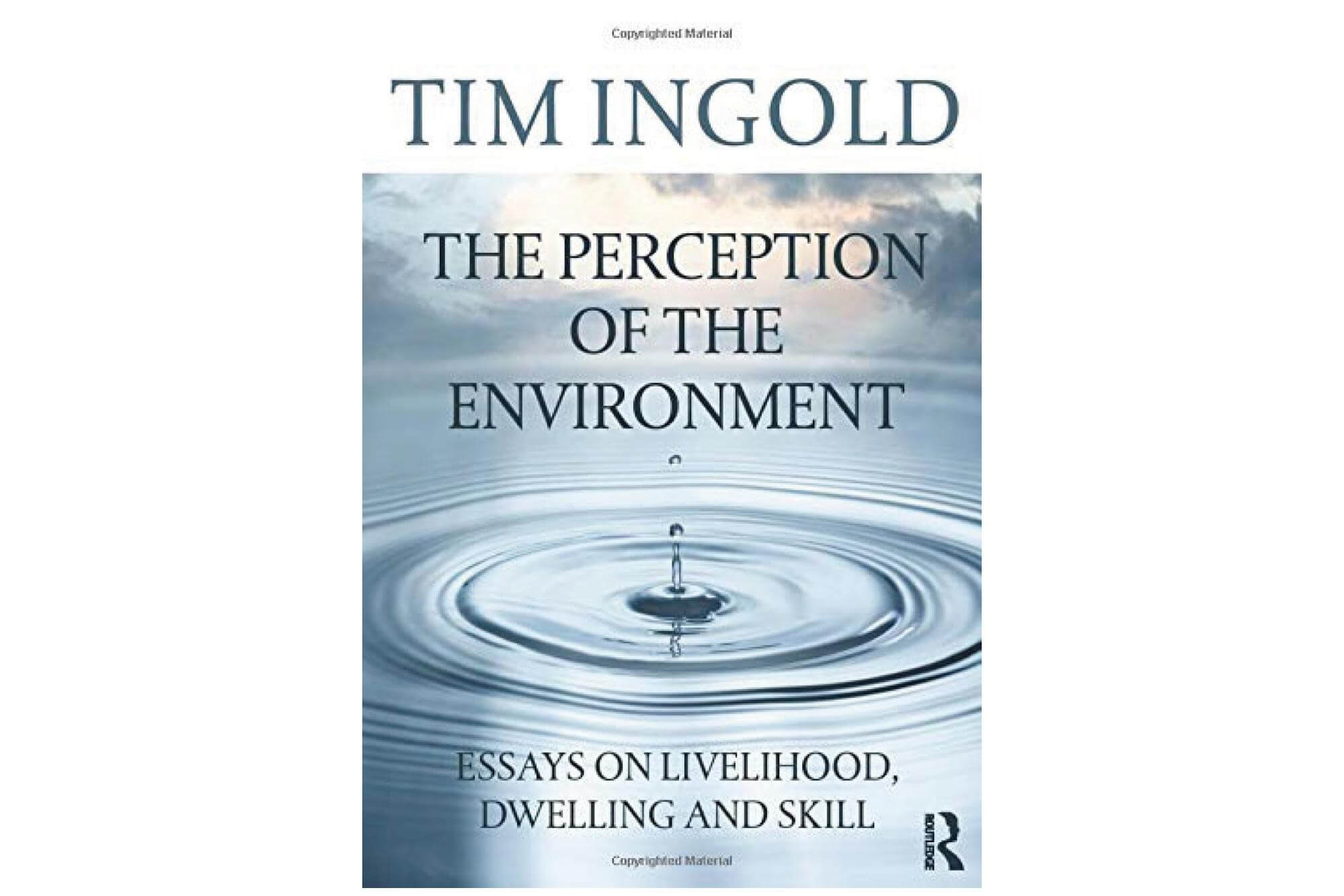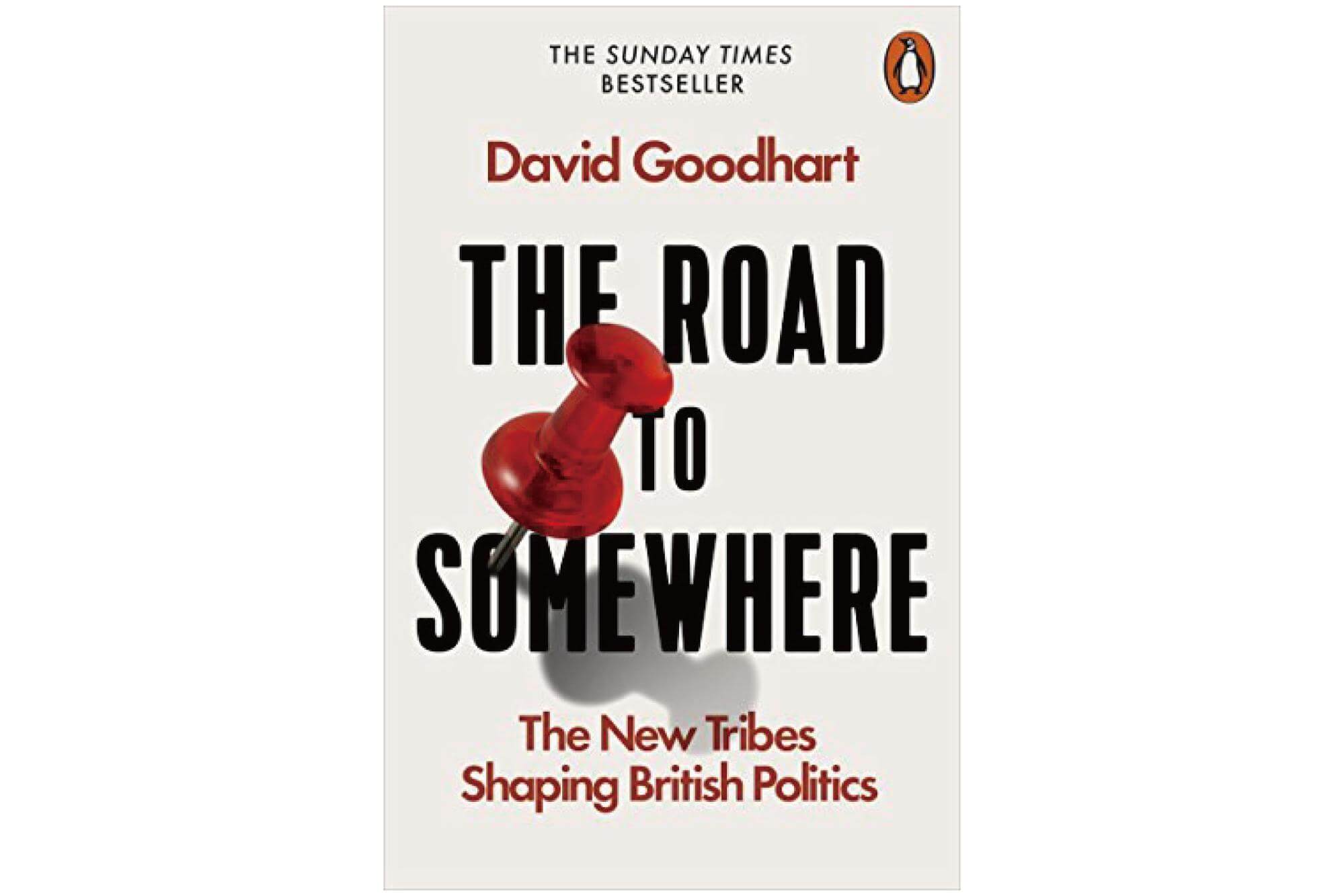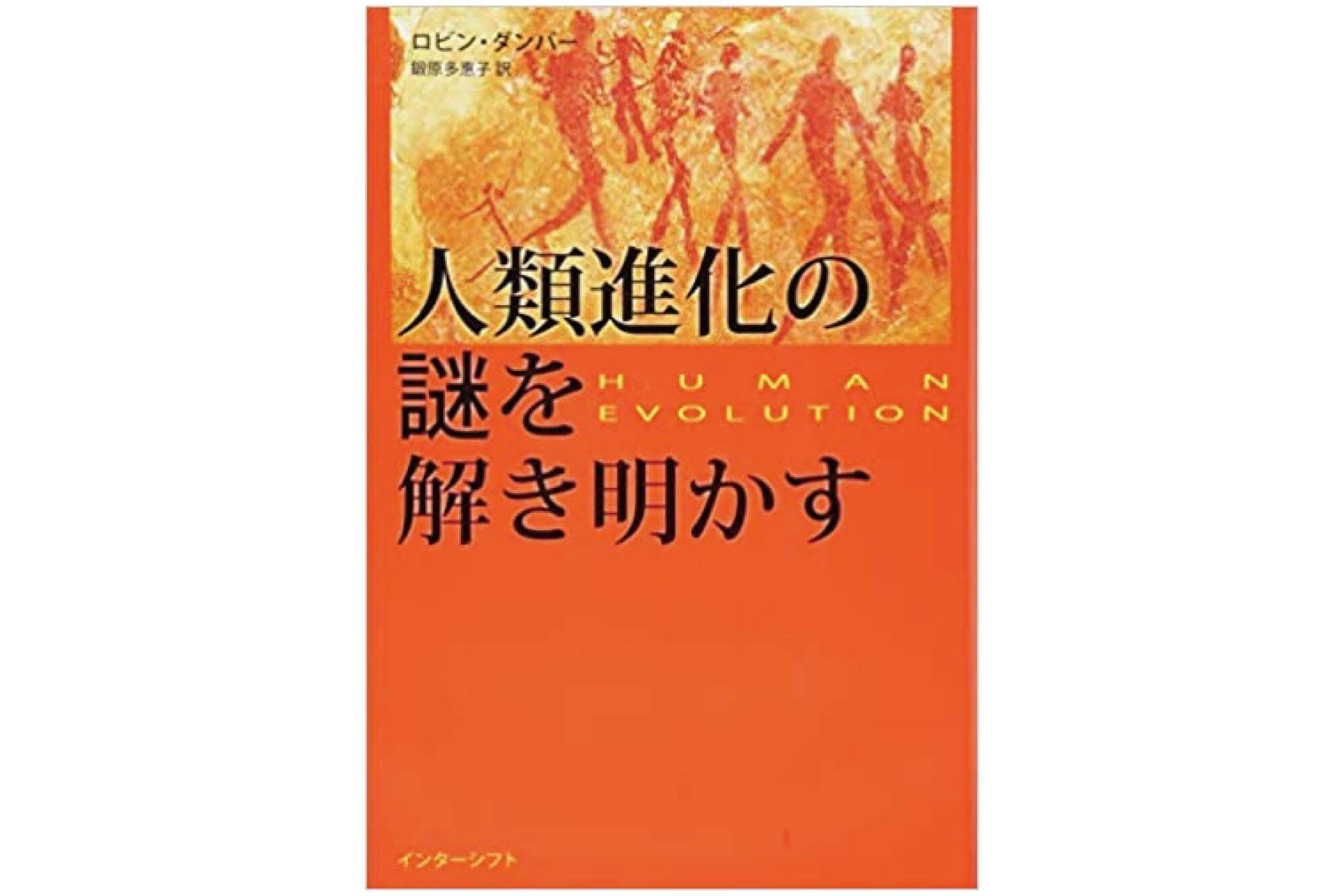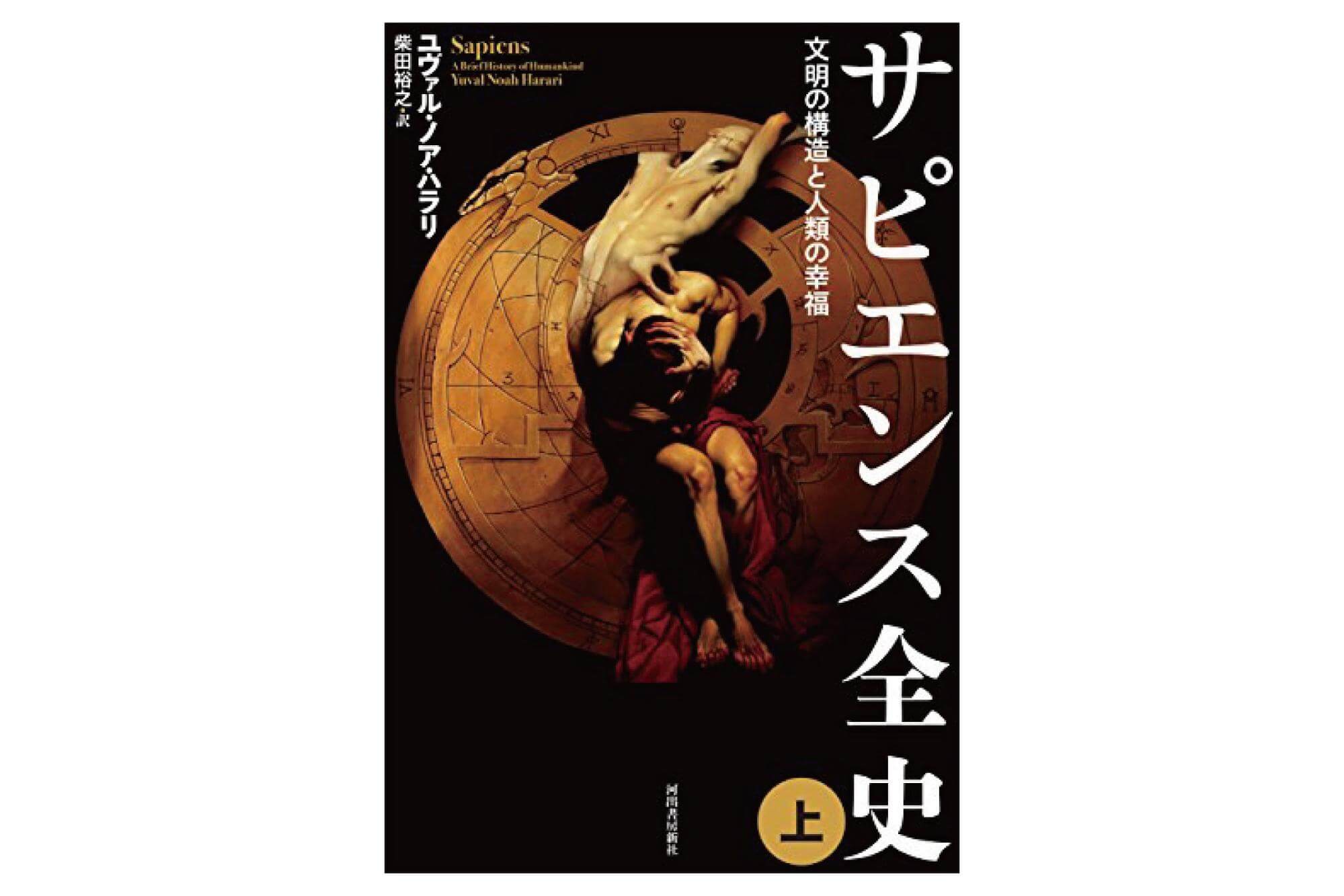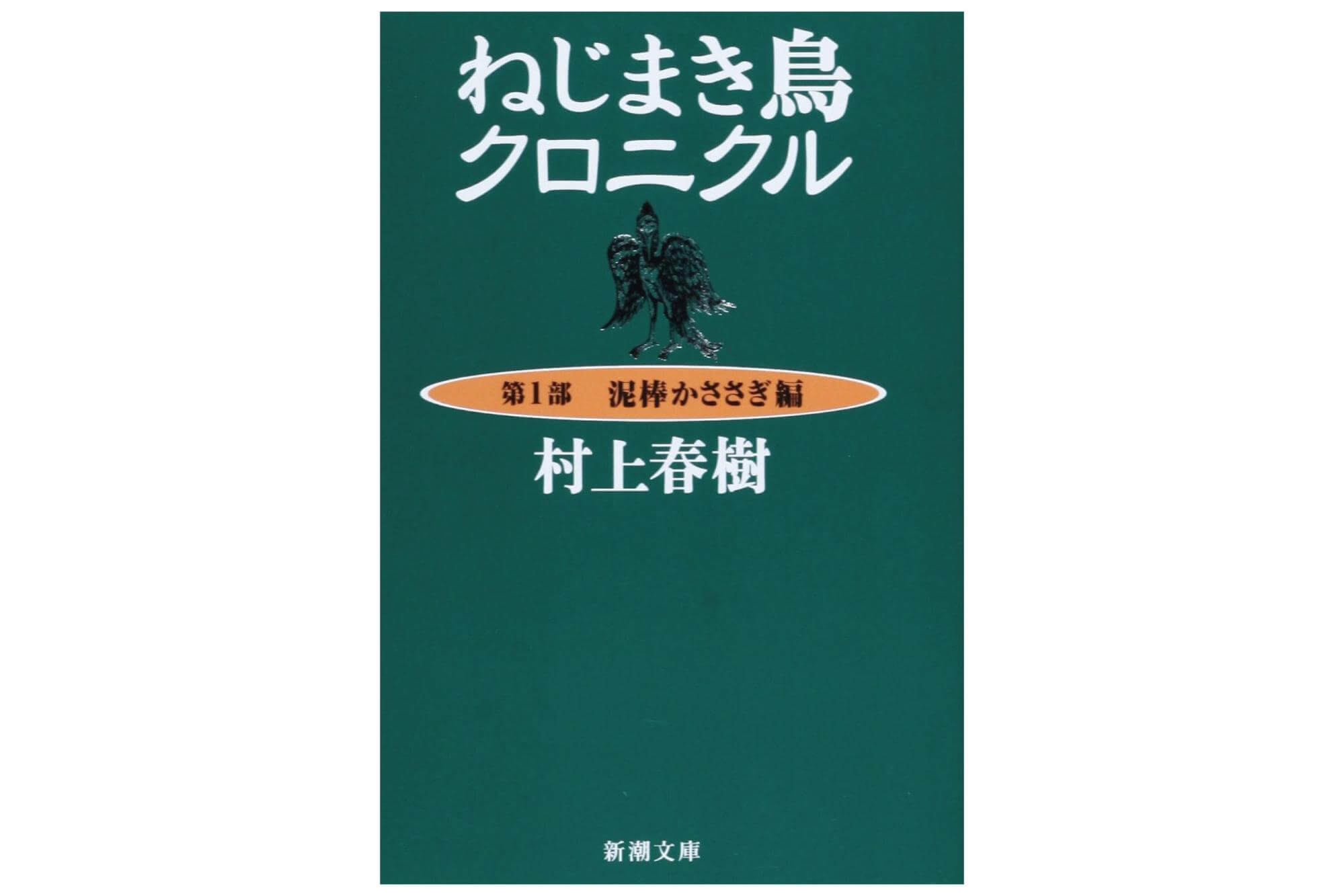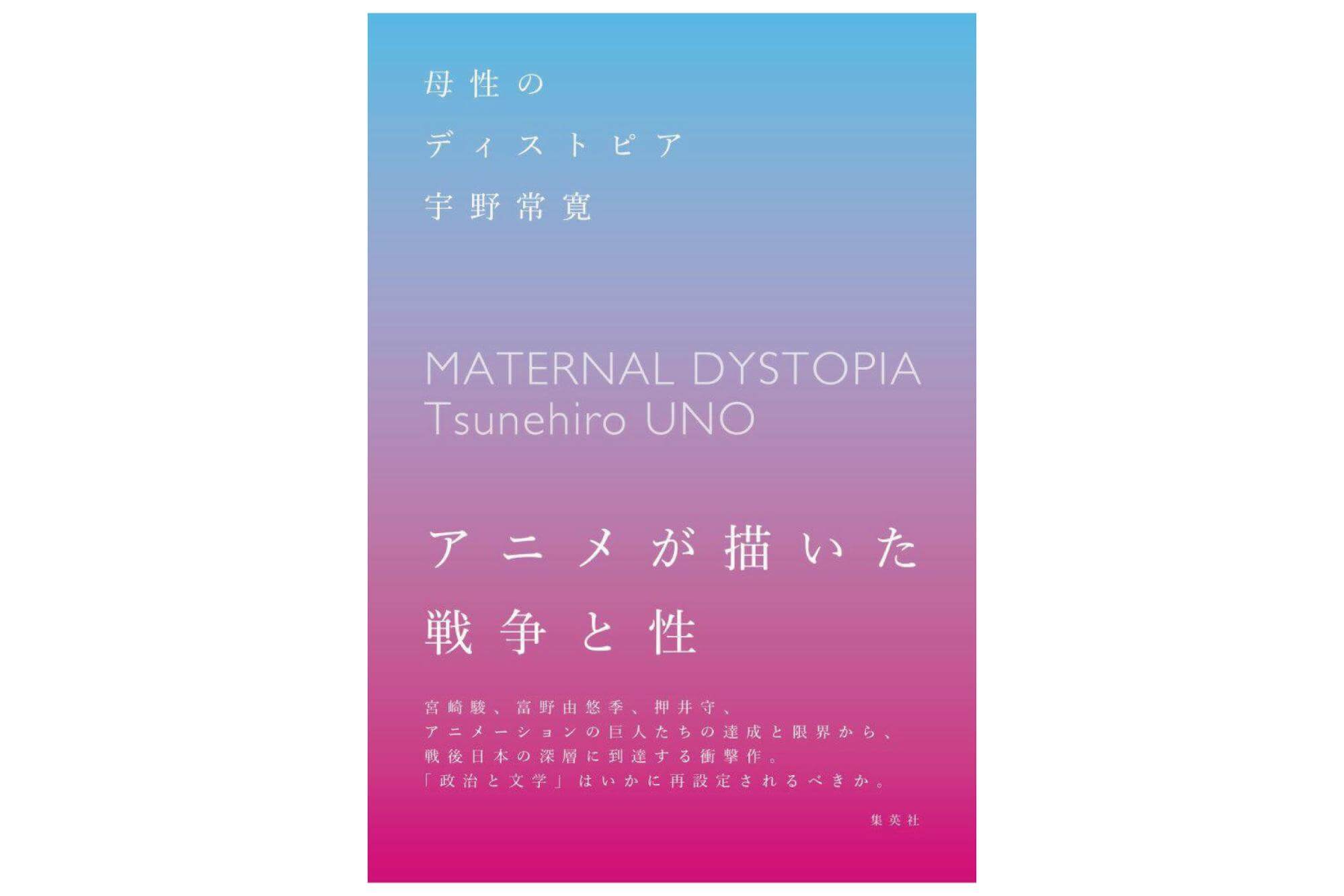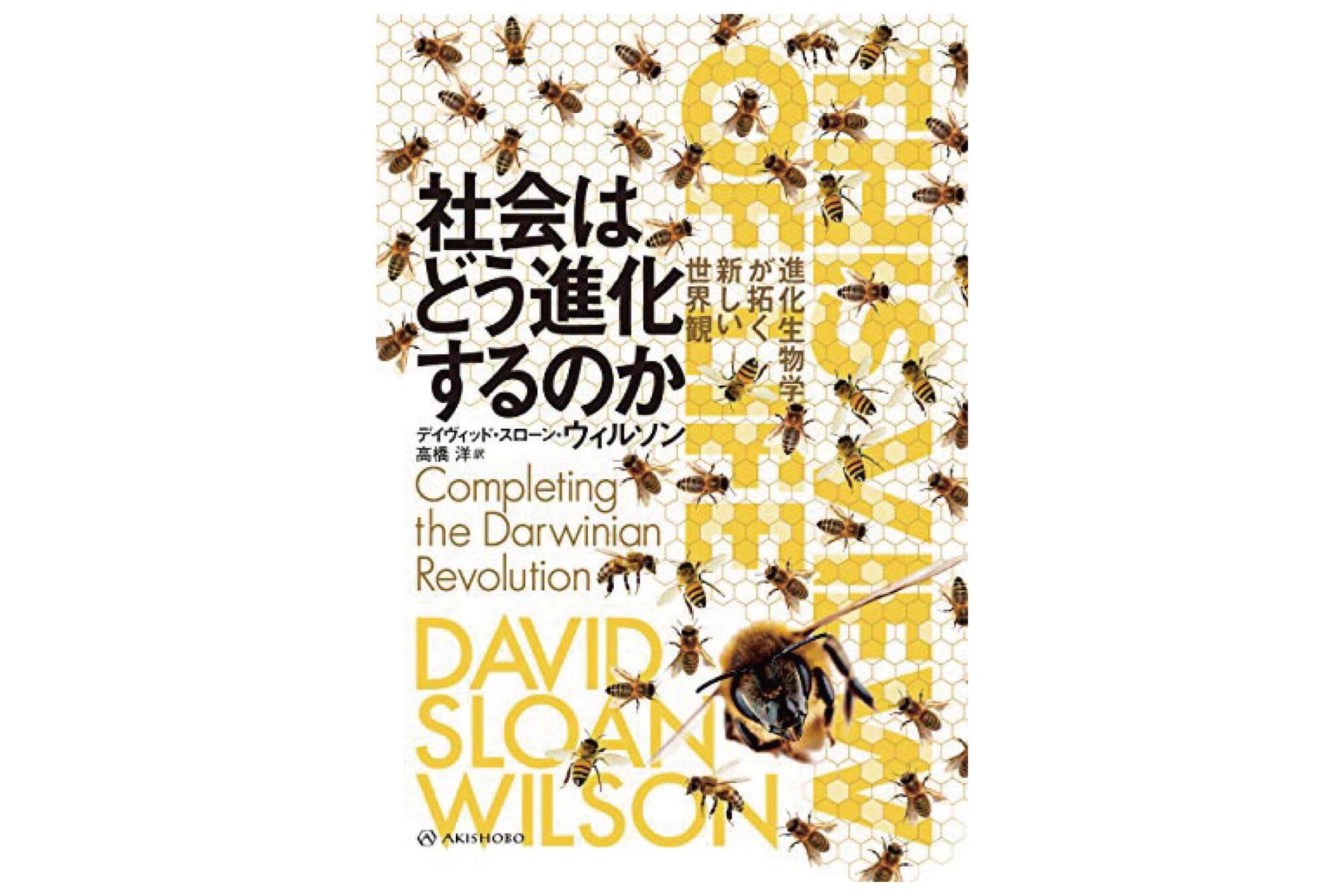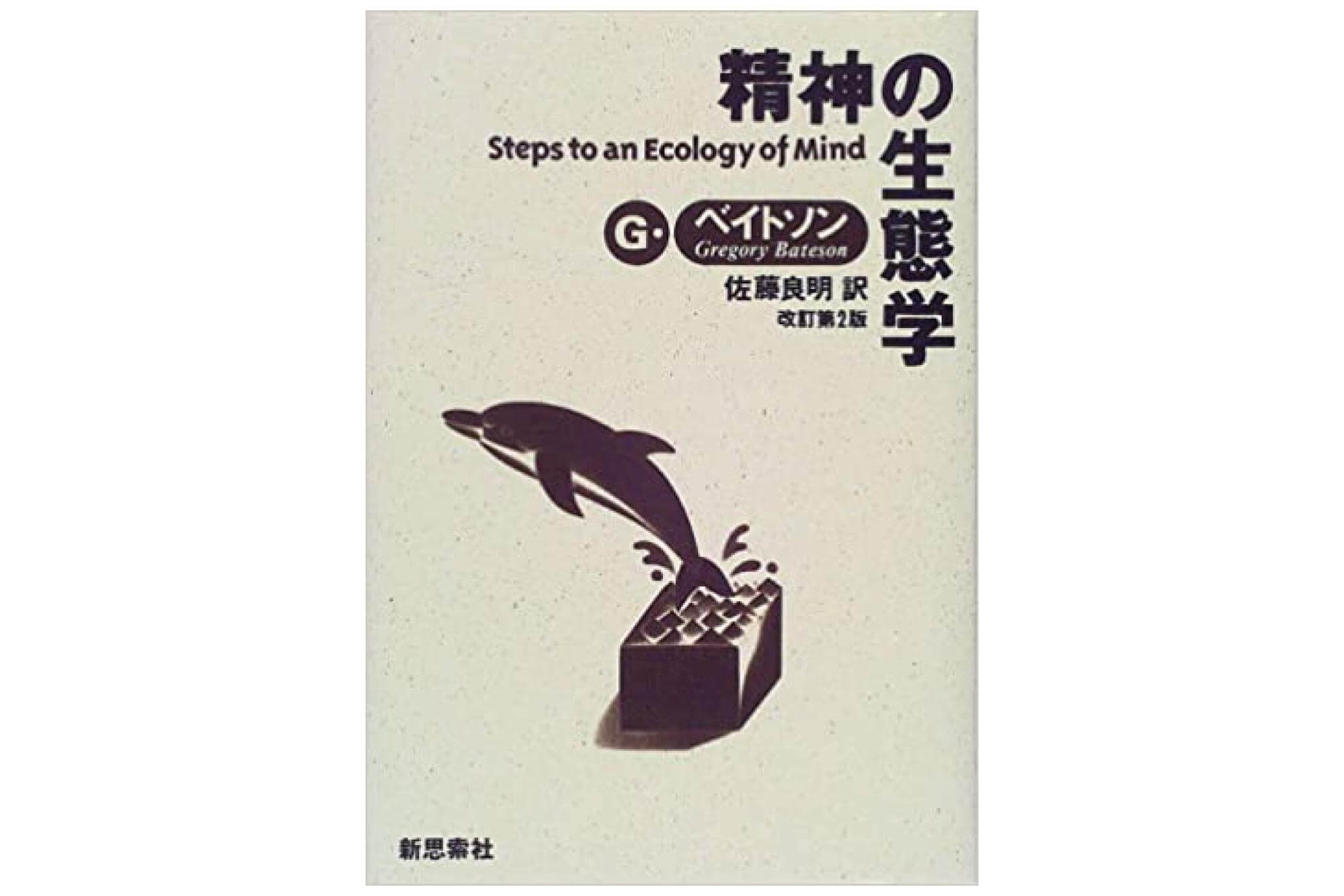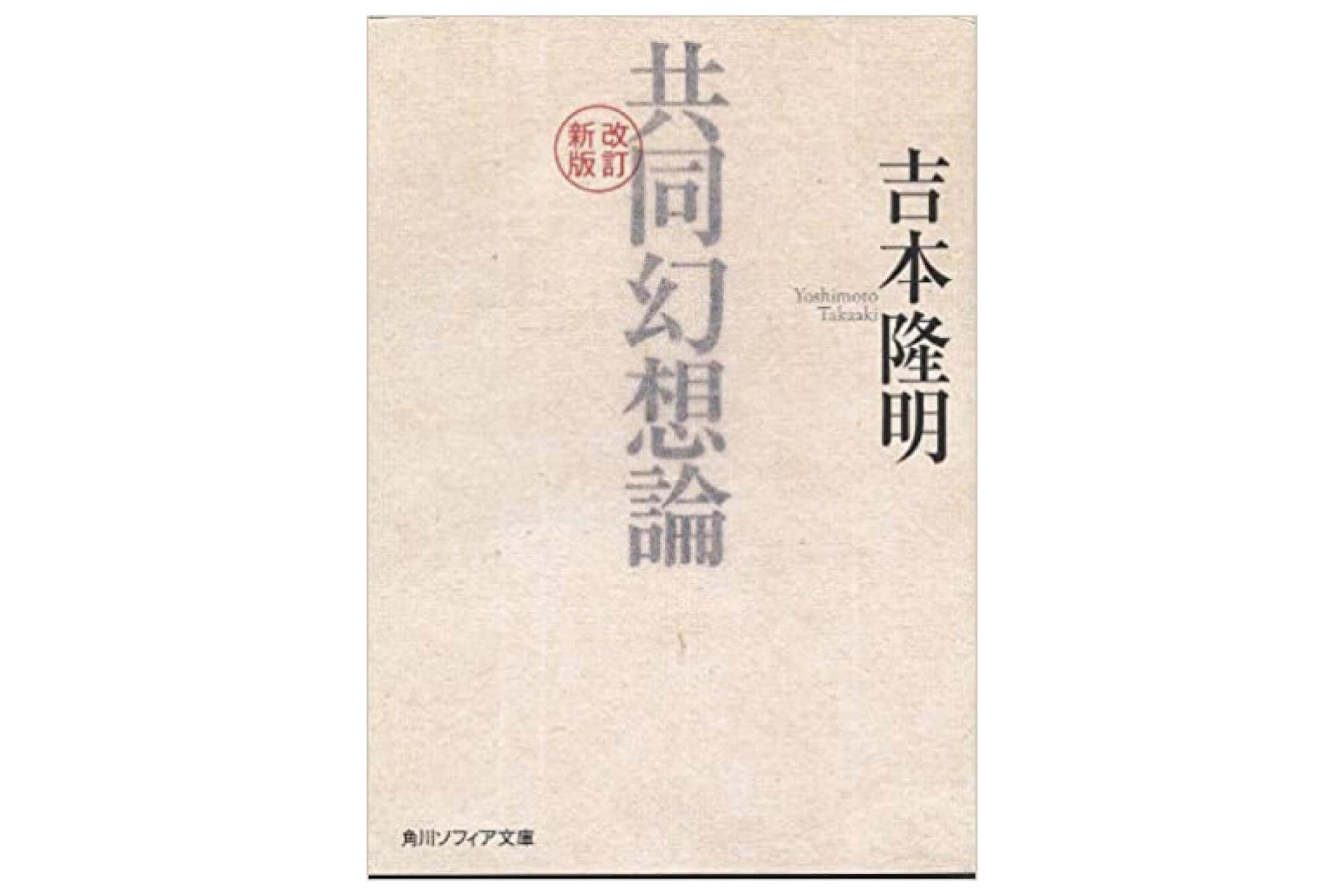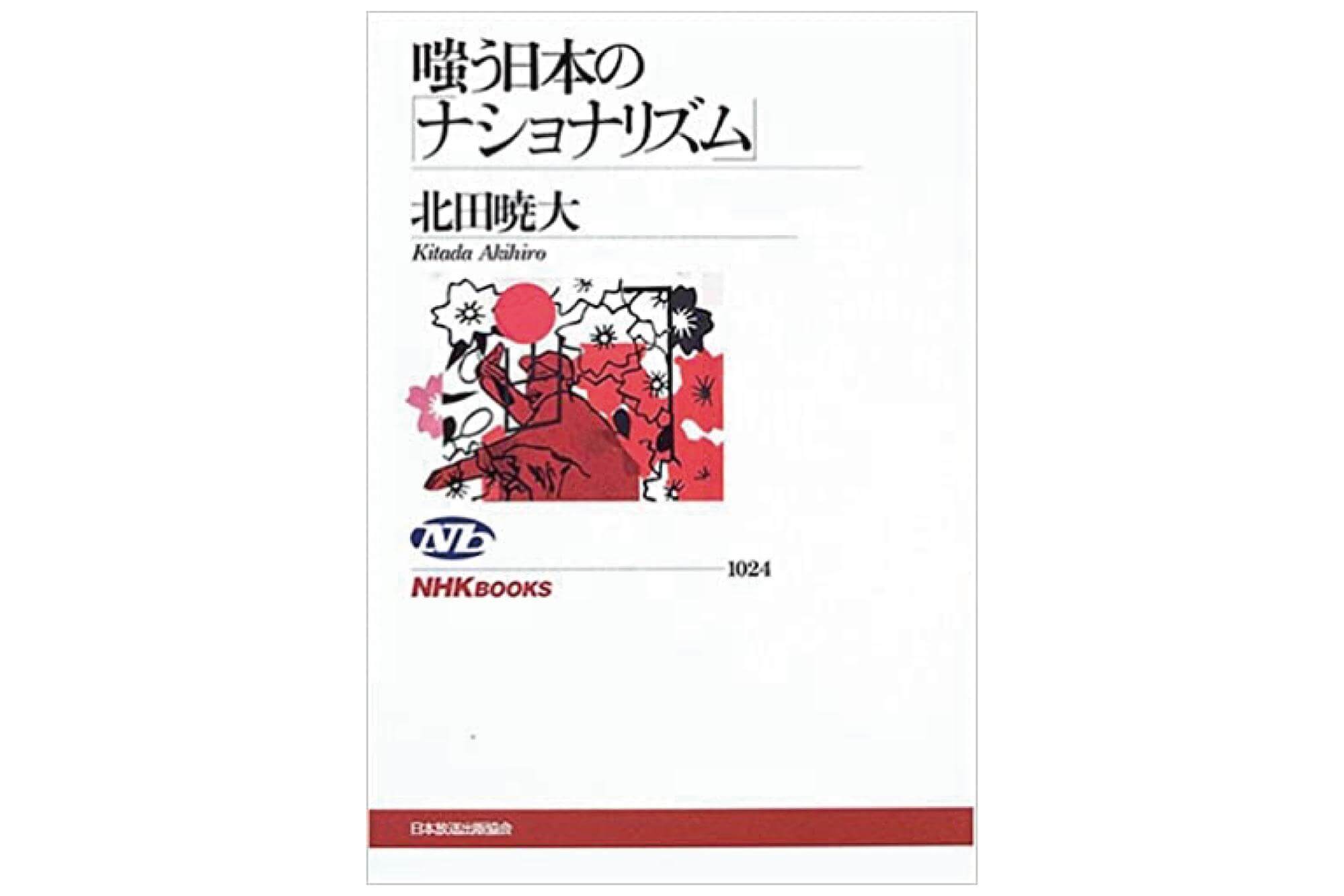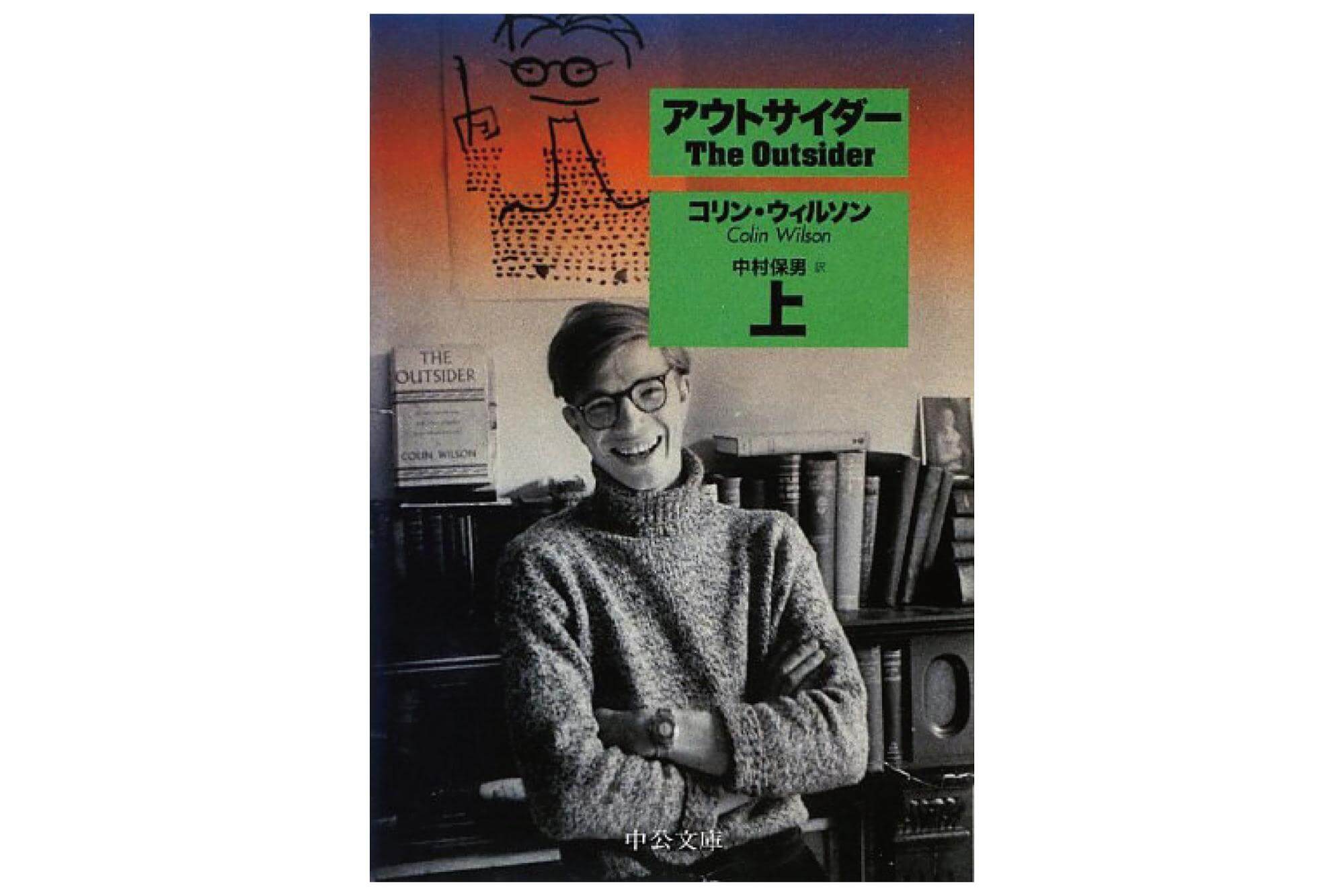「遅いインターネット」がこのウェブマガジンと、そして僕(宇野)の書いた本というかたちになって1ヶ月。想像よりだいぶ大きな反響をもらっていて、戸惑っているところもあります。そこで今回は上妻世海さんと僕たちが世の中に投げかけた「遅さ」について話してみることにしました。彼は、僕の知る限り社会の「速度」からいちばん自由な人間です。
本記事をはじめ、「遅いインターネット」では、現在の速すぎるネット社会の問題とその向き合い方について、様々な観点から特集しています。
端的に言うとね。
「走りながら考える」ことで見えてくるもの
上妻 こうして宇野さんと「遅いインターネット」について濃密に話せる機会ができて、とても嬉しいです。僕は良い本の条件の一つを、読んでいて誰かと対話をしたくなる本、言い換えれば、人と人の〈あいだ〉にある本だと考えていて、『遅いインターネット』を読んだ時に僕が感じていたことは、まさにそれだったからです。
読書は単に情報を得る手段としてだけでなく、自らの無意識と対話する手段でもあります。そして、読書は自らの意識と無意識の対話だけに収まらず、人と人の対話を促し、それを可能にする媒介でもあります。実際、僕は古典を通じて過去の偉人たちとの対話を行い、自分の無意識の癖を何度も教えられたことがありますし、読書会などで様々な人と対話をすることで意見の多様性に触れてきました。僕は読むことから沢山のことを学んできました。しかし、それは僕のような仕事をしている人間が掲げる一種の理想論でもあります。確かに、本にはそのような潜在的可能性があります。しかし現実的には、大部分の人は各々の仕事と生活に時間を使わざるを得ません。本を無意識との媒介として扱うには特殊な訓練が必要ですし、他者との対話を行うには訓練だけでなく場所や機会も必要になります。そういった多様な状況を前にして、本には上述したような可能性があるのだから、その可能性への道は各々の責任で進めば良いというのは作家の無責任だと思っています。
今回、宇野さんは『遅いインターネット』という本と、「遅いインターネット」というプロジェクトという同じ名前の2つの〈形〉、あるいは「作品」として表出されている。このことは非常に重要だと思っています。実際、本の中で一番最初に書かれている「走りながら考える」というフレーズはこの2つの形の繋がりを見通し良くしている。一方で宇野さんのプロジェクトが実際に進んでおり、他方で、本自体が書かれているという仕方ではなく、「走りながら考える」というスタンスが示されていることで、プロジェクトと書くことが分離ではなく、日常と地続きのものとしてあることが示唆されている。これは僕のコア概念である「制作」と通じることでもあります(* 上妻世海『制作へ』)。
宇野 そう感じてもらえたのは、とても嬉しいです。日常と非日常というテーマは僕にとっては以前から、具体的には『リトル・ピープルの時代』の頃から温めていたもので、要するにインターネットが代表する情報技術が破壊してしまったものは両者の境界線だと僕は思います。冷戦下のアニメが描いてみせたように、ある日突然核ミサイルが飛んで終わりなき日常を破壊し、ドラマチックな非日常がはじまるのではなく、日常の中にノイズのように非日常が入り込んでくる。このあたらしい世界をどう受け止めるか、ということを僕はずっと考えてきた。このあたらしい世界に耐えられないと、閉じた相互評価のネットワークの中でのポイント稼ぎに夢中になり考える力を失う。あるいは、安定剤代わりにイデオロギーに回帰して、やはり考える力を失う。
だから、僕はこの日常と非日常が、吉本隆明的( *吉本隆明『ハイ・イメージ論』)に言い換えれば普遍視線の中に世界視線が入り込んでしまった世界に望まれる「主体」のことを論じる本を書いて、実際にあたらしい主体を獲得するための運動を立ち上げた。それが、『遅いインターネット』という本であり、そしてこのウェブマガジンを中心とした「遅いインターネット」というプロジェクトなのだけど、両者はまさに非日常と日常の関係にある。
非日常というのは、幻冬舎のNewsPicksBookというレーベルから発売された書籍としての『遅いインターネット』で、日常はこのウェブマガジンを一つの柱にしたプロジェクトとしての「遅いインターネット」で、もちろん後者の方が主体で、前者は後者の理論的な意味付けとマニフェストです。要するに、日常の側から非日常へのアプローチを考えていて、逆ではないんですよね。
上妻 今の宇野さんの意見は、僕自身の関心領域である生態学や人類学とも共鳴関係があると考えています。近年の生態学や人類学では、主体は環境と一体化した仕方での一時的かつ局所的な固体化と捉えられる傾向があります。言い換えると、そこでは主体と環境はあらかじめ分離したものではなく一体化したものとして捉える視点を取ります。例えば、「芸術とはAである」というように主語が述語を規定していく仕方ではなく、「Aは芸術である」といった仕方で、主語が述語の方から規定される様を捉えます。「芸術とはAである」の視点では、事前に芸術の定義があり、それに当てはまるものが芸術とされます。経験は定義に当てはまるものを次々に蓄積していく、そういった視点ですね。他方で、「Aは芸術である」という視点では、経験が言語的定義を統合していきます。ここで経験は、現時点で教科書的に芸術と見なされていないものを捉え、価値を見出し、それによって芸術の定義を再定義していきます。後者の視点では、経験は情報を蓄積する手段ではなく、前提を書き換える目的になります。人類学者ティム・インゴルドは前者の視点を「建築の視点」と呼び、後者の視点を「住まうことの視点」と呼びます。そして、彼は後者の視点を重要視しました( * Tim Ingold 『The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill』)。
「住まうことの視点」は人類学の方法論としてだけでなく、複雑性が増加し、不安定性が増していく現代社会においても重要です。なぜなら、環境が技術革新や新たな技術の膾炙によって常に変化に晒されている現代社会において、確定的な範疇を前提にして思考することは不毛だからです。これまで確定的な範疇を前提に蓄積的な思考ができたのは、環境変化が緩やかで、一定の安定性を維持していたからです。行為を意味付ける環境が変わっているのに、環境が定数かのように語ることはできません。先の読書の例で言えば、僕たちの環境は、読むことがメディアの中心であった19世紀から変化し、読むことの意味が変わっています。過去の理想的な環境を前提にして読むことを語ることは無責任としか言えません。環境を理想化した状態で語るのではなく、僕たちは人類学者のように他文化だけでなく、自文化に参加し、自らがその書き換えや演出に携わり、一次情報に身体を持って浸りつつ、思考するしかないと思います。変化する環境に生きる僕たちは、自文化であるからといって超越的視点から語ることはできません。もちろん、これは他文化についても同様です。自文化と他文化という区別ではなく、変化する環境と主体化という視点から見れば、もはや固定的な環境の定点を前提した議論は有効性がありません。
▲『The Perception of the Environment』
前述したように、インゴルドは「建築の視点」と「住まうことの視点」を分け、後者を重視しました。しかし、実は、このような視点の差異は、日本哲学ではおなじみのものです。自著『制作へ』では、西田幾多郎や中村雄二郎を引き受けるかたちで、前者を「主語的統合」と呼び、後者を「述語的統合」と呼びました(* 西田幾多郎『西田幾多郎哲学論集 I』—「場所」)(* 中村雄二郎『共通感覚論』)。そして、僕はインゴルドとは異なり、「主語的統合」と「述語的統合」の循環こそが「制作」の核であると主張しました。実際、経験によって言語的範疇を書き換えるためには言語的範疇を知っている必要があります。歴史と向き合うためには歴史を知る必要があります。主語的に統合されていない主体は述語的に再統合することもできません。インゴルドのように、述語的統合こそが本質的なのだ、という方向に偏ってしまうと、それは人間は動物に過ぎない、環境に受動的に反応するだけだという主張になりかねない。もちろん、人間は動物だけど、どんな動物なのかを曖昧なまま残すことになる。ヒトは主語的に、能動的に、言語的範疇によって規則を持てるし、計画を構築できる。また、情動と葛藤しながら一貫しようとする倫理を持っている。ゆえに主語的統合を正当に評価しなければ環境に溺れることになる。もちろん、上述した理由から、主語的に硬直化した自我では現代社会で有効な処方箋を出すことは不可能です。僕たちは走りながら、速度を落としたり、注意を逸らしたりしながら、思考を、文字を走らせる必要があります。事前に規定された言語的範疇を期待できないがゆえに、ゴールも目的も仮説的にしか持つことはできない。走りはじめると、僕たちは当初の予定とは異なる場所に辿り着いています。だからこそ、僕は主語的統合と述語的統合の循環の制御という非常に高度な技術が必要だと考えています。主語的統合と述語的統合のどちらかに偏るのではなく、両者を調和させる方向性で考える必要があると思います。環境に溺れるのでも、環境から分離した主語を前提するのでもなく、環境に浸りながら頭も動かす必要があります。
宇野 上妻さんが指摘するように、この本で僕が前提としていたのは、主体というのは環境との相互関係の結果発生する状態でしかないという考えです。主体の問題を考えるとき、安易なアプローチを取ると、まず望ましい主体の在り方を考えてしまう。たとえばグローバル資本主義と社会の情報化に対して抵抗する主体はこういうものだ、といったかたちで思考してしまう。僕はここに罠があると思う。固着した主体の形そのものではなくて、世界と継続的に関与する中で主体が結果的に立ち上がる、と考えないといけない。僕が比喩的にランニングを用いているのは、そのことを念頭に置いているからなんですね。ナルシスティックなボディビルダーは筋力トレーニングの成果を鏡で確認するし、同じランナーでも村上春樹のように競技スポーツ的にランニングを捉えている人はタイムを縮めて喜ぶ傾向がある(*村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること 』)。しかし僕たちは走り続けることが目的で、そのためのアプローチを身体と環境の関係として考えている。僕のように単に趣味として、ライフスタイルスポーツとしてランニングを続けている人間にとって筋力やタイムはどうでもよいことで、走りたいときに好きなだけ走ることができるコンディションを整えることや、自身の身体や気候の変化に合わせて走り方やコースを変化させていくことが重要で、それは単に足腰を鍛えればよいということじゃない。どれだけ屈強な筋肉を作り上げて鏡に向かってうっとりしても、その身体を環境とのコミュニケーションの中で柔軟に変化させていくことができなければ気持ちよく走りつづけることはできない。あるべき主体について議論するのはよいのだけど、だからその完成形を決めつけてそこに向かってがんばろう、というかたちで掲げても必ず失敗してしまう。だから、そのための身体には環境にというか外部に開かれながら、しっかりと自分の意志で速度やコースを決定できる強度がないといけない。
つまり、筋力トレーニングが外界の環境から自分の身体を遮断して防衛するためのものだとするのなら、ランニングは、外界の環境の変化を取り入れながらも、そこから自由であるためのものだと思えばいい。ただ歩いているだけでは、既存の街の文脈をたどることしかできない。それは流されているのと変わらない。かといって、そこに抵抗するためにジムにこもって筋トレしても、ナルシスティックに閉じるだけ。なので、僕は走ることにしたわけです。外部に出るが、流れにただ身を任せることはしない。
上妻 お話を聞いていて、「まず望ましい主体の在り方を考えてしまう」というのはとても重要な指摘だと思いました。いま宇野さんがおっしゃられたように、これまでの多くの議論は環境の多様性と変化を考慮せずに、環境とは分離した理想化した主体を措定するところから議論を構築してきたために、現実化不可能な、人文系の人たちの世界にだけしか存在しない机上の空論になっているように思います。この本では、理想化された主体から日常と地続きの、動的で不安定な主体へと、前提が落ち着いているところが見逃せない点です。
そして、当然それだけでなく、この本では、ここまで二人で話してきたような身体−環境基準の人間観を前提に、現代における民主主義を問い直すという大きな縮尺度の問題が議論されています。まず、21世紀現在の地球社会では、グローバルで境界のない世界に生きている「Anywhereな人々」と、境界のある世界に取り残されている「Somewhereな人々」の分断が顕在化していることが指摘され(*David Goodhart『The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics』)、さらにそのどちらも虚構に立脚していることが指摘されます。ここで重要な点は、「Anywhereな人々」と「Somewhereな人々」の両者が共に虚構における「祭り性」の優劣について争っていることです。前者はグローバル経済と交換経済の優位性を、後者は国民国家と民主主義の優位性を主張します。そして、宇野さんは、その両者の議論の不能性について論じているように思います。
▲『The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics』
ここでの宇野さんの解決策は、①立憲主義と民主主義のバランスを見直すこと、②政治をテクノロジーを媒介に日常−生業の延長線上に位置付けることです。両者が虚構であるという点については「Anywhereな人々」が交換経済における量的均質性を前提にしており、「Somewhereな人々」が国民国家という虚構を前提にしていることから、その機能的等価性が指摘されます。また、両者は近代において要請された制度にすぎず、それらを通じて世界への一次性は担保されません。それらは共に非日常として体感からは乖離しています。また、一方で、ポピュリズムの暴走を抑制する意味で立憲主義への傾きを強めることが提案されていますが、それは民主制の暴走を抑えるための防御壁として要請されており、むしろ重要なのは、人々が世界との接触を感じられるのは日常の、生活の、生業の中であることの自覚であり、しかしながら、それだけでなく、日常性に埋没するのではなく、そこから社会への段階的かつ反省的な関与可能性の拡大を、vTaiwanなどの事例を挙げながら、制度的に支援する方向性が示されている点だと思います。
宇野 今日の民主主義は、日常から非日常へ人間を動員することでしか成立しなくなっている。選挙もデモも、対象にしている層が違うだけで基本的には「Somewhereな人々」に承認を再分配して動員するゲームになっている。民主主義というゲームに参加することで、「Somewhereな人々」は世界に素手で触れる幻想を獲得できる。たとえば世界経済に素手で触れられない人間は、国家という共同体に依存することによって尊厳を回復するべきだというのがトランプの言動の背後にあるメタ的なメッセージです。
しかしこれは、もはや民主主義が問題そのものではなく、問題についてのコミュニケーションしか扱えないことを意味している。移民の流入による経済への影響を分析的に議論するよりも、移民を排斥して「自分たち」と「それ以外」の間に明確な線を引く言説のほうが、効果的に集票できる。これは何も民主主義に限ったことではなくて、誰もが発信能力を持った状態で閉じた相互評価のネットワークが成立すると、評価経済的に有利な選択は常に「問題そのものではなく、問題についてのコミュニケーションに最適化すること」になる。
この状態から脱出するために考えたのがこの本で僕が示した「民主主義を半分諦めることで、守る」ための3つの提案です。具体的には上妻さんが指摘した2つに加えて、3つ目に情報環境の整備、それも草の根の運動としての介入を提案しています。それが「遅いインターネット」計画なのだけど、この3つの提案は要するに民主主義というフィクションをどう作り直すか、ということなんですよね。そして3つとも要するに人間を非日常に動員して政治化する、という発想から離脱するためものでもある。僕の考えは、万民が発信能力を得た今日において民主主義とはこれまで以上に、というか完全に閉じた相互評価のネットワーク内での動員のゲームになるしかない。しかし、政治とはこのゲーム(問題についてのコミュニケーションが生む評価経済)ではなく、問題そのものにアプローチしないといけない。
前者は非日常的な物語で、後者は日常的な生活の中にある。政治をいかに後者の側に引き寄せるかを考えなければいけない。承認の再分配としての動員ゲームから可能な限り離脱するしかない。
これはこれまでの基準から考えると転倒した思考で、要するに人類はこれまで無知蒙昧な大衆を啓蒙して市民として教育し、民主主義に参加するに足る主体に育てあげようとしてきた。つまり半径5メートルの自分の生活を効果的に守るためには、国家という想像の共同体のレベルのことまで考えないといけないという、論理的に考えれば当然だけれども実感が難しいものを教育して刷り込んできた。しかし、今日において民主主義はどちらかといえば承認の確認装置になっている。むしろ半径5メートルの自分の生活を忘却するために、麻薬的に民主主義というゲーム(投票と情報発信)に参加することになる。僕の考えはインターネットの与えた発信能力を、半径5メートルの生活とそれを支える経済や軍事のシステムとの接続を、より可視化して実感しやすくするために活用する他ない、ということでその具体化がこの本の3つの提案になっているわけです。
上妻 僕は『制作へ』の出版以降、「制作」という概念を人類史から捉え直すという仕事をしているのですが、宇野さんの今おっしゃられた「日常と自分の物語から社会的次元への多元的拡張という路線」は、人類史や進化論の立場からも支持できるように思います。丸山眞男の時代から、中間共同体の自立性の欠如、あるいは中間共同体それ自体の空洞化が社会の機能不全に繋がっているという指摘はありましたが(*丸山眞男『忠誠と反逆』)、現代の視点からは、その必要性が人類という種の視点から捉え返されているように思います。
例えば、人類学者ロビン・ダンバーによれば(* ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』)、霊長類が維持できる関係の数は、その社会的行動の複雑さに依存し、社会的行動の複雑さは、脳の新皮質の大きさに依存しています。僕たちは霊長類や他のホモ属の種よりも複雑な社会的行動(歌や踊り、酒や噂話)を用いることで、150人という群れを維持することができます。しかし、もちろん規模が小さければ、容易に親密な関係を継続できるため、狩猟採集民は、捕食者や近隣集団の襲撃に対する防御の有無によって、集合・離散を調整してきました。 実際、農業革命以前の人類は、150人程度の共同体と50人程度のバンドと呼ばれる野営集団を使い分けていたという考古学的証拠もあります。
ホモ・サピエンスは種の前提環境として、自然だけでもなければ、社会(近代の国家や民族のような想像の共同体)だけでもなく、顔見知りの群れとしての共同体を持っていました。サピエンスは少なくともチンパンジーと共通の先祖から分岐した約600万年前以降、おそらくそれ以前から、顔見知りの群れを前提に生活してきました。だからこそ、系統発生の視点から言えば、社会脳の大部分と関連する新皮質の拡大が見られるのです。自然だけを淘汰圧としていたと考えるなら、身体能力が退化し、コミュニケーション能力が発達していることの説明がつきません。近代的な個人や社会を前提に生活が行われるようになったのは、かなり最近の話で、それは本来、非常に特殊歴史的な事例だと考えて良いと思います。
特殊事例的であることは問題を孕みます。なぜなら、僕たちの脳や身体はそんなに急に進化できないからです。人間の脳は近代の環境に系統発生的に充分に対応できる機能を持っていないし、個体発生的に、多少無理して学習し、適応する必要があります。そして当然それらに対する不安やストレスは生まれます。生物学的な基盤を顧みることなく、啓蒙主義の時代に「望ましい主体の在り方」を設定し、それに基づいて制度設計してしまったがゆえに、僕たちは個人主義の前提のもとで、本来なら不得手なことに常に挑戦しなければならない状況に置かれています。だからこそ、その埋め合わせとして、グローバリズムでの勝ち組幻想や、国民国家への一体化幻想も生まれます。
歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは、ホモ・サピエンスが150人以上の集団を維持できるのは虚構を作る能力があるからだと看破しています(* ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』)。つまり、神話や法や貨幣などの幻想によって、知らない人たちの社会がなんとか維持されているわけです。なので、近代は虚構だからダメだというありがちな指摘は、僕の観点からはナンセンスです。なぜなら、現代社会において、150人を上限とした顔見知り集団だけで社会機能を維持するのはもはや不可能だからです。ゆえに、日常と共同体の縮尺度から地続きの形で社会の次元まで橋渡しするしかありません。具体的には、150人の血縁・地縁的な共同体だけでなく、趣味や関心を通じた1000人程度の社会との中間にあたる自立的な群れが必要だと思っています。それらは個体発生を支える学習の前提としても機能するものです。そして、入離脱可能なそうした基盤があるからこそ、民主制が機能すると思っています。熟議が必要だと声高に叫ぶだけでは、ヒトは議論しません。体感できない抽象的なシステムに適応するように僕たちの身体は進化していないからです。しかし、中規模の共同体で様々な年齢の人たちと直に触れ合い、様々な専門性を持った人と具体的に意見を交換できれば、興味や関心の持ち方から動機付けのあり方まで、適切な関係に収まると思ってます。
宇野さんの議論の重要かつ新しい点は、中間共同体の機能不全に戦後民主主義の問題を見ていながら、問題の分析に留まらず、テクノロジーを媒介にヒューマンスケールでの中間共同体の制作へと歩みを進めている点だと思っています。今回の本の中ではプラットフォーム、メディア、コミュニティを対比的に語っています。そして、それぞれの利点と欠点を示した上で、『Ingress』や『ポケモンGO』の系譜を批判的に継承することで、「いいプラットフォームさえ用意すれば自然に学んで自然に教育されていく」といった主体を前提にした思想ではなく、プラットフォームで生き抜くために、メディアで濃密な情報を届け、コミュニティでそれを読むための学習を具体的に後方支援することを提案している。現代社会の状況を分析した上で、人々が「走りながら考える」ことを継続可能なかたちで実現するためのプロジェクトを動かしている。
宇野 この本の最後に書いたことだけれど、僕は「遅いインターネット」計画は当初このウェブマガジンを中核にした、ネットサーフィンの復権運動を考えていたわけです。この国で言えば、週刊誌とテレビがネタを投下して、そしてTwitterでユーザーが好感度の獲得を目的にコメントを加えるといった閉じた相互評価のネットワークの外側にどうあたらしい批評とジャーナリズムの場を創るか、を考えていた。それはこうしてこつこつと実行しているのだけど、計画を準備して本を書いている間に考え方が変わってきた。それだけじゃダメで、やはりコミュニティを引き受けて、そこから人材を排出していく運動が併置されていないとシリコンバレー的なプラットフォーム主義への批判的な応答としては不十分なのではないか、と考えたわけです。そこではじめたのがPLANETS Schoolという僕の「発信」のノウハウを共有するワークショップみたいなものです。
これも本に書いたことだけれど、僕はジョン・ハンケの手掛けた『Ingress』に半年ぐらいハマった後にやめちゃっているんです。それはゲームが嫌になったのではなくて、単純に『Ingress』を通じて街歩きのコツがわかってきて、散歩のほうがおもしろくなりゲームが不必要になった。それは思想家としてのハンケの狙い通りの結果だと思う。彼が結果的に体現してしまっているシリコンバレー的なプラットフォーム主義には、正しく環境を整備すればユーザーは自分からそれを使い倒し、あたらしい快楽に目覚めたり、学習したりするようになるという発想があるわけだから。しかし多くの人は僕のようなルートは通らないのが現実だったと思う。実際に『Ingress』は都市部のアーリーアダプターにしか支持されなかったし、その普及版である『ポケモンGO』は要するに映像の世紀に半歩戻ることで、つまり人気のキャラクター産業とコラボレーションすることで、情報化された世界を歩き回り、自然や歴史に直接的に触れる楽しさを味わうという『Ingress』のコンセプトを半分捨てている。モンスターの捕獲という要素を入れることで、ポピュラリティと引き換えに直接性を半分捨てたのが『ポケモンGO』ですからね。
だから、『Ingress』から『ポケモンGO』に後退するのではなく、正しく方向でなく散歩に行くには、さらに散歩からランニングに向かうためにはどうしたらいいのかということを考えて書いたのが、この本だという言い方もできると思うし、PLANETS Schoolという実践なんですよ。
吉本隆明の問題設定をアップデートするために
上妻 そうした人間、共同体、社会の問題を統一的に把握しながら、これからのやり方を探る理論的なフレームとして、吉本隆明の再評価をされているのが、思想書としてのこの本の白眉ですね。つまり、宇野さんは現代の問題を、情報技術が吉本の説いた三幻想(自己幻想・対幻想・共同幻想)を相互接続させている現状の元で、いかにして社会と自立の関係を考えるのかと捉え返しています。
そこで宇野さんに質問したいんですが、SNS等の情報技術が三幻想を相互接続させ、自己幻想の肥大化を生んでいるのであれば、対幻想という入り口から自己幻想のマネージメントを行なうという戦略もありえるんじゃないでしょうか。
吉本は国家のような共同幻想からの自立を唱えて、性愛関係や友愛関係のような一対一の対幻想に軸足を置くことで自立を促した。しかし、対幻想に浸ることが国家や企業を支える家族の再生産になり、むしろ共同幻想の強化につながったわけですね。これに対して1980年代当時の上野千鶴子は、家族制度に必ずしも回収されない他者性との対峙としてのロマンチック・ラブを説いた(*上野千鶴子『女という快楽』)。彼らが期待したような自立はありえないにせよ、現実世界における性愛関係や友愛関係の重要性は変わらず存在しています。現代社会において、対幻想はもはや逆立的とは言えないまでも、相互関連しながらの独立的機能を持っています。
ゆえに、僕は無意識に潜んでいる家父長制の入れ子的構造やメディアが作り出すロマンチック・ラブという幻想を反省的に織り込みながらの対幻想の訓練は、宇野さんの解決策と両輪で働くのではないかと考えています。マスメディアが男らしさや女らしさの定型文や既存の恋愛幻想を使い回すことなく物語を作れるとは思えないし、そうであるならば、普段接するドラマや映画だけでなく、ニュースやワイドショーなどでも、吉本や上野が陥った幻想が振りまかれ続けることになる。また、現代社会は宇野さんの言うように三幻想が相互接続している状態になっている。だからこそ、それらの幻想はより過剰に、より日常的に利用されていると思っています。
実際に幻想が崩れるのは現実の関係を通じてです。そして、幻想が崩れた後に、幻想なんかよりも重要な日常生活が学べるのも、二者関係を通じてです。もちろん、この再構築された幻想も幻想ではあるわけですが、絶体的な期待から離れて、つまり一方的な理想像の当てはめを超えて、漸進的な対話の中で作り壊され作り壊されの循環があるという点で異なります。言い換えれば、日常的な関係とは対話の中で幻想が相互に書き換えられていく経験であって、一方的な期待と欲求の投影を超えるところにあります。僕がここで提案しているのは、幻想を維持するためではなく、幻想を破壊し、再構築し続けるための訓練としての一人称−二人称関係です。これらの理由から、僕は性愛関係も友愛関係も、現代においてより重要になっていると考えるし、また同時に訓練される必要があると考えています。いかがでしょうか。
宇野 結論から言うと、僕は対幻想は社会的な機能として重要だけど、自立の契機にはならないと考えてます。当然のことだけど人間は、共同幻想や対幻想を否応なく抱えてしまうものだと考えたほうがよくて、共同幻想と同じように対幻想も、そこから自立するべき対象と考えたほうがいい。
対幻想を足場にした自立のプロジェクトがなぜ失敗するか。対幻想の内包する共同幻想、この場合は家父長制に絡め取られるから、というのが僕がこの本で指摘した第一の理由です。これは『リトル・ピープルの時代』で触れた村上春樹批判と同じです。『ねじまき鳥クロニクル』の主人公は、歴史に接続するために井戸に潜って、日本占領下の満州に生きた人間の記憶と「壁抜け」的に接続する。しかし一方でその「壁抜け」を可能にする、世界に対する蝶番として古い家父長制を内包した対幻想を、はっきり言ってしまえば性搾取的に導入してしまっている。もちろん、このセクシスト的な態度を糾弾するのは簡単なのだけど、それと同じくらい僕はそもそも対幻想に依拠した「自立」というプランに問題があったと考えていて、実際に僕はこの本でもう一つの罠を指摘している。吉本隆明に背中を押された団塊世代の活動家たちは、「家長として自立する」という方便を、社畜として埋没している本音を覆い隠すために用いていた。いわゆる「複アカ」を思い浮かべるとイメージしやすいと思うけれど、要するに、政治的に、経済的に、情報環境的に近代社会はどんどん人間を解離的に振る舞うことを可能にしているので、ある幻想に依拠することが他の幻想から自立することにつながらなくなっている。これが第二の理由ですね。
上妻さんの提案を掘り下げると、僕は『母性のディストピア』で、吉本の家父長制的な対幻想でも、上野のロマンチック・ラブ的な対幻想でもなく、同性の並列な仲間関係、ボーイズラブ的な対幻想は可能かという問いを立てている。前二者とは性愛的な対幻想で、後者は友愛的な対幻想と言い換えられて、前者は時間的、後者は空間的な関係性を構築する。アニメファン的には前者は『エヴァンゲリオン』の碇シンジで、後者は『ガンダムW』の5人組を思い浮かべればいいと思う。前者の碇シンジは両親から与えられた拡張身体がないと、それが父権へのあこがれであるにせよ母胎回帰的な願望を満たすものにせよ、自我が保てないのに対して、後者の5人組にとってロボットは全能感をもつ美少年たちのアクセサリーに過ぎない。前者の対幻想は結局ナルシシズムの確認しかできなくて、吉本/上野の陥った罠から逃れることがでない。では後者の対幻想はどうか。彼らの全能感を支えるのはボーイズラブ的な対幻想なのだけど、空間的な関係性だけでは「壁抜け」のように歴史とは接続しない。実際にボーイズラブ化したロボットアニメたちは、書き割りのようにしか歴史を描くことができない。ロボットが美少年のアクセサリーであるのと同じように、そこで描かれている歴史はボーイズラブのBGMでしかない。
つまりエヴァンゲリオン的な主体は「Somewhereな人々」がそうであるように閉じた相互評価のネットワークの中で逼塞するしかない。新ガンダム的な主体は、まるで今日を生きる「Anywhereな人々」のように歴史から切断されてしまっている。ではどうするか、というのが『母性のディストピア』の最後の問いで、あの本ではギーク的なものの亜種としてのオタク的な主体に活路を見出す、という結論に着陸している。つまり西海岸のギークはリベラルなヒッピーと金儲けのうまいヤッピーに取り込まれた結果、政治性を失ってしまったけれど、東京のオタクたちの遺伝子を活かせばそうではないルートも辿れるはずだ、という仮説を立てた。もちろん、実際はカリフォルニアのギークは加速主義に流れて、日本のオタクはAnywhereな主体にはなれずSomewhereな主体のまま左右のイデオロギーに回帰してしまっているので、あれはあくまで思考実験的な理想像の提示に留まっている。
だから僕はこの延長で、ただしもう少し別の角度から攻めようと思って、「発信する」主体という問題設定を『遅いインターネット』では試みているわけです。
上妻 なるほど。『リトル・ピープルの時代』と『母性のディストピア』での議論を更新するかたちで、今回の『遅いインターネット』における提案があることがよくわかりました。だからこそ宇野さんは、人々が国家や民族のような大きな物語と直接的に一体化したり、SNSでの「いいね」を集めるような「承認の再配分」と化した政治からは距離を置いて、「閉じた相互評価経済」を自己幻想のマネージメントの水準で乗り越えることを提案するわけですね。そして、そのために、コト(政治)ではなくモノ(生活)の水準でものを考える必要性を唱えられているわけですが、地縁や血縁と自分を切り離せない「Somewhereな人々」にはそれは難しい。現状それができるのは、境界のない世界に生きている「Anywhereな人々」寄りのライフスタイルに限られてしまっている。しかし、他方で「Anywhereな人々」は個人主義に適応できるがゆえに、現実離れしたグローバリズム一元論で解決しようとする。彼らはもはや民主主義を時代遅れのものとしか捉えていない。両者の議論がそもそも噛み合わないのは前提が異なるためです。
宇野さんのコミュニティ観で重要だと思うのは、コミュニティを単なる相互承認の場として扱っていない点にあると思っています。コミュニティというのは、中世までは学習の共通の足場として考えられていました(* リチャード・セネット『クラフツマン』)。実際、職人や伝統芸能では現代でも、そこに“いる”ことが学びの前提にあるわけです。“いる”ことで作法や振る舞いを見て、感じ、学ぶわけです。学ぶことは抽象的な規則を記憶したり操作することではなく、具体的な場で具体的な振る舞いを習得することでした。もちろん、中世の徒弟制を現代にそのまま移植することはできない。しかしながら、自発的に学ぶことが前提とされるプラットフォームの思想だけではうまくいかないことは明白で、読んだり書いたりすることに対して若い時から自然と訓練を積んできた僕や宇野さんのような人を一般化し前提化してしまうことは危険です。そうじゃない人たちにとっては、読むことも書くことも苦痛だったり面倒だったりするのかもしれない。僕も大学生と話すと衝撃を受けることも多々ある。だからこそ、中世とは別の仕方で、学ぶための場が必要となる。大上段に構えた知識人は、そういう「大衆の原像」を身近に受け取る人が少ないと思うんですが、宇野さんの場合、そこをしっかり受け止めていて、そのリアリティと向き合ってきたからこそ、そこをどう楽しく、継続可能なかたちで後方支援するかを考える必要があるんだという主張に繋がるわけですね。
宇野 うん。僕たち自身は全然読むことが苦痛にならないからこの仕事をしているわけで、「読むのは嫌いだけれど書くのが好き」というのはちょっと想像がつかない。ただ、生まれたときからネットワークにつながっている人間はそうなっているということは構造的に理解できる。
今日のSNSのあり方に僕が批判的なのは、自立の不十分な主体に対して共同幻想(タイムラインの潮目を読む)や、対幻想(「いいね」やタグ付け)を用いて、自己幻想を補填する仕組みになっているから。今日のSNSは人間をどんどん自立から遠ざけていく。 『遅いインターネット』の結論は、読む/書くことを再定義することで、共同幻想や対幻想に依存しない自立した発信を継続的に行うこと。そうすることで、主体と呼びうるような状態が結果的に立ち上がるというイメージです。 同じ書く行為でも、タイムラインの流れに加担するのではなくて、むしろそこから逸脱して、世界に素手で触れるために書くスキルを共有することが、ひとつの処方箋になるんじゃないか。それをいま、試験的に自分のコミュニティで試している。
それを補完するものとして『水曜日は働かない』というエッセイの連載を、『母性のディストピア』の担当編集者とはじめた。これは要するにひとり遊びの教科書のようなもの。走ることで、食べることで、模型をつくることで、どう対幻想や共同幻想に依存せずに世界と関わるかをできるかぎり身近な視点から考えている。『遅いインターネット』が上妻さんの言葉で言えば「制作」の次元に帰着したので、これはもう少し手前の「遊び」の次元で考えようとしている。
自己目的化しないコミュニティをつくる
上妻 現代社会は未だ消費主義を引きずっていて、買うことが即消費することに繋がるという前提があるように思います。例えば書籍などでも、分からない部分があればクレーム対象になり、じっくり読んで、数年後また読んで、といった愛好の姿勢が忘れられているように思います。楽器にしても、演奏できない人にとってはオブジェですが、誰しも訓練を積めば、それは美しい音楽を奏でるパートナーになります。さらに訓練を積めば、演奏が自分だけの楽しみではなく、他者にとっても価値のあるものとなります。楽器だけでなく、食べることでも読むことでも、なんでもそうですが、ある段階で分からないものや意味のないように思えていたことが、学習の過程を経ることで味わい深いものと化していく「愛好」の過程は至る所に存在します。僕は「消費から愛好へ、生産から制作へ」というテーゼを掲げていますが、実際、僕が言おうが言わまいが、文化には否応がなく段階的な敷居が存在します。作品を制作するのにも、鑑賞するのにも、批評するのにも、ある種の訓練は必須です。それは近寄りがたいものでもなんでもなくて、実は敷居があるから楽しめるものでもあります。うまくなることは自己満足でも楽しいですから。
さて、僕は、プラットフォーム、メディア、コミュニティという三幅対のどれかに偏ることなく主体化を考え、実践している人は宇野さんしか知りません。なので、その立場から、その訓練の場や環境づくりについて、どう考えているのか伺ってみたいです。
宇野 僕はずっと読者のコミュニティをつくることは意図的に避けてきた人間なのだけど、この数年で考え方を変わってきたんです。それはどういうことかというと、こうして独自のメディアを運営して何年も活動しているとコミュ二ティはなかば自然発生していく。その発生してしまうコミュニティを引き受けていくことは大事なことなのではないかと感じるようになっていった。
それはこの本で取り上げた糸井重里さんと「ほぼ日」のことを考える中で決めたことでもあって、要するに糸井さんがコミュニティから距離を置くのは、彼なりの倫理観のようなものが作用しているわけですよね。つまり全共闘的なものへの反省から、表面的に政治性を排除することで正しく政治的であろうとする「政治的ではない、という政治性」を行使する1980年代的な主体を糸井さんはいまも、時代に合わせてマイナーチェンジしながら維持していると思うのだけれど、僕はこの80年代的な、消費社会に適応した新人類世代から団塊ジュニア世代的な主体が政治的なものへの免疫のなさから、今世紀に入って情報環境にも支援されてネトウヨと放射脳の温床になっていったのを目の当たりにして生きてきたところがある。だから僕はちょっと違うやり方を取らないといけないと考えたわけです。コミュニティは引き受ける。しかし、そこでその場にいない敵の悪口を言って結束を固めるような飲み会論壇を再現するのではなくて、もっとオープンな学びの場にしていこうと思っています。そして政治的な態度表明もためらわない。しかし是々非々の態度は崩さずに、支持できないと思ったら率直に批判する。しっかり線は引くし、態度表明もする。しかし、常に留保もつけるし柔軟に反省もする。このスタンスでいきたいなと思っているんです。
上妻 プラットフォーム至上主義者は価値判断を保留することに価値を見出しているわけですが、プラットフォームを実際に収益化し、運営していくかを考える段階になると、三人称的な、抽象的なマスを扱わざるを得なくなります。つまり、ウェブ上のプラットフォームは、旧来的なテレビと同様に、結局、広告モデルに頼ることになります。三人称型のビジネスモデルは無料で多くの人に届けることで広告価値を高めるので、価値判断を留保しているつもりでも、実質的には「敷居のないもの」しか扱えないことになります。前述した文化の条件を考慮するなら、文化的なものは一切扱えず、誰でも即物的に消費できるコンテンツのみを無意識的に選択しているのと同じことになります。僕は、価値判断を留保するという態度は消費主義を加速させると考えています。
宇野 それは僕がプラットフォームからではなく、メディアとコミュニティからアプローチしようと考えた理由の一つで、僕のやり方は完全に寄付モデルです。僕たちの理念に共感して活動を支援して寄付してくれる人には優先的に僕らのスキルを共有するし、彼らに限定のコンテンツも提供する。多分これは間違いなくスケールしないんだよね。でも、スケールしなくてもいい。いまは僕しかいないかもしれないけど、同じことを考えるプレイヤーが、もっとできれば若い世代に10~20人現れてきたら、少なくとも国内の言論シーンは変えられると思います。
ただ、僕はいまのところ、上妻さんほど顔の見える者同士の対幻想への期待値を中心に用いて自己幻想のマネージメントを企む方法論は採ってないんだよね。もう少し個人の次元でモノを考えようとしてる。というか人間対人間で考えるのではなく、人間対事物の次元で考えてみたい。だからこのコミュニティで実験的に書くスキル、ノウハウを共有することに成功したら、だんだん解放していこうと思っている。人間の側でしっかりとスキルをどう共有するかという方向に軸をずらしたほうがいい。
上妻 僕が対幻想の水準を重要視する理由は二つあります。
一つは先に挙げたように、系統発生の論理から言って、ホモ・サピエンスは個人を前提に進化してきた生き物ではないので、個人主義や自己責任論は負担が大きすぎると考えていることです。最近、デイヴィッド・スローン・ウィルソン『社会はどう進化するのか』という書籍が翻訳されましたが、その中でも、前提にすべきは個人や社会ではなく、その間の信頼できる中間的な群れであるという理路が進化論の観点から述べられています。例えば、精神科医が患者に話を聞くにしても、これまでは患者と医者という個人を前提にした一対が前提とされていましたが、奧さんや子どもなど信頼できる人に来てもらって、手を繋いだ状態で質問すると、それまでの拒否的な反応が和らぎ、前向きに対話が進展することが示されています。患者は医者とはいえ、初めて会う人とコミュニケーションする状況に慣れているわけではありません。それは非日常です。その状況では、ぶっきらぼうで冷たい人に思えても、家族や友人の前では優しくユーモアのある人だったりします。状況が変われば、行為も変化します。ゆえに、普段となるべく同じような状況を作って診察する方がうまくいくと考える方法論もあるようです。
▲『社会はどう進化するのか――進化生物学が拓く新しい世界観』
また、グレゴリー・ベイトソンが家族療法といって、患者ではなく、患者の環境を含めて診察するようになったことも、個人は環境から意識的にも無意識的にも学習することを前提にした考えであり、個人は環境と分離した存在でないことが前提にあります(* グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』)。もちろん、その環境として家族を選んだのは現代的ではないかもしれませんが、僕と彼が一致するのは学習環境としての群れと個人は切り離せないという前提です。
国家との一体化幻想の背景には、個人主義があると思ってます。個人に耐えられない人は何かより大きいものと同一化することで不安を埋め合わせようとする。しかし、僕が提案しているのは、中間共同体との一体化を目的とするのではなく、それを足場とすることです。具体的かつ直接的な安心の基盤があることで、何かに同一化せずに生きられる個が可能になるのであって、そういった群れがなければ国民国家やグローバリゼーションなどの抽象的なシステムに同一化することでなんとか維持するしかない。目的としてのコミュニティは安定剤としてしか機能せず、足場としてのコミュニティは社会と個人という別の水準への発信基地になりうると考えています。これは『遅いインターネット』で距離感と侵入角度として論じられていたこととも関連すると思っています。
宇野 他の記事でも取り上げているように、僕はこの2年間、安宅和人さんを中心とした「風の谷を創る」という運動に参加してます。要はいろんなジャンルの工学的な知を運用して自然と共生するあたらしい暮らしのかたちをつくる運動です。僕はこの運動の中で、岩佐文夫さんと一緒に「風の谷憲章」というものの作成に主に参加しているんです。この憲章で僕は「風の谷話法」と呼んでいるものを提案しました。どういう話法かと言うと、まずは「Aである」と一回きちんと態度表明する。「しかしBも許容する」とか、「Aである、しかしCの場合は例外も認める」といったかたちで、必ず留保をつけて、そして可能な限りジョークも仕込んだ。このコミュニティに対しての距離感も、この憲章と同じようなアプローチでいくしかないなと思っている。
▲都市のオルタナティブとしての「風の谷」と
それをつくるための「語り口」についての覚え書き | 宇野常寛
上妻 「風の谷話法」良いですね。条件文抜きの命題は現実には存在しないにも関わらず、日常的なコミュニケーションではコスト節約のためにも省略されることが多いですから。そして、偶然ですが、「風の谷話法」は、僕が対幻想の水準を重要視する二つ目の理由と関わっているように思えます。「風の谷話法」は条件付きでかつ部分的な命題のやりとりをコミュニケーションの主な方法と決めることなので、絶対的な正解という幻想を許さない方法として有効だと思いました。そして、僕の二つ目の理由は絶対的な正しさという幻想を打ち崩す上で、一人称−二人称の視点の往還が有効だと考えているというものなのです。
僕はミメーシスを二つの方向から捉えています。一つは認知的なミメーシス、もう一つは情動的なミメーシスです。認知的なミメーシスとは、例えば、チェスや将棋のように、相手の視点に立って、自分がどこにどう打つか考え、再度自らの視点に戻るような視点の往還運動です。認知的な視点移動は原理的には終わりはありません。「相手は僕のことをこう考えていると僕は考えていると相手は考えていると僕は考えていると相手は考えていると……」と理論的には永遠に続きます。しかし、もちろん認知能力的に限界はあり、うまくできる人は将棋やチェスなどを上手にこなすはずです。そして、社会的に気がきく人として周知されている一方、もしかしたら気にしすぎて疲弊しやすい傾向があるかもしれません。
情動的な同一化は宇野さんもおっしゃるように、否応なく訪れるものなので、僕は単に他者に吸収されるのではなく、適切な距離をなんとか制御するための技術として訓練する必要があると思っています。例えば、人類学者レーン・ウィラースレフは、恋に落ちるとは「自分自身を拡張して、相手に同化すること」であり、狩りの現場における愛は、愛だけでなく死も意味すると書いています(* レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』)。時にシベリア・ユカギールの狩人はヘラジカの魅力に惹き込まれ、撃つことはおろか、何も考えられなくなる者がいるらしいのです。自分は誘惑しているつもりでも、それがいつ愛に変わるか分からない。誘惑は常にする/されるの間を不安定に揺らめく不安定性を帯びています。「007」シリーズでも、初めはジェームズ・ボンドを誘惑する敵側の美人スパイだったのに、気がついたら殺すべきボンドを愛してしまったという話がありますよね。そこでも愛はスパイの死を意味する。これは近代社会でも良くある話です。
▲『ソウル・ハンターズ――シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』
重要な点は、言語では認知的と情動的と分けて思考できたとしても、実際的にはそれらは深く入り混じっていることです。人と人が将棋を打つ場合、仕草や表情や姿勢などが大きく盤面に影響することがあります。数十年前の名対局をYouTubeで見ると、威圧的な表情でバッチンと駒を盤に打ち付けるなど、露骨に盤面以外のやりとりがあって面白いです。また、読書においても、認知的かつ情動的に作品に入り込まないと読むことはできない。そもそも単なる文字の羅列に過ぎないテキストを読んで感動して涙が出たり、恐ろしくて震えるのは、僕たちにミメーシスの力が備わっているからです。言い換えれば、僕たちは将棋や読書や絵画を認知するのではなく、それらと誘惑する/されるという不安定な関係にいると考えた方が良いのです。
他方で、SNSで有名人に「幻滅しました。もう応援しません」などとリプライしている人がいるじゃないですか。ああいうのは視点の往還ではなく、一方的な幻想の投影があるだけです。「『幻滅する』って言ってるけど、アンタそもそも何を知ってるの?」って話です。対面的な場でミメーシス関係が起こる時には、認知的にも情動的にも一人称−二人称の視点の往還が起きている。誘惑する/されるの関係が生じている。こちらの働きかけに対して、言葉なり姿勢なり仕草なり表情なりの応答、あるいは変化が起きる。それに対して、さらにこちらも応答、あるいは変化する。対面の場では意味が満ち満ちています。何も応答しない、何も変化しない、というのさえ、無視するという意味深い応答です。一人称、二人称の往還の中では、勝手に抱いていた幻想は崩れては作り変えられ、崩れては作り変えられが繰り返されている。ある作家についてとか、ある作品について読解していく中で、読み手が最初に抱いていた刷り込まれたイメージとは違っても、それを何度も崩していくというプロセスを経ることで、別のイメージや意味が染み出してくる。そして、その中で読み手自身も変わっていきます。
上記の二つの理由で、僕は、対幻想に対するアプローチとして、対面の場における一人称−二人称の往還を重視しています。誰しも未経験のうちは、主語的統合の世界を生きています。体感を伴う経験ではなく、見ただけ聞いただけで言語的な範疇の世界を正しいと思い込んでしまう。誰しもある程度は、メディアが垂れ流す家父長制的な幻想やロマンチック・ラブ的な幻想に浸っていると思うんです。しかし、対面の場におけるミメーシス関係は、それを具体的に崩しては作り変えていくプロセスであり、そこに可能性を感じています。これは宇野さん自己幻想へのアプローチ批判ではなくて、自立の方法論として自己幻想の方向と対幻想の双方からアプローチする可能性があるのではないかと思っています。
人間以外のモノと対話するということ
宇野 それはそのとおりですね。もちろん両立します。ただ、読むという行為も、自分に対しての手紙として読むのか、世界に対しての記述として読むのか、そういった違いがある。そこに書かれたのがただの叙事詩でも、ミメーシスは起こると思う。僕は二人称的なものが必要だとは考えていない。むしろ対象を人格化して、二人称に押し込めてしまうことが想像力を殺してしまうのではないかと考えているわけでです。だから僕はどちらかと言えば人間と人間ではなく人間と事物との関係に注目してきた。特に僕が批評してきたポップカルチャーは、必ずしも特定の作者個人に紐づいて成立しているわけではないですからね。
そこで改めて吉本隆明に絡めて言うと、『共同幻想論』を読むと、吉本は自立と言っておきながら、実は自己幻想についてほぼ何も書いていない。1960年代当時の日本では「個人」はあってなきようなもので、戦後的にマイナーチェンジすることでしっかり生き延びた家父長的な対幻想に絡め取られるか、ベタにマルクス主義や天皇主義といった共同幻想に取り込まれてしまう。だから前者が後者よりはマシである、という立場を彼は取ったのだけど、1980年代の消費社会のもとで、やっと初めて自己というものが出てくる。そのとき彼が普遍視線と世界視線ということを言ってたわけですよね。僕の考えでは世界視線は三人称的なもので、普遍視線は実は一人称じゃなくて二人称的なものなんだと思う。そして吉本に限らず、20世紀の知識人は、きちんと他者として機能する二人称は何かを考えてきたところがある。
吉本隆明は「対幻想を根拠に共同幻想から自立せよ」と言い、上野千鶴子は「吉本の自立の思想は家父長制を内包しているので、家族未満の性愛に留まれ」と言った。そして宮台真司は「上野千鶴子のロマンチック・イデオロギーは結局共依存なので、変態になれ」と言った。このルートでは宮台さんがひとつの臨界点なのだけど、それゆえに大衆は耐えられない。対して吉本自身は結局親鸞的に「絶対他力」による救済という方向に着地していく。これはどういうことかというと、要するに人間は自立するためにこそ、二者関係的に他者と対峙しなければいけない、という考えが突き詰められるとどうなるかということですよね。他者と向き合っているつもりで、実は依存している。それは所有しているだけで関係していない、それではダメだ、そんなものは他者ではない、と論理的に考えると究極的には成立しない完全な「他者」を求めてどんどん無限後退していく。
その結果どうなったかというと、片方では大半の人々は宮台的な臨界点まで耐えていくことはできずに、無限後退のゲームを自己目的化していく。具体的には「より強い他者」を探し出してきては、それに無自覚な誰かにマウンティングして指弾することを目的とした大義名分としてのポリティカル・コレクトネスのゲームが発生し、もう片方の後期吉本的なアプローチは人間は自力では自分を救済できないという諦念を共有することで、シリコンバレー的なプラットフォーム主義に行き着く。もちろん、どちらも相応の成果があったと思うし、むしろその成果をどう活かすかを考えるフェイズではあると思う。だからこそ、その批判的な検証がいまは必要なわけです。
なので僕はそのどちらでもなく、二人称の思考からいったん離れてみたい。具体的には直接に人間に向き合うのではなく、人間以外のものが持っている他者性とコミュニケーションすることを考えたいと思った。プラットフォーム主義とは異なるかたちで、人間と事物の関係を考えてみたいわけです。
上妻 人と対話するうえで、作品や事象が媒介として間に入ることで、初対面でもその人の人格とか、そういったもろもろの属性とは切り離されたかたちで、対話というかコミュニケーション可能になるわけですね。語る対象は他者との共通の足場にもなる。良質なコミュニケーションには媒介が必要なわけで、直接的なつながりは「いいね」の数を集めて安心するような、無意味なつながりのためのつながりになってしまう。実際、今回も『遅いインターネット』という二人を繋ぐ足場があるからこそ、対話が成立しているのであって、媒介なしにいきなり話してくれと言われても、挨拶と天気の話くらいしかできない。
宇野 もっと言えば、人間以外とどうコミュニケーションを取るか、を考えているわけです。僕は批評家として、他人の物語に自分が侵食される体験について言語化してきたのだけど、この回路の社会的な機能不全に突き当たってしまった。では、どうするか、と考えて書いたのがこの本だったりする。「他人の物語を読む」ことから「自分の物語を書く」ことに人間の欲望の中心がシフトしたときに、いかにして対話は可能か。 ヒトについて書いてはいけない、というのが僕の暫定解です。
僕はそこで「書く」ことを一つの処方箋にしている。他人の物語を読むのではなく、自分の物語を書くこと。ただし、ヒトについては書かない。あくまでコトやモノ、つまり事物について書くことを提案している。ヒトについて書けば書くほど、対幻想や共同幻想への依存が高くなる(原理的にゼロにはできない)。人間「ではない」ものを媒介にコミュニケーションをとることが重要だと考える。だからこそモノやコトへの「批評」が重要になる。
本で紹介したvTaiwanが採用しているJoinというアプリケーションは他人の発言に「レス」がつけられない。あくまでルールメイキングという事物についてのコミュニケーションが求められる。ヒトと対話してはいけない。事物と対話する、という態度がアーキテクチャのレベルで貫徹されている。もちろん、繰り返し本で述べたとおり民主主義における法がそうであるように、資本主義におけるアーキテクチャは低きに流れる。なので、あくまで主体(と呼ばれる環境との相互作用)の水準で考えるべきです。
上妻 自分は20代の前半、直接のコミュニケーションではなく、作品を介してコミュニケーションをする、作ったものを介して他者とつながることに強いリアリティと希望を感じていた時期があったんです。具体的に言えば、MyspaceやSoundCloudに音楽をアップロードし、それを介して、ファンが増え、ライブやグッズ制作につながっていくことが盛り上がっていた時代がありました。会話のための会話ではなく、作品を介した対話を可能にする土壌ができつつある実感がありました。しかし、現在、そのような対話は一般的になりませんでした。当時は様々な理由から、それがうまくいかなかった。だから僕はそこをしっかり分析し、理論化する必要があると思った。なぜなら、すでに技術的に充分それを可能にする環境があるからです。それは僕の「消費から愛好へ、生産から制作へ」というテーゼの原体験としてある。
しかし、資本主義下の社会で低きに流れるのは価格だけじゃなく態度でもあります。普段の生活から無意識に短期的合理性を追求する方が有用性が高いと内面化していってしまう。しかし、それは不安や不全感を満たす上でより良い適応ではない。ある過酷な状況への適応として、アルコール依存症や共依存があるように、消費主義に適応してしまっている。しかし、一つの適応からより良い別の適応へと適応の仕方を変えなければならない。適応度地形という考えがありますが、ある適応から別の適応に移行する際には一度現状の適応の山を降りなければならない。強い渇望が起こり、苦しい時には短期的に言えばアルコールに手を出すのが早い。そうすれば渇望は収まります。しかし、長期的に見れば、それは破滅に少しずつ近づいていっている。依存症治療が難しいように、短期合理性の考えのままだと、「消費から愛好へ」は不利益をもたらすものに見える。しかし、一度切り替わってしまえばそうではない。アルコール依存症が治った後、そこに戻りたいと思う人がいないように、消費依存症が治れば、そこに戻りたいとは思わない。
じゃあ、それに対して僕がこれからやるべきことは何かというと、楽しく継続的なかたちで、いまいる山を降り、再度別の山に登る方法を実演しつつ示すことです。山下りと山登りをしながら、降り方と登り方の両者を理論的に示すこと。生活と制作のあり方を再定義することで、それによって他者を取り込むものとして作品や制作へ巻き込んでいく。それが僕としては、北田暁大さんの言う「繋がりの社会性」ではない人間以外のものを含めた社会性、他者を特権視する仕方でない仕方でのつながりになりうると思うんです(*北田暁大『嗤う日本の「ナショナリズム」』)。
作品には人と人の媒介としての役割、つまり、文化としての役割もあるのですが、制作にはそれ自体でモノとの対話という側面もあります。これは自著『制作へ』の中で分析したものですが、例えば、パウル・クレーを初めとして多くの芸術家がこのプロセスについての言葉を残しています。彼らはキャンバスや木や石や粘土などと接触していく中で、モノとのコミュニケーションを行なっています。例えば、誤って引いてしまった線によって、当初思い描いていた完成像とは異なる場所へと導かれていくといった経験が多数、様々な仕方で報告されています。僕は青写真通りに同じものを作り続けることを生産と呼び、作る過程の中で青写真そのものが書き換えられていく過程を制作と定義しているのですが、まさに制作の現場の中ではモノとの対話はよく起こることなのです。
僕は最近、比較心理学者の森山徹という人の『ダンゴムシに心はあるのか』という本を読んだのですが、この本の中に、NHKでやっていたリニアモーターカーの板金職人のドキュメンタリーが出てくるんです。ドキュメンタリーで焦点を当てられているのは、元々新幹線の板金を作っていた職人で、彼は新たにリニアモーターカーの板金制作の依頼を受けた。しかし、リニアで用いる金属は新幹線で使われている金属と違っていて、いままで通りの叩き方では全然思ったように曲がらない。そこで彼は人との対話と同じく、どうすればコミュニケーションに応じてくれるかと、様々な仕方で叩き続ける。すると、「こういう叩き方をしたら、こういうふうに曲がってくれる」ということが段々わかってきて、徐々に思った通りに板金の形を変えられるようになっていく。彼がリニアの板金職人として、リニアの完成した状態から見てしまうと、恐らくこのプロセスは捨象されてしまいます。しかし、彼は叩き続けることで、彼自身の変身を遂げたわけです。叩くことで返ってくる反応は金属ごとに異なる。そして、叩き続けることで、少しずつコミュニケーションの仕方を学んでいく。叩き方によって、返ってくる反応は異なる。人が無視するのと同じように、しっかり対応しないと「曲がらない」「思ったように曲がらない」という返答を返してくる。無視すらも意味を帯びてしまう。そして、その絶え間ないプロセスの中で、彼自身も変化していく。それはモノとの対話ともいえるわけです。そこでの調和的な関係が作れないと、お互いが望んだ形の曲がり方をしてくれない。そういったモノとの対話は、職人さんも普段から思っていることなんですね。
それははじめに設計図や方法論があって、それに従ってやればいいということではなくて、淡々と叩いていくことで気が付いていくプロセスです。それは板金だけでなく彼自身も生成していく過程であり、まさにモノとの共−生成の過程そのものです。アリストテレス図式のように、形を物質に押し付けることで机や椅子があるわけではなく、そこには人と素材の対話があり、その結果、作品と人は生成されるということです。心は相互関係の間に出てくる創発現象として存在しているのであって、ダンゴムシとか僕たち自体に独立して存在しているわけではない。僕は板金を叩いているわけではないから板金に対して心を感じないけど、板金を叩いている職人は板金との間に心の応答を感じているだろうし、ダンゴムシと応答関係にある人はダンゴムシに心を感じるだろう、というわけです。
宇野 まさに制作物との対話ですね。
上妻 これは翻って言うなら、人だってタンパク質の塊だと思う人もいるかもしれないということでもあります。幻想を押し付けられたり、押し付けたりするコミュニケーションしかとれない人は、そこに応答関係はなく、調和的関係を築けずにいる。言い換えれば、心を感じられない状態にある。
僕も、文章を書くことで同様の体験をしているわけです。書くことはあらかじめ頭にあることを白紙に押し付けることではなく、書いていく過程の中で、いままで考えもしなかった場所に連れていかれる経験です。いま書いた一文が、僕を別の一文を誘惑し、僕もそれに対して書きたいように誘惑する。そこには誘惑する/されるという官能的関係があります。文章を書くこと、職人が金属を叩く行為、絵を描くことでも何でも、何らかの対象と関わっていくことの中では、不安定性が発生してそれをうまく制御できないと作品にならない。自分が能動的に関わりつつ受動的な側面も同時にあって、自分で舵も取りながら流れを見ていくわけです。
「生活」と「制作」の関係
宇野 僕は川上弘美さんの小説が好きで、彼女の初期のころの作品では日常の中にファンタジー的なものが入り込んでくる。隣の部屋に熊が引っ越してきたり、いつの間にか蛇の妖怪と同居していたりする。その半分人間で、半分人間ではないものの存在は、性的なメタファーにもなっていてヒロインの身体と世界とをつなぐ蝶番の役割を果たしている。要するにファンタジーの力で身体と世界が直接つながる、といったことを反復しているわけです。
それが『真鶴』という小説で、結果的に自己解説的と言うか、種明かしのようなことが行われることになる。あれは夫が失踪して精神を病んだヒロインがずっと自分の影のような存在につきまとわれている、という妄想に悩まされて、その状態が治癒していく過程を描いているのだけれど、この影のような存在はここでは自分の母親とか、娘とか、特に後者の自分の身体から発生しているんだけど自分とは異なる存在のもつ不気味さをもつものとして描かれている。これはどういうことかというと、世界に対する蝶番としての二者関係の対象、吉本的に言えば対幻想というのは、自分の影なんだ、自分の身体の延長なんだ、ということだと思うんですよね。つまり家族や性愛の対象にあらわれる自分の影を妖怪的なものに置き換えるということを、川上さんはずっとやっていた。他者として機能しないものを、どう機能させるか。自分の身体とつながっているからこそ、湧き上がってくる不気味なものを受け止めるために、それに人間の顔を与えない、人間のかたちをしているものを異化していく、ということをずっとやってきたのだと思う。
ただ、僕がいま考えているのはこれをさかさまにした発想で、自分の身体の延長線上にないけど、侵入してきてしまうようなものをどう考えるかということ。他者というと悪い意味でロマンチックだから「異物」のような表現でいいと思うのだけれど、川上さんが家族を妖怪に読み替える、人間を人間ではないものに異化したときに、それには近親者や性愛の対幻想のもつグロテスクさを緩和すること以上の意味があったと思う。それは要するに、完全に自分の身体から切断されたものが自分の身体に侵入して、開くことの恐怖と快楽を取り入れること。そのことで、身体を世界に開くという感覚だったのだと思うわけです。親子とか恋人とか友人とか、自分から垂直な位置や平行な位置にある存在ではなくて、ねじれの位置にありながら自分と関係してしまっているものをどう捉えるか? 閉じた相互評価のネットワークの外側に出るためにはそういうことを考えないといけないと思うんですよ。たとえば放射能とかウイルスとかは、要はそういうものですからね。
▲『真鶴』
上妻 今おっしゃったような「異物」への開かれ方を考えると、そもそも「知識とは何か?」という話につながると思うんです。他者を超越的で理解不可能な点として理解する伝統は、カント哲学に由来するもので、現代風に言えば、認知科学の図式にも引き継がれているように思います。それを要約すると、僕たちは外からやってくる刺激を解釈するコンピューターのようなもので、我々の理解できる範囲は我々の解釈可能性の限界によって規定されており、モノそれ自体について思考することはできない、とまとめることができます。例えば、コップのコップ性は人間が解釈する限りにおけるコップ性であって、コップそれ自体の性質ではない。なぜなら、そこを歩いているアリにとって君がコップだと思っているものは巣に帰る途中にある障害物に過ぎない、といったようにです。
しかしながら、それは主語的統合のみを前提にした考え方です。主語的統合は、すでに解説したように、前提に正しい言語的な範疇を置き、それに当てはまるものを経験していく方法です。そこでは正しい前提に従って、知識は蓄積されていくものとされます。そこでは「あれも当てはまるし、これも当てはまる」といった仕方で、知識は増えていくものと考えられます。他方で、述語的統合ではむしろ経験によって、言語的範疇が書き換えられてしまうことを指しています。「ねじれた位置」にある「異物」が侵入してくることは、まさに述語的統合の良い事例だと思いました。なぜなら、異物は既存の言語的範疇ではすんなり解釈できないものだからです。それらは謎と共に、すっきりとしない感じ、不安や不全感を残しながら、僕たちに言語的範疇それ自体を書き換えるよう迫ってきます。知恵は、知識とは異なり、前提の上に蓄積されていくものではありません。むしろ、この「異物」と共−生成するための身体的な知です。リニアモーターカーの板金職人にとって、リニアの板金は「異物」でした。叩いても応答してくれないモノとしてありました。しかし、彼は互いに生成することへの信を持っていました。だからこそ、彼は根気強く叩き、叩く中で共に変化していくことで、身体の文法を別の範疇へと書き換えたのだと思います。そう考えれば、述語的統合とは異物と共に変わり続ける知恵と呼ぶことができるように思います。
宇野 閉じた相互評価のネットワークが完成する前は、自己の延長に存在するけれど自分とは異なるものと対峙することが、他者との対峙の第一歩だったし個人と世界とを結ぶ回路として有効に機能した。しかし、これからはむしろ人間の身体に否応なく侵入して、不可逆的に変えてしまうもののほうが、この閉じたネットワークの外側に出て世界に触れるためには重要になる。具体的には直接人と対話するのではなくて、制作物を通してコミュニケーションする、という上妻さんの議論はその実践として位置づけられると思います。
その上で尋ねたいのは、「制作」と「生活」の問題です。上妻さんの議論ではこの2つは結びついているわけですね。コリン・ウィルソンは『アウトサイダー』で、アウトサイダーとは自身の欲望を作品の制作だけでは表現することができず、生活そのもので表現するしかなかった人々(結果として社会から逸脱する)と定義しています。アウトサイダーとは、自身の欲望を作品の制作レベルでは表現できない存在で、だからもう全部壊してしまう人たちなんですね。たとえばゴッホとか、ヘミングウェイとか、生活そのものを作品化して壊してしまう人たちです。しかし、今はSNSがあることによって、生活と制作の境界が良くも悪くも消失してきている。その結果多くの人が自分の生活をフィクション化することになる。Instagramに写真や動画をアップして見せてるセレブは多いけど、ああいうものは過剰に社会化されることで、むしろ貧しい身体を生んでいるように僕には思えるときがある。しかし、同時にそれは何か制作物と身体との距離感というのをポジティブに再設計する契機にもできるのではないか。上妻さんの制作論を僕が重要だと考えるのはこの点です。
上妻 確かに、近年再生回数やら注目やらを集めやすいとされているのはセレブのお金持ち自慢動画ですね。それ以外にも、YouTubeなどの動画サイトには、破産するまでギャンブルやFXをして、大負けして絶叫しながら泣いているおじさんの動画とか、人間の生のカオスを演出≒表出した動画が上がってる。そういうのを見ていると、刺激という意味で言えば、近代的自我の葛藤やら、女に振られて悲しいとか、酒に溺れて云々みたいな私小説では、もはや全然物足りない。
しかしその一方で、初めのほうで語ったように、自己も他者も環境から立ち上がる一時的な現象としてとらえた上で、現象自体を豊かにするための環境の再設定を絶えず行なっていくなら、単に現象が立ち上がるのに任せるだけでなく、各々の持つスタイルが重要になると思います。スタイルといったのは、メルロ=ポンティの影響で、彼はスタイルこそ芸術家の内在的な振る舞いとして、鑑賞者に直観的に作用するものであると看破しました。また、スタイルは制度的社会の中で、様々なスタイルとスタイルの交叉によって、制度的言語とは異なるところに立ち上がるものでもあります(*メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)。言い換えれば、制度的社会に適応した結果の再生回数や注目といった価値観、とは別の仕方の、各々のスタイルを立ち上げることです。そしてスタイルを意志することです。「異物」と共−生成することによって立ち上がる〈形〉への美意識です。先日の濱野さんとの対談で宇野さんもおっしゃってましたが、それは僕や宇野さんであれば、文体ということになると思います。
「異物」との関わりによって、それまでいなかった自分が必然的に立ち上がることになる。ウィルスとの共生で不安な〈私〉が生成されるかもしれないし、キャンバスとの共生でこれまで描こうともしなかった作品と〈私〉が生成されるかもしれない。共−生成であればなんでも良いわけではなく、述語的統合への美意識、知恵への意志というのが作品制作には重要です。それは消費されることを目指すのではなく、愛好されることを目指すものです。なので、いまバズるとか再生されることではなく、長期のあいだ共にいることで共に変化していくものを作ることを目指すことになります。
それは次なるスタイルのための足場になります。僕が様々な作家の交差点でスタイルを紡ぎ出すように、次の作家に差し込む線を描き出したいのです。発信することと生活することの境界がなし崩しになっているなら、作品として自ら納得できるものを形作るという態度を持つことで、発信と制作は区別しなければならないと思います。制作は繰り返し板金を叩く時間と共にあります。それは発信のように脊髄反射的に行うことはできないものです。もはや、生活は制作の外部ではない。ゆえに「発信せよ」という誘惑から身を守り、異物との時間を楽しむ技術が必要かもしれません。
宇野 これは単純に、生活が制作の外部でなくなった今、どう制作は可能かという問いですね。良くも悪くも、いまや生活というものが制作の一部となって、両者の境界線が失われて、制作の外部として機能しなくなっている。もともとインターネットの可能性は、万人に発信能力を与えることではなくて、万人に制作能力を与えたことだと読み替えるべきだと思うんですよ。僕らは、充実した生活があるから良い制作物ができると考えてしまうんだけど、ある意味では逆のことも言えて、制作という日常の句読点、区切りがあるからこそ、生活が内部から異化して、世界が拡大していく。誰かに見せるためではなく、自分のために制作する。
インターネットは発信を民主化して、人々が閉じた相互評価のネットワークで誰かとつながる快楽を貪った結果、魔女狩りとフェイクニュースが溢れかえって民主主義の機能を半ば麻痺させている。しかしインターネットが代表する情報技術を、発信の民主化ではなく制作の民主化のための道具と考えたらどうだろうか。制作する日常を送ることで、走りながら考えることで、僕たちは少なくとも半分は閉じた相互評価のネットワークの外部にまで出ていくことになる。そうすることで初めて自己幻想のマネジメントが生活レベルで可能になる、と考えたほうがいいんじゃないか。というか、もともとこれこそがインターネットの初期の理想への回帰なんだから。
上妻 いま宇野さんがおっしゃった「発信の民主化から制作の民主化へ」は、まさに僕の原体験からいまの活動への道筋を説明するテーゼだと思います。僕は、発信ではなく制作をいかにして可能にするかを考え、実践していかなければなりません。いま、『遅いインターネット』という本について対話しているように、互いに批評的に読解することが前提となる作品=足場こそが、現在のSNSのような速いコミュニケーション全般を遅らせる契機となるし、それはとても楽しいと思うわけです。今回の対話によって、それまで知らなかった場所にたどり着き、別の〈私〉が現れたように思います。今日はありがとうございました。
宇野 非常に光栄です。またタイミングをみて話しましょう。
[了]
この記事は佐藤賢二と中川大地が構成し、2020年4月6日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。