「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、「庭プロジェクト」ボードメンバーの一人でもある哲学者・鞍田崇さんによるプレゼンテーションが行われました。テーマは「制作」における「傷」、そして「見守る」という営みの可能性です。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた鞍田さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、参加メンバーでのディスカッションの内容をダイジェストします。
「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
「見守る」と「傷」をめぐって
まず鞍田さんのプレゼンテーションに対して、『魔女の宅急便』を引きながら応答したのは、建築家の門脇耕三さんです。
「『傷』の話を聞いて、映画『魔女の宅急便』を思い出しました。(主人公の)キキがスランプになって飛べなくなったときに魔法力が落ちて、(相棒の黒猫)ジジの声が聞こえなくなりますよね。劇中にキキが初潮を迎えたことを暗示するシーンがあるのですが、大人になったから、つまり人間と動物の世界が曖昧だった子どもの状態を脱して大人になってしまったからジジの声は聞こえなくなってしまう、ということを描いていると思うんです。そしてキキは、ウルスラという女の子の絵描きのもとに行くと、『自分に向き合うしかない』と言われるわけです。あれは要は『傷』なのだと、今日のお話を聞いて思いました。
ただ一方で、(プレゼンテーションで触れられていた)民謡のように、違うバイブレーションを共鳴させていくというかたちでの『制作』もあり得るのかもしれません。ダナ・ハラウェイが、連帯の実践としての『あやとり』がすごく興味深いと言っています。『傷』によって個になって、切り離して、自立して……という『制作』はわりと男性的になっている気もしており、連帯的で共鳴するような、フェミニズム的な『制作』のかたちもあり得るのかもしれません」(門脇さん)

そして東京小金井にある福祉施設「ムジナの庭」代表の鞍田愛希子さんは、植物とケアにかかわる実践に取り組んできた立場からコメントしました。
「まず、今日のプレゼンテーションを受けて改めて自分の仕事を顧みたときに、支援職や心理職はやはり『傷』を介してつながっているのだなと思いました。言い換えれば、『傷』がなければつながらない関係性でもある。深い心の傷から、自分の理想とのズレによる傷つきまで、この傷が回復しない状態というのが、精神疾患の前提条件にあるのだなと改めて気づきました。
それから『制作』と『見守る』は対になっているのだなとも思いました。投稿者とフォロワー、つくる人と周辺で見ているギャラリー……そうした対で考えると、『庭』の作り方もまだまだ広がりがあるなと。植木屋をやっていたときも、見る人がいるから綺麗にしていましたし、『制作』は『見守る』人がいるから成り立っていると言えるのかもしれません。

また、障害福祉の現場における『制作』は、当事者自身が生活や人生を作り上げていくことを指すのかなと思いました。『見守る』という言葉は支援の中でも使われるのですが、障害にかかわる歴史でいうと、もともとは自由や権利をはく奪された状態で、たとえば監禁・中絶など身体的な拘束さえも強いられることがあった中で『当事者主体』『自己決定』が叫ばれるようになり、『当事者が選択する権利』が回復されるようになりました。さらに昨今では、逆に先回りの支援がなされすぎることへの問題提起として、『失敗する権利』の重要性が議論されるようになっています。『浦河べてるの家』を立ち上げたソーシャルワーカー向谷地生良さんの著書『技法以前:べてるの家のつくり方』の帯にも、『私は何をしてこなかったか。』と書かれています。伴走支援じゃなくて、常に斜め後ろにいる。その立ち位置を、私自身、ソーシャルワーカーとして活動する前に学べたことは、とても大きかったと感じています。そういう意味でも『見守る』というキーワードは重要だと思いました。」(鞍田愛希子さん)
「育てる」と「見守る」──自然と人工の二項対立を超えて
一方、創造社会/パターン・ランゲージ研究者の井庭崇さんは、「自然との関わり」という観点に重点を置いて応答しました。
「僕の研究室の修士の学生で、『暮らしと自然の紡ぎ方』というテーマで研究をしていて、家庭菜園や畑をやっている人たちにインタビューをしてパターンランゲージを作っている子がいるのですが、ちょうど最近大きな発見があったんです。インタビューした人たちは、単に自然に関わってるのではなくて、自然と関係を紡いでいたと。果樹を植えると10年20年のスパンで関わり続けるわけで、まさに関わりを育んでいる。対象としての植物ということではなくて、植物との関係がずっと育っていることに、最終的に気づかせてくれる研究になっていました。
人工物は『ボタンを押したら反応する』といった即物的な瞬間に接する側面が強く、関係性が育まれにくい。対して、庭とは毎日のように関係するので、関係自体も愛でて育てているところがある。『見守る』も何かをパッとその瞬間見ているというだけではなく、おそらくケアする関係が続いて、それが深まったり豊かになったりして、時間軸の中で関係がずっとあることが大切なのだと思います。
パターンランゲージの提唱者・アレクザンダーも、建物を建てるときの建材は、延々と変化がないものではだめで、朽ちていくものを使わなければいけないと言っています。人間は死ぬのだから、死を感じさせないようなもので作ってはだめなのだと。だんだん朽ちていったり剥げていったり、そういうところに時間経過が織り込まれるからこそ関わりが生まれるのではないでしょうか。それは人工物であっても同じで、たとえば僕がいま普段使っている机は、マウスを動かす箇所が削れているんですよね。それは関係が育まれているからこそのもので、だからこそ見守るし、ケアをする。
そして『育てる』には能動的なところもありますが、やはり大事なのは『感じる』ことだと思うんです。植物を育てるには、そこがいまどういう状況にあるのか、土の状態を見たり、植物の状態を見たりして、肥料をあげたほうがいいか、水をあげたほうがいいか、何が好きだろうかと考える──すなわち感じる力が必要です。状況を見ないと育てられないので、『見守る』とはすごく近い概念なのだと思います」(井庭さん)
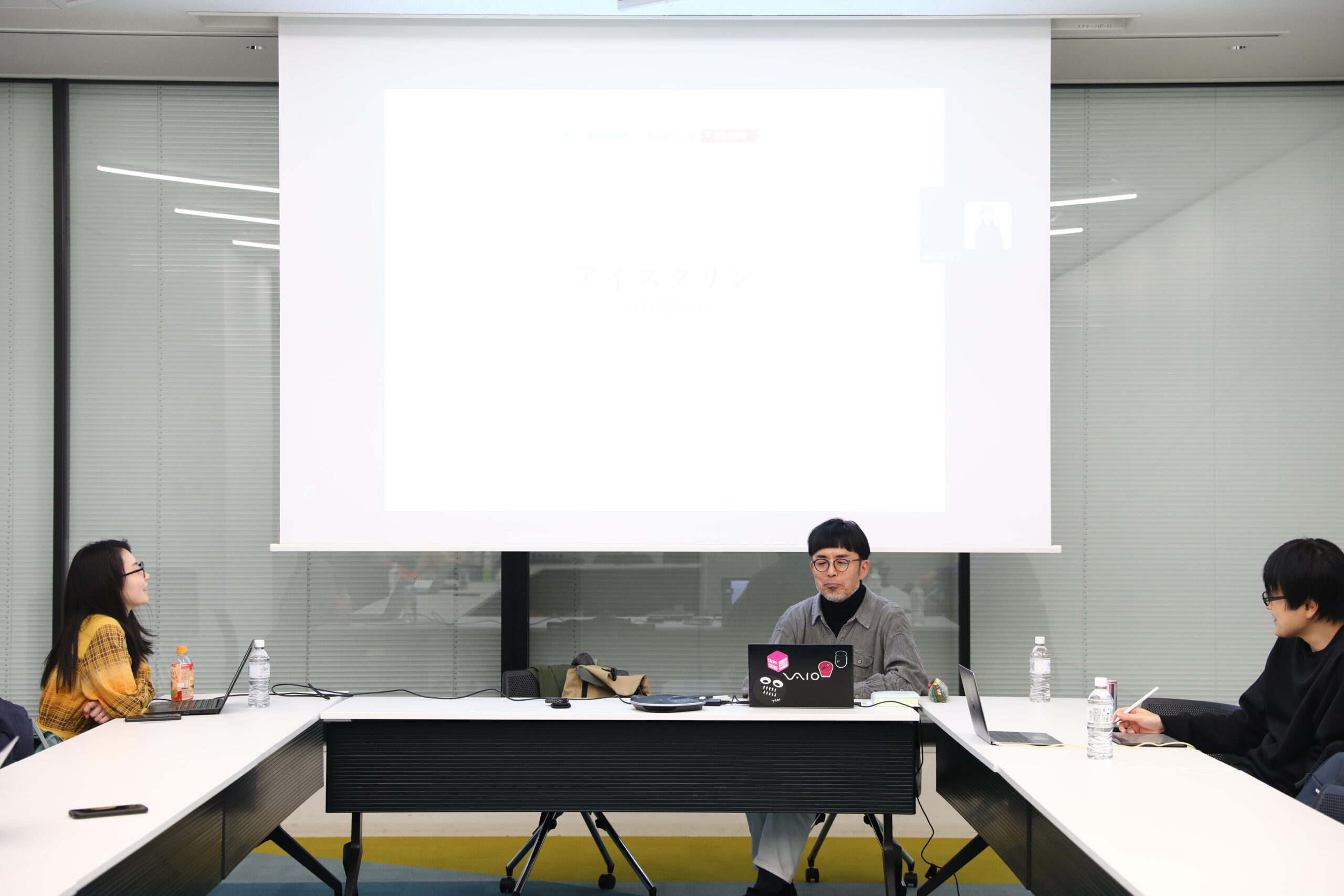
対して、デジタルファブリケーションや3Dプリンティングの研究者である田中浩也さんは、「箱庭療法」を起点に、「自然」と「人工」の二項対立を脱することの重要性を説きました。
「僕も1995年、京都で大学生をしていて、一年生から二年生に上がるときだったんですよね。法然院の下宿ですごく揺れて、その後西宮の炊き出しのボランティアとかに行って、その後箱庭療法を学ぼうと思いました。箱庭療法って、箱を渡されて、人とか動物とか木とか、そういうオブジェクトのフィギュアと、砂と、水を模した水色の砂が配られるんですよね。その箱の上にぼんやりと自分の心象風景みたいなものを作っていくのですが、あれは僕にとっては『制作』と『見守る』の中間地点だったのだと思います。一つひとつのフィギュアなどは用意されてるので、素材から制作するわけではないのですが、それらを配置する、アレンジするという行為に促され、その日の自分を投影して庭を構成する。そのときに、その庭をまた自分とは別の角度から見ている人がいて、ときどき『この水はどっちに流れるの?』といった問いを投げてくるんですよね。すると頭の中に水の流れが想起されて、ではそれに沿ってまた別のものを配置してみようか、といったことが繰り返されていく。こうした『制作』なのか『見守る』なのかわからない、両者のアレンジメントのようなことに昔から興味がありました。
それから僕は、庭という概念は、自然物と人工物という二項対立を解くものであってほしいと思っています。自然物だけで作るのであれば庭ではなく、そこにどうやって人工物が混ざってくるのかが重要です。野菜や木といった自然のものとは異なり、人工物は育たないですが、その代わりにたとえばベンチや椅子の向きといったレイアウト・配置をときどき変えることができる。日本庭園には植物も植えますが、石などもあって、石は材料は自然のものだけれど育たないし成長もしないので、限りなく人工物に近いと思っています。
そう考えてみると、自然の樹木は時間軸を担っていて、時間とともに変わり、成長していく。一方で石やベンチ、椅子といった類の人工物は、空間性を担保している。つまり、時間的な要素と空間的な要素をいかにして混ぜていってアレンジをするかそしてときどきシャッフルするかが、僕にとってはわりと庭の醍醐味になっているところがあるのだと思います。そういう話が、もしかすると箱庭療法でなんとなくぼくが興味を持っていた、『制作』と『見守る』が両方その中で中和しているという世界観とつながるのかもしれません」(田中さん)
「井庭さんと田中さんのお話を聞きながら思ったのですが、『育てる』が『見守る』に通ずるのかもしれません。僕はもともとそこまで思い至っていなかったのですが、民藝運動に関わる人々がよく言う『つくるのではなく生まれる』という話と通ずる世界が、この『見守る』にはあるのだということを、お二人の話から気が付かされて、とてもありがたかったです」(鞍田さん)
「見えない」と「見える」の二重性
「見守る」という概念の射程をさまざまな角度から深めていった一方で、文化人類学者の小川さやかさんは「見えないもの」という論点を提示し、「見る」という営みそのものを問い直していきます。
「石井美保さんという人類学者が、『精霊たちのフロンティア』という本で妖術や呪術の研究について論じているのですが、彼女は『小人が見えた』と書いています。私はこの感覚がけっこうわかる気がします。私たちは理性によって、現地の人たちが語る妖術や呪術が存在しないと思っていますが、毎日その世界の中にいると、少し感覚が変わってくる。アフリカの夜は本当に真っ暗闇なのですが、そこで人々が妖術とか呪術について語っていて、小人がいると思って人々が振る舞っている中に自分も身を置いていると、存在しないと思い込んで振る舞うことがもはや不可能になってくる。違う環世界と自分自身の折り合いをどうやってつけたらいいのかを探る中で、結果として見えてきちゃったりするんです。ただ一方で、その世界に住んでいる人たちもまた、精霊が本当にいると思っているわけでもなくて。いるかもしれない、けどいないかもしれない……みたいにずっとふらふらしている中で、実は環世界のように閉じた輪みたいなものが、どこかで交通しまうことがあるのだという話を石井さんは書いているんです。
私たちは近代的な理性や合理的な発想の中で生きてはいるのですが、精霊のようなものが全然ないものとして生きてるかというと、そうでもないなというところがあって。『アザンデ人の世界』という妖術についてすごく合理的な説明を書いた本があるのですが、石井さんは『文化人類学の思考法』という本で、著者のエヴァンス・ブリチャードは『妖術なんてない』と書いている一方で、『わたしは一度だけ妖術が移動するのを見たことがある』とも書いてしまっている。明かりが飛んでいくときに、みんながそれを妖術の魂なんだって考えていることを知っていて。徹頭徹尾妖術なんかないはずだって思ってるのに、一緒に追いかけてしまったりするのだと。私たちは常にそういう二重性の中で生きているのだと思います。
また石井さんは同書で人類学者ウィリアム・イェイツさんの話も書いていました。イェイツさんも、村で民話の収集をしていたとき、ある老婦人からたんまりと妖精譚を聞き取ったそうです。やがて暗くなってきたので『そろそろ帰ります』と言いながら、そのおばあさんに『あなたは妖精を信じていますか?』と聞くと『そんなまさか』と言ったそうです。しかし家を出て行く道すがらに、『でもいますよ、イェイツさん、いますとも』とも言ったのだと。本当はそんなものはいないと断じるのではなく、でもそうした世界を生きていると想定するのでもなく、私たちにとって別の世界がふとしたきっかけで開いてしまうことってあると私もどこかで思っています」(小川さん)
「僕が深く関わっている会津で長年調査されている赤坂憲雄さんが、会津にはキツネに化かされたとか、いわゆる遠野物語的な世界がまだあると言っていたのを思い出しました。原発事故があった福島の現実の向こう側に、まだそういう世界がある。たしかにおっしゃるように、『見えるかもしれない』という可能性を開いておくことの大事さはあるのだと思います」(鞍田さん)

双方向でない「見守る」の可能性
最後に、今回の鞍田さんのプレゼンテーションの応答先である『庭の話』の著者として、評論家/PLANETS編集長の宇野常寛が応答して締めくくりました。
「まず考えさせられたのは『受け止める』ということの問題です。『制作』も僕の人生にとって大きな要素ではあるのですが、一番はその手前で『受け止める』側の人なんですよ。元来オタクで、20代半ばまでろくに働かず、アニメを見たりゲームをしたりしていることに人生のほとんどを費やしていた。本当は受け止める側が好きな人間で、だからこそ、いまのコミュニケーション消費にはかなり抵抗があります。たとえばみんなが褒めている作品を自分も褒めて繋がって気持ちよくなる、といったコミュニケーションは、表現そのものに触れることが置き去りにされてしまっているような気がして、違和感が拭えない。だから今回の鞍田さんの話は、僕が引き戻ってきたところをもう一回ちゃんと直視しないとダメだよと言われた感覚があって、とても考えさせられました。
そして、『見守る』はとても良い概念だと思いました。『庭の話』では『制作』のハードルをいかにして下げるかということを考えたのですが、『見守る』ということ自体が『制作』の延長であるという考え方には大きな可能性を感じました。『庭の話』でも、田中さんのお仕事を紹介しながら動脈産業と静脈産業の話を出しましたが、同じように『制作』と『見守る』をセットとして捉える、言い換えれば『制作/見守り』という概念にアップデートするということが、この先にやっていくべきことなのだろうなと気付かされました。かつて柄谷行人は『教えるー学ぶ』の一方向的な、非対称のコミュニケーションだけが他者との対話なのだという話をしていましたが、自分からは返さず一方的に関わっている『見守る』という概念も、同じように使えるのではないかと思いました。
それは『庭の話』で虫とのコミュニケーションの比喩を用いた理由にも通じていると思います。僕が虫が好きなのは、要するに犬や猫のように擬人化できないからです。『ご飯だよ』と言ったら寄ってきたり、『ただいま』と言ったら玄関に迎えに来たり、抱っこしてほしいときは足にすがりついてきたりする犬や猫とは違って、虫は甘い匂いや蛍光灯の光に寄せられる程度のことしかやらないわけです。でも、僕はそのほうが他者性があって好きなんです。対話の可能性はゼロに近い、まったく違う環世界を生きている究極の他者だからこそ、非対称のコミュニケーションが発生する。言い換えればそれは『見守る』ことしかできない関係で、しかしそういった関係からしか生まれないものもあって、そういったものを大切にしていくことが必要なのではないかと思いました」(宇野)
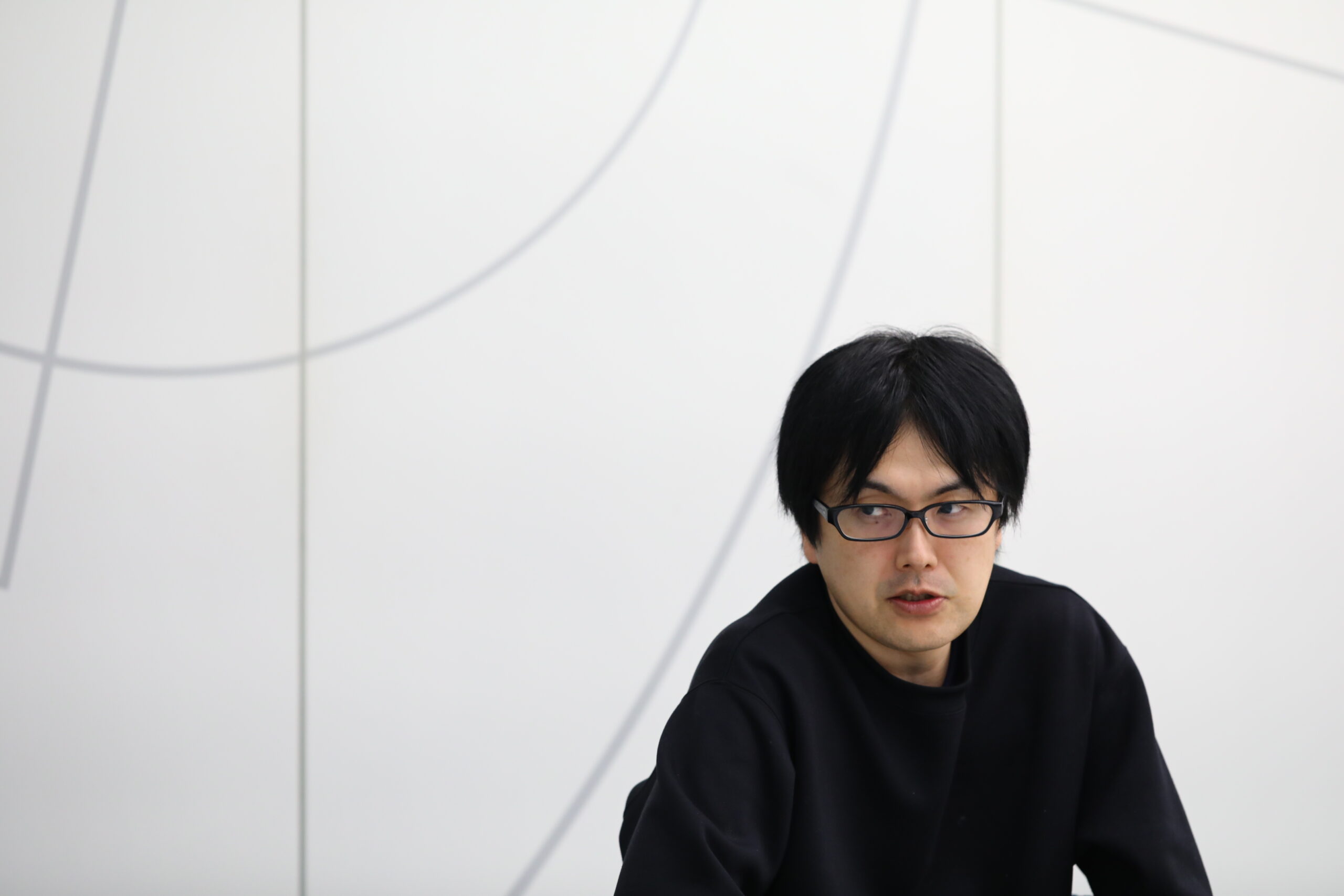
[了]
この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2025年3月27日に公開しました。Photos by 蜷川新。



