【刊行記念特別公開】「世界文学のアーキテクチャ」——はじめに:世界・小説・商品|福嶋亮大
批評家・福嶋亮大さんの新刊『世界文学のアーキテクチャ』の刊行を記念して、本書序章を特別公開します。18世紀以降「小説」が「世界文学」の中核を占めるようになる過程で何が起きていたのか。心的/社会事象を言語に変換するプログラムは資本主義に連動しながらいかに進化してきたのか。「世界文学」の起源を探り、その設計思想の変遷をひとつの物語として大胆に描き出します。
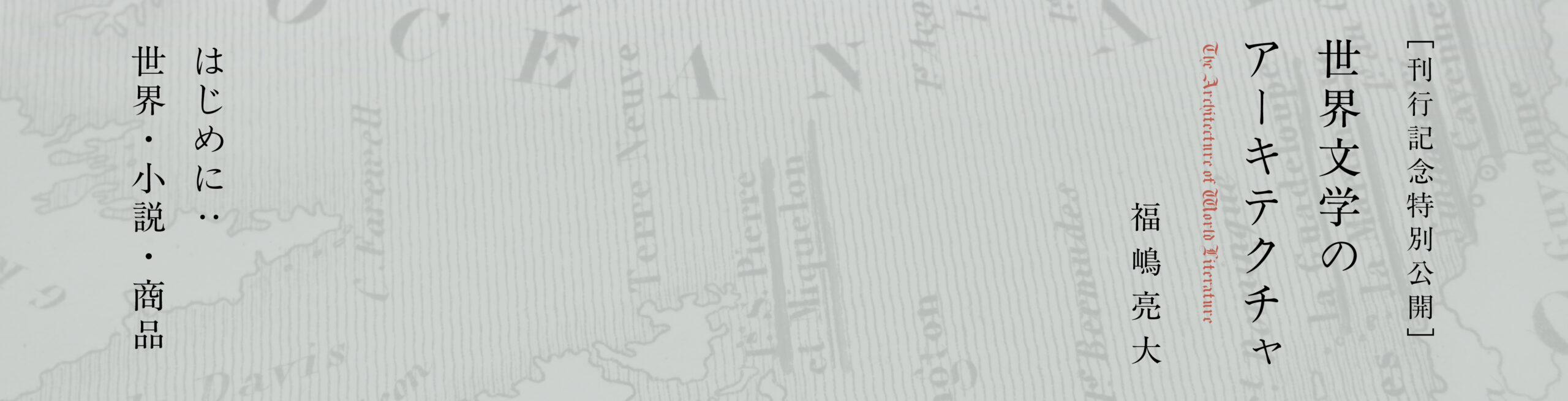
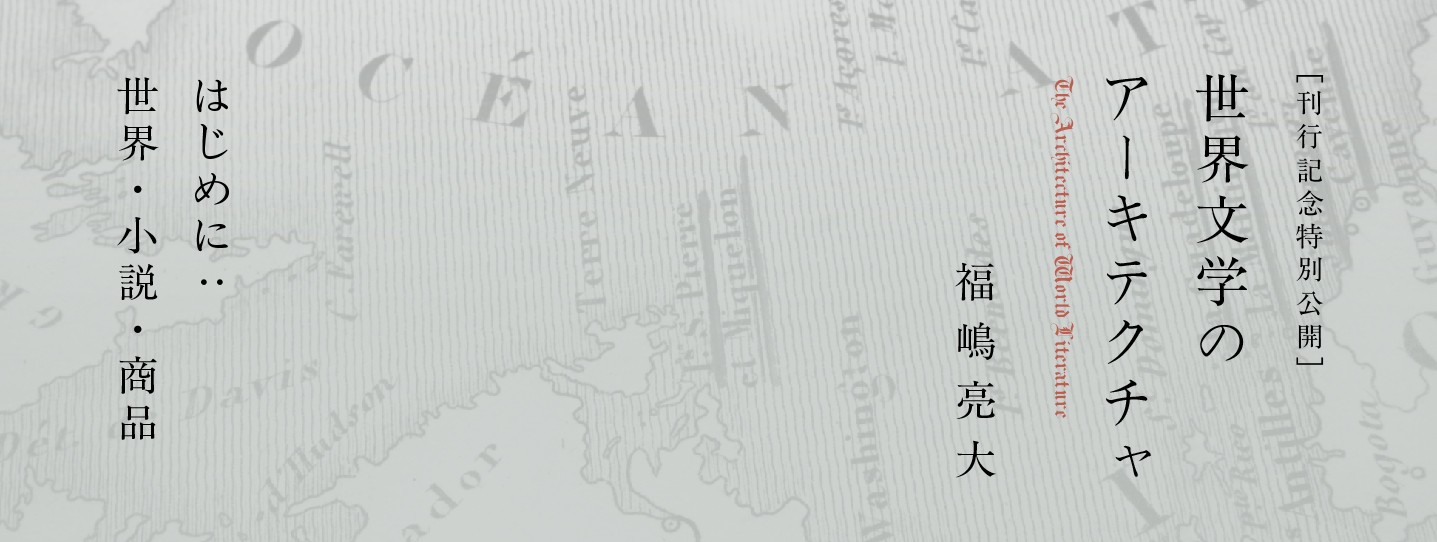 記事を読む
記事を読む

批評家・福嶋亮大さんの新刊『世界文学のアーキテクチャ』の刊行を記念して、本書序章を特別公開します。18世紀以降「小説」が「世界文学」の中核を占めるようになる過程で何が起きていたのか。心的/社会事象を言語に変換するプログラムは資本主義に連動しながらいかに進化してきたのか。「世界文学」の起源を探り、その設計思想の変遷をひとつの物語として大胆に描き出します。
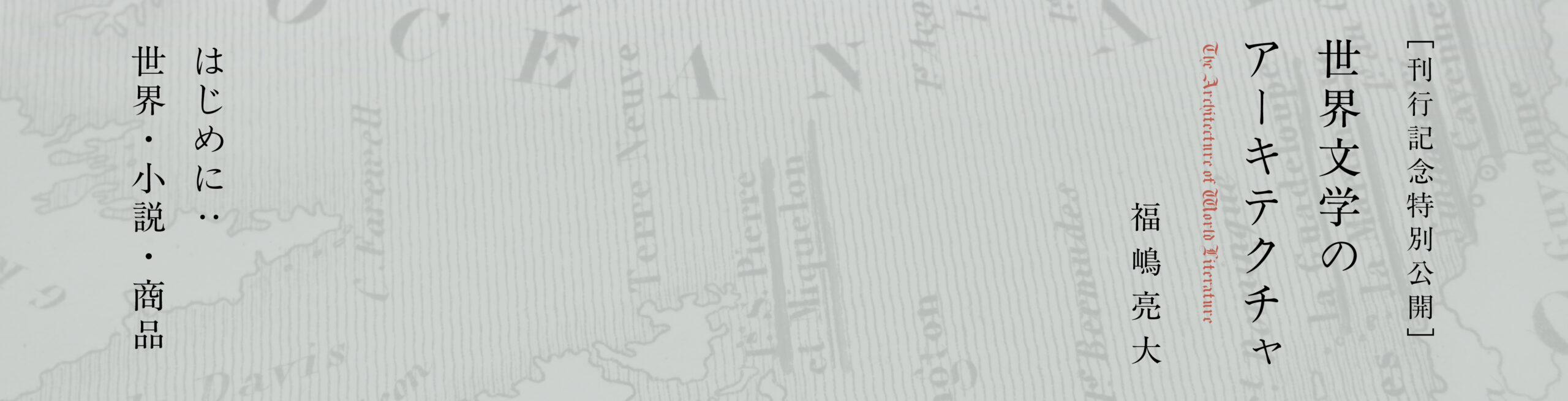
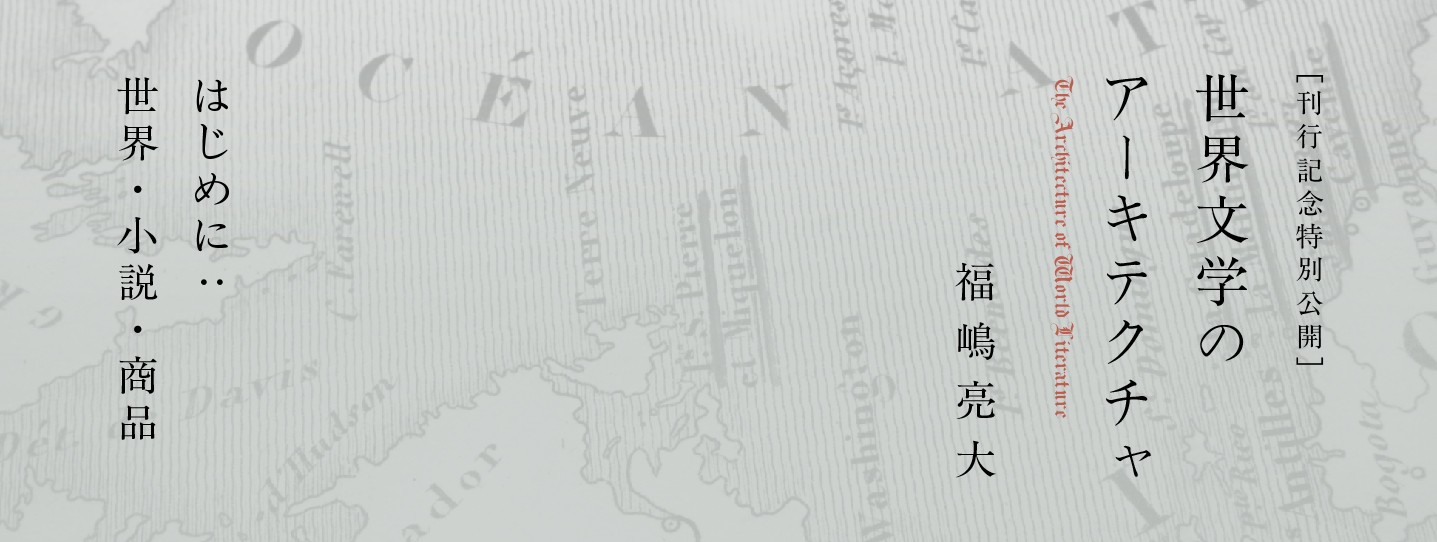 記事を読む
記事を読む編集長・宇野常寛の新刊『庭の話』が12月11日に刊行されます。「群像」で1年半連載したものを、丸1年かけてブラッシュアップしました。「たぶん、今までの僕の本の中で一番遠くまで行けた本だと思います」。『遅いインターネット』から4年、その続編であり(かなり変わったかたちでの)アップデート版です。
プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?
ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想します。
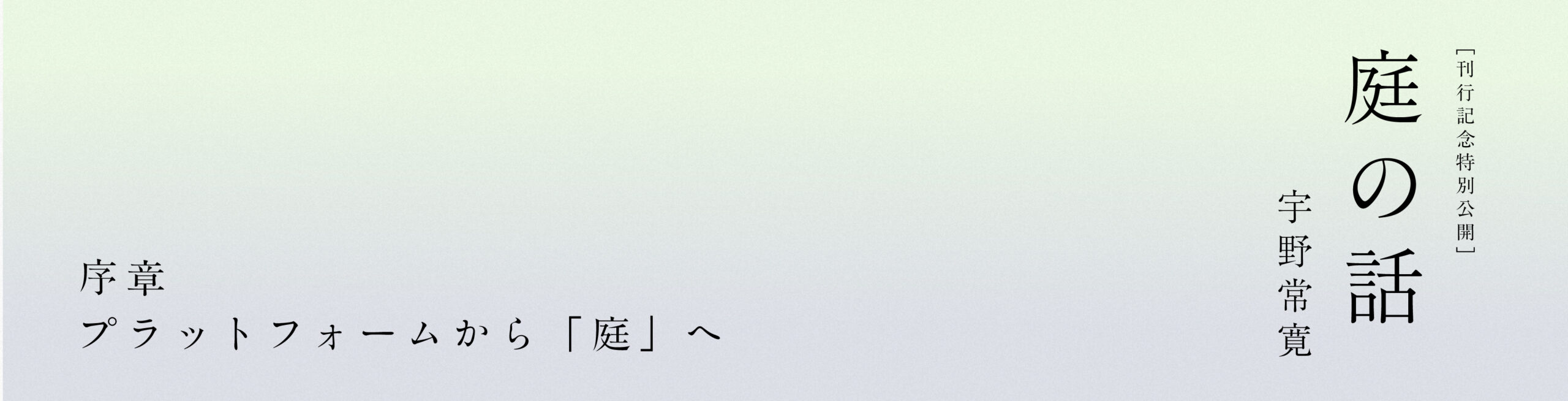
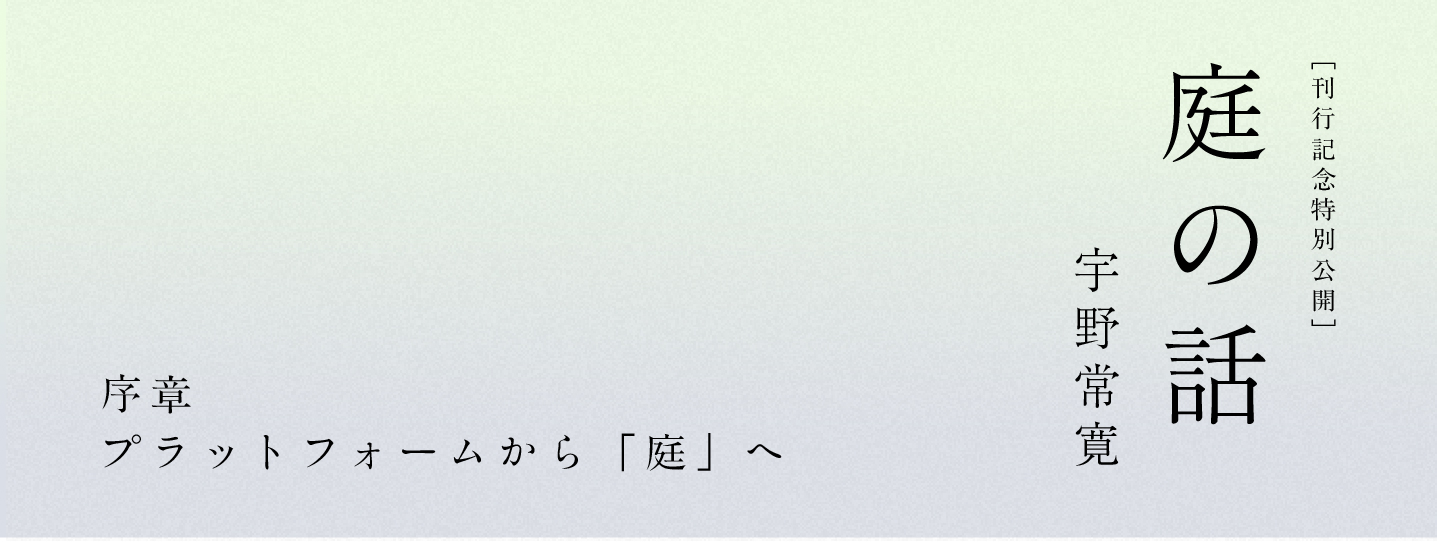 記事を読む
記事を読むいまやアジアの共通言語になっている「異世界転生」、そのストーリーテリングの本質を掘り下げます。
日本でのその隆盛の発信源となった「なろう系」の作品傾向で突出する、異世界で「2周目」の人生をやりたい放題に生きるという物語。たとえば2000年代には同じ人生を何十、何百周もやり直す「ループもの」が流行したのに対し、なぜ圧倒的に「2周目」なのか? ゲーム体験の掘り下げから、その疑問を分析します。

 記事を読む
記事を読むいまやアジアの共通言語になりつつある「異世界転生」ジャンル。その多くが「復讐劇」の形態をとる点はよく似ていますが、日本ではいじめられっ子が個人的動機から強者を見返すパターンが多い一方、中国・韓国ではそれぞれの社会の特質を反映し、復讐にまつわるモチベーションのあり方が大きく異なるようです。
今回はゲーム研究者の井上明人さんに、韓国・中国での「異世界転生」ものの方向性の違いを考察していただきました。

 記事を読む
記事を読む2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』の放送から10年。東日本大震災後の岩手県久慈市を舞台に、宮藤官九郎のオリジナル脚本による物語で社会現象的なブームを巻き起こした本作は、現在の朝ドラ隆盛を築いた歴史的名作として、現在も多くのファンに愛されています。ちょうど今年4月から本放送当時と同じタイムラインでの再放送もされていたさなかの秋、ロケ地・久慈では、大友良英スペシャルビッグバンド with のんによるコンサートをはじめ、10周年を記念する数々のファンイベントが行われました。
コロナ禍を経て久々に全国の『あまちゃん』ファンたちが結集したこの機会に、かつて文藝春秋×PLANETSのコラボ出版『あまちゃんメモリーズ』の副編集長を務めた中川大地も参加。そこでの旅路から持ち帰った本作のファンムーブメントにまつわるある思いを、10年越しの編集後記として綴ります。

 記事を読む
記事を読む村上春樹『街とその不確かな壁』の発売のタイミングで、僕が半年前に出版した『砂漠と異人たち』に掲載した村上春樹論を期間限定で全文公開します。『街とその不確かな壁』については、近いうちに批評文を発表する予定ですが、この合計約4万字のテキストは『街とその不確かな壁』の予習としても、おそらく多くの読者が頭を抱えるであろう同作を考える上でも大きな手がかりになるはずです。
そして、もし心に引っかかるものがあれば『砂漠と異人たち』の全文を読んでもらえたら嬉しいです。ここで指摘している村上春樹が乗り上げた巨大な暗礁から脱出する方法を、僕なりに考えて示しています。(宇野常寛)
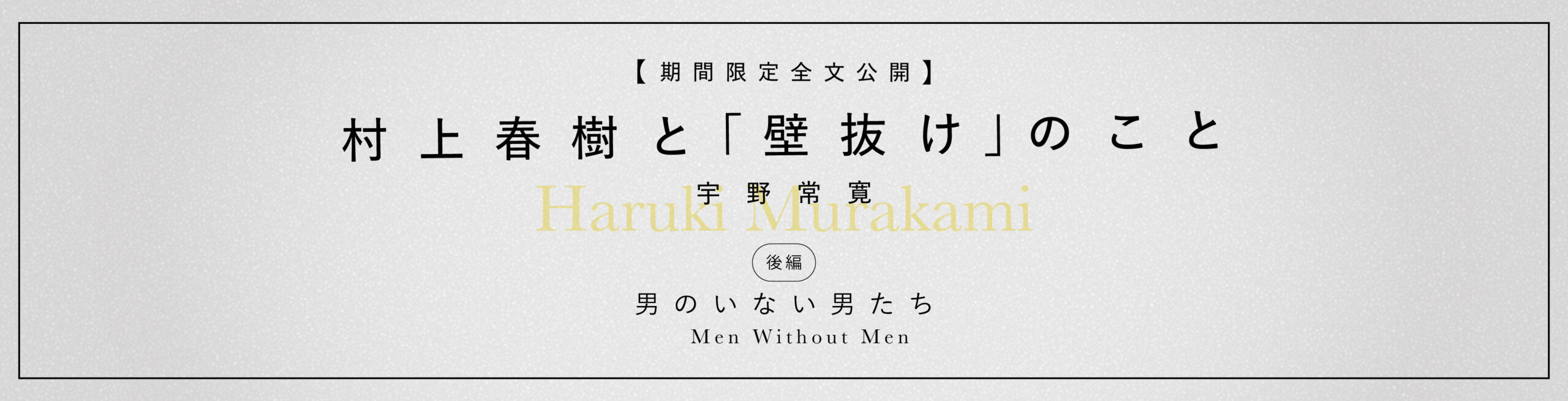
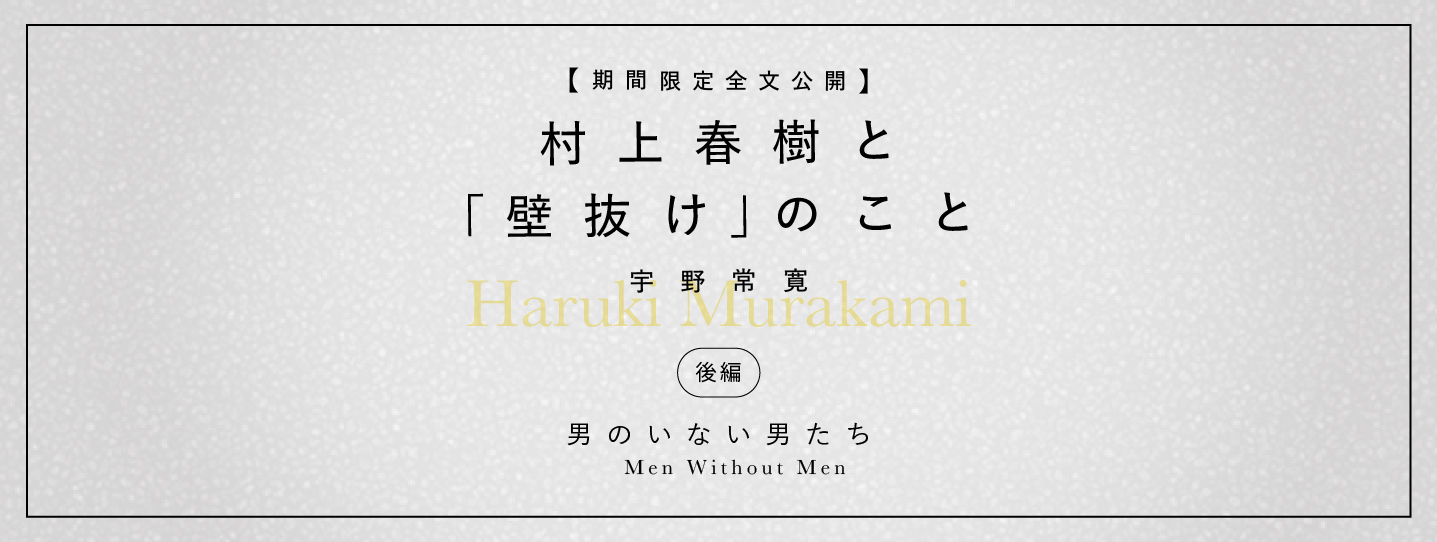 記事を読む
記事を読む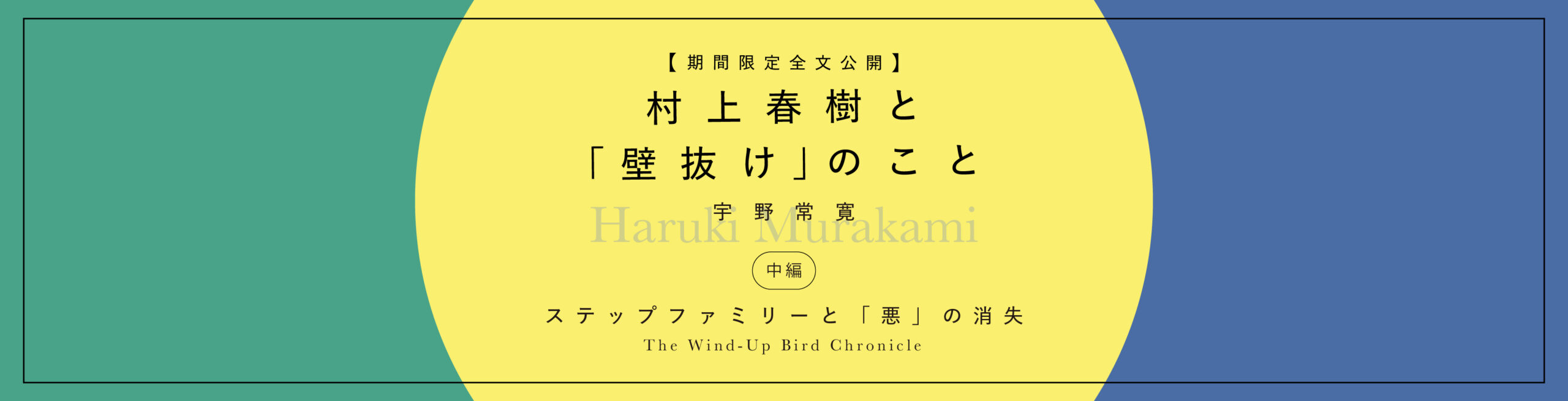
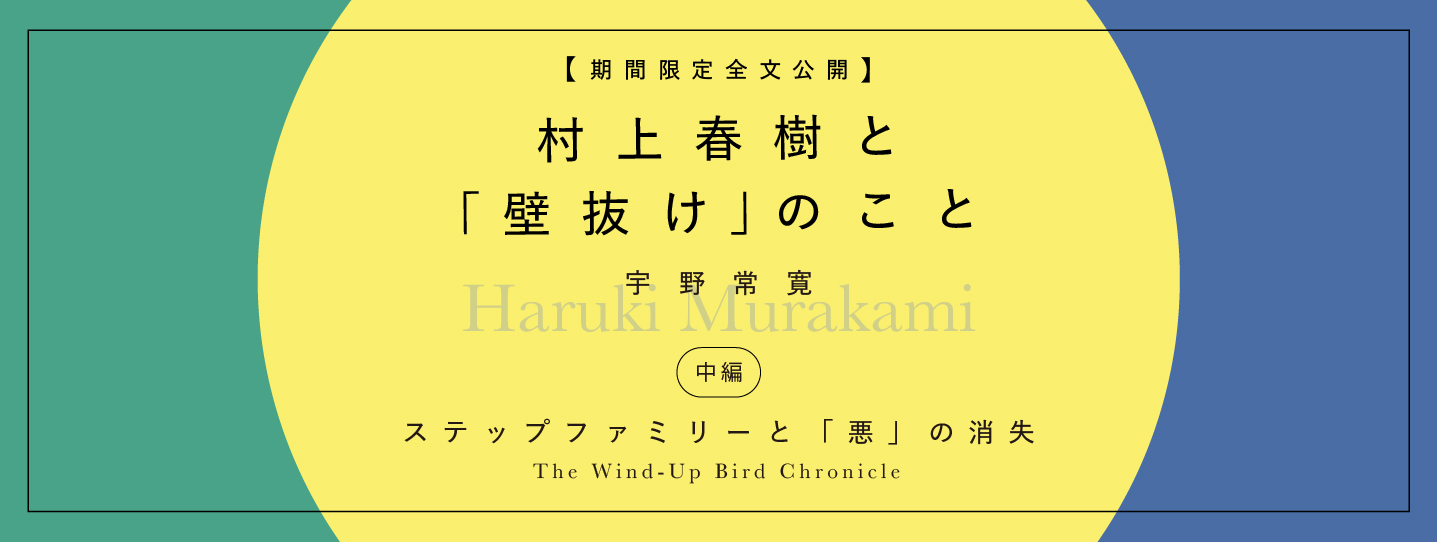 記事を読む
記事を読む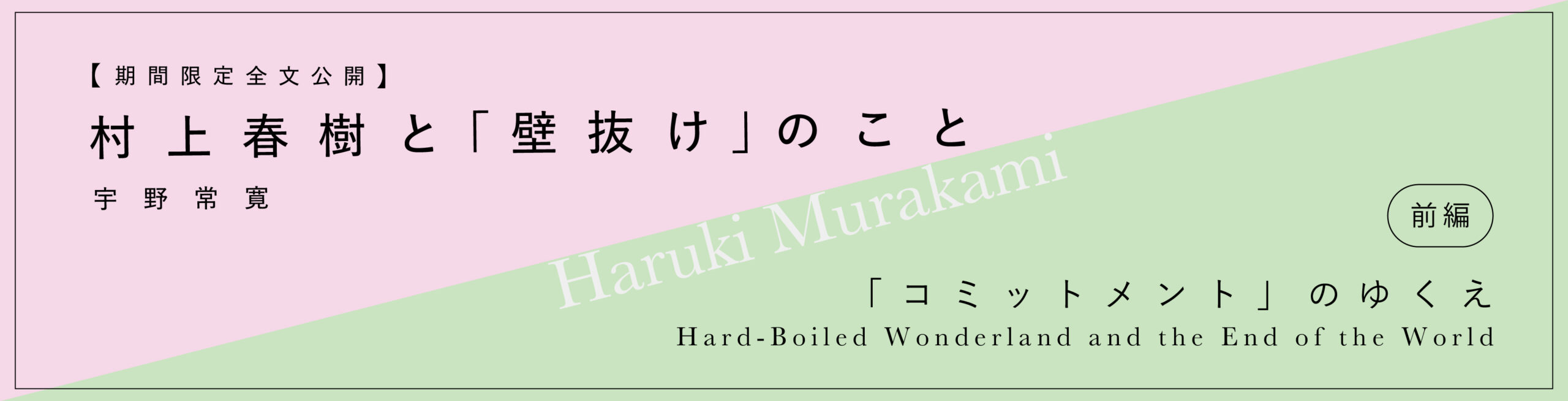
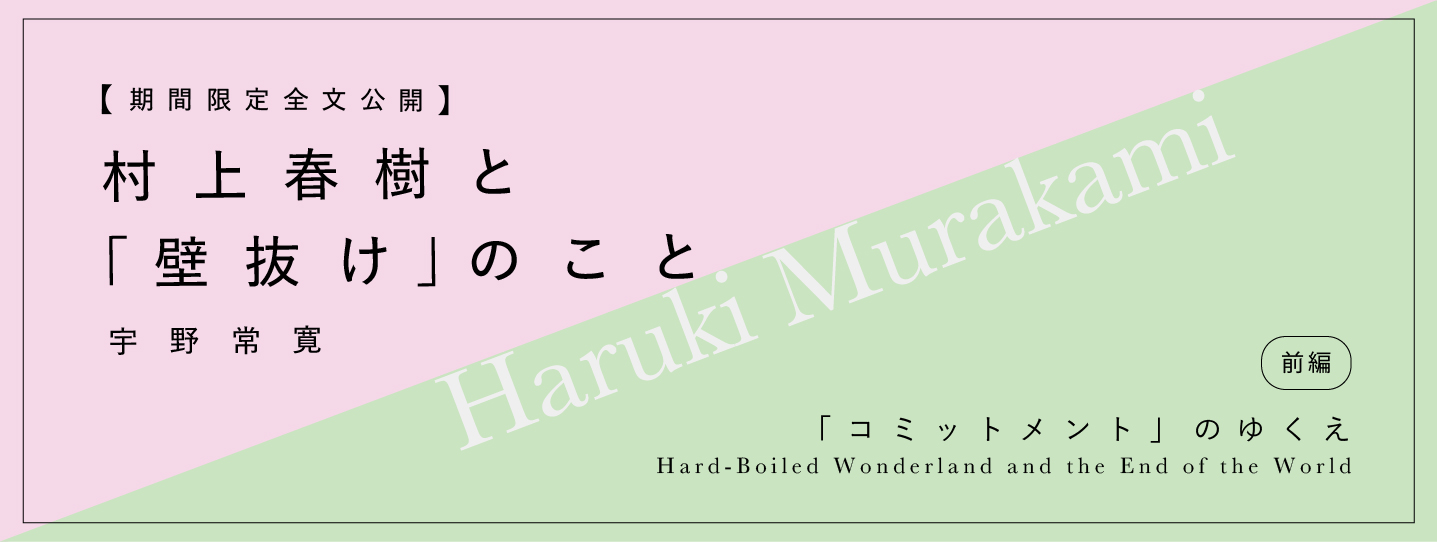 記事を読む
記事を読む21世紀以降の高級レストランでみられるようになった「現代料理」は、食材の生態系や採取地の文化を料理によって伝えるものとされています。今回は「現代料理」のフィールドワーク研究をおこなう文化人類学者・藤田周さんが、「食」を批評的にとらえるための足がかりについて論じました。

 記事を読む
記事を読むパンデミックによる決定的な社会システムの変容が引き起こされはじめていた、2020年2月。編集長・宇野常寛によるマニフェスト的な主著『遅いインターネット』(幻冬舎, 2020)が刊行されました。
それから約3年。疫病と戦争の時代を経た人類は、ますます「速く」なったインターネットに翻弄され続けています。なぜ人々は、プラットフォーム上の相互評価のゲームに抗えないのか? 『遅いインターネット』文庫化のこのタイミングで、パンデミックから3年間の情報環境の変化を踏まえた中間報告と、これからの対抗戦略を宇野が書きました。
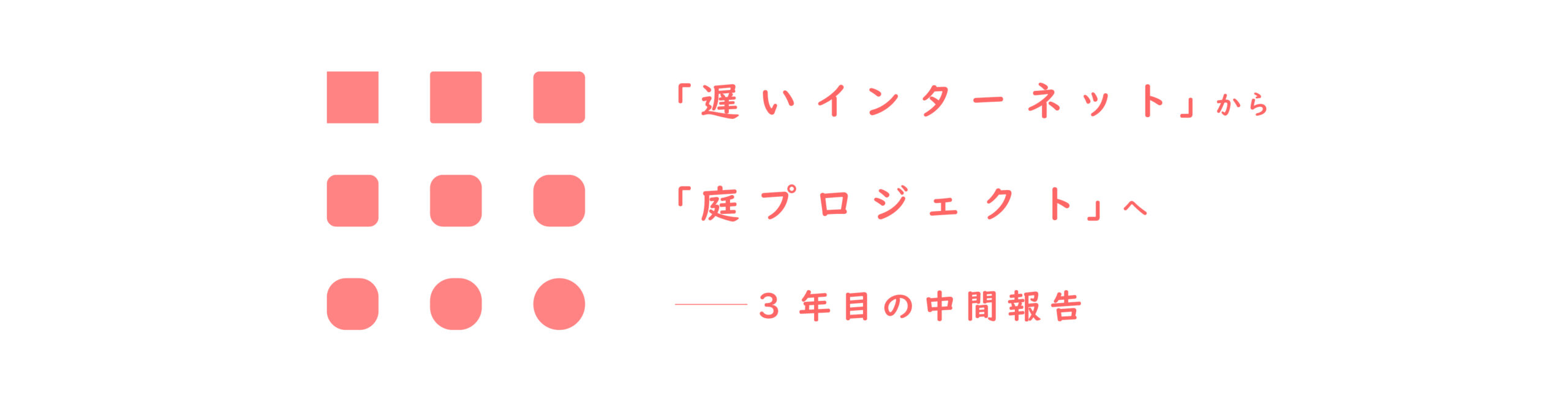
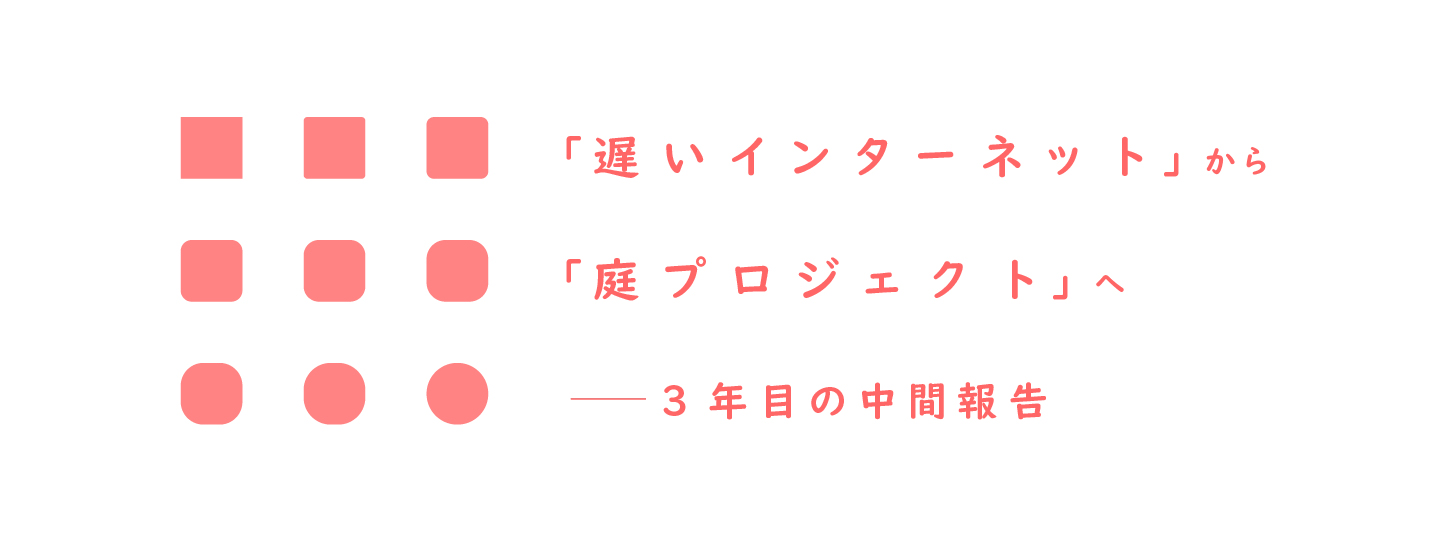 記事を読む
記事を読む2022年5月、編集長・宇野常寛の新刊『水曜日は働かない』(ホーム社)が刊行されました。水曜日が休みになると1年365日がすべて休日に隣接する──その真実に気づいた宇野は「急ぎすぎ」で「がんばりすぎ」なこの国の人々に提案します。「水曜日は働かない」べきなのだと。毎週水曜日を「自分を大切にするための時間」に充てることにした宇野の日常を綴ったこのエッセイ集の、最初の一章を特別公開します。
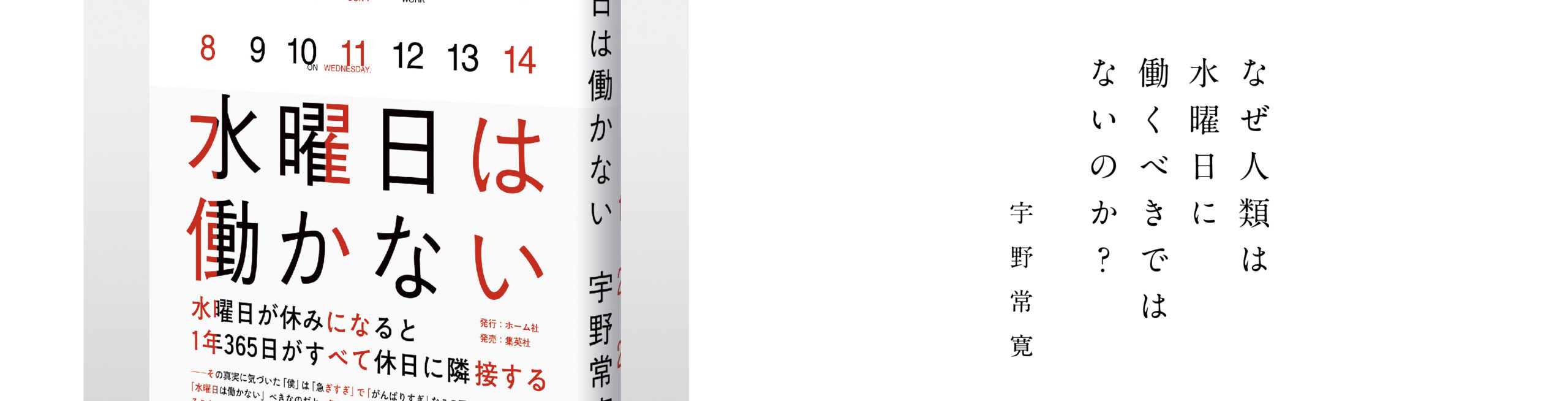
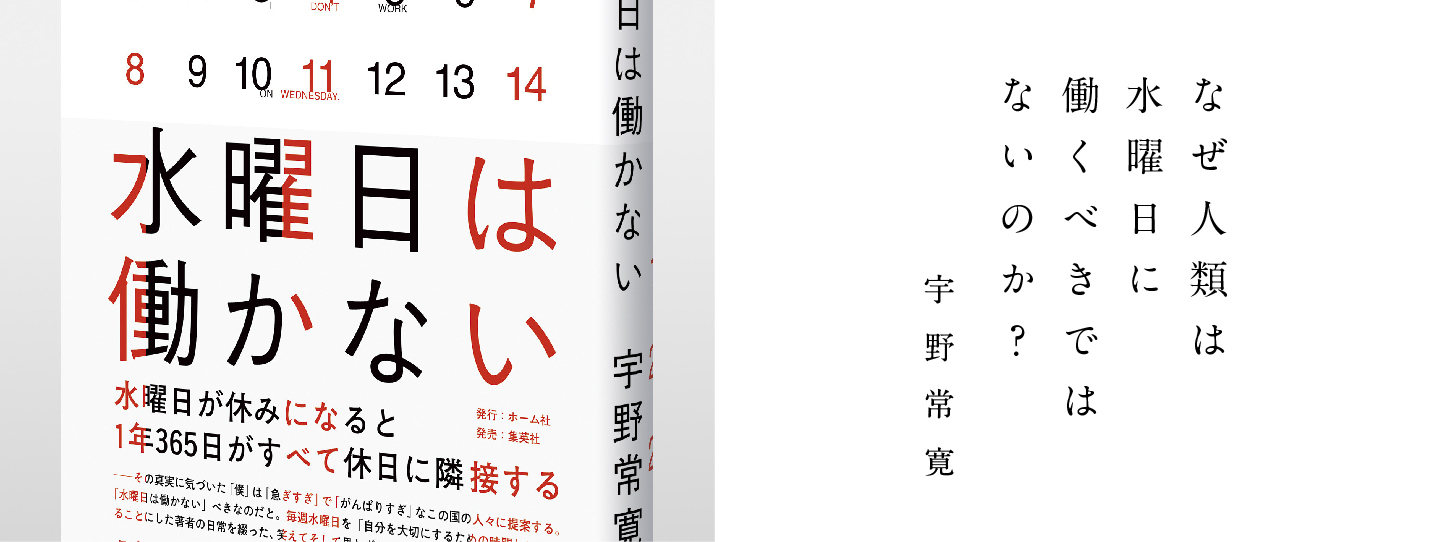 記事を読む
記事を読む近年人気を博している、何気ない「散歩動画」やゲーム実況動画はなぜ人々を夢中にさせるのか。人間の動機付けに介入する「ゲーミフィケーション」についての著書もある、ゲーム研究者の井上明人さんが、改めて「没入」を可能にする体験デザインとは何かを捉え直しました。
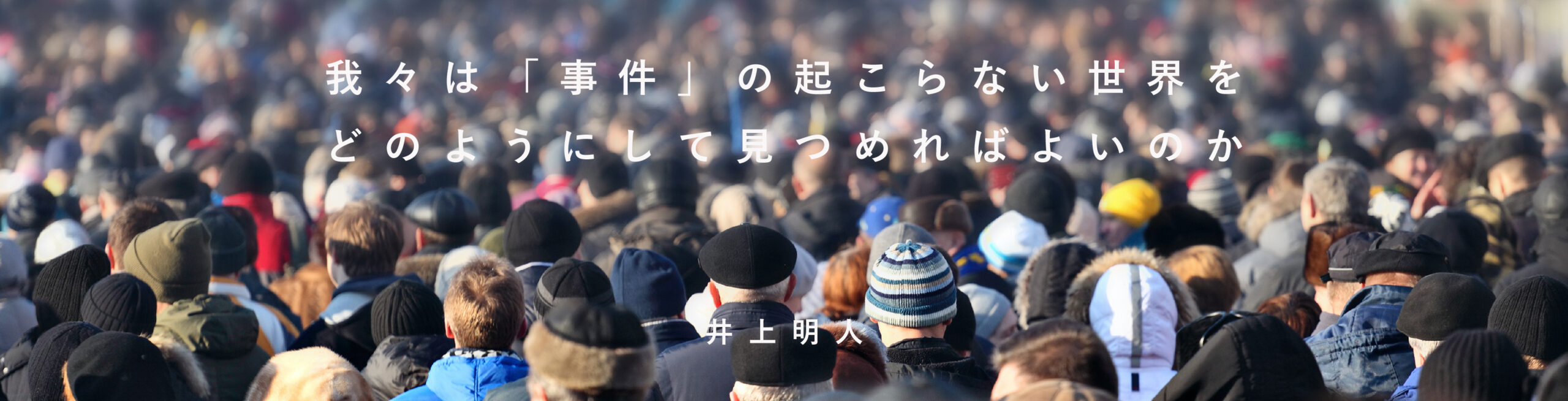
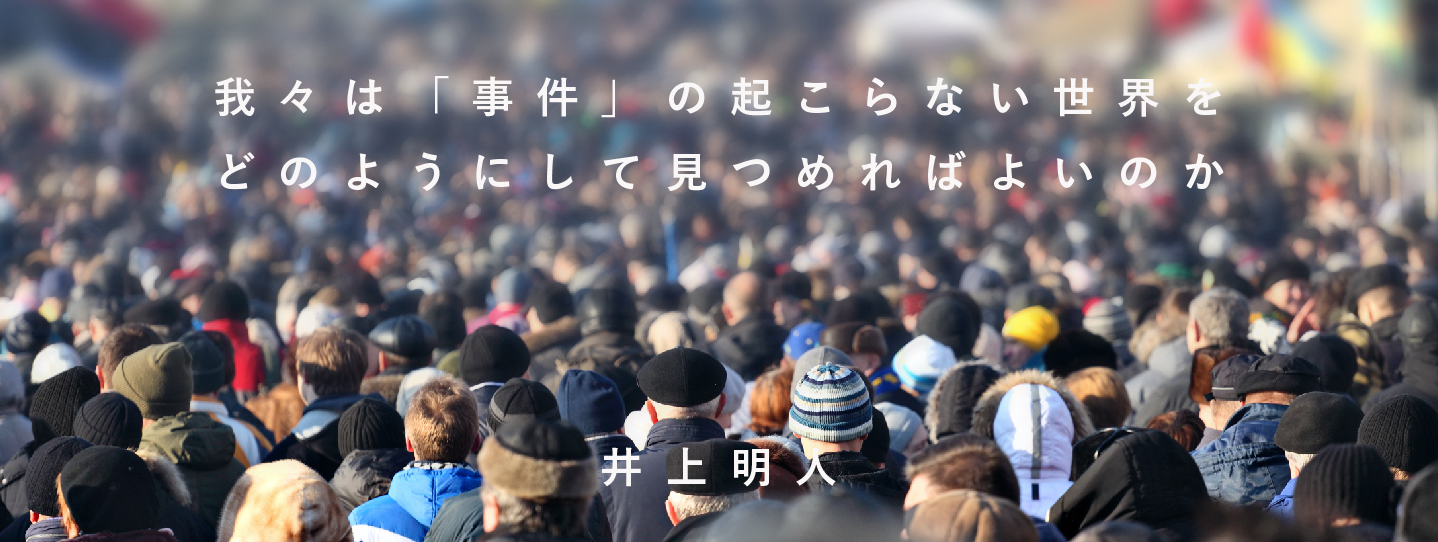 記事を読む
記事を読む