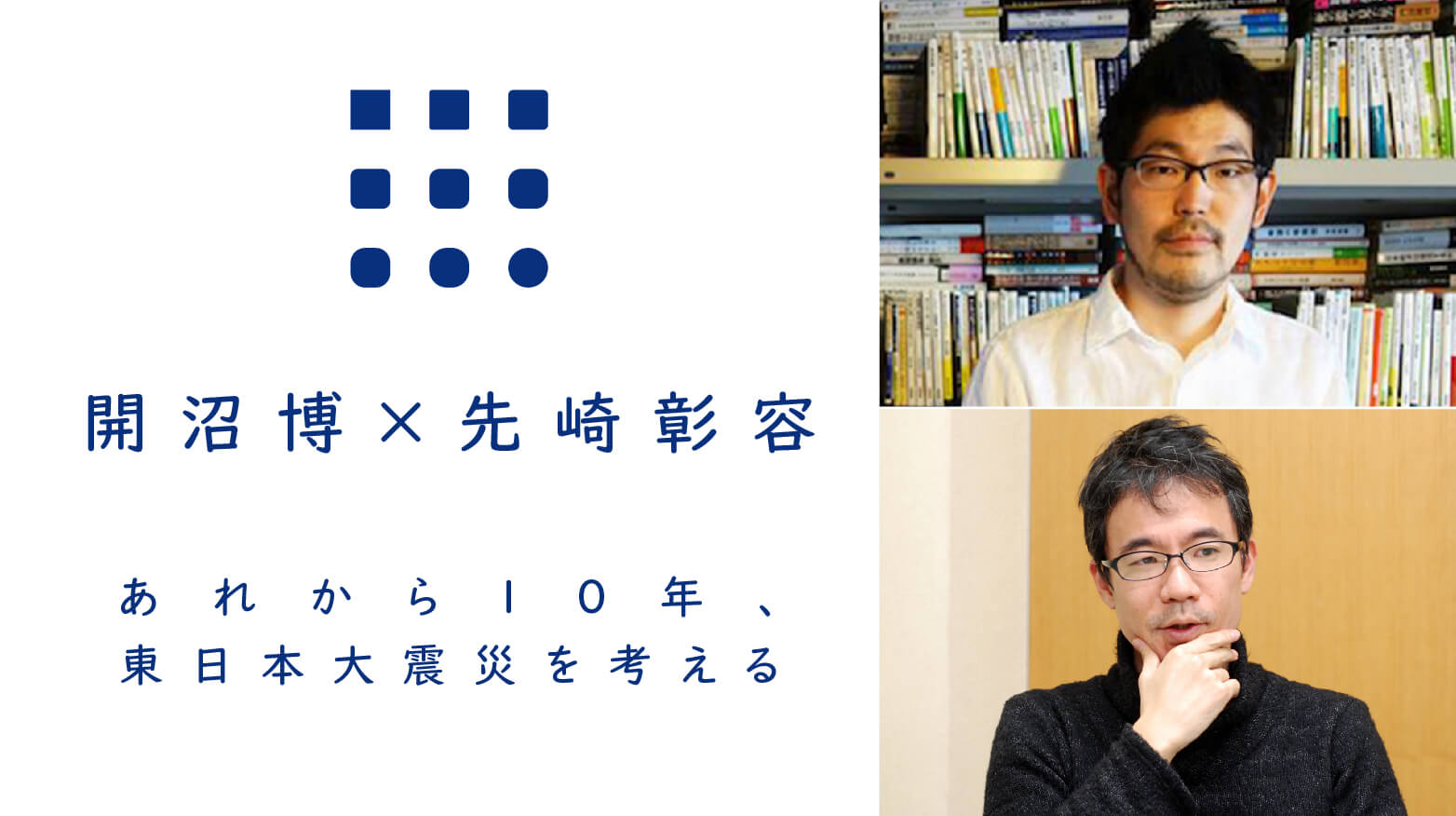2011年の東日本大震災から、10年の歳月が過ぎました。コロナ禍という現在進行中の危機に人々の意識が上書きされるなか、戦後日本の転換点だったはずの未曾有の災害の記憶と教訓を、私たちはどう自分事として今に活かすべきなのでしょうか。震災と原発事故がもたらした社会の変化に、社会学者として向き合い続けてきた開沼博さん、日本人にとっての思想の問題として引き受けてきた思想史研究者の先崎彰容さんをお迎えし、改めて考え直しました。
端的に言うとね。
危機が常態化し、人々は“饒舌”になった
先崎 私は現在は東京に住んでいますが、福島県いわき市で東日本大震災に遭い、その後5年ほど福島で暮らしていた経験があります。一人の被災者として個人的に体験したことを基盤に、思想史的な観点から少し抽象化しながら捉え直すというのが、日本思想史を専門とする私の役目だと理解しています。
その前提で震災当時からのことを振り返ると、この10年で「危機の常態化」という変化が生じたように思えます。熊本県と大分県で最大震度7を記録した2016年4月の熊本地震、北海道で最大震度7を記録した2018年9月の胆振東部地震、そして都心でも二子玉川駅や武蔵小杉駅に浸水をもたらした2019年10月の台風19号……そして言うまでもなく2021年現在、日本のみならず世界を覆っている新型コロナウイルスによるパンデミックと、本来は「非常事態」を意味するはずの危機が常態化してしまった時代になっているのではないでしょうか。
ただ、実はこうした状況は、日本の近現代史の中では決して珍しいものではありません。たとえば、戦前は1917年に第一次世界大戦が終わるや否や、1918年にスペイン風邪で大量の人がバタバタと死に、1923年には関東大震災が発生、そして太平洋戦争に突入していくわけですよね。そう考えると、大きな災厄が何もなかった10年間のほうが稀有なのであって、少し大げさな言い方になりますが、逆に1945年以降の数十年は、奇跡的に何も起こらずに済んだように見える時代とも捉えられる。もっとも、「ように見える」と留保したとおり、実際はいろいろとあったわけですが。たとえば、実は終戦から1年4ヶ月後の1946年12月に、西日本を中心に最大震度6を記録した南海道地震が起き、たくさんの人が津波に飲まれて亡くなっているんですよね。敗戦というのが衝撃的すぎて、その後話題にのぼることは少なくなってしまいましたが。
さはさりながら、やはり戦後というのは比較的何も起こらずに済んだ時代だったというのが、災害についても言えるだろうと思います。そしてこの10年で、そうした時代が終わりを告げた。「生きていることの方が稀有であって、世の中はしんどいものだ」という事態に向き合わなければいけないときに、中年を迎えているのが私なのかなという感じですよ。
開沼 おっしゃる通り、自然現象としての危機が連続して起こる時期になったと思います。地震もそうだし、気候危機的な話もそう。世界史を振り返れば、感染症だけを切り出しても、14世紀のペスト、16世紀の天然痘、19世紀のコレラと、危機の常態化の時期はあった。膨大な犠牲者が出て、社会の様々な分野に影響をあたえ、その痕跡は現代にも残っていたりもする。
しかし、そういう前提があっても、政策的・思想的な観点からは、具体的な危機に対応していくための準備を整えることができなかった10年、ともいえるのかなと。ここで深くは触れませんが、2010年代は「デモをやれば社会が変わる」という期待感から幕を開け、それは当初からの指摘があったとおりの明らかな失敗に終わり、その総括もされなかった。その中ではデマや陰謀論、自分の価値観を揺るがすものへのヘイトスピーチ、攻撃的言辞が渦巻いていた。2021年のいまとなって言えるのは、そののぼせ上がりの中で醸成されていたものは、後に世界の様々な場所で見られるものの先がけだったということです。つまり、たとえば、2020年の米国大統領選で注目されたQAnon的なものに象徴されるSNSとニセ科学とナイーブな被害者意識との現代社会的合作として、グローバルに様々な形で噴出している現象が、日本でも3.11がきっかけで先んじて顕れていただけだと評価できる。そんなことにかまけて、大きな方向転換もしないままに来る中で、危機の思想、あるいは危機に対する政策論が十分に練り上げられず、気づけば10年が過ぎてしまいました。
かなりペシミスティックで、アイロニカルな見方になってしまいましたね。でも、そう総括しないと、ここ数年で進んでいる“饒舌さ”中毒に取り込まれてしまう気がするんですよ。TwitterのつぶやきやFacebookのいいねというフォーマットなどに象徴されるような手触り感のある承認を求めて人々が饒舌になっていく不可逆な流れ。「で、その饒舌さから何が生まれたの?」というと、何も残っていない。危機が常態化しているのにもかかわらず。
システム化の波に飲まれ、消えゆく「友情」
先崎 非常に強い政府批判がなされるようになったことにも、饒舌さが関係していますよね。東日本大震災のときもそうでしたが、コロナ禍において、政府批判はさらに激しさを増しています。でも、私は「現金給付が遅い」のような政府批判ばかりをするのは、ちょっとおかしいのではないかと思っています。「お前は保守派だから政府擁護なのだろう」と思われるかもしれませんが、そういうことが言いたいわけでは全くありません。要するに、私たちは政府という、大きいといえば大きいものを批判することに精力を傾けている一方で、実は傍らにいる人に対する興味関心を急速に失っているのではないか。
東日本大震災の直後、私は福島県から、妹の嫁ぎ先である埼玉県北部に自主避難したんですね。そこで妹のご主人の実家が、200年くらい酒の問屋を営んでいます。もともと地元の名士だったその家も、量販店ができてからは完全にしぼんでいるわけです。そして、そのご友人がやっている灯油屋さんも、地元に昔からあるものの、より安価な巨大ショッピングモール系の量販店ができてからは、風前の灯です。ただ、友達同士だから、お互いにずっと酒や灯油を売り買いしあっていたんですよ。
そうした状況下で東日本大震災が起きて、どうなったか。量販店からはすぐに消えてしまったガソリンを求めて、その灯油屋さんに車の長蛇の列ができた。量販店が安い理由は、在庫をストックする倉庫を持たないから。それに対して地元の灯油屋さんは、量販店より1リットルあたり5円くらい高いのですが、ある程度のストックを持っていた。そして、その灯油屋さんはいつものように、私の妹のご主人に優先的にガソリンをあげたんですよ。すると、「何でそいつに優先的に渡すんだ!」と怒鳴り散らしている人たちが出てきた。ここに図らずも、大げさにいえば、戦後日本人の類型が出てきていると私は思った。
経済的な合理性を優先するという価値観にもとづくならば、5円でも安い方がいいんですよ。だけどそれは、脆弱な社会を作っているということでもある。非常事態のときに隣のやつと貸し借りをするとか、隣のやつから融通してもらうとか、そういう小さなコミュニティみたいなものを作ることを忘れる、ということです。一番安いところに行って買えばいいというのは、究極の個人主義なんですよ。だけど、私の親戚筋というのはそうではなく、1リットルあたり5円高いものを貸し借りしていたわけです。そこには、オークショットという思想家が「友情」と名づけているもの、つまり時間の積み重なりに伴う、人間関係の担保があった。その結果、非常事態のときには死なないで済んだ、簡単にいえば、生き延びたわけです。
東日本大震災にせよコロナ禍にせよ、饒舌に政府批判ばかりしている人たちは、私たちが不安に駆られたときにそれを安定化させる「友情」、つまり時間の積み重なりみたいなものを、おそらく一切合切失ってきたんですよね。ガーッと政府批判するのは構わないのですが、それより先に私たちは、人間について語るならやらなきゃいけないことがあるはず。あの友達の店はコロナ禍で店が閉まり続けているけど、食っていけているのか。あいつの家は津波でやられていないけど、大丈夫なんだろうか。津波でやられて食っていけなくなっているあいつの魚屋は、いつ復活できるのか。いつの間にか、思考の中からそういうことをどんどん失ってきてしまったのではないでしょうか。人間がただ単に不安を怒鳴り散らす相手になり、きちんとした意味での相互コミュニケーションが取れていない社会になってしまった。それがより顕在化しているのだろうなというのが、震災やコロナ禍に際して思ったことですね。
開沼 おっしゃることは、社会学的にいえば、ハーバーマスの言う「生活世界」と「システム」の区別の話ですね。言うまでもなく、近代化が進むとありとあらゆるものがシステム化していく。手触り感がある具体的な隣人ではなく、インターネット上の記号的・抽象的な悪役や政治家にリプライを飛ばすようになる。そうして因縁をつければ、「自分は政治家に勝ったぞ」と勘違いができる。そういう脊椎反射的な欲求を満たすのに最適化されたシステムが発達していくと。その流れに完全に抗うことは無理ですし、もちろんシステム化は危機がなくても進んでいたと思いますが、危機がさらにそれを加速させてしまっていることは間違いない。
ただ、たとえば東日本大震災の後に、ランドスケープデザイナーの山崎亮によるコミュニティデザイン的な視点や、藻谷浩介の里山資本主義が流行ったのは、システム的なものの脆弱さに気づいたことの表れだったはず。でもそれは、政策的な“地方創生”の動きが大きくなる中で、衰退していった。「関係人口」や「稼いで地域をどうしました」といった話もちょくちょく出てきますが、圧倒的なシステム化の波には勝てないですよね。
そうした状況下で、もっと中間集団や生活世界に目を向けないといけないということを、私はいろんなところで書いてきた。ただ、みんながついてくるとは自分でも到底信じられず、諦めて書いているところはあります。これからも書くとは思うけれど、自分の周りで気づいてくれる人が気づいてくれればな、くらいの気持ちですかね。

2010年代の地方創生トレンド、昭和10年代の日本浪漫派
先崎 よくわかります。手触り感のある小さなコミュニティが、システム化に完全に回収され、消費されているわけですよね。
開沼 ただし、違う風景が例外的に見えるところがある。それは被災地です。最近は被災地の中でも、システム化に回収されない野生の何かが渦巻いている部分がある。私は震災後の最初の5年は、あまり被災地にコミットする気はありませんでした。仕事としてはいろいろやっていたし、客観的にはコミットしているように見えるかもしれませんが。他方、ここ数年は明らかに、主観的にもコミット度合いを強めている。
なぜかといえば、衰退していく日本の中で、復興予算が福島以外も含めて30兆円、廃炉関係予算が主に福島向けて20兆円集まってきている。これは、現場にいても多くの人は気づかないが、現代先進国にまれに見る一つの盛り場感がある。賠償金詐欺のような話とか、除染でトラブルが起こっているとか、あるいはそれを報じる側にも「一発当ててやろう」という下心がある有象無象が集まってくるし、ニセ科学と陰謀論を携えて経済的・政治的利権を探ろうとしがみつく人間も消えない。盛り場だからこその人間の生々しさが見える。ただし、これが何もリソースないところにだと、無いわけです。そして、被災地のような例外を除いて、日本の多くの地域には兆規模の資金が流れることは未来永劫ないらしい。結局システムに取り込まれてつまらないものしか見えない現実ばかりが立ち上がっている。
先崎 それについては、思想の歴史を振り返ると面白いことを言えると思っています。昭和10年代頃に活躍した萩原朔太郎という詩人が、こんなことを書いていまして。〈所で現代の青年やインテリゲンチアが、丁度またその通りである。彼等の多くは、時代的に去勢されて無気力者となり、何の反抗もなく気概もなく、町の卑猥な流行歌を聞きながら、ひとへにエロチシズムの刺戟を追求し、麻雀やダンスに当なきその日ぐらしをして居るのである〉。これ、昭和10年代の話なんです。
私が研究者として最初に勉強したのは、この昭和10年代の萩原朔太郎が所属していた日本浪漫派というグループなんですよ。このグループの特徴は、マルクス主義が昭和9年から10年にかけて退潮して知識人の間から「もう駄目だ」と言われ、社会は変えられないという無気力感の中で戦争に向かっていく時代に、ものを書いていたということ。社会を変えることはできないという感覚が非常に強かった20代の私には、自分の世代は彼らと同じなのではないか、という直感がありました。
一方で、この昭和10年代というのは実は改革の時代でもあって。これは橋川文三などの政治思想史家が書いていますが、たとえば革新官僚と呼ばれる岸信介のような人が、どうにかして日本社会を変えようとして、国家社会主義政策に近いことをやっていった。あともう一つあるのは、農本主義。日本は都市化してきたから農業へ回帰せよ、という改革案のようなものをもとに、地方に戻っていく人がいたんですね。そういうのが、20代の頃の私にはきわめて魅力的で。実は私も、大学院なんてとっとと辞めてIターンし、有機栽培の農業でもやろうかなというふうに、真剣に考えた時期もあったんですよ。
この10年間の、若者のある意味の改革派による地方コミュニティへの入り込み方は、たぶん20代の頃の私の気分と同じだと思うんです。勝手に憧れを持ったうえでの、農業回帰という気分。要するに、地方を変えていこうと言ったときに、それ自体が一つのロマンチシズムに彩られて、しかもそれを資本主義にうまい具合に回収されている、という印象を持っています。
開沼 そうですね。2010年代における若者の農業志向は、1970年前後に学生運動の季節が終わって有機農業とか自然との共生に移っていったのとも通底するものはある。わかりやすい反復の構図です。だとすれば、また違った時代感覚が世を覆うときも来るのかもしれない。たとえば、いまから10年後を想定したときに、振り子は変わっているのか。なかなか見えないけれど、この潮流はあまり持続しないと思うので、変わっている気もしますね。そのときに、さらにもうちょっと過激なところにいくのか、より虚無な何かにいくのか。
先崎 より過激になろうとする流れは、原発の後のデモも当てはまるでしょう。ただ私はどちらかといえば、よりペシミスティックな日本浪漫派に共感してしまうんですよね。彼らが言っていたことは、こうです。社会改革は絶対できない、デカダンスを生きているんだ。では何で変えられるかといえば、文学という言葉の世界なんだと。そうして彼らは日本の古典に回帰する文学運動による、ある種の革命運動に入った。
ちなみに、その影響を大きく受けた寵児として2000年頃に出てきたのが、我々より15年ぐらい年上の、当時30代だった福田和也ですよ。彼がハイデガーなどを使いながら、日本浪漫派の保田與重郎を読むことによって、「俺たちの時代はあの時代と同じなんだ」と書いて登場してきたのが、いまから20年前ぐらいの状況です。それを踏まえたうえで、いまの社会をどう考えたらいいのか、ということですね。
バブル期からコロナまで繰り返される、地方創生の失敗
先崎 でも、2010年代の地方創生の問題は、バブル期からいまの菅政権にまでつながる問題だという気がしていて。菅さんが総裁選に立候補したときに文藝春秋で語っていた言葉の中で、私が一番びっくりしたのが、「出稼ぎのない世の中を作りたい」というキャッチフレーズです。昭和ではなく、この令和の時代にですよ。梶山静六のもとで、ソフトタッチな原発政策をやり続けてきた彼がやってきた政策は、実は原発問題と構造が同じなんです。ふるさと納税は典型的にそうだし、新型コロナウイルス対策で自治体に3000万円の“コロナ交付金”を配ったのも、バブルの頃に「ふるさと創生事業」として各自治体に1億円を配ったのとほぼ同じ。海外から旅行者を呼ぼうというインバウンド政策も、東京が潤うことではなく、地方の隅々にまで外国人観光客に金を落としてもらうことが目指されたじゃないですか。
国が音頭を取って地方創生を進めようとした結果、何が生まれたか。たとえば、ふるさと創生事業のときには、北海道下川町で万里の長城のミニチュア版が作られたり、北海道伊達市で道の駅にピアノが鳴る大理石のトイレができたり。そして今回のコロナ交付金では、公園の鉄板で作られた表示を全部取り替えて、そこに「コロナだから近づかないにしましょう」と書くとかね。地方の復興のあり方は、やはり非常に難しい。国がアプローチすると、こうした笑いごとのようなことが起きるし、だからといって若い人を中心に手触りのある小さなコミュニティを作っていっても、先ほど話したように、ロマンティシズムと資本主義に回収されてしまう。
開沼 はい、本当におっしゃる通りで。90年代、00年代にあれだけ箱物行政はダメだと目の敵にしていたのに、平時には入らない復興予算を得た被災地は結局、箱物だらけになっている。それ自体がダメだとは言わないが、逡巡はないのかと。あいちトリエンナーレの問題も、根本にあるのはスケールダウンした現代風の箱物行政の矛盾。300億円で立派な美術館を作れば文化政策の実績を作れたねと体裁を整えていたのを、ゼロの数を減らしてやっている。最初はみんな良いねと言っていても、公共事業である以上、途中で利権化していく。そこに気づいて寄ってくる人間、逆に自分は蔑ろにされたと潰しにかかる人間。思惑がうずまきヘゲモニー争いで混乱していく。もちろん、身の丈にあった形でも素晴らしいアートプロジェクトをやっているところもあります。ただ、もう国内の大都市が猫も杓子もアートで地域に盛り上がりをとパッケージ化されてしまい、まさにシステムと共犯関係を結ぶようになってしまった。一連のパッケージが地域に新風を吹き込んだとか、田舎らしさや地元らしさだという話になってしまっている。グローバリズムと情報化の中で、地元らしさをでっち上げようとしているだけになっているだけなのだとすれば、それって何の意味があるんですかということは問われざるをえない。
先崎 さっき言った地方創生1億円の話以来、変わっていないと私は思うわけですよ。ばらまいた1億円で万里の長城のミニチュアを作るぐらいの発想しか出てこなかったのと同じことを、箱物でやっているわけです。コロナ交付金の話も同じです。
だから一言で締めくくると、やっぱり東京と光ですよ。地方が一番欲しいものって、たぶんスターバックスとかなんですよ実は。箱物を作ったときも、その中に何を入れるかといえば、見たこともないようなアーティストだったり、“東京のあの有名な人”が作った何かだったりする。やっぱりね、2000年の大規模小売店舗法の廃止は大きくて、地方はスタバが欲しいし、イオンモールができると楽しいということになった。それがたぶん、20~30年後には悲惨なかたちになる。東京で言えば団地とかニュータウンがオールドタウンになるように、さびれていくのでしょう。大学も同じで、十数億円という復興金がばらまかれたんですね。そうすると全壊した建物を建て替えるときに、一つの研究室に机が3台受注されたり、トイレがやたらと高級だったり、もう国の金だからとどんぶり勘定でむちゃくちゃな使い方をされてきた。
でも、ちょっと情緒的ですが、私はそういうのを見たときに、坂口安吾をはじめとした小説家が戦後のどさくさを描いたような作品を、非常にリアリティを感じながら読めました。人間というのが全く美しい生き物ではなく、善と悪を両方を飲み下しているということ。高校野球に感動することと、復興金に飛びつくことが、同一人格で容易に起こるということを見せつけられた。開沼さんがさっき言っていた人間の生々しい面白さと同じで、これこそが悲喜こもごもだと思いましたね。
開沼 じゃあどうすればいいのか、というところがわからない。箱物を作る、東京のアーティストが来てくれてなんかを残していく、よそ者・若者を呼んで一緒にコミュニティデザインをする。そういうことはやり尽くしました。10年前は「これは実験的な試みだから、そこから発展するはずだ」と言っていましたが、結局何が生まれたのか。ミクロに生まれたものがあることは当然だが、マクロに見て大きな変化の兆しがあるのか。全部実験段階で終わって、これから30年は超高齢化社会に向かっていくだけということでは、よろしくないですよね。

ショッピングモールがもたらす自己肯定感
先崎 地方のあるべき姿を考えていくうえで、自己肯定感というのは非常に大事だと思うんですよ。2020年、福島県の富岡町に行ってきました。街の中心部には、ツルハドラッグなどが入っている、さくらとみおかモールという場所がある。それから、警戒区域の中にあってずっと震災時から時が止まっていたけど、解体工事が少しずつ進められている「回転寿しアトム」もあった。あともう一つ出すとすれば、東京電力廃炉資料館にも行ってきました。これは、もともと福島第二原子力発電所のPR施設として富岡町に開設されていた「エネルギー館」の建物をそのまま流用しているのですが、アインシュタイン、キュリー夫人、エジソンの生家をがっちゃんこした建物なんですよ。要するに、未来を明るくするものとして作られたエネルギー館が、いろんなことがあって、いまは廃炉資料館になっているということです。
資料館の人に取材したときに出てきたキーワードの、一つ目が「出稼ぎ」。やはり、非常に大きな問題だったんだと。その人も高校を卒業した後、事務職員として原発に勤められて、「地元で安定した職業に就いた」と喜ばれた経験があるそうです。それからもう一つは、ボールプール。この中に昔、子どもを遊ばせるボールプールがあったんですよ。日曜日になるとここに来て子どもを遊ばせていた。表の庭では時々ヨーヨー釣り大会が開催されるコミュニティができていて、周辺にちょっとモノを売る所もあった。
出稼ぎとボールプール。この二つがもたらす生活実感や自己肯定感を批判することは、なかなか難しいですよ。要は、地方の自己肯定感を高める方法が、中央からの金による原発しかなかったということでしょう。地方のオンリーワンの個性を作れなかったわけです。ふるさと納税一つ取っても、みんな同じような炬燵や炊飯器を出しているわけですから、ただの競争原理を作っちゃっただけですよ。「個性を出す」ということはお題目にすぎず、金のない自治体がみんな金欲しさに競争して右往左往し、その成功したモデルだけがメディアで取り上げられるわけですよね。これが持つ構造的なしんどさを、どうしたらいいのでしょうか。地方を生かすということは、要するに東京化することだという状況が、残念ながらいまだに続いてしまっている。
開沼 いま被災地で震災伝承施設と呼ばれるものができていて、青森から北茨城まで、ちっちゃい石碑みたいなものも含めて公式見解で300オーバーくらいあるんですよ。この廃炉資料館もそうですね。で、こうした施設ができる過程でけっこう揉めるんですね。箱物取り合い的なところもあるのですが、揉めるいろんな文脈を見ていくと、復興が終わってほしくないと思っている人たち、復興の過程の中でそれが自らのアイデンティティの一部になって幸福感を感じていたその土地の方たちというのが、少なからずいることがわかってきます。
なぜか。やはりそこには、東京がある。復興が無ければそうなる条件、必然性を得ていなかった人が、復興を通じて東京とつながれるからです。東京のニュースで、復興の話を取り上げてくれる。無論「こんなの無ければそれで良かったんだ」という健全な感覚の人が大部分です。ただ、そうやって日常に戻った人がいる一方で、そうではない場合もある。震災伝承施設というオフィシャルな受け皿ができてしまうと、ゲリラ戦で復興に取り組んでいた人たちが、意図せずともアンオフィシャルな人になってしまう。「あなたたち、もう復興における役割は終わりですから」という肩たたきだと感じて、嫉妬やひがみも生まれる。復興を介して東京とつながっていた非日常が終わったあとにどうするのか、という問題。これはまさに先崎さんがおっしゃるところの地方の自己肯定感の問題を象徴する一例であり、復興じゃないところでも、同じような問題は起こっているでしょう。せっかく東京とつながれるチャンスが来たんだから、もっとつながろう、なんでそれを終わらせるんだ。皆がそうでもないが、しかし少数であっても、熱を帯びたその叫びが、意図せぬ悪しき慣習の継続を生んでいる。
先崎 その点、西日本の方に行ったときには別の可能性も感じました。松山、熊本、鹿児島、金沢といった人口70万人ぐらいの都市には、なんとなく東京や東北にはない街の落ち着きがあるんだよね。東北において人口が一番多いのは、100万人ちょっといる仙台ですが、次は秋田でも盛岡でもなく、33万人ほどのいわき市なんですよ。しかも仙台やいわきは、とてつもなくでかい。他方、鹿児島や松山などはかなりコンパクトで、街が綺麗に城下町で整備されているんですよ。チンチン電車が走っていて、語学学校をはじめ、あらゆるものがひと揃い一個ずつぐらいある。東京だったら、フランス語の学校だけで100個も200個もあるわけですが、ここは一個しかないわりにそれなりに揃っていたりする。あの落ち着き方には、けっこう大きなショックを受けました。
先ほど話に出した、妹の嫁ぎ先である埼玉北部の隣町である宮代町も、かなりコンパクトで綺麗なまちづくりをしていますね。綺麗な小川が流れているところに、「新しい村」という施設を作って、ちょっとご飯を食べられるスペースや有機農業を10坪ずつ貸すスペースを提供している。変に箱物を作ったりしないで、地元にもしっかりと根付いたかたちで、しかも明るい雰囲気の中で穏やかにうまくやっています。ただ、その町内の東武動物公園駅前の開発で箱物を作ろうとしたときに、「そんな箱物を作っても、隣の隣の駅である春日駅にあるもののミニチュア版ができるだけで、意味がない」と反対意見が出て否決されたこともあります。そして、その場所はいま空き地になっている。やはり、まちづくりの問題はどこでも同じような課題を抱えてしまいますよね。
中道・知識・外部という「夢」を諦める
開沼 先日刊行した拙著『日本の盲点』という本のあとがきで、どうこれまでを総括し次に向かうのかという点で自分なりの一つの見解を提示しました。それは、中道・知識・外部、この3点を社会が追求することを諦めつつ、それでもなお追求する道を探るべし、ということです。
たとえば、「中道」を目指すべき論って、色々な言葉を使いながら言われてきたわけです。「右も左もバカばかり」「リベラルを健全化すべし」というようなスタンスはある種のパターンだった。冷戦後ずっとそうだったかもしれないし、民主党政権が終わったここ10年はなおさらそうだった。でも、結局、どんなに一瞬秩序が崩れて状況が良くなりそうになっても、ジョナサン・ハイトが言うように、社会は右と左に分かれる。自分は右ではない、左でもないと言いながら、結局党派的なポジションをとってしか話せない人間ばかりになる。だから、もう、言い方は色々あるけど、右と左を超越するぞ的な中道をいずれ実現できるはずだという、その方向はもう無理だよね、と諦める必要があると思っています。じゃないと、自分は中道なんだと思い込んでいるが、実態は結局右のクリシェか左のクリシェを繰り返すだけの、botみたいな人間ばかりが増える現象に歯止めが効かなくなる。中道はないんだと、徹底的に諦める。それで、botみたいな言説を冷徹に仕分けする目を取り戻した上でしか、次のステージには進めない。
「知識」も同じで、もはや教養主義、知識があることで尊敬されるし自分もそうなりたいという前提が成立しない。無論、手軽に知識の断片を得られたような状態になれるツールは様々に発達していますが、そこで得られる知識は、本当に頭良くなりたいと思って求めるものではなく、それぞれが自身の信念を強化するために求めるものになってしまっている。「外部」についても同様で、たとえば、多様性や包摂というキーワードを皆言うが、実際は多様性が進むほど、自分の視界に入らない外部が増えていくことに不安を覚え、それを排除する力学のほうが社会を動かすようになっている。よく言われる話でいえば、トランプ支持者を叩くリベラルが、トランプ支持者もまたマイノリティというか弱者であると認識できていない。つまり自分の外にあるものを許せないし、想像もできていない、したくない。だから知識も外部ももう無い、と諦める必要がある。逆に言えば、諦めないであたかも中道があるかのように、私たちが知識を得たり外部を知ったりするつもりがあるかのように想定してきたこと自体が、良いか悪いかは別にして、幻想だったんだと認めずに来たことが、変化をここまで遅延させ病巣を拡大させてきたことに自覚的にならないとそろそろダメだよという話。
「中道」「知識」「外部」という3点セットの夢の不可能性が、この10年でわかった。だから中道を目指しましょうとか、外部とつながりましょうとか、ちゃんと知識を持って科学的事実を見ましょうとか、いろいろやってきたけど、一回全部諦める。それを認めたうえで、中間集団や隣人といった、地方の最適なかたちを考える必要がある。これが私なりの現実への一つの実践の結果であり、向き合い方です。
先崎 保守についても、ただ単に現状維持になってしまっています。保守というのは本来、リベラル、すなわち社会を変えようとする輩がいることが前提で、その人たちに対して保守的であるというスタンスを取ることで、ある程度の緊張感を得てきた。それにもかかわらず、現状では「自民党支持層には二十代が一番多くて困ったね」と語られるときと同じ程度の意味の「保守」でしかない。
さっきからの話につなげれば、ふるさと納税でもインバウンドでも何でもいいのですが、菅さんや安倍さんが「ふるさとのため」と言ってやっていることが実は東京化とか画一化を産んでしまっていることに対して、「それを価値の中心に置いてはいけない」と言い続けるのが保守の役割だと思っているわけですよ。画一化や東京化イコール愛国心、日本社会の地方が良くなることだという価値観は、すごく簡単に言えば、価値の中心軸が金に置かれているわけですよね。だけど、少なくとも精神の構えとして、それとは違う価値観があるんですよということを言わねばならない。
数日前にたまたまテレビで見たのだけれど、当時の東京電力の社員たちがこの10年間何をやってきたのかを追いかける番組をやっていて、ある元社員がこう言っていました。「東京電力の社員である限り、電力の供給をすることが善だった」と。これは私が一時期仲良くさせてもらっていた中国電力や四国電力の電事連の人たちも言っていましたが、北海道がブラックアウトしたときには、必死になって復旧しようとする。これは自衛隊ががけ崩れから人を救出するのと同じ意味で、彼らにとっては絶対自明の善なんですよ。なぜなら、電力を供給して豊かで便利な社会を作るっていうのが第一の価値観だから。
だけど、原発がぶっ飛んだことによってその価値観が自明ではなくなり、テレビに出ていたある社員は、福島県で農業を復興してくれる人材が枯渇していると聞いたから、農業の世界に飛び込んだそうです。その元社員が言っていたのは、この田舎町はたしかに不便だけれど、人と人とが助け合っているのだということ。助け合うことで不便さを補わないと、生きていけないからです。喧嘩しても意味がないから、たとえ仕方なくだったとしても、できるだけつかず離れずでうまくやっていこうとしているのだと。そのとき彼は、不便であるということにも価値があるんだということに、初めて気づいたと言っているわけです。一人格である彼の中で、非常に大きな出来事がドラスティックに起きていた。絶対に正しいと思っている価値というのが、2番目、3番目、4番目の価値になって、違う価値観がそこに座ることは、ありうるんですよね。
机上の空論で夢物語だと言われるかもしれないけれど、良質な保守派というものがあるのだとしたら、いまとは違う価値があるということを少数派になったとしても言い続けるという精神の構えを見せることにほかなりません。そういう時流におもねらない言論活動をするということが、いまの社会において保守が社会に対して物申す緊張感を持てる、唯一の道筋なんじゃないかなと思います。
社会の「たたみ方」を考える時代に入った
先崎 ただ、もちろん「金対人」の対立構図で考えればそれでいい、というわけではありません。さっきも紹介した萩原朔太郎が、群馬の前橋出身なのだけれど、彼が「都会は人を自由にする」と言っているんですよ。萩原は前橋の地方から、石を投げられるように都会に出てきた。地方は、向こう三軒両隣が何をやっているか、全部見えちゃう社会。私がいわきに住んでいたときすら、そう思いましたよ。「お前、知らない女性を連れて、車であそこの交差点曲がっただろう」というようなことが、その翌日に大学内で話題になってしまうような場所でしたから。いわきという都市部であってもそうだったので、もっとローカルな場所は、さらにその傾向が強いでしょう。だから、地方がユートピアだという夢物語を言いたいわけではない。地方における人間環境ほど、しんどくて面倒くさいものはないですし、ユートピアとはおおよそ違う、人間の悲喜こもごもを持っているんです。
私が思っていることは、月並みな言い方をすると、政治というものは清濁併せ呑まなきゃいけないということです。さっき出てきたような、復興関連の金なのか政府関連の金なのかというジャブジャブ同士の対立、それから地域における一人ひとりの「金は欲しいけど、隣には廃棄処理場を作らないよ」というエゴイズム。そうした現状を51%飲んでも、残りの49%では理想の社会を作る方法を模索していかないといけない。いまの日本社会に対して、ここまで喋ってきたように批判をしたうえで、では何か良いユートピア的な解決策があるのかというと、おそらくないでしょう。都会的なセンスやクリエイティブなセンスを持って入ってきた若者たちでさえ、地方においては旧来の政治に回収されちゃっている状況においては、「99負けても1を取る」という方法を模索していかないと、なかなか変えていくことは難しいのではないか。そんなことを私は机上の空論として考えているんだけど、開沼さんみたいに現場で全部見てきた人は、どう感じているのでしょうか?
開沼 ここまでの議論を総括し、あえて図式的に語れば設計主義と自生的秩序、の話を持ち出すべきなのかもしれない。設計主義的にやると、全てがシステムに組み込まれて、いびつなものができる。そして、そのいびつなものを守るために、また何かさらにいびつなものが生まれる……という構造になっている。だからもう地方創生、コミュニティデザインも復興政策もやらないで、自生的秩序に任せる。過疎地は自然と潰れていくような力学に任せて、本当に良いものが残る可能性にかけると。それがどういうかたちで実現するかは別にして、そういうチャレンジも意思をもってしていかないと駄目なのかな、という気もしますね。
先崎 ものすごく素朴な質問なのですが、さっき話したような、本当に誰が聞いても笑っちゃうような施設ができてしまう事態は、なぜ起こるのでしょう? 政治家の発想する「地方」がこんなにもずれたものになってしまうのはなぜか、現場にいらっしゃる開沼さんから見てどうですか?
開沼 政治家の問題もそうだし、実際そう結論づけられがちだが、それ以上にあるのは、それを反映する住民のレベルの問題です。つまり、そういうパッケージングするくらいしかアイデアがでてこない場では、それがベストアンサーとして出てきてしまう。『あまちゃん』で、若者が髪染めてジャージ着て小型犬を連れたヤンキーが出てくるという設定の場面がある。実際に地方にいけばあの通りの人に遭遇する。あれは、地方から見た都会的なもののパッチワークです。つまり、テレビに出てくるカッコいい都会の人が持っているように見えるアイテム揃えた結果があれだったりする。「テレビで見る人は茶髪だから、東京の人はみんな茶髪だ」と思って、そういう思い込みを積み重ねていき、なぜか一つの田舎ヤンキーの型が完全にデフォルメされたものとして出てくる。同じ構造だと思います。
先崎 地方、とりわけ新幹線から外れたところに住むと、そういう感覚をきわめて強く感じますね。
開沼 先程先崎さんがあげた例のように、人口規模が一つの要因となり都会的な利便性と自生的な地域性がうまく共存している場所もある。ただ全国的に見て、そうではないところが多いのも事実。じゃあどうするかを考える必要はある。たとえば市町村の町を消して、村としてもうめちゃくちゃ小さくやりますというところと、市としてミニ東京になるというところの行政制度をばっちり分ける、という話をしないといけないのかもしれない。いまは村も東京になりたがっているし、市は高速道路もあるから工場誘致も進み、意外とやれなくはないというところで満足するという、全てがダラーっと弛緩し中途半端な状態になっている。その機能を分化させたほうがいいのかもしれませんね。
先崎 やっぱり我々はなんのかんの言って、基本的には戦後70年で人口が倍以上になって拡張してきた。でも、いよいよどこか安定した人口、安定したかたちを模索する着地点を、見出さなきゃいけない時代に差し掛かっているのかもしれない。外交や防衛にもこれからまた金がかかりそうなときに、それを少ない金の中でどうやって進めていくのか、社会をたたんでいくのかという問題に直面しているのではないでしょうか。
鳥もちのようにねばついた社会を、どう変えるか
先崎 まったく東京化されていない村に住むか、ミニ東京としての地方都市に住むか。これは究極的には、死生観の問題でもある。日本人はこれから大量に死者が出てくるわけですが、死生観は多様であるべきだし、その中で「生命をずっとできるだけ維持した方がいいんだ」という考え方を第一の価値として全面的・画一的に適用していると、立ちゆかなくなる。長生きしなくてもいいから、生まれ育った土地で天寿を全うしたいというあり方も、尊重されるべきだと思う。私は震災の中で一番印象に残っているのは、震災直後にどこかの週刊誌をコンビニで立ち読みしたときに見た、火葬が追い付かないで土葬を次々にしていることを報じた白黒写真なんです。もちろん復興は生きる希望を持って、明るい未来を目指して行くことが大事だけど、やっぱり私らは戦後──ということは当然我々にとっては生まれて初めて、あれだけおびただしい数の死者を見たのだと思うんですよね。そしてこの国はその死者を巧妙なまでに排除し、生きることの論理だけでこの10年間を取り繕ってきた。これが私の中ではずっと引っかかっている。今回のコロナもそうだけど、やっぱり人は死ぬんですよ、当たり前なんですけどね。だから死というのを、もうちょっと勘定に入れた社会を作っていかないといけないと思います。
そのうえで、大雑把なんだけども、大きく3つの精神のありようを想定して、地方の作り方を考えていかなければいけないと思う。まず、地方で生きていくことに何も疑問を持たないで年を重ねていくことができた人たち、すなわち毎朝草むしりから始まって淡々とずっと過ごせる人たち。それと、地元にいることを否定したい気持ちから、イオンモールやスターバックスができたらいいなと考えている人たち。さらに、東京に生きていながらも、地方が持っている自然の豊かさとかそういうものにちょっとだけ惹かれて、あくまでも加工されたものにしかすぎない田舎に「スローライフ」とかいう名前をつけて、田舎の生活の面倒くさいしがらみがないかたちで関わりたいと思っている人たち。これら三者の共存を前提に、地方のありようを考える必要がある。たとえば福島だと、週末になるとディズニーランドとかに遊びに夜行バスで東京に向かう人も多い一方、東京の人たちは週末になるキャンプとかに大挙して押しかけますからね。
開沼 人間は、都会性と田舎性の両方に魅力を感じるということ。これは本質的で、無視できない問題です。地方にずっと住んでいる人でも、子どもがいたらディズニーランドには行くかもしれないし、別に地方が好きじゃなかった人でも、東京に出て疲れたときに地元の良いところを再発見するかもしれない。ロシアでは旧ソ連の頃から、菜園つきセカンドハウスの「ダーチャ」を持つ文化がシステムとして根付いていますが、そうした2拠点居住的なもののバランスをいかにして考えていくか。
先崎 ただ、いまの我々の社会で、そうした構造レベルから変えていくことはかなり至難の業でもあります。積極的に支持している人は少ないにもかかわらず、自民党が勝ち続け、変わることができないこの社会。たとえば、私が住んでいる世田谷区には、いまだに「標準世帯」であることを寿いで暮らしている、自信に満ちた主婦層みたいな人々がわんさかいるわけですよ。上野千鶴子を引くまでもなく、「標準世帯」的なものの崩壊は自明であるはずなのに、です。1980年代くらいのバブルの土地転がし文化も残っているし、「分厚い中間層」と言われていたようなものに自信を持っていたあの頃の雰囲気が、いまだに残っているんですよ。しかも世田谷区には90万人という、島根県とか鳥取県より多い人口が住んで生きているわけですよ。そういう現状を日々見せつけられるにつけ、当たり前の社会構造の変化に気がつかないで、なんとか過去の栄光にしがみつこうと思っている社会なのだと痛感します。鳥もちのようにねばついて動かない社会の中で、違う社会の形を目指そうとする人たちが、どこまでこの国のあり方を変えていくことができるのか。
あとはですね、開沼さんの言う中道というものを本当にやるなら、火中の栗を拾いに行く必要はあるなと思っています。これは保守派だと言われている私だからこそ、やるべきことなのではないかなと。自民党を中心とした、保守派と称している政治家たちの歴史および思想的な意味での学力は、はっきり言って相当に低いんですよ。知識人に勉強会で来てもらうときに、かなり陰謀論的な論者とかを呼んでしまったりするわけです。リベラルな人たちがこれをお酒の席でさんざん馬鹿にしているようなシーンに私は度々出会ってきましたが、それは実際に社会を1ミリも変えてないとも思いました。だったら私は、もしですよ、まんまと保守派になりおおせてそうした勉強会に呼んでいただけた場合には、火中の栗を拾ってでも入っていきます。たとえ御用知識人と呼ばれようと、「いや、本当はこう考えるべきなんじゃないですか?」ということをやってみてもいいのかなと思っていますけどね。一応私はそれなりに誠実に勉強してきたつもりだし、社会に対して嗅覚を持ちながら、歴史の中に竿をさそうと思ってきましたから。外側から馬鹿にし続けるだけじゃ、本当に両極にずんずん歩いていっちゃうわけですから。
人間というのはひだがある生き物だということを、わかってほしいんですよ。最後に出てきた結論は右でしたとか、左でしたとかいうことではない。私はよくこの例を出すのですが、保守的であったはずの江藤淳と、最も国家というものを嫌いだったはずの吉本隆明は、お互いを非常に認め合っていたんですよ。対談でもお互いに認め合っているし、両方をよく読んでみれば、この人たちはかなり、感受性において同じものがあるなとよくわかる。ただし、政治的な立場は逆。こういうことが余裕であるのだということを認識しないと、言論というものはどんどんなくなっていきますよ。陰影を失って痩せかれていって、ただの感情の呼応だけになっていくと思います。Twitterの140字なんて、言葉の機能の一面でしかない。言葉というものは、もうちょっと違ういろんなものを含んでいるものなんですよ。
[了]
この記事は、2021年3月2日に開催されたPLANETSのイベント『遅いインターネット会議』のトーク内容を再構成したものです。宇野常寛が司会、小池真幸が構成をつとめ、2021年6月3日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。