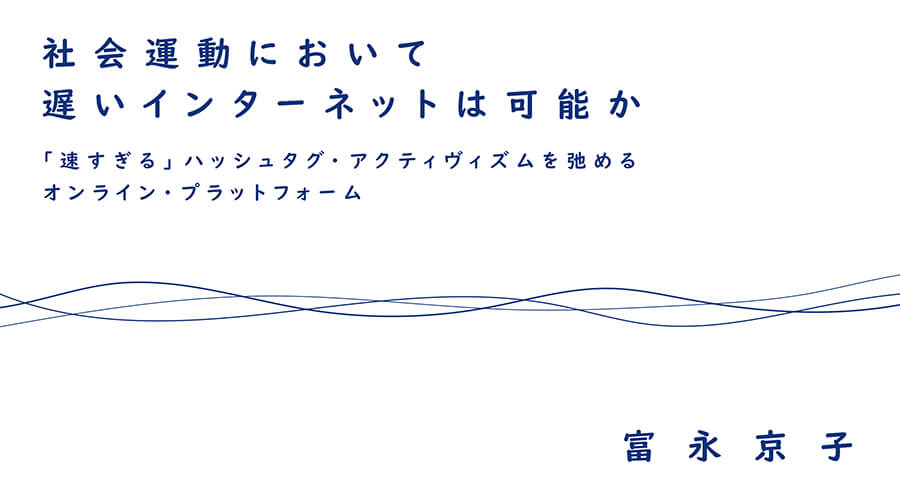SNSの普及に伴って、「声を上げる」という行為がより一層広がっていった2010年代。オンラインと組み合わさったかたちでの「社会運動」は、いかにして世界を変えてきたのでしょうか? SNS活用を前提とした2010年代の社会運動の成果と課題について、社会運動研究者の富永京子さんが総括します。最新の社会運動研究の成果にも目配せしながら、ソーシャルメディア型社会運動の困難を乗り越える、「手間」と「面倒くささ」ありきのプラットフォーム型活動の可能性に迫る試論を寄せてもらいました。
端的に言うとね。
社会運動における「出来事」と「日常」
ここ数年で定着した社会運動と言えば、日本と海外とを問わずやはり「ハッシュタグ・アクティヴィズム」に代表されるようなインターネット、とりわけSNS上の活動ではないだろうか。2014年のアイス・バケツ・チャレンジに遡るまでもなく、2015年の安保法制に対する抗議行動などでも盛んにSNSは用いられてきたし、近年でも「検察庁法改正案」「入管法案」に対してTwitter上で行われてきた。#MeTooや#FridaysforFuture といった形で、インターナショナルな連帯を喚起する際にも有効とされており、多くの先行研究がハッシュタグ・アクティヴィズムの研究に取り組んでいる。
筆者は10年と少しの間、日本の社会運動を中心に研究を続けてきたが、これまで、どちらかと言えばオフラインに重きをおいた社会運動を検討してきた(富永 2016, 2017, Tominaga 2017など)。社会運動と言うと多くの方が組織による集合行動、例えばデモや集会、あるいはアドボカシーやロビイングなどをイメージすると考えられるが、筆者は社会運動に従事する人々が個人的に営む「日常」もまた、運動の理念が反映された一行動として捉える。例えば、エネルギーの消費に反対する人々が自動車の利用を避け自転車で移動したり、菜食主義を貫いたりといった活動が例としてよく挙げられる(Haenfler et al. 2012)。どのような形の日常を社会運動として意味づけるかは、普段その人がしている活動や関心のある政治課題によって大きく異なるが、例えば選択的夫婦別姓制度を推進したい立場の人であれば、議員に陳情する、署名する、SNSでハッシュタグをつけてメッセージを書くなどが組織による集合行動(筆者の用語法では「出来事」)となるが、例えば法律婚でなく事実婚を選ぶ、場合によっては男女の既婚パートナーに対して「旦那」や「主人」といった呼称を避け、「パートナー」や「連れ合い」といった呼び方を選ぶ(筆者の用語法では「日常」)といったものがあるだろうか。
こうした枠組は、筆者が修士課程に進学し社会運動の研究を始めた2009年以降、G8サミット抗議行動(現在はG7)に参加した社会運動従事者の方々とやりとりを続けていて思いついたものだ(関連する研究にHaug 2013などがある)。サミット抗議行動とは、G7やG20サミット、WTO閣僚会議などが行われる現地に集まって世界中から参加した社会運動従事者がともにサミット抗議のためのデモやワークショップを行う活動を指す。しかし、数日行われるサミットに抗議するために遠方から来た参加者が多数いるということは、彼らが滞在する宿舎を用意しなくてはならないということでもある。そのため、抗議行動の中で社会運動従事者がともに暮らす「プロテスト・キャンプ」が生まれる。このプロテスト・キャンプは、ただの宿舎ではなく、社会運動の理念を反映した「オルタナティヴ・ヴィレッジ」と呼ばれることがある(McCurdy, Frenzel, Feigenbaum 2013など)。そこでは、例えば電力を使わないソーラークッカーなどが用いられたり、身体障害を持つ人々や子どもでも楽しめるオリジナル・ルールのサッカーが楽しまれるようになる。つまり、サミット抗議行動は、集団で行う、環境問題や途上国開発に関するワークショップやサミット抗議のためのデモという「出来事」に加え、プロテスト・キャンプにおいて振る舞われるヴィーガン食や、部屋を男女で分けない、誰でも使える寝室やトイレといった「日常」によって支えられていたのだ。
少し前置きが長くなってしまったが、冒頭でも書いたとおり、2010年代以降、オンライン社会運動の存在感はますます高まってきた。2011年の東日本大震災後、原発再稼働に反対する官邸前行動や激化するヘイトスピーチに対する反レイシズム運動、2014年に生じた特定秘密保護法案に対する抗議行動や2015年の安保法制反対運動など、オンライン上での社会運動の戦略は、オフラインでの抗議行動と絡み合う形でより洗練されてきた。そして2020年初頭より、コロナ禍のために外出できない状況からハッシュタグ・アクティヴィズムのみならずオンライン署名やクラウドファンディングといった活動もより顕著となってくる。
では、筆者の提示した分析枠組である「出来事」と「日常」を通じて、オンライン上の運動はどのように考察でき、またどういった課題点や革新性を見出すことができるのか。本格的にデータを収集し、最新の研究を渉猟した上での論文ではないため、あくまで「試論」に過ぎない試みではあるが、これを読んでいる読者の方が現代の社会運動を考える上で、何か補助的な役割ができたなら幸いである。
2010年代の社会運動とソーシャル・メディア
東日本大震災から10年が経つが、近年の日本の社会運動はインターネットとどのように付き合ってきたのか。日本でも代表的なものとして、伊藤昌亮(2012)の研究が参考になる。
伊藤は2012年時点でのデモにおけるソーシャルメディアの役割を、告知、実況、振り返りのツールとして捉えている。また、仮にオフラインでのデモが一段落しても、なおネット上で「祭り」が続くこともあるという。この典型例として、東日本大震災以後の反原発デモが挙げられているが、海外の事例として当時の代表的事例に「オキュパイ・ウォールストリート」「アラブの春」が挙げられるだろう。伊藤はこれらの事例にも触れており、オキュパイ・ウォールストリートでは「#occupywallstreet」というハッシュタグが用いられたことにも言及している。アラブの春においてもまたFacebookやTwitter、ブログで情報共有が大規模になされ、一部地域ではTwitterのハッシュタグを利用したムーブメントも見られたという(ちなみに「アラブの春」については、総務省のサイトがきわめて詳しい分析を掲載しており、興味深く読むことができる )。
しかしこうした活動は、あくまでオフラインの活動を下支えするオンラインの活動という位置づけがなされている点で、現在見られるハッシュタグ・アクティヴィズムとはやや異なる。伊藤と同様にMario Gerbaudoも、ソーシャルメディアに見られるこの効用を、オフラインの活動に対する「動員」の面から説明している。ソーシャルメディアにおけるデモや「集まり」の映像は、それを観ている側の「孤立」を煽ることになる。だからこそ、孤立を解消させるためにデモの現場に向かうのだというのが、Gerbaudoの議論である(Gerbaudo 2012)。両者の議論は、オフラインとオンラインの相互作用に重きをおいて説明していると考えられるだろう。
Tufekci(2017=2018)もまた、オフラインとオンラインの相互作用による活動「アラブの春」を検討しているが、過去の社会運動との対比のもとでオンライン社会運動の特性を議論した点で、伊藤やGerbaudoの研究とはやや位相が異なる。Tufekciによれば、オンラインの運動は、準備組織におけるロジスティクスの過程をオフラインの活動ほど必要としない点に特徴を持つ。この点では有効だが、しかし設営の期間がないために持続性が短く、短期的な盛り上がりを特徴としている。またソーシャルメディアを中心とした社会運動には、個人的参加が多く見られるが、他者や他組織とのつながりが弱いため運動全体が継続しにくい点もある(Tufekci 2017)。こうした解決策として、Einwohner and Rochfordは、イベントの後に運動の運営組織や参加者が継続的に発信することを挙げている(Einwohner and Rochford 2019)。この点では、ソーシャルメディアでの活動もまた継続するには組織性がある程度必要だということになるだろう。
このように先行研究の議論を踏まえると、ソーシャルメディアを通じた運動は、持続的に生活を通じて続く「日常」というより、短期性・集中性といった性質を強調される「出来事」として捉えたほうが実態にかなっていると言えるのではないかと考えられる。しかし、その後の先行研究では、ソーシャルメディアの「日常」的側面もまたクローズアップされていく。
ソーシャル・メディア自体が、私的な語りと公的な宣伝や宣言の重なる場所であり、両者の分離は使っている当人にすら意識的に不可能なときがある。実際に、例えば#KuToo や#MeTooといったハッシュタグによって生み出される多数の書き込みは、単純に性被害・セクシャルハラスメントへの賛否や学術的考察を交えた議論だけではなく、当人たちの体験談とともに語られる場合も少なくない。こうした「個人的な話」は、それぞれの話し手の日常から生み出されたものだが、かといってデモの現場やシンポジウムの登壇中といった「出来事」の中で語られるかと言うと難しく、ソーシャルメディアという媒体で、個人で発言しているからこそ可能になる「日常」の運動ということもできるだろう。しかし、そこで語られることは確かに他者とつながっており、一つのハッシュタグをつけ、そのタグのもとで繋がるからこそ、個人的な語であっても他者との間に連帯が生じるのである(Papacharissi 2015)。
かつこうした「ハッシュタグを通じた連帯」と「ソーシャル・メディアを通じた個人語り」の関連は、発言者全員に共有され、内面化されるものである。Wahl-Jorgensen(2019)は、この個人語りの他者への共有とその内面化を「パフォーマンス」という概念から位置づけ直している。自分語りを含む投稿は、「見えない」観客に向けて行われているため、すべての投稿がある種のパフォーマンスになるのである(Wahl-Jorgensen 2019)。つまりソーシャル・メディアで行われる日常の個人的な語りは、「見られる」ことを前提とした出来事の語りなのである。これもまた、ソーシャルメディアにおける「出来事」と「日常」の連関を難しくしているといえる。
ソーシャルメディア型社会運動の困難と、プラットフォーム型活動の台頭
日本においては、新型コロナウイルス感染症の流行と外に出られないという状況がオンライン社会運動の存在感を高めたのではないかと考えられる。日本でもアイス・バケツ・チャレンジなどの「ハッシュタグ・アクティヴィズム」のようにオンラインで完結する運動は見られたが、繰り返し広く行われることで、抗議の手法としてフォーマット化(定型化)され、多くの人が利用できるものになったと言うことができるのではないか。「#入管法改悪反対」「#わきまえない女」といったハッシュタグを、ここ数年の間に目にした人もいるだろう。
こうしたハッシュタグ・アクティヴィズムに関する参加率は、決して高くはない。2020年9月に実施した社会運動や政治参加の経験に関する調査(N=6,600, 性別・居住地域による割付法を用いてサンプリングしたWeb調査)では、「政治的な意見をシェア・リツイート」「ネット上で政治的な意見表明」を経験した人は約5%しかいなかった。これはオフラインでのデモ参加者の割合とそれほど変わらない。
日本労働組合総連合会(連合)の2021年調査「#多様な社会運動」によると、ハッシュタグ・アクティヴィズムへの意欲そのものは21.6%と、デモ(12.7%)やボイコット(19.2%)などよりも高いため、今後より多くの人が参加する可能性はある。しかし、それがSNSのアカウントだとしても、知り合いの前で「自分はこういう政治的立場だ」と提示することはまだハードルが高いだろう。路上で行われるデモとは異なり、匿名性が高いという考え方もあるが、ツイッターでの運動はフォロワーや知人に自身の政治的主張が明らかになるという側面もある(もちろん、「捨てアカ」や「政治アカ」を作るという対処法もあるが)。
また、Tufekci(2017=2018)が指摘したように、その短期性・集中性こそが、運動における「タイミング」の過度な重視に繋がる点も無視できないだろう。リアルな行動ならば、設営に時間を要し、コストもかかるので、その間にデモやワークショップのコンセプト、告知のキャッチコピーなど、「このやり方で本当に正しいのか」が議論されていく(Haug 2013)。一方ですぐに行動できてしまうオンラインでは、プロセスの吟味が深まらないまま実行に移してしまえるため、個々の発言や決定プロセスに対する判断や吟味の時間を省くことになる。その判断の参照点として、「誰が言っているか」「誰がリツイートしているか」という、発言内容でなく発言の「主」にフォーカスしてしまう傾向が生じてしまうとも考えられる。さらに言えば、タイミング重視の社会運動では目標達成のために迅速な行動をする必要があるため、内部批判がなくなりがちになる。そうなると、「有名な人が正義」「前に進めるのが正義」となり、反論や告発は時として運動に水を差す。オンラインでの活動では余計に影響力が可視化されるので、周りが批判しにくくなる。
ここまでの議論から、筆者はハッシュタグ・アクティヴィズムの課題を「速すぎる」点と考えている。過去の社会運動と異なり、設営のコストと時間がかからない一方、迅速な活動が可能になる。それだけに、運動のタイミングが重要となるため、すべてのプロセスが「速く」なっていき、そこで運動を「止める」「弛める」ことができなくなる。では、速くなりすぎ、止め難く進展する「出来事」としてのハッシュタグ・アクティヴィズムのスピードを弛める手立てはどこにあるのか。ここで筆者は、オンラインの日常を形成する運動として、プラットフォーム型の運動を提示したい。
「手間」と「面倒くささ」を運動に取り戻す──プラットフォームで支える日常
オンラインの社会運動と言うとハッシュタグ・アクティヴィズムのこととして捉えられがちであるが、例えば連合は2021年の調査において「ハッシュタグ型」のほか、「パフォーマンス型」「ネット署名型」「クラウドファンディング型」に分類している。パフォーマンス型はアイス・バケツ・チャレンジやエッセンシャルワーカーへの感謝を示す活動ということであまりハッシュタグ型と変わらないが、「ネット署名型」と「クラウドファンディング型」のような、「Change.org」や「CAMPFIRE」といったプラットフォームから署名をしたり、金銭支援をしたりといった活動はハッシュタグ・アクティヴィズムと別個のものとして捉えられるだろう。
この中には、例えば日常生活の政治的プラットフォームである「PoliPoli」、地域の議員に生活上の悩みを伝えられる「issues」、イノベーター、専門家、政策決定者それぞれをフラットにつなぐプラットフォーム「Pnika」、“社会課題の解決を目指す訴訟”の支援に特化したウェブプラットフォーム「CALL4」、気になる社会課題を選んで寄付が可能な「solio」など、政策決定者や社会起業家、法律専門職とユーザーを繋ぐ数多くのプラットフォームがある。ふるさと納税のプラットフォーム「ふるさとチョイス」なども、地域の福祉事業やNPOへの支援に繋がるという意味では広義のプラットフォーム型と捉えてよいかもしれない。
しかし、これらのプラットフォームを通じた活動もやはりある種のキャンペーンであり、一時的な「出来事」に過ぎないと考える人は多いだろう。Change.orgで署名を集め、CAMPFIREでクラウドファンディングに参加したとしても、それらはあくまで期間限定の一時的なものに過ぎない。2020年に行われた森元首相の性差別発言に対する署名行動のように、ハッシュタグ・アクティヴィズムと連結して一つのキャンペーンを成している場合も少なくないし、「速すぎる」アクティヴィズムのスピードを緩める「日常」がなぜプラットフォーム型の運動で可能になるのだろうか。
元々、日常をめぐる政治は、ライフスタイル・ムーブメントやリプロダクション、予示的政治(prefiguration)と呼ばれてきた(Tominaga 2017)。この概念を用いれば、日々の友人とのおしゃべり、子育て、余暇活動、食事、すべてが「政治」を形成するプロセスということになるが、その中でも重要なエージェントとなってきたのが日本の場合生協などの消費者運動団体である。そこで行われる商品自体の購入や、暮らしに関する情報の共有が日本の社会運動従事者における「日常」を形成してきた部分は大きい。
こうした「日常」をめぐる活動は、20万人が官邸に集まるデモや50万以上のリツイートを集めるハッシュタグ・アクティヴィズムと異なり、決して華やかではないし劇的ではない。情報収集の手間もかかる。例えば「暮しの手帖」を編集した花森安治は、編集部における商品テストの作業の冗長さと大変さを繰り返し主張していた(酒井 1992)。しかしこうした、商品の選定、情報収集といった「面倒くささ」「手間」こそが、言葉が猛スピードで回覧される「速すぎる」ハッシュタグ・アクティヴィズムを弛めるヒントとなるのではないか。
例えばプラットフォームを通じて貧困の状況にある子どもに支援したいというとき、そうしたサポートをするNPOや市民団体は数多くある。せっかく供出するお金なので有意義に使って欲しい人が大多数だろう。その中で、過去の実績や活動計算書などの財務データを積極的に公開しているかどうかを調べるという過程は、ハッシュタグをつけてツイートしたり、政策への反対を表明するよりはるかに手間のかかる作業であろう。しかし、一人ひとりが、インフルエンサーの言葉に依拠し、オーガナイザーによって提示されたハッシュタグの文言を繰り返すのでなく、運動の中で主体的に選択するプロセスを回復しているとも言える。
先日DHCによる差別的な文章のウェブサイト掲載が話題となったが、それに対して多くの自治体が包括契約を中止した。こうした自治体をサポートするためにふるさと納税をする、あるいはDHC以外の商品を使う、ということも、やはり自治体に関する情報収集や、オルタナティブな商品の選定の手間なくしては不可能だ。
まとめにかえて──「生活を通じた運動」を今こそ
社会運動組織や社会運動従事者の中には、こうした「生活を通じた運動」の「なまぬるさ」「ショボさ」を指摘する人々がいないわけではない(Craddock 2021)。筆者らの調査でも、「ボランティア」のような生活を通じた活動の経験者は「デモ」の有効性を認めるものの、「デモ」に参加した人々は「ボランティア」のような生活に即した活動にネガティブイメージを抱くようになる(金澤・富永 2020)。オンラインの、言わばプラットフォーム型運動に対する意欲の高さはめざましく、ネット署名への参加意欲が28.7%、クラウドファンディングが34.1%と、名前を書くだけ、金銭を支援するだけならば関わっても良いという人の割合は低くなく、とくに若年層の意欲が高いのも特徴的であるが、政治的有効性という点では、確かに日々の「日常」を通じた活動は、「出来事」としての組織的な集合行動にかなわないだろう。デモや陳情で多数の人の意識が変わったり、政策が変更される可能性はあるが、私たちが一生懸命ゴミの分別や寄付をしたからといって、環境問題が解決するわけでも子どもをめぐる貧困の状況が劇的に改善されるわけでもない。
しかし、日常を通じた活動は、運動を担う私たち自身のスピードを弛めるために重要なのだ。どこにどのくらい寄付額するか、どちらの商品を選んだほうが自分の暮らしと問題意識に対して適切か、どのエージェントのほうが信頼できるか。そうしたことをいちいち考えるのは面倒なプロセスだが、私たち個人個人が限られた資源の中でどの社会課題を特に解決したいのか、どういった人々と社会を変えていきたいのかを考える、オンライン運動の中で主体性と能動性を取り戻すためのきわめて大切な過程といえる。上で紹介したいずれかのサイトでもよい、あるいは他のプラットフォームでもよい。実際に寄付や署名をするかどうかはまだ決めなくてもいいから、どのプロジェクトなら自分に合っていそうか、じっくり時間をかけて考えてみるのはどうだろう。
<参考文献>
伊藤昌亮,2012『デモのメディア論―社会運動社会のゆくえ』、筑摩書房.
酒井寛,1992『花森安治の仕事』朝日文庫.
富永京子,2016『社会運動のサブカルチャー化──G8サミット抗議行動の経験分析』せりか書房.
富永京子,2017『社会運動と若者──日常と出来事を往還する政治』ナカニシヤ出版.
トゥフェックチー, Z.『ツイッターと催涙ガス―ネット時代の政治運動における強さと脆さ』(Tufekci, Z., 2017, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest,
Yale University Press.)中林敦子訳, ele-king books, 2018年。
Einwohner, R. L. and Rochford, E., 2019, “After the March: Using Instagram to Perform and Sustain the Women’s March”, Sociological Forum, 34: 1090-1111.
Papacharissi, Z., 2015, Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics, Oxford University Press.
Wahl-Jorgensen, K., 2019, Emotions, Media and Politics, Polity.
Haug 2013, “Organizing Spaces: Meeting Arenas as a Social Movement Infrastructure between Organization, Network, and Institution”, Organizational Studies 18: 83-104.
Gerbaudo, P. 2012, Tweets and the Streets, Pluto Press.
Haenfler, R. Johnson, B., and Jones, E., 2012, “Lifestyle Movements: Exploring The Intersection of Lifestyle and Social Movement in The Voluntary Simplicity and Social Responsibility Movements”, Social Movement Studies 11: 1-20.
Craddock, Emma, 2021, Living Against Austerity: A Feminist Investigation of Doing Activism and Being Activist, Bristol University Press.
Tominaga, Kyoko, 2017, “Social reproduction and the limitations of protest camps: openness and exclusion of social movements in Japan”, Social Movement Studies 16: 269-282.
Feigenbaum, A., Frenzel, F., and McCurdy, P. 2013, Protest Camps, Zed Books.
<謝辞>
本稿を作成するに当たり、楊雨双氏(立命館大学)より重要な示唆を得た。この場を借りてお礼申し上げる。
[了]
この記事は、PLANETSのメルマガで2021年6月17日に配信した同名記事をリニューアルしたものです。あらためて、2021年7月22日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。