「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
今回の研究会では、ゲストに招いたランドスケープ・アーキテクトの石川初さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマはランドスケープデザインの現在地と展望です。後編では、石川さんによるプレゼンテーションを踏まえた、参加者を交えたディスカッションの内容をお届けします。
「庭プロジェクト」の連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
「チューニングの設計」の難しさ、「日本庭園的管理」以外の可能性
まず石川さんがプレゼンテーションで提示した「スタイルとしての雑草」という近年のトレンドに対して、自身の研究対象である民藝の近年の動向との共通性を見出しつつコメントしたのは、哲学者の鞍田崇さんです。

「民藝もビジネスのモードに入ってくるときに、本来の土着のものから離れて『スタイル化』していく傾向があると思っているので、そこに重なるなと思って非常に興味深く聞いていました。そして、そうした『スタイル化』に対するものとして紹介いただいた『チューニング』の事例について伺いながら、植物との関わりとしての園芸的手法の可能性は、産業化してしまうスタイルとしてではなく、個々の相違を触発するような仕掛けとしてあるということかなとも感じました。個々人が自ずと園芸的アプローチにそそられるようにするための仕掛けづくりについて、お考えや事例があれば聞いてみたいです」(鞍田崇さん)
「そこが一番難しいと思います。一つには、ビジョンを掲げられないという、チューニングの宿命があります。完成形を示すと、結局、維持管理になってしまうんですよね。個々が現場で判断することがなんとなく積み重なっていって、事後的に『あれはチューニングだったな』というかたちでしか発見され得ない。
ですから、先行者に先に実施してもらう、のようなことがいいのかなと思ったりもします。逆に言うと、それぞれの地域に率先する人がいてもらわないと困るといいますか、率先する人をどのようにリザーブし、育てていくかということが課題かもしれないです。市民農園のように区画が割り当てられるかたち以外に、まちの一部を自分の場所として切実なものとして見始めるきっかけを作るためにどういう方法があり得るかなというのは、いつも色々なことを試しながら考えていることです。
最近やったのは、研究室で一人十粒ずつひまわりの種を学生に配って、今週どこでもいいから気になるところに撒いてください、というもの。それで咲いたら勝ちという、ひまわりレースのようなことをやってみたんです。わりと場所のリテラシーが問われて、変なところに撒くと芽も出ないんですよね。だけど一旦出たらもう研究室のslackで『芽出ました!』といったメッセージが殺到する。
おもしろいのは、全員そこが自分にとってかけがえのない場所になっていくんですよ。途中で剪定されてしまったり掃除されてしまったりなどするのですが、そのときに泣き顔絵文字がバーッて出てきたりして(笑)。そんなことから、それにうっかり巻き込まれた学生が、場所を自分の庭にしていく、といったことのきっかけがつかめるとおもしろいのではないかと思います」(石川初さん)
続いて、植木屋や花屋の経験を持ち、現在は福祉施設「ムジナの庭」を運営する鞍田愛希子さんは、自身の庭での実践を共有しつつ、日本の伝統的な「刈り込み」以外の管理手法や、在来種・外来種との向き合い方について石川さんに尋ねました。

「まずSFCのきれいな芝から遷移していく風景を見て、いまの自宅にとても似ているなと思いました(笑)。もともと大家さんが庭をきれいにされていて、ピシッと芝を整えていらっしゃったのですが、私がズボラだったのに加え、宮崎駿さんと半藤一利さんの対談で『トトロを描いていた頃は、まだ都市近郊に日本の在来植物がたくさん残っていた。その後、どんどん帰化植物が増えてしまって、なかなか在来種が見えない状況のときに、ボランティアさんと一緒に帰化植物を片っ端から引っこ抜くということをやってみたら、まずはキクイモなど、一世代前の帰化植物が出てきた。さらに、抜き続けたら、一面在来種のイチリンソウの花畑になった』といった話をされていたのがとても印象的で、人工的に植えられた芝の庭はどうなるのか気になってずっと放っておいたんです。そうしたら、カタバミなど小さな雑草から始まり、徐々にドクダミやヨモギなど、いろいろ賑やかに生えてきて、あっという間に芝はなくなりました。大家さんはイヤそうですが、わたしはとても気に入っています(笑)。ムジナの庭も、小さい庭なのですが、見せる庭というよりは使う庭としてつくってきていて、ハレとケで言うとケのほうの庭に私は興味があるのかなと思いました。
それから昔植木屋をやっていたときは、まず最初に掃除や刈り込みから学びました。街路樹や公園、緑地などの共有スペースが、日本庭園的管理に偏っていることはとても納得できます。ただ、限られた都市空間で樹木が育っていくと、強い剪定が必要になる時もあると思いますが、そうではない管理方法が日本でもあるのか、お聞きしてみたいです。またそもそも在来種は外来種と混ざり合って生きてきたと思うのですが、外来種について、石川さんはどうお考えでしょうか」(鞍田愛希子さん)
「1点目に関しては、たとえばいわゆる里山管理のようなやり方はあると思っています。たとえば都心のオフィスビルの外部の緑地を、20年にいっぺん丸裸にする、といったことです。。そうすると、またゼロからだけどひこばえが生えてきて、下草はササが生えてきて、雑木林状態になっていくんじゃないかと思います。そういう土手の草の管理のようなアプローチが、管理の方法として普及していくといいなと思っています。ただ、緑地を法律上全部丸裸にすること自体が許されないということ、そして育った木を大きいものから順番に切っていくというやり方に我々自身が慣れていないという難しさがあるとは思います。
2点目に関しては、たとえばこの谷戸の生物を保全するとき、在来の植物を圧迫して脅かすような種が侵入してきたら、もとある生態系を最優先して維持しないといけないとは思いますが、結局はゾーンごとに方針を立てるしかないと思います。ちなみに我が家の庭では雑草にする態度って一貫していて、それが在来か帰化植物かは関係なく、かわいい植物は残すようにしています(笑)」(石川さん)
「完成予想図」が阻むもの、切実な「物語」の重要性
建築家の門脇耕三さんは、近年のランドスケープ関連の仕事の経験も踏まえ、石川さんが提唱する「ランド・チューニング」という動的なアプローチを、特に新規の都市開発のようなトップダウン型の計画にどのように実装し得るのか、その意思決定プロセスや制度設計について深堀りします。
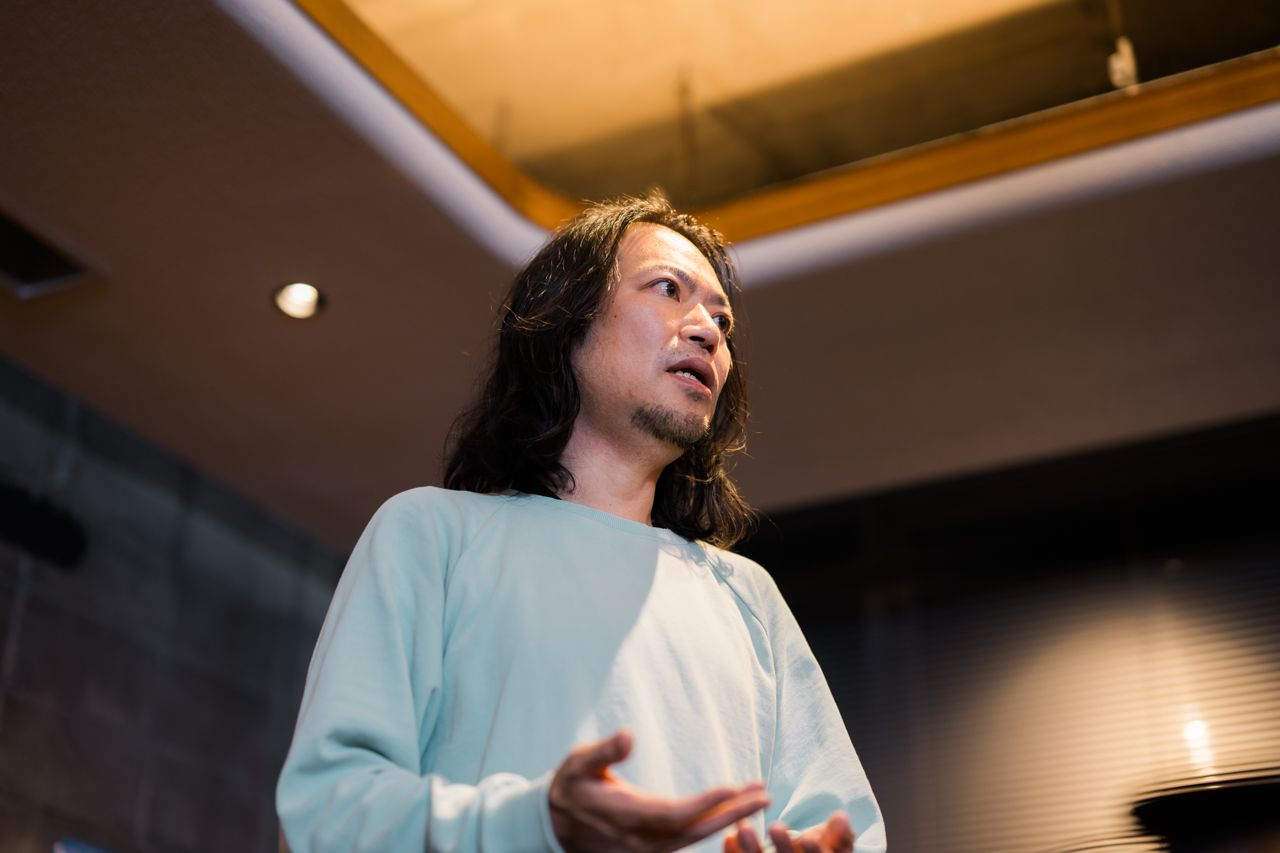
「世代によって造園に対する趣味は大きく変わりますよね。戦後の庭付き一戸建ては農村からの移住者の土いじりへの欲望の現れでしょうし、その後は管理の容易さからドライガーデンへ、そして現代人は再び植物との付き合い方を考え直し『雑草的ゆるさ』に惹かれている。そう考えると、植物はあくまでも人間の作ったものとしてあり、世代が変わるごとに様式も変わっていく。人間の世代間趣向と日本の気候的要件のバランスで、その時代の庭のあり方が決まっていくのだと思います。今の感覚では『雑草化する庭』は相性が良さそうですが、今後どうなっていくのかは気になりますね。
そして動的な庭、ランド・チューニングというコンセプトが現代的なアップデートとして紹介されましたが、これらはトップダウンの意思決定よりボトムアップで、いろんな人がそれぞれ植物と付き合う過程で全体像が浮かび上がる形がふさわしいと感じました。そうなると、新しいまちのランドスケープを提案するときに、ランド・チューニング的なあり方をどうすれば実現できるのかを具体的に考えることが重要だと思いました。行政が関わる計画はトップダウンになりがちで、人々のボトムアップな力や動的な遷移を織り込むのは容易ではありません。ランド・チューニングはガバナンスが放棄された状況ではリアリティがありますが、一からまちを作る際に、どう意思決定し、制度に落とし込めるのでしょうか?」(門脇さん)
「そこは本当に難しいですよね。我々が意見書を出す相手はトップダウンのトップの人たちなので、そもそもランド・チューニングと相性が悪い。そこを接続していくのが、これから私がしていくべき仕事かもしれません。いずれにしても資源は限られているのでトリアージは必要です。計画を白紙に描くのではなく、既存のものを選択するという発想、つまり計画を再定義し、その上でチューニングしていくという発想です。
また、『完成予想図』という考え方も捨てるべきで、あれが多くの人を不幸にしていると思います。『これが完成だ』と示してしまうと、それを目指し、維持することがミッションになってしまう。例えば都市開発における『賑わい』もそうですが、人が集い幸せそうな状態を完成予想図に描くから、常に賑わっていなければならないというプレッシャーが生まれる。多くの場合、賑わいのような状態を空間と切り離して実現できると思われがちですが、そんなはずはなく、完成予想図が場所から切り離されて独り歩きしている状態になっています。完成予想図なしでは、何にお金を出すのか、特にマンションなどは売れないという現実もありますが、それとは違うアプローチが必要です。賑わいも植物の状態も、そしてプロセスそのものも『完成』と定義すべきではないでしょう。建築が何世紀もかけ練り上げてきた完成予想図というメディアが、そもそも造園には合わないのかもしれません」(石川さん)
次にコメントしたのは、デザイン工学を専門とし、今回提案書を提出した藤沢市・鎌倉市の地域住民でもある田中浩也さんです。田中さんは、地域住民の「蛍が戻ってきてほしい」という切実な声を例に、ランドスケープ計画における「願い」の重要性を問いかけました。

「僕はたまたま最近庭プロジェクトで提案を出した鎌倉地域の住人でもあり、週末には地域のお父さんお母さんと一緒に活動もしています。そうした市民目線からすると、やはり将来への具体的な目標がほしい。そんな中で、例えば『蛍が戻ってきてほしい』という声は、いま地域でそれなりにあると思います。植物や賑わいといったものは、やろうと思えばある程度形にできるかもしれませんが、蛍はそう簡単には戻ってこない。しかし、そういう『こうだったらいいね』という純粋な願いや、本気で取り組む人たちにとっての北極星のような目標がないと、なかなか物事は進まないのではないでしょうか。こうした『願い』のようなものは、ランドスケープデザインの中でどう位置づけられるのでしょうか?」(田中さん)
「『蛍がきてほしい』というのは、ある種の物語であり、完成予想図よりもずっと良い目標だと思います。もちろん、別の物語があってもいい。たとえば『野原でゆっくり座ってトンボが飛んでいくのを見たい』という人もいるでしょう。
SDGsのような包括的な目標ではなく、蛍のような具体的な目標を本気で目指す人たちがいるというのは、とてもおもしろい。住民ワークショップで計画を考える際も、『蛍が来るようにしよう』という物語は、参加者みんなで共有しやすく、具体的な行動にも繋がりやすい。蛍を呼ぶためにはカワニナが必要で、そのためにはこれくらいの水量がいる、といった具合に空間計画に翻訳しやすいですよね。風景に根ざした具体的なイメージだからこそ、人々の心を動かし、トップダウンではない形でプロジェクトを進める力になりやすいのではないかと思いました」(石川さん)
「自主ルール」とチューニング、畑と庭
続いて文化人類学者の小川さやかさんは、石川さんのプレゼンテーションで紹介された、住民たちが自主的に庭を管理しているアパートの事例を引き合いに、フォーマルな規則とは異なる「自主ルール」がどのように立ち上がり、維持されるのか、そのメカニズムと計画への応用可能性について探りました。

「再開発前に住民の方々が勝手にガーデニングをしていたアパートの話はとてもおもしろかったです。法的なルールにもとづかないながらも、そこには使用者間の『自主ルール』が存在していた。そうしたルールがどのように生成され、機能するのか、とても興味があります。チューニングを実践していくには、このような自主ルールを育む環境がなければ難しいのではないでしょうか。
私の研究対象であるインフォーマル経済の現場も、一見カオスに見えても内部にはしっかりとしたルールが存在します。アフリカの農村で見られる畑も、無秩序に見えて同じ作物どうしで植えずに今作が基本で、実はリスク分散の知恵や長年の経験則が息づいている。混沌としたように見える状態から、人々が自律的にルールを紡ぎ出していく。日本でも、例えば最近、河川敷での『ヤミ畑』が問題になっているというニュースを見ましたが、こうしたものを一概に否定するのではなく、そこにある種の秩序やコミュニティが生まれているとしたら、その形成過程で起こるコンフリクトをいかにしてチューニングへと転換していくのか、考えていく必要があるように思います」(小川さん)
「おっしゃる通り、そのあたりは私自身ももっと深く考えていきたい領域です。しかし、むしろ現代は、そうした自律的な空間が生まれにくい状況にあるのかもしれません。例えば、かつての戸山アパートや北青山アパートのようなゲリラ園芸的な場所が今存在したら、SNSなどを通じてあっという間に注目され、共用スペースに勝手に園芸する行為が禁じられるような『正しさ』の圧力がかかってしまうかもしれない。
また神山町で農業インターンを経験した学生の話では、畑の美観は、必ずしも合理的な生産性だけでなく、地域の人々の目、いわば見栄と作法のようなものに大きく左右されるといいます。『これはみっともない』、『あれは怒られた』など、そうしたある種の煩わしさがあると。だから、自主的な空間管理の現場も、必ずしも常に平和なわけではないでしょう。都営住宅の事例を考えると、もともと地縁がない多様な人々が新たに関係を築き始めたという初期条件ゆえに、話し合いによるルール形成が促されたのかもしれません。そうした場で、どのようにして独自のルールが築かれていったのかを聞いておくことは大切かもしれませんね」(石川さん)
パターンランゲージや創造社会論の研究者である井庭崇さんは、自身の庭や畑での具体的な手入れの経験を共有しながら、植物との創造的な関わり方について語りました。

「家の前がプランターだらけで亜熱帯のようになっていく、という石川さんのお話がおもしろかったです。僕もここ数年、畑や庭で野菜づくりに取り組む中で、夏の暑さでゴーヤがよく育つ一方で、冬の寒さで南国系のマンゴーやバナナは難しいと感じていて、育てる植物も変化しています。
ここ最近僕が関心のあるテーマは、畑と庭の違いです。畑はどうしても生産性重視で手が回りにくいのですが、庭は毎日眺めることができる。日照条件の変化から、野菜も直植えからプランター栽培がメインになりました。プランターは、もともとは『限られたスペースでも置けるプランターでどこまで栽培することができるのか』という実験から始めたのですが、結果的にこれが非常に良くて。例えばパクチーも、プランターなら生育範囲が管理できますし、日当たりが悪ければ移動もできる。樹木のように大きな覚悟を強いられることなく、仮設的に運用できるのが魅力です。
僕はもともと複雑系の研究をしていたので、『カオスの縁』という概念を思い出します。完全に秩序化された状態でも、完全なカオスでもない、その境界領域にこそ生命性や創造性が生まれる。庭で言えば、プランター栽培は、ある程度の複雑さを許容しつつも管理可能な範囲に収め、多様な品種を混在させることで生まれる、ちょうど良いカオス具合を実現する一つの方法ではないかと感じています。日本庭園のようなきっちりとした刈り込みは苦手なので、プランターで植物が大きくなりすぎないように適度に手を入れられるのが、僕には合っているようです」(井庭崇さん)
「まさに井庭さんの手入れと周囲の環境との間で、日々チューニングがなされている状態ですよね。プランターが最適解であれば、それが一番良いと思います。新築の庭の相談を受ける際、私はよく『とりあえず全部芝生にしてみてはどうですか』と提案するんです。一年間そのままにしておけば、日当たりの悪い場所、人がよく歩く場所などが自然と見えてくる。そこから、ここは花壇にしよう、ここは敷石を置こうと、少しずつ手を加えていけばいい。みんな、そんなふうに時間をかけて庭をつくっていけばいいのだと思います。
そして公園のようなもっと大きなスケールで考えるなら、メンテナンスの頻度に応じたゾーニングが有効かもしれません。『ここは週に一度手を入れるエリア、あちらは半年に一度、そしてこっちは20年に一度大きく見直すエリア』というように。ただ、20年という時間はなかなか待ってもらえないので、説明が難しいところではありますが(笑)。地域スケールの『動いている庭』というイメージですね。もちろん、すべてを『動いている庭』にしてしまうと、日本の気候では『動いている森』になってしまうので、例えば芝生エリアや草丈の低いエリアだけでも明確に維持管理の方針を決める必要があるでしょう」(石川初さん)
チューニングとムラ的共同体、そして「庭の全体性」
最後に、庭プロジェクトを主宰する宇野常寛はこれまでの議論を総括しつつ、住民による自主的なランドスケープ管理が陥りがちな「ムラ的共同体」の閉鎖性という課題や、より開かれたチューニングを可能にするためのルールデザインの重要性を指摘しました。
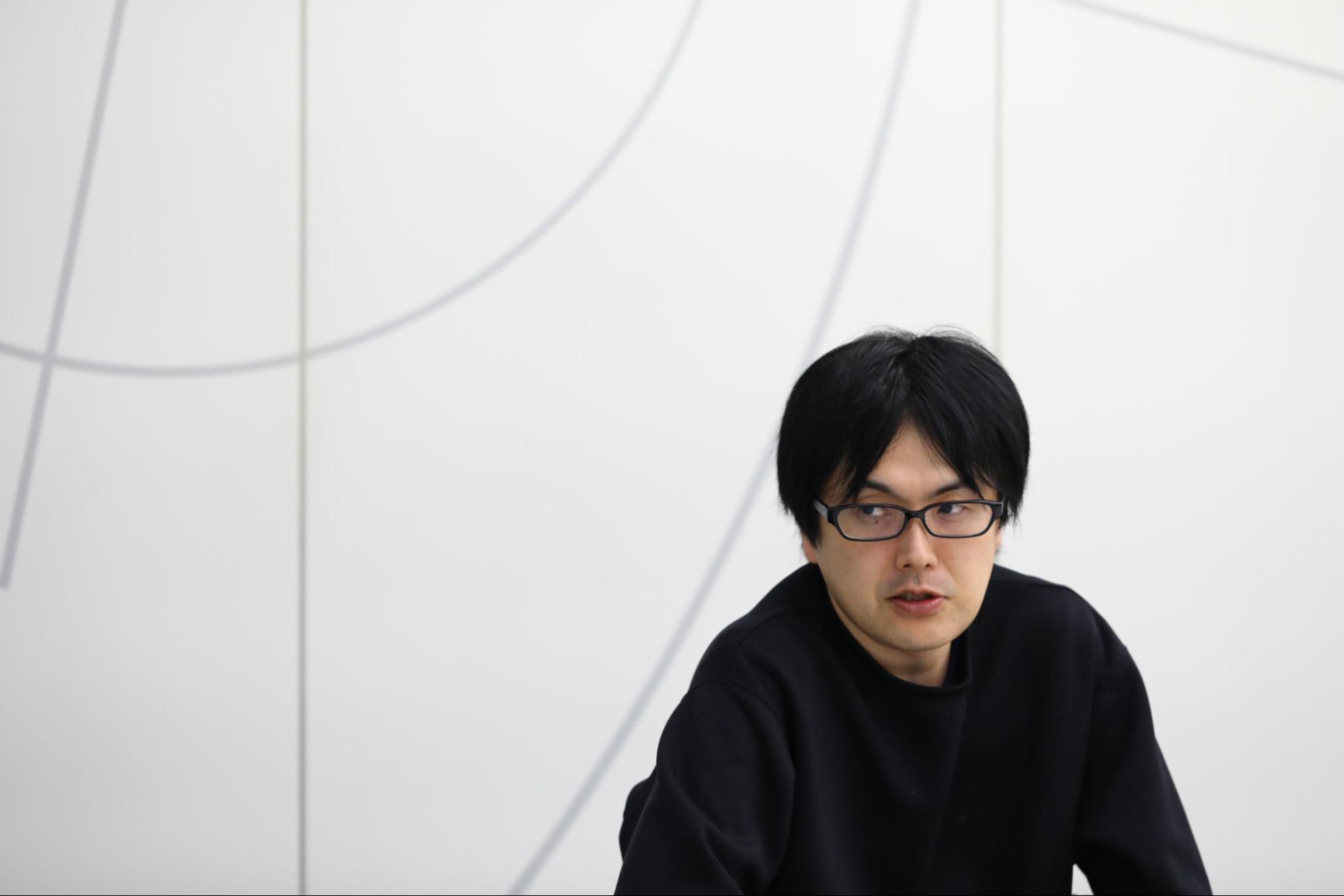
「今日のお話は、日本で緑を管理しようとすると、伝統的な日本庭園のような刈り込みがとりあえずの解になってしまう。そこで『そうではない』解としてチューニングという考え方が提案されるということだと理解しました。ただ、プレゼンテーションでご紹介いただいた戸山団地や多摩の団地の例のような場合に、住民による自主管理が、ムラ的共同体の同調圧力のようなものに繋がってしまうと嫌だなと思うんです。ここをどうお考えですか?
僕が小川さんが研究されているタンザニアの出稼ぎ商人たちの互助会を面白いと思うのは、ボトムアップに立ち上がったルールが共同体の『空気』による支配にならないように働いている点です。あれはルールで動いてるから、 WhatsAppやFacebookで管理できるのだと思います。このチューニングによる管理を、ムラ社会的な空気の支配ではないかたちで実現している例などありましたら、教えていただきたいです。
また僕の近刊『庭の話』ではジル・クレマンだけでなく『流域思考』の岸由二も引いていますが、岸さんの小網代の森での活動においては、雑木林が地元の住人と必ずしも関係ない人々の多い数十人規模の定期メンテナンスによって維持されている。この『小網代モデル』について、石川さんはどう評価されますか?
それから、庭的なものにコミットするのは全体的・総合的な体験だというお話がありましたが、あれは重要な指摘だと思います。おそらくいまの一般的な労働のスタイルは部分的なもので、ベルトコンベアの一部を担っている感覚はあっても、産業そのものやライフスタイルそのものを作っている手触りはない。そうした中で総合性を感じさせる世界との関与をいかにして日常に取り入れていくかを考えたときに、庭仕事のように、土に触れ、育て、収穫し、時には失敗も経験するという一連のプロセスが非常に魅力的に映るのだと思います。ただ、こうした総合性の与える充足は、偶然何かに出会ってしまうか、割と若い時期に何らかの事情で経験的に覚えてしまったというケース以外になかなか今日においては学習されないと思うんですね。言い換えれば僕たちはすっかり、生活世界から失われた総合性を、幻想領域において意味を与えられることで擬似的に回復する社会に生きている。国家や家族に生きがいを見出すとか、仕事そのものではなくて職場の人間関係で認められるとか、そういう回路ですよね。このギャップはどう埋めたらいいとお考えですか?」(宇野)
「まず自主管理のルールについてですが、戸山団地の事例では、初期に各戸の管理区画を明確に分けたことが、結果的にうまくいった要因の一つだと聞いています。つまり、空間の形状に託された形でわりとはっきりしたルールが存在したようです。『みんなで一緒に管理しましょう』という形だと、責任の所在が曖昧になり、不公平感から対立が生まれやすい。しかし、個人の領域をはっきりさせることで、各自が自分の庭として愛着を持ち、手入れをする。結果として、個々の営みが全体の良好なチューニングに繋がっていく、という形が理想なのかもしれません。
岸先生の『流域思考』は、まさにおっしゃる通り、重要な視点です。小網代の森がうまくいっている背景には、幸運な条件も重なりましたが、何より行政区画という枠組みを超えて、流域という自然の理に適った単位で環境を捉え、そこに住む人々が主体的に関わっている点が大きいと思います。水は行政区画などお構いなしに流れていきますから、その流れに沿って生態系全体を考えるというのは、トップダウンの計画ではなかなかできない、地面の側からの発想ですよね。
そして、土に触れる体験への導入ですが、やはり繰り返しになりますが、まずは私自身が楽しそうにやっている姿を見せること。そして、研究室の学生たちとの『ひまわりレース』のように、何か課題や遊びを通じて、知らず知らずのうちにその魅力にうっかり巻き込まれてしまうような仕掛けを考えることでしょうか。また、『庭の全体性』という言葉は、具体的な庭仕事だけでなく、もっと広く、現代社会で失われがちな『トータルな経験』とは何か、庭以外にもそうした体験の可能性があるのか、むしろいろいろな人に聞いていきたいテーマでもあります」(石川さん)
[了]
この記事は石堂実花・小池真幸が構成・編集をつとめ、2025年7月31日に公開しました。



