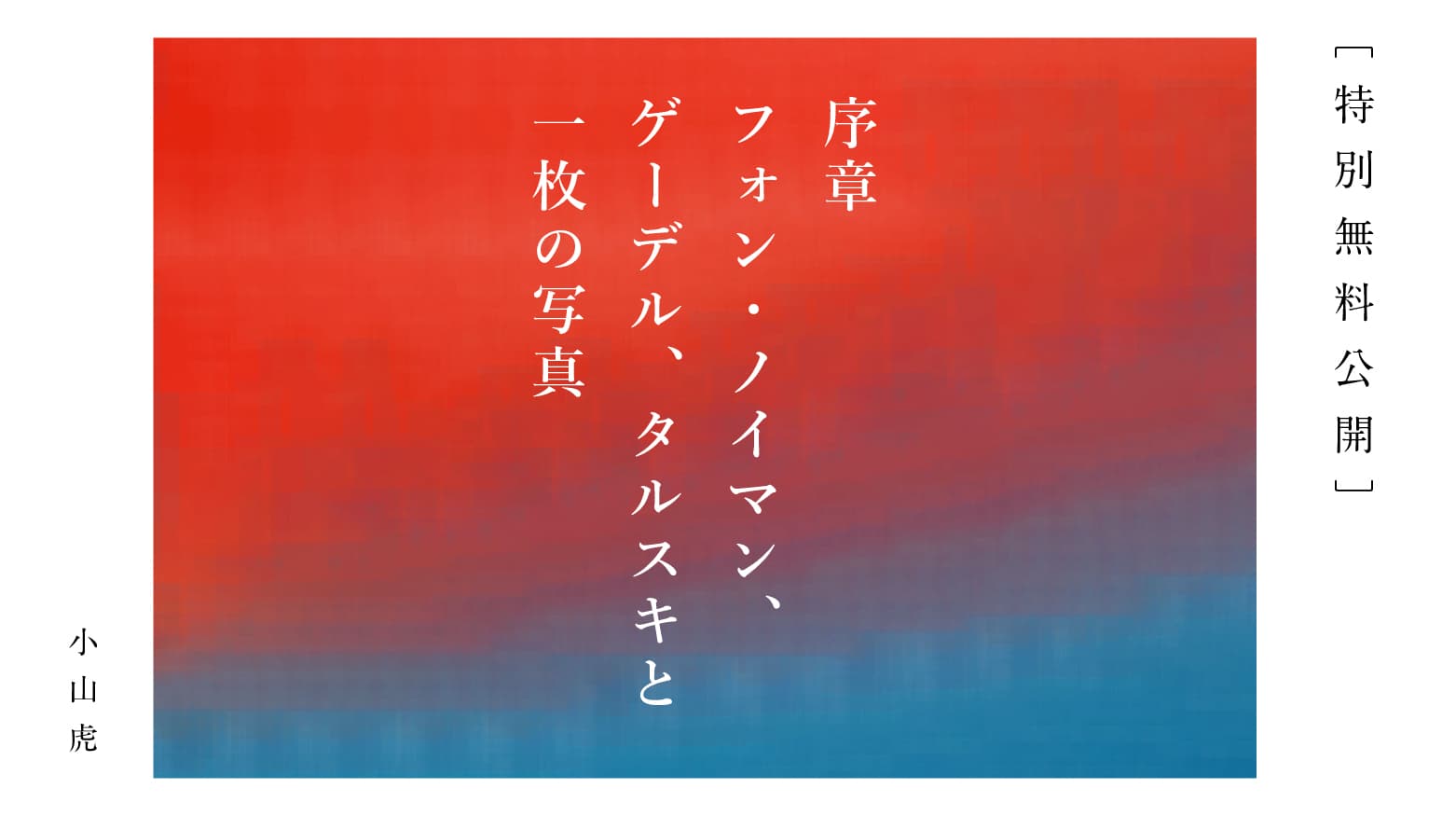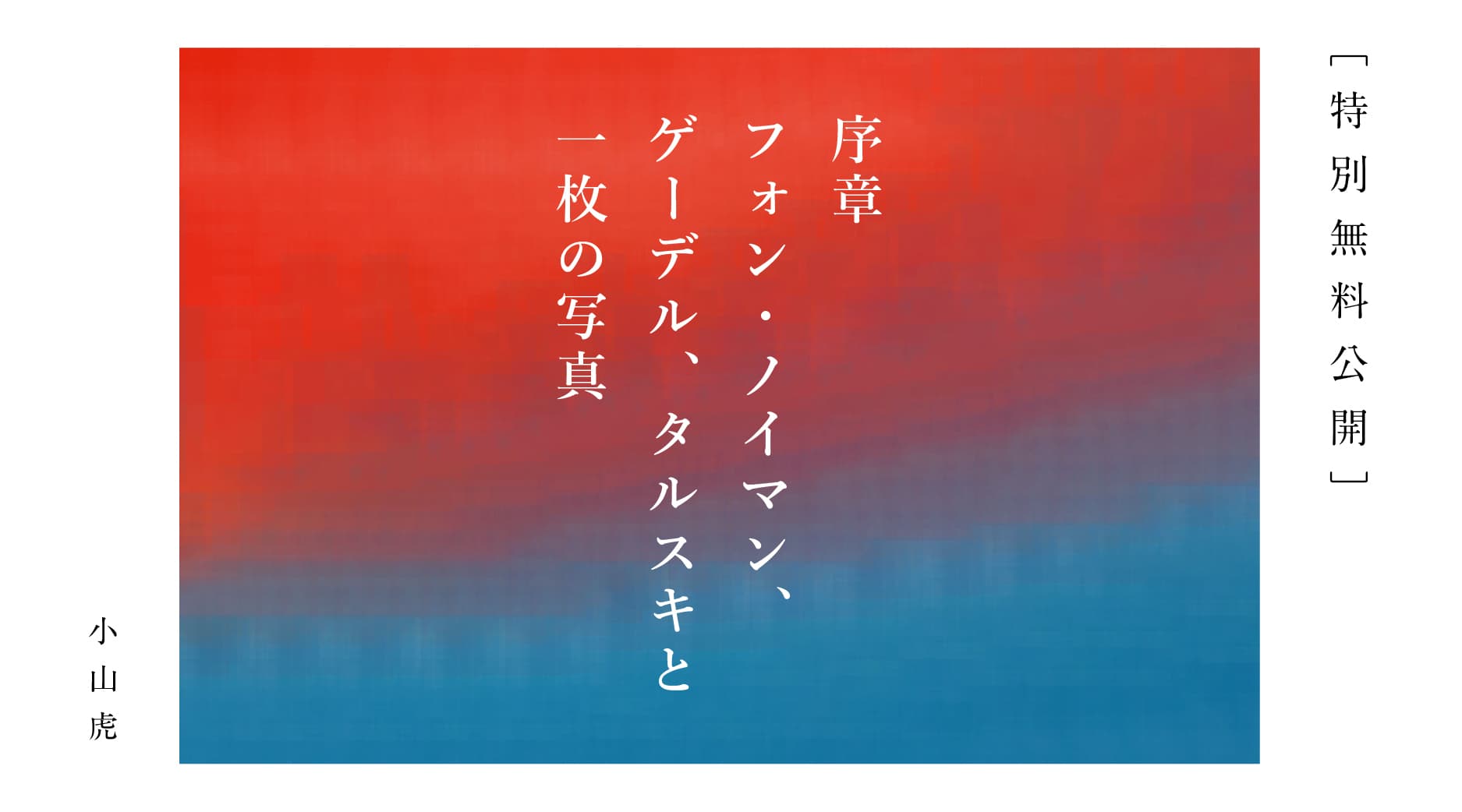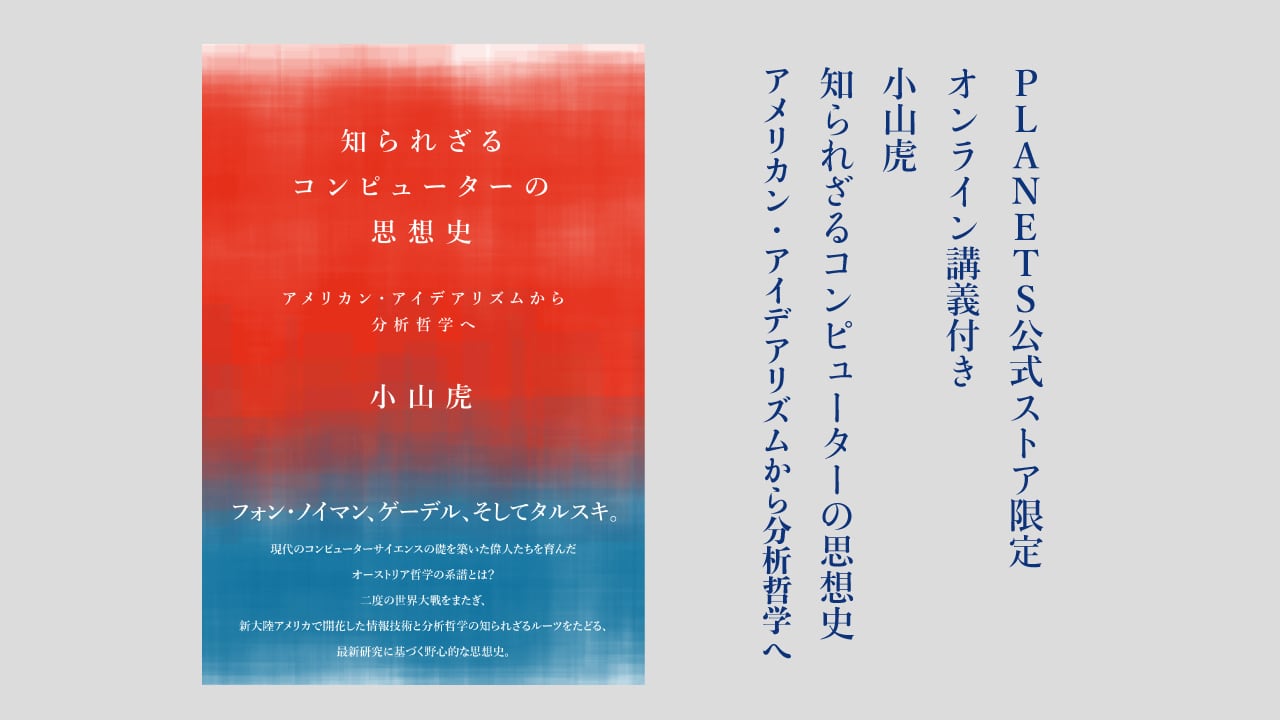ついに書籍化が決定した連載「知られざるコンピューターの思想史」より、連載時から大幅に加筆修正を加えた序章を全文無料公開します。
フォン・ノイマンやゲーデル、タルスキら現代のコンピューターサイエンスの礎を築いた偉人たちの「知られざる」系譜を追う本書。
序章では、ノイマン・ゲーデル・タルスキ3人が集ったとある学術会議から、コンピューターと思想史の重なりを明らかにします。
※PLANETS公式オンラインストアでは、限定特典として著者である小山虎さんが本書のポイントを解説するオンライン講義「100分de(本書のポイントがわかることで、ぐっと読みやすくなる)『知られざるコンピューターの思想史』」に無料でご招待します。
ご購入はこちら。
「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。
端的に言うとね。
1 1946年、プリンストン
一枚の写真がある。1946年9月にアメリカのプリンストン大学創立200周年を記念して開催された「The Problems of Mathematics(数学の諸問題)」という数学の会議での、参加者たちの記念撮影だ*1 。

この会議には当時の代表的な数学者が多数参加している。なかには読者が名前に記憶がある参加者もいることだろう。たとえば、右端から5人目、中段にいるジョン・フォン・ノイマン*2。ノイマン型のコンピューター・アーキテクチャにその名を残すだけでなく、ENIAC(Electronic Numerical IntegratorAnd Computer :最初期の電子計算機。米陸軍の依頼でペンシルベニア大学のジョン・モークリー、ジョン・エッカートらが主導して開発)を元にしたコンピューターをアメリカ各地に建造することを推進したことでも知られている彼は、第二次世界大戦で日本に投下された原子爆弾の開発計画であるマンハッタン・プロジェクトにも参加していた「応用」数学者だった。現在のコンピューター・サイエンスの全貌は「応用数学」の名前が与えるイメージよりはるかに巨大なものになっているのに対し、当時のそれはまだ数学とのつながりがかなり大きかったのである。フォン・ノイマンはこの会議で「新分野」と題されたセッションの座長を担当していた。
あるいは、フォン・ノイマンとは逆の左端から5人目、前から2列目にいるクルト・ゲーデル*3。不完全性定理という、あまりにも知られすぎたために多くの誤解を生み出したあの定理を証明した、20世紀、あるいは史上最大の数学者・論理学者である彼もまた、この会議に参加していた。
他にも著名な数学者、論理学者、物理学者、そして哲学者の顔が見られる。たとえば、ポール・ディラック、ヘルマン・ワイル、W・V・O・クワイン、アロンゾ・チャーチ、スティーヴン・クリーネ、J・C・C・ マッキンゼー、A・W・タッカー……本書のどこかでまた彼らに触れることになるかもしれないが、まずはフォン・ノイマンとゲーデルの間、フォン・ノイマンから左に5人目、ゲーデルから右に10人目にあたる、ある人物に焦点を当てたい。彼の名はアルフレッド・タルスキ*4。ゲーデルと並ぶ20世紀最大の論理学者とも呼ばれ、タルスキ型真理定義(意味論)やバナッハ・タルスキのパラドックスにその名を残し、幾何学の完全性証明やモデル論の基礎を築いたことで知られる彼のことは、哲学(とりわけ分析哲学)を学んだことのある人であれば聞いたことがあるはずだ。タルスキもまた、この会議に主要な参加者として招待されていたのである。 当時、1903年生まれのフォン・ノイマンは42歳、1906年生まれのゲーデルは40歳、1901年生まれのタルスキは45歳。この20世紀を代表する数学者・論理学者である3名は同年代でもあった。さらに、3人とも第一次世界大戦前、民族自決の激動に翻弄されていた中欧の生まれであり、母国で学位を取得した後、安定したポストに就く前の30代の時に、ナチス台頭によるユダヤ人迫害の影響でアメリカへ移民したという点でも共通している。
彼らのうち一人でも違う世代に生まれていたならば、あるいは、アメリカに移民してこなかったならば、20 世紀の数学の歴史だけでなく、コンピューターの発展にも大きな影響が出ていたに違いない。フォン・ノイマンだけでなく、ゲーデルもタルスキも初期のコンピューターの発展と無関係ではない。コンピューターは20世紀前半に大きく発展した数理論理学なしに生まれることはなく、ゲーデルとタルスキはフォン・ノイマン以上にそれに貢献したと言っても差し支えないからである。
本書では、この3人の邂逅に象徴されるアメリカのコンピューター・サイエンスの原点をめぐって、まだあまり知られていない思想史的背景をひもといていく。
現在のコンピューターやインターネット、あるいは人工知能といった情報技術の発展のルーツには、先述したマンハッタン・プロジェクトに代表される第二次世界大戦期の巨大軍事科学開発があることは、言うまでもないだろう。また、それが戦後にハッカー文化やヒッピーイズムといったカウンター・カルチャーの機運と結びつき、アラン・ケイやスティーブ・ジョブズなどによって体現されるような西海岸的なIT思想を生み落としていったという「物語」も、今ではよく知られるようになってきている。
しかし、分析哲学を専門とする筆者の視点では、それはあくまで一面に過ぎない*5。分析哲学とコンピューター・サイエンスは、その名を知っている人の多くにとってはまったく無縁なものだろうし、両者の共通点が指摘されることなどめったにないが、じつはどちらも19世紀ヨーロッパで生まれた数理論理学を源泉とし、戦後アメリカで本格的に発展した分野である。じっさい、戦後しばらく、まさにこの写真が撮影された1946年ごろまでは、分析哲学とコンピューター・サイエンスは互いに影響しあいながら発展してきた。たとえば、「コンピューターの父」と称されるアラン・チューリングは哲学者ウィトゲンシュタインの講義に出席しており、二人の間で熱心な議論がなされていたことが知られている*6。第二次大戦期の巨大科学と西海岸のカウンター・カルチャーの結びつきにしても、その背景に分析哲学の発展と通底する契機が見られるのである。
加えて、本書が進むにつれて明らかになっていくだろうが、その背景に、20世紀初頭の近代科学にキリスト教的世界観との衝突などさまざまな「危機」が生じていたことを受け、そのありかたを問い直す営みとして当時生まれつつあった新たな分野である科学哲学の存在があったことも無視できない。そして彼ら3人の結びつきもまた、数理論理学と科学哲学を介してのものだったのだ。
ところで、当然ながら、著名な数学者であるこの3人はこのプリンストンの会議で初めて出会ったわけではない。ただ、この3人が揃ったのはこの会議が最初かもしれない。少なくともアメリカでの公式な場としては、おそらく間違いない。3人のうち最後に移民したゲーデルがアメリカにたどり着いたのはすでに第二次世界大戦が始まっている1940年であり、この1946年のプリンストンでの会議は、アメリカでの戦後初の大規模な数学の会議として企画されたものだからである。
2 1930年、ケーニヒスベルクとウィーン

アルフレッド・タルスキ(1953年撮影)

クルト・ゲーデル(1925年撮影)

ジョン・フォン・ノイマン(1940年ごろ)
© Copyright Triad National Security,LLC. All Rights Reserved.
では、最初に彼ら3人が揃ったのはいつだろうか。ある資料によれば、1930年のドイツ・ケーニヒスベルクであるという。「厳密科学の認識論(Epistemology of Exact Sciences/ Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften)」と題された会議の2回目がその地で開催され、彼ら3人はそこに参加していたというのだ。もしかすると、読者の中には「ケーニヒスベルクの会議」でピンと来るほどくわしい人もいるかもしれないが、この会議こそ、ゲーデルが不完全性定理を初めて公表した、あの「ケーニヒスベルクの会議」である。当時ゲーデルはウィーン大学で博士号を取得したばかりであり、まだ大学で教えてさえいなかった(ゲーデルが「Habilitation」と呼ばれる博士号取得後に獲得できる大学教授資格を取得したのは1932年のことである)。それに対し、ゲーデルより3歳年長のフォン・ノイマンはすでに集合論の専門家として知られており、この会議にも招待講演者として呼ばれていた。当時の数学界の中心テーマの一つとして、数学の基礎づけという問題があり(現代では「数学基礎論」と呼ばれる分野が形成されるほどの発展を遂げている)、三つの主要な路線として、バートランド・ラッセルらの論理主義、ヤン・ブラウワーらの直観主義、ダフィット・ヒルベルトらの形式主義が知られていた。ゲッティンゲン大学でヒルベルトの指導のもと大学教授資格を取得したフォン・ノイマンは、形式主義の代表者としてこの会議に参加していたのである。
このときのフォン・ノイマンとゲーデルの会合は、もはや伝説となっている。ゲーデルが不完全性定理について言及したのは、形式主義の正しさを証明するプロジェクトである「ヒルベルトのプログラム」についてのディスカッションの中だという。しかし、その重要性に気づいた聴衆は、フォン・ノイマンただ一人だったとも言われるほど極めて少なかった。わずかな例外だったフォン・ノイマンはその詳細についてゲーデルに問い合わせ、さらに数ヶ月後には、ゲーデルが証明した不完全性定理から別の不完全性定理を証明することに成功した(前者は「第一」不完全性定理、後者は「第二」不完全性定理と呼ばれている)。そして後者の定理からは、ヒルベルトのプログラムを完全に遂行することは不可能であるという衝撃の事実が帰結するのである。ゲーデル本人も同じ定理を証明し、フォン・ノイマンの証明よりわずかに早く原稿が専門誌に受理されていたとは言え、これはフォン・ノイマンの超人的な能力を示す一エピソードとして知られている。
一方、タルスキはケーニヒスベルクで何をしていたのだろうか。
じつは、筆者の調べた限りでは、残念ながらタルスキはこの会議に参加していない。ただ、タルスキは当時すでにゲーデルと親しく、ゲーデル本人からケーニヒスベルクの会議、そして不完全性定理のことが書かれた手紙を受け取っている。タルスキも不完全性定理の重要性にただちに気づき、すぐさま翌1931年に地元の学会で発表するなど、早い段階から不完全性定理の浸透に一役買った。また、このケーニヒスベルクの会議はその後「統一科学国際会議」と名前を変え、第二次世界大戦が始まるまで定期的に開催されることになるが、タルスキはそのほとんどに参加している。おそらくこのことが、タルスキもケーニヒスベルクの会議に参加していたという誤解を生んだのであろう。
ところで、もしかすると、この「統一科学」という言葉に記憶がある読者もおられるかもしれない。当時「統一科学運動」というものがあった。それを先導していたのが論理実証主義の科学哲学者たち、いわゆる「ウィーン学団」である*7。ケーニヒスベルクの会議もまたウィーン学団による会議であり、数学の基礎づけと並ぶもう一つのテーマとして「量子力学の哲学的基礎」が掲げられていた。この当時のフォン・ノイマンがなした著名な業績の中に、量子力学の数学的基礎づけがあるのも偶然ではないだろう。
さきほど少し述べたが、この当時は科学の大きな変わり目だった。19世紀までに確立されていた近代科学は大きな成功を収め、それ以前の伝統に比べて確実な知を与えてくれることは明らかなように思われていた。しかし、20世紀に入ってから時代は大きく変わり始める。まず、ラッセルのパラドックスに代表される集合論のパラドックスの発見は、近代科学の確実さを保証している数学に基礎づけが必要であるということを広く知らしめた。
また、アインシュタインが一般相対性理論で非ユークリッド幾何学を採用したことにより、2000年近く君臨してきたユークリッド幾何学では、宇宙の構造を記述するのに不十分であることが明らかとなった。さらに、シュレディンガーらにより量子力学が生まれ、原子や電子のようなミクロの系に関しては、ニュートン力学によって得られていたような確実さは期待できないという認識が浸透していった。科学哲学は、こうした時代背景のなかで科学を捉え直す営みとして成立したものである。
そして統一科学運動は、数学を基礎づける中で発見された手法を利用して、経済学や心理学のような社会科学、歴史学や哲学のような人文学にも、自然科学と同等の厳密さを与えようとする試みだった。
フォン・ノイマンとゲーデルとの出会いが、数学の基礎づけを目的とする「ヒルベルトのプログラム」に関するディスカッションであり、ゲーデルの不完全性定理もそれに大きく関わるものであったことは上述の通りだ。また、タルスキの当時の業績の一つは、ユークリッド幾何学の「完全性」証明であり、その意味でユークリッド幾何学に基礎を与えるものだったといえよう。そして上述の量子力学に関するフォン・ノイマンの業績とは、それまで量子力学にはハイゼンベルクによるものとボルンによるものの二つの異なる定式化が与えられていたが、その両方に等価となる新たな数学的定式化を与えるものだった。このように、彼ら3人はそれぞれ、20世紀初頭の科学の大変化、およびそれに伴う人文社会学の激動の中で、大きな役目を果たしていたのだ。
「厳密科学の認識論」会議は、第1回が1929年にチェコのプラハで、第2回が翌1930年にケーニヒスベルクで開催された後はしばらく開催されることがなかったが、1934年にプラハで開催された第8回世界哲学会議に合わせ、「統一科学」と装いを新たにして国際会議として再開される。「統一科学」会議は、その後パリ、コペンハーゲン、イギリスのケンブリッジ大学、アメリカのハーバード大学で開催され、最後に1941年のシカゴ大学で開催されたのを最後に幕を閉じる。タルスキはこの会議の常連参加者だっただけではない。第二次世界大戦後この会議は、紆余曲折を経て、ユネスコ傘下の「科学史・科学哲学国際連合」の「論理学・方法論・哲学部門」として復活し、現在でも続いているのだが、1960年にアメリカ・スタンフォード大学で開催された第1回大会には、大会副実行委員長としてタルスキの顔があった*8。
3 1930年代のドイツ・ポーランド・オーストリア
さて、3人が初めて出会ったのがケーニヒスベルクではないとすれば、いつなのだろうか。とはいえ、フォン・ノイマンがゲーデルと出会ったのは、おそらくケーニヒスベルクの会議が最初である。じつは、フォン・ノイマンは大学教授資格こそドイツで取得し、ベルリン大学やハンブルク大学で教えていたものの、その後プリンストン大学で好待遇のポストを得ており、1930年ごろは年の半分はアメリカ、半分はドイツという生活を送っていた。ケーニヒスベルクの会議に参加できたのもこのためである。だが、この生活は1933年にナチスがドイツの政権を掌握した後に終わることになる。この1933年には戦後にアインシュタインやマンハッタン・プロジェクトを主導したロバート・オッペンハイマーによってアメリカ的な現代科学発展の立役者となるプリンストン高等研究所が設立され、フォン・ノイマンも最初のメンバーとなるのだが、これをきっかけに完全にアメリカに移住するのである*9。
タルスキとゲーデルの出会いも1930年。ただし、場所はウィーンである。この年の2月にタルスキがウィーン大学を訪問してセミナーを行っており、ゲーデルともこのときに出会っていたことがわかっている。タルスキは前述のように後にアメリカに移民するが、もともとはポーランド生まれであり、当時はワルシャワ在住だった。タルスキもフォン・ノイマン同様、若い頃から高い評価を得ていたが、大学で安定したポストを得ることはできておらず、高校で数学を教えるなどして生計を立てていた。ウィーン大学の数学者で、ウィーン学団のメンバーでもあるカール・メンガー(経済学のオーストリア学派の祖として知られる著名な経済学者のカール・メンガーは彼の父であり、スペルが異なる)が1929年にワルシャワ大学を訪問した際にタルスキと出会い、彼をウィーンに招待したのである。
メンガーの博士論文を指導したのはハンス・ハーンというウィーン学団創設時からのメンバーでもある数学者であり、彼がメンガーを学団の会合に誘ったのだが、ハーンはゲーデルの博士論文の指導者でもあった。こうしたつながりもあり、メンガーが企画したウィーンでのタルスキのセミナーには当然ハーンもゲーデルも参加した。さらにゲーデルは、その後メンガーに頼んでタルスキとプライベートで会う機会もつくってもらうほどだった。
タルスキとフォン・ノイマンとの出会いはあまり定かではないのだが、おそらく1929年だ。この年の9月、ポーランドの首都ワルシャワで、第1回スラブ国家数学者会議という数学の国際会議が開催されたのだが、この会議にタルスキは参加しており、フォン・ノイマンは数少ないドイツからの招待講演者の一人だった*10。
この最初の出会いからしばらくの間、タルスキとフォン・ノイマンに会う機会があったとは考えにくい。タルスキがポーランド国外の数学者と交流を持つのは上述のウィーン訪問からである。その後タルスキは1935年にロックフェラー財団の奨学金を得てウィーンに半年間滞在するなど、ヨーロッパ各地に積極的に赴くが、フォン・ノイマンは1933年以降、ヨーロッパにあまり戻ってこなくなる。タルスキが母国で安定したポストを手に入れることができず、フォン・ノイマンが年の半分しかヨーロッパにいなかったことを考えれば、1930年から1933年までにタルスキがポーランド国外でフォン・ノイマンと会うチャンスはまずなかったと言ってよいだろう*11。
加えて、当時のポーランドとドイツの関係は良好とは言えない。ドイツは第一次世界大戦の敗北により、領土の一部がポーランド領になった。このポーランド領は「ポーランド回廊」と呼ばれているが、これが意味することの一つは、ドイツ領の一部が「ポーランド回廊」を挟んだ飛び地になることだった。この飛び地にはケーニヒスベルクのある東プロイセンも含まれており、当時広まっていたドイツ民族主義からすれば認めがたい事実だったはずであり、多くのドイツ人知識人もポーランドには非友好的だったという。フォン・ノイマンはプリンストン移籍後もドイツの大学に籍を残していたものの、こうしたドイツとポーランドの緊張関係の中で、わざわざポーランドを訪れる理由はなかったはずである。
興味深いのは、メンガーのワルシャワ訪問である。どうしてメンガーはワルシャワを訪れたのだろうか*12。それは彼の父(すなわち経済学者の方のカール・メンガー)の出身地がポーランドだったことと関係している。そもそもメンガーは生まれも育ちもウィーンだったが、彼の父の故郷は父方の親族がいるだけでなく、その地域は第一次世界大戦前までは同じオーストリア・ハンガリー帝国に属していた(だから彼の父は首都のウィーン大学で学ぶことになるわけである)。そうした彼にとって、ドイツのポーランドに対する民族主義的な敵愾心は無縁であり、だからこそポーランドの数学者と交流することも、彼らからの誘いを受けてワルシャワ大学を訪問することもできたのである。このことは、現代の我々が忘れがちな世界史上の事実を思い起こさせてくれる。第一次世界大戦までのオーストリアは大国であり、1871年に普仏戦争で勝利したプロイセンが統一ドイツ帝国となる(プロイセン王がドイツ皇帝を兼ねるようになる)までは、プロイセンとドイツ統一を競っていたことを。
タルスキは1939年に渡米する。1933年にワルシャワを訪問したアメリカ人哲学者クワインの強い誘いを受け、ハーバード大学で開催される第5回統一科学国際会議に参加するためである。同じ船には、ポーランド人数学者のスタニスワフ・ウラムが乗り合わせていた*13。ウラムは当時プリンストン高等研究所でフォン・ノイマンのもとで働いていた(のちにマンハッタン・プロジェクトにも関わることになる)。ニューヨークに着いたタルスキらには二人の出迎えがいた。タルスキを出迎えたのは、ウィーン学団とともに統一科学国際会議を開催していたベルリンの科学哲学者グループに属し、一足早くアメリカに移住していたカール・グスタフ・ヘンペル。彼は後にプリンストン大学の哲学科をアメリカ科学哲学・分析哲学の拠点の一つにまで育て上げる。そしてウラムの出迎えとしてヘンペルと共にタルスキの前に現れたもう一人は、フォン・ノイマンその人だった。おそらくこれが、タルスキとフォン・ノイマンの生涯二度目の出会いだったろう。
ゲーデルが本格的に渡米するのは翌年の1940年。それ以前に何度か訪問していたプリンストン高等研究所にポストを得る。1941年にはタルスキもグッゲンハイム・フェローとして一時的に同研究所に所属し、両者は旧交を温めるが、タルスキは1942年の夏にプリンストンを離れる。カリフォルニア大学バークレー校で比較的安定したポストを得ることができたためだ。フォン・ノイマンもプリンストン高等研究所に所属していたため、どこかでこの3人が顔を揃える機会があったという可能性は否定できない*14。だが、3人が揃ってプリンストン高等研究所に所属していたのは1年ほどに過ぎない。そして1957年にフォン・ノイマンは他界する。もしかすると、あの写真が撮られた1946年のプリンストンの会議は、彼ら3人が揃った最初で最後の機会だったのかもしれない。
フォン・ノイマン、ゲーデル、タルスキ。この20世紀を代表する3名の数学者が同世代であり、みな中欧生まれであることはすでに述べたが、それだけではない。じつは3人とも「オーストリア的」教育を受けている。フォン・ノイマンが生まれたのは、当時はオーストリア・ハンガリー帝国領だったブダペストであり、またブダペスト大学で博士号を取得している(ベルリン大学でヒルベルトの指導を受けるのは博士号取得後のことである)。ゲーデルはこれも当時はオーストリア領だったチェコで生まれ、そして首都であるウィーン大学で博士号を取得した。タルスキがポーランド生まれであることはすでに述べたが、彼はワルシャワ生まれであり、ワルシャワ大学で博士号を取得している。ワルシャワはオーストリア領ではなかったが、タルスキの博士論文を指導した哲学者のスタニスワフ・レシニェフスキをはじめ、当時のワルシャワ大学はオーストリア領内の大学で学位を取得した教員で占められていた。
彼ら3人がみなアメリカに移住し、大きな影響力を残した背景には、ドイツとオーストリアの関係、数学と科学哲学の関係、戦前と戦後でのアメリカ哲学の変化、アメリカ大学制度の変遷など、多岐にわたる要因があるが、これをあえてひとことで述べるならば、「オーストリア的」なもののヨーロッパからアメリカへの移行である。20世紀前半に起きた数学、物理学を中心とする科学の大変革は、19世紀までに確立されていた西洋近代科学が迎えた「危機」と、それを克服するための努力から生まれたものであり、数理論理学と科学哲学もその克服の過程で誕生した。そして、これらはすべてヨーロッパ、とりわけドイツを中心として起きたのである。
しかし、周知のように、第二次世界大戦後、科学の中心はアメリカへと移行し、アメリカ固有の背景のもとで我々の知る現代科学が確立されることになる。それにともない、数理論理学と科学哲学もアメリカへと主軸を移すことになり、同様の変遷を遂げ、コンピューター・サイエンスと分析哲学の発展を大きく促すことになる。フォン・ノイマン、ゲーデル、タルスキの3人はその際に大きな役割を果たすのだが、これは、さまざまな分野で「オーストリア的」な背景を持つ学者が活躍の場をドイツからアメリカに移したことの象徴的事例なのである。
本書でこれから試みられるのは、19世紀から20世紀にかけて行われた「オーストリア的」なもののヨーロッパからアメリカへの移行を、コンピューター・サイエンスと分析哲学という、一見何の関係もなさそうに見える二つの学問の複雑に絡み合った成立史として描き出すことである。そのため本書は、第Ⅰ部「ヨーロッパ編」、第Ⅱ部「アメリカ編」、第Ⅲ部「コンピューター編」の3部で構成されている。各部の概要を以下に示しておこう。
第Ⅰ部「ヨーロッパ編」は、「オーストリア的」な知が誕生した19世紀から20世紀前半にかけてのヨーロッパが舞台だ。周知のように、コンピューター・サイエンスは第二次世界大戦後のアメリカで成立するが、その下地は「オーストリア的」と対をなす「ドイツ的」な数学と哲学によって第二次世界大戦以前につくりだされていた。「オーストリア的」な知によって育まれたフォン・ノイマン、ゲーデル、タルスキの3名は、一方でそうした「ドイツ的」な数学と哲学ともかかわりあいながら、最終的には、第二次世界大戦が近づきつつあった生まれ故郷のヨーロッパを離れ、アメリカへと移住することになるのである。
第Ⅱ部「アメリカ編」は彼ら3名を受け入れることになったアメリカの知的風土を紐解く。19世紀後半、アメリカは植民地時代から続くイギリスからの影響を脱しつつあった。それが決定的になったのは南北戦争後だ。ドイツを範とする新たな国づくりがあちこちで進められ、ヘーゲルに代表されるドイツ哲学は、それを支える思想として確固たる地位を築く。ドイツ型の大学教育の輸入はそうしたドイツを範とする新たな国づくりに拍車をかけるものだった。その一方で、南北戦争後のアメリカには、オーストリアとその周辺地域から貧しい移民が大量に押し寄せており、特に中西部とニューヨークは、そうした新たな移民たちの安住の地となっていた。フォン・ノイマン、ゲーデル、タルスキの3名を受け入れたアメリカとは、このように、「ドイツ的」なものの上に「オーストリア的」なものが根付きつつあった土地だったのだ。
第Ⅲ部「コンピューター編」では、第Ⅰ部と第Ⅱ部で描かれた背景を踏まえつつ、黎明期のコンピューター・サイエンスの足跡をたどる。その背景にあるのは、20世紀のアメリカで確立された、旧来のヨーロッパの大学とは異なる新たな大学のありかただ。人工知能研究の拠点として知られるMITとスタンフォードは、軍や政府、あるいは産業界から資金を得ることによって、無名の一大学から世界トップクラスの大学へと躍進した新たな大学の代表だ。コンピューター・サイエンスや人工知能、あるいは分析哲学といった20世紀後半のアメリカで花開いた新たな学問分野の成立は、こうした20世紀型の新たな大学像の成立と切っても切り離せないものなのである。
ところで、「オーストリア的」とはいったいどのようなことを意味するのだろうか。まずはここから話を始めたいと思う。「オーストリア的」とは何かを理解する上で鍵になるのは、もしかすると意外かもしれないが、2人の歴史的哲学者、カントとアリストテレスである。
*1 この会議の詳細については、Hourya Benis Sinaceur. (2000). “Address at the Princeton University Bicentennial Conference on Problems of Mathematics.” Bulletin of Symbolic Logic, 6(1), 1-44. を見られたい。
*2 本書を通じて、フォン・ノイマンの生涯については、https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Von_Neumann/ に従う。
*3 本書を通じて、ゲーデルの生涯については、ジョン・W・ドーソンJr.(村上祐子・塩谷賢訳)『ロジカル・ディレンマ ゲーデルの生涯と不完全性定理』(新曜社、2006年)に従う。
*4 本書を通じて、タルスキの生涯については、Anita Burdman Feferman and Solomon Feferman. (2004). Alfred Tarski: Life and Logic, Cambridge University Press. に従う。
*5 読者の中には分析哲学(analytic philosophy)についてご存じない方もおられるだろうが、分析哲学とはどういうものかを手短かに説明するのはとても難しい。むしろ、多くの入門書でされているように分析哲学を特定の方法論やスタイルとして特徴づけるのはよくない、というのが本書のスタンスである。とりあえずは、分析哲学もコンピューター・サイエンスや人工知能と同じように20世紀後半にアメリカで確立された学問分野の一つと考えていただければ十分である。
*6 本書を通じて、チューリングの経歴については、伊藤和行(編)・佐野勝彦・杉本舞(翻訳、解説)『コンピューター理論の起源 第 1 巻 チューリング』(近代科 学社、2014 年)に従う。チューリングとウィトゲンシュタインについては、序章「チューリングの人生と業績」、5頁で言及されている。
*7 ウィーン学団については、第3章を見よ。
*8 科学史・科学哲学国際連合の論理学・方法論・哲学部門については、https://dlmps.org/ を見られたい。ちなみに、2019年大会はそれこそ1934年以来のプラハ開催だった。
*9 プリンストン高等研究所の設立経緯については、第11章第4節を見よ。
*10 この点については、Ryan Stansifer. (1984). “Presburger’s Article on Integer Arithmetic: Remarks and Translation.” Technical Report. Department of Computer Science, Cornell University, 1-2. を見よ。ただし、フォン・ノイマンの友人で、タルスキが渡米した船に乗り合わせていたポーランド人数学者ウラムの自伝によれば、フォン・ノイマンは1927年にもポーランドのルヴフを訪れており、もしかするとこの時にタルスキと出会っていたかもしれない。Stanisław M. Ulam. (1991). Adventures of A Mathematician, University of California Press., 23. を見よ。
*11 ウラムによれば、フォン・ノイマンは1935年にワルシャワ、1937年にルヴフに招かれて講演しているが、そこにタルスキはいなかったようである(Ulam (1991), 66-67, 107-109)。
*12 タルスキがウィーンを訪れる経緯については、Karl Menger. (L. Golland, B. McGuiness, and A Sklar (eds.).) (1994). Reminiscences of the Vienna Circle and the Mathematical Colloquium. Springer, ch.12 を見よ。
*13 ウラムの生涯については、Ulam (1991)を見よ。
*14 ゲーデルはプリンストン到着後、研究に関するディスカッションをノートに記録し始めるようになるが、ゲーデルの性格もあってか、その多くは旧知のタルスキ、そしてフォン・ノイマンとのディスカッションだったとのことである。Jan von Plato. (2021). “Von Neumann Explains His Game Theory to Gödel,September 1940.” Mathematical Intelligencer, 43, 42–44. を見よ。
[続く]