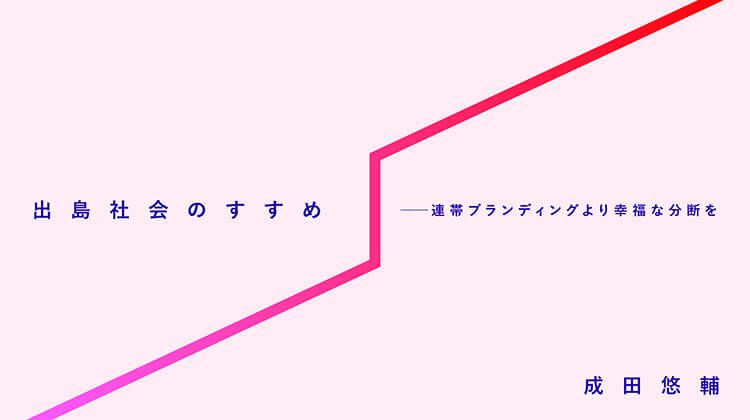混迷をきわめた米国大統領選は、いま民主主義社会が直面している「分断」の深刻さを、世界中の人々に改めて印象づける出来事になりました。危機感をおぼえる良識的な人々は、この状況を乗り越えていくための「連帯」を呼びかけますが、その問題設定そのものに、かえって問題の根が潜んではいないか。イェール大学助教授で経済学者の成田悠輔さんが、むしろ分断を徹底化する「出島社会」を提案します。
端的に言うとね。
社会の分断をしっかりと推し進めていこう。そういう話をしたい。奇をてらった逆張りではない。素朴な肌感にしたがった素直な結論だ。数千年前に語られていたような。
「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。
さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよう。
こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。
これによってその町の名は喧騒と呼ばれた。」(旧約聖書)
言語と文化の統合により高い塔を建設、天に近づこうとする人類への神の一撃を通して、多様な言語の喧騒の本質性を暗示する。乱された言葉たちの交わらない喧騒を表す言葉が「バベル(babel)」だ。
気持ち悪い壁
コロナ鎖国で日本に島流しされる前、私は米国東海岸のイェール大学の大学街ニューヘイブンに住んでいた。研究室はかつてマーク・トウェインが「全米でもっとも美しい道」と呼んだ緑路に佇むどっしりとした一軒家にあり、この家はかつてブッシュ大統領親子一家の自宅だった。この道を中心に広がる大学キャンパスは表情豊かな学生や教職員ばかり、98%白人かアジア人だ。
だが、キャンパスから逸れて歩くことほんの数分、ある道を1本越すと、突然ほぼ全員黒人の寂寥とした住宅街が出現する。無邪気に散歩していてこの場所に紛れ込み、黒人盆踊りとでも呼ぶべきお祭りに遭遇したことがある。聞いたことのない爆音楽にサンバの衣装のチンドン屋のような謎ダンス。溢れかえる数百人の中で黒い肌を持たない者は私だけだったと思う。ここにあるのは黒と白を隔てる空間の壁──私はさしずめ壁にぶつかった黄色いハエだった。濃い色の肌を持つ友人の女性法学者は、この大学街を「気持ち悪い(creepy)」と評す。
ところ変わって、2019年から20年にかけてはイェール大学での業務から解放され、西海岸のスタンフォード大学の訪問教員をした。スタンフォードを囲むシリコンバレー地域は世界で最も物価が高い場所の一つで、東京のど真ん中と比べ体感で2〜3倍。私も1DKの小さな部屋に月4000ドル以上(45万円くらい)の家賃を注ぎ込んでいた。
ショッピングモールと映画館に挟まれプラモデルのように人工的だったマンションの外には、ソファーベンチが置かれていた。住人が車を待つのに腰かけるためだ。ちなみにFacebookの本社にも車を待つ専用ソファがある。こちらはフカフカ、さらにパラソル付きだ。
だが、夜中になると空気が一変。夜の冷たくパサパサした空気に誘われて、家財道具入りのゴミ袋を抱えたホームレスがどこからともなく現れる。物価の高波に家を押し流された彼らの寝床は、ソファーベンチだ。ここにあるのは、時間の壁である。
見える壁、見えない壁
東西二つの大学街の時間の壁と空間の壁には共通点がある。生活していればふと目に入る、見える壁だという点だ。
しかし、壁はやがて見えなくなる。一人ひとりが経験する時空間は仮想化され個人化され、知る必要やメリットや喜びのある出来事で埋め尽くされていく。逆にメリットのない出来事は、黒人盆踊りも車待ちソファーで眠るホームレスも、私たちの時空間から消去されていく。知らない方が幸福だからだ。
見える壁と見えない壁、どちらが「気持ち悪い」だろうか? その問題に答えるには、しかし、壁をもうちょっと解像度高く凝視してみる必要がある。
分断とは何か
社会的分断を心配する声をよく聞くようになった。断絶といっても、格差といっても、気分としては同じことだ。
しかし、「分断」とは何だろうか? この言葉には多彩な意味がこもっている。たとえば経済格差。トップ◯%の所得が全体に占める割合とか、資産の上位半分と下位半分の差が広がっているといった話だ。アメリカを見れば、そして2012年頃までの数十年間を見れば、たしかに経済格差は拡大してきた。
政治的断絶もある。保守派とリベラル派の政治的イデオロギーがどんどん先鋭化し、二極化しているといった話だ。これもアメリカを見れば、たしかにその傾向があるようだ。
政治と経済のツートップだけではない。生命の格差もある。住む場所や経済状態によって健康状態や寿命は驚くほど違う。アメリカでは、所得が下位半分の中高年白人男性(要は貧乏なおっさん)の寿命がここ数十年で「落ちて」いるという痛恨の事実が知られている。
さらに、体の客観的状態が同じでも、教育水準の低い人ほど体が痛いと訴えがちらしい。なぜか? 調べてみたら、教育水準の低い人ほど肉体労働に就いていて、体の酷使が痛みを引き起こしているからだという。目に見えない心や体の痛みの不平等に、今の医療制度は何もできていない。
百の分断、百の格差、百の断絶がある。
しかし一方、アメリカから視野を広げて世界や日本に目を向ければ、違った光景が広がる。経済格差の様々な指標では、そもそもアメリカもこの10年弱でほとんど変化がない。世界平均ではここ20年ほど変わりないか、むしろ格差が縮まってさえいる。日本の経済格差も拡大していないことが知られている。日本が直面しているのは、格差拡大ではなく一億総貧困化だ。
政治的断絶も同じである。見出し力ゼロの退屈な事実だが、政治的イデオロギーは二極化している国もあれば逆に均一化している国もあり、ケースバイケースとしかいいようがないことが示されている。
分断の深度は、定義や場所によって様々だ。世界を支配する単一の「分断」などない。当たり前と言えば当たり前な事実が浮かび上がってくる。
分断扇動マーケティング、そして私もまた扇動者
分断はあるともないとも言える。にもかかわらず、アメリカばかりか日本でも分断への懸念がざっくり高まっているのはなぜか? それは悪意、そして悪意の放置によって分断が増幅されていると考える人が増えているからだろう。
情報・コミュニケーションの独占流通業者になったSNS、そしてSNS上を駆け回って金と票になるユーザーの目と手を貪り回るCambridge Analyticaのようなどぶネズミ代理店。彼らの悪行が、人々の感情と行動を操作し、分断を先導し、大統領選をはじめ重大な行事や意思決定を牛耳っていると多くの人が信じはじめている。映画『グレート・ハック: SNS史上最悪のスキャンダル』にも描かれた通りだ。
しかし、何か引っかかる。どぶネズミの悪意やどぶネズミを泳がせる独占プラットフォーマーの未必の故意を雄弁に告発する声にもかかわらず、告発の根拠は驚くほど乏しいことだ。『グレート・ハック』でも、根拠の中心は元Cambridge Analytica勤務のおばちゃんの勇気ある証言。具体的に何をどうやったのか、それがどれほどの影響を持ったのかの検証はほぼ何もない。
実のところ、Facebook上のフェイクニュースは過去の大統領選の結果を左右するには程遠かったようだという研究がある。Twitterも大統領選の大勢には影響なさそうだという解析もある。「ソーシャルメディアが選挙を操作してる」という自称情報強者の鉄板ネタ自体が、ソーシャルメディアによって作られている可能性があることになる。私たちは操られているのか、あるいは操られていると妄想するように操られているだけなのか。ますますややこしい。
そう考えていくと、本当の敵は分断やその首謀者ではないのかもしれない。
問題は断絶や格差そのものではない。むしろそれらに関する人々の認知ゲームの構造こそが問題である。自分で大衆を操作したことがあるわけでもなければ、大衆が操作されているとデータをいじって確かめたわけでもない者に限って、フェイクニュースに感染する情弱を哀れみはじめる。その根拠はドキュメンタリーと新聞雑誌で手に入れた2時間分の知識、そして友達との雑談での信念強化だ。しかし、哀れむ彼らがフェイクニュース信者でないという根拠は、実は驚くほど薄い。
そしてこう思う。真の敵は私たち自身の認知の歪み、必要なのは歪みを除去するためのもっと徹底した分断だ、と。
格差は成長痛
なぜ分断を徹底すべきなのか? 分断は幸せに生きることの副産物だからだ。そもそも格差や断絶は豊かになることと表裏一体だ。 経済成長が続く局面では格差が広がりがちだという歴史的な事実は、ピケティ『21 世紀の資本』やシャイデル『暴力と不平等の人類史』などを引くまでもなく、古くから知られている。成長の兄弟としての格差に抵抗できるのは、戦争や疫病、ハイパーインフレなど、全員を痛めつけてふりだしに戻るパルプンテ的不幸でしかない。
格差を糾弾するなら、では戦争・疫病・恐慌などの焦土戦の覚悟はあるのかと問わなければならない。格差は進歩の排泄物であって、排泄物は醜く臭いかもしれないが、その醜さを取り除くには主を殺すしかない。
世界は広い
さらに、良いか悪いか以前に、世界は人間が他者の圧倒的多様性と向き合えるようにできていない。
仮に1日に100人の他者と対話し連帯を深めたとしよう。1日も欠かすことなく100年続けたとして、100人×365日×100年=365万人、静岡県の人口にわずかに届かないくらいだ。100年間全力疾走で連帯を続け、結べる絆は地球の片隅の日本の片隅の静岡程度(静岡の皆さんすいません)。
ずいぶんと頭の悪そうな計算ではあるが、これはクソリプ的な揚げ足取りだろうか? 私はそう思わない。コミュニケーション総量の耐えられない有限性こそ、死にゆく生物に刻み込まれた本質の一つである。私たちは世界はおろか同じ種のメンバーについてさえほぼ何も知らずに死んでいくことを運命づけられている。生きて死ぬことは他者から分断されることそのものなのだ。
次元の呪い
連帯を深めた少数の同志たちの足元にも地雷が埋もれている。米国の多くの企業や大学の採用では「男を一人採ったら女も必ず一人採る」のような厳格な男女平等が有言実行されている。過去半世紀にわたり多くの人々を社会的に血祭りにあげて遂行されてきた多様性革命の賜物だ。
「日本とは大違い!」といいたいところだが、そしてそれは正しいが、その結果なにか奇妙なことが起きている。勝ち取られた「女性枠」が「肌は白めで、髪は金か茶で、なんかキレイ目な人」で埋め尽くされているように見えるのだ。目の錯覚だったらお詫びする。
もはや物理法則かもしれない。ある次元で差別を撤廃すればするほど、他の次元に差別が溜まっていく。たとえば、PaypalやPalantirを興して『ゼロ・トゥ・ワン』を著した起業・投資の哲人で、トランプ大統領の公然支持者としても知られるピーター・ティール。彼はスタンフォード大学の学生だった1980年代後半、当時立ち上がりはじめた多様性運動に「反対」する運動を組織していたことで知られる。女性や少数民族の登用、教育内容の西洋中心主義脱却といった当時の先進潮流に表立って反対したティールは、今でもこう迫る。「見た目や属性の多様性を自己目的化した先に待つのは内容や思考の単調性でしかない」と。
あらゆる選択は差別であり、分断である。差別をなくすには、選択をなくしサイコロをふるか、窓際で何もせずに佇むしかない。分断をなくしたければ全人類をミキサーでぐちゃぐちゃに混ぜるか、脳を電線で繋いで一緒に感電するしかない。厨二的極論かもしれないが、厨二でもわかる真実もある。
壁、ホロコースト、ブランディング
人類はバカではないので、分断の不可避性に古くから気づいていた。避けがたい分断を抱きしめながら他者とかりそめの「共生」をする方法を、人類は三つ発明した。壁、ホロコースト、そしてブランディングだ。
汚い肌をして鼻につく臭いを発しながらわけのわからない言葉をまくしたてる連中は気持ち悪い。私たちはまずそう感じてしまい、それを抑圧してなかったことにして微笑するエチケットを身につけたり、逆に開き直ってヘイトデモで派手に炸裂させたりする生き物だ。抑圧や炸裂を社会的な制度や文化にすれば、三つの共生の作法のどれかに行き着く。
ホロコースト: 「だから気持ち悪い異人は根絶やしにしよう」
壁:「見ないで済むよう視界の彼方に追いやって忘れよう」
ブランディング: 「本能に逆らって気持ち悪さを受け入れ、その立派な振舞いで補助金か賞をもらおう」
ホロコーストが大規模化した政治経済と化学反応するといかに苛烈な悪夢を生み出すか、過去数百年をかけて人類は学んだ(が、再び忘れかけているようにも見える)。
とすると残る選択肢は二つ。ブランディングは今世紀のオシャレである。多様性な他者との対話と共存を尊び、分断解消を謳う組織や個人がガールズバーのキャッチ並みの乱立状態だ。「無数の分断線を埋めるにはどうしたらいいのか、社会が全体として考えなくてはならない」(ある国会議員の所信)。「社会の分断に挑む」(あるスタートアップの所信)。
しかし皮肉である。政治的分断解消PRが成功すればするほど、その成功は広告・クーポン・寄付収入として蓄えられ、経済的格差に貢献する。ある分断を憂うエリートが別の分断の権化になる、分断解消ブランディングの逆説がここにある。忘れてはならない。今ではトランプという爆弾に着火した戦犯として吊し上げられている民主党的な偽善リベラリズムも、つい5年前までは人種間の断絶を乗り越えて初の黒人大統領を実現した英雄だと見なされていたことを。
問題は根深い。たとえば米国の名門は人種差別と深い関係にある。冒頭で触れたイェール大学の創設者エライヒュー・イェール氏も、実は奴隷貿易で財をなした事業家で、その財がイェール大学の起源にある。他の米国の名門組織にもほぼ必ず似た黒歴史がある。今では当たり前にリベラルな名門エリートたちが名刺代わりのマイノリティ登用や格差是正を合唱すればするほど「差別のない世界だと気分がいい。だが差別で稼いだ特権と資産は手放したくない」という二枚舌になってしまう。断絶で儲けた者たちだけが断絶と戦うチケットを手に入れられるという地獄である。
「愛ってやつはコレクションじゃない ましてやファッションじゃないでしょ」(小出祐介・岡村靖幸「愛はおしゃれじゃない」)
身を切らないおしゃれとしての連帯ブランディングも、愛ではないだろう。
残る唯一の道は壁だ。壁が求められている。数学者の望月新一(宇宙際タイヒミューラー理論を開発し、そのちょっとした帰結としてABC予想を解決したとされる)は、テレビや新聞の取材は固辞しながら、「新一の『心の一票』」と題された自身の楽天ブログでは饒舌なことが知られている。新垣結衣をはじめ社会の重要問題が論じられる同ブログのあるエントリーには、こんな一節がある。
「異質な者同士の間に適切な「壁」を設定しないと、当事者の手に負えない複雑度の爆発が発生し、当事者同士の間の認識解像度が著しく低下することによって通常の人間らしい社会が破綻してしまうような状況に追い込まれてしまいます。これは政治的な問題、あるいは語学力の問題として誤解されがちですが、問題の本質は状況全体の論理構造にあり、一種の数学の問題として理解されるべき事象です。」
望月自身の体験例として挙がるのが、日本語と英語(圏)の往来がもたらす解像度の崩壊だ。
「「海苔ご飯を箸で食べる」ということを英語で表現するとなると、「海苔」を「シーウィード=つまり、海の雑草」、「箸」を「チョップスティック=ものをつついたり刺したりするための木の棒のようなイメージ」というふうに表現するしかなくて、「未開人どもが、木の棒を使って、そこいらへんの海に浮かんでいた雑草のようなゴミをライスとともに、未開人っぽい原始的な仕草でもくもく食べている」といったようなイメージに必然的になってしまいます。日本・日本語では大変な品格があったり、溢れる愛情や親しみの対象だったりする事物が、英語で表現した途端に、「どうしようもない原始的な未開人どもが、やはり原始的な未開人どもらしく、世にも頓珍漢で荒唐無稽なことをやっているぜ」というような印象を与える表現に化けてしまいます。私は子供のときから英語のこのような空気に対しては非常に強烈なアレルギー体質で、自分たちがどれだけ根源的にコケにされているか全く自覚できずに英語や英語的な空気を浴びせられることに対して憧れのような感情を抱くタイプの日本人の精神構造が全く理解できません。」
世界の解像度を保ち、非対称な優劣感から解放されるための武器が壁だ。だが、トランプのように国境に鉄板の壁を敷いてしまうのは、笑えるが想像力に欠く。肉体や国土よりデジタルIDやSNSの方が重要になった世界では、物理的国境に築かれた壁はもはや象徴的意味しか持たない。物理世界に依存せずに、壁をデジタルに再建できないだろうか?
「知らない幸福」のデジタルトランスフォーメーション──社会をいったん閉じ、そして開く
想像してみよう。デジタル化され個人化された壁を張り巡らせて作られる「出島網(デジマウェブ)」だ。イメージの具体性が欲しければ、以下はソーシャルメディアの改造案だと捉えてほしい。
1) 出島のために壁を敷く
2000年代以降のウェブデータには著しい特性がある。個人や個人間の関係(ネットワーク)だけでなく、コミュニケーションという関係性の変化や関係上の情報・情動の流れを捕らえられるようになったことだ。各個人がどんな属性の持ち主で、過去にどんな言動やコンテンツを生成したのかだけでなく、誰とどんな風に絡んでどんなコミュニケーションが発生し(なかっ)たかのデータが貯まっている。
コミュニケーションデータは、コミュニケーション不全を教師付き機械学習することを可能にする。「どんな特性や履歴の人同士がどこでどんな風に出会うとコミュニケーションが毒物化するのか」の学習だ。
学習結果を使えば、生まれてこない方がよかったコミュニケーションを予知できる。まず、まだ出会っていない人々同士の仮想のコミュニケーションの行く末を予測する。世界認知が隔絶しすぎていて、接触したところで相互理解など不可能、単にフリーズや拒絶反応、罵詈雑言、一方通行の嘲笑や粘着や説得ごっこに終わるしかない、混ぜるな危険度の高い人々の組み合わせはどれか判定する。判定はプラットフォームのプログラムが自動で行い、データの変化とともに絶えず更新していく。
仮にXとYの二者は混ぜるな危険だと予測されたとする。ステレオタイプな例として、新型コロナウイルスはビル・ゲイツが開発して中国共産党と結託してばらまいたという物語に心が高鳴ってるトランプシンパXと、Xと引き合わせれば憐れみの視線で「客観的事実」や「エビデンス」を挙げながら説得をはじめるファクト野郎Yを考えれば良い。
そんなXとYは接触しないよう壁を敷く。相互ブロック・ミュートを代行すると言ってもいい。誰かを非対称に排除するのではない。両者を対称的にミュートする。XとYの関係は壁がデフォルトとなり、愛憎も憐憫もない、無関係による知らない幸福が機械的に成立する。その精神はこうだ:
「何もしない。求めない。協力しない。一見、最大に不親切であるような姿勢が、その実、他人に対して最大の親切になりうる場合があると知りましょう。」(叶恭子『あなたの心にファビュラスな魔法を』)
2)壁で挟まれた出島に入る
デフォルトでは閉じた関係が開くこともある。XやYが意識的に望めば壁を越え、反対側にオプトインできる。ただ、壁を壁たらしめるため、オプトインは有償だ。
オプトインの代償は金銭で支払われるかもしれないし、時間(情報や接続の遅延)など他の形態でまかなわれるかもしれない。言語による支払いという可能性もある。情報の一部が別の言語に勝手に機械翻訳されたり雑音が入って鬱陶しくなるイメージだ。そして、Yのような混ぜるな危険な者の側にオプトインする者は、Xに似た者たちとコミュニケーション不全だと予測される可能性が高まり、X的世界からは隔離されやすくなる。これもオプトインのさらなる代償になる。
代償を伴うオプトインの先にあるのが、異界からの情報に晒される「出島」だ。Xがオプトインした出島ではXがYからの情報を浴びることができる。ただ、まだXとYが直接交信することは避ける。Yもまた出島にオプトインしない限り、XがYに絡むことはできない。出島はしたがって、XとYの二枚の壁に挟まれた場所で、それぞれの壁は一方からしか見えないマジックミラーである。
17世紀のオランダ人は鎖国中の日本を訪れる選択肢を持っていた。死のリスクを犯しさえすれば。ただ、日本を訪れたオランダ人が日本人に絡む自由を持っていたわけではない。長崎の出島という壁で囲まれた人工空間にわざわざオプトインしてきた日本人のみが、オランダ人と交信した。これが隠喩としての出島である。
出島たちが散らばるウェブは、そこそこデフォルト閉鎖されたコミュニケーション空間の個別最適自動生成である。
トランプのメキシコ国境の壁とは異なり、誰との間に壁が敷かれているか、そして出島が有人かどうかは、誰から見た世界かによって異なる。個人ごとに閉鎖された空間は、その人の意識的な選択オプションではなく、むしろデータとアルゴリズムによって勝手に生成されるデフォルト環境になる。
現在のインターネットでは、精神と時の部屋のような人々を見渡せる開放空間が原点にあり、壁を敷くことが意識的な選択だ。開放空間は無料(という名の広告を通じた行動課金)のデフォルトで、閉鎖空間が有料のオプションである。これを逆転してみる。可能な関係の多くが自動生成された壁で塞がれた状態がデフォルトで、その壁を超えた出島での交信が人間の意思になる。
スイスチーズとしての出島、あるいは電脳のバベル
出島網は、理想と現実の可能な融合を目指す。
分断の理想的解決は、事実の共有と歩み寄りによる対称的な相互理解だった。しかし、すでにグニャグニャ論じた通り、はなから不可能な相互理解の幻想こそが問題を悪化させている。誰かに見せびらかすための歩み寄りはステレオタイプなラベルづけにいたることが多く、ラベルづけされた者は拒否反応で先鋭化、ますます相互不信と両極化が深まる。結果として、技術的には事実が共有しやすくなればなるほど、コミュニケーションがしやすくなればなるほど、分断がむしろ広がっていくというアリ地獄に人類がはまり込んでいる。
夢破れた現在の人類は、即効性のある劇薬に頼るしかなくなっている。断絶するいずれかの陣営を何らかの正しさの基準で裁断する非対称な審判だ。「フェイク」や「陰謀論」を通報し、警告し、凍結し、排除する。米国議事堂ジャック事件後のトランプの排除がその里程標となるだろう。
しかし、この即効薬には明らかな副作用がある。ホロコーストという禁じられた手段と同じ、一方を排除して他方を承認する非対称性だ。では、対称性を取り戻すことは本当に不可能なのだろうか? 相互理解の理想の不可能性を踏まえながら、しかし理想の持つ対称性という美点を現実に注入したい。その試みが出島網構想だ。出島は対称性を持つ。
感染症対策についてよく語られる、いわゆるスイスチーズモデルも良い比喩になるかもしれない。壁で挟まれた出島はスイスチーズの一枚のスライスをかたちづくる。出島群というスライスチーズの束が通過速度を緩めるのは、混ぜるな危険なコミュニケーションや分断解消ブランディングが作り出すラベルづけ→拒否反応→不信嫌悪の増幅伝播だ。
冒頭の旧約聖書に描かれたバベルの塔の一節を思い出そう。交われない多様な言語と文化の喧騒(=「バベル」)を、デジタルに再生できないだろうか? 溶解せず劇物反応しない幸福な分断をデザインできないだろうか? 「情報→対話→理解」というバベルの塔にしがみつく人類への新たな一撃のデザイン──それが出島網構想だ。感染症によって図らずも日本と世界が鎖国に追い込まれた現在は、出島社会に向けた格好の出発点である。
[了]
この記事は2021年2月1日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。