できるかぎり大きな視野で、できるかぎりゆったりした時間感覚で、「つくる」ということを考え直していくため、文筆家/キュレーターの上妻世海さんが、さまざまな知恵の持ち主たちを尋ねまわる連続対談が始まります。
最初の対話の相手は、都市や建築と大地との関係を「生環境」というアプローチから探求する松田法子さん。人類の文明やライフスタイルが、いかに地形や自然風土など土地そのものの力との相互作用でつくり出されてきたのかを、千年・万年単位の壮大な視野からとらえ直します。
端的に言うとね。
自然と人間の協働関係をさぐる「生環境構築史」
──最初に上妻さんから、なぜ松田さんと対話をしてみたいと思ったのか、趣旨説明をしていただいていいでしょうか?
上妻 2019年10月に建築系ウェブサイトの特集「建築・都市・生環境の存在論的転回」で、別々の記事でご一緒していたことがきっかけでした。僕は座談会に参加し、松田さんは論考を掲載されてるんですが、そこで初めて松田さんたちの「生環境構築史」というアプローチを知りました。
関心を持った理由を説明する上で、すこし個人的な話をすると、僕は2018年に前著『制作へ』で展開した制作論からの関心の広がりとして、都市生活者、狩猟採集民、農耕民や遊牧民の関係をフィールドワークするということをやっています。具体的に言えば、本が出た年(2018年)にはボルネオのプナン族(狩猟民)にフィールドワークに行き、2019年にはモンゴル(遊牧民)に行きました。実は、今年の5月にもフィールドに行くことになっていたのですが、それがこのコロナ禍で行けなくなってしまって、今こうしてリモート環境での対談に至ったという次第です。

▲上妻 世海『制作へ』オーバーキャスト エクリ編集部、2018年
上記の関心の広がりは、「制作」という概念がいわゆる制度化された括弧付きの「芸術」に留まらず、「人間とはいかなる存在か」という問いと密接に関わっているという直観に導かれてのものです。確かに、一見芸術における「制作」とフィールドワークの間には繋がりが見えにくいと思います。しかし、しっかり見ていくと、「制作」には完成までの過程で「作りつつ、作られ、作られつつ、作る」という円環的な構造があります。たとえば、多くの文筆家は原稿に文章を書くことで、自らの書いた文章によって次に書く文章を教えられるという経験をしています。作ることは能動的に自我を投影するだけではなく、受動的に環境から書き換えられることでもあります。つまり、文化も自然も「作りつつ、作られる」経験の中から生成されるものであり、そうであれば、天候、土壌、地形などを含めた生態学的環境の差異は自然と文化が未分状態である「制作」にとって切っても切り離せないものであるわけです。
さて、このような「制作」の構造を見出していくと、生物としてのヒトが自らの生き場所をつくり出していく営みにも興味が向かっていました。ヒトは自然の中で自らの生態学的地位を見出すだけでなく、自然の中で自らの環境を作り、その環境によって作られます。ラジオ、テレビ、インターネットなど有名な例を含め、発明された物や事が発明者の意図通りに使用されないこともこの構造が根底にあるからです。もちろん、他の動植物も自らの環境を作っているわけですが、それらは棲み分けなども含め、他種との調和を前提にしています。しかし、ヒトの場合、近代都市のように多くの動植物を締め出して、理想的には単一種の空間を作り出そうとします。調和は他種や気候や土壌など他者ありきですが、計画は自己中心的なので諸々の問題を生じさせます。
それは今回の主題との関わりで言えば、建築、都市、あるいは生活を進化生態学、動物行動学、霊長類学、そして人類の中でもサピエンス以外の種との比較(人類史)の観点から、もっと根源的にとらえ直す必要があるんじゃないかということを示唆しています。僕はこの方法を建築や都市だけでなく、広くヒトについて思考する際の方法論として、「縦(進化や歴史)と横(動物や植物)に非連続の連続性を見出すこと」と呼んでいます。
松田さんの論考でも、1万年前の農耕革命や1万5千年前の定住革命をヒトの分岐点に挙げられていましたが、まさにそうした文化と遺伝子の共進化の流れの中に「非連続の連続」を見出すようにヒトが生きる現場と「制作」について考えてみたくなったのです。当初の僕は「作る」ということについて、近代美術や和歌、あるいは文化人類学や仏教思想との関連といった切り口から考えていました。それは結果として僕をもうすこし広いタイムスケールからの思索に導いてくれました。そして、上記の興味を聞いてもらえればわかっていただけると思うのですが、松田さんたちのスケールの大きな包括的な理論からの整理は非常に魅力的な枠組みでした。なので、ぜひ意見交換させていただく機会が設けられたらと思っていました。
ということで、都市史を専門にされている松田さんが、なぜ生環境構築史という概念に辿り着いたのか、そのご研究の来歴から伺ってもよろしいでしょうか。
松田 生環境構築史に興味をもっていただき、ありがとうございます。
私の研究歴は、いま在籍している京都府立大学にあった住居学科にさかのぼります。そこでは大文字の建築だけでなく、人びとの暮らしや生活の場についての学びがコアになっていました。3回生後期に建築史系研究室に入ってからは、京都市内や近畿一円で、伝統的民家や集落・まち並みの学術調査や、それらを文化財に登録したり推薦するための所見や報告書をつくる仕事などに関わるようになりました。
京都での私の師匠の系統を辿ると、3〜4代でちょうど日本の建築史研究の展開に併走していたような流れになります。まず法隆寺など国宝級の価値がある歴史的建造物の学術調査が3代前くらいで行われ、2代前ではそうした逸品的な名建築だけでなく、戦前にはほぼ無名だった上層農家などの民家建築が研究対象になり、1代前、つまり私が直接師事した先生の代では日本の都市型住居である町屋(町家)を本格的に学術対象にするようになりました。
古民家や集落・まち並みが建築史の研究や保存の対象になっていったことには、農地解放、高度成長、列島改造、再開発など、第二次世界大戦後の日本各地で社会と空間の構造が激変し、伝統的住居やその集合体の形と実態が急激に失われていった背景があります。それらを危機と捉えて各地で取り組まれた緊急調査がまずひろく戦後民家史の基礎データをつくっていきます。ところでこうした研究の系譜を京都でストレートに継いでいたならば、自分もたとえば近代などの歴史的住居を研究対象にしたはずなのですが、こうした伝統住居の調査にも携わる一方で学部生のときに私が関心をもったのは、伝統的な住居や建築、集落やまちとしてオーソライズされたある種の「ひな形」的存在の調査研究だけではなく、その外側に常にあぶれてきたようなものたちのことについてでした。住宅としてはまず、国や地域社会を形づくる基礎単位としての家族やイエという人的集合を納める建物たるそれがまずあるわけですが、そうした規範的集合形態からはみ出して漂っていくような存在が、どう住むか、生きるのか、ということの場や器、その集合のあり方などに関心をもったんですね。
上妻 なるほど。都市とか集落といった定住のための空間を前提にしつつ、その枠組みに納まらない生き様がどのように包摂されたかというご関心ですね。
松田 都市には、一定度定着する住民層と短期的に流動するそれとの双方があると思いますが、4回生で宿の建築の調査と国の文化財登録に関わったあとで、次のフィールドに選んだのは温泉地でした。
温泉町はある種のるつぼというか、いろいろな存在が流れ込んでいってたどり着くようなイメージがあったし、中世や近世には行き倒れの人も少なくなかった。そこは規範的な家族やイエ社会が集合しているような土地ではなくて、宿など在地のイエが構成する受け手の器があったうえで、たくさんの破片的な人びとが行くわけですね。それはまず病者という身体です。またずっと時代を下りますが、近代や戦後には仲居さんなどとして温泉町では単身女性が人口比としてはかなり多い。大名が逗留するような一方では馬を治療する浴槽もあったり、また受け手側の宿もたどれば流浪の人だったりして、ともかく温泉町というのは大地がいろいろな存在を同時に受け止めてそこで生かしてきたような、何か懐深いイメージがありました。
ここで話題を「人間」に拡張すると、近年ロージ・ブライドッティなどが人間をめぐって、それがいかに人間=Manを規範とした概念として需要されてきたものであり、それはたとえばダ・ヴィンチのウィトルウィウス的人体図に表象されるように、五体満足で比例の美に適合する白人の男性という特定の文化的存在を理性と接合させてヘゲモニーを形づくり、それによって世界に非-人間、人間以下、人間未満などの他者を生みだしてきたのかについて痛烈な批評を行っていますが(ロージ・ブライドッティ『ポストヒューマン──新しい人文学に向けて』、門林岳史監訳、フィルムアート社、2019/原著=2013)、歴史学を営むにあたって、規範的なところからこぼれおちているものが何なのかということには一貫して関心があります。

▲ロージ・ブライドッティ『ポストヒューマン──新しい人文学に向けて』、門林岳史監訳、フィルムアート社、2019/原著=2013
さてこの規範というレベルにはいろいろあるのですが、たとえばふつう建築史や都市史は、古代・中世・近世・近代・戦後といったようにまず歴史区分に準じた各時代の建築や都市の姿とその特徴を見定め、その前後の時代区分や同時代の国際的状況などと比較検討して、建築や都市の創建時の理念やその計画の実現状況、また規範的な先行作品との優劣関係や影響関係、そして前時代からの「発展」などを明らかにすることがまずオーソドックスな関心としてありますし、研究史も長らくそのように推移してきたと思います。たとえば近代なら西洋の都市計画思想や理念がどんなふうに受容あるいは変形されて日本の伝統都市を変えたのか、あるいは変えなかったのかなどということが着目点になったりします。もしくは、日本ではそもそもはっきり「都市」といえる集住体が西洋などのそれに比して手薄いと感じられていて、それはなぜなのかとか、東京もムラの巨大な複合体だと言われたりしてきました。そんな中で、国際的にも日本独自の「都市類型」だといえそうなまちとして近世城下町の成立と成熟が注目されたり、あるいはこの近世城下町と平安京などの中国モデル都市である古代都城に挟まれて「都市はなかった」といわれる中世の「都市的な場」に注目していくといった研究史が、歴史学と建築史学の四半世紀を超える学際的研究を通じて築かれてきました。
私もこうした研究史も学んでいますが、一方こうした議論に対して、温泉町はいまだにうまく位置付かずに外れてしまうんですよね。都市史において温泉町がうまく位置付かない、あるいは逆に都市史が温泉町をうまく位置付けられないとしたら、その最大の理由は、たぶん温泉町が発生させていることのその根底にあると思えます。それは、人びとがモノやカネ、労働との交換ではなくして、大地と身体を交えるために集まるからではないかと思うのです。
都市が都市たる最大のゆえんは、個人的には「交換」にあると思っています。モノとモノの交換から始まり、モノとカネ、労働とカネ、カネとカネの交換ですね。それをより多量に発生させ、交換される事物により優位に価値の水位差を設定できる場が大都市になります。都市は、モノ、カネ、労働を引き寄せ、吸い上げ、蓄積し、交換します。しかし本来温泉町はそうではないんですよ。発達した温泉町はこういう都市っぽい特徴も併せもっていきますが、さっきも言ったとおりその原点は肉体と大地の力との交わりにあるわけです。
大地の産物に依拠する町場としては、温泉町のほかに鉱山町や製陶町などがありますが、鉱山町は大地から一方的に資源を収奪するといえます。製陶町の収奪性はそれよりはずっとゆるやかで、かつ造形という芸術的プロセスも発生させますが、温泉町はうまくやれば大地から何かを大幅に奪うわけではない。限られた温泉をどう持続的に使うかという公共性に江戸時代から各地で腐心してきたわけで、ただそれは公共という理念であったというよりは宿の営業権や温泉利用権の限定性などの仕組みづくりによる共同化を伴いましたが、しかし温泉の入会〔いりあい〕性というのは基本的前提としてきわめて重要で、その原点をきちんとすれば温泉地は環境的に最も長期循環的な仕組みで運営できるはずなんです。
それと温泉地にまちを作ろうと思っても、地表の計画法としての都市計画的手法は、どうもぴったりこない。修士1回生のときに大分県の別府温泉に行き始めたのですが、別府市は明治末にグリッド状の都市計画を敷いて「大別府」や「泉都」を名乗るものの、まちの発展は元来、まったくもって大地のあり方に規定されているんです。つまり、温泉の湯脈が地下のどこを流れていて、そのどこが地表に近くてお湯が噴出しやすいのかとかいったことですね。大地に内蔵されている温泉の脈動のようすが重要なわけで、その動きと地表のグリッドというのはほとんど無関係なわけです。温泉地が都市を目指すときに生じるそういうちぐはぐさ、そして地表をどう計画するかといった近世的・近代的な理知とはあまり関係なく、温泉の湧出地点の所在や強弱がまちの空間構成を決定づけてしまうような原理、そして個々人が大地の恵みにつながるために三々五々集まっては生き延びる「まち」だということが、何か妙に魅惑的だったんですよね(松田法子『絵はがきの別府』左右社、2012)。
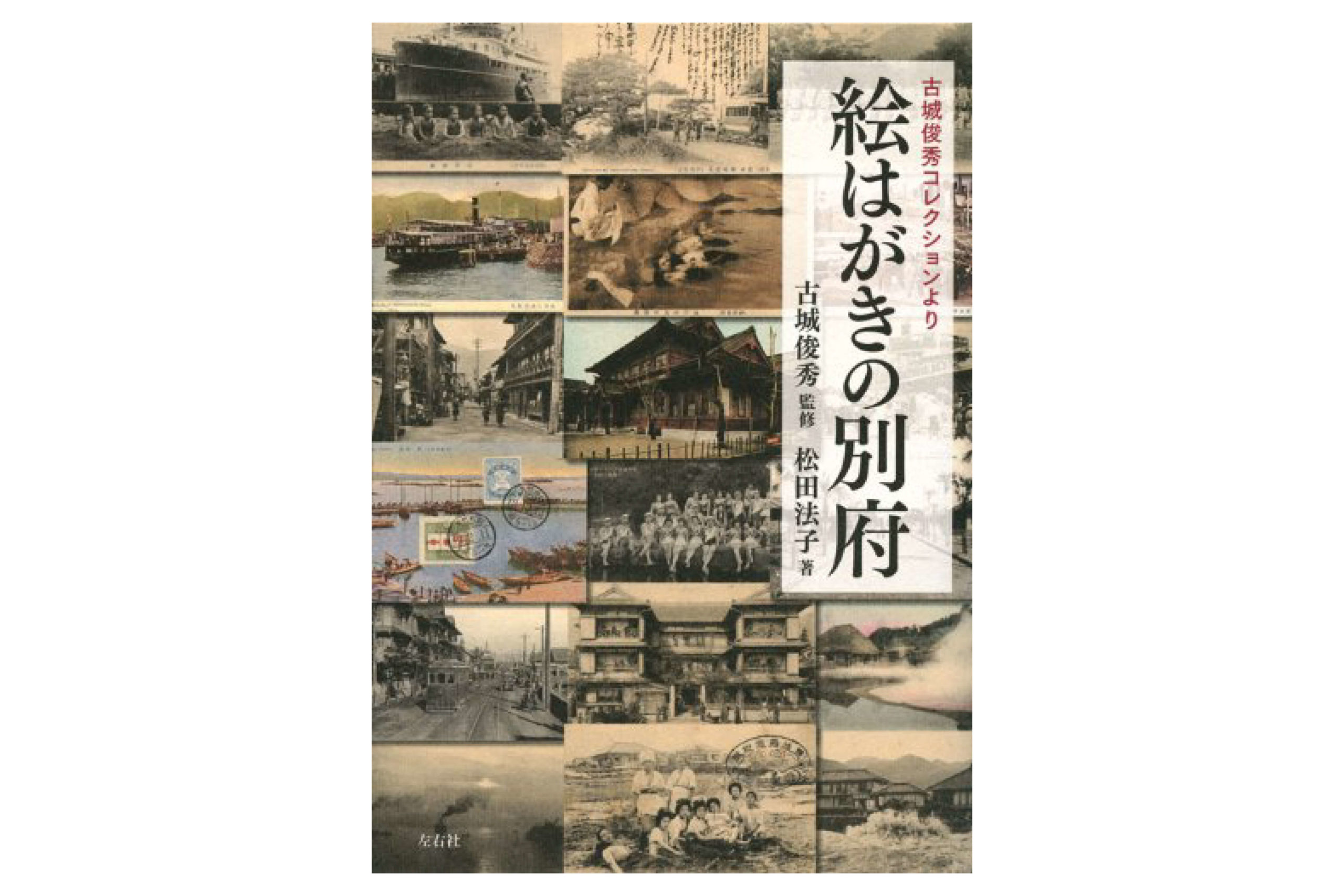
ああ、温泉町のことを話していたら、つい長くなってしまいました。
ともかく、そうやって民家研で別府と熱海の都市史で博士論文を書いたので、もう少し本格的に都市史研究の方法と現在を知ろうと東大の都市史研究室に移り、そこで研究員やスタッフとして6年ちょっと過ごしました。そのさなかに立ち上がった共同研究が「沼地研究会」といいまして、何だか聞くだに怪しいですが(笑)、それは、都市はいったい何を手がかりにして発生するのかを探るという、都市の原点を真摯に追求するための学際的研究会でした。オランダ・フリースラント、イタリア・ヴェネト、フランス・ラングドック、そしてアイルランドの各フィールドを探求する「沼地研」が順次立ち上がってゆき、私はその調査のおおむね全体に参加しつつ、諸々のマネジメントを担当することが最終的な役目になりました。加えて、オランダ沼地研(以下、蘭沼研)が始まった2010年の翌年におこった東日本大震災の経験が、研究視角の掘り下げや転回にとって大きなきっかけになっていきます。震災直後は宮城県岩沼市の集団移転についての活動にも一部参加しながら、沼地研の共同研究のほうもいっそう進んでいきました。
この沼地研が始まった初期の関心はその後の展開にも関わるので、少しだけ紹介しておきます。たとえば中世日本の「都市的な場」がどんなふうに発生するかというと、その多くは水陸の交通の結節点に生まれます。異なる領域から運ばれてきた物同士が出会い、交換される場ですね。あるいは近世城下町は、武士たちの闘いや領土経営のなかでいろいろな地理が読み取られて城が設置され、城下に呼び寄せられた市などが町人地の原型になっていく。しかし、そもそも地面がなかった場合、あるいは地面なのか水面なのかあいまいな領域に都市ができる場合、大元のその立地選定を含めて、いったい何に依拠し、どこにどう「土地」のラインを引いて都市を配置するのか。オランダには、「世界は神がつくったが、土地は人間が作った(Man-made lowlands)」という有名な格言があるんです。都市がそんな地面の上にどんな経緯や理念によって成長するのか、といったことが問題になり、それらについて現地調査をしながら現場で考えてきました。オランダは国土の多くが海抜0メートル以下で、そこを排水して陸地と都市が築かれてきました。この蘭沼研の数年間の調査成果は、つい先頃刊行されています(伊藤毅編『フリースラント ーオランダ低地地方の建築・都市・領域』中央公論美術出版、2020)。

▲オランダのポルダー(干拓地) アムステルダム近郊〔撮影:松田〕
そして東日本大震災では、集落やまち、陸地だったところが一瞬で海の底になりました。陥没して湿地に戻った土地もありました。たった数時間で、一帯の領域はとてつもなく変貌したわけです。あの津波の到達線は、6000年前、縄文時代の海進期の海岸線にほぼ近かったことなども知りました。東日本大震災は、貞観地震という1000年前の巨大地震・津波の再来といったことも言われましたよね。
これらの経験を通じて当時感じたのは、居住史を考えるには、中世・近世・近代といった、100年やその倍数を基本単位とするような従来の時間軸だけではなく、1000年程度を基本単位にするような時間軸も導入していかなければならないのではないか、ということでした。1000年もさかのぼってしまえば、建築分野から読み取れるような対象はほとんどないのではないかと思われるかもしれません。しかし、むしろそういう長期的な時間の射程からこそ、建築や居住、都市を考えるときに来ているのではないかと感じたのです。それは、人や都市、建築の時間軸が、地球の時間軸とまざまざと交錯していく、あるいはいつも交錯していたのだということに、はっきりと気づかされる経験でした。
そうした時間的な様相と、極大でも極小でもあるようなスケールの具体の現場を同時に捉えるような概念を探していたときに、ある日、ふと訪れてきたことばが『汀』でした。
上妻 汀(ミギワ)ですか?
松田 そう、汀です。
波打ち際や水際、平らかな場所、水と陸地が接するところ、というような意味があります。うみやまの間、水際の平地、揺動する境界。そこは異質なものが常に交差する領域で、そういう領域にこそ、都市ができていく。中世史の網野善彦は、中世の「都市的な場」を論じた重要な研究者ですが、とくに日本の中世都市は福山の草戸千軒や博多の中州のように、地形的にも水と陸地が交わるところに生まれる。それは交換という都市の本質的機能と、地理的にもよく一致するものです。
そう考えてみると、たとえばロンドンやニューヨークなどにしても、世界の多くのメトロポリスは水際の低地にできているんですね。江戸-東京や上海なども同様です。これらは交換に特化した集住体だともいえる。何らかの形で人口も交換に接合することで集積してきた。こうした意味においても、都市は食料や物資の直接生産地にはなりがたいのです。たとえばヴェネツィアがその典型ですが、都市はそれ自身では自活できないわけです。そこは高度に交換機能が集積されるべき場であって、食糧や資材、労働力などは都市周辺の「領域」から移入される。そういった機能をもつヴェネツィアの本土領をテッラフェルマというのですが、都市が領域をいかに支配し、コントロールするかは、都市が自らのために都市の外部で営む重要な日常業務でもある。よって都市の日常的な維持と歴史的持続を考えるには、都市が紐付いている周辺領域のことも同時にみていく必要がある。都市の立地は汀によく重なるのですが、そこに交換拠点として成立した都市が周辺領域をどのように再編・運営することで、ある圏域を歴史的に構造化してきたかを、建築から地形などまでをスケール・事物横断的に考える試みを2014年ごろに「領域史」として構想しました。そしてこの領域史は、私たちの居住や生存を立ちゆかせている基盤や支持体とともに人文的歴史を考えるという視角をもちます。これを都市史の伊藤毅と共に立ち上げてきました(* 特集「都市史から領域史へ」『建築雑誌』2015年5月号)。
また、東日本大震災の経験を経た学術的転回から領域史構想へのアクチュアルな架橋的書物として、伊藤毅・フェデリコ・スカローニ・松田法子編著『危機と都市 Along the water: Urban natural crises between Italy and Japan』(左右社、2017)があります。

▲特集「都市史から領域史へ」『建築雑誌』(日本建築学会、2015年5月号)
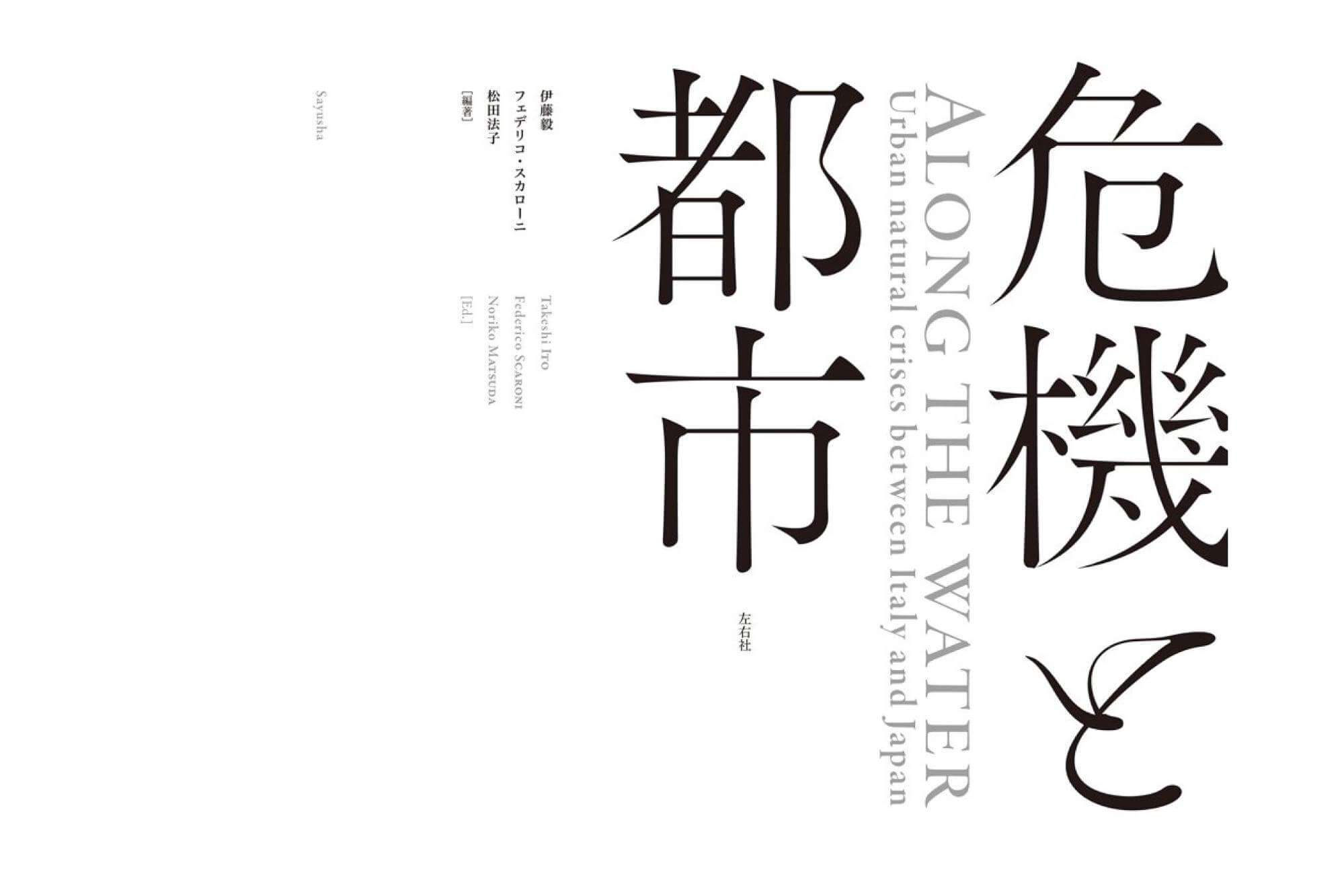
そして生環境構築史(Habitat Building History / HBH)は、わたし個人の関心のつながりのなかでは、こうした「汀」の人文史や「領域史」、また「都市と大地」というテーマについて思考する取り組みとも連動しながら、しかしより明確に「構築」という人為の作動局面に着目することに歩を進めた、次段階の概念です。
「生環境」とは、ヒトが生きるために構築した環境の全般のこと、「構築史」とは、ヒトがその環境を獲得し、何らかの空間としてかたちづくってきた歴史のこと、というふうに定義しています。
ヒトは構築のあり方を、地理的・歴史的条件に応じて展開させてきた。生環境構築史では、「人間」を「ヒト」に拡張したうえで人と構築様式の史的関係を問うていきますが、ここで重要なキー概念になるのが、「構築様式」(building mode)です。これは、人の生存様式という生物的根源とその変化とを、構築史を通じて歴史階梯に問うということです。
そしてさらに、地球それ自体の自律的構築運動として「構築0」を定立し、これらとヒトの構築様式との関係を抽出しようとすることが大きな特徴です(* 松田法子「生環境構築史の見取り図」,10+1 website, 2019)。
私たちは、人が地球のある地点に住むことは所与のことではなく、それらは構築行為によって獲得されてきたものだと捉えています。別の言い方をすると、いま現在の生環境も所与のものではなく、歴史上のある段階で構築を通じて獲得されてきたものだというわけです。
ホモ・サピエンスは地球上のさまざまな地点に移動し、各地の環境に適応して生存してきました。その過程では種々の相克と創発の機会が生じ、そこでの偶然が新たに体制化されながら構築様式がつくられてきたものと考えています。
また、ヒトの構築様式がどのような階梯によって歴史的に作動し、「構築0」の自律的運動と関係してきたのかを、アジア的-古代的-封建的-近代ブルジョア的(資本主義的)という4つの歴史段階からなるマルクスの「生産様式」や、互酬-再分配-商品交換-Xからなる柄谷行人の「交換様式」といった先行するすぐれた世界史の把握法も踏まえたうえで、さらにそれらとは異なり、人類史を生環境の「構築様式」によって思考してみようという批評的着想が、生環境構築史の始まりです。
これをまず建築史の中谷礼仁・青井哲人両氏と2018年秋に立ち上げました。基本概念や用語は両氏と練り上げてきたものです。今年に入ってからは生環境構築史を考えていくためのマニフェストとして、「生環境構築史宣言」を発表しています(* 松田法子「生環境構築史宣言」 協力:青井哲人・中谷礼仁、2020)。
また、今秋からは6年ほどをかけて、生環境構築史のポータルサイト上で特集記事を順次パブリッシュしていく予定です(* 現在の仮サイト「生環境構築史WEB・準備号」)。その編集同人としては、建築史系である先の3名と、現時点で、伊藤孝(地質学・鉱床学・地学教育)、小阪淳(美術家)、日埜直彦(建築家)、平倉圭(芸術学)、藤井一至(農学・土壌研究)、藤原辰史(農業史・環境史)、マシュー・ムレーン(建築史)の各氏と編集者の方々が加わっています。ムレーン氏はアメリカからの参加で、中国にもサポートメンバーがいます。
WEB誌の発行と特集趣旨は、構築様式の史的階梯とその具体像を多様な「構築」の具体例を通じて学際的・多角的に明らかにしながら議論を重ね、最終的には来たるべき第4の構築様式としての「構築4」について考えることにあります。
5つの構築様式の変遷から見えてくるもの
上妻 ありがとうございます。まさに僕がヒト以外のものとの関係の中で「作ること」を考え始めたのと同じ山に反対側から登ろうとするアプローチだなと思って聞いていました。つまり、僕の場合、ミクロな視点から人間と環境の行い/行われる個々の「制作」を捉え直していこうという方向なのに対して、松田さんはマクロな環境の側の自律的な運動に「構築」を見出す方向ですね。
実際、「制作」を広い観点から見ると、興味深いことがいくつかわかります。まず、「制作」はホモ・サピエンスに特有のことではないということです。ダーウィンのように自然淘汰と性淘汰を区別するだけでは理解できない事例は鳥類や他の哺乳類にも見られます。たとえば、ニワシドリが各々のデザインで巣を作ることも(人為的にデザインに介入すると、再度彼らは自らの嗜好に合うよう作り直す)、キジオライチョウの儀式的な舞踏も(誰からも寵愛されなくても何年も舞踏に身を投じる)、ビーバーのダムも(世界最大のものは850mもある!)、より多くの子孫のためや生活に対する機能的側面だけではなく、各々の楽しさのためであります(* アルフォンソ・リンギス『変形する身体』水声社、2015年)。また、教科書では、「作ること」はヒト科ヒト属の分化に大きな意味を持っていますが(ヒト属はオルドワン石器と一緒に化石が発見されたことから「器用な人」という意味の命名をされたホモ・ハビリスから分化されている)、アウストラロピテクスも単なる石と大して見分けはつかないにせよ礫石器を使っていますし、チンパンジーにも蟻を食べる際に枝で穴から搔き出す群れもいれば、石で安定した台を作り硬い実を別の石で叩き割る群れもいるように、文化が群れごとに異なることも知られています(* 松沢哲郎『想像するちから』岩波書店、2011年)。
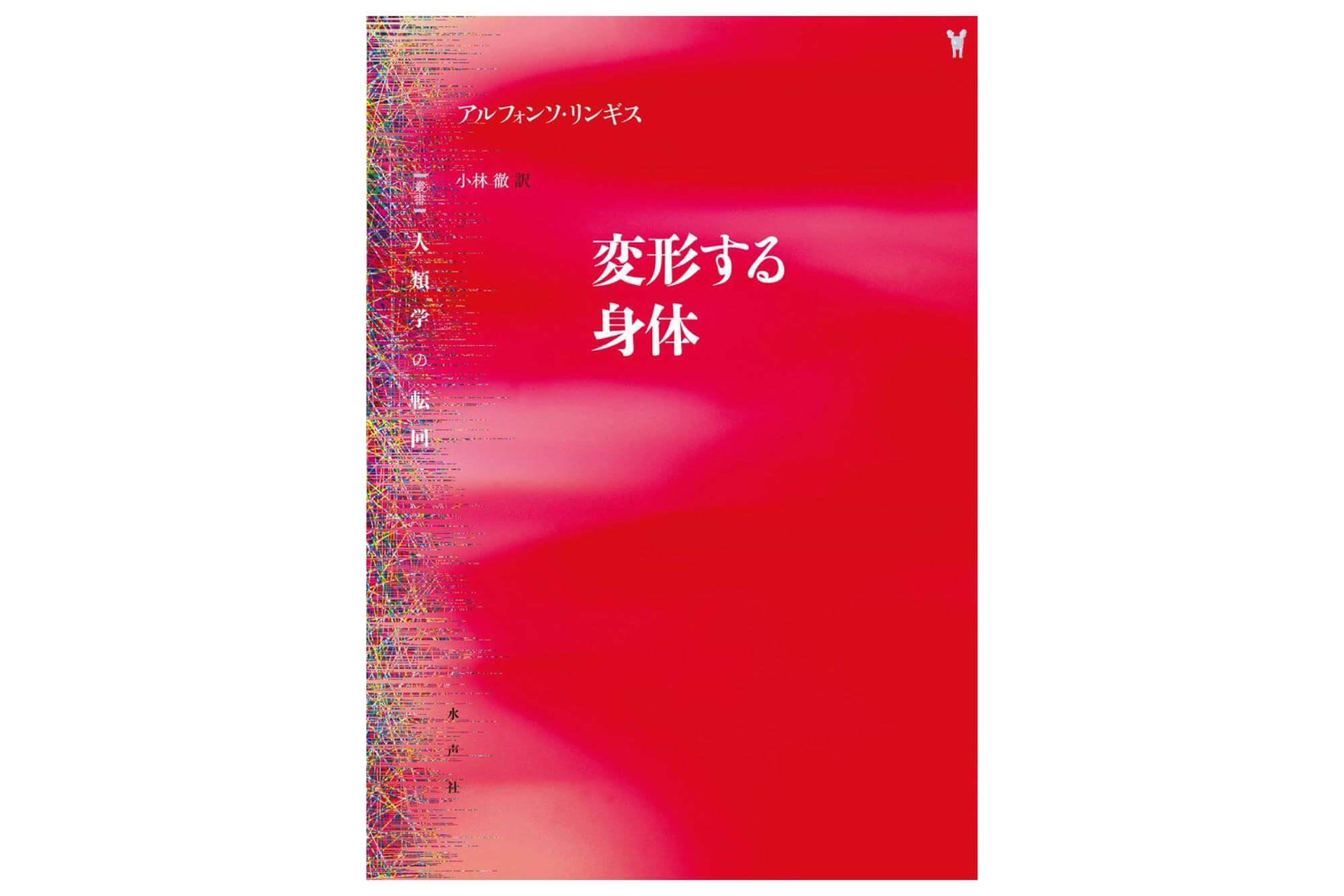
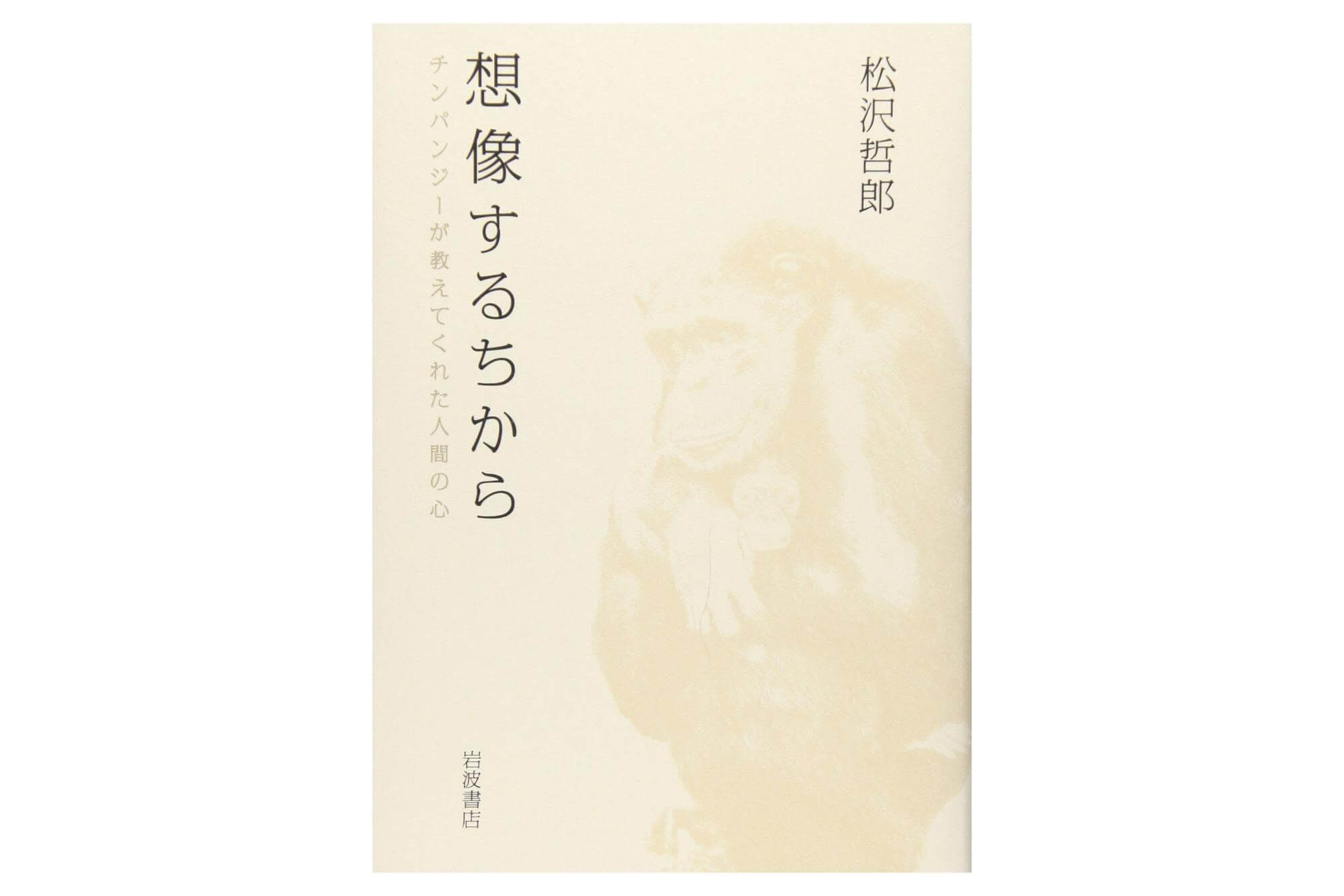
さらに言えば、約600万年前にチンパンジーと共通の祖先から人類の系列が分化した際、最も重要視されるのは二足歩行ですが、現行のチンパンジーを見るかぎり、直立自体はそれほど大した適応ではないことも知られています(* ニコラス ウェイド『五万年前』イースト・プレス、2007年)。一般的に、類人猿は樹上で直立して木の枝にぶら下がって腕を交互に切り替えながら移動していますし、地面を歩く時も前肢の背面をつけながら歩く、いわゆるナックルウォークという独特の歩き方をしています。これはサル目が4本足で四つ這いで移動することと比較すると違いが歴然です。また、脳の大きさから見て、アウストラロピテクスは認知能力や社会的知性の面でチンパンジーとほとんど違いはなかったと考えられています(*ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』インターシフト、2016年)。
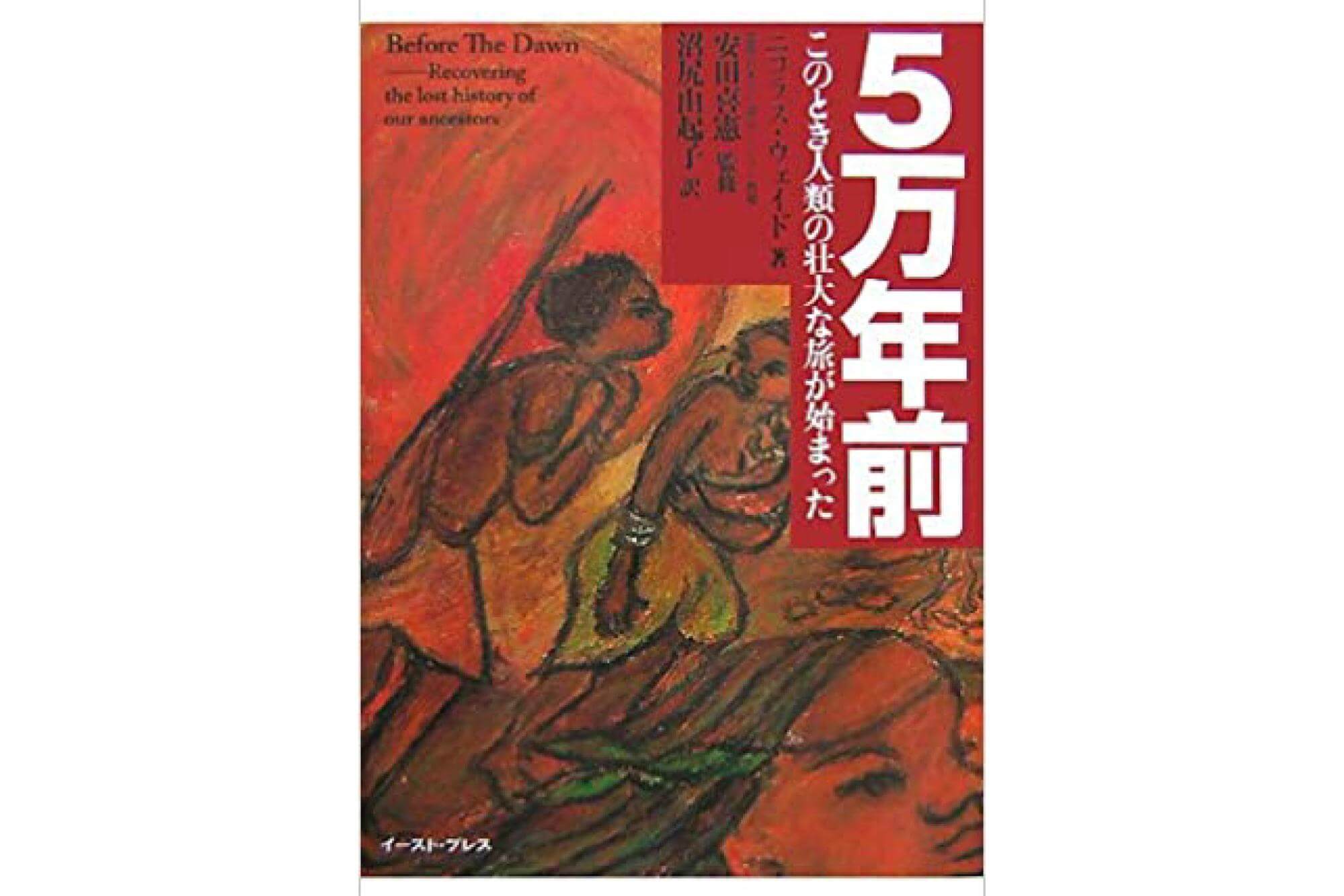
▲ニコラス ウェイド『五万年前』イースト・プレス、2007年

▲ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』インターシフト、2016年
確かに直立二足歩行は大した適応でなかったにせよ、アウストラロピテクス属とチンパンジーの間にはそれくらいしか区別するところはありませんでした。では、なぜアウストラロピテクス属からホモ・サピエンスまで進化するに至るのでしょうか。僕は鍵になる概念を「過剰性=欠如」と呼んでいます。簡単に言えば、相対的な「弱さ」が過剰性を帯びる要因であるということです。たとえば、200万年から300万年前には地球は再び寒冷になり、乾燥しました。アフリカの森林は減少し、森で生活する多くの種が絶滅しました。その気候変動は当然アウストラロピテクスにも淘汰圧として働き、小さくなった森で食料源を他の中型霊長類と争うよりも、我々お得意の二足歩行でサバンナに出るしかなかったと言えると思います。実際、チンパンジーは今でも森で暮らしているわけですから、ある意味で僕たちの祖先は森を追い出されて疎林やサバンナに適応するしかなかったわけです。疎林やサバンナでは移動距離や日光の当たる面積という点で二足歩行の方が有利です。
さらに、古人類学者フリードマン・シュレンクの論考「アフリカ──人類発祥の地?」によると、ヒト属の誕生(ホモ・ハビリス)すら、この弱さや欠如に由来します。アウストラロピテクスは頑丈型と華奢型に分けられますが、頑丈型アウストラロピテクスは、歯を含めた咀嚼器官の発達によってサバンナの乾燥していく気候に適応していき、より硬い果実や植物を食料とすることできました。他方、華奢型アウストラロピテクス(ホモ・ハビリスへと進化するヒト属の祖)は、硬い食料を食べるだけの咀嚼器官を持たないため、道具文化を発達させるようになるわけです。頑丈型は強かったからこそそのまま環境に適応できたのに対し、弱かった僕たちの祖先は道具の「制作」によって環境を改変し、環境からの独立を徐々に推し進めていきました。こう見ると、ヒト属の歴史は始めから「制作」に表層を彩られ、過剰性=欠如を深層に抱えていると言えるのです。
しかし、ただ単純に作るということだけであれば、鳥類にも他の哺乳類にも見られます。アウストラロピテクスの時点ですでに礫石器を作っているし、チンパンジーだって見方によれば打製石器を使っているという言い方もできる。そういった分類学的な議論はたくさんされているんですが、特に僕が説得力を感じているのが、生態人類学者の西田正規さんの『人類史のなかの定住革命』での議論です。
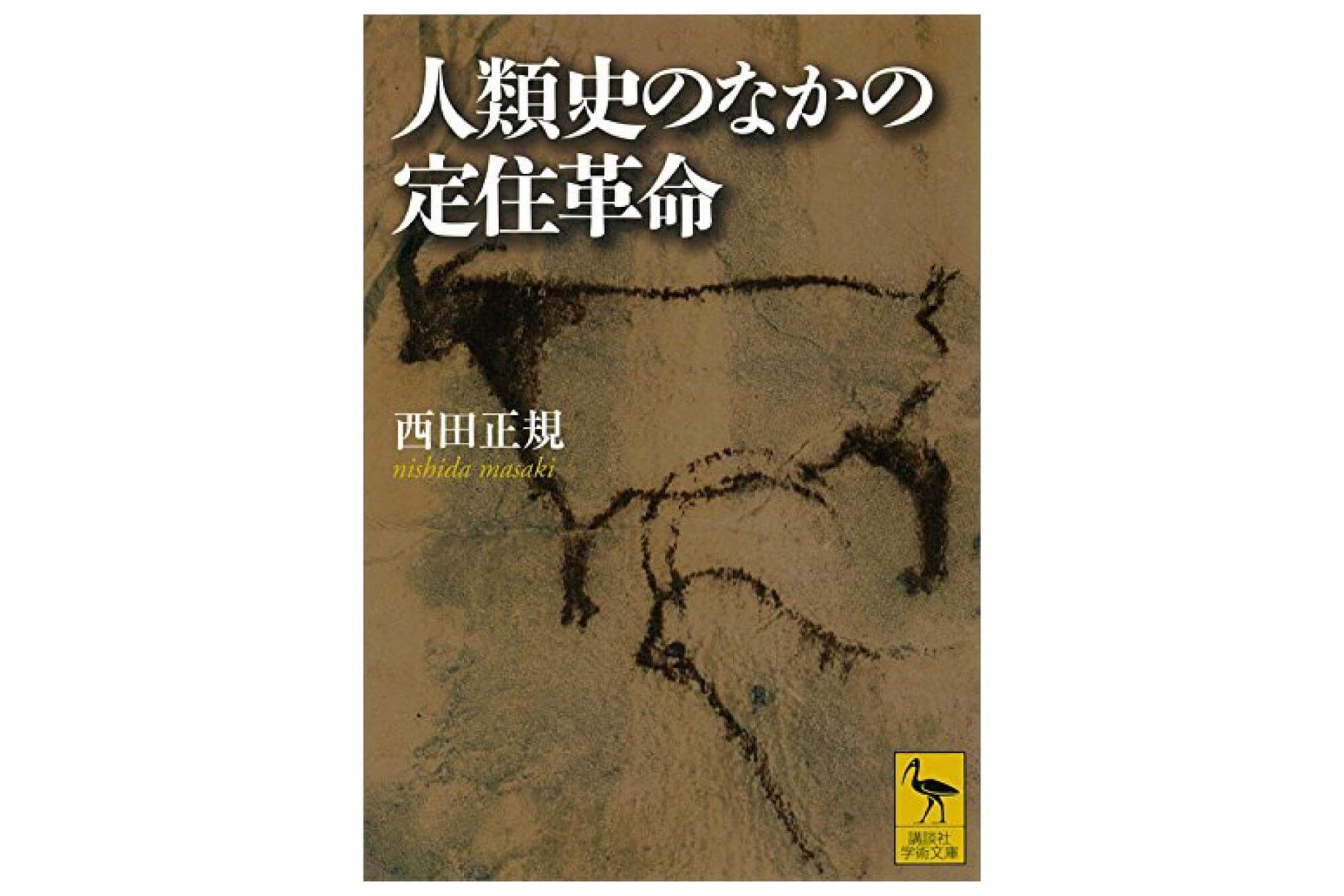
西田さんは今西錦司の生活形(形態と生活の場を通じて具体化している生活様式)の概念を中心に脊柱動物を口型と手型に分け、数億年におよぶ進化の過程で出現した動物を比較することで、手型化の傾向を描き出しています。そして、人類にとって道具をつくること自体よりも、それを持ち運んで常に身に帯びるようになったことがポイントだと述べています。西田さんの言葉を引くと、「野生チンパンジーの道具使用が明らかになるにつれ、道具を使う者、作る者として人類を定義することが苦しくなったが、たえず携帯される道具、あるいは、高い運搬能力を前提にして使用される道具は、ただ人類だけが持てるものである」ということです。
一見すると二足歩行によって道具を絶えず携帯できるようになったことは大したことではないように思えますが、実はこの「作ること」と「携帯すること」の融合こそが、先に挙げた「制作」の持つ循環性の条件なのです。何故なら、それによって外部への適応としての道具が内部の変化をもたらすようになったからです。具体的には、キリスト教の説教や聖書を聞くために役立つと発明されたラジオが我々の生活形を大きく変えてしまったように、目的-手段としてだけでなく、作り出したものが人間の生活形そのものを作り変えてしまうことに繋がるわけです。
先に述べたように、生活形とは身体の形態と生活の場を通じて具体化している生活様式のことですから、生活形はその生物そのものを表しています。道具の発明が生活形を書き換えるということは、この時点でもはや人類は皮膚で区切られた形態で定義されるものではなくなり、道具と物理的身体を統合した者として捉えなければならなくなったということでもあります。僕たち人類は「作りつつ、作られ、作られつつ、作る」の循環に入ったとも言えます。認知科学者アンディ・クラークの言葉で言えば、「生まれながらのサイボーグ」になったとも言えます。そして、西田正規さんは「外への適応が内への悩みをもたらし、内への適応は外への悩みをうむ」ようになったと仰っています。
僕たちの身体は「作りつつ作られる」ものとなりました。しかし、その過剰性=欠如の埋め合わせとして必要となるものが生じます。それこそが、西田正規さんによると、家族、分配、言語だというのです。霊長類は群れの中に順位関係を築きます。順位関係は重要です。実際、アルファ雄は優先的に餌を得ますし、遺伝子研究などでもアルファ雄が非常に多くの子孫を残すことは確認されています。しかし、その秩序は安定的なものではなく、いつ順位が入れ替わり下剋上が起こるかわからない不安定なものです。秩序は霊長類でも不安定なわけですが、人類は道具を携帯するようになったわけですから、それは身体の大きさと殺傷能力が相関しなくなったということです。そうなると、身体が大きいとか力が強い雄が群れのボスになるといったような生物学的な個体差があまり重要ではなくなって、別の仕方で社会的な秩序化を行うことが重要な焦点になってきます。さらに言えば、狩猟採集民は150人程度の共同体と実際に行動を共にする30-50人程度のバンドを集合離散することで、恨み、辛み、妬みを解決できたのですが、定住革命以降は物理的距離によって解決することができなくなったので、家族、分配、言語など三人称的制度によって群れの性と食の緊張関係を和らげる必要が生じたわけです。
実際、これは進化人類学者ロビン・ダンバーの言う社会脳仮説の議論やニコラス・ウェイドの議論とも相補的です。ダンバーは、群れに伴う社会的緊張に対して安心と信頼(互酬性)を築くために、酒や踊りや歌や語りや共同飲食などの文化が役立ち、人類の進化は社会的知性を向上させる方向に淘汰圧がかかった結果であると主張します。また、ニコラス・ウェイドの議論でも五万年前の認知革命(後期旧石器革命)に伴ってさらなる華奢化が生じたと言います。それは身体的な強さよりも社会的知性の方が選択圧として機能したということを意味します。
まとめるなら、過剰性=欠如は「制作」(道具+携帯)を通じて、物理的大きさや強さによる秩序ではなく、三人称システムとしての秩序(法、官僚、警察など)と互酬性(一人称-二人称)のための文化(宗教、音楽、踊り、絵画、彫刻など)を必要としたということです。そして、このような視点から見ることで、文化と人間の共進化をより詳細に捉えることができます。サピエンスに至る人類の大脳皮質の拡大は、人類が過剰性=欠如による「制作」の埋め合わせとして、コミュニケーションや象徴交換を必要とし、それが環境となりさらなる「制作」を促すようになった結果と考えることができます。
その部分的証拠はいくつかあります。たとえば、約5万年前に始まったとされる後期旧石器革命(認知革命)とそれに伴う遺伝子変化の加速です。ご存知のように、後期旧石器革命では投げ槍、槍投げ器、弓矢などの武器から服をつくるための錐や針、洞窟画や象牙や石でできた女性裸像など芸術の高度化、弔いの高度化が見られました。そして、この文化自体が淘汰圧となり、遺伝子の変化が加速しました。道徳心理学者ジョナサン・ハイトはあらゆる大陸から募った数千人のゲノム塩基配列決定の調査結果を見て、「遺伝子の進化は過去五万年の間に著しく加速しており、選択の圧力に反応して遺伝子が変化する速度は、およそ四万年前に上がり始め、二万年前からはますます急激な上昇を見せている。そして完新世に入ると、アフリカ大陸とユーラシア大陸で最高潮に達する」と綴っています(*ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか』紀伊國屋書店、2014年)。これは、人類と環境の「制作」における循環的進化、いわゆる共進化の加速が後期旧石器革命の時期とほぼ重なることを意味しています。また、完新世、すなわち約一万年前、大陸ヨーロッパにおける氷床の消滅、そして農業革命の時期に加速度は最高潮に達していると言えるわけです。人類と環境は互いに変化しつつも、いくつかの臨界点でギアが切り替わり、加速度が上がっていると言えるのかもしれません。

▲ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか』紀伊國屋書店、2014年
僕は現在、発展途中ですがこのように考えています。そして、そういうレベルから制作にまつわる人類史を見直していこうとしていたときに、松田さんたちが図解されている「構築0」から「構築4」への構築様式の変遷は、とても触発的だったんです。改めて、この変遷のポイントを、順を追って解説していただいてよいでしょうか。

▲「生環境構築史」概念図(中谷礼仁・松田法子・青井哲人、2019年9月版 / 作図 徐子)
松田 はい。私たちのダイヤグラムの一番の特徴は、人の構築様式=ビルディングモードの階梯図の提示と、さらにそこには地球それ自身の構築運動である「構築0」を常に据えているというところです。地球はヒト・人間存在の出発点や基盤であるだけでなく、人が文明や社会、都市などを構築したあとも常に自律的に作動しているからです。
「構築1」は、そのような地球から、石や土や木、あるいはセメントのように、構築0から即地的に何らかの断片を取り出す段階です。いま上妻さんが話していたような、ヒトによる構築活動の始まりの地点ですね。たとえばいわゆる木造文化圏と石造文化圏の違いなどもこの段階に由来しているわけで、伝統建築の構法やマテリアル、ローカルあるいはヴァナキュラーな建物は、構築0の地表・気候環境との兼ね合いから具体的な形へと結ばれます。つまりあらゆるヴァナキュラー建築の多様性とは、その地点の構築0の地表近くの状況と連動的に体系をつくったその結果的姿だといえます。
なお構築1はヒトだけではなくある程度までは動物などヒト以外の動物による構築様式でもあります。これはさっき上妻さんが例を出されていましたね。
それに対して「構築2」以降は、基本的にヒト固有の構築様式になります。構築2は定住や農耕が成立し、それらを農業に再編した都市及び都市国家の誕生とも連動的です。構築素材には交換価値が見出され、その流通や蓄積が発生します。それは構築にとってより使いやすいといった価値もあれば、象徴的価値もあります。それらの交換価値が貨幣のようなものにも転化されながら、集落や都市の文明構造と連動的に流通し、構築素材の価値は社会資本化されていくと考えられます。またここで「交換」の中には略奪も含まれます。
上妻 そうですね。その構築1から構築2の流れというのは、さっき話したような「つくる」ことの帰結としてのサピエンスの象徴交換のモードチェンジとしても語ることができて、暴力による個体差が次第に小さくなっていくにつれて、狩猟採集民における共有経済の秩序が形成されていくし、さらに集団が定住して労働集約しようとしていくときに法体系なり神権政治なりの必要性が生じていく、ということの背景説明にもなっていると思います。日本でもベストセラーになったユア・ノヴァル・ハラリの『サピエンス全史』で言えば、大脳の認知革命によって「虚構」が共有されるようになったことで、社会化された人間の環境改変能力が飛躍的に高まる段階のことですね。
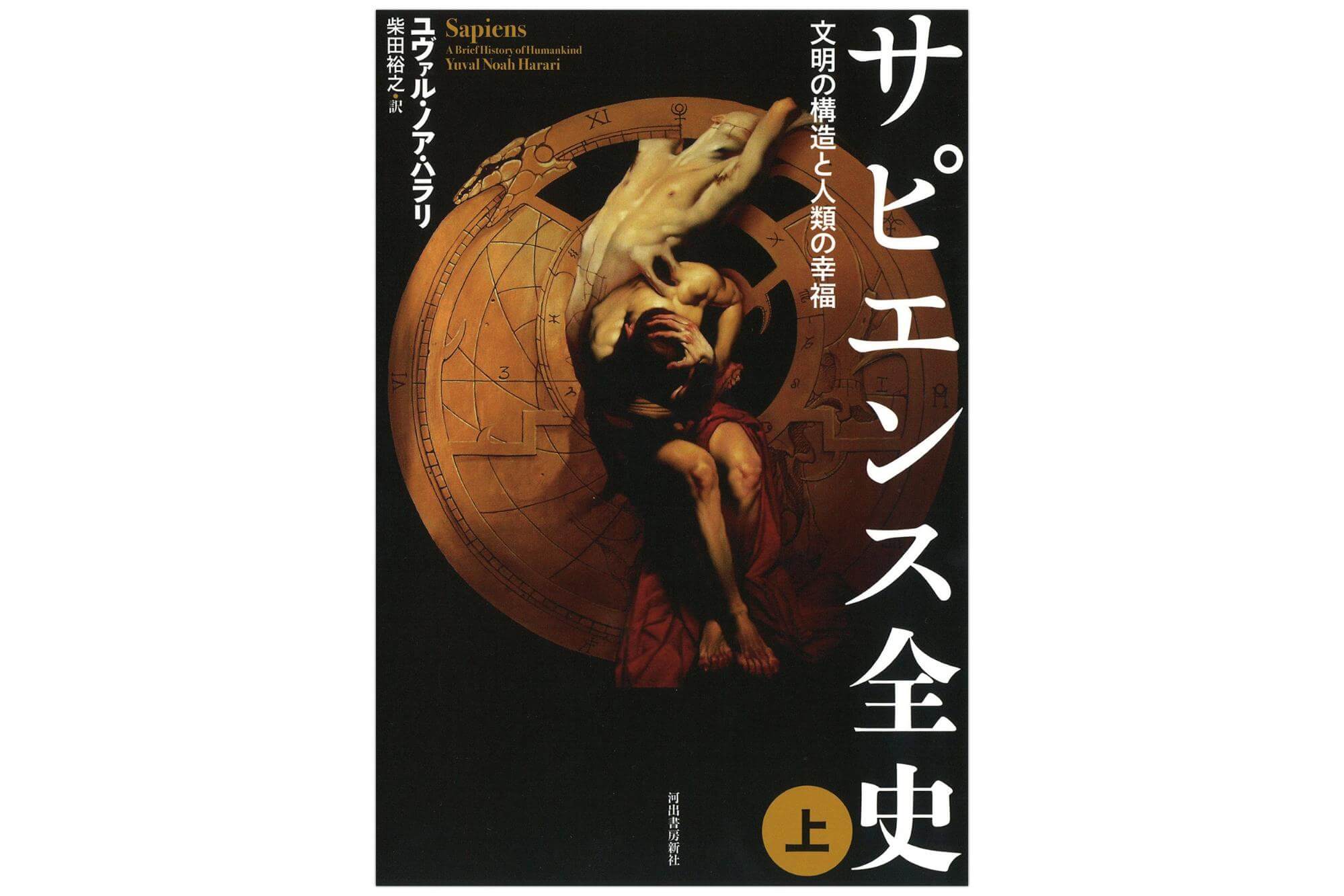
▲ユヴァル・ノア・ハラリ 『サピエンス全史(上)』河出書房新社、2016年
松田 虚構の力は構築様式を大きく駆動してきたと考えています。言うなれば虚構自体も構築の産物ですよね。言語・神話・宗教・貨幣・経済・政治・理念(イデア)など、物質的なモノではない諸物による構造を仮に広義の虚構だと考えると、そのあるフェーズは生環境の構築様式とも不可分の関係にあると思います。
構築3は、そうした「虚構」の構築力とも深く関わり合いながら、人工的な環境構築を最大限に増殖しようとするモードだと考えています。これは産業革命を経た18〜19世紀の実装以降、現在まで続く様式で、人類史上最高の技術をもって生環境をつくり、拡張する段階です。
構築3は初期近代にあたる17世紀後半から18世紀の啓蒙時代に準備され、同時代の科学革命、18世紀半ばからの産業革命、19世紀における工学の広範化、そしてこれらと両輪的に成長してきた資本主義の絡み合いのなかで巨大化したと考えています。そこで重要なはたらきをしたのは、人間の可能性や社会の進歩に関するさまざまな想像力だったと考えています。
構築3が構築1や2と大きく画される特徴は、人間が打ち立てた設計的ビジョンの質とその実現可能性です。それは構築の構想によって出来事をつくりだしていくような階梯だったようにも思われます。構築3は、科学や工学によって鮮明化された地球を、資本主義経済の資源や消費物として捉えていくことも大きな特徴です。近代的思考は、資源の利用によってその文明時点での課題を越えようとします。たとえある資源が枯渇しても、別の素材や物質からエクセルギーを引き出せるというエンジニアリングと資本運動の発展史観的な合一こそは構築3の強力な原動力となってきたとみなせるのであって、それは最終的にはたとえ地球を資源として消尽しても、地球外に新世界を発見しうるという未来像を伴います。
わかりやすい例としては、たとえばスペース・コロニーの建設やテラフォーミングといった宇宙開発の長年の構想がありますが、実はそれは人間にとって廃棄物としての地球をその背後に従えているとも言えるのではないか。そしてこれらは構築0からの離脱志向ともみることが可能ですが、こうした志向性は現代というよりも構築3の発生の端緒において仕込まれていたのではないかとも予見されます。
そして構築3では、構築0の自律運動が最大級に災害化します。なぜなら構築3世界がいかに最高の技術によって精緻に作り上げられたとしても、地球のエネルギーはいつも変わらずそこにあるからです。ですから私たちは構築3というモードを、人間の近視眼的な技術至上主義の限界を抱えた様式としても捉えています。
そして構築3の限界に関するこのような問題意識をもとに、現在から未来にかけての構築様式として私たちが展望しているのが「構築4」というモードです。
上妻 ありがとうございます。よくわかりました。しかし、こうして改めて構築4までのプロセスを辿ってみると、人類史のifとして、構築2から4にもっとシームレスに進んでもよかった気もするんです。なぜそんなことを思うかというと、構築4は存在論的な議論でもあると思うからです。たとえば、ウイルスとの共存にしても、今いきなりそうなったわけではなく、人類が(あるいは生物が)誕生してから常に起こっていたプロセスだったわけですから。だから、構築4における人間+植物や動物や細菌やウイルスなども含めて、共進化的な構築というのは常に生物史における存在論的前提としてあったはずです。もしそう考えることができるのなら、なぜ僕たちの実際の歴史は構築3のような逸脱を抱えてしまったのか、という逆の問いかけが成り立つと思うのです。
ポイントになる気がしているのが、先程の「弱さ」の問題です。つまり、他の霊長類と比較しても弱かった人類の欠如態の埋め合わせが、道具の制作や住居の構築といった身体拡張の本質にあり、その過剰性がある捻れを抱えた時に構築3に至るのではないでしょうか。だからこそ、構築3が僕たちの社会に浸透していることが現実問題として否定できない中で、どう具体的に構築4に向かう道筋を、単なる近代批判や環境保全の規範意識としてではない仕方で、かつ、説得力のある必然性や内在的な動因として想定できるのかというのが、僕自身の制作にまつわる問題意識の中でもモヤモヤしている部分なんです。そのあたりはいかがでしょうか。
松田 構築3が芽吹いていく時に、人間はそれを悪い逸脱と考えてはいないというところがまずポイントでしょうね。構築0のよりうまい利用や調停、より高度な人間世界の実現、そして多様なレベルでの構築0からの自立と離陸、ということを考えたのではないかと思います。構築3に進まなかったとしたら、いっけん世界は構築1と2で充分だったように思われるかもしれませんが、ヒトの構築行為における構築様式1は2を、2は3を生んできたという史的階梯そのものにこそ意味があるのだと思います。
それと、ヒトが異種や多種、生命や非生命との共進化的存在だというのは、構築3時代の科学がなければわからなかったことでもあります。もちろん神話としてそうした自己像を備えうる可能性はあると思いますが、少なくとも微生物やウイルスとの共進化イメージをもつことまでは難しかったかもしれないですね。
私たちの見立ては、しかし構築3はその初発時点において地球からの逸脱志向を含んでいたのではないかということなのです。そして一度駆動し始めた構築3の過剰性はきわめて強力です。
そのうえで、ヒトの「弱さ」や欠如が、つくることや構築することをうながしてきたのだろうという見方は、生環境構築史の前提でもあります。類人猿研究者、島泰三さんが『はだかの起源ー不適者は生きのびる』でも示すように、人は動物としてはきわめて不利な毛皮を失った身体へ「進化」したがゆえ住居をつくらなければならなかったし、またそこで火を管理するようになって、食生活、生活様式、そして類人猿としての形質を大きく変えることになった。
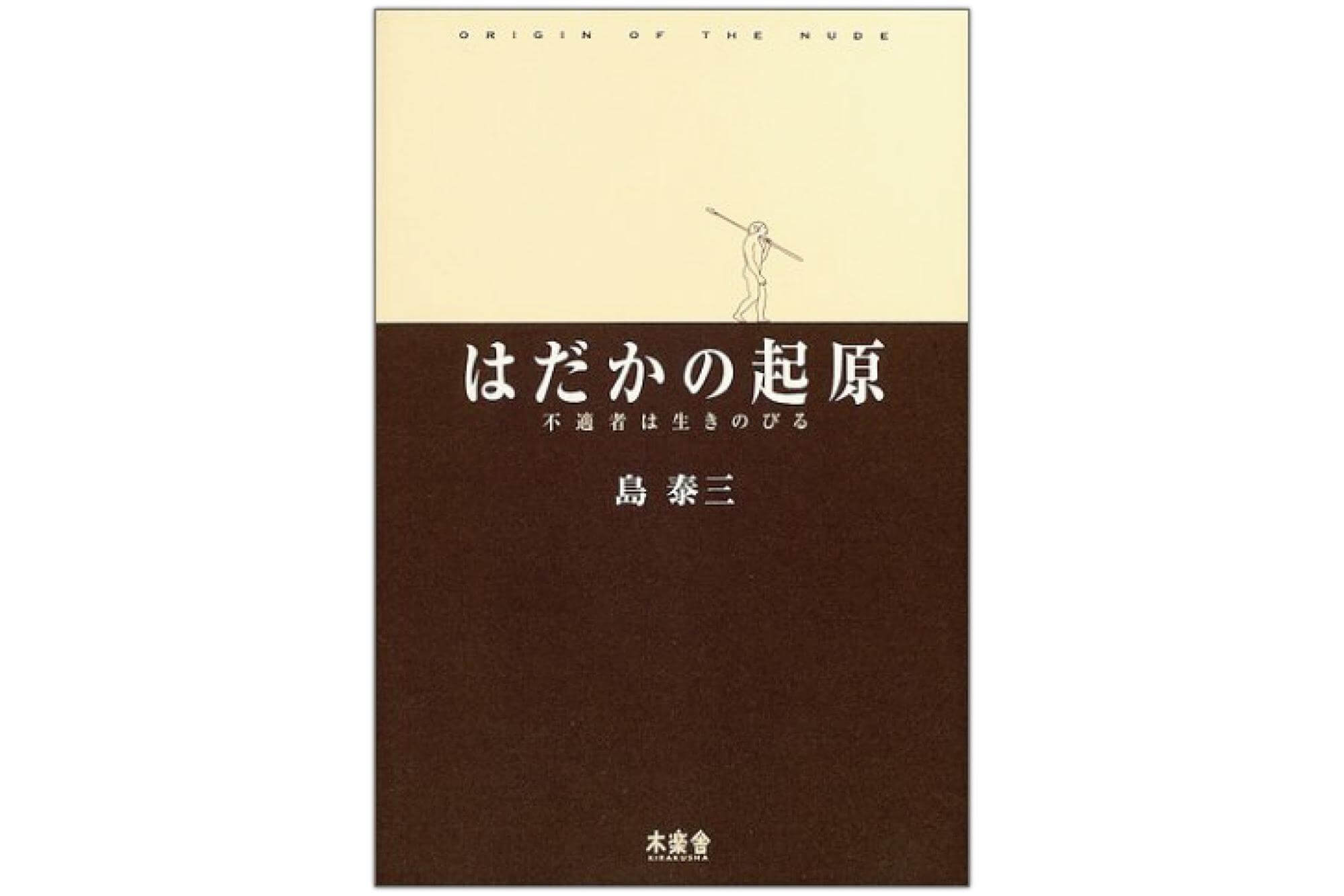
▲島 泰三『はだかの起源ー不適者は生きのびる』木楽舎、2004年
構築1の力を高めた人類は、構築0世界にニッチ(生物学的地位)を確立してゆき、 構築2の高度化を伴いながら文明に高められた古代世界は、植民地の拡大、帝国化、遠隔交易などを経て世界=経済(ブローデル)の構築段階に進み、中世から近世には世界=経済圏の複合と強化を経て、近代世界システム(ウォーラーステイン)が準備されていく。航海や科学の知見を通じて世界像も書き換わっていくなかで構築3というプロジェクトが芽生えて醸成され、科学と技術と資本主義の三位一体的進歩が構築3を強烈に駆動していった。その過程では量としてのヒトも爆発的に増加します。バイオマスとして甚大になったヒトの量と、その活動を収容するテクノマスとしての構築3のひろがりも連動的だと思われます。ただ、構築3的建築、つまり典型としては鉄の高層建築などはまず世界経済の拠点都市に交換の舞台として広がっていくのであって、住居への適用は応用的だったとも思われるので、構築3的建築もまずは交換に結び付いて発生・拡大するのだと思います。
構築3の実装は、多くの人びとが健康かつ長寿命に生きられるようになった諸科学の発展と連動しており、またその過程では自然科学を通じて構築0の性格とその歴史もますます詳らかにされてきました。
しかし構築3は構築0を支配したり、制御したりできるというわけではありません。構築0を人間世界に調和的な存在として方向付けることもできないのです。
ですから構築4というのは、構築3段階で達成された諸科学や技術の成果を充分に受けとめた上で、しかしちょっと立ち止まって、世界の未来像として、では次に何を考えるのかという思念でもあると思うんですよね。構築4の提起とは、構築3の人間世界が一定の閾値を越えたからこその、必然的で内在的な提案であると私たちは考えているんです。
[第2回につづく]
この記事は、中川大地が司会・構成をつとめ、2020年7月31日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。
都市史の探求から「生環境構築史」というアプローチに辿り着いた松田法子さんとの濃密な対話は、やがて地球全体の人口拡大が落ち着く未来に向けて、土地との関係を見直すことで、どんなライフスタイルや社会像が提案できるかの展望に向かっていきます。


