「クールジャパン」と呼ばれた時代も久しく、平成年間を経て日本の経済力はじわじわと力を失っていきました。そんななか2020年代の日本文化はどうやって国際競争力を発揮すべきか。アートからアニメ、ファッションや特撮、音楽、あらゆる分野のスペシャリストとともに議論しました。
(特別協賛:東急株式会社、協賛:オクトパスエナジー)
※この記事は2023年6月21日開催のトークセッション「2020年代の日本文化の世界発信|石岡良治×宇野常寛×草野絵美×増田セバスチャン×吉田尚記(渋谷セカンドステージ)」の内容に加筆修正を行い、記事化したものです。
▼「Hikarie +PLANETS 渋谷セカンドステージ」について
東急株式会社・渋谷ヒカリエとPLANETS(主宰・宇野常寛)の共同で運営されているこのプロジェクトでは、渋谷からの情報発信により新たな文化コミュニティの形成を目指し、2020年、そしてコロナ禍を経てなお進化を続ける“これからの渋谷”を考えています。
端的に言うとね。
吉田 今日のトークテーマは「2020年代の日本文化の世界発信」です。「クールジャパン」がすっかり無力化してしまった平成を経て、2020年代の日本文化はどうやって国際競争力を発揮すべきか。クリエイターと批評家のみなさん、それぞれの立場から議論していきたいと思います。
宇野 よろしくお願いします。一応僕がこの会の主催なので、今回みなさんに声をかけた意図を簡単に説明させてください。御存知の通り、増田さんは90年代の原宿の「Kawaii」文化を確立した人の一人で、最初にお会いしたのは15年ぐらい前だったと思います。当時、増田さんは90年代の歩行者天国のあったころのようにストリートから新しい文化が生成して来る回路が当時の原宿では死んでしまっている、という問題意識を抱えていて、この点について議論したのを覚えています。そのときの結論は、既に「Kawaii」の遺伝子は全世界に拡散していて、その原宿はその「聖地」としての役割を果たすべきではないか、ということだったと思います。実際にその後、増田さんはきゃりーぱみゅぱみゅを中心とした「原宿」の2010年代の展開に大きくコミットし、その「聖地」化を進めていった。
あれから10年ほど経ったわけですが、今はこうしてもう一度増田さんとじっくり話すよいタイミングだと思っています。要するに「あの」オリンピックをきっかけに、ようやくこの国の人たちも目が覚めたところがある。「クールジャパン」という発想自体の、自分たちでその近過去の実績を「クール」だと誇るようなみっともなさに、当時はしゃいでいた人たちもさすがに気がつきはじめていると思うんですね。なので、このタイミングで改めて増田さんと議論したいと考えてお呼びしました。
増田 よろしくお願いします。いわゆる「Kawaii」と言われるものをコンセプトにいろいろなものを作っています。宇野さんとは今年3月に、いま拠点にしているニューヨークで再会して、これからの日本のポップカルチャーをどういうふうに世界に持っていけるかといった議論していたところ、今回こういう場があるということで誘われてやってまいりました。
アメリカに一年以上住んでいると、日本人が日本にいると意外と気が付かないことがすごくたくさんあって、「日本人」というのがアメリカでは個性になるんです。ニューヨークでは6万人の日本人が住んでるんですけれど、1,000万人ぐらいいるなかでの6万人ということは、それも一つの個性なのではないかと思います。今日はよろしくお願いします。

宇野 そしてもうひとりが、こちらにいるアーティストの草野絵美さんです。草野さんは僕よりもだいぶ、10歳以上年下なのだけどなぜか異常に80〜90年代のポップカルチャーが好きで、この時代のカルチャーを参照した作品を発表しています。そして、NFTやAIを活用した、新しいタイプの表現者でもあるので、このテーマに相応しいと考えました。
草野 よろしくお願いします。私はレトロフューチャリスティックなものが大好きで、2010年代の始め、シンセウェーブ(Synthwave)という80年代のポップカルチャーから影響を受けたウェブ上で始まったコミュニティーで、ミュージシャンとして活動していました。
今年からAIを使ったアート活動を始めました。これは実は全部私のボキャブラリーからAIで作った写真なんです。

この場合は、60年代のイギリスでミニスカートやツイッギーなどが流行った時代の雰囲気に加えて、特撮のエッセンスも入っています。場所は80年代の秋葉原を設定して、数百字の英文から画像を出力させるんです。
ちょうど今週の「WWDJAPAN」というファッション業界紙では、私の顔をモデルにしたAIが表紙を務めました。日本のファッション誌においてはAI画像が表紙を使用されたのは初めてのことなんです。

あとは一昨年からNFTをやっていて、以前スティーブ・アオキが小学生の作ったNFTを3点合計240万円で購入して話題になったニュースがあったんですが、それがうちの息子なんですね。それをきっかけに自分でも「新星ギャルバース」というNFTプロジェクトを共同創業している、新しいテクノロジーが大好きな新人類タイプのオタクです。よろしくお願いします。
宇野 よろしくお願いします。最後に、批評家の石岡良治さんです。
石岡 はい。私はPLANETSではよくマンガやアニメ批評の番組に出演したり、早稲田大学の文化構想学部で授業を持ったりしています。興味関心は視覚文化全般で、映画や現代アートなどビジュアルに関わるものは大好きです。たしかに「クールジャパンってダメだったな」と思いながらいろいろ話したいと思いますので、よろしくお願いします。
日本人の国民性ならではのクリエイティビティ
吉田 それでは、ここから議論をしていただくにあたって、「2020年代の日本文化が国際競争力を発揮するにはどうすべきか」というお題に対して、キーワードを挙げていただきたいと思います。それでは増田さんからお願いします。
増田 僕は「日本(人)的クリエイティビティ」としました。括弧があるのは、日本人でなくても日本の風土で育って日本文化に慣れ親しんだ人なら誰でもいいという意味です。みなさん少なからず海外に行ったことはあると思うんですが、世界に出れば出るほど日本の良さがわかってくるんです。とくにアフターコロナの時代において、日本人的なきめ細やかさとか、緻密にものを組み立てていくクリエイティビティがかなり必要とされていると思います。

少しスライドを交えながら説明していきたいんですが、たとえばこれはニューヨークで10年前に開いた個展の様子で、おもちゃやリボン、アクセサリーなど「かわいい」ものを細かく貼り付けて構成された作品を展示したものです。その頃アメリカで流行っていたアーティストはレディー・ガガやケイティ・ペリーなどで、インタビューではこぞって日本のポップカルチャーに影響を受けたと公言していたので、かなりの人が見に来てくれたんです。「レディー・ガガやケイティ・ペリーが愛してやまない日本のカルチャーって何だろう」という興味で、ある意味そこで初めてニューヨークの人たちが「Kawaii」ものを理解した展覧会になったんですね。
吉田 こういうものが「Kawaii」であり、かつ日本人的なセンスがあるというのはほとんど日本にしかいない自分ではわかるんですけど、海外にいてどんなときにこういうセンスが特殊だと感じますか?
増田 そうですね。たとえば本当に細かいこと一つ一つができないんですよ。いまニューヨークでレストランのプロデュースをしているんですが、工事業者さんと仕事をしていても掃除ができなかったり、ペンキを塗るときに養生をしなかったりするんです。小さいブロックを一つ一つ並べるようなことも苦手で、バケツの中に入ったブロックをザーっと流すというようなことになってしまう。結局そこは教育の違いだなと思うんですよね。でもこういった、日本人なら当たり前にやっているようなちまちましたことが意外にも個性になりうるというのが、ニューヨークに一年いて一番感じることですね。

こちらはオープンしたばかりの寿司レストラン「SUSHIDELIC(スシデリック)」の内装です。日本で飲食で成功された方はだいたいニューヨークに進出したいという方が多いんですが、そのときにどういうふうに考えるかというと、ほとんど内装が障子で提灯があって、職人のおじさんがしかめっつらで腕を組んで待ち構えているような典型的な「伝統」の日本イメージを持ってくるんですよ。でもニューヨークの人たちがそういった日本をイメージするかというとそうではなくて、今の時代ヤンガージェネレーションは、マンガやアニメ、ゲームの世界観を欲しがっているんですね。だから今回僕が寿司屋をプロデュースしてくれと言われたときに、今までの固定観念をひっくり返して、いま日本で強いといわれているポップカルチャーと併せてプレゼンテーションをしようと思ったわけです。回転寿司にしても日本では単に手間を省略するために回していると思うんですけど、アメリカ人からすると「寿司を回しちゃってる日本おもしろい」という感覚なんです。そういうことを全部逆手にとって、日本的な要素が全部エンターテイメントになることをプレゼンテーションしたんです。この「SUSHIDELIC」というのはサイケデリックとデリシャスを合わせた造語ですけれども、こういった店をつくっています。
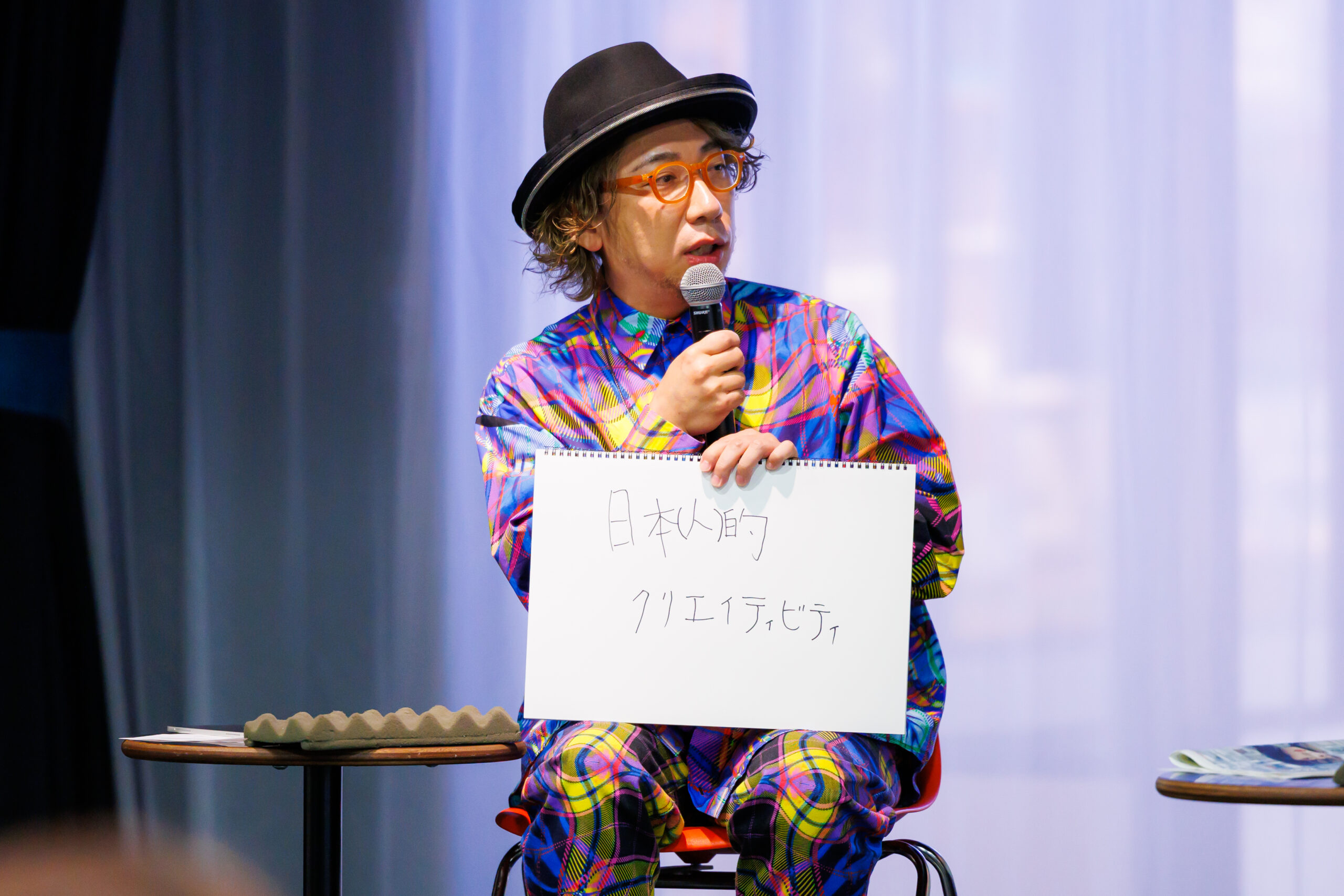
吉田 ありがとうございます。それでは草野さんにキーワードを頂きたいと思います。
草野 はい。「テックユートピアニズム」と書きました。テクノロジーに対して楽観的に考えることができるのが日本人の強みかなと思っています。たとえば子供たちがロボットを作るにしても西洋では兵器のようなデザインになるのに対して、日本だとみんなかわいいデザインになる。それは国民性として本当に染みついているものだと思っています。あるいはNFTもそうだし、AIやWeb3.0とかに関しても、日本ではとりあえず様子見の態度を取ることが多いと思います。アメリカはやっぱり白黒はっきりつける人が多くて、本当に嫌いな人は嫌い、好きな人は好きというのがはっきりしているんですけど、日本は「クリエイターがマネタイズできる仕組みになるんだったらありなんじゃないの?」「ちょっとわからないけど興味あります」くらいの距離感の人がすごく多いので、そこは希望かなと思っています。
コレクターさんの気質も全然違って、西洋では投機目的の人が大半なんですけど、日本人はただ作品を買ってそれを愛でることがすごく多くて、西洋の人もみんなびっくりするんです。

増田 たしかに僕の作品も、ファンの方が買ってくれはするものの、その後なかなか市場に出回らないんですよね。
草野 そうですね。そこがけっこう日本人の感性でおもしろいところだと思います。新しいクリエイティブを加速してくれるテクノロジーが出たときに、前向きに取り組めるクリエイターがすごく多いのではないかな、と。動画を作ったりPixivに絵を投稿したりする人も多く、人口の割合的にはクリエイターがすごく多い国なので、そこはチャンスかなと思います。
吉田 なるほど。すみません、日本人の国民性の点で文脈がつながってしまったので、ここで僕からも出してもいいですか?
僕は「ファンごと輸出する」ことが必要だと思ったんですよ。僕はアイドルファンなんですが、アイドルファンのクリエイティビティって異常に高いんです。全然おもしろくもなんともない10代の女の子からおもしろさを勝手に引き出して、「ここすごいよあなた!」とSNSやライブでずっと言い続けることによって、ときどき本物になってしまう子がいるんですよ。この「お客様側が何かやる」という文化はあまり世界にないらしいですよね。
草野 それすごくわかります。
増田 ある意味二次創作も含めてそうですよね。
吉田 ちなみに僕が10年以上推している高城れにちゃんの30歳の誕生日が今日(6月21日)なんですけど、その例で言うとももいろクローバーZのコンサートで「世界のももクロナンバーワン」というコールがいつの間にか生まれ、ファンのことを「モノノフ」と呼ぶようになったのは、運営が用意したわけではなく完全にファンメイドなんですよね。ファン主導で作られて、そこに変な勢いが生まれていくというのを目の当たりにしてきたんです。こういうももクロのムーブメントはとてもユニークだったんだと思うんですが、じゃあこれがいまどうやったら輸出できるのかと考えると、VTuberで同じことが起きているんですよ。VTuberの世界中のファンが、日本人のVTuberのファンと同じ振舞いをしているんです。「全員が設定に乗っかって楽しむ」という振舞いが世界的に発生していて、僕が一番好きな例は、VTuberは当然男性が女性のアバターを使うときもあるので、そうすると配信中に「どうせ俺おっさんだしな」というような自虐的なことを言う美少女が現れるんです。そしたらファンが「またこの美少女は自分のことおっさんだと思ってる」みたいなコメントが返される世界観ができていて、このクリエイティビティはおそらくまだ世界にそんなに多くないだろうなと思います。
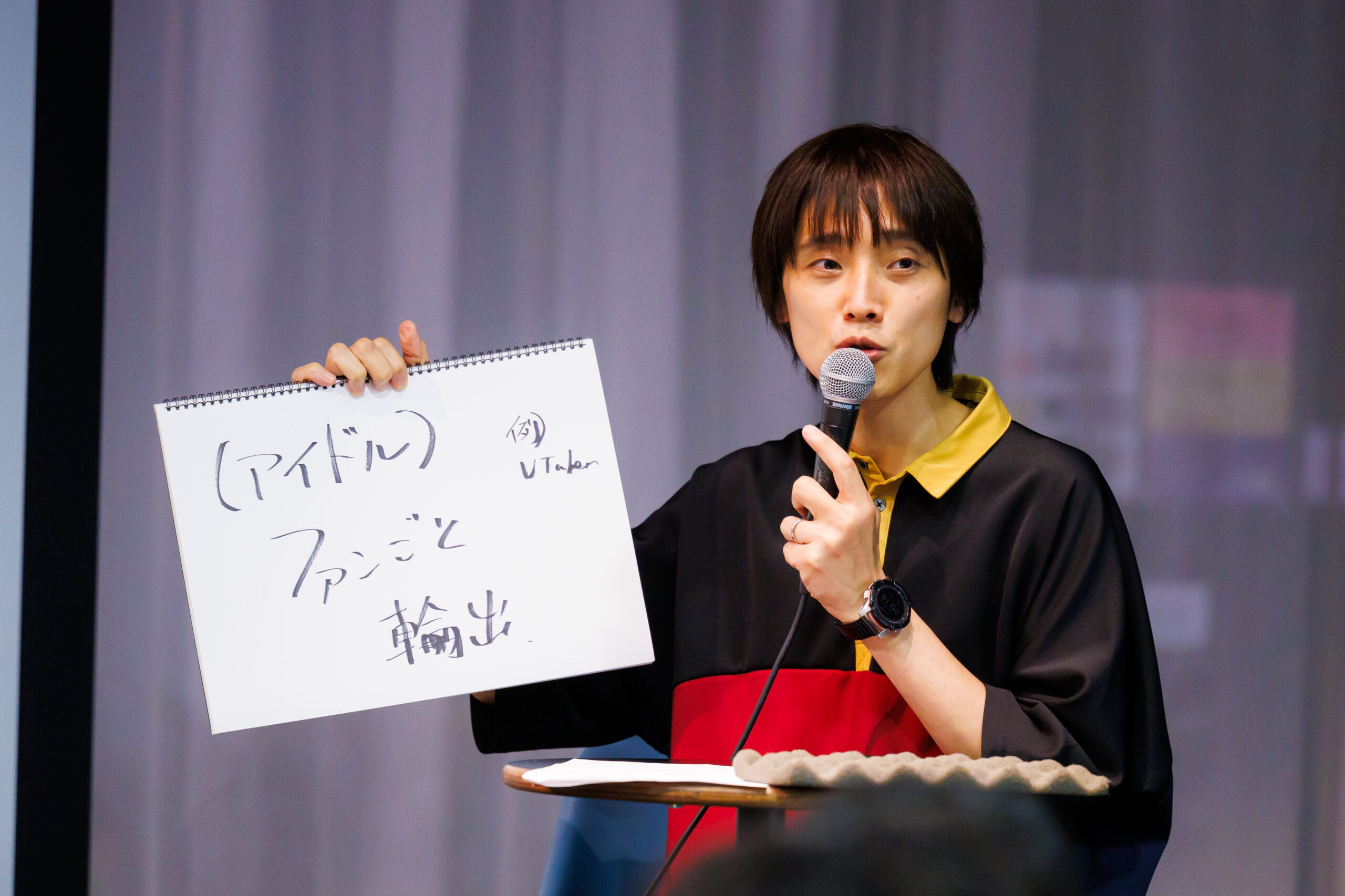
日本文化の(日本人の)捉え方
吉田 さて、そろそろ批評家のお二人にお聞きしましょう。石岡さんはどうですか?
石岡 私は一歩悲観的になってから二歩前に出るようなことを言いたいんですが、「楽しい“廃墟”としての日本」というテーマです。なぜ日本が「廃墟化」したかというと、簡単に言えば一つは人口の意味での廃墟で、要するに少子化がどんどん進みました。にもかかわらず2020年代になって、マンガ・アニメのマーケットはいま未曽有の事態になっていて、非常に流行っていますよね。そこで鍵になる作品が、みんなが知っている『鬼滅の刃』です。実感として『鬼滅の刃 無限列車編』がとてつもない事件を起こして、2020年代にアニメ映画のヒットが連発する状況を作り出したことは大きいと思っています。日本の映画興行からアニメを消したらたぶん半額以下になってしまうとか、トップ10にアニメが半数以上を占めるとかそういう規模感ですよね。『ONE PIECE』や『コナン』の映画興行収入が100憶円突破というのも実はつい最近のことで、これも『鬼滅の刃』以降の話です。
ところが、アニメの社会的地位はおそらくそこまで上がっていません。財界もアニメの特集を組んだりしますが、心底すごいとは思いきれていないのではないでしょうか。保守的なエンタメ界の人たちも、いまなお日本映画史上最大ヒットした映画が『鬼滅の刃 無限列車編』だという事実を、きちんと受け止めきれていないと思うんですよね。たとえば監督が外崎春雄さんだと言われてもピンとこないと思うんですよ。同じくグローバルヒットした新海誠の『すずめの戸締まり』とか、井上雄彦の『THE FIRST SLUM DUNK』はすごく作家性が強いものですが、『鬼滅の刃』が作家性で評価されているかというと別にそうでもなく、どちらかといえばアニメスタジオのufotableの色が強いと思うし、内容面もわりと批判が多いですよね。炭治郎が何もかもセリフに出してしまうので。
こういうことも含めて、日本人は自己意識と実際に達成していることが、おそらく常に一致していないのではないでしょうか。だから国一丸となった「クールジャパン」のようなものは結局到来しなかったのだと思います。たとえば私は団塊ジュニア世代で、思春期は日本の洋楽マニアみたいなキャラだったんですよ。当時の洋楽マニアというのは、たとえばビジュアル系とか90年代の小室サウンドなんかを、ドメスティックで恥ずかしいものだとみなしていたんですね。あえて言うと「渋谷系」だけはかっこいいと思っていた。だから最近K-POPグループのNewJeansなんかが、SPEEDなど日本のレトロポップを参照して楽曲を作っているというような話があると、当時の「マニア」たちが「渋谷系がルーツですか?」なんてうっかり聞きにいってしまうんですが、じつはそんなことは全然関係なかったみたいなことがあるわけですよ。たぶんそれとは関係ないところで日本のレトロポップの良いところを拾っていて、でもその拾い方こそが、日本の廃墟のなかの真の砂金を拾っているということなのではないかと思っています。
アニメにしても、偉い人たちが「日本のマンガ・アニメは素晴らしいです」と言うと手塚治虫を持ち出すわけですが、現代のポップカルチャーに手塚治虫の系統はもはやあまり残っていないと思うんですよ、正直。これは手塚さんが素晴らしくないということではないですよ。とにかく自分たちがすごいと意識しているところと、実際にすごいとされているところが食い違っているという話です。

この点で少し悲観的なことを言うと、日本人は「リブート」が下手くそなのではないかと思うんです。2020年代に入ってから、2010年代以前のカルチャーに一切興味がなくなっている学生の子が増えたんですよ。興味あるのはみんな流行りの「ジャンプ」アニメなんですよね。つまり、一つのメディア表現とその歴史が好きという人が実は思いっきり減っているということです。だから日本のカルチャーやIPの遺産はいろいろあると思うんですが、たとえば『鉄腕アトム』が蘇る未来はあまり想像できない。自分たちにとっての美点と、実際の評価点が食い違っているから、いまや歴史化(=廃墟化)した20世紀のポップカルチャーの遺産を自分たちではうまく引き出せないのではないかと思っているんです。
ただ、その一方で、特殊な趣味でむしろ恥ずかしいと思われていたものこそが時代を超えて生き延びていたりして、「Kawaii」なんてその最たる例の一つですよね。このパターンはけっこう重要だと思っています。だから2020年代の課題としては、その食い違ったものをどう修正して、そしてその廃墟にある砂金をどうやってピックアップしたり拾ったりするかが重要かなと思っているんですよね。
宇野 日本人が「これすごい」とドヤるものって、ずっと勘所を外してきたと思うんですよね。だから、僕の最初の提案は「日本を見せつけない」ことです。みなさん、リオデジャネイロオリンピック閉会式での「安倍マリオ」を覚えていますか? よく出来たパフォーマンスでしたけど、あそこには一つも「未来」がなかったと思いませんか? オリンピックというのは次の時代の国家像を国際社会に対して示すためのプレゼンテーションであるべきだったはずなのに、そんなときに近過去のまだ元気だった頃の日本を、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」なんて言われていた頃の自己像を「みんなが好きな日本これでしょ」とドヤってしまった。あれに僕は限界を感じたんですよね
国境のないアプローチ
宇野 じゃあどうするかというと、必要なのはむしろ「国境のないアプローチ」だと思うんです。先程述べた震災の少し前の、原宿が元気がなかったころに増田さんが何を考えたかというと、「Kawaiiはもうすでに世界中にある」という世界を見て、「原宿は世界中のKawaiiものが好きな人たちの聖地になればいいじゃないか」という大転換をした。僕はあれは一つの正解だったと思います。僕や石岡さんが好きなオタク文化もそうで、世界中にすでに遺伝子はばら撒かれているわけです。何年か前に中国の『羅小黒戦記』というアニメの映画版が日本でも公開されたときに話題になっていましたけれど、驚くほど日本のアニメーションのエッセンスが継承されていて、しかも現地で独自の進化もはじめている。こうしたケースは既に山のようにあるはずで、僕は国産の作品を見せつけるのではなく、こういった遺伝子を継いだ作品を世界中の人々と一緒に楽しむ運動を、日本がリードする、くらいの気持ちでやるのがいいと思います。実際にいま日本のテレビアニメも、ほぼ毎週同時に見られていたとえば『水星の魔女』を見て「スレッタに死んでほしくない」なんてことを世界中の人間がほぼ同時につぶやいて楽しんでいるわけですからね。

だから僕は「日本にすごいものがあるので、それをみんなが見に来てほしい」というインバウンド的な発想はやめるべきだと思います。まずは世界中に散らばっている日本的なカルチャーを一緒に楽しむんだという前提がないといけなくて、それはさっきよっぴーが言った「ファン文化を輸出する」ことにもつながっていくと思います。日本人と日本以外のファンたちが一緒に同じ様式で楽しめば自然とファンの輸出もできてくるはずですからね。今までのクールジャパンはここが決定的に欠けていたのではないでしょうか。
増田 そう思いますね。僕、コロナ禍の時期に何をしていたかというと、各国のKawaiiコミュニティの人たちとZOOMでセッションをしていたんです。それぞれの国でどんな活動があって、Kawaiiというものがどういうふうに捉えられているのか、十何カ国分全部リサーチしていました。先ほどのアイドルオタクやVTuber配信のコミュニケーションの中での新しいカルチャーは、そういったコミュニティで生まれるんだと思います。人種・宗教・性別、全部関係なく、コミュニティが力を持っていくというふうに思っているんですね。それで僕が名付けたのが「Digital Tribe(デジタルトライブ)論」と言って、今まではその土地に由来した宗教やファッションといったカルチャーが生まれてきたけれど、いまこの時代ではデジタル上に趣味趣向を共有するコミュニティができて、ある種の国家ではないですけど、そこから文化が生まれていくのだと思います。
草野 すごいわかります。オンライン上のストリートがあるような感じですよね。
さきほど石岡さんがおっしゃっていた、今の若い子たちが歴史をディグらないという話もよくわかります。本当に情報が多すぎて、若い子たちにとってはたぶん80年代の音楽も先週出た楽曲も同列に映っていて、それが日本産なのか韓国産なのかハリウッドなのかもあまり気にしてないし、すごくフラットに見ている感じがします。いまAIアートのなかで「耽美系」という単語が流行っていて、耽美系というのはヴィジュアル系の特定のジャンルなんですが、この言葉を使うとそのメイクがすぐ反映されるんです。AIアートを作る上でのエッセンスとして日本のサブカルチャーが結構引用されています。
宇野 文化の日本史ではなく世界史を書くべきなんだと思うんですよね。石岡さんがさっきおっしゃっていましたが、90年代の日本では文化に明るい人はみんな渋谷系を聞いていた。でも世界的には90年代の日本のポップスで残るのは、まさにいまAIアートで引用されているようにV系の可能性のほうがむしろ高い、と言われていたりもする。世界史で見たときにはたぶん「90年代の日本のポピュラーミュージックからV系という特殊なジャンルが発生して、それがグローバルな広がり方をした」と記述される可能性が高い。このあたりに「「日本人の書く日本史」の限界がある。たぶん日本人の自意識とは全然違った日本文化史が必要で、それはもちろん僕らにとっては違和感のあるものになっていくのかもしれないけど、「日本人の考える日本文化史」と「グローバル視点の日本文化史」とをぶつけた上で何をすべきかと考えて初めて有効なアプローチができるんだと思います。クールジャパンの失敗というのは「日本人の書く日本史」を押しつけようとした問題なんですよ。
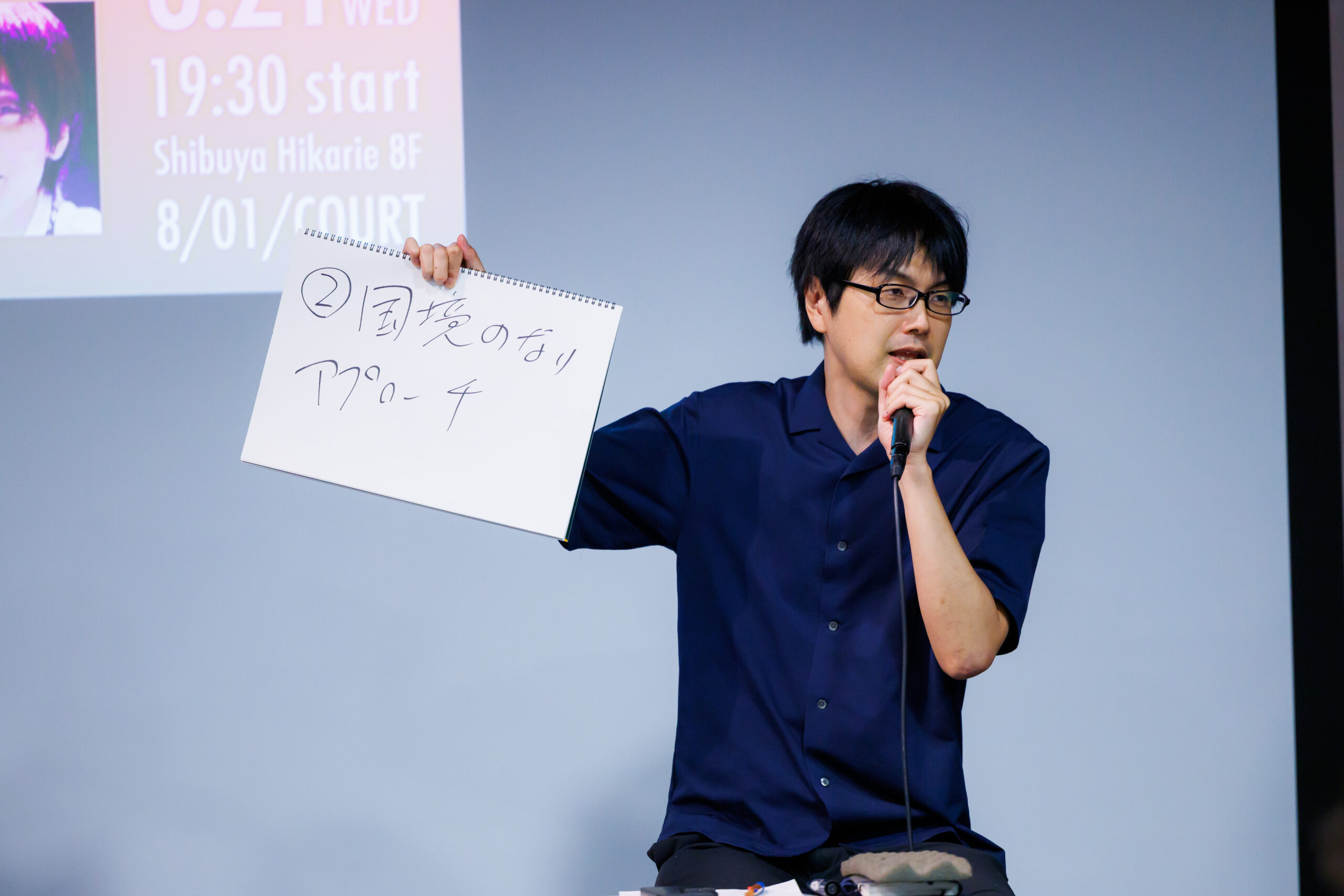
増田 クールジャパンの話が出てきていますが、これは元を正すと経産省の施策で、当時何を持っていったかというと結局ラーメンだったんですよね。税金を動かして最終意思決定権を持つおじさんたちの正解がラーメンだったんですよ。ラーメン自体は成功したのでそれはそれでよかったんですけど、どこに優先的にお金を使うべきかよくわかっていなかったのだと思います。そういうわかってないおじさんの言うことを聞きながらどんどんクリエイティブが小さくなっていくというようなことを、クライアントワークをする我々クリエイターはよくわかることですが、そうやって結局何もできずに輸出もできなかったというような状況に陥ったのがクールジャパンの失敗じゃないかなと思いますね。
石岡 分野によって異なる部分もあると思うんですよね。たとえば任天堂がビデオゲーム界のディズニーポジションにいるという事実の重みを、最近になって痛感しています。今の日本のゲーム業界には特にクリエイティビティの最先端性はないんですよ。にもかかわらずディズニーポジションを任天堂が持っているということはある意味一番すごいわけです。たった一個のIPで状況を覆してしまうのが任天堂の恐ろしさだと思っていて、「ポケモン」はその典型でしょう。「Wii U」という端的に言うと失敗していたハードがあったわけですが、『スプラトゥーン』を生んだことによってあのハードは黒歴史ではなくなったんですよね。『スプラトゥーン』はジャンルで言うとTPSという基本的には戦争のメタファーでのみ機能しているジャンルで、モニターとPCのスペックを上げてひたすら精密射撃を目指していくようなカルチャーなのに、とりあえずイカになってスミに潜るというとんでもないアイディア一発で状況をひっくり返したわけです。そんなことができるのは任天堂しかありえなくて、それはたぶん無理して輸出するとかではなくて、たまたま任天堂はできてしまっているという状況はありますね。
それとアニメに関しては、私は日本のアニメの今のすごさはどちらかというとテレビアニメというよりは、ミュージックビデオなどに使われているアニメイメージのようなもの、「アニメっぽいもの」がまさに遺伝子としてばらまかれていると思っています。草野さんの作品もまさにそうですし、あるいはYOASOBIの「アイドル」があれほどウケたのは、やはりそこにアニメが乗っかっていることが大きかったと思います。だから、一個一個のピースがたまたま組み合わさってできた奇跡の産物があるとしてそれが広まったとしても、その再現を目指しても今度は自意識が邪魔をして失敗する。しかしたまたまの組み合わせでうまくいくことはしばしばあると思います。
宇野 僕は別に国策なんて極めてどうでもいいと思っています。だけどクリエーションのためにこそ、戦後のガラパゴスに発展したポップカルチャーが一度思いっきり拡散したほうが良いと思っています。たとえば僕や石岡さんが主戦場にしてるマンガやアニメはもう明らかに成熟期にある。宮崎駿のようにアニメーションの描けるもの自体を拡張するような作家はもうこのタイミングではなかなか出てこない。成熟期に突入した表現がより発展するためには、もう戦略的に「閉じる」時期は終わったんだと思います。僕らは「最近面白いアニメないな」とか「最近面白い作家出てこない」なんてことを言いますが、その考え自体がわりと国内のドメスティックなシーンに閉じた思考ですよね。別に中央沿線のアニメスタジオが何軒潰れようと、その遺伝子を引き継いだ、それがサウジアラビアでもタイでもフィリピンでもどこでもいいんですけど、そこで面白い表現が生まれてそれを僕らが見れればそれでいいと思うんですよ。じゃあそのために僕らは何ができるのかという話だけをするべきだと思います。そのとき御上がやっていることが利用できるなら利用しようくらいのつもりで挑まないと、悪い意味で振り回されてしまうんだと思うんですよね。
草野 NFTでは国内市場あまりにも小さいので、若手のデジタルクリエイターで初期からNFTをやっている人たちは、Google翻訳などを使って英語のプロフィールで海外に向けて発信したりしています。私のコレクターも多くが日本国外の人たちです。ミュージシャンとしてグローバルニッチに活動してた経験が生かされました。2018年には「SXSW」でライブをしたんですけど、すごく自分の中でいい体験になりました。いろいろな国の人と音楽を通して交流して、そこでもまた推し文化が出てきて、日本のアイドルオタクの人とかがやっている、あの、ダンスみたいな……。
吉田 オタ芸ですか?
草野 そうそう! オタ芸をしているアメリカ人に会ったりして、そういう文化は広まっているんだと感じました。
一方で、そこで世界中のアーティストの人と会うんですけど、韓国のラッパーやバンドミュージシャンなんかは、旅費は全部政府のお金だったという人が大半だったんです。私たちは自腹を切って出ているのに、そういうところは違うなとたまに感じます。
増田 いや、本当にそう思います。僕、コロナ前に韓国で開催された「文化コミュニケーションフォーラム」に日本代表として参加したんですが、韓国は世界中の優れたアーティストやシェフ、映画監督などあらゆるジャンルの優れた人を呼んで、国内の若手の人材と一緒にワークショップなんかをやるんですよ。G20加盟国から各国の文化を代表するリーダーを招待しているそうなんですが、自分もそこに呼ばれていったときに韓国の方がいろいろなところを案内してくれて、ほんとうに日本よりよっぽどおもてなしがすごかったです。SAMSUNGの新型オーディオ機を聴ける部屋に行けば、そこでかかっている曲がBTSだったりして「ここまで推すんだ」と思いました。いまK-POPが世界を席巻していると思いますが、これくらいわかりやすく国主導で施策をおこなうのもグローバル展開には必要かなと思います。
草野 本気で取り組んでいる若手のクリエイターにもっとお金が回るといいですよね。
増田 今はほとんどのことがネット上で済むので、若い子たちがなかなか海外に出ていかなくなっています。でも、僕はニューヨークのハーレムに住んでいるんですが、隣にブロンクスという地域があって実はそこに若い日本人が結構住んでいるんですよ。そこはだいたい6万円程度で住めるので、ニューヨークでも来ようと思えば来れるんですよ。ただ、そういう日本人はなかなか人目につかないので、密かに若い人が起こそうとしているムーブメントを細かく拾って掬って、注目してあげるのもこれからの日本のクリエイティブに必要かなと思います。
宇野 僕や石岡さんは、増田さんや草野さんとは違って作品を作っているわけではなくその批評をしている側なんですけど、やはりここで足を引っ張っているのは国内のジャーナリズムと批評シーンだったりする。特にアートの世界では作品に対する言説が大事にされたりするのだけど、増田さんがニューヨークに拠点を移したのは増田さんの仕事を評価する国内の言説が弱かったからでもあったと思っているんです。実際の影響力で言えばものすごい大きいものがあったと思うんですが、増田さんの仕事についてきちんと批評しているものを僕はあまり見たことがありません。これはたぶんいろいろなジャンルに言えて、日本の場合ローカルな業界内のパワーバランスに影響されて批評やジャーナリズムがその業界の文脈の中に悪い意味で収まってしまっているという問題があると思います。
だから僕がもう一つ提案したいのは「グローバルな批評ジャーナリズムの確立」ですよ。たとえば僕や石岡さんのような批評家は一つの作品を総合的に見るわけなんですよね。一本のアニメを論じるときも、時代背景や政治的なメッセージのことを考えれば、作画や演出など技術面のこと、それがYouTubeで配信しているのかアマプラで配信されているのかなど流通するプラットフォームの問題も、それが20世紀以降の映像史の中でどういう位置づけにあるかとかいったことを踏まえて総合的に批評するんですが、そういうのは端的に言うと嫌われている。業界の外側から総合的に批評されることを恐れているし、ファンコミュニティや業界誌のライターには知的なコンプレックスから総合的な批評を嫌う人もすごく多い。だから日本のアニメジャーナリズムの主流はスタッフのインタビューを取って解釈の正解を聞いてくるようなものがいまだに主流になっている。そういったものに付き合っていると文化を拡大していく、広く共有していくためのエンジンとして言説がまったく機能しなくなるんだと思います。だから僕は国内で閉じるのはやめて、翻訳環境もどんどん整っている今、グローバルな批評ジャーナリズムがあらゆる分野に必要だと思っていて、それが実現する環境が近づいていると思うんですよ。これが僕の最後の提案です。
増田 Kawaiiコミュニティって世界中にあって、すべて合わせるとほんとうに小さな国くらいの人口になるんですよ。なにもオシャレやファッションに興味がある人だけではなく、その人の親兄弟や友達まで含めるとほんとうに大きなコミュニティになっているし、たとえばゲームクリエイターなどテクノロジーに詳しい人がコンタクトしてくれて、「セバスチャンの世界観をこういうゲームのキャラクターでやったら面白いと思うんだよね」という形で提案をしてくれたりもするんですね。そういったコミュニティの中のコア層ではない、少し周辺にいる人たちから新しいクリエイティブが発生するという確信もあって、それは日本に限らず、こういう形でコミュニティを通じたクリエイティビティというのがこれからも生まれる可能性があると思っています。
(了)
この記事は徳田要太が構成を、岡田久輝が撮影を務めました。

