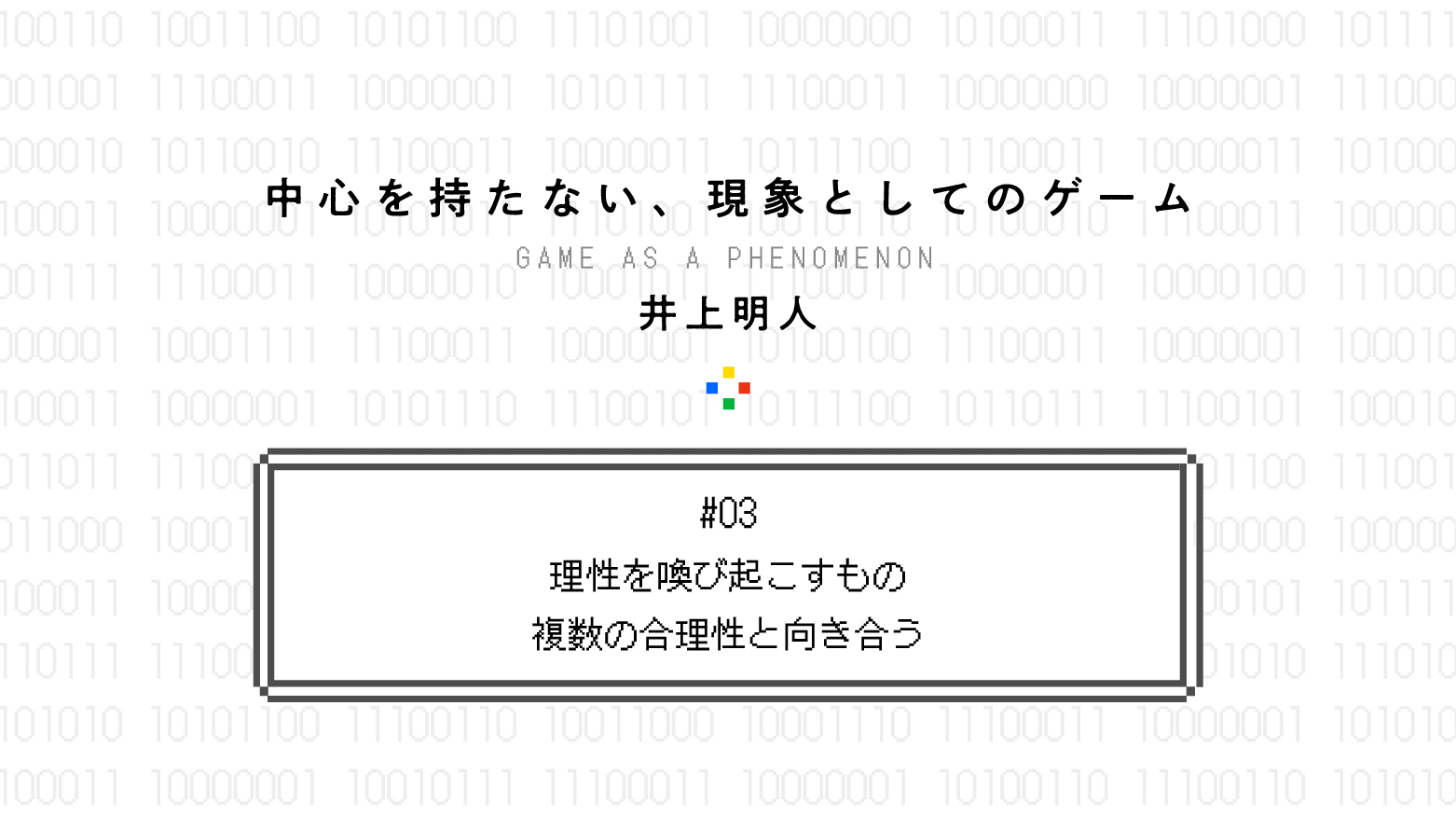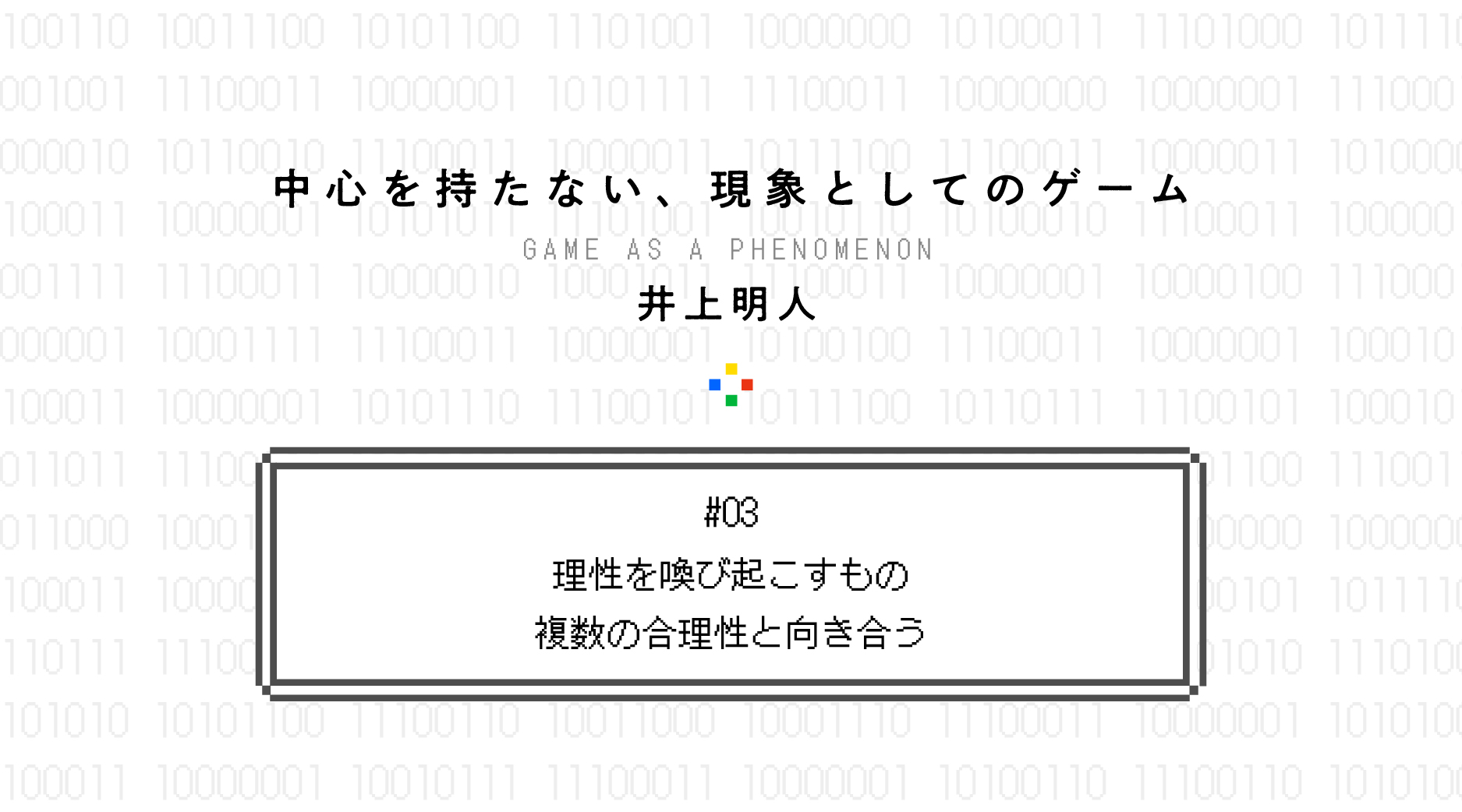ゲーム研究者の井上明人さんによる連載「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「ゲームや遊びとは何か?」。この問いに答えるべく、ゲームや遊びに関わる多様な現象——ルール、コミュニケーション、非日常など——が興味深いかたちで相互に関係しあっている、その複雑さを論じます。
第3回では、ゲームがいかに個人の理性では理解が難しいほどの複雑な集合的行為を理解させやすくするのか。都市運営や戦争に関わるゲームを例に考えます。

「中心をもたない、現象としてのゲームについて」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
※この記事は書籍として刊行予定の『中心をもたない、現象としてのゲームについて』のイントロダクションとして書かれているため、「本書」という表記となっております。
端的に言うとね。
ゲームが我々の感覚や価値判断を形づくり、それを通して世界を把握する媒介たりうることを示したが、ゲームの力は必ずしも感性的な理解のみを促すのではない。都市運営シミュレーションのゲームや戦争に関わるゲームなどを例に、ゲームがいかに個人の理性では理解が難しいほどの複雑な集合的行為を理解させやすくするのか。また、複数の合理性が衝突しあう時の厄介なジレンマをゲームが描き出しうるのかを見ていく。
1.2.1 人々の集合的振る舞いを理解するメディア
前回、現地の兵士の行動に周囲の環境がどのように把握されているかという話をしたが、現場だけではなく組織トップに見えている世界も、文字だけではわからない複合的なプロセスで成立している。そして、ビデオゲームは、そうした複合的なプロセスで思考する体験をプレイヤーに与えてきた。
たとえば都市運営シミュレーションのゲームである『シムシティ』はそうした作品の好例だろう。このゲームで効率的な大都市建設を追求しはじめると、まずは原子力発電所を建ててみたくなる。都市の区画は碁盤目状に整えて、住民が「ここまでは耐えてくれる」というぎりぎりの税率まで引き上げてしまう。
どうしてそんな極端な方策に走るのかといえば、その成否が「数値」としてはっきり見えるからだ。人口と資金をどんどん増やしたいと思うなら、お金を増やしたいと思ったとき、原子力発電は多少のリスクを考えたって割安になる。ちょっとくらい税金が高くても、住民がぎりぎり我慢できる範囲もわかる。そうして節約と増税で貯めた予算で道路を整理すれば、都市インフラの発展効率がぐんと向上する。こうした要素が一目で関連づけて把握できるわけである。
実際、小学生の子どもですら、しばらくプレイを続けるうちに「工業税率を下げておこうか」「住宅税率も見直したほうがいいのでは」といった提案を平然としてくるので、驚いたという話もある[1]。
もちろん、シムシティで原発を推進すればうまくいくからといって、そのまま実際の社会政策に転用できるわけではない。当然、実際の原発政策には様々な課題がある。ただ、ここで確認したいのは、あるさまざまな前提が与えられた枠組みの中で、そこから眺める風景がどういったものであり、そこからどういった秩序が合理的に映るか、ということだ。原発政策の例でいえば、原発政策が正しいかどうかが問題なのではなく、どのような前提を与えられた時にそれが効率的であるという発想になるのか。その仕組みを理解できるのかということだ。
ゲームを使わなくても、「原発はメルトダウンさえしなければコストも環境負荷も小さい」という論旨を書くことは可能だし、各種発電のコストを数字で比較するだけでも、伝統的な手法としては十分に理性的な理解を促すことができる。
ゲームをプレイするときも、それとほぼ同様のことは理解することになる。そして、そのうえで、原発政策を推進することでどれだけ財政上の負担が減るか。大気汚染を防ぐことの重要性はどれほどのものなのか。一見、無関係とも思えるさまざまな前提が絡み合う中で、何をどこまで妥協できるのか。太陽光、風力発電などの比率のバランス感を具体的に把握したうえでの政策把握が可能になる。こういった多面的でグラデーション的な理解を促すものとしては文章での把握よりも、ゲームのような形式のほうがよほど優れている場面がある[2]。
都市のように、多様な関係者が同時に意思決定する状況というのは、あたりまえだがとても複雑である。その複雑な状況を、何の道具もなしに、理解しようとするのはとても大変なことだが、シムシティのようなゲームが切り開いたのはそういった複雑な状況理解である。
1.2.2 ゲームで表現される複雑性はどこまで妥当か?
「多様な関係者が同時に考えながら意思決定をする状況」を理論的に理解しようとする試みは多くの学者が取り組んできた課題の一つでもある。
20世紀後半に、社会科学者や人文科学者たちは、多様なシミュレーション手法を用いて、なぜ利己的な人々が協調行動をとるように進化してきたのか(アクセルロッドなど)。なぜ利己的な人々の集まりでも、平等のような概念が大切にされるのか、といったことが説明するモデルがつくられた(ロールズ)。多くのモデルにおいて、利己的行動を突き詰めていった結果として、多くのプレイヤーが協調的な振る舞いをとりはじめる可能性が指摘されている。
実際、ゲームを遊んでいると利己的行動をとることもできるはずなのに、協調的な行動をいつの間にか選び取っているという体験をすることはある。利己的に有利な戦略をとろうとすればするほど、協調的であることを選び取らざるをえないゲーム[3]もあるし、逆に協調的であろうとしても、利己的な利益追求しかできないようなゲームもある[4]。
人々の振る舞いは、しばしば与えられた前提によって変化する。利他的な行動のコストを抑えて、報酬を期待しやすいゲームにすれば「仲間のために助け合う」行動を体験させやすい。逆に、利他的な行動を採るコストを高くして、報酬を得にくいゲームをつくれば利己的な行動を促しやすい。ゲームの中では人々の振る舞いを調整するインセンティヴ構造をいじることが現実世界よりもかなり簡単にできる。そのため、同じゲームプレイヤーであっても、与えられた利得の構造によってはまったく別の振る舞いをみせる。そして、こうしたシミュレーション手法の一部は「ゲーム理論」と呼ばれている[5]。ゲームと、数学的な意味でのゲーム理論との相性は――その名からしても、ある意味で当然のようではあるが――かなりよく、ゲーム理論が説明してきたような社会科学諸分野の説明の仕方をほとんどそのまま、コンピュータ・ゲーム上に表現としてもってくることは可能だろう。実際、こうしたことに中心的にとりくむ分野として「ゲーミング・シミュレーション」と呼ばれる独自の取り組みがあるほどだ。
ただし、こうしたインセンティヴ構造に支えられて振る舞うプレイヤーたちは、自分たちがどういった前提のもとで動いているのかを必ずしも意識しない。協調行動をとることが明らかに有利な戦略である場合や、敵対行動をとることが明らかに有利な戦略である状況下で、ほとんど何のジレンマも発生しないようなケースでは、意思決定に悩んだり、良心の呵責を感じたりすることはそれほどない。
先ほど述べた『シムシティ』でも、原発をどんどん建設してほどよく増税するような意思決定が「得策」になるのは、そもそもゲームの“お約束”に縛られているからこそだ。こうしたゲームの性質は批判されることもある[6]。『シムシティ』に限らず、ほとんどのゲームは現実世界そのものを再現しているわけではない。現実世界の複雑な要素のごく一部を切り出して、プレイヤーを楽しませるようにシミュレーションしているにすぎないのだ。シミュレーションゲームは、プレイヤーの行動や実際の社会観に変なバイアスをかける恐れもある。
先の人間の道徳的振る舞いのシミュレーションモデルは、多くの論者に刺激を与えた一方で「モデル通りに、実態が成立してるのだろうか?」という批判も呼んだ[7]。現実はシミュレーションの「前提」よりも、多様である。
あたりまえだが、組織的意思決定の複合的プロセスを理解するのは、簡単なことではない。巨大組織である「政府」の複合的な意思決定プロセスを扱ったグレアム・アリソンの古典『決定の本質』[8]では、政治的意思決定が(1)合理的な行為者としてのあり方 (2)組織内のルーティンなどに縛られたあり方 (3)政府内の関係者の対立・協力関係など複数の意思決定の文脈が相互に引き合いながら、大きな意思決定をなしているという。巨大な組織のトップの意思決定は常に複数の文脈に晒されていると言っていい。
その結果として、組織の外側から見ると、とうてい支持できない不可解な意思決定がなされることも少なくない。たとえば、センセーショナルな事件ばかり報道するマスコミの組織構造、各国の警察の横暴な行動、ナチスの虐殺に加担した官僚の意思決定の構造[9]…こうした例はいくらでも挙げることはできる。そして、これらの意思決定に関わったトップの人々も、それ周辺の個々人も、全員が異常な人々だというわけではない。人間の意思決定は置かれた状況次第でいかようにも歪んだり、複雑になる。複数の合理性が相互にぶつかりあいながら、一見すると理解の難しい複合的な状況はそうして生まれる。
古典的なゲーム理論のシミュレーションでは[10]、しばしば人間を比較的シンプルな合理的な行為者として扱いがちである。しかし、人間は、合理的な行為者であると同時に、道徳感情や、人間関係など多様なものの間で揺れ動くものでもある。ゲームはこのような複雑さを扱うことはできないのだろうか?
1.2.3 妥協せざるを得ない状況のジレンマを表現する
たとえば、『伝説のオウガバトル』(クエスト、1993、SFC)は、そうした作品の一つだ。『伝説のオウガバトル』も、複雑な行動のシミュレーションとしての側面をもっている[11]。
このゲームの際だった特徴は、「民衆の評判」を常に気にしながら軍を運営しなければならないことだ。民衆の評判が低ければ、毎月の軍資金を民衆から寄附してもらえず武器も供給も兵士の給料もままならなくなる。民衆から見放されて軍資金を調達できなくなった軍隊は、当然とても弱い軍隊となってしまう。
では、民衆から支持されるためには、どうすればよいのかというと(1)弱い者を殺す戦い (2)僧侶など聖職者を殺す戦い (3)都市を戦場にした戦い、 などを民衆の眼前で繰り広げないことだ。たとえば、強そうなバーサーカーが弱い僧侶を何人も虐殺するような戦いを都市の真ん中で見せてはいけない。「人は見た目が9割」ではないが、軍隊の見え方が「民衆から見た正義」を決定する。
一方、軍隊を率いる事情からは、民衆ウケのよい戦闘ばかりでは軍に十分な戦闘経験を積ませることができず、次第に敵に勝てなくなる。民衆からの支持を得るような戦いだけを行おうとしすぎてもいけない。 それゆえ、プレイヤーは「戦闘に勝利する」という欲望と、「『民衆の支持を得る正義』の戦いをしよう」という引き裂かれた二つの欲望を同時に達成するように誘い込まれる。
しかし、当然この2つのジレンマはそのままでは解決できない。
そこで、このゲームには抜け道がある。民衆はあくまで限定合理的[12]な存在でしかないため、民衆の「視力」の限界よりも向こう側――つまり町から遠く離れた場所――ならば、いくらでも汚い戦争ができるのだ。この状況に気づいた多くのプレイヤーは「正義の味方」のような顔をしながら、見えないところで敵を抹殺して回ることを選び取らされてしまう[13]。キラキラとした聖騎士と僧侶が街を解放しに訪れ、その一方で魔法使いやバーサーカーで構成された殺戮部隊が市街地から遠く離れた場所で敵を殲滅する。オモテでいい顔をしながら、裏でとても見せられないような戦いを展開する。この汚い抜け道こそが、このゲームを攻略するうえで、もっとも効率的でバランスのとれた強者の振る舞いなのだ。
ただ、当然、この決断を選びとらされたプレイヤーは「戦闘に勝利」することはできるが、「『民衆の支持を得る正義』の戦い」ができているかと言われると、表向きはさておき、実態としては民衆の期待と逆の行為に手を染めているということを意識させられてしまう。
プレイヤーは、ゲーム世界内で非道な選択をしても、実際の人生で何か責任を取らされることはない。にもかかわらず、そこで感じる後ろめたさや達成感はどこから来るのだろうか?
第一に、「民衆の支持率」というものを常に確認させられるため、民衆が期待していることは何かということを常に意識せざるを得ない。第二に、たとえ割り切ったプレイをしようとしても、ゲーム内のキャラクターたちが、軍隊行動が「ただの殺し屋ではないのか?」ということを問いかけるような問答を繰り広げることだ。


第一の側面は、ゲームの構造によって要請される仕掛けであり、第二の側面はゲーム内のテキストによって要請される仕掛けである。 そうして「戦闘に勝利しよう」「『民衆の支持を得る正義』の戦いをしよう」という2つの視点に加えて、「何が正義なのか」という3つめの視点が物語を通して与えられている。
そうして、プレイヤーは自らの創意工夫の結実として「汚くてキレイな戦争」を遂行する純粋な善人とはとても言えないような主体となっていることを意識させられることになる。
このジレンマは、現実の政治そのものの戯画化でもある。表と裏があって、表では善意や正義を謳いながら、裏では冷酷な計算がなされる。そして、その構造を常に誰かから批判的に問われ続ける。このゲームは、そのような状況を記述するのではなく、プレイヤー自身がそのジレンマの中で選び取らされるよう仕向けられている[14]。
1.2.4 社会的なジレンマを体験させる作品たち
戦争などのシビアな状況下における妥協点を探すことを求められるゲームは他にもある。
たとえば、2010年前後のアフガニスタンらしき地域[15]を舞台としている『Rebel Inc: Escalation』(2016)はその一つだ。このゲームでは、戦後統治を行いながら現地の武装ゲリラへの対応と、地域のインフラ整備をすすめることを求められる。武装ゲリラなどを抑え込むために、ゲリラのアジトを空爆すると、国際世論から反発されて統治のための資金を得にくくなってしまう。現地人の軍隊を育成して治安維持に当たらせると現地からも国際世論からも反発が起きにくいが、現地人の軍隊を育成するのには時間がかかるため、どうしても統治開始初期には海外からの軍事力介入をせざるを得ないジレンマ状況に置かれる[16]。
また、プレイヤーが警察官となって被疑者の書類を整備する仕事をする『リーガル・ダンジョン』(2019)もそうした作品である。「被疑者の書類整備」というと、いかにも地味に聞こえるかもしれないが、この作品における警察は実質、検察官の役割を果たしている。被疑者を軽犯罪として裁くのも、重犯罪として裁くのも、プレイヤーの裁量で決めることができる。このゲームでは「適切な法の運用」をすることが評価されるだけでなく、いかなる形であれ「重犯罪者を多く挙げても評価がされる」ようになっている。つまり、偉くなりたいなら、正義心に蓋をして軽犯罪者を重犯罪者にしていくことができてしまう。この作品は、日本や韓国、欧米の司法制度が抱える構造的ジレンマの一部を表現している。
他にも『This War of Mine』(2014)や『HEAD LINER』(2017)など、こうした作品は近年になって増えつつある。
いずれも、ゲームプレイヤーは、複数の異なる合理性の間でトレードオフを意識し、その中での葛藤が促されるときに、はっきりと、そこに基準の異なる別々の合理性が存在することを見て取ることになる。そのあいだの調停を考えるような手立てにコミットするようにもなるだろう。
反省や葛藤を通じて、理性的な思考や理解が発現するということ自体は何も変わったことではない。数多くの小説や映画がそれを描いてきた。ただ、ゲームを通じた、複数の合理性の説明戦略が特殊なのは、その必ずしも道徳的規範などは参照せずとも、独立したゲーム内で構成される有利・不利といった要素だけで、トレードオフを表現し、さまざまな合理性の現れ方について理解を促すことができるということにある。そして、その上でさらに道徳的規範と最適な振る舞いとのジレンマを考えさせることにある。
1.2.5 感覚と理性を担うメディア
こうした理解は、感覚的な理解というよりは理性的な理解の一種である。こういう「頭で考える」方法に対して、「考えるな、感じろ!」という発想がダンスや絵など芸術についての言説では、昔からカウンターとして存在していた。前回説明したのはゲームというメディアが人間の理性的な判断の前提となる「感覚」自体を形成する装置として大きな役割を果たしうるという可能性についての議論だった。そして、今回、議論してきたことは、ゲームは複雑な合理性の間の調停や、その葛藤について考えようというような、すぐれて「理性的」な思考を理解するための装置として大きな役割を果たしうるという点だ。
このように整理すると、どちらの話をしたいのか、話が混乱しているように思う人もいるかもしれない。一体、ゲームは、感覚的な理解を媒介するメディアなのか?それとも理性的な理解を媒介するメディアなのか?ある意味で反対のことを、同じゲームというメディアについて論じている。
ゲームはどちらかの理解だけを媒介するメディアだと考えると混乱してしまうかもしれないが、おそらく、ゲームはそのどちらの側にも立っている[17]。別にゲームが万能の道具だと言うわけではない。テレビ通販のように「これ一本でどんな悩みも解決!」ということはない。むしろ扱いづらいし、気を抜くと危なっかしい点も多い。
*
感覚について研ぎ澄ましていくためのツールとして最適なものが、理性的な思考を促すためのツールとしても最適だという、この都合のよい性質は何なのだろうか?
ゲームというものが何かその時々によって、まったく別の仕方であらわれているということなのか?それとも、そもそもにおいて、ゲームという概念が単一のものではなく、もっとキマイラ的なものなのか?
その実体がそもそもあるのかないのか?筆者はその実体が完全に空虚なものではないということを前提にして、このテキストを書き進めているが、だとしても、その実体の捉えにくさは、それ自体をさぐることが一つのゲームになるような複雑さを兼ね備えている。その捉えにくさの仕掛けを考えることが、本書の大きな目的となる。「ゲームとはXXである」という短い結論は出てこない。しかし、ゲームという現象のありようについて、可能なかぎり確かだと言えそうなことを明らかにしていきたいと思う。
[1]スティーンブン・ジョンソン/乙部一郎監修、山形浩生訳 2006『ダメなものは、タメになる』翔泳社, p. 40
[2]もっとも、社会シミュレーション的な側面を持つビデオゲームやボードゲームのすべてが複雑な問題を精密に理解させることができるというわけではない。ゲームによっては、問題の簡単な理解を楽しく啓蒙するための入門として作られている作品もあるし、本格的な理解を促すシミュレーションに近い作品もある。
[3]ボードゲーム『パンデミック』など。またソーシャル・ゲームや、オンラインゲームなどでは特にこうした構造はよくみることができる。MMORPGなどではほとんどのゲームで「熟練したプレイヤーによる、初心者プレイヤーのサポート」といった協力行動が見られ、MMORPGのプレイヤーたちが、こういった構造的な背景もあり濃いコミュニティを形成するさまは洋の東西と問わず世界中のゲームプレイヤーたちに見られた行動となったすべてのMMORPGで協調的行動が標準的だというわけではない。プレイヤー対プレイヤーの対戦を主として行わせるようなMMORPG作品もある。
[4]Nicky Case(2016)『We Become What we behold』など
[5]本稿で「ゲーム理論」といった場合、一般的な用語法と同様に、フォン・ノイマンらによってはじまった数学や経済学の分野でのゲーム理論のことを指す。それ以外のゲームに関わる理論に関しては「娯楽に関わるゲームに理論」、コンピュータ・ゲームに関する理論については「コンピュータ・ゲームの理論」「ビデオゲームの理論」などといった形でその都度区別する。原則、助詞が何もない「ゲーム理論」と表記した場合は、フォン・ノイマンらによるものを指す。
[6]たとえば、パソコンの父と言われるアラン・ケイは教育用ツールとしてのシムシティを最低だと批判している。 ref: Don Hopkins (2007), “Discussion with Alan Kay about Visual Programming” Don Hopkins’ Web Site u̇rlhttps://web.archive.org/web/20180715223435/http://www.donhopkins.com:80/drupal/node/140 (2023年11月14日閲覧)
[7]アクセルロッドに対する批判としては、例えば、ビンモアによる批判(Ken Binmore/山形浩生訳, 1998「アクセルロッド『対立と協調の科学』書評:「しっぺ返し」はそんなにすごいものではありません」https://cruel.org/candybox/axelrodhype.html <2025年3月12日閲覧>)、ロールズに対する批判としては、マイケル・サンデルの批判などがある(M.J. サンデル/菊池 理夫訳,1999『自由主義と正義の限界 第2版』三嶺書房)。
[8]Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston: Little, Brown and Company, 1st ed., 1971,2nd ed.,1999.(宮里政玄訳『決定の本質–キューバミサイル危機の分析』第1版,中央公論社,1977年
[9]アレントがアイヒマンを論じた「凡庸な悪」の議論を思い起こす読者が多いと思うが、アイヒマンの主体性が実はアレントの観察よりも、実際にはかなりあったはずだという批判がある(もちろん、独特のリアリティが形成される環境があったとは言え)。本論の主題からやや逸れる論点だが、詳細については田野・小野寺ほか2023『〈悪の凡庸さ〉を問い直す』大月書店などを参照されたい
[10]進化ゲーム理論や、進化ゲーム理論を応用した制度派経済学などでは、さまざまなルーティーンや、慣習(convention)の問題を扱っており、ゲーム理論系列の議論が素朴な合理性のみを想定しているというわけではない。
[11]実際、『伝説のオウガバトル』を開発した松野氏は、経済学の世界に触れていた時間が数年間ほどあったという。この作品の開発前に、おそらくロールズやセンの議論か、あるいはそのエッセンスのようなものに触れていると思われる。松野泰己(聞き手:井上明人、中川大地)(2010)「【インタビュー】松野泰己/市場が鍛える「作家性」のゆくえ」『Planets vol.7』第二次惑星委員会
[12]本稿で特に注釈なしに「合理的」という言葉を使うとき、基本的にはこの「限定された合理性」という意味合いで用いている。「合理的=論理的に正しい」という意味ではない。
[13]細かい話をすると、すべての兵士にこの行動をとらせるとうまく立ち行かなるなるように設計されているため、ごく一部の最強暗殺部隊をつくって運用するのが非常にラクになるようになっている
[14] 文化的背景が異なると、同じジレンマゲームでも「当然だ」と感じる利害や優先順位が異なってくるかもしれない。たとえば、海外のプレイヤーと日本のプレイヤーで“原発政策”への反応が異なるといったことはあるだろう。
[15] Ndemic creations(2020)”Rebel Inc. now available in Afghanistan, https://www.ndemiccreations.com/en/news/176-rebel-inc-now-available-in-afghanistan <2025年3月12日閲覧>
[16] ややくどいようだが、この作品によって提示された描写自体が現実の写し絵としてどこまで適切かどうかは、判断が難しい。特にこの作品は、ゲーム開始前半~中盤まで「空爆」がかなり効果的であるなど、議論を呼びそうな設定がかなり多く埋め込まれている。
[17]ゲームは、理性的討論に対する重要なカウンターとしての側面は、ある種のカウンターカルチャーとも相性がよかった。二〇一四年には、ゲーマーたちがゲームコミュニティにとって何が重要なのかを議論するための運動が、一部で加熱した結果、アンチ・フェミニスト、アンチ・アカデミズム運動のような状況を産んだ(Gamergate事件)。ゲームというメディアの性質上、ゲームに関わる運動が「腹落ち」を重視するような、アンチ・アカデミズム的指向性と、、熟慮を促すような反省的思弁の双方を並列させてしまう特性があるのかもしれない。この特性があるかぎりにおいて、ゲーマーゲート事件的なものが周期的に繰り返される可能性はあるだろう。
この記事は、2025年4月3日に公開しました。本連載では、書籍に掲載される内容とは別に、連載としてはゲ
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。