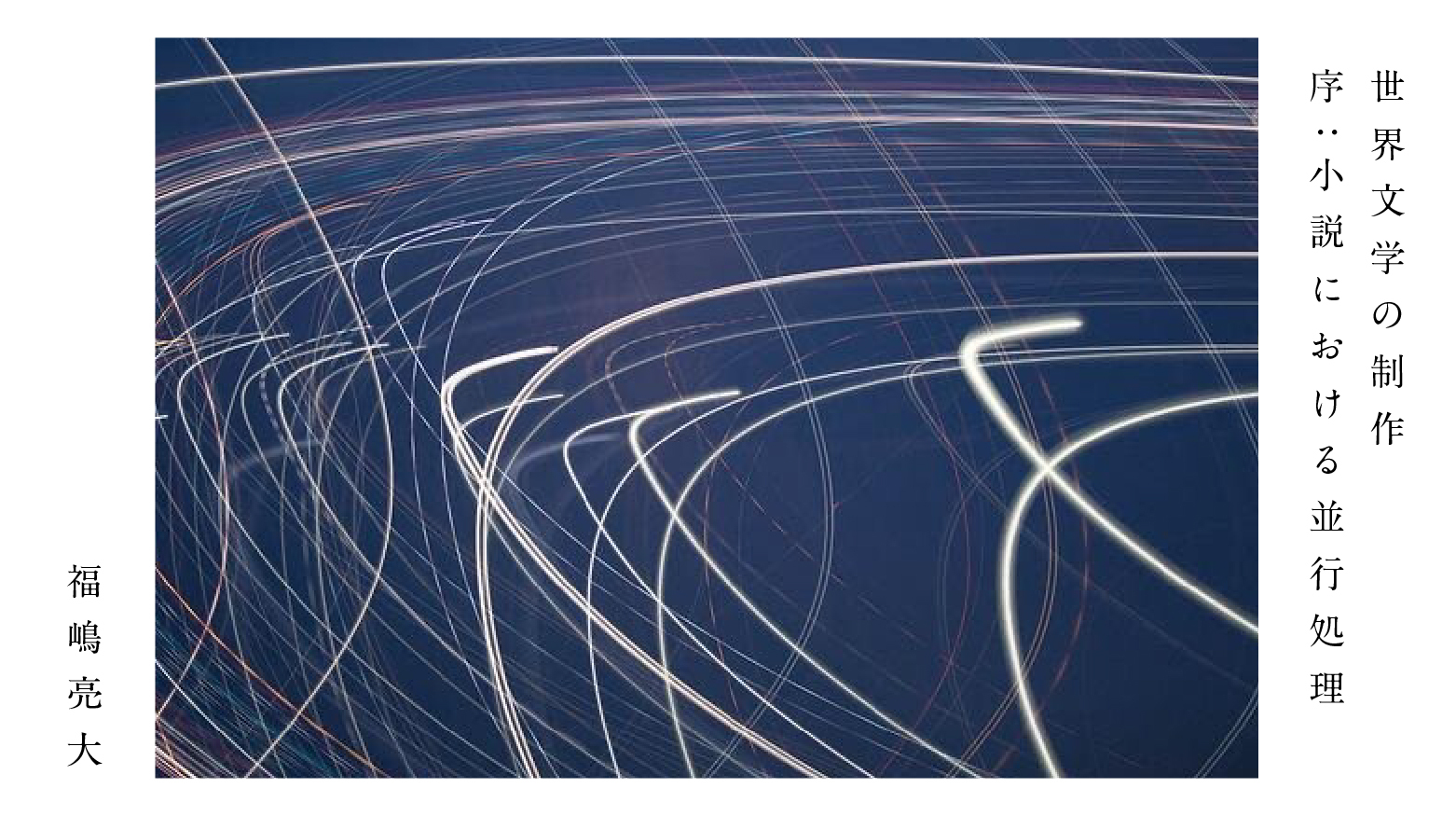文芸評論家の福嶋亮大さんによる、小説と文学の現代的な可能性を改めて考え直していく本格評論。その序論として「心」と「言葉」が交錯する場としての小説の表現特性を原理的に検討します。
「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。
端的に言うとね。
1 心と言葉
われわれは小説について何かを言ったり考えたりするとき、ふつう二つの領域に拠りどころを求 める。一つは心であり、もう一つは言葉である。作者にとって、小説は心で書くものであり、かつ言葉で書くものである。そして、読者は小説の登場人物から心らしきものを読みとり、かつ小説を言葉の集合として読むのである。
小説が公表され、そこから理論や批評や感想が生じるとき、それらのコミュニケーションが心的領域か言語的領域と関連しないことはほとんどない。しかも、この二つの領域は平行しており、小説についての語りがいずれか一方に完全に還元されることは、ありそうにない。ここから言えるのは、小説という装置が一種の並列処理(パラレリズム)を内包しているということである。心的なものと言語的なものはパラレルな二つの領域である。この異質な二つの焦点をもち、しかもそのいずれも優位に立つことのない楕円形の地平を形作ったところに、小説の特性がある。
もっとも、この両者のうち、二〇世紀の文芸理論の関心が言語のほうにより強く向けられたことも確かである。文学を言語に向かって純粋化するのは、モダニズムの洗礼を受けた作家や評論家の夢であった。例えば、吉本隆明の一九六〇年代の主著『言語にとって美とはなにか』の序文にはこう記されていた。
「わたしは、文学は言語でつくった芸術だという、それだけではたれも不服をとなえることができない地点から出発し、現在まで流布されてきた文学の理論を、体験や欲求の意味しかもたないものとして疑問符のなかにたたきこむことにした。〔…〕もんだいは文学が言語の芸術だという前提から、現在提出されているもんだいを再提出し、論じられている課題を具体的に語り、さてどんなおつりがあがるかという点にある。」*1
ここには文学を原理・原則から考えようとする態度があるが、にもかかわらず文学を「言語でつくった芸術」という一点に収束させていくと、もう一つの焦点を逸してしまうように私には思える。そもそも、吉本自身、心的なものに狙いをつけた言語使用のあり方に注目していた。吉本は「指示表出」と「自己表出」を区別しつつ、このうち後者の自己表出という概念によって、言語(日本語)がいかに自己意識を先鋭にしたかを、歴史的に説明しようとした。
ただ、言語的なものと心的なものの関係は、そうたやすく解きほぐせるものではない。両者が密接に関わっているのは明らかだが、にもかかわらず、言語にとって心は(あるいは心にとって言語は)異質なもの、つまり消化=同化しきれない何ものかである。特に小説について論じるとき、言語に集中すると、それだけでは処理できない残余として心が浮かび上がってくるし、逆もまた然りである。小説に一方向から光を当てようとすると、必ずその影が現れて、分析者の整合性を脅かすことになる。それゆえ、われわれには小説の内包するパラレリズムを──心と言語の二重らせん構造を──できる限り尊重するような態度が必要なのである。
2 絵画と小説
小説という現象にアプローチするには、いくつかの問いの立て方が考えられる。例えば、小説はどのように生まれ、どこに向かっているのか。これは発生論的な問いである。あるいは、小説の力、人間を触発するその力の源泉はどこにあるのか。これは美学的な問いである。
私はこれらの問いにもいずれ取り組もうと思う。ただ、先回りして言えば、これらの基礎的な問いに対して研究者や批評家のあいだでコンセンサスはとれていないし、誰もが納得する答えを導き出すのは今後も無理だろう。小説の始まりや仕組みを究明しようとするとき、われわれは必ず理論化しきれないあいまいなものにぶつかる。言い換えれば、小説には根源的・理論的な態度を座礁させるものが含まれており、あえて言えばそれこそが小説の根源なのである。
しかし、そうは言っても、私はあいまいさに居直るつもりはない。私は以下、未熟な試行に留まることは承知の上で、小説の特性を測る物差しをいくつか示してみたい。
ここで美術の理論、特にモダニズムの理論を比較対象として導入しよう。カントの批判哲学を継承した批評家のクレメント・グリーンバーグは、絵画のモダニズムの根拠を、支持体の「平面性」に求めた。
「絵画芸術がモダニズムの下で自らを批判し限定づけていく過程で、最も基本的なものとして残ったのは、支持体に不可避の平面性を強調することであった。平面性だけが、その芸術にとって独自のものであり独占的なものだったのである。〔…〕平面性、二次元性は、絵画が他の芸術と分かち合っていない唯一の条件だったので、それゆえモダニズムの絵画は、他には何もしなかったと言えるほど平面性へと向かったのである」*2
グリーンバーグによれば、演劇とも彫刻とも区別される、絵画にのみ独占されている固有の条件とはその平面性(二次元性)であり、モダニストの画家たちはこの条件を積極的に引き受けることで、絵画をそれ自体として──他の何ものにも依存しないジャンルとして──自律させようとした。モダニズムとは絵画自身による自己発見=自己証明の試みであり、一種の独立宣言である。モダニズムのプログラムが完遂されれば、絵画は外部の教師に教わらなくても、ただ内的な規則と手順に基づいて、ジャンルに固有の価値を築けるようになるだろう。そして、この独立したジャンルは、道徳や政治のような外部の基準に従属することなく、その専門領域の諸問題を(ちょうど科学と同じように)自己批判=自己修正しながら探究できるようになるだろう……。
グリーンバーグによるモダニズムの定義は、その後さまざまな批判も受けている。ただ、ここで問題にしたいのは、このような明快な議論がそもそも小説ではできないということである。絵画のモダニズムは内容(何が描かれるか)ではなく、絵画を産出する平面性の形式を際立たせたが、小説で同じことをやるのは無理である。二〇世紀のロシア・フォルマリズムや構造主義の努力にもかかわらず、小説において何が「形式」なのかを厳密に見定めることは容易ではない。小説の形式の問題はナラティヴ(語り方)の問題にある程度置き換えられてきたが、それによってすべての小説について形式と内容が峻別できるわけでもない。グリーンバーグ自身、そのことを問題にしている。
「一九世紀中葉以降、ある芸術は、多少なりとも、他の芸術よりも根本的にメディウムの革新を強く求めてきた。いま、散文小説のメディウムが質を維持するのに刷新兼革新を比較的必要としなかったということに注目すべきである。〔…〕文学において何がメディウムで、何がそうでないのかを区別することは、いずれにせよ甚だ学的で、アレクサンドリアニズム的であり、実際の文学経験からかけ離れすぎていて、労を取るわけにはいかない。」*3
グリーンバーグによれば、モダニズム絵画は支持体や素材というメディウム(媒体)に固有の性質、つまりメディウム・スペシフィックな属性を戦略上の基盤としたが、それが可能であったのは「絵画のメディウムが他と比べて容易に孤立できた」からである。逆に、文学においては形式と内容、メディウムとそうでないものとの区別は厳密には立てられそうにない。グリーンバーグが述べた通り、文学を論じるのに「メディウムそれ自体という概念」そのものが「狭すぎる」。だとすれば、小説の特性を考えるには、恐らくメディウムとは別のモデルが必要なのである。
3 メディウムとフィールド
小説の言葉は、日常的な言語使用の場から得られる。比喩的に言えば、小説の胃袋は強くない。小説家がどれだけ努力しても、日常言語を制作プロセスのなかで完全に消化=同化し、芸術言語へと変換することはできない。
例えば、西洋音楽は十二平均律という数理的にコード化されたイディオムをもち、それが無数の楽曲を生み出してきた。しかし、小説はそのような精錬されたイディオムをもたない。小説にできるのはせいぜい、日常言語に磨きをかけたり、その配置を変えたりする程度のことである。このような仕事の質が、小説史における「俗語化」および「翻訳」の重要性を際立たせる。俗語化においては、話し言葉の領分が小説に吸収され、その結果としてイディオムに変異が生じる。翻訳においては、複数の言語体系が衝突し、その結果としてイディオムに変異が生じる。ちょうどウイルスが国境を超えて感染するうちにヴァリアント(変異株)を生み出すように、小説のイディオムも俗語化や翻訳を通じて変異するのである。
ここから言えるのは、小説の言葉が、自分以外の何ものかになろうとする自己超越の運動を潜在させていることである。俗語化がいわば下向きの超越だとしたら、翻訳はいわば横向きの超越である。しかも、この捨て身の変異=超越にはデザイナーがおらず、ランダムな揺らぎを含んでいるため、小説の言葉はときに滑稽で、洗練されていないものになる(いわゆる「翻訳文体」とは、まさに洗練を欠いたぎこちない文章を指す)。しかし、このような強張りは自己超越の副反応であり、それを解消することはできない。
小説家は、自分以外の何ものかになろうとする衝動を含む言葉を「作品」として個体化する。絵画がいわば「窓」のように、イメージを切り抜いて(カットアウト)提示するのに対して(ここからグリーンバーグの言うメディウムの孤立性が生まれる)、小説は日常言語のなかに割り込んで(カットイン)そこを占拠する。日常言語を広大な菜園にたとえるとしたら、小説はそこに立てられた「畝」のようなものである。
菜園と畝のあいだには厳密な境界はない。小説は日常言語の菜園の一角をかすめとって制作される。そして、その畝で育った作物=言葉が、今度は菜園の一部である読者の言語使用のコンテクストに働きかけるのである。小説の言葉は、日常言語とのあいだで流入と流出を繰り返しており、しかもこの言語ゲームの全体を統御するデザイナーはいない。強いて言えば、この流入と流出の運動は《生活》の歴史のなかで起こるのである。
このような言語的運動体については、メディウムのモデルではなく《場》(フィールド)のモデルから考えるのが、より適しているのではないだろうか。なぜなら、菜園のなかに畝を立てることは、他から孤立したメディウムを設置することではなく、環境の形状やその土壌の成分の分布を変えることに近いからである。絵画のメディウムは《生活》を遮断して恒常性を保とうとするが、小説の場はむしろ《生活》の変化にさらされ、デザイナーなしに変異していく。小説家が言葉の庭師だとしたら、小説の文体は錯綜したフィールドを操作するための作庭の技術であり、言語的運動体の制御と深く関わるものである。文体の問題は、たんに審美的な観点から判断することはできない。ただ、この点について今は簡単に触れるに留める。
[つづく]
*1 吉本隆明『言語にとって美とはなにか』(2001年、KADOKAWA)
*2 C・グリーンバーグ/藤枝晃雄編訳『グリーンバーグ批評選集』「モダニズムの絵画」(2005年、勁草書房)
*3 C・グリーンバーグ/藤枝晃雄編訳『グリーンバーグ批評選集』「モダニズムの絵画」(2005年、勁草書房)「ミディアム」という訳語は「メディウム」に変更した。
この記事は、2021年9月刊行の『モノノメ 創刊号』所収の同名記事の特別公開版です。あらためて2022年8月11日に公開しました。
本稿のつづきや特集「〈都市〉の再設定」が掲載された『モノノメ 創刊号』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。