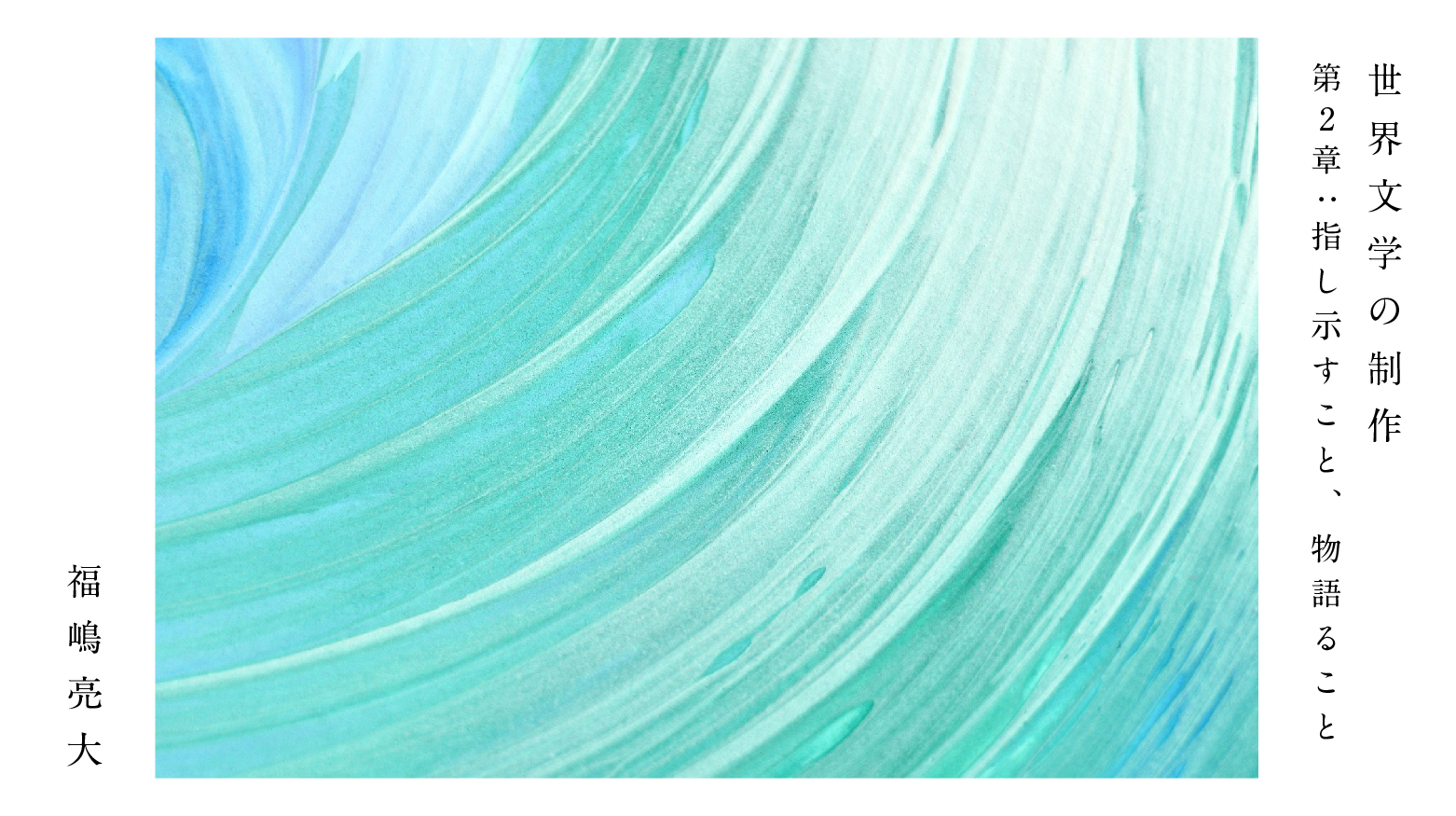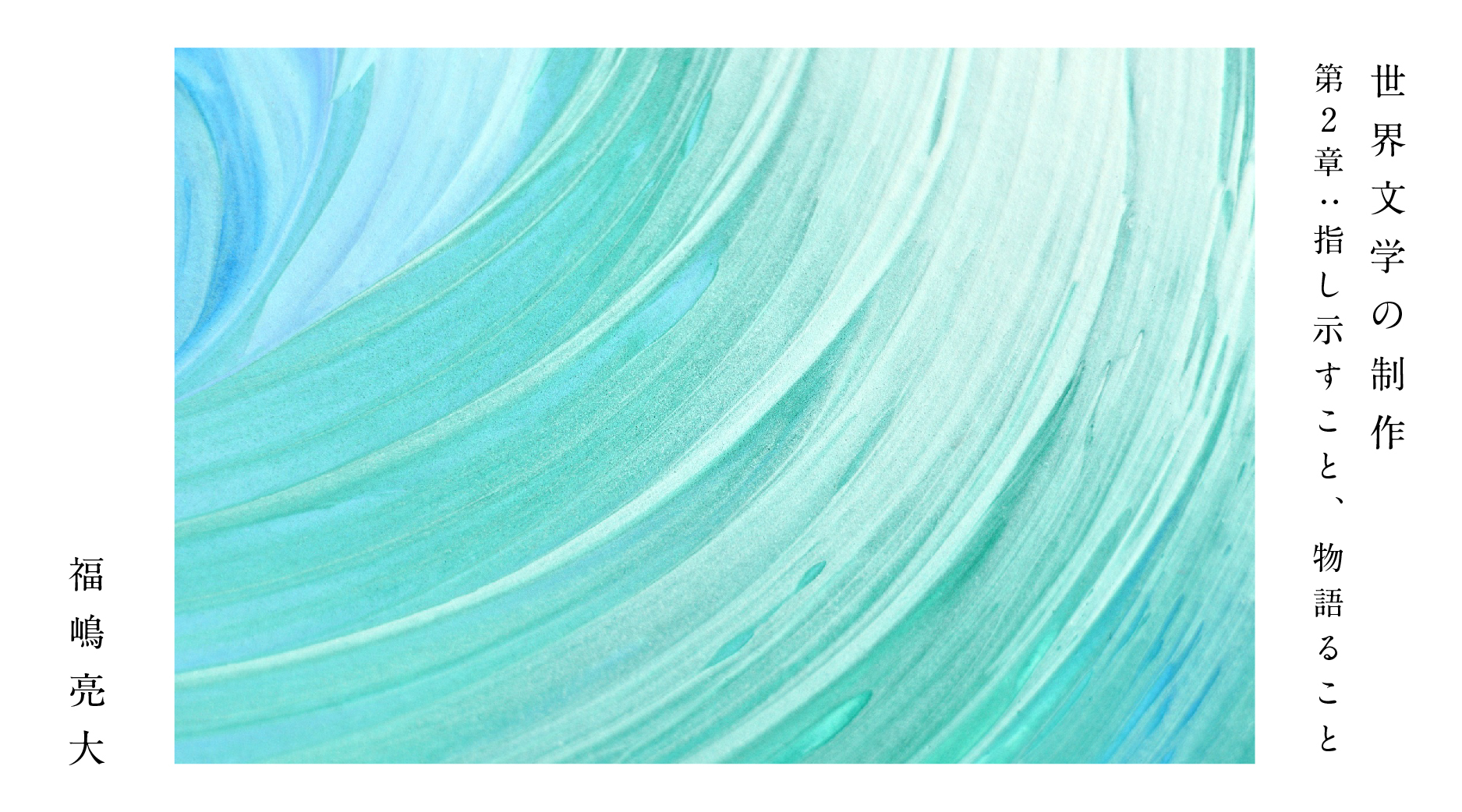文芸評論家の福嶋亮大さんによる、小説と文学の現代的な可能性を改めて考え直していく本格評論。その第二章として、「指し示すこと」と「物語ること」という視点から、小説の機能を捉え直します。
「遅いインターネット」は、PLANETS CLUBの皆さんのご支援で運営しています。記事を読んでおもしろいと思ったら、ぜひPLANETS CLUBにも入会してみてください。
端的に言うとね。
1 心の同調
小説を主題とするとき、言語よりも心に注目するのは、いささか素朴に思える。虚構の登場人物に心的に共感できるとかできないとか、そのようなことばかりこだわる読み手は、いかにも素人くさい。しかし、登場人物の心をわがことのように感じる感情移入が、小説の根幹にあるのも否定できない。それが示唆するのは、小説が読者との心の同調を必要とするということである。
そもそも、心の同調は、コミュニケーション一般の成立する要件でもある。話者が指示する対象に、受け手がまったく同調の姿勢を示さなければ、会話は成立しない。コミュニケーションを続行するには、相手の意図を読み取ろうとする相互の協力が不可欠である。認知心理学者のマイケル・トマセロの仮説によれば、この協力に基づくコミュニケーションの起源にあるのは、幼児の身ぶりや指さしである。
トマセロは幼児の指さしについて「認知的に豊かで利他的な動機を持つ」と見なしている。指さしには大別して、外界の対象を共有しようとする「陳述的機能」と、何かを要求する「命令的機能」がある。幼児は言葉を話すようになる前から、手ぶりや身ぶりで外界を指示し、大人に対して共有や要求の意志を伝えながら、共通理解の基盤を築いてゆく。類人猿と比較しても、これはきわめて特徴的なコミュニケーションのスタイルである(※1)。
私も自分の息子が、誰に教わるまでもなく、指さしをしきりにやり始めたことには驚かされた。そして、そのジェスチュアには明らかに、自分のものの見方を大人に教え、共有しようとする意図がある。しかも、彼は現前する知覚可能なモノだけではなく、不在の祖母や音だけ聞こえる飛行機をも指示しようとする。ここに想像力(不在のものを現前させる能力)の萌芽を認めても、さほど的外れではないだろう。子どもは一歳の段階で、大人から教育されるだけではなく、指さしや身ぶりを通じて大人を教育しようとするのであり、その途上で現前しないもの──広く言えば「虚構」──を指定する術を身に着けてゆく。トマセロはそこに、人間のコミュニケーションの起源を認めたのである。
2 協力的なコミュニケーション
幼児の指さしは、大人の心的な同調を期待している。幼児は大人たちが指さしに何とか反応しようとすることを知っており、だからこそしきりに対象を指示し、大人とそれを分かち合おうとする。トマセロによれば、人間の共同生活の地盤にあるのは、他者の意図を推測し、かつ他者に利益を与えようとする利他的な心のあり方であり、言語的なコミュニケーションもそこから派生したものである。人類は協力的なコミュニケーションを土台に進化してきたからこそ、今のような言語を生み出せたのであり、その逆ではない。
では、他者にメッセージや注意を伝え、情報を共有しようとする協力的=利他的なコミュニケーションの代わりに、競争的なコミュニケーションが人類を支配していたとしたら、どうなっただろうか。トマセロの考えでは、そのとき、言語の形式はわれわれの想像を絶したものになる。
「さらに注意を引くのは、もしも協力でなく競争というコンテクストで進化していたなら、人間の『言語』はどんな風になっていただろうか──それを『言語』と呼びたいなら、の話だが──と想像してみることである。この場合、共同注意も共通基盤もないことになるから、指示するための行為を人間のようなやり方では行えなくなる。とくに視点や、その場に存在しない指示対象に関してはまず無理である。お互いに協力的であるという想定の下での伝達意図は存在しないし、それゆえどうしてある人が自分とコミュニケーションをしようとしているのかを一生懸命に見つけようとする理由もない──またコミュニケーションの規範もない。慣習とは人々が協力に基づく理解と関心を共有している場合にしか生じないものだから、慣習もないことになる」※2
この「仮想上の競争的な『言語』」は、今の言語とは似ても似つかないものになるだろう。トマセロによれば、それはフィクションも生み出せないし、協働の道具にもならない。そこからは慣習も発生せず、他者の意図を読み取ろうとする動機も生じない。このような競争的な言語でもコミュニケーションは可能かもしれないが、それは協力的な言語によるコミュニケーションに比べれば、ひどく貧弱なものとなるに違いない。
トマセロが言うように、われわれの言語は進化的に獲得された「生活形式」(ヴィトゲンシュタイン)に深く依存している。言語は決して無軌道に進化したものではなく、協力的なコミュニケーションという古くからの生活形式によって、あらかじめレールが敷かれている。いわば肺がなければ呼吸できないように、利他的な振る舞いへの傾きがなければ言語も成立しない。意識的な選択以前に獲得されたプログラムが、われわれのコミュニケーションを条件づけているのである。
ブルガリア出身の思想家ツヴェタン・トドロフにも、似たような考え方がある。トドロフによれば、なぜ人間は社会を作るのか(ホッブズ)とか、社会への欲求はどこからやってくるのか(ショーペンハウアー)とかいう問いには、意味がない。なぜなら、人間は好むと好まざるとにかかわらず、社会なしでは生存できないように、進化してきたからである。
「人間が社会をつくって生きるのは、利欲によって、美徳によって、あるいは──それが何であれ──別の何らかの理由の必然によってではない。人間が社会をかたちづくって生きるのは、彼らにはそれ以外に可能な実存形態がないからである。」※3
トドロフが言うように、対他関係は自我に先立つ。これは、協力というコンテクストが言語に先立つというトマセロの見解と符合する。社会的な協働は生存上捨て去ることができない初期値として、人類に与えられた。この個々人の選択以前の規格化はある意味では理不尽であり、それゆえときに強いストレスをもたらす。人間がカントの言う非社交的社交性、すなわち「社会を求めかつ社会から逃れようとする、その矛盾した傾向」(トドロフ)に深く囚われているのも、この理不尽なデファクトスタンダードゆえである。
3 痕跡とドメイン
繰り返せば、小説は外界をしきりに指し示し、読者の心をそれに同調させる。これが、ここまで述べた協力的なコミュニケーションの派生物であるのは明らかである。子どもが指さしで大人にものを教えようとするように、小説もものごとを指示して読者と共有する。見返りを期待せずに、世界の一部をしきりに共有しようとする小説には、読者を無条件で歓待するプログラムがもともと備わっている。
ただ、小説が協力的なコミュニケーションに根ざすことは確かだとしても、その指示と共有はたんに「共同生活」に役立つだけではない。小説における指示には、たんなる利他的な振る舞いに還元できない余剰がある。ここでは二つのポイントを挙げておきたい。
(α)痕跡
第一に、小説において指示されるのは、知覚できるモノではなく、あくまでその痕跡である。ちょうど水上の航跡が船のありさまを想像させるように、行為や言葉の記録は、人物や事物の存在の痕跡として、その主人のありさまを想像させる。小説の読者は、想像力(Einbildungskraft/像を作る技能)を活用して、痕跡の本体を思い描くように誘導される。ためしに、あるSF作品の冒頭を引用してみよう。
「ライジ・ベイリは、デスクのそばまで来てはじめて、R・サミイが用ありげに彼を見まもっているのに気づいた。
面長なライジの、気むずかしい顔がこわばった。『なんの用だ?』」※4
ベイリやサミイが何ものかは、この書き出しの時点では判然としない。サミイはロボットなのだが、それは後になって明かされる情報である。この場面では、ベイリやサミイのごく限られた痕跡──デスクのそばまで来る、見まもる、顔がこわばる──だけが読者に与えられている。「気むずかしい顔」という言葉は、無数にある顔のイメージをどのように絞り込めばよいか、その推論の手がかりを読者に示すが、顔を確定する情報ではない。
読書とは、言葉として残された痕跡をヒントにして、人物や事物のありさまを推論するプロセスである。しかも、どれだけ物語が進展しようと、この推論のプロセスには終わりがない。なぜなら、痕跡が知覚可能なモノとして確定されることは、小説では決して起こらないからである。読者は痕跡を集め、そのもとの姿を想像力によって復元しようとするが、それでもそこには必ず不確定なものが残る。登場人物とはいわば確率論的な揺らぎを含んだ雲であり、読者は推論を重ねて、この雲に一時的な輪郭線を与える。
(β)ドメイン
第二のポイントは、小説による指示の手法はさまざまということである。小説には会話があり、独白があり、場面や心理の記述がある。小説は歴史的には新参者であるにもかかわらず、あっという間に文学の場をハイジャックし、ウイルスのように世界じゅうに広まっていった。この文化的なパンデミックの一因は、何よりもまず、小説における指示の性能が近代世界の複雑さに対応していたことにあるだろう。
明治の坪内逍遥は、日本人にはまだ見慣れなかった小説について、単純明快な診断を下している。「小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ」(『小説神髄』)。逍遥が言うように、小説の核心は、主観的な心(人情)と社会的な事物(世態風俗)を横断できることにある。小説はもっぱら一人称(作中人物の視点)と三人称(世界を俯瞰する視点)の語りを用いて、心と事物、内的世界と環境世界を同等に扱う技術を蓄えてきた。この視差を含んだ語りによって、子どもの単純な指さしではうまく指定できないものにも、小説は一種のドメイン(領域/領土)を与えることができる。
その際、外界を認識=消化することは、語りの中心的な仕事ではない。例えば、フォークナーの『八月の光』では凄惨な黒人差別のありさまが語られるが、フォークナー自身、この差別の正体が何かを十分に「認識」しているとは思えない。それは、作中で黒人への憎悪を憑かれたように語る老レイシスト──主人公ジョー・クリスマスの祖父──にしても同じである。彼は自分自身でその強烈なバイアスの由来を了解しているわけではないが、その長大な語りは黒人への憎悪に満ちたドメインを形成することになる。
大江健三郎は柄谷行人との対談のなかで、理解できないものでも物語る技術があれば書けてしまう、という趣旨のことを述べているが(※5)、それは疑いなく小説の核心である。フォークナーの小説にせよ大江の小説にせよ、何らかの特殊な感情を備えた語り手が、心や事物を横断的に指し示す。彼らの小説の本体は、それらの指示を貯蔵するドメインである。そして、そのドメインの内部を「理解」することは、あくまで読者に任されている。
4 フレーゲ再訪
私は前章で、意識(心)と小説はともに、自分以外の何ものかへの志向性をもつと述べた。サルトルのフッサール論におけるたとえ話を用いれば、意識はたえず渦巻いて「炸裂」した状態にある。サルトルがやろうとしたのは、外界の同化=吸収という認識論的なモデルを破棄することである。意識は対象を同化=吸収するのではなく、ひっきりなしに外界を志向する。これをもう一歩進めれば、意識は環境とともにあるというメルロ・ポンティ流のエコロジカルな哲学に到るだろう。
同じように、小説にも自己超越の衝動がある。小説は言語でできているが、常に言語以外の何かを指し示そうとする。小説の読者は、言葉を読みながら、たえず言葉の外に追い立てられる。それでいて、先ほど引用したSFの例からも分かるように、読者が言葉の外で出会うのは、知覚可能なモノではなく、ただ作中の人物や事物の痕跡だけである。小説はその語りの力によって、この不確定なものたちを収集したドメインを公開するのである。
このように考えていくと、小説のやっている仕事を厳密に把握するのは、決してたやすくないことが分かってくる。小説を何気なく読めてしまうことそのものが、実は異常であり、その異常さをつかまえるには理論の助けが要る。そもそも、指示や意味というテーマは、一九世紀末以来、哲学でも本格的な研究対象となってきた。その理論上のモデルは、われわれの考察にとっても有益である。
例えば、一八九二年の古典的な論文で、哲学者のゴットロープ・フレーゲは記号の「意味」(Bedeutung/指示対象)と「意義」(Sinn/提示様式)を区別した。平たく言えば、このモデルの骨子は、指示対象が一つであっても、そこに到るための記号のルートは複数あり得るということである。フレーゲの出す例で言えば、「宵の明星」と「明けの明星」は、金星という同じ一つの意味(指示対象)をもつが、その意義(提示の仕方)は異なっている。あるいは私の息子は今、自動車を指すのに「ぶー」と「くるま」を適宜用いているが、これもやはり意義が二つあるケースである。
一つの意味(金星や自動車)に付与される意義は、一つとは限らず、複数あり得る。ただ、意義は個人が任意に増やせるものではない。現に「宵の明星」や「くるま」のような意義(提示の仕方)は、共同体の文化的伝承のなかである程度規定されている。意義は「多数の人の共有物」であり得るもの、つまり「世代から世代へと承け継いできた思想の共通の蓄積」(フレーゲ)に基づくものであり、共同体の意味論的プラットフォームと呼んで差し支えない。
その一方、明らかに意義をもっていても、意味をもつかは疑わしいケースもある。フレーゲによれば「オデュッセウスは深くねむったまま、イタカの砂浜におろし置かれた」(ホメロス)のような文は、まさにそのような疑問を引き起こす。なぜなら、オデュッセウスは架空の人物であり、オデュッセウスとして名指される存在は実在しないからである。フレーゲの考えでは、指示対象が存在しないならば、当然「意味」もない。このホメロスの文は確かに意義をもつ。しかし、それが実在の対象と紐づいていない以上、意味をもつと言えるだろうか。これはあいまいである。
5 意義から意味へ
そもそも、われわれはなぜオデュッセウスという架空の人物を、実在する対象のように扱ってしまうのだろうか。「オデュッセウス」という記号が意味(指示対象)をもつかどうかなど本来どうでもよく、ただホメロスの言葉の芸術的な美しさに身を委ねていれば、それで十分ではないだろうか。フレーゲはまさにそのことを問題にしている。
「しかし、そもそも我々が固有名の一つ一つに意義のみならず意味もあるということをなぜ期待するのであろうか。〔…〕例えば、叙事詩に耳を傾けるとき、我々を動かすものは、言語の心持よい響きを別にすれば、文の意義とそれによって惹き起こされる表象と感情だけである。それに対して、真理を問題にするならば、芸術の楽しみを去って学問的考察へと向かうのである。これゆえに、例のホメロスの韻文を芸術作品として理解している限りは、例えば『オデュッセウス』という名が意味をもつか否かということはどうでもよいことですらある。」※6
ここでフレーゲは「なぜ人間は意義だけでは満足できずに、意味(指示対象)を求めてしまうのか」という問いを出しつつも、明示的な答えを避けている。そして、それは賢明である。それをあえて説明するならば、トマセロやトドロフを引用して述べたように、人間にはもともと協力的なコミュニケーションへの傾きがあるからとしか答えようがないだろう。共同生活を営まざるを得ないわれわれは、意味(指示対象)の共有という所与のプログラムから逃れられない。そのため、われわれは架空の固有名に対してすら、意味や真理、つまり世界との対応を期待してしまう。
私は先ほどから、小説の登場人物は知覚可能なモノとして確定できず、ただ「痕跡」を残すだけだと述べてきた。にもかかわらず、われわれはこの痕跡から、その本体らしきものを復元するように促される。フレーゲふうに言えば、意義から意味へと誘導される。ライジ・ベイリやオデュッセウスが「意味」をもつかは疑わしいが、しかし大方の読者は、これらのキャラクターはただの言葉の集まりではなく、言葉の向こう側にある存在と見なすだろう。そして、この無自覚な「見立て」こそが、小説の成立する条件なのである。
6 感情の染み込んだ表象
ところで、フレーゲはもう一歩進んで「表象」(Vorstellung)というもう一つの区分を用意した。「意義」が共同体の共有財産であるのに対して、フレーゲの言う「表象」はあくまで主観的なものである。表象とは記号と結びついた私的な像である。
例えば「ぶー」という記号に対して、私と私の息子とでは、異なる内的な像(イメージ)をもつだろう。表象は個人の魂のあり方に根ざしており、モノのように存在し、知覚できるわけではない。それゆえ、フレーゲによれば、表象には「しばしば感情が浸透しており、個々の部分の明瞭さは千差万別であり、かつ、うつろいやすい」※7。息子にしても一年後に、今と同じような明瞭さ(?)で「ぶー」という記号のイメージをもつことはないはずである。
こうして、フレーゲは指示対象としての「意味」と、その共同的な提示の仕方である「意義」、そして他人からはうかがい知れない私的で不安定な「表象」を区別した。このような区分は、文学の状況とも共鳴する。なぜなら、二〇世紀文学の大きな課題は、一見して公共性を帯びない私的な表象を、どのように小説に取り入れるかにあったからである。
二〇世紀文学は総じて「語り」に強い負荷をかけたが、それは感情的なバイアスを広く許容することとつながっている。例えば、先述した『八月の光』のレイシストの語り手は、一九世紀的な全知全能の語り手とは似ても似つかないが、彼の偏見の染み込んだ「表象」は、強烈なインパクトを伴って、憎悪に満ちたドメインを形成してゆく。彼の負の感情は共同体の歴史が生み出したものだが、それでいて、彼の語りは他人にはうかがい知れない闇を強く感じさせる。
何度でも繰り返すが、われわれはたとえ架空の人物であっても、その意義(文章や音声)だけでは満足できず、そこに意味(指示対象)を求めてしまう。では、老レイシストの偏見に満ちた表象の束は、果たして指示対象をもつだろうか。
ここにこそ、フォークナーの仕掛けた罠がある。そもそも、『八月の光』の主人公ジョー・クリスマスは黒人の血を引く混血児だと祖父に決めつけられ、施設に送られる。しかし、この小説を読んでも、クリスマスが本当に黒人なのかどうかは、実は分からない。ただ、祖父の──あるいは過去を回顧し自問自答するクリスマス本人の──異様なパッションが、黒人としてのクリスマスのイメージを強烈に「指示」するだけである。
われわれはクリスマスの姿形を推論し、ある程度絞り込むことはできても、小説からそれを確定することはできない。オデュッセウスの場合、意義から意味への通路は比較的通りやすい。読者はあまり疑念も抱かず、砂浜で横たわっているオデュッセウスの姿を想像するだろう。しかし、ジョー・クリスマスの場合、読者は意義から意味への途上でつまずかざるを得ない。なぜなら、われわれに与えられるのは、あくまでレイシストの感情の染み込んだ「表象」だからである。それが指示対象をもつと考えるのは、彼の偏見に同調することになる。しかし、そのような偏頗な語り=表象がなければ、クリスマスは亡霊のように消えてしまうだろう。
クリスマスのアイデンティティの核心には、明らかに黒人性がある。しかし、その黒人性はまさに「痕跡」そのものであり、不確定性を免れることができない。われわれはつい、いつもの小説を読むときの癖でそれを「意味」として確定しようとするが、『八月の光』はその慣習を疑わせる。『アブサロム、アブサロム!』や『響きと怒り』もそうだが、フォークナーの語りは不在のものと実在のものをミックスさせる。それによって、小説のもつ本源的な不確定性が強調されるのである。
[了]
※1 マイケル・トマセロ『コミュニケーションの起源を探る』(松井智子+岩田彩志訳、勁草書房、2013年)105頁
※2 同右、306頁
※3 ツヴェタン・トドロフ『共同生活』(大谷尚文訳、法政大学出版局、1999年)12頁
※4 アイザック・アシモフ『鋼鉄都市』ハヤカワ文庫、(福島正実訳、1979年)
※5 『大江健三郎 柄谷行人全対話』(講談社、2018年)
※6 「意義と意味について」(土屋俊訳)『フレーゲ著作集』(第四巻、勁草書房、1999年)頁。さらに、フレーゲの言語論をその同時代の文学の課題と結びつ>けたのがフランコ・モレッティである。『ドラキュラ・ホームズ・ジョイス』(植松みどり他訳、新評論、1992年)第七章参照。
※7 同右、75頁。むろん、純粋に私的(主観的)な言語があるかは、大いに疑問である。本稿における私的とか主観的とかいう言葉は、一種の近似値だと考えてもらいたい。
この記事は、2022年3月刊行の『モノノメ #2』所収の同名記事の特別公開版です。あらためて2022年11月10日に公開しました。
本稿や特集「『身体』の現在」が掲載された『モノノメ #2』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。