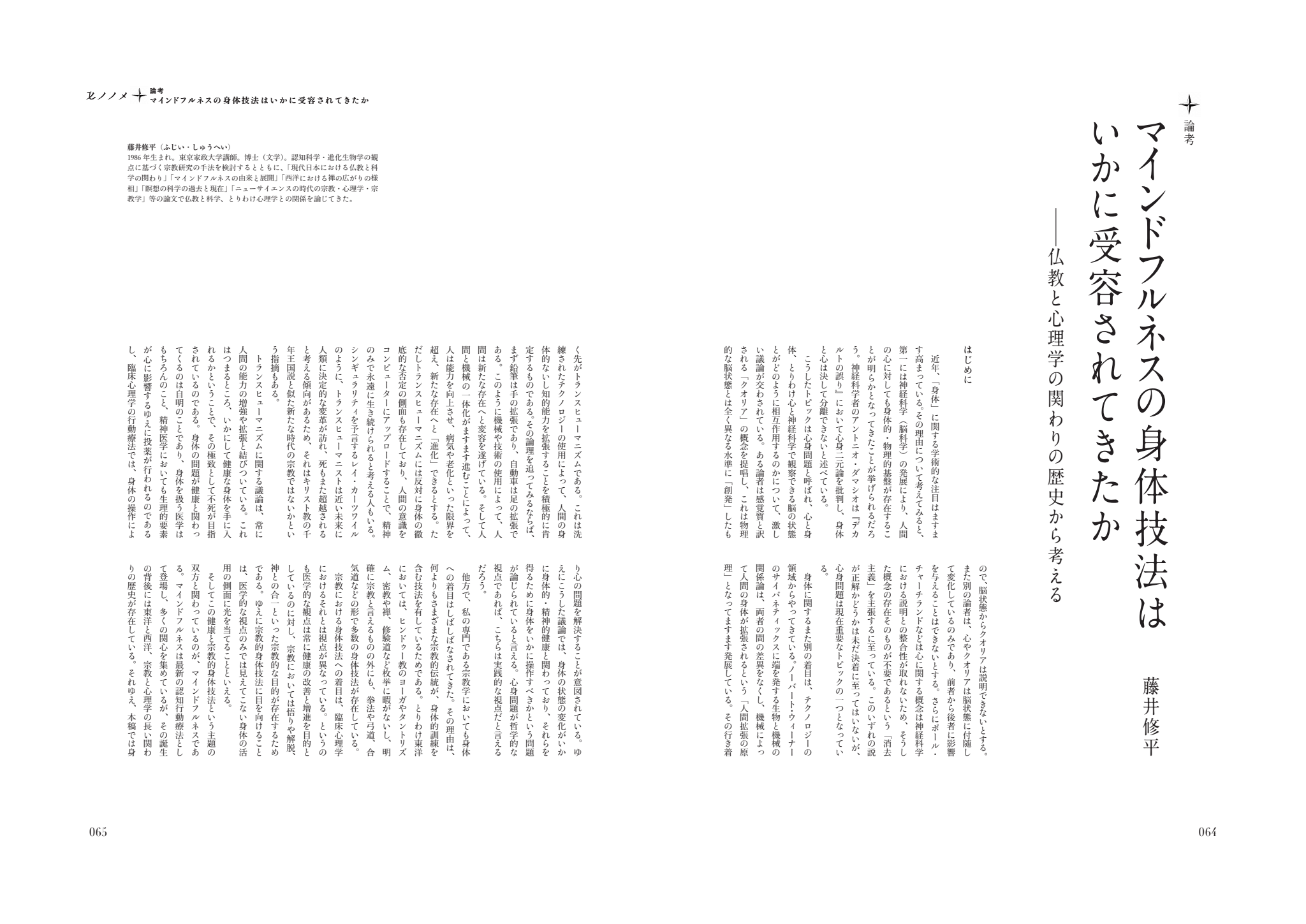近年耳にすることが多くなった「マインドフルネス」は、いかにして現在のような受け取られ方をするに至ったのでしょうか? 宗教学研究者の藤井修平さんが、身体技法の扱われ方を軸にして論じます。20世紀後半のアメリカでの「禅ブーム」、ニューエイジ思想との合流から、日本国内での自己啓発としての利用まで、仏教と心理学の関わりの歴史から体系的に整理していただきました。
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
はじめに
近年、「身体」に関する学術的な注目はますます高まっている。その理由について考えてみると、第一には神経科学(脳科学)の発展により、人間の心に対しても身体的・物理的基盤が存在することが明らかとなってきたことが挙げられるだろう。神経科学者のアントニオ・ダマシオは『デカルトの誤り』において心身二元論を批判し、身体と心は決して分離できないと述べている。
こうしたトピックは心身問題と呼ばれ、心と身体、とりわけ心と神経科学で観察できる脳の状態とがどのように相互作用するのかについて、激しい議論が交わされている。ある論者は感覚質と訳される「クオリア」の概念を提唱し、これは物理的な脳状態とは全く異なる水準に「創発」したもので、脳状態からクオリアは説明できないとする。また別の論者は、心やクオリアは脳状態に付随して変化しているのみであり、前者から後者に影響を与えることはできないとする。さらにポール・チャーチランドなどは心に関する概念は神経科学における説明との整合性が取れないため、そうした概念の存在そのものが不要であるという「消去主義」を主張するに至っている。このいずれの説が正解かどうかは未だ決着に至ってはいないが、心身問題は現在重要なトピックの一つとなっている。
身体に関するまた別の着目は、テクノロジーの領域からやってきている。ノーバート・ウィーナーのサイバネティックスに端を発する生物と機械の関係論は、両者の間の差異をなくし、機械によって人間の身体が拡張されるという「人間拡張の原理」となってますます発展している。その行き着く先がトランスヒューマニズムである。これは洗練されたテクノロジーの使用によって、人間の身体的ないし知的能力を拡張することを積極的に肯定するものである。その論理を追ってみるならば、まず鉛筆は手の拡張であり、自動車は足の拡張である。このように機械や技術の使用によって、人間は新たな存在へと変容を遂げている。そして人間と機械の一体化がますます進むことによって、人は能力を向上させ、病気や老化といった限界を超え、新たな存在へと「進化」できるとする。ただしトランスヒューマニズムには反対に身体の徹底的な否定の側面も存在しており、人間の意識をコンピューターにアップロードすることで、精神のみで永遠に生き続けられると考える人もいる。シンギュラリティを予言するレイ・カーツワイルのように、トランスヒューマニストは近い未来に人類に決定的な変革が訪れ、死もまた超越されると考える傾向があるため、それはキリスト教の千年王国説と似た新たな時代の宗教ではないかという指摘もある。
トランスヒューマニズムに関する議論は、常に人間の能力の増強や拡張と結びついている。これはつまるところ、いかにして健康な身体を手に入れるかということで、その極致として不死が目指されているのである。身体の問題が健康と関わってくるのは自明のことであり、身体を扱う医学はもちろんのこと、精神医学においても生理的要素が心に影響するゆえに投薬が行われるのであるし、臨床心理学の行動療法では、身体の操作により心の問題を解決することが意図されている。ゆえにこうした議論では、身体の状態の変化がいかに身体的・精神的健康と関わっており、それらを得るために身体をいかに操作すべきかという問題が論じられていると言える。心身問題が哲学的な視点であれば、こちらは実践的な視点だと言えるだろう。
他方で、私の専門である宗教学においても身体への着目はしばしばなされてきた。その理由は、何よりもさまざまな宗教的伝統が、身体的訓練を含む技法を有しているためである。とりわけ東洋においては、ヒンドゥー教のヨーガやタントリズム、密教や禅、修験道など枚挙に暇がないし、明確に宗教と言えるものの外にも、拳法や弓道、合気道などの形で多数の身体技法が存在している。
宗教における身体技法への着目は、臨床心理学におけるそれとは視点が異なっている。というのも医学的な観点は常に健康の改善と増進を目的としているのに対し、宗教においては悟りや解脱、神との合一といった宗教的な目的が存在するためである。ゆえに宗教的身体技法に目を向けることは、医学的な視点のみでは見えてこない身体の活用の側面に光を当てることといえる。
そしてこの健康と宗教的身体技法という主題の双方と関わっているのが、マインドフルネスである。マインドフルネスは最新の認知行動療法として登場し、多くの関心を集めているが、その誕生の背後には東洋と西洋、宗教と心理学の長い関わりの歴史が存在している。それゆえ、本稿では身体論について幅広い視点から考えるために、マインドフルネスが生まれるに至る歴史を、関係する宗教や心理療法の発展の面から記述してみたい。
マインドフルネスの概要
その歴史を探る前に、まずはマインドフルネスについて簡単に解説しよう。マインドフルネスという言葉はしばしば瞑想のような実践を指すものとして使われるが、それらはいずれも「マインドフルな状態」を目指しているからそう呼ばれるのであって、根底にはマインドフルネスという心構えないし考え方がある。マインドフルネスとは、上座部仏教で用いられるパーリ語のsatiを英訳したもので、日本語ではこれまで「念」と訳されてきた。これは仏教の八正道の一つ「正念」の念であって、その意味では馴染みのある概念といえる。この概念は、「現在の瞬間に注意を払うこと」を意味し、上座部仏教ではとりわけ重要視されている。
こうした上座部仏教由来の概念と実践を心理療法として取り入れているのが、「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」および「マインドフルネス認知療法(MBCT)」であり、この二種が現在の多くのマインドフルネスの大元といえる。いずれもうつ病などに苦しむ人を対象としたもので、マインドフルな心構えに至ることを目指して、瞑想等が行われる。例としてMBSRの八週間のプログラムでは、週六日、「静座瞑想」「ボディー・スキャン」「ヨーガ」などを行う。いずれも現在の瞬間に注意を払うことが強調され、一歩一歩を意識しながら歩く歩行瞑想や、五感を使ってゆっくり意識しながら食事を行う食べる瞑想も日常で行うことが推奨されている(※1)。こうした心理療法が効果を上げたことが、マインドフルネスブームの出発点となっている。
ただし、マインドフルネスがここまで広がったのは、単なる医療行為の枠に留まらずに展開していったゆえである。詳細は後に触れるが、もう一つの大きな側面がビジネス領域における能力開発としてのマインドフルネスである。これは、二〇一四年に米『タイム』誌で「マインドフル革命」の特集が組まれたことが転機とされる。グーグル、ゼネラル・ミルズ、ゴールドマン・サックス、アップルなどの企業でマインドフルネスが導入されたことが伝えられ、その知名度はますます高まった。ビジネス領域では、マインドフルネスの実践によって集中力が強化される、ストレス下で平静を維持できる、記憶力が向上する、チームワークが良くなるなどの効果が得られ、生産性の向上に繫がると言われている。
こうした能力開発としてのマインドフルネスは、時期を区切って集中的に行うよりも、日常生活の細かな場面で実践するものである。たとえば『ハーバード・ビジネス・レビュー』のある記事では、目が覚めたら横になったままで二分間自分の呼吸を意識する、出社したら自分の席で十分間目を閉じて意識を呼吸に集中させる、会議の最初の二分間、全員で呼吸への集中を行う、午後は一時間おきに一分間の瞑想をする、帰宅中に十分間呼吸に意識を集中する、などの実践を勧めている(※2)。
マインドフルネス普及の背景
現在では、このようなマインドフルネスの実践法やその効果については至るところで語られており、心理学の学会においても毎年多くの発表が見られるほどとなっている。他方で、そうしたマインドフルネスがどのようにして誕生したのか、これまで多数存在した瞑想法とは何が違うのかという点は、落ち着いて見直されることはほぼなかった。マインドフルネスの誕生と普及には、とりわけ米国の社会と宗教、そして心理学が複雑に関わりあっているのである。そこで本稿では、マインドフルネスの誕生に至る米国社会の変化を、とりわけ宗教の面に着目して記述していきたい。
一九五〇-六〇年代:アメリカ仏教の形成と禅ブーム
マインドフルネス普及の根底にあるのは、「アメリカ仏教」の発展である。マインドフルネスの流行を研究したジェフ・ウィルソンも、「マインドフルネス運動は仏教の表現と、アメリカ的な形而上学的宗教の表現の双方によるものである。すなわち、アメリカ仏教的・形而上学的宗教である(※3)」と述べている。米国で仏教が広がっていると聞いて驚かれるかもしれないが、ケネス・タナカの『アメリカ仏教』によると、米国には約三百万人の仏教徒がおり、なおかつ仏教に何らかの重要な影響を受けたというアメリカ人は約二千五百万人にも及ぶという。書店には「tricycle」「Buddhadharma」など仏教系の雑誌が並び、仏教の教えを学べる本も多数出版されている。寺院や禅センターを訪れる人もいるが、その何倍もの人が書籍によって仏教に触れており、就寝前にこうした本を読んでいることから「ナイトスタンド・ブッディスト」と呼ばれている(※4)。
西洋の仏教研究では、米国をはじめとする西洋諸国に仏教が伝わる道筋は「輸出」「輸入」「手荷物」の三種類あるとされる。「輸出」は、一般にイメージするような宣教師(開教師)がその国に赴き、仏教を伝える過程である。特徴的なのが残り二つで、「輸入」は西洋人自らが他国から仏教を取り入れることで、「手荷物」は仏教徒である移民がその国に移住する際に、自らの宗教を持ち込むことである。マインドフルネスと関わりの深い上座部仏教も、主にこの手荷物の過程によって米国に広まった。一九六〇年代以降、上座部仏教圏であるスリランカ、ビルマ(現ミャンマー)、タイなどからも米国に移民が行われるようになり、同時に彼らの仏教も持ち込まれた。さらにベトナム戦争やカンボジアのポル・ポト政権樹立により生まれた多数の難民も、西洋諸国に受け入れられた。
こうしてアジアの仏教が米国やヨーロッパに根付いていったが、それに対し西洋人が関心を示したため、仏教は民族的な枠を超えて広がった。前述の「輸入」の過程である。その最初の表れが、一九五〇-六〇年代の「禅ブーム」である(※5)。その担い手として著名な鈴木大拙は戦前から米国を訪れ、仏教の著作の翻訳などを行っていたが、一九四九年に再び米国に赴き、コロンビア大学などで講義を行う傍ら、英語の著作を多数著した。その読者や彼の講義を聞いた学生、とりわけ米国で支配的なキリスト教的価値観に反発していた「ビート世代」は強く共鳴し、西洋的なものとは対照的な「東洋の神秘」として禅の教えを称えた。
そうして禅への関心が大いに高まったところに、実践を指導する人物が現れた。曹洞宗の鈴木俊隆である。彼は一九五九年の渡米後にサンフランシスコ禅センターやタサハラ禅マウンテンセンターを開設し、多くの西洋人に坐禅の指導を行った。同様にヨーロッパにおいても弟子丸泰仙が一九六七年にフランスに渡り、独力で禅を広めた。
これらの人物の活動により、西洋において禅は一大ブームとなった。彼らの教えを受けた人物は各地で次々と「禅センター」を開設し、現在では米国、フランス、ドイツ、スペインをはじめとして五百を超える数が存在している。また、社会に十分に浸透したために「Zen」は仏教的な枠を超え、日常的な概念として定着するに至った。そこでのこの言葉は平穏な、調和的な、シンプルな、リラックスしたなどを意味しており、化粧品メーカーのロレアルが「 Zen」と名の付く商品を販売しているかと思えば、紅茶メーカーのタゾには「Zen」という緑茶のブレンドがある。ASUSの「ZenFone」にもこうした意味合いが込められている。後述するように、マインドフルネスの普及はこの禅ブームの過程をなぞっており、同様の水準で米国社会に浸透しているのである。
一九七〇年代:心理学における宗教への着目
マインドフルネスの誕生に至るもう一つの流れは、米国の心理学における宗教的身体技法への着目にある。心理学と宗教というのは、一方は学問でありもう一方は組織的な実践であるため、一見して別のもののように思われる。ところが、とりわけ米国においては、宗教と心理学の発展は大いに関わり合ってきたのである。
その接点は主に、応用の領域である臨床心理学に存在している。日本の臨床心理学にも大きな影響を与えているカール・ロジャーズは自己実現という言葉で人間の成長の可能性を説いたが、彼が目指していた人格は、ニューエイジ的な要素が多分に含まれていることが指摘されている。(※6)
同じく著名なアブラハム・マズローもまた自己実現を論じたが、彼は後にさらなる成長の目標として「自己超越」を掲げるようになる。この言葉は、アイデンティティや自己の感覚が個人を超えて広がり、人類や生命そのもの、ないし宇宙と結びつく体験を指しており、ここから自己超越を目指すトランスパーソナル心理学が生まれた。この分野では何よりこの自己超越を体験することが目指されるわけであるが、ここではそのような体験として、すでに具体的なものが想定されている。それが坐禅や瞑想による宗教的体験である。同分野を日本に紹介した吉福伸逸は、この点について率直に語っている。
「トランスパーソナル心理学というのは最終的には悟りの心理学であって、今まで、宗教とか神秘主義というような言葉で括られてきて、非常に特殊なものとされていた、特定の意識状態を、日常的な正常といわれている意識状態の延長線上に据えて、それほど特殊ではないというところにきちんと理論的に置いていくものだと思うんです。(※7)」
これは換言すれば、宗教的体験を積極的に得ようとする心理学ということであって、「トランスパーソナル心理学は科学というより宗教や哲学に近い(※8)」と述べられているように、宗教とほとんど区別できないものといえる。
このような展開は、ヒューマン・ポテンシャル・ムーブメントと呼ばれる。それはマズローやロジャーズを出発点とし、カリフォルニアのエサレン研究所を中心に多数の心理療法や、潜在能力開発法が生み出されてきた。ここでは例として、精神科医スタニスラフ・グロフが開発したホロトロピック・セラピーを挙げてみよう。これは通常、豊かな自然の中で合宿形式で行われ、ヨーガを参考にした「ホロトロピック呼吸法」を中心に、音楽に合わせて体を動かすボディワーク、直感的に絵を描くマンダラ・ドローイングなどが実践される。こうしたワークの中で、しばしばスピリチュアルな体験が得られ、それが心身の解放に繫がるとされる。ある男性の体験はこう記述されている。
「エネルギーを解放したセッションの間、彼は、娘の存在を感じた。それまで彼は、娘の死により、深い悲しみと痛みのなかにいた。『心の中では廃人』同様だった。今回、『娘の励ましで、心が満たされ、癒された』のである。彼は、深い安らぎの状態を体験し、自他の境界がなくなり、ひとつになった感じがした。この幸福な状態にいる時、彼は自分に話しかける声のメッセージを受け取った。その声は、この平和と喜びの感覚、『暖かい励ましと癒し』を、苦しんでいる人たちと分かち合ってください、というのだった。(※9)」
ここでは自他の境界がなくなるという自己超越の感覚や、何者かのメッセージを受け取るという超自然的な体験が語られる。こうした体験はスピリチュアルあるいは宗教的とみなすのに十分であろう。
心理療法の中に宗教的要素が含まれる一方で、東洋の宗教的身体技法も注目され、とりわけマハリシ・マヘッシュ・ヨーギーによる超越瞑想は大いに実践や研究が行われた。そうしてこのような宗教と心理学との関わりの中で、マインドフルネスの源流になったインサト・メディテーションもまた生まれたのである。
一九八〇 - 九〇年代:マインドフルネスの誕生と展開
インサイト・メディテーション協会はジャック・コーンフィルドとジョゼフ・ゴールドスティーンによって設立された。彼らはタイやビルマで学び、上座部仏教のヴィパッサナー瞑想を西洋的にアレンジし、宗教性を薄めてより受け入れられやすいものとした。そして彼らのもとで学んだのが、MBSRの開発者ジョン・カバットジンである。彼はマサチューセッツ工科大学に通う傍ら、インサ イト・メディテーションをはじめとしてベトナムのティク・ナット・ハンや日本で禅を修行したフィリップ・カプロー、韓国系の観音禅に学び、それらの技法を取り入れたものとしてMBSRを作り上げた。その手法は、一九九〇年に刊行された『Full Catastrophe Living』によって広く一般に知られることになった。同じく九〇年代にMBCTを開発したジョン・ティーズデールも、カバットジンの手法を参考にしただけではなく、超越瞑想やチベット仏教、英国で上座部仏教を実践しているガイア・ハウスに学んでいる。
このように記述すると、マインドフルネスもまた、禅ブームやニューエイジ、トランスパーソナル心理学の系譜に属することが理解されるであろう。米国ではここまで一貫して東洋的な身体技法への注目が存在していたのだ。しかし現在では、超越瞑想やトランスパーソナル心理療法などとマインドフルネスの立ち位置は大いに違って見える。ではその違いはどこにあるのだろうか。
前述のウィルソンの分析によると、それは脱文脈化と脱宗教化のゆえである。脱文脈化とは、東洋的な要素を取り除くことだと言える。仏教が「アメリカ仏教」になり、上座部仏教からインサイト・メディテーションとマインドフルネスが生まれる際には、仏教文化が「東洋の神秘」から、西洋的・アメリカ的なものに変化する過程が存在している。この過程で、涅槃を目的とする来世志向的側面は取り除かれて健康を目指す現世志向的なものとなり、師匠と弟子の絶対的関係や、女性の立場の低さは批判された。こうして、よりアメリカ的に見えるものが作り出されたのである。
瞑想が東洋的なものではなくなった末に、それは仏教でもなくなる。これが脱宗教化である。この点に関しては、カバットジンは意図的にマインドフルネスの仏教性を秘匿していたことがわかっている。彼は「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)は仏法をどうにかして主流の環境に持ち込むための多数の方便の一つとして発展した(※10)」と述べているように元来は仏教的な技法を広めたいという目的があったが、プログラムを作り上げる際に仏教性を隠し、非宗教的な実践に見えるようにした。
こうした仕掛けが功を奏し、マインドフルネスは米国で爆発的な広がりを見せた。宗教性を排除したゆえに、それは企業が従業員に勧めても問題ないものとなり、宗教教育が禁止される公立学校でも実践されうるものとなった。さらに「Zen」という言葉が辿ったのと同様、「 Mindful」も日常語となり、マインドフルな食品や化粧品が販売されることとなった。
試しにウォルマートの通販サイトでこの言葉を検索してみると、まず多数の本がヒットする。瞑想に関するものに加え、マインドフルな食事、人間関係、仕事、運動、子育てなど人生のあらゆる場面に対するガイドがあり、『マインドフルな出費』や『マインドフルなキリスト教徒』などというタイトルの本もある。後者は、マインドフルネスの考え方は宗教的なものではなく、他宗教とも両立が可能だということを示している。続いて多いのが健康・美容関係の商品で、マインドフルなスキンケア用品や、化粧品などが売られている。さらにインテリアや手芸用品もあり、「マインドフルなエプロン」「マインドフルな座布団」なども見つかる。こうした書籍以外の商品には、健康的、エコ、優しいなどのイメージがついていることがわかる(※11)。
日本におけるマインドフルネスの広がり
この波はしばらくして日本にも到達した。興味深いことに、前述のカバットジンの著書は一九九三年に『生命力がよみがえる暝想健康法』として刊行されていたが、その際にはさほど注目されず、同書は二〇〇七年に『マインドフルネスストレス低減法』に改題されて復刊している。それでもこの時期にはまだ、一般社会への浸透はなされていなかった。丹羽宣子の調査によると、日本の新聞・雑誌記事では二〇〇〇年に米国のマインドフルネスに言及するものがあるが、その後十数年間は増加の傾向は見られない。風向きが変わるのが二〇一五年で、この年から新聞や雑誌でも積極的に取り上げられるようになる(※12)。学界の動向はこれに数年先行している。日本心理学会ではカバットジンの著作の翻訳者である春木豊らが二〇〇七年にワークショップを開いており、二〇一〇年代からは日本心理学会、日本行動療法学会などで毎年いくつもの発表が見られるようになる。また二〇一〇年に日本マインドフルライフ協会が、二〇一三年に日本マインドフルネス学会が設立されたことも、その普及を示しているといえるだろう。
こうした日本での広がりに際しても、カバットジンらの仕掛け、すなわち脱文脈化と脱宗教化は効果的に働いたように思われる。前者に関しては、「念」ではなくマインドフルネスと呼ばれ、グーグルなどでの導入が強調されることによって、それは東洋的ではなく「アメリカ的」なものとして受け入れられたといえる。また後者については、とりわけ日本ではオウム真理教による一連の事件により、瞑想ひいては宗教一般に対して警戒心が広がっていたが、「『瞑想』と言うと日本では敬遠する人がいるけど、『マインドフルネス』という言葉になると、なんとなくいい感じがするのではないでしょうか(※13)」と言われているように、宗教性の秘匿によってそうした警戒を回避できたのである。
マインドフルネスへの批判的見解
ここまで拡大を続けているマインドフルネスであるが、この風潮に対しては批判的な見方も存在する。以下ではマインドフルネスの功罪を考えるにあたってまず、それらの批判を見ていこう。
第一の指摘は、マインドフルネスの商品化に関するものである。前述のウィルソンはマインドフルの名を冠した商品の登場だけではなく、プログラムの商標化やブランド化が進んでいると指摘し、マインドフルネスは「根本的に、人々にお金を消費させ、他の手段では購入されないような製品を消費させるための道具(※14)」となっていると述べている。これに対しチベット仏教僧のチョギャム・トゥルンパは「スピリチュアルな物質主義」という言葉で批判し、エゴから脱するための実践が、かえってエゴを強化することになっていると述べている(※15)。また日本で活動する僧侶のネルケ無方も、「マクマインドフルネス」という言葉を取り上げ、マインドフルネスが人々の欲望を喚起する役割を果たしていると指摘する。(※16)
こうした指摘はアメリカ的な消費主義社会への批判でもあり、ある面では米国固有の問題ともいえるが、別の観点からの批判も持ち上がっている。米国でマインドフルネスの実践に携わっている大谷彰は、マインドフルネスには「ピュア・マインドフルネス」「臨床マインドフルネス」の二つのパラダイムが存在すると指摘している(※17)。前者は仏教的な視点であり、マインドフルネスも悟りに至るための教えの一つとみなしている。後者は実利的な視点であり、治療もしくは健康増進を目的としている。そしてこの二つは、必然的に衝突するものと言える。というのも、前者から後者を見ると、それは「現世利益」を求めて宗教的な修行を行っていることになるからである。上座部仏教の教えを論じた魚川祐司は「瞑想は役に立たない」とし、瞑想の「『効能』を説き、それが得られないとすれば瞑想のやり方が悪いのだと、あたかも瞑想が万能の処方箋であるかのようなことを言う人(※18)」は瞑想を誤解していると批判している。また曹洞宗僧侶の藤田一照は、仏教の八正道のうち「念」のみを重視するマインドフルネスに対して、現在の瞬間のことのみを重視し念の記憶的側面に触れないマインドフルネス概念は一面的であるうえ、倫理的な側面が考慮されていない点が問題だとして、念だけを独立して取り上げることのない新しいマインドフルネスを構築しなければならないと述べている(※19)。
ここでは二つの問題が指摘されている。前者は現世利益の問題であり、禅は「無功徳」だと言われているように、効能を求めて行うのは本来の実践ではないという視点が見られる。また後者は、宗教的実践から一部分のみを取り出すことが問題視されていると言える。藤田は倫理的側面が無視されていると指摘していたが、同様に米国でもマインドフルネスが個人の癒しや意識の改善のみを追求していることに対し批判が行われている。そこでは他者にも気を配るために社会全体のマインドフル化を目指さねばならないとされており、人種差別の撤廃やフェミニズム、環境保護といったリベラルな運動と結びついている。
これらの点には、ピュア・マインドフルネスと臨床マインドフルネスの姿勢の対立が表れている。前者は後者が効能を求めていることを批判するが、心理療法としては効能がなかったら治療にならないのであり、功徳なしとすることはできないだろう。さらにマインドフルネスは宗教性を取り除くことで広まったのだが、倫理的な側面への指摘では、再び集団化・宗教化しなければならないと言われているのである。大谷は「マインドフルネスは手段か、それとも人間としてのあり方か?」(※20)という問いを立てているが、それぞれの立場の目指すものが異なる以上、答えの出ない論争であろう。
宗教的身体技法とビジネスの関わり
こうした批判に加え、議論すべき点をさらに一つ取り上げたい。それはマインドフルネスとビジネスとの関わりから浮き彫りになるものである。 そもそもマインドフルネスは、なぜそこまでビジネスの領域で注目されるのだろう。
その答えの一つは歴史的なものである。マインドフルネスを含めたアメリカ仏教の展開を振り返ってみると、それは常にアメリカ西海岸、とりわけカリフォルニアを中心に起こっていた。カリフォルニアはもっともアジア系の移民が多い州で、日系移民のための寺院が存在するゆえに、前述の鈴木俊隆も同地で活動していたのであった。上座部仏教についても同様である。同時に、ヒッピー文化やニューエイジもまさにサンフランシスコが中心であり、トランスパーソナル心理学の拠点も存在していた。そして周知のように、ハイテク企業が集まるシリコンバレーもカリフォルニアにあり、アップルやグーグルも創立当初から同州に本社を構えている。つまりこうした企業と、仏教やニューエイジは常に隣り合わせだったのである。カリフォルニア生まれのスティーブ・ジョブズの経歴はその典型と言え、彼がアップルを興しPCやスマートフォンを開発するとともに、インドへ旅し、禅僧の教えを受けたことは二つの要素の接点を如実に表している。他方でインサイト・メディテーション協会やカバットジンはマサチューセッツ州が拠点であるが、彼がMITで学んでいたように、やはり最先端の技術と瞑想が結びついている。
このように、とりわけ米国のIT企業と仏教やニューエイジとの繫がりが深いことがわかるが、ビジネスの領域全体に、より本質的に宗教的身体技法との結びつきがあることを次に指摘したい。話は一九六〇年代の日本に遡る。精神科医の平井富雄や心理学者の佐藤幸治はこの時期に「禅心理学」を提唱し、世界的に見ても先駆的な坐禅中の脳波測定を行った。佐藤はその成果を元に、禅には心理療法としての効果があるとして「禅の十徳」を説いたが、その中には意志が強くなる、能率が上がる、頭がよくなる、人格が整ってくるなどの効能が含まれている。彼は「禅における身心の調整が作業能率を高め、事故を減少させることも、むしろ当然である(※21)」として、経営者に対し企業での坐禅の導入を勧めている。
さらに時代は進んで一九八〇年代から九〇年代、バブル景気を背景に、企業では研修として社員の自己啓発セミナーの受講を推進していた。自己啓発セミナーは宗教とは異なると思われるかもしれないが、その源流はトランスパーソナル心理学と同様、ロジャーズらの人間性心理学および ヒューマン・ポテンシャル・ムーブメントにある。そこから生まれた「エンカウンター・グループ」と、ネットワークビジネスの販売員向けの研修が組み合わさって「ライフダイナミックス」などのセミナー会社が生まれた。そうした自己啓発セミナーに、コミュニケーション・対人能力、やる気の向上などの効果を期待して、企業から社員が送られていたのである。
こうした歴史を踏まえると、禅心理学、自己啓発セミナー、マインドフルネスはいずれも、宗教的身体技法を会社員に実践させることによって、能率の向上が図られていたことがわかる。そしてその問題点もまた共通である。ブライアン・ヴィクトリアは『禅と戦争』において、戦時中に挙国一致体制に沿うように行われていた皇道禅の手法が、戦後の企業において「規律、服従、上位者への忠誠という伝統的価値観を回復させるための手段(※22)」として用いられていたと指摘している。自己啓発セミナーにおいても、その中心にある「世界はあなたがどう見るかにかかっている」という価値観が、「職場の不満も人間関係の困難も、原因はすべて自分にある。そこをブレークスルー(突破)すれば、すべて解決するのだ(※23)」というメッセージとなり、従業員の搾取に繫がることが懸念されている。
もちろん、ここに挙げた中でも臨床心理士や精神科医など専門家の手によるものはそれを支える訓練と責任が存在し、無資格の実践とは大きな違いがあるが、それでもこうした技法には共通の要素もある。『セラピー文化の社会学』を著した小池靖は、宗教、心理療法、自己啓発セミナーなどはいずれも、成員を物理的、社会的、イデオロギー的に外部から遮断し、新たなグループとの密接な相互作用のもとに置くことで、アイデンティティの変容を促す「アイデンティティ変容組織」である点で共通するという見方を伝えている(※24)。ここでは身体のコントロールを行うことによって、心のコントロールも進んでいると言え、それが極端な用いられ方をした場合には、さまざまな問題に繫がりうるものである。
マインドフルネスの可能性
このような批判や懸念は存在するにせよ、それでもマインドフルネスには注目に値するだけの、大いに革新的な要素が含まれている。次にそうした点について論じてみよう。
第一に、マインドフルネスの登場は、心理学および心理療法の領域に東洋的身体技法への注目をもたらすことによって、これらの領域を変えうるものである。前述のように、これまで米国では禅やニューエイジの要素が心理学に取り入れられていたが、それらはあくまで周縁的なものに留まっていた。それに対しマインドフルネスの普及は、より主流の心理学にこうした技法が受け入れられていることを示している。同じく第三世代の認知行動療法とされる「弁証法的行動療法」や、「アクセプタンス&コミットメントセラピー」にもマインドフルネスの考えが取り入れられており、宗教的身体技法や思想を参考にすることはより当たり前のこととなっている。また心理学一般についても、米国の宗教心理学の分野では、宗教が精神的健康の改善に役立つという研究が近年増えてきている。
第二に、宗教の側もまた変化している。西洋ではしばしば、仏教は宗教ではなく、むしろ心理学に近いものであると言われる。ダライ・ラマ十四世は仏教の心についての教えを「仏教の心理学」と呼び、西洋の心理学との共通性を指摘しているし、日本でテーラワーダ仏教(上座部仏教)を広めているアルボムッレ・スマナサーラは「仏教は時間の経過とともに宗教化が進んだのですが、現在でもテーラワーダ仏教はいわゆる宗教とはずいぶん違います。宗教というより、むしろ科学というほうがしっくりきます(※25)」と述べている。もちろん、アジアで実践されている仏教に宗教的要素がないわけではなく、間違いなく宗教と呼べるものなのであるが、重要なのは西洋ではそのような非宗教的な仏教の表象が好まれるという点である。また実際に、「心の科学としての仏教」では科学との親和性が強調され、瞑想中の脳状態を測定する実験が行われるなどして、多くの研究成果を生んでいる。このような研究協力は、宗教自体の解明にも貢献するものである。
加えて、ビジネス領域においても宗教的身体技法の導入は新たな展開を見せている。前述のように日本の企業における宗教的身体技法の実践は、どうしても「ストレスを感じず、特に疑問を持たずに働き続ける従業員」を生む方向に向かいやすいが、米国ではまた別の価値を生み出しうる点が強調されている。経営学の分野では近年、「職場のスピリチュアリティ」に注目が集まっている。これは企業文化あるいは企業倫理として、組織および働く個人がスピリチュアルになることを推進すれば、働く人の幸福感の向上、働く意味や意義の獲得、働く場への帰属感の向上などの効果が得られ、企業パフォーマンスの向上に繫がるという見方である。その際のスピリチュアリティとは、「自己超越(自分が他の人々、考え、自然、あるいはある種の高次の力と繫がっているという信念)」、「全体性と調和(自己のさまざまな側面を統合して、首尾一貫した共生的な自己の概念にすること)」、「成長(自己実現を達成するために、自分が何になろうとしているのか、何をすべきなのかを明確に認識すること)」という要素が含まれている。これらの性質を高めるための実践として、マインドフルネスやヨーガ、太極拳などが挙げられている。ここでは必ずしもストレス低減に重点が置かれず、従業員のモチベーションの向上や企業の社会的責任(CSR)を果たすことが目指されている。(※26)
おわりに
本稿では、身体技法としてのマインドフルネスの誕生に至るまでの歴史と、その応用可能性について見てきた。最後に再び、心と身体の関係性について考えてみよう。これまで見てきたものはいずれも、心を変容させるにはまず身体を操作すべきという、身体の心に対する優位の立場を示しており、その点では身体の重要性を強調するものといえる。しかし一方で、心に関するものが登場する場面もしばしばあった。マインドフルネスは何より心構えであり、瞑想もそのマインドフルネスを目指して行われるものである。禅ブームも同様で、坐禅という実践以上に、禅という心構えに共感が持たれたゆえに、さまざまな商品にこの名がつけられることになった。そのように考えると、心と身体のどちらが先にあってもう一方を変化させるのかは曖昧であり、両者の関係性はより複雑なものだということがわかる。
身体と心は切り離せないものだとしても、マインドフルネスはその両者について変革をもたらすものであり、その可能性にはますます注目が集まっている。ではここから、マインドフルネスをはじめとする東洋的・宗教的身体観もまた、見直されてきていると言えるだろうか。確かに禅ブームやニューエイジにはそのような側面があるが、マインドフルネスの普及の際には、東洋性と宗教性を取り除く過程が存在していたことを思い出してもらいたい。単純に東洋的・宗教的なものではなく、それらと西洋的・心理学的要素が複合し、新たな形態へと変化したのがマインドフルネスなのである。
本稿ではマインドフルネス誕生の過程を振り返ることで、この変化が突発的に起きたのではなく、禅ブームやトランスパーソナル心理学などを経由して、少しずつ進んでいたことを示した。この変化はゆっくりではあるが、着実にある方向に向かっており、それが今の時代の特徴を表していると言える。その一つは、宗教的なものがより意識されない形で、姿を変えて存続していることである。マインドフルネスにおいても職場のスピリチュアリティにおいても、組織的な宗教とは異なるものの、宗教的要素の含まれるものが改めて注目されている。これは、米国で近年になって世俗化ないし無宗教化が目立っていることとも関係しており、ギャラップ社の世論調査によると、教会、シナゴーグ、モスクなどの宗教組織に所属するアメリカ人の割合が、二〇二〇年に初めて半数を下回っている(※27)。そのような社会において、宗教性はより水面下に隠れ、意識されずに影響を及ぼすものとなっているのである。これは、米国が日本の状況に近づいているとも言えるだろう。
もう一つの変化は、宗教とテクノロジーの接近である。科学と宗教の対立という旧来のイメージにもかかわらず、両者が混ざり合う例はますます増えている。日本のロボットづくりやアニメないしゲームのキャラクターの創造には最新のテクノロジーと精霊崇拝的な精神性が結びついた「テクノ・アニミズム」が寄与しているという言説も、近年注目を集めている(※28)。とりわけ仏教とテクノロジーの関わりは深く、日本でもアンドロイド観音が造られたり、宇宙寺院の計画が進められたりしている。最新の神経科学や心理学の技術を取り入れたマインドフルネスもこの傾向を示すものであり、宗教的技法とテクノロジーの融合は、今後ますます進むものと思われる。
こうした点を踏まえれば、マインドフルネスが生まれ、広まっていったという出来事のもつ意味や革新性についても十分に理解できるだろう。
[了]
※1 ジョン・カバットジン著、春木豊訳『生命力がよみがえる瞑想健康法』実務教育出版、1993年。
※2 ラスムス・フーガード、ジャクリーン・カーター「朝起きて、通勤、会議前……すきま時間の活用法」、ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳『マインドフルネス』ダイヤモンド社、2019年、77-84頁
※3 Jeff Wilson, Mindful America: The Mutual Transformation of Buddhist Meditation and American Culture, Oxford University Press, 2014, p.192.
※4 ケネス・タナカ『アメリカ仏教:仏教も変わる、アメリカも変わる』武蔵野大学出版会、2010年。
※5 西洋の禅ブームに関しては拙論「西洋における禅の広がりの様相」、宗教情報リサーチセンター編『海外における日本宗教の展開:21世紀の状況を中心に』宗教情報リサーチセンター、2019年、50–73頁を参照。
※6 斎藤環『心理学化する社会:癒したいのは「トラウマ」か「脳」か』河出書房新社、2009年。
※7 吉福伸逸『トランスパーソナルとは何か』春秋社、1987年、28頁。
※8 渡辺恒夫「トランスパーソナル心理学」、伊藤隆二、松本恒之編著『現代心理学25章』八千代出版、1995年、296-297頁。
※9 ティム・マクリーン、高岡よし子「ホロトロピック・ブレスワーク」、諸富祥彦編著『トランスパーソナル心理療法入門』日本評論社、2001年、125頁。
※10 Jon Kabat-Zinn, “Some Reflections on the Origins of MBSR, Skillful Means, and the Trouble with Maps”, Contemporary Buddhism, Vol. 12, No. 1, 2011, p.281.
※11 https://www.walmart.com/ (2022年1月29日閲覧)
※12 丹羽宣子「マインドフルネスの流行と日本仏教界」、宗教情報リサーチセンター編『日本における外来宗教の広がり:21世紀の展開を中心に』宗教情報リサーチセンター、2019年、155-164頁。
※13 香山リカ『マインドフルネス最前線:瞑想する哲学者、仏教僧、宗教人類学者、医師を訪ねて探る、マインドフルネスとは何か?』サンガ、2015年、101頁。
※14 Jeff Wilson, Mindful America, p.156.
※15 Chögyam Trungpa, Cutting through Spiritual Materialism, Shambhala, 2002.
※16 ネルケ無法「禅の立場から指摘する『マクマインドフルネス』の問題点」、蓑輪顕量監修『別冊サンガジャパン3 マインドフルネス:仏教瞑想と近代科学が生み出す、心の科学の現在形』サンガ、2016年、342-355頁。
※17 大谷彰「アメリカにおけるマインドフルネスの現状とその実践」、『精神療法』金剛出版、第42巻4号、2016年、491-498頁
※18 魚川祐司『仏教思想のゼロポイント:「悟り」とは何か』新潮社、2015年、67–68頁。
※19 藤田一照「『日本のマインドフルネス』へ向かって」、『人間福祉学研究』関西学院大学人間福祉学部研究会、第7巻1号、2014年、13–27頁。
※20 大谷彰「マインドフルネスの進化と真価:臨床パラダイムの知見から」、飯塚まり編著『進化するマインドフルネス:ウェルビーイングへと続く道』創元社、2018年、29頁。
※21 佐藤幸治『心理禅:東洋の知恵と西洋の科学』創元社、1961年、48頁。
※22 Brian Daizen Victoria, Zen at War, Second edition, Rowman & Littlefield, 2006,p.182.
※23 柿田睦夫『自己啓発セミナー:「こころの商品化」の最前線』新日本出版社、1999年、176頁。
※24 小池靖『セラピー文化の社会学:ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ』勁草書房、2007年、59頁。
※25 アルボムッレ・スマナサーラ『仏教は心の科学』宝島社、2008年、246頁。
※26 Paul Tracey, “Religion and Organization: A Critical Review of Current Trends and Future Directions”, The Academy of Management Annals, Vol. 6, No. 1, 2012, pp.87-134.
※27 https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-fallsbelow-majority-first-time.aspx(2022年1月29日閲覧)
※28 アン・アリスン著、実川元子訳『菊とポケモン:グローバル化する日本の文化力』新潮社、2010年。
この記事は、2022年3月刊行の『モノノメ #2』所収の同名記事の特別公開版です。あらためて2022年12月1日に公開しました。
本稿や特集「『身体』の現在」が掲載された『モノノメ #2』は、PLANETSの公式オンラインストアからご購入いただけます。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。