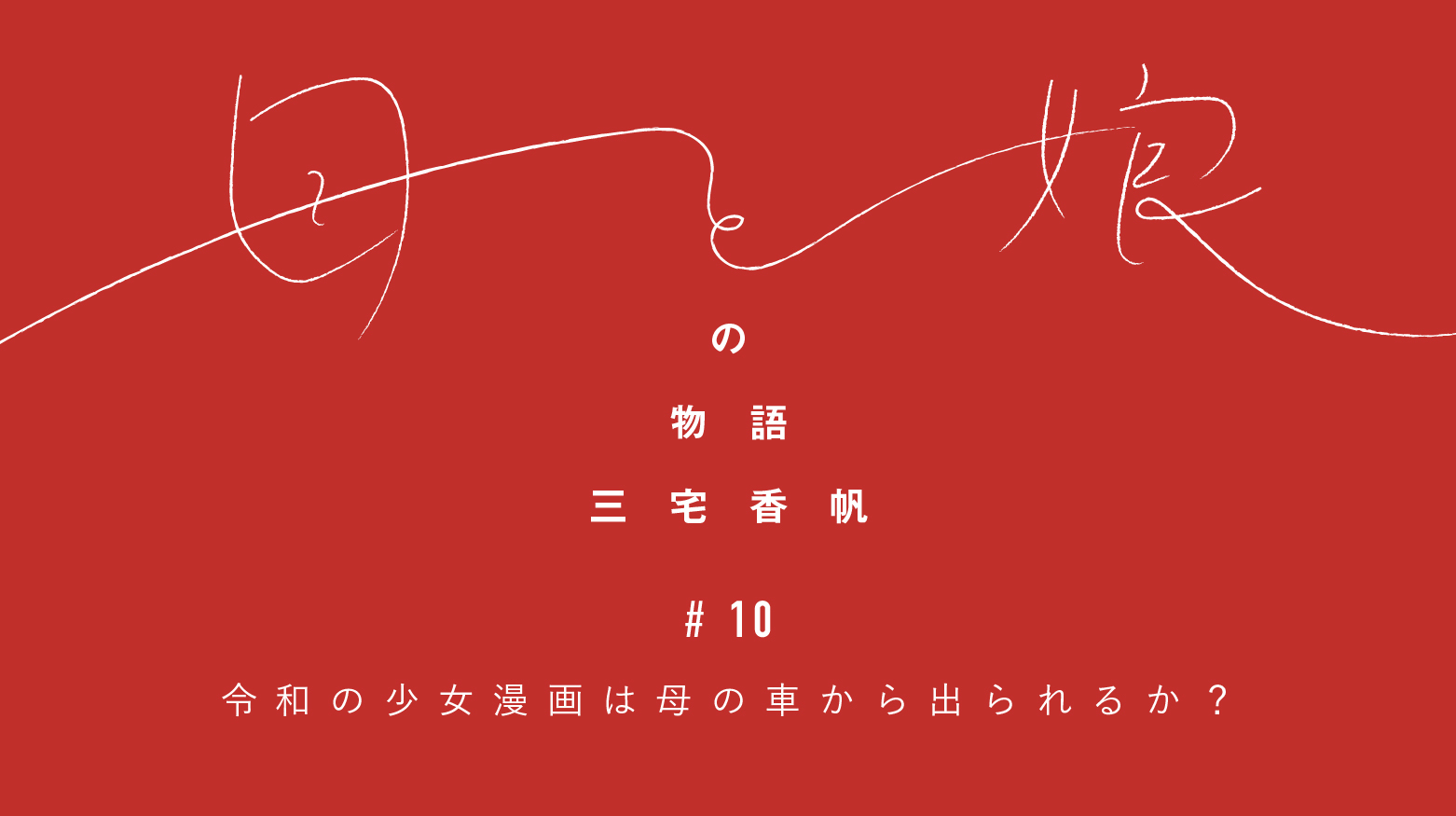書評家の三宅香帆さんによる連載「母と娘の物語」。2010年代以降の〈娘〉の成熟像とはどのようなものか。『逃げ恥』『違国日記』『凪のお暇』といったコンテンポラリーなフィクション作品を手掛かりに、その困難さを分析します。
「遅いインターネット」で好評を博した三宅香帆さんの連載「母と娘の物語」がついに書籍化します。 萩尾望都、山岸凉子、氷室冴子、吉本ばなな、よしながふみ、川上未映子、宇佐見りん……。
多数のフィクション作品から「母娘問題」に向き合ってきた本連載が、ほぼ全編にわたる加筆・修正のうえ単行本となりました。
ご予約はこちら→
端的に言うとね。
2010年代の夢見た楽園
〈母〉探しの旅路。それこそが少女漫画が描いてきた一つの軌跡なのだったことを分析してきた。24年組と呼ばれる作家が残した課題は「〈母〉に捨てられた少女を肯定し理解してくれる完璧な〈母〉はどこにいるのか?」という問いだった。だが00年代、よしながふみと芦原妃名子は〈母〉を断念する。自分を理解し支えてくれる存在などどこにもいない、〈母〉のいない孤独を抱えたまま成熟するモデルを少女たちに提示する。
社会学者の中森弘樹が『「死にたい」とつぶやく 座間9人殺害事件と親密圏の社会学』(慶応義塾大学出版会、2022年)においてまさに〈「死にたい」をシェアする暮らしを考える〉という検証を行っているが、これは2000年代に提示されたよしながふみ的世界観を延長させたものだろう。中森は「死にたい」と呟く人間に対し、一時的にでも親密圏=家族や恋人といった固定的な関係性から逃げる場所があることの有用性を解説し、逃げ場のひとつの可能性として、流動性のあるシェアハウスの提供を検討する。その流動性を担保した場の提供というテーマは、存外〈よしながふみ的関係〉に近しいものを見る。
そしてそれは『愛すべき娘たち』刊行時から10年以上経った、2010年代の現代において理想とされる関係のひとつになった。
たとえば2016年にテレビドラマ化され話題となった『逃げるは恥だが役に立つ』(海野つなみ、講談社)は合理的な「契約結婚」を提言した物語だが、このヒットもあくまで主人公のみくりと平匡が流動性を残した関係性を構築したところが一つの理由ではないだろうか。あるいは同じくテレビドラマ化された『かしましめし』(おかざき真里、祥伝社)は2016年から始まった物語だが、それぞれ傷を抱えた男女三人がシェアハウスすることによって傷を癒してゆくのだが、そのシェアハウスはいつか終わる前提の存在として語られる。つまり「流動性を担保した関係」は2010年代において、傷ついた人々が集まる逃走先として機能する。前章で見た2000年代の少女漫画が共同体を恋愛や自己実現の場として描いていたのに対し、2010年代は傷ついた人々の逃避先として共同体を描いているのである。
また拙著『女の子の謎を解く』(笠間書院)では、2010年代後半に流行した乃木坂46という大人数女性アイドルグループの歌詞を読むと、「市場に傷ついた人々の逃走先」として少女たちのグループが表象されていることを論じた。秋元康プロデュースの大人数女性アイドルグループはまさに、少女たちの「卒業」を前提とした、流動性を常に抱えた関係性の象徴である。
2010年代の少女漫画は、永遠の〈母〉は存在しない代わりに、流動性のある共同体を用意した。すべてを肯定せずとも、ゆるやかに、逃げ得る関係性のなかで、傷ついた人々は癒されていく。それこそが2010年代の提供した代理母――つまり疑似家族という名の楽園だったのだ。
『違国日記』と『後ハッピー・マニア』と『くるまの娘』―流動性の残る「不安」な関係
だが2020年代になると、〈よしながふみ的関係〉つまり「流動性のある関係性」に不安を抱える物語が増える。
たとえば2023年現在も連載中の『違国日記』(ヤマシタトモコ、祥伝社、2017年~)がある。この作品は、少女漫画に受け継がれてきた〈母〉探しというテーマを引き継ぐ。母と父を突然事故で亡くした朝は、叔母の槙生に引き取られる。次第に両親の死を受け入れる朝は、「さびしい」という感情をあまり持たない叔母と暮らすことによって、自らの「さびしい」という感情がどこから来るのか見つめる。そして朝は、亡くなった母の日記を読み、母、そして父のことを知ろうとするのだった。
父がコミュニケーションを取ろうとせず、母が常に規範となって物事を判断する家庭に朝は育った。結果として朝は、母に何でも決めてもらうような習性があったことを、両親の事故後初めて気づく。しかし叔母の槇生は、朝の自主性を重んじ、選択肢を提示はすれども判断は任せるという。朝は槇生が理想の〈母〉になってくれないことに苛立ちながら、いつしか彼女の個性を受け入れてゆく。槇生は、朝の〈母〉の代理になっていく。
だが一方で、朝は高校卒業が近づくとともに「いつまで槇生は自分の母でいてくれるのか」という不安を抱えるようになる。
「なんかぁ 大人になっても槇生ちゃんとこにいられる理由ってあんのかな」
(『違国日記』10巻)
そう、不安なのである。
疑似家族の課題はここにある。流動性とは、自由でありながら、不安なのだ。私たちは約束しないと不安になる。家族とは永遠の夢を曲がりなりにも見せてくれるものであったが、疑似家族とはいつ終わるかもわからない関係性であり、それは常に孤独と紙一重な関係である。
あるいはもはや家族であっても永遠の夢は見られないことがよく分かる作品に『後ハッピーマニア』(安野モヨコ、祥伝社、2020年~)がある。2020年に単行本1巻が刊行された本作は、1990年代を代表する少女漫画『ハッピー・マニア』(安野モヨコ、祥伝社、1995~2001年)の続編である。
物語は『ハッピー・マニア』で永遠の愛を誓った夫・タカハシが、45歳になった妻・カヨコに「別れてほしい」と告げるところから始まる。カヨコは動揺し、そして独身になることに不安を抱える。これは現代の結婚が永遠の夢を見るものではなくなっており、流動性のある関係である不安を描いた作品である。それが90年代の少女漫画の金字塔である作品の続編なのだ。
『ハッピー・マニア』のカヨコは、とにかく幸せになりたいがために、様々な男と恋をする。そして自分に恋するタカハシはとくに魅力に思えない。だが結婚という関係性を手に入れるため、最終的にカヨコはタカハシとの結婚を決める。ふたりは90年代には永遠の愛を誓ったのである。むしろ、嫌々ながら。だがその夫婦は、2020年代には別れ得る不安な関係に変化している。
考えてみれば、「流動性がある」ことこそが〈よしながふみ的関係〉及び2000~2010年代の夢だったはずなのだ。日本特有の閉塞感、つまり固定されたムラ社会の閉じた〈母〉との関係性を打破する夢だった。しかし『後ハッピーマニア』になると、「流動性がある」ことこそに不安を抱えるようになる。なぜなら「流動性がある」ということは、常に市場にさらされるということであり、常に評価される不安を抱える世界だからである。
〈よしながふみ的関係〉。それは自ら傷を引き受けた者同士の、流動性を残した、ゆるやかな繋がりであったはずだった。たしかに私たちは『きのう何食べた?』を読んでも、『逃げるは恥だが役に立つ』を読んでも、『かしましめし』を読んでも、そのゆるやかさに、完璧に自分を肯定してくれる〈母〉はいなくとも、私たちは流動的な共同体に癒された。
だが一方で、このような「お互いの傷を理解し、適切な距離感を取り合い、ゆるやかに繋がっておく」ことは極めて都会的・インテリ的な、登場人物全員に成熟を促すモデルでもある。そして常にどれだけ成熟しているかを評価し、評価に見合わなければ断絶することのできる関係性である。
はたして、そのような成熟は、私たちに可能なのだろうか?
つまり流動的な市場評価に耐えられるほど、私たちは孤独に成熟できるのだろうか?
流動性とは、〈娘〉として絶対的な肯定を求めて〈母〉を探してきた旅路を、途端に、ある種の人間的成長を求められる〈息子〉の物語に変更させられる条件なのではないだろうか?
実際、成熟という点で考えてみると、『愛すべき娘たち』の麻里が50歳を過ぎてはじめて健との関係構築が可能になったことは示唆的である。つまりそのような成熟した関係を作り上げるために、麻里はその年齢になるまで待たなくてはいけなかったのだ。むしろ50歳を過ぎてはじめて、他人の傷に対して、適切な距離感を取れるようになる、と考えた方が正確なのかもしれない。『きのう何食べた?』のシロさんもまた年齢を重ねてからケンジと出会った点を強調している。
なによりも〈よしながふみ的関係〉に、田舎は出てこない。〈よしながふみ的関係〉が目指す地点つまり流動性は、人間関係が固定化された「逃げ」を許さないムラ社会には存在し得ないものだからである。『きのう何食べた?』も『逃げるは恥だが役に立つ』も『かしましめし』も、すべて都会が舞台の物語なのだ。
だとすれば、〈母〉を探す少女たちは、〈よしながふみ的関係〉を目指さなければならないとすれば、大人になるべく成熟し、そして都会に出なくてはならないのである。自らの傷を一人で受け止め、他人の傷を理解し、適切な距離を保つという、きわめて成熟した関係を、少女たちは引き受けられるだろうか? つまりこれは、必要以上に市場へ晒す圧力を仕掛けるモデルではないだろうか。
それはまさに、2020年代に刊行された宇佐見りんの小説『くるまの娘』のかんこが嫌悪する「大人」像そのものである。
もつれ合いながら脱しようともがくさまを『依存』の一語で切り捨ててしまえる大人たちが、数多この世をこそ、かんこは捨てたかった。
(宇佐見りん『くるまの娘』河出書房新社、2022年)
ここにあるのは、個人の過度な自立を信仰し、流動性のない関係を切り捨てようとすることへの警戒そのものである。『後ハッピーマニア』で離婚したカヨコが不安になっていることと同じ不安なのである。
傷を引き受けた者同士が、家族の内側に留まって依存することなく繋がる、シェアハウス的な〈よしながふみ的関係〉。これは〈母〉探しをおこなってきた少女漫画が、「完璧な母なんていなくても、ゆるやかな共同体を作ることができれば、それが楽園になる」と唱え、2000年代から2010年代に辿り着いた地点のひとつであった。
だが一方で、流動性がそこに残っているのは、やはり不安でもあるのだった。〈よしながふみ的関係〉はたしかに正しい。正しいのだが、あまりに成熟を促しすぎる。都会のインテリにしか不可能な関係なのだ。
流動性のない関係性を依存と切り捨てるにしては、私たちは家族という名の固定した関係性を捨てられない。捨てられないのだと、小説も少女漫画もどうやら叫んでいる。
だとすれば、どこに答えはあるのだろう。
『凪のお暇』と〈母〉探しの旅路
『凪のお暇』(コナリミサト、秋田書店)は2016年から連載開始し、2023年現在も連載が続く少女漫画である。連載開始当初、『凪のお暇』が描く地点は、2010年代的な〈よしながふみ的関係〉の延長にあるものだった。
OLの仕事をする凪は、田舎に住む母の押し付ける規範意識に縛られながら生きていた。
でもそんなこと言って結局私は この人の望むルートをなぞろうとしてきた気がする 北国駅発東京駅行 「ちゃんと」経由 仕事駅通過安定駅通過 終着点は「ちゃんと」した人と「ちゃんと」結婚駅 これなら文句は言わせないって
(『凪のお暇』2巻)
凪は、母の望む言葉、望む進路を、なぞろうとしてしまう。そうでなくては、母は許してくれないからだ、と凪は言う。
「だってお母さん 大丈夫な私のことしか許してくれないじゃない」
「何それ あなたがこんな汚い部屋で一人でみじめなのは お母さんのせいってこと?
進路も住まいも仕送りも あなたが勝手に選んで決めてやってたことでしょう
お母さんは自由にやっていいよって言ってるじゃない いつも」
(あーもう矛盾 さっきあんなに人の頭のこと罵っといて いつもそうだこの人は 自分の望む方に人を誘導しといて しらばっくれて)
(『凪のお暇』7巻)
ここにあるのは、母の許す範囲内で動こうとする娘の姿である。しかし凪は会社を退職し、彼氏と別れたことを契機に、近所の人々と交流を深める。〈母〉を不在とした、近所付き合いをベースにしたゆるやかで流動的な繋がり。会社や家族といった閉鎖的なムラ共同体から逃げるための凪の「お暇」には、近所づきあいによる疑似家族こそが、逃げ場としての「楽園」として描かれていた。まさに〈よしながふみ的関係〉としての理想的な逃走先であろう。
そして凪は、その「楽園」で出会った人々に母の不完全さを指摘される。たとえば慎二に「親もしょせん人間なんだって認めること」が厄介な親と付き合うコツであると教えられたり、あるいはバイト先の店主から「あんたのお母さん超人?」と言われ「あんたの頭の中にいる仮想的だから無敵に感じられてしまうのだ」と指摘されたりする。そしてそれによって凪は、自分がむしろ母の姿を大きくしすぎてしまったことに気づく。つまり凪は「楽園」のおかげで、『愛すべき娘たち』『イグアナの娘』で見られたような「自分の不完全さを作った母の不完全さを知る」という発見を可能にする。
だが物語は、7巻を契機に転回する。東京で出会った疑似家族との労りの物語から、舞台を北海道に移し、故郷の実家の問題を描き始めるのだ。凪は、母の怪我を契機に、地元の北海道へ戻ることになる。
凪の母はシングルマザーである。凪の父・武とは東京で出会ったのだが、妊娠を知った武は失踪する。そして凪の母は北海道に戻ることになる。北海道へ帰った凪は、母の生き辛さが自らの生き辛さと酷似していることを理解する。
「でも お母さんとおばあちゃんのまっくろな目を見たとき あ これもうだめだって思ったの 目の奥覗き込んだら お母さんのお母さんのお母さんのお母さんが見えたの それがずっと層になってるの たぶん私の目も」
「だからそういうの一回断ち切れたら 何か変わるんじゃないかって思ったの」
「今いる世界だけが全部じゃないって 解放感とかそういうので」
(『凪のお暇』)
ある日、凪はゴンという青年に「結婚してくれ」というプロポーズされ、動揺する。ゴンのプロポーズは「君のすべてを受け入れるよ」というものだったからだ。それは本書が提示してきた、母の代理になり得る、完璧な〈母〉から、結婚の申し出そのものだった。ちなみに作者のコナリも〈娘〉の物語の文脈を分かって描いているのだろう、コナリは凪に「棚に並んだあまたのマンガ達の憧れの主人公シチュエーション「ありのままで過ごしてたらなんかキラッとしたおのを見出されて見染められる枠」に入れたことが嬉しくて はしゃいでテンパりました」(『凪のお暇』9巻)という台詞を与えているのである。
だが完璧な〈母〉であるゴンの申し出を凪は断る。なぜなら私の母の問題が残っているからだ、と凪は告げる。
「でもごめんなさい 私が今恋してるのはお母さんなんです」
「初恋なんです 呪いに近いやつ」
「この恋をおわらせてからじゃないと 私 誰とも向き合えない」
(『凪のお暇』9巻)
〈娘〉としての少女漫画は、代理〈母〉を探すのではなく、「実の母からの呪い」を清算しなければ前に進めないのだ――と『凪のお暇』は宣言する。
そう、凪は〈娘〉として、母の呪いを解く方法を見つける決意を固める。
それは芦原妃名子らの残した課題、つまり母からの呪いを解く方法を探す、という主題の継承であった。
父の逃走、母の〈母〉となる娘
凪の母・夕は、東京で過ごすことになる。そして東京で夕が見つけたのは「自分は夫にぶつけるべき感情を、凪にぶつけて搾取していた」という事実であった。
欧米諸国と東アジア圏の母性の在り方を研究した社会学者の瀬地山角は『東アジアの家父長制 ジェンダーの比較社会学東アジアの家父長制』(勁草書房、1996年)の中で、欧米と比較して日本は家事役割のなかでも、「母性愛」が女性に求められる役割として強いことを指摘する。その理由は「近代家族を支える軸としての夫婦愛の弱さ」「子供が父系血縁のなかに一人飛び込んだ孤独な存在たる嫁を唯一守ってくれる存在であること」(p150)であった。つまり日本の場合は近代家族の形成過程で、夫婦愛が希薄であったがために子供にのみ特化して情緒化が進み、ある意味特殊な「母役割を重視する家父長制」が形成されたのだと説明されている。
つまり『凪のお暇』はこの研究結果と同じ地点を指摘する。母子が密着し、母が子に必要以上の枷を掛けてしまうのは、夫との関係の不在が理由にある、ということである。凪の父・武は、夕の〈夫〉であることから逃走したのである。
流動性はたしかに重要である。酷い配偶者からは逃げたほうがいいし、お互いいなくなるかもしれないという緊張感をもって接したほうが、私たちは成熟した自立した関係を作りだすことができるだろう。だがそのような流動性は、結果的に凪の父のような〈夫〉の逃走を許してしまう。そして逃走した〈父〉の代わりに、娘は母の〈母〉になろうとしてしまう。母が本来夫に求める役割を、娘に求めてしまうのだ。そう、『凪のお暇』とは、娘が母の〈母〉になろうとしてしまう呪縛を描いた物語だったのである。
〈娘〉の物語を生きる夕は、フネ(夕の母、凪の祖母)に傷つけられ、その傷を理解してくれる代理〈母〉を、東京に住む若き武に求め、そして結婚しようとする。だが武は〈夫〉の役割から逃走した。そして夕の〈母〉は不在となる。そうして生まれた娘・凪は、夕に向かって「大丈夫?」と心配そうに尋ねる。それはまさに夕の求めていた〈母〉であった。そして夕は凪に〈母〉を求めるのである。
「それは母が許さない」と呟く娘・凪は、夫の代わりに、母の〈母〉になった娘の姿だったのである。
繰り返し説明しよう。本来、夕は〈母〉をパートナーの武に求めていた。だが凪に〈母〉を求めることになってしまった。凪は夕への感情を「初恋に近い」「呪い」だと表現したが、それはある意味、〈母〉を求められた娘の必然だったのだろう。
つまり、母娘の呪いの根幹は――夫の逃走にあったのだと『凪のお暇』は告げる。
思えば、〈娘〉の物語の多くにおいて、母がシングルマザーであったことは、夫が逃避していたことの証なのである。『白雪姫』も『シンデレラ』も『インストール』も『乳と卵』も『残酷な神は支配する』も『日出処の天子』も『愛すべき娘たち』も、一度はシングルマザーになった、あるいは夫の出てこない母親を描いているのである。それはまさに〈娘〉の物語が夫の逃走によって生まれたことを指している。
少女漫画は、娘たちに〈母〉の代わりを提示し続け、そして断念し続けてきた。しかしその裏側にあるのは、家庭内の〈夫婦〉関係の不在なのだった。母という女は、夫の妻であり、子の母である。だが後者のアイデンティティが強くなる限り、母は子への重圧が強くなる。夫が〈母〉の役割から逃走する。だから母は子に〈母〉を求めてしまう。とくに同性の、娘に。
東京で「逃げる」武の姿は、北海道から「逃げられない」夕と凪の関係とは対比的である。ここには明確なジェンダー差がある。母性信仰――女性に自己犠牲的なケアを求める日本の構造は、夫を家庭から逃走することを許し、そして母になることを美化して語る。だから娘たちは母から傷つけられ、そして娘たちは母になる。それは娘たち自身も母性信仰の内部にいるからである。
少女漫画が提示してきた完璧な〈母〉。それは相手を肯定し、傷を理解し、そして支える存在であった。だが弱き母たちは、娘にそのような〈母〉を求める。だがそれは本来、夫の役割なのだ。凪は夕の傷を理解し、支えようとする、つまり〈母〉たろうとする。だがそれは〈母〉の役割ではなく、夫の役割なのである。
夫婦のディスコミュニケーションを解消し、そして、母親という役割の自己犠牲的な美談を削除すること。それこそが母と娘の呪いを解く方法なのだと、『凪のお暇』、そして少女漫画の長い長い〈母〉探しの旅路は、少女たちに告げるのだった。
(続く)