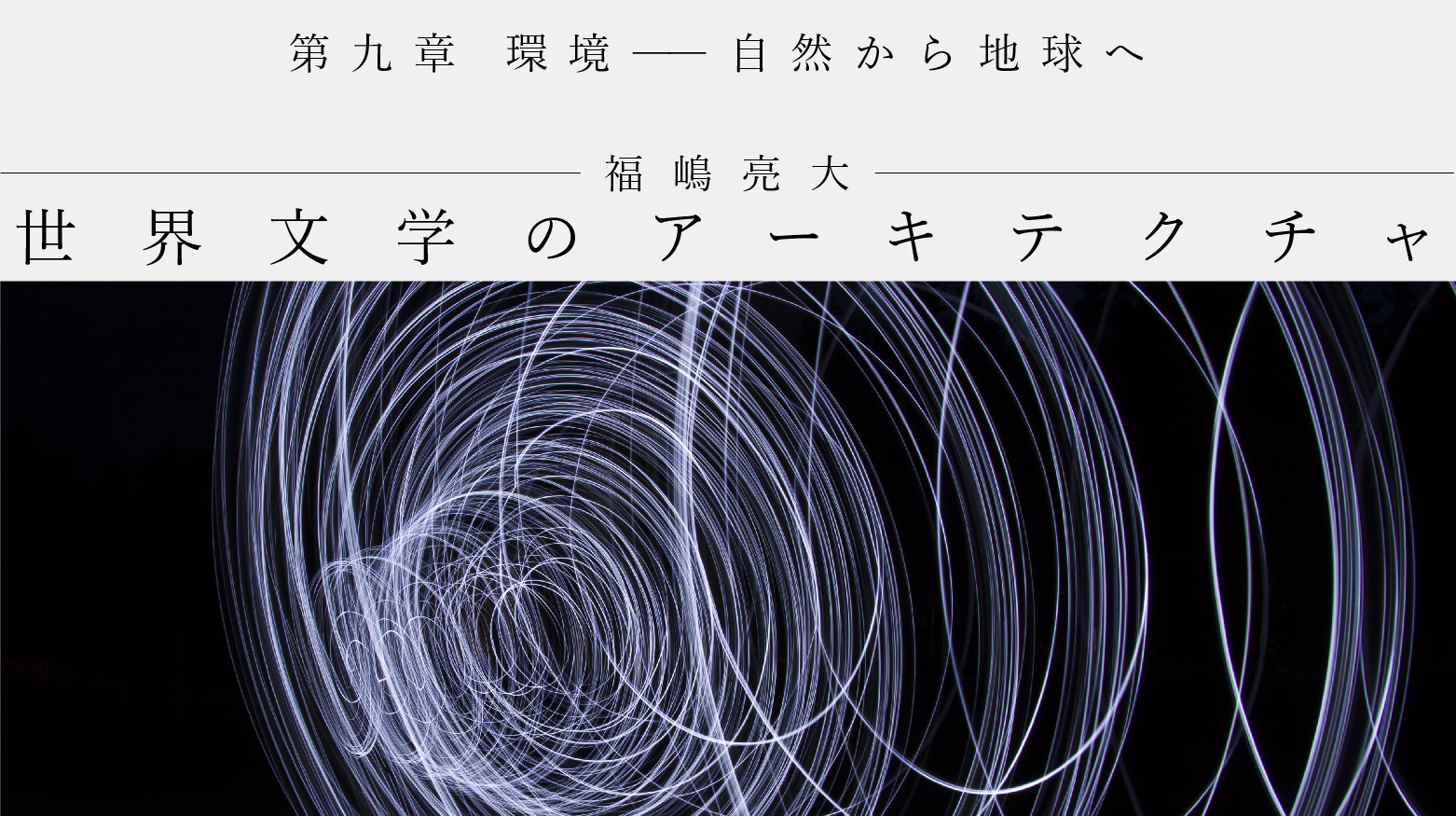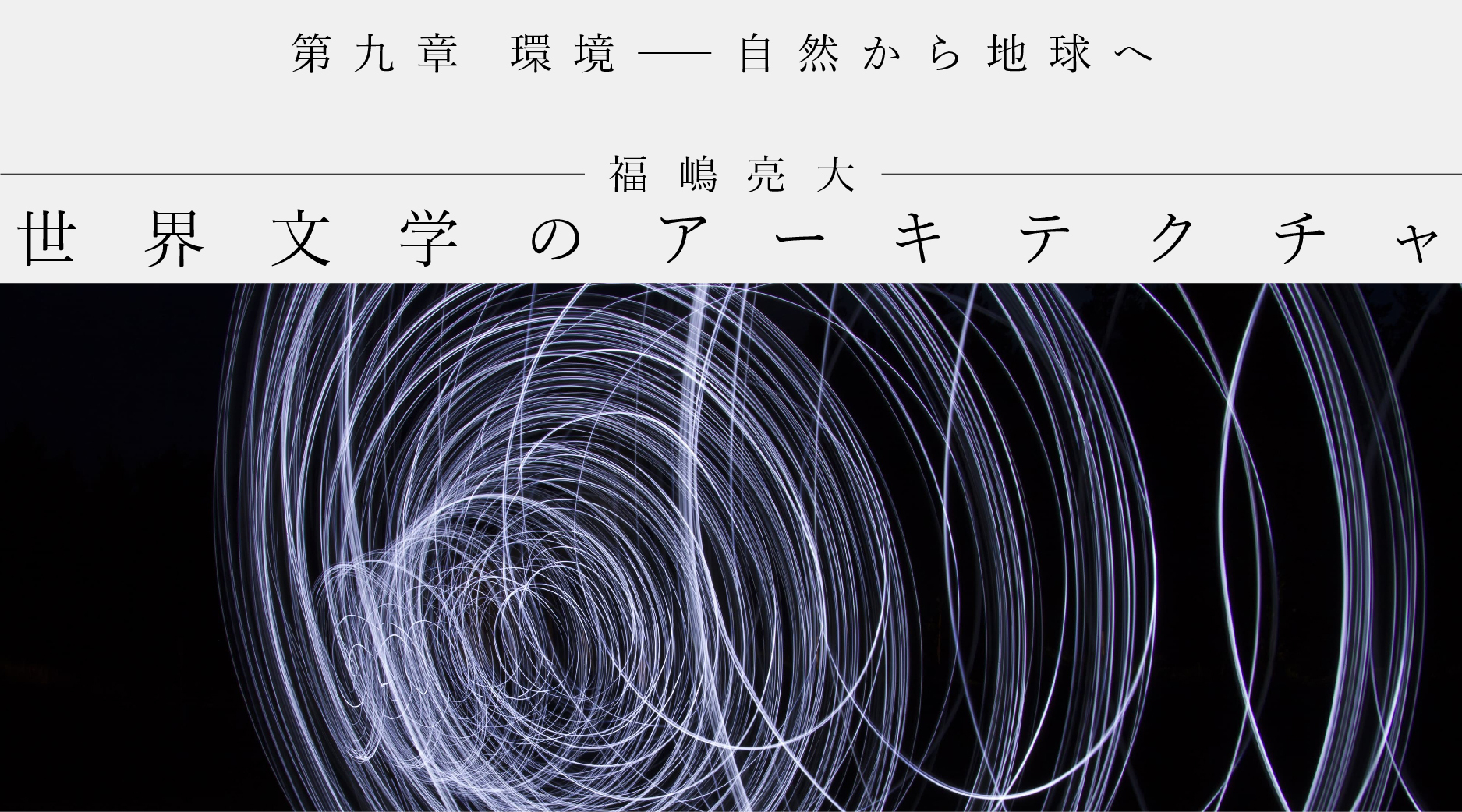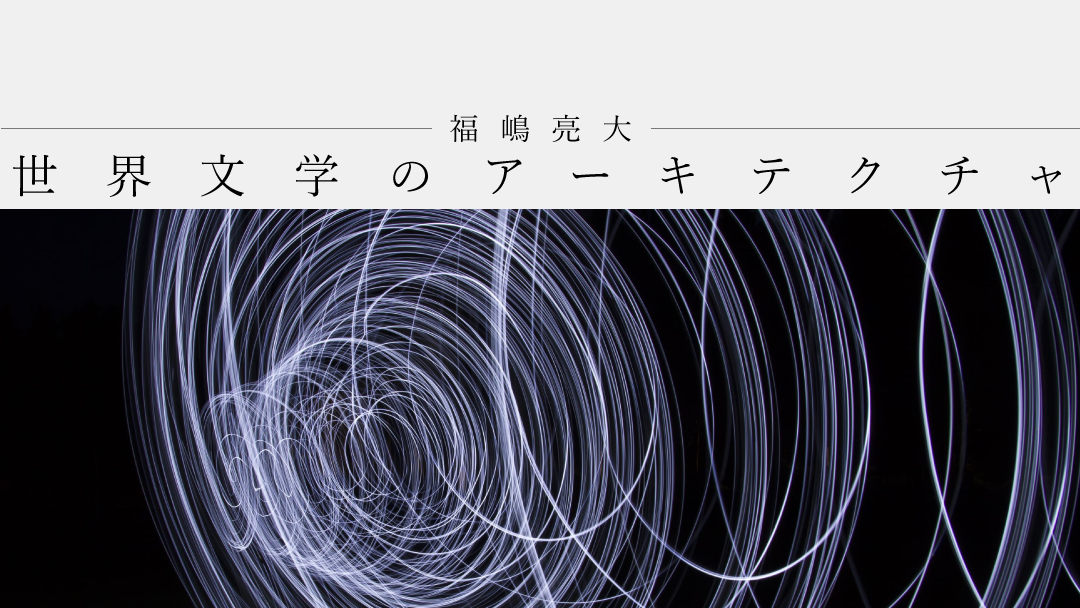
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、物質ともつれあった心の生成
近代文学が生成したのは、環境に心を創作させる技術である。物質的な環境(自然)の記述が、心的なものの表現として利用される――この心と自然の共鳴現象が、近代文学を特徴づけている。例えば、小説における風景描写はたんなる記録という以上に、語り手の心の動きと相関関係にある。つまり、ある特定の風景の選択は、心のステータスを間接的に説明しているのである。
もとより、心的なものと物質的なものは、さしあたり別個のシステムである。しかし、近代文学はこの二つのシステムを交差させ、物質(自然)を心のあり方の隠喩として使用する道を開いた。そのパイオニアの一人であるアメリカの詩人エマソンは、有名な論文「自然」(一八三六年)で「そもそも人間はアナロジストであり、あらゆる物象のなかに関係を探る」「自然全体が人間精神の隠喩だ」と記したが、これはまさに心と自然のあいだの相関関係を強調したものである。エマソンによれば、この両者は「鏡」のように顔を向きあわせており[1]、ゆえに自然を深く精密に理解することが、そのまま心の正確な表現となる。
エマソンをはじめ欧米のロマン主義者は、この「鏡」のアナロジーを推し進めた。それが意味するのは、物質ともつれあった新しいタイプの心が、文学にプログラミングされたということである。このような現象が生じたのは、近代における文化的・学問的関心の中心が、神学から人間学に移ったことと無関連ではない。
もとより、神とは隠喩的に語られるしかない存在である。ドイツの神学者エーバーハルト・ユンゲルの言い方を借りれば「神自体はただ隠喩的にのみ表現しうる。言いかえれば、そもそも隠喩的に語られる時にのみ、神について語りうるのである」。神は「この世の言語」では記述できない何ものかであり[2]、ゆえに神をこれこれと言語的に定義するのは、すべてメタファーとなる。
かたや、近代文学は神を記述する代わりに、もっぱら人間を説明することに舵を切ったジャンルである。小説において、神についての語りは、心についての語りに凌駕されたが、この新たな関心事となった「心」もまた、隠喩なしには語れない不可解な何ものかであった。神的なものは変形されて、小説の心=中心(heart)に残り続けた。ポスト神学時代の表現と呼ぶべき近代文学は、心を表現するのに、物質的な環境を隠喩として導入するという新たな技法を編み出したが、それはエマソンの汎神論的世界像に見られるように、心=自然が神のオルタナティヴになったことも意味していた。
ゆえに、近代文学における心は唯物論と宗教の交差点に位置している。心は感覚的・物質的なものでありながら、ときに神に似たものとして――ジョルジュ・バタイユの言う意味でのコミュニケーション(霊的交通)の場として[3]――記述される。前章で述べたように、ジョン・ロックやディドロは心を感覚的反応の集合体として捉え、それが文学上のリアリズムやモダニズムの源流となった。逆に、ルソーやドストエフスキーにおいては、心はこのような唯物論に還元されない神的あるいは霊的なものと結びつく。ただ、その場合でも、心はいきなり神に跳躍するのではなく、あくまで特定の環境(ルソーのスイス、ドストエフスキーのロシア)ともつれあいながら、神的な境地に到るのである。
では、近代の著述家たちは、環境と心をいかに「もつれ」させたのか。さらに、自然との接触の仕方を反映した文学的言語、すなわち「エコ言語」(ecolect)はいかなる変化を遂げてきたのか[4]。これらの問いについて、以下《一八世紀的自然から一九世紀的地球へ》という大きな見取り図をもとに論述を進めていこう。
2、自然環境のアドリブ演奏――ルソーの『孤独な散歩者の夢想』
このテーマを考えるのに、まず参照されるべきは一八世紀のルソーである。というのも、ルソーこそが物質的なものと心的なものの「もつれ」を仕掛けた先駆者であったからである。その手法は、晩年の美しい散文作品『孤独な散歩者の夢想』(一七七六年執筆開始/以下の引用は永田千奈訳[光文社古典新訳文庫]に拠る)において高度な水準に達した。
ルソーはそこで、かつて『告白』を書いたときからの心境の変化を語っている。市民社会から自分自身を追放した老人のルソーにとって「今さら、告白するような自慢も自責もありはしない。私はもはや人間のうちに数えられていないのだ」。自らを「どこかよその惑星から落ちてきた異星人」と同様に見なす彼は、自然科学者が「日々の気象状況」を調べるように、自らの心にメーターを取り付け、その微細な推移をそのつど「計測」しようと試みる(第一の散歩)。この心の気象学的観察を通じて、散歩中のとりとめのない不定形の夢想が、いわば生まれたばかりのようなフレッシュな姿で立ち上がってくるのだ。
自然との偶発的な接触によって、散歩するルソーの心はたえず変化し続ける。『告白』が唯一無二のオリジナルな人生のあり方を論証しようと意気込むのに対して、『夢想』では自己の明瞭な輪郭が崩れ、不定形の心的世界が広がってゆく。ルソーはそのありさまを自然の流動性と結びつけた。彼がスイスのビエンヌ湖に浮かぶサン・ピエール島に住んだときの回想場面には、次のような有名な記述がある。
寄せては返す波の音。いつまでも続き、ときに大きく聞こえてくる波の音。夢想が心のざわめきを消し、空っぽになった内面を満たすように、水の音と眺めが私の耳と目に休みなく流れ込んでくる。そうしていると、わざわざ頭を使って考えなくても、ただこうしているだけで存在することの喜びを感じることができるのだ。
この世のすべては絶えざる流れのなかにある。同じ形のまま、不動のままでいられるものはない。自分以外の事物に執着する私たちの心も、それらの事物と同じように移り変わっていかざるを得ない。(第五の散歩)
夕暮れの波打ち際にたたずむルソーは、六〇年後のエマソンを先取りするように、自然と心を鏡のように向きあわせた。『夢想』のテクストはちょうどジャズの即興演奏のように、移ろいやすい自然を楽器として、それに反応する心を随時アドリブで浮かび上がらせる。ルソーの内面は衰えて、とりとめのない夢想に沈み込むが、その虚無の心の空洞には、寄せては返す「波」のリズムが響き続けていた。
もとより、自然と心がたえず移り変わる以上、波打ち際のルソーの感じる充足や喜びはエフェメラルなもの、つまり「はかない幸福」でしかない。しかし、ルソー的な心=自然は、その最も純粋な形態においては有限の時間を超えて、永遠の領域を垣間見せる。サン・ピエール島の幸福な時間を想起しながら、ルソーはその永遠性を神的な状態になぞらえた。「この幸せな境地が続く限り、自分が自分であることだけで神のように満足できるのだ」。寄せては返す波のようなテクスト上のアドリブ演奏によって、心的なものを神的な境地にオーバーラップさせること――この繊細な操作が『夢想』に前例のない音楽的な性格を与えたのである。
自然を鏡として、自己の心をたえずフレッシュに生まれ変わらせるルソーのパフォーマンスにおいて、他の人間は邪魔なノイズにすぎなかった。サン・ピエール島はちょうどロビンソン・クルーソーの島と同じく、一種の無人島として描かれる。いささか驚くべきなのは、ルソーがそこで「バスティーユの監獄」に言及したことである。サン・ピエール島は無人の牢獄なのであり、しかも老いた音楽家ルソーはそこに甘美な孤独を見出していた。「私は、この孤島を永遠の監獄とし、人々が私を一生ここに閉じ込めておいてくれればと願った」。
この人間が事実上消滅した世界では、物言わぬ植物だけが隣人となる。野趣に溢れた人影のない孤島にすっかり魅了されたルソーは、「サン・ピエール島植物誌」を作ろうと思い立ち、カール・フォン・リンネの植物図鑑『自然の体系』とルーペを携帯して、植物観察にいそしんだ。孤島のルソーにとっては、自然の精緻なシステムを自らの目と手で一つ一つ丁寧に理解し直すことが、至上の喜びとなった。彼の「夢想」とは劇的な新発見ではなく、あくまで過去を再認する心的作業である。しかも、ルソーにとっては、現前する自然よりも再認された自然にこそリアリティがあった。
現在、夢想が深みに向かえば向かうほど、私はあの島の光景をありありと思い浮かべることができる。実際にあの島にいたときよりも、パリにいる今のほうが、あの島を五感でとらえ、さらに心地よく感じているのだ。
ここには島そのものではなく島の記憶、つまり島のVR(ヴァーチャル・リアリティ)のほうが、いっそう感覚的に豊かであるという逆説が記される。夢想という心的なノイズ・キャンセラーが作動するとき、邪魔な他者は消え去り、波と植物の与える音楽的な快楽が際立つ。自然と心のルソー的な「もつれ」は、無人のVR空間において純粋に表現された。そこにルソーの「エコ言語」の特異さがある。
3、ユートピアのなかのユートピア――『新エロイーズ』における庭
興味深いことに、この甘美でヴァーチャルな無人島=牢獄のイメージは、すでに『夢想』以前のルソーの著作、特に『新エロイーズ』で重要な役割を果たしていた。一二世紀フランスのエロイーズとアベラールによる名高い往復書簡文学を下敷きとしながら、ルソーはジュリとサン゠プルーの恋愛を書簡体小説の形態で描いた。音楽の隠喩を使えば、『新エロイーズ』は伝統あるスタンダード・ナンバーをルソー流の新技術で演奏し、大胆に生まれ変わらせた文学だと言えるだろう。
この演奏のユニークさは、恋愛を主軸としながら、ルソーならではの風景論やユートピア論があわせて展開されたことにある。サン゠プルーは故郷のヴァレ地方を旅し、その山岳の民の暮らしをジュリに手紙で書き送った。巨大な岩、高い滝、そして底の見えない深淵――このような崇高な風景をルソーは旅人の視点から描き出し、読者を驚かせた。このいわば山の発明によって、『新エロイーズ』は大衆を登山に目覚めさせる導火線になった。
それだけではない。ジュリの結婚でショックを受けたサン゠プルーは、世界周遊の旅に出て、新大陸におけるヨーロッパ人の植民地政策の失敗を確認した後、スイスに帰還する。折しもジュリの夫となったロシア貴族出身のヴォルマール――その無神論と理性への信奉は、どこかドストエフスキーの登場人物にも通じる異常性を感じさせる[5]――は、妻とともに、レマン湖のほとりにあるクラランに理想の共同体を創設していた。ヴォルマールはサン゠プルーとジュリの過去の関係を知っていた。そのうえで、彼はサン゠プルーの過去の記憶を現在の状況によって上書きするために、わざわざこの恋敵を招待し、自作の共同体のありさまを見せるのである。
ヴォルマール夫妻の築いたクラランの小さな農園共同体では、その成員たちがお互いを尊重し、親密で平等な関係を築いていた。そこでは労働の成果は他者に収奪されることなく、共同体の内部だけで享受されるので、外界から干渉を受けることがない。経済的に完全に充足した、自己完結的なユートピア[6]――このヴィジョンは秋の葡萄の収穫祭において、最も鮮烈な次元にまで高められる。音楽家ルソーの面目躍如と言うべきこの箇所では、樽の物音、収穫する民衆の歌声、素朴な楽器のしわがれた声が「音響的」な世界を出現させていた[7]。誰もが分け隔てなく楽しむこの祝祭の光景は、都市の社交空間の虚飾を批判し続けたルソー自身のユートピア思想を具現化したものである。
もっとも、誰もが気づくように、クラランは立法者ヴォルマールに完全に制御された世界であり、そこでは自由な振る舞いはあり得ない。共同体の成員は強制されているという意識なしに、ヴォルマールの定めたルールに服従している。秋の収穫祭は一見すると完璧なシステムだが、それは理性の専制政治とコインの裏表の関係にある。ヴォルマール=ルソーの理論上のユートピアは、その完璧さゆえに逸脱が許されない《歴史の終わり》の空間を思わせる。ルソー自身、その「退屈さ」を承知していた[8]。
だからこそ、クララン共同体の内部にもう一つのユートピア、つまりジュリの作品と呼ぶべき≪エリゼの庭≫が含まれることは見逃せない。この庭は思わせぶりに鍵がかけられた、秘密めいた場所である。ジュリはサン゠プルーと初めてキスをかわした運命の木立の代替として、その庭――作中では「果樹園」と呼ばれる――で多種多様な植物を育てていた。つまり、過去の愛の記憶は、自然の豊かさを人為的に構築された庭に置き換えられたのだ。花々が咲き誇り、清らかな水が流れ、鳥の歌声が響くこの清涼な庭は、サン゠プルーを奇妙な考えに導く。「わたしは自然界の中で最も未開の、最も寂しい場所を見る思いがし、わたしこそこの荒涼たる所にかつて足を踏み入れた最初の人間であると思われました」[9]。
世界周遊からの帰還者サン゠プルーは、この高度な人工自然としての果樹園に、ポリネシアの「未開」の島のイメージを重ねた。この庭=島は自然の美しさや多様性を最も高度に実現したことによって、かえって無人の荒涼とした「無人島」として現れる。サン゠プルーはこのジュリを作者とする美しくも寂しい庭に、否応なく引き寄せられる。
今朝わたしは早く起きて、子供のようにいそいそとあの無人島に引き籠りに行きました。〔…〕これからわたしを取巻くあらゆるものは、あれほどわたしに愛しかった人の造られたものです。これからわたしは自分のまわり至る所にその人を眺めるのです。眼にふれるものでその人の手が触れなかったものは一つもないのです。その人の足が踏みしだいた花々に口づけするのです。その人の呼吸した空気を朝露と共に呼吸するのです。[10]
サン゠プルーはジュリの痕跡に満ちあふれた無人の庭を歩きながら、その一つ一つの身体的な細部に同化しようとする。この変態的なフェティシズムによって、エリゼの庭はまさに「エロスの庭」の様相を呈するだろう[11]。このときサン゠プルーは生身のジュリではなく、ジュリの残した過去のログ、つまりVRとしてのジュリの探索に熱中していた。それが可能なのは、庭の無数の植物がノイズ・キャンセラーとなり、愛するジュリの痕跡を美しい環境と齟齬なく合致させるからである。ここには明らかに、『夢想』のサン・ピエール島と同じ仕掛けがある。
クラランとエリゼの庭は、ヴォルマール夫妻という同一のデザイナーによって構築されている。にもかかわらず、後者が前者に吸収されることはない。鍵のかかったエリゼの庭はまさにユートピアのなかのユートピア、ヴォルマールの理性的・父権的なユートピアに穿たれた母性的なユートピアである。この秘密めいた庭では、心的なものと物質的なもの、つまりジュリの心と多種多様な植物とが融合している。共同体のメンバーが全員参加するクラランの平等主義的な祝祭空間には、このような心的装置が欠けていた。
ここから示唆されるのは、『新エロイーズ』のユートピア思想が二重底になっていることである。政治的なユートピアをめざす理性の革命は、そこから零れ落ちる「心」を収容する環境のデザインによって補われなければならない。優れたルソー論を書いた批評家ジャン・スタロバンスキーが、クラランとエリゼの庭の関係について「止揚(社会そのもの)は、いったんそれが止揚したものを保持している」と簡潔に評したように[12]、クララン(社会)では消化吸収(止揚)しきれないものがVRとしての《庭》に濃縮されたのだ。
4、模型と歩行――ワーズワース的景観
このように、ルソーはサン゠プルーにマクロな世界とミクロな共同体を横断させ、ヴォルマールという異邦人をユートピア社会のデザイナーとして登場させながら、望ましい社会とは何か、自然と人間の関係はいかなるものであるべきかを読者に考えさせる。『新エロイーズ』のエコ言語は、ユートピア論と環境論を不可分に結びつけた。
ルソーはフランス革命の思想的なナヴィゲーターになったが、彼のユートピア思想には穴があいている。クラランの共同体は理性の産物だが、それは自然に似せた人工のユートピアであり、人間に関わる問題のすべてを解決することはできない。ゆえに、『夢想』では波の打ち寄せる無人島が、『新エロイーズ』ではノイズを排した無人の庭が、それぞれ心=自然のVR的な収容所として導入される。このような理性の剰余こそが、ルソーの環境文学の見出したものである。
では、ルソー以後、理性的なユートピアには還元されない心=自然は、いかに描き出されたのだろうか。ポスト・ルソーの自然詩人として最も注目に値するのは、一七七〇年生まれのイギリスのロマン主義者ウィリアム・ワーズワースである。サン・ピエール島のルソーがたった一人で自然を観察し享受したのに対して、ワーズワースは自然と接触する自己を複数化した。彼の代表的な詩「グラスミアの我が家」が、妹ドロシーとのカップルの視点から自然との調和を称揚したのは、ルソー的孤独と好対照をなすものである。さらに、自己の精神の成長を描いた長編の詩『序曲』も、過去と現在の「私」を多重に重ねあわせた一種のパリンプセスト(過去の痕跡を残した羊皮紙の写本)として書かれていた。
ワーズワースが詩以外の表現でも、読者に自然への参画を呼びかけたことは特筆に値するだろう。例えば、『湖水地方案内』(一八三五年)は、イギリスのウィンダミア湖を中心とする湖水地域――彼自身その近辺のコッカマスの生まれ――の旅行者に向けたガイドブックであり、「私」がその風景の魅力や歴史を伝えるという体裁をとる。その目的は「イギリス人に自国の景色の価値を認識してもらうこと」にあった[13]。ルソーはアルプスの山岳のブランド価値を高めたが、ワーズワースはアルプスよりも湖水地方のほうがずっと優れていると述べる。この明快なメッセージ性もあいまって、『湖水地方案内』は当時、彼の詩以上の有名作となった。
ワーズワースがそこでブランド化したのは、湖水地方の谷の複雑に入り組んだ地形である。この谷間は、光と影のコントラストを効果的に作り出す。「光と影が風景の崇高な、あるいは美しい様相に与える影響が、これほど狭い地域内でこれほど多様なところを、私は他には知らない」[14]。雄大さで競うのではなく、たとえ小ぶりであったとしても、切り立った山と峡谷の組み合わせの妙から、無限の多様性を引き出すことができる――それがワーズワースの発見した《谷》の風景であり、彼はその景観の保護こそを訴えた。
もっとも、このすばらしい景観を四角い額縁に嵌め込み、その躍動感を殺してしまっては意味がない。ワーズワースの詩は伝統的な自然詩とは異なり、まるで風景全体が動き出すような運動性を内包している[15]。『湖水地方案内』でも、山と谷にアプローチする方法論が詳しく記述されるが、そのマニュアルはワーズワース自身の文学と切り離せなかった。ある歩行コースの説明のなかで、彼は自作の『逍遥』の詩の一篇を引用し、それを湖水地方の体験のモデルとした。「すると突然、/足元に小さく、ちっぽけな谷が見えてきた。/確かにちっぽけではあるが、山々に抱かれ/高所に位置していた。この谷はあたかも/それを人間界から隔絶したいという願いにより/太古にここに据えられたかのようであった」[16]。
社会から隔離された小さな谷を、歩行者が高所から見下ろし、その内部に視覚的に分け入っていく――このクローズアップの技法にはワーズワースの自然体験の方法論が凝縮されている。ルソーが無人島のような《庭》のイメージに託したものは、ワーズワースでは視線と身体を動かして体験されるミニチュア的な《谷》に置き換えられた。これを風景の模型化と呼んでおこう。実際、『湖水地方案内』には次のように記される。
スイスのルツェルンには、四つの州に及ぶ湖を内包したアルプス地方の模型が展示されている。〔…〕この展示物に接すると想像力は大きな喜びを感じ、谷から谷へ、山から山へと、アルプスを隈なく飛び回ろうとするだろう。だが、この模型はより実体のある喜びも与えてくれる。つまり見物者は、アルプスの崇高で美しい地域を、そこに隠れている珠玉の光景や地域間に存在する関連性とともに、一瞬のうちに会得できるのである。[17]
これは、ワーズワースの詩そのものの注釈として読める。彼は、谷と山をくまなく歩き回ろうとする熱心な歩行者であり、かつその歩行のログを「碑文」のように固定化しようとする模型作家でもあった[18]。
この自然の模型的把握を手がかりとしながら、ワーズワースは人里から隔離された《谷》の住民たちの素朴な生活にこそ、ユートピア的な社会を見出した。彼の考えでは、湖水地方のグラスミアの谷では羊飼いと耕作者が身分差のない共同社会、つまり「純粋な共和国」の形態を保存していた。彼は人間が野生の動物たちとも共生するこの地域を「国民の財産」として称揚する。ワーズワースの《谷》は、ルソーの描いた「クラランの共同体」(小さな共和国)と「エリゼの庭」(豊かな感情の場)を矛盾なく統合した場だとも言えるだろう(余談ながら、この点でワーズワースの谷は、宮崎駿の『風の谷のナウシカ』の遠祖にもあたる)。
むろん、このようなロマン主義は一見するとナイーブに思える。現に、ワーズワースに対しては、フランス革命への幻滅をきっかけに、非政治的なエコロジーの幻想に転向しただけだという根強い批判がある。ただ、それは完全な誤りではないにせよ、いささか偏狭な意見だろう。というのも、ワーズワースは政治的な革命だけでは真の解放には到らないからこそ、自然とのつながりの回復が必要だと考えたからである。
ゆえに、ワーズワースはたんに社会や政治から逃避して、自然に引きこもったわけではない。彼の考えでは、社会のマジョリティこそが広大な自然から逃避して人間だけの関係に引きこもり、よりよい生を実現するための政治をないがしろにしている。ジョナサン・ベイトが指摘するように、グラスミアの谷の生活様式は社会主義に似ているが、それは「自然と人間界との接合」なしにはあり得ない。自然のなかでよりよく生きる可能性を追求したワーズワースは、たゆまぬ歩行を、自然との接触面を確保する最良の手段と見なした[19]。
そう考えると、ワーズワースのエコ言語には、人間の価値観の変化を促す機能があったことが分かる。エコロジー(緑)と社会主義(赤)のワーズワース的融合は、その後ジョン・ラスキンやウィリアム・モリスらにも引き継がれた。湖水地方の「歩き方」を示した観光案内を書くことは、まさにその政治的実験の一環であり、それは後の国立公園創設や景観保護運動の機運にもつながる。『ピーターラビット』で有名なビアトリクス・ポターが湖水地方の保護を訴え、ナショナル・トラストの支援者となったのも、ワーズワース的プロジェクトの延長線上にあるだろう。
5、思想としての歩行
ルソーにせよ、ワーズワースにせよ、歩行そのものが物質的環境との関係を変えるための思想的な技術であったことに違いはない。この技術は大まかに言って、二つの対となる性質――連続性と親密性、および即興性と操作性――を際立たせる。
第一に、歩行のリズムは風景を細かく分割し、それをなめらかな運動に吸収する。例えば、精神的成長を主題とするワーズワースの『序曲』では、たゆまぬ歩みのリズムが作品の思想そのものを形作っている。レベッカ・ソルニットが言うように、『序曲』では「この歩く者のイメージがさまざまな逸脱やまわり道のなかに連続性をつくりだしている」[20]。
この断絶のないなめらかさゆえに、歩くことは家族的な親密さを呼び覚ます。ワーズワースの『逍遥』では、カークストーン峠の山々が「兄弟」と呼ばれる。詩人にとって、山と谷のおりなすアップダウンをくまなく確認し、その歩行のログをとることは、人間と自然のあいだに兄弟的な連続性を作り出すことと等しかった。これは『新エロイーズ』のサン゠プルーがエリゼの庭を歩きながら、愛するジュリの痕跡を一つ一つ収集することを思わせる。歩くことは自然との接合面を増やし、それとの関係を唯一無二のものとしてイメージさせる行為なのだ。
第二に、歩くことには即興的な連想を引き起こす効果がある[21]。繰り返せば、ルソーの『孤独な散歩者の夢想』はジャズのアドリブ演奏のように、古い自己をたえず新たに生まれ変わらせたが、それは歩行なしにはあり得ない。ルソーは『告白』の第四巻で「わたしがひとり徒歩で旅したときほど、わたしがゆたかに考え、ゆたかに存在し、ゆたかに生き、あえていうならばゆたかにわたし自身であったことはない。歩くことはわたしの思想を活気づけ、生き生きさせる何ものかをもっている」と記し、次のように続けた。
〔ウォーキングによって束縛から遠ざかることが〕わたしの魂を解放し、思想にいっそうの大胆さをあたえ、いわば万有の広大無辺の中にわたしを投げこんで、何の気がねも、何の恐れもなく、存在するものを結合、選択させ、思いのままに自分に従わせるのである。わたしは全自然を自由に処理する。心は一つのものから他のものへとさまよい、好きなものに結びついて同化し、美しいイメージにとりかこまれ、快い感情に酔う。[22]
ウォーキングが思想を活気づけ、ルソーの自己を修復するとき、自然は心の思いのままに結合し、即興的にサンプリングできるデータの集合体に近づく。即興演奏は主観を解放し、自然をコレクションの対象に変える――むろん、それは決して永続的なものではないにせよ。
そして、散歩の与えるなめらかな連続性のなかで心を組織する以上、ルソーやワーズワースら歩行する思想家たちにとって、強烈な刺激に身を委ねるのは禁物である。ゆえに、ワーズワースが当時の煽情的・暴力的なゴシック小説に対する厳しい批判者でもあったことは、不思議ではない。盟友コールリッジとともに刊行し、ロマン主義運動の金字塔となった『抒情歌謡集』の序文で、ワーズワースは「人間の心は、粗野で強烈な刺激を加えずとも、結構興奮させられるのである」と記したが、これはゴシック小説の大流行を念頭に置いた言葉であった[23]。
暴力やホラーのショックで読者をノックアウトすることは、連続性を重んじる歩行の思想の対極にある。逆に言えば、自己を活気づけつつ鎮静化作用ももつルソーやワーズワース的な歩行は、それを脅かすショッキングな表現に取り囲まれつつあった。ワーズワース自身『序曲』の第一巻で、幼いときに鳥を罠にかけ、ボートを盗んだ記憶を呼び起こしつつ「自然の美しさとともに、自然の恐ろしさによっても養われて、私は生長した」(三〇六行)と記した。ゴシック小説がまさにこの「恐ろしさ」の部分を拡大したとすれば、ワーズワースの環境文学はゴシック的な恐怖を潜在させつつ、そのひび割れの可能性を散歩の微細な記述によってコーティングしたのである。
6、環境文学のビッグバン――フンボルトの惑星意識
以上のように、ルソーやワーズワースが《自然》と心を同調させる歩行の技術を定着させたことは、文学史上のブレイクスルーと呼ぶべき事件であった。レベッカ・ソルニットが示唆するように、この技術は二〇世紀のモダニズム文学にまで及ぶ[25]。主人公の行動履歴を細かく再現したヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』やジョイスの『ユリシーズ』は、歩行のログを感覚の基盤とし、それを思考や記憶の触媒とした。
ただ、ここで見逃せないのは、彼らの自然のイメージがあくまでヨーロッパに限定されていたことである。彼らの「エコ言語」の特性と限界は、ワーズワースと同世代のドイツの知的巨人、一七六九年生まれのアレクサンダー・フォン・フンボルトと比べるとき、いっそうはっきりするだろう。
博物学者にして地理学者、そして何よりも野心あふれる冒険家であったフンボルトは、地球の全体性を思索の対象とした画期的な著述家であった。ルソーの主人公サン゠プルーが海の向こうの忌まわしい新世界から、スイスの静謐な庭に引き返したのに対して、フンボルトはむしろヨーロッパ人の知らない南米への冒険を敢行し、その驚くべき世界のありさまを詳しく報告した。フンボルトは名文家とは言えなかったが、本人もお気に入りの『自然の諸相』(一八〇八年)はベストセラーとなり、その後の科学者や文学者に多大な影響を与えた。彼の一連の著作は、まさに環境文学のビッグバンと呼ぶにふさわしい。
シニカルなゲーテですら、この猛烈な知識欲を備えた二〇歳下の若者のとりことなり、その来訪を心待ちにしていた。彼はフンボルトから献呈された『アンデス山脈の景観と先住民の遺跡』に熱中し、新世界の未知の景観にすっかり魅了された。興味深いことに、ゲーテのファウストは、当初からフンボルトとの類似性が指摘されていた。フンボルトの優れた評伝を書いたアンドレア・ウルフが指摘するように「ファウストもフンボルトも猛烈な活動と探究が知識につながると信じ、どちらも自然に強靭さと一体性を見ていた」[26]。
フンボルトは同時代人にとって驚異の的であったが、それは何よりも、彼のファウスト的な冒険が文字通り「グローバル」な地平に及んでいたためである。もともと、ジェイムズ・クック船長の同行者に触発され、著名な探検家ブーガンヴィル――ディドロの『ブーガンヴィル航海記補遺』の着想の源泉でもある――を訪問したこともあったフンボルトは、一八世紀の初期グローバリゼーションの遺産の継承者でもあった。のみならず、彼の活動は非ヨーロッパ的な異文化との出会いというディドロのプロト人類学的なテーマを超えて、物質としての地球の発見を伴っていた。
一七九九年にスペインからベネズエラに渡った際には、フンボルトはその眩暈をもたらすような魔術的な自然に熱中しながら、博物学的な調査にいそしんだ。なかでも、彼を強く触発したのは火山である。彼は一八〇二年には六千メートル級のチンボラソ山の初登頂に成功し、その後もエクアドルの火山を踏破した。この一連の探検は地球物理学の基礎となり、フンボルトの数多い知的貢献のなかでも突出した事例となった。彼にとって、火山は人間の諸文化をはるかに凌駕して、自然そのもの、ひいては地球そのものの力を顕現させる崇高にして驚異的な場なのである。
フンボルトの前例のない冒険は、ヨーロッパのエコ言語にも質的な変化をもたらした。メアリー・ルイーズ・プラットの指摘によれば、従来のヨーロッパの旅行記では自己中心的で情緒的な書き方が主流であったのに対して、フンボルトはむしろそのような個人のナルシシズムを取り去り、旅行記を科学的な客観性と融合させた。強靭な「惑星意識」(planetary consciousness)を備えたフンボルトの文体は、精神を人間の尺度をはるかに超えて、惑星のスケールにまで拡大した[27]。非人称的な科学のスタイルが、この意識の拡大を支えたのである。
この新しい「惑星意識」は、ゲーテのような先行する学者の想像力を逸脱するものであった。一七八七年にイタリアのナポリを訪れたゲーテは「ナポリは楽園だ。人はみな、われを忘れた陶酔状態で暮している。私もやはり同様で、ほとんど自分というものが解らない。全く違った人間になったような気がする」とあけすけに記し、動揺を隠さなかった。ゲーテをこの錯乱の危機から救ったのは、ナポリ近辺のヴェズヴィオ山の偉容であった。彼はこの火山に三度も登り、そのつど測量をおこなった。ルソーのみじめで孤独な人生を反面教師としながら、狂気じみた世界に秩序を与えようとしたゲーテにとって、エネルギーに満ちた火山を科学的に観察することは、精神を治癒する手段になったのである[28]。
逆に、南米で苛酷な冒険を経てきたフンボルトにとって、ヨーロッパの自然は地球のほんの一部にすぎなかった。彼はたまたまイタリア滞在中にヴェズヴィオ山の噴火を目撃したが、その迫力は南米の火山とは比べ物にならないと感じられた。地球そのものと接触し続けてきた冒険家フンボルトからすれば、ナポリ程度で自分を見失ってしまうゲーテはヤワな文人ということになるだろう――むろん、フンボルトが偉大な先人ゲーテから多大な知的影響を受けたことは確かだとしても。
してみると、フンボルトの惑星意識が、一九世紀の先進的な自然科学者たちを鼓舞したことも不思議ではない。若きダーウィンはフンボルトの著作に魅了され、ビーグル号でもずっと手放さなかった。ダーウィンの進化論に影響を与えた地質学者チャールズ・ライエルも、フンボルトの研究を継いで、地球を形成する「深い時間」(後述)を見出した。フンボルトはまさに「地球というウェブ」(アンドレア・ウルフ)に基づく思考を、自然科学の基盤に据えつけたのである。
7、資本主義というウェブ、地球というウェブ
この《自然から地球へ》という意識革命が、従来の自然観に及ぼした影響は大きい。ヨーロッパに帰還したフンボルトは、一八〇五年に「植物地理学上のエッセイと熱帯世界の自然画」をゲーテに捧げる。喜んだゲーテは、リンネが植物種を分類するアルファベットを考案したのに対して、フンボルトが植物を生きた集団として把握したことを絶賛した[29]。
リンネおよびビュフォンは、一八世紀ヨーロッパの博物学を代表するスターであった。リンネがまさに「アルファベット」のような機械的な分類システムを創出する一方、ビュフォンはむしろリンネ的なシステムを忌避して、人間との近さを基準にした、いわばアナログな序列化に向かったという違いはあるものの、両者ともに自然を分類学の対象としたことに変わりはない。ビュフォンがフランスの王立植物園の園長となり、リンネがスウェーデンの中心都市ウプサラの植物園で研究を進めたことも、彼らの自然観察がともにヨーロッパの自己完結したシステムの内部にあったことを示唆する。リンネの図鑑を片手にサン・ピエール島を歩き回ったルソーも、新しい植物の発見ではなく、あくまでリンネ的システムの内部で既知の植物の「同一性」を再確認することによって、心を鎮静化させたのである[30]。
しかし、フンボルトはまさにこの鎮静剤のような自然モデルを克服しようとした。メアリー・ルイーズ・プラットは、フンボルトの自然観がリンネの自己完結的なカテゴライズと異質であったことを強調している。「フンボルトが呼び出すのは、見えるものに依拠した自然のシステムではなく、見えない力の終わりなき拡大と収縮である。この観点から、フンボルトの言説はリンネ派の先人とはっきりした対照をなしている」[31]。
リンネは自然を視認できるもののシステムに還元し、その分類にいそしんだが、フンボルトは不可視の地球のウェブにこそ注目し、それへの自然科学的なアプローチを試みた。例えば、気象学への一大貢献となった彼の「等温線」の発明は、地球というウェブの作り出すパターンを図示し、比較気候学への道を切り拓くものとなった。その一方、彼は南米の火山の観察から、万物は地下ではつながっていることを直観していた。火山は個別の存在ではなく、地球のネットワークの一部なのだ。驚くべきことに、二〇世紀後半にプレートテクトニクス論が証明されるはるか以前に、フンボルトは大陸移動を促す「地中の力」があることを察知していた[32]。
このようなラディカルな惑星意識は、人間中心主義からの逸脱を含んでいる。例えば、ビュフォンの『博物誌』は人間を中心として、それに近い動物が順々に並べられる。ゆえに、彼が原生林をおぞましいものと感じ、人間による自然の開発を正当化したのも偶然ではない。逆に、自然の連関に気づいていたフンボルトは、地球=ウェブの有機的全体性から思考を組み立てる。特に、彼がヨーロッパ人の植民地化による南米の生態系の破壊、いわゆる「傍若無人な人新世(Anthrobscene)」のもたらす諸問題を早い段階でつかんでいたことは、特筆に値するだろう。ベネズエラのバレンシア湖でヨーロッパ人の入植者たちによる森林の過剰伐採を目撃したフンボルトは、それが将来世代に禍根を残すと警告した[33]。この明快な植民地主義批判から分かるのは、フンボルトが一八世紀の思想家とは異なる《世界性》にアクセスしていたということである。
ゲーテはエッカーマンに、画期的な事業をなすには「頭がいいこと」と「大きな遺産を受け継ぐこと」が肝心だとあけすけに語ったが(一八二四年五月二日)、抜群の知力と活動力を備えたフンボルトにとっては、地球そのものが最大の「遺産」であったと言えるだろう。彼は多くのヨーロッパの知識人が空想するしかなかった新世界の景観を、いわば人力で構築されたビッグデータとして提出した。フンボルトが「物質的な世界全体を一冊の本にしようという狂気」に憑かれ[34]、地球環境そのもののミメーシス(模倣)を試みた『コスモス』は、そのビッグデータの集大成と呼ぶべき巨人的著作である。
フンボルトの空前の環境文学が、後続の作家たちにも強烈なインパクトを与えたのも不思議ではない。例えば、アメリカのエマソンやヘンリー・ソローは、フンボルトの『自然の諸相』から大きな影響を受けた。E・A・ポーの『ユリイカ』はフンボルトの『コスモス』に捧げられ、フランスのジュール・ヴェルヌの『海底二万里』に登場するネモ船長は、フンボルトの著作のコレクターとして描かれた。のみならず、地球の力を呼び覚ますフンボルト的なエコ言語は、政治的なエネルギーにも転化された。彼の描いた崇高な景観は南米の革命家たちにとってナショナル・プライドの源泉となり、フンボルトと交友のあったシモン・ボリバルらによる南米の独立運動を鼓舞することになった。
してみると、晩年のゲーテが世界文学論を構想していた一八三〇年代に、フンボルトが『コスモス』に着手したことは、実に興味深い符合である。この時期以降、西洋の知的システムは二つの《世界性》、ないし二つの《ウェブ》をもはや無視できなくなった。一つは、文学や学問を商品として結びつける資本主義というウェブである。諸国民の「精神的交易」を加速させようとするゲーテのフリーメイソン的な構想は、事実上このグローバルな市場に根拠づけられる。もう一つは地球というウェブである。フンボルトは万物が相互につながりあった有機的全体性として、地球を再発見したのである。
ゲーテとフンボルトはそれぞれ異なる世界性にアクセスし、西洋人の認識の地平を刷新した。では、後者に象徴される《地球》の浮上は、環境文学にいかなる変化をもたらしたのか。アメリカのソロー、ドイツのロマン主義者のエコ言語から、その一端を探ってみよう。
8、地球という恐るべき物質――ヘンリー・ソロー
一八一七年にボストン近郊のコンコードに生まれたヘンリー・ソローは、ルソーとワーズワースに続く歩行の巨匠と呼ぶべき作家である。ソローにとって、歩くことは生活と思索の根源にあった。彼の有名なエッセイ「ウォーキング」では、散歩は何かのための手段ではなく、それ自体が「その日の事業」だと記される。それは「狭苦しい原っぱ」のような政治を離れて、真の世界を保存した「野性的なもの」(Wildness)にアクセスするための冒険であった。しかも、ソローはワーズワースのようなイギリスの湖畔詩人の飼い慣らされた穏健さを批判しながら、野生の回復を訴えたのである[35]。
ゆえに、ルソーやワーズワースの自然とは異なり、ソロー的な自然は原生林や荒野によって特徴づけられる。コンコードを拠点とした超越主義者エマソンを師と仰ぎつつも、ソローはやがてフンボルトと同じく、自然の細やかな観察を通じた有機的全体性への接近を試みるようになった。ただ、フンボルトの冒険がグローバルな範囲に及んだのに対して、ソローの散歩=冒険はアメリカ東海岸の一地域に集中した。例えば、ソローの『メインの森』では、メイン州を覆う原始の森で《地球》の地肌と接触した経験が再現されている。
ここは世にいう「混沌」と「いにしえの夜」とから造られた大地であった。ここには人の園はなく、ただ封印をしたままの大地があるのみだった。それは、芝地、牧草地、採草地、森林地ではなく、詩にうたわれる草原や耕地でも、荒地でもなかった。それは地球という星の真新しい、天然のままの表面であった。〔…〕それは世にいう母なる大地ではなく、巨大で恐るべき物質であった。[36]
もともとアメリカ文学の伝統には、ヨーロッパ各国を舞台とするワシントン・アーヴィングの『スケッチ・ブック』に始まり、パリの探偵デュパンを主役とするポーの推理小説、さらにはメルヴィルの一連の海洋文学に到るまで、アメリカを超越することこそが最もアメリカ的であるという逆説が刻印されている。ソローがアメリカの原生林のなかで「巨大で恐るべき物質」としての地球と接触したことも、まさにその逆説の一例と言えるだろう。
私は先ほどから、近代文学が「環境によって心を創作する技法」を発明したと述べてきた。ただ、そのエコ言語は、一九世紀の「惑星意識」の浮上によって変容を遂げる。一八世紀のルソーは『夢想』で「植物学は孤独で怠惰な暇人の趣味にぴったりなのだ。観察に必要なのは、ピンセットとルーペだけ」(第七の散歩)と述べる一方、体力勝負で解剖もせねばならない動物界の研究は面倒だと言ってはばからなかった。逆に、ほぼ一世紀後のソローは、ルソー的な怠惰さを蹴散らすように、ヘラジカを追って原始の森林に入る一方、豆畑を一人で耕作して自給自足の生活を営む。それはVR的な《庭》への回帰ではなく、むしろ物質との共生を意味していた。
現に、ソローの惑星意識は、自覚的に土に根ざすことによって保持された。自然と共生するライフスタイルを思索的かつ実践的に語った代表作の『ウォールデン――森の生活』(一八五四年)では、彼は自らを原野と耕作地のあいだにいる「土の子」(native of the soil)と称する[37]。驚くべきことに、ソローの日記には「私は一塊の土を食べることができそうな気がする。私はこれほど土的な存在だと感じたことも、大地の表面とこれほど共鳴したこともなかった」とすら記されていた。彼は自然をただ観察するだけではなく、それを試食し、味わい、取り込む次元にまで達しようとする[38]。地球と限りなく接近することが、ソローにとっては自己保全に不可欠の手段となった。
冒頭から《私》という一人称に執着する『ウォールデン』は、コンコードの自然のなかをいわば動物的に散歩し、野生を味わい尽くしながら《私》を生成しようとする著作である。そこにはワーズワースのように高所から見下ろす視点の代わりに、獣のように土と接触する生命がある。ユーモア作家としての一面をもつソローは、街の人間のゴシップの対象にもなった自らの風変わりな生き方を客観視しながら、地球との接触をほとんどまじめな冗談のように語った。その際、マイケル・ギルモアが強調するように、ソローの単独的な「私」が「交換への呪い」と対になっていたことは見逃せない。
ソローはテクストを書くことと作物を植えること、つまり作家と農民をアナロジーで結んだ。この隠喩的な農民としての作家は、交換経済の外に根ざしながら、自然をコモディティ(商品)に還元してしまうことに抵抗するのだ[39]。かつて農本主義者トマス・ジェファーソンが市民道徳の担い手として理想化したアメリカの自営農民は、すでに交換経済に巻き込まれていた。しかし、ソローは同世代のロシアの作家ツルゲーネフの『猟人日記』のように狩猟民の生き方に注目するのではなく、あくまで大地=庭を耕す簡素な農民的ライフスタイルを惑星的なスケールのもとで再創造しようとする。「太陽から見れば、地球全体が等しく耕されている一つの庭園のようなものだ」[40]。
ソローはユーモア作家としての手管も尽くしながら、自らが居住し耕作するウォールデンにかけがえのない固有性を与える。ウォールデンはまるで人格をもった親友のように、ソローから気兼ねなく語りかけられる。このような霊的なコミュニケーションを通じて、ソローは市場では交換不可能な野生的自然を際立たせた。「ホワイト湖とウォールデン湖は地上の大水晶、《光の湖》だ。〔…〕この二つの湖はあまりにも清冽な美しさをたたえているので、市価などつけられない」[41]。ソローの《私》のかけがえのなさは、ウォールデンのかけがえのなさとの類比として描き出され、ウォールデンそのものから独自の主体的視点が発生する。ソローがディープ・エコロジーの祖となったのは、まさにこのような自然の主体化を演出する隠喩的操作のなせる業である。
さまざまな意味で、『ウォールデン』は同時期のメルヴィルの『白鯨』と好一対の作品である。両者はともに、人間を圧倒する「巨大で恐ろしい物質」の世界と接触している。ただ、『白鯨』が捕鯨船というベンチャー企業を核として、恐るべき自然物を交換可能な商品に変えようとする欲望を描いたのに対して、『ウォールデン』はそのような商品経済から撤退した野性的農民の暮らしに《私》の基盤を求める。ソローが「自分の心の中にだけ存在している自分の領海としての大西洋や太平洋を探検すること」が、実際に海を航海するよりもはるかに困難だと記すとき[42]、メルヴィルとの差異は鮮明になるだろう。
9、ドイツ・ロマン派の「深い時間」
ところで、ここまで挙げたロマン主義者たちがウォーキングの思想家であったことには、産業社会への批判という一面がある。例えば、ルソーは『夢想』で「鉱物界それ自体には、可愛らしさも、魅力も感じない」と述べながら、石切り場、坑道、製鉄所、溶鉱炉、工場、さらには鉱山が、のどかな農村に取って代わったことを嘆いている。彼にとって、鉱業とは人間と社会を汚染し、穏やかな暮らしを破壊する「醜いキュクロプス(単眼の巨人)」にすぎなかった(第七の散歩)。
しかし、同世代の博物学者ビュフォンが製鉄企業の経営者でもあったことから分かるように、すでにルソーの時代には自然研究と産業社会が結合し始めていた。ルソー自身、散歩中に手つかずの未知の自然に出会ったと思い込んだ次の瞬間、そのそばに稼働中の靴下工場があることに気づいて、すっかり幻滅したエピソードを記している(第七の散歩)。このような自然物と人工物の隣接は、文学のエコ言語に変異をもたらすきっかけとなった。
特に、ドイツの著述家たちは鉱業と切っても切れない関係があった。例えば、地質学や鉱物学に早くから関心を寄せたゲーテは、イルメナウ鉱山再開発の監督を務めるとともに、花崗岩へのフェティシュな情熱をもとに、花崗岩を「原岩石」とする「地球の生成」に関わる壮大な理論を構築しようとした[43]。かたや、ドレスデンに近い小都市フライベルクの鉱山大学で学び、若くして鉱山官に抜擢されたフンボルトは、ヨーロッパ各地の鉱脈を調査する一方、ゲーテとは違って玄武岩をより古く根源的なものと見なし、地質学を二分する論争を巻き起こしたが、両者ともに、鉱山を地球の謎を解き明かす入口としたことに違いはない。アメリカのメルヴィルにとって捕鯨船が「大学」であったとすれば、ドイツの思想家たちにとっては、まさに鉱山こそが科学的な知を集約し発展させる場となった[44]。
さらに、鉱物はドイツの文学的想像力にも決定的な影響を与えた。ドイツ・ロマン派の旗手ノヴァーリスは鉱山学校の出身であり、その体験は彼が「メルヒェン」と称する代表作『青い花』(一八〇一年)で生かされている。主人公の青年ハインリヒ・フォン・オフターディンゲンは夢で見た変幻自在な青い花に惹きつけられ、その憧れから旅に出る。それは、野蛮で粗野な原始社会でもなく、洗練されてはいるが平凡でつまらない近代の産業社会でもない、いわば第三の中間地帯、つまり「質素な服装の下に高雅な姿をつつんだ深遠なロマン的な時代」を探し求める旅であった[45]。
ノヴァーリスは、そのロマン的な時空を鉱山に凝縮させた。彼の描く坑夫たちは、採掘の作業に無心で取り組む一方、それを地上で商品にすることには関心がない。彼らは、富や名声への欲望に縛られない質素にして高雅な精神的自由人として描かれる。ノヴァーリスにとって、何ものにも変身できる青い花、ひいては鉱物的なものは、まさにロマン主義の理念を凝縮したオブジェそのものとなった。
やはりドイツ・ロマン派を代表する小説家E・T・A・ホフマンも、印象的な短編小説「ファールンの鉱山」(一八一九年)で、若い坑夫が鉱山で結晶化したという逸話をリメイクした。その主人公エーリス・フレーボムは、東インド貿易の拠点であるスウェーデンの港町イェーテボリの喧騒を離れ、リンネも調査した巨大なファールン鉱山へと導かれる。すでに海の荒々しい冒険にうんざりしていた彼にとって、鉱山の地底は自然の奥深い秘密を知らせる秘儀の場となった。彼は鉱脈の「澄みきった水晶」のような透明さに魅惑される。地下の「壮麗きわまりない金属の樹木や草花にあふれた楽園さながらの広野」は、女王の統治するユートピアとして描き出され、彼の心身はやがてそこに吸収されてゆく[46]。
ホフマンはここで、グローバル産業を支える《海》を、鉱物の溢れる《地下》にそっくり置き換えた。ルソーがリンネの植物学を背景としてエリゼの《庭》を描き、ワーズワースが観光業を背景に《谷》を模型として提示したとすれば、ノヴァーリスやホフマンは地質学や鉱業のイメージを利用して《地下》を造形した。彼らはいわば地下を庭の代替物として、人間の解放をもたらす「楽園」の保持に向かった。ここには、産業社会の発見した鉱山を、かえって産業社会に汚染されていない庭に読み替えるという逆転の戦術がある[47]。
もとより、ノヴァーリスにせよホフマンにせよ、鉱山にまつわるロマンティックな幻想が勝りすぎている感は否めない。ただ、彼らが示そうとしたのが《地球》のもつ手触りであり、地質学的なスケールから生じる崇高な「深い時間」(deep time)であったことには、やはり注意しておく価値があるだろう。ロマン派が活躍した後、チャールズ・ライエルが飛躍させた地質学は、時間の尺度を数十億年という単位にまで拡大した。あまりにも長大な地質学的時間においては、起点や終点という線的な概念は無効化され、循環する時間が現れてくる[48]。それが《地球》に基づくエコ言語の効果なのである。
10、ひび割れた鏡
繰り返せば、近代小説が直面したのは、資本主義というウェブと地球というウェブ、この二つの《世界性》である。環境文学の系譜において、地球の発見は最大の事件の一つであった。
ルソーやエマソン、ワーズワースのような《自然》の著述家たちは、自然と心が「鏡」のようにお互いを照らし出すと考えた。それに比べると、《地球》というウェブに身をもってコミットしたメルヴィルやフンボルトは、より唯物論的である。彼らの接触した環境は、一人の人間の心には到底収容しきれない怪物的なリヴァイアサンであり、ゆえに『白鯨』の惑星意識は独身者たちの多声的空間へと展開され、フンボルトの『コスモス』は不可視の地球がおのずからその全体の姿を現すように書かれた。
その一方、メインの森のソローが地球を「巨大で恐るべき物質」と見なし、ドイツ・ロマン派の作家たちが鉱山のなかで地質学的な「深い時間」に気づいたとき、つまり《自然から地球へ》という意識革命がエコ言語に侵入したとき、自然と心のあいだの鏡には大きなひびが入り始めた。この両者の関係はもはや対等ではあり得ない。怪物化した環境によって心をむりに隠喩的に制作すれば、心は人間らしさをすっかり失って、見慣れない物質に近づいてしまうだろう。ドイツ・ロマン派の文学ではこのひびは目立たなかったが、その亀裂がいずれ大きくなるのは時間の問題であった。
このテーマを最も過激に推し進めたのは二〇世紀後半のSF、特にイギリスのJ・G・バラードによる一九六〇年代の一連の作品群である。彼の『沈んだ世界』、『旱魃世界』、『結晶世界』は、一九世紀のドイツ・ロマン派の地質学的想像力をラディカルに更新した特異な文学として解釈できる。環境によって心を創作するという近代文学のプログラムは、バラードに到って一つの極点に達したと言えるだろう。
ノヴァーリスの『青い花』においては、ロマンティックな「質素で高雅」な鉱物が、心の隠喩となった。しかし、原子力と生命科学の時代に突入したとき、このような一九世紀的なロマン主義は時代遅れとなる。ひとたび核兵器が炸裂すれば、もはや人間の心とは無縁な異様な物質世界ができあがり、遺伝子操作は心のあり方そのものを技術的に変えてしまいかねない。バラードのSF的エコ言語がクールに記述したのは、まさにこのような不気味な時代の生態系である。
哲学研究者のダヴィッド・ラプジャードが指摘するように、バラードには「心的なものと物理的なものがあわさって、唯一の同じ現実を構成しているという考え」がある。シュールレアリスムから出発したバラード的エコ言語においては、怪物化した環境が心的なものと一体化する――ということは、心そのものが外部の物質的な環境にそのまま露出してしまうのだ。こうして、人間そのものが地質学的な時間に巻き込まれた物質となる。ラプジャードが言うように、そこでは「人間は塵埃と区別がつかない」[49]。しかも、バラードは一切驚いたそぶりもなく、冷静沈着なエンジニアのようにこの心の物質化を遂行するのである。
このような環境文学の極北は、われわれを新たなテーマへと向かわせる。というのも、飛躍を恐れず言えば、そもそも近代文学には、人間的なものが事実上絶滅してしまった状況へのオブセッションがあるからだ。ならば、バラードの黙示録的なSFは、異常な突然変異というよりは、むしろ近代文学のもつプログラムを純粋形態にまで推し進めた文学として読み解けるだろう。次章ではこのテーマに迫ってみたい。
[1]「自然」『エマソン論文集』(上巻、酒本雅之訳、岩波文庫、一九七二年)五九、六四頁。
[2]P・リクール+E・ユンゲル『隠喩論』(麻生建+三浦國泰訳、ヨルダン社、一九八七年)一九〇‐一頁。
[3]ジョルジュ・バタイユ『文学と悪』(山本功訳、ちくま学芸文庫、一九九八年)一四頁。
[4]エコ言語という名は、ジェイムズ・C・マキューシック『グリーンライティング』(川津雅江他訳、音羽書房鶴見書店、二〇〇九年)から借りた(六七頁)。
[5]小西嘉幸『テクストと表象』(水声社、一九九二年)九七頁。なお、東浩紀は『訂正可能性の哲学』(ゲンロン、二〇二三年)で『新エロイーズ』のクララン共同体について込み入った解釈を施しているが(第八章)、肝心のエリゼの庭についてはなぜか無視している。
[6]J・スタロバンスキー『透明と障害』(山路昭訳、みすず書房、一九七三年)一七六頁。
[7]ジャン゠ルイ・ルセルクル『ルソーの世界』(小林浩訳、法政大学出版局、一九九三年)二七五頁。
[8]ルソーは理論的には都市の演劇を批判し、農民の素朴な祭りやダンスを称揚したにもかかわらず、感情的にはそれとは真逆なことをさりげなく告白している。「わたしは踊っているのを見ると退屈する。〔…〕わたしは道楽といってもいいほど芝居が好きなのだ。〔…〕事実は、ラシーヌはわたしを魅了するし、モリエールの上演を気が進まないので見なかったことも一度もない」。ルソー『演劇について――ダランベールへの手紙』(今野一雄訳、岩波文庫、一九七九年)二七七‐八頁。訳文一部変更。
[9]ルソー『新エロイーズ』(第三巻、安士正夫訳、岩波文庫、一九六一年)一二八頁。訳文一部変更。
[10]同上、一五〇頁。
[11]小西前掲書、一一二頁。
[12]スタロバンスキー前掲書、一七七頁。
[13]ウィリアム・ワーズワス『湖水地方案内』(小田友弥訳、法政大学出版局、二〇一〇年)一一四頁。
[14]同上、三〇頁。
[15]マキューシック前掲書、一〇六頁。
[16]『湖水地方案内』、七‐八頁。
[17]同上、二五頁。
[18]ワーズワースの詩における場面の碑文化については、ジョナサン・ベイト『ロマン派のエコロジー』(小田友弥+石幡直樹訳、松柏社、二〇〇〇年)一四六頁。
[19]同上、六二、七四頁。Jonathan Bate, Radical Wordsworth,
[20]レベッカ・ソルニット『ウォークス』(東辻賢治郎訳、左右社、二〇一七年)一七二頁。ただ、批評家のポール・ド・マンは『ロマン主義と現代批評』(中山徹他訳、彩流社、二〇一九年)で、環境と心が「鏡」のようにお互いを照らしあうというワーズワースのヴィジョンが、いかに不安定なものかを詳細に論じている(一三〇頁以下)。
[21]ソルニット前掲書、三九頁。
[22]ルソー『告白』(上巻、桑原武夫訳、岩波文庫、一九六五年)二三二頁。
[23]デイヴィッド・パンター『恐怖の文学』(石月正伸他訳、松柏社、二〇一六年)一二頁。
[24]ワーズワース『序曲』(岡三郎訳、国文社、一九六八年)二六頁。なお、ゴシック小説の流行を加速させたアン・ラドクリフの『ユドルフォ城の怪奇』(一七九四年)では、鬱蒼とした森の散歩を好む主人公のエミリーが、フランスのガスコーニュからトゥールーズを経て、イタリアのヴェニスの美しい海岸を見た後に、谷間の荘厳な城で恐ろしい事件に出くわす。そこには、恐怖と崇高を結びつけるエドマンド・バークの著作の影響が認められるが、同時にワーズワースの環境文学のカウンターパートと呼べる要素もある。
[25]ソルニット前掲書、三九頁。
[26]アンドレア・ウルフ『フンボルトの冒険――自然という〈生命の網〉の発明』(鍛原多惠子訳、NHK出版、二〇一七年)六八頁。
[27]Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, Second Edition, Routledge 2008, p.122.
[28]ゲーテ『イタリア紀行』(中巻、相良守峯訳、岩波文庫、改版二〇〇七年)五三、六〇頁。
[29]西川治『地球時代の地理思想』(古今書院、一九八八年)一九頁。
[30]スタロバンスキー前掲書、三七七頁。
[31]Pratt, op.cit., p.121.
[32]ウルフ前掲書、二六三、二八七頁。
[33]そもそも、リチャード・グローヴによれば、ヨーロッパにおける「グローバルな環境主義の起源」そのものが、ヨーロッパの公害以上に、エデンの園のように目されていた熱帯地方の生態系の破壊にある。植民地主義がいわば逆流し、ヨーロッパの環境意識を変えてゆく際に、フンボルトの著作の普及は大きなインパクトをもった。Richard H. Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and Origins of Environmentalism 1600-1860,Cambridge University Press, 1995, chap 7.
[34]ウルフ前掲書、三四〇頁。
[35]H・D・ソロー「歩く」『市民の反抗 他五篇』(飯田実訳、岩波文庫、一九九七年)一一三、一一七、一三七頁。
[36]ヘンリー・D・ソロー『メインの森』(小野和人訳、講談社学術文庫、一九九四年)一〇四頁。
[37]ヘンリー・D・ソロー『森の生活 ウォールデン』(佐渡谷重信訳、講談社学術文庫、一九九一年)二三六頁。
[38]ドナルド・オースター『ネイチャーズ・エコノミー』(中山茂他訳、リブロポート、一九八九年)一〇九頁。
[39]Michael T. Gilmore, American Romanticism and the Marketplace, The University of Chicago Press, 1985, p.48.
[40]『森の生活』二四八頁。
[41]同上、二九五頁。
[42]同上、四六一頁。
[43]詳しくは、『ゲーテ地質学論集・鉱物篇』(木村直司編訳、ちくま学芸文庫、二〇一〇年)の訳者解説参照。
[44]ドイツ・ロマン派の作家はたんに現実から夢想に逃避していたわけではなく、鉱山から大学に到るまで新しい「制度」を構築しようとする運動も内包していた。詳しくは以下参照。Theodore Ziolkowski, German Romanticism and Its Institutions, Princeton University Press, 1990.
[45]ノヴァーリス『青い花』(青山隆夫訳、岩波文庫、一九八九年)三一頁。
[46]E・T・A・ホフマン「ファールンの鉱山」『ドイツ幻想文学傑作選』(今泉文子編訳、ちくま文庫、二〇一〇年)二五八頁。
[47]なお、鉱物を商品経済から隔離したドイツ・ロマン派とは逆に、鉱山に政治・経済を突き動かすフェティシュ(物神)を認めたのが、ジョゼフ・コンラッドの長編小説『ノストローモ』(一九〇四年)である。この特異な小説は、南米の架空の国家コスタグアナを舞台に、「帝国の中の帝国」たるサン・トメ銀山――イギリスにルーツをもつ意欲旺盛なチャールズ・グールドを経営者とする――を、大地と政治を盲目的に変形し続ける異様なメカニズムとして描き出した。そこには二〇世紀後半のラテンアメリカ文学を先取りする諸要素(独裁、外資の導入、フェティシズム等)があり、近年では『ノストローモ』に批評的に応答したコロンビアの作家フアン・ガブリエル・バスケスの『コスタグアナ秘史』(二〇〇七年)のような興味深い小説も書かれている。
[48]ロザリンド・ウィリアムズ『地下世界』(市場泰男訳、平凡社、一九九二年)四一頁。
[49]ダヴィッド・ラプジャード『壊れゆく世界の哲学』(堀千晶訳、月曜社、二〇二三年)七七‐七八頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年1月23日、1月30日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年2月29日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。