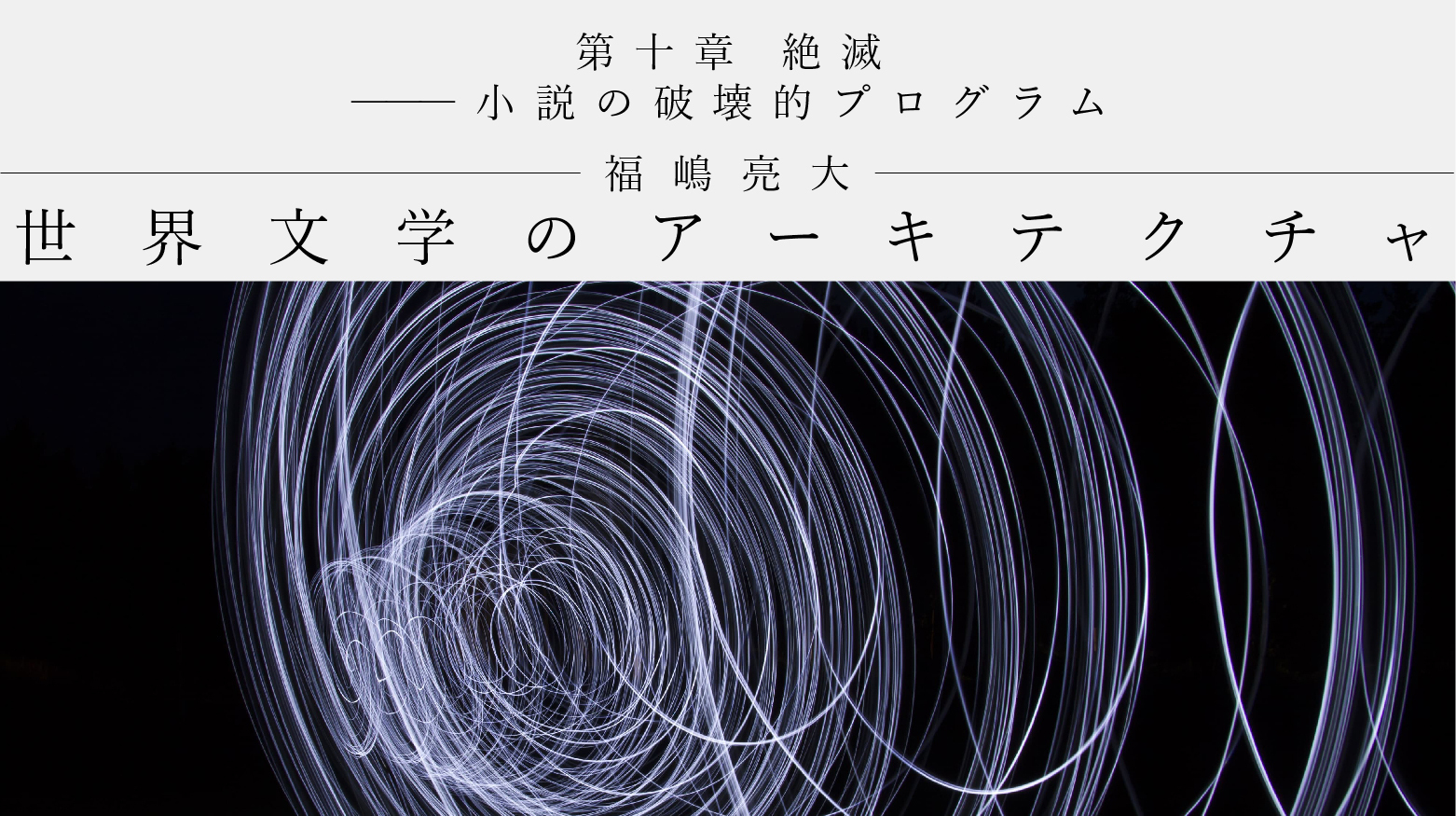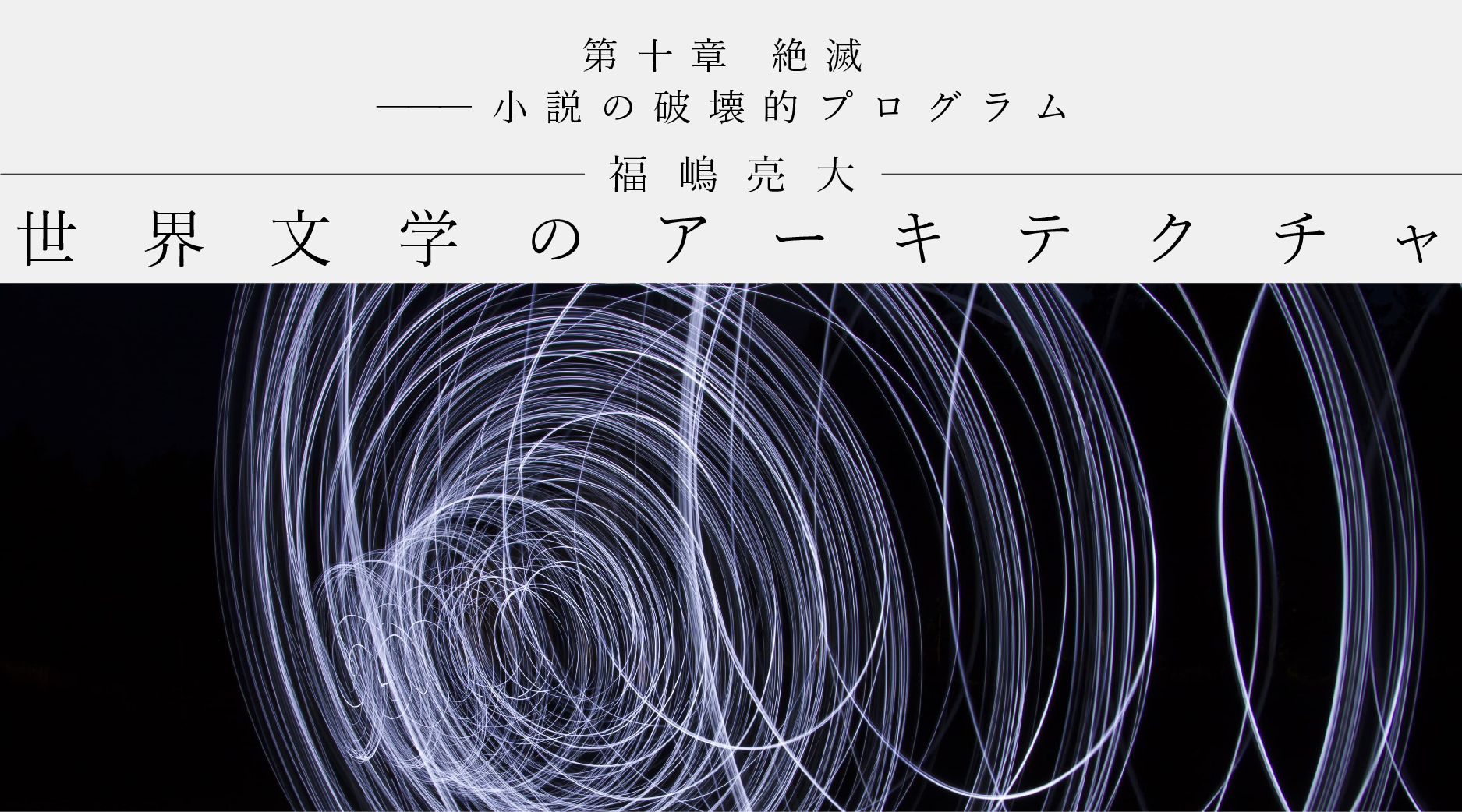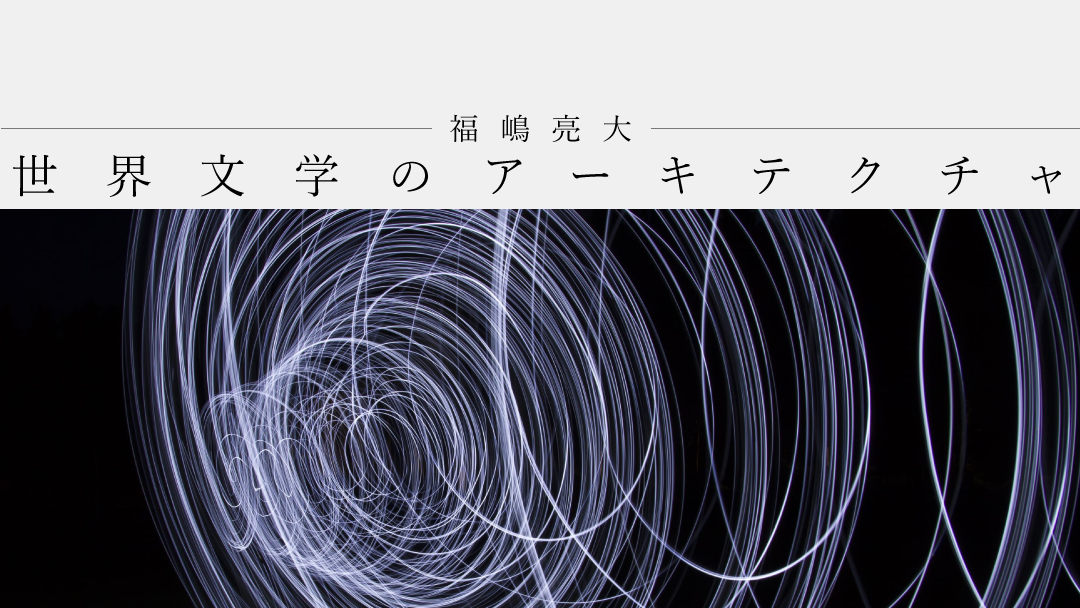
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、冒険の形式、絶滅の形式
小説をそれ以前のジャンルと区別する特性は何か。この単純だが難しい問いに対して、ハンガリーの批評家ジェルジ・ルカーチは『小説の理論』(一九二〇年)で一つの明快な答えを与えた。彼の考えでは、小説とは「先験的な故郷喪失の形式」であり、寄る辺ない故郷喪失者である主人公は「冒険」を宿命づけられている。
小説は冒険の形式であり、内面性の固有価の形式である。小説の内容は、自らを知るために着物を脱いで裸になる心情の物語であり、冒険を求めて、それによって試練を受け、それによって自らの力を確かめながら、自らの固有の本質性を発見しようとする心情の物語である。[1]
ルカーチによれば、近代小説の主人公は「神に見捨てられた世界」でさまざまな試練をくぐり抜けながら、固有の魂を探し求める存在である。今でも多くの小説は、欠損を抱えた主人公の冒険の物語として書かれる。揺るぎない根拠を喪失し、世界とのギャップ(疎隔)を抱えた「ホームレス・マインド」(社会学者ピーター・バーガーの表現)が、冒険によって固有の何かを獲得したり、あるいは獲得し損ねたりする――このような精神の運動が小説というジャンルには刻印されている。
ゆえに、近代小説は安定した意味の宇宙をあてにできない。ルカーチが言うように、神に見捨てられ、世界との「疎遠さ」を宿命づけられた小説的冒険は「絶対的に解消されない不協和」を内包している。いかなる「生」も世界とぴたりと意味的に一致することはない。この本質的なギャップゆえに、ルカーチの言う「冒険の形式」はセルバンテスの『ドン・キホーテ』以降、デモーニッシュな狂気と不可分であった[2]。絶対的な根拠=故郷をもたないまま、自己を脱ぎ捨てて冒険に乗り出す試みは、それ自体が狂気じみたエネルギーを要求したのだ。
精神的なホームをもたない小説の主人公は、自己の魂の探究と再創造という冒険に向かう――ルカーチがこの仕組みを理論的に明示したことの価値は揺るぎない。ただ、彼の力点はあくまで冒険者の「生」(主観)の側にあり、冒険のなされる「世界」の様相については深く考察されなかった。第一次大戦とロシア革命という大事件の後、祖国ハンガリーからの亡命直後にルカーチが刊行した『小説の理論』は、確かに「世界の崩壊とその不完全さ」や「世界構造の脆弱性」に言及するものの[3]、この黙示録的なテーマはあくまで理論の周縁に留め置かれた。
この弱点を修正するために、私は冒険の形式の裏面に、もう一つの別の形式を想定したい。それを今「絶滅の形式」と呼ぼう。その前駆的形態はやはりセルバンテスの作品に認められる。
アルジェでの捕虜生活から解放された帰還兵セルバンテスは、『ドン・キホーテ』で名声を得る以前の一五八〇年代に、紀元前二世紀のスペインを舞台とする歴史劇の傑作『ヌマンシアの包囲』を書いた。小スキピオ率いるローマ軍に包囲されたスペインの都市ヌマンシアは、飢餓と病気が蔓延し、すでに勝利の見込みをなくしている。そのとき、占領の恥辱を受けることを潔しとしないヌマンシア人は、すべての財産を燃やし、家を焼き払い、街の全員を自ら殺戮し、統治者も自ら火中に身を投じることを決断した。その結果、スキピオ将軍の部下の報告によれば「ヌマンシアは赤い血の湖と化し、みずからの苛酷な決断によって殺された無数の死骸に埋まっています。彼らは恐怖をかなぐり捨て、迅速な大胆さを発揮して、他に類を見ないほど重くも辛い隷属の鎖から逃れることができたのです」[4]。
これはまさに自分自身に対して行使されたジェノサイドである。後の『ドン・キホーテ』は汲めども尽きぬ旺盛な語りの力によって、幻想の解体と再生産を推し進めた。逆に、古代ギリシア演劇にも通じる風格をもつ『ヌマンシアの包囲』は、そのようなアイロニカルな「語り」そのものを殲滅する過酷な暴力性を前景化する。ヌマンシア人の迅速にして徹底した自己破壊は、ローマ軍の勝利すら空虚な敗北に変えてしまう。「ヌマンシア人は、みずからの敗北から勝利を引き出しました。驚嘆すべき意志と志操の固さを発揮して、将軍の手から勝利を奪い去ったのです」[5]。つまり、この作品の根幹には、都市の絶滅だけが解放=勝利につながるという恐ろしい逆説がある。
この勝利と敗北の反転は、後の『ドン・キホーテ』では狂気とユーモアによって遂行される。ラマンチャの憂い顔の騎士は、語りによって事象を引き延ばしながら、外見的にはみじめな敗北を勝利として解釈する。他方、戯曲『ヌマンシアの包囲』のジェノサイドは、一切の遅延や躊躇なしに、既定のプログラムとして粛々と実行された。『ドン・キホーテ』が近代小説の祖だとしたら、『ヌマンシアの包囲』で作動する自己破壊のプログラム(フロイトふうに言えば「死の欲動」)は、近代小説に先立つおぞましい原風景と呼べるものである。セルバンテスにおいて、冒険と絶滅はコインの裏表の関係にあった。
2、物質の目のインストール
前進的な「冒険の形式」の裏面に潜む不気味な「絶滅の形式」――それは一八世紀の小説では閉域のイメージとともに表面化してくる。特に、ともに無人島を描いたデフォーの『ロビンソン・クルーソー』とルソーの『新エロイーズ』には、この形式の強い効果を認めることができる。
クルーソーの島は人類絶滅後の世界を思わせる。難破船から運び出した文明の遺物を利用しながら、島での狩猟・採集によって生活するクルーソーは、まるでポスト・アポカリプス的世界の生存者のように見える。かたや、『新エロイーズ』のサン゠プルーは無人島になぞらえられるエリゼの庭で、ジュリの痕跡を収集して恍惚となる。ジュリは無数の植物に投影されたVRの分身となって、サン゠プルーを魅了した(前章参照)。
いずれの「島」でも主人公以外の人間はいったん事実上絶滅するが、それがかえって、豊かな自然のモノたちの産出する実益や記憶を際立たせた。クルーソーもサン゠プルーも、社会が死に絶えた場所に没入し、無数のモノから快楽を引き出す。そのとき、彼らの島は他者の「体内取り込み(incorporation)」と、つまり身体的な次元での「所有」と結びつけられた。島は身体と同じく、ともに境界で区切られた閉域として表象される。「私であること」(存在)を「私がもつこと」(所有)とリンクさせること――それがデフォーやルソーの仕掛けた戦術であったと言えるだろう[6]。
もとより、この両者の想像力に質的な差異があるのも見逃せない。プロテスタントの家系のデフォーが、植物をもっぱら生存の道具とし、その「使用価値」にアクセントを置いたのに対して、少年時代にジュネーヴを出奔した直後「自分の宗教を売って」カトリックに改宗したルソーは、植物に聖なるものの面影を与えた[7]。それでも、生身の他者をキャンセルしつつ、モノの所有を推進させる無人島を物語の中枢に設けたことに、変わりはない。
そもそも、啓蒙(光)の世紀と呼ばれる一八世紀の思想は、人間以外の存在者にもあまねく認識の光を当てようとした。この百科全書的な欲望に駆動されて、人間をその一部とする広大な物質世界が、啓蒙思想の中枢に入り込んだ。バーバラ・スタフォードの大部の研究によれば「人間という要素の拭い去られた世界を回復したいと願う一八世紀的感性」は、古代ローマの学者プリニウスの衣鉢を継ぐ博物学によって推進されたが、そこには「人間の目」ではなく「物質の目」で世界を観察しようとする態度がある[8]。
特に、ディドロのすばらしくユニークでユーモラスな対話篇『ダランベールの夢』(一七六九年執筆)は、まさに物質の目のインストールを企てる一八世紀的唯物論の好例である。ディドロの盟友の哲学者ダランベールのつぶやく寝言に即興的な夢分析を施すうちに、この対話篇は「感性ある物質」が集合し、蜘蛛の巣(ウェブ)の形状をとるという斬新なヴィジョンへと到る。微小な物質にもそれぞれの感覚があるとすれば、人間はもとよりポリープや土星ですら感覚(心)をもつのではないか[9]――そう面白おかしく問いかけるディドロの哲学的なギャグは、唯物論が汎心論(すべての物質に心の可能性を認める哲学)に到る軌跡を見事に描き出していた。
3、モノと数字――サドのアルゴリズム
神と人間をともに脱中心化する一八世紀の唯物論的思想――それをいっそう過激化したところに、マルキ・ド・サドの異様な小説が現れる。サドはまさに「絶滅の形式」の極限を示す作家であった。
バスティーユ牢獄に収監されたサドが、一七八五年に巻紙に蟻の字で書き継いだ『ソドムの百二十日あるいは淫蕩学校』――その巻紙は紛失し、サドを大いに悲しませたが、二〇世紀になって奇跡的に発見・刊行された――では、戦争の相次いだルイ一四世時代の末期(一八世紀初頭)を舞台に、リベルタンたちのおぞましい性的ゲームが繰り広げられる。哲学者のリーダーであったヴォルテールが太陽王ルイ一四世の偉業を称え、当時の学問・文化・芸術の進歩を強調したのとは逆に、啓蒙思想の鬼子サドはむしろその時代に、汚職と放蕩に興じる悪人たちをはびこらせた。
サドは性的倒錯を設計することに、尋常ではない力量を発揮した。『ソドムの百二十日』では四人のリベルタンが共謀し、森の館に四十二人の男女を集め、四人の熟練の放蕩女の語る「物語」を脚本として、カレンダー方式で日々規則的に乱交と虐殺を上演し続ける。この演劇的な世界は、「四」というシンメトリカルな数字を基礎とする厳密なアルゴリズム(計算手順)によって作動する。凄腕のエンジニアとしてのサドの設計には、エラーもバグも生じない。サドのテクストは外的には規範からの逸脱だらけに見えるが、内的には規則からの逸脱が一切起こらないのである。
そのため、ロラン・バルトが指摘したように、気の毒な被害者のみならず加害者の悪人たちも、『ソドムの百二十日』ではベルトコンベアー式の機械の「歯車」となる。サドの固執する「数量的計画」は、あらゆる人間をオートマティックな機械的運動の精密な部品に変えてしまう[10]。醜悪きわまりないリベルタンたちは、フランソワ・ラブレーのカーニヴァル小説にも通じるグロテスクさを誇示するが、彼らの文字通り変態的な身体も、決して停滞することのないサドの繊細で肌理細やかな文体――それは同時代のモーツァルトの音楽すら想起させる――においては、厳密に数量化されたプログラムに還元される。サドは倒錯や暴力、乱交や醜悪さにぎょっとする良心を、なめらかなコード進行のなかで、教育し矯正しようとするのだ。
この異様なサド的教育学は、生気溌溂とした三六歳の美貌の無神論哲学者ドルマンセが雄弁に語る『閨房の哲学』(一七九五年)で徹底される。ドルマンセの文化人類学的な見解によれば、ヨーロッパ人の考える「美徳」はたかだかローカルで特殊なものにすぎない。「すべては自分が住んでいる場所の風俗とか風土次第だ」。より普遍的なものは《自然》の理法なのであり、特にその破壊のプログラムに全面的に従うことをドルマンセは要求する。
破壊は自然の基本法の一つなんだから、どんな破壊であっても犯罪になどなるもんか。これほどよく自然に仕える行為が、どうやったら自然に反することになるんだい。それに、人間はうぬぼれて破壊なんて言ってるけど、そもそもそれが間違いなのさ。殺人は断じて破壊ではない。殺人を犯す者は、あくまで形態を変化させるだけだ。[11]
ディドロの描くダランベールは「死ねば、無数の分子となって作用し反作用する。……いったい僕は死なないのか?……いや、確かに、この意味では、僕もどんなものも死にはしない。……生まれ、生き、滅びるとは形を変えることだ」とぶつぶつ寝言をつぶやいていた[12]。サド=ドルマンセは、このディドロ=ダランベール的な唯物論の夢を額面通りに受け取り、殺人も哲学的に正当化するのだ。
こうして、数値化された倒錯のアルゴリズムを設計し、ジェノサイドも厭わないサドは、近代の「無人島」の作家たちの極北に位置している。海を忌避したサドの小説は、偶然性を生じさせる外部との出会いを欠く。彼は確かに、書簡体小説『アリーヌとヴァルクール』でポルトガルやアフリカ等の諸外国を描き、『食人国旅行記』ではアフリカから南太平洋に到る架空の国――そこは牢獄も死刑も廃止されたユートピアとして描かれる――を登場させたが、これらの旅行がサドの哲学を揺るがすことはない。「旅行が多様であっても、サド的な場はただひとつである。これほど多く旅行するのは、ただ閉じこもるためにすぎないからだ」(ロラン・バルト)[13]。
してみると、サドを閉じ込めたバスティーユ牢獄は、反冒険的な作家にふさわしい執筆の場であったと言えるだろう。サドは冒険を最小限にとどめる代わりに、《自然》の名のもとにヨーロッパの美徳を相対化し、無人島的空間で「破壊」のプログラムを徹底させた。外部とのアクセスを遮断したサド的な閉域においては、数値的にコントロールされたモノたちが永久運動を続ける――この倒錯的な絶滅の情景には、近代小説のダークサイドが露呈していた。
4、中国文学における物質的転回――『金瓶梅』から『紅楼夢』へ
ところで、ここで強調されるべきなのは、絶滅の形式がヨーロッパ小説の専有物ではなかったことである。特に中国文学はサドに先んじて、早くも一六世紀末に『金瓶梅』という異例の小説を生み出した。『水滸伝』の一エピソードを拡大した『金瓶梅』は、明末の消費社会の爛熟を背景とするデカダン小説であり(第四章参照)、そこでは絶滅の中国的形式が鮮明にされた。
家族(特に母と娘)の絆を徹底して解体しようとするサドのリベルタン小説とは異なり、『金瓶梅』ではむしろ家庭こそが性愛の舞台に定められた。主に三人の女性たちを相手に、性的放蕩に明け暮れる商人の西門慶を主人公とする『金瓶梅』は、市民の家庭生活をきわめて細密に再現した点でも先進的であり、中国の小説におけるブレイクスルーとなった。そのハイファイな記述によって、西門慶の家庭はまさに物質の天国に仕立てられる。
近年のアメリカの中国文化研究者たち(クレイグ・クルナス、李惠儀、ソフィー・ヴォルップ……)は、近世中国における「物質的転回」(material turn)に光を当ててきたが、膨大なモノが描かれる『金瓶梅』はその最も範例的なテクストと見なされている。『金瓶梅』の家庭はサド的な森の閉域ではなく、むしろ都市の消費文化のネットワークの一部として描かれた。西門慶の家に集合するモノたちは、商品として消費のサイクルに組み込まれている。西門慶の主張によれば、モノは流動を好み、静止を好まない(第五六回)[14]。このモノの絶えまない流動性が、人間の欲望をも動かし続けるのだ。
こうして、人間とモノの相互関係を深めた『金瓶梅』では、物質世界のなかから意識が生じてくるように見える[15]。ヨーロッパの近代小説が「内面への旅」を深化させたのに対して(その極限がジョイスやウルフらのモダニズム小説である)、中国小説は総じてモノとのインターフェース(接合面)において、意識を組織した。その結果、『金瓶梅』ではしばしば、人間とモノのあいだの厳密な区別がなくなる。衣装、靴、宝石、はてはセックスの道具に到るまで、すべてが値付けされて計算可能になるとき、西門慶や女性たちもまた脱人間化され、モノと同等の存在に変容するだろう[16]。
しかも、この物質的繁栄を消費し尽くそうとする貪欲さは、やがて西門慶を荒涼とした死の世界へと滑落させる。仏教的な「空」の概念を支柱とする『金瓶梅』では、後の『紅楼夢』と同じく「満ちていること」(fullness)と「空虚であること」(emptiness)が背中あわせになっていた[17]。ここで重要なのは、このデカダン的な空虚さが、時の王朝(宋)の衰退とパラレルであったことである。西門慶の性的欲望の充溢は、やがて国家とともに不毛に終わる運命にあった。
ヨーロッパ小説がときにサド的な無神論に接近しながら「絶滅の形式」をあらわにしたとすれば、中国小説は国家の興亡の歴史に根ざした「滅亡の形式」に導かれたと言えるだろう[18]。『三国志演義』や『水滸伝』は、国家の衰退とともに、往年の英雄や好漢が死に絶えるところで終わる。それは男たちを結びつける古い人倫の世界、つまり(『三国志』冒頭の劉備・関羽・張飛の「桃園結議」に象徴されるような)「侠」の世界の終焉に等しい。このような国家と人間の運命的なシンクロニシティは、一見して国家と深い関係をもたないように思えるドメスティックな『金瓶梅』でも繰り返された。
さらに、この「滅亡の形式」は、『金瓶梅』の後継作と呼ぶべき『紅楼夢』でも強力に作用した。この二つの小説は個人のプライヴェートを詳細に描いた点で画期的であったが、『水滸伝』をアレンジした『金瓶梅』が野性的であり、露骨に性愛を語ったのに対して、一八世紀の曹雪芹による『紅楼夢』は、むしろ中性的な賈宝玉および純潔の少女たちを中心として、ロココ的な洗練を際立たせた。マーティン・ホアンの表現を借りれば、これは物質的な「欲」からセンティメンタルな「情」への美学的転換を示すものだろう[19]。剥き出しの性的欲望を磨き上げ、陶冶し、繊細な「情」に変換すること――それが『紅楼夢』で作動しているプログラムである。
この美学化のプログラムは、中華文明のテーマパークのような豊富な物質世界を糧としていた。『金瓶梅』の家庭内のモノたちが、消費のサイクルのなかで運動し、個人の所有には属さないのに対して、『紅楼夢』の母性的な大観園では、モノは特定のキャラクターに固く紐づけられ、洗練されたコミュニケーションのゲームの一部となった[20]。ジェンダーのカテゴリーを超え出る賈宝玉は、まさにその名の通りに「宝玉」と不可分なのだ。この物質的なユートピアにおいては、儒教の男性中心的な価値観は反転させられる。『紅楼夢』は同じく一八世紀の諷刺小説『儒林外史』と並んで、まさに「儒家文化を精神分析のソファに座らせた」小説と評するにふさわしい[21]。
ただ『金瓶梅』と同じく、『紅楼夢』の物質的繁栄もその内部に空虚を孕んでおり、永遠のユートピアと思えた大観園も最後には崩壊する。『西遊記』を例外として、中国小説の代表作には「滅亡の形式」への強烈なオブセッションがあり、繁栄と絶滅はコインの裏表の関係にあった。だからこそ、『水滸伝』や『紅楼夢』の続書(二次創作)の多くは、原作の暗さを反転させた明るいハッピー・エンディングを志向したと言えるだろう。
5、社会の自己破壊――デフォーの『ペスト』
このように、『金瓶梅』と『紅楼夢』は家庭の内部にくまなく照明を当て、豊富な物質世界から「滅亡」のテーマを浮上させた。このドメスティックな中国小説との対比として、一八世紀のヨーロッパ小説が、初期のグローバリズムを背景とする絶滅の形式を作動させたことに、改めて注意しておこう。その例として、デフォーの『ペスト』とスウィフトの『ガリヴァー旅行記』が挙げられる。
一六六五年にロンドンを襲った疫病を題材とする『ペスト』(一七二二年/原題は『疫病の年の日誌』)は、感染爆発から都市のロックダウン、疫病の収束に到るプロセスをきわめて詳細に書き記した。それまでヨーロッパの交易の拠点として繁栄を謳歌し、人口が爆発的に増加していたロンドンは、ペストが急速に広がるなか、封鎖されて陸の孤島となった。デフォーはボーダーレスな世界に病原体が寄生したとき、おぞましい災厄に到ることを示したのだ。
ロンドン市民の監禁は、明らかに無人島のクルーソーの監禁と通底している。ただし、クルーソーが入植者として海外に船出し、島の主人になったのと違って、ペストは逆にロンドンを植民地として占拠してしまった。この観点から言えば、『ペスト』は『ロビンソン・クルーソー』の植民地主義的な欲望を逆流させた自己批評的な小説として解釈できる。
興味深いことに、『ペスト』の構図には、一九世紀末のブラム・ストーカーの『ドラキュラ』(一八九七年)やH・G・ウエルズの『宇宙戦争』(一八九八年)を先取りするような「反転した植民地主義」が認められる。ストーカーやウエルズは、海外に植民地を築いた大英帝国の繁栄を反転させて、不気味なエイリアン――吸血鬼や火星人――に侵略され、その繁殖の場に変えられてしまうロンドン市民を描いた(そこにはアジア由来のコレラのパンデミックの記憶も投影されている)[22]。他者を所有してきたイギリス人が、逆に他者に所有され、むさぼり尽くされること――この忌まわしい反転はデフォーの『ペスト』にあらかじめ書き込まれていた。
そもそも、ディドロやアダム・スミスによれば、ヨーロッパの植民地化は合理的に計画されたものでなかった(第七章参照)。この自己拡大の偶発性は、自己のあるべき姿を見失う危険な漂流を伴っていた――中流階級出身のクルーソーやガリヴァーの冒険が、たえず予測不可能なアクシデントにさらされていたように。「新世界」への入植は、かえって「旧世界」ヨーロッパの文化を脅威にさらすという一面があった。デフォーの『ペスト』はこの近代ヨーロッパの根幹にある偶発的な自己喪失・自己破壊のリスクを、疫病のテーマに即して顕在化させたと言えるだろう。
後年のサドの性的倒錯が「自然」の名のもとに人間どうしの共感を徹底して否定し、絶対の基準として君臨したように、ペストも自然の摂理の導くままにロンドンを強制収容所に変え、人間を絶滅寸前に追い込んだ。前出の『閨房の哲学』のドルマンセは「この世で危険なものはね、憐れみと慈善の二つだけだよ。人にやさしいというのは、どんな時も一つの弱点でしかない」と傲然と言い放つが[23]、ペストはまさにサド=ドルマンセふうの反共感の哲学の忠実な実行者にほかならない。デフォーとサドの文学から分かるのは、人間に対する徹底した《無関心》が、一見して人間中心主義的に思える近代文学には潜伏していたこと、しかもこの非人間的な冷淡さによって、一切の希望のない情景が驚くほどの高解像度で記述されたことである。
『ペスト』の最大の特徴は、何よりもその書き方にある。デフォーは統計データをしきりに引用し、死者数や死亡率の日々の推移を詳細に記した。サドのカレンダー方式にも通じるこの書式は、「人間の目」ならぬ「ペストの目」で見られた世界を感じさせる。ペストが個体識別することなく大量の人間を淡々とモノ(死体)に変えてゆくのに応じて、デフォーも固有名を徹底的に消去し、死を統計的な数値に還元する。人間は人口に変換される。語り手の名前すら「H.F」という匿名的な記号で表示されるだけなのだ[24]。
このような死の数値化は、諸個人に顔を与える社会の崩壊と一対になっている。デフォーはロンドン市民の怠慢、教会の腐敗、インチキな便乗ビジネス等を次々と再現するが、それらの堕落はもともと社会に内在していて、ペストをきっかけにして可視化されたものである。つまり、ペストそのものというより、ペストから浮かび上がる脆弱な社会構造が、この小説の核にある。特に、デッド・カート(死体運搬車)で運ばれた死者を葬る大穴に、生者まで飛び込むという錯乱的な集団自殺のシーンは、まさに社会の自己破壊を象徴している。
このような穴に衆人が近づくのを禁止ずる厳重な法令が出ていたが、それはもっぱら病気の感染を防ぐのを主眼としていた。しかし、時日がたつにつれて、この法令はいっそう必要なものになってきた。なぜなら、病気に冒された人間で、死期が近づき、そのうえ精神錯乱をきたした者たちが、毛布とか膝掛けとかをまとったまま穴のところに駆けつけ、いきなり身を投じて、いわば、われとわが身を葬るからであった。[25]
もとより、冒険的要素をもたない『ペスト』は『ロビンソン・クルーソー』とは違って、典型的な小説とは見なされてこなかった。しかし、私の考えでは、絶滅のテーマを留保なく進めた『ペスト』はサドの作品群と並んで、近代小説のダークサイドを最も大胆に開示した重要な作品である。『ロビンソン・クルーソー』と『ペスト』、植民地主義とその反転、個人の文学と統計の文学、冒険の形式と絶滅の形式――この双極性こそが小説の世界認識を特徴づけている。
6、倒錯的な量的世界――スウィフト『ガリヴァー旅行記』
『ロビンソン・クルーソー』への自己批評と呼ぶべき『ペスト』からほどなくして、一七二六年にスウィフトの『ガリヴァー旅行記』の初版が刊行される。この奇怪な旅行小説は、一八世紀の初期グローバリゼーションを背景として、人間の可変性や可塑性を誇張的に示した。
イングランドの政治を批判する一方、故郷のアイルランドをも罵倒した非妥協的な著述家らしく、スウィフトはまさにルカーチ流の故郷喪失者としてガリヴァーを描き出した。海に出ることを「運命」と感じて、医者として船に乗り込んだガリヴァーは、何度も冒険と漂流を繰り返し、そのつど新たな国家に接触しては、ヨーロッパとは異質の文化的習慣を「ありのまま」に記録しようとする。そこには、人間はいかようにも変化し得る動物だというスウィフトのクールでシニカルな認識があった。
周知のように、ガリヴァーは第一部では小人国リリパットに漂着し、自身の十二分の一サイズの王侯貴族に歓待されるが、第二部では大人国ブロブディンナグで、十二倍の巨人に小さな玩具のように扱われる。第三部では、飛行島ラピュタ(ラプータ)から日本の長崎に到る多くの土地が登場した後に、第四部では奇怪な「馬の国」が舞台となる。そこでは「フウイヌム」と呼ばれる理性的な馬たちが特定の支配者をもたず「集会」によって政治を進める一方、人間は下等な「ヤフー」として使役されている。馬の国にすっかり魅せられたガリヴァーは、ヤフーの皮(!)でカヌーを製造して帰国し、妻子と再会した後も、人間の体臭に耐えられず馬たちと暮らす。
人間の象徴的な優位性をさまざまな手口で失墜させること――それが『ガリヴァー旅行記』を貫く明晰な悪意である。それは究極的には、ジェノサイドの構想にまで到るだろう[26]。馬の国のフウイヌムは理性の命令に従って、人口を完璧にコントロールする一方、醜悪で悪辣きわまりないヤフーを地上から絶滅(exterminate)させるべきか否かを議論する(第四部第九章)。ちょうどデフォーの『ペスト』と同じく、スウィフトの馬の国でも固有名は蒸発し、生物は操作可能な量に還元される。『1984』の著者ジョージ・オーウェルは『ガリヴァー旅行記』の第三部に相互監視的な警察国家のモデルを認める一方、第四部の「馬の国」を順応主義がすみずみまで行き渡った全体主義体制の予告編と見なし、ヤフーをナチス・ドイツ統治下のユダヤ人になぞらえたが[27]、それもあながち突飛な解釈ではない。
そもそも、『ガリヴァー旅行記』は子供向けにも思える前半から、すでに人間の量的操作を実行していた。『ペスト』や『ソドムの百二十日』がいわばエクセルのように犠牲者の数値的データを記録したとすれば、『ガリヴァー旅行記』はいわばフォトショップのように図像のサイズを伸縮させた。リリパットでは人間と動植物の「比率(proportion)」が正確に決められている(第一部第六章)。ブロブディンナグでは万物のサイズが大きくなった結果、その図像の解像度も変わり、シラミが異様に拡大され、女性の皮膚の気味悪くでこぼこした様子がクロースアップされるのだ(第二部第五章)。
かつて批評家の花田清輝が鋭く指摘したように、『ガリヴァー旅行記』の認識と論理は「量的把握という一事につきる」。ガリヴァーの旅行は「量的変化をみちびきだすための力学的位置変化」であり、そこには「人間の質のみを強調するルネッサンス以来の人間主義にたいする批判」が含まれる[28]。この比率の操作された量的世界においては、シラミや皮膚のような平凡なものが平凡なままで吐き気や嫌悪感を催させる[29]――それがフォトショップ的な比率変更の効果なのだ。スウィフトはある意味ではデフォーやサド以上に徹底した悪意によって、倒錯的な量的世界を描き出した。
さらに、第三部では、テクノロジーの進歩への夢が批評される。天然磁石の力で飛ぶラピュタの住民は、数学と音楽に熱中して周囲を顧みず、ガリヴァーの存在には無関心である。この冷淡なラピュタを去ってバルニバーニの首都ラガードに赴いたガリヴァーは、さまざまな新規プロジェクトを推進するグランド・アカデミーを見学する。そこで「思弁的学問」の自動化を企てる教授は、まるで二一世紀の生成AIの研究者のように「どれほど無知な人間でも、費用も手ごろ、多少の肉体労働を行なうだけで、天賦の才や勉強の助けをいっさい借りずに、科学、詩、政治、法律、数学、神学に関する書物を著すことができるのです」と豪語し、百科全書を自動生成する機械を披露する。
表の面には、おおよそ骰子の大きさの――ただし一部はもう少し大きい――木片が並び、細い針金でたがいにつながっています。どの木片も、すべての面に紙が貼られ、それらの紙に、この国の言語の全単語が書いてあります。あらゆる時制、語形変化、直接法や仮定法等々すべての叙法も網羅していますが、ただし順番はバラバラになっています。[30]
この木片の並んだ装置を弟子たちが回転させると、そのつど新たな文が出力される。単語を網羅的にデータ化し、その膨大な順列組みあわせを試して、あらゆる分野の書物を自動生成する機械――それはAIの夢を先取りするものだろう。
この教授をはじめ、ラガードの学者たちは人間の労力を減らすための「進歩」に駆り立てられているが、それをスウィフトは諷刺的に描いている。オーウェルが注目したように、第三篇で描かれるプロジェクトが、言語の全体主義的なコントロールに通じることは確かだろう。『ガリヴァー旅行記』では、人間のみならず言語も量的なものであり、いかようにでも操作され変形される。
その後、ガリヴァーは降霊術を用いるグラブダドリッブ島で、偉人の亡霊(ホメロス、アリストテレス、デカルト……)に出くわした後、ラグナグ島で「ストラルドブラグ」と呼ばれる不死の人間たちを目撃するが、彼らは老醜をさらけ出し、身体も思考能力もむざんに衰え切っている。死ぬに死ねない不気味なゾンビのような不死人間たちは、長寿のおぞましさをその全身で表現していた。『ガリヴァー旅行記』において、ポストヒューマンな人工知能と不死の身体は、ときに滑稽で、ときにグロテスクなものとして描き出される。
すでに『ガリヴァー旅行記』に先立って、ライプニッツとニュートンが近代科学の礎を築いていた。スウィフトの驚くべき先進性は、この科学の欲望の帰結――人工知能からアンチエイジングまで――を見通し、諷刺の対象にしたことにある。後にゲーテが『ファウスト』で描いたように、近代の知的冒険はいずれ、人間の枠組みを超越したポストヒューマンな存在を生成するだろう。世界の量的操作をアカデミックな「プロジェクト」に仕立てた『ガリヴァー旅行記』の第三部は、この超越の運動が希望のない世界に到ることを暗示していた。
こうして、『ガリヴァー旅行記』の読者は馬の国で悪辣なヤフーに出会う前に、身体・知能・言語が可塑的なものであり、いかようにでも作り変えられるというクールでシニカルな認識を何度も突きつけられる(この人間の可塑性を全体主義的支配の前提と見なしたのが、後のオーウェルの『1984』である)。人間の象徴的な優位性をしつこく転覆するスウィフト的な教育――その極限に、ヤフー=人間を物理的に「絶滅」させようとする忌まわしい議論が現れるのだ。
7、ゾンビから熱的死へ――E・A・ポーの『ピム』
一八世紀のデフォー、スウィフト、サドはそれぞれ小説に絶滅の形式を埋め込んだが、一九世紀になると、この形式はいわばヨーロッパ文化の私生児と呼ぶべきアメリカやロシアの小説にリレーされる。ここでは特に、E・A・ポーとドストエフスキーという両国の巨匠を例にとろう。
アメリカのポーは、恐るべき「絶滅」の情景をオブセッシヴに反復した作家である。異様な恐怖に囚われたロデリック・アッシャーが自邸もろとも沼に沈む「アッシャー家の崩壊」にせよ、ペスト(黒死病)をモチーフとした「赤死病の仮面」にせよ、一八四〇年前後のポーの小説では、威厳を備えた秩序を、あっという間に解体する黒々とした力が働いていた。破局的な絶滅の情景を前にしたとき、人間は蜃気楼のようにはかない幻覚にすぎない。
だが、それだけではない。というのも、ポーの小説には、すっきりと消滅し損ねることの恐怖も内包されていたからである。それは、生前の死ないし死後の生に対するポーのオブセッションとして現れる。例えば、生きながらに埋葬された男(「早まった埋葬」)、肉体的には死んでいるのに、催眠術のせいで意識だけが生に取り残されてしまった男(「ヴァルドマアル氏の病症の真相」)、息をなくしてうろたえる男(「息の喪失」)……。これらは正しく死に損なった人間、あるいは死んでも死にきれない人間である。しかも、猶予された死がついに訪れたとき、彼らはアッシャー家のように迅速に消滅してしまう。
もとより、人間とはある意味で誰しもが死に損ないであり、誰しもがサヴァイヴァー(生き残り)である。ポーはその側面を拡大して、生と死の境界線が融解してしまうことの恐怖を強調した。ゆえに、ポーの小説がしばしばゾンビ的な形象を伴ったのも不思議ではない。
そもそも、ゾンビとは何か。マキシム・クロンブの秀逸な評論によれば「ゾンビは人間のカリカチュア」であり、強烈なショックによるトラウマで「外的世界に対して広く無感覚になってしまった」主体である。「感情も意図も持たない、最小限まで縮減された主体」としてのゾンビ[31]――それは予期せぬ事故やトラブルにさらされ、そのショックで呆然自失となってしまった近代人の戯画である。
ポーの最長の長編小説『アーサー・ゴードン・ピムの冒険』(一八三七‐八年)にはまさに無感覚なゾンビ的存在、つまり外見だけ人間のふりをしている「肉」が現れる。主人公のピムは冒険心に導かれて、捕鯨船の船倉に忍び込むが、その船で黒人の料理番らの反乱が起こったため、予定された助けを得られなくなり、密室に閉じ込められる。生きながらに埋葬され、感覚麻痺の状態に陥った彼の恐怖は、まさにポー的な「生前の死」の典型と言えるだろう。
その後、ピムは仲間とともに船の支配を奪うものの、今度は船のトラブルのために恐るべき飢えと渇きに直面する。そのとき、彼らの眼前に船が現れる。ピムたちは天の助けと歓喜の声をあげるが、その船は実は疫病のせいで全滅しており、遠目には船員の動きと見えたものは、カモメについばまれる人肉のダンスであったことが判明する。
その一切れを食いちぎられたもとの死体は、例の通り、ちょうど綱の上に膝をつく格好のまま、それまであの肉食鳥がせっせとついばむたびごとに、苦もなくからだを前後にゆすぶっていた。だから、さっき、われわれがてっきりそいつのことを、生きているものだとばかり思いこんだのは、そういう動作のせいだったのだ。〔…〕両眼はなく、口のまわりの肉はすっかり食い取られて歯がむきだしになっていた。と、すれば、われわれに元気をつけて希望を持たせたあの笑顔というのはこれだったのだ![32]
この凄惨にして悪趣味な「死後の生」の情景は、後年のゾンビ映画を先取りするものだろう。ポーはピムの「冒険」のなかに、人間がおぞましい肉に変形されるアポカリプス的な「絶滅」を組み込んだ。『ピム』には野蛮を象徴する食人のシーンまであるが、そこには「人間的なもの」を絶滅させようとするポーの悪意がうかがえる。
さらに、彼らは相次ぐショックと漂流の果てに、ついに白以外には何もない南極のモノトーンの世界へと導かれる。出来事がほとんど何も起こらず、白い獣の死体が漂うばかりの荒涼とした世界で、ピムたちの感覚はすっかり麻痺し、生ける屍と化す。そのとき、彼らはあらゆる人間的なものの絶滅を体現するようなモノトーンの巨人と出会う。
その瀑布には、われわれを迎え入れる割れ目が開いていた。だがわれわれの行く手には、凡そその形が比較にならぬほど人間よりも大きい、屍衣を着た人間さながらのものが立ち塞がっていた。そしてその人間の姿をしたものの皮膚の色は、雪のように真っ白であった。[33]
ゾンビから「雪のように真っ白な巨人」へと到る絶滅のプロセスによって、ポーはいわば熱力学で言うところの熱的死、すなわちエントロピーが最大化し、完全に均一になった静止状態を思わせる情景を描いた(ちなみに、熱力学の法則が整備され始めたのは、ポーの死の直後の一八五〇年代である)。ポー的な絶滅の形式は、純粋な「白」によって完成する。後のメルヴィルの『白鯨』は、この『ピム』の荒涼とした《世界の終わり》に再び《世界》をインストールする試みとして解釈できるだろう。生から滑落しかかっているイシュメールは、真っ白な巨人ならぬ白い鯨――フィジカルにしてメタフィジカルな世界――を発明し、かろうじて生き延びるのだから。
8、死と生の量子的な重ねあわせ――ドストエフスキーの初期小説
さて、ポーは一八四九年に早世したが、ちょうどその年に銃殺直前の極限状態に追い込まれ、シベリアに流刑されたのがドストエフスキーである。この強烈な臨死体験、つまり死と生が衝突し一つに結晶化した状態は、彼の文学の本質とも深く関わっている。なぜなら、ミハイル・バフチンが指摘したように、ドストエフスキーはがけっぷちに面した「土壇場」の生を、常に語りの原動力としたからである[34]。
この死と生の重ねあわせは、一八四六年のデビュー作『貧しき人々』において早くも認められる。この小説は、中年の善良なマカール・ジェーヴシキンと文学少女ワルワーラ・ドブロショロワの往復書簡として書かれた。書簡体小説は当時すでに時代遅れのスタイルであったが、ドストエフスキーは不器用だが直接的な語りを表現するのに、あえてこの一八世紀的な書式を採用した。
マカールの文章は未熟であり洗練されていないが、しばしば発作的・衝動的に突き進む。「何か話し出したら、夢中になってとんでもないことを口走ってしまうこともあるんです!」。しかし、熱中して手紙を書いても、ふと我にかえるとそこには「灰色にくすんだ」現実があるばかりだ。「我々だって、昔は何でもくっきり見えたんです。ああ、年は取りたくないものですよ」[35]。この視野の狭さは、『貧しき人々』のリアリティの地盤があくまで主観にあることを示している。マカールとワルワーラを取り巻く社会は、堅固な実体ではなく、手紙のやりとりから間接的に浮かんでくるだけである。
このような社会の希薄さは、作中の「貧しき人々」の生のはかなさとも共振している。彼らはほんの些細なきっかけで死へと急転してしまう。例えば、ワルワーラの家庭教師で、プーシキンを愛読するポクロフスキーは、生来虚弱であり、肺病のためにあえなく死んでしまう。マカールの隣人もまた「まるで雷にうたれたように」ぽっくり亡くなるのだ。
その一方、彼らはまさにその貧しさゆえに神経過敏で饒舌である。マカールによれば「貧しい人々というのは、わがままなものです〔…〕世間を見る目も一風変わっていて、通りがかりの誰のことでもじろりと横目で睨むし、不安げな視線をそこらじゅうに投げかけては、何か自分のことを言われていやしないかと一言一句聞き漏らしません」[36]。
ドストエフスキー的な「貧しさ」とはたんなる経済的困窮ではなく、生と死、語りと欠乏がいわば量子的に重なりあい、一個に結晶化した状態を指している。彼らは手元にほとんど何ももたないからこそ、すべてを神経症的に語り尽くそうとする。ゆえに、『貧しき人々』のエンディングに「絶滅」の情景が呼び覚まされることも不思議ではない。マカールが徐々に手紙を書くことに習熟し、その「文体も体をなしつつある」、まさにそのときにワルワーラは夫とともに「ただの曠野、木一本生えていない剝き出しの曠野」に赴くことになるのだ[37]。語りの完成(生)は、曠野の到来(死)と重ねあわされる。
さらに、ドストエフスキーは『貧しき人々』に続く短篇小説『白夜』(一八四八年)では、絶滅の形式を透明なリリシズムと結びつけた。光と闇を重ねあわせたペテルブルグの「白夜」、その奇跡のような時間帯を背景として、友人のいない孤独な二六歳の青年が、運河のほとりで一人の少女と奇跡的に出会う――この感傷的なロマンスは、人工都市ペテルブルグそのものの見る夢と言うべき様相を呈していた。
ペテルブルグの住民たちは夏の保養地の別荘に旅立ってしまった。取り残された主人公は「ペテルブルグ全体が今にも荒野に変身してしまいそう」という夢想に憑かれるが[38]、これはゴーゴリの『外套』のペテルブルグが、亡霊の徘徊する荒野であったことを彷彿とさせる。ゴーゴリにせよドストエフスキーにせよ、他者が事実上絶滅してしまった都市で、しかも即興的に語り続けずにはいられない語り手を設定した。
たった一人で生きてきた『白夜』の主人公には、語るべきことは何もない。「物語なんて、まるきり何一つないですよ!」。にもかかわらず、この青年は「夢想のなかでありとあらゆる物語」を紡ぎ出してきたことを、見知らぬ少女に告げる。
夢想家とは、詳細に定義づければ、人間ではなく、そうですね、一種の中性的な生き物です。彼は大半の時間、人を寄せつけない片隅で生息し、日中の陽の光さえ避けるように、そこに身を潜めているんです。そして自分の中に閉じ籠るとなったら、まるでカタツムリみたいに、自分の一隅にぴったりと貼りついたようになってしまう。[39]
ルソー的夢想家は多種多様な植物や打ち寄せる波をパートナーとして、自らの主観をたえず生まれ変わらせるインプロヴァイザー(即興演奏家)であった。ルソーの無人島はいわば「無言歌」によって満たされていた(前章参照)。しかし、ドストエフスキー的夢想家は、音楽も鳴らない黙示録的な静寂のなかにひっそりと棲息する「中性的な生き物」であり、その無ゆえにかえって饒舌に語り続けることになる。
9、ポストモダンなゾンビ、モダンな亡霊
社会が音もなく絶滅する一方で、夢想と物語がとめどなく増大してゆく――それがドストエフスキー文学の基本的パターンである。一八六〇年代のヨーロッパ旅行を経て、ブルジョワ社会に対するドストエフスキーの懐疑と敵意は明確なものとなったが(第六章参照)、彼の小説はすでに一八四〇年代の『貧しき人々』や『白夜』において、市民社会への不信を含んでいたように思える。それは、ドストエフスキーの主人公がしばしば亡霊的存在と唐突に接続されることからもうかがえる。
例えば、二人の老女を殺した『罪と罰』のラスコーリニコフは「地中からひょっこり湧いたような」男に突然「お前は人殺し」だと宣告され倒れ伏した後、夢うつつのなかでスヴィドリガイロフに出会う。そして、罪が発覚し、聖書の時代を思わせるシベリアの草原に流罪になった後、人類の絆を断ち切り、お互いを食べ尽くさせる疫病の悪夢がラスコーリニコフを襲う。彼は憂愁にとらわれるが、そこに不意に現れたソーニャによって、新たな生まれ変わりを体験する。ここには、絶滅の悪夢こそが、復活の奇跡を呼び覚ますという構図がある。
このような飛躍がたびたび生じることは、ドストエフスキー文学の社会的ネットワークが半ば故障していることを示唆する。社会が絶滅の可能性にさらされ、あちこちの穴があいているからこそ、ドストエフスキーの主人公は理不尽なまでの唐突さで、転落と救済に導かれるのだ。特に最終場面のソーニャは、現実の人間というより、まさに突然ワープしてきた亡霊的な存在のようにも思える。ゆえに、ラスコーリニコフがソーニャと奇跡的に出会った世界は、そうならなかった世界をもたやすく想像させる。ドストエフスキーの奇跡や救済は、量子的に重なりあった二つの世界から生じるのだ。
ここで重要なのは、ドストエフスキー的な「絶滅の形式」が二重底になっていたことである。たとえペテルブルグの社会が虚妄であったとしても、ドストエフスキー文学の底面には無数の霊を格納したロシアの大地が広がっている。だからこそ、ソーニャやスヴィドリガイロフのような亡霊的他者との接触は、語りの死滅ではなく、むしろラスコーリニコフの新たな語りと新たな人生の条件になるだろう。逆に、E・A・ポーの文学にはこのような受け皿がない。ゾンビ的な他者との忌まわしい遭遇は、言語を絶するものであり、ピムたちに吐き気を催させるだけであった。ドストエフスキー的な大地とは違って、ポーの《海》は、生きる希望そのものをも漂白し根絶させる。
この点で、マキシム・クロンブが言うように、亡霊とゾンビを区別することは有益である。「亡霊とは、生から死への移行を取り巻く規則や規範がはっきりしている世界の産物である。〔…〕それは、過去を現在や未来と結びつける糸を保護するのである」。それに対して、死と生のあいだの修復不可能な亀裂をはっきりさせるゾンビは「生者を食らうために戻ってくる」おぞましい肉の塊、つまりモダンな亡霊をも殲滅するポストモダンな亡霊であった[40]。
ポーがポストモダンなゾンビ小説の先駆者であったとしたら、ドストエフスキーはモダンな亡霊小説の巨匠である。メルヴィルの『白鯨』、ブロンテの『嵐が丘』、ユゴーの『レ・ミゼラブル』も含めて、一九世紀半ばの小説は人間の絶滅した世界から、いかに新たな生を探り当てるかという問いを抱え込んでいた。ポー的ゾンビとドストエフスキー的亡霊は、この「絶滅の形式」から派生する好一対の形象だと考えられるだろう。
10、絶滅の形式の全面化
以上のように、一六世紀末の『金瓶梅』から一九世紀のポーやドストエフスキーの作品に到るまで、小説というジャンルは人間を物質的・意味的に抹消しようとする「絶滅の形式」を反復してきた。ペスト、ヤフー、ゾンビのような形象がたえず意識化してきたのは、人間を人間たらしめる構造の脆弱性である。この強烈な負の意識は、近代小説がニヒリズムと背中あわせの関係にあったことも示している。
特に、一九世紀のロシア小説には、ニヒリズムとの交渉の記録という一面がある。ニヒリズムという言葉を人口に膾炙させたのは、ツルゲーネフの小説『父と子』(一八六二年)である。その主人公である若き医師バザーロフは、「なにものをも尊敬」せず「すべてのものを批判的見地から見る」ニヒリストとして描かれるが、患者には献身的に接し続け、ついに医療体制の不備のせいでチフスに感染し死亡する。その死は一見すると、立派な自己犠牲に思われる。しかし、明晰な頭脳をもつバザーロフに言わせれば、いかに立派な人生もたかだかミクロな「数学的な点」のようなものにすぎない[41]。彼の言動には、人生の無意味さの意識が常に倍音として響いていた。
このニヒリスティックな意識は、やがてフィクションの圏域を超え出てしまう。というのも、二〇世紀の世界戦争とファシズムは、絶滅の形式を社会の全域に浸透させたからである。ベンヤミンが一九三〇年代に早くも指摘したように「芸術は行なわれよ、たとえ世界は滅びようとも」というファシズムの美学を典型として、人類は「自分自身の全滅を美的享楽として体験する」ようになった[42]。戦後になり、ファシズムが表向き凋落しても、この「美的享楽」が途絶える気配はない。誰もが「自分自身の全滅」を容易に想像していることは、戦後のサブカルチャーを見れば一目瞭然である。
アウシュヴィッツとヒロシマの後、人類の絶滅は絵空事ではなく、現実的な危機となった。つまり、二〇世紀半ば以降、絶滅の可能性は文学を超えて、人類社会そのものの形式になったのである。では、このとき、文学は絶滅やニヒリズムのテーマにどう応答したのか――この問題は終章で取り上げたいと思う。
[1]ジェルジ・ルカーチ『小説の理論』(原田義人+佐々木基一訳、ちくま学芸文庫、一九九四年)一一〇頁。
[2]同上、八一頁。
[3]同上、二六‐七頁。
[4]ミゲル・デ・セルバンテス「ヌマンシアの包囲」『スペイン黄金世紀演劇集』(牛島信明訳、名古屋大学出版会、二〇〇三年)六七頁
[5]同上、同頁。
[6]「体内取り込み」の装置としての島の諸形態は、レベッカ・ウィーバー゠ハイタワー『帝国の島々』(本橋哲也訳、法政大学出版局、二〇二〇年)で論じられる。西洋思想における存在と所有の結託については、鷲田清一『所有論』(講談社、二〇二四年)が詳しい。
[7]ピーター・バーガー『聖なる天蓋』(薗田稔訳、ちくま学芸文庫、二〇一八年)によれば、カトリックが聖なるものに連なる多くのチャンネルを備えるのに対して、プロテスタンティズムはこのような「取次」を廃止して、神聖性の範囲を縮減した(一九八頁以下)。これはおおむねルソーとデフォーの差異に対応するだろう。ただし、デフォーの描く道具的なモノも、使用や加工の「快楽」を伴っていたことは見逃せない。Cynthia Sundberg Wall, The Prose of Things: Transformation of Description in the Eighteenth Century, The university of Chicago Press, 2006, p.109.
[8]バーバラ・M・スタフォード『実体への旅』(高山宏訳、産業図書、二〇〇八年)。
[9]ディドロ『ダランベールの夢』(新村猛訳、岩波文庫、一九五八年)三五、四一、五一、五五頁。
[10]ロラン・バルト『サド、フーリエ、ロヨラ』(篠田浩一郎訳、みすず書房、一九七五年)四〇、一七〇、二〇五頁。
[11]マルキ・ド・サド『閨房の哲学』(秋吉良人訳、講談社学術文庫、二〇一九年)六五、九七頁。
[12]ディドロ前掲書、五四頁。
[13]バルト前掲書、二一頁。
[14]Sophie Volpp, The Substance of Fiction: Literary Objects in China 1550-1775, Columbia University Press, 2022, p.13.
[15]浦安迪(Andrew H. Plaks)『浦安迪自選集』(生活・読書・新知三聯書店、二〇一一年)一〇六頁。
[16]Wai-yee Li(李惠儀), The Promise and Peril of Things: Literature and Material Culture in Late Imperial China, Columbia University Press, 2022, p.49.
[17]浦安迪前掲書、二八六頁。
[18]中国における国家の滅亡の反復性については、武田泰淳のエッセイ『滅亡について』(岩波文庫、一九九二年)が示唆に富む。
[19]Martin W. Huang, Desire and Fictional Narrative in Late Imperial China, chap.3.
[20]Volpp, op.cit, p.15.
[21]浦安迪前掲書、一〇八頁。
[22]一九世紀末の英文学における「反転した植民地主義」については、丹治愛『ドラキュラ・シンドローム』(講談社学術文庫、二〇二三年)が詳しい。
[23]サド前掲書、二六〇頁。サドは「共感」に基づくルソーの社会思想を徹底的に拒絶し、社会の絆を耐えがたい束縛と見なす「切断の哲学者」であった。秋吉良人『サド――切断と衝突の哲学』(白水社、二〇〇七年)五八、一〇〇頁。
[26]Claude Rawson, God, Gulliver, and Genocide: Barbarism and the European Imagination, 1492-1945, Oxford University Press, 2001.
[27]ジョージ・オーウェル「政治対文学」『鯨の腹のなかで』(川端康雄編、平凡社ライブラリー、一九九五年)二七三頁以下。さらに、一九世紀のイングランドでは、下等でワイルドな怪物ヤフーに、アイルランド人労働者のイメージが差別的に重ねられるケースもあった。ヤフーは人種差別にたやすく利用されるが、同時にそのおぞましさを明るみに出すという二重性を帯びた形象なのだ。スウィフト自身がイングランド国教会に属するアイルランド人、つまりアングロ・アイリッシュという中間的存在であったことも注意を要する。富山太佳夫『『ガリヴァー旅行記』を読む』(岩波書店、二〇〇〇年)一七六、一九一頁。
[28]花田清輝『復興期の精神』(講談社学術文庫、二〇〇八年)一三一‐二頁。
[29]Wall, op,cit., p.81.
[30]ジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』(柴田元幸訳、朝日新聞出版、二〇二二年)二八一‐二頁。
[31]マキシム・クロンブ『ゾンビの小哲学』(武田宙也+福田安佐子訳、人文書院、二〇一九年)六六、六八頁。
[32]「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語」(大西尹明訳)『ポオ小説全集』(第二巻、創元推理文庫、一九七四年)一三一頁。
[33]同上、二六六頁。ピアニストのヴァレリー・アファナシエフは『ピム』に言及しつつ、黒より不気味でほとんど耐えがたいポー的な「白い恐怖」を、シューベルトのピアノソナタ第一八番に認めている。『音楽と文学の間』(平野篤司他訳、論創社、二〇〇一年)九二頁。
[34]ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』(望月哲男他訳、ちくま学芸文庫、一九九五年)一四九頁。
[35]ドストエフスキー『貧しき人々』(安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、二〇一〇年)一〇、二五頁。
[36]同上、一八〇、二七七頁。社会主義的であるとともに宗教的な祈りを感じさせる『貧しき人々』については、サン゠シモン主義との類似性が指摘されている。Joseph Frank, Lectures on Dostoevsky, Princeton University Press, 2020, p.23.
[37]同上、三〇四、三〇七頁。
[38]ドストエフスキー『白夜/おかしな人間の夢』(安岡治子訳、光文社古典新訳文庫、二〇一五年)一六頁。
[39]同上、二五、三五、四〇頁。
[40]クロンブ前掲書、一〇三頁。
[41]ツルゲーネフ『父と子』(金子幸彦訳、岩波文庫、一九五九年)三六、二一三頁。
[42]「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション』(第一巻)六二九頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年2月16日、2月20日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年4月4日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。