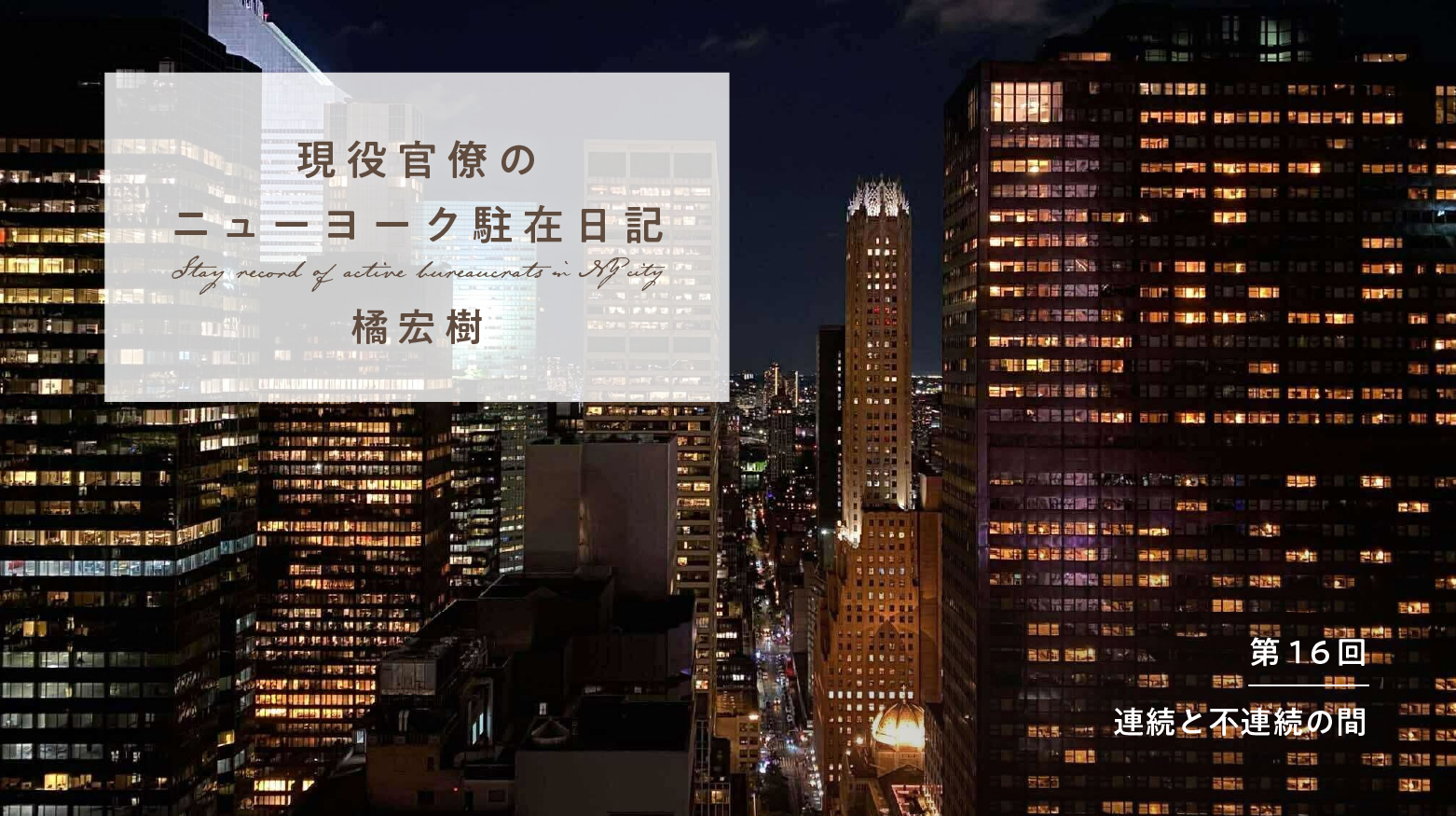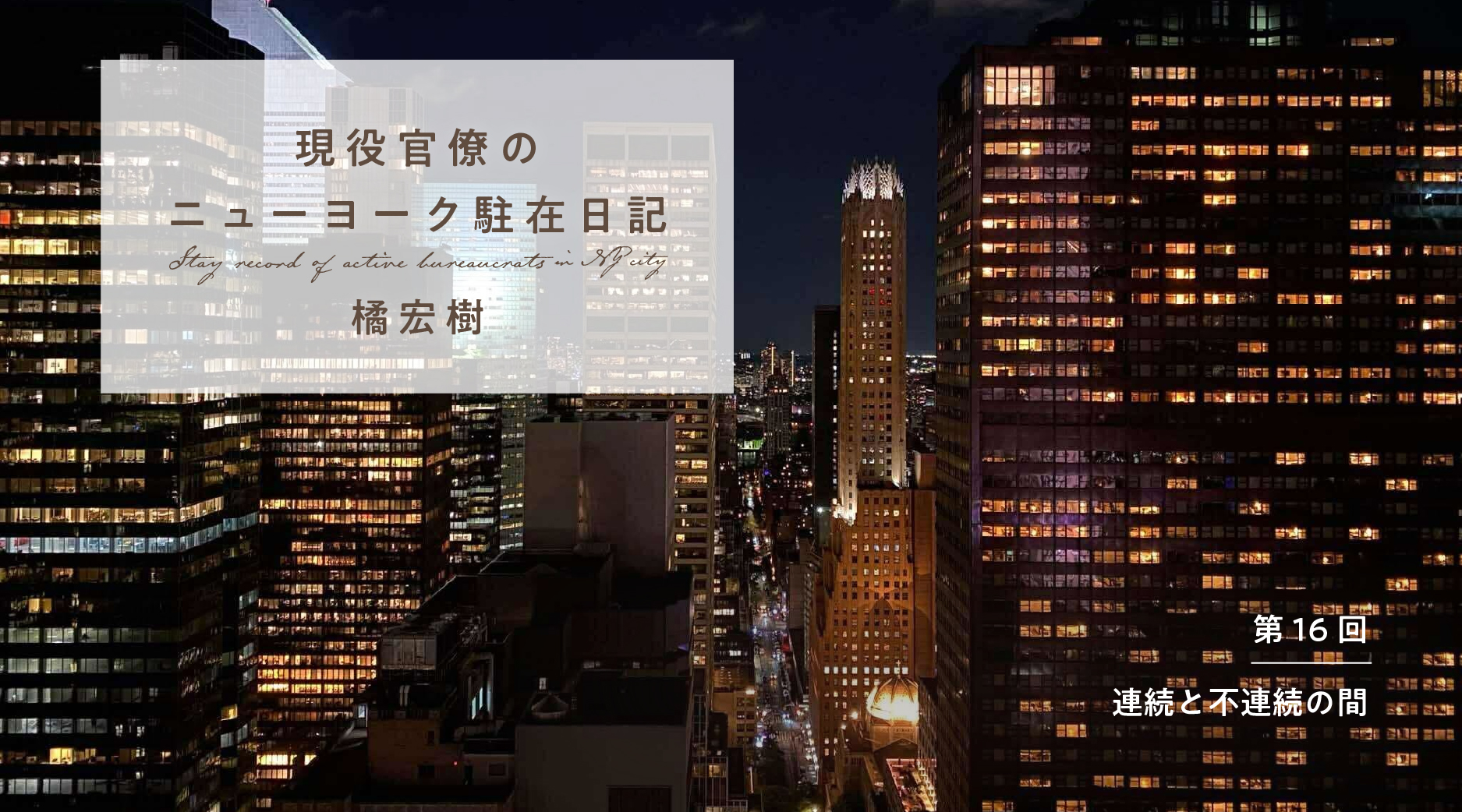橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。
ニューヨークの社交場では、どのような振る舞いが求められるのでしょうか好機をつかむための社交戦術を紹介します。
 「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください
「現役官僚のニューヨーク駐在日記」の連載記事は、こちらにまとめていきます。よかったら、読んでみてください
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
こんにちは。橘宏樹です。本稿は総括編3部作の第2部です。前号では、日系人社会内部の連係の重要性と改善点の話をしました。特に駐在組日本人の社交のあり方について長々と綴ってしまいました。NYは世界最高の社交場のひとつです。ひょんな出会い、ほんの小さな会話が、本当にビッグ・ビジネスへと繋がります。展開のスピードやスケール感にはシビれるものがあります。日本人もこの場の力を活かさない手はありません。そのためにはどうすればいいか。今号では、社交の話をもう少し掘り下げつつ、何でも繋がっている、一見繋がってなさそうなものでも、繋げて考えましょう、ていうか繋げましょう、NYでは特にそれが問われます、というお話をしたいと思います。
1 攻めと守りの社交術──日系人社会の生存戦略
攻めの社交──気前よく「貸し」を仕掛ける
NYは、世界屈指の社交の舞台です。偶然の出会いや何気ない会話が、驚くほどのスピードとスケールで大きなビジネスに結びつくことがあります。この場の力を活かすためには、受け身で待つのではなく、自ら積極的に仕掛けていく社交が欠かせません。相手との距離を一気に縮め、「また会いたい」と思わせるための戦術が必要です。
前号では、初対面の相手と仲間になるための「三段構えの社交戦術」──相手のニーズを瞬時に読み取り、それに応えられる姿を示し、さらに気前よく提供する──について述べました。当たり前のように聞こえますが、重要なのは、それを人々がどれだけ多くの初対面相手に対して、その場その場で的確かつ瞬時に実行できるかです。立食パーティーのように一人と話せる時間が限られる場では、この瞬発力が勝敗を分けます。そして、その行動を積み重ねていけば、やがて巨大な「貸し」の資産、つまり社会関係資本(Social Capital)が築かれます。これはビジネスにおいて「どれくらいの人に、どれだけ頼めるか」という債権総量そのものであり、その構築には、日頃の情報収集、気前よく提供できる手札の充実、相手と向き合うときに貢献できるポイントを探す姿勢、そして総合力としての機転が欠かせません。
もっとも、「損得を考えず自然体で付き合うことこそ人間関係の本質だ」と考える方もいるでしょう。確かに、自然体のまま、初対面から人種・宗教・貧富を問わず相手への貢献を第一にできる人間であれば、それで十分です。しかし、自然体ではそうすることが難しい人々にとっては、意識的に打算を組み込むことが有効になります。要は、目の前の相手の幸福を左右する要素に無頓着なままでは仲間は増えない、ということです。
守りの社交──「空恐ろしき慈悲」への警戒
一方で、気前よく社交することは攻めの戦術ですが、逆に自分が気前よい社交を受けているときには、守りの視点が必要です。なぜなら、その厚意が「空恐ろしき慈悲」として作用し、知らぬ間に相手の支配の網に絡め取られている可能性があるからです。
私は、打算は極まると限りなく慈悲に近づくと考えています。打算とは本来、私利私欲のために人間が行う計算です。しかし、人々が「情けは人のためならず」の原理を会得し、相手の利得に寄り添えば自らの利得が満たされると理解すれば、その行動は促進されます。感謝される機会が積み重なれば、人間の中には他者を包み込む度量や善行心が育っていきます。
しかし同時に、利欲の都合上、「貸し」を活用したい時は必ず訪れます。その瞬間、「債権者」となった人間は、時に容赦なくカードを切ります。NYの社交界を何世代にもわたって勝ち抜いてきた富裕層は、人種や宗教を問わず、観音様やマリア様のような温かさを漂わせています。しかし、その優しさに包まれ、助力や助言を受けた人間は、心からの感謝と尊敬を抱き、「この人のために何か返したい」という気持ちを持つようになります。特に、尊敬する目上の人物が「恩返しは不要、恩送りでいい」と諭せば、日本的な恩送り文化に育った人間は感動とともに恭順してしまいます。利欲と自我の軸たる打算が、根本から持って行かれる瞬間です。真の博愛精神に至った「真人」──例えば前掲した古本武司さんのような人物──に恭順するのは安全だと思いますが、まだ野心や利欲を残す有力者に大きな貸しや弱みを作ることは極めて危険です。彼らは「空恐ろしき慈悲」をもって相手を支配し、支配下に入った人間は何を頼まれるかわかりません。場合によっては、断るという発想すら失われます。極端な例ですが、マフィアが孤児を引き取り育て、恩義を理由に危険な仕事をさせる構図と同じです。

貸し借りの論理は人間と国家で違う
人間同士の間には、情愛や友愛などに基づく、打算なき純粋な利他も確かに存在します。しかし、組織同士、国家同士の関係には、それはほとんど存在しません。そこでは打算こそが唯一の共通言語です。
「貸し借り」の概念は、人間の心に忍び込み、利欲の中枢を書き換え、行動を支配します。そして感謝と報恩の理屈は、美徳の形をとってその行為を正当化します。しかし、国や企業は恩送りの文化に感動することはなく、純粋な利他では動きません。国際社会においては、相手にどれだけの「貸し」を積み重ねているかが、生き残りを左右します。
超大国に囲まれ、資源を輸入に頼る日本にとって、他国や外資との「貸し借り」に敏感であることは不可欠です。そしてこの論理は、日系人社会にもそのまま当てはまります。日系人一人ひとりが、米国はじめ海外の人々に対してどれだけの「貸し」を作っているか──その個々の行いと社会的な積み重ねが、最終的には日本という国の国力を形作っていきます。
国際社会では、トランプ大統領に限らず、時の権力者に対してどれだけの「貸し」があるかが重要です。あるいは、その権力者に「貸し」を持つ人物に対して、自分たちがどれだけ「貸し」を築けているか──これは間接的に「債権」を行使できるかどうか、という意味でもあります。そして「借り」は少ない方がよく、ましてや弱みを握られてはいけません。日系人社会全体の社会関係資本における債権総量が、常に試されるのが外交の本質であり、国際社会を生き抜くということではないでしょうか。
だからこそ、日系人社会のサバイバルは「貸し」の積み重ねにかかっています。攻めとしての「気前よい社交」と、守りとしての「空恐ろしき慈悲への警戒」。この両輪を回し続けながら、貸し借りのバランスを巧みに保つことが、世界の中で生き延び、存在感を高める唯一の道なのです。NY駐在期間を通じ、私はその現実を強く思い知らされました。
2 「ソーシャル」と「ビジネス」
橘流社交論の補論として、「貸し借り」の生まれる社交の現場は2種類あり、マナーや勘所がそれぞれ異なることもおさえておかなければなりません。
とある経緯で、NY在住(グリーンカード保持・非日系人)の女性実業家セレブと共催でホームパーティーを開催することになった際、彼女から電話がかかってきて曰く、「Hiroki-san、今度のパーティはビジネスなの?ソーシャルなの?どっち?」とのことでした。僕は、ああ、やっぱりプロは、そこの峻別は、はっきりさせるんだな、準備する関係者の間で事前認識を揃えるんだな、さすがNYだなと、思いました。
どういうことかというと、まず、ビジネス(Business)とは、文字通り、仕事メインの会です。主催者は、誰と誰に何のビジネスの話をさせたいか、ある程度青写真を描いていて、それに沿った人が招かれます。職業や肩書きがものを言うのであって、個人の魅力は問われません。アイスブレイクもほどほどに、単刀直入に本題に入り、選択肢や条件をテーブルに並べ、この場で決められること、次のミーティングまでの宿題などを特定します。ディナーが主流ですが、朝食やランチもかなり多いです。前菜から始まって、メインディッシュを済ませ、デザートやコーヒーの段階になって、雑談などができるようであれば、お互いの人間性も見えてくるので、お互いに魅力を感じたら、またあらためて、別の機会(ビジネスまたはソーシャルの会合)をセットして交流を深めていく展開が生じます。SNSの交換はもっぱらLinkedIn(NY界隈ではもはや名刺として機能している)か社用携帯番号に紐付いたWhatsAppです。
対して、ソーシャル(Social)とは、要するに、プライベートな交流会です。参加者は、招待された人か、主催者の許可を得て招待者が連れてくる人に限られます。信用できる善人で、話が面白かったり、何らか特技や魅力があったり、他の客を楽しませることができる人に限られます。その場ではなるべくビジネスの話はしないのが暗黙の了解です。ビジネスしか能のない、つまらない人という評価を受けるリスクを避けたいからです。紹介する時も、きっと海外ドラマ等でご覧になったことがあると思いますが「こちら、トムよ」「トムです、はじめまして」「こちらは、エイミー」「エイミーです、よろしくお願いします。」(英語だと、“Hi, Aimie, this is Tom. Tom, this is Aimie”で終わり(笑))と、ファーストネームだけしか伝えません。仕事は何をしているとか、紹介者はほとんどあんまり伝えません。日本人ならきっと、え、紹介って、情報それだけ?と感じると思いますが、その裏には、「自分はビジネス抜きでも興味深い人を連れてきたのだ」というある種の建前があります。また、プライバシーを誰にどの程度明かすかは本人の判断なのでその権利を侵してはならないという面もあります。出会った人同士でもし色々話が弾んで、ビジネスの話をしたい、ということになれば、今度、あらためて、と連絡先を交換し合います。
ちょっと隅っこの方で二人きりで話すのもアリですが、長くなってしまえば他の人と交流する折角の時間が失われてしまいます。プライベートのSNSはNYならばFacebookです。米国人のFacebookは家族写真の投稿で埋め尽くされがちなくらいもっぱらプライベートな使われ方をします。または私用メアドか私用携帯番号に紐付いたWhatsAppです。ソーシャルの開催場所はやはり主流は誰かの家や別荘です。金曜日の夜や休日の昼夜に開催されやすく、3~4時間は費やしながら、(潜在的な)友人同士として、リラックスタイムを楽しみます。講話やゲームや音楽など何らかエンタメ的な余興も挟まれたりします。

この場は、ソーシャルなのか、ビジネスなのか、会の趣旨ははっきりと峻別されつつも、両者にはもちろん、連続性があります。ソーシャルな場で出会った人と後日ビジネスの話をする、ビジネスの場で会った人と後日ソーシャルな場で楽しむ。この無限ループを繰り返すなかで、人脈が広がっていくわけです。裏を返せば、次の場に呼んでもらえるか、が勝負なわけです。
実は、僕はピアノがちょっとした特技なのですが、NY滞在中の3年間、ソーシャルな場で(は特に。実はビジネスでも時々出番がありましたが)、これがめちゃくちゃ威力を発揮しました。富裕層の家には大抵(ユダヤ系の家にはなぜかほぼ必ず)、小型のグランドピアノが置いてあります。行く先々で臆面もなくぽろぽろ弾いたことで、出会いの機会がどんなに広がったことか。はっきり言って、僕ごとき「あなたは魅力的なので是非うちのソーシャルに来てください、他の皆さんにもぜひご紹介したい」などと言ってもらえるほどの人物ではありません。しかし、そんな敷居高めの場でも、「今度、ちょっといらしてみなさんにも聞かせてちょうだいよ」と軽く誘えるので、招待する方としても、呼ぼうか呼ぶまいか迷った場合など、声がけする口実としてちょうどよかったと思います。こちらも「それでは、BGM要員として伺います」と言いながら、いそいそと上がり込めます。弾けば余興として座持ちに貢献できますし、僕としても初対面の人たちとの会話のきっかけにできます。そのソーシャルの場に呼ぶか呼ばないかの絶妙なライン上または呼ばないゾーンにいた僕が、ピアノのおかげで呼ばれたというケースは、実際かなり多かったのではないかと思います。チャンスとはデジタルなものです。土俵に上がれるか上がれないか。家に呼んでもらえるかもらえないか。出会うか出会わないか。そこで別れる未来には、天と地ほどの差が生まれます。ソーシャルな場で出会った方々との協働によって、僕のビジネス上の選択肢やパフォーマンスがどれだけ拡大したことか。人生の学びがどれだけ深まったことか。まったくもって、筆舌に尽くしがたいものがあります。ピアノには、本来ならばその土俵に上がれなかったはずの僕を、上がれる方へと、ジリジリ寄せてくれる力がありました。つくづく、幼少期の僕にピアノを習わせてくれた親に感謝です。
ちなみに、僕のピアノは、英国留学時代においては、もっぱら駅や街角のパブリック・ピアノが主戦場で、往来の人々との交流がメインでしたが、NY駐在時代においては、インナーサークルに入り込んでいく武器として機能したというのも、好対照だなと思います。

前号で述べたとおり、日本から数年単位で赴任してきている大企業等の「駐在組」は、ビジネスの場では活躍できます。そして、ソーシャルの場に「呼ばれる」ところまでは、こぎ着けられます。しかし、そこから、更に次のビジネスやソーシャルの場に招待してもらい、芋づるをたぐっていくことにはかなり難儀しているように見えます。その先に、最も旨味のあるインナーサークルが待っているわけで、そこにどれだけ近づけるか、入り込めるかが、NYのビジネスシーンにおける勝負です。また、セレブとお近づきになるといったミーハーな価値はさておいて、面白い人、素晴らしい人、成し遂げたシニアやこれから伸びていく若者に出会い、多種多様な業界人と交流できることは、やはりそれ自体、人生の醍醐味だとも思えます。せめて「駐在組」は、言語を同じくする「永住組」のソーシャルの場にくらいはしっかり食い込んで、自身の帰国後に来日した彼らに返礼の接遇ができるくらいの関係を築くことができれば、日系人コミュニティのポテンシャルは最大化されると思います。
3 政治と経済と文化は一筆書き
「政治とは、常に経済的で文化的である。」「経済とは、常に政治的で文化的である。」「文化とは、常に政治的で経済的である。」これらは世界中どこでも当てはまる、普遍的な関係性を示すフレーズです。中でもNYは、その結び付きの強さと速度が際立つ土地です。「政治、経済、文化。土俵は互いに繋がっている」というのは当然の前提として、その中で人間が勝負している土俵に、他の土俵をどれだけ自分本位に繋げられるか、繋がる局面や瞬間をどの程度支配できるかが、勝敗を左右します。言ってみれば、すべては「場外乱闘」で決しているのです。
こうした背景を踏まえると、まず目に入るのがNYの政治の特徴です。ここでは、時の政権によって施策が180度変わることも珍しくありません。行政も、正義や筋論、公平や中立を盾にして前例を踏襲する官僚主義ではなく、担当者やタイミングによって判断が異なる柔軟さと恣意性を併せ持っています。ビジネスに直結する規制も頻繁に変わります。裏を返せば、ロビイングが成功すれば政治家が動き、規制改革(あるいは強化)が行われる可能性が高いということです。行き詰まれば訴訟、勝てそうな地域の裁判所に起訴、結果が不満なら控訴。やがて選挙が訪れ、キャンペーンに資金を投入すれば勝機が見えてくる──NYは変革が進みやすい一方で、おぞましいほどの金権主義の街でもあります。
この金権主義の色合いは、私が過ごしたロンドンとの対比でより鮮明になります。10年前の英国留学時、日本人の友人がロンドンのハイド・パークで当時出たばかりのドローンを飛ばしていたところ、警察から「ここは女王の土地だから」と使用中止を命じられました。女王が許可しない限り、いくら支払っても使用はできないだろうと感じました(ただし、貴族などのコネを使えば別かもしれません)。一方、NYのセントラル・パークで同じことをすれば、やはり止められるでしょうが、テロリストでないことを証明し、手続きや「誰かの働きかけ」を通じて多額の使用許可料を払えば、限定的に許可される可能性がある──そんな感覚を抱きます。この「お金で解決できそうかどうか」の肌感覚の違いは、両都市の最も大きな差のひとつだと思います。
さらに、政治と経済の関係を考えると、日本人は政治資金や贈収賄を連想しがちですが、政治家にとって経済とはまず選挙区の活気のことです。在任中に失業率が下がり、賃金や経済成長率が上がれば、再選の可能性は高まります。つまり経済は、政治家にとって最も現実的かつ身近な関心事なのです。
起訴取り下げ、判断保留=NY市長の汚職事件―連邦地裁(時事通信2025年2月22日)
そして、こうした政治や経済の土俵に並び立つのが文化です。現状において、日本がNYや米国で影響力を発揮できる最大──ほぼ唯一──の武器は文化です。ウォール街には富裕層が集まり、潤沢な資金が動いていますが、日本が投資額や雇用規模で存在感を示せる時代は過ぎ去りました。再びその時代が訪れる兆しも見えません。その一方で、日本文化の繊細さや華やかさ、ミステリアスな魅力は、ニューヨーカーの関心を強く引きつけています。高級割烹からB級グルメ、浄瑠璃からアニメまで、間口の広さは群を抜きます。寿司、抹茶、ラーメン、味噌といった日本食は民族・宗教・世代・階層を問わず着実に浸透しています。この文化的強みを梃子に、NY、さらには米国内の日系人社会の経済力・政治力をどう最大化するか──そのヒントになりそうな、政治・経済・文化が密接に絡み合う二つのエピソードをご紹介したいと思います。



ジャパンフェスの主催者の特別講演会を9/4木に実施しました。

講演内容はこちら↓からご視聴いただけます。
・焼酎販売の規制緩和と日系ロビー
まず、NY州における焼酎販売の規制緩和の際のお話です。日本政府は日本酒の海外展開に力を入れていますが、同様に焼酎の米国進出にも力を入れています。NY州では、2022年7月1日に新たな法律が施行され、日本の蒸留酒「焼酎(shochu)」がアルコール度数24%以下であれば、「ビール・ワインライセンス(いわゆる「ソフト・リカー・ライセンス」)」の下で販売できるようになりました。この法改正により、焼酎は初めて正式に「shochu」として認識され、販売が可能となりました。 以前は、焼酎は「ハード・リカー」として分類され、販売には高額(ソフト・リカー・ライセンスの2~3倍の費用がかかる)で取得が難しいハード・リカー・ライセンスが必要でした。そのため、多くの日本食レストランでは焼酎の提供が困難であり、代わりに韓国の焼酎である「ソジュ(soju)」という名称で販売されることもありました。
この法改正は、NY州議会のアナ・M・カプラン上院議員(S.7913)とディディ・バレット下院議員(A.8620)の主導により実現しました。日本酒造組合中央会(JSS)やNY日本レストラン協会(NYJRA)などの団体も、長年にわたり法改正を求めて活動してきました。この変更により、焼酎はNY州内の多くのレストランやバーで提供されるようになり、日本文化のさらなる普及と焼酎の認知度向上が期待されています。
これらの法改正に貢献した議員の選挙区においては、日系人やアジア系住民は数%と少数派なのですが、ハード・リカー・ライセンスを取得せずとも売れるお酒の選択肢を広げたことは、飲食・小売業等の中小企業支援策として有効でしたし、2議員ともに民主党ですが、日本文化を代表する焼酎の展開支援は、文化的多様性や寛容性の拡大を訴える党是にも沿います。特に、カプラン議員はイラン系ユダヤ人として亡命し、難民としてアメリカに渡った経歴を持ち、「多様性と寛容の象徴」を一貫して政治理念として掲げていますから、個人の信念にも当てはまっていたことが推測されます。
そして、ここが面白いポイントなのですが、同法改正の裏では、元弁護士でシェフ歴のあるNYJRAのジョン・マッカーシー法務顧問がロビイングにおいて活躍しました。彼のレストラン「The Crimson Sparrow」の近隣に事務所を構える州議員にも積極的に働きかけを行ったそうです。元弁護士で元シェフの飲食店経営者という、NYJRAにとってはうってつけの素晴らしい経歴を持つ人材が日系人団体の一員であること、今回、焼酎販売の規制緩和に活躍してくれたことは、本当に幸運で決定的だったと思われます。一人格のなかで政治・経済・文化をひとまたぎするマッカーシー氏のロビイング現場における舌鋒は、きっと非常に説得力があったことでしょう。
この事例は、文化的資産(焼酎)を政治・経済の領域へと橋渡しし、制度を変えることで新たな市場を開いた好例です。人材とネットワークが結びつけば、少数派であっても大きな変革を起こせることを示しています。
・チャック・シューマー降臨
想像してみてください。例えば、仮に、墨田区の錦糸公園でブラジル・フェスティバルが開催されたら、その辺りを選挙区に持つ、政治家はどのくらい駆けつけるでしょうか。どういう意図を持って、どのくらいの時間滞在するでしょうか。挨拶するとしたら、どういうことを述べるでしょうか。その前後に、もしブラジル大使館主催のレセプションや大使公邸の食事会が開催されたとしたら、墨田区界隈の政治家はどのくらい招かれるでしょうか。その場所でどのような話がなされるでしょうか。
NY市ブルックリン区は、民主党のチャック・シューマー上院議員の地元です。議員は民主党の上院院内総務です。バイデン前大統領のすぐ後ろを歩いている姿をテレビで見たことがある人も多いと思います。要は米国民主党の最高幹部トップ3の一角です。
聞くところによれば、ある時、ブルックリンで日本食の屋台が立ち並ぶ大人気イベントが行われた際に、前触れなく、チャック・シューマー議員が現れて、その場で演説しようとしたことがあったそうです。ブルックリンでこういうイベントをしてくれてありがとう、みなさん楽しんでくれ、文化的多様性を象徴するこういうイベントは歓迎だ、といった趣旨の挨拶をしたかったみたいです。しかし、担当スタッフは(日本人かどうかわかりませんが、アメリカ人なら絶対にわかると思います)、氏が誰だかわからず、不審者として扱い、マイクを渡さなかったそうです。議員もさぞかしびっくりしたことでしょう。このブルックリンで、自分を知らない者がいて、自分にマイクを渡さないイベント主催者がいるとは夢にも思わなかったと思います。

もし、イベントの主催者が状況に気づいて、さっとマイクを渡し、チャック・シューマーと写真を撮ってSNSに載せていれば、その後の日本文化の広報において、どれだけ絶大な効果が生まれたことでしょうか。イベント主催者は日系人ではなかったかも知れませんが、随所でその写真を使えば、今後ブルックリンにおいて、日本関連のイベントがどれだけやりやすくなったことでしょうか。もしこれを機に、ブルックリン界隈の和食系飲食業者とチャック・シューマー議員の交流を深め、いかに日本食店が貴選挙区で賑わいをつくっているかをアピールして理解を得ることができていれば、困ったときに何かしら頼ることができるかもしれません。ひいては、その伝手を日本国政府も活用できるかもしれません。日本の文化的影響力は、選挙において絶対盤石なチャック・シューマーですら無視できない、むしろ利用しようとすら考える域に至っているわけなのです。日本にとって巨大なチャンスが訪れ、そしてそれを逃した、というエピソードでした。
政治・経済・文化は、決して別々の線ではなく、一筆書きで描かれるひとつの軌跡です。文化は人々の感情や価値観を揺らし、経済はその基盤を整え、政治は方向を定めます。しかしその順番は一定ではなく、時に文化が政治を動かし、経済が文化を広げ、政治が経済を促します。ニューヨークでの日々は、この三者が瞬時に交差し、絡み合い、時に予想もしない形で未来を変えていく現場を見せてくれました。だからこそ私たちは、自分の立つ土俵だけでなく、隣接する土俵、さらには全く別の土俵への橋を常に意識しておくべきです。
日系人社会の生存戦略も、この一筆書きの構造の中でこそ磨かれ、力を発揮していくのだと思います。文化の魅力は人を惹きつけ、経済活動はその輪を広げ、政治的な影響力がそれを守り強化します。三者が繋がるとき、日系人社会は少数派であっても、その存在感を何倍にも高めることができるのです。
4 連続と不連続の間
NYでの日々は、互いに断絶して見える領域をどうつなぐかが、生き残りと飛躍の分かれ目になることを教えてくれました。冒頭に述べたように、人間関係に潜む「貸し」と「借り」を意識せずに過ごせば、知らぬ間に、切れたはずのカードを失ったり、「債務」を背負ったりと、選択肢を大きく減らすことに繋がります。また、ソーシャルとビジネスの場は表向き峻別されていても、その間に橋をかけられる人こそが、次の機会を手にします。そして、日本人がしばしば別々の土俵と考えがちな政治・経済・文化も、実際には一筆書きで結ばれていて、瞬時に交差し合うものです。こうした連続と不連続の境目には、日系人社会が本来つかむべき好機が数多く存在しています。これまで、我々は、それらをたくさん取りこぼしてきたのではないか、と思えて、口惜しくてなりません。不連続に見える境界をまたぎ、連続の回路を描く力こそが、アメリカで、そして、世界で、少数派である日系人社会の存在感を何倍にも高める道なのです。
次号はようやく最終号です。
駐在の日々と本連載の集大成として、私なりに「NYとは何か」を総括したいと思います。
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年9月1日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2025年9月11日に公開しました。