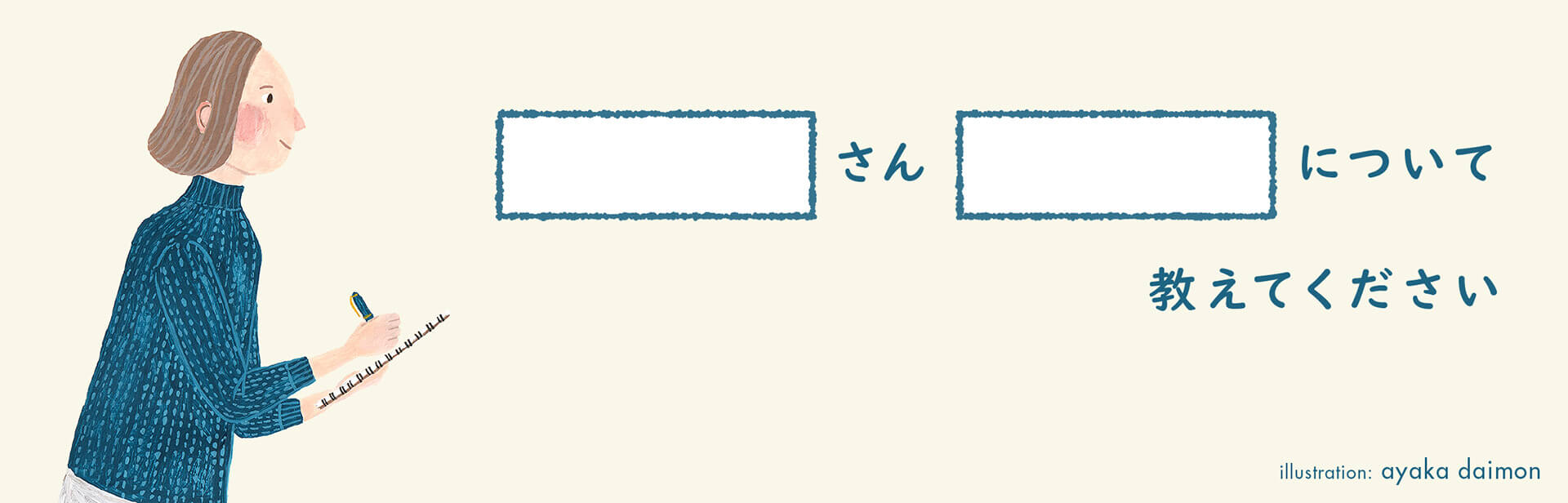「民藝」ってご存じでしょうか? 芸術家ではなく、名もなき人の手から生み出された日用品にこそ、美術品を凌駕する美しさが宿る。そんな信念のもとで作られ、使われる「民衆的工芸」のことです。「日常の中に非日常を見出す」民藝のまなざしは、現代社会にどんな示唆を与えてくれるのでしょうか。この民藝の捉え直しに取り組む哲学者・鞍田崇さんのお話を伺いました。

教えてくれた人:鞍田崇さん
くらた・たかし/哲学者。1970年兵庫県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。現在、明治大学理工学部准教授。近年は、ローカルスタンダードとインティマシーという視点から、現代社会の思想状況を問う。著作に『民藝のインティマシー 「いとおしさ」をデザインする』(明治大学出版会 2015)など。民藝「案内人」としてNHK-Eテレ「趣味どきっ!私の好きな民藝」にも出演(2018年放送)。
本記事をはじめ、「遅いインターネット」ではこれまでなんとなく気になっていたけれど、きっかけがなくて触れてこなかったことについて「この人なら」と思う人に教えてもらいに行く連載を行っています。
端的に言うとね。
いまなぜ「民藝」なのか──日常の中に非日常を見出すということ
──今日は鞍田さんに、「そもそも民藝とは?」という基本的なお話から、なぜそこに人々が惹きつけられてきたのか、さらに現代社会においてどういう意味を持つのかといったところまで、いろいろと教えていただければと思っています。
「民藝」は1920年代に柳宗悦による民藝運動で提唱されたものですが、誕生から1世紀近くの時が流れて、「民藝」が意味するものも、その社会的な位置づけも否応なく変質しているのではないかと思います。こうした変化を認識した上で、いま「民藝」というものを考える手がかりを鞍田さんからもらえたらと……そんなことを考えています。
そもそも僕がなぜ民藝に興味を持ったかと言うと、それは長年手がけてきたサブカルチャー批評と通ずるものを感じ取ったからです。
サブカルチャー批評というのは、市場に流通しているジャンクな表現の中に、結果的に生じた奇形的な変化や過剰なものを見出していく作業なんですね。一方で、民藝を好きな人たちもまた、普段使いされているありふれたモノの中に、機能に回収されない余白や過剰なものを発見しているように思えます。つまり両者には、平凡の中に非凡を、言い換えれば、日常の中に非日常を見出すという共通点があるんじゃないかな、と。だから民藝の思考を身につけることは、自分にとって大きな学びになると、漠然と思っていたんです。
鞍田 そのお話を聞いて思い出したのですが、僕が民藝と深く関わるようになったきっかけの一つが、まさにサブカルチャーでした。岐阜県の多治見市に、陶芸家の安藤雅信さんが主催している「ギャルリももぐさ」というギャラリーがあります。そこで2008年に「サブカルチャーと民芸」と題するシンポジウムが開催されたことがあって。安藤さんに加えて、古道具店「古道具坂田」の店主・坂田和實さん、美術史家・土田真紀さん、陶芸家・内田鋼一さんが登壇したこのシンポジウムを見に行って、大きな刺激を受けたんです。
シンポジウムの中で、安藤さんは「民藝をサブカルチャーという俯瞰的な視点から捉え返す必要がある」と話していました。いわゆる教科書的な伝統工芸としての枠組みを超えた、広がりのあるものとして、民藝を捉え直すきっかけになりましたね。
──僕が民藝に興味を持つようになった理由はもう一つあります。この四半世紀の情報環境の変化を背景に、紙媒体やモニターを通じて他人の物語を享受することから、体験を通じて自分の物語を見つめ直すことへと、自分自身も含めて人々の関心が大きく移ってきている。これは俗に「モノからコトへ」と言われている変化で、今日の情報社会を考える上での前提になっています。こうした変化を前提としたとき、モノでありながらコトを、というかモノを通じてコトを扱ってきた民藝について考え直すことが重要なのではないか、と思ったわけです。
ということで、前置きが長くなってしまいましたが、まずは「そもそも民藝とは?」という話からお伺いさせてください。
鞍田 はい。言葉としての「民藝」が誕生したのは、いまからちょうど100年ほど前の1925年頃です。柳や陶芸家の河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉らが作ったパンフレット「日本民藝美術館設立趣意書」が初出です。この趣意書は、いまで言うクラウドファンディングのようなものですね。もともと柳は、民藝運動に先だって仲間たちと一緒に、文芸誌『白樺』の創刊に携わっていました。『白樺』は文芸作品だけでなく印象派の紹介なども行う芸術総合誌としての面もあったのですが、その延長線上で「民藝」という言葉を作り、価値あるものとみなされていなかった生活道具たちに新しい光を投げかけようとしたのだと思います。
当時は工芸全体が芸術や美術の二番煎じ的な位置付けにあり、その社会的ステータスや価値を高めていくための試みが、さまざまなアプローチで行われていました。アートとしての表現性を追究していく動き、技巧を極めていく動きなど、いくつかの流れがあった中で、柳たちが着目したのが「用の美」でした。白樺派で最年少でありながら編集を任されていた柳は、概念を編んで言語化する能力が高かったのでしょう。生活の中で日常的に使われること、すなわち“用”を通じて自ずと形成される美しさ。芸術で追求される「美のための美」ではなく「用と結びついた美」を工芸の本来の姿に見出し、「民藝」という言葉のもとに集約していこうとしていたんです。
「日本民藝美術館設立趣意書」が美術館建設を旗印としていたことからも、当時は美的なものを掲げることが、多くの人たちの共感を集める求心力を持っていたことがうかがえます。それまで作り手すらも美的価値があるとは思っていなかったところに、こうした言説や運動が起こったことにより、もちろん作り手自身は励まされる思いがあったでしょうし、世間の人も新しい美的価値を発見できた意義があったと思います。

▲柳宗悦『民藝とは何か』(1941)。論考「何を『下手もの』から學び得るか」(1928)を下敷きに、『工藝美論』(1929)、『美と工藝』(1934)と増補改訂を経て刊行された、柳の代表的著作のひとつ。
──料理を盛ったり、床を掃いたりするために「使われる」ことによってはじめて発動する良さというものがあって、それはストレートに「モノの美」とは言えないということは、僕もなんとなく感じます。僕が親しくさせてもらっている物書きの先輩に、よく地方の作家の器を買っている人がいるのですが、こう言うと申し訳ないですが普段はあまり片付いていないアトリエのキッチンの食器棚に押し込められていて、正直すごく邪魔になっている。でも、その人は料理が趣味で、遊びに行くとよく手料理を振る舞ってくれる。そのとき、棚の奥から引っ張り出してきた器に料理を盛り付ける、ガラクタのようにしか見えなかった器がそれまでとはまるで違って見えるわけです。
鞍田 そういうこともあるでしょう。ただ僕自身は、「民藝が見出したのは、果たして美的なものだけなのか?」という問いを立てているんです。もちろん、それまで誰も価値を認めていなかったモノに新しい美的価値を見出すまなざしには、大きな共感を寄せています。でも、あえてそこから一歩距離を置き、これまであまり注目されてこなかった新しい可能性を探っているんです。
そうした探求の中で浮かび上がってきたキーワードが、『民藝のインティマシー―「いとおしさ」をデザインする』という本でも主題として取り上げた、「いとおしさ(インティマシー)」です。実は柳も、キーコンセプトとして使っているわけではありませんが、ときおり「工芸の美の本質は親しさにある」といった言及をしています。僕らが民藝を通じて再確認できる感性的価値が、この「親しさ」にあるのではないかと思っていて。現代において僕らが欲しているのは、新しい美のあり方というより、ともすると遠くなってしまった社会や生活と自分との距離感をもう一度わがことにさせてくれる近しさ、つまり「いとおしさ」なのではないでしょうか。身近な生活道具に見出した民藝のまなざしを通して、どこか他人事になってしまった社会や生活との距離を、埋められるのではないかと考えています。

▲鞍田崇『民藝のインティマシー―「いとおしさ」をデザインする』
──この場合の「いとおしさ」は、美しさとは異なる別の価値なのか、それとも美しさをその一部として包摂するものなのか、どちらなのでしょう?
鞍田 後者ですね。僕は「いとおしさ」を、機能性や美しさを根底で支えているものとして捉えています。日本民藝館の館長・深澤直人さんが、館長就任後に「カーサ ブルータス」に掲載されたインタビューで、次のように語っています。「民藝は生活道具で、その意味では機能性と美しさが揃って合格だと思うけれど、それだけでは尽きないなにかが立ち昇っているのを感じた」と。そして、そのプラスアルファのなにかを「愛着」と呼んでいるんですね。僕もこの見方に共感しています。
──鞍田さんが提唱している「いとおしさ」は、「モノの時代」が終わったからこそ出てきた概念のように思えます。20年以上前からずっと「モノからコトへ」と言われていますが、これは要するにポスト消費社会≒情報社会を迎えたとき、モノは入れ替え可能であり、コトという自分の体験だけが固有だと考えられるようになったということです。1980年代のように「モノ」の消費を通じて自己表現する人がいなくなり、「コト」のほうに価値があるとみなされるようになった流れと、鞍田さんが民藝にモノの「美しさ」ではなく「コト」としての「いとおしさ」を見出すようになったことが、シンクロしているように感じたんです。
鞍田 僕もそう思います。少し見方を変えると、僕は「ゴールよりもプロセス」という言い方もしているんです。形ある完成形としての「ゴール」ではなく、そこに至るまでの「プロセス」が意味を持ちはじめている。いかに効率良くゴールにたどり着き、そこで何を得るのかではなく、プロセスを分厚くし、満喫していく方向に、まなざしの向きが変わっている気がします。
そして、「プロセス」には、弱いものを弱いものとして受け入れる側面がある。「ゴール」までいけた時点で、生存競争の中で勝ち残った、強い存在だと思うんです。ものづくりやデザインも同じで、さまざまな可能性があった中で、達成感を覚える形までたどり着き、人に受け入れられたものは、なにか強さを秘めている。
一方で、「プロセス」に着目すれば、もしかしたらどこにも至らないかもしれないものであっても、大切にできる。「生産性がないからダメ」ではなく、その過程に参画している時点で対等に扱える、包容力があるような気がするんです。冒頭で「民藝は平凡の中に非凡を見出す」とおっしゃっていましたが、まさに柳もある時期「平凡」という言葉を繰り返し使っています。もちろん、誰もが「平凡ではいたくない」と思ってしまうので、アンビバレントな要素もありつつ、「いとおしさ」にはその平凡さをあえて受け止められる余地が潜んでいるのではないでしょうか。
「民藝」と名付けた瞬間、雲散霧消してしまうもの
──民藝について書かれたものを読んでいると、生活の中にこうした「モノ」たちがあって、そしてその価値を柳たちに見出されて「民藝」と名付けられた瞬間、なにか大事なものが雲散霧消してしまい、その負債を返すために100年間試行錯誤を続けていた世界のように考えることもできると思います。「民藝」と名指しされた瞬間に、なにか一段上のものになり、柳が嫌悪したタイプの美術に接近してしまう。しかしモノの「美しさ」の次元で考えている以上、どうしてもそうなってしまう宿命を抱えてしまう。だからこそ、鞍田さんは100年経ったいまだからこそ、ちょっと別の角度からのアプローチを取られているように思えるのですが、それは要するに、美しいモノを発見するのではなく、人とモノの美しい関係性、モノを通じた人と世界の関係性を見出すということですよね。そこには「強い」も「弱い」もなく、そこに起きている関係を生む運動そのものが豊かなのだという立場から考えている。
鞍田 おっしゃる通りです。もちろん柳の時代は、現代とは違う圧倒的な貧しさがあり、そこから少しでも逃れたいという、想像を絶するほど強烈なモチベーションがあったのだと思います。「美しさ」と名指した途端に別物になってしまうかもしれないけれど、別物にして救済せざるを得ない状況があったのかもしれません。
ですから、柳たちのふるまいそのものを、いたずらに腐すつもりはありません。それでもおっしゃる通り、「民藝」と名付けることで変わってしまったものも大きかったのだろうなと思う。プラトンの「洞窟の比喩」でたとえると、かつての民藝運動は「洞窟の外」に出ていこうとしていた。「モノ」が飽和してしまった現代、僕らは柳たちが求めた「上昇」とは違う方向で、もう一度「降りて」いかなければいけないと思うんです。
──つまり、今日における「民藝的なもの」の再評価は、100年前の民藝運動に決定的な示唆は与えられているけれど、別の思想運動だということですね。100年前に柳たちが「民藝」と名指してしまった瞬間にはまってしまった罠のようなものは確実にあって、その後の民藝ブームはその縮小再生産という側面が確実にある。現代における「ていねいな暮らし」的なもののブームだって、基本的にはコマーシャリズムに回収されてしまっている。
日常の生活空間に存在する平凡の中に、非日常への裂け目や、狂気とか、異常なものを見出す運動も、一度見出してしまった対象は結局、権威や市場によって価値づけられる。そうすると、日常の中に非日常を見出す力を失ってしまう。だとすれば、モノそのものではなくコトに、つまり民藝品そのものではなくその平凡なものの中に異常を見出す運動のメカニズムのほうに焦点を移して考えることが大事なのかもしれないですね。
鞍田 平凡を異常なものとして評価するのではなく、平凡のままで価値あるものとして見るまなざしを、新しく作らなければいけないと思うんですよね。弱いものを強いものに仕立て上げることで弱さを価値付けるのではなく、弱いものを弱いままに評価する。これまでの民藝が、いかにして洗練された「図」にしていくのかに躍起になっていたとすると、いまは「地」を「地」のままにすることが必要なのだと思います。もともと僕らが拠って立っていた足元に、もう一度立ち返ることが求められている気がするんですよね。
──民藝を論じたものを読んでいると、ときどき「道具を使いこなす」「自分のものにする」といった表現が出てきますよね。でも、僕は実際に民藝品に触れた経験が少ないので、いまいちよくわからないところがあるんです。この感覚は、まるでその道具が自分の身体の延長にあるもののように錯覚する、いわば身体拡張的な感覚なのか、それとも自分の身体からは切り離された道具という他者との関係性なのか、どちらなのでしょう?
鞍田 どちらかと言えば、前者だと思います。ペンを使い込むうちに、手の一部のようになっていく感覚に近い。こうした身体拡張の重視は、柳たちが機械を仮想敵としてののしっていたことの裏返しでもある。そして、その背景には、機械が身体から乖離していくことに対する危惧があったのだと思います。
現代的な例でお話しすると、AIによる僕らの大脳的な認識の拡張が、どんどん進んでいますよね。しかし、たとえば手には、おそらく大脳的認識とはまた違う感度、解析能力、判断能力を持ったセンサーがあるはずなんです。言語化される以前の、僕らの身体性が持っている世界認識の力がきっとある。一見同じ仕草を繰り返している職人さんでも、実は土を掴んだ瞬間に粘性や多くの要素を判断し、微妙な調整をしていると思いますし、職人レベルまでいかなくても、きっと僕らが日常的にやっていることであるはず。ともすると僕らは、わかりやすく言語化された情報に引きずられがちですが、そうではない、使いこなした「道具」的なものに対する評価も必要でしょう。

──僕は一切運転免許の類をもっていないし、取得しようと思ったこともないのですが、僕のちょっと上の団塊ジュニア世代くらいの人までは、特に男性にオートバイや自動車が好きな人が多い。彼らは愛車を自分自身そのもののように考えて、大切に運転し、手を加えている。しかし、こうした身体拡張の快楽と、柳をはじめ民藝運動で言われていた「道具」的なものとの関係がもたらす身体拡張は明らかに違うように思えるんです。
むしろ、柳たちは「壊れたら取り替える」ような儚さも含めて、「いとおし」んでいるように、僕には見える。この「いとおしみ」は愛車のバンパーが事故で凹むと、自分の顔に傷がついたように悔しがるドライバーの愛車への感情とは決定的に異なっているように感じます。
この違いをどう考えたらよいのでしょうか。たとえば柳も、工場で大量生産されたものを否定する一方で、作家のイニシャルが付けられているような「作品」も否定しており、手作りなんだけど無名な、中間的な存在を称揚していた。柳たちが民藝運動の中で、結果的にかもしれないけどたどり着いた、こうした対象への中間的なアプローチは、柳たちの運動の蓄積から現代に通じる「民藝的なもの」を抽出するときにカギとなってくると思うんです。
鞍田 なるほど、面白い。もちろん、柳はものすごい民藝品のコレクションを作り上げていたので、フェティシズムがまったくなかったわけではないと思います。でも、愛車に名前をつけてしまうようなフェティシズムは、民藝のまなざしから考えると、健全さから乖離しているかもしれないですね。
──距離感の話でいえば、「他力」が民藝運動のキーワードになっていますよね。対象を人間の力でコントロールしていく「自力」ではなく、その外側にある「他力」に頼ることが大切だと。
鞍田 民藝において、「自力」と「他力」を区別する一つの基軸として、自己意識の有無があります。道具を使いこなしているとき、自己意識は生まれてこないと思うんです。たとえば、自転車を漕いでいるとき、いちいち「右足を出している」「左足を出している」とは考えませんよね。同じように、ろくろを回すときも、回っていくがままに任せ、委ねている。「こうしてやろう」といった企みから離れることが、「自力」からの乖離を叶えると考えられていたのだと思います。
──卓越した職人は、ろくろを回しているのではなく、回されているということでしょうか?
鞍田 おっしゃる通りです。また、自然素材のものを扱うことが多かったので、何でも人間の意のままにはならないと伝える意図も、「他力」という言葉には込められていたと思います。たとえば、焼き物を作るにしても、最後は窯の中で委ねるしかない。対自然という観点で考えたとき、人間の限界を自覚し、「自然に委ねる」「自然からいただく」と関係性に託すことが必要だと思うんです。
それと、過去に対する現在の限界、その土地に蓄積されてきた経験値への敬意も表されていると思います。柳たちの時代にも、現代で言うところのグローバリゼーションのような、ローカリティを希薄にしていく圧があった。それに対する防波堤として「他力」を提唱していたのだと思います。過去の膨大な経験値を考えたとき、限られた自分自身の一生で創出できるものなんて、たかが知れていますから。
あらゆるコトが画一化するいま、モノこそが固有の体験を生み出す
──「美しさ」から「いとおしさ」へ、「民藝」そのものから「民藝的なもの」の抽出へ、ということをこれまでお話しいただいてきたわけですが、こうした地に足のついた生活空間の中から、外部に越境するのではなく、内部に潜ることで超越したものにアクセスしていくという路線で物事を考えようとする試みは、常にあるパターンで失敗してきた歴史があると思うんですね。それは要するに、潜って、降りて深いところまでたどり着く前に、共同体の内部で展開する文脈操作のゲームに取り込まれて、そこで止まってしまうという現象だと思います。たとえば日本の1980年代の消費社会論がそれだったはずで、ミクロな「暮らし」への視線の誘導が、マクロな政治や経済のメカニズムに対しての視線を殺してしまった。当初は1960年代、1970年代的な左翼の失敗に対する反省から生まれてきた言説だったものが、結果的に自分たちが依存している構造の問題を忘却するメカニズムとして機能してしまう。こうして日常の中に閉塞してしまうと、たとえば全体主義的なものに抵抗し得る自立した個は絶対に形成できない。このような批判を乗り越えない限り、いま抽出しようとしている「民藝的なもの」の力を信じることは、なかなか難しい気もするのですが、いかがでしょうか。1990年代に民藝運動がカルチュラル・スタディーズの文脈で手厳しい批判を受けていたという話もありますが。
鞍田 「民藝的なもの」そのものを批判しているわけではないのですが、ハンナ・アーレントの『人間の条件』でも、「親密さ」が低い評価で扱われています。ドイツで生まれた全体主義的なものから被害を受けたアーレントは、近しい者に対する愛着や親密圏的なものが、ある種の排他性をはらんだり、情緒的なものに促されたポピュリズムを胚胎したりすることへの警戒心を持っていた。もちろん、柳が社会貢献や国の政策への協力を試みていたわけではありませんが、「いとおしさ」がそうした危うさをはらんでいる点は意識しておく必要があると思います。
民藝が様式化してしまったことで生じた本末転倒さや、柳の朝鮮文化に対するまなざしに隠れたオリエンタリズム、文化的なバイアスが指摘されています。
そうした批判に対して、民藝運動の側は本質的な反論ができず、甘んじて受け入れてしまっていました。1990年代当時、学生だった僕から見ても、民藝運動はカルチュラル・スタディーズからの批判を跳ね返せる思想的な強固さはなく、評価しづらい印象を受けていましたね。僕がもともと専門としていた哲学においても、同時代の他の哲学的言説と比べて、柳の言葉遣いに素人っぽさを、その思想に貧弱性を見出す共通認識がありました。
──片方では、柳が100年前に名指した瞬間に権威化し、事実上の美術と化していった「民藝」という制度があり、もう片方では、消費社会とコマーシャリズムに巻き込まれていった「民藝」ブームがある。前者は美術のバリエーションの一つであって、かつて柳が見出した批判力はないし、後者はアーレント的な批判から逃れられない。この二項対立を超える方法を考えたときモノそのものではなく、モノから生まれるコミュニケーションに力点を移すことが糸口になるかもしれないと思いました。それが「美しさからいとおしさへ」という視点の切り替えなのかもしれないですね。
鞍田 自分でもそこまで整理したことはなかったのですが、おっしゃる通りだと思います。そして、美術化していく流れにせよ、コマーシャライズされていく流れにせよ、弱くて平凡だったはずのものを、より強く価値のある別のものへと仕立て上げてしまっている点に問題がある。先ほども指摘しましたが、弱さを弱さとして、平凡を平凡のままに受け入れることが、最も大事だと思います。
少し話が逸れますが、こうした考えを抱くようになったきっかけは、大学の授業での学生さんからのコメントでした。2020年6月に期間限定で公開されていた、バンクシーによるものと思われるネズミの絵と、日本の入国管理局の難民収容問題に反対するグラフィティとの対比に焦点をあてた短編ドキュメンタリー映画『INVISIBLE – A Rat and Refugees』を見せて、日本の寛容性の低さを指摘したときに、「でも、アートになっているだけ良いですよね。自分たちの想いを表現できない人たちが実はたくさんいるはずで、そうした人たちへの向き合い方を考えなければいけないのではないでしょうか」とコメントしてくれた学生さんがいて。
確かにそうだな、と思わされました。「グラフィティまで作れている人は恵まれているよ」という視点こそ、僕らが見落としていたものだったのではないかなと。僕らが見ようとしている「いとおしさ」は、表現や言語化に至らないものから、見出していかなければいけないと。言葉にすること、デザインすること、形にしていくことを一度封印し、それ自体と向き合うところからしか見えてこないものがあるのではないかということです。とはいえ、僕は言葉を扱う人間なので、さらにもう一度言語化していかなければいけないのですが。

▲身近にある木や草を素材としてカゴやザルなどをつくる編み組細工という技術がある。写真は編み組用にヤマブドウの蔓を割いているところ。手のたくましさに見入ってしまった。福島県大沼郡三島町にて。(撮影:鞍田 2016)
──「それ自体と向き合う」とは、具体的にはどういった取り組みを思い描いていますか? たとえば、名もなき職人がつくった民藝品があり、それに対してすごく魅力や批判力を感じても、それを美術批評として制度に接続するかたちで語ることも、コマーシャリズムに乗せて「ていねいな暮らし」のイメージとして流布するのでもなく、固有の体験としてそのまま取っておく、ようなイメージでしょうか。
鞍田 まさに、おっしゃる通りです。制度に拠るわけでも、産業に寄り添うわけでもなく、その場限りの、極めて個的な体験として受け止める。それは語りようも形にしようもないので、一度はどこかでコミュニケーションの断絶を経験しなければいけません。
でも、本当のコミュニケーションは、その断絶からこそ生まれてくるものなのかもしれません。語りえない、つながりえないと思ったとき、はじめて「なんとかつながりたい」という試行錯誤が始まります。すでに出来上がった「つながれる」ツールに自分を託すのではなく、つながれない体験こそが、切実な“つながりたさ”を生み出していくはずです。民藝は、そのもがきの痕跡のようなものを、僕らにチラ見させてくれているのではないでしょうか。
──僕の問題意識に引きつけると、インターネットが普及するまで、ものをしっかり考えている人間はみんな、消費社会批判を一生懸命にやっていたわけです。ここのままいくと、マクドナルド的なものにライフスタイルが画一化されていくので、どうにかして固有の体験を取り戻さなければいけない、と。そして、インターネットはそのための武器だと考えられていた。モノは一様だけどコトは多様で、モノからコトへの変化を後押しするのがインターネットだ、と。
でも、それから四半世紀ほど経ち、むしろ逆であるとわかってきた。インターネット、特にSNSが中心となった現在のインターネットは、ボトムアップの全体主義の温床になっている現実がある。この状況を踏まえたとき、僕はむしろモノのほうが自由な状況下にあると考えています。むしろ現代の情報環境下では人間の考えている「コト」や、やってしまう「コト」のほうがよほど画一的になってしまうし、人間は「コト」の次元では自ら右にならい、長いものに巻かれることで安心するようになっていくことが証明されてしまった。対して、モノの世界はマクドナルド的な大量生産の外側にいくらでも広げていける。メイカーズ・ムーブメントなどはその一例だったはずですね。要するに、モノは閉じた相互評価のネットワークの外側にいくらでも存在することができるけれど、人間の意識は自ら閉じた相互評価のネットワークの中に引きこもってしまう。いま、考えなければならないのは、放っておけば画一的になってしまうコトを、どうモノの力で多様にしていくのか、ということじゃないでしょうか。僕は現代はもう一度、モノの水準で考えることに挑戦しなきゃいけないタイミングだと考えています。
鞍田 むちゃ共感します。別の言い方をすれば、モノには僕らが考えている以上のコトが秘められている。コトが多様で個別的になるための要も、結局はモノなのかもしれません。時間や空間、その場所にあるモノの個別性こそが、体験の個別性をかたちづくる。コトだけが宙ぶらりんで浮くことは、決してないと思うんですよね。
僕が民藝に深く入り込んでいくようになった大きなきっかけに、岡本太郎がいるんですよ。岡本は日本文化論を語るとき、「生活」というキーワードを使うんです。地方の文化や縄文土器などを訪ねたとき、「生活の肌理(きめ)」という言葉を使っていました。いま話している固有性の話も、「きめ細かさ」の問題といえるのではないでしょうか。一様化していく言説ではすくい上げられない、きめの細かい言葉、きめの細かい体験を得ること。これは、ノイズのようなかたちで絶えず残っているものを、うやむやにしないということでもあると思います。
現代社会に「民藝的なもの」が発露する意外な場面
──「いま、民藝とはなにか」という問いが繰り返される中で、前提として「『民』も『藝』も変わってしまった」ことがよく指摘されます。たしかに今日において「民」は一度は戦後中流を指す言葉になって、もはやいまはそれすらも解体されつつあるし、「藝」といえば情報技術が想起される。近代化のもたらした物資文明に生きる民衆と、20世紀を席巻した重工業。この二つの仮想敵が変質してしまった現代、民藝はいかにしてあるべきなのでしょうか。
こんな質問をするのは、僕が鞍田さんのお話を聞いていて、おそらくいま考えられているのは、優れた職人さんの優れた手仕事を探してきて、「これが現代におけるよい民藝です」と提示することではないだろうな、と想像できるからです。先ほども触れましたが、やはり民藝ではなく「民藝的なもの」こそが、現代における民藝として機能する。だとするとモノからコトの水準に移して考えるしかないと思いました。
鞍田 そうですね。もちろん、たとえば3Dプリンターが登場したときに起こった、「これが現代の民藝だ」と捉える議論を面白いとは思いました。「ただ買えば済む」消費社会に対するアンチテーゼとして、作ることを民主化していく。工芸が変質したことによって、作ることがもう一度自分たちの手元に戻ってきていることは、アリなのではないかと思っています。その時代特有のリアリティが希薄になっていくことを危惧し、何とかしてそれを取り戻そうとしている点では、100年前も現代も変わらないはずです。
でも、おっしゃる通り、リアリティを取り戻すための手段として、現代における「民藝的なもの」を探る必要もあるとも思います。そういう意味では、僕は最近、たとえば福祉は「民藝的なもの」が発露する舞台としてあり得ると考えているんですよ。
──福祉ですか。まったく想像もしませんでした。
鞍田 福祉の現場は今後、より日常化していくはずです。社会の高齢化がますます進んでいくのはもちろん、ある種の精神的な疾患も、どんどん他人事ではなくなってきている。日本の人口あたりの精神病床数が他国と比べて圧倒的に多い点はよく指摘されますが、精神バランスを崩した人たちを社会の中でいかにして受け入れていくのかは、大事な潜在的課題であるはず。介護や精神疾患が日常化していく中で、心身両方において、パーフェクトではない不完全なかたちでも生きていけることが求められると思うんです。
そこでは、生きづらさをどれだけ共有できるのかが問われている。僕らは何がしかの不完全さを持ちながら生きていると思うのですが、そこに対する寛容性が、いますごく乏しくなってしまっている気がするんです。健全でなければいけない、完全でなければいけないという圧がある。だからこそ、社会の中で「負けて」しまった人たちと、勝ち負けではないフラットな関係性を再構築していくことが求められているはずですし、「民藝的なもの」はそのきっかけになり得ると思っています。実際、『民藝のインティマシー―「いとおしさ」をデザインする』を読んでくれた福祉現場の人からの問い合わせも、何件かありました。福祉の現場でもう一度「いとおしさ」を考えていくために、「民藝的ケア」のようなものがあるのではないかと言ってくださって。

▲刈り取ったカラムシ(苧麻)から繊維を取り出す作業の様子。カラムシは古くからの衣料素材。福島県大沼郡昭和村では、畑での栽培から糸作り・機織りまで、すべて手仕事で営まれている。(撮影:鞍田 2017)
──完全に想定外だったので、すごく驚きながら聞いていました。たしかに福祉は今後、誰もが当事者になり、生活の一部に入り込んでくるはずですし、勝ち負けに回収されない「中間的なもの」が福祉の現場に結果的に発生していくという話は、とても納得感があります。
一方で、福祉の現場で、美しさを包摂する「いとおしさ」が具体的にどのように現れてくるのか、いまいちイメージしきれていないところもあります。いわゆる民藝品であれば、器が半ば結果的に表現している美学や世界観があり、その器を使い続けることで自分の生活が変わり、自分の美学や世界観が変化するという運動が発生する。これはよく分かる。つまり、モノとの関係が変わることで、自分の世界の見え方も変わっていく。対して、福祉現場においては、圧倒的に「対モノ」ではなく「対ヒト」の世界が広がっている。つまり「モノ」ではなく「コト」の世界ですね、そこでは、どのような現象、どのような運動が生まれるのでしょうか。
鞍田 たとえば作業療法のように、手を動かしてモノを作る営みを通じて治癒されていくかたちがあります。与えられたモノに対峙するだけではなく、自分自身が作る営みを経験することで、コミュニケーションのあり方や世界との接続の仕方をもう一度整え直すことは、すでに実践されている。
うちのゼミに来ている作業療法士の方から、面白い話を聞きました。近年の作業療法は、「作る」が拡大解釈され、陶芸のようなものだけでなく、たとえば「パジャマを着る」といった日常的な振る舞いも「作業」と位置付けられるようになっているそうです。その方は「『作業』の意味するものがジェネラルになってしまって、本質から逸れてるんじゃないか」といった問題意識を持ってゼミに入ってくれたのですが、なんと作業療法はもともと、アーツ・アンド・クラフツ運動に影響を受けて始まったものらしいのです。柳の民藝運動にも、アーツ・アンド・クラフツ運動からの影響が指摘されていますが、同じ原点から民藝、作業療法、福祉と枝分かれしていったものが、もう一度結び直されている感じがしますよね。
──民藝が福祉に結びつくのは、ルーツをたどれば必然的な流れだったんですね。
鞍田 民藝運動が勃興した時代を振り返ると、日本だけに限って言っても、生活改善運動や民俗学、それから社会主義的な運動まで、同じ景色を見ているけれど目標や目的が異なるアプローチがいろいろと並行して起こっていて、民藝はその一つにすぎなかったと思うんです。
以前、中沢新一さんに「マルクスは100年もたなかったけれど、民藝はもっているよね。なぜだと思う?」と問われたことがあって。マルクス主義的な社会運動は空中崩壊してしまったけれど、民藝は紆余曲折あってコマーシャライジングに吸収された部分もありつつも、ひたひたと続いている。民藝や福祉の中には、社会改革的な要素も趣味的な要素もあるけれど、なにか僕らの社会や生活で乖離してしまったものを回復しようという志向性が通底していると思っていて、僕らはいま、その「なにか」を掴もうとしているのだと思います。

▲三島町や昭和村は福島県の最奥部に位置し「奥会津」とも呼ばれる。山深く豪雪地帯でもある。奥会津には、いまも日々のいとなみとしてさまざまな手仕事が息づき、近年は域外から移り住む若者もいる。写真は昭和村にて。(撮影:鞍田 2016)
──こうして考えると福祉の現場は、自分の身体の不自由さを抱えている人たちが、モノと向き合うことでもう一度、自分と世界との関係を結び直していく現場なのかもしれませんね。アーツ・アンド・クラフツ運動が起こったのも、それまでは存在しなかったものが存在するようになり、ある種の不自由さを抱えていた人びとが、「モノ」を通して自分と世界との関係を結び直した時期のように考えられます。もしかしたらいま、同じような運動が福祉の現場で反復されているのかもしれないですね。
鞍田 そう思います。とは言っても、いわゆる伝統工芸としての民藝は、なにがしかの共感者がいないと経済的に維持しえない状況に置かれていると思います。現代において、素材や技術にこだわったものづくりはニッチな営みですから。だから、もし良いと感じるのであれば、積極的に応援してほしいです。
ただ、「民藝的なもの」はまた別の話です。地域的、技術的、素材的に閉じたものではなくて、半径5kmの中にもたくさん潜んでいるものだと思う。もちろん、伝統工芸としての民藝が持つローカリティや製品の安全性、伝統とのつながりも大切です。でも、それを特別視して遠ざけてしまうのではなく、身近に潜む「民藝的なもの」、一見よそよそしくなってしまった社会や生活を、もう一度自分たちの手に取り戻すための入り口に手を伸ばす人たちがどんどん増えてきてほしいと思います。自分の生活でそれを体感してこそ、地続きで存在している伝統工芸的な民藝も応援できるはずですから。そうすることで、微々たるものかもしれないけれど、きっと社会は少しずついいものになっていくのではないでしょうか。
──個人的にも教わるところの多い刺激的なお話で、大変勉強になりました。ありがとうございました。
[了]
この記事は、宇野常寛が聞き手を、小池真幸が構成を担当し、2020年10月5日に公開しました。Portrait photos by Akemi Kurosaka
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。