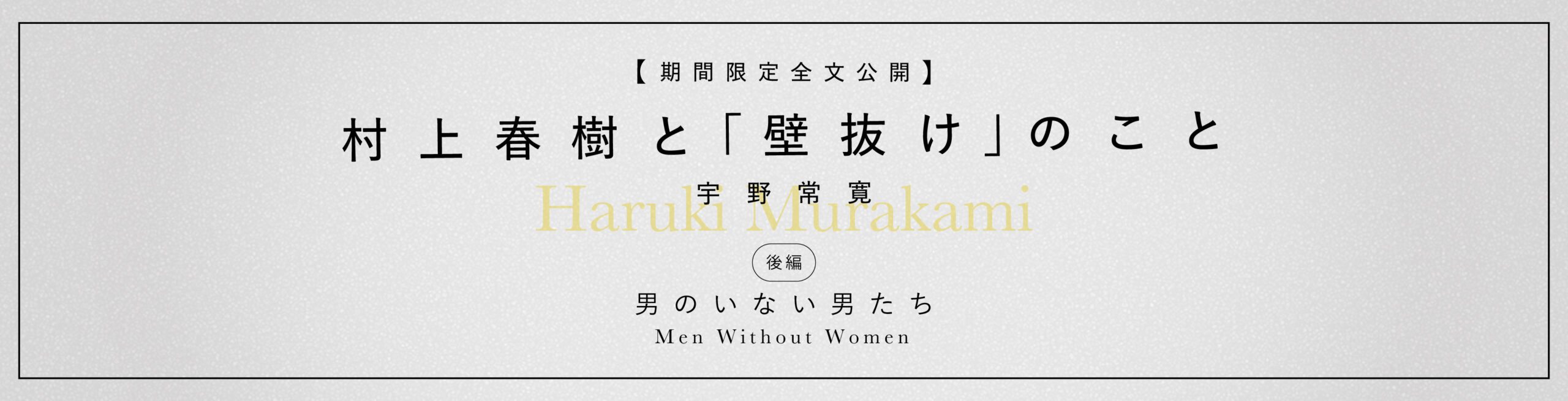村上春樹『街とその不確かな壁』の発売のタイミングで、僕が半年前に出版した『砂漠と異人たち』に掲載した村上春樹論を期間限定で全文公開します。『街とその不確かな壁』については、近いうちに批評文を発表する予定ですが、この合計約4万字のテキストは『街とその不確かな壁』の予習としても、おそらく多くの読者が頭を抱えるであろう同作を考える上でも大きな手がかりになるはずです。
そして、もし心に引っかかるものがあれば『砂漠と異人たち』の全文を読んでもらえたら嬉しいです。ここで指摘している村上春樹が乗り上げた巨大な暗礁から脱出する方法を、僕なりに考えて示しています。(宇野常寛)
端的に言うとね。
21 村上RADIOと京都マラソン
村上 こんばんは、村上春樹です。
美雨 こんばんは、坂本美雨です。JFN年末年始特別番組「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」ここからの二時間、全国38局をネットしてお送りしています。そして今日はわたしたち、京都某所から生放送でお届けしていきます! 春樹さん、大晦日、しかも生放送ですね。
村上 生放送、緊張しちゃいますよね。生まれて初めてです、こんなことは。
美雨 今年はいろいろなことが初めてだったと思いますが、やはりコロナ一色の一年でした。いろいろキーワードも出てきた、3密とか、ソーシャルディスタンスとかありましたけれども……春樹さんにとって「最大のニュース」は何でしたか?
村上 もちろんヤクルト最下位です、というのは冗談で、やはりコロナはやはり大きな話題になりました。コロナなしでは、今年一年は考えられないですよね。
美雨 ほんとうにそうですね。多くの人の人生が変わった一年だったと思います。春樹さん、初の生放送ということで、今日はお友達が来てくださっていますが……。
村上 猫山さん(みゃ~)も、羊谷さん(めぇ~)もいますね。あとでもう一人で来ますが、とりあえずいまはまずこの二人です。
二〇二〇年から二〇二一年への年越しを、僕は村上春樹がDJを務めるラジオ番組を聴きながら過ごした。この作家が以前から度々ラジオで話していることは知っていたが、実際に聴いたのはこのときがはじめてだった。はじめての生放送らしいその番組で話す村上は、明らかに緊張していた。これまで海外の文学賞の授賞式をはじめとして僕には想像もつかないような大舞台を経験してきたはずの人でも、慣れない舞台に上げられると靴の裏にこびりついたガムのように硬くなってしまうのだなと意外に感じた。そして、村上が時々口にする――おそらくはかなりがんばって、無理をして差し込んだ――冗談の数々は、びっくりするくらいおもしろくなかった。特に、取り上げたEメールの送り主に村上がつけてあげるラジオネームの類がなんというか、ちょっとした事故と言えるレベルで寒々しくて、でも、僕はそれがとても微笑ましかった。「あなたには、ラジオネーム『牛に引かれて〈いきなりステーキ〉』を差し上げます」と言われた東京都の三十歳の女性が、少し羨ましかった。気の若い団塊世代のおじいちゃんがこの年末――それは世界中の人たちが疫病に怯え、苛立ちながら家の中に隠れて過ごす年越しだった――に一生懸命に楽しい時間を演出しようとしてくれていることが、なんだか嬉しかった。
僕は実際に番組を聴く前には、村上春樹はもっと彼の書く文章の、特に一人称の小説のように饒舌に、気の利いた固有名詞をちりばめながらユーモアを交えて軽快に話すものだと思いこんでいた。しかし、逆だった。そこにいたのは、どちらかと言えば人前で話すことに慣れないまま七十代を迎えた一人のおじいちゃんだった。彼の声からは一生懸命にマイクに向かって話しながら、その難しさを楽しんでいるのが伝わってきた。そのぎこちなさに僕はとても、好感を抱いた。このようなおじいちゃんになるのも悪くないなと思わせてくれる、知的で、内省的な人間なりの「できない」ことを引き受ける姿に、僕はちょっとした感銘のようなものすら受けていた。ただ一つだけ、引っかかるものがあった。それは村上が(ゲストとして登場した山中伸弥との会話の中で)その年の二月に出場した京都マラソンで、完走に失敗したことを繰り返し嘆いていたことだ。
〈山中 ちょうど1年前に、中国の武漢で訳の分からない肺炎が出ているというニュースがあったわけですが、こんなことになるなんて誰も予想していませんでした。僕は2月に京都マラソンを走りまして、自己ベストを更新しましたが、天気が悪くて寒い日でした。
村上 一緒に走ったんですよね。でも僕は脱落してだめだったんです。生まれて初めて完走できなかった……。悔しくて、今年中になんとかしようと思っていました。〉
村上春樹が熱心な市民ランナーであることはよく知られている。三十代前半で経営していた喫茶店を他人に譲り渡し、専業作家としての生活を開始したときに走り始め、それから週に六日、十キロメートルを目安に走り、小説を書くための体力を維持しているのだという。そしてそれから四十年間、七十代を迎えた今日にいたるまで村上は世界各地でフルマラソンやトライアスロン・レースを走り続けている。
僕も走ることが好きなので、村上のこの話をとても興味深く聞いた。京都マラソンは僕もいつか出場したいと考えている大会だったし、村上の肉声で走るという身体的な行為についての言葉を聴くことにも興味があった。そしてこのとき僕は同じ市民ランナーの一人として七十歳を過ぎたランナーがフルマラソンの完走に失敗したことを悔やむ姿に疑問を抱いたのだ。
僕はまだ本格的に走り始めて数年で、いまだに大会らしい大会に出場したこともない。月に十回ほど十キロメートルを走ることを目安にしていて、ときどき時間のあるときには二十キロメートルを走ることもある。二十キロ走ってもあまりへこたれなくなってきたのでそろそろ走行距離を増やしてフルマラソンの大会へのエントリーを考え始めているのだけれど、そのような僕からしてみればランナーとしての村上は遥か前方にいる。自分もよく走っているからこそ、村上春樹の高い走力には驚くしかない。そもそもあの年齢でフルマラソンの大会にエントリーしていること自体が、並大抵のことではないはずだ。しかし、それでも村上は自分の衰えが気になって仕方がないようだった。実際に村上にとって、この失敗は相当大きな出来事だったらしく、彼はこの一年ほど、ことあるごとにこの話題について触れている。たとえばスポーツを専門にする雑誌のインタビューに答えて、村上はこうも述べている。
〈実は今年の2月に京都マラソンに出たんです。ところが調子がよくなくて、制限時間(6時間)を超えちゃったんですよ。途中、賀茂川の河川敷を走るんですが、そこがぬかるみになっていたので歩いちゃったりして。だから記録なし。38年間走ってきて、こんなことは今までなかった。これまでは必ず完走していたんです。初めてのことでショックでした〉
〈「タイムはどんどん落ちていくわけですから、僕は負け戦を闘っているんです」
さらりと語る春樹さん。
――負け戦なんですか?
「そう。ミッドウェー(海戦)以降の日本軍みたいなものです。ソロモン、ガダルカナル、レイテ……。つまり撤退戦ですね。それは壮絶な闘いになる」
――壮絶なんですか。
「ナポレオン率いるフランス軍がモスクワから撤退する感じ。撤退戦をどう闘うか。戦局を挽回するためのバルジ大作戦みたいなもの。最後の反抗なんですよ」〉
僕は村上のこのような態度を、彼がラジオでちょっと無理をして話しているあまりこなれていないジョークと同じように微笑ましく思う。そのいじらしさを、愛おしくすら思う。この結果的に生じる親しみは、村上の書く小説の主人公のもつ堅牢なナルシシズムからは決して得られないものだ。
だがその一方で、この村上の負け惜しみに、正確には走ることへの態度に微かな、しかし決定的な違和感を覚えるのも事実だ。それは七十歳を過ぎたのだから、そろそろタイムが落ちることや完走に失敗することを受け入れてもいいんじゃないかといったことではなく、もっと根源的な違和感だ。僕もまた、走ることを自分の生活の中で欠かせないものにしている市民ランナーの一人だ。そして、こうして村上が走ることについて書いたエッセイの類や、走ることについて話した雑誌などのインタビューを目にするたびに、僕は村上のように走ることはできないし、そもそも彼のようには走りたくないと感じてしまうのだ。以前は――自分自身が走るようになる前は――それを彼のストイックな美学の表明として好ましく感じ、むしろささやかな憧れをすら抱くことが多かった。しかし、今は僕と村上は、走るという行為を根源的なレベルで全く異なるものとして捉えていることを強く感じる。そしてこの「走る」ことについての捉え方の違いは、村上の小説の、特に近作に感じる違和感につながっているように思えるのだ。
そう、僕の判断では小説家としての村上春樹はいま、巨大な暗礁に乗り上げてしまっている。そしてそこから脱出できなくなっている。いま村上の小説をそこに閉じ込めているものと、僕がランナーとしての彼の言葉に覚えた違和感の原因はおそらく同じものだ。村上春樹はそれにとらわれて、なにか大切なものを見失ってしまっているのではないか。そのために、小説家として設定したハードルに対して、撤退戦を強いられているのではないか。それが僕の判断だ。そして、この村上春樹が乗り上げた暗礁は、「アラビアのロレンス問題」を考える上でも、決定的と言っていい示唆を与える。そう、僕は考えている。
これは村上春樹という小説家の作品に対する批評であるとともに、ランナーとしての村上春樹に対しての批評でもある。それが入り口だ。出口があればいいと思う。もしなければ、文章を書く意味なんて何もない。
22 「コミットメント」のゆくえ
〈コミットメント(関わり)ということについて最近よく考えるんです。たとえば、小説を書くときでも、コミットメントということがぼくにとってはものすごく大事になってきた。以前はデタッチメント(関わりのなさ)というのがぼくにとっては大事なことだったんですが。〉
〈ぼくは思うのですが、いま日本の社会というのは、さっきもオウムと地震の問題が出ましたが、精神的なコミットメントの問題で、大きな変革の地点にいるんじゃないかなと感じるのです。この二〜三年で日本はずいぶん変わっていくんじゃないかという気がするのです。〉
これは『ねじまき鳥クロニクル』の刊行後に行われた河合隼雄との対談での村上の発言だ。「デタッチメントからコミットメントへ」――村上春樹は、およそ四十年の作家としての活動のうち、後半の二十年間を費やして現代におけるあたらしい「コミットメント」のかたちを模索してきた。デタッチメントとは何か。なんに対しての「関わりのなさ」か。それは、二〇世紀を席巻した政治的なイデオロギーによって人々を動員する回路からのデタッチメントだ。一九六八年の記憶――国内においては全共闘の勃興と衰退として現れた、世界的な学生反乱の季節――から出発した村上春樹にとって、マルクス主義が代表するイデオロギーに対する「デタッチメント」こそが、その後の(七〇年代の、そして八〇年代の)文学的な主題の中心にあったことは間違いない。
デビュー作『風の歌を聴け』、第二作『1973年のピンボール』、そして続く『羊をめぐる冒険』の初期の三部作は、連続して登場する主人公の「ぼく」(村上春樹と同世代の男性)とその友人の「鼠」との対比で物語が展開する。
「ぼく」と「鼠」は小説内で、世代的に六〇年代末の反乱の季節と、七〇年代初頭の挫折を経験していることがほのめかされる。そして彼らはそのかかわりの深度こそ描かれないが、精神的にあの時代につかまれてしまい、結果として傷を負っている。その傷とはイデオロギーの力が個人を塗りつぶして、全体の一部に取り込んでしまう現実に直面したことによるものだ。
イデオロギーの力によって自分の生が歴史上に意味づけられることの昂揚と安心を覚えてしまった人間は、思考する力を失う。歴史を前に進めるためにコミットしているという昂揚と、その行為が集団の中で認められる安心に支配され、目の前の一つ一つの物事について考えることを放棄する。こうしてマルクス主義に代表されるイデオロギーに魅入られた人間が集団の中に埋没し、破壊と殺人に加担する機械と化していった時代への反省から、「ぼく」は物事に対する「デタッチメント」を選択して生きている。イデオロギーの力で歴史上に自分の生に意味を見つけるという二〇世紀の世界を席巻した生き方に対して、彼らは――他の多くの同世代の活動家がそうであったように――距離を置いたのだ。
そして「ぼく」は古い世界に距離を置くように、その後に訪れた「消費社会」や「ポストモダン」といった言葉で形容された新しい世界にも距離を置いている。「ぼく」は新しい世界を支配する、高度資本主義の代表するシステムを拒絶しない。しかし、流されもしない。それが「ぼく」の倫理として選択したあらゆるものに距離を置く「デタッチメント」だ。
しかし、「鼠」はそうはできない。「ぼく」と異なって「鼠」は新しい世界を受け入れることができない。「ぼく」は新しい世界に心地よさと喪失感の相反するものを感じている。新しい世界の実現した、個人であることの快楽と歴史が個人の生を意味づけない虚しさという二つのことを受け入れることで精神的なバランスを保っている。しかし「鼠」は新しい世界を受け入れることができずに、後ろめたさを感じ続けている。彼はその後ろめたさから「コミットメント」を断念できない。しかし、学生反乱の敗北を経た彼には「コミットメント」の方法が分からない。スターリンの強制収容所や連合赤軍の末路が象徴するもの――イデオロギーによる生の意味付けのもたらす副作用――に直面し、それを克服する方法を見つけることができずに敗北した若者たちの多くは、「ぼく」のように(そして「ぼく」ほど自覚的ではなく)新しい世界の快楽を享受することでその喪失感を埋め合わせてきた。しかし、「鼠」にはそれができない。村上のデビュー作『風の歌を聴け』と第二作『1973年のピンボール』は、古い時代にその精神を置き去りにしてきた「鼠」と、新しい世界を受け入れた「ぼく」を対比することで、時代に対する距離感と進入角度を描いた作品だと考えればよいだろう。
最初のターニングポイントは三作目に当たる『羊をめぐる冒険』だ。一九七九年にデビューした村上春樹はその二年後に学生時代に開業したジャズ喫茶を他人に譲り、小説に専念する。こうして書き上げられた『羊をめぐる冒険』は、村上春樹がはじめて発表した本格長編であり、その物語は後の多くの村上の作品の原型となっている。
同作で村上春樹はマルクス主義が失敗した後の新しい世界を受け入れながらも、そこに新しい悪を見出そうとする。高度に発達した資本主義の中では像を結ぶことの難しい、しかし確実に存在する、僕たちを見えない力で縛り付けているシステムのもつ暴力性を物語の力で、それもファンタジーの想像力を用いて提示してみせる。それは所得格差や環境破壊といった目に見えるものではなく、戦後の日本社会に出現した中流層がその豊かさと引き換えに生への実感を失っていく高度資本主義のシステムのひずみが生んだものだ。イデオロギーによって歴史上に生の意味を見出す回路が後退したことによって浮上する新しい人間疎外、世界に素手で触れている感覚の喪失がもたらすものを村上春樹は現代における「悪」として設定したのだ。
この新しい世界の、新しい悪の原型となったものが、『羊をめぐる冒険』に登場する「羊」だ。この「羊」は実体を持たない、超自然的な存在で人間に憑依し、その人物を支配することで「目的」を遂げていく。物語の舞台となる一九七九年時点では、ある老人に憑依して国内の保守政党と広告業界を支配する「羊」は、物語の中で「鼠」に憑依する対象を移し、彼の自殺によって永遠にこの世界から消失することになる。「ぼく」は「鼠」に導かれて「羊」をめぐる冒険に出発し、そして「鼠」の遺志に従って彼と「羊」との対決の後始末をすることになる。ここで、「ぼく」のコミットメントはささやかなものだ。実際に自らの命を差し出して「羊」を消滅させるのは、「ぼく」本人ではなくその親友の「鼠」であり、「ぼく」は一連の出来事を目撃し、「鼠」がやり残したことを引き継いでその試みを完遂するだけにすぎない。そして、再び新しい世界に対して中距離を保つデタッチメントを選択し、新しい世界の豊かさを享受して貧しさをやり過ごす世界に回帰していく。そこに描かれているのは、自分の分身的な存在(親友の「鼠」)の自死による正義の執行=コミットメントに、目の前の多くのものに「やれやれ」とデタッチメントし続ける「ぼく」が巻き込まれるかたちで、結果的に自身もコミットメントすることになるという物語だ。この「受動的なコミットメント」のモデルは、後に一九九五年以降の村上春樹の小説の中心に置かれる回路として発展していく。同作における「羊」は、この後の村上の小説に登場する超自然的な「悪」の原型だ。その「悪」とは『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「やみくろ」であり、『ねじまき鳥クロニクル』の「綿谷ノボル」であり、「かえるくん、東京を救う」の「みみずくん」であり、『海辺のカフカ』の「ジョニー・ウォーカー(に憑依していたもの)」であり、そして『1Q8 4』の「リトル・ピープル」である。そして「ぼく」のバリエーションであるこれらの作品の男性の主人公は、時代とともに更新される「悪」と対峙することになる。
村上春樹が「デタッチメントからコミットメントへ」を標榜し、その小説の中心的な主題に設定するのは一九九五年に完結した『ねじまき鳥クロニクル』以降のことだが、『羊をめぐる冒険』に既にその新しい「コミットメント」の原型が、提示されているのだ。
しかし、村上春樹は「コミットメント」に至るまでに一度「デタッチメント」に回帰していく。続く長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』がそれだ。
このとき村上春樹が提示したのは、いわば「倫理としてのデタッチメント」ともいうべきものだ。この小説は自分の深層心理をブラックボックスとして用いて高度な暗号を生成する「計算士」を生業とする「私」の物語(『ハードボイルド・ワンダーランド』)と、その「私」の深層心理の世界を描く『世界の終り』――こちらでは主人公の一人称は「僕」に変化する――の二つの物語が一章ずつ交互に語られるという形式を持つ。
同作には、高度資本主義のもたらすひずみの象徴として「やみくろ」と呼ばれる超自然的な「悪」が登場する。『ハードボイルド・ワンダーランド』のパートでは、この「やみくろ」の手先である「記号士」の組織とそれに対抗する「計算士」の「私」が、数日後に意識が消滅する(事実上の死を迎える)運命に直面する。当初は抵抗を試みていた「私」だが、やがて運命を受け入れ、一人孤独に意識の消滅を受け入れる。
対してその「私」の深層心理の世界を描く『世界の終り』のパートでは、「壁」に囲まれた街に「僕」がたどり着く。この街に暮らす人々は、感情を失っている。そのために、街のなかは平和が保たれている。この街に暮らす人々が感情を失っているのは、森に住む一角獣がその感情を吸収し、街の外に運び出しているからだ。そして人々の感情を吸収した獣は、その「重さ」に耐えきれずに死ぬ。街の平和は獣の犠牲のもとに成立していると聞かされる。
壁に囲まれたこの街のシステムを理解するにつれて、「僕」はこの街からの脱出と感情の回復を考えるようになる。しかし、物語の結末で「僕」はそれを拒否する。「僕」は「壁」の内側にとどまることを選択する。ただし、平穏な街の中ではなく過酷な森のなかで暮らすことを選択し、その中に消えていく。「僕」は告げる。それが「責任」を取る行為なのだ、と。作中では、『ハードボイルド・ワンダーランド』の結末で消失した「私」の意識に対する無意識の領域が『世界の終り』であることが示唆される。つまり、『ハードボイルド・ワンダーランド』で改めて示された社会的なデタッチメントを選択せざるを得ないという態度表明が『世界の終り』で象徴的に描かれていると考えればよいだろう。
ここで村上春樹が提示しているのは責任ある態度としての、「倫理としてのデタッチメント」ともいうべきものだ。自己完結し、かかわりのなさにとどまることこそが、目に見えない巨大な力に抗うことになる。自らの意識の消滅を受け入れること、そして「壁」の外部に脱出して人間性を回復する――歴史がイデオロギーを介して人間の生を意味づけていた時代に回帰する――のではなく内部にとどまること、しかし感情を失っていることに無自覚なまま「街」で生かされるのではなく過酷な「森」に暮らしながら苦しみを自覚しデタッチメントのもたらす虚無に耐えること。このようなかたちでナルシシズムの記述法を完成することで、コミットメントの代替とすることがこの時代に村上春樹の提示した生のモデルだったと言える。
村上春樹を国民的な作家に押し上げたベストセラー『ノルウェイの森』は、この新しい生のモデルから逆算して、六〇年代末の記憶を精算したものだったと考えればいい。そこで主人公の青年(ワタナベ)は、政治の季節の終わりを象徴する恋人の「直子」の自殺に直面し、そしてその死を受け入れて、新時代の予感を体現する「緑」へと手を伸ばし始める。物語の結末で、主人公は緑に電話をかける。緑は彼に問いかける。「あなた、今どこにいるの?」と。「僕はどこでもない場所のまん中から、緑を呼びつづけていた」という一文で、物語は終わる。ここで村上はある時代につかまれた自身の青春の総括として、この小説の結末に自身の創作のコンセプトを示したと考えればいいだろう。村上にとって、これから書かれる小説はそこが「どこでもない場所」でしかあり得ない新しい時代の中で、世界に触れるための蝶番(「緑」の体現するもの)を求める行為なのだ。それが『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で示されたデタッチメントのもたらす虚無に耐えることに、つまりナルシシズムの記述法を完成することでコミットメントの代替とするために必要なことなのだ。時代は人間にコミットメントとデタッチメントのあいだで宙吊りにされることを求め、その苦しみに耐えうる生の肯定をもたらす回路が物語には必要とされる。それが、この時期の村上が示した自身の小説が備えるべき回路だったのだ。
〈それが高度資本主義社会というものだった。気にいるといらざるとにかかわらず、我々はそういう社会に生きていた。善悪という基準も細分化された。ソフィスティケートされたのだ。善の中にもファッショナブルな善と、非ファッショナブルな善があった。悪の中にもファッショナブルな悪と、非ファッショナブルな悪があった。ファッショナブルな善の中にもフォーマルなものがあり、カジュアルなものがあり、ヒップなものがあり、クールなものがあり、トレンディーなものがあり、スノッブなものがあった。組み合わせも楽しめた。ミッソーニのセーターに、トゥルッサルディのパンツをはき、ポリーニの靴を履くみたいに、複雑なスタイルを楽しむことができた。そういう世界では、哲学はどんどん経営理論に似ていった。哲学は時代のダイナミズムに近接するのだ。
当時はそうは思わなかったけれど、一九六九年にはまだ世界は単純だった。機動隊員に石を投げるというだけのことで、ある場合には人は自己表明を果たすことができた。それなりに良い時代だった。ソフィスティケートされた哲学のもとで、いったい誰が警官に石を投げられるだろう? いったい誰が進んで催涙ガスを浴びるだろう? それが現在なのだ。隅から隅まで網が張られている。網の外にはまた別の網がある。何処にも行けない。石を投げれば、それはワープして自分のところに戻ってくる。本当にそうなのだ。〉
これは一九八八年に発表された長編小説『ダンス・ダンス・ダンス』の一節だ。この物語はバブル景気下の日本を背景に『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』――俗に初期三部作と言われる――に登場した「ぼく」のその後の姿が描かれる。
『ダンス・ダンス・ダンス』の舞台は八〇年代後半のバブル景気下の東京だ。「ぼく」はそこで相変わらず「倫理としてのデタッチメント」を生きている。具体的には広告や出版業界の片隅で、当時は花形の仕事の一つだったフリーランスのライターの仕事を、事実上無内容な「文化的な雪かき」と自嘲しながらそつなくこなしている。『羊をめぐる冒険』で親友の「鼠」を失い、彼の死と引き換えに新しい世界の悪(羊)も消滅した世界に生きる「ぼく」には、「倫理としてのデタッチメント」を生きることだけが残されている。この世界には「羊」のような悪は設定されていない。バブル景気の時代の東京を支配していた高度資本主義の昂揚と空疎さ、その地に足のつかない居心地の悪さのようなものに囲まれながら、どう生きるのかが問われることになる。
物語の中でその答えを探す「ぼく」は異界に導かれ、『羊をめぐる冒険』の中で出会った超自然的な存在(羊男)に再会する。そして告げられる。「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ」と。
〈「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ。おいらの言ってることはわかるかい? 踊るんだ。踊り続けるんだ。何故踊るかなんて考えちゃいけない。意味なんてことは考えちゃいけない。意味なんてもともとないんだ。そんなこと考えだしたら足が停まる。一度足が停まったら、もうおいらには何ともしてあげられなくなってしまう。あんたの繋がりはもう何もなくなってしまう。永遠になくなってしまうんだよ。そうするとあんたはこっちの世界の中でしか生きていけなくなってしまう。どんどんこっちの世界に引き込まれてしまうんだ。だから足を停めちゃいけない。どれだけ馬鹿馬鹿しく思えても、そんなこと気にしちゃいけない。きちんとステップを踏んで踊り続けるんだよ。そして固まってしまったものを少しずつでもいいからほぐしていくんだよ。まだ手遅れになっていないものもあるはずだ。使えるものは全部使うんだよ。ベストを尽くすんだよ。怖がることは何もない。あんたはたしかに疲れている。疲れて、脅えている。誰にでもそういう時がある。何もかもが間違っているように感じられるんだ。だから足が停まってしまう」
僕は目を上げて、また壁の上の影をしばらく見つめた。
「でも踊るしかないんだよ」と羊男は続けた。「それもとびっきり上手く踊るんだ。みんなが感心するくらいに。そうすればおいらもあんたのことを、手伝ってあげられるかもしれない。だから踊るんだよ。音楽の続く限り」
オドルンダヨ。オンガクノツヅクカギリ。〉
「倫理としてのデタッチメント」にとどまっているだけでは、高度資本主義下を生き延びることはできない。『ダンス・ダンス・ダンス』で提示されるのは、ある種の態度表明のようなものだ。「音楽が続く限り踊り続ける」こと。それが村上春樹の見出した、高度資本主義に対する回答だった。時代に抗うことはしない。しかし、流されてはいけない。そのためには村上春樹が七〇年代に選択した「倫理的としてのデタッチメント」から、ほんの少し世界との距離を詰める必要がある。それが「踊り続けること」だ。
この小説の中で、「ぼく」は旧友の「五反田君」と再会する。「五反田君」は注目の若手俳優で表面的にはバブル景気の狂騒を満喫している。しかし彼の内面は、この新しい世界のもたらす虚しさに耐えられなくなっている。彼はその生に意味を見出すことができず、まるでゲームを攻略するようにあらゆる物事を器用にこなしてしまうだけの自分に絶望し、最後は自らその命を絶つ。言ってみれば「五反田君」は甦った「鼠」のようなものだ。「鼠」は古い世界から離脱することができずに死を選び、そして「五反田君」は新しい世界に適応しすぎることで自ら命を絶ったのだ。
そして、「ぼく」の周囲には去っていく人たちと入れ替わるように「ユミヨシさん」や「ユキ」といった女性が現れる。
これらの女性は「ぼく」にとって異界との接触面を担う存在だ。「ぼく」と物語の冒頭で出会い、そして最終的に結ばれることになるユミヨシさんは、強い感受性をもち、「ぼく」が『羊をめぐる冒険』から引きずる超自然的な体験を共有する力を持つ。ユキは「ぼく」が偶然シッター的な役割を引き受けることになるローティーンの少女で、第六感のようなものをもち、「ぼく」の周囲で起こる死の存在を察知する。「ぼく」の周囲には、異界に接する力を持った女性たちが存在し、彼女たちと関係を結ぶことによって「ぼく」は羊男との接触に成功する。この羊男との接触が、「ぼく」の「デタッチメント」から「ダンス」への微妙な、しかし決定的な変化を可能にする。「ぼく」は歴史が個人の生を意味づけない新しい世界を受け入れるために、それでいて「五反田君」のように時代に流されてしまわないように、この新しい世界を「踊り続ける」ことを選ぶ。そしてこのとき「ぼく」は異界に、超自然的なものに触れることを通じてはじめて、自分を程よい位置に保つことができる。「ぼく」は異界に接することで外部の視界を得て、自分を中距離に保つことができるのだ。その外部への回路は、異界を覗く力を持った女性たちが彼を事実上無条件に愛することで開かれる。そしてこの構造が発展することで『ねじまき鳥クロニクル』における「デタッチメントからコミットメントへ」の展開は可能になるのだ。
23 悪と性搾取
一九九五年に完結した『ねじまき鳥クロニクル』から村上春樹は本格的に「コミットメント」へと舵を切ることになる。
〈僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる〉
これは村上春樹の二〇〇八年の新聞紙上での発言だ。
村上が小説を書き始めたころ、マルクス主義の代表する政治的イデオロギーが人間を取り込む力は徐々にその求心力を失いはじめていた。このとき大事なのは壊死をはじめたこの古い悪から、きちんとデタッチメントすることだった。しかし、やがて村上は新しい時代を距離を取りながら受け入れていく過程で、新しい時代の新しいタイプの悪、つまり「羊」の系譜に連なる悪との対決をその小説の主題とするようになっていく。マルクス主義の代表する政治的イデオロギーの退潮の結果として明らかになったのは「多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない」という現実であり、その新しい世界に出現し始めたのがそのような多くの人々の弱さとして現れ、新しい世界の仕組みに対するアレルギー反応として噴出する新しい悪――オウム真理教のような悪――だった。それはかつて彼が「羊」に象徴させたものが、具体的なかたちを伴って現れ始めたことを意味した。
村上が引用したインタビューに答えた当時に執筆中であったと思われる『1Q84』にはオウム真理教をモデルにした「さきがけ」という新興宗教の教団が登場する。一九九五年以前の村上春樹の想定していた現代における「悪」は、新しい人間疎外(歴史の喪失)をもたらす高度に発達した資本主義のシステムのひずみとして描かれた。マルクス主義の敗北は、一つの社会思想に基づいた運動の失敗である以上に、イデオロギーを用いて人間の生を歴史によって意味づけるという回路そのものの破綻だった。歴史が個人の生を意味づけない新しい世界をどう生きるのか。それが、一九七九年のデビューから一九九五年までの村上春樹の主題であり、その創作の中心にあったのが「デタッチメント」という概念だった。マルクス主義の象徴するイデオロギーからも、資本主義の肥大がもたらす時代の加速からも「デタッチメント」を維持すること。そのためにハードボイルドに自己完結し、その孤独の空虚さに耐えること。そうすることで、「責任を取る」こと。それが『ノルウェイの森』で直子(=古い世界)を失った後の、緑(=新しい世界)の「あなた、今どこにいるの?」という問いかけに対する、より深いレベルでの答えだった。
しかし、村上はこのとき「転向」する。「デタッチメントからコミットメントへ」――それはマルクス主義的なもの、イデオロギーによって自分の生を歴史的に意味づけることによる悪から距離を取るだけでは、もはやオウム真理教の生む現代的な悪に抗うことができない、という現状認識の表明だと考えればいいだろう。
そして、マルクス主義の代表するビッグ・ブラザー的な悪に対するデタッチメントから、オウム真理教の象徴するリトル・ピープル的な悪に対するコミットメントへと村上春樹は移行していった。
一九九五年三月に発生したオウム真理教によるテロ(地下鉄サリン事件)に村上は強い衝撃を受けた。村上はその後、同事件の被害者にインタビューを行い、それを『アンダーグラウンド』というノンフィクションとして出版するのだが、村上にとって、オウム真理教の存在はそれまで抽象的な概念に留まっていた新しい時代の、新しい悪に輪郭を与えるものであったと思われる。
『ねじまき鳥クロニクル』は一九九二年から翌九三年に雑誌連載された〈第1部 泥棒かささぎ編〉と書き下ろしの〈第2部 予言する鳥編〉が一九九四年に、〈第3部 鳥刺し男編〉は一九九五年八月二十五日に書き下ろしでそれぞれ出版されている。つまり、第3部のみがオウム真理教による地下鉄サリン事件の影響下にあった可能性が高い。そのために同作第3部の、つまり物語全体の結末はまさにこの「デタッチメントからコミットメントへ」の移行を体現する展開を迎えることになる。
〈完璧なスイングだった。バットは相手の首のあたりを捉えた。骨の砕けるような嫌な音が聞こえた。三度目のスイングは頭に命中し、相手をはじき飛ばした。男は奇妙な短い声を上げて勢いよく床に倒れた。彼はそこに横たわって少し喉を鳴らしていたが、やがてそれも静まった。僕は目をつぶり、何も考えず、その音のあたりにとどめの一撃を加えた。そんなことをしたくなかった。でもしないわけにはいかなかった。憎しみからでもなく恐怖からでもなく、やるべきこととしてそれをやらなくてはならなかった。〉
物語の結末近くで主人公の僕(岡田亨)は同作における「羊」である綿谷ノボルをバットで撲殺する。綿谷ノボルは、当時のマスメディアで影響力を持っていたニューアカデミズムの潮流で登場したポストモダニスト(浅田彰)と、新保守系の政治家(小沢一郎)を足して二で割ったような――言ってみれば陳腐な――設定を与えられている。この村上春樹らしからぬ流行に踊らされたような安易な設定は、今日この小説を再読するときの大きなハードルになっている。しかし、ここで重要なのは村上春樹がはじめて悪に対して暴力によるコミットを選択したことだ。
『羊をめぐる冒険』の「ぼく」は「鼠」が自死を選ぶことでその存在を抹消した「羊」の後始末を、その遺志を引き継いで完遂するだけだった。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「僕」は、「やみくろ」が象徴するものからデタッチするために死を受け入れることを選択した。しかし岡田亨は違う。彼は自らバットを握り、悪を撲殺(コミット)したのだ。ただし、それは彼が超自然的な力を得て接続した夢のような異世界の中でのことだ。現実の世界で実際に綿谷ノボルを殺害し、正義にコミットするのは彼の妻の久美子であり、その責任を取り、彼女は法で裁かれることになる。
〈『ねじまき鳥クロニクル』の中においては、クミコという存在を取り戻すことがひとつのモチーフになっているのですね。彼女は闇の世界の中に引きずり込まれているのです。彼女を闇の世界から取り戻すためには暴力を揮わざるをえない。そうしないことには、闇の世界から取り戻すということについての、カタルシス、説得力がないのです。〉
村上春樹はこの結末について、前述の河合隼雄との対談の中でこう述べている。しかし、実際に描かれている物語は逆の解釈が可能だ。この物語は夫が妻を救うのではなく、実質的には妻が夫を救っているのだ。
岡田亨に代わって、兄である綿谷ノボルを殺害した久美子は逮捕されその罪を償うことになる。そう、ここでは岡田亨のコミットのコストを久美子が支払っているのだ。かつて、ゲバ棒を振りかざし、火炎瓶を投げること、つまり正義の暴力の快楽を村上春樹は拒否した。なぜならば、それは連合赤軍の末路が代表するように一つの悪を滅ぼすために無数の新しい悪を生み出してしまうからだ。だから「ぼく」も「鼠」もあらゆることにデタッチすることから、七〇年代を生き始めなければいけなかった。しかし村上春樹は一九九五年に、新しい悪を設定することで新しい正義を描き、デタッチメントからコミットメントへと舵を切った。そのコミットメントは暴力と同義であると、村上春樹は捉えている。そして暴力にはカタルシスと責任が発生する。主人公はカタルシスを、世界に素手で触れているというコミットの感触を手にする。しかし、その責任を負うのは実際に手を汚した妻なのだ。
同作において「羊」や「やみくろ」に連なる「悪」の象徴として登場する綿谷ノボルは、実妹であり主人公の妻でもある久美子をその超自然的な力によって精神的に支配している。そのため主人公が暴力によって綿谷ノボルを殺害することには、社会的な正義の執行と個人的な妻の救済とが重ね合わされている。
ここでは実質的に、夫(岡田亨)が妻(久美子)に救われている。六〇年代の終わりの敗北を経験している村上春樹は、直接的に正義の実現(社会的なこと)を信じることができない。そのため、その正義は妻の救済(個人的なこと)と重ね合わされなければいけなくなる。妻を解放するという大義名分を与えられることで、岡田亨は初めてバットを握ることができるのだ。
しかし、ここに罠がある。綿谷ノボルから妻を救うのは、なぜ岡田亨でなければならなかったのか。綿谷ノボルを殺害し久美子を救済する存在が岡田亨である理由を、村上春樹は久美子がそれを無意識のうちに求めたからだとして描く。岡田亨は妻に乞われ、彼女を救済するためにバットを握る。このとき岡田亨は妻に選ばれている。久美子は自分で自分を救済できる可能性も、岡田亨ではない他の誰かに救済を求めることも論理的には可能だ。しかし久美子は夫である岡田亨に救済を求める。まるで、彼に正当な暴力の根拠を与えてあげるかのように。
村上が『ねじまき鳥クロニクル』で描き出した新しいコミットメントのモデルは妻を夫の所有物として描くことで――この表現が強すぎると思うのなら、妻を夫にその暴力の正当性を与える存在として描くことで、と言い換えても良い――はじめて成立するものなのだ。傷つき、そしてその救済を夫に求めることで妻が夫に暴力=コミットメントの正当性を与える。そして、その暴力に伴う罪は、妻(久美子)が償うことになる。現実の世界で綿谷ノボルを撲殺するのも、その結果として法で裁かれるのも岡田亨ではなく久美子だからだ。ここで夫はその妻に、正義の執行権とそのカタルシスを与えられて、さらにその責任を免除してもらっているのだ。
(続く)
この記事は、2022年10月刊行の宇野常寛『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版)の一部を期間限定で全文公開したものです。2023年4月19日に公開しました。