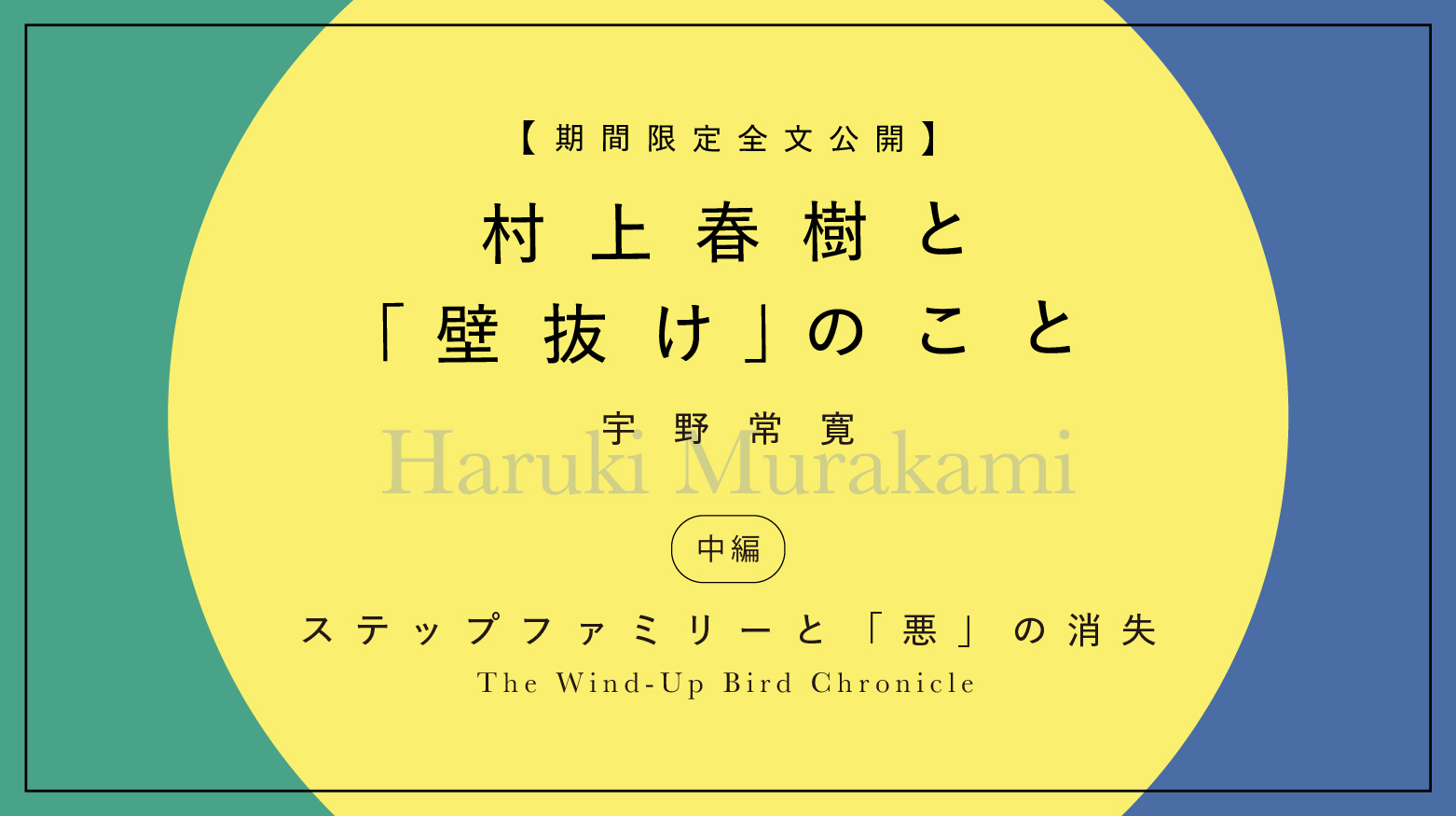村上春樹『街とその不確かな壁』の発売のタイミングで、僕が半年前に出版した『砂漠と異人たち』に掲載した村上春樹論を期間限定で全文公開します。『街とその不確かな壁』については、近いうちに批評文を発表する予定ですが、この合計約4万字のテキストは『街とその不確かな壁』の予習としても、おそらく多くの読者が頭を抱えるであろう同作を考える上でも大きな手がかりになるはずです。
そして、もし心に引っかかるものがあれば『砂漠と異人たち』の全文を読んでもらえたら嬉しいです。ここで指摘している村上春樹が乗り上げた巨大な暗礁から脱出する方法を、僕なりに考えて示しています。(宇野常寛)
端的に言うとね。
24 「壁抜け」の問題
『ねじまき鳥クロニクル』において、主人公(岡田亨)が夢の中で悪(綿谷ノボル)を撲殺し、それを現実の世界において妻(久美子)に代行させることができるのは、彼がその前に「壁抜け」を経験することで、時空間を超越して事物とコミュニケーションを取る能力を身に付けているからだ。より正確には、岡田亨を取り巻く複数の特殊な力をもつ女性たちが巫女のように超自然的な存在を媒介し、彼は彼女たちから無条件に(つまり「母」的に)肯定され、愛されることで「壁抜け」の能力を手に入れるのだ。そしてこの「壁抜け」を通じて岡田亨は、「羊」から「リトル・ピープル」の系譜に属する根源的な「悪」の力の存在を知ることになる。
この「壁抜け」は井戸のメタファーを用いて描かれる。岡田亨は近所の不思議な井戸の中に降りて、瞑想する。すると、彼の意識は少なくとも現実の場所ではない、夢の中のようなホテルにワープする。彼はその非現実の世界の中で久美子の無意識と対話し、綿谷ノボルの分身と対決することになる。そこで、岡田亨は顔にあざを持つようになる。このあざは、彼を半世紀以上前の満州の記憶と接続する。岡田はその直前に、ある兵士がノモンハン事件で体験した凄惨な出来事の記憶を彼の口から伝えられている。その記憶が同じ時代の満州に生き、その後の満州国の崩壊に立ち会ったある獣医と岡田亨を接続する。岡田亨にできたあざは獣医の顔にあったものと同じもので、こうして岡田亨は超自然的な力によって歴史に接続されることになる。この経験によって岡田亨は異界を覗き、そこに触れる力を手にして、時空間を超えて事物とコミュニケーションを取ることができるようになる。これが村上春樹の考える新しいコミットメントの条件だ。
岡田亨は元兵士の記憶を通じて、ノモンハン事件が起きた一九三九年の満州で「皮剥ぎボリス」という存在に出会う。捕虜を残虐に殺害することに悦びを得るこの皮剥ぎボリスこそが、「羊」から「リトル・ピープル」の系譜に属する根源的な「悪」の力の本作における継承者だ。正確には、人間の「弱さ」を触媒に拡大し、継承されるこの「悪」は、当時の満州においてはこの皮剥ぎボリスに宿っている。そしてこの「壁抜け」を通じて、岡田亨は皮剥ぎボリスにかつて宿っていた根源的な「悪」が現代においては綿谷ノボルに宿っていることを知り、対決を決意する。
なぜ、このような複雑な回路が必要になったのか。かつてまだマルクス主義が世界を変えると信じられていた時代に、村上春樹と同世代の若者たちは歴史を一つの物語と見なして、その物語によって自分の生が意味づけられると考えていた。そして、それゆえに彼らは失敗した。そう考えたとき、人間は一人の個体であることを許されなくなるからだ。ばらばらの個を、物語の中で一つの全体に位置づけようとするとき、暴力によって多くの個は抹殺され、そして多様であることよりも一様であることを選んだ運動は進化を止め、自らを袋小路に追いやって自滅していった。村上春樹はこの失敗から出発した作家であった。そのため歴史を物語と見なし、その物語によって自分の生を意味づける考え方から「デタッチメント」することを小説の中核に置いていた。したがって「デタッチメントからコミットメントへ」転回したときに、かつてのモデルに戻ることは許されない。村上春樹はもう一度社会に、歴史にコミットする必要があった。善悪を峻別し、世界にコミットする必要があった。しかしそのコミットの方法は新しいものでなければならなかったのだ。
そして村上が『ねじまき鳥クロニクル』で提示した新しいコミットメントのかたちが、一人の人間がある回路(たとえば小説)を通じて、時間的にも空間的にも離れた別人の記憶に直接的に接続するというモデルだった。そうすることで、人間は物語の文脈にかかわらず存在する普遍的な悪の存在を把握することができる。まったく別の時空間に存在する個人と個人の意識が直接的に接続されなければいけなかったのは、それが社会に共有されるもの、つまり物語になった瞬間にマルクス主義のような個人の存在を抹消して集団の中に取り込むイデオロギーとして機能してしまうからだ。しかし、村上がここで示したモデルは異なっている。夫が妻への愛という個人的なものを動機に(暴力を伴う)コミットメントを選択し、それを彼が接した超自然的な力(小説の力)が支援する。そしてこのコミットメントのもつ暴力は、まず夫の妻への愛として正当化され、次にそれが歴史の中に潜む普遍的な悪への対抗と重ね合わされることで正当化される。そしてこのとき岡田亨は、イデオロギーから自由に歴史を見ている。
皮剥ぎボリスは、どのような国家に属し、どのような時代に生きていたとしてもその存在が否定される普遍的で根源的な「悪」だ。しかし歴史を物語と見なす古い想像力に縛られていると、人間はこの「悪」を捉え損なう。満州に進出した日本とスターリンの支配下にあるソビエト連邦のどちらが正当であるのかという視点が導入されたその瞬間に、人間は皮剥ぎボリスという存在そのものの悪を捉え損なってしまう。彼の悪は政治的な視点から相対的に捉えられてしまう。しかし、夫が妻を救うという個人的なことを通じてその時代を生きた別の個人の記憶に接続し、イデオロギーから離れただの出来事として歴史に触れたとき、人間は物語の文脈を排除して善悪を峻別することが可能になるのだ。
しかしこの「壁抜け」には巨大な罠が潜んでいる。それは、この「壁抜け」的な歴史へのアプローチ(歴史を物語ではなくデータベースとして見ること)は、既存の文脈(たとえばマルクス主義)から自由になるその一方で、それを「見る」側の、つまり僕たちの条件が整っていなければ簡単に陰謀論や歴史修正主義の温床になり得るからだ。個人的な動機から個人的に記述された歴史の記憶に触れ、そこに記されていた出来事を前後の文脈やイデオロギーとは切り離して捉え善悪を判断する――今日においてこの「壁抜け」はインターネット的なものを強く想起させる。一九九五年当時において、村上春樹は来るべきインターネットの時代の世界観(歴史への距離感)を先取的に表現していたとすら言えるだろう。しかし、村上が提示したこの「壁抜け」と実際に普及していったインターネットを用いた歴史へのアプローチには大きな開きがあった。
読者の多くが、自分がGoogleで五分間検索して発見したブログには隠された歴史の真実が記述してあり、それによると南京大虐殺はGHQと中国のでっち上げであるといった類の虚偽を信じ込んでしまった主張を繰り返すFacebookやTwitterのアカウントを目にしたことがあるはずだ。こうしたアカウントの所有者は最初から自分が望む結論を導いてくれる記述を求めていて、Googleの文字検索は商業上の理由からその欲望に忠実に彼ら/彼女らの望む情報を探し出して与えてくれる。歴史をデータベースと見なすとき、ある程度でも自分の欲望を自覚して検索したその瞬間に、「見たいものだけを見せる」検索サービスによって人間はフィルターバブルの中に閉じ込められるのだ。いや、たとえその欲望を自覚していなかったとしても(そして仮にその対象に交通事故のように偶然出会ってしまったとしても)既存の文脈から解き放たれ、時間と空間を超えて出会った事実はむしろそれゆえにその人が抱いていた欲望によって歪められて受け取られてしまう。これが、今日におけるフェイクニュースや陰謀論の拡大する構造だ。
村上の提示した新しいコミットメントのモデルには、強力な副作用が伴っていた。歴史を物語ではなくデータベースと見なし、文脈から切り離して引用することは既存の文脈から解放された解釈を許容する一方で、陰謀論的なアプローチを誘発するのだ。人間は自由にその対象に触れるからこそ、それを予め抱いていた欲望によって歪めて捉えてしまうのだ。
歴史を物語として捉えること、つまりマルクス主義の代表するイデオロギーを用いた歴史へのアプローチは近代小説的であり、そして劇映画的だ。個人の生が歴史という物語の中で果たす役割によって評価され、人間はその評価に意味を見出す。
対して、歴史をデータベースと見なすことは、極めてインターネット的だと言える。あらゆる出来事は、本来の文脈から切り離され、恣意的に引用される。その自由は人間の創造性を誘発する一方で、それゆえに人間は自己正当化のために歴史のある部分を切り出して恣意的に引用し、新しい物語を創作するようになる。実際に、SNSの時代は陰謀論の時代でもある。今日のSNSでは二〇二〇年にアメリカ合衆国を席巻したドナルド・トランプの狂信的な支持者の唱えた陰謀論(Qアノン)から、二〇二一年に世界各国を席巻した新型コロナウイルスのワクチンの副反応についての陰謀論まで、それを目にしない日はない。
人間は物語から逃れられない。トップダウンに与えられる大きな物語による自己正当化からデタッチした空白を埋め合わせるのは、ボトムアップの小さな物語を自ら生み出し自己正当化を図る行為になる。
村上春樹の示した「壁抜け」という新しいコミットメントのモデルは結果的にインターネットを強く想起させる。距離や時間を飛び越えて、人間と人間、人間と出来事が結びつく。しかしそのために、今日のSNSのプラットフォームに支配されたインターネットの抱える問題をも先取的に内包してしまっている。このアプローチが陰謀論的なものを回避するためには、それを用いる人間の側に高い能力が要求される。およそ百年前に、古典の世界の預言者たちのように砂漠で英雄になることを夢見てアラビアに赴いた人物が、それゆえに砂漠そのものに触れられなくなったことの悲劇を僕たちは既に知っているはずだ。「壁抜け」の力を手にした僕たちは、そこで触れたものを自分の欲望する物語に沿ったものに歪めて受け止めることを避けるための能力を、砂漠を走る足と見る目を求められるのだ。
そしておそらく村上春樹もまたこの問題の存在を理解していた。しかし、その対応を誤った。それが僕の判断だ。では、その対応の誤りとは何か。次の節では、この問題を論じるために、村上春樹の「壁抜け」にある種の仮想敵として大きな影響を与えたと思われる彼の時代の並走者について考えたいと思う。
25 一九八四年のヨガ教室
こうした(物語としての歴史からの)デタッチメントから(データベースとしての歴史への)コミットメントへの転回は、村上春樹の問題である以上に、彼の生きた時代の問題だと言える。六〇年代末の学生反乱の敗北は、革命を通じて世界を変えることを断念させ、その代わりに自己の内面を変革することで世界の見え方を変革することへと世界規模でユースカルチャーのモードを移行させた。アメリカにおいてヒッピー・ムーブメントを起点に音楽やファッションの領域から、より内面的な文化へ、具体的にはエコ思想、オリエンタリズム的な禅の受容、ニューエイジ的な精神世界への接近、ドラッグ・カルチャー、そして後にこの時代を終わらせる原動力となったサイバースペースの追求などに拡大していった。これらは、資本主義に支配された現実の、もう変えることができないと断念されていた現実の外側に若者の精神を擬似的に連れ出す装置となった。そして、日本においては、マンガやアニメなど子供向けとされていた表現の大人の受け手への拡大と、「オカルト」と呼ばれた分野の流行に特徴があった。UFO、超能力、高度な科学を持ちながらも滅んだ超古代文明、前世の存在、そして埋蔵金――これらの一見、まったく無関係な妄想の類が、豊かで平和だけれども退屈な(宮台真司のいう)「終わりなき日常」の外部に擬似的に連れ出してくれる装置として、若者の支持を集めていた。このモードが解除されるのは四半世紀後の九〇年代後半だ。冷戦終結によるグローバルな市場の拡大と、インターネットを中心とした情報技術の進化は、再び若者たちに世界を変える可能性を信じさせはじめた。そして現在、世界は情報技術をグローバルな市場に投入することで、めまぐるしく変化してしまう時代に突入している。
そして、この二〇世紀後半の巨大な潮流の中で生まれ、やがて破綻していったのが、村上春樹が長くその仮想敵として、現代における悪の象徴として位置づけることになるオウム真理教だった。
オウム真理教は一九八四年にヨガ教室の一種として設立された団体だ。オウム真理教もまた虚構の世界に撤退することで、世界を変えるのではなく自分の内面を変え、世界の見え方を変えることを目的にした、世界的なサブカルチャーの潮流の中で生まれた運動の一つだった。彼らが自分たちの用いた空気清浄機に「コスモクリーナー」という『宇宙戦艦ヤマト』に登場した放射能の除去装置の名前を与えたこと、教団のスポークスマンがオウム真理教の考える解脱者とは「ニュータイプ」――『機動戦士ガンダム』に登場する超能力者たち――のようなものだと述べたこと、そして『風の谷のナウシカ』を模倣した広報用のアニメーションを制作したことなどが広く知られているが、そこには必然性があったのだ。戦後日本のユースカルチャーにとってオカルトとアニメーションはともに、マルクス主義が敗北した後――歴史が個人の生を意味づけることが難しくなった後――にもう一つの歴史を仮構し、若者たちを「ここではない、どこか」に(虚構の世界に)連れていく役割を果たしていた。しかし、虚構の世界の中でその生を完結することに、当時の若者たちは耐えられなかった。
世界を変革するのではなく、自己の内面を変革するというコンセプトと、教団を維持し、拡大するというコンセプトは矛盾を起こす。なぜならば、教団の維持と拡大は極めて社会的な行為であり、自己の内面を変えるのではなく世界を変えることに属する行為だったからだ。そのため、麻原彰晃は自己の内面を正しい状態に維持することと、オウム真理教という団体に帰属することとを結びつけるために、自分たちは日本政府や創価学会に攻撃されているといった類の陰謀論を必要とした。そして、多くの信者たちは麻原彰晃の指導する修行――その多くは修業とは名ばかりの荒唐無稽なものであったが――を通じて獲得される内面の変革ではなく、たいていの近代の新興宗教がそうであるように教団という共同体に所属することによる承認の獲得を必要としていた。
オウム真理教は、自分たちの作り上げたもう一つの世界、虚構の世界を維持するためにこそ――正確には、その虚構をともに信じることで成立する共同体を維持するためにこそ――現実の世界との関係を構築する必要に直面していった。自分たちは国家や他団体から攻撃を受けているという陰謀論を必要とした。共同体の外部に敵を設定することで、その求心力を維持することを必要とした。その虚構を独りではなく複数の人々と信じ、現実の共同体を維持するために現実の世界の「敵」を必要としたのだ。ここに革命の代替として虚構への耽溺を用いること、世界を変えることの代替として世界の見え方を変えるというプロジェクトの限界が露呈することになった。オウム真理教は、ある虚構を維持するためにこそ現実に介入する必要に迫られたのだ。そしてこの問題に対する解答として彼らはまず衆議院選挙に出馬し、それが失敗するとテロを企てるようになった。そして最終的には首都の地下鉄に毒ガスを撒いた。彼らは偽物の神――発泡スチロールのシヴァ神――を狂信し、地下鉄に毒ガスを撒いたと考えられている。しかし僕の考えでは逆だ。彼らは彼らの物語を、狂信を維持するために毒ガスを撒くことが必要だったのだ。
このオウム真理教の末路と、村上春樹のコミットメントの問題は根底でつながっている。これまで検討してきたようにオウム真理教もまた、この時代にデタッチメントからコミットメントへと舵を切った存在だったからだ。そしてオウム真理教と村上春樹の共通点は、歴史への態度にも見られる。歴史を物語的に捉えるのではなく、データベースと見なし、恣意的に引用する。歴史を文脈から切り離して引用することで、歴史そのものの本質に直接触れることができる。そのことによって、普遍的な善悪の判断基準を手にする。これが、村上春樹とオウム真理教がともにたどり着いたあたらしい「コミットメント」のモデルだった。
そう、村上春樹とオウム真理教は、おそろしいほどに並走していた。同じ時代を生き、そして時代の変化に対して、ほぼ同じように対応してきた。そして、その結果として一九九五年にオウム真理教が起こしたテロに、村上春樹は大きく動揺した。それはおそらく、村上春樹の考える新しいコミットメントのもたらす強烈な副作用を、オウム真理教の末路が体現していたからだ。オウム真理教がやがて陰謀論を用いて集団の求心力を維持するようになり、その結果としてテロに手を染めていったことは言ってみれば無数の陰謀論が流通し、民主主義を半ば機能停止に追い込みつつある今日の情報社会を予見しているとすら言えるだろう。今日の陰謀論は、村上春樹がオウム真理教に見出した「特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなもの」のもっとも先鋭化したものだ。ではオウム真理教と同じように物語としてではなくデータベースとして歴史に接することで、新しいコミットメントを可能にすることを選んだ村上春樹は、この「精神的な囲い込み」の罠をどう回避したのだろうか。それは「孤独」であること――より正確には共同体に取り込まれていないことだった。
そう、オウム真理教と村上春樹に違いがあるとすれば、オウム真理教が集団を維持することに固執した反面、村上はあくまで個人的であろうとしたことだ。
オウム真理教が陰謀論を必要としたのは、教団の共同体を維持するためであったと思われる。対して村上春樹は共同体に回帰することを選ばなかった。歴史をデータベースと見なして恣意的に引用するという手法を、オウム真理教と村上春樹とは確実に共有していた。オウム真理教は、この新しいコミットメントによって、新しい共同体を構築しようとした。そして、失敗した。しかし個人が共同体の一部に取り込まれてしまう力に対する反省から出発した村上春樹は、オウム真理教のような集団を形成することを拒否した。小さな個人が大きな共同体の一部になるのではなく、小さな個人が大きな共同体に飲み込まれない強さを獲得することを、村上春樹は選ぶ。そのため村上が『ねじまき鳥クロニクル』で提示した新しいコミットメントの根拠となったのは、共同体ではなく一対一の、対の性愛関係(夫婦)だった。
それは言い換えれば、女性から承認されることに支えられた男性的な全能感の獲得によって得られる強さだ。前述したように村上春樹の小説にはある種の霊感を備えた女性たちが登場する。彼女たちはたいてい、主人公の男性を無条件に肯定し、ときにその身体を差し出すことで、異界に触れる力を付与する。この異界とは現実の社会から切断されており、そのためにそこで主人公は、現実の距離や時間を超えて自由に事物に触れることができる。この自由が村上の提示する新しいコミットメントを可能にする。言ってみれば、今日においては情報産業がサービスとして技術的にユーザーに提供する全能感を、村上の書く物語では女性が主人公の男性に奉仕することによって精神的に実現されるのだ。
精神的な囲い込みを行い、個人を集団の中に塗りつぶしているとオウム真理教を批判する村上春樹は、自分の提示するモデルはあくまで個人的であることを維持しているのだと反論するかもしれない。しかし、このとき「岡田亨」の個を維持したままでの新しいコミットメントを可能にするために、無条件で彼を肯定し、自己犠牲によって環境を整える女性たち――対等なパートナーとしての「妻」ではなく、実質的には幼児が求める絶対的な庇護者である「母」として機能することを求められる「妻」――の個は、確実に塗りつぶされている。彼女たちは、「壁」の外の世界を生きる一角獣のような犠牲者に他ならない。少なくとも彼女たちの犠牲の上に、暴力と結びついた社会的な自己実現が「責任を取る」ことだという居直りを正当だと考えるのは難しい。陰謀論に抗うために、性搾取による自己の強化を選択したのが村上春樹のモデルなのだ。
このように村上の新しい「コミットメント」に潜む性搾取の構造を指摘することは容易い。しかし、問題はそれ以上に、村上がここで母であり、妻であり、娘である性搾取的な依存対象の女性にコミットメントの執行と責任を丸投げすることで、そこに発生する思想的な困難から目を背けてしまっていることだ。村上春樹の想像力はこのとき暗礁に乗り上げ、そしてまだ帰還していない。ある「精神的な囲い込み」を回避するために、自分ではない他の誰かに依存することそのものに罠が潜んでいる。そのことを、村上春樹の小説の行き詰まりは示しているように思えるのだ。
26 ステップファミリーと「悪」の消失
ここでもう一つ論点を提示したい。それは「コミットメント」そのものの弱体化の問題だ。村上春樹は共同体の(政治的な)正しさの副作用を忌避するあまり、個人の強さを性急に求め、結果的に性搾取の構造を導入してしまう。この選択は明らかに無自覚な性差別のもたらした、安易なモデルの導入であったと言わざるを得ない。そしてこの安易さは、結果的に悪への対抗をも失敗させてしまっているのだ。
村上春樹が二〇〇二年に発表した『海辺のカフカ』では、カフカと呼ばれる十五歳の少年を主人公にした物語が展開する。主人公のカフカは、東京の自宅から高知に家出をする。カフカはそこで生き別れた母親と思われる佐伯という女性と出会い、性的な関係を持つ。並行して、カフカの近所に暮らすナカタという知的な障害を持つ老人は超自然的な力に導かれ、「羊」の系譜にある悪の体現者(カフカの父)を刺殺し、そしてカフカの後を追うように高知に向かう。ナカタは高知で死ぬが、道中で知り合ったホシノという青年にその役割(「羊」的な悪との対決)は受け継がれる。その過程と並行してカフカは「壁抜け」的な体験から過去の戦争の記憶に触れ、一方でその壁抜けのコストを支払うかのように佐伯は死ぬ。「壁抜け」のコストを代わりに引き受けるのは、ここでも「母」的な女性なのだ。
そして注目するべきは「壁抜け」の主体と「コミットメント」の主体が分かれていること、つまり十五歳の少年カフカが「壁抜け」を経て強い男性性を獲得する物語と、ナカタからホシノへ、「コミットメント」が継承される物語とが並行して語られていることだ。
このとき、カフカの「壁抜け」からは「コミットメント」が結果的に排除されている。十五歳の少年カフカは、これから大人になり、生きていくために強くなることが要求される。それは、村上春樹がこれまで描いてきた、孤独を好むハードボイルドな男性性の獲得として描かれる。「母」的な女性(佐伯)に身体を差し出され、その霊的な力を得たカフカは「壁抜け」を達成する。しかし、そうして得た強さを用いて彼は「コミットメント」すること、つまり悪と対峙することはない。「コミットメント」をするのはナカタとホシノであり、カフカではないのだ。そして、この物語ではナカタとホシノのコミットメントが、まるでカフカの強い男性性の獲得を、その「父殺し」を代行することで支援しているかのように機能している。この物語は明確に、カフカの成長物語として描かれている。少年の強い男性性の獲得は、このときに手段ではなく、目的になっているのだ。
村上春樹はこのとき、二度目の過ちを犯したように僕は思う。一度目は『ねじまき鳥クロニクル』において、新しいコミットメントの責任を「母」的な存在(主人公の妻)に転嫁して、そこに存在する本当の問題から目を背けてしまったときだ。そして二度目は、『海辺のカフカ』において『ねじまき鳥クロニクル』では「壁抜け」に耐えうる強い主体の獲得の手段でもあった男性性の強化を、完全に目的にしてしまったときだ。
現時点(二〇二二年)で、村上春樹が「羊」の系譜に連なる悪との対峙を描いた最後の作品が、長編『1Q84』になる。二〇〇九年に〈BOOK1〉と〈BOOK2〉が、翌二〇一〇年には〈BOOK3〉が出版された同作では前述の通り「リトル・ピープル」と呼ばれる根源的な悪を象徴する超自然的な存在と、そのリトル・ピープルを信奉する新興宗教「さきがけ」(オウム真理教がモデルと思われる)が登場し、主人公たちと対決することになる。
村上のこれまでの小説と同じように、『1Q84』の主人公(天吾)もまた「文化的雪かき」によって生活の糧を得る中年(の入り口に立った)男性で、社会に対してのデタッチメントを保っている。そして彼にコミットメントの機会と能力を与えるのは、やはり女性だ。一人は「ふかえり」と呼ばれる少女だ。小説家を志望する天吾は知り合いの編集者から、新人賞に応募された小説を洗練された文章に書き直す仕事を依頼される。その文章表現こそ稚拙だが物語としてはとても魅力的な応募作が、ふかえりの書いた「空気さなぎ」だ。実はふかえりは「さきがけ」の教祖の娘であり、リトル・ピープルと交信する能力を持っている。そして彼女はリトル・ピープルの存在を危険視している。「空気さなぎ」とはふかえりが人々にリトル・ピープルに対するある種の抗体を植えつけることを目的に生み出した物語で、天吾はその普及に力を貸すことで「コミットメント」を果たすことになる。
そして、もう一人の女性である「青豆」は子供時代に天吾と出会い、心を通わせ、そして別れ別れになった過去を持つ運命的な存在だ。彼女は表向きはスポーツクラブのインストラクターをしているが、実は性暴力の加害者を暗殺する裏稼業を営んでいるという荒唐無稽な設定を与えられている。青豆は所属組織からの依頼で、信者に対するレイプを繰り返すさきがけの教祖を暗殺するが、そのために教団から生命を狙われることになる。
この二人の女性は、ともに天吾のコミットメントのコストを背負ってくれる存在だ。ふかえりは天吾に社会との接点(コミットメントの機会)を与え、青豆は天吾に代わって教祖を暗殺し、その罪を背負う。これは『ねじまき鳥クロニクル』で提示された「壁抜け」的なコミットメントのアップデートだと言えるだろう。『ねじまき鳥クロニクル』の主人公(岡田亨)は妻(久美子)を精神的に救済し、その結果として妻は岡田亨に代わって悪(綿谷ノボル)を殺害し、その罪を背負う。対して『1Q84』ではまず、ふかえりが天吾にその身体を差し出す。それが、二人の共同作業を実行するために必要なことだと彼女は述べる。そして天吾とふかえりが性交したその夜に、青豆は「さきがけ」の教祖を殺害する。天吾の射精(男性性に対する承認の獲得)と、教祖の殺害(正義の執行)は重ね合わされる。おそらく今日の多くの読者が、二一世紀初頭の段階で性交による男性性の確認と暴力による正義の執行を重ね合わせてしまう前時代的な感性に面喰らうだろう。そして、ここに「壁抜け」が発生する。天吾とふかえりの性交の結果として、時空間を超えて青豆が妊娠するのだ。そして、物語の後半では「さきがけ」は事実上物語から後退し、天吾と青豆の再会に物語の焦点は絞られる。天吾はその課程で不仲であった父との和解を果たし、そして再会した青豆が妊娠している子供を自分の子供として育てることを決意する。
ここでは男性性に承認を与えられること、つまり美少女にその身体を差し出され、父と和解し、運命の恋人と再会することと、自らの手を汚すことなく悪と対決することが重ね合わされている。そして、「壁抜け」的なコミットメントは、血のつながらない子供を育てることに結実する。
血のつながらない子供を育てること。それは阪神淡路大震災をテーマにした連作短編『神の子どもたちはみな踊る』に収められた短編(「蜂蜜パイ」)から、現時点(二〇二二年)での最新の長編(『騎士団長殺し』)まで、村上春樹の掲げる新しい「コミットメント」の象徴として度々用いられている。これは『ねじまき鳥クロニクル』で示された、物語ではなくデータベースとして歴史にアプローチする発想を応用したものだ。日本やロシアといった国の歴史=物語の文脈を排除することで、いや、したからこそ皮剥ぎボリスという絶対悪の存在を正しく認識できるように、自分の遺伝子を継いでいなくても、いや、ときにはいないからこそ子供という慈しむべき存在に正しく接することができる。それが、村上の提示した「壁抜け」の進化だった。
その一方で、この『1Q84』による「壁抜け」の進化によって失われたものがある。それはコミットメントの宛先だ。そもそもこの「壁抜け」はマルクス主義的なものの敗北と反省から出発した村上春樹が、小説の力で、これまで(二〇世紀のイデオロギー)とは異なる形で社会にコミットすることを目的に模索されたものだった。しかし、『1Q84』の後半、つまり三部作の最後にあたる〈BOOK3〉ではリトル・ピープルとその手先であるさきがけ――つまり現代社会の構造のひずみと、そこから発生する悪――は後景に退き、主人公の男性(天吾)の内面の問題、とりわけ「父」との和解と運命の恋人である青豆との再会に物語の重心は移動し、天吾がこれらを達成することで終わる。そう、村上春樹はこの物語の途中で、「デタッチメントからコミットメントへ」を掲げて開始した、現代的な「悪」との対峙を半ば放棄している。そして代わりに追求されるのが、天吾の「父」としての自己実現だ。
『ねじまき鳥クロニクル』における男性性の強化は、少なくとも表面上、データベースとして歴史にアクセスしながらも、陰謀論に陥らないための(オウム真理教にならないための)手段としての側面があった。そこにはコミットメントに対する責任を妻(事実上の「母」)に転嫁するという深刻な問題が発生していたが、少なくとも「悪」との対決を、社会との対峙を、村上春樹は強く意図していた。ところが『1Q84』の〈BOOK3〉では、明らかにこの手段と目的は逆転している。〈BOOK3〉の主題は悪との対決――「精神的な囲い込み」をもたらすものへの抵抗――ではもはやなく、主人公の男性性への承認に移行している。そこで問われているのは、これまでとは別のかたちでどう男性性に承認を与えるかということだけだ。
村上春樹はそれまで、家族形成に対してのデタッチメントを反復して描いてきた。言い換えれば、村上は父になることと政治的であることを結びつけ、この二つを同時に拒否し続けてきた作家だった。たいていの主人公は中年の入り口に立った独身男性として登場し、行きずりの性的な関係を適度に楽しむ描写がやや過剰に反復される傾向があった。彼が結婚している場合は、その夫婦関係は破綻し、妻は彼のもとを去っていった。そして、二人の間に子供が儲けられることはなかった。これらの男性主人公たちの両親が描かれることもなかった。「デタッチメントからコミットメントへ」は、村上春樹の描く男性主人公たちが、徐々に「父」になることを受け入れていく過程でもあったのだ。そしてそれは、ただ妻との間に子供が儲けられ、家族が形成されるのではなく「壁抜け」的な家族形成=ステップファミリーというかたちで描かれることになった。
二一世紀の今日においては、ステップファーザーになることを何かの到達であるかのように語ることそのものに、滑稽さを感じる人も少なくないだろう。養子はまず――封建的な家制度の一部としてだが――昭和中期まで国内でもそれほど珍しいことではなく、また今日の国際社会においては現代的な拡張家族の形態としても定着しつつある。これはつまり、村上の想定する家族観が異様なまでに戦後的な核家族のそれに引きずられており、相対化し、アップデートする対象としての「家族」のイメージが昭和後期のそれに固着していることを意味している。妻の連れ子の父であることを引き受ける(程度の)ことを決定的な一歩として記してしまうこれらの物語の展開は、今日においては階段の最初の一段に片足をかけた段階でまるで頂点に立ったかのように旗を振るようなものだ。これまで確認してきたとおり、村上の小説の世界はいまだに、同世代(団塊世代)に属する都市部のホワイトカラー(戦後中流)男性の生きる数十年前の価値観にとどまっている。そのため残念ながら村上にとっては、この程度の柔軟さが非常に大きな一歩に見えてしまう。驚くべきことだが、それで自分たちの男性性を相対化したつもりなのだ。村上春樹にとって「父」になることは自己実現にとって不可欠な要素であり、だからこそステップファーザーであることを引き受けることは大きな進化として位置づけられている。村上にとって子供が自分の遺伝子を継いでいるということは決定的に重要なことらしく、そのためにそれを断念することは大きな決断として描かれているのだ。
かくして『1Q84』の〈BOOK3〉以降の村上春樹による小説では、「羊」の系譜に連なる悪の存在は事実上消失し、「壁抜け」による歴史へのアプローチは、男性主人公の父性にステップファーザーであることを受け入れる程度の柔軟性(最低限の現代性)を与えるための装置に位置づけられ直した。
その一方で村上春樹は、この時期から――二〇〇九年のエルサレム賞のスピーチから――それまで控えていた小説外での政治的な発言を頻繁に行うようになった。前述のラジオ番組においても、度々時の政権批判や、歴史修正主義運動への批判を試みている。前提として村上のこうした態度を、僕は支持したい。その一方で村上の小説が乗り上げてしまった巨大な暗礁と、その創作的な難破によって露呈してしまった思想的な課題については、別途に検討する必要があるだろう。つまり、村上春樹は小説内で描かれるコミットメントを縮小させるその一方で、小説外においては拡大させているのだ。村上による小説外の雑誌のインタビューや、ラジオの雑談で行う社会的な発言はタイムラインの大きな潮の流れの中に収まるもの、村上の代わりに他の固有名詞を代入しても成立するものばかりで、取り立ててここで取り上げる価値のあるものではない。
こうした小説外の最小公倍数的に正しい政治的な発言は、この時期に書かれた村上春樹の小説内で、一つの達成として描かれる父性像や家族像の最小公倍数的な(そして政治的な)正しさへの接近と並走している。小説外ではタイムラインで支配的な潮流の中から穏当なものを選択するかたちで政治的な正しさを前面に押し出した発言が反復され、小説内ではこれまで半ば無自覚に提示されてきた性搾取的なモデルの緩和が試みられているのだ。僕はこの「正しさ」を、あるレベルでは評価する。この作家は七十代にして、自己の古い部分を克服しようとしている。しかし、その方法として提示されるビジョンに決定的な安易さを感じることも間違いない。そこに創作としての想像力はなく、この十年で村上春樹の紡ぐ言葉は、タイムラインの潮流と一体化しつつあり、個人的であることを失いつつあるのだ。
ここに村上春樹の乗り上げた暗礁の本質が存在する。村上春樹は、もはや現代的な悪の像を設定できない。小説内のコミットメントは中年男性のナルシシズムの確認にまで縮退し、歴史へのアプローチはそのための手段でしかなくなっている。こうして小説内から消失した社会的なアプローチを、小説外での他の誰もが口にしているような、FacebookのシェアやTwitterのリツイートといった機能が促すコミュニケーションと実質的には変わらない凡庸な「社会的発言」が埋め合わせている。そして、この大作家の乗り上げた巨大な暗礁を体現しているのが、現時点(二〇二二年)における最後の長編小説『騎士団長殺し』だ。
(続く)
この記事は、2022年10月刊行の宇野常寛『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版)の一部を期間限定で全文公開したものです。2023年4月20日に公開しました。