編集者・ライターの小池真幸さんが、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介する連載「横断者たち」。今回は、都市環境の微生物コミュニティの研究者であり、バイオベンチャーBIOTAの創業者でもある伊藤光平さんに話を伺いました。「除菌」ではなく微生物の多様性を高めることを目指す方向への衛生観念の刷新、その実現に向けて必要な「微生物の身体性」獲得の方法を考えていきます。

端的に言うとね。
多様性の議論から抜け落ちる「人間ならざるもの」
2021年現在、人類史上かつてないほど「多様性」に注目が集まっていると言っても、言い過ぎではないだろう。思想や批評のトピックとしてはもちろん、「D&I(Divercity and Inclusion)」のような標語に代表されるように、ビジネスにおける実務的な問題にもなっている。
もちろん、筆者はこうした潮流に基本的には賛同している。言うまでもないが、マイノリティに対する不当な差別的扱いはできる限り解消されるべきだろう。たとえマジョリティ側が多少の息苦しさを抱えることになったとしても、多様性の増進は進められるべきだと、総論としては考えている。それは政治的な理由だけでなく、「楽しみ」や「生きやすさ」の次元でも同様である。文化的に一様な世界は物足りないし、一つの選択肢しかない状況はとても息苦しい。
ただ、「多様性」というキーワードを追いかけることに執心するあまり、見過ごしてしまっているものがあるとも思う。その一つが、「人間ならざるもの」の存在である。一般に、多様性についての議論の対象は人間で、拡張したとしても、せいぜい親しみやすい動植物止まり。しかし、それはいささか視野狭窄だったのかもしれないと、今回のインタビューを通して気付かされた。
話をうかがったのは、アカデミアとビジネスを〈横断〉しながら「微生物の多様性」という問題に取り組んでいる、伊藤光平さんだ。都市環境の微生物コミュニティの研究・事業者である伊藤さんは、高校生の時から微生物研究に従事し、Forbesの「30 UNDER 30 JAPAN 2018(世界を変える30歳未満の日本の30人)」にも選ばれた。「微生物との共生社会を実現し、より快適で健康な都市を創る」ため、研究開発や製品開発、教育・文化醸成といった事業を展開するBIOTAを創業した、若手起業家でもある。
一見すると「汚いもの」「除去すべきもの」として忌避されがちな微生物の多様性を高めることが、なぜ「健康的な都市づくり」につながるのか? 「除菌」を絶対善とする既存の衛生観念を覆し、微生物多様性を高めていくためのカギは「身体性の獲得」。伊藤さんの問題提起は公衆衛生の議論を超えて、ヒトとヒトとの関係性にがんじがらめのSNS全盛時代における「新たな快楽」の獲得に結びつきうる、射程距離の長いヒントを与えてくれるものだった。
「除菌」はサステナブルではない
コロナ禍に際して、多くのメディアがウイルスを「撲滅」の対象として報じてきた。「コロナに負けるな」と戦いのメタファーを用いた表現も、しばしば見かける。
ウイルスだけではない。細菌、菌類、微細藻類、原生動物……「ほとんどが1ミリメートル以下」の「目にみえないくらい小さな生物」である微生物(参考:日本微生物生態学会)に関しても、除去すべき対象というイメージを抱いている人が少なくないだろう。これは「抗菌」や「殺菌」といった表現が頻繁に使用されていることからも明らかである。
しかし、伊藤さんはこうした衛生観念に疑義を挟む。除去すべき邪魔者ではなく、共生していくパートナーとして微生物を捉えているのだ。より多様な微生物との共生こそが、健康で快適な都市生活の鍵であり、「微生物多様性」を高めることが必要だというのが、伊藤さんの問題提起である。
都市において、ヒトが暮らしている室内は、実は“微生物の楽園”とも言える環境が整っている。そもそもヒトの身体には、腸内細菌や皮膚常在菌など38兆を超える数の微生物が住んでいると言われており、それらは1秒あたり約数千ずつ体外に排出されているという(参考)。皮脂やフケ、食べこぼしといったさまざまな有機物、濡れている水回りなど、微生物の生育を促進する要素も満載だ。
室内に生息するヒト由来の微生物の中には、病気を引き起こすものも一定数存在するという。それゆえ、安全や健康を獲得すべく「除菌」によって微生物を排除しているわけだが、伊藤さんはそのアプローチの限界を指摘する。
「一言でいえば、サステナブルじゃないと思うんですよ。いくら除菌しても、ヒトが室内にいる限り病原微生物は増え続けますし、除菌を繰り返す中で耐性を持つものも現れはじめます。つまり、除菌を重ねることで、除菌では死なない微生物を増やしてしまっていて、その中に一定数の病原性微生物が存在するのが現状なのです。これが顕著に起こっているのが病院です。病院は、その他の場所よりも頻繁に除菌・殺菌を行う必要があります。その結果、薬剤に対する耐性を持った、死なない病原微生物がどんどん生まれてしまっている。もちろん、薬剤に対する耐性を持った菌を発生させないための方法についても研究が進められていますが、いずれにせよ除菌は新たに現れた微生物に対してコストをかけ続ける必要があり、サステナブルではありません。病院以外でも、一般住居の建材の塗料、歯磨き粉、洗剤や化粧品にも抗菌剤が含まれていることが多いですし、除菌スプレーも至るところに設置されている。そもそも、ヒト由来の微生物の中で、病原性を持つものは2〜3割しかいないとも言われています。たしかに除菌することで病原微生物はいなくなりますが、そうではない残り7〜8割の無害な微生物も一緒に殺してしまうことになる。除菌がすべて悪だとは言いませんが、微生物を無差別的に殺すというアプローチが、あまりにも自然に行われすぎていると思うんです」
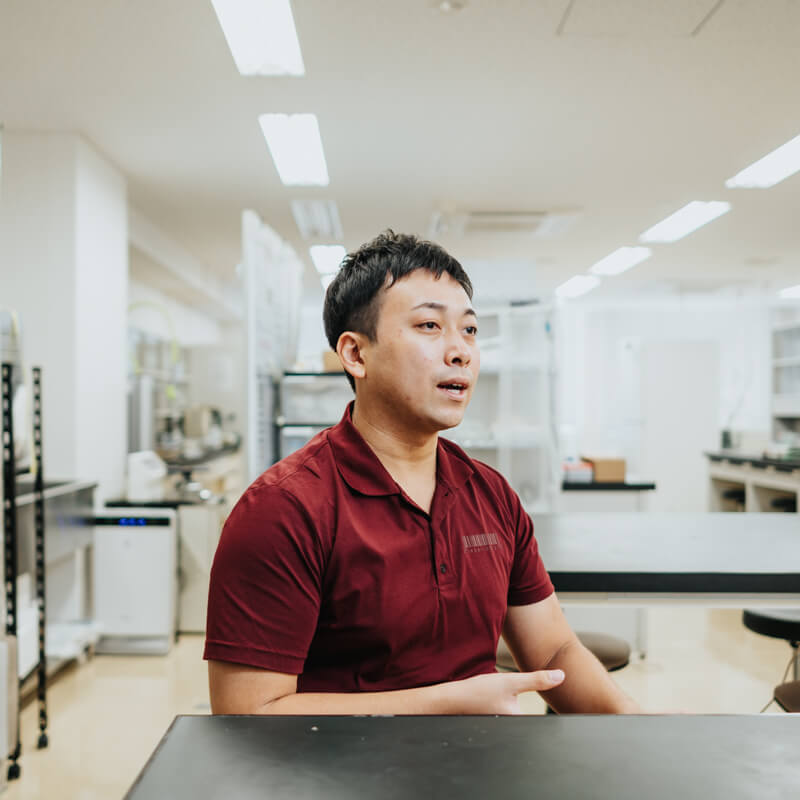
そこで伊藤さんが推し進めている代替案が、「都市の微生物多様性を高める」ことだ。ヒト由来の微生物に加えて、森林や土壌といった自然由来の微生物も室内に住まわせることで、病原微生物の増加を抑えられると語る。
「微生物の多様性が高まれば、多様な微生物が環境中で同時に混じり合うことになるので、病原微生物だけが増えすぎることを抑制されるのではないかということが、研究でわかりつつあります。たとえば、微生物に対しての餌の総量が一定だとすると、その餌を分解する微生物が多様であればあるほど、栄養源を奪い合うことになる。すると拮抗作用が働いて、一部の病原微生物だけが増えづらくなるはずです。また、微生物が出す産生物質が、他の微生物の生育を阻害することもわかっています。対して、微生物の種類が少ないマイクロバイオーム(微生物コミュニティ)は、特定の種の微生物が増えやすい環境なんです。ですから、微生物多様性を増やすにあたっては、普段は土壌や森林、海や河川の中にいるような、自然由来で、ヒト由来の微生物とは系統的に遠い微生物を増やすべきだと思います。自然換気によっても、自然由来の微生物を室内に増やすことができますが、都市部だと高層部ゆえに窓が開けられなかったり、そもそも外に土壌や植生がなかったりする。したがって、場所によってはある程度は人為的に自然由来の微生物を加えてあげて、室内の微生物多様性を高めることが必要だと考えています」
除菌から“加菌™”へ──いま必要な衛生観念の刷新
都市における微生物多様性を高めることは、免疫の発達にも大きく寄与する可能性があるという。乳幼児期までの非衛生的な環境が、その後にアレルギー疾患の発症リスクを低下させるかもしれないことを示す「衛生仮説」という理論がある。山間部で育った子供に比べて、都市部で育った子供は免疫の学習機会が少なく、アレルギー症状が悪化しやすい、というものだ。
その要因はさまざまだが、室内に生息する微生物の種類の違いも大きいのではないかと、伊藤さんは見ている。家のすぐ近くに森林や田畑がある山間部では、室内にいる自然由来の微生物の割合も高くなる。対して都市部では、森林や田畑が少ないのはもちろん、機械換気が多いがゆえに、屋外の微生物がダクトの中に落ちてしまい、室内まで入ってきづらい。「都市部では微生物と触れ合う機会が奪われてしまっているんです」。
しかし、微生物多様性を高めることで、都市部でも田舎と山間部と同じくらい多様な微生物と触れ合えるようになり、免疫の発達にも寄与することが可能になる。除菌から“加菌™”へ──これまでの衛生観念を覆すパラダイムシフトを、伊藤さんは起こそうとしているのだ。
「衛生観念の中から、『生き物を排除する』という考え方をなくすべきだと思うんです。というか、においや汚れは有機物がもとになっており、生物ではなく物質の問題です。もちろん、そうした有機物を作り出しているのは微生物なのですが、それを取り除くのはベストな問題解決法ではないと思うんです。においや汚れを出す生物を減らしていくことが『衛生的』なのであれば、極端な話、ゴミを出す人間だっていないほうがいいという議論になってしまいますし、生態系そのものの否定にもつながりかねません。人間だけで頑張って『不衛生』の原因となる微生物を除去し続けるのは、持続可能ではないと思います。すべての状況で微生物を除去することが本当に『衛生的』なのかどうか、慎重に再考していく必要があるでしょう」
誤解してはいけないのが、伊藤さんは決して、あらゆる微生物の存在比率を完璧にコントロールしようとしているわけではないという点だ。あくまでも「多様性」を高める、すなわち種類を増やそうとしているだけだ。そもそも「良い」微生物と「悪い」微生物、もしくは善玉菌と悪玉菌のような区別も本質的には意味がなく、「人間中心的で上から目線の考え方」だと伊藤さんは指摘する。
「室内にせよ腸内にせよ、『どういった微生物のバランスが最適なのか?』という質問をよくいただくんですよ。でも、考えてもみてください。たとえば、ある都市に住んでいる人の職業や人種に関して、多様性が重要という議論こそしますが、厳密に“最適”な割合を考えたりはしませんよね? それにもかかわらず、微生物の話になった途端、人間がすべてをコントロール/デザインできる前提での議論になってしまう。しかし、人間社会と同じで、マイクロバイオームも非常に複雑なものです。下手にコントロールしようとするのではなく、多様性を高めるための施策を打ったほうが、結果的に安全かつ持続可能なエコシステムが実現すると思うんです。もちろん、自然由来の微生物の多様性を高めていく、など大きな軸は定める必要があります。でも、都市はさまざまな変数があり、ベストな解決方法は常に異なるので、多様なアプローチで状況に合わせて変えていくしかない。生態系の中で、少しかき混ぜること。それが人間が果たすべき役割だと思います」
これは言わば、マイノリティポリティクスにおける「アファーマティブ・アクション(積極的格差是正措置)」に近いイメージだ。不当な差別が発生している状況を改善するため、あえてマイノリティに対して優遇措置を取る。しかし、これはあくまでも「差別の解消」が目的であって、「神の比率」を追求するものではない。ジェンダーバランスの解消は、特定の人々が被っている不当な扱いをなくすことであり、厳密に「理想のジェンダー比率」を実現することではないからだ。微生物も同じで、都市の室内において、自然由来のものを増やしてあげることで十分なのである。
いま微生物に足りないのは「身体性」だ
なぜ人は、こと微生物に関して、「最適な割合バランス」を求めてしまうのだろうか。言い換えれば、なぜ同じ生物であるにもかかわらず、人間における多様性の議論と、微生物多様性の議論を別物として捉えてしまうのだろうか。伊藤さんはその理由を、微生物の「身体性」という観点から考察する。
「犬や猫のことを『よくわからない』と言う人は多くないじゃないですか。飼ったことも触ったこともなくても、さまざまなメディアや日常生活から得られる情報を通して、犬や猫がどんなライフスタイルで、どんな生活をしているのか、僕らはある程度は知っている。でも、なぜか微生物は『よくわからない』と言う人が多い。スケール感が違うだけで、本当は同じ生物で僕たちの体の中やあらゆる環境にいるはずなのに、です。これは結局、身体性を獲得しているかどうかの違いだと思うんです。僕は街を歩いているときに『ここにはこんな微生物がいるだろうな』と感じたり、発酵現象が起きている時に『いまはこんな微生物が働いているんだな』と想像したりします。山に登って『この足跡はイノシシかな?』と考えるのと同じです。とはいえ、僕はもともとゲノム解析のプログラムこそ書いていましたが、顕微鏡で微生物を観察するようなスタイルの研究をしていたわけではありません。でも、勉強を重ねる中で、少しずつ微生物に対する想像力が上がっていった。そうして身体性を獲得することが、『ぞんざいに扱っていいや』というイメージを覆すために重要だと思うんです」
たしかに、程度の差こそあれ、現代日本において、犬や猫は人間同様の尊厳を持って扱われる存在となっている。それにもかかわらず、微生物に対しては躊躇なく「除菌」できてしまう(ちなみに例外的ではあるが、微生物を供養する「菌塚」なるものも京都に存在するという)。その背景には、我々の微生物に対するイメージの貧困さが起因しているという仮説は、説得力があるように思える。
伊藤さんのような微生物の専門家でなくとも、微生物に自然と身体性を感じている人びともいるという。たとえば、伊藤さんの創業したBIOTAも共同研究を進めているような、酒蔵で働く人たち。麹菌や酵母の働きによって酒造りをしている人びとは、温度やタイミングなど、あらゆるパラメーターを微生物の存在を感じながら判断しており、見えない微生物の動きに応じて大きく味が変わることを体感している。
また、アフリカの先住民族で、吐いたものを仲間の顔に塗ることで、結果的に腸内細菌の交換を引き起こしていたり、帝王切開で生まれた子供に母親の膣液をかけることで、結果として本来受け継ぐべき微生物が受け継がれたりしている者たちもいるという。これらは「微生物」とは認知されていなかったとしても、微生物の身体性に近いものを感じ取っていたのではないかと、伊藤さんは推測している。
「微生物の身体性」。この独特なキーワードを聞き、小倉ヒラク『発酵文化人類学──微生物から見た社会のカタチ』や藤原辰史『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考──』をはじめ、ある種の文化的な観点から微生物の働きに注目する議論が思い起こされた。こうした議論も、伊藤さんの言葉を借りれば「微生物の身体性獲得」を手助けするのかもしれない。
「そうした議論もとても重要だと思います。『都市と微生物』という文脈においては、社会的・文化的なアプローチが果たす役割はとても大きい。ただ、これは微生物を擬人化する必要があるということではありません。そもそも、他の生物を人間として解釈しようとすること自体、人間中心主義的すぎますから。教室で飼っている金魚のような感覚で、言葉は通じないけれど、新しい視点や知識を与えてくれるような存在として、微生物を捉えられるようになるといいなと思っています。僕たちの身体は、38兆を超える微生物のマイクロバイオームなので、微生物に身体性を感じてケアしてあげることは、自分自身を大切にすることにもつながりますしね」
古くは「朝シャン」や「デオドラント」の登場、昨今であればタバコに対する社会的排除の強化など、社会全体で「清潔化」「潔癖化」が進んでいるという議論がある。もちろん、明白な他者危害や身体的な悪影響をもたらすものの中には、適度に排除すべきものもあると思う。しかし、奈良の里山で人間ならざる動植物や微生物と共に生きることのもたらす「腐爛文化」の快楽を祝いだ東千茅『人類堆肥化計画』でも描かれているように、清潔ではないものだけが与えてくれる喜びが世界に存在するのも、また事実だろう。微生物に身体性を付与することは、こうした「清潔」ではないものがもたらす快楽を取り戻す、一つの取っかかりになるかもしれない。
ビジネスを通じて「微生物多様性」を社会実装する
都市における微生物多様性を高めるため、微生物に身体性を獲得させ、衛生観念を刷新する。その壮大なプロジェクトの端緒として、伊藤さんが創業したのが、バイオベンチャーのBIOTAだ。「微生物との共生社会を実現し、より快適で健康な都市を創る」をビジョンに掲げ、研究開発や製品開発、教育・文化醸成などの事業を展開している。

研究開発としては、微生物コミュニティ(=マイクロバイオーム)の①機能②種類③環境・宿主に及ぼす影響という3つの軸をメインに、ゲノム解析を実施。自社の研究に加え、アカデミアや企業との共同研究も積極的に行っている。
製品開発としては、自宅の室内環境を改善する微生物噴霧デバイス「GreenAir」を、目下開発中だ。小さな子どもと暮らす親にとって、室内における病原菌やカビ、ダニが原因で生じる子どもの喘息やアトピー、花粉症などのアレルギー症状などの疾患、さらにはペットのトイレや料理のにおいは、大きな問題になっている。こうした問題を引き起こす微生物は、空気中に浮遊しているだけではなく、家具や壁、床などの表面にも付着している。微生物の代謝能力や多様性による拮抗作用を利用し、この問題を解決するのがGreenAirだ。GreenAirから放出された自然由来の微生物は、室内の多様な有機物を消費して増殖し、病原菌の増殖を阻害したり、においや汚れを分解したりする。空気清浄機は、つけ続ける必要があり、フィルターの廃棄なども問題化している。対して、「加菌™」するGreenAirはコスト効率が良く、サステナブルなアプローチを可能にするという。まさに、「微生物多様性で健康な都市を創る」を具現化したプロダクトだといえるだろう。

教育・文化醸成も、BIOTAにおける欠かせない要素だ。「除菌」を是とするメインストリームに対するある種のカウンターとしての性質を持つ事業であるため、地道な啓蒙活動の積み重ねが求められる。そのため、微生物多様性の重要性を発信するための講演活動やワークショップも、積極的に行っているという。文化醸成の一環として、植物、木、モビリティ、食と、微生物にとどまらず幅広い領域で都市を醸している実践者を深掘りしていくインタビュー企画「都市を醸す」も、伊藤さんのnoteで展開中だ。
社会通念を中長期的に覆していく事業ゆえの難しさは、やはり存在するという。昨今は日本においても、「ディープテック」と呼ばれる、研究開発段階の科学・エンジニアリング技術を強みとした事業を手がけるスタートアップに中長期的な視野で投資していく潮流が見られる。とはいえ、革新的なアイデアであればあるほど、簡単には世に受け入れてもらえない。
「そもそも市場としても、まだまだ未熟ですし、投資家さんに魅力的に感じてもらえるような急成長を実現するのはなかなか難しい。文化醸成も、資本を投下すれば劇的に進んでいくようなものではないですしね。顧客に対しても、価値提供以前に、『なんとなく微生物って危ないんでしょ』という固定観念を打ち砕くところからスタートしなければいけないので、コミュニケーション上の難しさを感じています。エビデンス伝達以前の、イメージの問題。だからこそ、『伝え方』に関してはかなり気を遣っていて、創業期からデザイナーのメンバーにも加わってもらっています」
人と仲良くできないコンピュータ少年、「微生物」に出会う
「都市における微生物多様性」に多大なる熱意を注ぐ伊藤さんだが、この一見ユニークなテーマに、いかにしてたどり着いたのだろうか。
1996年10月生まれで現在24歳の伊藤さんは、慶應義塾大学先端生命科学研究所が設置され、バイオベンチャーがひしめく地としても著名な、山形県鶴岡市で生まれ育った。小中学生の頃よりコンピュータやインターネットに強い関心を持ち、ガジェットや自作PCソフトウェアにのめり込む。「色んな人と仲良くするのが苦手だったので、一人で楽しく生きていきたいと思っていました」と振り返るが、人ならざる微生物への圧倒的な情熱の素地は、その頃から形成されつつあったのかもしれない。
「受験勉強」「部活動」「集団行動」に象徴される画一的な価値観への馴染めなさを感じながら、コンピュータの世界に没頭していった伊藤さんが、高校生のときに出会ったテーマが微生物だ。地元鶴岡の研究所が出していた研究生の募集が、「人と異なった意思決定をし続けたい」と感じていた伊藤さんを惹き付けた。応募の結果、晴れて採用された伊藤さん。高校生ながらに特別研究生として皮膚のマイクロバイオーム研究に取り組むようになり、これまで慣れ親しんだコンピュータと微生物の交差点であるゲノム解析に、のめり込んでいった。
2015年には、微生物の研究を続けるべく、慶應義塾大学環境情報学部に進学。情報科学と生物学を合わせたバイオインフォマティクス研究に取り組み、微生物ゲノム解析をテーマに国際誌に論文を複数投稿した。
「都市における微生物多様性」というテーマが見えてきたのは、この頃だ。ニューヨークの地下鉄に生息し、人の移動に伴って移動している微生物の、公衆衛生の観点での意義を研究した論文を読んだことがきっかけだった。それまで「いかに殺すか」という前提のもとで研究が行われるのが一般的だった、室内における微生物研究にパラダイムシフトを起こしうる画期的な内容に、刮目させられたのだった。
ただ、とりわけ日本においては、そもそも都市における微生物に関しては、トラッキングや生息する種の解明すら進んでいなかった。そこで伊藤さんは2016年、都市から大規模に微生物をサンプリングするための学生団体GoSWABを立ち上げる。「人と関わるのは苦手でしたが、『都市』というテーマに取り組むにあたって社会とのつながりは必須だと思ったので、頑張るしかないと思いました」。自主的な研究費申請などで資金を調達し、多くの人を巻き込みながら、鉄道駅など、都市におけるさまざまな場所で微生物をサンプリングし、解析していった。
GoSWABの活動においては、インドやスウェーデンで学会発表にて、世界中の研究者との議論も重ねた。腸内細菌や皮膚常在菌など、ヒトの体内における微生物の研究が主だった中で、都市における微生物に着目した伊藤さんの研究は注目を集めたという。2018年には、「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」にも選出された。
「都市における微生物多様性」というテーマの社会的意義をますます実感した伊藤さんは、2019年までGoSWABの活動を続ける。そして次の道として浮上したのが、起業だった。これが、2019年7月にBIOTAを創業するに至った経緯である。
「高校生から学部生まで、大体7年間ほど研究に一生懸命に取り組んだことで、アカデミアの雰囲気や使えるお金のスケール感、かかる時間軸などは、なんとなくイメージがついてきました。そのうえで思ったのが、つぎ込める資金や研究のスピードといった観点で、この研究領域の場合はビジネスの方がさまざまなプレイヤーと協力しながら、柔軟に研究を進めていけそうだということ。また、20代の体力があるうちは、これまでやったことがないビジネスというアプローチを取ったほうがいいのではないかと考えたんです」
「他人を意思決定における判断基準にしていない」
アカデミアとビジネスを行き来しながら、「都市における微生物の多様性」という問題に取り組み続ける伊藤さん。〈横断者〉として、一つの領域にとどまることなく活動できているのはなぜなのだろうか? そう問いかけると、微生物への多大な熱量を持った伊藤さんらしい答えが返ってきた。
「そうですね……衝動的に『やりたい!』と思ったらすぐに着手するタイプなので、基本的にはいまやりたいことをやっているだけなのですが、なんというか、他人を基準に考えないようにしているからかもしれません。他人というものを、自分の意思決定における判断基準にしていないんですよ。ですから、ロールモデルのような人もいなくて。『他人がどう思うんだろう』という想像力がなさすぎて、逆に問題が起こったりもするんですけどね(笑)。ただ、苦手な中でも必要に駆られてさまざまな人とかかわっていく中で、昔よりは人と楽しく関わることができるようになりました」
伊藤さんが微生物に対して強く身体性を感じているのは、人に対する関心が強くないことの裏返しなのかもしれない。
「僕にとって微生物は、人間とニッチが違うだけで、同じ地球というリソースを使っている生態系の一員、たとえるならクラスメイトのような存在なんです。ペットとも近いし、ライオンのように一般にイメージしやすい動物とも同じ。そうした微生物の良いところを活かすことで、地球自体も良くなると思いますし、サステナビリティを重視する昨今の趨勢にも通ずるところがあり、人類ももっと幸せになると思います。合理的に考えたら、微生物と共に生きるほうの決断を、人類は選択するのではないかと考えているんです。ですから、いまの僕は、ちょっと先にその方向に走りはじめているだけ。何も、突拍子もないことや目新しいことをやろうとしているわけではありません」

そもそも、この連載「横断者たち」のコンセプトは、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介するというものだった。連載スタート前、「界隈や業界での評価ではなく、問題そのものに真摯に取り組んでいるからこそ、意識せずとも結果として〈横断〉してしまっているのではないか?」という仮説を立てていたが、伊藤さんの話を聞き、その妥当さが確かめられた感覚がある。
コンピュータ、そして微生物と、一貫して「人ならざるもの」に関心を抱き続けてきた伊藤さんだからこそ、人が構築した虚構にすぎない「界隈」や「業界」の縛りから、自然と抜け出ているのだろう。SNSを中心としたインターネット空間における、デジタルな人間ばかりに気を取られてしまう昨今だからこそ、「人ならざるもの」の身体性に向き合う伊藤さんのような視座が、ますます重要性を帯びているのではないだろうか。
[了]
この記事は小池真幸が聞き手・構成をつとめ、2021年8月2日に公開しました。photo by 高橋団
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

