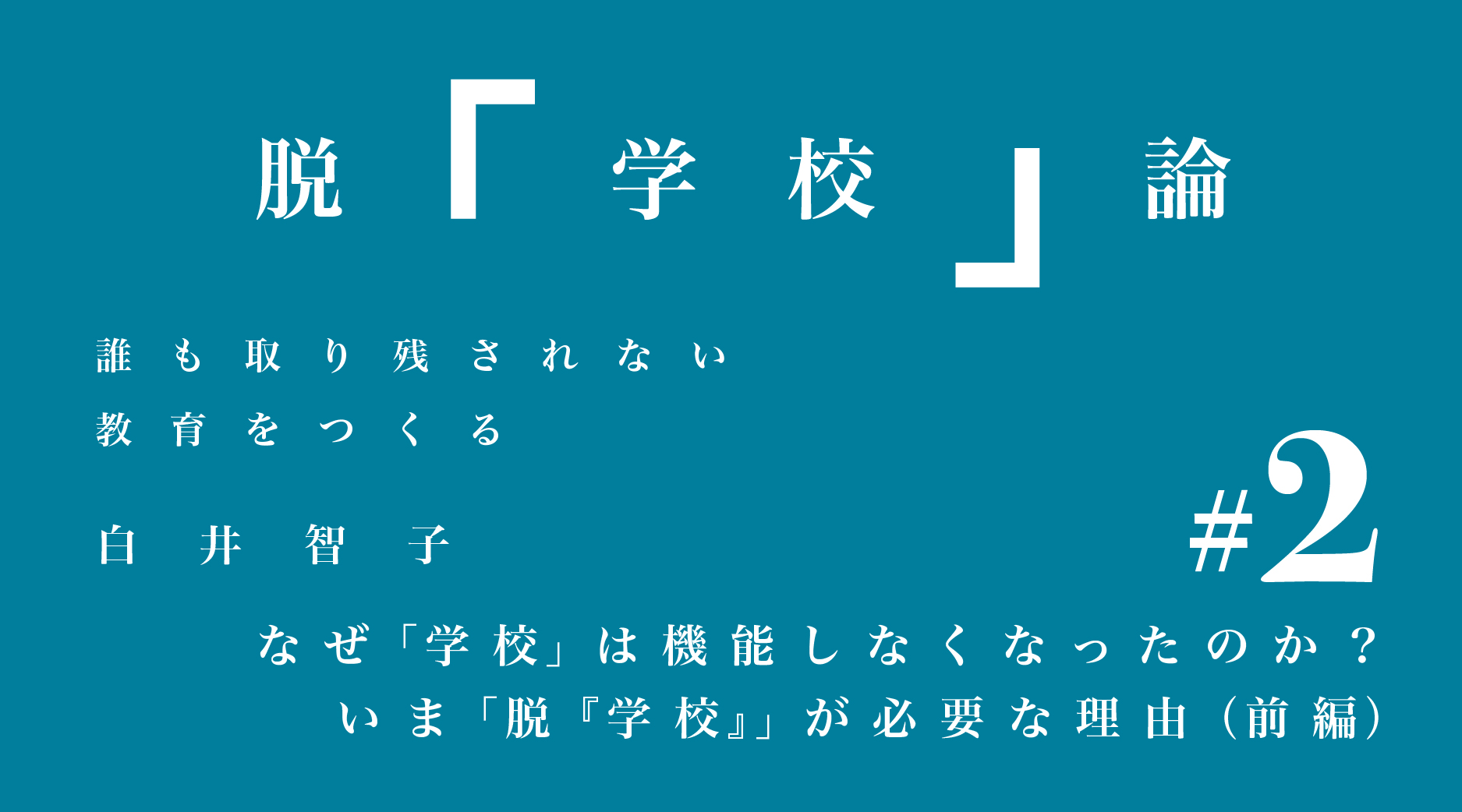日本におけるフリースクールの先駆者、白井智子さんによる新刊『脱「学校」論:誰も取り残されない教育をつくる』の先行配信連載です。
子どもたち一人一人に対応できていない「学校」というシステム、そして現代の「親ガチャ」の世界。そんな日本の学校教育が抱える生々しい問題点、そしてその足りない部分を補完する新たな教育システムの具体的な構想を、国内の「フリースクール」黎明期より約30年、「誰も取り残されない教育」づくりに奔走してきた白井さんが分析・提案します。
(関連記事)白井智子 | ゼロから考え直す「教育」のかたち
第2回は、書籍の第一章より、既存の「学校」というシステムに対して白井さんが感じている問題意識を綴ります。

端的に言うとね。
子どもの可能性を削ぐ、「とめ・はね・はらい」への執着
みなさんは「書字障害」をご存知ですか? 知的発達には大きな遅れがないにもかかわらず、文字がうまく書けなかったり、書いてある文字をそのまま書き写すことができなかったりと、「書く」能力に問題がある学習障害のことです。書字障害のある子どもの多くは、それらしい字は書けるのだけれど、とめ・はね・はらいといった細かな部分まで全部再現することはとても難しい。
ところが、現代の一般的な公教育の場では、書字障害のある子どもであっても、全員が細部に至るまで完璧に書くことを要求され、何十回と練習を繰り返させられています。繰り返しますが、書字障害のある子どもは、本人がいくら書けるようになることを願い、いくら長い時間をかけて練習しても、障害のない子どもと同じように書けるようにはなりません。点が一つ足りないまま、何時間もかけて20回ずつ書いた字に、全部バツがつけられて返ってくる。こうした「指導」を重ねた結果、その子どもの心は、ついには折れ、字を書くことそのものに拒否感を持ってしまう。現在の学校では、字を書くことを拒否することはそのまま学習を拒否することと同義になります。最初は字を書くことや勉強することに憧れて学校に入学してきたのに、そんな悲しい目に遭って学習への意欲を失ってしまった子どもたちに、私は何人も出会ってきました。
もちろん、「正しい漢字」を学ぶことの意味はあります。でも、それがどうしても難しい子どもについては、実際に使用する場面においては、読む人に伝わりさえすればそれでいい、という扱いにできないでしょうか。そもそも多くの人々にとって、パソコンやスマートフォンを使わずに手書きで漢字を書く機会さえ、かなり減ってきています。私自身、住所と名前を書く以外に字を書く機会がほとんどなくなってしまったので、いざ書くとなると簡単な漢字が思い出せない、なんてしょっちゅうです。
それでも私たちの多くは、特に大きな問題はなく、社会生活を送ることができています。それどころか、書字障害を持っている子に、「タブレットやパソコンを使ったらいいよ」と言ってツールを渡してみると、それまで「勉強ができない」と周りも本人も思い込んでいた子どもの中に実はとてつもなく高い能力が眠っていた……という場面に立ち会ったことは一度や二度ではありません。
それなのに、いまの学校教育では、「はねがない」もしくは「とめができていない」漢字は減点の対象になり、「書けない子」は「できない子」とみなされてしまう。これはまさに、子どもたちの可能性を潰し、一人一人が持っているはずの価値を貶めている事例と言えるでしょう。画一的な指導のもとで「ペーパーテストで点数を取ること」が価値の最上位に来るという教育のかたちが、子どもの可能性を削いでしまっているのです。
この「とめ・はね・はらい」は一例にすぎません。今日の公教育では、何十年も前に定められた形式を守ることが優先され、実際に子どもたちがその可能性を伸ばし、社会を生きていく知恵やマインド、スキルを身につけることが大切にされていません。現在の学校では、「正しい答え」を教師が教えた通りに正確に覚える子どもが「優等生」とされて褒められます。それができない子やそれに対して疑いを持つ子は「問題児」と簡単に決めつけられてきました。このような環境では、子どもたちは自分で物事を考えたり、決めたりすることを学ぶことが難しくなります。自分の心の声を隠してただ指示されたことをこなすだけの方が、目立たず、嫌な思いをせずに過ごせると無意識に学びとってしまっているからです。その結果として、子どもたちは学校を通じて本当に必要なことを学ぶ機会を奪われ、そして学ぶことの楽しさに触れる機会も奪われてしまっています。
それで学校を卒業して企業に入って、突然「自分の頭で考えろ」と言われても、何をどうしたらいいか、途方に暮れてしまう。多くの企業で求めている人材と実際に出会える人材にミスマッチが起こっていることにも、こういう背景があると思っています。
「塾頼み」の公教育が広げる教育格差
このような「学ぶ」楽しさに触れられない学校の現状は、教育の現場がいま置かれてしまっている厳しい環境の結果として生み出されたものでもあります。
これは私が一人の母親として直面した「実体験」です。我が子が中学2年生になり、授業参観に参加したときのこと。「ママ友」の一人からLINEが入り、「ちょっとうちのクラスに来て! すごいことになっている」と、私を呼ぶのです。そうして、その友人のお子さんが在籍しているクラスの授業を覗いてみると、そこでは数学の授業が行われている……はずでした。
しかしそこで私たちが目にしたのは、30人から40人ほどの生徒たちが黙々と紙にプリントされた問題を解いている姿でした。そして、3人の先生がうろうろと巡回する……。これがこの教室での「授業」でした。そして保護者はその光景を遠巻きに眺める「授業参観」をすることになりました。百歩譲って、せめてどの単元の学習かだけでも黒板に書いておいてくれればと思いましたが、それすらありません。「個別指導塾の劣化版を見せられてるのかな……?」というのが、正直な私の感想でした。保護者は、しんと静まりかえる教室で、プリントに黙々と向き合う生徒たちと、その間を歩き回る先生方の姿を見つめるしかなかったのです。私がその教室に到着したとき、保護者は私と私を呼んだ友人含め3人しかいませんでした。もともと、中学校の授業参観にはそこまでたくさんの親が来るわけではありません。しかし、それでも3人は少ない。おそらく私がその教室に到着するまでに、その〝授業〟の内容を見て、帰ってしまった保護者の方々もいたのだろうと思います。
最初は「保護者をなめているのか?」と思いました。しかし、すぐに「先生たちを責めることもできない」と思い直しました。30〜40人のクラスで、全員が同じスピードで同じ教え方で理解ができるような、そんな授業を展開すること自体が無理な話なのですから。現状の授業システムの限界については、この本の中でも追って詳しく書いていきますが、先生たちも限界を感じているからこそ、授業参観の際にも、「プリント学習」を実施するしかなかったのかもしれない。言うなれば、この授業参観は現状のシステムの中、個人の力ではどうすることもできない先生方のSOSだったのかも──そんなことを感じました。
とはいえ、この授業参観で感じた違和感を先生に伝えないわけにもいきません。担任の先生との個人懇談の際に、一人の親として抱いた感想を伝えたことがあります。その際、先生は「お母さん、この学校の学力レベルはそれなりに高いんですよ」とおっしゃって、納得がいってないこと丸出しの私の顔をちらっと見たあと、慌ててこう付け加えました。「もちろん、塾のおかげですけどね!」。塾の存在がなければ、一人一人の生徒が十分な学びを得ることはできないと、先生自身も理解していることをそこで知りました。
しかしすべての家庭に、塾に通わせる経済的な余裕があるわけではありません。子どもを塾に通わせたいのだけれど、その費用を十分には捻出できず、歯がゆい思いをされている親御さんもいらっしゃるでしょう。我が家も、子ども3人が行きたい塾や習いごと、全てさせたら月に数十万円の出費になります。厳選せざるを得ません。
公教育が正常に機能していれば、塾は学力を向上させるための補完的な要素として機能します。しかし、現状そうはなっていない。公教育が担うべき本来の役割の一つは、格差の再生産を止めることだと思っています。すべての子どもたちが生まれた家庭の貧富を問わずのびのびと学び、やがては「生まれた環境の差」を乗り越えることができるようにする──現在の公教育はその役割を果たせていません。それどころか、公教育の貧しい現状が、社会的格差の固定化に寄与してしまっていると、私は考えています。
「学校教育」にひそむ人権侵害
そして今日の公教育は「学びの場」として多くの子どもを取り残しているだけでなく、子どもたちの心の成長を見守る環境としても崩壊しているケースが多発しています。
これはある地方都市の公立中学校、それもその学校に通うために家族ごと引っ越してくるくらい評判のいい学校で実際に起こった──実は他でもない、私の息子の話なのですが、すでに成人した本人の了解を得た上で、事の顛末を記します。
息子が中学3年生になってしばらく経った頃のことです。コロナ禍での1ヶ月あまりの一斉休校が明け、学校が再開したのちもなんだか表情が暗く、学校へ行きたくなさそうな様子が続いていました。ある日彼は学校に出かけたと思ったら10分後に帰ってきて、真っ青な顔で「校門まで行ったけど、死にたい気持ちになったから帰ってきた」と言うのです。何が起きたのかと問うて初めて、その学校で、新年度になるたびに、全学年に対してまるで軍事教練のような授業が続けられてきたということを知りました。毎年、体育の時間は新学期が始まって10時間、準備体操と行進だけを練習させる授業が行われていたのです。
そこでは、足並みが揃っていないことはもちろんのこと、「振り上げる腕の角度が不十分」「指の第二関節が曲がっている」と生徒に罵声を浴びせ、「連帯責任」の名のもと、全体にやり直しを課していました。1年生のときも、2年生のときも、きっちり10時間ずつ、行われていたことを初めて知り、驚愕しました。3年生時、コロナ禍で一ヶ月あまり一斉休校になった後に再登校できるようになり、流石にこの状況ではやらないだろうと期待していたけどまた同じことが始まったと……私はそれまでその状況に気づいてやれていなかったことを猛省しました。
まさか、そんな軍隊のような教育が、令和の時代に公立の中学校でまかり通っているなんて──私は衝撃を受けました。我が息子が、母親の私同様、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person、周りの人の感情や気分に気づいたり影響されたりしやすく、繊細な人)と呼ばれる特徴があり、自分自身が怒鳴られなくても他者が怒鳴られるのを見ているだけでとても辛くなるタイプであることも改めて感じました。そういう人にとっては特に、合わない環境は、死に至る凶器にすら、なり得ます。
私は「死にたくなるようなところにはもう二度と行かなくていい」と息子に告げ、すぐさま私が運営していたフリースクールに通う手続きをしました。環境が変化したことで、息子はみるみる元気を取り戻していきました。「このフリースクールに出逢えていなかったらこの子はどうなっていたことか。校長先生、この学校をつくってくれてありがとうございます」とそれまで何千人もの保護者から言われてきましたが、よもや自分で自分にありがとうを言う日が来るとは想像していませんでした。
でも、私がフリースクールを運営する立場ではなく、他の選択肢も知らずに「学校に通う」ことを「当たり前」のことだと信じていて、無理に息子を学校に通わせようとしていたら……今生き生きとエンジニア養成機関に通って楽しそうに学んでいる彼の姿は見られなかったかもしれない。本当にゾッとします。
当時、校長や担任にも話を聞きに行きました。「なぜこの令和の時代にこんなことをやっているのですか?」と。学校の校長からの説明はこうでした。
「お母さんね、お気持ちはわかるのですが……体育って、ケガするんですよ」
「そうですね、わかります」
「ケガすると、学校が訴えられるんです」
「それもわかりますけど、そんなこと言ってたら何もできなくないですか?」
「その通りです、お母さん!!」
……これは話が通じないぞと、心折れる私。そこからは、校長が指示をしても教員が従うわけではないこと、教員の質が落ちていること、地域がこの教育を支持しているので変えづらいことなど、もはや校長や担任の愚痴に近いような話が続き、少なくとも我が子が通学している間は環境が変わらないことを理解せざるを得ませんでした。さらにPTA役員はどう考えているのかなと、路上で出会った際に立ち話で聞いてみたのですが「これがうちの伝統なのだ。嫌なら私学でもどこでも行けばいい」と激怒。「え? 公立の中学ですよ? 私学でそういう教育方針を求めて入学してきた子たちに対しての話ならまだわかるけれど……」と問うても、聞く耳持たず怒り続けているので、私も怖くなってしまって、そっとその場を離れました。
このとき感じたのは、「学校」というシステムの影響力の大きさです。私も含め、現在の親世代は、学校に適応できなければ「落ちこぼれ」「出来損ない」といった烙印が押される時代を生きてきました。学校という環境はいつも〝正しく〟、その環境に疑問を持つことは間違っている——多くの人が知らず知らずのうちに、そんな認識を内面化させてきたのではないでしょうか。そして、学校が行ってきた軍隊的な教育も、特に疑問を持たずに受け入れ、むしろ賞賛してきたのではないかと思うのです。
だからこそ、先のPTA役員をはじめとする大人たちは、指の第二関節が曲がっていただけで生徒たちを精神的に追い込んでしまう〝指導〟にも疑問を持たないばかりか、それを未来永劫守るべきだと主張したのでしょう。公教育による「価値観の刷り込み」が、地域に、国に、及ぼしている影響はあまりに大きい。
繰り返しになりますが、これは高度経済成長の頃の話でもなければ、バブル景気の頃の話でもありません。「ほんの数年前」、令和の話です。一般社会においては許されないような人権侵害が学校においてはなぜか容認されてしまっているのです。なぜならば、現代日本では「学校」が社会から孤立した別社会として存在しているからです。
なぜ「学校」では〝治外法権〟が許されるのか
「治外法権」という言葉が、歴史の授業で出てきたことをご記憶されているでしょうか。治外法権とは、外国籍の方が居住している国の法律に従わなくても良いとする権利のことで、1858年に江戸幕府がアメリカ政府と結んだ日米修好通商条約などに盛り込まれていました。治外法権を有する国の国民(日米修好通商条約の場合は、アメリカ人)が、日本で日本の法に触れるようなことをしてしまったとしても、日本の法律では裁けない、ということになります。
私からは、この治外法権を、現代の「学校」という空間自体が有しているように見えるのです。日本の学校の中で起こる出来事には、なぜか法律の効力が及んでいない──学校には〝治外法権〟(同然のもの)が存在する、と私は感じてきました。「そんな馬鹿な」と思われるでしょうか。でも、私自身、実際に明らかな犯罪行為があったにもかかわらず、警察を介入させず、学校内で処理しようとした現場をフリースクールの子どもたちが体験した事例を通じていくつも知っています。みなさんもさまざまなメディアを通して、学校の〝治外法権〟を感じるニュースに触れたことがあるのではないかと思います。ニュースになるような事例は氷山の一角で、実際にはもっと身近に溢れています。
学校に存在する治外法権の最たる例が「いじめ」でしょう。通常いじめにはなんらかの「犯罪」行為が含まれます。人を殴れば、暴行罪が適用される。誰かを物理的に傷つければ傷害罪が、あるいは精神的に傷つけてしまえば名誉毀損罪や侮辱罪が、物を盗めば窃盗罪が、危害を与えることをほのめかせば脅迫罪が適用されます……当たり前のことです。しかし、現在の学校ではその「当たり前」が通用しません。
明らかな犯罪行為が起こっているのに、学校内で解決しようとすることが、あまりにも多いように感じます。いや、解決しようとするならまだしも、当事者しかいない状況の中では結果的に解決に至らず、うやむやになってしまっていることがほとんどです。加害側はお咎めなし、あるいは形ばかりの謝罪をして楽しく学校に通い続け、被害者は不登校になり、泣き寝入り。そんな環境で、子どもたちが安心して学ぶことができるでしょうか?
先生も生徒も法律を守り、もし法に触れることがあれば、それ相応の報いを受ける。つまり、法治国家として当たり前の原則を守る。そんなことすらできていないがために、加害者が跋扈し、被害者は泣き寝入りするしかない状態になっている。これが、今の教育現場で現実に起こっています。「泣き寝入りする」だけでは済まなかったケースも枚挙に暇がありません。「犯罪」が原因となり、被害者が学校に行くことのみならず、生きることすら諦め、悲しい結末を迎えてしまった。みなさんも、さまざまなメディアを通してそんな痛ましい事件に触れたことがあるでしょう。
当然ながら、学校も社会の一部です。そこで起こった犯罪行為は、犯罪行為として対処されるべきです。
私がフリースクールで校長を務めていた際、校内で生徒のゲーム機がなくなってしまったことがありました。状況的に明らかに紛失でなく、「盗難」です。
私は警察に連絡をしました。「ちゃんと解決したいが我々には捜査権がないので捜査をしてほしい。ただし対象が未成年なので、子どもの未来にマイナスの影響ができるだけ少ないように配慮をお願いしたい」と話すと、優しそうな警察官が自転車に乗って駆けつけて来てくれました。状況の確認をしていたところ、どうしても欲望に負けてとってしまったという子がそっと名乗り出て、返してくれました。警察官とその子と私とで話をして二度としないと約束をし、そのまま警察の方は帰られました。無論保護者の方にもこういうことがあったことをご報告し、丁寧に対応していただいてありがとうございます、と感謝と労いをいただきました。
警察に連絡をした目的は、「罰を与えること」ではなく、学校側として決してうやむやにしないという姿勢を見せること、悪いことをしても見過ごされる環境をつくらないことでした。もちろん、具体的な対応方法はケースバイケースで適切に判断する必要がありますが、いずれにせよ「身内だけで秘密裏にどうにかしようとしないこと」が大切だと、この事例からも学びました。
私自身は、学校内の犯罪には第三者を介入させるべきだと考えています。最近では「スクールロイヤー」(学校内弁護士)の力を借りることも提案したりしています。スクールロイヤーとは、学校内でいじめなどの問題が起きた際に、学校に派遣され、学校・教育委員会・学校法人に対してさまざまな問題について助言・アドバイスをする弁護士のこと。生徒たちにも、保護者たちにも、事前に「何かあれば第三者を介入させる用意があること」を伝えておくことが無用なトラブルの防止になり得ます。
繰り返しになりますが、何よりも重要なのは事態を「なあなあ」にしないこと。なあなあにすることが加害者を助長させ、被害者を苦しめ、そして無秩序を生むことにつながるのです。被害者が学校に行けなくなり、加害者がのうのうと学校に通い続け、二次加害を続けているケースがどれほど多いことか。先生と生徒双方が当たり前に法律を守ること。たったこれだけで、学校の環境は大きく変わるはず。もしかしたら、これを徹底するだけで、不登校の数が半減するのではないかとすら、私は考えています。
〔つづく〕
この記事は、2024年12月にPLANETSから刊行される、白井智子『脱「学校」論:誰も取り残されない教育をつくる』の先行配信連載です。全文を読みたい方はぜひ同書のご予約をお願いします。