NHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回は『メインの森をめざして―アパラチアン・トレイル3500キロを歩く』を紹介します。著者の加藤則芳さんはアウトドアにおける「ロングトレイル」を日本に紹介した人物として知られる方。その著者が「これはアメリカ論だ」と述べるこのアウトドア本の背景について、井本さんは読み解きます。

「井本文庫」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
この書評コーナーでは、暮らしにまつわる本を紹介しています。アウトドアとか自然とか、そういったものを含めた「暮らし」です。今回は、加藤則芳さんの著書『メインの森をめざしてーアパラチアン・トレイル3500キロを歩く』をご紹介します。著者の加藤さんに言及しておきたいなと思って、この本を選びました。加藤さんは、いま日本でも普及への気運が高まりつつある「ロングトレイル」の紹介者として、アウトドア界で知られている方です。ロングトレイルというのは、山頂を目指す登山ではなく、自然の中を長距離歩くというスタイルのアウトドア・アクティビティであり、そのコースのことです。アメリカにはいくつか有名なコースがあるんですが、カリフォルニア州にあるジョン・ミューア・トレイルで全長約340km、アメリカ東部を南北に渡って続くアパラチアン・トレイルにいたっては全長3500kmと、「長い」と言っても、とてつもなく長いんです(笑)。たとえば、日本の本州の長さが約1500kmです。この本は、そんなアパラチアン・トレイル3500kmを加藤さんが踏破したアウトドア紀行本だと、まずは言えると思います。
ところが実際は、この本はそう簡単な本じゃないんですね。彼はこの『メインの森をめざして』で〈アメリカという得たいの知れない、そして摑みどころのない怪奇な国〉の〈秘密の一端を、アパラチアン・トレイルを歩く中で考え、検証しようと思った〉と述べています(〈〉内は引用。以下同じ)。つまり、この本は、アウトドア本であるというより、彼の〈アメリカ論〉として構想されているんです。
読み進めてみればすぐにわかるのですが、『メインの森をめざして』は、多くの人たちが登場する本です。3500kmの自然道を歩く加藤さんの旅には孤独感がないんです。僕は、好きでアウトドア紀行本をそれなりに読んでいて、もちろんさまざまな局面で人的交流も描かれますが、やはりメインには自然と向き合う自己があり、そして概して孤独が描かれるというのが多いんですよね。ところが本書には孤独な雰囲気がない。トレイルを歩く人間をハイカーと呼ぶのですが、加藤さんはまず多くのハイカーたちと交わっていきます。道行きで出会うこともあるし、野営地で多くの人と語り合う夜もあります。アパラチアン・トレイルを運営・管理する人たちとのやりとりもあります。また、アパラチアン・トレイルほどのロングトレイルをハイクするとなるとサポートを担う協力者も求められます。さすがに全行程分の食料など持ち運べませんから、一定の間隔で町に降り調達する必要もあって、そこでの町の人たちとの交流もあります。僕なんかはお遍路さんの「お接待」を思い出したのですが、そんなアパラチアン・トレイルのハイカーを応援し、ボランティアで歓待するルート上の住民たちもいます。
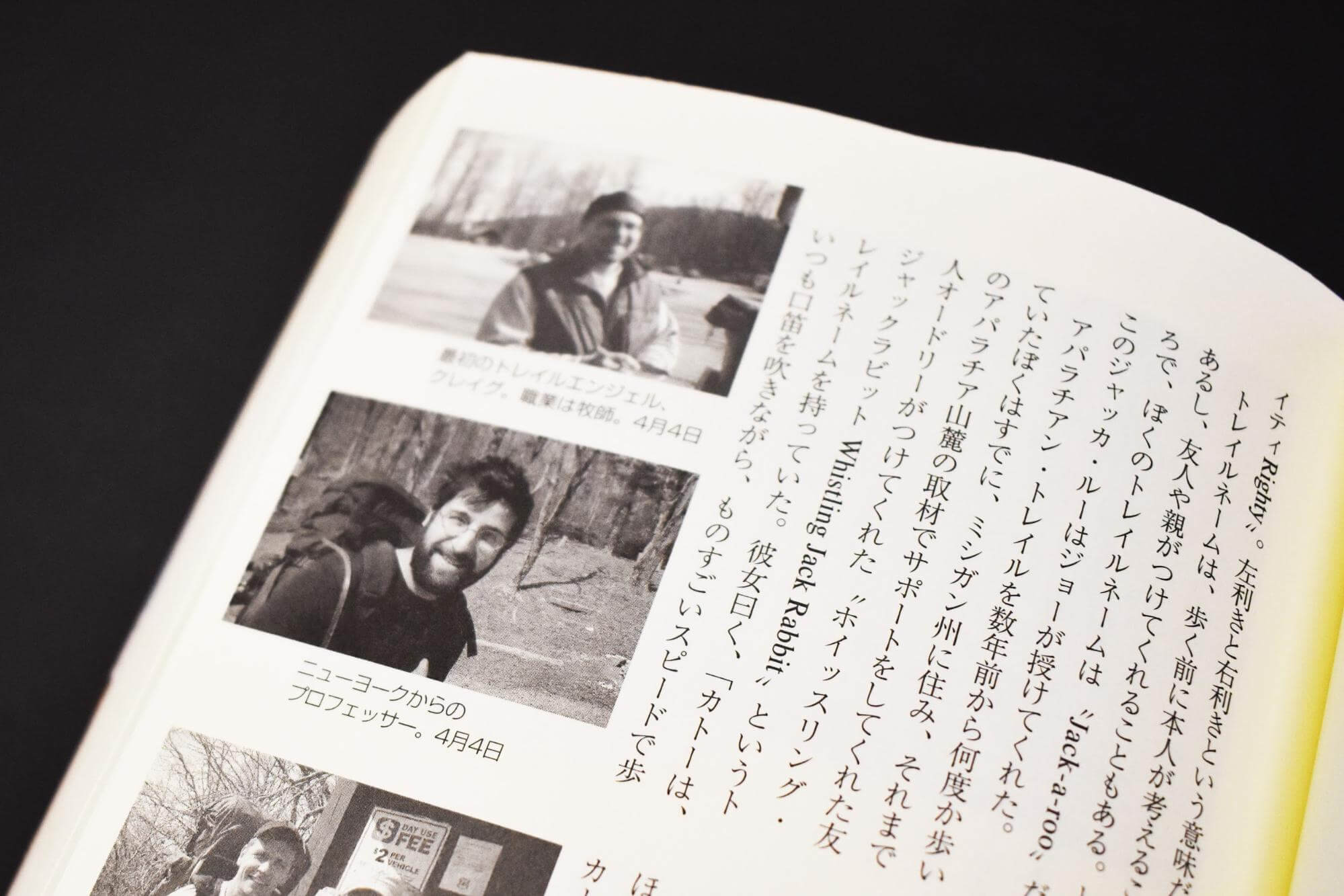
これは、もしかしたらロングトレイル一般というよりも、アパラチアン・トレイルに特徴的なのかもしれません。加藤さんは本書でこう記しています。〈アパラチアン・トレイルはネイチャー・トレイルであるとともに、それ以上に、じつはソーシャル・トレイルなのだ〉。もちろん、「自然」「森」「山」を自分の力で歩くという体験がロングトレイルの中心なわけですし、本書には加藤さんが撮影した自然写真も多数掲載され、アパラチアン・トレイルの自然の魅力を伝えています。そもそも、本書のタイトルは、文明を離れて森で隠棲した19世紀アメリカの自然思想家ヘンリー・D・ソローの著作からとられているんです。ソローが畏敬の念を込めて「混沌といにしえの夜から造られた大地」と表現したメインの森に足を踏み入れた加藤さんは、〈彼の表現は、一六〇年後、多くのバックパッカーが通るアパラチアン・トレイルを歩くぼくの視点からしても、そのまま理解できる。それほどにメインの森は今もなお、その奥深さと神秘性が漂い溢れ、ぼくもまた畏敬の念を持って歩き続けた〉と記しています。しかし、それでも、本書の印象を形成しているのは、ソーシャルの部分なんですね。加藤さんが、ある種類のアメリカ社会を生きた記録が本書なんです。つまり、「加藤さんがソローと同じように自然と向き合った」と言うよりも、「加藤さんが『自然と向き合った自然思想家ソローを生み出した社会』と向き合った」のだと言えると思います。それが加藤さんの言う、「本書がアメリカ論である」ということの意味だと思うのです。
では、なぜアメリカなのか。しかも、「アウトドア」というジャンルを通して。それを理解するために、加藤さんの来歴を紹介したいのですが、加藤さんは角川書店(現:KADOKAWA)の小説誌「野生時代」の創刊間もないころの編集者でした。やがて角川書店をやめ、信州・八ヶ岳でペンションを経営するかたわら、書き手として活動するようになります。編集部時代から一貫しているのは自然保護思想への関心なんですが、やがてそれがアウトドアに対する関心にも結びついてくるんですね。自然保護思想からアウトドアへと言うと、一見、わかりやすいなりゆきに思えます。ところが、それがそうでもないというのが、複雑なところなんですね。この本が単なるアウトドア本ではなくアメリカ論であるゆえんなんです。
ひとつ大きなポイントは、加藤さんが「野性時代」編集者だったときに、片岡義男の担当を7年間していたというところだと僕は思います。加藤さんの本には、折に触れて片岡氏が登場します。片岡義男という作家は、アメリカ文化の紹介者として1970年代から1980年代に若者から圧倒的な支持を集めた存在です。マガジンハウスの雑誌などをひとつの中心として展開したアメリカ文化の日本への導入に対して、先駆的と言える存在だと思います。ただし、片岡義男には単なる「アメリカ文化への憧れ」といったもの以上のアメリカ文化へのオブセッションがありました(そもそも、マガジンハウス的なアメリカ文化導入自体が、ファッショナブルな表層に反して複雑な含蓄を持つと思うのですが)。ひとつには、輸入元のアメリカ文化自体がその時代には、ビート運動やヒッピー・カルチャー、ベトナム反戦運動、ロックンロールなど、それまでのアメリカを批判的に捉え返すカウンター的なものになっていたということ。そして、片岡氏自身が、素朴にアメリカへの憧憬を抱く作家ではなかったということ。彼は幼い日に、アメリカが広島に落とした原子力爆弾の光を実際に目にしているんですね。つまり乱暴にまとめれば、片岡義男にとってのアメリカ文化が、非常に精神的なものだということなんです。

加藤さんがアメリカに対して持ち続けたオブセッションは、この片岡義男と共有していた、あるいは受け継いだものではないかと僕は思います。それを、アウトドア本のかたちを借りて記したのが『メインの森をめざして』ではないか、と。そこで、「なぜアウトドアというジャンルを通してなのか」です。1980年代、ファッション誌やライフスタイル誌を中心に導入がはかられたアメリカ文化が、ある種の成功と失敗を迎えた後、つまりよくもわるくも一般化していったあと、輸入文化としての外部性を残していたのがアウトドアというジャンル(のハードコアのところ)だったのではないかと思うんです。そして、現在もアメリカ文化の影響が外部性を残している数少ないジャンルのひとつがアウトドアではないかと僕は考えています。日本のポピュラーカルチャーでアメリカの影響を受けていないものなんて、本当に少ないでしょう。でも、それがまさにアメリカからの輸入物であるという外部性を今も残しているジャンルとなると、実は、けっこう少ないんじゃないかと思うんです。和様化しきっていないジャンルと言いますか。たとえばアメリカからの多大な影響を受けてきた日本のポピュラー音楽だって、現在の日本で和様化しきってないのってヒップホップぐらいでしょうか。そして、そんな数少ないジャンルのひとつがアウトドアなんです(アウトドアというジャンルのなかでもハードコアな領域でですが)。だからこそ、この『メインの森をめざして』というアメリカ論は、アウトドア本として書かれたのではないでしょうか。本書で、やや唐突な印象さえ残して「片岡義男が教えてくれたもの」という節が登場しますが、そこにはこのような文脈があるのだと思います。

さて、2011年に刊行された本書のあとがきで、加藤さんは2010年にALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断されたことを自ら記しています。そして、たいへん残念なことに2013年、永眠されます。とはいえ、ここまで述べてきた流れで比喩的に名前を挙げれば、彼が片岡義男から受け取ったバトンは、この本によって現在のアウトドアの流れのなかに繋がっていったんじゃないでしょうか。あるいは、繋がっていく可能性があるのではないでしょうか。本書でもそのオープニングフェスティバルのために一時帰国する信越トレイルという日本のロングトレイルづくりに、加藤さんは熱心にかかわっていました。そこで彼は、もちろん日本の自然ということを考えていたのだと思います。信越トレイルは、原生に近いブナ林や豪雪地帯ならではの植生を持ちつつ、親鸞の布教の道であったり上杉謙信が川中島に向かう道であったりという、歴史的な背景も持ったトレイルです。それは、自然と歴史に培われた日本そのものと言ってもよい80kmのトレイルなのです。加藤さんは、〈ぼくは決して、民族主義者ではない〉と留保しながらも、〈押し寄せてきた西洋文明の雪崩のなかで、日本固有の文化をないがしろにしてきた国民意識〉を(自己)批判し、〈あれほどの微妙な美を育んできた日本的な繊細な神経が、西洋的なるものに目が眩まされてしまった〉と嘆きます。そして、この日本そのものと言える信越トレイルに、加藤さんは愛情を注ぎ続けました。でも、一方で加藤さんが日本への紹介に力を注いだロングトレイルという文化に、抜きがたくアメリカという外部性があったということ。少なくとも加藤さんがアパラチアン・トレイルをそのようなものとして捉え、歩き続けたこと。僕にそのことを教えてくれたのが、本書『メインの森をめざして』でした。
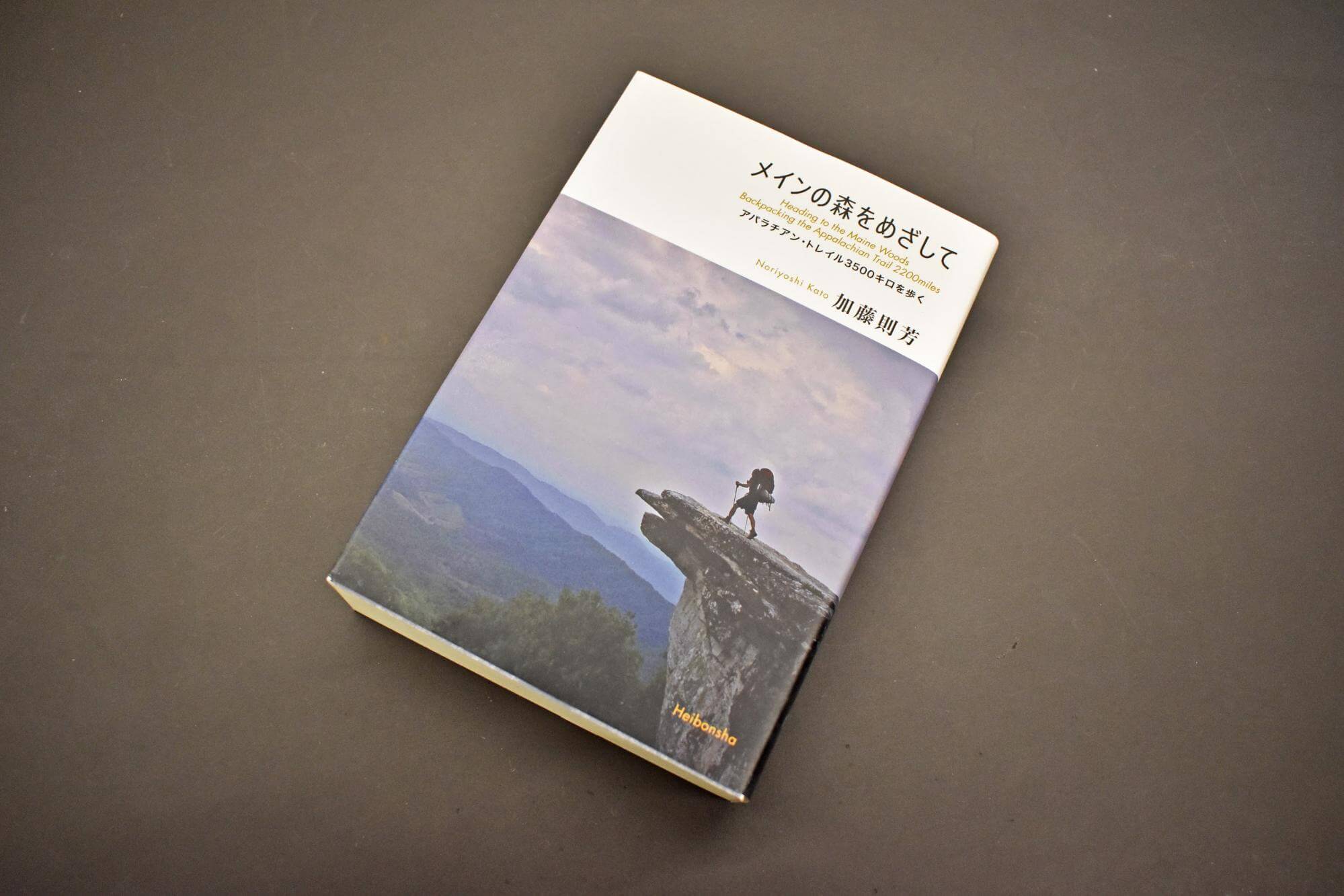
[了]
※この記事は、2018年1月10日に配信されたPLANETSのインターネット番組『木曜解放区』内のコーナー「井本光俊、世界を語る」の放送内容を再構成したものです。石堂実花が写真撮影をつとめ、2021年1月4日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。