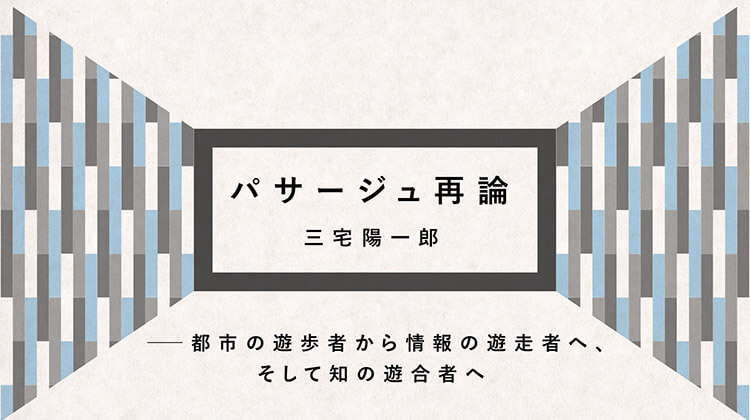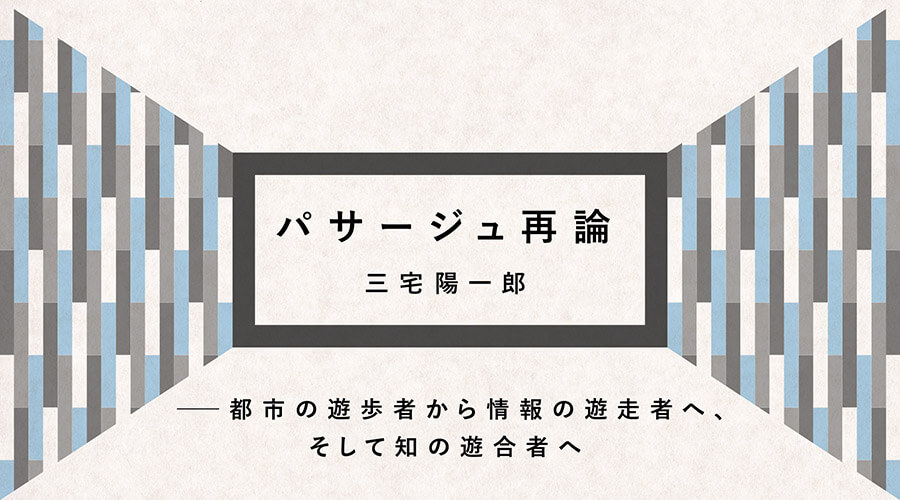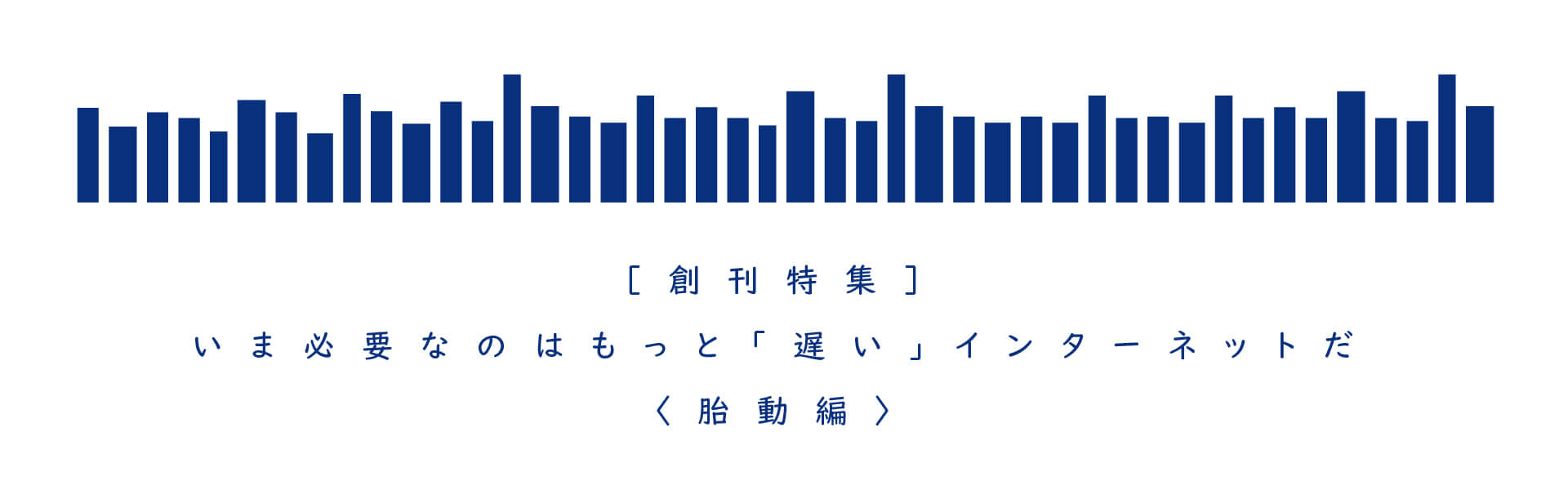かつてパリを歩いたベンヤミンは、都市の街路(パサージュ)を人々の多様なつながりと創造性を育む場と考えました。その役目を引き継いだはずのインターネットは、過密なムラ社会と化しつつあると、三宅陽一郎さんは指摘します。街から人影が消えたいま、改めてインターネットを新しいパサージュとして再生させるには。そのヒントを探す、人工知能技術者の思索です。
本記事をはじめ、「遅いインターネット」では、現在の速すぎるネット社会の問題とその向き合い方について、様々な観点から特集しています。
端的に言うとね。
現代の「パサージュ」としてのインターネット
私の前に二つのテクストがある。ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)の『パサージュ論』(1927-1935)、宇野常寛氏の『遅いインターネット』(幻冬舎, 2020)である。どちらも英知のほとばしる断章の集合であり、それでいて一つの筋が通っているテクストである。
両書には約90年の開きがあり、宇野さんは2019年の東京を走りながら、ベンヤミンは1920〜30年代のパリを歩きながら考えた。共通するのは風景を幻視しようとするところである。風景の向こうに時代の流れを感じ、感じたことをまた風景に重ねて思考するスタイルである。この二人の時代の幻視者が見る世界は、90年の時を経て、まったく違う様相を示すと同時に、とても良く似ている。ベンヤミンにとってパサージュとは実際の店舗が立ち並ぶパリの街路であり、宇野さんにとってのパサージュはインターネットである。
ここで描きたいのは、ベンヤミンが幻視した未来を、宇野さんが幻視した現在と対照することで、この社会の正体を僅かばかりでも描き出したい、ということである。
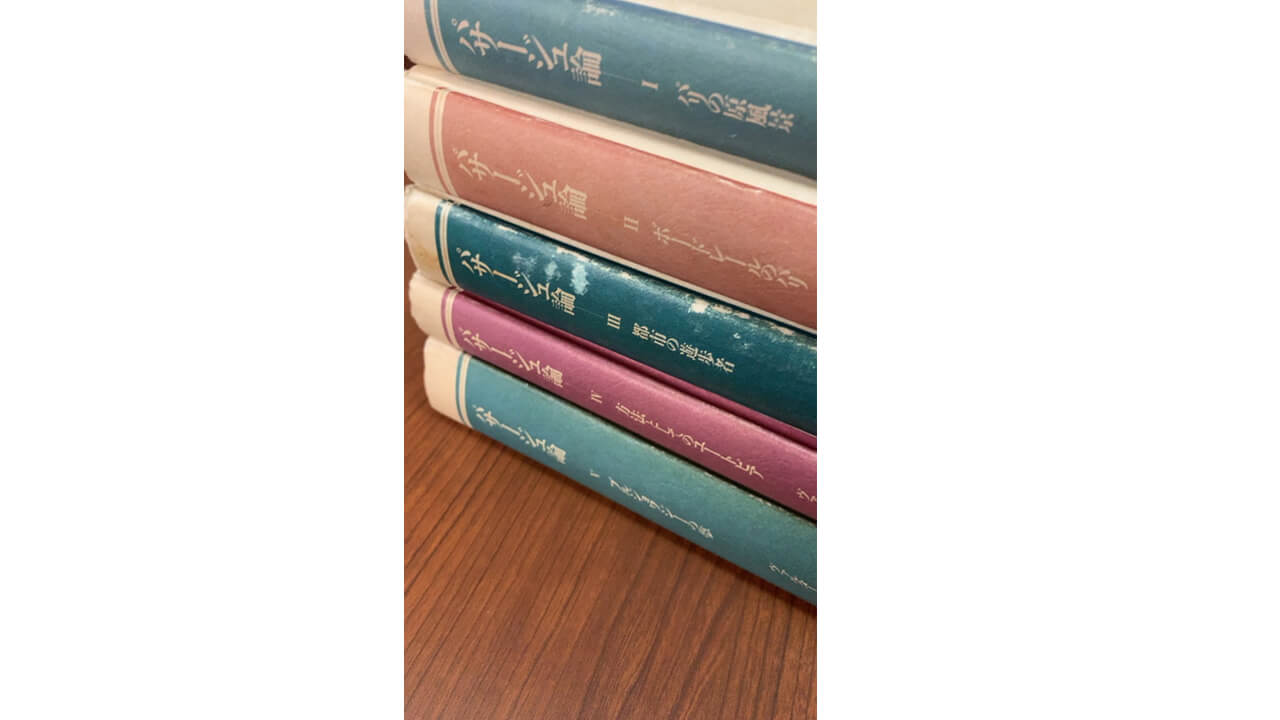
ベンヤミンはドイツの思想家である。結果として在野にあり、その独特の思考を発信し続けた。彼の文章は「折り畳まれた弁証法」と形容されるように、一つひとつの文章の中に戦術的にロジックが張り巡らされ、全体として多次元な構造を持つ文章体が出来上がる。そこに、縦横無尽に具体的な世界への参照や比喩や哲学が織り込まれる。読む者は、そのパッケージを紐解いていくことで、次々に現れるパースペクティブに驚かされる。
ベンヤミンの最も親しい友人には哲学者テオドール・アドルノ(1903-1969)がおり、『パサ―ジュ論』はベンヤミンが亡命中に原稿を託したバタイユがパリ国立図書館に隠し、一部はアドルノが亡命先のニューヨークで保存したものから構成されたという。ベンヤミンがパサージュ論で目指したのは引用文の配列によって全体を構成する書物である。パリの商店通り(パサージュ)を歩きながら、街並みが提起するさまざまな感覚・問題に対して、引用文をあてて並べる、という手法によって、まるで街路の商店の配列のように引用文が立ち並んでいる。
ここで引用する文章、そして上記の解説は今村仁司・三島憲一訳『パサージュ論』(岩波書店, 1993-1995)に依っている。『パサージュ論』自体が巨大な引用の集合であるから、『パサージュ論』からの引用は、引用のさらに引用ということになる。
まずは『パサージュ論』の引用から始めよう。
「産業化へ向けてもっとも重要な一歩は、銑鉄や鋼鉄を使い、機械的手段で、ある特定の形態(形鋼)を作ったことである。さまざまな分野が絡み合うようになった。つまり、建築物の各部分からではなく、線路をつくることからはじめるようになった…一八三二年のことである。形鋼。つまり、鉄骨建築の基礎の始まりがここにある」ギ―ディオン「フランスにおける建築」二六ページ
(ヴァルター・ベンヤミン著、今村仁司・三島憲一訳『パサージュ論』、I、P.275)
ベンヤミンはパリの過去の歴史を遡る。実際のパリの街の風景と、パリ国立図書館の膨大な文書をたどって、他者によって紡がれた言葉をつないでいく。鉄骨は線路を作り、建築を作り、橋を作り、アーチを作り、通り(パサージュ)を作り、機関車を作り、パリの骨格を形成して行く。骨格の隙間には、店が立ち並び、さらに店の中にはさまざまな商品が陳列されて行く。ベンヤミンはそのような物の動きの中に、歴史の作用を見ようとする。
一方、宇野さんの見る世界は、インターネット後の世界である。インターネットが世界の構造として張り巡らされ、ブログを作り、サイトを作り、SNSを作り、動画サイトを作り、そこにコンテンツが編み込まれ、人の存在を拡張していく。宇野さんはそのようなインターネットの発展の中に、社会の流れを見ようとする。
現在のインターネットは人間を「考えさせない」ための道具になっている。かつてもっとも自由な発信の場として期待されていたインターネットは、いまとなっては、もっとも不自由な場となり僕たちを抑圧している。それも権力によるトップダウン的な監視ではなく、ユーザーひとりひとりのボトムアップの同調圧力によって、インターネットは息苦しさを増している。
(宇野常寛『遅いインターネット』、P.184)
インターネットは世界を変えたが、変革の時期が来ている。かつてはオープンであることを旗印に他のメディアと戦ってきたインターネットは同調圧力を集約するレンズとなり、社会、団体、個人に対して、大きなプレッシャーをかける存在となった。発言者の意図に関わらず、一度作り出されたうねりは自律的に成長していく。一方、物の流れを注視するベンヤミンは、万国博覧会について、次の文章を引用する。
「万国博覧会はそれが当初もっていた性質の大部分を失っている。一八五一年にきわめて広汎な人々を包みこんだあの熱狂は消え去り、その代わりに一種の冷めた打算が登場するにいたっている。一八五一年にはわれわれは自由貿易の時代にいた。…いまではわれわれは数十年来、保護関税の領域がますます拡張してゆく時代にいるのである。…博覧会の参加は…一種の代表制となる。…一八五〇年には、このことには政府が口出ししない、ということが最高の原則とされていたのに対して、いまや一国一国の政府が本来の企業家と見なされるにいたっている。」ユリクス・レッシング『万国博の五〇年』ベルリン、一九〇〇年、二九―三〇ページ
(今村仁司・三島憲一訳『パサージュ論』、V、P.76)
物の流通は、自由貿易という熱狂と共に始まり、自由な交易が街にさまざまな商品を溢れさせ、万国博覧会というイベントを生み出した。しかし、商業は次第に国家の掌握するところとなり、各政府の介入によって冷ややかなものになって行く。政府は介入しない、という了解のはずが、その真逆を行く。これはトップダウンによる圧力である。本来自由であったものが束縛に変わっていく。時代を超えて、インターネットと自由貿易は同じオープンからクローズへの路をたどることになる。
流通の加速がもたらす体験の「アウラ」の喪失とどう向き合うか
自由貿易から保護貿易への流れは国益を守るための砦を築くことだった。では、インターネットの領域化は何のためにあるだろうか?
だが21世紀の今日において重要なのは、その「非日常」の「他人の物語」をどう「日常」の「自分の物語」としていくかだ。「報道」された事実を、「他人の物語」を知ったことでどう自分の考えが、世界の見え方が、距離感と進入角度が変化するかだ。ここで、「自分の物語」を編み直す力を蓄えなければ、結局人間はインターネットの「速さ」に流されてしまう。
(『遅いインターネット』、P.208)
自分の物語が、SNSに流れてくる小さな他人の物語の群れに浸食されてしまう。自分自身を「他人の物語」の主人公として、当事者でない人間があたかも当事者のように振舞う「他人事主人公」現象が頻発している。このような個人の物語の消失の仕方は、新しいがゆえに蔓延してしまっている。
かつて高度成長期やバブル期では、個人を上回る大きな物語が個人の物語を消失させたり、逆にバブル後の世界では大きな物語の喪失が個人の物語を喪失させたりした。しかし、今、個人から物語を奪うものは、小さな他人の物語の集合なのだ。かつては過酷な労働が人々から「根をもつこと」を奪っていた。対して現代では、余暇の時間の言説が現代人から根を奪っていく。
「速度」が人から考える隙を奪っていく。しかし、それは19世紀の芸術にも起こったことだとベンヤミンは言う。
ヨーロッパ的視点からすれば事態は次のように見えた。すなわち中世には、そして一九世紀の初めにいたるまでも、あらゆる商業製品にかかわる技術の発展は、芸術の発展よりもはるかにゆっくりとしたものだった。芸術はたっぷりと時間をかけて、技術が提供してくれる方法のまわりで様々な仕方で戯れていることができた。だが、一八〇〇年をさかいに始まる事態の変化によって、芸術にはテンポが求められるようになり、このテンポが息もつかせぬものになればなるだけ、モードの支配があらゆる領域に波及してゆくことになった。そして、ついに生じたのが今日の事態だ。つまり、技術のプロセスになんとか適応してゆく時間を見つけることが芸術にはもはや不可能となる、そんな可能性がもう目に見えるものとなっているのである。… [G1.1]
(今村仁司・三島憲一訳『パサージュ論』、V、P.51)
技術の加速に目を奪われて、自分の中にゆっくりと力強い物語が喪失している。だから、力強い物語を発信するための拠点が必要なのだ。
人は変化するものに目を奪われる。読み得るものは読んでしまうというのが、知恵の実をかじった者の宿命である。場所も時間も関係なく、地下鉄でも、路上でも、職場でも、デパートでも、エレベーターの中でも、特に急ぐ必要のない、その時だけに価値のある言説を飲み込み続ける。時間を奪われていく。
この背景には、1990年代後半から始まる情報化社会に適応する教育がある。そこでは、常に情報に対する感度を上げるような訓練がなされてきた。またそれが情報化社会で抜きんでるためのアドバンテージでもあった。
ところが、感度の高まった集団はたやすく情報に流されやすい。最も速く情報を持つものが真実を知っていると誤解し、最も速く伝わる情報をキャッチアップし、踊らされるようになる。あるところから、この社会には情報化社会を利用して人を操作するという悪意が混ざり始め、情報化社会の脆弱性を露呈することとなった。この状況を改善するには、情報と自分との距離をひらく必要がある。
この国を包み込むインターネットの「空気」を無視して、その速すぎる回転に巻き込まれないように自分たちにペースでじっくり「考えるための」情報に接することができる場を作ること。…そうすることで少しでもほんとうのインターネットの姿を取り戻すこと、そしてこの運動を担うコミュニティを育成すること。そのコミュニティで、自分で考え、そして「書く」技術を共有すること。それが僕の考える「遅いインターネット」だ。
(『遅いインターネット』、P.185)
「遅いインターネット」は発信者とコミュニティを一度分断し、結び直す、質の高い言説空間を作り出す試みである。コンテンツの質いかんにかかわらず、何もかもが流れていくインターネットの中で、激流の脇の静かな湖のような場所を作って、そこで生成した言説を再び流れの中に放流しようという試みである。この試みは、ベンヤミンの言う「アウラ」の復権でもある。
いったいアウラとは何か? 時間と空間とが独特に縺れ合ってひとつになったものであって、どんなに近くにあってもはるかな、一回限りの現象である。ある夏の午後、ゆったりと憩いながら、地平に横たわる山脈なり、憩う者に影を投げかけてくる木の枝なりを、目で追うこと―これが、その山脈なり枝なりのアウラを、呼吸することにほかならない。
(野村修訳「複製技術時代の芸術作品」、多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』、P.144)
言説を載せるメディアが、書物そしてインターネットへと変化していく中で、インターネットは言説を空間と時間から切り離し、ベンヤミンの言う「アウラ」を消失させた。「アウラ」の対義語は複製を繰り返し運ぶものとしてのメディア、特にインターネットである。インターネットはいつ、どこででもコンテンツを鑑賞し得るように芸術の体験を変化させた。さらに双方向のやり取りが、すべての創作されたものに対するアウラを喪失させていく。
インターネット上のプラットフォームはなし崩し的に発信者と受信者の境界を喪失させた。そして結果人々は発信の快楽に溺れることで、より容易に、愚かに、そして拙速になっていった。
(『遅いインターネット』、P.191)
数世紀にわたって文学においては、一方は少数の書き手がいて、他方にその数千倍の読み手がいる、という状態が続いていたが、前世紀の終わり頃、その点に変化が生じた。新聞が急速に普及し、さまざまな政治的・宗教的・学問的・職業的・地域的組織をどんどんと捲きこんでゆき、読者となじませるにつれて、しだいに多くの読者が―最初は散発的に―書き手に加わるようになった。同時にこのような読者のために新聞は「投書欄」を設けはじめた。こうしていまでは、ヨーロッパのほとんどすべての労働者は、その労働の経験や、苦情や、ルポルタージュなどをどこかに公表するチャンスを、基本的にもてるようになっている。それゆえ、作家と公衆とのあいだの区別は、基本的な差異ではなくなりつつある。
(野村修訳「複製技術時代の芸術作品」、多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』、P.168)
インターネットに、あえて「遅さ」を導入することで書き手を訓練しコンテンツの質を高めて発信する。宇野さんの「遅いインターネット」は、インターネット上の個人の尊厳までそぎ落としかねない現状に対する抗議の宣言であり、質の高い言説空間を復権させるための実行である。インターネットは新しいステージに入りつつある。
ベンヤミンが立っていたのは、工業技術の発展によって、物を生み出すことの手間暇が激減し、複製・量産化が可能になってから、さらに100年経った時代だった。そして、その影響が芸術に及ぶ時代でもあった。物からアウラが喪失し、さらに芸術までアウラを喪失する時、物と人、芸術と人、文章と人の関係が変化していくのを彼は見た。それは、特権性を排除することによる民衆中心の時代を形成する奔流でもあった。
インターネットが生まれ40年にも満たない現代は、情報に人が張り付いている時代である。情報を取得し、記憶し、行動する。いまや現代人は、インターネットから離れられない。そして価値の暴落した情報群に投げ入れるには、薄い情報で十分であるという考えのもと、脊髄反射のようにSNSへリプライを繰り返している。熟考した言説と、反射的に出てきた言葉が同じ土俵に立たされるとき、悪貨は良貨を駆逐する。
人に時間を、言葉に場所を。これは「遅いインターネット」が掲げる、これからのインターネットの新しい価値でもある。
現実空間とインターネット空間が融合する「新しいパサージュ」の完成のために
1920年代のベンヤミンは、資本主義によって工業化されたパリの遊歩者として、未来を幻視した。2020年代の宇野さんは、インターネットによって情報化された東京の遊走者となって、現代の変化を直視する。
では、これからの人間とインターネットの関係をよりよいものにしていくために、技術の側は何を目指すべきなのだろうか。
ここからは、人工知能技術の研究者としての私自身が幻視する未来像を述べていきたい。
人間は新しいメディアに弱い。声、文字、映画、ラジオ、テレビ、どれもその黎明期には人の言説空間を一時的にせよ支配する強い力を持っていた。しかし、それらのメディアに慣れてしまった現在では、人はそれぞれのメディアとの距離の取り方をわきまえている。しかしインターネットというメディアと人の関係はまだそこに到達していない。
人はインターネットのデマや中傷に翻弄される。インターネットが世間に普及してから20年以上が経つが、衝突の度合いはますます強くなるばかりである。現実空間で、他人に対して罵詈雑言を言う人は稀である。現実空間ではそんなことをしたら実際に身体を危険にさらすために自然と防衛本能が働く。しかし匿名化されたネット空間では身体と自分を結びつけるものがない(実際はあるが自覚できない)。そこで頭だけの存在となって言語空間の中で自我が肥大化していく。
さらに、もう一つの問題点としてインターネットには忘却がない。忘却は寛容の友である。決して忘れない、というインターネットの性質は、怒りや不満が消えずに積み重なる状況を作り出す母体となっている。
このようにインターネットは現在も発展途上の未完成の場であり、これを完成させるためには、人工知能が必要である。インターネットは現在でも、エージェント(小型の人工知能)たちがサイトをクロールして形成したデータベースを活用する「検索エンジン」や、エージェントがWebサイトの内容をフレームベースで解釈可能にする「セマンティックネット」という形で導入されている。しかし、インターネットをさらに完成させるためには、支配的なプラットフォーマーの側だけが独占するのでなく、ユーザー個々人に寄り添って支援する人工知能の解放が必要である。
現在のインターネットの問題点は、各個人がインターネットに張り付いていなければ、情報に取り残されてしまうという、強迫観念である。おそらく1ヶ月も世の中と隔離されていて戻ってきたら、まず見るのがインターネット上のニュースやSNSだろう。
しかし、本来情報処理は、人間よりソフトウェアの方が圧倒的に速く正確である。だからこそ、検索エンジンを使うわけである。インターネットの世界ではAIの方が人間より高い能力を持つ。対して、現実ではそれが逆転する。現実世界ではAIはほぼ無力であり、人間の方が圧倒的に高い能力を持つ。人間はAIのようにインターネットに融合することはできないし、同時にまたAIは人間のように現実世界で活動することはできない。
したがってAIと人間を結びつけて一つのユニットにすることで、インターネットと現実世界を結ぶ存在を作り上げることができる。インターネットにおける検索、情報統合、発信などは、AIが主体となって人間のサポートを受けつつ行う。現実世界においては、人間が主体となって、AIのサポートを受けつつ行動する。
現在、インターネット上で人間が直接アクションしているのは、まだインターネット技術が発展途上期だからであって、これからは人工知能越しにインターネットへアクセスする時代になるだろう。SNSへの接続もまた、人工知能を介したものとなる。
また、さらに大きな変化としては、もはや人間がインターネットに張り付き、没入する、という状況が消える。かわりに、自分を中心とした世界の側が、現実空間とインターネット空間が融合する形で再編され、宇野さんが『Ingress』などの先駆例から洞察したように、ますます「拡張された現実」としての様相を見せるだろう。現実世界は人間の足で移動しつつ、ネット空間は人工知能によって移動する。そして、二つの空間は混ざり合い、シームレスに行き来できるようになる。
その時、融合した世界は新しい「パサージュ」となり、人はその遊歩者と成り得る。「人間-AI」のペアは、初めて現実空間とネット空間の融合した世界の主体となることができる。
かつて村落共同体から離脱した人々のアジール的な場として都市が形成され、都市は誰もが匿名であると同時に、誰もが自由であり誰もが主人公であるような「雑踏」となることを可能にした。さらに資本主義的な都市の躍進は、消費者を消費都市の主人公とした。たくさんの人がいながらも、各人が都市の主人公となり得る。それがパサージュの魅力である。パサージュは人に「都市の遊歩者」の特権をもたらす。ブランド品や流行りの服は、RPGのように、主人公たちの装備となる。
言い換えればそれは、人間の地理と歴史への感度、世界を見る目を鍛える行為でもあるだろう。自分たちが生きているここ=「この世界」の深さを、多層性を把握し得る世界を見る目なくしては、「ここではない、どこか」=世界に果てまで旅をしても何も見えてこない―そんな確信が『Ingress』のゲームデザインの根底にある。
(『遅いインターネット』、P.185)
ある都市で道がわからないということは、たいしたことではない。しかし、森の中を迷い歩くように都市の中を迷い歩くには、習練が要る。迷い歩くひとには、さまざまな街路の名が、乾いた小枝が折れる音のように語りかけてこなくてはならないし、また都心の小路という小路が、山中の窪地のようにはっきりと時刻の変化を映し出してくれねばならない。
(野村修編訳「1900年前後のベルリンの幼年時代」、『暴力批判論 他十篇』、P.267、1994年)
中世の都市は城や教会を中心に街が作られ、城主や教主が特別な主人公であった。現代の都市は、誰もが主人公だと思うことのできる空間である。誰からの干渉も束縛も受けず、行きたい場所に行き、お金を払えば歓迎され、好きなものを買うことができる。それでいて、単に消費の欲望を満たすだけの空間に最適化されきらず、偶発的な他者との出会いやすれ違いが発生するだけの余剰がほどよく担保されているときに、都市は最大のパフォーマンスを発揮する。ベンヤミンが愛したパサージュは、そういう匿名性と余剰性との「ちょうどいい規模感」の都市風景のことだったのである。
インターネットも、本来はそのような解放の場であるはずだった。まだ参加者が少なく、それぞれが創意工夫の余地があった頃は、インターネットもまた都市的なパサージュだった。しかし、SNSが人だらけになって過密になり、相互監視状態に陥った現在のインターネットでは、大きな野原で誰が最も大きく声を出すか、という村落に似たマウント合戦が行われている。この人口密度を緩和し、本来は広大なはずのインターネットで、一人ひとりが主人公となりながら、適度に集まったりすれ違ったりできるような「ちょうどいい規模感」の都市性を、現実とネット空間の双方に取り戻すためにこそ、人工知能による自動調整が必要になるのだ。
インターネットの場が都市の様相に変わるとき、そこにパサージュが拓かれるとき、各人の意識も人工知能と混合することで変化していくことになる。発展した現実-ネット空間では、誰もが主人公であり、争うことも少なくなるだろう。
つまり、人間とAIが互いに結び合い遊ぶように協働しながら二つの空間を融合させていく「知の遊合者」になること。それこそが、私の幻視する新しいパサージュの風景である。
[了]
この記事は2020年4月27日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。