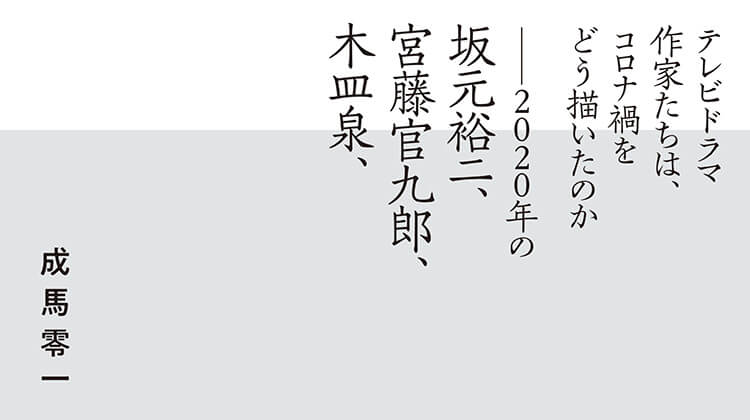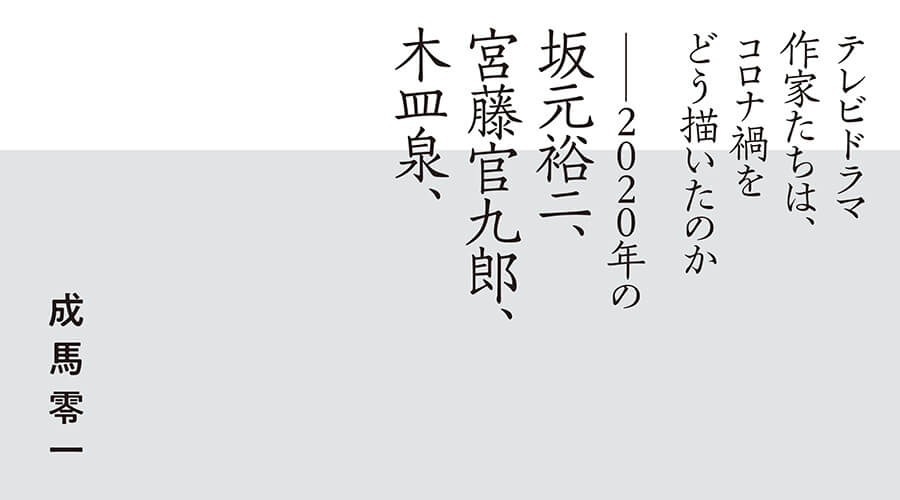世相の変化に最も密着した物語表現として時代を映し出してきたテレビドラマは、2020年から進行中のコロナ禍の現実を、どのように描いてきたのか? 新著『テレビドラマクロニクル 1990→2020』で平成・令和のテレビドラマ史を綴った成馬零一さんが、現代ドラマを牽引する坂元裕二、宮藤官九郎、木皿泉の3人の脚本家の短編作品を通じて振り返ります。
端的に言うとね。
2020年5月4日、政府の専門家会議は「新しい生活様式」を提示した。
厚生労働省のホームページに掲載された「新しい生活様式」の実践例には「感染防止の3つの基本」として
① 身体的距離の確保
② マスクの着用
③ 手洗い
と書かれている。
また、「日常生活を営む上での基本的生活様式」として「密集回避」「密接回避」「密閉回避」「換気」「咳エチケット」「手洗い」のピクトグラムが表示されている。
この「新しい生活様式」は二つの意味で、以後のドラマ制作に大きな影響を与えることになる。
一つは、ドラマを作る上での基本的なガイドラインとして、もう一つは「新しい生活様式」を前提とした「新しい日常」を、ドラマの中でどう描くのか(あるいは描かないのか)という、物語面での影響だ。
本稿では、現代のテレビドラマを牽引する3人の脚本家・坂元裕二、宮藤官九郎、そして木皿泉が、こうした環境下で制作した短編作品を通じて、どのようにコロナ禍の現実に応答していたのかを振り返ってみたい。
坂元裕二『リモートドラマ Living』
寓話的アプローチで迫ったオムニバスファンタジー
5月30日と6月6日の2週にわたって土曜夜11時30分から放送された『リモートドラマ Living』(NHK)は、打ち合わせも撮影もオールリモートで制作された1話15分、全4話からなるオムニバスファンタジードラマだ。

作家(阿部サダヲ)と喋るドングリ(声・壇蜜)とのやりとりから生まれる4つの物語は、第1話が広瀬アリスと広瀬すずの姉妹、第2話が永山瑛太と永山絢斗の兄弟、そして6日に放送された第3話が中尾明慶と仲里依紗、第4話が青木崇高と優香(声)という実の家族(姉妹、兄弟、夫婦)が共演。これはリモート撮影ゆえの苦肉の策だが、こんな時だからこそ実現した夢のラインナップだろう。
脚本は2018年の『anone』(日本テレビ系)以来のドラマ執筆となる坂元裕二。制作統括は連続テレビ小説『あまちゃん』(2013年)や『いだてん~東京オリムピック噺~』(2019年)の訓覇圭。
坂元は『最高の離婚』(フジテレビ系、2013年)で、訓覇は宮藤官九郎が脚本を担当した『あまちゃん』で、フィクションの中に“震災以降の現実”が侵食してくる姿を2010年代に描いていた。
『ユリイカ2021年2月号 特集=坂元裕二』 (青土社)に訓覇が寄稿した「アスリート・坂元裕二 リモートドラマ『Living』ができるまで」には、制作当時の状況が書かれている。
元々、訓覇と坂元は同じ年齢の飲み友達だったが、偉大な才能ゆえに、一生、仕事はしたくないと訓覇は思っていた。
しかし、緊急事態宣言の期間に、NHKに縁のある俳優たちでトーク番組を作ってもらえないか?」という話が訓覇に持ち込まれる。番組は、CGアニメーションのMCが役者の自室を尋ねてトークする場面を数珠つなぎで見せるという内容で、それを緩やかなストーリーがある感じで作りたいという要望だった。「誰か、いい構成作家はいない?」 そう聞かれた訓覇は「それはバラエティーの仕事だよね」と思いつつも、何故か断る気になれなかった。
そして、「こんな時を背負える人」だと直感的に思い、坂元裕二に連絡する。坂元は「コロナに対して何かを表現したいというより、表現の場が確実に約束されていることが嬉しい」といって仕事を引き受ける。制作期間は1ヶ月。打ち合わせはすべてリモートで行われた。まず二人が確認したのが、リモート画面を使わないことと、コロナに対する直接的な表現を避けるということだった。
ギリギリのスケジュールの中、坂元は講師を務める東京藝術大学の教え子たちから「家族」というテーマのプロットを一週間の〆切で募集。そのプロットを元に坂元が「台詞化」したドラマが、この『Living』である。
打ち合わせから撮影まですべて“リモート”というコロナ禍の現在をもっとも象徴する映像手法で作られたドラマを手がけたのが『Living』だが、本作のスタンスが他のリモートドラマとスタンスが違ったのは、「コロナ禍の現実」からは距離をとり、寓話的な物語を通して現在を見つめるドラマとなっていたことだ。
第1話「ネアンデルタール」は、絶滅間近のネアンデルタール人の物語。シイ(広瀬アリス)とクコ(広瀬すず)は、多数派のホモサピエンス(人間)と結婚すると自分たちの種族が滅んでしまうため、なんとか絶滅を阻止するためにネアンデルタール人と付き合いたいのだが、なかなか出会いがない。二人の会話から伺えるホモサピエンスは多数派でコミュ力があり、ちょっと悪くてちょっとかわいいのに対し、ネアンデルタール人は少数派のマイノリティで、いまいちパッとしない。人類とネアンデルタール人の関係はマジョリティとマイノリティの対立にも見えるし、坂元が『問題のあるレストラン』(フジテレビ系、2015年)で描いた日本社会における男女の格差の話にも聞こえる。基本的には広瀬アリス&すず姉妹がイチャイチャしている姿を観ているだけで、あっという間に時間が過ぎてしまう楽しくてかわいいドラマなのだが、会話の背後にある世界を想像すると、絶滅間近のネアンデルタール人から見た野蛮で獰猛な人類という支配構造が浮かび上がってくる恐い話である。
第2話「国境」は、ハク(永山瑛太)とライ(永山絢斗)の兄弟が、ひき肉と玉ねぎを炒めてじゃがいもを混ぜたものを丸めてパン粉で固めたものを油でカリカリに揚げた料理を作ろうとする話。
二人は、“令和時代”や“昭和時代”といった昔の食べ物を作る労働をしている。この時代には「怒る」「悲しい」という言葉は使われなくなっており「どうせ失敗するんだから諦めなさい」という価値観が常識化している。そして、再び戦争が始まることが二人の会話から次第にわかってくる。
メガネをかけた永山兄弟がお互いのエプロンの背中の紐を結び合うシーンはかわいく、広瀬姉妹以上のイチャイチャ感があるのだが、楽しく語られる未来の状況は不穏で、それが「新しい日常」となっていることの不気味さが表現されている。
どちらの話も、ドングリとの対話を通して小説家が紡ぎ出す物語だが、ドングリは「人類が滅びる。センセー、それはとってもすばらしいことです」「人間が終わっても、世界は別に終わりませんよ」と、人間は愚かで滅びてもいい存在なのだと「かわいい声」で語りかけてくる。
作家は、そんなドングリに反発して「人間のすばらしさ」を描こうとするのだが、出来上がった物語は捻れてしまい、むしろ人間に対する不信感が強く現れたものとなっていく。
ドングリに「もうおわかりのはずです。人類はこの世の嫌われものだってことに」と言われた作家は「わかってる」「ずっとそう思っていた、そう言いたくて作家になった」と言った後、「作家というものは人間の醜い部分を書くものなのだ」「危険な毒を吐くものなのだ」と言いながら「それが今やなんだ? 正直、現実の人間が醜くすぎて、私の吐く毒が毒じゃなくなってしまった」と嘆き、こうなった以上「人間ってすばらしい」という物語を書こうと決意する。
作家の言葉は、醜い現実ではなく美しい理想を描くと宣言しているように聞こえる。しかし、作品から受ける印象は真逆で、今のコロナ禍では、口に出すと不謹慎だと言われかねない毒のある絶望を優しく楽しい語り口で展開するという、フィクションでしかできないことを、しれっとやってのけているのだ。
その表現者としての大胆不敵さに、筆者は救いのようなものを感じた。
6月6日に放送された、第3話「おでんとビール」は、シゲ(中尾明慶)とアキ(仲里依紗)という夫婦の物語。小さなすれ違いが大きくなり、最後に妻が夫に離婚を切りだすという展開は、『最高の離婚』等で坂元裕二が展開した、もっとも得意とする物語である。
「夫がね、妻に言う「ごめん」ってね、「もうその話やめろ」って意味なのよ」「ごめんねって言葉でごまかされるたんびにさ、シゲくんが遠くに見えて、どんどん私、一人になっていくんだよね」といった台詞は、聞くたびに胃が痛くなるもので、この4作の中では一番生々しいエピソードだった。
同時に面白いのは、物語自体は時間SF的なアイデアで書かれていること。
シゲの妻には催眠術がかかっており、ある言葉を言うと記憶がリセットされる。だから、シゲはアキが「別れよう」と言うたびにその言葉を口にして、ゼロからやり直そうとする。
恋愛シミュレーションゲームやその影響下にあるドラマやアニメでよく見られる時間巻き戻し&ルート分岐系の物語だが、同時に壊れた夫婦の関係をやり直そうとする物語をコロナ禍のぶつけることで「一度壊れたものはやり直すことができるのか?」とこちらに問いかけているようにも見えた。
姉妹・兄弟の会話がイチャイチャ感に溢れていたのに対し、夫婦だとギスギス感(外から見ているとそれが面白いのだが)が強く、実際の夫婦が演じているだけに、こんなやりとりを演じて二人は大丈夫だろうか? と心配になるくらいだ。
もちろん、それくらい迫真の二人芝居だったということだが……。
そして、最終話となる第4話「敬遠」は、微熱を出して赤ん坊に風邪をうつさないように別室で自宅隔離されている東山(青木崇高)の物語。
テレビ局のベテラン社員(おそらくプロデューサー)らしき東山は、若手社員が放送しようとしたスクープにストップをかける。「メディアの“えりもち”が」と矜持(きょうじ)もまともに読めない若い社員をバカにし、テレビで放送されているバラエティ番組には「そんなに笑いたいのかね」、ドラマ(さっきまで放送されていた第3話)には「つまんなそうだな。2秒でわかるわ」と文句を言いながら、SNSに書かれたテレビ批判には「出たよ。批判だ、批判、テレビはクソですよに~」と悪態をつく。
そこで突然テレビが付くのだが、放送されているのは過去の高校野球の映像。ピッチャーは玉白高校の東山、つまり過去の東山だ。そしてバッターは朝倉学園の4番で超高校級スラッガーと言われた坂口。
当時、東山は監督の命令で、5打席連続敬遠をした。試合は朝倉学園の勝利で見事甲子園に出場。逆に坂口は選手生命をここで終えた。
連続敬遠は批判されたがこっちは勝ち組、相手は負け組と言い訳をする東山。スクープをもみ消そうとする今の姿と重なる。
しかし、第5打席でも敬遠するはずだった過去の自分は、ストレートを投げる。監督の指示を無視して勝負する自分を東山は応援する。結果的にホームランを打たれて試合には負けるのだが(ありえたかもしれない)過去の自分の姿を見て奮起した東山は後輩に「俺が責任取るから」と言ってスクープを放送させようとする。
テレビマンを主人公にしているため、作り手による自己言及的な作品とも言えるが、テレビモニターの側から東山を映しているため、鏡越しに自分の姿を見せられているような気まずさがある。
その意味で東山は、テレビを見ている私たち視聴者の分身なのだろう。
作家とドングリの対話によって紡がれる4つの短編を見終えて、筆者は村上春樹の連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』(新潮社、2000年)を思い出した。1995年に起きた阪神淡路大震災をモチーフにした本作は、東京で起きる地震を防ぐためにかえるくんがミミズくんと戦う「かえるくん、東京を救う」のようなファンタジーテイストの作品と被災した男女の恋愛を描いたリアルな作品が入り混じっており、最後に収録された「蜂蜜パイ」では、作者を思わせる小説家が「これまでとは違う小説を書こう」と決意して終わる。
コロナ禍に『Living』を書いたことが、坂元裕二の作風に今後どのような影響を与えるかは未知数だが、あれだけ作家の悩む姿を見た後だと、どれだけ人間に絶望してもいいので書き続けてほしいと願う。多分それくらいのことしか、作家にはできないのだから。
宮藤官九郎『JOKE~2022 パニック配信!』
「笑えない笑い」が恐怖に変わるとき
つづく8月には、宮藤官九郎と木皿泉の単発ドラマが放送された。
宮藤が脚本を手がけたのは8月10日の夜10時からNHKにて放送された『JOKE~2022 パニック配信!』(以下、『JOKE』)。
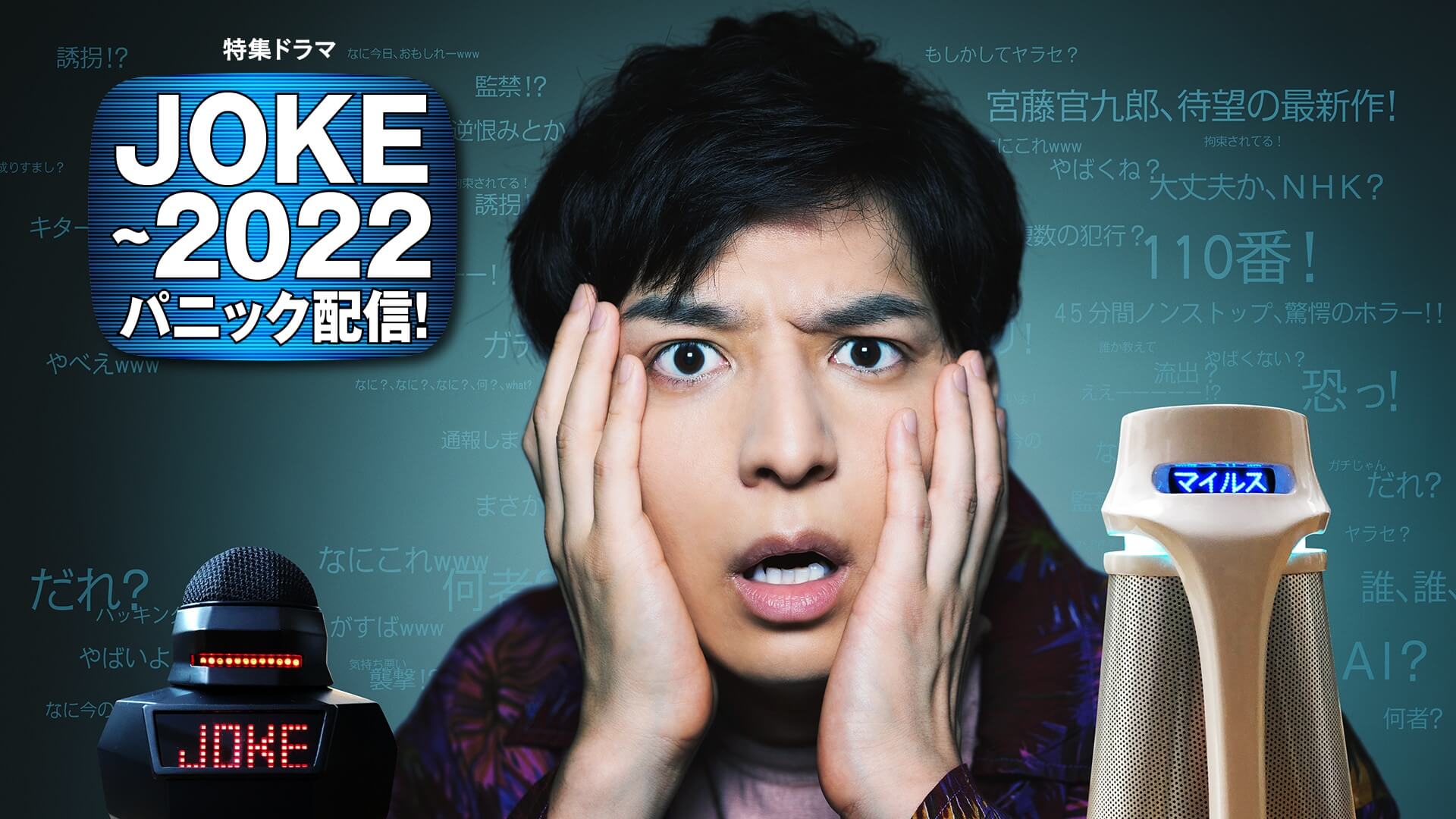
物語の舞台はポストコロナが叫ばれる近未来。漫才コンビ「俺んち」のボケ担当・沢井竜一(生田斗真)は不祥事を起こしてテレビのレギュラー番組をすべて降板。相方とも絶縁し自宅に引きこもっていた。起死回生のために沢井はAIロボットを相方にネット配信で大喜利番組「俺んちチャンネル」をスタート。番組は好調だったが、生配信中にかかってきた電話で状況が一変し劇場型犯罪に巻き込まれてしまう。
ドラマは、芸人が配信するネット番組でのやりとりが45分間ノンストップで放送された。映像のほとんどは、主演の生田斗真による一人芝居だ。
演出を担当するのが日本テレビ所属の水田伸生。坂元裕二脚本の『anone』や、野木亜紀子脚本の『獣になれない私たち』(日本テレビ系、2018年)といった話題作を手がける演出家で、宮藤とはドラマ『ゆとりですがなにか』(同、2016年)などを手がけている。
坂元裕二の脚本を演出した『モザイクジャパン』(WOWOW、2014年)など、日本テレビの制作会社アックスオンとNHKが共同製作をおこなう事例は近年増えているが、日本テレビのディレクターがNHKのドラマを演出しているという意味でも珍しい作品となっていた。
宮藤はこの企画の経緯についてエッセイで以下のように書いている。
昨年の今頃、芸人さんが立て続けに不祥事を起こし、謝罪会見、そして自粛という魔のループが繰り返されたこと。ネットやSNSで集中砲火を浴び、民放各局は対応に追われ、お茶の間の顔が突然TVから消える。気の毒と思うと同時に違和感もあった。
出典:宮藤官九郎「いま なんつった?」 連載597「 放送は8月10日です!」週刊文春8月13日・20日 夏の特大号(文藝春秋)
その違和感から、干された若手芸人がテレビからYouTube等の配信に活路を見出し、そこで人気者となるが、番組配信中に脅迫電話がかかってきて見えない敵との戦いになるというプロットを思いつく。その後、水田伸生に持ち込み、話が進みかけたが、実際にユーチューバーに転身する芸人が増え始めたことで「今やったらシャレにならんな。置いとこう。」と思って一度、止めた企画だったという。
確かに2019年は、お笑い芸人やタレントが、YouTubeで自分の番組を立ち上げることが急増した年だった。劇中にユーチューバーが登場するドラマも急増し、番組配信が一気に市民権を得た年で、だからこそ「現実に追いつかれてしまった。」と宮藤は書いているのだろう。確かに当時放送しても新味は感じなかったかもしれない。
そんな経緯もあって企画を練り直し「いずれ映画にしよう」と宮藤は考えていたと、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組(*)で語っている。
(*)TBSラジオ「ACSION」(2020年7月21日放送回)
しかし、違う映画の台本を書いていた時に、現代を舞台にした作品で「三密」を意識すると書くことが難しいシーンが多く「やりづらいな」と思っていた時、この『JOKE』のことを思い出し、今ならできると思い、6月後半に企画を改めて提案。
そして、許可を待つ間に脚本を仕上げてしまったという。
製作統括は坂元裕二脚本の『リモートドラマ Living』を手がけた訓覇圭。
宮藤とは、『あまちゃん』と『いだてん』を共に手がけている。前述のラジオで宮藤は、今回の『JOKE』は、コロナ禍にNHKが作ってきたリモートドラマのノウハウが生かされているのではないかと語っていたが、一人の登場人物がずっと画面に登場して喋るという舞台テイストの映像となっており、リモートドラマとは違った形で、コロナ禍と向き合った新しいドラマの試金石となっていた。
宮藤、訓覇、そして7月に放送された、コロナ禍にスナックを営む家族の姿を描いたホームドラマ(とその制作現場を撮影したドキュメンタリー)『不要不急の銀河』(NHK)を手がけた井上剛は『あまちゃん』、『いだてん』を手がけた作り手だが、それぞれ、コロナ禍と向き合ったドラマを作っている。
井上演出の作品は、ドキュメンタリー性とファンタジー性を兼ね備えた虚実が融合したものが多く、綿密に取材を重ねてリアリティを追求すればするほど、幻想的な映像に仕上がっていた。
訓覇が手がけた『Living』も、物語自体は近未来を舞台にしたファンタジーテイストの作品でありながら、広瀬アリス&広瀬すずといった、実際の姉妹、兄弟、夫婦が出演しており、ファンタジーでありながらドキュメンタリー的な作品だった。
宮藤脚本の『JOKE』は生配信を題材にしたAIの登場する話だが、本作もまた、虚実の入り混じったドラマだ。芸人の家の中で物語が展開され一人芝居の多い本作はドラマというよりは演劇の実況中継を観ているようで、大人計画に所属する宮藤の資質が活かされた、とてもライブ感のある舞台演劇のような作品となっていた。
物語はAIスマートスピーカーのマイルスとやりとりをしながら、おれんちチャンネルの準備をする沢井の姿が実況されていく。画面には視聴者数とコメントが同時に表示されるのだが、コメントのほとんどはアンチによるもの。理由は30万部売れた際のエッセイの帯(に書かれた本文の抜粋)が金子みすゞと相田みつをのパクリだと問題になったからだ。
かつての相方が放送する番組を流しながら「テレビ終わってるわー」と言う沢井。タイトルから2022年の出来事だと思うのだが、番組は“何度目かの再放送”でコロナ禍の状況は今とあまり変わらないようにみえる。
マイルスの他にもJOKE先生というAIのスマートスピーカーもいて、彼とのやりとりで番組は進んでいくのだが、沢井は視聴者の大喜利の相手から脅迫されることになる。
犯人は妻と子のいるマンションの前にいると言う。イーバーフード(フードデリバリーサービス)を装ってマンションに入り、妻と子を襲って監禁したことが音声で暗示される。そこから犯人?とのやりとりと沢井を煽るコメントが交互に流れるようになりネットを題材にした劇場犯罪へと変っていく。妻と子からの「助けて」という電話と視聴者の電話、犯人の電話、イーバーフードの配達が交互に入る。配信を止めようとしている沢井に対して犯人は「軽くおいしいと思ってんだろう、今?」と言われる。犯人の喋り方と相方の喋り方が似ていると思い、犯人は相方か? と匂わされる。嫁からスマホのメッセージアプリが帰ってきたから嘘だと思ったら、コメント欄に「SMSのアカウントが乗ってられましたね」と表示され、(嫁と子を乗せた)車がコンビニに突っ込む映像が送られてくる。他にもイーバーフードと配達サービス雨天の荷物がたくさん送られてくるといったイタズラまで始まり、何が正しくて何が正しくないのかわからなくなっていく沢井だったが、やがて犯人はスマートスピーカーのAIだったことが明らかになる。つまりすべては、(お笑い担当の)JOKEが発した「参ります」という音声にマイルスが反応して大喜利の答え「生配信中に妻と娘が誘拐される」や「アクセルとブレーキを踏み間違える」といった声を命令と勘違いして実行したことで起きたトラブルだと明らかになるのだ。
コンビニに突っ込んだ動画もフェイク動画で、実はモニター越しに話している相手もマイルスによって作られたものだとわかっていく。
「全部俺じゃん……、俺発じゃん」
「こいつがネタ(JOKE)振ってこいつ(マイルス)がボケてたってこと」
「こいつとこいつで、漫才やってたってこと?」
何でこんなことをしたのだ? と詰め寄る沢井に「その質問にはお答えできません」とマイルスは言う。沢井は結局、これは自分のやったことだと思い、自分は何でこんなことをしたのだと自問自答をはじめる。
AIが自我に目覚めて自分の意思で行動するというのであれば、SF映画によくある展開だが、本作のAIは「もうひとりの自分」として描かれている。
初期化されそうになったマイルスがある行動に出ることで、実はAIにも生存本能や自我のような自立意思が芽生えているのではないかと匂わせ、皮肉な終わり方で本作は幕を閉じる。すでに現実となったAIとの生活を通して宮藤は「現代の怪談」とでも言うようなドラマに仕上げた。
矢継ぎ早に展開される最新のアイテムを使ったエピソードとミステリーとしての意外な展開など、45分飽きることなく楽しめるのだが、終始居心地が悪いのは動画配信、AI、SNSといった最新のテクノロジーに対する宮藤の不信感が強く現れていたからだろう。スポンサー関連の制約が多い民放放送ではないNHKだったため、筆が滑って「毒」が強く出過ぎたのかもしれないが、テレビを敵視する干された配信芸人という構図には逆にテレビの側の怯えのようなものが見えて、それがそのままAIに脅かされる人間という構造と重なってみえる。何よりしんどいのは、宮藤が一貫して描いてきた「笑い」というモチーフの見せ方だ。
本作は、ある種のブラックジョークだと思うのだが、「笑えない笑い」が暴力や恐怖に変っていく瞬間を切り取っていくことで、気まずい笑いに転換している。この手触りは2019年にヒットしたトッド・フィリップス監督の『ジョーカー』に近いものがある。
トッド・フィリップスは宮藤のように『ハング・オーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009年)等のコメディを基調とした映画を取り続けた監督だが、コメディ作家がシリアスに転換した時に、それまでにない怖い作品を作るということはあらゆるジャンルで見受けられることだ。そういう作品は、良くも悪くも作家にとって大きな転機となるのだが、おそらく宮藤は自分自身がコロナに感染したことで、思うことがたくさんあったのだろう。
東日本大震災で宮城県にある実家が被災した経験は、2010年代の宮藤の作風に大きな影響を与えた。そして、コロナに感染した際にはネットニュースやSNSで大きな反響を沸き起こした(残念ながらそれは必ずしも同情的な意見だけではなかった)が、『JOKE』本編で登場するシニカル発言が並ぶコメント欄には、その時の影響が強く現れていたようにも感じた。
おそらく、コロナに罹患した経験は、今後の作品に大きな影響を与えることとなるだろうと思うのだが、『JOKE』からみなぎっていた悪意は、作品の出来とは別のところで、今の宮藤が心配になるものだった。
木皿泉『これっきりサマー』
変わってしまった日常のリアルを切り取る優しい目線
木皿泉が脚本を担当した『これっきりサマー』はNHK大阪で放送された1話1分弱のショートショート。全5話の作品で、関東地区では10分弱の1本にまとめられてNHKの深夜枠で放送された。

主人公は、コロナウィルスの感染予防のために「夏の甲子園が中止」になったことで「かわいそう」と言われることに困惑して「ウザい」と思っている高校球児の藤井薫(岡田健史)と、夏フェスに行けなかった女子高生・水守香(南沙良)。
藤井は、かわいそうな高校生として過ごさないといけないこと(周囲からかわいそうと言われるたび)に「ウザい」と感じている。そんな藤井の姿(スマホを見て喋っている)を見てマスクをつけた香は「うざっ」と言う。
河川敷の階段に腰掛けた香はギターを弾いている。
薫が近づくと後ずさりして「ソーシャルディスタンス」と香は言う。
マスクをした高校生二人の会話は表情が読み取れないのだが気持ちは痛いほど伝わってくる。
香は携帯用扇風機を手に持ち「夏フェス行きてぇ。夏フェス行きてぇ」と叫ぶ。
友達も引っ越してしまい、香にはやることがない。
香「何だろうね? この何もかもうまくいかない感じ。大人の都合っていうの?」
薫「じゃなくて地球の都合じゃねぇの? 俺たちここに住まわせてもらってるわけだからさ。地球に合わせていくしかないんじゃないかな」
香「かっけえ、大人の都合とか言ってる私、すげえダサい」
二人は代わりに野外で一緒に音楽をかけてTシャツを作る「香フェス」を開く。
野球の面白さがわからない香は、薫もロックが理解できていないことを知っている。
香は、二人は異星人みたいなものだと言って映画『E.T.』を例えに出す。
香「でもさ、あんたは知ってるんだよね……。ロックが私の帰る場所だってこと……。そこへ帰そうとしてくれたんだよね」
そういった後、『E.T.』で有名な指と指をくっつけるポーズをとる香だが、その後、除菌と言って薫の指をウェットティッシュで消毒する。
フェスをやってくれた薫のために香はお返しとして架空の「甲子園の実況」をしてくれる。想像の中の甲子園でボールを投げる薫。
香の実況を聞いた薫は涙を流して「俺、本当は甲子園、行きたかった」と、はじめて本当の気持ちを口にする。
物語は全話合わせても10分弱という短い話。ドラマというよりは今の高校生の日常を切り取った他愛ない小品だ。
木皿泉作品の特徴である幽霊、ロボットといった異界からの目線は本作には登場しないのは、すでに現実の方が異界になってしまったからだろう。
マスクをつけた高校生の男女が河川敷で会話する風景はドラマとしては奇異なものに映る。だが、今やファンタジーなのは、マスクやソーシャルディスタンスをとりあえずなかったことにして(コロナがなかった平行世界の)物語を展開しているプライムタイムのドラマの方であり、本当にリアルは、こっちなのなのだ。
日常をファンタジックに描いてきた木皿泉がありのままの現実を描いているという状況自体が倒錯した現在に対するもっとも的確な批評となっていたと言えるだろう。
同時に感じるのは、コロナ禍の若者たちに向ける木皿泉の優しい視線だ。周囲の「かわいそう」という言葉に対して当初は困惑する薫。筆者は彼よりも大人だが、その気持はとてもよくわかる。会社がテレワークになり学校がリモート授業になり、大きなイベントが続々と中止となった2020年の夏は、大人から見れば、今までの日常が失われた窮屈な世界だが、高校生の二人にとっては、この瞬間こそが10代の夏休みなのだ。
二人が行う夏フェスや高校野球の真似事は失われた現実を埋めるためのごっこ遊びに過ぎない。しかし、このごっこ遊びが、二人にとってかけがえのない夏の想い出に変わっていく姿を短い時間で本作は描ききる。そしてそれを踏まえたうえで薫に「甲子園、行きたかった」と言わせるのだ。
寡作の木皿泉の新作ドラマだからこそ、放送当時はもっと長い尺で観たかったと思ったが、一気に駆け抜けるスピード感もまた、エアポケットとなった一瞬の夏を切り取っていたと言えるだろう。
坂元裕二の『Living』、宮藤官九郎の『JOKE』、木皿泉の『これっきりサマー』。それぞれ日本を代表する脚本家の作品だが、特殊な状況で作られた短い話であるため、異色作という評価が妥当で、数年後には忘れさられてしまうのかもしれない。
だが、制約の多い中、短期間で書かれた作品だからこそ、それぞれの作家が抱えるテーマがむき出しとなって現れていたと、筆者は感じる。
コロナ禍に坂元はファンタジーを選び、宮藤はブラックユーモア(笑えない笑い)を選び、木皿泉は(コロナ禍の高校生の)リアルを選んだ。
今までならリアルを描くのは坂元で、ファンタジーを描くのは木皿泉だった。宮藤の「笑い」も、今までは救いとして機能していたが、今回は悪意に満ちた暴力に反転していた。そこに作り手としての迷いや混乱を感じるが、これは逆に作家としての誠実さの現れだったように感じる。
前述した訓覇の論考には、「コロナのことを直接テーマに書いたら、放送できないことを書いてしまいそう」と、坂元が語ったことが書かれている。
訓覇はこの発言を「恐ろしい言葉」と書いているが、これは坂元に限らず、フィクションと向き合っている作り手全員がどこかでいることではないかと思う。おそらく本当に恐ろしいことは、まだドラマでは書かれていない。
[了]
この記事は2021年3月22日に公開しました。本稿の一部は、「リアルサウンド映画部」にて2020年6月9日公開の記事を初出としています。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。
成馬零一さん最新刊『テレビドラマクロニクル 1990→2020』が、2021年4月23日よりAmazon・全国書店等で発売中です。バブルの夢に浮かれた1990年からコロナ禍に揺れる2020年まで、480ページの大ボリュームで贈る、現代テレビドラマ批評の決定版です!
[カバーモデル:のん]

さらにPLANETSの公式オンラインストアでご購入いただくと、本記事の完全版を含む特別電子書籍『テレビドラマクロニクル 2020→2021:コロナ禍の進行はテレビドラマをどう変えたか』をプレゼント! 書籍本体に収録できなかった現在進行形のドラマ史の最新展開を、さらに9万字超のテキストで補完します。詳しくはこちらから。