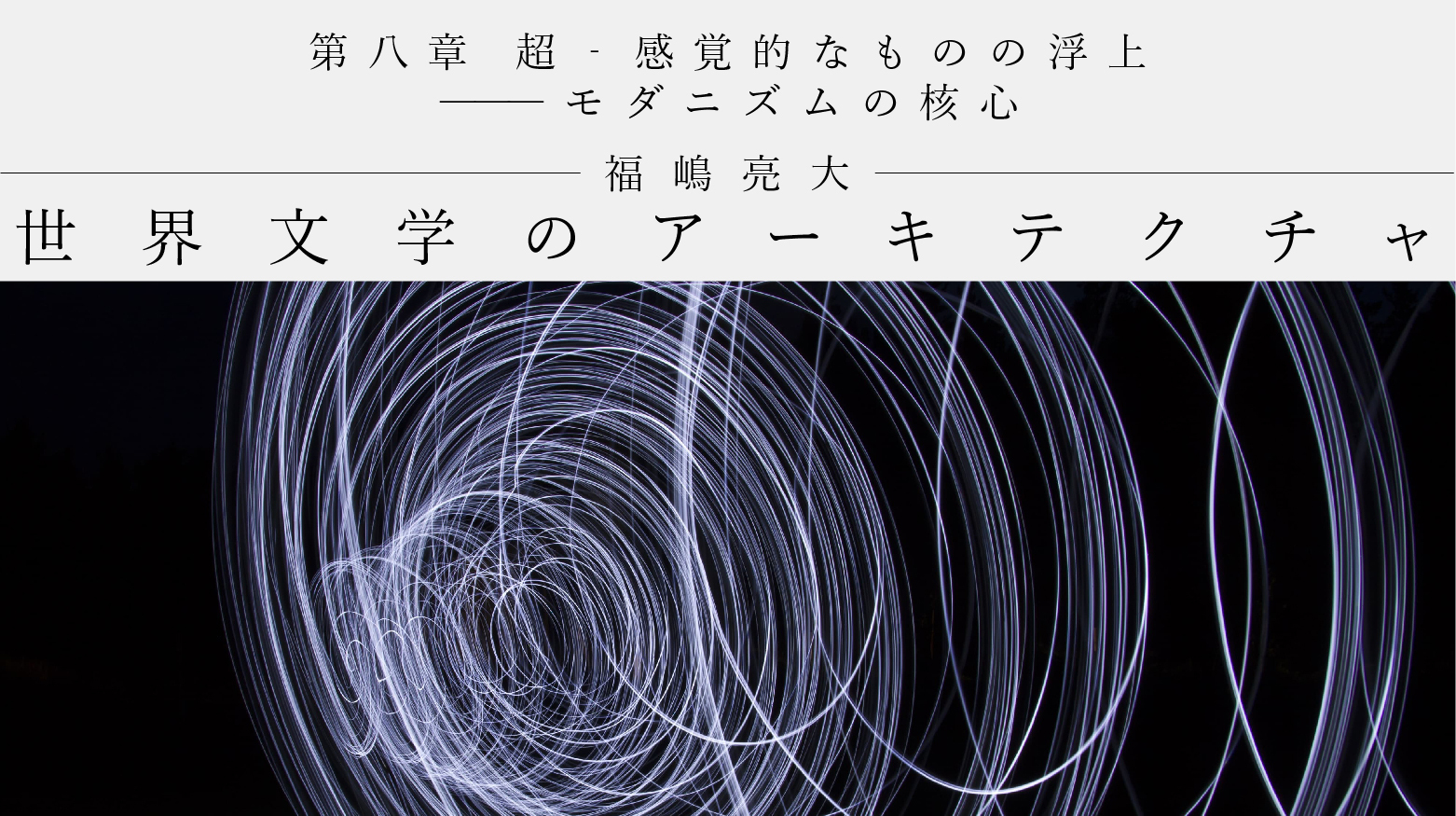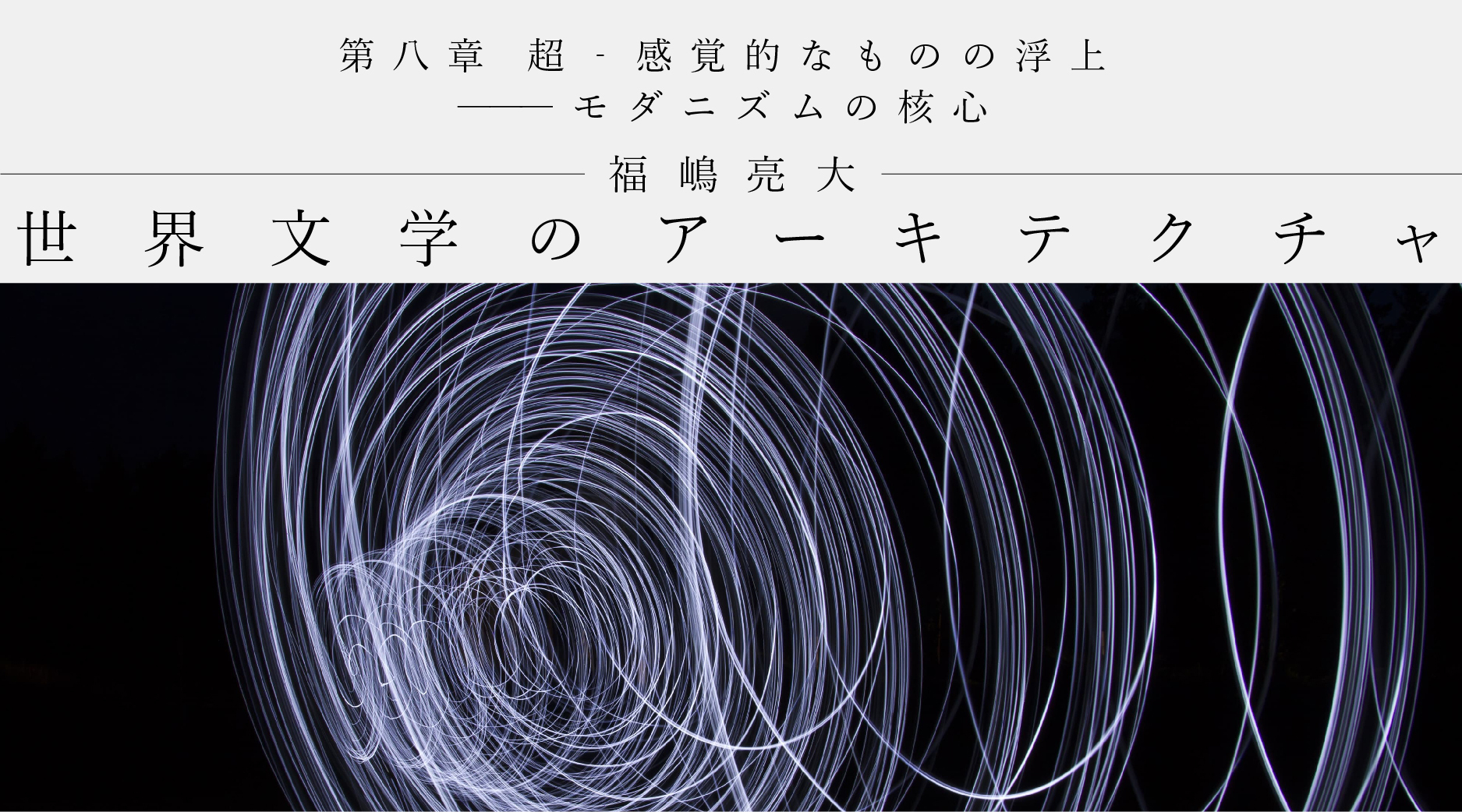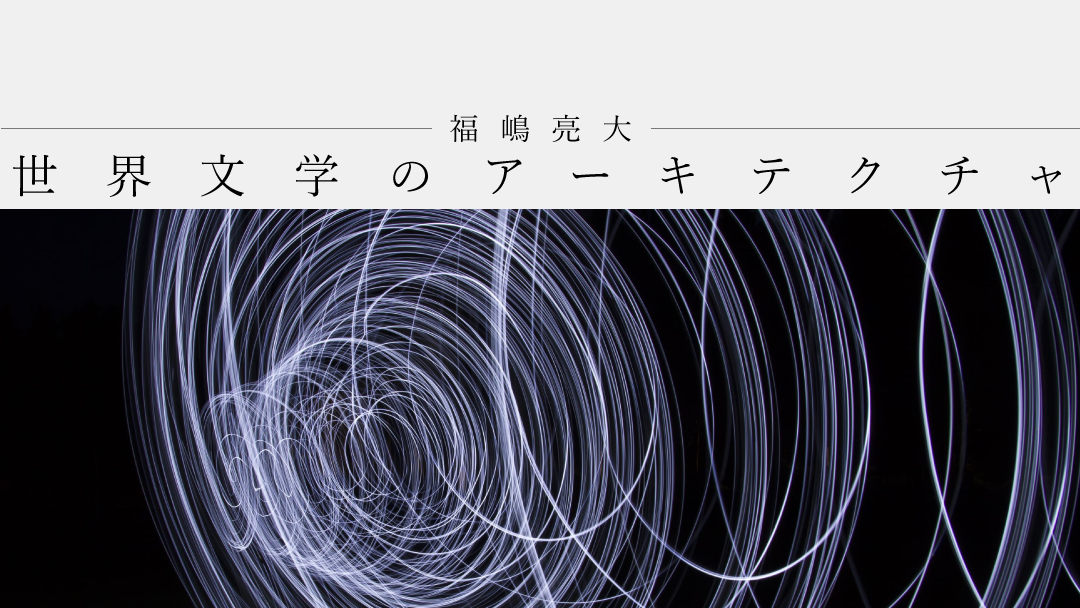
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、五感に根ざしたリアリズム
小説の台頭は、それ自体が世界認識のパラダイムの変化と結びついている。私はここまで、それを初期グローバリゼーションと植民地の拡大という政治的な観点から説明してきたが、そこに心理的な次元での変革が関わっていたことも見逃せない。例えば、英文学者のイアン・ワットは名高い研究書『小説の勃興』のなかで、デカルトやジョン・ロックの哲学と、それに続くデフォーやリチャードソン、フィールディングら一八世紀イギリス小説のリアリズムの共通性について論じている。「近代のリアリズムは〔…〕真実は個人の五感を通じ、個人によって発見され得るという立場から始まっている」[1]。
近代以前の世界認識においては、神やイデアこそが不動の「リアル」であり、人間の移ろいやすい五感で捕捉された情報は、あてにならない不規則な現象として処理された。しかし、近代の文化はこの前提そのものを転倒させ、むしろ個人の感覚器官において時々刻々と受容されるデータこそをリアルなものと見なし、それを思考の出発点とした。ワットによれば、それは「新奇〔ノヴェル〕なるものを前例のないほど高く評価」する文化への転回であり、小説は「個人的な経験に対する忠実さ」によって、この新興のリアリズムの文化における中心的な地位を獲得した。
小説のリアリズムは、個人の束の間の感覚的反応の記録を「真実」の基盤として受け取ることから始まる。ここで興味深いのは、この新たな真実性のモデルが、当時の先端的な記録装置とも関連性をもったことである。
例えば、ジョン・ロックの『人間悟性論』(一六九〇年)やニュートンの『光学』(一七〇四年)は、知覚のモデルを当時の写真装置であるカメラ・オブスキュラ(「暗い部屋」の意)に求めた。これは外部から入力された刺激をノイズも歪曲もなく正確に記録する「暗い部屋」のようなものとして、人間の知覚の仕組みを理解するものである。もし人間の知覚がカメラ・オブスキュラのように外界を複写できるならば、そこで得られる無数の表象は世界に近似するものとして捉えてよい――このような機械的な透明性への信頼は、小説で言えば、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』の文体にも当てはまる。クルーソーはまるで帳簿をつけるように、自身の冒険の顛末や島での孤独な生活を詳細に記録した。クルーソーの島はいわば、さまざまな情報を取り込み整然と並び変えるカメラ・オブスキュラ、より現代的なメタファーを使えば、彼の行動履歴をビッグデータとして逐一保存する高性能の記録装置であった。
このように、小説のリアリズムの背景には、それまでは浮かんでは消えるばかりであったエフェメラルな個人的経験のデータにこそ価値を認めようとする新しい信念がある。加えて、ここで重要なのは、この新興のリアリズムが読者との共犯関係を必要としたことである。
読者は作中のデータを、自らの経験上のデータと照合しながら、架空のキャラクターに想像上の肉づけをおこなう。小説を読むとは、キャラクターの心や思考を、断片的な情報を手がかりとしていわば「即興」で創作する作業である。作者は独立した架空の人生をそっくりそのまま再現するというよりは、むしろ読者側で起こる即興的創作をあてにして、前後のつじつまがあうようにキャラクターの記述を編集する。ごく限られた記述で説明されるだけのキャラクターの心は、あくまでフラット(=表面しかない)だが、読者はそこに心の深みを創作する。小説のリアリズムは、薄い感覚的な記述に虚構の深みを与える、読者の心の動きに依存している[2]。つまり、小説における心を創作するのは、作者である以上に、実は読者なのである。
2、ゲーテと感覚の生産力
そう考えると、五感に基づく近代のリアリズムは、実はカメラ・オブスキュラのモデルだけでは捉えきれないダイナミックな創造の動きも含むことが分かる。デフォーの大西洋の島は確かにカメラ・オブスキュラのように機能するが、それは次の段階では、豊かな感覚を自己生成する力を発揮し始めるだろう。人間の感覚は外界の複写であるばかりではなく、それ自体として動的な生産力を備えている。つまり、外界をデータとして引き写しながら、そのデータから新たな現実を創作する――それが感覚のもつ能力である。
この考え方を前進させたのが、自然研究者にして自然愛好者であったゲーテの理論である。ゲーテは一八一〇年の『色彩論』で、ニュートンの視覚理論を批判し、人間の身体感覚がいかに生産的な力をもつかを示そうとした。ジョナサン・クレーリーが指摘するように、ゲーテおよび彼に続くショーペンハウアーは、観察者の眼が閉じているときにも、身体は色彩のイメージを生起させることに注目した。つまり、身体はただ外的な刺激をカメラ・オブスキュラのように受容し所有するだけではなく、自ら工場のように外界の表象を創作する。ゲーテとショーペンハウアーは「感覚の場であると同時に生産者でもあるような主体」、つまり「表象の形成が行われる場としての主体の生理学的構造」を際立たせた[3]。
ロックの知覚の哲学において、カメラ・オブスキュラは外界を透明に秩序化し、データ化する精密な記録装置であった。しかし、一九世紀のゲーテやショーペンハウアーになると、生理学的な身体が表象を自ら生産するという、新たな思想が勃興する。そこでは、静的な「暗い部屋」は動的な表象の工場に取って代わられた。しかも、ゲーテにとって、このような感覚の生産力への信頼は、彼自身の学問的探究を基礎づけるものでもあった。彼はエッカーマンにこう明快に語った。
私の研究の方向は、いつもこの地上にあって私のすぐ周りに存在し、私が感覚でじかに知覚できるような対象にだけ向かっていた。だからまた私は、天文学には決して手をつけなかった。天文学では、感覚ではもはや役立たず、そればかりかこの分野ではきっと器具や計算や力学の世話にならなければだめだが、これは優にそれだけのための一生を必要とするもので、私の本分ではなかったからだよ。(一八二七年二月一日)
ゲーテは「器具や計算や力学」を使って超‐感覚的なものにアプローチしようとする天文学を忌避し、あくまで対象を感覚的に把握する色彩研究や植物学、動物学、地質学、気象学等にその関心を集中させた。ゲーテが感覚の機械化を拒絶し、感覚のもつダイナミズムを重視したことは、個人的な体験や感覚への彼の忠誠心が、それだけ深かったことを物語っている。つまり、彼は五感に根ざした近代リアリズムのプログラムを、より深化させたのである。
もとより、政治家でもあったゲーテが、科学的な器具一般をすべて排除したわけではない。植物学における顕微鏡、気象学における気圧計の使用については、彼はむしろ積極的であった。ただ、石原あえかが指摘するように、天体望遠鏡はゲーテの後期小説、特に『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』で否定的に扱われている。ヴィルヘルムはかつてガリレイの発見した木星と衛星を望遠鏡で観察するが「息苦しく」「不安」になり、「私たちの感覚を補助するこうした道具が、人間に決して倫理的に良い影響を及ぼさない」と述べる。高性能の光学レンズを通すことによって、身体の感覚と頭脳の判断力のつりあいがとれなくなり、ついに認識能力や倫理観が減衰してしまうという深い懸念が、後期ゲーテのテクストの端々に書き込まれていた[4]。
一般に『ヴィルヘルム・マイスター』は、文学における教養小説(ビルドゥングス・ロマン)、つまり精神的な成長のモデルを樹立した作品と目される。ゲーテはこのたえまない運動と成長、つまり「形成」(ビルドゥング)の力を、人間の精神だけではなく有機物にも認め、とりわけ植物の「変態」(メタモルフォーゼ)に強い関心を示した[5]。ゲーテの考えでは、自然も精神も内側から湧き上がる力によって段階的に自己形成するが、天体望遠鏡はこのしかるべき形成のプロセスを省略し、感覚の尺度を超えたものにいきなり人間の眼を出会わせてしまう。彼はこの感覚の「補助」の行き過ぎに、倫理的な危機を認めたのだ。
3、超‐感覚的な音楽機械――ディドロの『ラモーの甥』
このように、身体的な感覚の豊かさを信じる詩人科学者のゲーテは、高度な光学機械や計算に依存した学問には足を踏み入れなかった。しかし、それは裏返せば、ゲーテの生きた一九世紀の科学や文化の状況がすでに、人間の感覚の範囲を超過しつつあったことを示唆している。
興味深いことに、エッカーマンはゲーテの邸宅で、メンデルスゾーンの新作の弦楽四重奏を聴いた日のことを記録している(ゲーテの友人カール・フリードリヒ・ツェルターの門弟であったメンデルスゾーンは幼少期にすでにゲーテと面会しており、この弦楽四重奏を作曲したのは一八歳のときであった)。ゲーテはそれを「技術と楽器構造が極度に発達」した音楽、つまりテクニックとメカニックの高度な融合体として理解し、次のような感想を述べた。
彼らの仕事はもう音楽の域にとどまっていない。人間の感覚の水準をこえてしまって、こういうものにはもう自分の精神や心ではついていけないところがある。君はどうかね、私にはすべてが耳にひっかかって、まだそのままガンガンいっている。(一八二七年一月一二日)
晩年のゲーテの耳には、神童メンデルスゾーンの弦楽四重奏は、いわば人間の可聴領域の限界で響く未知の電子音のように感じられたのかもしれない。それは心地よいサロン的な音楽というよりも、耳もとでいつまでも執拗に鳴り響き続ける魔術的な音響に近かった。実際、ゲーテはこの曲の高速の部分を「永遠の渦と旋回」と評しながら、そこに自作の『ファウスト』の「ヴァルプルギスの夜」で描かれたブロッケン山の魔女のサバトを重ねあわせている。ゲーテの誇らしげな自評によれば、『ファウスト』は「とんでもない代物で、あらゆる日常の感覚を超越」(一八二五年一月一〇日)した文学作品であったが、若きメンデルスゾーンの音楽ないし音響は、まさにそれに匹敵するような異常な「渦と旋回」を室内に出現させたと彼には感じられた[6]。
ヴァルプルギスの夜の饗宴を思わせるほどに、日常的な感覚や認知能力を超えてしまった新しい音楽――このテーマは実は、すでにゲーテ以前にフランスのディドロによって先取りされていた。ディドロの生前には刊行されず、ほかならぬゲーテの翻訳・紹介によって有名になった対話体小説『ラモーの甥』に、この厄介な問題が織り込まれている。
音楽家ラモーの甥は心理的に屈折した複雑な人物であり、哲学者の「私」を相手に、音楽から人物談義まで気の向くままに議論を繰り広げるが、そのうちに楽器のパントマイムを即興的に披露し始める。つまり、彼は自意識の空転を、激しい身体的なパフォーマンスに転位させずにはいられないのだ。ただし、この楽器のミメーシス(模倣)は、やるせないほどに滑稽なパフォーマンスとして演じられる。
しかし読者とても、彼が色々な楽器をまねる格好を見ては、思わず吹き出さずにはいられなかっただろう。両頬をはちきれんばかりにふくらまし、しゃがれた陰気な音を出して、彼はホルンとファゴットをまねてみせた。オーボアをまねるためには爆発するような鼻にかかった音を出した。弦楽器をまねるには、信じられないほどの速さで自分の声をせきたてて、楽器にごく近い音まで出そうとした。
こうして、一人でオーケストラを即興的に演じ尽くそうとするラモーの甥は、正気を失って、口から泡を吹き、汗だくになって泣き笑いする。彼がヴァイオリン奏者を模倣すると「苦悶」や「苦痛」が際立ち、クラヴサンの演奏を汗だくで真似ると、その表情には「愛情と憤怒と快楽と苦痛」が浮かび上がる[7]。つまり、あらゆる感情および感覚が、彼の身体を押しつぶさんばかりに雪崩のような負荷をかけてくるのである。
ディドロはいわば、ラモーの甥を狂気じみた《音楽機械》として描き出した。彼はヴァイオリンからクラヴサン、さらにオペラ歌手の声まで、あらゆる楽器の音を合成できるシンセサイザーのように身体を機能させようとするが、それは音楽的な快楽ではなく、いわばミメーシスの苦行とでも呼ぶべき強烈な受難の相を示す。音楽家として傑出した才能をもち得なかった彼は、次から次へとひたすら楽器を模倣するばかりであり、しかもその滑稽なパフォーマンスには内在的な終わりや限度がない。人間に経験可能なすべての感覚を引き写そうとするラモーの甥は、近代のリアリズムのプログラムを自己崩壊する直前の臨界点で作動させたと言えるだろう。
こうして、『ラモーの甥』における音楽のシミュレーションは身体をひどく歪曲させ、消耗させ、不自然な苦痛を強いる。メンデルスゾーンの悪魔的な音響の渦がゲーテの耳を混乱させる前に、ディドロ的音楽機械はすでに、人間の感覚の限界をさらけ出すような極端な次元、つまり超‐感覚的な次元を垣間見せていた。あるいは、ゲーテが感覚の高度な補助装置(天体望遠鏡)が人間の知性を荒廃させると見なしたのに先立って、ディドロは感覚が近代の文化のなかでとめどなく膨張し、その自重でつぶれてしまう悲喜劇的状況を捉えていたと言ってもよい。
4、リアリズムの臨界点――メルヴィル再訪
いったんまとめよう。イアン・ワットはデフォーらの一八世紀イギリスの小説――イギリスが文化的独立性を獲得したとされる「オーガスタン時代」の文学――をモデルとして、近代小説のリアリズムが移ろいやすい五感に根ざすことを強調した。この根源的な不安定さは、デフォーの半世紀後のディドロにおいて、早くも狂気のテーマとして描き出された。この明敏な哲学者が見抜いたように、近代のリアリズムを根拠づける感覚的なものは、人間の心身に強い負荷をかけ、その収容能力を超過するような超‐感覚的なものへの横滑りを当初から内包していた。ゲーテはそれを学問においては抑圧し、『ファウスト』のような悪魔じみた文学においてむしろ解放したのである。
このように、近代のリアリズムはあくまで個人的な感覚に根ざしながらも、感覚の限界を超えたものをも示すという二重性を備えていた。感覚的なデータを収容する「暗い部屋」は、そこに入りきらない異常な何ものかの影を伴っていたのだ。ここで重要なのは、この超‐感覚的なものの領野が、ゲーテにおいては永遠の渦や旋回という「無限」の観念と結びついたことである。そこでは時間は線的には進まず、それ自体が迷宮化する。つまり、感覚の超越はときに時間の超越と関連づけられた。
この点で重要な範例となるのが、前章で論じたアメリカのメルヴィルである。ゲーテの『ファウスト』が魔女の集う神話的なブロッケン山で永遠の渦を演出したとすれば、メルヴィルの『白鯨』はそれをもっとフィジカルかつメタフィジカルな《海》に置き直した。実際、『白鯨』の海は「非情の無限空間」(93)であり、人間を惑わす幻で充満している。
世界がただ平面で、どこまで行っても終わりがないのならば、東へ東へ航海をつづけることはつねに新たな距離を創造することとなる。〔…〕しかし、夢に見る神秘を遠くはるかに追跡しつづければ、いや、いつも人間の魂の直前を遊弋するあの魔の色を帯びた幻を狂おしく追跡しつづければ、しかもそれをこの球形の天体の上に追いつづければ、我々はいずれ荒廃の迷宮に迷い込み、そしてやがて志半ばにして波荒き海に難破するほかはない。(52)
メルヴィルの多くの小説は、潔癖なまでに男性的である。特に『白鯨』は、女が不在であることに何の感傷も抱かないまま、無限の彼方にいる怪物を追跡し続ける男たちの小説であり、それが作品の「非情さ」をいっそう際立たせている。しかも、その追跡はやがて「荒廃の迷宮」へと船乗りたちを迷い込ませずにはいないのだ。
この「非情の無限空間」では、陸地を境界づける所有の観念は成立しない。海的実存は大地の取得者にはなれない。狂気じみた船長エイハブは、せいぜい船上でほんの小さな領土――自らの義足をつっこむ穴――を占めるだけである。しかし、彼は何も所有しない(dispossessed)からこそ、白鯨に取り憑かれる(possessed)。つまり、大地との結びつきの希薄さが、かえって海への没入を深めるのだ。白鯨ならぬ黒船とともに、日本に捕鯨船の寄港地を求めた実在の船長マシュー・ペリーに先駆けて、架空の船長エイハブの率いるピークオッド号ははるばる日本列島にも接近したが(111)、それは所有者のいない海の空間が、陸地の限界を超えた速度や広がりを海的実存に与えることを物語っている。 繰り返せば、カメラ・オブスキュラ(暗い部屋)は外界を表象として取り込む写真装置であり、それが近代リアリズムの原初的な理念型となった。カメラ・オブスキュラに映じた表象は、ジョージ・バークリーのような一八世紀の哲学者によって一種の「私有財産」のように語られたが[8]、それは感覚そのものが所有可能な対象と見なされたことを示唆する。
それに対して、ディドロの『ラモーの甥』に始まり、ゲーテの『ファウスト』やメルヴィルの『白鯨』に到る異常な作品群が示すのは、もはや感覚的なデータとしては所有も収容もできない怪物が浮上したことである。特に、メルヴィルにとって、鯨は学問的に適切な場所を割り当てられない不可解な存在であった。彼は「鯨学なる学問の不安定、かつ不透明な現状」を強調し、博物学も「組織的体系化」の限界に直面せざるを得ないと記す(32)。ミステリアスな鯨は意味のビッグバンを引き起こし、その全貌を捉えようとする学問的な企てをことごとく座礁させてしまう。
さらに、鯨は学問的に捉えがたいだけではなく、絵画的な表象にも試練を与える。メルヴィルは抜かりなく、鯨と絵画という興味深いテーマにもアプローチしていた。船出前のイシュメールはニューベドフォードで「潮噴き荘」という寂れた宿に泊まるが、その壁には「何ともどろりとしてぬらぬらとした粘液質を帯びた絵」がかかっていた。この絵がどうやら、三本のマストの真上に「長く、しなやかな、禍々しい黒い塊」(3)を描いた絵であることが理解されたとき、イシュメールはその塊が巨大な鯨ではないかと推測する。
この「見る人をしてその視線を釘付けにしてしまう体の未生の崇高さ」を感じさせる異常な絵は、イギリスの画家J・M・ターナー――海難事故を含めて海を執拗に主題化し、抽象画の先駆者となった――の作品を思わせる[9]。ターナーと同じく、メルヴィルもまた黒を基調とした禍々しい抽象性に強烈な引力を与えた。彼にとって、鯨は決して、その存在を一望できるような具象的なイメージを結ぶものではなく、そこからは感覚では捉えきれないものがたえず滲み出してくる。それをあえて絵画的に表象しようとすると、粘液質の黒い塊という抽象的なイメージが浮かんでくるのだ。
海という「非情の無限空間」を舞台に、きわめて具象的であるはずなのに、抽象的にしか描けない超‐感覚的な鯨について、異常な思考と表象を延々とめぐらせるメルヴィル――その異様な姿はひたすら楽器を模倣し続け、ついに身体の限界にまで到る無一物の音楽家ラモーの甥ともどこか重なってくる。アーシュラ・ル゠グウィンの有名なSFの題名を借りるならば、ディドロとメルヴィルはともに《所有せざる人々》(The Dispossessed)、つまり感覚を「部屋」のなかで正常に所有できない人間たちを描いた。身体という容器に収まりきらない超‐感覚的なものが、デフォー流の具象的なリアリズムを超えて、狂気じみた異常さを呼び覚ますことを、この両者は的確に把握していたように思われる。
しかも、メルヴィルはもう一歩進んで、内部の感覚と外部の現実のズレという問題にも足を踏み入れていた。この厄介な問題は、『白鯨』に続いて不確実性のテーマを前景化させた『ピェール』(一八五二年)や『ベニート・セレーノ』(一八五五年/邦題『漂流船』)において現れている。
例えば『ピェール』の主人公の容貌は、母と瓜二つであり、両者はお互いを姉弟と呼びあっている。その一方、ピェールの前に唐突に現れた女性イザベルは、ピェールの姉を自称し、ピェールも最初は当惑しつつもその宣言を受け入れる。彼らは感覚的な類似性を手がかりとして、あっという間にアイデンティティの核となる血縁関係を創作する。しかし、それを裏打ちするだけの客観的な根拠は、読者には与えられない。ピェールたちは自らの思い込みに基づいて常識離れした判断を下し、それをもとに物語は進行するので、読者は確からしさの地平が融解してしまったような不安を感じるだろう。
その一方、『ベニート・セレーノ』では詐欺やなりすましのテーマが、感覚と現実のズレを際立たせる。アザラシ漁に従事するアメリカ人のアメイサ・デラーノ船長は、漂流中の奴隷輸送船と出会ってその支援にあたるが、この謎めいた船のスペイン人船長のベニート・セレーノは不可解な言動を繰り返し、デラーノは不審の念を募らせる。しかし、ベニートの船は実は、反乱を起こした黒人奴隷バボウに支配されており、彼はその操り人形にすぎなかったことが終盤に明かされる。黒人奴隷に主人の役割を演じさせられてすっかり消耗したベニートの生命は、救出された後にあえなく尽きてしまう。
この狡知に富んだ小説では、メルヴィル得意の「反転」が仕掛けられている――デラーノがベニートに対して抱くあれやこれやの推測や不信感は、結果的に、読者をも欺く無自覚の罠になったのだから。かたや、メルヴィルの小説には珍しく女性が主導権を握る『ピェール』では、家族の再創造がほとんど批判的な内省なしに進められるため、読者はいつまでも不確実な印象のなかを漂流し続けなければならない[10]。メルヴィルが《海》という規格外の怪物から引き出したものは、有限の感覚は主体を欺くので、確かなリアリティの足場にはなり得ないという認識である。それは近代リアリズムの土台が、メルヴィルにおいてその根本から揺らいでいたことを示している。
5、海の隣人――モダニストの場所
このように、メルヴィルは海という「非情の無限空間」の化身である超‐感覚的な鯨に執拗にアプローチし、そこから多くの新たな問題を引き出した。彼の小説は人間の感覚能力を超えたものを文学が志向するようになった、その最も早く、最も力強い実例の一つである。メルヴィルを二〇世紀文学の父祖と呼んでも、言い過ぎには当たらないだろう。
そもそも、長く忘却されていたメルヴィルが復活を遂げたのは、第一次大戦後の一九二〇年代イギリスの文壇においてであった。D・H・ロレンスの『アメリカ古典文学研究』(一九二三年)やE・M・フォースターの『小説の諸相』(一九二七年)のような小説家による評論が、メルヴィルの再評価を力強く推進した。新しいスタイルや認識を模索していた小説家たちが自らの先祖を戦略的に構成したという点で、メルヴィル・リヴァイヴァルには小説による小説の発見という興味深い一面がある。
特に、ロレンスはメルヴィルについて「海棲動物特有の、不可解でうす気味悪い魅力があり、嫌悪感を抱かせるところもなくはない」と無遠慮に批評する一方、『白鯨』を「かつて書かれた最も偉大な海の本」と絶賛し、そこに「白さ」という「壮大な抽象」を求める強靭な意志を見出す。さらに、メルヴィルの『ピェール』については「善良になろうとすればするほど、人間はますます混乱して収拾がつかなくなり、正義の道を歩むことは破滅に至ること」を示した小説だという鋭い批評もなされる[11]。得体の知れない人間離れした作家が、世界の混乱をものともせずに未知の海へと突き進んでゆく――このように人間から人間ならざるものへの移行を強調しながら、ロレンスはメルヴィルを神話化した。
折しも、当時のアメリカは享楽的な「ジャズ・エイジ」を迎え、スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』(一九二五年)が、ニューヨーク郊外を舞台として華やかな都市生活の裏面にある孤独や荒廃を描いていた。それと同時期に、『グレート・ギャツビー』とは逆にニューヨークを退出して海に向かう『白鯨』とその作家が復活したことは、注目に値する。
ヨーロッパの場合、メルヴィルの再評価は第一次大戦というトラウマ的なショックと無関係ではなかっただろう。例えば、ロレンスの代表作『チャタレー夫人の恋人』(一九二八年)は「現代はまさに悲劇の時代である。だから時代に絶望だけはするまい。先の大戦であらゆるものが破壊され、あとには瓦礫だけが遺された」と書き出された後、大戦で下半身不随になり心に「無感覚の空白」を穿たれた作家クリフォード・チャタレーの姿を浮かび上がらせたが[12]、このショッキングな光景が『白鯨』と気脈を通じているのは明らかである。陸地での財産所有に関心をもたず、怪物に魅入られて「非情の無限空間」という迷宮に入り込む『白鯨』の独身者たち――とりわけ片足を失ったエイハブや戦争帰りの兵士のように傷だらけのクイークェグ――は、世界戦争の時代に蘇るのにふさわしい存在であったと言えるだろう。
ロレンスの小説も含めて、一九二〇年代のモダニズム文学の台頭において、第一次大戦のショックは不可欠であった。戦場となったヨーロッパでは、未来を担う世代がごっそり消失するという前代未聞の惨事に見舞われた[13]。しかし、思考し感覚する人間が世代ごと絶滅し、ヨーロッパが無感覚の「瓦礫」で覆われたとき、かえってモダニズムの運動は活気づいたのである。そのとき、禍々しい黒や白という抽象への意志を備えた『白鯨』は、まさにこの黙示録的な世界を予告していた恐るべき先祖として再創造された。
ただ、その一方で、二〇世紀のモダニストたちが《海》から一歩退いたことも見逃せない。モダニズム小説の金字塔であるジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』(一九二二年)およびヴァージニア・ウルフの『灯台へ』(一九二七年)が、ともに浜辺を舞台にすることは示唆的である。ジョイスの主人公スティーヴン・ディーダラスは、海辺の崖のそばにある塔で友人たちと暮らし、海からの呼びかけに耳を傾ける。かたや、ウルフの描くラムジー一家もまた、スコットランドの孤島の波打ち際のリズムを聴きながら、感覚をいっそう精妙化させてゆく。ジョイスもウルフも明らかに海に惹かれているが、彼らの関心は海そのものと同化することではなく、あくまで海を思考や感覚の増幅回路として利用することにあった。メルヴィルのような海的実存ではなく、むしろ《海の隣人》であろうとすること――それがモダニズムの選んだ場所だと言えるだろう。
西洋のリアリズム小説の歴史には、海との関係の再創造という巨大なテーマが横たわっている。リアリティの更新を求める文学的想像力は、一八世紀のデフォーとともに環大西洋世界に船出し、一九世紀のメルヴィルの海洋文学を経て、二〇世紀のモダニズムにおいて海と陸のあいだの浜辺の空間に帰還した。では、モダニストたちはこの見かけ上のスケールの縮小によって、何を企てたのだろうか。
6、感覚の雪崩――ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』
ヴァージニア・ウルフの一九一九年のマニフェスト的な評論「現代小説」には、その重要な手がかりが記されている。
ちょっとの間、普通の一日の普通の心を調べてみよ。心は無数の印象を――些細な、とてつもない、はかない、あるいは鋼の鋭さで刻まれた印象を受け取っている。あらゆる面からその印象はやってくる。それはおびただしい原子のたえまないシャワーだ。そして、それらの印象のシャワーが落下し、月曜日ないし火曜日の生活へと自らを形成するにつれて、そのアクセントは以前とは変わる。重要な瞬間は、ここではなくあちらに訪れるのだ。[14]
何でもない日常の心を仔細に観察すると、そこには無数の原子化した印象が離合集散するさまが浮かんでくる――こう述べるウルフは自らの小説においても、五感に根ざしたリアリズムのプログラムを、その臨界点に推し進めた。彼女の狙いは、不定形のまま揺らめき続ける無数の印象の戯れを、「カメラ(部屋)」の図像として所有するのではなく、言語を超えた「ヴィジョン」として図示することにあり、絵画で言えばセザンヌら後期印象派に対応するこの手法は、『灯台へ』(To the Lighthouse)で頂点に達した[15]。
このそっけなく無造作なタイトルからは、ウルフが印象の戯れを妨害することのない、控えめで重量感のない目標物を求めたことがうかがえる。ディドロの『ラモーの甥』はあらゆる感覚を一人の音楽機械的男性に集中させ、メルヴィルの『白鯨』は超‐感覚的な鯨を「象形文字」に仕立てあげたが、ウルフの『灯台へ』は逆にそのような不動の重心からたえず逸れようとする。ウルフ自身「人生は、光まばゆい暈輪である。意識のはじめから終りまでわれわれをとり巻く、半透明の包被である」と述べ、人生そのものというより、そこから滲み出す半透明の暈(halo)の伝達こそが小説の任務ではないかと問いかけていた[16]。
このような脱中心化の志向は、ウルフが女性の生活を描こうとしたこととも深く関わっている。そもそも、彼女の評論で述べられたように、女性の担ってきた家事や育児は「試験され検討されることが男性よりはるかに少ない」。ゆえに「女性の生活は名なしという性格を帯びていて、極端に不可解で謎めいている。この暗黒の国がはじめて小説の中で探検され始めている」[17]。『灯台へ』でも名を与えられない女性の生活と感情を、どこか一点に収束させる代わりに、むしろ限界ぎりぎりまで微分しようとする戦略が貫かれている。ウルフは「不可解で謎めいた暗黒の国」としての女性の生活やコミュニケーションを、昼の光のもとで鮮明にするのではなく、むしろ感覚が波のように流動する「夕暮れ」の時空のなかで、いっそう増幅させたのだ[18]。
このようなウルフ流のモダニズムは、一家の精神的な支柱であったラムジー夫人の描き方によく示されている。第一部では彼女がいかにその細やかな神経によって周囲を支えてきたかが述べられるが、第三部では彼女がもう亡くなったことが前提となっている。彼女の死そのものには焦点があわされず、故意に脱中心化された。しかし、そのことによってラムジー夫人は、この一家を取り巻く半透明の「暈」の領野に静かに移行した。彼女が純粋な印象の束になったとき、その存在の本質は生き残ったひとびと、さらには読者においてかえってより強く感じられる。
ウルフにとっては、人生の「暈」における不定形の揺らぎ、その弱くはかない運動にこそむしろ強度なリアリティがあり、『灯台へ』はそれを手法のレベルで展開した。特に、ラムジー一家を観察する画家リリー・ブリスコウの感受性は、ウルフの手法そのものの見事な絵解きになっていた。リリーは知人のバンクスの誠実さや几帳面さに触れたとたん、強烈なショックを感じる。
リリーがバンクス氏について密かに抱いてきた印象の山が少し傾いだかと思うと、彼女の思いのすべてが、大きな雪崩となって一気に溢れ出した。一方でそのような感覚に押し流されつつも、他方バンクス氏の存在のエッセンスが、そこに霧のように立ち昇るのを見届けた気もした。彼女は自らの知覚したものの激しさ、強さに圧倒されたが、それはバンクス氏のこの上なく厳格で善良な姿にほかならなかった。(四四頁/以下『灯台へ』の引用は御輿哲也訳[岩波文庫]に拠り、頁数を記す)
ウルフ的印象には明確な形が与えられず、たえず不可解なショックにさらされるために、いつでもインフレーションを起こす可能性がある。しかし、ウルフにとっては、この不意の「感覚の雪崩」こそが、存在のエッセンスを瞬間的に顕現させる。つまり、感覚や印象が人間のなかに留まらず、アンビエントな広がりをもったとき、それを地(ground)として存在の図(figure)が改めて描き直されるのだ。 ここで重要なのは、この感覚や印象のインフレーションが、語りによる評価や判断をも超えてしまうことである。リリーは次のような思考をめぐらせる。
人を評価し判断するとはどういうことなのか?あれこれ考え合わせて、好き嫌いを決めるためには、どうすればよいのだろう。それに「好きだ」「嫌いだ」っていうのは、結局どういう意味なのか?梨の木のそばに釘づけにされて立ちつくしていると、二人の男性のさまざまな印象が降りかかってきて、目まぐるしく変わる自分の思いを追いかけることが、速すぎる話し声を鉛筆で書きとめようとするのにも似た、無理な行為に思われてくる。(四五頁)
語りとはまずは人間や出来事を評価し、それを他者に伝達する行為である(第二章参照)。特に、イギリスの近代リアリズム小説では、捉えがたい対象についての多面的な評価を累積するプロセスが、しばしば物語の中核となってきた。
例えば、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』は、未知の孤島の環境に関するアセスメントの記録そのものであり、『モル・フランダース』はその評価の対象を新世界にまで拡大した。あるいは、ジェイン・オースティンの代表作『高慢と偏見』(一八一三年)では、結婚相手の資質や性格を見定めようとする女性たちの評価が、会話や手紙のような複数のチャンネルでなされる。当初の低い評価が、さまざまなパラメータの加味によって次第に逆転してゆく――このような評価の揺らぎの緻密な再現にこそ、オースティンのリアリズムの本領があった。
それに対して、『灯台へ』はむしろ、そのような環境の評価や個体の識別そのものを不可能にする領域に肉薄しようとする。「人間の心も体もすっかり闇に包みこまれてしまい、「これは彼だ」「こっちは彼女だ」と言える手がかりすらなくなった」(二四〇頁)。しかも、この個体の消えた世界では第一次大戦のショックをはじめ、見えない爆発がたえず起こっているのだ(実際、ラムジー家の音楽家アンドリューが戦争で即死したことが、断片的なヴィジョンとして示される)。画家リリーは「神経の受ける衝撃そのもの、何かになる以前のものそれ自体」(三七六頁)をつかみたいと願うが、それはどこにも中心がない夕暮れの世界に身をさらすことに等しかった。
7、神話の爆縮――ジョイスの『ユリシーズ』
無限の海を舞台にして、感覚と意味のビッグバンを引き起こしたメルヴィルがいわば《爆発》(explosion)の作家だとしたら、ごく限定された空間のなかで思考や印象のインフレーションを仕掛けたウルフは《爆縮》(implosion)の作家と評せるだろう。『灯台へ』はあくまで静謐であり動きは抑制されているが、その内部には無数の爆発が閉じ込められていた。この高度な技法には、モダニズムの一つの極点がある。
その一方、ウルフと同じ一八八二年にアイルランドに生まれたジェイムズ・ジョイスも、小説というジャンルに前代未聞の爆縮を仕掛けた。彼の長大な『ユリシーズ』は、一九〇四年六月一六日というダブリンの特定の一日を、ホメロスの神話『オデュッセイア』との緻密な照応関係に置いた。この操作によって『ユリシーズ』の登場人物たちはギリシア゠アイルランド人という二重人間になり[19]、ダブリンの一日は壮大なものと卑小なもの、頭脳的なものと猥褻なもの、古代的なものと現代的なものが複雑に絡みあう不可解な時空として再創造される。『ユリシーズ』に起こる出来事は平凡なものばかりだが、それらは急激に爆縮されて化学変化を起こした神話の断片でもある――この二重性がジョイス流のモダニズムを特徴づけていた。
もとより、それは恐ろしく手の込んだジョークでもある。ホメロスの神話を火種として、ダブリンの街に言語と意味の爆縮を引き起こす。と同時に、この高度に頭脳的な小説が、家族の危機という手垢のついたテーマを下地としていたことも見逃せない。前作の『若き芸術家の肖像』の末尾で「おのれの魂の鍛冶場において、わが民族の創造せざりし良心を鍛えに行く」ことを決意し、パリに赴いた意気軒高なスティーヴン・ディーダラス――この不思議な名はギリシア神話の工匠ダイダロスと響きあう――は、『ユリシーズ』では母の危篤の報を受けてダブリンに戻り、一家の零落に直面している。気高い使命を帯びたアーティストは、壊れかけの家族のもとへと半ば強制的に引き戻された。
その一方、もう一人の主人公レオポルド・ブルームはダブリンで広告取りの仕事をしているが、息子を生後間もなく亡くし、妻モリーとの関係は冷え、寝取られ夫(コキュ)の屈辱に甘んじている。そして、ホメロスの主人公オデュッセウスに擬せられるブルームが、その息子テレマコスに擬せられるディーダラスとやがて交錯したとき、ブルームはディーダラスに亡き息子のイメージを重ねあわせる。その意味で、『ユリシーズ』には父を探す息子の話にして、息子を探す父の物語というファミリー・ロマンスの一面があった。ただ、その根底には、『オデュッセイア』と違って家族の崩壊は避けられないという、ひどくやるせない気分がある。猥褻で下品な言葉が濫用されるほどに、そのやるせなさはいっそう募るだろう。
だとしても、『ユリシーズ』が男性視点のファミリー・ロマンスに決定的な亀裂を入れていることも見逃せない。『ユリシーズ』の最後の章がモリーの恐ろしく長大で切れ目のない独白にハイジャックされるとき、物語は再び爆縮されて不定形の言葉の塊へと化学変化を遂げる。モリーのめくるめく独白は、一六年前のブルームからの求婚の瞬間を思い出し、yesを何度も繰り返すところで終わる――この短い肯定の言葉は、ディーダラスとブルームという擬似親子関係によって組織された物語から脱け出すための、ミニマルな暗号でもあった。
批評家のエドマンド・ウィルソンがつとに鋭く述べたように「ジョイスには恐るべき活力があるが、動きはきわめて少ない。プルーストと同様に、彼は物語的というよりもむしろ交響楽的である」。その異常なまでの精密さは、読者の理解をはねつける。「ジョイスもまたプルーストと同じように、読者の注意力の限度というものをほとんど顧慮していない」。しかし、この感覚の限界を超えたところに、ジョイスは複雑な「声」を響かせようとする。
『ユリシーズ』のダブリンは声の都会だ。ブルームやモリー・ブルームの外観をはっきりと思いえがく人はいるだろうか?また、もしジョイスの写真を見たことがなかったら、われわれはスティーヴンの姿をはっきりと思いえがくことはできないのではないだろうか?ところが、彼らの永久に独白する声はわれわれの親しい友となり、末長くわれわれにつきまとう。[20]
ジョイスの記述は、人物の外見よりもむしろその「声」に重点がある。彼らの発する言葉は洒落や皮肉のめくるめく渦に巻き込まれ、ウルフ的な印象の原子のように浮遊し、意味の離合集散をいつまでも繰り返す。それは聴覚的に受容できる肉声というよりも、むしろ無数の文化的記憶を覚醒させる超‐感覚的な声にほかならない。『ユリシーズ』とは、神話の爆縮の生んだ空前絶後の「声」の化合物なのである。
8、時空のリプログラミング
シェイクスピアの『テンペスト』からメルヴィルの『白鯨』に到るまで、英米の文学は地中海から大西洋、さらには太平洋へという認識の地平の拡大を推し進めた。それに対して、ウルフやジョイスら二〇世紀のモダニスト、つまり《海の隣人》たちは、むしろ地中海的な内海や浜辺に回帰したように思える。私はそれを「爆発から爆縮へ」と要約した。彼らはこの見かけ上の収縮によって、メルヴィルの提示した問題群――超‐感覚的なものや不確実性の上昇――に、別の手法でアプローチしたのである。
そもそも、二〇世紀のモダニズムを突き動かしたのは、一九世紀の実証主義的なリアリズムへの強い不信である。特に、世界戦争という強烈なショックに直面したモダニストたちは、客観中立的な立場から現実を把握できるという実証主義の信念を捨てて、むしろ言語に強い負荷をかけながら、空間や時間を根本的にリプログラミングする戦略をとった。有限の時空で、言語や感覚の爆縮をたえまなく生じさせること――それは映画や絵画とは異なる、いわば小説の小説性を際立たせる企てでもあった。
しかも、モダニズムの運動は国際的な広がりをもった。フランスのプルーストが『失われた時を求めて』(一九一三~一九二七年)で、時間を記憶の場として再創造したのに続いて、一八九七年にアメリカ南部のミシシッピに生まれたモダニズム最後の巨匠ウィリアム・フォークナーは「時間の形而上学」(サルトル)を展開した。フォークナーの『響きと怒り』(一九二九年)では、語り手の一人クエンティン・コンプソンが祖父譲りの時計を破壊し、それとは異質の時間を生きることを鮮明にする[21]。フォークナーはこの計測不可能な時間性に、破局寸前の強烈な緊張感を与え続けた。彼の小説はもはや線的には進まず、過去と現在が語りのなかで複雑にもつれあっている。この大胆にリプログラミングされた非線形の時空は、もはや通常の感覚に根ざした旧来のリアリズムでは捉えきれない。
こうして、モダニズムは超‐感覚的な領野にどうアプローチするかという難題を抱え込んだが、マージョリー・パーロフも指摘するように、文学上のモダニズムにも大きく二つの系統があったことは見逃せない。一つはウルフやジョイス、プルースト、フォークナー、トーマス・マンら誰もが引用する作家たち、もう一つは一八八〇年生まれのオーストリアの作家ロベルト・ムージルをはじめ、カール・クラウスやヨーゼフ・ロートらオーストリア゠ハンガリー帝国を母体とするよりマイナーで、鋭利なアイロニーを武器とする作家たちである[22]。
私なりに言い換えれば、ウルフやジョイスが極度に圧縮された時空のなかで、感覚の微分と意味のインフレーションを仕掛けたのに対して、特にムージルはむしろ現実感覚そのものが実は穴だらけであるというアイロニカルな認識を、エッセイの形式によって結晶化した。ムージルのエッセイズムの極致である一九三〇年代の大作『特性のない男』では、《可能性感覚》というユニークな概念が提示されている。それは「ありうることを、実際にあることより、軽くとらない能力」あるいは「実際にあることを、あるかもしれないことより、重くはとらない能力」として定義される[23]。
ムージルの主人公は、特性(社会的な属性やラベル)をもたず、出来事を産出する内面性をもたない。ムージルは属性や内面をすっかり分解した後で、感覚を微細な原子の運動として観察し、それらをモンタージュする――そのとき、五感に根ざした現実感覚は、むしろ「ありうること」を重くとる可能性感覚に取って代わられるだろう。カメラ・オブスキュラ的なリアリズムのモデルは、感覚をモノとして所有し記録できるという幻想を与えた。それに対して、機械工学を学んだエンジニアでもあったムージルは、感覚を現実的なモノではなく、むしろ可能的な痕跡や働きとして組みあわせようとする。この所有不可能な穴だらけの《可能性感覚》から小説を立ち上げるムージルの力業は、現実感覚未満のもの、あるいは現実感覚以上のものを浮上させようとする試行にほかならない。
9、植民地主義とモダニズム――コンラッドの『闇の奥』
ジョイスやフォークナーら英米系の文学にせよ、ムージルやトーマス・マンら独墺系の文学にせよ、言語や物語に前例のないほど強い負荷をかけることによって、旧来のリアリズムの現実感覚や時空を大胆にリプログラミングする実験的な運動であったことに違いはない。これらの企てが文学を飛躍させたのは確かだが、ここで確認すべきなのは、彼らに先駆けるメルヴィルの二つの重要なテーマが、モダニズムにおいては退潮したことである。その一つが海であることはすでに述べたが、もう一つのポイントが労働である。
モダニズム小説の主人公たちは総じて、労働すること――物質の世界との相互作用にコミットすること――から遠ざかった。メルヴィルの『白鯨』が労働者の文学であり、鯨を資源として獲得し加工するプロセスを執拗に書き込んでいたのに対して、ジョイスの『ユリシーズ』が消費者の文学であったのは象徴的である。特に、主人公のブルームは消費を刺激する広告産業に属しながらも、消費への満たされなさを感じている[24]。メルヴィルは資本主義を支える物質的なインフラへと肉薄したが、ジョイスはその物質の層には手をつけず、むしろ消費行動を媒体として、文学のインフラである言語へと集中した。このような脱物質的な記号化が、やがてモダニズムの熱気を衰えさせたことも否定できないだろう[25]。
ゆえに、私は本章を閉じるにあたって、一九世紀のメルヴィルと二〇世紀のモダニズムの、さらには政治上の植民地主義と文学上のモダニズムの「あいだ」を橋渡しする作家に注目しておきたい。それは、一八五七年に帝政ロシアの支配下にあったポーランド領ウクライナのベルディチェフに生まれたジョセフ・コンラッドである。
革命運動にコミットしてロシア当局に逮捕された両親をもつコンラッドは、孤児になるものの数か国語をマスターし、内陸生まれにして海に強い憧れをもった。イギリス商船に乗り込んで、ロシア国籍を捨ててイギリスに帰化した後の彼が、船乗りを続けながら、母語でない英語で小説を書き始めたことは、彼の「二重人間」としてのあり方を際立たせた。ポーランド語と英語、船乗りと小説家――この二重の存在様式のあいだの不規則な「隔たり」が、コンラッドの文学を特徴づけている[26]。
この点で、コンラッドはまさにポスト・メルヴィルの小説家と呼ぶにふさわしい。ともに海に魅せられた両者は、その文体においても「言語の異質さ、その語法の異様なまでの不規則性」(サイード)を共有している。「言語を絶する経験」を描き出そうとするこの二人の作家は、怪物的なものを象るのに、文体に強力な負荷をかけることを恐れなかった[27]。そして、この怪物の捕捉というコンラッドの企みが、世紀の変わり目に書かれた『闇の奥』(一九〇二年)で一つの頂点に達したことは間違いない。
コンラッド自身の船乗り時代のコンゴでの体験――そこはベルギー国王レオポルド二世による非人道的な植民地政策が実施されており、シャーロック・ホームズの生みの親コナン・ドイルは一九〇九年にその悪行を『コンゴの犯罪』で告発することになる――を反映させた『闇の奥』は、ヨーロッパの植民地主義がいかにアフリカの人間と大地を荒廃させたかを語る。語り手の船乗りマーロウは、コンゴでの象牙取引によって莫大な利益をあげるもののやがて消息不明となった社員のクルツを捜索するために、コンゴ川を上流へと遡ってゆく。合理主義も進歩主義ももはや信じていない世紀末人のマーロウにとって、この不吉な予感に満ちた旅は「有史以前の地球」への遡行として感じられる。そして、船が奥地出張所という「闇の中心(Heart of Darkness)」に到ったとき、マーロウはアフリカ人を支配する異常な王となったクルツに対面するのだ。
植民地主義の尖兵であり、カリスマ的な人心掌握術をもつクルツは、ヨーロッパの達成の象徴でもある。「ヨーロッパ全体がクルツという人物を作り上げるのに貢献していた」(一二三頁/以下『闇の奥』の引用は黒原敏行訳[光文社古典新訳文庫]に拠り、頁数を記す)。しかし、このヨーロッパの生み出した気高い「作品」こそが、故郷になぜか背を向けて、未開の状態へと退行してしまう。ここには、メルヴィルにも似たショッキングな反転がある。しかも、クルツの反転の理由は明快さを欠いており、どこか気まぐれでふらついた印象も与えるだろう。後で述べるが、このあいまいさは『闇の奥』の核心に関わるものである[28]。
その一方で、『闇の奥』には明らかな植民地主義批判ととれる記述もある。出張所に近づいたマーロウは、白人に酷使されるアフリカの黒人労働者の惨状を目撃する。
その木の近くには、もう二つ、坐り込んで身体を鋭角に折り、両膝を胸に引きつけている人影があった。一人は顎を膝頭に載せ、虚ろな眼をしていて、見るに堪えないおぞましい姿だった。その兄弟分の幽霊は、疲労困憊して打ちのめされたように、額を膝頭につけている。そのほかありとあらゆるねじ曲がった姿勢の男たちがあちこちに散らばり、まるで大虐殺か疫病の流行を描いた絵のようだった。(四五頁)
身体を不自然に捻じ曲げられて姿勢を保てず、尊厳も活気も失ったコンゴの男たちの惨状は、ヨーロッパにとっての「象牙の国」で、おぞましい非人間的な暴力がふるわれたことを示唆している。前章まで説明してきたように、ヨーロッパのキリスト教徒による暴虐な植民地化は、ラス・カサスからデフォー、ディドロらに及ぶ知識人たちに、文明の野蛮化というトラウマ的な事件として受け取られてきた。コンラッドもここで同種の認識の系列に連なっている。
繰り返せば、二〇世紀のモダニズムの作家たちは、物質的なインフラよりも言語的なインフラの操作に傾斜した。それに対して、世紀の変わり目にいたコンラッドは、むしろヨーロッパの物質的繁栄を支える植民地の労働の実態に肉薄した。メルヴィルの多人種的な労働者が《海》という無限空間で活発に動くのに対して、コンラッドの黒人労働者は《川》の周囲の植民地空間の力によって心身を異様に歪曲され、活力を奪われてしまっている。メルヴィルが語り続ける鯨学には、そのバカバカしさゆえのユーモアがあったが、ポスト・メルヴィルの作家コンラッドの描くコンゴは、人間的なものの絶滅という逃げ場のない破局に直面していた。
10、植民地の怪物、脆弱なホムンクルス
ボルヘスが指摘するように、『闇の奥』は海よりは川ないし三角州(デルタ)を思い起こさせる小説であり[29]、その点でも《海の隣人》たる多くのモダニズム文学に先駆けている。『闇の奥』の冒頭では早くも、ロンドンのテムズ川の停滞した雰囲気が描写される。薄黒くて陰鬱な空気が重たくのしかかるなか、マーロウは河口に停泊する遊覧船ネリー号の一室で、四人の聴き手を相手に、クルツの物語を、まるで内緒話を打ち明けるようにして思わせぶりに語ってきかせる。
コンラッドはこのような非公式的でくだけた語り口を好んで採用してきた(例えば代表作の『ロード・ジム』では、やはりマーロウが登場し、法廷での公式的な語りから零れ落ちる問題こそ語ろうとする)。マーロウの語りは、たびたび眼前の聴き手を意識して中断をはさみつつ(それはダイビング中の束の間の息継ぎに似る)、クルツという不確定な怪物に、まさに川のようにうねうねと蛇行しながら近づこうとする。マーロウはトラウマ的な秘密を同乗者に伝えようとする証言者であり、しかもその恐ろしい悪夢を語り尽くせないことも弁えた経験豊富な語り手でもあった。
もとより、マーロウの不規則でときに突飛な語り口を、客観中立的な証言として扱うのは難しい。例えば、出張所の惨状を語り始める前に、彼は「まるで地球がすさまじい速度で宇宙の中を飛ぶ音が、不意に聴こえ始めたかのようだった」(四三頁)と告げる。このいかにも大袈裟な、いわば《ダーク・コスモロジー》とでも呼べるような表現は、『闇の奥』にたびたび現れる。後にナイジェリア人作家チヌア・アチェベは、アフリカ人を非人間として定型化し「否定の場」に押し込めた人種差別主義者としてコンラッドを糾弾したが、このような厳しい批判の生じる一因は、社会性や歴史性をしばしばあっさり省略して、宇宙に飛躍してしまう彼の無防備な記述にある。
だとしても、『闇の奥』のダーク・コスモロジーは、マーロウが地上の感覚では捉えられないものに接触したことを示してもいる。実際、川を遡るうちに、マーロウたち船員の視界は極端に狭まってゆく。「世界のほかの部分は、俺たちの眼と耳にとってはどこにも存在していない。どこにもだ。それは消えてしまった。なくなってしまった。囁きも影も残さず、搔き消されてしまったのだ」(一〇〇頁)。クルツのいる荒野では、感覚はもはや機能せず、世界そのものが消失したような宇宙論的錯覚が生じる。この「世界の終わり」を思わせる黙示録的光景が、後に『地獄の黙示録』のコッポラ監督をも強烈にインスパイアしたことはよく知られている。
こうして、マーロウはひどく制限された感覚を手がかりとして、クルツという「闇の中心」の怪物に近づくが、それは一向に明快な像へと「翻訳」されない。イアン・ワットがその優れたコンラッド論で指摘したように「コンラッドの方法は、知覚を因果的ないし概念的な用語に翻訳することの困難を反映している」[30]。多くの感覚を遮断され、しかもそれを概念に変えることもままならないマーロウは、クルツの「声」だけを特別に強く感じ取る。
クルツは語った。声! 声! 声は最後の最後まで深く響いた。体力が尽きたあとも生き残り、雄弁の華麗なひだの中に心の不毛な闇を潜ませた。(一六八頁)
その後、すでに容体の悪化していたクルツは「二度、囁くような、ほとんど息だけの声」で「怖ろしい!怖ろしい!(The horror!The horror!)」(一七一頁)という言葉を残して、世界から消失する。ただ、マーロウはその死の瞬間から目を背け、ただ「クルツの旦那――死んだよ」という黒人召使のふてぶてしい報告を聞いて、遅れて死を理解するだけである。
メルヴィルの鯨は、学問・芸術・経済等の多角的なアングルから観察される巨大な獣であり、そこにはフィジカルな実在性が与えられていた。逆に、もともと「声」だけの空虚な幽霊的存在であり、最後は息だけになってフェード・アウトするクルツは、ほとんどマーロウの語りのなかでのみ存在している。植民地主義の優秀な尖兵としてコンゴに入り、やがて狂気じみた「変身」を遂げたクルツが、ヨーロッパの理想そのものの破局を体現するのは確かである[31]。しかし、この恐ろしい怪物は、証言者の語りに一方的に創作されるだけの脆弱なホムンクルスでもあった。クルツはヨーロッパ文明の明暗を凝縮した怪物であるにもかかわらず、その実体はひどくはかないものとして語られる。
現に、帰国したマーロウは、クルツを立派な人物と信じる婚約者に「彼が最期に口にした言葉は――あなたのお名前でした」(一九一頁)と嘘をついて、彼女のはかない幻想を守ろうとする。この過去の改竄をどう捉えるかをめぐって、多くの研究者が議論を交わしてきた。ただ、まず驚くべきなのは、超‐感覚的な受容能力をもち、闇の世界を誰よりも鋭く感じ取った強烈なアンチ・ヒーローであるクルツの人生が、語り手によってあっけなく印象操作されてしまったことではないか。マーロウは確かにクルツという存在の一部を闇の奥から救出し、聞き手に伝達した一方、彼が最期の力で振り絞ったメッセージを歪曲することも厭わなかった。
繰り返せば、二〇世紀のモダニズムは超‐感覚的な次元へとアクセスした。ウルフは無数の原子的な印象を、ジョイスは駄洒落に突き動かされた言語を、ムージルは可能性感覚を、それ自体独立したアンビエントな生き物のように操作してみせた。それは逆に言えば、もはやいかなる事実も確定的でなく、ミクロのレベルでの《爆縮》にたえずさらされざるを得ないということでもある。超‐感覚的な息となった植民地の怪物クルツの遺言を、語り手が修正する『闇の奥』は、この二〇世紀文学の危うさを見事に先取りしていた。われわれはこの改竄の容易さこそ「怖ろしい」と言うべきではないだろうか。
[1]イアン・ワット『イギリス小説の勃興』(橋本宏他訳、鳳書房、一九九八年)七頁。
[2]以上は、ニック・チェイター『心はこうして創られる』(講談社、二〇二二年)から示唆を得た。
[3]ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』(遠藤知巳訳、以文社、二〇〇五年)一一八、一二〇頁。
[4]石原あえか『科学する詩人ゲーテ』(慶應義塾大学出版会、二〇一〇年)一三四頁以下。
[5]「形態学序説」(前田富士男訳)『ゲーテ全集』(第一四巻、潮出版社、一九八〇年)四四頁。E・カッシーラー『十八世紀の思想』(原好男訳、思索社、一九七九年)が指摘するように、ゲーテはカントと違って「造られた自然」に満足せず、あくまで「生成する自然」を考察の対象とした(一四一頁)。それが「形成」や「変態」への彼の強い関心として現れている。
[6]音楽に強い関心を寄せたゲーテは、器楽曲よりも声楽曲を好み、『ファウスト』にも音楽劇との親和性を与えたが、それはあくまで潜在的な音楽性に留まった。『ファウスト』の音楽性を顕在化させたのは、その後のロマン派の作曲家たち――シューベルト、シューマン、ベルリオーズ、リスト、グノー等――である。詳しくは、ハンス・ヨアヒム・クロイツァー『ファウスト 神話と音楽』(石原あえか訳、慶應義塾大学出版会、二〇〇七年)参照。
[7]ディドロ『ラモーの甥』(本田喜代治+平岡昇訳、岩波文庫、一九四〇年)三九、四〇、一二一‐二頁。なお、ミシェル・フーコーはラモーの甥の錯乱的なパントマイムに「狂気の言葉なき偉大な紋章」を認める一方、それをサドの厳密にコントロールされた不動性の狂気と対比している。『フーコー文学講義』(柵瀬宏平訳、ちくま学芸文庫、二〇二一年)四五頁以下。
[8]クレーリー前掲書、六八頁。
[9]メルヴィルは海の災厄や事故を織り込んだターナーの絵を実見し、それを「潮噴き荘」のミステリアスな絵に生かしたと推測されている。詳しくは以下参照。Robert K. Wallace, “Bulkington J. M. Turner, and “The lee Shore””, in Christopher Sten ed., Savage Eye: Melville and the Visual Arts, The Kent State University Press, 1991.
[10]なお、この二つの作品の親類と呼べるのが、近年評価の高いメルヴィルの『バートルビー』である。ウォール街で法律事務所を営む「私」は、書記としてバートルビーを雇うが、バートルビーは決められた仕事をやる以外は、最小化された拒否のプログラム(「しない方がいいと思います」)を機械的に反復するばかりであり、雇い主はこの不可解な振る舞いに翻弄され続ける。ここには、主人が奴隷に支配されているという『ベニート・セレーノ』と同種のテーマがあるが、加えて、デッド・レター(配送不能の郵便物)になぞらえられるバートルビーの感覚が完璧に「デッド」であることに注意すべきだろう。石柱や死人を思わせるほどに無感覚のバートルビーは、リアリズムの成立する条件そのものを拒絶する不可解な空白地帯なのである。
[11]ローレンス『アメリカ古典文学研究』(大西直樹訳、講談社文芸文庫、一九九九年)二五〇、二七一、二九〇、三〇四頁。
[12]D・H・ロレンス『チャタレー夫人の恋人』(木村政則訳、光文社古典新訳文庫、二〇一四年)一五、一七頁。
[13]ジョージ・スタイナー『青ひげの城にて』(桂田重利訳、みすず書房、二〇〇〇年)。
[14]ヴァージニア・ウルフ「現代小説」(大沢実訳)『世界批評大系』(第五巻、筑摩書房、一九七四年)一九頁。ただ、訳は原文をもとに変更した。
[15]いわゆるブルームズベリー・グループに属したウルフは、後期印象派を評価した批評家ロジャー・フライと付き合いがあった。『灯台へ』の美学を、印象派と後期印象派の中間点において解釈した論文に、丹治愛「印象主義とフォーマリズム」『モダニズムの詩学』(みすず書房、一九九四年)所収がある。
[16]ウルフ前掲論文、一九頁。
[17]「女性と小説」『ヴァージニア・ウルフ著作集』(第七巻、朱牟田房子訳、みすず書房、一九八二年)一九九頁。
[18]『灯台へ』における夕暮れの特権性については、丹治前掲書、一四四頁。
[19]リチャード・エルマン『リフィー河畔のユリシーズ』(和田旦+加藤弘和訳、国文社、一九八五年)一九頁。
[20]エドマンド・ウィルソン『アクセルの城』(土岐恒二訳、ちくま学芸文庫、二〇〇〇年)二七一、二七九、二八三、二九一頁。
[21]サルトル「フォークナーにおける時間性」(渡辺明正訳)『シチュアシオンⅠ』(人文書院、一九六五年)所収。
[22]Marjorie Perloff, Edge of Irony, Modernism in the Shadow of the Habsburg Empire, The University of Chicago Press, 2016.
[23]古井由吉『ロベルト・ムージル』(岩波書店、二〇〇八年)一三八頁以下。
[24]フランコ・モレッティ『ドラキュラ・ホームズ・ジョイス』(植松みどり他訳、新評論、一九九二年)二三〇頁。
[25]モダニズムの衰退を鋭く捉えていたのが、アメリカのフィッツジェラルドである。彼は晩年の長編小説『夜はやさし』(一九三四年)で、南仏のリヴィエラ海岸を舞台として、精神科医ディック・ダイヴァーの崩壊のプロセスを描き出したが、面白いのは、ジョイスの『ユリシーズ』の影響を受けて自分でも小説を書こうとしている――しかし「肉体で感じられる世界」については何も知らない――自称社会主義者の旅客マキスコがそこで戯画化されていたことである。ダイヴァーらが戦場のガイドブックを片手に、第一次大戦時の塹壕の跡をめぐる場面も、モダニズムを加速させたヨーロッパの戦争がすでに回顧的対象となっていたことを物語る。
同世代のフォークナーが非妥協的な怒り(fury)を文体に転移させたのに対して、フィッツジェラルドはヨーロッパの前衛的・戦闘的なモダニズムの終焉を、まもなく有名なリゾート観光地となるリヴィエラの弱く優しい(tender)情調のなかに包み込んだ。一九三〇年代は、ヨーロッパの大戦からアメリカに帰還したヘミングウェイら「ロスト・ジェネレーション」――彼らは伝統を根こそぎにされた、いわば「白紙」の状態からアメリカ的現実を再発見したと評される――が国際的に評価された時代だが、この世代の中心人物であったフィッツジェラルドは逆にヨーロッパの浜辺で、文学的実験の熱量が静まってゆくさまを捉えたのである(なお、パリおよびリヴィエラ滞在中の衰弱したフィッツジェラルドの様子は、ヘミングウェイの『移動祝祭日』で追想されている)。
[26]J・H・ステイプ編『コンラッド文学案内』(社本雅信監訳、研究社、二〇一二年)第一章参照。
[27]サイード「『白鯨』を読むために」『故国喪失についての省察』(第二巻)六一‐二頁。
[28]丹治愛『神を殺した男』(講談社、一九九四年)はH・G・ウエルズの『タイムマシン』とコンラッドの『闇の奥』を並置し、その人類の「退行」のモチーフを、ダーウィン革命を経た世紀末イギリスの文化現象の一部に位置づける。ただ、私が注目したいのは、タイムマシンを開発して時間旅行するウエルズの明快な小説とは違って、『闇の奥』の「退行」がアンビエントであいまいな印象の伸縮のなかで生じることである。
[29]ボルヘス『記憶の図書館』四八頁。なお、riverrun(川走)の一語で始まるジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』(一九三九年)は、ダブリンのリフィー川を(その汚さを含めて)賑やかに称えるが、それは停滞したテムズ川に始まる『闇の奥』の祝祭的な《爆縮》としても解釈できるだろう。
[30]Ian Watt, Conrad in the Nineteenth Century, University of California Press, 1979, p.178. ワットはここで、「光の暈」を捉えようとするヴァージニア・ウルフ流のモダニズムを、コンラッドの印象主義と巧みに結びつけた。
[31]なお、「世界の終わり」に生きる空虚な人間クルツを後年図らずも反復したのが、アラビアのロレンスことT・E・ロレンスである。一八八八年生まれのロレンスはヨーロッパ列強の植民地獲得という《グレート・ゲーム》(ハンナ・アーレント)に没入し、ストイックな砂漠の民ベドウィンと共闘した後、自らの身体をマゾヒスティックに痛めつけ、最後は速度の快楽に憑かれてバイクで事故死した。この自己消滅を求める「空っぽの主体」の陥った罠については、宇野常寛『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版、二〇二二年)第二章が詳しい。植民地主義という大掛かりなゲームの突端で非ヨーロッパ人と交わりながら、自滅的な「変身」に雪崩れ込んでいった点で、クルツはロレンスに先駆けている。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年12月22日、12月26日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年2月1日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。