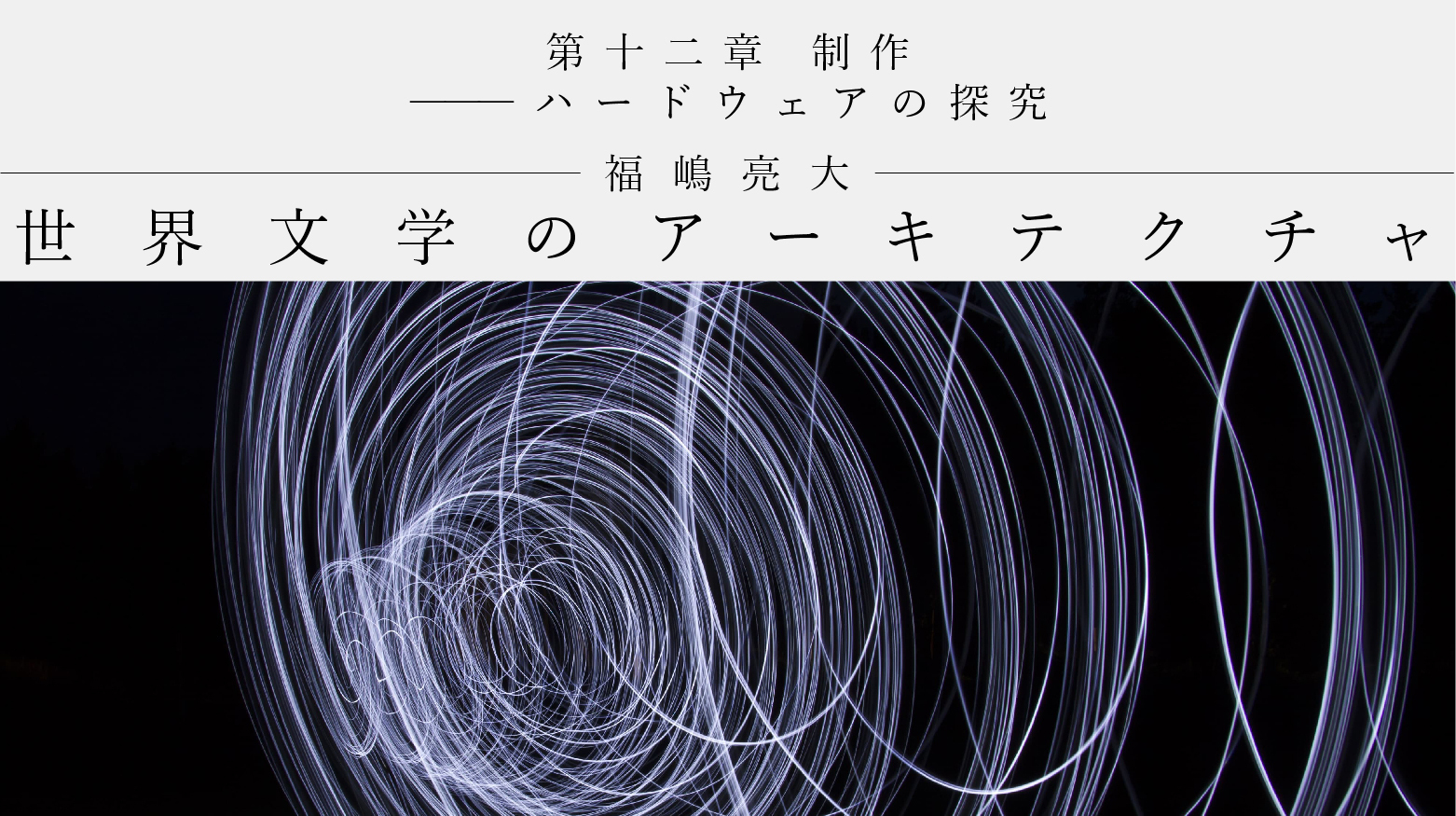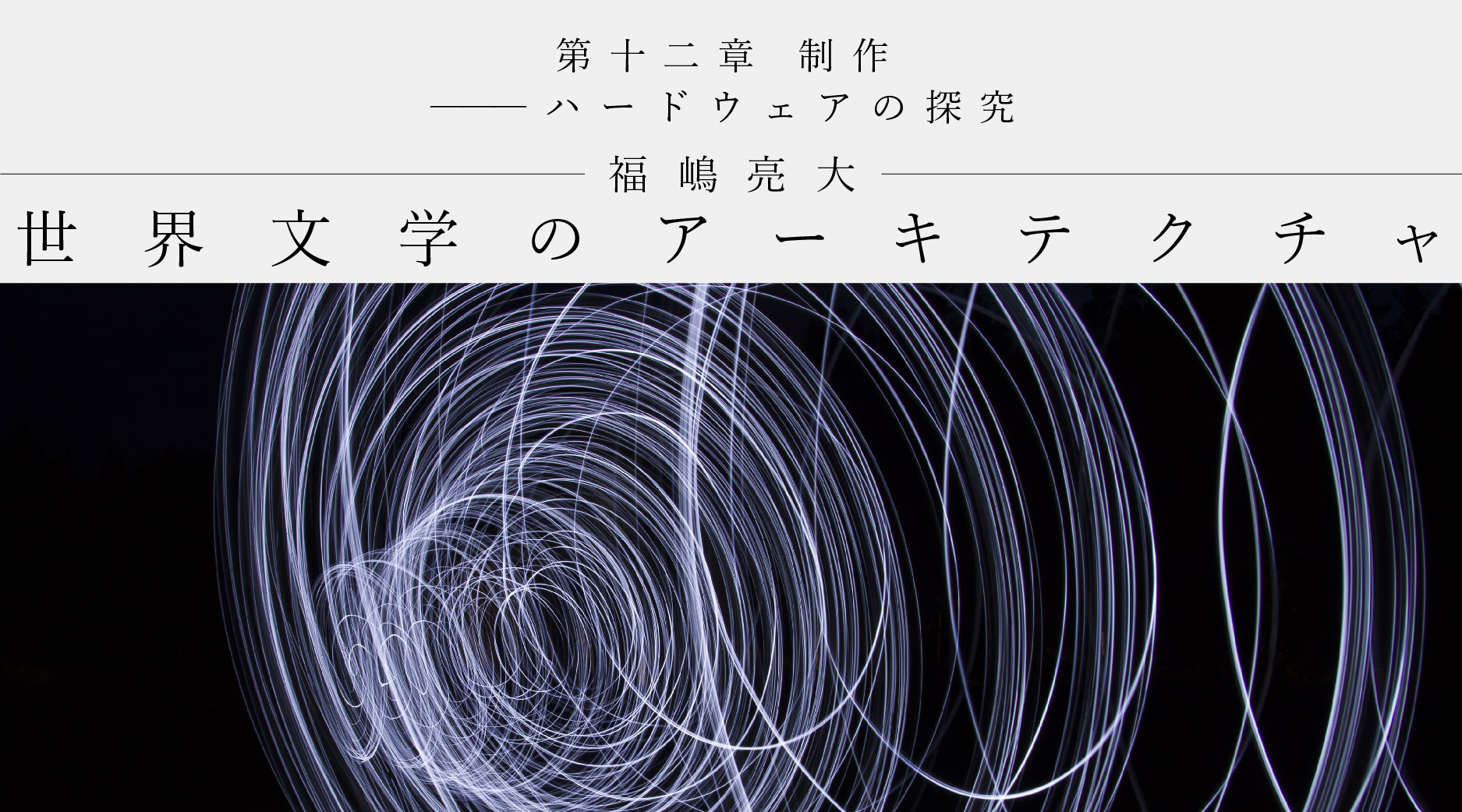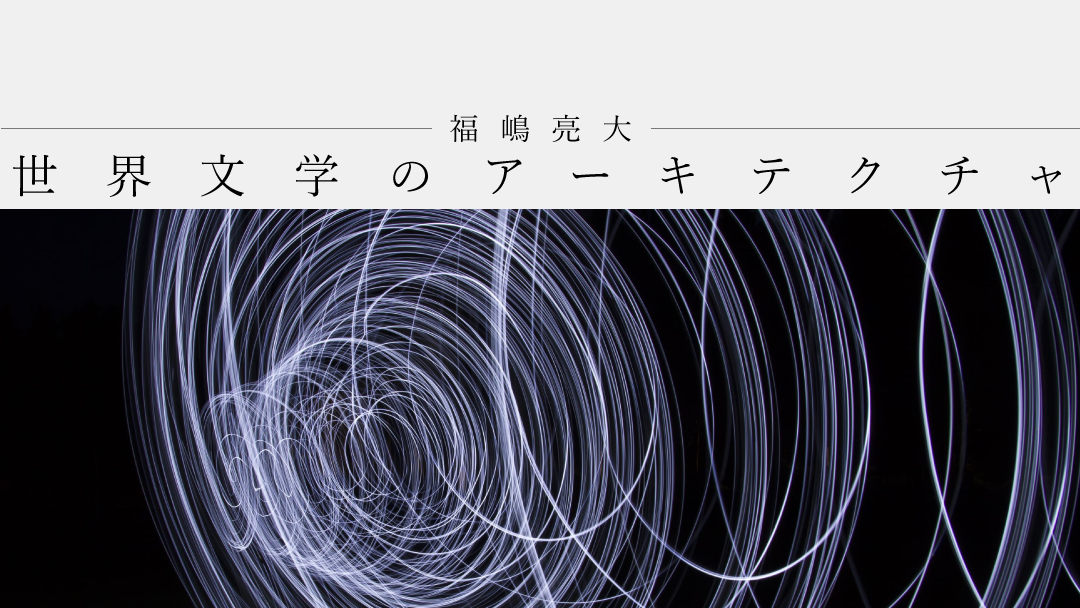
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、読むこと、見ること、作ること
私は前章で、近代小説の主体性の源泉が「読むこと」の累積にあることを示した。一八世紀の書簡体小説では、登場人物たちが大量の手紙を送受信し、相手のテクストにエントリーし続ける。手紙はいわば瞑想用のアプリケーションであり、心(主観)の状態をその揺らぎも含めて、きわめて詳細に書き込むことができた。さらに、近況を報告しながら、知識や感情を親しい相手とシェアする手紙は、速報性と共同性を兼ね備えた媒体でもある。書簡体小説はこのアプリケーションに支援されながら、主観とコミュニケーションを文学の中心に据えた。
この文学的発明によって「読むこと」はたんなる情報の獲得ではなく、相手の心を深く了解するための没入的なコミュニケーション行為となる。他者の書いたテクストへの反復的なエントリー(学習)によって、書簡体小説の主人公たちは、心的な一貫性をもつ主体として組織された。しかも、彼らのプライヴェートな送受信の記録は、なぜか読者に漏洩し、覗き見されることになる。ゆえに、書簡体小説には「読むこと」そのものがテクストの内から外に転移するという構図がある[1]。
書簡体小説を含め、近代小説は『ドン・キホーテ』から二〇世紀のハードボイルド探偵小説に到るまで、《読む主体》を核として進化してきた。日本文学でも、ダンテやセルバンテス、ポーを読み解く大江健三郎からレイモンド・チャンドラーを翻訳した村上春樹まで、このタイプの主体性が継承された。村上の『街とその不確かな壁』(二〇二三年)という曖昧模糊とした小説になると、読む行為が何のてらいもなくロマンティックに美化されている。
もともと、ヨーロッパ小説で「読むこと」の進化を促したのは、宗教的権威からの離脱の動きであった。メキシコの作家カルロス・フエンテスによれば、『ドン・キホーテ』の母胎となったのは「ローマ教会とその一義的な世界の読みとりに背を向けたヨーロッパ」である[2]。世界の解読の方法がもはや一つの絶対的な規範=信仰に従属しなくなったとき、セルバンテスは「読むこと」を小説の中心的問題に引き上げた。一義的な読みへの圧力が弱まれば、読むことはいつなんどきエラーや暴走を起こし、主体=読者を狂気や誤解に導くか分からなくなる――それが二一世紀のインターネット時代にも通じる『ドン・キホーテ』の教えにほかならない。セルバンテスにとって「読むこと」は、信仰とも理性とも異なるやり方で世界を学習する行為であり、それゆえに危険かつ魅惑的であった。
ただ、《読む主体》を抽出するだけでは、小説のアーキテクチャを解明するにはまだ不十分だろう。われわれは「読むこと」に回収されない問題を把握せねばならない。例えば、ゲーテは『若きウェルテルの悩み』で書簡体小説の時代の終わりを告げる一方、自然科学者として「見ること」の価値を高めた。彼にとって、科学は深遠な自然にアクセスし、感覚を豊富化する学問的アプリケーションであった。自然のもつ無尽蔵の生成力に沿いながら、文学者ゲーテは『イタリア紀行』では火山の測量のような調査を含めて、自らの視覚的体験を詳しく再現した(第九章参照)。
言うまでもなく、自然の旺盛な生成力は凶暴な破壊力にも転じる。少年時代にリスボン大地震の惨状を何度も聞かされたゲーテは、自然の過剰さに心を揺るがされた作家であった。リスボン大地震は哲学者や神学者による世界の説明を疑わしいものとし、前例のないスピードで恐怖を蔓延させた。彼の自伝『詩と真実』によれば「恐怖の悪霊がかくも迅速に、かつ強力に、その戦慄を地上にくり広げたことは、おそらくかつてないことであった」[3]。このメフィストフェレスのような悪魔じみた自然に対しては、もはやテクストを「読む」だけでは太刀打ちできない。ゲーテの《見る主体》は、科学というアプリケーションに支援されながら、生成=震動する自然にアクセスしようと試みた。
さらに、「読むこと」のちょうど対になる行為として、「作ること」や「書くこと」が挙げられるだろう。私はそれを「ハードウェアの制作」というテーマとして論じたい。まずは、このテーマが浮上してくる文学史的背景を整理しよう。
2、フィクションとノンフィクションを区別しない言説
ヘーゲルは『美学』の叙事詩を論じたくだりで、近代的な小説(Roman)の前提となるのは「すでに散文的世界として秩序づけられた現実」だと述べた。散文と化した現実は、神々や英雄の非凡な業績ではなく、取るに足らない日常的・偶然的な事柄によって構成される。ヘーゲルによれば、小説家の個性はこの平凡で、散発的で、とりとめのない現実の「捉え方」に現れるが、そこには二つの手法があった。一つは散文化した現実を承認し、それと和解すること、もう一つは平凡な現実をより美的・芸術的な現実に置き換えることである[4]。ごく大雑把に言えば、これは「日常系」と「非日常系」の差異に対応する。
近代小説はまず、前者に力点を置いたジャンルとして現れた。「散文」となった現実を承認した小説は、平凡な人間の心理および社会の状況を描くことに、エネルギーを注いだ。小説家が関心を向けるのは、前もって何が起こるか予測できない、社会という偶然の場である。イギリスの古典的な文学や批評(とりわけシェイクスピアやジョン・ドライデン)を吸収した明治日本の坪内逍遥が「小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ」(『小説神髄』)と的確に評したことも、ここで思い返しておこう。
特に書簡体小説は、まさに坪内逍遥の言う「人情」(心)と「世態風俗」(社会)を記述する散文的なリアリズムを前進させた。サミュエル・リチャードソンやモンテスキューに始まり、ルソーの『新エロイーズ』やゲーテの『若きウェルテルの悩み』に到るまで、手紙の記述はもっぱら身辺の出来事の報告に向けられ、超自然的な現象は排除された。加えて、書簡体小説は自らが本物の手紙の集まりであり、創作されたフィクションでないことを強調した。現に、ルソーやゲーテは創作家ではなく、ジュリやサン゠プルー、ウェルテルの書いた実在の手紙の編集者として自己演出したのである。
ゆえに、一八世紀の書簡体小説は自らを「フィクション」として規定しない――というより、当時はフィクションとノンフィクションの区別そのものが厳密ではなかった。テリー・イーグルトンによれば「リチャードソンの特異な文学生産様式は、言説を「フィクション」と「ノンフィクション」に厳密に分節化しない社会、つまり私たち自身の社会とは異なる社会において、はじめて可能な様式であった」[5]。現代のわれわれは、小説とはフィクションであると無造作に考える。しかし、一八世紀ヨーロッパの作家たちにとって、小説はむしろ「人情」や「世態」を高精度で再現するハイパーリアルな書式であり、その言説をわざわざ虚構の文書と宣言する意味はなかった。同じく、中国でも小説は歴史書、つまり事実の文書を擬態して書かれたのである(第四章参照)。
フィクションとノンフィクションをボーダーレスにつなぐ言説の形態は、書簡体小説に限ったものではない。リチャードソンより約三〇歳年上のデフォーは『ロビンソン・クルーソー』や『ペスト』を、出来事を忠実かつ詳細に記録したfactual(事実的)な文書として読者に差し出した。デフォーにとって、文書の価値は巧みな虚構の創作にではなく、いわばfactfulness(事実に満ちていること)にあった。二〇世紀のヴァージニア・ウルフが『ロビンソン・クルーソー』について「この本は個人の労作というよりはむしろ、民族が生み出した作者不明の所産の一つに似ている」と評したように[6]、作家デフォーはクルーソーの島を覆う無数の「事実」の影に隠れている。一八世紀の作家は、ノヴェルという新しい高精細の記録装置によって、散文化=日常化した世界と和解したのである。
3、散文化した現実に抗するゴシック小説
続いて(こちらが本章の主要なテーマだが)ヘーゲルの示したもう一つの手法、つまり現実を美学化・芸術化するという戦略について考察しよう。それは必然的に、取るに足らない現実を記述の中心としたリチャードソン的なリアリズムへの抵抗を含む。
この戦略を代表するのが、一七六〇年代から一八二〇年代にかけて盛期を迎えたイギリスのゴシック小説である。当時ベストセラーとなったホレス・ウォルポール『オトラントの城』を嚆矢として、ウィリアム・ゴドウィン『ケイレブ・ウィリアムズ』、アン・ラドクリフ『ユードルフォの城』、マシュー・ルイス『マンク(修道僧)』、C・R・マチューリン『放浪者メルモス』、ジェイムズ・ホッグ『悪の誘惑』、そしてゴドウィンの娘メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』等がそこに含まれる。女性のラドクリフやシェリー、アイルランドの牧師マチューリン、もとはスコットランドの羊飼いであったホッグが、その経歴において周縁的な存在であったことも見逃せない。
ゴシック小説はリチャードソン流のセンティメント(情緒)の表現を引き継ぎつつ、その主人公に神経過敏な感受性を与えた。このような異常感覚は社会生活には役立たないが、超自然的な「恐怖」の受信装置にはうってつけである。ゴシック小説は、人間を耐えがたいほどの極限状態に置いたとき、その心はどうなるかを実験する場となった。そこでは小説のリアリズムの基本的なルールが食い破られ、超自然的な要素が物語の中枢を占めるようになる。興味深いことに、ラドクリフやルイスは散文や小説ではなく、むしろ詩や演劇に強い関心を寄せたが、これもゴシック小説が小説を踏み越えようとする小説、つまりノヴェルの領域を拡張する試みであったことを裏づけている[7]。
ゴシック小説は、平凡な現実との和解を拒んだ。なかでも、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』(以下、同書からの引用は小林章夫訳[光文社古典新訳文庫]に拠り、頁数を記す)は、そのタイトルがはっきり示すように自らを現代の神話に近づけようとした。しかも、ヴィクター・フランケンシュタインという科学者を主役とするこの神話は、怪物の制作という過剰な想像力に導かれた。散文的な現実と和解したはずの小説を、再び神話に差し戻したという点で、『フランケンシュタイン』は文学史上の「スキャンダル」とすら評せるだろう[8]。
ゴシックの時代錯誤的で感情過多な表現は、しばしば小説のリアリズムの側から反撃や嘲笑を受けた。ゴシック小説をパロディにしたジェーン・オースティンの一八一七年の小説『ノーサンガー・アビー』は、その筆頭である。だとしても、『ノーサンガー・アビー』の出た翌年に、シェリーが匿名で刊行した『フランケンシュタイン』が画期的な作品であったことも、疑う余地はない。ゲーテが同時期の『イタリア紀行』で自然を「見ること」に集中したとすれば、『フランケンシュタイン』は怪物を「作ること」によって、散文的な現実を超越しようと企てた。
4、オルタナティヴな人間――シェリーの『フランケンシュタイン』
ルソーと同じくジュネーヴに生まれたヴィクター・フランケンシュタインは、錬金術に惹かれ、解剖学や生理学を学んだ後、独房で研究に没頭し、ついに死体の部位を集めて人間を創造するが、この被造物のあまりのおぞましさに戦慄し、自らの息子と呼ぶべき怪物を遺棄してしまう。哀れな捨て子は自分で自分を教育し、リテラシーや感情を身に着けるが、その醜さゆえに決して人間社会には受け入れられない。彼の怒りと屈辱が復讐心に変わったとき、怪物は生みの親フランケンシュタインとその家族を執拗に襲撃し始め、彼らを死に到らしめる。つまり『フランケンシュタイン』には、自らの制作したものに食いつぶされるというモチーフがある。
クリス・ボルディックが指摘したように、この小説の基礎にあるのは「親子関係」である[9]。ただし、この関係は性愛を介さない。女性を排除した生殖=制作――それが『フランケンシュタイン』という「二」の小説を支配している。逆説的なことに、科学者と怪物という擬似的な「親子」はお互いを憎悪しながら、お互いの境遇を理解できる世界でたった一組のカップルとなる。ちょうどドン・キホーテとサンチョ・パンサがお互いを模倣し始めるように、『フランケンシュタイン』でも「二」は次第に「一」へと横滑りする。制作者(親)と被造物(子)のカップルがともに憎悪と復讐心を燃やし、感情をもつれあわせながら、一つの奇妙なアマルガム(混合物)へと変身してゆく――そこに『フランケンシュタイン』の怪物性は凝縮されている。科学者フランケンシュタインが怪物の名と混同されがちなのも、決して偶然ではない。
メアリー・シェリーはこの小説で、女性をただ排除するためだけに登場させたようにすら思える。あまりの孤独に苦しむ怪物は、フランケンシュタインに自らの伴侶を作ってくれるように懇願するが、科学者は結局、作りかけの女性を破壊してしまう。怒りに駆られた怪物は、フランケンシュタインを追跡し、その婚約者を殺す。今度はフランケンシュタインが復讐心に駆られて、怪物を追跡し、ついに北極海にまで到る。つまり、この二人の孤独な男たちは周囲を顧みることなく、お互いの女性の伴侶を破壊し、お互いの行動を模倣する。
要するに、『フランケンシュタイン』は子が父を乗り越えるというオイディプス的な父殺しの神話ではなく、社会から切り離された父と息子が、鏡に映した双子に近づくミメーシス(模倣)の神話である。人類の誰とも共有できない呪いを背負ったフランケンシュタインは、スコットランドの極貧の僻地やアイルランドの殺伐とした海辺をさまようが、それはまるで孤独な怪物のさすらいの模倣のように思える。次に引用するフランケンシュタインの激しい心の動きは、怪物のものか科学者のものか。判別は難しいだろう。
まるでさまよえる亡霊のように、島を歩き回りました。愛するものすべてから切り離され、惨めな思いにうちひしがれる亡霊。昼になって太陽がさらに高く昇ると、草の上に横たわって、深い眠りに襲われました。昨夜はずっと起きていたので、神経が興奮して、目は寝不足と苦悩で血走っていましたが、それが眠ったことで元気になり、目覚めると再び、自分はやはり人間なのだと思えるようになって、過ぎたことを冷静に振り返って考え始めました。(三〇一頁)
フランケンシュタイン=怪物は、強烈なショックを受け、自らの惨めさやおぞましさのなかに沈み込む。しかし、その心は夜には極度の興奮状態に陥り、破壊的な行動へと彼らを導く。自分は人間であり、人間ではないという認識の揺れ動きは、まさに一九世紀的な「二日酔い」を思わせる。このような躁鬱的な心は、もはや社会には収容されない。現に、このカップルが最後に行き着くのは、社会も文化も尽き果てた北極海であった。「人類のなかでいちばん惨め」(三一八頁)なフランケンシュタイン=怪物の受け皿は、もはや最果ての極地以外にはないのだ。
周知のように、プロメテウスは神から火を盗んで、人類に分け与えた。この神話が示すのは「作ること」に「盗むこと」(=制作不可能なものの略取)が先立つということである。しかも、自然の一部をかすめとり、それを人類に贈与したプロメテウス自身は、火の恩恵にあずかることなく、神罰を下される。ただ、メアリー・シェリー版のプロメテウス神話では神は不在である。怪物と合一する現代のプロメテウス=フランケンシュタインが、地球上で最も冷えきった海で死ぬとき、そこには「神の死」というニーチェ的なテーマが浮かび上がってくる。
こうして、シェリーは「制作すること」を、神にも人間にも、文化にも社会にも関わらない未知の領域と結びつけた。フランケンシュタイン作のハードウェアは、既存のネットワークにはもはや回収されないからこそ、怪物と呼ばれる。この怪物の制作は、科学者フランケンシュタインに最上の喜びと最低の地獄を味わわせる。「長い間、自分の糧であり、喜びを与えてくれたあの夢が、今や地獄と化したのです」(一〇八頁)。この二日酔いの激しさのなかでは、ゲーテ的なビルドゥングスロマンのプログラムは頓挫せざるを得ない。
実際、怪物が悲劇的なのは、心=ソフトウェアは正常に人間化されているのに、身体=ハードウェアには一切の社会的な承認が与えられず、成長や成熟のチャンスを奪われているためである。シェリーは怪物の置かれた状況の「耐えがたさ」を、驚くほど念入りに描いている。怪物は森をさまよい歩くうちに、その正義感のせいでパリを追放されてドイツの田舎に逃れ住む良心的な一家を知り、その家の老人による本の朗読に耳をすませる。知識を得た怪物はプルタルコスの『対比列伝』、ジョン・ミルトンの『失楽園』、そしてゲーテの『ウェルテル』を偶然に読んで、それぞれに自らの境遇を重ねて感情移入する。これは「読むこと」に支援されたビルドゥングスロマンの予兆を感じさせる。
しかし、勇気を振り絞って老人の前に姿を現した怪物は、その家の住人たちにただちに排除されてしまう。迫害を受けてきた良心的な人間にまで迫害される怪物――彼はアウトサイダーにすらなれない究極のエイリアンであり、ヘーゲルの言う「散文」になった社会的現実では決して承認されることがない。そして、この孤独な怪物を制作したフランケンシュタインも、誰にも救済しようのない真っ黒な罪の意識に呑み込まれる。シェリーが描いたのは、ビルドゥング(教養/成長)と承認の可能性を完全に断たれた人間、いわばオルタナティヴな人間なのである。
5、ピュグマリオン神話――オウィディウスからルソーへ
ビルドゥングスロマンは、主体が自らのソフトウェア=知性を修正しアップデートする軌跡を描いた。逆に、社会や文化に帰属しないレディメイド(できあい)の死体で構成されたフランケンシュタイン的なハードウェア=身体は、社会的な承認のネットワークから切り離される。フランケンシュタインは自らの子ども=制作物から強い敵意を向けられ、怪物と同じく永遠のさすらいを宿命づけられる。
その一方、『フランケンシュタイン』とは逆に、制作物を愛の対象に変えるというモチーフもある。それを象徴するのがピュグマリオン神話である。紀元前一世紀のオウィディウスの『変身物語』によれば、女性たちの乱倫にうんざりしたキュプロス島のピュグマリオンは、理想の女性を雪白の象牙で彫刻し、自らの制作物にすっかり魅了される。彼がウェヌス(ヴィーナス)に「象牙の乙女」を与えてくれるように願った結果、彫像は生身の女性に変わり、ピュグマリオンと結ばれる(第一〇巻)。
ピュグマリオンの神話は、鏡面に映った自己像に恋して水死したナルキッソスの神話と比べたくなる。美術史家のヴィクトル・ストイキツァはこう要約している。
ピュグマリオンの話は錯乱の物語であるが、それは、神々が先例のない寛大さで遇した錯乱である。彼らは、自分自身の反射像に恋したナルキッソスを罰したのに対し、自分の作品に対する欲望に囚われたピュグマリオンの願いは叶えてやったのである。ナルキッソスとピュグマリオンのあいだの対照は、イメージへのエロティックな備給の二つの様態にかかわっている。[10]
ナルキッソス神話には手で触れられる作品がなく、逆にピュグマリオン神話は身体化された作品をもつ。あるいは前者は二次元的(絵画的)であり、後者は三次元的(彫刻的)である。この彫刻的な作品が、ピュグマリオンを錯乱させる。
ピュグマリオンには二面性がある。それは一面では、アンチ・ナルキッソスとしての意味がある。自己のはかない鏡像とともに滅びたナルキッソスと違って、ピュグマリオンは他者としての作品(ハードウェア)を制作し、その作品に神が心(ソフトウェア)を吹き込む。しかし、別の面から言えば、この「作品」を道具として所有し、自己の願望を充足させたという点では、ピュグマリオンは新しいナルキッソスとも言える。なぜなら、そこでは自己が他者と合一し、拡張しているのだから。
ここで興味深いのは、ルソーがこの神話をリメイクしたことである。若くして戯曲『ナルシス』を書いた彼は、著述家として円熟期にあった一七六二年に音楽つきの劇『ピュグマリオン』を発表し、国内外で人気を博した。ナルキッソス神話では描き切れない問題、つまり作品制作の問題が、ルソーによるピュグマリオン神話のリメイクに託されたように思える。
オウィディウス版のピュグマリオンは、固い象牙から柔らかい身体への変身(メタモルフォーズ)を神の恵みとして受け入れるが、ルソー版のピュグマリオンはむしろ神の意志に頼らないアトリエの「芸術家」として現れる。だが、すでに冒頭から彼の「想像力」は凍りつき、冷たい大理石に熱を吹き込むことができない。ルソーはピュグマリオンを、作品を生み出す力を失った芸術家、制作者失格の制作者として描いた。しかも、ピュグマリオンはちょうど躁鬱的なフランケンシュタインと同じく、自己の無力さにすっかり打ちひしがれながらも、ときに興奮に駆られて二日酔い的に憤慨する。からっぽの心が激しく脈動する――それはまさに零度の熱狂と呼ぶにふさわしい。
かたや、女性の彫像(ガラテと名づけられる)も、冷たい大理石にすぎないのに、最も肉感的な他者として現れる。ピュグマリオンとガラテのカップルはともに、空虚であることと過剰であること、0と1が重なりあった量子的な状態にある[11]。そのことがピュグマリオンを錯乱へと導く。
この立像からは驚くべき火の矢が放たれて、わたしの五感を燃え立たせ、わたしの魂をともづれにもとへ引き帰していくようだ!ああ!それなのに、身動きもしないで、つめたいままだ、これの魅力に燃え立つわたしの心が自分の体を離れてその体をあたために行こうとしているのに。錯乱のなかにあって、わたしは自分の外へ飛び立つことができるような気がする。〔…〕いつまでもガラテとは別の存在であって、ガラテになりたいといつも思っている、彼女を見つめ、愛して、愛される……それがいい……[12]
ピュグマリオンはガラテによって自己の「外」に連れ出される一方で、ガラテとは独立した自己として、ガラテを愛したいとも願う。彼の錯乱は、自己を消去されながら、なおかつ自己であろうとするというパラドックスに由来する。同じくガラテも、冷たい物質でありながら、ピュグマリオンを燃え立たせる存在者として現れる。自己(制作者)と他者(作品)が、存在のオンとオフをめまぐるしく切り替えながら、やがて一体化してゆく――ルソーにとって、この奇妙な絡みあいこそが「制作」の帰結であった。
6、制作の哲学――他者性のオン/オフ
制作者は、素材=ハードウェアとしての他者を象る。これは他者性の創設である。しかし、この被造物が制作者と合一するとき、他者性はむしろ打ち消される。制作者にとって、素材の他者性はときにオンになり、ときにオフになる。さらに、制作者自身も自らの制作物の魅力や恐怖に屈するとき、自己がオンの状態とオフの状態が重なりあう。『フランケンシュタイン』と「ピュグマリオン」が示すのは、まさにこの量子状態である。
ここで議論の補強のために、哲学的な観点も導入しておこう。「制作的態度」を現象学的に分析したハイデガーは、およそ次の二点を指摘している。
(α)制作的態度において、制作されるものはそれ自身に引き渡される。材料や素材がそれ自体として自立したものとして了解されるのは、作るという態度によってである。「材料や素材といった概念の起源はまさに、制作に定位した存在了解にあるのです」[13]。もう一歩進んで言えば、制作的態度こそが制作を必要としないもの、制作不可能なもの、つまり「自然」を浮上させる。
(β)制作者の狙いにおいては、制作物は「できあがれば自由に使用されるもの」として把握される。この態度において、制作物は「引き離して置かれるもの」ではなく「こちらへ招き立てられるもの」[14]、つまり手元で自由に扱える存在となる。ここには、技術の本質を自然の駆り立て=徴発(Gestell)と見なしたハイデガーの見解の反響が認められる。
ハイデガーによれば、制作者は素材=ハードウェアをそれ自身の権利において確立し、自立的なものとして了解する。つまり、自己とは異なる他者が創設される。その一方、制作物は完成したとたん、使用者の手元へと招き立てられる。つまり、隔たった他者ではなく、むしろ自己に近接的な他者として現れ直すのだ。他者を創設する一方、その他者と自己が限りなく近づいてゆくというパラドックスがここにはある。ルソーとシェリーはこの制作のパラドックスを的確に把握していたように思える。
ただ、一八世紀半ばの「ピュグマリオン」からおよそ半世紀後の『フランケンシュタイン』に到ったとき、制作のテーマがより厄介な問題を含むようになったことも見逃せない。フランケンシュタインと彼の制作物は、ピュグマリオンとその彫像が和解するのと違って、お互いを最大最強の敵と見なす。呪われたカップルとなった二人には、もはや相手を殲滅する選択肢しか残されていなかった。制作物が制作者を圧倒するような怪物として現れること――それがシェリーのつかんだ新たな問題なのである。
7、社会に先行する悪夢へのアクセス
イギリスのメアリー・シェリーとフランスのルソーはともに神話的な制作者(プロメテウス/ピュグマリオン)を参照しながら、散文的な現実に回収されない素材=ハードウェアの制作をテーマとしたが、『フランケンシュタイン』が示すように、その制作物は制作者自身を破局に追いやる怪物へと変身した。この制作物の怪物化という問題を探究するには、ヨーロッパだけでなくアメリカ大陸の文学も考慮に入れなければならない。
もとより、アメリカという国家そのものが、フランケンシュタインの怪物のような合成物である。アメリカの作家たちは総じて、自らの社会的現実が、稠密に組織されたヨーロッパとは異質だと考えていた。アメリカ的現実には穴があいていて、あちこちに飛躍や断絶がある。そのため、アメリカ文学は安定的な居住ではなく、踏破(メルヴィル、ジョン・ミューア)、探索(ヘンリー・ソロー、レイモンド・チャンドラー)、放浪(ナボコフ、ジャック・ケルアック)のような落ち着かない心情に由来する行為に導かれてきた。二〇世紀半ば以降は、これらのモチーフはSFに受け継がれる。特にロシア系移民のアイザック・アシモフの作品には、銀河帝国のファウンデーション(創設)からロボットまで、既存の社会や人間の限界を超え出る「制作」のテーマが息づいていた。
この安息を振り切ったアメリカ文学の系譜のなかで、一八〇四年生まれのナサニエル・ホーソーンは枢要な位置を占める。彼はE・A・ポーと並んで、ゴシック小説の陰鬱な想像力を駆使しながら、人工物の「制作」の問題に取り組んだ作家である。クリス・ボルディックが言うように、ホーソーンの一連の芸術家小説――「イーサン・ブランド」「美の芸術家」等――では「被造物は、きまって自律的な力を持つようになり、やがては自らを生み出した創造者を圧倒するに至るのである」[15]。ホーソーンには、制作者が制作物に食いつぶされるというモチーフがある。
ただ、これだけならば、ホーソーンの小説は、およそ半世紀前の『フランケンシュタイン』の亜流に留まるだろう。ホーソーンやポーの創意は「制作されたもの」に過去の悪夢的な重さを与えたことにある。ゴシック小説研究者のデイヴィッド・パンターによれば「ヨーロッパの過去の重圧は、美であると同時に恐怖を意味した。この過去の重圧によってヨーロッパは窒息死する危険にさらされていたのだ。ホーソーンやポーの全体にわたって存在しているのは、この窒息状態である」[16]。ホーソーンとポーの「制作」は、過去の呪縛のせいで「窒息」しかかっている社会や人間を浮かび上がらせる。そのため、彼らの小説はたいてい陰鬱で安らぎを与えない。
特に、マサチューセッツ州のセイラムを拠点としたホーソーンは、散文的な「ノヴェル」を希求しつつも、それ以前の古い文学形態である「ロマンス」をあえて戦略的に選び取った作家である。彼の企ては、散文的な現実との和解を拒み、社会に先行する悪夢にアクセスすることにあった。しかも、そのあらゆる安息を奪う悪夢を、制作された物質=ハードウェアに結びつけたところに、彼の真骨頂がある。
8、ホーソーンのハードウェア思考
ハードウェアの作家としてのホーソーン――彼の代表的なゴシック小説『七破風の屋敷』(一八五一年)では、セイラムのピンチョン家がかつて強奪した土地に建てた屋敷が舞台となる。この呪われた屋敷に老いた妹と住むクリフォードは、興奮して次のようにまくしたてる。
電気の力によって、物質界が、あっという瞬間に数千哩にわたって震動するひとつの偉大な神経となったということは、事実でしょうか――それとも、ただ私が夢に見ただけなんでしょうか?いや、むしろ、このまるい地球そのものが、巨大な頭、知性に満ちあふれた頭脳にほかなりません!それとも、それ自身が思想であり、思想以外のなにものでもなく、もはやけっしてわれわれが考えていたような物質などではないとでも申しましょうか?[17]
地球というハードウェアそのものが、世界規模の「頭脳」として立ち現れる――この錯乱的なヴィジョンにはアレクサンダー・フォン・フンボルトふうの「惑星意識」があるが(第九章参照)、フンボルトとは違って、ホーソーンはそれを最新のエレクトロニクスと関連づけた。そして、もし電気の力が地球を巨大な知性体にするのであれば、それ以前の物質も、実は思考能力をもつのではないか。現に『七破風の屋敷』では二百年前に制作されたハードウェア=屋敷が、過去の呪いの重みを背負って、その居住者たちの思考をハイジャックするのだ。
さらに、『大理石の牧神』(一八六〇年/以下、同書の引用は島田太郎他訳[国書刊行会]に拠り、頁数を記す)になると、ホーソーンのハードウェア思考はローマという都市に適用される。ニューイングランド生まれで模写を得意とする画家のヒルダ、同じくアメリカ人の彫刻家ケニヨン、謎めいた黒眼の画家ミリアムという三人の芸術家に加えて、古代の彫刻家プラクシテレスの「牧神像」にそっくりなイタリア人のドナテロ、この四人が主要な登場人物として現れ、それぞれの「制作的態度」によってローマおよび古代芸術を把握しようとする。
プラクシテレスの彫像は「固い大理石」(Ⅰ・一五頁)を素材としながら、牧神特有の軽やかで奔放な運動性を内包している。牧神とは、純真で気まぐれな踊る獣である。プラクシテレスはこの活気あふれる半人半獣を、冷たい不壊の大理石のなかに封じ込めた。ホーソーンの描く大理石は、クールな不滅性にホットな野性が宿るという、量子的な重ねあわせを実現する物質である。大理石がときに「おぞましさ」(Ⅰ・一一六頁)を感じさせるのも、この素材が二つの相反する属性をあわせもつからである。これらに、ルソーの「ピュグマリオン」と同質のモチーフを認めることは容易である。
ドナテロは、この牧神を先祖とする野生の血を受け継いだ自然児だとされる。ミリアムは純真なドナテロに「あなたは何世紀も遅れてこの世界に現れてきたのよ」(Ⅰ・四四頁)と告げる。この世紀を跳躍したかに見える神話的なドナテロの育った土地を、ケニヨンは次のように観察する。
人間の注意深い技術と労働とがかつては飾っていたものを、長い歳月の間にいつの間にか荒廃がおおい尽す。その甘美で印象的な有様には、いかにも絵画的な美しさがあった。そして人間の力がもはや及ばぬとなると、「時」と「自然」とが手に手を携えてやって来て、落ち着きのある古色豊かな完成をもたらすのである。(Ⅱ・一五頁)
ここで語られるのは、人工のハードウェアはその荒廃によって完成するという逆説である。ホーソーン的なハードウェアは、自然の作用を受け、人間のコントロールの限界を超えたとき、特異な「制作物」として立ち上がってくる。
さらに、ローマという「廃墟の本場」も、人知を超えたハードウェアとして現れる。ローマの「重苦しい記憶の堆積」は「過ぎ去った人類の生の過剰なまでに濃密な感じ」をたたえ、四人の芸術家たちは「ローマ人がその歴史を組上げてきた花崗岩の石材に比べれば、現在なるものは夢幻に近いという意識」を抱く(Ⅰ・一二頁)。つまり、大理石にせよ花崗岩にせよ、ホーソーンにとっては膨大な記憶を蓄えた物質であり、芸術家はこの素材から人体や都市を「制作」し、過去の歴史をよみがえらせる。『大理石の牧神』では徹底して、芸術家たちの「制作的態度」に基づいて、ローマが把握される。そのプロセスで、ハイデガーの言う「制作を必要としないもの」(自然)の奥深い作用が引き出される。
もとより、小説家である以上、ホーソーンの仕事は彫刻でも都市建設でもなく、あくまで「書くこと」にあった。しかし、その彼が「作ること」を小説に執拗に組み入れるとき、「書くこと」を超えたものへのアクセスが試みられたことも確かだろう。彼にとっては、世界を形作る素材=ハードウェアこそが、あらかじめ多くを記憶し思考している――この眩暈をもたらすような記憶=思考する物質に没入するとき、今を生きる人間のほうが夢幻に近づく。
9、ラテンアメリカ文学の量子的ハードウェア
ゴシック小説の盛期の最後尾に位置するメアリー・シェリーは、既存の文化的秩序には収容できないオルタナティヴな人間=怪物を創出した。同じくゴシック的な想像力に根ざしたホーソーンは、クールかつホットな大理石の牧神を象りながら、ローマという廃墟化した都市=ハードウェアを作中で制作した。制作のテーマに即するならば、ホーソーンは二〇世紀文学のパイオニアとしての地位を占めるだろう。
例えば、二〇世紀のラテンアメリカでは、グアテマラの作家アストゥリアスの『大統領閣下』を皮切りに、フアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』、カルロス・フエンテスの『アルテミオ・クルスの死』、ガブリエル・ガルシア・マルケスの『族長の秋』に到るまで、多くの独裁者小説が書かれてきた。ラテンアメリカ文学の発明は、芸術家に代わって、独裁者や権力者を制作者のポジションに据えたことにある。それによって、都市や国家というハードウェアの制作=創設が、小説の根幹的なテーマにまで格上げされた。これは、ホーソーンの『七破風の屋敷』や『大理石の牧神』の延長線上にある。
しかも、これらのハードウェアは総じてホーソーンのローマと同じく、自然の廃墟化の作用を強く受けている。例えば、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』(一九六七年)の舞台となったマコンドは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアラン夫妻によって制作=創設され、商業化が進んで繁栄するが、やがてバナナ会社に蹂躙され、最後には風とともに消滅する。マコンドは存在と不在、オンとオフが重ねあわされた腐食性の物質の総体、つまり《量子的ハードウェア》として把握できるだろう[18]。
さらに、多くの創設的な小説(foundational fiction)を生んだラテンアメリカ文学の「制作的態度」は、かえって「制作不可能」な自然条件を際立たせた。ガルシア・マルケスの語りには「気候的・気圧的オブセッション」があり、熱帯的な暑さや雨の描写が、多くの小説で繰り返される[19]。都市にフォーカスするとき、かえって不可視のアンビエントな気候のほうが、読者に強く知覚される――ゲシュタルト心理学で言う「地と図の反転」のような現象が、ガルシア・マルケスの小説を特徴づけている。「町が暑さに浮いていた」という類の記述は、堅固な都市=ハードウェアが次の瞬間、まるごと無に帰しかねないという印象を強めるだろう。
ルソーは『孤独な散歩者の夢想』で自己をランダムに変化する気象にたとえたが、ガルシア・マルケスの小説では、都市そのものが異常気象の産物であり、人間はそこを枯葉のようにはかなく浮遊する。もともと、ガルシア・マルケスはデフォーの『ペスト』を愛読していたが、デフォー譲りの「絶滅の形式」は彼の小説全般に及んでいる。マリオ・バルガス・ジョサが指摘するように「マコンドへの余所者の到来は、疫病か自然災害のように描かれている」[20]。ガルシア・マルケスは制作された図(figure)としてのマコンドを反転させて、制作不可能な地(ground)を浮き彫りにする。自己を消滅させるスイッチに常時指をかけている都市――それがマコンドと言えるのではないか。
さらに、ガルシア・マルケスの『族長の秋』(一九七五年)になると、国家というハードウェアは冒頭から腐敗しきっており、植民地時代に築かれた大統領府は牛たちの闊歩する廃墟と化している。その最奥には、ハゲタカについばまれる無名の「大統領」の死体が孤独に横たわっている。しかも、この残虐非道の独裁者はいわば何度でも死に直すために、死体のシミュラークルとして再生される。
ハゲタカにいいように食い荒らされた大統領が、おなじ執務室で、おなじ服装で、おなじ姿勢で、横たわっている発見したのは、それが二度めだったが、われわれの誰ひとりとして、一度めのことを記憶しているほど年を食ってはいなかった。[21]
死をやり直し続ける存在、死んでも死にきれない存在――それがガルシア・マルケスの描く孤独な独裁者=制作者の姿である。彼自身、バルガス・ジョサとの対話で「ラテンアメリカ史における神話的怪物とでも呼ぶべき独裁者こそ、権力の孤独を表現するのに最適な人物だと思います」と述べている[22]。神話的な時空にジャンプした独裁者は、確かに国家や都市を「制作」したのだろうが、そのことを本人も含めて、もはや誰も覚えていない。独裁者は、自ら制作したと思しき作品=ハードウェアの最果てで、亡霊的な死体となって明滅する。創設と絶滅、制作可能なものと制作不可能なものの重なりあった怪物的なハードウェアは、ガルシア・マルケスにとって、ラテンアメリカの政治に肉薄するための装置になったのである。
10、カフカの反建築的建築
こうして、一九世紀にシェリーやホーソーンの示したハードウェアの怪物性は、二〇世紀後半のラテンアメリカの独裁者小説によって、都市や国家のスケールにまで拡張された。ただ、われわれはこの両者の「あいだ」に、もう一人の重要な制作者がいたことを忘れてはならない。それはフランツ・カフカである[23]。
セルバンテス的な「読むこと」、ゲーテ的な「見ること」、シェリー的な「作ること」――これらは信仰とも理性とも異なるやり方で世界にエントリーするための手法であった。しかし、カフカの小説にはそもそもエントランスがない。哲学者のギュンター・アンダースはカフカ特有の「円環構造」を強調しつつ、次のように述べた。
カフカの場合には、人間は生涯こういう挫折の人生に定められ、それを逃れることができないために、人間はいわば牢獄に繋がれている。事実、カフカは繰り返して――彼の日記でも『審判』でも『あるアカデミーへの報告』でも――牢獄の比喩を使い、たびたび窒息の比喩を用いている。――もっとも、彼の言う牢獄は負の牢獄である。というのは、カフカは閉じ込められていると感じているのではなくて、閉め出されていると感じているからである。彼は脱出しようとするのではなく、――世界のなかへ――入ろうとしている。[24]
サルトルの実存主義的戯曲は「出口なし」の密室=牢獄を描いたが、それ以前のカフカの小説は、むしろ「入口なし」の状況を詳述した。しかも、この入口のない世界(負の牢獄)になぜか閉じ込められるという理不尽さが、カフカを特徴づけている。アンダースが言うように、負の牢獄の人間は「閉め出される」ことによって、特定の状況に「閉じ込められる」というパラドックスを強いられ、時間が「麻痺」してしまうのだ。
この不可解な反転を考えるのに、カフカ最晩年の傑作「巣穴」(一九二三年執筆/もとは無題で生前は未発表)は不可欠のテクストだろう。この驚異的なパズルのような小説には、カフカ的ハードウェアの実態が見事に描き出されていた。
その無名の(もぐらのような?)語り手は、自らが制作中の「巣穴」について倦むことなく語り続ける。自慢の巣穴にはさまざまな回路や広場があり、通路にはさまざまな機能が与えられる。ただ、この交通システムの発達した「巣穴建築」は、その多孔性ゆえに、かえって反建築的な迷宮のようにも感じられる。つまり、巣穴は建築であり、かつ建築を崩壊させる無数の穴や経路の集まりでもある。制作と解体が同時にプログラミングされ、ひたすら複雑になってゆく反建築的建築――そこでは建築の「変身」(メタモルフォーゼ)がたえず継続されている。
しかも、このもぐら的な語り手のポジションは、巣穴の内と外のボーダーラインにあった。巣穴の入口に入らず、しかもそのことに安らぎを感じるという、いかにもカフカ的なパラドックスが作中には書き込まれている。
どうしても巣穴のことが気にかかる。巣穴の入り口から素早く走り去っても、すぐに戻ってきてしまう。身を隠すのに都合のよい場所を探し出し、我が家の入り口の様子を――今度は外側から――昼となく夜となく、幾日も観察し続けることになる。馬鹿げたことだと言われるかもしれないが、そうすることが、言いようのない喜びと、またそれ以上の安らぎを与えてくれるのだ。[25]
語り手=制作者はときに巣穴の入口を監視する一方、ときに制作の途中経過を報告する。巣穴はまさに迷宮的な≪負の牢獄≫となり、語り手をそこから締め出し、かつ閉じ込める。そのうえ、巣穴の制作はいつまでも終わらない。語り手は巣穴の終わりなき模様替えに没頭し、ハードウェアをひたすら変身=変容させ続ける。ホーソーン的ハードウェアが過去の重たい呪いで人間を窒息させるとしたら、カフカ的ハードウェアはむしろスカスカの穴の集合体であり、いつまでも結論の出ないプロセスのなかに、存在者を引き入れるのである。
11、機械の怪物――カフカの「流刑地にて」
カフカの「制作」は、変容のプロセスと結びつけられる。例えば、『変身』(一九一五年)では虫という形態学的な乱数の発生が、部屋=ハードウェアの形状も含めて、家族をも「変身」させる。虫になったグレーゴルの介護を中心にして、家庭内の力関係も組み直される。そして、最も献身的なケアラーであった妹が、グレーゴルの世話を打ち切り、遺棄されたグレーゴルが「からっぽで平和な気持ちのなか」で一人静かに息絶えた後、幸せで朗らかな家族が再創造される。この変身=変容のプロセスを、特定の超越的な視点から制御することはできない。奇怪な介護小説と言うべき『変身』は、一連の不可解な変身のプロセスの報告書である。
この場合、『変身』がサラリーマン家庭を舞台とすることは、重要な意味をもつ。なぜなら、カフカの小説において、家族的な「近さ」は必ず破局を呼び込むからだ。例えば、『城』の測量士Kは、目で見える距離にある「城」にいつまでも入れずに、堂々巡りを続けるが、この近くて遠いというカフカ的なパラドックスは、実は一種の安全弁でもある。『城』の「負の牢獄」は確かにつらいが、それと『変身』のつらさは異質である。ボルヘスが言うように「カフカのもっとも議論の余地のない長所は、耐えがたい状況を創り出したことである。忘れ難い状況を刻みつけるのに、彼はわずか数行あれば足りる」。[26]『変身』の耐えがたさは、グレーゴルが家族のすぐそばにいて、完全に隔離できないことと切り離せない。
現に、「田舎医者」や「流刑地にて」「判決」のような短編小説では、家族や病人、機械と隣接していることが、状況の耐えがたさを増幅させる。なかでも「流刑地にて」(一九一四年執筆)の不気味な処刑機械は、人間のすぐ近くで作動し、おぞましい情景を出現させる。
名のない植民地を舞台とするこの小説では、処刑機械が囚人の身体にその罪を刻み込む。囚人は自らの判決を耳で教えられるのではなく、息絶える前に身体で知るのだ。この機械はギロチンのような合理的な処刑機械とは異なり、実に十二時間にわたって受刑者を長々と責め苛む。しかも、精巧さを売りにするわりに、予算不足のために部品は古びて粗悪であり、それが処刑をいっそう陰惨なものにする。このオンボロの機械を近くで観察するとき、正視に耐えない無惨な光景が現れる。
カフカより二〇歳ほど年長のマックス・ヴェーバーは、官僚制に基づく近代の合理性を「鉄の檻」のイメージで捉えた。それに対して、カフカはこの一見して堅固で合理的なシステムを《機械の怪物》に置き換える(プラハの労災保険局に勤務し、企業での事故防止の啓発運動に取り組んだカフカにとって、機械は事故の可能性と切り離せなかったことも、忘れてはならない)。このおかしな機械は機械のまねをして作動し、旅人には判読できない命令――「迷路のように幾重にも折り重なった無数の線」[27]――を受刑者に刻み続ける。ホーソーンの『緋文字』のヒロインであるヘスター・プリンに刻印されたAの文字は、重層的な意味を帯びた(adultery/angel/able……)。逆に、解読不可能なカフカ的文字は、受刑者の身体に苦痛をもたらすばかりだ。
不完全な機械が機械的に作動したとき、いかに不気味で恐ろしい状況が出現するか――それが「流刑地にて」の差し出した問いである。『フランケンシュタイン』のおよそ一世紀後、カフカはまさに怪物的な機械を制作した。フランケンシュタインが制作したのは、人間のように行動し思考するオルタナティヴな人間=怪物であり、しかもこの怪物が恐るべき反逆者となった。同じく、カフカにとっても、怪物化した旧式の機械こそが、前代未聞のやり方で受刑者の身体を作り変える。ともに「変身」の作家であるメアリー・シェリーとカフカが記録したのは、ハードウェアの制作のもたらす予期せぬトラブルとその耐えがたさである。
しかも、「流刑地にて」は必ずしも荒唐無稽なファンタジーではないだろう。自壊寸前の姿をさらけ出しながら、それでも機械的に動く《機械の怪物》――そう聞くと、われわれはただちに事故を起こした原子力発電所を思い出すのではないか。完全な崩壊をかろうじて免れた事故後の原発は、しかし本来の機能を失ったまま、人間には判読できない放射性物質という「文字」を延々と環境に刻みつけている。これはまさに、変身した機械のもたらす惨事である。
われわれはここで、原爆の炸裂と原発の事故のあいだの差異に注目すべきだろう。原爆を制作した科学者ロバート・オッペンハイマーは「アメリカのプロメテウス」にたとえられた。人間を一瞬で殲滅する核兵器は、合理的な機械の極限形態である。逆に、名もない辺境で作動するカフカ的機械は、物事に一瞬でケリをつけるどころか、だらだらと処罰を長引かせる。カフカの小説では、訴訟(プロセス)も刑罰も一向に終わらない。この間延びした麻痺的状態こそが、原発の事故の本質を先取りするものではなかったか。
カフカは合理的な機械に基づく近代社会が、その機械の突然の「変身」によって、きわめて厄介な状況に到ることを予告していた。壊れた原発――この怪物的な≪負の牢獄≫に、われわれは決して入れず、かといってそこから脱出もできない。それはいつまでもたどり着けない「城」であり、囚人を長々とさいなむ怪物的な機械でもある。幸か不幸か、二一世紀においても、カフカは依然として現代の作家であり続けている。
[1]一八世紀ヨーロッパでは、文通は共通の目的をもつ思想集団を結びつける公的な手段であり、「文芸共和国」の基礎となった。ジョン・ブルーア『スキャンダルと公共圏』(大橋里見訳、山川出版社、二〇〇六年)六二頁。逆に、書簡体小説の特性は、公開を求めない秘密の手紙こそをおおっぴらに公開するという冒瀆性にある。
[2]カルロス・フエンテス『セルバンテスまたは読みの批判』(牛島信明訳、水声社、一九八二年)二七頁。
[3]『ゲーテ全集9』(山崎章甫他訳、潮出版社、一九七九年)二七頁
[4]『ヘーゲル全集』(二〇巻c、竹内敏雄訳、岩波書店、一九九六年)二二八三頁。
[5]テリー・イーグルトン『クラリッサの凌辱』二九頁。
[6]「デフォー」『ヴァージニア・ウルフ著作集7』(朱牟田房子訳、みすず書房、一九七六年)八三頁。感覚の事実を大量に収集し、それらを《爆縮》してみせたウルフ自身のモダニズム小説もまた、フィクションとノンフィクションの区別を溶解させるものである(第八章参照)
[7]デイヴィッド・パンター『恐怖の文学』(石月正伸他訳、松柏社、二〇一六年)九八、一一〇頁。横山茂雄『異形のテクスト』(国書刊行会、一九九八年)三〇頁。
[8]クリス・ボルディック『フランケンシュタインの影の下に』(谷内田浩正他訳、国書刊行会、一九九六年)一五頁。近年でもゴシック的な想像力の評価は、スキャンダラスで転覆的な意味をもつ。作家ミシェル・ウエルベックや哲学者グレアム・ハーマンらによるH・P・ラヴクラフトの再評価は、その一例である。
[9]同上、二六頁。
[10]ヴィクトル・I・ストイキツァ『ピュグマリオン効果』(松原知生訳、ありな書房、二〇〇六年)一六頁。
[11]ポール・ド・マンが『読むことのアレゴリー』(土田知則訳、講談社学術文庫、二〇二二年)のルソー論で指摘するように、「ピュグマリオン」は「過剰と欠如の力学的なシステムとして劇的に構造化されている」(三二二頁)
[12]「ピグマリオン」(松本勤訳)『ルソー全集』(第十一巻、白水社、一九八〇年)一六三頁。なお、ピュグマリオン神話はルソーに限らず、近代文学においてたびたび再来した。理想の女性を創造し、それに翻弄されるE・T・A・ホフマンの「砂男」、ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』、谷崎潤一郎の『痴人の愛』はいずれもピュグマリオン神話の変種である。
[13]マルティン・ハイデガー『現象学の根本問題』(木田元監訳、作品社、二〇一〇年)一九一頁。
[14]同上、一八九頁。
[15]ボルディック前掲書、一〇四頁。
[16]パンター前掲書、三一五頁
[17]「七破風の屋敷」(大橋健三郎訳)『ホーソーン マーク・トウェイン』(筑摩書房、一九七三年)一六〇‐一頁。
[18]なお、大統領の腐敗を描く一方で、バナナ会社の権力にも注目したアストゥリアスをはじめ、ラテンアメリカの小説家たちは制作者の複数性に気づいていた。政治と資本によって多重に「制作」されたラテンアメリカの世界像――その源流には、コンラッドの『ノストローモ』がある(第一〇章参照)。
[19]マリオ・バルガス・ジョサ『ガルシア・マルケス論』(寺尾隆吉訳、水声社、二〇二二年)八二頁。
[20]同上、一四四頁。
[21]ガブリエル・ガルシア゠マルケス『族長の秋』(鼓直訳、集英社文庫、二〇一一年)六五頁。
[22]『疎外と反逆 ガルシア・マルケスとバルガス・ジョサの対話』(寺尾隆吉訳、水声社、二〇一四年)二一頁。
[23]以下のカフカについての説明は、拙稿「カフカ的牢獄、日本的密室、カフカ的二一世紀」『現代思想』(二〇二四年一月臨時増刊号)所収を再構成したものである。
[24]ギュンター・アンダース『世界なき人間』(青木隆嘉訳、法政大学出版局、一九九八年)一二三‐四頁。
[25]「巣穴」(由比俊行訳)多和田葉子編『カフカ』(集英社文庫、二〇一五年)二三二頁。
[26]J・L・ボルヘス『序文つき序文集』(牛島信明他訳、国書刊行会、二〇〇一年)二〇二‐三頁。
[27]「流刑地にて」(竹峰義和訳)カフカ前掲書、一六〇頁
この記事は、PLANETSのメルマガで2024年4月23日、4月30日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2024年5月24日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。