「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学まで、ケアから哲学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。
プロジェクトのキックオフから約1年が経ったタイミングで開催された第11回の研究会では、ボードメンバーそれぞれが中間報告として、これからの1年間に庭プロジェクトでどんなテーマに取り組んでいきたいかをプレゼンテーションしました。
前編では、哲学者の鞍田崇さん、文化人類学者の小川さやかさん、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。
(同日出席されていた井庭崇さんの発言については後日追記いたします。)

端的に言うとね。
コレクティフな場のありかた──民藝とボイスを手掛かりに
鞍田崇さんが庭プロジェクトの第2期に設定したテーマは「コレクティフな場のありかた 民藝とボイスを手掛かりに」。以前の研究会でも紹介してくれたように(「民藝」の思想的意義──「インティマシー」から考える|鞍田崇)、2025年で誕生100年を迎える「民藝」。節目を前に世間的にも注目を集めているこのタイミングで、「この研究会ならではの形で掘り下げていければいいなと思っている」。
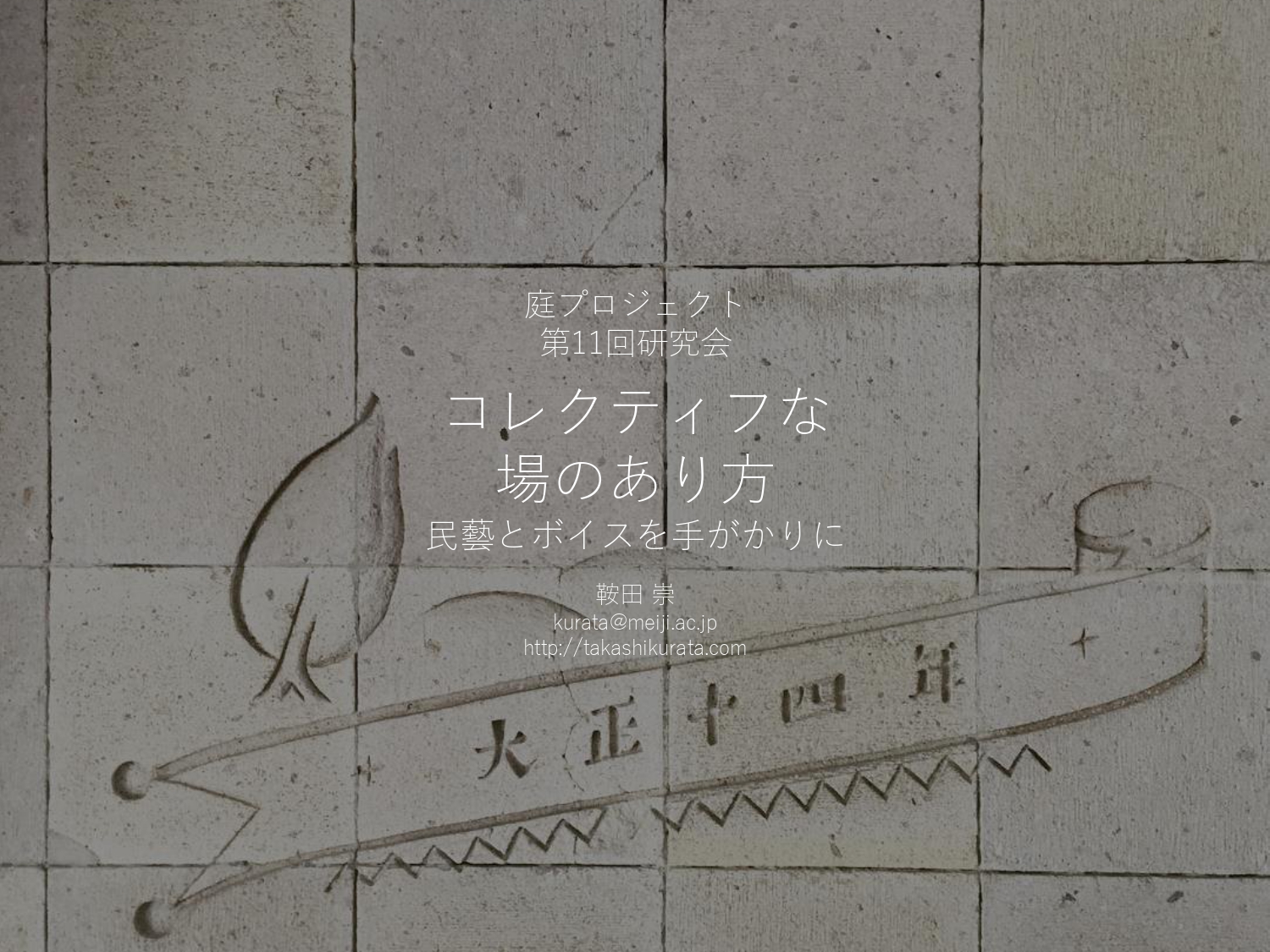

そもそも、崇さんが民藝のどういった点に注目してきたのかを振り返ってみると、民藝をテーマに初めて本を出した『〈民藝〉のレッスン つたなさの技法』(フィルムアート社, 2012)が思い起こされたといいます。
「この本の巻頭に、戦後すぐくらいに柳宗悦が書いた晩年の代表的な著作『美の法門』の一節を掲げました。『不完全を厭う美しさよりも、不完全をいれる美しさのほうが深い』という言葉です。こうしたパーフェクトではない部分や余白、『やりきらないこと』のような不完全さが、いま求められていることかなと思っています。『つたなさ』ということをこの本の副題に掲げたのも、うまく立ち回る、スマートになるということよりも、ずっこけたりへなちょこだったりするくらいのほうが、実はナチュラルなのではないかということを考えたいということだったんです。そんな思いを、それこそつたない言葉なのですが、この本の冒頭でぼく自身は、『ぎこちなさ』という言葉で表しました。あるいはもう少しふつうの言い方で言うと、『スマートに生きることよりも、自分なりの感性で人やものとの出会いを創造していく』ということになると思います。
一方で世間一般の関心は、2018年から行われている鳥取大学の公開講座『「民藝」という美学:地域にひそむ新たな価値の発見』の副題にあるように、『地域社会のあり方』や『そこに潜んでいる価値を見出すまなざし』としての民藝です。個人の生き方というよりも、むしろ地域やコミュニティのあり方の視座としての民藝というものに、一定の関心があるようで、実際そういう可能性もあると思うんですよね。個のあり方を問う視点としての民藝ということもあるけれども、一方でざっくり言うと、社会のあり方、そこに潜んでいる価値をどういうふうに見出していくのかという視点としての民藝というものもある。そこを接続していくことが、100年越しに改めて求められているのかなと思います」(崇さん)

そして、民藝に改めて目を向けるときに大事なのは、「単なる抽象論ではなく、具体的なものの形としてどう立ち現れてくるのかを問うこと」だと鞍田さんは言います。この点に関して、鞍田さんのもともとの出発点であったハイデガーの哲学的な視点とも掛け合わせながら探っていく際に、一つ補助線として入れたいと思っているというのが、ドイツのアーティストのヨーゼフ・ボイスの理論です。
「ボイスは現代アートというものをいまの形でインスタレーションなどの方向へ大きく展開していった先駆けの一人ですが、この人の思考が意外と民藝に通じるところがあると最近思えてきたんですね。たとえば、彼は特別な美術館とかギャラリーとか、あるいは限られたアーティストの営みといった形で特殊化していた芸術というものを、日常へと引きずりおろしていくような姿勢を見せます。そういう態度表明をした最初の世代だったわけです。それは何も、営みとして日常化していっただけではなく、担い手も特殊な芸術家だけではなく、実は誰もが芸術家なのだという視点に立っていました。それこそ井庭さんの創造社会論的な視点の先駆けでもあるかなと思います」(鞍田さん)

その視点に立ってボイスが取り組んでいたのが、「社会彫刻」という試みでした。彫刻は石や木を彫ったりするかたちでアート作品として認められてきたものですが、彼自身が彫刻していこうとしたのは実は社会だったと、崇さんは続けます。
「十数年前に、水戸芸術館でボイスの展覧会がありました。残念ながら僕は行けなかったのですが、そのときの図録にボイス用語集が収録されていて、そこでは彫刻というもの、あるいは芸術というものについて、特殊な営みとして位置付けるのではなく、我々が生きる社会や世界を、人間の創造性によって未来を造形していくプロセスそのものだと書いてありました。具体的にボイスがやったことはある種の教育活動だったり、緑の党の設立などといったことです。1980年当時の西ドイツで、世界で最初にエコロジカルな公約を掲げた政党として緑の党ができましたが、ボイスはその立役者の一人でもありました。社会運動というものが彼自身の社会彫刻的な活動の具体例、実践例としてあったということですね。
中でもよく知られているのが、1982年から5年間にわたって手がけられた、『7000本の樫の木』というプロジェクトです(彼自身は亡くなってしまったので、できあがった完成形を本人が見ることができなかったのですが)。酸性雨の問題など、当時のドイツで地球環境問題への意識が高まっていたときに、まずは一本一本の木を植えていこうという、世界中の人に呼びかけて行ったアートプロジェクトです。当時のボイスは『社会彫刻』というコンセプトを掲げながら具体的な活動の一つとしてこういうことをしていたわけです。一方で、では僕たちはいま、社会を彫刻するという視点で、多くの人にオープンな形で何ができるのだろうということを、民藝とボイスをかけ合わせることでこの一年間で考えてみたいと思っているところです」(崇さん)

その際、崇さんがキーワードとするのが、かねてより注目してきた「コレクティフ」という概念です。ボイスの没後約40年が経ったいま、問われている社会のあり方や個人のあり方も変わっているなかで、一つのあり方として可能性があると感じているのが「コレクティフ」だといいます。
「これは『グループ』の対義語で、もともとサルトルが社会運動の理論を掲げるときに提唱していたものだと言われています。サルトルは一つの目的へと多くの人が一致団結していくようなグループというものを理想として考えました。対して、バス停でたまたま人が居合わせているような、単なるたまたまの集団、つまりコレクティフではよくないとサルトルは言っていたのですが、ジャン・ウリという精神科医はそれを反転して『むしろコレクティフでいいんじゃない?』と言うわけです。
ウリは個々人が自分の独自性を保ちながら、しかも全体に関わっていて、全体の動きに無理に従わせられることがないという状態を言っていたようです。一つの目的へと人々を集約的にまとめていくような集い方ではなく、たまたま居合わせているぐらいのイメージです。もちろん精神科クリニックの運営という、ある種特別な社会状況のなかでの人の集い方ということであったからということもあるとは思うのですが、翻っていまの社会では、むしろそういうあり方が問われているのではないでしょうか。
社会に対しての『彫刻』のあり方として、ボイスは木を植えるということを具体的な活動として行ったわけですが、いま別の何かを考えられないか。そんなことを一つの目標として掲げながら、バス停的なるものとしていま何があるのだろうと考えてみたいと思います。人々がたまたま居合わせて、緩くそれぞれの独自性を保ちながら集えるようなあり方として、何があるのだろうかと。『庭プロジェクト』で掲げている『庭』も、そういうものに近いのかなと思ったりしています」(崇さん)
「エスノグラフィー・プロトタイピング」の可能性
次にプレゼンテーションを行ったのは、文化人類学者の小川さやかさん(タンザニアのインフォーマル経済から考える、これからの資本主義経済のかたち|小川さやか)。「コレクティフはすごく面白いと思っている」と鞍田さんの議論に関心を示しつつ、最近関心を持っているテーマとして「エスノグラフィー・プロトタイピング」についての話題を提供しました。
昨今、ビジネスにおける人類学の活用が注目を浴び、ジリアン・テット『Anthro Vision(アンソロ・ビジョン) 人類学的思考で視るビジネスと世界』(日本経済新聞出版, 2022)なども話題になり、小川さんにも企業からさまざまな依頼が舞い込むようになったといいます。そうした中で、「エスノグラフィ、つまりフィールドワークによる観察記録をそのまま体験してもらったほうがいいのではないか」という思いを強めていった小川さんが模索するようになった手法が「エスノグラフィー・プロトタイピング」です。
_page-0001.jpg)
「もともとは雑誌『WIRED』から『SFプロトタイピングを一緒にやろう』と誘われたのがきっかけです。SFプロトタイピングというのは、たとえばいつかデジタルツインができるような未来についてまずは専門家がお話しして、その専門家が話した理想について、みんなで物語を書くという取り組みです。もし自分のデジタルツインができたらどんな未来ができるのか、たとえば交通事故で子どもを亡くした親がデジタルツインと共に生きていく未来とか、デジタルツインでお見合いをするとか、いろいろな妄想を書くわけです。そういう物語を書くことによって、そこから逆転して『いま理想に近づけるためにはどういう製品やシステムを開発すれば良いのか』を考えるというわけです。
でも考えてみると、別にSF小説ではなくても、実在する異世界を研究しているわたしたちのエスノグラフィをもとにして、エスノプロトタイプとでも言うようなものができるのではないかと思っているわけです。『まなざしの革命 ; 世界の見方は変えられる』(河出書房新社, 2022)を著したハナムラチカヒロさんという風景デザイナーの方が、先行きが不透明であるべき未来が想像できない中では、いまの延長から未来を想像するフォアキャスティング思考も、理想像からいまを考えるバックキャスティング思考も役立たないのではないかと述べていました。それゆえ、多くの人が釘付けになっている問題をひとまずリセットして、まるで無法者や革命家のように常識の外側からものごとを考える『アウトキャスティング』が大事なのではないかと言っています。この本を読んだときに思ったのは、人類学では基本的に毎日アウトキャスティングをしているということなんです」(小川さん)
では、人類学者がフィールドワークの記録をまとめた民族誌を読んでもらえばいい、という話なのでしょうか? そこで問題となるのが、「一般の起業家やビジネスマンたちが、学術用語が散りばめられた多くの民族誌を読んで何かを妄想するのは難しく、ほとんどの場合は遠い世界の不思議な話として終わってしまう」という点です。
「私たち人類学者は、基本的に身体を移動させて、そこで人々と暮らしたり活動したりして、それを模倣する過程で、異なる世界もありなのではないかと思えるようになります。そうして身体的に理解していくプロセスを経験しているのですが、それならば仮想空間の中で研究者以外の人たちも参与観察できたら、私たちのいまの世界観とは全然違う世界観からわたしたちの世界をもう一度眺めなおすプロセスが体験できるのではないか、と思うようになりました。
とはいえメタバース空間を作るのはハードルが高いので、まずはゲーム研究者たちと一緒に、エスノグラフィ的シリアスゲームを開発しているんです。シリアスゲームというと、教育用ゲームや防災ゲーム、リハビリテーションゲーム、軍事シミュレーションゲームなどいろいろなものがあるのですが、最近はもう少しフィールドワークベースのゲームも増えてきています。
たとえばドイツに移住したシリア難民の困難を学ぶ『21Days』というゲームがあります。アルバイトをしないと紛争地にいる家族に仕送りができなくて家族が死んでしまうのですが、一方で働きすぎるとホスト社会に適応するための語学の勉強ができなくて、ホスト社会からパージされる。アルバイトも勉強も頑張ると、宗教的義務が果たせず精神的病に陥る……というゲームです。実際に起きたネパール大震災を完璧に再現していて、そこでいかにしてサバイブしていくのかというものも再現されていて、たとえば人助けをすると裏切られるんです」(小川さん)
ただ、こうしたシリアスゲームは、基本的にどれも目的志向のゲームであり、基本的に「こうすべき」という理想の規範が設定されていて、防災や協同などが大事だということを実感させられるように仕組まれているといいます。そうではないゲームをつくりたいと思った小川さんが開発しているのが、「人類学者になるゲーム」です。
「ゲームの世界ではアバターを通じて動植物や精霊など非人間の世界も簡単につくれるので、マルチスピーシーズの難解な話を読まなくても、ゲームを通じてわかるのではないかということを考えています。たとえば、以前の研究会でお話しした前回お話ししたタンザニア商人たちの世界などを、ゲーミフィケーションで体験してもらおうと思っています。このゲームではあまり狡猾に儲けすぎるとだめで(笑)、ときどき贈与や恩を売っておいて将来自分が助けてもらえる分人をつくる過程をゲーム化しているわけです。
私たちの社会でも、副業解禁などをはじめとして、コミュニティではないネットワーク的な関係でやっていける仕組みが話題になります。私の民族誌の話を聞いているだけだと、ドライすぎるのではないかとか考えてしまうと思うのですが(笑)、自分自身で生計多様化、たとえば20個くらい仕事をするのが当たり前で、そういう生活を通じて誰に何を贈与するのかということを実践してもらえば、実感的にわかってもらえるかなと思って開発しています」(小川さん)
_page-0018.jpg)
また最近は、小川さんは「貨幣とSFプロトタイピング」というテーマにも関心を強めているといいます。
「多くの人にとって『未開』に思われがちな社会の論理と最先端のテクノロジーの組み合わせは、意外と相性がいいんです。人類学のうち貨幣論においては、貨幣というのは空っぽの器などではなく記憶や歴史、人格が刻まれていたと論じられるわけです。たとえばヤップ島の石の貨幣は非常に大きくて動かせません。これは記憶媒体という意味ではブロックチェーンとシステムは一緒なんですよね。けれども文化的な論理は別にもとづいていて、石の貨幣は財の移動を記録するだけではなく、贈与や交換に関する出来事も記録していた。だから和解や同盟など、重要な出来事のときには過去の重要な出来事に利用された貨幣しか交換できなかったんですね。それはよく考えてみるとすごく合理的で、交通事故で息子が亡くなったとかいうときに『じゃあ現金を積まれたら許せるか』というと許せないですが、でも、かつてその人が同じく親族を亡くしたときに泣く泣く受け取った貨幣だったらもらってやってもいいかなと思えるかもしれない。そういう論理なんですよね。
他方で、有名なブロックチェーンゲームの『CryptoKitties(クリプトキティ)』というのは、キティちゃんを交配させてよりレアなキティを作ることでお金を稼ぐシステムですが、であればこのヤップ島の生計多様化もゲームとして再現できるのではないかと思うわけですね。たとえばさまざまな色のトークンがキティのように貨幣として扱われるとして、何度も交配を重ねるなかでいろいろな色が混ざったトークンを貯めていくと、それは人生で得た人間関係の多様性の結晶であるともみなせるようになります。何世代も前からずっと紛争中だったグループに対して、彼らが出したトークン貨幣の模様がマーブル模様のように多様な色をしていたら、和解してもいいかなと思うこともあるかもしれない。商品としてのチョコを買ったりするのであれば、どんな貨幣だとしても金額さえ合っていればいいし、大量のお金を積んだら和解できることもある。だけどそれよりも特別なトークンを使ったほうが話が早いこともあって、『さっきのトークンは、自分が大変だった時期に助けてもらったときにもらったものなのだ』と言えば、額面的には一枚でパンしか買えないような『値段』だとしても、大ピンチのここぞというときに見せれば、きっとこれまで交配に関わったみんなが助けてくれる、これを見たらわたしがどれだけ多くの人たちに愛されているのかがわかるはずだと。一万枚の無色のトークンよりも、一枚の特別な色のトークンが効果を発揮する未来が来ると想像しています。私がタンザニアで知った、ドライなのか温かいのかよくわからない人間関係とかのあり方、いわゆる『コミュニティ』とは違うような集まりのあり方、そういうもののなかでいろいろなものを回していくシステムをゲーミフィケーションしたり、デジタルトークンを作ったりして体験してもらうことを考えていています」(小川さん)
_page-0031.jpg)
「中都市」から考えるまちづくり
小川さんと「まったくトーンの違う話を用意してきました」と話を切り出したのは、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さん(ポスト・スマートシティの都市を構想する──「デジタルものづくり」から考える|田中浩也)。田中さんが取り組んでいきたいのは、「庭レイヤー」とでも言うべきものを、街の一箇所ではなく全体の、それも表層ではなく深層に忍ばせることだといいます。
「ふつうは上空写真を見て『このへんが公園だよね』『このあたりが自宅だよね』『このへんは緑が備わっているから庭だよね』というように、空間分布として都市の中に自然の要素がありそうな場所のことを『庭』と特定しているような気がします。ただ、まずはレイヤーで都市を捉えるというところから始めたい。スチュアート・ブランドによる『ペースレイヤリング』という、我々の都市の中に流れるものの速度を示す指標があります。レイヤーにするとゆっくりの速度から目まぐるしく移り変わるものまで、異なる速度のものが同じ区域に重なっていることがわかります。PhotoshopやIllustratorなどデジタルツールが普及してきて、レイヤーで世界を見るというような発送もふつうのことになってきたと思いますし、こうやってレイヤーに区切って都市を捉える中で、そこに『庭』のレイヤーを差し込んでみたいという野望があるんですね」(田中さん)
「庭」のレイヤーで都市を捉えるとは、具体的にどういうことなのでしょうか?
「この発想に近いものとして、2001年にカッセル・プロジェクトというものがありました。カッセルという街で街ぐるみで行われた6カ月間の実験で、ここで野菜から生分解の樹脂を作る技術ができて、その街で育てられたサトウキビやトウモロコシから材料をつくり、牛乳パックなどの食品の容器をつくったと。それを地域の人が買って、その食品の容器やパックを食後にゴミ箱に捨てるのではなく、近所にある生分解用コンポストまで持っていくんです。そのコンポストを土に戻し、その土でサトウキビやジャガイモなどを育てようという実験が半年間行われました。そして衛生面で問題ないか、こういうやり方でつくった野菜は本当に食用として大丈夫なのか、消費者は習慣化にあたってめんどくさがらないか、といったことを半年間調べたんです。市民20万人・10万世帯の街なんですけれど、かなりの人がこのフローを楽しいと感じていたようです。値段は少し高くなりますが、こちらのほうが環境に良いのであれば選ぶという人が統計で見ると多かったわけです。
以前の研究会でも紹介した、僕が鎌倉で取り組んでいる実験はこのカッセル・プロジェクトを参照していて、まず20万人くらいの規模が街ぐるみの実験としてサイズ的に良いのだろうなと思いました。中都市にあたる人口20万人都市というのは日本に260くらいあり、わりと似たような場所が当てはまると思います。なんとなく歴史・文化があって城下町もわりと多くて、たとえば小田原や山口などでは漁業や農業がある程度栄えていて山や自然に囲まれていて、人口は20万人ぐらい。こういうところが好条件として見えてきて、鎌倉で実施することになりました。ただ、この鎌倉型資源プロジェクトがカッセル・プロジェクトの時代と違うのは、いまはデータを取る方法がすごく多様化しているということです。地域通貨、コミュニティ通貨なども絡めて地域の資源を回収したものを回していくことで、お金の流れも同時に観察できるんです」(田中さん)



さらに、「中都市」というのは、必ずしも人口規模だけがファクターなわけではなく、地理的な特徴もあるといいます。
「環境省が出している『地域循環圏形成推進ガイドライン』というものがあるのですが、これを見ると、大都市と小都市の境界領域に中都市が入っているんですね。これがけっこう重要で、循環系の説明になっていて、生活スタイルが大都市型だと大量の廃棄物が出るので、それをどう処理するかというのが課題になります。一方で小都市は森の中にあったり、里山・里海型の暮らしなので天然の資源がすごく多い。たとえば森があったり薪があったりするので、身近なローカルな天然の資源をどう再利用するかということが課題になる。そして中都市は、大都市と小都市両方の課題にかかわります。基本的にライフスタイルは都市型なのですが、そこに先ほどのような山や海、自然の要素も適度にミックスされているという地理的な特徴があるんです。
鎌倉を見るとまさにそうで、かつさらにこの中でも特殊な事情があって、それはネイチャーコネクテッド率が高いということです。住宅地と自然がかなりモザイク状に入り組んでいるんですね。そうすると、住宅地のすぐ近くに緑が見られるという空間構造になります。去年から年に一回内閣府が実施している『地域幸福度調査』がありますが、これによると鎌倉市の自然景観は、上空から観察すると緑化被覆率が40パーセント程度なんです。しかし住民主観で統計を取ると、市民は自然の要素が80パーセント程度混ざっているのではないかと思い込んでいるわけです。対極的なのが相模原市で、相模原市は上空から見ると山がすごく多くて面積で見ると80パーセントが森なのですが、住民の主観で見ると自然の要素は40パーセントだと感じてしまっている。なぜかというと住宅地と山が完全に分断されているので、住宅地に住んでいる市民は自分の周りには自然がないと感じているということなんです。
したがって、客観的に自然の量が何パーセントかということと主観で感じられる自然の量にはずれがあって、鎌倉の場合は実際の緑の量よりも人々が感じている主観的な自然の量というのが二倍程度に高く、相模原の場合は二分の一になっているということなんです。横浜や小田原などはそこまで主観と客観がずれていないのですが、鎌倉のように住宅地と自然の要素が近いところでは、自然型のDIYというか、木を切ったり山で何かをしたり野菜を育てたりするようなことと、プラスチックや金属、コンクリートなど人工世界を象徴するようなマテリアルが混ざりやすいという特徴があります。そういうものをミックスするのが、中都市の開拓できる創造性としては面白いのではないかと思っています」(田中さん)
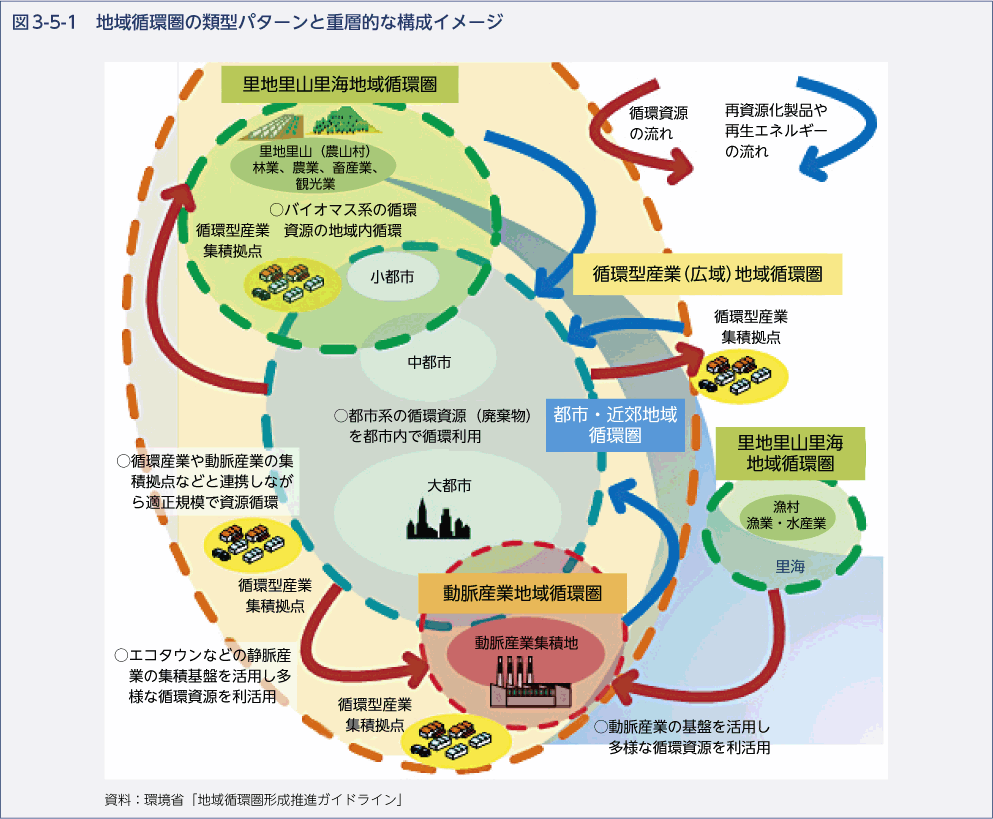
こうした問題意識も踏まえ、田中さんがさらに考えているのは「このモデルをいかにして日本全体に展開していけるのか」ということだといいます。
「こうした中都市モデルに、最近は興味を持っています。大都市も区画を分ければ中都市になるし、小都市も複数都市を合わせれば中都市になるんですよね。たとえば私がいまやっている取り組みを少しだけ参考にしてもらって、横浜市などは市全体を6分割してそれぞれを中都市サイズに切り分け、それぞれの中での資源循環を考えるということをやってもらっています。小都市も長野県の諏訪市の方がいらっしゃって、諏訪市は人口が5万人なのですが、諏訪湖の周りの町を全部足せばちょうど人口が20万人なので、中都市圏になるというんです。そういう中で新しい都市の類似性とでも言うようなものを見つけながら、鎌倉以外のフィールドも開拓できないかなと思っています」(田中さん)
以上、前編では鞍田さん、小川さん、田中さんによる議論を紹介しました。続く後編では、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」施設長・鞍田愛希子さん、建築家の門脇耕三さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。
[了]
この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2024年7月4日に公開しました。


