茂木健一郎さんと、久々にじっくり話しました。(そんなつもりはなかったけど)結果的にコロナ禍の時代とシンクロしてしまった『遅いインターネット』の脳科学的な掘り下げを出発点に、身体と情報のつながり方の問題や、戦後思想のあたらしい受け止め方、それにこれからの世界のゆく先など、射程の長い対話ができたと思います。ぜひ、何かのヒントを持ち帰ってください。
本記事をはじめ、「遅いインターネット」ではコロナ禍が浮き彫りにした社会や生活の課題をめぐって、様々な観点から特集しています。
端的に言うとね。
コロナ禍と『遅いインターネット』の同時代的共振
茂木 宇野さんの『遅いインターネット』を読んで、すごく感銘を受けたんですよ。この本では、まさに新型コロナウイルスで明らかになった世界の変化について、とても明晰に語られてるじゃないですか。でも、出たのが2月だから、書いてたときには新型コロナウイルスの話はほとんど知られてなかった頃ですよね?
宇野 『遅いインターネット』はほぼ昨年末くらいには書き終えていたんですが、結果的に時代にマッチしたものを書いてしまったな、という奇妙な気分です。かつての東日本大震災がそうであったように、こうした巨大な危機はスイッチのオンとオフを切り替えるように何かを変えるというよりは、すでに潜在的に眠っていた21世紀の全世界的な問題を引きずり出している。
この時代に対する応答として書いた本なので、結果的にいま僕たちがぶつかっている壁のようなものがこのパンデミックによって引きずり出されてしまったがゆえに、時代と寝すぎたものになってしまっているんじゃないかなという実感があります。
茂木 カミュの『ペスト』や小松左京の『復活の日』とは別の意味で、予言書的なところがありましたよね。脳科学を専門としている人間が扱いたくても扱えないものの一つが、ヘーゲルの言う「時代精神」です。これらは再現性がなくて二度と繰り返されないから、実験科学では扱いようがない。宇野さんの『遅いインターネット』には、そうした細やかな時代精神の変化に対する感受性の深さ、評論家、批評家としての感度の高さをすごく感じました。
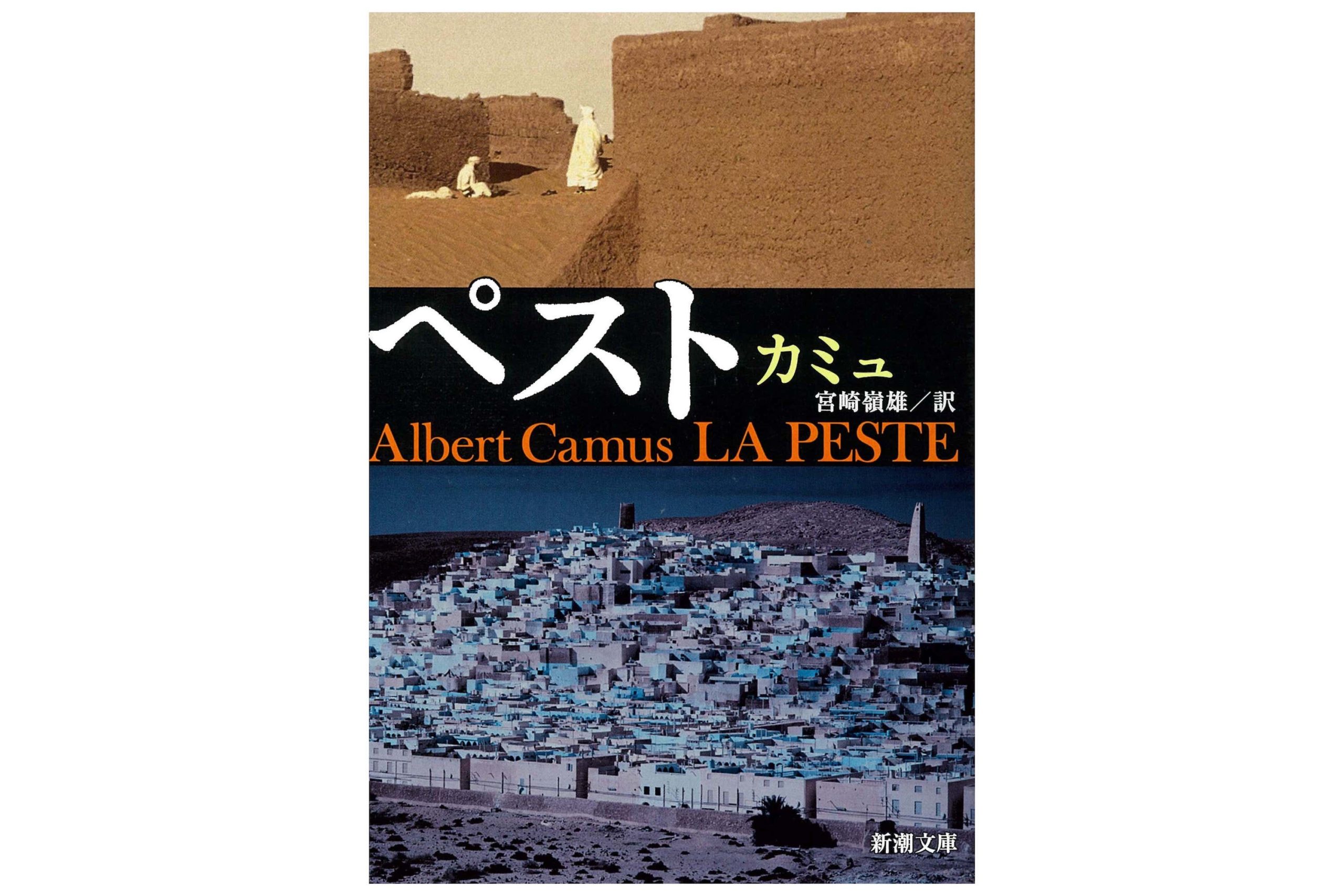
インターネットが啓蒙主義的な文脈の中で動員の革命を起こす、最も近い例で思い出すのは、2011年のアラブの春、チュニジアから始まった民主化への胎動です。ここから、インターネットの見え方がどんどん変わってきた。
宇野さんが『遅いインターネット』の本の中で指摘された様々なことが、このコロナウイルスの蔓延でもリアルタイムで起こっています。時代精神という時代の様々な相互作用のパラメータの変化は、個々の脳の中では収まらない話ですが、世の中に確かに存在している。我々はそれを捉えないといけないんだけど、相変わらずインターネットを啓蒙主義的に考えてる人もいるし、スティーブン・ピンカーや、昨年出版された『FACTFULNESS』もそうですが、「世の中はどんどん良くなってるよ」という文脈でしか語れない人もいる。
要するに僕が言いたいのは、時代の捉え方はひょっとしたら千通りも万通りも温度計を用意しないと測れないものなのに、未だに一つの捉え方でしかSNSを中心としたインターネットを見ることができない人たちがいて、そこでは扱えない事象を宇野さんはあの本の中で扱っているということです。そう強く感じました。

宇野 ありがとうございます。そこに関して僕はふたつのことを思っていて、まず一つはまさに「動員の革命」の問題です。2010年代はとにかくソーシャルメディアを使って人々を街頭に引きずり出していた時代だった。政治的には「アラブの春」から現在進行中の香港の民主化運動まで、SNSの動員を用いた社会運動が定着した10年だったと総括できるはずだし、ポップカルチャーで言うと、音楽産業の収益の柱はCDの販売からフェスへと変わっていった。オタク文化の中心が「観る」アニメから「推す」アイドルに移っていったし、ソーシャルメディアでは「インスタ映え」を目的に人々が特定の場所に集まっていった。とにかくこの10年はソーシャルメディアで人々の日常をハックして、非日常へと動員していくことを人類は覚えた。そのことによって人類はひたすら政治と経済を回していた時代だったわけです。
しかしその結果、非常に大きなツケを払うことになっている。その代表が、この本で扱ったインターネットポピュリズムの問題です。この動員の革命がこれまでの動員と何が違うかというと、人々には動員されているという自覚がないことです。あくまでも自分の物語を自分で発信していると思っている。そして、むしろ世界に対しての手触りを確認するために自ら進んで行動している。あくまで彼らは他人の物語に感情移入するのではなく自分の物語を生きているという実感を持っているわけです。
ここで重要なのが、発信そのものの快楽についての問題です。たとえどんなことでも、自分が吐き出した言葉に対してリアクションをもらうということには莫大な快楽が伴う。承認欲求も満たされる。でも、すべての人に発信能力が行き渡ってわかったことは、発信に値する能力を持ってる人間がほとんどいないことだった。
その結果、人々はタイムラインの潮目的に「いまこいつは叩いても良い」という空気になった奴に対して石を投げることや扇情的なニュースを無批判にリツイートしたり拡散したりすることしかしなくなってしまった。これは一方では下からの全体主義的な同調圧力を再強化し、もう片方ではデマやフェイクニュースの温床になっている。今回のパンデミックでは、前者はいわゆる「自粛警察」による私刑の問題として、後者はインフォデミックによる社会的混乱の問題としてあらわれています。この弊害を乗り越えていかないと、人類は次のステージに進めないという思いがあったからこそ僕は『遅いインターネット』を書いたんです。
ただ、そのことによってグローバリゼーションや情報技術そのものを否定しようとは思っていません。やはり僕は『FACTFULNESS』は基本的に正しいことを書いてると思っているし、情報技術の発展で世の中は総合的にはマシになっていると考えています。ただ、「だからこそ」いま僕たちがぶち当たっている壁の存在を明らかにして乗り越えなければならない。この警鐘のつもりで『遅いインターネット』の本を書いたわけです。今回の世界的なパンデミックは、僕がこの本で書いた壁の存在が、目に見える形で世界中に溢れかえってしまったということだと思います。
改めて「幻のオリンピック」を考え直す
茂木 今回のパンデミックは、グローバリゼーションというものの本質を脅かしてしまった気がしています。宇野さんはこの本の中でもオリンピックに批判的なスタンスを取っていますが、オリンピックはまさにグローバリゼーションの象徴じゃないですか。特に近年のオリンピックは「これだけ多くの国と地域からアスリートが参加しました!」ということを謳い文句に開催されてきた。今回の事態で明らかになったのは、こういった状況になると、人や物の自由な移動が不可能になるので、多くの国や地域から自由にアスリートが参加できるという前提自体が覆ってしまったということです。
宇野 僕はずっと東京オリンピックに対して批判的で、5年前には『PLANETS vol.9』という書籍で「自分たちだったらオリンピックをこうするんだ」という意見を一冊にまとめました。
でも、いま作るならもうそもそもの近代オリンピックの形自体を変えようと思っています。
当時の僕たちが考えたのは、たとえば開会式をインターネット時代に相応しい市民参加のインタラクションのあるものにするアイデアだったり、オリンピックとパラリンピックの境界線を失くすためのあたらしいスポーツの発明だったわけです。でも、いまだったら「そもそも180カ国一同に集まって開催するオリンピックを止めよう」と提案すると思うんです。要するにオリンピック自体は分散開催でも良いと思っているわけです。たとえばマラソンはギリシャで毎回やればいいし、柔道は九段下の国技館でやればいい。
世界中の都市でそれぞれの競技をやっているんだけど、それがインターネットでつながってダイナミズムをもたらすということも、いまのテクノロジーを使えばできると思うんです。地球全体で何かをやる、ただし無理やりそれを一つのイベントにまとめる必要はないのかもしれないな、と最近は考えています。確かに世界中の人間や物事は貨幣や情報のネットワークでつながっている。しかし、つながっていることで一つにまとまってはいない。つながっているのだけど、バラバラのままで良いというビジョンが、これから先の人類社会には重要だと思うんです。
茂木 それで思い出したんだけど、音楽やスポーツの試合が中止になって、無観客という状態が新たなキーコンセプトとして立ち上がってきたと思っています。先日、びわ湖ホールで開催予定だったオペラ「神々の黄昏」がネットでライブ中継されていたのを観たんですが、すごく不思議でした。誰も拍手しない中に演者が出てきて、パントマイムでお辞儀したりして。
以前、宮内庁の楽部にいらしたことのある東儀秀樹さんに話を聞いたことがあるんですが、宮内庁では場合によっては誰も聞いてないところで雅楽師たちが演奏することがあるそうです。そうすると、歴代の天皇の御霊が空から降りてきて、しばらく一緒に音楽とか舞を楽しんでから戻っていかれる、と。
このように「無観客」はこのご時世で新たな可能性を獲得したコンセプトのような気がするんですが、どう思います?
宇野 無観客は大事な概念になっていくと思います。たとえば僕はオリンピックは嫌いだけど、スポーツ観戦はそんなに嫌いじゃないんです。僕は同じ日本人だからこの選手に感情移入して感動しなさい、といわれると本当に不愉快で冷めちゃうけれど、でも、アスリートのプレイを見て「美しいシュートだな」とか「美しいランだな」と感じることはよくあります。ルールに詳しい競技なら、ゲームの駆け引きや優れた戦術に感心することも多いです。
何が言いたいかというと、要するに無観客でのプレイは、もしかしたら競技そのものの面白さ、プレイそのものの面白さに我々が回帰するチャンスなのかもしれない、ということです。もちろん、プレイする選手は勝手が違って大変でしょうが、観る方としては実際に競技場に行っても、豆粒のような選手しか見れないわけです。だったら5GとVRの組み合わせで、目の前で100メートル10秒くらいで走る奴らの走りを見たら「おーっ!」と思いますよね。そういう人間のプレイは、美しい景色や、美しい蝶や花と同じように、人間の心を震わせると思うんです。
だからこそ、無観客は表現が「共通の話題」という触媒として存在するのではなく、表現そのものが個人の精神を魅了していくという、本来の機能に立ち返る良い契機だと思っています。みんなでナショナリズムを確認するためのオリンピック競技ではなく、100メートル10秒で走る人たちのプレイを最新のテクノロジーで間近で見よう、と。それがオリンピックでいいと思うんですよ。
グローバル文明の転換をどう見るか
茂木 グローバリゼーションの問題に話に戻すと、宇野さんがイギリスのデイビッド・グッドハートの『The Road to Somewhere』を引用して書かれていた「Somewhereな人々(グローバル化の恩恵に乗り遅れ「ある場所」で一生を過ごしていく低学歴の保守的な層)」と「Anywhereな人々(グローバル化に適応し「どこでも」生きていけるリベラルな高学歴エリート層)」の分断の問題も、今回のパンデミックでかなり重要な見直しを迫られている気がします。これまではどこでも仕事ができて暮らしていけるAnywhereな人々という、いわば国際的な意識高い系のライフスタイルが良しとされる暗黙の前提がありました。しかし、今回の件ではその見方が大きく変わってしまったのではないでしょうか。
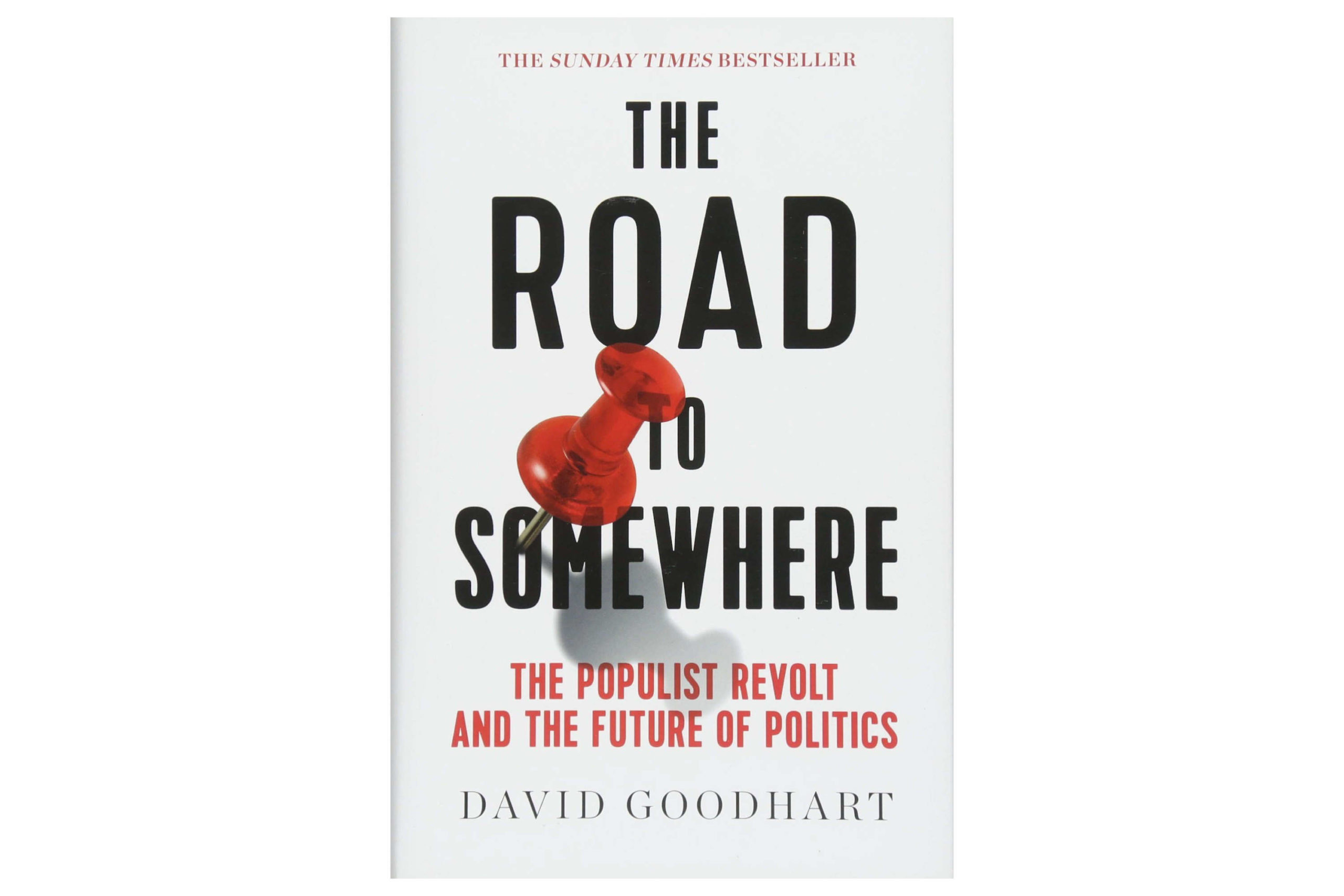
宇野 僕も同感です。たとえば90年代前半、世界中の知識人たちは、冷戦後の新国際秩序は多極化していくだろうと唱えていました。
ところが実際は多極化せず、アメリカ中心のグローバリゼーションが進行していった。しかもそれは、政治のレベルではなく経済のレベルで進行した。あたらしい情報産業や金融産業を中心とした経済の単一化だった。
これはインターネットにも同じことが言えます。インターネットは本来中心を持たないものだった。それがGoogleを筆頭とするグローバルなプラットフォーマーが21世紀に台頭し、擬似的に中央集権的な秩序を与える装置になっていった。
そこに今回のパンデミックは、そういった本来バラバラであるものを地球という一つのゲームボードにまとめてしまうことは非常にリスクが高いということを証明してしまったような気がします。
茂木 その話は、僕が最近気になっている問題とすごく接続している気がします。1989年、フランシス・フクヤマは『歴史の終わり』という本を書きました。当時は冷戦が終わった直後で、議会制民主主義と資本主義経済が社会主義に対して最終的に勝利したという視点から書かれたものでした。当時はこの視点が唯一の解かのように思われていましたが、ここ何年かでデジタルレーニン主義という言葉が出てきて、中国はまったく違う体制を作ってきたことがわかった。いまのトランプと習近平の対立も、自由を基盤としながらもポピュリズムで暴走しやすい社会と、中国みたいな個人レーティングシステムで銀行の融資も学校に進学できるかどうかとかも決まってしまう社会の対立という、ちょっとディストピア的な語られ方をしている。
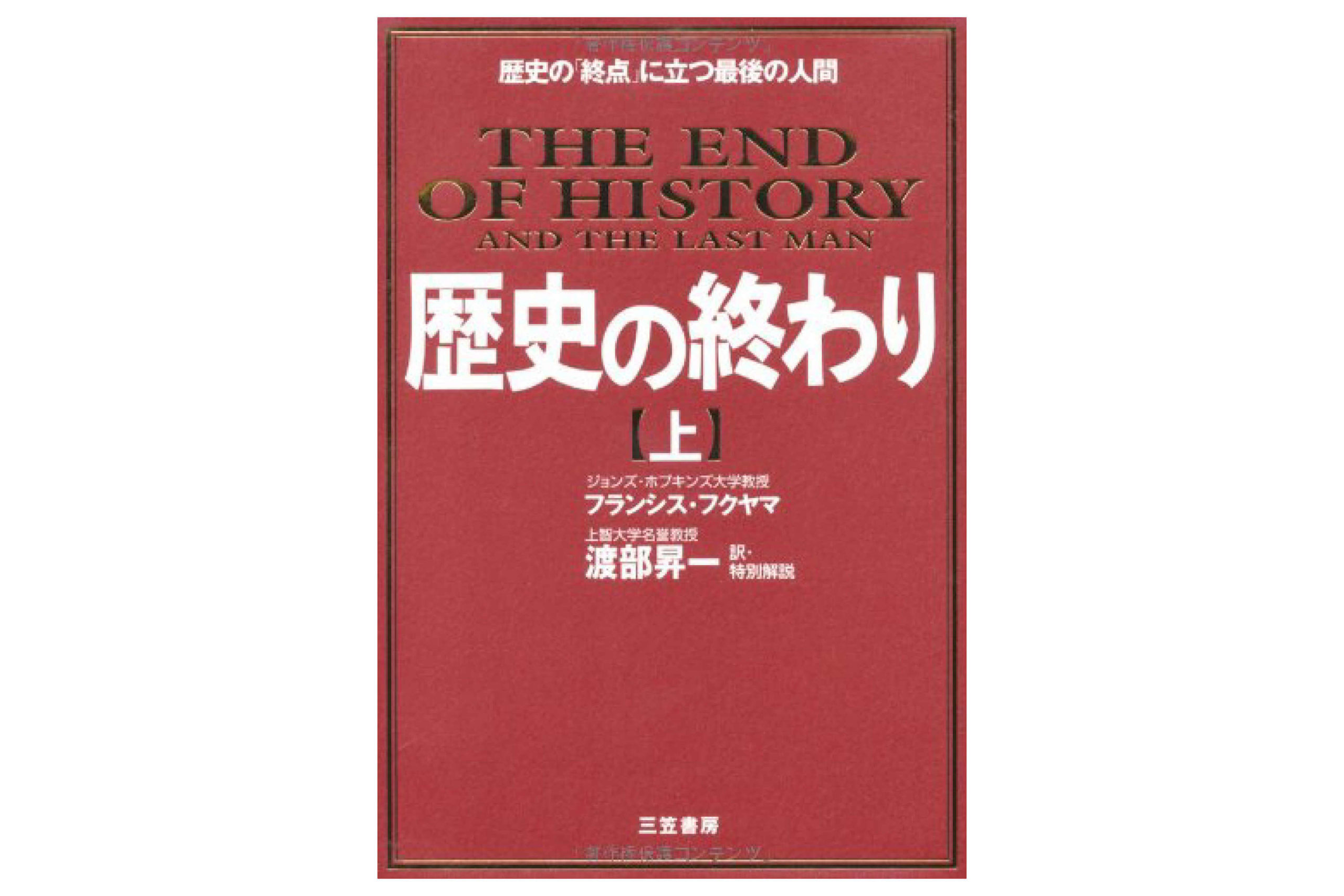
冷戦のときにはソ連のような社会主義と資本主義だと、一見資本主義が勝ったように見えたから決着がついたはずだったんだけど、中国的なデジタルレーニン主義は人工知能とか情報技術との相性がすごく良いので、中国的なやり方とアメリカ的なやり方、どっちが良いのかがまだわからないような状態になってきている。
今回のパンデミックが本当に武漢で始まったものかどうかはまだわからないし、アメリカとイギリスのメディアには中国の初動の隠蔽体質から人工的に撒いたウイルスだという論調もありますが、一方ではそういう権威主義的なやり方が幸いして、中国は封じ込めに成功したように見えます。
人々の生活を強烈に監視し、場合によっては濃厚接触者の様子をスマホアプリで記録して対策に役立てるといった話も、実はイギリスやフランスといった西側諸国から出てきました。デジタルレーニン主義はジョージ・オーウェルの『1984年』的なイメージで語られがちですが、実はもう世界中がそういうシステムを必要とするフェイズになってきているかもしれないということを、このパンデミックは強烈な形で我々につきつけてきました。これは僕にとってはものすごく衝撃的だったんです。

ジョージ・オーウェルの『1984年』の場合は、人々の言動を明白に統制するビッグ・ブラザーという存在がいて、非常にディストピア的に語られます。でも実際のところは、そこまでディストピア色が鮮明ではない、たとえばカフカの『城』や『審判』のような不条理劇に近いポエティックというか、もっととらえどころのない何かになるのかもしれません。
そこで僕は宇野さんに批評家としての見方を聞きたいんですが、我々はこれからの世の中をどう構想するべきでしょうか?
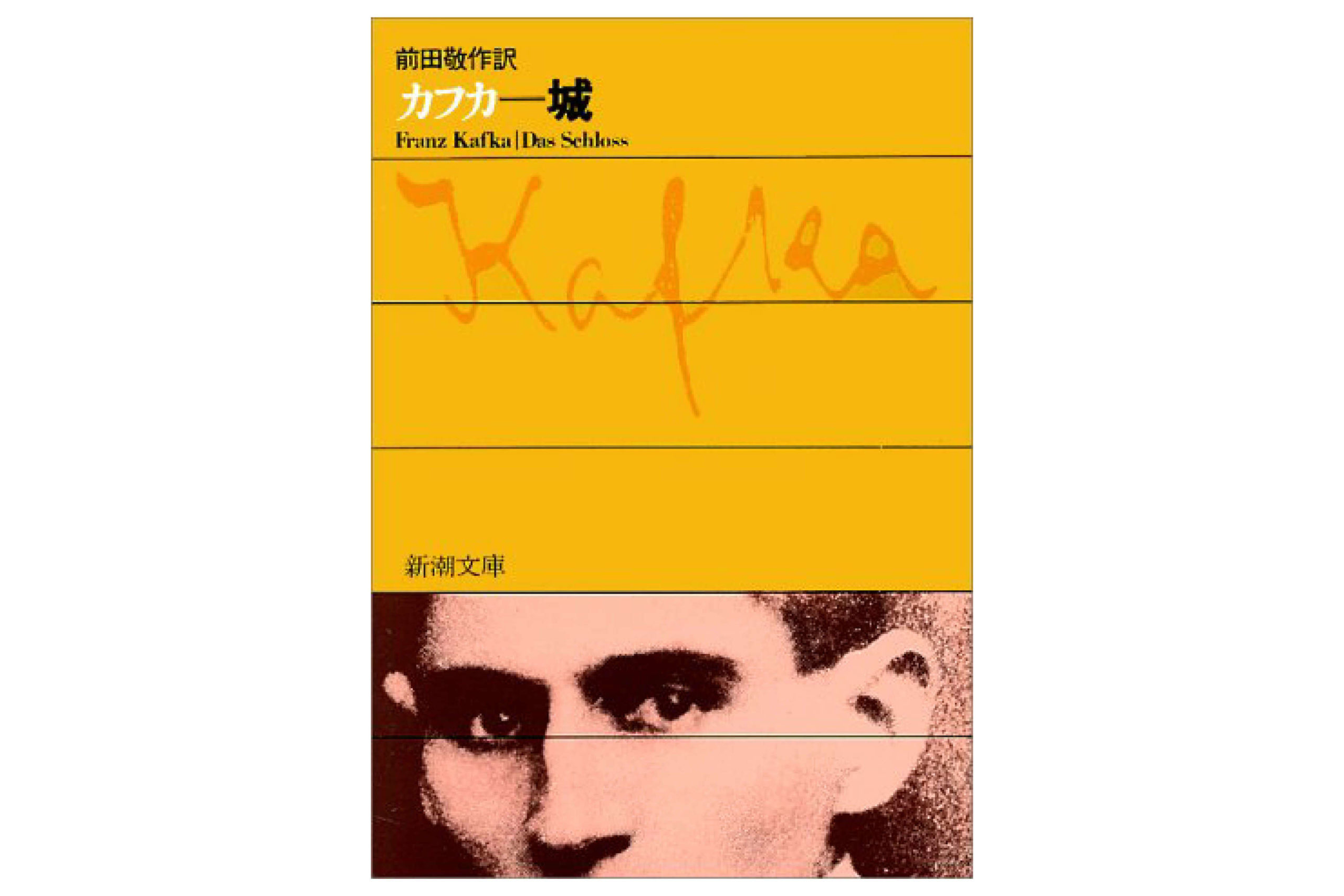
▲『城』
宇野 今回のパンデミックは、西側諸国のソフトなデジタルレーニン主義への軟着陸を促すと思っています。もちろんそれは中国のような形のものとは異なっている。だからあくまで、「ソフトな軟着陸」だと言えるわけですが、そもそも、こうなる前からGAFA的なプラットフォームと国家の関係には緊張感があったわけです。徴税をめぐる問題もそうだし、個人情報の保護をめぐる問題に関してもそうです。そして、その結果としてGAFAは社会インフラを担う企業として重商主義的に国家と接近していくケースが増えていく可能性が高い。これを国家と市場との和解と見ることもできるのかもしれませんが、ソフトなデジタルレーニン主義への軟着陸の扉が開いたと考えることもできると思うんです。これが本当に僕らがインターネットが普及したときに望んだ世界なのだろうか、と考えると、違うと思う。
茂木さんの質問に直接答えることにはなりませんが、インターネットというものはそもそも人間が世の中につながるときの回路を爆発的に増やしてくれるもののはずだった。僕らはそのことによって、もっと精神的な自由や経済的な自由の可能性が広がる未来を獲得しようとしていた。だからこそ、最近の流れについては非常に危機感を持っています。
日本で言えば特に下からの全体主義の問題についてはじっくり考えたほうがよいと思います。東日本大震災の頃には自粛ムードのさなかに遊びに行ったりしたらそれだけで攻撃をされたり、「自分たちが辛い思いをしてるのになんでお前は楽しそうなんだ」といった戦時中を思わせるような同調圧力がどんどん高まっていった。日本におけるソーシャルメディア、特にTwitterは下からの全体主義を生んでいるわけです。その結果、問題そのものじゃなくて問題についてのコミュニケーションが、そして本当の問題ではなく擬似問題だけが共有されていってしまう。
たとえばシングルマザーがネグレクトで子供を事故死させてしまったという事件があるとします。このとき、本当は再発防止のためにも「シングルマザーに対する公的な補助はどうだったのか」「行政の支援は適切だったのか」といったことが重要ですが、実際には子供を死なせてしまった親のプライベートを暴き出して、人格批判をするイジメショーのたぐいが視聴率とツイート数を稼いでいくわけです。
同じようなことが様々なことに当てはまっていると言えます。たとえばあいちトリエンナーレの問題一つに取っても、表現の自由と公共性の問題や、地域アートのあり方という本当の問題は語られず、「この事件を通して津田大介がヒーローになるのは面白くない」「これを機会にこのエリアのボスは知事なのか市長なのかはっきりさせたい」といった、付随する人間関係の問題の方ばかりがアテンションを集めていく。
でも、これを支えてるのは明らかに人々の「発信したい快楽」です。人々は発信することによって快楽を得ていて承認を得ている。複雑で専門的な問題は彼らの承認欲求を満たしてはくれないので、具体的な課題解決よりは、その問題にまつわる人間関係や、当事者の人格批判の方にどんどん流れていく。いまのマスメディアも基本的にはポピュリズムによって成り立っているので、この流れを食い止めることができない。だから僕はこの本の中で、いわゆる普通選挙の外側の民意の汲み上げ方というのをもっと重視することによって、相対的にその決定力を下げるしかないという提案をしています。
もちろんそれと同時に「遅いインターネット計画」がこのメディア状況に積極的に介入すべきであるということも提案しています。
丸山眞男と吉本隆明の擬似対立をめぐって
茂木 すごく共感します。最近よく思うのは、宇野さんも本の中で言及されていた吉本隆明さんとか加藤典洋さんとかが、もし生きていたらいまの世の中を見て、どんなことを考えていただろうということなんですよ。宇野さんがそうした戦後日本の思想家たちをなぜ取り上げようと思ったのか、改めて聞かせてもらえますか?
宇野 加藤典洋さんは戦後50年の節目に『敗戦後論』で「国民の物語を再起動しよう」と主張した。彼は日本の戦没者をまず追悼した上で、海外の犠牲者も追悼するという形で国民の物語を語り直す提案をして、左右両陣営から批判されていた。あの時の加藤さんの提案は非常に建設的で優れたものだったと思いますが、あれから四半世紀たったいま見てみると、そもそもナショナル・アイデンティティの再構築が当時ほど有効な処方箋にはならないだろうな、とも思うんです。

デイビッド・グッドハートのAnywhereな人々とSomewhereな人々の対比で述べれば、Anywhereな人々がリベラルな傾向を持つのは、むしろこの人たちのアイデンティティが国家と結びついていないから、国籍を自分についているタグの一つくらいにしか考えていないからです。『遅いインターネット』で指摘したとおり、この種の人たちの脱国家性は別の問題を生んでもいるのですが、彼らは国家を軽視しているかこそ、「そりゃあ隣国とは仲良くしたほうがいいに決まっている」と柔軟な対応を取りやすいのも事実です。そして同時に、このAnywhereな人々があたらしいナショナル・アイデンティティを共有して欲しいといわれても、そもそもそれをあまり必要としていない、という問題もあります。
だから僕は国民の物語を再構成するよりも、国民の物語を必要としないゆえに現実的な落としどころを効果的に模索することができる主体を育成するほうが、現実的だと思うわけです。
よく使うたとえですが、僕はマンションの隣に住んでいる団塊世代の老夫婦とはほぼ没交渉です。僕は午前中は基本的に家でずっと原稿を書いていて、Amazonがやってくると部屋着のまま出て受け取る。その僕を、隣の老夫婦はいつもいぶかしげな目で見ていて、おそらくは無職かニートだと思っている。アラフォーの中年男性が勤めに出てないということが、たぶん未だに「おかしなこと」だと思っている。一方で、僕はたとえば面白い映画を見たとき、真っ先に感想をシェアするのが、いまは京都の大学に勤めているのだけどずっと香港にいた香港人の社会学者の友人なんですよね。これは特別なことでも何でもなくて、世界中の人間が当たり前のように共有しているリアリティです。僕は加藤さんの仕事を十代の頃に読んですごく衝撃を受け、影響を受けているからこそ、彼が考えていた理想というものを、別の形でどう今日に再現できるかを考えているんです。
それは吉本隆明さんに関しても一緒で、吉本さんの知識人対大衆という図式は、いまはほぼ無効化されていると思います。日本の戦後社会では永らく丸山眞男的な建前主義と、吉本隆明的な本音主義は対立関係にあるとされてきましたが、実はこれらは共犯関係にあったことを考えなければならない。実効性を度外視した空疎な理想主義も、その反動としての現実主義への居直りも、結局はどちらも現状肯定の思想なんですよね。「理想主義者は現実に落とし込めるようなつまらないことを言ってはいけない」という思想と「現状肯定こそが現実主義なのだ」という思想は、55年体制下の進歩派と保守派がそうであったように、かなり明確な共犯関係にあるんです。これらの思想がこの国を戦後のある時期までは安定させていて、冷戦終結後は大きく停滞させていたことは間違いない。『遅いインターネット』では、こうした丸山眞男的なものと吉本隆明的なものを、セットで批判的に乗り越えていかなければならない、と書いています。
茂木 先日「週刊文春」にメルビルの『白鯨』の話が出てたんです。船の上で理想主義と現実主義が対立して、現実主義が勝ってしまう。これはいまのアメリカのトランプみたいな感じだと書かれていました。

▲『白鯨』
吉本さんは「進め!電波少年」というバラエティ番組の企画で、伊豆で溺れかけた直後に番組プロデューサーから「この洗面器の水に顔をつけてくれ」と言われて、顔をつけたんですよね。あれをどう評価するか。たとえばこれが丸山眞男だったら絶対つけないと思うんだけど、僕は吉本さんのそういうところ好きなんですよね。なぜならソクラテスがそういう人だった気がするから。
吉本隆明はそういう意味でソクラテス的なイメージがあって、生活者としての大衆性、いわゆる実感と思想が自然に共存していた人のような気がします。日本だと知識人ってほとんど死語になってるじゃないですか。特に啓蒙主義的な知識人が社会を先導していくみたいな生き方がほとんど存在しない現代において、理想と身体性をどう融合させるかというスタイルを我々はもっと研究したほうがいいのではないかと思うんです。
宇野 たとえば僕はこの本で、糸井重里さんの話をしています。彼の態度で一番引っかかるのは政治性なんですよね。前提として、僕は「ほぼ日手帳」を2003年から使っているヘビーユーザーで、「生活の楽しみ」展にも行っているし、TOBICHIは青山も京都もよく行く。

▲宇野の今年のほぼ日手帳。
その一方で、僕は糸井さんのようなアプローチはもう通用しないなと思うところもたくさんある。一番重要なのは、政治性の問題です。糸井さんは「政治的ではないという政治性に留まる」、という80年代的な倫理を堅持している。60年代の反省から、政治的であること自体に背を向けてみせるというパフォーマンスが有効であったことは間違いない。しかし、こうした態度は今日においては完全に裏目に出ていると思うんですよね。糸井的な「政治的ではない、という政治性」は、彼らの作り上げた80年代以降の消費文化の中で育った世代には、単に政治性への免疫のなさとしてしか受け取られていない。要するに「あえて」政治的ではない「ふりをしてみせる」のではなく、単に政治性に免疫がなく、その結果すこし心の弱い人や考えの足りない人はSNSが普及するとかんたんに「動員の革命」の結果、左右のイデオロギーに依存していった。だから僕は吉本隆明から糸井重里に引き継がれたものを反面教師にしないといけないと思っています。吉本的な「政治的であっても、党派的であってはならない」という「自律の思想」が80年代に、糸井的な「(表面的には)政治的であってはならない」にアレンジされることで大衆化したわけですが、僕はここが間違いだったと思うんです。
だから僕は政治的な立場を鮮明にするために、毎回自分の投票先とその理由を公表しています。政治的であるけれど党派的ではないということを、愚直にやるのが僕の選択なんです。態度表明をしない、あえて線を引かないというのは、吉本隆明の思想を糸井重里が実践する際にたどりついた、ある種の倫理のあり方であったと思います。ところがそのあり方はもう通用しない。しっかり線は引く。しかし、常に引き直す準備をしておく。引き直したときにはその理由を説明する、というスタンスで行くしかないと思っているんですよ。それはコミュニティとの距離感にもなっていて、糸井さんは絶対に自分のコミュニティを持たないけれど、僕は自分の読者たちのコミュニティを引き受ける方向に行こうと思っている。そこから人を育成して、世に出していきたいと思っているし、それが僕なりの丸山眞男的なものと吉本隆明的なものの、対立に見せかけた共犯関係を突破するための一つの回答なんですよね。
茂木 政治的なことと党派性が別だというご指摘には、すごく共感するところがあります。認知科学で有名な「ミニマルグループパラダイム」という言葉があるんですが、とある教室の生徒をパウル・クレーが好きな人とカンディンスキーが好きな人でそれぞれグループに分けるんです。それでいくつかゲームをやるんだけど、お互い相手のことを評価させたりすると、党派性がでてきてしまう。クレー派の人はカンディンスキー派の人をネガティブに評価したり、偏見を持ったりして、逆に同じカンディンスキーグループはカンディンスキーグループにいる人を身びいきするようになる。そういう、どうでもいい小さなことでも、いざ人間をグループ分けすると、自然とグループダイナミクスで党派的な対立が発生してしまうという論文が出て、すごく大きな影響を与えたんですね。
だから、たとえばリベラルと保守の対立とか言うと、深遠な哲学的思考にもとづく違いのような気がしてしまうけれど、おそらく本当はクレーとカンディンスキーくらいのことかもしれない。なのに党派性が重要視されすぎていて、そのゆえに本質が見えにくくなっていることが多々ある気がする。でも、それくらい政治性と党派性というのは、現実的に切り分けることが難しいということだと思うんですよね。
宇野 僕はあまり人間についてコミュニケーションしすぎないほうがいいと思うんです。何かを批判するときにも、人間について批判するのではなく、あくまで制度や構造を批判することがすごく大事だと思っています。あまり考える力が強くないのにプライドだけ高い人って、Twitterのリプライとかソーシャルブックマークとかで「叩いていいもの」の揚げ足を取って鼻息荒くしちゃうじゃないですか。字数制限とか見出しの付け方で書ききれなかったことをドヤ顔で指摘してみたり、書いてある内容を自分が批判しやすいように脚色して、それを叩ける俺カッコイイ! みたいに悦に入ることにばかり腐心する。彼らは「この人よりも自分が上に立ちたい」という自意識と承認欲求の問題からああしてるわけですよね。そうした対人マウンティングのコミュニケーションではなく、きちんと事物に対してコミュニケーションすると、そんな卑しいことは相対的にしなくなると思うんですよ。
『遅いインターネット』で紹介した「vTaiwan」というクラウドローのシステムでは、ジョインというアプリケーションが使われてるんですが、ジョインでは人の意見にレスがつけられないようにしているんですよね。これは人に対してのコミュニケーションではなく、物事に対してのコミュニケーションに人を誘導してるから、というのが僕の解釈なんです。僕はインターネットを使って、人以外のものとコミュニケーションするということが、これからの知性にとっては重要なんじゃないかと思っています。それが政治的であっても党派的でないことに結びついていくと思いますね。
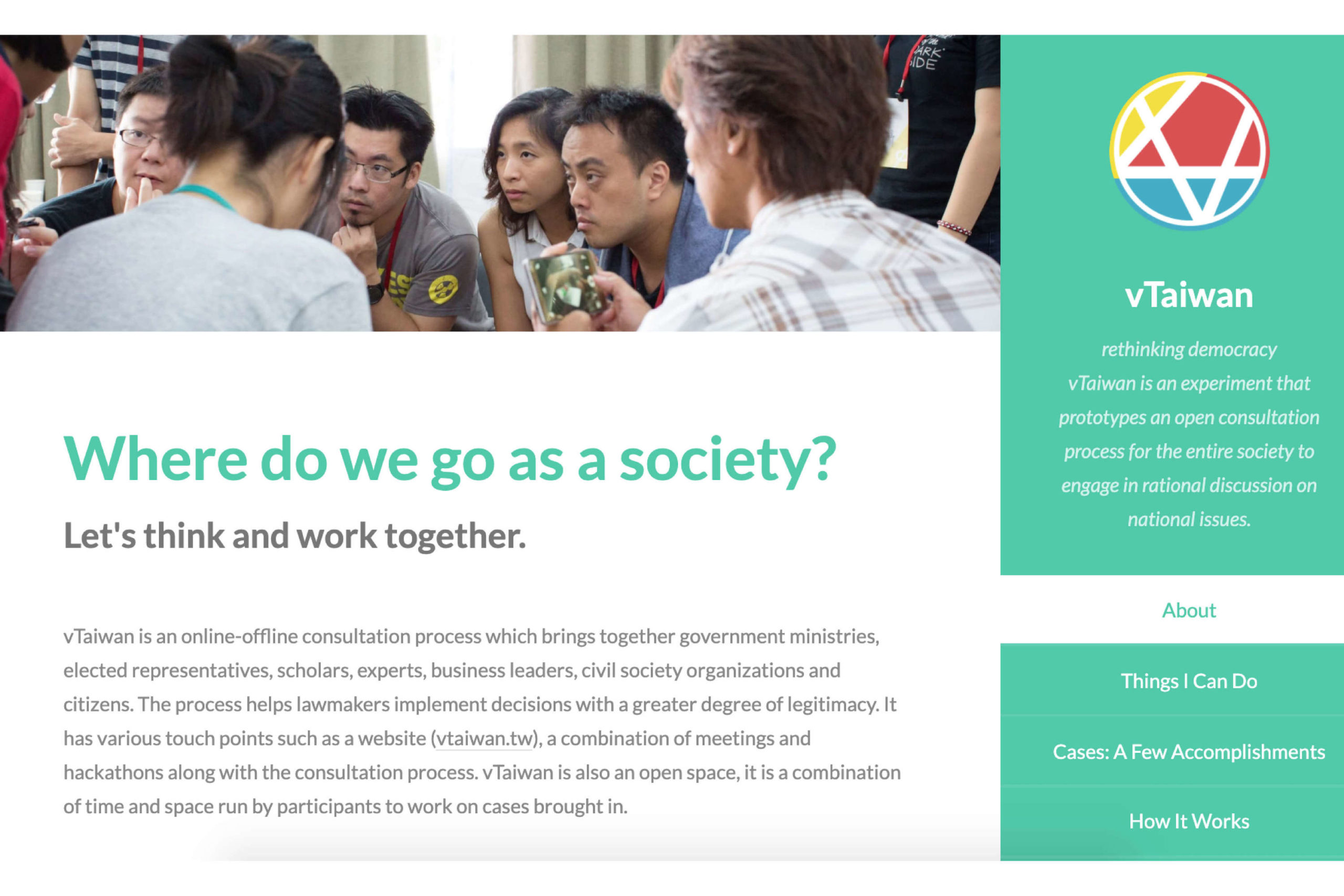
「わからない」ことを受け止めるために
茂木 「吉本隆明さんや加藤典洋さんが生きてたらいまの世の中をどう思うか」なんて、なぜそんなことを思ったかというと、いまは3ヶ月先のことさえまったく予想できない、とても脳の認知的に負荷の大きすぎる世界が訪れているからなんです。
コロナのことだけじゃなく、たとえばFacebookが構想しているLibraのような暗号通貨が実際に実現したときに、通貨というものがどうなるのか。シニョリッジ(通貨発行益)という概念がありますよね。たとえば日本だったら円という通貨を発行していますが、基本的に日本銀行は1万円札を刷るのに20何円しかかからないから、その分の利益を国家が得ているわけです。じゃあLibraの母体となっているFacebookのような、ある程度公益性のある国家ではない団体が通貨発行益を得るのってどうなんだろう? といったことがいまのホットトピックになってますよね。
でも、一方で最近は量子コンピュータのキュービット(量子ビット)がどんどん増えてきているので、ビットコインであれLibraであれ、仮想通貨・暗号通貨が流通し普及した後で、それが一瞬にして破られてしまうという事態も起こりうる。こうしたことも含めて、我々はこれからの世界を見なくてはならない。
人工知能の分野では、技術の進歩が人間の手を離れて完全に予測不可能になるシンギュラリティ(技術的特異点)という言葉がよく取り沙汰されますが、これは元々はI・J・グッドという人が言い出した概念です。彼は『2001年宇宙の旅』のHAL 9000のコンピュータのコンセプトを手掛けた人で、アラン・チューリングと一緒に「エニグマ」というナチスドイツの暗号を解読したりもしています。しかし、いま考えられているような人工知能の発展が本当にシンギュラリティと呼べるような状況を実現できるのかどうか、まだわかりませんが。
いずれにせよ、ほんのすこし先も予想できずに一瞬にして世界の様相が変わってしまう状況は、今後ますます加速していくような気がします。前提としていた議論の枠組みが一瞬にして無効化されてしまうようなことが、これからも起こるでしょう。宇野さんはこのあたりをどう感じますか?
宇野 いま茂木さんがおっしゃったことは、より卑近に言えばリスク社会的な議論だと思うんですが、僕は基本的に足腰を鍛えるしかないと思うんです。何が襲ってくるかわからないなかで、いま僕らはわからないということに耐えられずに社会的に躁状態になってしまっている。でも、何が起こるかわからないというのは別にいま始まったことではなくて、実際世の中はずっとそうだったわけなんですよ。
そしていま、情報と流通のスピードが速くなってサイクルも速くなってる。サイコロを振る回数がどんどん増えているから、当然変な目に出くわす可能性も高くなっているわけです。そのときに僕らが一番やらないといけないことは、「わからない」ということをどう受け入れるかということだと思うんです。いま、人々はわからないということを受け入れられないから、とりあえず発信して、つながることで誤魔化そうとしている。みんなでわかったふりをすることも同じで、どこかに悪者がいてその悪者を叩けば解決するとか、どこかに隠された陰謀があってそれを暴けば世の中は正常化するという物語も、ごまかしの一つに過ぎません。そういった、わからないということを受け入れることができずに、擬似的にわかることにしようとすることによって、人々は過剰につながろうとしていると思うんです。
でも実際にそんなことでは何の解決にもならない。いまはわからなくても、少しでもわかるようにしないといけない。そのためにはやはり多方面から時間をかけて攻めないといけないことがたくさんあるわけです。今回の新型コロナウイルスの対策とかもまさにそうですよ。でも人々はその時間にも耐えられないから、結果として不必要につながって、それが陰謀論やフェイクニュースの温床になっていって、最終的には本当に必要なウイルスへの対策の足を引っ張ることになっている。これは世界各国で起こっていることです。だから僕はいま一番大事なことは、このわからないということ、いますぐ答えが出ないとか、いまはわからないということを僕らがしっかり受け止める強さなんだと思うんです。
茂木 僕は個人的には意識、クオリアの問題を扱っているから、すごく共感します。でも、最近のAIの研究者には「人工意識なんてすぐ創り出せますよ」とか「もうできてますよ」とか、安易に言う人が意外と多いんですよね。あと、実は僕は底辺ユーチューバーなんですが、解説系のYouTubeを見ると、宇野さんが言った「わからない」ということを排除したような語り口が多いんです。世の中はこうなっているとわかったことにして、その中で擬似問題が解決されていく。
たとえば、自動運転に関する研究で今後何が最大の問題になるかというと、自動運転のアルゴリズムが明らかになってしまうことなんだろうと思うんです。つまり「子供が飛び出してきたときは車に乗っている人の危険を少々増してでも子供の命を救うべきだ」みたいなアルゴリズムがあるとする。いわゆるトロッコ問題ですよね。つまり「一方を救うために他方を犠牲にする」というようなアルゴリズムを、自動運転車などの危機管理の局面では導入せざるをえないはずです。でも、そういうアルゴリズムが明らかになってしまうと、人間の意識としてはものすごく困ると思うんです。
もう一つ別の例を出すなら、たとえば今この対談をZoomで収録していますが、そもそも「宇野さんといま対談する/しない」という決断は、「宇野さんだったらすごく面白い話になりそうだからやりたいな」といった無意識の評価関数によって決まっているわけです。あるいは、恋人の選択とか、自分は日々の時間のリソースを何に費やしているのかといったことも、実は全部、人間の意識が自覚していない暗黙の評価関数をもとに動いているんです。
しかし、それが明示的に意識化されてしまうと、人間は自己決定の負荷に耐えかねて、自我が崩壊してしまうんです。たとえば小説『ソフィーの選択』ではソフィーがナチスの将校に強制収容所へ連れて行かれる際に、「収容所へ連れて行ける子供は1人だ。お前の2人の子供のうちのどちらかを選べ。選ばないと2人とも死ぬぞ」と言われて1人を選んでしまうという、すごく痛々しいシーンがありますね。あるいは夏目漱石の『こころ』でもいい。先生が友情と恋愛の板挟みになってKを犠牲にしてでもお嬢さんを獲得してしまう、という状況がありますよね。あのとき実は我々の脳の中では「Kとの友情が何点」と「お嬢さんと一緒になることが何点」とか、そういった評価関数に基づいて動いているかもしれないんですが、それが明らかになってしまったとき、我々は自我が崩壊するような恐ろしさを覚える。
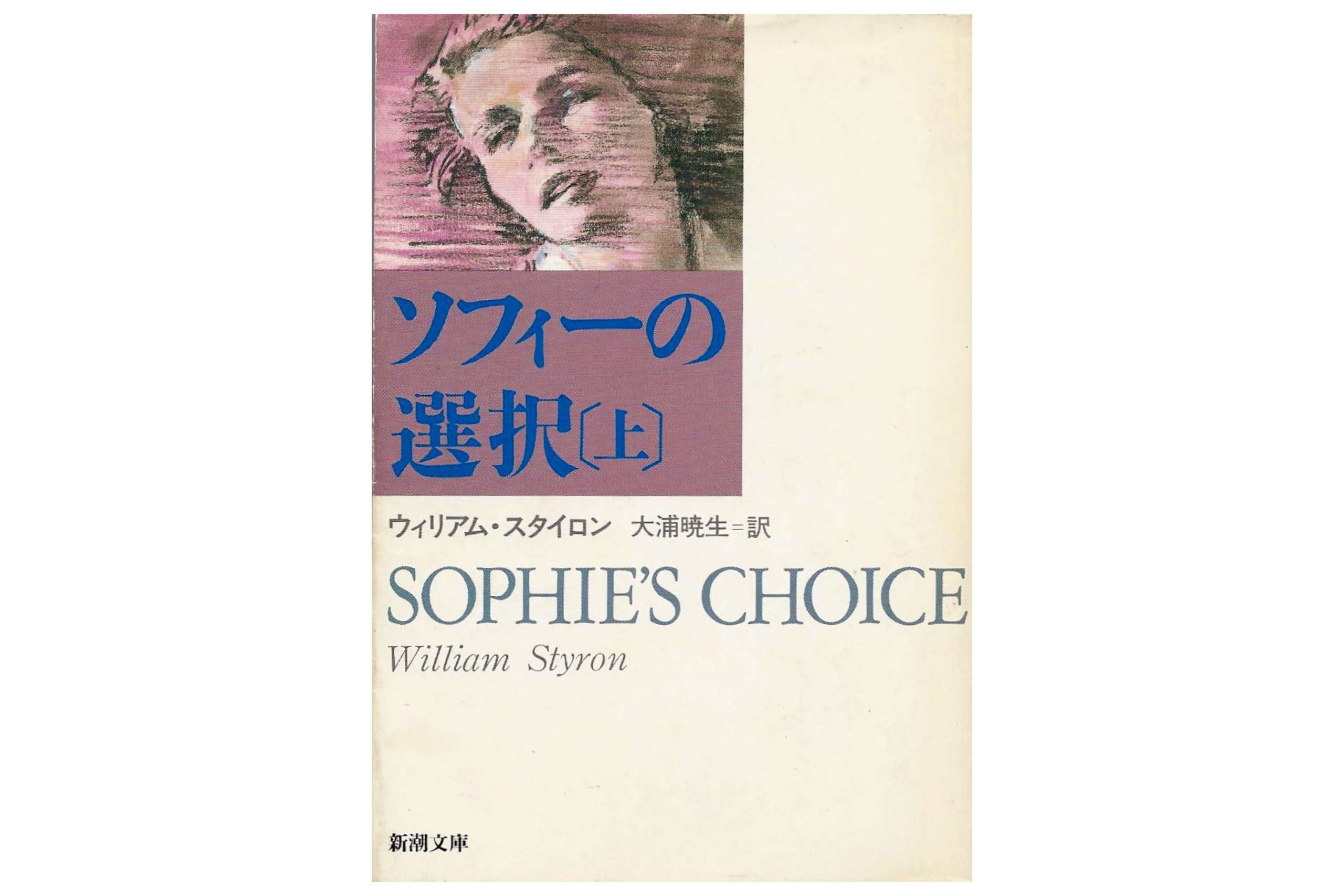
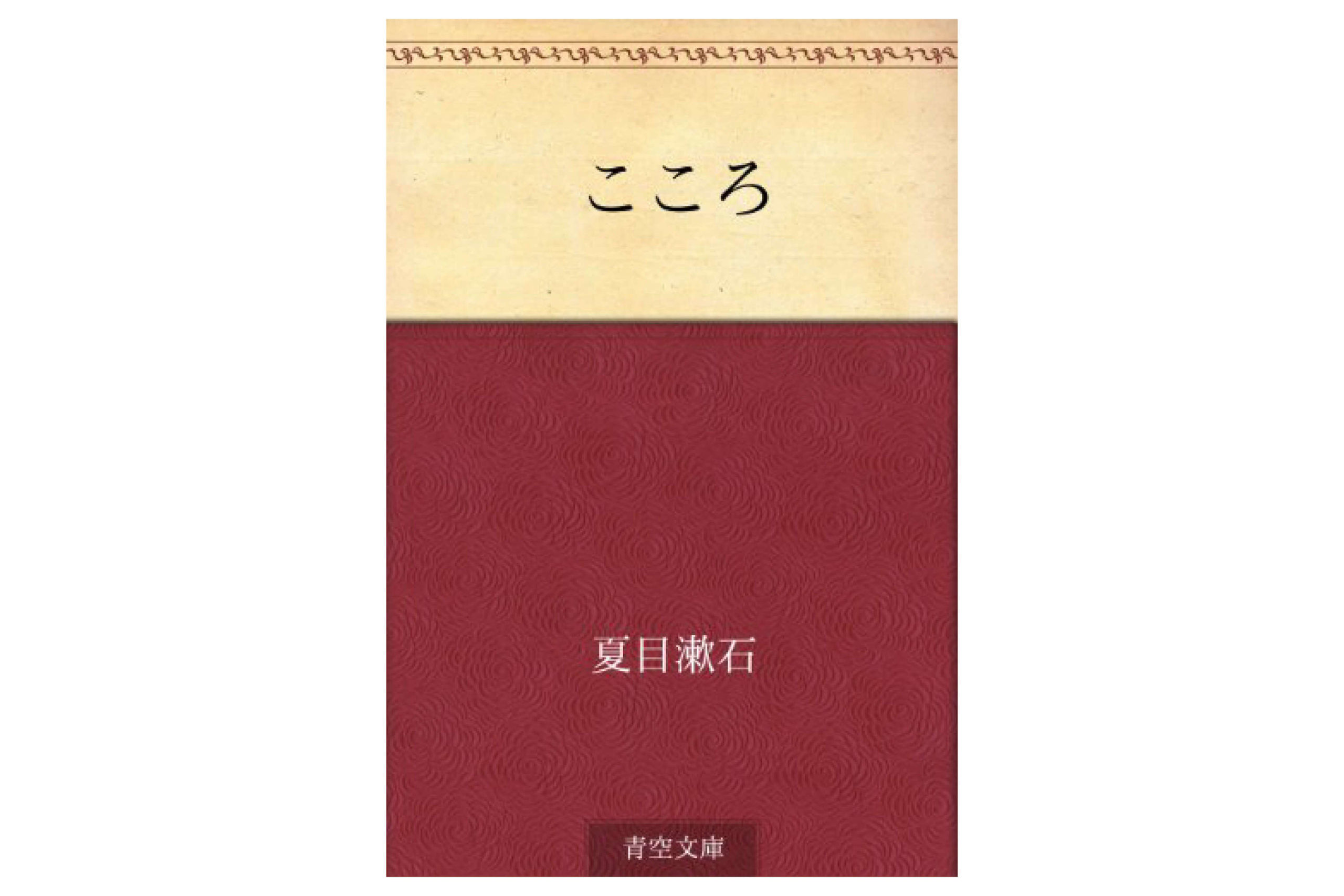
自動運転のアルゴリズムも、おそらく我々には、ブラックボックスでいてほしいという気持ちがある気がします。だって車に乗ってる側からすると、ある程度通行人の安全を犠牲にしても自分のことを守ってほしいというのが本音じゃないですか。でも、それを自動運転の車の人が謳い文句で謳っていたら困るわけです。
結局、身体性というものはすごく便利にできているんですよね。我々はその自分の突き動かされている原理や評価関数を知らないままに意識の中で何かを選択するというアーキテクチャになっているから、自我が崩壊しないで済んでいる。
宇野 僕が「遅いインターネット」のようなことを言い始めたのは、そういう人間の身体的・認知的な限界に、現在の「速いインターネット」が適した設計になっていないと気づいたからなんですよ。いま僕らは「ソーシャルディスタンス」と称して、現実空間で他者との物理的な距離をとっている。でも本当にとらないといけないのは、情報的なソーシャルディスタンスだと思うんです。みんなこの未曾有の人類史的な危機というものに対する不透明さから、不必要につながって擬似問題を作り上げようとしている。いまはパンデミックをインフォデミックで補完してるというすごく頭の痛い状態なんですよね。その結果、認知限界を超えた情報を無理矢理処理しようというモードになって、わかりやすい元凶を仕立て上げて排斥しようとしたり、デマに躍らされたりする。
このインフォデミックを乗り越えることがパンデミックを乗り越えることにつながると思うんです。そのために、僕ら人間はわからないことも受け入れなければならないし、孤独にも耐えなければならないと思っています。
身体的な知をどのように取り戻すか
茂木 「遅いインターネット」って、僕がやってる脳の立場から考えるとすごく身体性と深く結びついているところが面白いんですよ。たとえば我々は「2ちゃんねる」のような、匿名の本音が垂れ流される空間を、なぜ嫌だと思っていたのか。あそこで我々が目にしたのは、フロイト的な無意識の原理というか、それまでは個々人を突き動かす潜在的な衝動としてはあっても表には出てこなかったものが、インターネットの普及によって表面化して高速に飛び交うようになってしまった光景ですよね。大江健三郎さん的に言えばディーセンシー(節度)みたいなものがインターネットによって破られてしまったから、すごく嫌な気がしていたんだと思う。
しかも、いまや経済や社会までがそういったものに突き動かされるようになってしまった。だからこそ、先ほど言ったような評価関数があまり明示的には出てこないようにしたり、もっとゆっくりした時間係数で我々が色んなことを選択できたりするような構造を再現しないと、人間の中核が失われてしまいかねない気がしていて。僕は宇野さんの『遅いインターネット』を、そういう身体性の問題と結びつけながら読んでいたんですよ。
宇野 もちろん僕も、身体性のことを頭に入れて書きました。だからあの本って、ランニングの話から始まってランニングの話で終わるんです。
茂木 そういえばそうだね。
宇野 僕らはいままで、身体は不自由で精神は自由であると考えてきた。しかし今日においてそれは逆なんじゃないかと思うんです。むしろ情報技術は精神の方をどんどん不自由にしていって、そこから抜け出すために身体の水準からアプローチしたほうが良いんじゃないか、と考えたわけですね。だからこそ、僕はプラットフォームから僕らが自由になるために、速度という入り口を見つけた。タイムラインの潮目に沿って脊髄反射的に反応するのではなく、一回間を置いてみよう、自分の中で一回引き取ってみようということを提案しています。それは単にゆっくり考えようということを言いたいのではなく、いまの情報技術や、その情報技術を使っているプラットフォームから僕らの精神活動を自由にすることが目的です。
そのためには、実は身体性のレベルで管理するのが一番早いわけです。寝る前にスマートフォンを見ないとか、自分をネットワーク環境から一回切断してみるとか。この四半世紀の間に、視覚情報や言語を情報技術を掛け合わせることで、身体よりも精神のほうが支配されやすくなってしまった。今日の言葉で言いかえるなら、身体よりも精神のほうが動員されやすくなっているわけです。だから、動員の回路を一時的に遮断してみるとか、距離をとってみるということが、結果的により大きい自由を確保することができるんじゃないか。身体を一回経由することによって精神的な自由というものをもう一回取り戻すことができるんじゃないかということが念頭にあります。
茂木 すごく面白いですね。宇野さんがおっしゃったような、精神というか脳神経系と情報ネットワークの関係だけでは収まらないようなことについては、我々の研究分野ではembodiment(身体性)とかembodied cognition(身体化された認知)として研究されています。単純なところだと、暖かい飲み物を持っている人は他人に対して優しくなるとか、誰かの履歴書を見ているときにその履歴書が重いバインダーに挟まれているとその人のことをより高く評価するようになるとか、そういった認知科学の研究があります。
ダニエル・カーネマンが『ファスト&スロー』という本の中で、まさにゆっくり進むものと速く進む思考の間の関係を議論しているんですが、これも広い意味での身体性です。このところの脳科学だと脳腸相関ということが注目されていて、腸内細菌のバランスと脳の状態が実はすごく関係しているという事例が知られてきています。たとえば最近だと、うつ状態で調子が悪いと思ってる人は、実は脳の中のセロトニンという物質が不足しているだけではなく、腸内細菌のバランス、腸内フローラのバランスが悪いからそういうふうになってしまっている、というような研究がかなり出てきている。
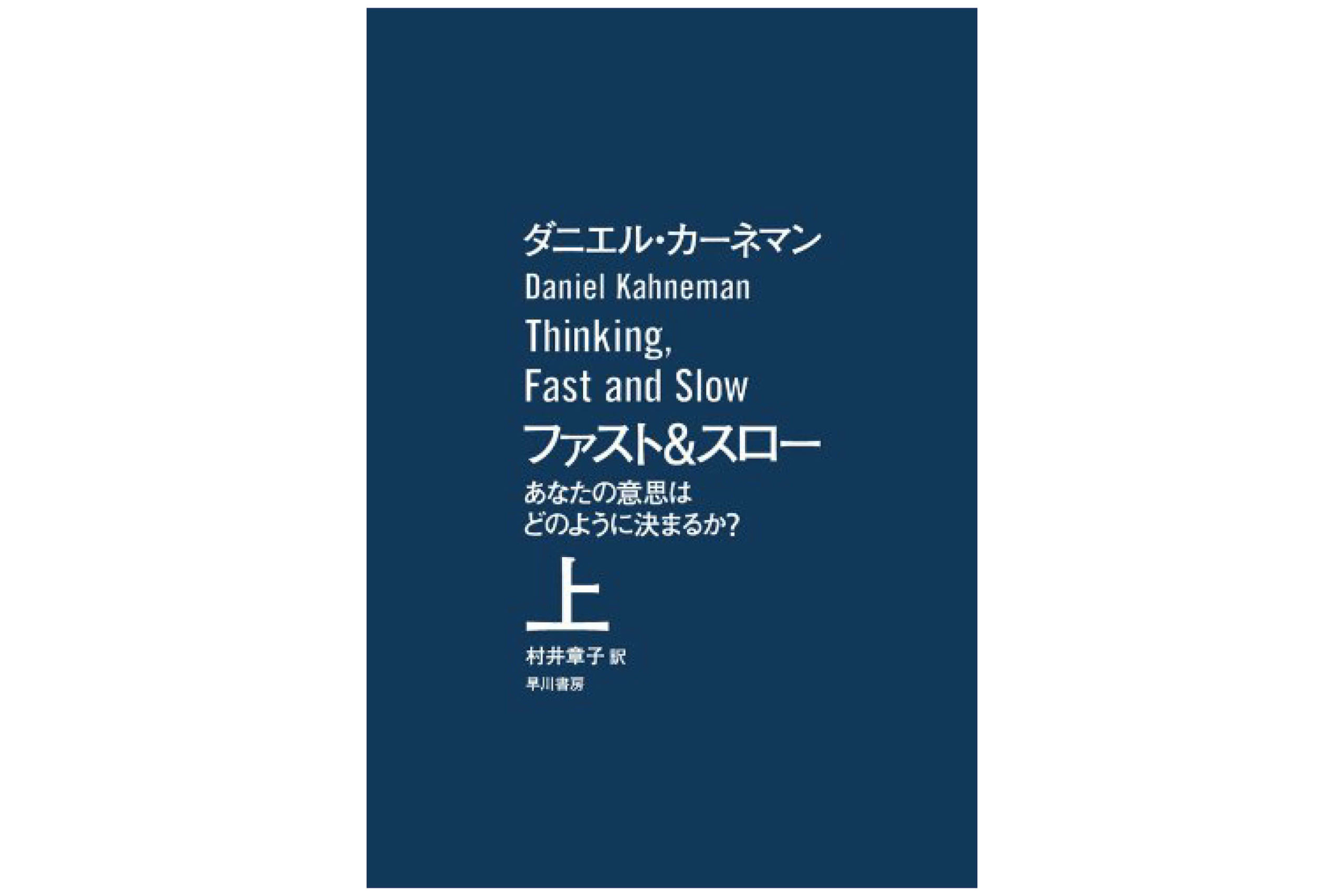
だとすると、その人が何を食べたり何を飲んでいるかということもまた、すごくゆっくりとその人の思考や態度に影響を与えているはずなんです。最近、僕はお風呂に入りながら内田百閒の『まあだかい』という本を読んでるんですが、これは彼の還暦が過ぎたあと、教え子たちが集まって酒を飲んでいる話です。それを読んでいると、内田百閒が考えることは、普段飲んでるものとか食べているものに影響を受けているだろうな、と強く思わされます。
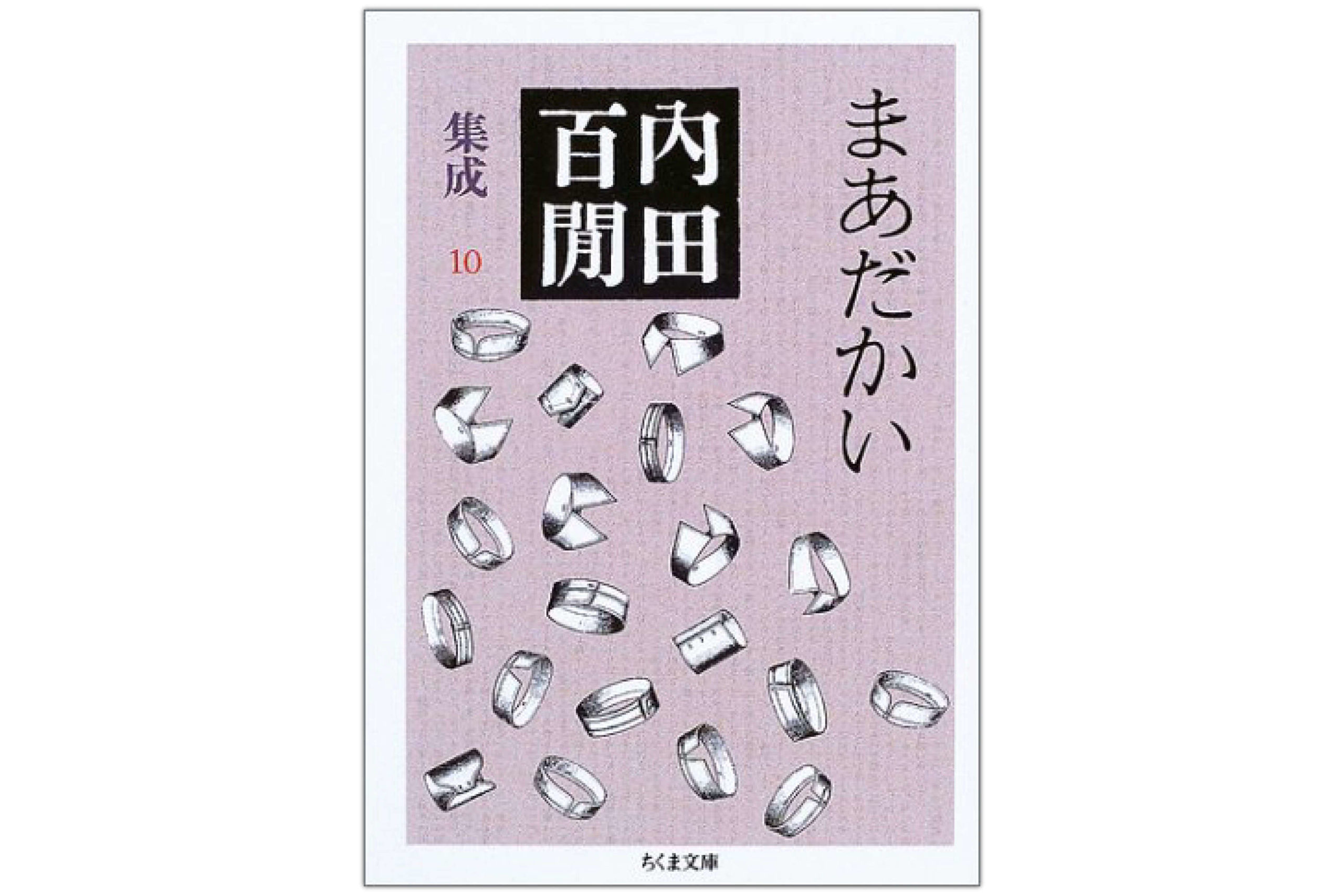
昔、NHK教育テレビが埴谷雄高のインタビューを数日間にわたって放送していたことがあったんですが、彼はずっとインタビューを受けながらトカイワインを飲みまくってるんですよ。同じように、ヨハン・セバスティアン・バッハも作曲時にワインをやたらと注文していたそうです。もし他のお酒を飲んでいたら、あんな曲にはならなかったのかもしれない。
そう考えると、たとえば宇野さんはランニングをしているけど、村上春樹さんも走ってる。いつも走ってる人が考えることや文体には共通の型があるんじゃないか、とか、そういう類のことは絶対ある気がするんですよね。たとえば夏目漱石は胃弱だったからああいう文体になったのかもしれない。そしてそういう身体的な知は、確かにいまの情報技術とかインターネットが、まだ扱えていないものだよね。
宇野 ただ、一方で僕は、身体と情報技術を対立的に捉えるべきだとは考えていないんです。むしろ問題の本質は、SNSを中心としたいまの情報ネットワークが、人と人とをつなげることにのみ、過剰に特化しすぎていることにあると思っています。
たとえばこのパンデミック下で、世界中の企業がリモートワークに切り替えていますよね。そんな中で、この前ある大企業の人と話していたら、社内のコミュニケーションを活性化させるためにZoom飲みをやるんだみたいなことを自慢げに話していたんですよ。僕からしてみるとこんな状況になったからこそ、飲みニケーションみたいなものからは積極的に距離を置いて、自分が孤独であるからこそ初めて見えてくることや、自分の生活というものをしっかりと見つめ直すことに時間を使ったほうが絶対に面白いことや、あたらしい気づきが得られると思うんですよね。
多くの飲み会はメンバーシップの確認に過ぎなくて、昭和のものづくり企業からいわゆる論壇みたいなところまで、メインイシューが欠席裁判じみたものになりがちじゃないですか。僕はこのパンデミックは、そういったものと自分を一切切断して、人間以外とのコミュニケーションというものをしっかりとる契機だと思うんです。
たとえば僕がフリーの文筆業者として10年以上前から考えてきたことなんですが、いまの日本のLDKの建物って全然リモートワークに向いていないです。ソファとテレビが中心のリビングに設計されていて、基本的には昼間は専業主婦しか家にいないというスタイルが未だに想定されている。結果的に、すごく時代錯誤な設計になってると思うんです。家で単身、もしくは夫婦で仕事をしているという状態に適した物件ってほとんどないと思うんです。僕はこういった人間と空間の関係や、現代のワークスタイルや家族構成とか家族観を根本的に見つめ直す機会にもなると思っているわけです。
こういった真面目な話だけではなく、好きなものを自分一人で料理してみるのでも良いし、僕は模型が趣味だから模型を作るとかでも良い。人と触れ合うだけではなく、空間や環境、物と触れ合う時間を作る良い機会だと思います。僕らはソーシャルメディアのせいで、人間と人間のコミュニケーションばかりに囚われてしまっている。
それはやはり人間と人間のコミュニケーションがコントローラブルになったからですよね。いままで見えなかったものが見えるようになったからです。だってFacebookで親しい男女がいきなり「いいね」をつけ合わなくなったらそれって付き合い始めているということじゃないですか。人間関係に関しての情報量が爆発的に上がってしまったがゆえに、みんなそこに夢中になりすぎている。この10年は、情報技術のせいで人間が人間のことしか考えなくなってしまった10年なんですよ。ところが本来人間は人間以外とも大量にコミュニケーションをとっているわけです。その豊かさをみんな忘れてしまっていると思っていて。実はこのパンデミックはその忘れ去られた人間と物、人間と事、人間と空間との関係を取り戻す良い機会になりうると思うんです。結果として身体というインターフェースが重要になっていくと考えています。
茂木 すごく共感します。いま、「セルフ・アイソレーション(自主隔離)」という言葉が国際的なバズワードになっていますよね。あえて孤独になることで創造的な価値が生まれるという発想は、ニュートンが万有引力の法則を思いついたのがペストが蔓延したときの疎開時だったとも言われているように、古くから存在するものです。そういう時間をクリエイティブ・バケーション(創造的休暇)とも言いますよね。
たとえば先日、望月新一さんが数学の難問であるABC予想を解いたことで一躍話題になりました。あの方は元々変わり者で、ABC予想を解いた論文をいきなりネット上に出したんです。それも所属の京都大学も一切書かず、いきなり「こんなのが出ましたけど」という感じで出してきた。その査読が京都大学の数学の研究所の雑誌に載ることが決まったんだけど、そもそも望月さんが使っている言葉が普通の数学者でもまったく理解できない言葉で、まず「この人は何を言ってるんだろう?」という勉強会からスタートしたそうです。それで8年くらいかけてやっとチェックしたと。
あるいはルートヴィヒ・ヨーゼフ・ヨーハン・ヴィトゲンシュタインは、ノルウェーの山小屋に何年間か篭って『論理哲学論考』を書きあげたとも言われています。僕が好きなグスタフ・マーラーは、作曲するためのコンポジションハットという、ひとり専用の小屋を持っていて、そこで作曲をしていたという話もあります。

そういう孤独を、否定的な意味ではなく肯定的な意味で捉え直すことは重要ですよね。ネットワークで流れてくるものは、どうしても同時代的になりがちだし、同化しやすい。何かを共有するのには良いけれど、望月さんみたいに数学者がまったく理解できないようなあたらしい言語を作るだとか、従来の哲学と一線を画したオリジナルな思考をまとめるには、あまりよくないと思うんです。かつては華やかな社交界の寵児だったオスカー・ワイルドも、同性愛の罪で獄中に入れられて、初めて自分を見つめ直して『獄中記』を書けたわけだから。
せっかくこういう孤独になれる機会があるのに、それをZoomの飲みニケーションにしてしまうというのは確かにもったいないですよね。
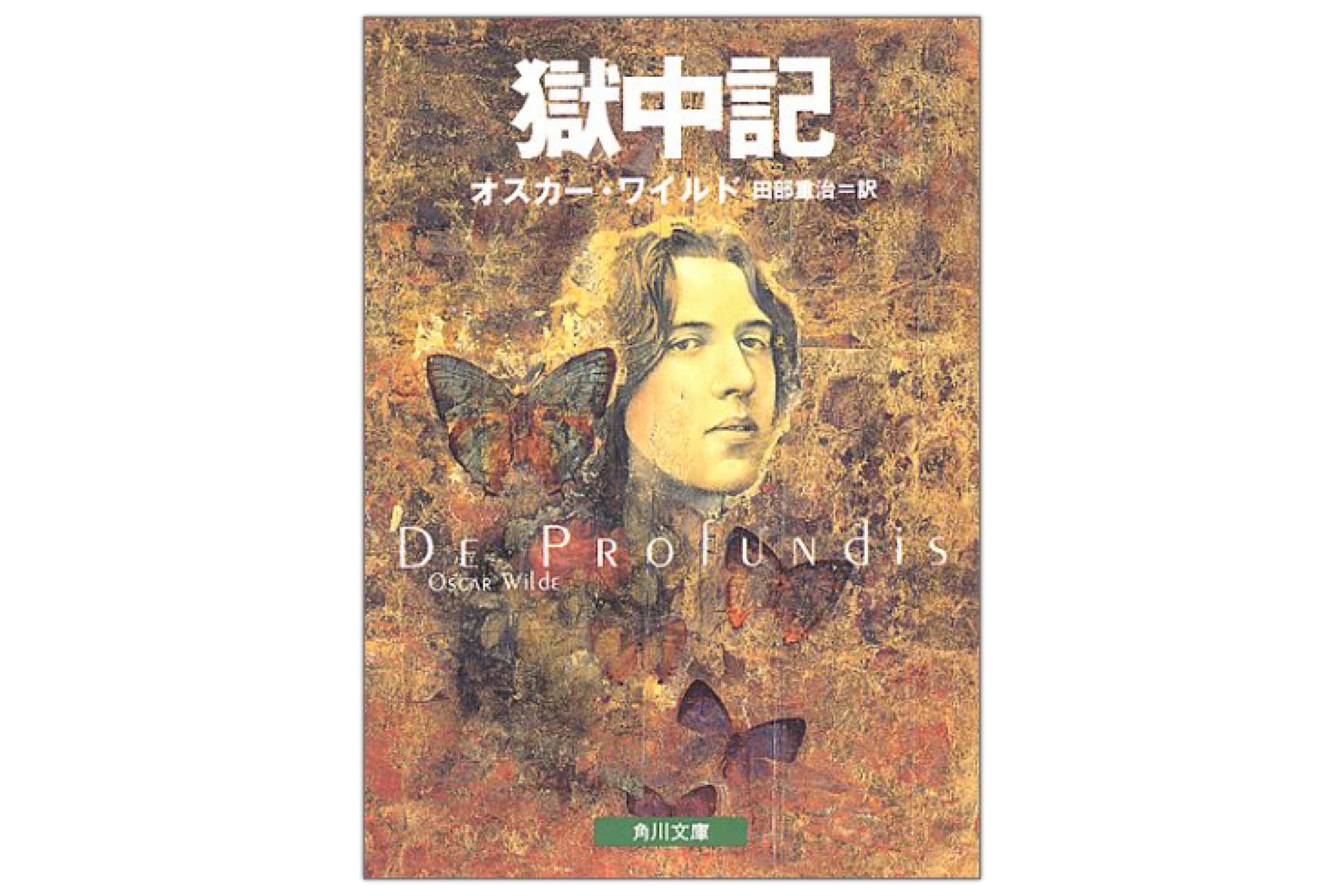
宇野 人が引きこもるためには、しっかりとした思想と技術がいると思うんです。この状況が終わったあとに外に出ても、ちゃんと見る目が養われて、歩く足が鍛えられていないと意味がない。たとえば地球の裏側まで行っても絵葉書と同じ写真でセルフィーを撮って、名所旧蹟の前でWikipediaを引いてるだけなら読書と変わらないんですよ。わざわざそこに行く意味がないんです。
同じように、孤独になったとしても、「孤独キャラの自分カッコ良い」って毎日ツイートしてたらそれは意味がないわけです。あんなのはただのソーシャルな承認欲求に飢えているゾンビじゃないですか。そういうことではなくて、大事なのは人間とコミュニケーションしないことだと思うんですよ。自然でも良いし、物でも良いし、地理でも良い。非人間的な物としっかりコミュニケーションをして思考をちゃんと練磨してるかどうかという問題だと思うんです。だから引きこもれば良いというわけではなく、むしろ引きこもる技術やコンセプトが必要で、そしてそこにテクノロジーも必要なんだと思うんです。
茂木 立ち止まるって、すごく大事なことですよね。日本はここのところ、やれインバウンドだオリンピックだと走ってきて一本足打法みたいになっていましたが、こうなっては今年の経済成長率はマイナス二桁は間違いないでしょう。学校にも行けなくなってるし、会社にも行けなくなっている。脳には実は「デフォルトモードネットワーク」というものがあって、まさに人が立ち止まってアイドリングすることで、初めて自分の魂を探求する「ソウルサーチング」というプロセスが始まるんです。その時に何が見つかるかというのは、すごく大事な気がしますね。
さっきも話したように、僕はいま、内田百閒やドナルド・キーンと司馬遼太郎の対談といった古いものを読んでいるんですが、そこには「こんなものあったんだ!」というあたらしい発見がたくさんある。宇野さんの言うように、みんなSNSとかYahoo!ニュースを見すぎなんだと思いますよ。
インフォデミックに流されずに「走る」ということ
宇野 あと、さっき村上春樹さんの話が出ましたが、僕は同じランナーでも春樹さんとは距離があると思っています。たとえば彼の『走ることについて語るときに僕の語ること』には、最後に「ただの一度も歩かなかったことを誇りに思う」みたいなことが書いてあるんですよね。僕はあの気持ちがわからないんです。

筋力トレーニングやタイムにも一切関心がなくて、単純に街の成り立ちがよくわかるとか、空気を楽しむとか、街を走るのが面白くて楽しくて走っているのであって、ああいうふうに何かのために走っているんじゃないんですよ。あくまで走るために走っている。対して、春樹さんが走るときって実は自分としかコミュニケーションしていなくて、それが村上春樹という作家の個性を作っているんだと思うんです。
ただ、最近はいわゆる競技スポーツではなくライフスタイルスポーツ、いわゆるランニングやヨガの方が競技スポーツに比べて増えていますよね。こういったライフスタイルスポーツのプレーヤーは、ほとんど僕のような感覚を持っていると思うんです。つまり、単に走れば良いということではなく、人間以外とのコミュニケーションで自分の思考というものを見つめ直す機会として捉え直せるはずじゃないかと。
茂木 宇野さんがおっしゃる「孤独」になるということの価値は、引きこもって自分の内奥にある創造性を追求したりすることだけでなく、外に出て街並みを体感するということも含まれているということですね。
宇野 はい。近年のランニングの広がりは、走ること自体を楽しむ文化が浸透してきていることのあらわれだと思います。これはもっと言ってしまえば、近代スポーツが持っていた五体満足主義を解体していくことにもつながっている。自分の意思でコースとスピードを調整できるなら、車椅子だっていいんですよ。
茂木 なるほど、冒頭の方でおっしゃていた、オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払うオルタナティブ構想の話ともつながっている。
宇野 そうです。先ほど話したように、僕は真面目にオリンピックは分散開催したほうがいいんじゃないかと考えています。でも、もっと本音を言うと、もう自分が勝手に走ることにしか興味がないんですよね。『PLANETS vol.10』ではランニング特集を組んでたりするんだけど、もう、一人ひとりがどう走るのかということに問題の中心が移ってきているんです。つまり、オリンピックを分散開催するよりも、みんなが勝手に走って楽しんで、人間ではなくて非人間的なものとコミュニケーションをとって面白がれば十分なわけです。「そもそも競わなきゃいいんですよ」というのが、いまの僕の考えです。
茂木 「競わなきゃいいんだ」というのは目から鱗というか、本当にそうですね。そこから豊穣な世界が開けてくるということはあると思います。
いまの話を聞いて、修験道のいちばん厳しい行とされる「千日回峰行」を二度達成した酒井雄哉さんという方と対談したときに聞いた話を思い出しました。この「回峰行」っていかにも難しいことを考えながら山の中を歩いてるように聞こえるんですが、一日のうちにカバーする距離と時間を計算すると、実質、山の中を走っているんです。つまり、今風に言うとトレイルランニングなんですよ。なので酒井さんは「千日回峰行というのは体育会系の世界ですから」とおっしゃっていて、我々が思う修行とずいぶんイメージが違うことに気づかされました。
宇野さんがおっしゃるような、100mをどれくらい速く走れるかとか、42.195kmを2時間で走れるかとか、そういった競技のために走るという世界にばかり囚われてしまうと、走るということが元々もっていた多様性を見失ってしまうんですよね。
宇野 「走る」というモチーフがいいなと思った理由がもう一つあって、SNSのタイムラインの潮目を読んで大喜利しているような人たちは、乗り物に乗って移動しているようなものだと思うんですよね。彼らは、自分の意思で速度や進入角度を決定することができない。僕は散歩も好きなんですが、歩くというのは基本的には一つの駅前、一つの街を深掘りするのに向いていて、歩くだけでは街と街のつながりや、そのエリアの地理を体感するのには向いていないんです。普段は歩いているんだけど、時々走るという瞬間があったほうが、思考は広がっていくと思うんです。
これまで僕たちは、基本的には乗り物に乗って移動して、時々歩くことで思考のバランスをとってきた。でも、そこに走るという第三項を挿入したいと思っています。「遅いインターネット」はそれを実践をしたいと思って言い出したことでもあるんですよ。
茂木 宇野さんのおっしゃる「勝手に走る」というアプローチは、僕も好きです。僕はもともとメキシコのタラウマラ族という人たちが好きなんですが、『BORN TO RUN』という本の中で書かれているエピソードがすごく良くて。彼らはとうもろこしのビールを飲んでてヘラヘラして、突然「走るか!」と言って何百キロも離れている集落へ向けて走り出すという、よくわからない人たちなんです。
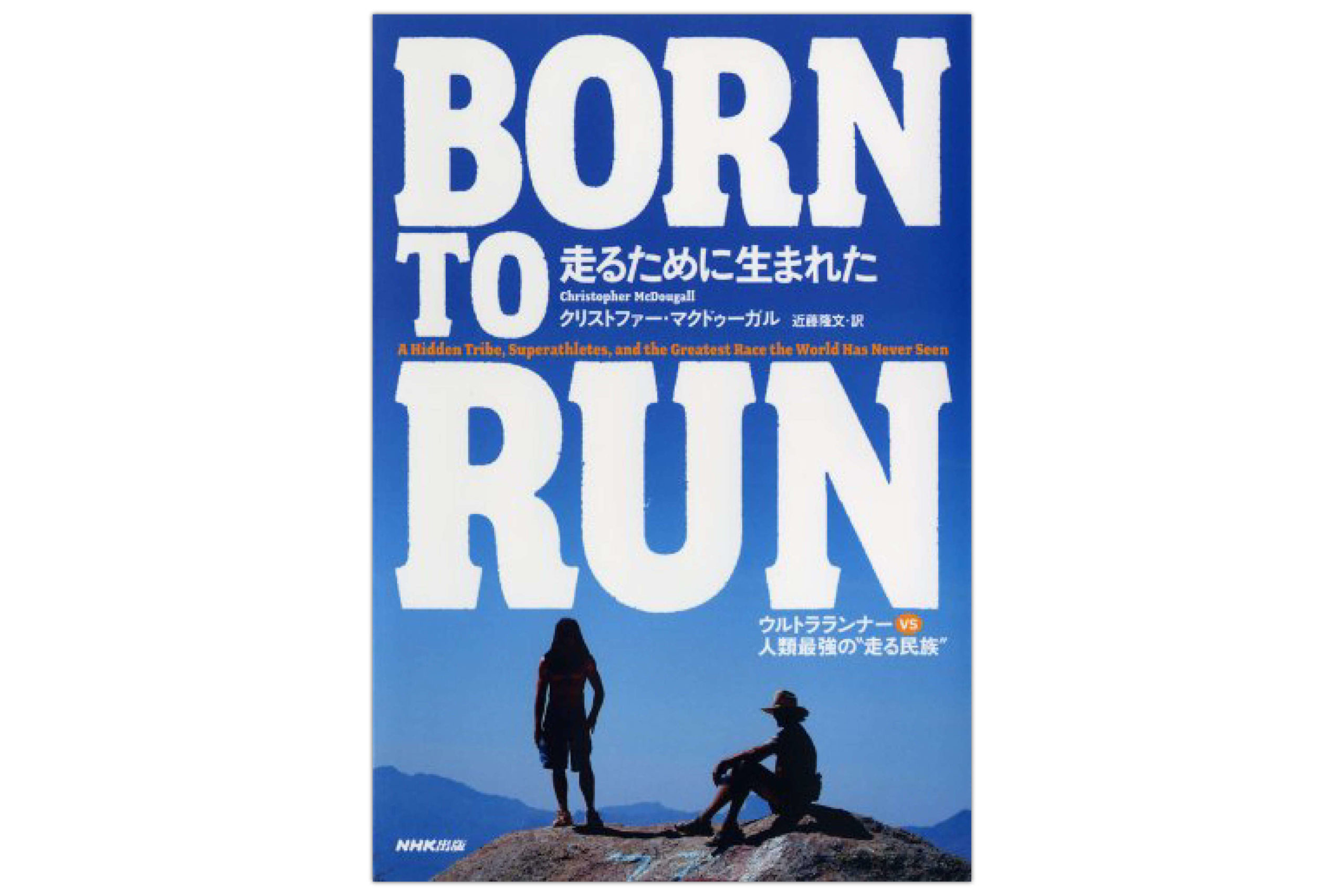
あと、たとえばアフリカの人たちが野生動物を追いかける時に、人間より野生動物のほうが速いのでなかなか捕まらないんですが、人間のほうは2日も3日も追いかけることができるので、野生動物が諦めて止まったところを捕まえる、ということがあるらしいんですが、僕はそういう走るというメタファーが大好きなんです。
宇野 そう、「勝手に走る」というのは、この情報社会と一人ひとりがどんな速度や進入角度で向き合うか、ということのメタファーなんです。
ここで大事なのは、速くあるべきか遅くあるべきというよりも、速度を自分の意思で設定するということなんですよね。いま、出版を代表とするオールドメディアは遅くしか読めない。かといってタイムラインに流れてくるネットワーク上の情報は速くしか読めないわけで、人間は自由を失ってるんです。そうではない、人間が情報に対してのアプローチの主導権を取り戻そうという運動が、僕は大事だと思ってるんですよね。それが乗り物に乗るでもなく、歩くのでもなく、走るということなんです。
茂木 脳の回路でいうと、ジョセフ・ルドゥーという人が研究しているんですが、速い回路は、感情の回路なんです。一方で遅い回路は、大脳新皮質の理性や記憶、熟慮のときに働く回路なんですよね。速くはたらく感情の回路と、ゆっくり立ち上がる理性や記憶の回路が両立することで、初めて脳のアーキテクチャとしての機能が保たれていると言います。先ほど出てきたダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』とも関係するんですが、要するに両方とも、人間の脳にとっては速いのも遅いのも、大事な回路なんですよね。
でもいまのメディアとか社会の状況を見ていると、あまりにも速い回路だけが優勢になってしまっている。今回のCOVID-19のパンデミックでは、そのことが改めて浮き彫りになりました。
宇野 この状況は、当面続くと思ったほうがいいと思います。このウイルスを退治しても似たようなものが新たに出てくる可能性は高いし、世界が一つの原理で動いという状態は絶対に同じようなリスクをもたらします。やはり長期的には、物理的にも情報的にも、密集型ではなく分散型にしていくしかないということが、改めてわかったわけです。
今回のコロナ禍は、大局的には安易なインフォデミックの拡大をもたらした一方で、孤独と向き合ったり勝手に走ったりする経験になった人も少なくなかったはずです。その後者の側の気づきを、どれだけの人が持ち帰れるかが、いま問われているのだと思います。
[了]
この記事は石堂実花と中川大地が構成し、2020年6月8日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。





