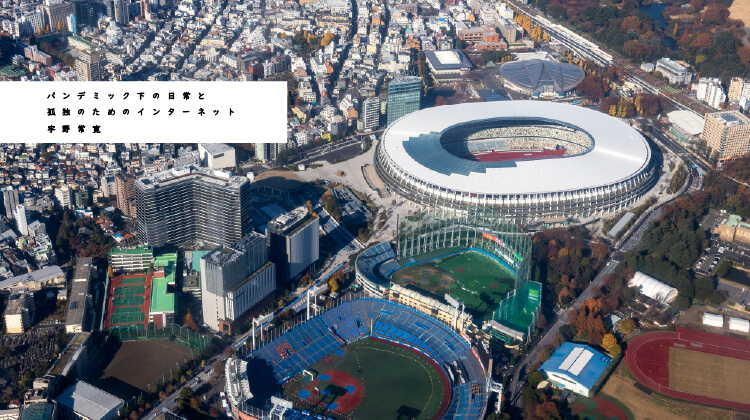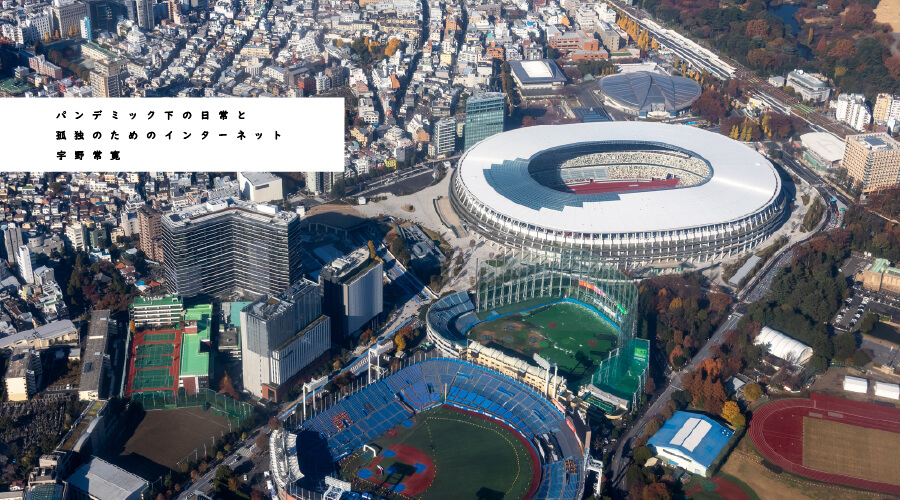ウイルスに破壊されてしまったオリンピック
そもそもほとんど高田馬場から出ない生活だったのだけれど、緊急事態宣言が東京に出る少し前からほとんど外出しなくなってしまった。そんな中で、朝のランニングは黙々と続けている。大体の場合は自宅のある高田馬場から走りはじめて、明治通りを南下する。そのまま新宿を過ぎて、北参道の交差点を左折し、しばらく走ると右手に新国立競技場が見えてくる。本来ならば、この2020年の夏に二度目の東京オリンピックを迎えていたはずの、あの新国立競技場だ。僕はこのオリンピックには基本的に反対で、いつも走りながらこの競技場の巨体を眺めてはこんなものは壊れてしまえばいい、とテロでこの競技場が破壊される姿を妄想していた。
2020年4月現在、神宮外苑の新国立競技場の周辺は奇妙な静けさに包まれている。この地区には新国立競技場を筆頭に神宮球場や、アイススケート場などさまざまな施設があって休日は家族連れやカップル、あるいは僕のようなランナーでそれなりの賑わいを見せている。しかし、この1ヶ月は休日でもすっかり家族連れやカップルの姿は消えて、ランナーの姿もめっきり減った。平日の朝にいたっては、ほとんど人とすれ違わないゴーストタウンの様相すら呈している。都心には珍しく神宮外苑の付近には高層建築がないので、とても日当たりが良い。4月の後半になると、初夏めいた気持ちのいい明るい日差しの降り
自宅から走りはじめると、新国立競技場の北向かいにある神宮外苑アイススケート場の前で5キロになるので、僕はいつもそこで折り返す。閉鎖中のスケート場の入り口には、大きなモニターが設置されていて広告映像をエンドレスで映している。少し前までは、オリンピックに向けてこの東京の街をアピールするものがよく流れていた。僕の記憶では、このモニターにはつい最近まで都心でよく目にしていた東京オリンピックをテーマにしたイメージビデオが流れていたはずだった。それは歌舞伎や人形浄瑠璃といった伝統文化と、初音ミクやPepperといった現代文化が対比され、古い伝統と最新のテクノロジーが融合した東京という都市をアピールするものだ。映像の内容はもしかしたら別のものだったかもしれないけれど、とにかく東京オリンピックをテーマにしたその類のものが流れていたのは間違いない。そして僕はこの映像を目にするたびに、なんだかこっ恥ずかしい気持ちになっていた。その場にいる全員が退屈してスマートフォンをいじっているのに、ノリノリでザザンオールスターズのナンバーを、それも中途半端な上手さで歌い上げる熟年管理職(付き合わされているのは若い部下たちだ)の姿を目にしてしまったカラオケボックスの店員のような気持ちにさせられていた。しかし空回っていたものが恥をかく機会すら与えられず根本からひっくり返されてしまった今は、どちらかと言うと気まずさではなく寂しさを感じている。無人の神宮外苑はただただ静謐だ。そしてその本来あってはいけない静謐さが、明るい、そしてそれゆえに薄ら寒い不気味さを醸し出しているのだ。
もうひとつの東京五輪
僕はオリンピックがウイルスによって破壊されてしまったこの現実に対して、とても複雑な感情を抱いている。なぜならば僕自身がこの2020年の東京オリンピックに対して、極めて批判的な立場を取り続けてきたからだ。
「失われた30年」を直視することに背を向け、国威発揚を目的に極めて安易に誘致された2020年の東京オリンピックの開催に対し、僕は一貫して反対だった。首都高速道路から東海道新幹線まで、高度成長を支える首都と国土の整備のための錦の御旗でもあった1964年の東京大会と比べても、2020年大会が向こう半世紀を見越した計画はおろか、事実上の無コンセプトであることは明白だった。
そして僕は反対だからこそ、魅力的な対案を示すことにこだわった。「うっかり呼んでしまったオリンピックのダメージコントロール」に終始していると言わざるを得ない現行案に対し「自分たちならこうする」というもう一つのオリンピック開催案を一冊にまとめたのだ。それがオルタナティブ・オリンピック・プロジェクトだった。
▲【特集】東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト再考
だから僕たちはこう考えた。2020年のオリンピックは、これから来るべき社会の「かたち」を象徴的に提示するものであるべきだ。そしてその来るべき社会の「かたち」とは人間が「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」社会だと考えた。モニターの中のアスリートたちの活躍に、同じ日本人であるという理由で国民たちが感情移入し、社会がひとつになる。しかし人間の心が社会という単位でひとつになることには、極めて強い副作用が伴うことを人類は20世紀までの歴史で、嫌というほど思い知っている。しかし、僕らはそれでも他人とつながり、社会を維持しなければならない。だから僕たちは心を一つにすることなく、ばらばらのままつながる社会を実現できないか、と考えたのだ。いま、僕たちが求めているのは、人間の心を支配して一つにまとめなくても、社会の規模を維持すること=「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」ことだ。
だからこそ、僕たちは徹底してこのコンセプトからあらゆるプランを練り上げた。開会式の演出に、街頭の市民が参加する案を考えたのはアスリートという他人の物語に感情移入するよりも自分が「参加」することで、あくまで「自分の物語」としてのオリンピックにすることが重要だと考えたからだ。一人ひとりが、それぞれの「自分の物語」を発見する。それは夏の日に家族で夕涼みに街に出る楽しさでも、彼氏との初デートの思い出でもいい。他愛もない「自分の物語」の一つとして、街頭のデジタルアートに触れてグラフィックが変化する。この変化が競技場で行われるオープニングの演出に反映される。こうして、僕たちは「ばらばらのままつながる」ことができる。そう考えたのだ。オリンピックとパラリンピックの境界線をなくす新しいゲームを考えたのは、近代スポーツの持つナチス的な「五体満足主義」を解体したかったからだ。そうすることで、「みんな同じ」「標準」が正しくて、そうではないものが排除され、周辺に追いやられる社会にNOを突きつけて、人間は「ばらばらでいい」存在だというメッセージを出したかったからだ。
どうせやるなら、オリンピックは未来への青写真であるべきだと、僕たちはこのとき確信していた。この決して採用されることのない対案をこのタイミングで示し、後世に残すことがこの国の、そして世界の人々にとってこれからの社会を考える上で必ず役に立つという確信があった。
そして現在(2020年4月30日)、パリ、ロンドン、ニューヨークといった各国の大都市は軒並み封鎖状態にある。この東京も、非常事態宣言が政府によってなされ、従順な国民たちは外出を大きく「自粛」している。不要不急の外出の自粛が呼びかけられ、多くの企業や団体が出勤を制限しリモートワーク主体の業務への切り替えを余儀なくされている。集会やライブイベントの大半が中止され、飲食店の多くが営業を停止している。そう、いま世界中の都市に暮らす人々が、自宅に縛り付けられている。必要最低限以上に人と会うことを望まれない社会が急速に広がっている。しかし、それでは社会から活力と豊かさが失われることは自明だ。ではどうするべきか。僕たちはこの状況に抗うためにこそ、「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」知恵を発揮するしかない。皮肉な話だけれども、僕たちが当時「オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト」で訴えた「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」社会の必要性は、2020年の東京オリンピックではなくそれを破壊した新型コロナウイルスの世界的な流行によって否応なく認識されつつあるのだ。
パンデミックと憲法9条
しかし パンデミックは、二者択一を迫る。そのことで「ばらばらのものを、ひとつにまとめる」ことを要求する。安全か、それとも自由か。国家の監視と統制を受け入れるか、それを拒否してリスクを受け入れるか。大衆は前者を選ぶだろう。多くの社会は、民主主義という制度に支持されて監視と統制を受け入れるだろう。この国でも、パンデミックに対する社会不安を背景に超法規的な国家による行動規制を求める声が多い。そしてこの選択を、ウイルスへの感染リスクも社会的混乱のもたらす経済的損失のリスクも相対的に低い文化人や大学人、マスメディアなどが批判することに、残念ながら多くの人々は説得力を感じない。彼らが生命の危機のリスクを受け入れて、自由を守れと述べたとき、そのリスクを引き受けるのは彼らではなく階層的に分断された人々であることは自明だからだ。僕は現時点(2020年4月)においては、ある程度の監視と統制は不可避であると考えている。しかしその一方で多くの人々は、監視国家的なアプローチに対するこのなし崩し的な肯定のリスクを、低く見積もり過ぎていると考えている。
このパンデミック下で進行しているのは、(あえて大げさな表現を用いれば)世界的なデジタル・レーニン主義への接近に他ならない。そして西側諸国の極めてソフトなデジタル・レーニン主義への接近傾向は、パンデミックの以前からはじまっていたものだ。GAFAをはじめとするインターネット・プラットフォーマーの台頭が代表するグローバルな市場とローカルな国家との対立は、当面重商主義的な歩み寄り以外の解を持たない。それは言い換えれば程度の問題があるだけで、それがソフトなデジタル・レーニン主義への軟着陸であることは自明だ。僕が「遅いインターネット」という言葉を掲げて、グローバルなインターネット・プラットフォーマーへの批判と、草の根的な離脱運動を提唱した背景の一つがここにある。
では、どうするのか。僕の回答は監視が不可避であるならば、その監視が自由を侵害しないための知恵を絞るしかない、というものだ。具体的には防疫のために取得された個人の情報のそれ以外の目的への本人の同意のない参照の禁止、「忘れられる権利」の保護、自分のデータにいつ、誰がアクセスしたのかが記録され、追跡可能にすること、そしてこれらを可能にする情報環境と法の整備が暫定解だ。ここにはインターネット初期の電子公共圏のための試論から、電子政府の導入に際する実務的なものまで、膨大な議論の蓄積がある。そもそも、国民総背番号なくして行政の電子化と効率化はあり得ないし、治療医学から予防医学へのシフトは生権力そのものである身体のリアルタイム管理(監視)を前提とする。すべてはコロナ禍以前からはじまっていた問題の表面化に過ぎないのだ。そして、誤解してはいけないが、ここで述べられているのは技術的な解決ではなく、既に存在している技術をどのような倫理に基づいて応用するかを問うアプローチで、つまり極めて人間的な、政治的な領域での解決が必要なものだ。
この国では民意を背景にルールを有名無実化することを、むしろ清濁を併せ飲む柔軟で、成熟した運用として評価するという考えが、いつの間にか支配的になっている。その象徴が憲法9条の問題だ。護憲/改憲による戦後民主主義の精神の護持/戦後レジームからの脱却という「建前」となし崩し的な解釈改憲という「本音」の対立を装った共犯関係に、無関心という名の民意が消極的な支持を与える。この消極的な民意の支持が、パンデミック下の社会不安を背景に積極的な民意に切り替わろうとしている。そして、民意の支持を背景にした、ルールの有名無実化は歴史が教える通り、ポピュリズムと全体主義の温床以外の何者でもない。既存のルールが現実に対応できなくなったとき、ルールを有名無実化して運用レベルで骨抜きにするか、ルールそのものを現実に適合したものに改変するか。パンデミックの終息後、僕たちはより切実にどちらかの選択を迫られるはずだ。危機の時代には前者が緊急避難的に選択され、それを今日のインターネット・ポピュリズムに翻弄される民主国家は止めるすべを持たない。だからこそ、僕は後者こそが長期的なリスクの低い選択肢であることを主張し、平時のうちに実現させる必要があると考えるのだ。(僕が5月5日に「いま、あえて」憲法を考える会を主催したのは、そのためだ。)
オリンピックから「風の谷」へ
オリンピックから憲法まで、僕たちはいま、急速に「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」知恵を求められている。誤解しないでもらいたいが(批判しやすいように、意図的に誤解したがる人は多いだろうが)もちろん僕はスイッチのオンとオフが切り替わるように、このパンデミックによって「ばらばらのものを、ひとつにまとめる」中央集権的な社会から、「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」自律分散的な社会に切り替わるとはまったく考えていない。僕は都市にせよ、メディアにせよ、中央集権的なシステムを手放せないからこそ自律分散的なオプションを用意し、いつでもこのカードを切れるようにしておく必要があると考えている。このパンデミックがその必要性を認識させたのは間違いない。しかしこれは決してこのパンデミックによってはじめて浮上した課題ではない。たとえばインターネットが世に普及しはじめたころには既に、地域コミュニティからテーマコミュニティに人間が等身大の生活のレベルで所属する共同体の基礎単位が変化する(あたらしく加わる)という問題が議論されていたはずだし、近年ではブロックチェーン技術を背景にした暗号通貨の普及が、自立分散的な小さな経済圏の乱立を生む可能性について注目されている。
僕が「遅いインターネット」で、FacebookやTwitterなどのグローバルなSNSに支配された現代のインターネットを批判したのは、それが(たとえば日本のTwitterのように)ボトムアップの全体主義として社会を一つの「ムラ」にしてしまう傾向があるからだ。僕たちはインターネットによって、誰もが同じ話題に関心を持っていなくても社会を維持できるようになる可能性を手にしたはずだった。しかし、僕たちは自らその可能性を手放して、気がつけば週刊誌とワイドショーの与えた話題で全国規模の大喜利をすることに(それも大抵の場合はいまならこの人物を貶めて良い、という潮目が形成されたターゲットへの集団リンチをすることに)夢中になってしまっている。「遅いインターネット」はプラットフォームによって、擬似的に中央集権的なかたちに歪められたインターネットを自律分散的なものに、ユーザーの側から読み替える運動でもあるのだ。
そして、この「ばらばらのままつながる」モデルは、このコロナ禍によって、サイバースペースの理想から、実空間設計のオプションとして認識されつつある。僕は2年ほど前から、安宅和人さんの主催するあるプロジェクトに参加している。この「遅いインターネット」でも継続的に取り上げているので、既に知っている人も多いはずだ。「風の谷を創る」というこのプロジェクトは、都市という人間の空間利用のかたちのオルタナティブをつくるための運動だ。詳細は安宅さんによるこの記事や、僕のこのエッセイを読んで欲しい。
そして現在進行中の世界的なパンデミックに対して、安宅和人さんは社会の「開疎化」というキーワードを提出している。密閉的なものから、開疎的なものへ。これから僕たちの社会は基本的な仕組みを作り変えていくことになる。現行のSNSのプラットフォームによる寡占的な支配は、本来自律分散的なものであるインターネットを擬似的な中央集権的なものに組み替えている。「遅いインターネット」がこの状況からの離脱とオルナタナティブの提示をユーザーの側から仕掛ける運動だとするのなら、「風の谷を創る」は都市というこれまでの歴史で人類が選んできた密閉的な空間利用そのものを見直す運動だ。言い換えれば、「風の谷を創る」はかつてのインターネットが掲げた「ばらばらのまま、つながる」理想を実空間に応用し、都市という制度のオルタナティブを獲得するプロジェクトなのだ。21世紀に、特にアジアを中心に予測されている1000万人超のメガシティを中心とした社会は、言ってみればSNSのプラットフォームへの集中が常態化した今日のインターネットのようなものだ。この流れは普通に考えれば不可避だ。しかし本当にそれ「だけ」でよいのか。「風の谷を創る」プロジェクトは、安宅さんのそんな「直感」からはじまった。そしてその直感が正しかったことを、この2020年のコロナ禍は結果的に証明してしまったのだ。そして僕個人としても、オルタナティブ・オリンピック・プロジェクトから「遅いインターネット」計画、そして「風の谷を創る」という三つのプロジェクトは一直線につながっているのだ。
「動員の革命」が挫折したそのあとに
街頭から人の姿が消える──この現実は、一つの時代の終焉を感じさせる。今から10年近く前、SNSが普及しはじめたとき「動員の革命」という言葉が生まれた。新聞やテレビというマスメディアを介したトップダウンの動員に対して、SNSの普及は市民一人一人の自発的な発信の連鎖が生むボトムアップの動員が可能になる。この「動員の革命」こそが、あたらしい民主主義の起爆剤になるだろう。「動員の革命」はこうした期待を込めた言葉だった。
マスメディアによるトップダウンの動員に対して、SNSによるボトムアップの動員はその動員力そのものは劣るものの、参加者のより強い没入をもたらす。マスメディアのそれが他人の物語への感情移入にあるのに対し、SNSのそれは自分の物語の発信だ。そして人間は、ロマンチックな他人の物語を受信するよりも、それがどれほど凡庸で陳腐なものであったとしても自分の物語を発信することに強い快楽を覚え、世界に素手で触れる感触を手にするのだ。「アラブの春」から、東日本大震災後の反原発デモまで世界を席巻した「動員の革命」──それは、決して市民運動に留まる現象ではなかった。CDの販売からフェスへの動員への音楽産業の収益構造の変化、「観る」アニメから「推す」アイドルへの国内サブカルチャーの中心の移動、すべてそうだ。そもそも2010年代とはSNSによって、人間が非日常に動員され続けた時代だったのだ。そして、2010年代はモニターの中の他人の物語に感情移入する時代から、自分の物語をモニターの中に発信する時代へ切り替わった時代だったのだ。
しかし突如として襲来した新型コロナウイルスによって、「動員の革命」は遮断された。もちろん、この世界中の街頭から人影が消えてしまった時間は長くは続かないのかもしれないし、続かないほうが間違いなく「よい」。それはウイルスによる一瞬のテロリズムのようなものなのかもしれない。しかし、このテロは少なくともこの一瞬だけ、僕たちが前提としていたものの中に潜んでいた落とし穴を明らかにしたことは間違いない。そして、残念ながら再び街に人々が戻る日がいつ来るかも分からないし、第二、第三のパンデミックがいつ襲ってくるかも分からないのだ。
多くの人は、こう考えるだろう。僕たちはこれまでの暮らしを取り戻すべきだと。再び街頭には人が溢れ、握手を交わし、酒場で祝杯を上げるべきだと。もちろん、僕も「半分は」そう考えている。今すぐに、魔法的な技術が実用されて、新型コロナウイルスの驚異から人類は解放されれば、どれほどよいかと思っている。しかし、その一方でこう「も」考えている。このパンデミックは、「動員の革命」の崩壊は、僕たちに自分の足元を見つめ直す大きな機会を与えているはずだ、と。
あらゆる人間に発信力が付与された今日において、人々は動員された非日常での体験を「自分の物語」として発信する。それは、モニターの中の「他人の物語」を受信するよりも強い快楽を、世界に素手で触れている感覚を与える。2010年代は、SNSによってもたらされたこの快楽が高い動員力を発揮し、人々を街頭に、フェスに連れ出していった。しかし、僕は思う。本当のそこは「外部」だったのだろうか。そして動員されることで、人はほんとうにより考えるようになったのだろうか。
僕は外部に出ることの価値をまったく否定したいとは思わない。人々が外部に接することの価値は、出会いにある。自分が選択したものではない事物に偶然触れ、そのことで変化が訪れる。目当ての本を買いに本屋に出かけて、偶然目にした本を衝動的に買って帰る。このインターネットにはまだ補えない機能を、街頭に出ることはまだ保持している──それは当たり前のことだ。しかし、僕は問いたい。この10年のあいだ、SNSによって動員されたそこは本当に「外部」だったのか。偶然目に映り、耳に入るものに溢れた出会いの場だったのだろうか。
僕には、そうは思えない。SNSによって動員されたそこは、むしろ目に入れたいものだけを目に入れ、耳に入れたいものだけを耳に入れる場所ではなかったのか。SNSによって動員されたそこは、閉じた相互評価のネットワークの一部で、完全に内部に取り込まれた場所だったのではないか。ほとんどの人が、外部に、街頭に出ているつもりで実は、SNSの延長でしかない閉じた人間関係の中に閉じこもっていたのではないか、と思うのだ。
たとえば結果から述べれば「動員の革命」とその背景となったSNSは、あたらしい民主主義の起爆剤になるどころか、むしろポピュリズムの拡大に加担しているのが現状だ。民主主義という個人の能力の高低にかかわらずすべての人々に平等な参加の権利を与える装置は、SNSという新しい武器を備えることで進化した。誰もが簡単に声を上げる力を得たことそのものを、決して否定すべきではない。しかしこの武器を有効に用いるためにこそ、その副作用に対して僕たちは目をつぶるべきではない。そして、SNSのもつあたらしい動員と没入のメカニズムは──人々を非日常的な自分の物語へと動員するメカニズムは──いま、一方では自分たちはマジョリティの、「普通」の、「まとも」な側であることを確認するための私刑を提供する場にあり、もう一方では見たいものだけを目に入れ、聞きたいものだけを耳に入れることで、精神を安定させたい人々にフェイクニュースや陰謀論という名の麻薬を与える場となっている。
あるいはそこが、古い日本的な企業や団体で行われてきた(いまも行われている)陰湿な「飲み会」的コミュニケーションの場であったとき、そこは本当に偶然の出会いをもたらす外部なのだろうか。その場の中心人物の気持ちに忖度して、その場にいない誰かを中傷して下卑た笑いが起こる。そうすることでメンバーシップが、友敵の境界線が確認される。それは、まさにSNSのように人間を閉じた総合評価のネットワークに閉じ込める場なのではないか。
僕たちは非日常に動員されることで実体が伴わなくても何かをしたつもりになっていた。たとえその主張が愚かなものや、悪をなすものであったとしても街頭に出ること自体に価値を見出してしまっていた。革命のあとにどのような社会をつくるのかの青写真とそれを実現する計画がなければ独裁者を倒しても、意味はない。絵葉書と同じアングルでセルフィーを撮り、史跡名勝を前にうつむいてWikipediaを引く観光旅行は手の混んだ読書に過ぎないし、結局SNSでの好感度獲得競争と同じように噂話と中傷合戦を居酒屋やイベントスペースで繰り返してもそれは結局閉じた相互評価のネットワークの内側の外部に立つことにはならない。
SNSの与えた「動員の革命」とは、言い換えれば誰もが当事者として「自分の物語」を発信する快楽を得られる環境に依存した動員だ。しかし、その結果多くの人々が街に出ること、発信すること自体が目的化してより「考えなく」なってしまった。
世界を見る目と歩く足腰が鍛えられていなければ、結局人間はどこに動員されても、問題そのものを直視することはできずに問題についてのコミュニケーション(閉じた相互評価ネットワークの中での好感度獲得競争)しか考えられなくなってしまうのだ。そう、「動員の革命」の少なくとも半分は、閉じた相互評価のネットワークの中に人間を閉じ込めてしまった。街頭をむしろ、何一つ出会えるもののない「飲み会」的な人間関係の輪の中に閉じ込めてしまったのだ。
閉じた相互評価のネットワークから離脱するための「孤独」の価値について
世界を見る目と、走る足腰がなければ、どこに動員されても結局出会えるものは一つもない。2010年代を席巻した「動員の革命」の副作用はそのことを証明しているのではないかと僕は考える。このパンデミックが終息したあと、ほとんどの人々はその記憶を払拭するためにむしろ、積極的に街に出るだろう。たぶん、僕自身もその一人だ。しかし、このパンデミック下のこれまでとは違う日常をどう受け止めたかで、そこで出会えるものの豊かさには大きな差が出るはずだ。ほんとうに外に出なければ出会えないもの何か、しっかりと考えておく必要があるはずだ。それがないと僕たちは街頭を言葉の最悪な意味で「SNSのような」場所にしてしまう。
だからこそ、僕は『遅いインターネット』という、ついこの間書いた本の中であくまで日常のレベルからのアプローチを取ることの必要性を訴えた。動員された非日常の場所で誰かに出会うためには、日常の中で既に世界を見る目と、歩く足腰が養われている必要があるからだ。僕は『遅いインターネット』では、僕なりのやり方で「読む」ことと「書く」ことの再定義と学習を一つの答えとして提案して、僕なりの実践を試みている(このウェブマガジンもその試みの一つだ)。そしてそれに加えて、僕がこの場で強く述べたいのは閉じた相互評価のネットワークから離脱するために、一度「孤独になる」ことだ。孤独に世界に向き合う時間をもつことだ。
だから僕は、いまこそ一度正しく引きこもるべきだと考える。同時に声を上げ続け、再び街頭に出るためにこそ引きこもる時間を大事にするべきだと考えている。いま、多くの人々が不安に抗うためにとりあえず誰かとつながろうとしている。不安に抗うためにとりあえず何かを発信しようとしている。そしてそのことが、フェイクニュースと陰謀論の温床となり、パンデミックを結果的に拡大させている。不安を解消するためにとりあえず誰かとつながり、何かを発信するのではなく、本当に必要なことについて声を上げるためにこそ一度しっかりと引きこもることが必要なのだ。
パンデミック下の新しい日常に、孤独に向き合うことは多くの気づきを僕たちにもたらしてくれる。
たとえば読書ひとつとっても、世相に食らいつくことを目的に話題の本に目を通すという作業から解放されて、長い射程をもつ読書の豊かさを久しぶりに体験した人も多いはずだ。また、行政の休業要請に応じて多くの飲食店がテイクアウトや出前での提供をはじめている。お気に入りのレストランの料理を自宅で食べられることに、飲食店の提供するプロの料理を自分で工夫して盛り付けたり、アレンジする楽しさにパンデミック下の数少ない楽しみを見出している人も多いだろう。このとき同時に多くの人々が外食でも、自炊でもない中食という選択が、ライフスタイルとワークスタイルに大きな幅をもたせてくれることに気づいたはずだ。
あるいはこうしている今、多くの人々が自宅でのリモートワークを試してるはずだ。実質的には上司や取引先に対する愚痴のシェアでしかなかった「会議」や「打ち合わせ」の不毛さや、成果ではなくメンバーシップに給料が支払われる日本的な企業のアンフェアな構造が次々と明るみに出ているはずだ。
いま多くの人がこの国の住宅のほとんどが、夫婦が在宅で仕事をすることはほぼ想定されていないことに気づくだろう。それどころか、いまだに昼間に専業主婦が在宅していて、かつリビングでソファに座り、テレビを観ることが生活の中心だという前提に設計されている。要するに半世紀近く前のライフスタイルが、今日においても「正解」としてスタンダードの座にあるのだ。不動産ポータルサイトがこの国で普及しはじめたころ、切り札として導入されたフリーワード検索がほとんど使用されず事業者はひどく落胆したという。このエピソードが象徴するように、僕たちは自分たちの「住まい」について、考える文化をほぼ失ってきたのだ。その背景には、家族や働き方の多様化に対して社会の仕組みがまったく追いついていないという現実が浮かび上がってくる。
そして何より、ウイルス感染のリスクに敏感にならざるを得ないこの状況によって、引きこもりの生活やリモートワークを支える側の人々と、それを享受する側の人々に大きな階層の断絶が横たわっていることにも改めて気付かされるはずだ。afterコロナ、withコロナのあたらしいワークスタイル、ライフスタイルはいま、階級的、業種的に生き延びていける人々が、生き延びてはいけないリスクを背負っている層に支えられることで実現していることは明らかだ。
この断層はコロナ禍以前から存在していたもので、パンデミックはそれを浮き彫りにしたに過ぎない。イギリスのジャーナリスト(デイヴィッド・グッドハート)の述べる「どこでも」生きていける「Anywhere」な人々と、「どこかで」しか生きていけない「Somewhere」な人々との断絶は、グローバル資本主義とそれに対するアレルギー反応(トランプ/ブレグジット)として既に世界中に噴出していたものだ。トランプが「壁を作れ」と叫んだように、時計の針を逆回転することは、実現不可能であり、そして仮にできたとしても問題は解決しない。あたらしいワークスタイルが、ライフスタイルが、この断層を超えて共有されるための(「政治的な」ものがおそらくは中心となる)知恵が、いま求められているのだ。
その一方で先日SNSを覗いていたら、昔からの仕事仲間たちが気炎を上げていた。彼らの多くは、出版や放送といったオールドなメディアにかかわる人々で、彼らはこう述べていた。afterコロナ、withコロナという発想は、よくない。僕たちはかつての生活を取りもどすべきだ、と。このコロナ禍を契機に社会の仕組みを変えるべきではない。こうした変化は、弱者の切り捨てにしか向かわないだろう、と。
この投稿に僕は、大きく首を傾げた。もちろん、社会の変化は既存のシステムに依存してる人々に不利に働く。この人たちの犠牲を必要悪として受け入れる社会は、人間を幸福にするという目的をそもそも見失っており、到底受け入れられるものではない。
しかし、その一方で彼らは忘れている。本当に今のシステムは自由で、平等なのだろうか。彼らはafterコロナ、withコロナの新しい社会は(特に検証もせずに)弱者を切り捨てるものだと断罪する。私たちは、Uber Eatsの配達員とヤマト運輸のドライバーにウイルス感染のリスクを押し付けて、新しい日常の豊かさを謳歌しようとしているが、それは欺瞞である、と。僕もそこは同意する。しかし彼らが「取り戻せ」と叫ぶ飲食店の配膳係や、劇場のもぎりの存在はコロナ禍以前のシステム下で既に彼らに搾取されていた「弱者」ではなかったのだろうか。
当たり前のことだけれども、低所得者がリスクの高い職業に流れてしまうことは福祉と再分配の問題であって、Beforeコロナ(たとえば外食中心の都市生活/オフィスワーク)とafterコロナ(中食やリモートワークという選択肢がそこに加わる)のどちらが豊かな社会かという問題とは、基本的に別問題だ。しかし彼らはコロナ禍が既存のシステムを大きく変えてしまうこと自体をその内実を検証することなく否定したい、という願望に負けてこのふたつの問題を混同してしまっている。変化を恐れ、憎むあまりに、既存のシステムの問題を都合よく忘却してしまっている。
僕はコロナ禍で結果的に表面化する所得格差の問題や、社会の分断に対しては積極的にケアをすべきだと考えている。しかしそれは、afterコロナ、withコロナという視点から既存の社会の問題点を改善していこうとする考えと何ら矛盾しない。
このパンデミックが僕たちの足元を照らし出し、そして既存のシステムの弊害を浮かび上がらせるのならば、それは正しく改善されるべきなのだ。僕は、どちらかといえば既存のシステムで甘い汁を吸っている側の古いマスメディアの周辺にいる人たちが安易にすべてをもとに戻せと述べることに、言ってみれば欺瞞を感じる。僕には彼らが、自分たちが豊かで安全な側にいられるいまの世界をそっとしておいて欲しい、と言っているようにしか思えなかった。
そして彼らは、彼らが批難するafterコロナ、withコロナの社会を急進的に構築すべきだと主張する/にもかかわらず社会のソフトなデジタル・レーニン主義への接近のリスクに無自覚な人々と、その主張こそ表面的には正反対だけれども、まるでコインの裏表のように実質的に同じような安易さに陥っているように思うのだ。
もちろん、人類は一刻も早くこのウイルスに打ち勝って、失われたものを回復すべきだ。しかし、ここで忘れてはならないことがある。それは、パンデミック前の日常は、本当にすばらしいものだったのだろうか、ということだ。
僕は一刻も早くまた、深夜のバルト9で映画を見て、歌舞伎町の「いわもとQ」で蕎麦を食べて帰る夜を取り戻したいと思う。毎年この季節には、仲間たちと三浦半島に出かけてバーベキューをして、そして夜はホタルを見る。今年は無理そうだけれど来年は必ず行きたいと思っている。しかし、その反面、こうも思う。前述したように実質的には上司と取引先に対する愚痴の類である「会議」や「打ち合わせ」の類は消滅するべきだし、成果ではなくオフィスへの滞在時間が評価される働き方の仕組みを呼び戻すのも疑問だ。21世紀の今日に判子を押した書類を物理的に提出する文化は問題外だし、あの非人間的な通勤ラッシュを感受する社会を「取り戻す」気には到底ならない。友と敵を確認することを裏目的にして、気がつけばその場に居ない誰かの悪口大会になりがちな「飲み会」文化の不毛さと陰湿さも、これを機会に見直されるべきなのだ。かつての生活の何を残し、何を改めるのかを見極めること。それが今求められていることなのだ。
これらはすべて、コロナ禍の、パンデミックのはるか以前から存在していた問題だ。ただ、僕たちが閉じた相互評価のネットワークの中で誰かの顔色を伺うことにばかり気を取られていて、問題そのものではなく問題についてのコミュニケーションに気を取られることでそのことに気づかなかっただけなのだ。
しかしこうした他愛もない日常の再発見を重ねることで、それを(閉じた相互評価のネットワークの中で「シェア」するのではなく)しっかりと考えることで、世界を見る目と走る足腰を手に入れることにつながっていく。こうして自分たちの日常の足元について考える力を養うことで、自分たちの半径5メートルの生活と世界経済や民主主義といった普段は遠くに感じている問題とをつなげることができる。しかし。閉じた相互評価のネットワークの内部で、他の人間の顔色をうかがうことに夢中になっていると、この回路が閉じてしまうのだ。僕たちがいま、しなければならないのは不安を「つながる」ことで誤魔化すことではなく、こうして日常が変化したことではじめて見えてくるものに対峙することなのだ。僕たちはいま、正しく引きこもることで、世界を見る目と歩く、いや「走る」足腰を養うべきなのだ。
僕たちが外部に触れて何かと出会うとき、その相手をつい、人間に想定してしまいがちだ。しかし人間という社会的な動物は厄介な存在で、うまく距離感と進入角度を調整して触れないと、たちまち閉じた相互評価のネットワークの中に取り込まれてしまう。そして、自分で考える力を失う。だから僕はときには孤独に、人間「ではない」事物に触れることが重要だと思う。それはモノであっても、場所であっても構わない。人工物であっても、自然物であっても構わない。他の人間と対話することではじめて見えるものがあるように、人間「ではない」事物に、孤独に触れることではじめて見えてくるものもある。僕たちはいつの間にか、閉じた相互評価のネットワークの中に閉じ込められることで、そのことを忘れてしまっているのではないかと思う。そしてその忘れ去ってしまったものが大きすぎるために、非日常へ動員され、より強固に閉じた相互評価のネットワークの中に閉じ込められ、考える力を失ってしまうのだと思う。
こんな話がある。人間などの動物とは異なり、ある種の植物は生殖のために昆虫などの自分たちとは同種ではない存在を誘惑する。その異種を誘惑するための器官が「花」だ。僕たちがいま、必要なのは人間同士をつなぐネットワークの中での、人間からの評価を得るための思考ではなく、人間「ではない」ものについて考えること、「虫」を誘惑するための「花」のようなアプローチなのではないか。それがウイルスという人間「ではない」ものの脅威にさらされた人間にとって欠けてはならないアプローチなのではないか。ウイルスによって絶たれた人間同士のつながりを回復することで、ウイルスに対抗するのではなく人間以外のものとつながることでウイルスに耐えられる社会を獲得する。この知恵を得たときに、人間同士のつながりもまたより強固で、建設的なものとして蘇るはずだ。
[了]
この記事は2020年5月11日に公開しました。
Banner Photo By northsan / PIXTA(ピクスタ)
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。