みんなで集まって一緒に遊ぶことが、いろいろ難しい世の中になってしまいました。これまでのように羽目を外せないことに、フラストレーションを溜めている人も多いかもしれません。けれども心配ご無用です。当代きっての遊びの達人・AR三兄弟の川田十夢さん、ゲーム研究者の井上明人さんをお招きし、本誌編集長と副編集長で寄ってたかって、世界がこうなってしまったからこその「新しい遊び」を、徹底的に考えました。さあ、一緒に(ならずに)あそびましょう!
本記事をはじめ、「遅いインターネット」では「遊び」とエンターテインメントの現在と未来について、いろいろな切り口から特集しています。
端的に言うとね。
「みんなで一緒に」楽しむエンタメの危機に
中川 今日は皆さんと、これからの「新しい遊び」やエンターテインメントについて考えていければと思います。
2020年になってからというもの、このコロナ禍でオリンピックは流れるし、音楽ライブやコミケみたいな大規模イベントは軒並み中止だし、新作映画もかからないし、エンターテインメント産業全体が、もう踏んだり蹴ったりな状況になってるわけじゃないですか。
もちろん家庭用ゲームとかNetflixみたいな映像サブスクリプションサービスとか、インドア系のエンタメにはむしろ追い風になってるとは思うんですけど、これだけ自粛ムードで不要不急の外出を咎められたり、夜の街に繰り出したりすることが目の敵にされたりするようになると、やっぱり多くの人々の実感として、「遊ぶ」ことそのものに対するマインドが萎縮してしまっていると思うんですよね。特に5月の緊急事態宣言中あたりは、僕の行きつけのバーなんかは近所に咎められないよう、光が外に漏れないようにこっそり営業するというふうに禁酒法時代みたいなことになってたし(笑)。
だから僕らは、今までの社会で支配的だった「遊び」が、いろいろな意味で難しくなりつつあるいま、これを機会にした新しい遊びかたとか、そもそも遊びって何なんだろう、というところから見つめ直していく必要があるんじゃないか。そんな話ができたらなと思います。
宇野 僕から少し補足すると、2010年代の10年間はとにかく人類がSNSによって「動員」されていた時代だった。政治的には「アラブの春」からはじまるSNSの動員を前提とした街頭デモが存在感をもった10年だったと総括できるし、文化的にもたとえばCDの販売からフェスへの動員へ、国内音楽産業の収益構造が変化したり、アニメからアイドルへオタク文化の中心点が移動するというかたちで、同じような現象が起きていたと言える。
要するに、この10年僕たちはSNSによって家の外に動員され続けて、出かけた先では情報技術で「拡張」された現実を楽しむことに夢中になっていた。
これは別に技術としてのARに触れているということではなく、スマートフォンという基本的にインターネットに常時接続されたコンピューターを持ち歩くことによって、常に情報の付加された現実を遊んできたということです。比喩的に言えば、Google Mapで検索した経路を移動した場所でInstagramに「映え」るセルフィーを撮ってハッシュタグをつけて投稿することを楽しみにしてきた。これが情報技術によって「拡張」された現実の楽しみ方だったのだけど、ところが、2020年代の幕開けとともに発生したコロナ禍によって、この流れに一言で言えば「水が差されて」しまった。では、このあと僕たちはどうするのか、ということですね。
中川 まず、コロナ禍前後の皆さんの遊び方についてお伺いしていけたらと思うんですが、川田さんの場合はどうですか?
川田 音楽のエンターテインメントでいうと、最近僕、長渕剛さんと仲良くなったんですよ。たっての希望で番組にお呼びしたら、すごく共鳴・共振しました。

▲川田十夢さんナビゲーターのJ-WAVE「INNOVATION WORLD」にゲスト出演した長渕剛さんと感激のツーショット! 2週にわたってオンエアされました。
宇野 ちょっと待って(笑)。そもそもなんで長渕さんを呼んだんですか?
川田 僕が小学6年生くらいの時に『とんぼ』というドラマをやってたんですが、その中で長渕さん演じる主人公の英二が、最終回で背中を刺されて街中でぶっ倒れるというシーンがあるんです。で、背中にある神経をやられちゃってるから手が動かないんですね。だから吸ってたタバコが地面に落ちちゃってるんだけれど、街の往来のなかで倒れたまま口からもらいにいくっていうシーンがあって。
それを僕は覚えていて、友達と外で遊んでるときに急に街中でやる「『とんぼ』ごっこ」という遊びを自分で考えてやってたんですよ。それがけっこうまわりで流行ったし、それが僕の中で新しい遊びを発明した初めての大ヒットだったなって(笑)。

中川 AR三兄弟の原点は長渕だった! コツコツとアスファルトに刻んできてたんですね。
川田 長渕さんって特殊な存在で、ドラマの主人公を演じて主題歌を歌うって人はあんまりいないじゃないですか。それで、何かお話してみたいなと思ってお呼びしてみたら意気投合しちゃって。いま僕、長渕さんのコンサートとかの配信を準備してるんですけれど、そのブレーンをチラッとやらせてもらってるんです。
宇野 もうすぐ、拡張現実としての長渕剛がやってくるわけですね。
川田 そうそう(笑)。やっぱり、コンサートしていたものをただ配信するのでは、アーティストの長渕さんみたいな人からすると物足りないんですよね。それをいかに補完しようかというのを、まさに今やろうとしてて。
昔から、あの人のコンサートって特殊で、お客さんに照明を当てるんです。最初に武道館でやったときも、まずお客さんに光をあてて「おまえらが(俺を武道館に)つれてきてくれてありがとな」って言うんです。最初から双方向なんですよ。そういうことをやっている人が、今コロナ禍でどうやって立ち回っていくのか、アドバイスしながらも、文字通り会議とかでとなりにいて、そこでどういう発言をしたり、何に嫌悪感を抱いているのかを観察しているんですけれど、すごくおもしろいです。
やっぱり、手を上げさせたりすることとかもオンラインだと遅れちゃう。ウェブ会議みたいにお客さんの顔を映してやってもリアクションが遅れちゃうんですよね。そういうのをいかに技術的に解決するかもあるし、もうコンサートとまったく同じにはできないから、いかに代替案を作っていくのかが業界全体的に求められていて、そのへんは考えどころですね。旧来からあるコール・アンド・レスポンスはやっぱり遅れちゃうので、リーチとしてはちょっと弱いんです。それよりはむしろ、一人ひとりに話しかけた方がいいんじゃないかという方向にきてますよね。だから、一対多のコミュニケーションのやり方が変わりつつあります。
今のところスタジアムクラスのミュージシャンがやっているのはコンサートをただ配信しているだけで、本当の意味でも次のレベルのエンターテインメントにはなっていない。なので、どうしていこうかを考えていますね。あ、山下達郎さんのライブ配信に関しては、ミックスをご自身でやられてて、達郎ならではみたいなところがありました。つまり、そういう方向になってゆくかと。
中川 なるほど。強制的に停止させられただけだから、対面のエンターテインメントにおける体験共有における楽しさに向かう時代の流れ自体は、今でも変わってないわけです。そのやり方の代替手段として、音楽系だと今の流れでは『フォートナイト』でジャスティン・ビーバーとか米津玄師がバーチャルライブするみたいに、オンラインのVR(仮想現実)空間に置き換えようみたいな方向性が脚光を浴びてますが、それとは違うやり方を目指しているわけですね。
川田 そうですね。今まで僕らがやってきたAR(拡張現実)も、旧来のやり方だと小手先になってしまうので、どうやっていこうかなって模索中なんですけど。今考えているのがグッズですね。コンサートグッズって個人的な体験から関係性を感じるものじゃないですか。だから、たとえばタオルを買ってARでかざしたら、そのタオルを使ってトレーニングをしている長渕さんが映ったりするとかね。つまりモノ越しに個人との一対一の関係性を築きながら、それを手元に持ちながらアーティストとの関係性を示す。それをARで強化するという方向性は、わりとアリだなと。
こういう時期にも、物流は止まらないじゃないですか。結婚式とかお葬式とかもその方向ですよね。たとえば、お弁当とか同じものを届けながら配信したり、その現場にいる体験とはならないけれど、せめて同じものがそこにあるとか、モノで補完するという方向は、意外と有力なんじゃないかと思ってますね。
衝撃の『デススト』風三密回避センサー
川田 AR三兄弟はもう10年ちょっとやってますけど、僕はどんなゲームや物語に接しても「これ、現実に移植できないかな」って思いながら暮らしてるんですよ。古くはまだガラケーしかなかったときにアニメ『東のエデン』に登場した「東のエデン」システムを現実に移植できないかな、と思って作ってみたりとか、物語世界にしかまだないシステムを現実に移植することを、自分の中でライフワークにしています。
で、そのうちのひとつで、2019年の小島秀夫監督のゲーム『DEATH STRANDING(以下、デススト)』に出てくる「オドラデク」という空間スキャニングセンサーにインスパイアされたAR作品を作ってみたんですよ。東京都現代美術館でこの7月18日から9月27日まで開催の企画展「おさなごころを、きみに」でちらっと展示してるんですけど。ちょっと画面共有しますね。
井上&中川 うおおお、すごい!!!
川田 これ、『デススト』のゲーム中ではサムが運ぶ荷物がどこにあるかが検知されるセンサーなんですけど、現実空間上で人口の過密情報を拾えるAPIがあるので、その情報を拾ってARでリアルタイムの風景に重ね合わせて『デススト』っぽく表示されるというシステムとして実装したんですね。
つまり、人が集中しているところはヒートマップみたいに赤くなるので、これを利用すると三密回避のツールみたいに使えるわけです。
井上 なるほど。この人口ヒートマップの元情報は、どこかの調査会社とかから提供されてるんですか?
川田 はい。これは吉祥寺のローカルな情報を利用していて、もともとのUIではYahoo!の地図とかに重ね合わせて平面的に粗密が確認できるんですけど、こうやってサムが荷物を探して周辺をスキャンするみたいに、あらかじめ3Dスキャンしておいた現実の空間上にARでオーバーレイしてみせると、自分が今いる場所から見てどこが混んでいるかが風景として可視化されて楽しいでしょ。「あ、あそこのスーパーに買い物に行ったらだいぶ密だな」とか。
こうやって僕は、ゲームとか映画に出てきた価値観を現実に移植するというシリーズをいろいろやってきています。まあ、これは小島監督に許可を取らないと怖いなと思ったので、直接連絡して「こんなの作ったんですけどいかがですか?」って聞いたら、「いや、ぜんぜん嬉しい」って言っていただいたので、ほっとしましたけど(笑)。
中川 さすが小島監督、神ですね(笑)。
川田 あとは同じ企画展に出したシリーズで、Noritakeさんというイラストレーターの方が描いた展覧会のポスタービジュアルの子供の目からビームが出て、煙が出るみたいな小ネタのARもやりたかったんだけど、本人からNGが出ちゃって。なんだよ全然おさなごころじゃないじゃんって腹が立ちつつも頭を切り替えて『メタルギアソリッド』のオマージュ風に作ってみました。
これはAR三兄弟の紹介番組でも流れたので、こっちも動画共有しますね。
宇野 この三密回避センサー、吉祥寺でしかできないんですか? 高田馬場にも作ってほしいな。
川田 うん、馬場も作る作る。でも、これを作るにあたって使う街のデータって、地図会社とかがドローンを飛ばしてデータ化してたりするんだけど、すごく高いんですよ。GoogleのAPIも3D情報を持っていて、それもAPI越しに拾えるし、Google APIを使ったバージョンも作ってみたんだけど、現実とリアルタイムにオーバーレイできるほどの精度がないので、こうやって『デススト』風に遊べるものにはならないですね。
宇野 なるほど、もっと土着の業者の詳細なデータが必要なわけですね。
川田 他には、今は六本木も作ってあるんですけどね。これは自分たちでフォトグラメトリっていう技術を使って、自分たちで町を練り歩いてバーッと写真を撮りまくって作ったんですけど、すごく大変なんです。この画面の左下にある平面地図と同じデータを作ったってことですからね。
井上 ここを作るだけで、どれくらい大変だったんですか?
川田 でも、慣れたら2日で作れました。だから、iPhoneとかで写真さえ撮りまくっていけば、普通の人でも全然できるんですよね。そうやって町で定期的にこういうのを記録していくみたいな活動を、それこそゲーミフィケーションとか使いながらベーシックワーク化して、どんどんデジタライズしちゃえばいいと思う。
宇野 そもそも、僕は「外に出る」というときにみんな「人」に会いに行きすぎている、と思うんです。せっかくフェスに動員されて苗場の山奥に行って、すごくいいスピーカーで大音量で音楽聞いてるのに、隣でぴょんぴょん跳ねてる彼女の顔しか見てなかったりするわけじゃないですか。それはそれで青春の思い出としていいと思うけど、もう少しヒトではなくてその場にあるモノやコトに関心を向けたほうが豊かな経験になるのは間違いない。
そして、SNSの動員はその性質上どうしてもヒトへの関心を増大させすぎてしまう。どんなにいいイベントに行っても、Facebookで有名人にタグ付けしてチェックインすることに終始してしまったら意味がない。十夢さんのこのアイデアが素敵なのは、コロナ禍で「ヒト」がいなくなった街に人間を連れ出して、場所そのものに向き合わせることに成功しているところですね。
中川 十夢さんのこのリアル・オドラデク、あくまで元ネタの『デススト』が持っていたUIのパロディなんですけど、モノの検知を人の検知に置き換えたことで、現代批評としての作品の主題性と現実の2020年の状況に対しての、二重の意味での批評として成立している点が、すごくクリティカルですよね。ちょうど僕はこの収録の翌日から福岡でやっている「ストリートファイター」の企画展の取材のために出張するので、天神の密な屋台とかで飲んだりするとめっちゃリスキーなわけですが、GoToトラベルキャンペーンがダメだったのって、今の観光業が想定するお金の落とし方の中心が、わざわざ人が集まるところで飲食したりすることでしかなかったりすることじゃないですか。そこで見知らぬ旅先で十夢さんセンサーがあると単純に便利だし、今すぐアプリとして使いたい状況なわけです(笑)。
つまり、人に会わずに場所の魅力そのものと孤独に向き合って楽しむことに対する提案的なメッセージ性が、『デススト』を経由することで特に強く備わったんじゃないかと。
「YouTube散歩」で体感できる風景
中川 といったところで、井上さんがコロナ禍でやり始めたことのお話しも伺いたいんですけど。
井上 はい。じゃあコロナ禍でダメになったことからお話するとですね。ちょうど僕は『コモンズの悲喜劇』という、経済学でよく使われる概念を楽しめるようにしようと、知り合いと一緒にボードゲームを作ってたんです。
これが完成したのが3月1日で、もともとは「ゲームマーケット」というボードゲームの即売会で売る予定だったんですがCovid-19対応で、中止になってしまいました。ボードゲーム系の遊びは対面で遊ぶものでもあるので、通販にしても、あまり売れていなくて、惨憺たる状態になっていますね。
あと、毎年5〜6月くらいに京都でやっているビットサミットという世界的にもかなり有名なインディーゲームの大きいイベントも僕はちょっとだけ手伝っていて、毎年楽しみだったんですが、リアルではできなくてオンラインでやったんだけれども、盛り上がったと言っていいかは、正直わかりません。ゲームマーケットも、オンラインでやるにはやったんですけれど、リアル前提だったものをオンラインでやるのって、やらないよりはよかったのかもしれないけれど、いつ始まって、いつ誰と場を共有して盛り上がったのかが非常にわかりにくくて、やや微妙だなという感じではあります。
中川 同人即売ものは基本、祭りの場の土産物ですからね。祝祭というか、誰かと同じ場で何かを共有する楽しみは、「Spatial Chat」とかいろいろリモートの代替ツールは提案されてはいるけれど、基本厳しいですよね。
井上 その一方で、このコロナ禍で、何かゲーミフィケーション的なことをやらないんですかと、三宅陽一郎さんとかにつつかれたりして、2ヶ月ぐらい前から友達とかと一緒にいろいろと試行錯誤してるんですが、その中でも、これ結構おもしろいじゃないかと思ってるのが「YouTube散歩」です。
たとえば、こんな動画を画面共有するので観てほしいんですが、「walking 4K」とかのキーワードでYouTubeを検索すると、ただの散歩している動画がすごくたくさん上がってるんですよ。これが、けっこうアツくて、家に4Kのちょっとでかいテレビがあるのでそれに映し出して、その前で人と一緒に足踏みしていると、けっこう普通に散歩している感が出てくるんですね。
一同 おおおお、本当だ(爆笑)!
井上 もともとはGoogleストリートビューを自動でランダムでクリックしてくれるサービスの「Street View Random Walker さまよえる私」を展開している東信伍さんという方の作っているものがあって、「面白そうだからその前で足踏みしてみようか」と始めたのがきっかけだったんです。それも面白かったんだけど、これだったら高精細の4K散歩動画とかもYouTubeとかにあるんじゃないかと思って探してみたら、これがすでにかなりの量がアップロードされている。これはアツいな、と。1人で足踏みしているとちょっと空しいんだけれど、2人で足踏みしながら動画内のものを「何あれ」とか言いながら話してると、ダラダラと散歩している感じがすごいありますね。
これはセネガルの散歩風景ですけれども、コロナ禍じゃなかったとしてもなかなか行けないところじゃないですか。セネガル、ソマリアなどのアフリカやら、イエメン、レバノンなどの中東とかの動画もあって、世界各国の散歩動画があるんです。
宇野 いいなあ、これ。僕もやってみよう。
川田 ここの国の人たち、みんな足が長いですねぇ。
井上 そうなんですよ。しかも、このセネガルの人たちは足も長いし、着てるものもすごくカラフルでおしゃれなんです。
川田 おもしろいですよね。こうやって、それぞれの歩く相手とのツッコミどころも変わってくるだろうし。
井上 そうそう。見たものをWikipediaとかで探しながら歩けるし、車や建築に詳しい人と一緒に歩いたら、それでまた話す内容が変わりますし。こうなると、下手な観光地に旅行に行くよりもおもしろいし、素晴らしいなと思って、けっこう友達と一緒に歩いていました。
あとは、僕の友人で『シェンムー』が好きなやつが多いんですけど、「横須賀 4K ウォーキング」とかで探すともちろんあって、『シェンムー』の聖地巡礼みたいなことも容易に可能です。
宇野 あるんだ(笑)。
井上 あとおもしろいのは、プライド・パレードという世界中で行われているLGBTQのお祭りがあるんですけど、そういうお祭りの日を歩いている動画もあって。そういうお祭りの盛り上がり感もわかるし、一緒に歩いていると「なにあれ?」と思うものがあっても、「見えない見えない、人ごみ多いから無理だ」みたいなもどかしい感じも含めて、その場にいる感はかなりありますね。
それと、国家安全維持法が施行されてしまった今となっては記念碑的な感じとなってますが、香港の抗議運動のデモ内を散歩している人ももちろんいて、今となっては不可能になってしまった体験をすることもできたりする。
ここ最近にアップロードされてきているものだと、まだ画質のいいものがあまりないですが、Black Lives Matterのデモ・パレードで、警察と一触即発の状況になっているデモ隊と一緒に歩くこともできます。
今の環境だと、こうしたものも含めて、まさにその場にいる感覚というのが擬似的に味わえる。もちろん一方では、パリとか渋谷の街を3Dモデルで1から作り込んで再現して、VRゴーグルとかを被って自由に歩き回れるようにしようというアプローチとかが注目されやすいですけど、ただ単にiPhoneとかを持って散歩しているだけの動画でも、これだけリッチな体験ができるコンテンツが溢れてるということがわかったのは、すごい発見でしたね。
中川 これ、撮影者側もみんな4K機材で撮影してアップしてるんですね。
井上 そうです、4Kで撮影しているものも多いです。でも、マイナーな地域とかになってくると、やっぱり4K動画が見つからなかったりもするんで、「しょうがない、4Kじゃないから我慢するか」みたいな感じになったりはしますね。
中川 この臨場感の本質って、VRゴーグルを使うテレイグジスタンスみたいなものとの違いは、人間にとって大事なのは視野角を覆うことよりも解像度というようなことなんですかね?
井上 解像度の問題もあるんですけど、それより重要なのは足踏みという身体運動を伴うことに加えて、友達とか家族とかと「なにこれ?」とか言い合ったり、ダラダラ話しながらできるという部分でしょうね。我々のリアリティの構成って、やはり複合的にできているので、単純な視覚以外のところでもいろいろと誤魔化しが効きます。「なにあれ?」とか突っ込みながら、他人と何かを確認するみたいなことがかなり大きいと思うんですよね。もちろん、一人でやることもできるんですけど、10分ぐらい歩くとちょっとだるくなってやめてしまうだろうなとは思います。
中川 なるほど。VRゴーグルだと完全に孤独な体感になっちゃうけど、ゆるくシェアはできた方がいいんだ。あと、この動画の場合は、自分の歩く感覚とはまったく違う身体感覚で歩いている人に憑依することで、自分にはない感覚への発見とかツッコミ感とかが生じ得るってことですよね。
井上 「ちょっとこの人、あー止まった止まった。あれ、行っちゃった」みたいなそんな会話もありますね。「そこに猫がいる!」みたいな時にうまく止まって、猫にズームアップしてくれたりすると心が通じた感じがあったりします。
川田 おもしろい! これってすごく高次元の遊びじゃないですか。何がおもしろいって、井上さんが説明しているときに、「ここ歩いたときにですね」って、もう歩いた体験になってるのがおもしろいですよね。
井上 ありがとうございます。基本歩いたようなものですよ(笑)。
無目的なウォーキングから考える2010年代の難点
中川 ここから連想的に思い出すのは、デジタルゲームでは3DCGでの表現が一般的になってオープンワールド系のタイトルとかが普及していく中で、『Dear Esther』なんかを皮切りに「ウォーキングシミュレーター」というジャンルが出てくるようになったじゃないですか。
つまり、ある目的に沿ったクエストをこなしたり、所定の挑戦課題のあるゲームをやるというよりは、基本的にはそういうゲームメカニクスがゆるくて、世界観の雰囲気とか物語を味わう要素がメインにあるのがウォーキングシュミレーターと呼ばれていて。そういう目的性から解放される体験性への需要が、ゲームを含めた最近の遊びに求められている潮流のひとつの本質なのかなと思いましたね。
井上 ああ、中川さんらしいコメントですね。ウォーキングシミュレーターって、ある種のクラシックなゲーマーから言うと「あんなのはゲームじゃない、ただ単に歩いてるだけじゃん。バカじゃね?」みたいな、ディス用語的な側面もある言葉なんですよね。
でも一方で、「別にゆるくてもいいじゃん、むしろこれがいい」というユーザーさんもたくさんいる。そこはちょっと乖離がありますけれど、そのコンテンツに入っていく解像度の問題さえ調整できれば、全然これでいいんですよね。
宇野 僕はここにいるお三方ほどゲームをやらない人間なんですが、ゲームをやるときに感じる億劫さって「攻略」しなきゃいけないことなんですよね。操作して土管を乗り越えていかなきゃいけないとか、レベルを上げなきゃいけないとか、大陸を統一しなきゃいけないとか、それこそがおもしろさだというのはよくわかるんだけど、逆に「攻略」することで見えなくなるものがあるようにも僕には思えるわけです。やはり『スーパーマリオブラザーズ』の土管は「攻略」のために潜ったり、乗り越えたりするためのものとしてどうしても認識してしまって、土管そのものの機能美や土管のある風景の魅力、あるいはどの土管が敷設された土地の記憶のようなものはぜんぶ二の次になってしまう。
この4K散歩はその点ですごく惹かれるものがあって、要するに何かを「攻略」しなくても充分、いや、しないからこそ街の魅力に触れられる。その面白さですよね。
中川 むしろこれまでのデジタルゲームで「ゲーム」であることが必要だったのって、4K散歩の動画とかで感じられるような世界の多様性がこれまでのデジタル技術の情報量では提供できなかったから、従来のデジタル・エンターテインメントはゲームメカニクスを楽しみの主軸にするしかなかった、みたいなことも逆に思ったりします。
近年のインディー系のアートゲームとかでも、古典的な意味でのゲームメカニクスをいかに覆したり脱臼したところで、どんな未規定性と出会えるかという遊びの原点を見つめ直していこうというモードが強くなってきている傾向があるし。
宇野 やはり僕らが観光客としてセネガルに行ったときにはこういう視線を得られない。どうしても「この時間はここを回ろう」と決めてブラ歩きしたりとか、滞在中に何か目的を持って歩くことになる。実際にこの町を無目的に歩いていることが、はじめて風景そのものを直視させることになっていて、どこか特定のところにフォーカスしない豊富な情報量につながっている。
2010年代は人類がとにかくSNSを通じて「動員」されていた時代だったことは冒頭に指摘しましたが、僕はこの「動員の革命」に潜んでいた罠について考えるタイミングだと思うんですよね。
たしかに、こうして「STAY HOME」を続けていると、人間は街頭に出ることによって、はじめて偶然性に身を晒し、多様なものに触れて豊かな経験ができるという当たり前のことを思い出そう、という主張が説得力を持って聞こえてくる。しかし、ここで本当に問われなければいけないのは、ただ「外に出ればいい」のかという問いです。
2010年代の「動員の革命」の流れの中で生まれた運動が、むしろ失敗例に溢れていることは広く知られていますが、その失敗の原因の一つがSNSによる動員が分断を加速することにあったことは明らかです。SNSの見たいものだけを目に入れ、信じたいものだけを信じやすいように、自分の情報環境を整えられてしまう性能がいわゆるフィルターバブルとして機能してコミュニティの分断を加速し、対話の可能性を閉ざしていくという分析がありますが、同じことが文化的なことにも当てはまるんじゃないかと僕は思います。
つまりSNSに「動員」された時点で、どれだけ遠くに出かけてもそこは偶然出会えるものも目に入りにくくなるし、多様なものにも触れられないのではないか。「動員」されるということは、要するに「こうした刺激が欲しい」という欲望を自覚した状態で出かけることを意味するわけです。インスタ映えスポットを目指して旅する観光客は、どうしてもそれ以外のものは目に入りづらくなる。たとえそれが多様な客が入り乱れる街中のお店でも、その場のボスのご機嫌を伺うためにその取り巻きたちが忖度して、ボスの嫌いな人の悪口を率先して述べていくような「飲み会」に出ても、何にも出会えるわけがない。やはり、僕たちは「動員された先のその場所は、本当に豊かな場所なのか」を問わないといけないタイミングなのだと思います。ただ、外に出ればいいわけじゃない。
中川 その動員の革命のひとつの局面として、2010年代前半にキーワードになったゲーミフィケーションの功罪とも直結しているわけです。つまり、SNSを含む情報技術の支援によって、ビジネスとか政治運動や社会運動とかのリアルな活動にポイントとかレベルアップの仕組みを可視化するとかのゲームメカニクスを導入することで、人々にゲーム的な動機づけを与えて特定の目的に動員するという情報技術のトレンドがあって、井上さんも著書『ゲーミフィケーション』でオバマ前大統領の運動とかについての分析をしたり、3.11のときには自分でも実践されてたわけじゃないですか。
その点を自己検証してみると、いかがですか?
井上 はい。9年前の東日本大震災のときには、原発事故を受けて節電ムードが高まりましたけど、それを受けて「#denkimeter」というのを作ったんですね。これは自宅の外にある電気使用量のメーターの値を1時間とか30分とかおきくらいにチェックすると、電気使用量のフィードバックが得られる。それをツイートすることもできて、それをやっていくと、どれくらい減らせたか他の人と比べたりすることもできる。そういう簡単なアプリを友人と一緒に作ってやったんですが、多くの方に遊んでいただきました。

▲「#denkimeter」のiphone版アプリ『iDenkimeter』
これの何が楽しいかというと、エアコンの使い方とかでめちゃくちゃ変動があったりして、電気の使い方のノウハウって想像以上に奥が深いなということなんですよね。そうすると家電量販店に行くのとかが今までにない楽しみ方ができるようになるんですよ。「これは安くてスペックはいいけど電気使用量が多いのが惜しいな」とか、店にあるすべての製品の電気使用量を気にしながらチェックする。家に帰っても、それぞれの電化製品が何ワットかというのを全部記憶して使うようになるから、それこそARのように家庭内の各電化製品のワット数が脳内に浮かび上がって見えているわけです。そうなると、まったく違った空間の見え方が立ち上がってきて、電気を感じながら生きるようになるんですね。
ある意味で修行っぽくもあるんだけども、少なくともハマってる間は楽しくて、何年間もやっていました。最近は改善することもほとんどなくなってきたので、ヲタを続けられなくなってきてるんですけど。
川田 いや〜、井上さんおもしろいなあ。
中川 つまり井上ゲーミフィケーションの特徴って、ゲーム的な挑戦課題を数値化したり可視化したりといった設計もするんだけど、ルールとかゲームメカニクスを精緻にデザインするというよりも、ある種の逸脱性というか、それをきっかけにして世界の見方とか生活体験そのものが変わっていくことに、より醍醐味を置いている感じですよね。
これは2010年代エンタメの大きな潮流を作ったジョン・ハンケにおける『Ingress』とか『ポケモンGO』で言えば、位置情報を利用したゲームそのものよりも、ゲームのための街歩きを通じて意外な風景を発見したりするほうが楽しくなる感覚に近いんですけど、今度の4K散歩に関しては最初からフックとしての目的設定そのものも取り払ってしまってますよね。もう補助輪なしでも自転車漕げる、みたいな。
川田 わかります。価値観を束ねる方向じゃないもんね。いろんな価値観の人がこれを見たらいろんな感じ方があるし、だからこそめちゃめちゃおもしろい。
テレウォーキングから考える次世代ツーリズムの可能性
川田 僕が思い出したのは、ミュージシャンの大瀧詠一さんが生前、音楽を極めすぎて音楽以外の趣味がほしいということで「映画カラオケ」っていう遊びをしてたんですって。映画の中のロケ地を自分の中で調べ上げて、その映画を流しながら同じ風景をただ歩いたり、ドライブしたりするんです。それに近しい粋な遊びですよね。
あと、他人が歩いていくのに憑依する感覚に近しいものを、僕もちょうどARで研究開発してたりします。いま作っているのは、食材と味の素で何が作れるかというレシピを出せるARを作っているんですね。ここにはチャンネルという概念があって、「和の鉄人ならこういうアプローチ、中華の鉄人だったらこういうアプローチがある」みたいに、達人と一緒にスーパー練り歩くだけでエンターテイメントになるような、そういうARなんですけど、それにも近しいですね。ここには、すごくいろんな遊びの原点があるような気がします。
井上 ありがとうございます。やっぱり「ブラタモリ」的にこの土地にめっちゃ詳しい人とかと歩きたいですね。
川田 星野リゾートの星野佳路さんが「マイクロツーリズム」というのを訴えているじゃないですか。それは長い時間をかけてする旅行ではなく、数分間でできる身近な旅を、ということなんですけど、これもある種のマイクロツーリズムですよね。肖像権の問題とかはあるので、本格的にやるならテレウォーキングコンテンツの国際ルールみたいなのが必要だとは思うんですが、ガイドラインができたら世界共通でできそうですね。これは流行るかもしれないですよ。
そこで思ったのは、ライブエンターテインメント業界と同様に観光業界も大変だということでGoToキャンペーンみたいお金の使い方がされてるわけですけど、逆に考えれば、こんなに観光地に人がいないことって、千載一遇のチャンスないですか。だから、この機会に観光素材をデジタル的にミラーリングして保存しておく活動に予算をつけて、各自治体のベーシックワークみたいにすればいい。さっきの『デススト』インスパイアの三密回避センサーみたいに、それがあったら絶対、僕らみたいなのがお金落として使うから。
いま国とか業者は観光地に人を呼ぶことしか考えていないけれど、将来的にそのミラーリングデータを使えば、リアルに人を呼ばなくても観光地にきちんとお金が落ちて回していくような原資にしていける可能性もあるじゃないですか。
井上 たとえば今まさに首里城とかの修復に文化庁はお金をかけようとしているので、そういう公共的な文化財・観光資源のアーカイブ事業の一環としても予算化できそうですよね。それとさっき十夢さんがおっしゃってたような現地のモノのお取り寄せとかを組み合わせることで、僕がプチプチ流行らせようとしていることの延長線上に次世代ツーリズムのようなものが見えてくるのかもしれません。
川田 ARでゲームをつくろうと思ったときに、やっぱり場所のデータが必要じゃないですか。これは以前、新海誠さんとも話したことがあるんですけど、ロケハンに行ってデータに起こして、映像の中に取り込むってすごく大変なんです。でも、たとえば各地域にロケハンに行ったときに雛形として3Dデータもあるよ、みたいなことがあったら、自分で作るよりもぜんぜん安あがりだから、映画でもゲームでも、クリエーターは絶対にお金を落とすんですよ。
そういうデジタル方向でのロケ地の提供が、地方自治体のベーシックインカムの一つにもなると思うんですよね。対症療法的に、リスクを抱えながらおっかなびっくり観光客を呼ぼうとすることなんかより、そっちのがよほど将来的に有効な投資になるでしょ。
中川 おもしろいですね。井上さんのこのメソッドが、もっとエンターテイメントコンテンツの可能性として認知されて、そこに着目するビジネスプレイヤーが出てくることで、その流れはできるかもしれない。たとえば人が訪れすぎるとまずい世界遺産とか、風情が損なわれてしまう京都の祇園みたいなオーバーツーリズムの問題とか、まさに2010年代の動員の革命がもたらした弊害を解消していくための機運にもつなげられそうです。
このYouTubeの4K散歩は記録された映像アーカイブだけど、リアルタイムも含め好きな時間帯に好きなだけブラタモリ的な詳しい人の視点で歩けるようになるリモートパッケージツアーとかは普通に構想可能ですよね。あるいは十夢さんが言うような『HELLO WORLD』的な3Dデータ化の方向は、実際に人が行くとなると物理的なインフラが必要になるために地方がテンプレ観光地化してしまう流れを変えて、場所の多様性そのものが情報的な資産になるような時代への転換の可能性も示唆しているようにも思いました。
半径500メートル〜5キロメートルをひたすら掘り下げることの意味
中川 それでは最後に、宇野くんの場合はどんな感じですか?
宇野 いや、僕は十夢さんや井上さんみたいにすごく新しいことは何も考えていないですね。それはどういうことかというと、たしかに「ARで三密回避を遊びにするぜ」とか「居ながらにしてセネガル散歩できるぜ」というのもすごくおもしろいなと思う一方で、今のこのタイミングってむしろ半径500メートルくらいの生活圏をひたすら掘り下げるためのいいチャンスなんじゃないかとも思うんです。
実際、僕個人はこの状況に、全然苦痛を感じていないんです。もちろん、それは僕がたまたま、職種的にもその他の環境的にもあまり「STAY HOME」の影響を受けない状態にあったからだというのは理解した上で、あくまでこうした視点「も」あるのだと提案しているだけなので、そこは誤解しないでほしいのだけど、そもそもコロナ禍以前と以後で、仕事はいろいろと大変だけど、ほとんど生活は変わっていません。
これまでと同じように朝起きて近所を走って、仕事をして、夜はNetflixを観て本を読んで、そして寝るという生活を繰り返している。特に僕は「飲み会」が嫌いなので、むしろ誘われなくなってほっとしているくらいです。友人とは、話したいときに一緒に走ったり、散歩したり、Zoomで話していて、それで十分です。
そして、ここからが重要なのですが、僕のこの500メートルくらい離れたオフィスと自宅を往復するだけの生活圏に触れるときの解像度がこの半年で異常に上がっているんです。そして、それが意外とおもしろい。たとえば、よりにもよってこのタイミングでできたランドリー喫茶がマジで客が入ってなくて倒産しそうだとか、毎年大型のガマガエルが発生するエリアが高田馬場1丁目に1ヵ所あるんだけど今年は1回も見てないとか、8月になってもまだ咲いているアジサイがあるとか、近所のほっともっとやセブンイレブンに、何時ぐらいに行くとどんな弁当が入っているか、ということにものすごく詳しくなっていく。
昔『小泉今日子の半径100m』という、普段の生活のことを写メと一緒に載せるという「InRed」のエッセイの連載があって、当時は芸能人ブログがまだ珍しかったからすごく売れていて、僕も買った記憶がある。あの感覚に近いんですよね。いま僕は小泉今日子的なリアリズムで生きているわけですよ。

一同 (笑)。
宇野 これは別に小市民的な日常に埋没すればそれで満たされるという話じゃないんです。たとえば、この高田馬場の事務所か半径500メートルだと、学習院のキャンパスをはじめ、目白から下落合の緑地がいくつも入る。僕は子供の頃から昆虫や植物が好きで、このあたりは歩いているだけでまったく飽きない。もちろん、それなりに歴史のある街なので、「ブラタモリ」的な歩き方をしても楽しい。ただ、重要なのは生活の一部の中に埋め込むように、こうした楽しみ方を「ついで」にやれることで、これができると半径500メートルの日常の世界にいたまま、すごく遠くの物事に接続することができるわけです。別に目を皿のようにしてさがして回らなくても、今日の言葉で言うなら「攻略」しなくても何気なく歩いているだけで、ふとその空間にあるものに気づくようになる。こういう目が開発されると、他の街に出かけても全然見え方が違う。
川-1.jpg)

▲宇野が朝のランニング中に撮影した風景。「近所の川も、本来ならオリンピックが行われていたはずの新国立競技場も早朝は普段とはまるで違った顔を見せるんです」とのこと。
僕らはつい、Beforeコロナの「動員の革命」と、Afterコロナの「STAY HOME」の二項対立で考えてしまうけれど、そこ置き去りにされてしまうのが、この半径500メートルの解像度を上げることで、遠くの場所や遠い過去に接続する目を養うことじゃないかと思うわけです。
「そうは言っても半径500メートルじゃ……」って考える人も多いと思うんですが、それなら500メートルを5キロメートルにすればいい。僕は日々のランニングで、だいたい10キロメートルくらい走っていて、多いのは5キロメートル走って戻ってくるパターンです。いま、電車やバスなど公共の交通機関には頼りづらい状況だと思うのだけれど、走ることによって、僕たちの生活空間は500メートルが5キロメートルへと、一気に10倍になる。だから僕は個人的にはあまりいまアクロバティックなことをやろうという気持ちにならないんですよね。
川田 誰しも宇野さんじゃないからなあ。宇野さんみたいな感覚を備えて、自分の半径5キロメートルを生きるんだったらそれは豊かだけど、宇野さんになれるようなARはなかなか作れないと思う(笑)。
宇野 いや、そこはARのような特別な技術はもちろん、特別な知識や訓練も必要ないと思います。たとえば僕はこの夏、よく散歩やランニングのついでに、それこそ半径5キロメートルの世界でよくカブトムシやクワガタムシをさがしているのだけれど、僕が知っているだけでも新宿区で4箇所は観察できるところがあるわけです。単純に、こういうことに気づかないで、いまメディアの情報に流されて自分たちは日本で一番感染リスクの高いエリアに住んでいると恐怖を覚えている新宿区民は多いはずで、僕はここにボタンの掛け違いがあると思う。
これは別に虫や花に興味を持とう、ということではなくて、自分の足元の半径500メートルや5キロメートルを見る解像度が低いと、どれだけ遠くに行っても何にも出会えないということが重要なんだと思います。

▲新宿区某所の林で宇野が見つけた昆虫たち。彼らも日によってまったく違う姿を見せてくれます。
いまのカブトムシの例について言うと、僕はよく朝に探しに行きます。本当は夜中のほうが虫はいるのだけれど、ランニングのついでに行くので朝が多いんですね。早朝の街は、住宅街もオフィス街も歓楽街もそれぞれ別の理由でまるで別世界で、歩いている人も違えば目に入るものも違う。僕はこのコロナ禍の「STAY HOME」を通じて、自分たちの足元の生活の現場から見えてくる大きな課題に気づいていくことが大事だと繰り返し述べているんです。満員電車の問題、押印という文化の問題、いまだに専業主婦を前提とした住宅設計の問題……山ほど、足元に視線を落とすからこそ見えてくる課題もあるはずなのだけど、同じことが文化的にも言えるのではないかと思うわけです。
井上 宇野さんのおっしゃる「半径500メートルを見つめる」ということの意味をもうすこし掘り下げたいんですけど、たとえば「地元観光」のような概念が仮にできたとして、みんなが地元観光するようになるのが理想ということですか?
宇野 いや、「地元観光」とは全然違いますね。生活の一部をどう遊ぶか、ということが鍵だと思うので。あまり言葉に縛られたくないのだけど、やはり観光といった瞬間に、日常から切り離されてしまう。人間って「今は非日常で、自分は日常の生活をしていないんだ」と思った瞬間に開く回路と閉じる回路がある。ここは慎重に見極めないといけない。
2010年代の「動員の革命」と、その背後にあった当時のゲーミフィケーション的なものというのは、非日常に開く回路をハックしてどう人々をどう動員させるか、悪く言えばどう人々を思考停止させるか、ということを考えていた。もちろんこうした技術が極度に発展するなかで初めて「開かれた」ものもたくさんあって、それを否定するべきではないと思うんだけど、そこで捨てられたもののほうに、つまり日常の思考回路が開いているからこそアクセスできるものに、今の僕は興味があるんです。だから、生活の一部として遊びをどう組み込んでいくのか、ということだと思ってるんですよ。
たとえばランニングについても、一応アプリで記録はしてるけど、それは単に走ったということの記録だけで、一切タイムは気にしてないし、疲れたら歩いているし、筋トレ的な目標もまったく立ててない。単純に街を走るのと体を動かすのが楽しいという二つの理由でしか走っていないんです。その延長線上で、何か単に買い物に行くとか、単にオフィスを往復することを、どう豊かにしていくのかを考えているんです。
川田 宇野さんが「観光」という言葉を使わないっていうのは、けっこうクリティカルですよね。僕の仲が良かった劇作家で、劇団「悪魔のしるし」主宰の危口統之さんは、「観光とは土地の演技である」という言葉を残したんです。土地が演技することが観光で、土地が演技してるってことは、台本があるんですよ。僕らが観光地にちょっと冷めちゃうときって、台本のような存在のことをわかっちゃったときですよね。
たとえばゲームでNPCの町人が同じことを何回もループして喋ってて、「あ、この人は物語を持っていない書き割りの人なんだ」って思ったときの冷め方に近いというか。そういう、演技とか台本といったものの存在がない方向に本当はシフトしないと、次がないよね。
宇野 たとえば、『2001年宇宙の旅』のボーマンって、宇宙の果てに行った結果スター・チャイルドに進化して、もう人間の認識の外側に完全に出ているから、スター・チャイルドがどう世界を見てるか、僕らにはまったく想像不可能なわけですよね。その想像不可能なものをアーサー・C・クラークは概念として提示して、スタンリー・キューブリックがそれを手探りで視覚化した。対して、それから半世紀くらい後に作られたクリストファー・ノーランの『インターステラー』では、同じように宇宙の果てにたどりついた主人公が多次元空間にアクセスして確認してくるのは、結局「わたしパパのお嫁さんになるの」的なメンタリティを持った娘からの承認にすぎなくて、僕はあの冒頭から概ね予測がつく結末を見て、だったら別に旅なんかしなくてもいいんじゃないか、と思った。それはそれでバカにしたものじゃないし人間としてすごく大事なことだと思うけど、わざわざ多次元宇宙に行く必要はない。
これは結局、目と耳が鍛えられてないと、どこに行っても変わらないということなんですよね。じゃあ、どうやって目と耳を鍛えるかと思ったときに、「目的」がありすぎる「攻略」するためのゲームは、人間の知性や創造性を爆発的に開拓している一方で、ある部分を殺してしまっているんじゃないかと僕は感じるんです。だから、僕は目的を持ったアプローチとか、観光的なアプローチとか、攻略的なアプローチとかの外側を、このステイホームの時代に顧みたほうがいいんじゃないかということを今考えています。この未知の領域を取り込んでいくことによって、「あそび」は進化していくはず。
「ゲーム」の限界から「遊び」の本質にいかにアプローチするか
井上 宇野さんがおっしゃりたいことはよくわかります。たとえば上田文人さんの『ICO』とか『ワンダと巨像』といった作品は、ゲームにおける「目的」や「攻略」をしようという意識について考えさせられる作品になっています。『ICO』は『天空の城ラピュタ』みたいな幻想的な城に閉じ込められた男の子と女の子が、手を取り合って城の中を探索する作品です。目的にせかせかしないタイミングをすごく意図的に組み込んでいて、すごく美しく描かれた風景の中で女の子に手をつながれて、急かされないことが多いんですよね。目や耳で楽しむ作品として、とてもよく作られている。
その一方で、これは、城の中から脱出するための「脱出ゲーム」としての側面も持っています。なので、ダラダラしてゲームとして間延びをすることはそこまでなくて、「いまは敵を倒さなきゃ」とか、「ここは謎を解かなきゃ」みたいな目的に向かって急かされる瞬間もある。『ICO』をやってると、「目的を達成するよう強制させられているな」っていう瞬間と、「いまは風景を楽しんでも大丈夫なタイミングだ」という瞬間が交互にでてきます。
『ICO』は、まさに宇野さんが指摘したような問題があるのを意識せざるを得ない作品です。多くのプレイヤーが目的に向かって何かをするということと、その外側にある目と耳の世界に対立があるということを意識させられてしまう。ゲームって、ここまでは達成できるけど、「目的」の外側にあるものを表現するのが難しくなりがちな形式だということは、確かにあります。
中川 そういうゲームの外側にある余剰性というか、遊びの領域をどう捉え直すかという問題は、まさに近年のゲーム研究の文脈でもホットになってる問題でもあるわけじゃないですか。遊びとかゲームをめぐる本質論的な研究って、だいたいホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やカイヨワの『遊びと人間』といった文明論的な視座で書かれた古典をベースに始まってるんだけど、情報技術とデジタルゲームが発展してきたことに応じて、イェスパー・ユールの『ハーフリアル:虚実のあいだのビデオゲーム』や、その翻訳者である松永伸司さんの『ビデオゲームの美学』といった著作を通じて、ゲームがゲームとして成立するための形式的な要件とか、物語との関係、あるいはプレイヤーの心理的な態度をめぐる議論の枠組みは、相当精緻に整備されてきてるんですね。こういう分野をゲーム・スタディーズと言うんですけど。
その一方で、かつてホイジンガが人間性なるものの本質は「遊ぶ人(ホモ・ルーデンス)」であると喝破したような人文社会科学の基盤となってさまざまな領域につながっていく遊び本来の豊かさとか逸脱性については、なかなか理論化できなくて、置き去りにされてしまっている部分がある。そのことに対する批判がゲーム・スタディーズの中からも出始めていて、その急先鋒の一人が『プレイ・マターズ 遊び心の哲学』という本を書いたミゲル・シカールという研究者なんですよ。シカールはこの本で、古典的な目的性のあるゲームやテクノロジーによって制度化されたビデオゲームのようなものには背を向けて、前半で話していたような、おもちゃや道具といったモノとの対話だとか、都市とか政治だといった幅広い領域を視野に、当初の目的からズレていく流用性とか創造性をもたらす「遊び心」の役割について、改めて現代的に捉え直そうとしている。理論的には粗削りですが、ここでの宇野くんの問題意識と非常に近しいことが模索されているわけですね。

井上 そういう遊び心が喚起される構造をいかに作るかというのは、やはりめんどくさい話なんですね。シカールの本でも公園や遊び場の話がよく論じられているんですが、いまの話は、建築家の青木淳さんが書いた『原っぱと遊園地』という本があって、ここで語られている遊園地と原っぱの対立の図式に近い話だと思うんですね。
たとえば、建築物を構想するときに、遊園地みたいに完全にルートまで含めて全部パースペクティブが設計されているタイプの空間を考えるのか、もっとフレキシブルな原っぱのようなタイプの見せ方を考えるのかという対立があるわけです。ただ、この対立を乗りこえてハイブリッド化していくことができれば、次の世界に行けるかもしれない。宇野さんが指摘しているのは、青木さんが言うところの原っぱ的なものをどう組み込んでいくかということで、今だからこそ対立の先に行けるんじゃないか、という話にも聞こえました。

川田 そこでちょっと思い出したんですけど、僕らはAR(Augmented Reality:拡張現実)の最初期からAR三兄弟と名乗って10年ぐらいARをやってるんですけど、最初期にはARG(Alternate Reality Game:代替現実ゲーム)の団体から仲間だと思われて、やたらそっちのイベントとかにも呼ばれたんですね。2010年前後って、特に海外でARGが盛り上がっていた時期だったので。
その中でいいかもなと思ったのが、『Cathy’s Book』という海外のARGの事例です。これはキャシーという女性が失踪して、彼女の日記とかモノだけが送られてくるところから物語が始まるという趣向なんですね。ある喫茶店には彼女が残したメモがあったり、ネット上にその痕跡が残されていたり、日常の中に紛れ込んだモノから推理して、だんだん非日常の世界に入っていくという仕掛けなんですけど、そういうモノから張り巡らされていく世界というのは、今この状況の遊びとして向いてるかもしれないなと思いました。
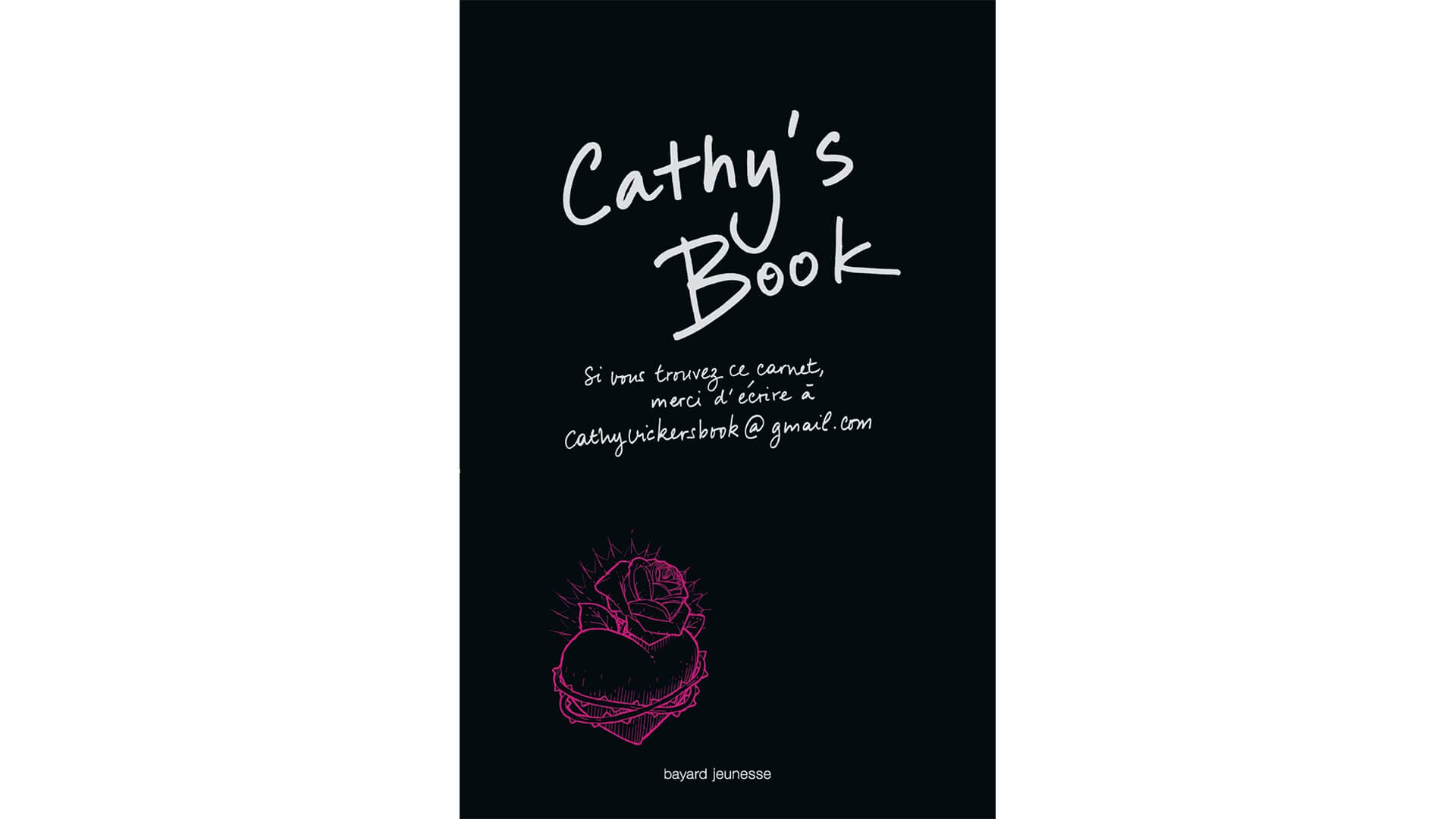
中川 そうですね。そういうかつてのARG的な遊びが、Zoomなどのリモート環境が急速に普及したことで、ちょっと復活してきてる部分があります。というか、この座談会と同じ特集で、SCRAPのきださおりさんと劇団ノーミーツの広屋佑規さんの対談記事も収録しているんですが、そのきださんはまさに今、モノを使ったりZoomでのライブ感を利用しながら、従来の謎解きをARG化する方向の作品づくりをされています。
つまり、みんなの日常の中にリモート会議ツールの真新しいインターフェース経験が入り込んできたことで、これをARG用語で言うところのラビットホール(『不思議の国のアリス』におけるウサギの穴。日常の中に隠された非日常的な物語体験への入り口)として活用して、ネットの世界の向こう側を非現実化して誘おうとするわけですね。
ただ、そういうラビットホールを探し出して落ちていくまではワクワクするんですが、謎解きが始まった瞬間、一気に段取り感出てくるんですよね……。
川田 謎解きの限界ってありますよね。しょせん、あれは作り手の思い通りじゃないですか。あまり納得いかないというか、ダジャレみたいな回答のときもある。あとは犯人がそれを残す必然性がないし、あんまり没入できないことが多いなあと。
宇野 「謎解き」のもつおもしろさの反面の「つまらなさ」の問題は、僕も最近よく考えているんです。たとえば、推理小説で探偵が起きてしまった殺人の犯人を推理することは、そこで起きている課題解決に全然ならないじゃないですか。たぶん本当におもしろいクエストって課題そのものを発見することのはずなんですよ。
そこでまったく関係ない話をすると、僕は最近、Yahoo! JAPANのCSOの安宅和人さんをモデルにした小説を書こうと思ってるんです。「コンサルティング探偵」という仮題をつけているんですが、殺人事件が起こると現場検証や人間関係の分析はそっちのけで、ひたすら事件が起きた場所や組織のデータを分析していくんです。
たとえば、田舎町で町役場の人が殺されるといった事件が起きたら、その町役場や関連団体の収支のデータを徹底的に分析する。そして、「この団体のこの事業の売上が異常な曲線で伸びている。これは絶対に何かある」とか、推理とかは一切せずにデータ的に不自然なところをついていく。
そして最後はこうして特定された犯人の動機が明かされるわけなのだけど、だいたい犯人は間違った問題設定をしたために間違った解決法で殺人を犯してしまったことが指摘されるんです。「そもそも町おこしの予算を守ろうという発想が間違っている。地場産業の構造にメスを入れないと本当の問題は解決しない」とか怒られる。そして最後は「イシューからはじめよ!」とダメ出しされる。
一同 (笑)。
宇野 これって雑談めいているけど本質であるような気もしていて、課題解決型か問題設定型か、という話なんですよね。与えられたお題に答える謎解きって、今日の話でいうと凱旋門の前でダブルピースして写真を撮る観光旅行のようなものじゃないですか。
「みんなと同じ」を確認する動員ではなく、自分自身の欲望を見つめ直す遊びのために
中川 与えられた課題解決で満足するか、自前で問題設定していけるのかというのは、これからのデータ×AI社会で人間はどう生きるかっていう話じゃないですか。落合陽一的に言えば、前者はAI×BI(ベーシックインカム)で基本的な生存リソースと共に与えられた生き甲斐として「貧者のVR」を宛がわれているみたいな世界観で、後者はAI×VC(ベンチャーキャピタル)で、この世界のまだプラットフォームに覆われてない未規定な部分を見つけてはイノベーションを起こして更新していくことに生き甲斐を見出すという世界観。『デジタルネイチャー』では、この二つの世界観が社会資本の格差に応じて身も蓋もなく分断していくだろうという話をしてるんですね。
ただ、この分断が固定的なものになるのかどうかは、いろいろなグラデーションや個別性に即したシナリオの振れ幅がありうると思っていて、現在のモデルケースとして考えておきたいのが、UberEatsのようなデリバリーフードサービスの配達員の話です。あれは構造的にはまさに人間がAIの奴隷になっていて、彼らは目的を与えられた課題解決型のゲームメカニクスによって働かされてるわけじゃないですか。つまり2010年代初頭にゲーミフィケーションとかゲームプレイワーキングとか呼ばれていたものの社会実装が、一方では着々と進んでいて、それがこのコロナ禍でいっそう鮮明になっている。
で、このサイトでは実際にフードデリバリーの配達員をやってみた濱野智史さんとアンチッチさんの体験記を掲載してるんですが、ゲーム的な仕掛けが搾取を搾取と感じさせずに働かせるディストピアのように批判されるけれど、実際にやった実感としては、手当もしっかりしてるし、都市を走ることでもっと多様な風景の発見もあるという話もされてるんですが、そういう世界の併存がどうあるべきかも視野に入れておくべきだと思っていて。
井上 フードデリバリーサービスは、なかなか評価が難しいですね。短期的なゲームプレイとしておもしろいということと、長期的にキャリア形成につながって所定の課題に縛られないスキルが構築されて、その人なりの持続可能な生き方ができるようになっていく状態というのが、遊びと労働の融合の理想的な姿だと思うんですが、現状はまだそのだいぶ手前にありますよね。この点は濱野さんもちゃんと批判してましたが。
ハンナ・アレントのアクション/ワーク/レイバーの分類で言えば、フードデリバリーはあくまで「レイバー」の段階ですよね。つまり、アリストテレスが奴隷にやらせていたルーチンワーク的なこととか、家事労働的な雑役です。それだけでなく、その人にしかできない自己実現的な仕事とか、社会を変えていくための創造的なタイプの「アクション」に相当する働き方にシームレスに移行できるゲーミフィケーションがあれば一番幸せな未来像になるんですが、それがゲームでできるかというのはすごく難しくて。
さっき宇野さんがおっしゃったように、「ゲームです」という構造を強くしすぎると、とりあえずフレームワークに沿って何かを極めたりはできるんだけど、その外側に出られなくなってしまう。だから「ゲームです」という構造をある程度提示しつつも、そのゲームの構造から出られるゲームみたいな、ある種自己矛盾的なゲームみたいなものを設計できるようになったら、そこにゴールがあると思います。
ただ、それこそこれはAIのフレーム問題に近くて、形式化されない遊び方をどうすれば形式から話から見つけ出せるかという話なので、ゲームの側からその回答を見つけ出すのは、すごく難しいのかなとは思いますが。
宇野 さっきの中川さんの話を含めて考えると、ゲームという問題設定から「遊び」という問題設定に少し広く考えることが重要なんでしょうね。
たとえば、僕が相対的に「STAY HOME」に適応している他の理由としては、集めているものがたくさんあるからだと思う。
たとえば今、僕の手元には「ヤモゲラス」というショッカー怪人のフィギュアがある。これは20年ぐらい前にメディコムトイから発売された「リアルアクションヒーローズ」っていうシリーズの一つです。中古で安く手に入るので、僕はこのシリーズを少しずつ集めているのだけれど、古いものなので状態が良いものが少なく、自分で修理というかメンテナンスしないといけない物が多い。その中で、プロポーションを自分好みに直したり、他の商品と組み合わせて改造したりしている。モノは集めたら終わりだけれど、それに手を加えることに終わりがないわけです。手を加えれば加えるほど、布やプラスチックや金属でモノを造形することについて理解が深まるし、こうした知識や技術の習得によって世界の見え方も変わるわけです。あ、この塗装は劣化してボロボロになっているけれど、たぶん何年くらい前につくられて野ざらしになっていたんだろうな、とか街を歩いていても考えるようになる。

▲宇野所有の「RAH220 ヤモゲラス」。『仮面ライダー』第12話「殺人ヤモゲラス」に登場。15年以上前の商品なので、経年劣化が激しく内部の素体は僕が修理、改造している。白川博士の開発した殺人光線デンジャーライトの入手が任務だが、最期はその博士にそのデンジャーライトを浴びせられて死んでしまう(仮面ライダーに倒されていない)。ショッカー史上最弱候補の怪人。

▲宇野所有の「仮面ライダー旧1号と旧サイクロン号」。これは雑誌付録のキーホルダーと、食玩の可動フィギュアとオートバイ(サイクロン)をミックスしてつくりあげた、いわゆる「3個1」の改造フィギュアとのこと。
他にも動物フィギュアとかミニカーとか、集めてるものがいっぱいある。こういうものを収集してるだけで人生まったく飽きないんですよね。
中川 つまり、冒頭の話題のような2010年代的な誰かと共有する関係性とかコト消費にアクセスするフックとしてのモノということからさらに進めて、むしろモノそのものの魅力とか環境構築力とかを再評価していく機会にできるんじゃないか、と。
宇野 そう。20世紀の終わりくらいから、消費社会批判とインターネット社会の台頭という文脈で「モノからコトへ」ということが言われてきたわけじゃないですか。消費社会批判の文脈では、一様に大量生産されたモノに執着してコレクションするなんていう趣味は、古い工業社会に魂をとらわれた空しい行為であって、街に出て人と交わって多様な関係性を築くことこそが、豊かで開かれた行為だという見られ方をしていたわけですよね。
でも、今ではこの構図は逆転してしまっていると思っていて、特にSNSが普及してからは、人間の自意識とかコミュニケーションのほうが特定のクラスタごとの同調圧力で動員されて、多くの人々が一様な動機のもとに行動するようになってしまっている。だから、今は人間ではないものがもつ多様性と奥深さと接することのほうが、むしろ豊かで開かれた体験になってきていると思うんですよね。
井上 実際、現代哲学とか人文学の領域では、10年ぐらい前からグレアム・ハーマンが唱えるオブジェクト指向存在論とかに影響を受けてイアン・ボゴストというゲーム研究の論者が、プラットフォーム・スタディーズといった流れを打ち出したりしています。
われわれが普段なにかと接したりコンテンツ消費をしたりする場面で、モノとか、物質の性質との関係のなかでわれわれの体験や欲求のあり方は形成されていくから、その性格をふまえて議論を再構築していこうという流れです。宇野さんがおっしゃる「コトからモノへ」の逆転は、そういう流れにも重なっているかもしれません。
あと、宇野さんの話を聞いていて、もうちょっとバカっぽい感想として思ったのは、『デススト』のプレッパーズの人たちの世界観って、この延長線上にあるんだろうな、ということ。プレッパーというのは、いつ核戦争とかウイルスで世界が滅亡して社会システムが崩壊しても生き延びていけるように、普段から自宅の地下室とか田舎に避難所をつくってシェルター化して大量にモノを備蓄したりサバイバルスキルを磨いて準備している人々のことで、特にアメリカで10数年くらい前から増えてきてるんですね。
今回のパンデミックで、そういう生活にもだいぶリアリティが出てきましたけど、ゾンビが発生するとかアルマゲドンが起こるとか、トンデモな理由で備えている人もたくさんいて(笑)、オンラインのコミュニティもあるらしいんですよ。何に備えているかは人によってバラバラなんだけど、世界が崩壊したときに必要になることはある程度共通しているので情報交換しつつ、それぞれがそれぞれの世界観で「これは◯◯だから××な理由で重要なんだ!」とこだわりながら、自分と家族が生きていけるような自分の城を築いている。本人たちは危機感を持ってやってるから、「楽しんでますよね?」って言われると否定するかもしれないけれど、プレッパーズの特集をした番組とかを見ているかぎり、あれって絶対楽しいはずだと思うんですよね。僕もできることならやってみたいと思うんですが、あれはアメリカみたいに広い地下室とかないしなあ、と。
宇野さんは、ある意味でそういうプレッパーズ的な完結した空間を、自分の家の中にうまく作っているんだろうなと。
中川 なるほど。するとやっぱり、小島監督の『デススト』がどれだけ今の世界に対して批評的だったか、ってことなんですよ。一方ではシェルターの中で自分の世界観を構築して巣ごもりしているプレッパーズがいて、その人たちの生活を成り立たせるコレクション品とかを主人公のサム・ポーター・ブリッジスたちが配達するというギブ&テイクの生態系が成立している。他方で、2010年代初頭型のゲーミフィケーションに取り憑かれて「配達依存症」になってしまうミュールみたいな問題も描かれつつ、サムの方には規定されたゲームから脱して、オープンワールドとして多様な世界との関わり方ができるような設計になってる、っていうね。
逆にサムには「対人接触恐怖症」という設定があって、それは2010年代のSNS社会がトランプとかブレグジットのような新反動主義を招いて世界の分断を後押しした問題に対し、物語上は改めて良きつながりを再構築することで克服していくために与えられた欠如なんですよ。ただ、実際の本作のゲームプレイとかコロナ禍で求められたのは、必ずしも接触できない欠如を克服することではなく、まずは世界の多様な地形とかモノとの孤独な戯れに、自分なりの楽しみを見出していくことでした。
実際、劇中に出てくるプレッパーズの一人に「ルーデンス・マニア」という、いまの宇野くんの話みたいなフィギュアコレクターもいるんですが(笑)、つまりコジマプロダクションのアイコンにもなっているホイジンガのホモ・ルーデンス(遊ぶ人)としての主体性は、そういう孤独と向き合う資質の中にあるとみなされているとも言える。
コロナ禍で始まった2020年代の社会への洞察として、日本を代表するゲームクリエイターの側からそういうメタ・メッセージが出てきていたのは、示唆的だったんじゃないかなと思うんですよ。

▲『ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み』
川田 遊び方を発見できる人って、自分を見つめた人じゃないですか。ここにはちょっと特殊な人たちが集まっていますが、多くの一般の人って、自分とか自分の足元とかを見つめるのが一番しんどい時間だと感じるんだと思うんですよ。そのしんどさと対をなすのが、旅行やお祭りだった。
たとえば「自分探しのために旅行行きたいな」という人がいますけど、やっぱり自分の外部に遊びを求めてるんですよね。本当の意味で自分を見つめるのはしんどいから、むしろ環境を変えることで自分が変わったと錯覚したいという気持ちがある。もちろん、そういう逃避的な部分も含めて遊びだとは思うので、僕はそっちも否定はしない派だけど。
ただ、半径500メートル以内くらいの世界でじっくり自分の価値観で見直して、そのなかで遊び方を見つけることができるなら、本当はそれが一番豊かだと思いますね。
宇野 小島さんのアプローチは、コンピューターゲームの置かれた状況を受け止めたゲーム作家の自意識の表現だとも言えると思うんです。今日の話は、そもそもコンピューターゲームに織り込まれた批評性などなくても、むしろ現代の情報環境では現実そのものにアプローチすることで、モノとのコミュニケーションの豊かさを味わうことができるという話で、コロナ禍によってその重要さがクローズアップされている、ということだと思うんですよね。だから言い換えれば、小島さんのアプローチはゲームが現実に上書きされてしまった現状への応答だと言える。
だからこそ、十夢さんは小島さんのゲームを応用して近所の風景を拡張したのだし、井上さんは遠くの街を擬似散歩することにした。そして僕はPS4のコントローラーを握るよりも、半径500メートルを歩き回り、半径5キロメートルを走ることを選んだ。
もちろん、自分の日常を見つめ直すことはしんどいことだという十夢さんの気持ちもすごくわかります。人間はすごく遠くのことが見えづらいのと同じように、すごく近くのことも見えづらいですからね。けれど、やっぱり自分の足元がよく見えていない人は、遠くに出かけても何も見つからないのは間違いないと思うんです。
だから僕は、こここそ十夢さんのような作家の出番だと思っていて、人間の創意工夫と想像力で、半径500メートルから5キロメートルの豊かさをしゃぶり尽くす「遊び」のバリエーションが、今日の議論に即して言えば同時に「対人」ではなく「対物」での遊びが、もっと豊かになればいいなと思うんです。そうすると、ソマリアやイエメンに実際に出かけたときもまた、見えてくるものがぐっと豊かになると思うので。
[了]
この記事は、中川大地が構成し、2020年8月20日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。








