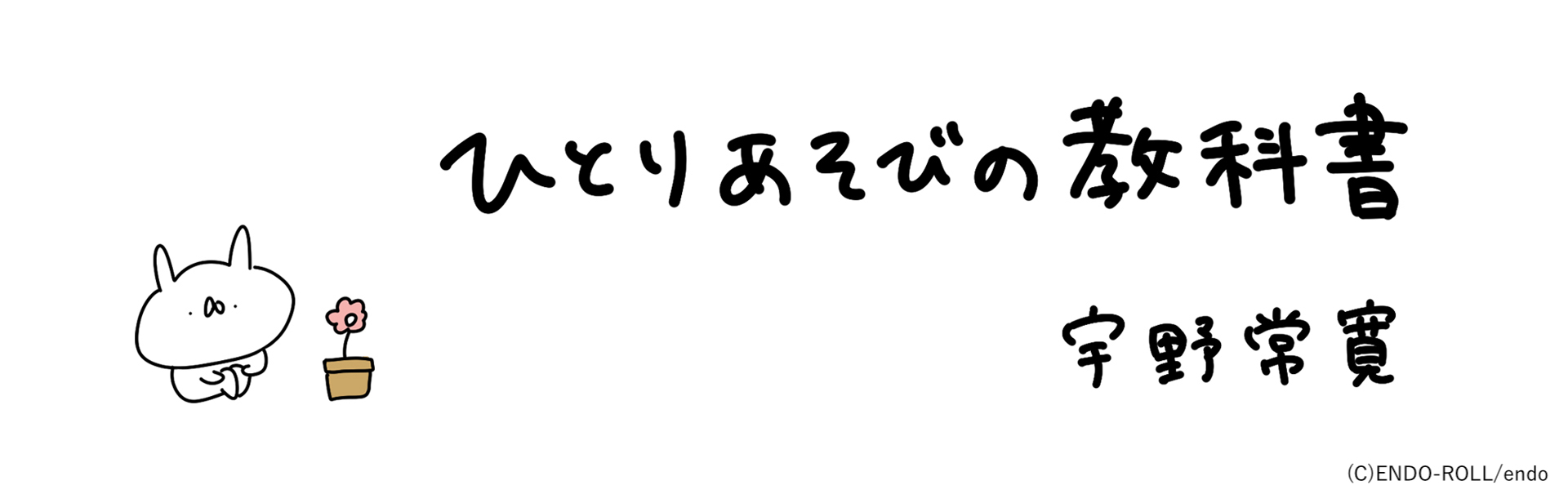僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の7回めです。
今回からしばらく、ひとりの「食べ歩き」の楽しみ方を紹介します。すべては、魔界都市〈函館〉からはじまります。
「ひとりあそびの教科書」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
この連載をもとにした本が発売になりました! 連載では扱わなかった模型作りやゲーム、読書などのエピソードをたくさん詰め込んでいます(当社比2倍以上!)。
中高生はもちろん、「ひとり」で「あそぶ」のが苦手になった大人たちも手にとってみてください。
端的に言うとね。
函館プリズン1994
前に書いたように大人の「あそび」はほとんどが、「みんな」で「お酒を飲むこと」だ。そして僕はこの「大人のあそび」がまったく好きになれなくて、ほとんどお酒を飲まない。その代わりに、食べることが好きだ。そもそも食べることが嫌いな人なんているのかなと思う人も多いかもしれない。でも、僕は子供のころはあまり食べることが好きじゃなかった。
僕は小学生のころアレルギーと喘息がひどく、そして食が細かった。その上好き嫌いが多かった。その結果どうなるかというと、給食の時間が地獄になった。当時僕は長崎県の大村市に住んでいたのだけれど、当時(1980年代半ば)の田舎の小学校では、給食を「たくさん食べること」がよいことだとされていて、そして好き嫌いは絶対に許されないことだった。給食を残すなんていう「もったいないこと」はまるで犯罪行為のように怒られた。農家の人が一生懸命育てたごはんや野菜を食べずに残すなんて、申し訳ないと思わないのかと教師たちは僕に詰め寄った。それなら、最初から配膳する量を減らして欲しいと思ったのだけれど、今思うとまったく科学的根拠はないのだけど「たくさん食べる」ことが「よいこと」だと思い込んでいた教師たちは、決められた量より少ない量を配膳することにも同意してくれなかった。そのせいで僕はいつまでも給食が食べられずに、昼休みを過ぎて、5時間目を過ぎて、放課後までそのままの状態で放置されたこともあった。現代の感覚で言うなら、児童虐待に近い何かだと思うのだけど、当時の日本の田舎町はほとんど迷信のような思い込みが幅を利かせている世界だった。

そんな僕が「食べる」ことが好きになったのは——今となっては、その日に許されるカロリー摂取の限界まで、好きなものをどう食べるかに全力を尽くしているくらいに「食べる」ことに執着する人間になったのは——高校の寮に入ったことがきっかけだった。
僕は函館にある、ある小さなミッションスクールの寮に入っていたのだけれど、この寮のごはんが壊滅的にマズかった。ほんとうに、現代日本でここまでのものがあるのかというくらいの味だった。一応、その寮には契約している栄養士がいて、その栄養士の指導で食べ盛りの男子高校生が必要な栄養をバランス良く取れるように計算されているはずだった。しかし、その計算は事実上意味のないものだった。たしかに、その栄養士の指導のおかげで、一食につき4品くらいはおかずがでてきた。だが問題はその4品のおかずのうち、人間が口に入れても苦痛なく咀嚼できるものは1品あるかないか、だということだった。僕たち寮生は、その1品を少しずつ口に運んで、できるかぎりたくさんおかわり自由の白米を胃に詰め込むことで、無理やりお腹をいっぱいにしていた。魚の小さな切り身一つで、どんぶり山盛りのごはんを胃に詰め込むこと。それが、あの寮で生き延びるための唯一の方法だった。
その結果、毎食大量の残飯が発生していた。ほとんどの寮生が、4品あるうちのおかずのうち1品しか食べないのだから、どうしてもそうなってしまう。当時のあの寮では、人間の背丈くらいある大きなポリバケツ数杯分の残飯が1日3回、発生していた。僕の母校は海外の有名な修道院の運営するミッションスクールで、毎年クリスマスには恵まれない人のために寄付を募ったりしていたはずなのだけど、毎食、おそらくはトン単位の残飯を出していた(寮に住み着いた猫たちはその残飯を無限に漁っていたため、自力歩行が不可能なほどまるまると太っていた)。校長先生をはじめとするローマの本部から派遣されたブラザー(神父)たちは、建前的には寮の食堂で僕たちと一緒にごはんを食べることになっていたのだけど、ほとんど彼らを夕食時に見かけることはなかった(後に、近所のとんかつ屋の常連であることが判明した)。
寮には1日1000円以上の食費が徴収されていたので、当時の物価を考えると決して安くはなかったのだけど、なぜか僕たちの食生活は信じられないくらい劣悪だった。
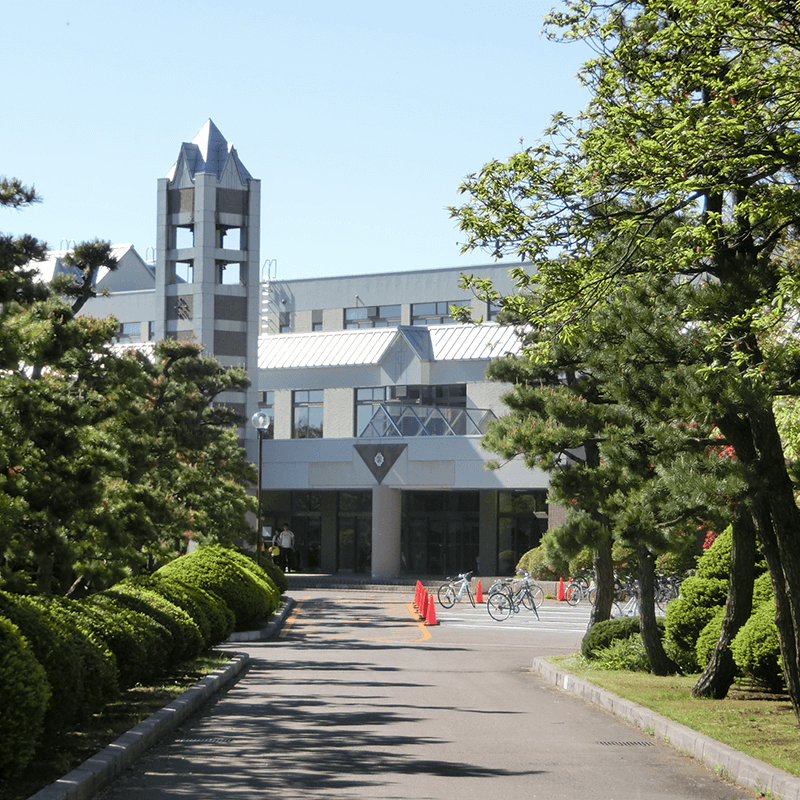
しかしそれでも、まだ4品中1品食べられるものがあるときは幸福だった。
いまだに忘れられないのだけれど、当時あの寮では「ゴム肉」と呼ばれていた、一応豚肉であると主張されていた謎の肉片がよく出てきた。これはあの寮で出てくるすべての料理に当てはまることなのだけど、基本的に冷え切っていて、パサパサと乾いていた。噛むと固くてなかなか噛み切れず、その通称の通り輪ゴムのような臭いがした。そしてほとんど、味がしなかった。肉自体に味がないのをごまかすように、無造作かつ大量にケチャップとパイナップルのソースがベチャッとかかった「ポークソテーハワイアン」がそのゴム肉を使った定番メニューだった。このメニューのときは、ゴム肉とケチャップの臭気が入り混じり、食堂に近づくだけで軽い吐き気がした。
ほかにも、骨ばかりでほとんど身がない正体不明の魚フライ(謎のフレンチソースがかかっていて、それがまた一口食べただけで失神するくらいまずい)とか、公衆トイレの臭いのするこれまた正体不明の貝のたくさん入った海鮮トマトスパゲッティとか、ほんとうに摂取不可能なメニューがいくつかあり、そんなとき僕らはなけなしの小遣いをはたいて、近所のダイエーでふりかけや生卵を、あるいは惣菜コーナーでコロッケやメンチカツを買ってきて飢えをしのいだ。僕はよく、食パンにマヨネーズをかけたものを寮のトースターで焼いて食べていた。
普段、こんな食生活だったので、寮のクリスマス会でモスバーガーとハーゲンダッツのアイスクリームが出たときは、この世でこんなにおいしいものがあるのかと涙が出てきた。
夏休みや正月に実家に帰省して母親の手料理を食べると、寮の食事とのあまりの違いに、生まれて始めて母の炊事に心から感謝した。そして、1日3回、夢中で貪り食った。僕に限らず、おそらくほとんどの寮生は入学後数ヶ月の寮生活でげっそりと痩せていた。そして1年生の最初の夏休みの帰省時に保護者たちは子供の健康上の危機を覚え、ひたすら食べさせるという行為に出ることが多かった。その結果として在校中の3年間、ほとんどの寮生は学期中に痩せて、休暇の帰省中に太るということを反復していた。


食べ盛りの男子高校生が3年間、このような食生活環境下に置かれた結果、何が起きたか——。まず、好き嫌いがほとんどなくなった。たとえばそれまで、僕は生野菜に苦手なものが多かった(トマトも、大根も嫌いだった)が、この寮において生野菜サラダはその存在が貴重であるだけではなく(冬場にはほぼ出なかった)、サラダというあまり手がかかっていない料理は誰が調理しても最低レベルの味が保証されており、これを食べないという選択肢は生存戦略的に存在しなかった。こうして僕は、生まれてから15年間悩まされ続けてきた偏食を、この3年間でほぼ克服した。僕は悟った。世界にはまずい食材なんてない。まずい料理があるだけなのだ。
そして、ほんとうに、ほんとうに意地汚くなったと思う。好きなものを、好きなように食べられることがどれほど人間にとって幸福なことか、それを僕はこの3年間で思い知った。そして寮から「娑婆に出た」僕は、「食べる」ことそのものが大好きな人間になっていた。


お酒を飲まない僕は「食べる」ことが好き
こういう事情があって、僕はいまでも「食べる」ことが大好きだ。夜寝る前は、必ず明日は何を食べようか楽しみに考えるし、死ぬまでの間に一食たりとて無駄にしたくない。これは当たり前のことのように聞こえるかもしれないけれど、意外とそうじゃない。「食べる」ことが嫌いな人はたしかにまずいないのだけれど、「食べる」ことをそこまで重要に考えない大人は実は結構いる。
何度も書いているように僕はお酒を飲まない。しかし大人の「あそび」はほとんど「飲みに行く」ことを指している。そうすると、誰かと「あそぶ」とき、だいたいどこかの飲食店に入ることになるのだけれど、僕はつねに「食べる」ことにとても関心があり、その一方相手はお酒を「飲む」ことに関心があるというすれ違いが起きる。
たとえば、お酒が好きな人はよく居酒屋に行く。お酒の種類が豊富で、食べ物のメニューもお酒によく合う「つまみ」が多いからだ。けれど、僕はこの「居酒屋」がすごく苦手だ。お酒を飲まない人間にとって、居酒屋のメニューはどれも味が濃すぎて、食べづらい。店の雰囲気もざわざわしすぎていることが多くて、酔っ払って気分が上がっている人じゃないとあまり居心地のいいものじゃない。

あと、お酒を飲まない僕は「コース料理」というものに違和感を覚えることが多い。それが和食でもイタリアンでもフレンチでも、コース料理は「お酒を飲みながら食べる」こと前提になっている。居酒屋と違って、味はお酒を飲まなくてもおいしく食べられるものが多いけれど、料理が出てくる間隔が、明らかにお酒を飲んで気分の盛り上がった人が高いテンションで話しながら料理を楽しむことを前提にしていて、僕のようにお酒を飲まない人はよほど会話が盛り上がっていないかぎり手持ち無沙汰になってしまう(だから僕はこういうレストランでは、アラカルトで頼むことが多い)。
だから僕はコース料理よりもプレート(定食)が好きだし、テイクアウト(中食)も好きだ。最近では、感染症対策でレストランの料理をテイクアウトして、自宅で食べることも増えていると思うけれど、これが意外と楽しいと思った人は多いんじゃないかと思う。後出しジャンケンみたいだけれど、実は僕はずっとそう思っていた。レストランでお酒を頼むと、それだけでぐっとお金もかかるようになるし、なによりこうして家で食べると食べ方がぐっと自由になる。盛り付けやアレンジを工夫して「食べる」ことには、お店で決められた食べ方をするのとはまた違った面白さがある。
「お酒を飲む人」のやり方とリズムに合わせる必要がなくなると、それだけでぐっと「食べる」ことが楽しくなるのだ。

そして、ここからが大事なのだけど、もちろん誰かと一緒に食事をすることは楽しい。けれど、そこにお酒という要素が加わると、その場は「お酒を飲む」というあそびのルールに支配された場所になってしまうと思う。特に3人以上で集まっているときはそうなりやすい。お酒を飲みながらワイワイ騒いで、「仲間」と「そうじゃない人たち」の間に線を引く。そのことで「安心する」。そんな「あそび」のほうが大事で、目の前の皿の上に乗っているものをあまりちゃんと味わっていないことがかなり多いんじゃないかと僕は思う(実際にそんな「飲み会」「食事会」をたくさん見てきた)。でも、それはちょっともったいないんじゃないかと僕は思う。
だから僕は、ある時期から——具体的にはお酒を飲むのを止めた30歳を少し過ぎたあたりから——ひとりで好きなものを食べ歩くようになった。
人と話すために「食べる」のではなく、「食べる」ことそのものを楽しむためには、ひとりで食べに行ったほうがいいときが多いと感じたからだ。もちろん、誰かとご飯を食べることはとても楽しい(ときもある)。しかし、楽しければ楽しいほど、意外とそこで食べたもののことをしっかりと覚えていない、そんな経験はないだろうか。僕にはある。だから僕は、本当に好きなものはなるべくひとりで食べに行くようにしている。ただひとりで、孤独に目の前の食べ物と向き合う、そうして自分のやり方とリズムで目の前の食べ物をじっくり味わうことができるのだ。
[了]
この記事は、「よりみちパン!セ」より刊行予定の『ひとりあそびの教科書』の先行公開です。2021年2月11日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。