NHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回は『亡命ロシア料理(新装版)』『海を渡った故郷の味』の2冊を紹介します。亡命した人々が、祖国の料理を紹介する両書。井本さんは、亡命者たちの「暮らしのリアル」がさまざまな箇所ににじみ出ていることに注目します。

端的に言うとね。
この書評コーナーでは、暮らしにまつわる本を紹介しています。アウトドアとか自然とか、そういったものを含めた「暮らし」です。いつもは1冊ですが、今回は『亡命ロシア料理(新装版)』(2014年、未知谷)と『海を渡った故郷の味』(2013年、自費出版)の2冊をあわせて紹介させてください。
まず『亡命ロシア料理』から。この本の著者は、ピョートル・ワイリさんとアレクサンドル・ゲニスさんという2人のロシア人文芸批評家です。原著が出たのが1988年なので、少し古い本ではあります。1970年代から80年代には、ソ連からアメリカへの亡命がたくさんあって、文学者だと反体制派の作家ソルジェニーツィンなんかが有名ですよね。本書の著者2人の場合、沼野充義さんの「訳者あとがき」によると1977年にアメリカに亡命していますが、「反体制派で命からがら逃げた」というわけではないようです。1970年代のソ連では、ユダヤ系市民の国外移住が合法的に許可され、多くの人がアメリカやイスラエルなどに渡った時期があるそうで、著者2人もこの流れにのってアメリカに移ったのではないかということです。
福田和也氏などがむかし指摘していたことですが、ソ連社会は文芸批評家の地位が高いそうなんです。かつての日本も、そういった風潮がありましたよね。アメリカやヨーロッパだとそんなに高くないんだけど、ソ連では文芸批評家がイコール文明批評家でもあるようなポジションとなるそうなんですね。本書の著者2人も、そんなソ連の文芸批評家ですから、この本はロシア料理の本なわけですが、純粋な料理本にはなりません。そこにはやっぱり文明批評的な目線が加わってくるわけです。この本の冒頭で、著者たちはこのように記しています。〈靴底の土くれのように故郷を外国に持ち出すわけにはいかない〉(〈〉内引用。以下同じ)けれど、故郷の料理なら持ち出すことができる。〈人間を故郷と結び付ける糸には、じつに様々なものがなり得る〉が、〈故郷から伸びているいちばん丈夫な糸は〉〈胃に繋がっている〉、と。人間は魂で故郷と結びついていることが必要なんだけれども、亡命して異邦人として生きるとき、故郷の土地を持っていくわけにいかない。だから、「料理を持っていくんだ」と2人は記しているのです。まあ、こういっちゃあなんですが、特に異論はないがわりと普通というか、ありそうな意見ではありますよね(笑)。1988年当時に冷戦下の世界的ムードを背景として読めば、いま読むのとは違う凄味があるのかもしれませんが、わりと普通の認識です。ところがなにしろソ連の文芸批評家の書くことだから、この本はそう一筋縄ではいかないんです。単に故郷ロシアのレシピを紹介し、料理を通した故郷との結びつきを確かめていくといった内容では、この本はないんですよ。
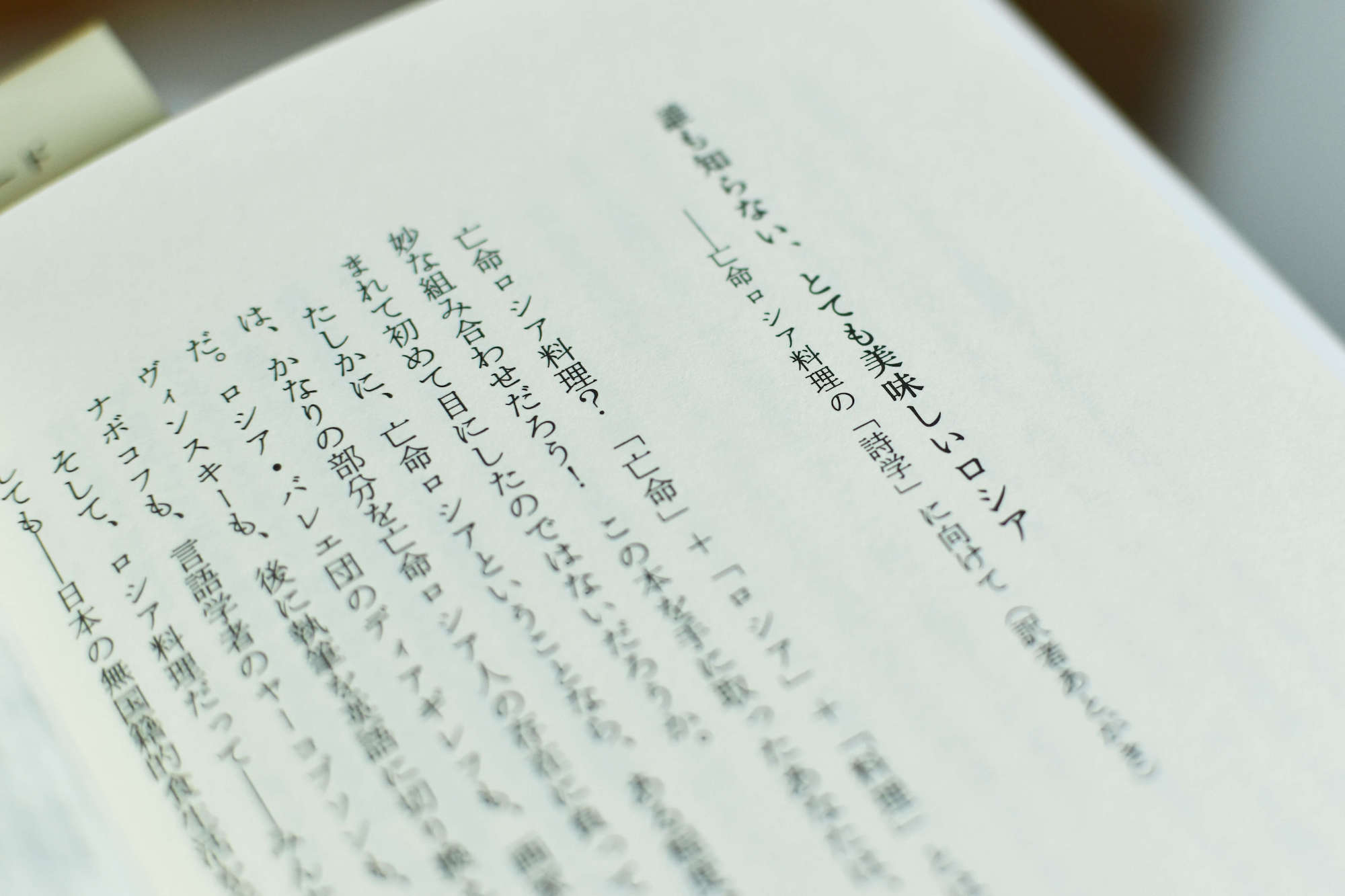
これも「訳者あとがき」に書いてあることで、「なるほどな」と思ったんですけど、さっき名前を挙げたソルジェニーツィンはアメリカへ亡命しても、暮らしはロシア風をつらぬき、アメリカ文化を強く拒否した亡命生活だったそうです。本書に描かれる著者2人の亡命生活は、ソルジェニーツィンとは逆です。アメリカ文化との遭遇のドキュメントとなっています。だから、ロシア料理のレシピであっても、それは「アメリカでつくるロシア料理」なんですね。アメリカのなかで生きていることのリアリティみたいなものが反映されているんですよ。たとえば本書によれば、ロシアからアメリカに亡命した人たちは、みんな一度はシーフードに惹かれる時期があるそうなんです。なぜかといえば、ロシアでは新鮮なシーフードが手に入らず、アメリカではじめてそのおいしさに触れて感化されるんですね。「アメリカに亡命して、シーフードに慣れてきて、こんな海鮮を料理しましたよ」なんて書いてあるんです。こんなふうに、故郷ロシアから持ち込んだ料理だけじゃなくて、ロシアからアメリカに来て出会う食体験の話も本書にはたくさん登場しています。亡命の暮らし自体が描かれているんですね。そのなかで亡命者たちの、苦労もあればそこで知恵も働かせるし、もちろん悲しいこともあれば、でもそれだけではなく喜びもあって、その両方が交差し続ける暮らしが食を媒介に描かれているからこそ、「ああ、これは現実に生きている人の話だ」って感じるんですね。具体的な人間の存在が見えてくる本なんです。
ひとつ本書から紹介しておくと、グルジア(現:ジョージア)料理というのが登場します。ジョージア料理はロシア料理のバリエーションで、本書でも〈ロシアの料理のなかでも一番色鮮やかで、ぴりっとして、生き生きとしていて、豪華に見えるのは〉〈グルジア料理だ〉と絶賛されています。たまにネットなんかで「実は日本人好みの料理」だと話題になることがありますが、そんなに日本で知られているわけではないですよね。東京で食べられる店も、ロシア料理店がそのメニューの一部としてジョージア料理を提供しているってかんじです。それも東京に数軒あるぐらいです。ちなみに、思いっきり話が逸れますが、そのうちの1軒である新宿のスンガリーは、ぼくが20代のときによく行った思い入れの強い店で、おすすめしておきます。メニューのうちのどれがジョージア料理だったのかは、わかってませんでしたが(笑)。それぐらい、ジョージア料理って、日本では知る人ぞ知る料理なんですが……話がずれ続けますが、そんな東京でも数軒のロシア料理店でしか食べられないはずのジョージア料理が、なんと全国で食べられるようになるんです! いま牛めしの松屋の一部店舗でジョージア料理のシュクメルリっていう、にんにくをきかせて鶏肉を煮込んだシチューのような料理が期間限定で提供されています。それがなんと、好評につき1月から全国の店舗で提供するらしいんですよ!!!(2019年放送当時。以下同じ)せっかくの機会ですから、ぜひジョージア料理を楽しんでみてください。
すみません、いいかげん話を戻します。なぜジョージア料理の話をしたかというと、ロシア料理自体が、一枚岩の純粋なものではないということです。ソ連という国が国際主義みたいなかたちでいろんな国の統合を指向していく過程で、ロシア料理も国際的にまざりあっていくんですね。著者は、〈国際主義の理想がわれらの祖国で実現したのは、料理の分野だけだった〉なんて憎まれ口を言うわけですが。たとえばペリメニという餃子みたいな料理がありますが、あれはシベリアの料理です。プロフっていうチャーハンみたいな料理は中央アジアの料理だったり、ジョージア料理のようなコーカサス地方の料理だったり、そういう色んな料理がロシア料理にまじりあっていくんです。国の成り立ちまで見えてくるのが本書の射程で、そこが面白いんですね。
さて、『亡命ロシア料理』は米露の話ですが、「日本も亡命と無関係ではないですよ」ということが伝わるのが、今回紹介するもう1冊、『海を渡った故郷の味』です。認定NPO法人難民支援協会の編著になります。これは日本に亡命してきた難民の方たちが、故郷のメニューを紹介するというレシピ本で、15の国や地域から日本に亡命してきた方たちのレシピが載っています。この本の冒頭には、『亡命ロシア料理』と似たようなことが書かれているんですね。〈家庭料理の味や匂いの記憶は、生まれ育った土地の記憶を呼び起こすもの〉、と。異邦の地で、料理が故郷を取り戻す手段だということですね。けれど、さきほどの『亡命ロシア料理』と同じように、この本もまた、実際に読むと単純ではないなと感じるんです。
たとえば異国にいて故郷の味って、どうしたってそのまんまでは作れないんですよね。材料も調味料も違うわけです。亡命を強いられるような政情の国ですから、取り寄せることだって困難な場面が多々あるでしょう。そこで、知恵を働かせた工夫が生まれるわけですね。僕がこの本で作ったレシピでいうと、ミャンマーのチン族の方の紹介する「鶏肉と小松菜のカレー」というのがあります。本書の紹介によれば、〈チン民族は標高3,000mの高山地域に住む少数民族〉とのことで、そうすると故郷のスパイスなんて日本では、まあまず手に入りませんよね。そこでなんと、日本でポピュラーな七味唐辛子をカレーのスパイスとして使うんですよ! 本書を見ていただきたいんですけど、このレシピでスパイスとして使用されているものは、本当に七味唐辛子だけです。カレースパイスとしての七味唐辛子というのは、目から鱗が落ちましたね。また話が脱線しちゃいますが、七味唐辛子って意外と賞味期限が短いうえに、そんなに大量に使う機会もないから、期限切れで無駄にしちゃうこと多くありませんか。この「鶏肉と小松菜のカレー」のレシピならまとまった量を使えるので、七味唐辛子の賞味期限せまったらこれ、作ってます(笑)。美味しいし、なにより「自分が食べ慣れてるはずの七味唐辛子でこんな味が!」という驚きが面白いんです。他にも、アゼリというアゼルバイジャンの地方の料理が載っているんですけど、このレシピを紹介している方はアゼルバイジャンの独裁政権への抵抗運動をして投獄などもされ、命からがら日本に亡命してきた方だそうです。〈日本に逃れてきて、20年〉〈まだ、母国には帰れない。出来るならば、今すぐにでも戻りたい。そして、母国にいる母や兄弟と一緒に、食卓を囲みたい〉と語るんです。ところが、この方の紹介するアゼリのレシピには、「日本人向けに人参を混ぜてみました」なんて書かれてるんですよ(笑)。いまも強く焦がれる故郷の味の再現ではなくて、いま暮らす日本の人たち向けに「日本ではこういう味がウケるでしょう」とばかりにアレンジしたレシピなんです。なんか、そういうところに、強く僕は胸打たれるんですね。いわば魂に結びついた純粋な故郷の味というのではなく、厳しい状況のなかでいま日々暮らしている日本の生活が反映しているんですね。そして、『亡命ロシア料理』と同じく、その暮らしのなかに、悲しみとともに喜びがあって、苦労とともに知恵があって、「人が、リアルに生きているんだな」って感じが伝わるんです。

日本には難民認定された人が1万人います。故郷で命も脅かされるような厳しい状況から日本にたどり着いたわけですが、日本が楽園というわけでもありません。そもそも2018年には、約1万人の難民申請に対して認定者42人、1%にも満たないのです。これは諸外国と比べてめちゃくちゃ、驚異的に低い数字です。それから、いまたいへん問題になっている入管施設の人権侵害の問題も、難民に関係する問題ですね。入管施設とは、在留資格がないなどの理由で国外退去命令が出された人を、退去までのあいだ収容する施設です。国外退去までといっても、難民の方や難民申請をしている方は、そもそも故郷の国にいることができなくて亡命しているわけですから、故郷の国には戻れません。そうすると、入管施設に長期にわたっていつまでも収容され続けることになります。この長期収容は、国連からも是正を勧告されるなど国際的に批判されていることは、ニュースなどでご覧になったことがあると思います。ただ、ニュースだけでは、「理不尽な状況に置かれているリアルな人間がいる」っていう実感までは、なかなか届かない場合があるかもしれません。そんな伝わりづらい、「リアルに存在し、生き、暮らしている」人間が、厳しく理不尽な状況に置かれているということが、このレシピ本を読むと伝わるように僕は思います。なので、そんなことも含めて、今回は『亡命ロシア料理』と『海を渡った故郷の味』の2冊をあわせて紹介しました。
【サイト掲載にあたっての追記】
松屋のシュクメルリは好評を受け、2021年1月19日より復活。ほかにも、コンビニ各社の弁当ラインナップに加わったり、カップ麺にアレンジされたものが発売されたりして、いまやすっかり知名度は上がっている。『海を渡った故郷の味』は現在、新装版(2020年、株式会社トゥーヴァージンズ)が購入可能。今回紹介した旧版から内容面での大きな相違はないとのこと。

[了]
※この記事は、2019年12月26日に配信されたPLANETSのインターネット番組『オールフリー高田馬場』内のコーナー「井本光俊、世界を語る」の放送内容を再構成したものです。石堂実花が写真撮影をつとめ、2021年3月18日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。