誰もが一緒に遊んで育った「おもちゃ」たち。そのデザインの裏側には、時代が求める「成熟」への願い(あるいは「呪い」)が潜んでいる……? ボーイズトイの歴史を辿りながら、デザイナー/小説家の池田明季哉さんが“kawaii”ならぬ“kakkoii”の解放を考えていく新連載。初回は「G.I.ジョー」とアメコミヒーローを通して、アメリカが理想とした男性像の変遷を追いかけます。
「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
子供のころ遊んだおもちゃのことを、覚えているだろうか。
そう言われて、まったくなにも思い出せないという人は稀だろう。買ってもらえたもの、買ってもらえなかったもの、大切にしていたもの、捨ててしまったもの、なくしてしまったもの、今でも大切に持っているもの……さまざまなおもちゃの思い出が、誰の心にもきっとあることと思う。
この連載では、そんなおもちゃのデザインを通じて、21世紀における男性的な「かっこよさ」について考えていく。
主に登場するのは、80年代から90年代──20世紀末に流行した、幼稚園から小学生程度までの男子を中心的なターゲットにする、いわゆる「ボーイズトイ」と呼ばれる日本のおもちゃ群だ。
トランスフォーマー、ミニ四駆、SDガンダム、ゾイド、ビーダマン、ミクロマン、勇者シリーズ……20世紀末に子供時代を過ごした現在30歳前後の世代ならひょっとすると懐かしさを感じるかもしれない。

▲トランスフォーマーより「コンボイ」(画像出典)

▲ミニ四駆「シャイニングスコーピオン」(画像出典)
私は多くの人と同じように幼少期におもちゃに慣れ親しみ、そして多くの人とは違って大人になった今もおもちゃで遊び続ける、おもちゃファンのひとりだ。そして遊び盛りの娘におもちゃを買い与える立場にある父親でもある。だからこの20世紀末のボーイズトイという世界が、一般的に「おもちゃ」という言葉からイメージされるものとは大きく異なる、著しく狭い領域であることもよくわかっているつもりだ。
この連載で紹介するおもちゃの多くは、教育を目的とした積み木のような知育玩具ではなく、あるいはアンパンマンや仮面ライダーのような、映像メディア上の存在を写し取ったキャラクター玩具でもない。メディアミックスされつつもプロダクトを中心として展開し、それゆえに独自の表現を発展させてきたユニークなデザインのおもちゃ群だ。「男の子」たちの欲望に徹底して応えていった結果、これまでになかった新しいデザイン文化がおもちゃの世界を舞台に花開いたのが、20世紀末というタイミングだったと私は考えている。
こうしたおもちゃのデザインについて考えることで、私はひとつの「やり残した宿題」を解くヒントを見出したいと思っている。20世紀の男性が解くべきだった、そしていまだ解かれていない難問。それは「21世紀の男性にとって、『かっこいい』とはなにか」ということだ。もし「かっこいい」という言葉が曖昧すぎるなら「男性的・父性的な成熟のイメージ」と言い換えてもいい。子供はどのように大人になり、社会と関係していくべきなのか。更新がうまくいかないまま停滞して久しい男性文化をリニューアルしていくヒントを、20世紀末のボーイズトイを振り返ることで改めて発掘していきたいと私は考えている。この20世紀のおもちゃのデザインから導かれる21世紀のあたらしい男性性を、アメリカ児童文化を大胆に再解釈し日本から世界に再輸出した偉大なる先達「kawaii」文化に倣って、この連載では「kakkoii」と呼ぶことにしたい。
こうしたボーイズトイ的なものに宿る美学を「kakkoii」と名指したのは、本連載がはじめてではない。宇野常寛編『PLANETSVol.8』に収録された鼎談〈「装い」の環境分析――身体の虚数化と僕らの資本主義〉で千葉雅也が紹介するように、現代アーティストのハヤマトモエは、ミニ四駆のステッカーを用いたコラージュ作品を作り、そこに宿る美学を「kakkoii」と命名した。本連載では、ハヤマトモエの提出したこの概念を拡張していく。具体的なことは、後にミニ四駆の分析に関連して詳細に論じることになるだろう。
もうひとつ断っておきたいのは「ボーイズトイ」という言葉の持つ意味合いと、この連載における使い方についてだ。私はおもちゃにおける伝統的な「男の子向け」「女の子向け」という表記は、ジェンダーの自由の観点からすぐにでも撤廃すべきだと考えている。身体的な性別や性自認がどのようなものであれ、人は自分の共感するおもちゃ、成熟のイメージを自由に選択できるべきだ。しかしながら、おもちゃのデザインの歴史を考えていく上で、理想の成熟のイメージとジェンダーが結びついてきたという事実を避けて通ることはできない。この連載ではおもちゃにまつわる男性的な美学を論じていく。そのため「男の子向け」「ボーイズトイ」といった、玩具を特定の性と結びつける言葉が頻出するし、ときにはその受け手を「少年」「男の子」と表現する場合もある。しかしそれはあくまで「象徴あるいは美学の上での男性」あるいは「当時のマーケティング上のセグメントとしての男性」であって、男性以外の性を、ボーイズトイそのもの、およびボーイズトイが表現してきた美学から切り離し排除する意図がないことは、理解してほしい。むしろこの連載は、こうしたボーイズトイの築いた豊穣な文化の素晴らしさを、あらゆる人に開き伝えていくために書かれている。
序章では、まずは前提として本連載で扱うおもちゃの範囲と位置付けを確認しつつ、世紀末ボーイズトイに接続される前日譚を整理しておきたい。この前編では、おもちゃ自体の社会的位置付けと、20世紀までのおもちゃが担ってきた男性性について確認する。次回の後編では、世紀末ボーイズトイの原点となったエポックメイキングなおもちゃを紹介しつつ、この連載で扱うおもちゃを定義づけていく。
原初のフィギュアが語る「成熟」のイメージ
おもちゃは一般には「子供のもの」と認識されていると言ってよいだろう。だからひょっとすると、おもちゃについて考えることで成熟のイメージを考えようという試みは、いささか唐突なものに聞こえるかもしれない。しかしむしろ児童文化であるからこそ、おもちゃは成熟のイメージと強く結びついてきたのである。
おもちゃの歴史は古く、先史時代まで遡ると言われている。これは人類はその文明の誕生とほとんど同時期から、連綿とおもちゃで遊び育ってきたことを意味している。長い歴史の中で培われてきたおもちゃの世界は広大であるが、その中でも本連載で注目したいのは「フィギュア」という分野だ。
おもちゃの文脈で使われるとき、フィギュアという言葉は「ある対象のかたちを写し取ったもの」を指す。対象と同じスケールのものもあるが、縮小されていることが多い。現代の日本でフィギュアといえば映像作品などに登場する美少女やヒーローを立体化した商品を指すことが多いが、ここでは原義に立ち返ってより広い意味でこの言葉を使っていく。
フィギュアは子供にとっての「大人」のイメージと深く関係している。
イギリスの歴史作家であるアントニア・フレイザーは、その著作『おもちゃの文化史』の中でさまざまな古代のおもちゃを紹介しており、フィギュアをもっとも原始的なおもちゃの一種として取り上げている。動物や人間を象ったフィギュアは新石器時代から存在しており、もともと祭祀や儀式に使われる宗教的なものであったと言われている。フレイザーは、こうした宗教的なフィギュアは役目を終えると子供に払い下げられ、おもちゃとして機能するようになったと指摘している。
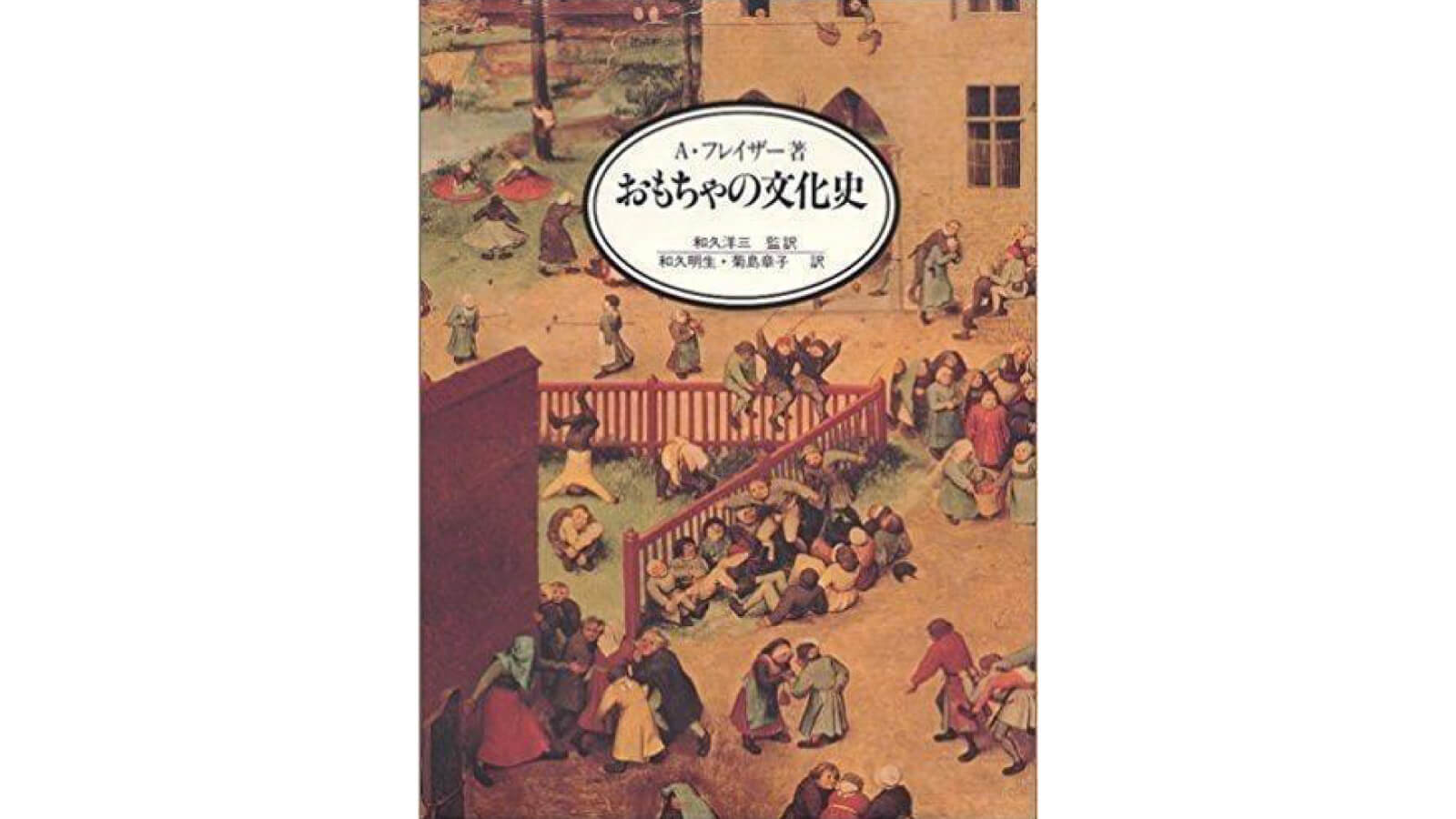
▲アントニア・フレイザー著「おもちゃの文化史」(画像出典)
フレイザーによれば、子供はこうしたフィギュアを使って、大人の行う祭祀や儀式を模倣して遊んでいたという。そして大人は、フィギュアを宗教について子供に教えるために使っていた。前近代の社会において、宗教的な規範を身につけることは、そのまま成熟し大人になる道筋となる。言い換えれば、フィギュアとは原始の時代から、子供が「理想の大人とはなにか」「成熟とはなにか」について学ぶための、さらに言えば世代を超えて文化を伝達するためのメディアとして機能してきたのである。
ある文化における「大人」のイメージがフィギュアを通じて伝えられるのなら、男女によって社会的役割が異なる社会において、フィギュアは自然にジェンダーと結びつく。
現在出土している中でもっとも古いフィギュアとされているのは、オーストリアで出土した「ヴィレンドルフのヴィーナス」と呼ばれるものだ。これは旧石器時代に多産や豊穣を祈願するために作られたと見られており、豊満な乳房や臀部、女性器といった性的な特徴が強調されている。
このフィギュアの用途は考古学者の間でもいまだ議論の分かれているところであるし、そのものが役割を終えた後おもちゃとして使われたかどうかは定かではない。しかしこれが当時の価値基準に照らして、理想化された女性の姿を描いているとは言ってよいものと思われる。この時代の子供たちが日常のなかでこうしたフィギュアを目にしていたとすれば、肥満した姿こそが理想の大人の女性の姿であり、多産こそが全うすべき女性の役割なのだということを学んでいった可能性は十分にあるだろう。

▲ヴィレンドルフのヴィーナス(画像出典)
フィギュアの身体は憧れの器
こうしたフィギュアの位置づけは、現代においても健在である。わかりやすい例は、アメリカのマテル社が1959年から発売している女児向け着せ替え人形「バービー」だ。

▲現代のバービー。(画像出典)
バービーはもともと、実際の人間に比較すると胸と尻が大きく、それ以外は非常に細い体型をしていた。登場した当初はファッションモデルなどを参考にしつつもおもちゃとしてディフォルメされた架空の体型として作られていたはずだが、近年はあまりに細すぎて実現不能な体型が子供に誤った理想像を押し付けていると批判されるようになっていた。これに応える形で、マテルは2016年、バービーに「petite(小柄)」「tall(長身)」「curvy(ぽっちゃり)」というより現実的な体型のバリエーションを発売することになった。また肌の色や顔の特徴についても、当初はステレオタイプないわゆる「白人」しかラインナップされていなかったのが、今ではさまざま肌色や顔立ちが用意されるに至っている。バービーの身体は、子供が理想として共感し目指せるものでなくてはならないと考えられているのである。

▲体型・人種ともにさまざまなバービー。(画像出典)
バービーのウェブサイトでは「YOU CAN BE ANYTHING(何にだってなれる)」というキャッチコピーと共に、複数の職業が並べられたバナーが配置されている。このリストは「妖精のお姫様」といった女性的でファンタジックなものを含みつつ、残りは「芸術家」「医師」「アスリート」「パイロット」「スケートボーダー」など、伝統的には男性的とされてきたような(そして統計的にはまだまだ男性が多いであろう)職業を、おそらく意図的に選択して配置している。あえて古い言い方をすれば「女の子であっても」こうした職業を目指せる、成熟のかたちとして選ぶことができる、というメッセージが強く印象付けられており、こうした理想像の発信がバービーというフィギュアのブランディングに必要だという、メーカーの判断が伺える。

▲2017年8月、公式ウェブサイトのトップに掲載されているバナー。(画像出典)
こうしたバービーの変化を見ても、フィギュアというものが理想の成熟のイメージを担っているという発想を、メーカーもユーザーも強く共有していることがよくわかる。このようなフィギュアの側面は、同じように古代から現代に至るまで存在しているボールやコマといったフィギュア以外のおもちゃにはない特徴と言える。
この連載では、最初に挙げたトランスフォーマーやミニ四駆のようなおもちゃにおける、こうしたフィギュア的側面について考えていく。たとえばミニ四駆は一般的な分類においてはフィギュアではないのだが、そのデザインに込められたジェンダー的な理想像にまつわる想像力を読み解いていくという意味では、ミニ四駆をフィギュアとして捉えていくことはできるだろう。確かにこれらのおもちゃのデザインはバービーに比べれば現実から遠く離れた空想のものであるし、それゆえにこれまで理想のジェンダー像としては真剣に語られてこなかったように思う。しかしこうしたおもちゃが「男の子向け」として販売され、そして主に男の子に支持され流行したことの背景に成熟のイメージの変化を読み取ることは、むしろ自然な発想ではないかと考えている。
日本おもちゃの「父」アメリカントイ
古代から現代に至るまで、フィギュアがジェンダーと結びついた成熟のイメージを伝える役割を持っていることを、バービーといういわゆる女の子向けおもちゃの例から見てきた。
この連載の目的は、男の子向けおもちゃのデザインを通じて20世紀末に現れた、新しい男性的な成熟のイメージについて考えることである。
そこでまずは20世紀という時代に一度完成を見た、旧い男性性のイメージについて整理しておきたい。
20世紀は、かつてないレベルの工業技術を手にいれた人類が未曾有の発展を遂げた時代だった。そして同時に、その工業技術が二度にわたる世界大戦を引き起こした時代でもあった。20世紀が暴力や競争といった男性的な原理によって駆動され支配された時代だったということは数多くの男性学の研究者によって語られているし、もはや一般的な認識と言って差し支えないと思う。
そんな20世紀を象徴する国をひとつ挙げるとしたら、おそらくそれはアメリカだろう。19世紀末に本土の開拓を終えて以来、20世紀を通じて新たなフロンティアを求め続けてきたアメリカは、結果として世界一位の経済大国として君臨することになった。そして文化においても世界をリードすることになったのである。
戦後の日本文化にアメリカ文化の強力な影響があったことは、もはや改めて議論する必要もないだろう。おもちゃの世界においても、それは色濃く表れている。戦後日本のおもちゃの歴史は、アメリカのおもちゃのローカライズの歴史であったと言っても過言ではない。
それではアメリカにおいて、おもちゃに現れた理想の男性性とはどんなものだったのだろうか。
「おもちゃの兵隊」の究極形
自然科学者でありながらおもちゃ研究家でもあるアンドルー・マクラリーは、その著書『おもちゃの20世紀ーアメリカン・トイ・ストーリー』の人形の項目において、アメリカの男の子向けフィギュアの代表として「おもちゃの兵隊」を挙げている。
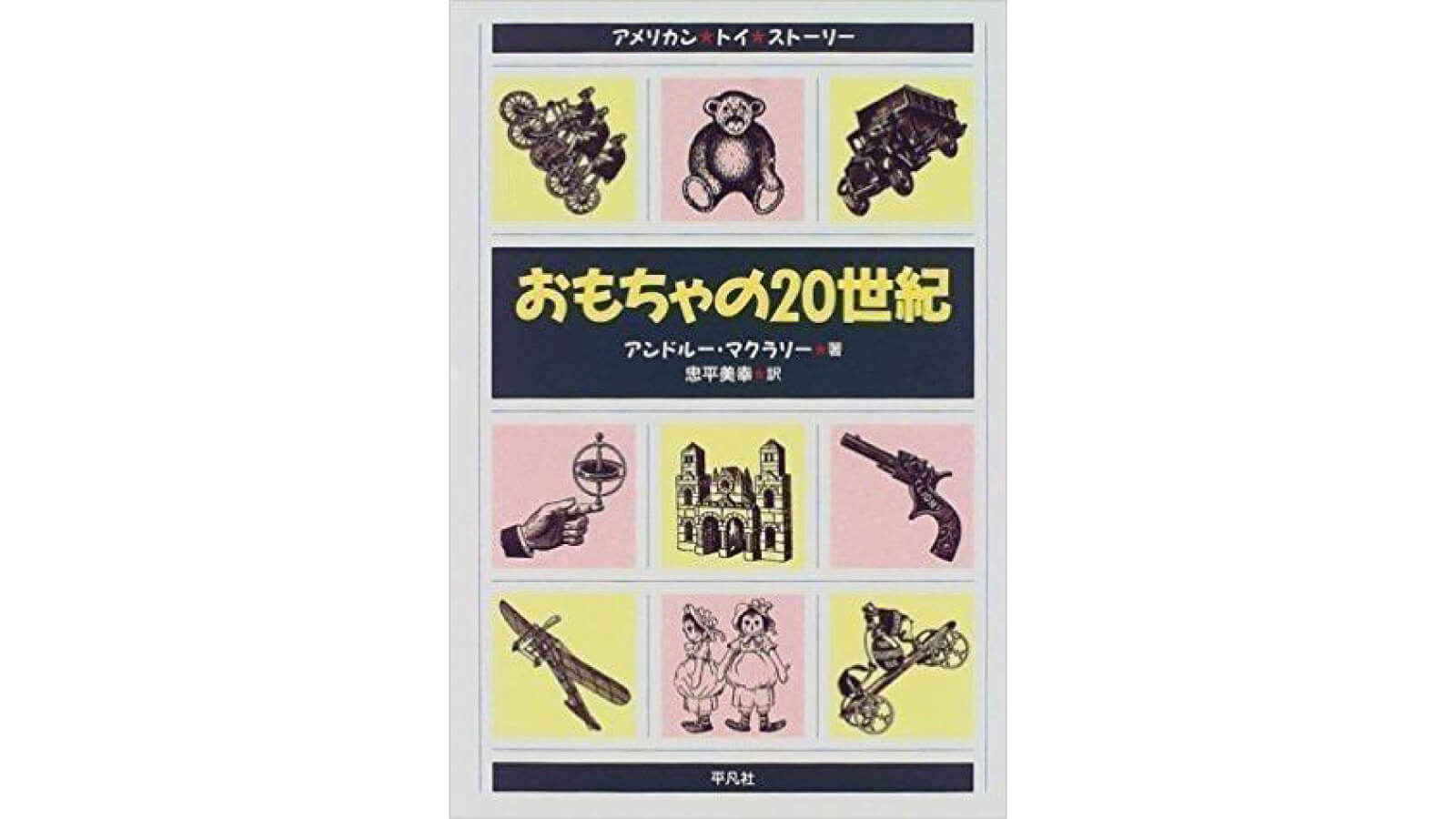
▲アンドルー・マクラリー著
『おもちゃの20世紀-アメリカン・トイ・ストーリー』
兵士の人形自体は古代からあり、マクラリーも中世ヨーロッパから存在したと記述しているのだが、これらは現代の感覚からすると「騎士」と呼ぶ方が適切なデザインだったのではないかと思われる。マクラリーによると、おもちゃの兵隊は20世紀に入って機械で作られるようになると爆発的に普及しその黄金時代を築いていった。私たちが「兵隊」という言葉から想像するような近代的な兵士のフィギュアは、これ以降のものだろう。
第一次世界大戦後、1930年代から1940年代にかけて、俗に「Army Men」と呼ばれるプラスチック製の小さな兵士のフィギュアが流行した。これは第二次世界大戦とプラスチック工業の発展によって、アメリカの男の子にとっては「通過儀礼」と言われるほどの地位へと成長していく。

▲典型的なArmy Men。(画像出典)
そして1960年代以降、プラスチック成型技術の向上という技術的背景もあり、兵隊のおもちゃは関節が可動する「アクションフィギュア」へと変化することになる。
こうした兵士のアクションフィギュアの原点と見なされているのが、1964年に発売された「G.I.ジョー」だ。
G.I.ジョーは、当時流行していたマテル社バービーのヒットを受け、ライバルであるハズブロ社がその男の子向けバージョンとして企画したものだった。1961年からバービーにはケンという男性のフィギュアがラインナップされていたが、あくまでバービーのボーイフレンドという位置付けの女の子向けおもちゃだったため、その体型やファッションもやや女性的であった。そのためハズブロ社は、G.I.ジョーの開発において、同性である男の子が憧れるようなフィギュアにこだわったと言われている。そこで検討の末採用されたのが、マッチョな戦争の英雄というデザインだった。

▲1961年にはじめて発売されたケンとバービー。(画像出典)

▲1964年に発売された最初のG.I.ジョー。(画像出典)

▲G.I.ジョーの素体。(画像出典)
結果G.I.ジョーは大ヒットとなり、このマーケティングが正しかったことを証明する。発売以降、コミックスやアニメーションなどさまざまなメディアミックスの後押しを得て、アメリカを代表するおもちゃへと成長していく。2009年にはハリウッドで映画『G.I.ジョー』が、そして2017には続編『G.I.ジョー バック2リベンジ』が公開されるほどの長寿シリーズとなっている。

▲ 『G.I.ジョー』(2009)(画像出典)
最強の肉体と、最強の知性
G.I.ジョーのデザインは長い歴史の中でさまざまなバリエーションを生み、中にはかなりファンタジックなものもあるが、基本的には現実の兵士を再現したものを基調としていた。
こうしたデザインが表現していたのは、国家という大きな存在のために戦う力強い男性性のあり方だった。戦争によって独立を勝ち取り、初代大統領にジョージ・ワシントンという軍人が就任し、現代に至っては世界最強と言われる軍事力を誇るアメリカという国家において、軍人という職業は他の国とはまた違った特別な意味を持っている。歴史を持たない、むしろヨーロッパ的な歴史から断絶することによって飛躍を遂げたアメリカという国が、ある意味ではナルシスティックとも言えるナショナリズムを歴史に代わる拠り所としていたということは、多くのアメリカ文化研究者によって語られている。フロンティアを拡大しアメリカそのものを作り上げてきた「軍人」たちは、愛国者の代表として、覇権的男性性としての地位を確立してきたのである。
G.I.ジョーが興味深いのは、その商品展開において乗り物が重視されていたことだ。日本の家屋感覚からはとても考えられないような巨大な装甲車や戦闘機が多数ラインナップされており、フィギュアと組み合わせて遊べるようになっている。

▲投光器つきのジープ。これは小型の部類。(画像出典)

▲G.I.ジョーの大型アイテム、空母。常識外れの巨大さ。(画像出典)
こうした乗り物は、マーケティング戦略上は遊びの幅を広げ、他のアイテムの購入を促す役割を果たしているのだが、男性性という観点からはふたつの点に注目したい。
ひとつはこうした乗り物が、工業社会の粋を集めた最先端のプロダクトであるという点だ。20世紀後半から21世紀に渡ってアメリカ軍を「世界最強の軍隊」たらしめたのは、兵士たちの愛国心だけではなく、高度に発展した軍事技術である。男性文化に属するプロダクトにおいて「アメリカ軍で採用」というキャッチコピーが魅力的なものとして使われているのを目にしたことがある人もいるかもしれない。20世紀は、高い工業技術こそが国家の繁栄に結びつく時代だった。こうした最先端のプロダクトは、「強い」という男性の価値をさらに高める象徴だったのである。
もうひとつ、乗り物に乗るということが、20世紀アメリカにおいては成熟の象徴として機能していた点にも言及したい。アメリカにおける自動車と成熟の関係についてはいずれ本格的に論じるが、基本的に免許を必要とするような乗り物は、搭乗者がミスをしないことを前提に運用されている。もちろんフェイルセーフは設けられているものの、それはあくまで補助的なものであって、常に正しい判断が行われるということを前提にしなければ、ハンドル捌きを少し間違えば大量の死者が出る自動車という乗り物がこれほどまでに普及することはできない。G.I.ジョーがモチーフとしているような兵器においてはなおさらである。つまりこうした兵器の操縦者であることは、いかなる状況でもパーフェクトな判断を下せる、20世紀的な理想の知性のあり方を象徴していた。さらに兵器が空母のような巨大なものになれば、単に乗りこなすだけではなく、クルーをまとめるリーダーとしての能力も求められるだろう。
強靭な身体を持ち、最先端の装備を駆使して、正義という大きな目的のために、常に正しい判断力を発揮する知的なリーダー。それこそがG.I.ジョーによって表現された理想の男性像であり大人像であった。
しかしベトナム戦争などの影響もあり、70年代に入ると、それまでの「強いアメリカ」像と、それにともなう理想の男性性のあり方も変化を余儀なくされる。G.I.ジョーの人気にも陰りが見えはじめ、商品展開も徐々に迷走していくことになる。迷走期にはときにファンから「狂気」と評されるほどのユニークなデザインも生まれているのだが、ここでは別の後継者について論を進めていきたい。
虚構へと移った戦場の先で
こうした流れを受けて、アクションフィギュアの主流はリアルな軍人からコミックスのスーパーヒーローへと移っていく。これはアメリカ文化全体におけるカウンターカルチャーの台頭と同期した変化だった。この時期、20世紀的な男性性の追求が悲惨な戦争にしか結びつかないという空気が、ベトナム戦争を通じて醸成されていった。政治的にはフェミニズムや公民権運動、文化的にはロックやヒッピーカルチャーなどが次々と生まれ、時代は男性性のオルタナティブな可能性を模索する段階へと移っていく。
アメリカン・コミックスの最大手であるマーベルは、60年代から70年代にかけて、これまでの男性性を更新したことによって大人気を博した。自らの怠慢で養父を失ったことからヒーロー活動に向かう『スパイダーマン』を皮切りに、それまでのG.I.ジョー的な「常に正しい」「強い」ヒーローではなく、「悩み苦しむ」「弱い」ヒーローを描いたのである。

▲自らの失策を悔い、素顔で涙を流すスパイダーマン。(画像出典)
しかしこうした試みによって当時のユーザーの心を掴んだスーパーヒーローたちが、軒並み筋骨隆々の肉体を誇っていたことは皮肉と言えるかもしれない。内面の弱さや葛藤を描かれながらも、身体のレベルでは軍人的なマッチョイズムから逃れることはできなかったのである。
たとえば最新のテクノロジーによって造られた鎧のようなスーツをまとうヒーローであるアイアンマンの初期のデザインは、スーツそのものよりも筋肉質な中身の方が強調される、コンセプトからすると奇妙とも言えるものになっている。

▲初期のアイアンマンのスーツ装着シークエンス。
筋肉が強調されるぴったりしたデザイン。(画像出典)
おもちゃにおいても、こうした筋肉質な体型は変化することなく、むしろ強調されていくことになる。プラスチック成型技術の高度化とコストカットの要求から、80年代にはそれまで縫製が主流だった衣服が省略されるようになっていった。布製の衣服を着てしまうと、素体表面のディティールはほとんど見えなくなる。樹脂成形でコスチュームが素体に一体化されると、ディティールはその存在感を増し、筋肉の隆起の表現はエスカレートしていくことになった。

▲MEGO社による1970年代のアクションフィギュア。コスチュームは布となっている。
この段階ではシルエットはG.I.ジョーとあまり変わらない。
(画像出典)

▲マテル社による1980年代のアクションフィギュア。布のコスチュームは省略され、樹脂成形の本体に統合されている。基礎的な体型が大きくパンプアップされているのがわかる。(画像出典)
スーパーヒーローは、内面の弱さを描くことによってG.I.ジョーの持っていたハードボイルド性や完璧さを解体することに成功したと言える。しかし身体性のレベルでは、マッチョイズムから離れることはできなかった。
70年代には、日本においてもG.I.ジョーの遺伝子を受け継いだおもちゃが登場する。それこそが、日本ボーイズトイ文化の原点と言える傑作、タカラ(現タカラトミー)社の「変身サイボーグ」である。この変身サイボーグが提出した新しい身体観は、その後のおもちゃ文化に決定的な影響を与えることになる。
[続く]
この記事は、PLANETSのメルマガで2017年8月9日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2020年3月23日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。


