デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回は映画版「トランスフォーマー」シリーズについての論考です。ラジー賞を受賞し「最低の映画」とまで評された本シリーズ。しかしその裏には、アカデミー賞も受賞したクリント・イーストウッドが監督・主演した名作『グラン・トリノ』と、驚くほど類似したアメリカ的な問題設定が隠されていたのです。
「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
ここまで、20世紀を代表する成熟した男性の理想像は、アメリカのアクションフィギュア「G.I.ジョー」が描き出したような、最強の肉体と最強の知性を併せ持つ「軍人」であったことを確認してきた。そしてそのイメージを更新した20世紀末のボーイズトイにおいて、「G.I.ジョー」の仕様変更品として生まれた「変身サイボーグ」は、自身の身体にテクノロジーを組み込むことで成熟を目指す「サイボーグ」というイメージを、そしてさらにその関連商品として発売された「サイボーグライダー」は、自らが乗り物になってしまうことで「魂を持つ乗り物」というべきイメージを提出した。
そして前回にあたる「第一章(1)「トランスフォーマー──ヒトではなくモノが導く成熟のイメージ」では、1984年の誕生当時のトランスフォーマーを、「魂を持つ乗り物」の先鋭化した姿のひとつとして、憧れの器となりながら、同時に成熟することを断念させる矛盾をはらんだ存在として論じた。
その後トランスフォーマーは、誕生から30年以上に渡ってさまざまなバリエーションを生み出し続けており、そのそれぞれがユニークな想像力を提案し続けてきた。ひとつひとつのシリーズを理想の男性性や成熟のイメージといった観点から詳細に分析していきたいところだが、それは重厚な歴史に伴ってあまりにも膨大な分量になってしまうことから、残念ながら断念せざるを得ない。そのためその重要性を認識しつつも、本稿では2007年からスタートし現在も進行中の、トランスフォーマー史上ある意味で最もポピュラリティを獲得したシリーズであるハリウッド映画版、およびそのおもちゃについて取り扱いたい。
まずは結論から述べよう。このハリウッド映画版はアメリカ主導で製作されることでアメリカン・マスキュリニティ(男性性)が中心的なテーマに据えられ、ダイナミックで野心的な実験が行われた。そして結果としてその挫折と更新の難しさに行き当たった、というのが本連載の立場である。
まずは映画の物語に注目しながら分析を加え、おもちゃのデザインがどのようにそれを引き受けたかという順で考えていきたい。その後ここまでの議論と合わせて考えることで、21世紀にトランスフォーマーが辿り着いてしまった限界と、20世紀末に置いてきてしまった可能性が明らかになるだろう。

▲タカラトミー『TLK-15 キャリバーオプティマスプライム』
『トランスフォーマー』は「最低」の映画か?
まずはトランスフォーマーの映画シリーズの全体像を確認しておこう。2017年末現在までに5作品が公開されており、第1作から第3作が主要キャストを統一した第1部、第4作から2019年公開予定の第6作までが、作中時系列には第1〜3作の続編でありながらも主要キャストなどを変更した第2部をなすとされている。また作中に登場する人気キャラクター「バンブルビー」を主人公にしたスピンオフ作品も2019年中に公開されることになっている。
本稿で論じる公開済みの5作品の内訳は、次のようになっている。
・第1作『トランスフォーマー(原題:Transformers)』(2007年)
・第2作『トランスフォーマー/リベンジ(原題:Transformers: Revenge of the Fallen)』(2009年)(以下『リベンジ』)
・第3作『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン(原題:Transformers: Dark of the Moon)』(2011年)(以下『ダークサイド・ムーン』)
・第4作『トランスフォーマー/ロストエイジ(原題:Transformers: Age of Extinction)』(2014年)(以下『ロストエイジ』)
・第5作『トランスフォーマー/最後の騎士王(原題:Transformers: The Last Knight)』(2017年)(以下『最後の騎士王』)

▲『トランスフォーマー』(2007年)
監督こそ全てマイケル・ベイが担当しているものの、10年にわたるシリーズ展開の中で脚本をはじめとしたスタッフは変化している。そのため単純に連続して設計された一貫性のある物語として扱うことには無理があるだろう。しかし、むしろそれゆえに、前作に登場したモチーフを次作で批判したり発展させることで、トランスフォーマーの映画シリーズはさまざまな興味深い視点を織り込むことになっていった。
興行的には、本シリーズは多少の浮き沈みはあるものの一貫して好調と言える数字を保っており、ハリウッドのブロックバスター映画としての地位を磐石にしている。またおもちゃをはじめとした関連商品についても、グローバルなマーケットにダイレクトに展開できることもあり、タカラトミー社(とハズブロ社)の重要な商品となっている。
しかしセールス的な好調の反面、批評的には大変に不評な作品でもある。トランスフォーマーの映画シリーズは「最低」とされる映画を選出するラジー賞(ゴールデンラズベリー賞)の常連となっており、2009年には『リベンジ』が「最低作品賞」「最低監督賞」「最低脚本賞」を、2014年には『ロストエイジ』が「最低助演男優賞」「最低監督賞」を受賞、ノミネートに至ってはさらに多数となっている。エンターテイメントに徹した娯楽映画というのが一般的な「トランスフォーマー」シリーズのイメージであり、ほとんど語るに値しないと思われているのが実情だ。

▲ラジー賞のトロフィー。アカデミー賞が「オスカー」と呼ばれるのと同様に、トロフィーが黄金のラズベリーを象っていることから「ゴールデン・ラズベリー賞」の通称を持つ(出典)
確かに純粋な映画としての脚本の完成度は(さまざまな制約があるだろうにせよ)疑問を呈されるのも無理からぬものではあるし、マイケル・ベイの3DCGによる極端な特殊効果や派手なカメラワークを前面に押し出した作風は、エンターテイメント作品としての(映画通の目線からすれば、ひょっとしたら低俗な)アクション・ムービーという見方を観客にほとんど強要しさえするものである。しかしそういった要素を差し引いて、トランスフォーマーというモチーフを通じたマスキュリニティの表現と解釈という点に焦点を当てると、意外なほど優れた部分も持ち合わせている。
本稿ではこの映画シリーズの内容を一作ずつ検討しながら、トランスフォーマーというモチーフの解釈を論じていく。しかし前述のような事情から、まずはこのシリーズをどのような視点で見ていくかという軸を設定するところからはじめたい。そのために、はじめにある映画作品について紹介し、これを見取り図とすることで議論をわかりやすくしたいと思う。『トランスフォーマー』の翌年に公開され、同じくアメリカン・マスキュリニティについて描き、そしてトランスフォーマーとは逆に高い批評的評価を得ている映画作品。それはクリント・イーストウッド監督・主演の『グラン・トリノ』である。
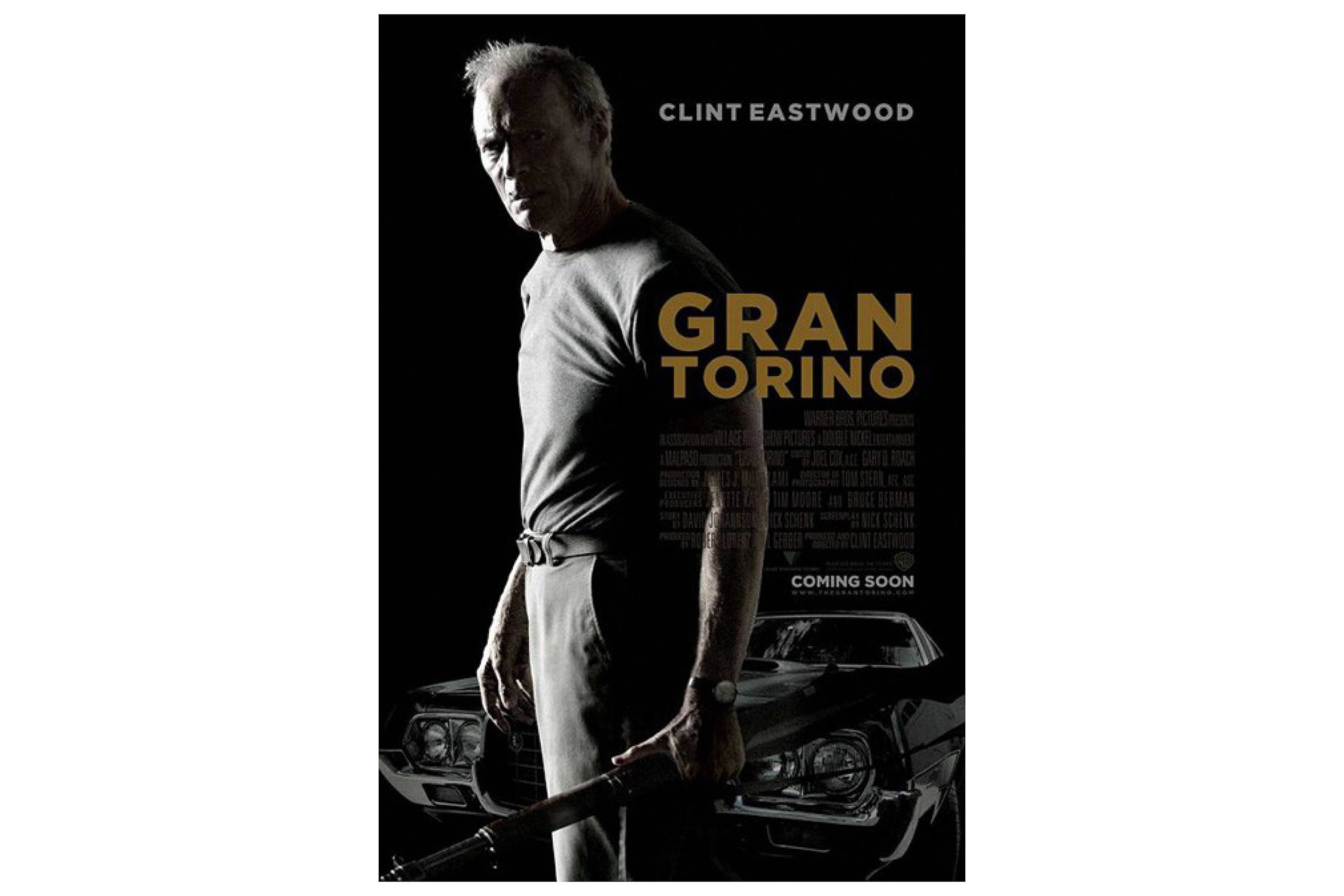
▲『グラン・トリノ』(2008年)
アカデミー賞監督の描く「良き男性」
クリント・イーストウッドは、生涯を通じてアメリカにおけるマスキュリニティのあり方について描き続けており、そのキャリアの初期においては俳優として自らの身体を通じて、そして後においては監督として作品を通じて、アメリカにおける理想の男性像と成熟のイメージを提示し続けてきた。
法哲学者であるドゥルシラ・コーネルは、こうしたクリント・イーストウッドとマスキュリニティの関係を『イーストウッドの男たち―マスキュリニティの表象分析』(2011年)にまとめている。自らを「倫理的フェミニスト」と規定するコーネルが、マスキュリニティを主要なテーマとするイーストウッドについて一冊をかけて論じているということ自体が大変興味深いのだが、その理由について述べた同書の序章において、コーネルは次のように語っている。
「監督作品の全体を通じてイーストウッドが挑戦し、開拓しようとしているのは白人のマスキュリニティについての深いテーマのネットワークであり、それはジャンル映画の中にコード化されてきたものだ。その作業によって、白人のマスキュリニティのジレンマ、とりわけ良き男性であるとはどういうことかについてのジレンマは、不愉快なステレオタイプの中で消去されるというよりもむしろ前面に押し出されることになる。人間性の倫理的理想に対するほとんど想像できないほどの暴力に圧倒された世紀においては、困難に立ち向かって成功する白人男性ヒーローのステレオタイプは弱体化しており、法の正しい側が単純な一筋の光によって照らし出されるような、古き良き時代を取り戻すことができるといった安易な幻想に安住することは、我々には望めないのである。」
この記述からコーネルは、イーストウッドが(かつてイーストウッド本人が演じてきたような)白人男性ヒーローのステレオタイプを現代の目線から描き直すことで、そこに発生する倫理的な問題について鋭く描き出している点を高く評価していることがわかる。
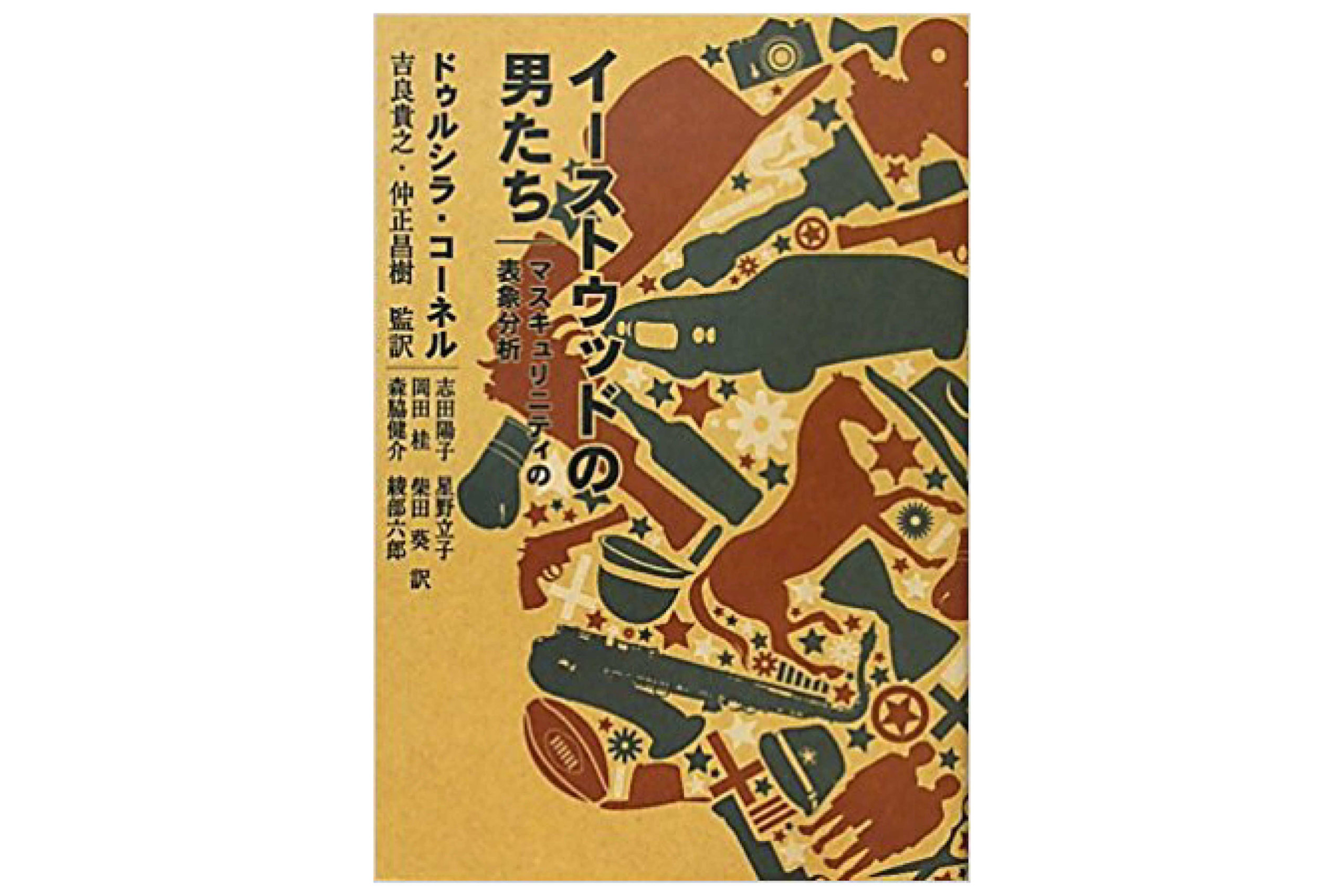
▲ドゥルシラ・コーネル『イーストウッドの男たち―マスキュリニティの表象分析』(2011年)
トランスフォーマーというブランドが、アメリカン・マスキュリニティを表現するべく再編されることによって成立したことは前回述べた通りである。そういった意味では、イーストウッドの取り組む主題とトランスフォーマーの主題はもとより親和性の高いものだ。
確かにトランスフォーマーの映画は、コーネルが言うような、そしてイーストウッドが批判するような「ジャンル映画の中にコード化されてきた」「白人男性ヒーローのステレオタイプ」を無邪気に肯定してしまっているように見えるし、おそらくはその鈍感さもラジー賞の受賞に寄与しているのだろうと思われる。しかしトランスフォーマーがこうしたアメリカン・マスキュリニティの限界について全く自覚的でないかといえば、そうではない。映画にポリティカリー・コレクトであることが厳しく求められる21世紀において、トランスフォーマーというアメリカン・マスキュリニティの結晶とも言える表象を描くという困難を通じて、むしろイーストウッドより深い絶望に、結果的には辿りつくことになったのである。
『グラン・トリノ』の描いた「軍人」「自動車」そして「キリスト教」
本稿では、まずイーストウッド作品の中から『グラン・トリノ』(2008年)を例に取り、アメリカン・マスキュリニティと深く結びついた「軍人」「自動車」「キリスト教」という3つのモチーフについて整理する。その上でこれらのモチーフがトランスフォーマーの映画シリーズにおいてどのように登場し深められていったのかを分析していくことで、(比喩的に言えば)トランスフォーマーをラジー賞作品を見る目線ではなく、アカデミー賞作品を鑑賞する目線で読み解いていく。
『グラン・トリノ』はイーストウッド監督作品の中でも傑作とされている評価の高い作品で、イーストウッドが監督と主演を両方務めた今のところ最後の作品となっている(2017年当時)。その物語は次のようなものだ。
イーストウッド演じる主人公のウォルト・コワルスキーは、かつて朝鮮戦争に従軍した元軍人である。彼はフォードの自動車工として勤め上げ、アメリカ自動車産業の衰退と共に斜陽都市となったデトロイトに隠居している。長年連れ添った妻に先立たれたコワルスキーは、生前の妻が世話になっていたという若い神父の熱心な誘いにも応じることなく教会からは距離を置き、毎日愛車のグラン・トリノをきちんと整備し磨き上げ、玄関先のポーチでビールを飲む日々を送っている。そんなある日、コワルスキーの隣家にモン族というラオスの山岳民族の一族が越してくるのだが、ある事件をきっかけに、コワルスキーはこのモン族の少年タオを一人前の男に育て上げることになる。このとき、コワルスキーの身体は病魔に蝕まれており、余命いくばくもないことが示唆される。タオは自立しようと懸命にコワルスキーに教えを請うが、同じモン族のギャングからの執拗な嫌がらせに悩まされていた。コワルスキーは最終的に、それまで敬遠していた若い神父に教会で懺悔を行った後に、このギャングのアジトに丸腰で向かい、懐から銃を取り出す真似をすることで意図的に自分を撃たせ死亡する。ギャングたちはこの事件によって長期刑を受けるであろうことが語られ、タオは自立することができるようになる。そしてコワルスキーは遺言状で、疎遠になっていた血の繋がった家族ではなく、タオにグラン・トリノを譲るのだった。

▲『グラン・トリノ』より、コワルスキーとタオ(出典)
コワルスキーは、アメリカン・マスキュリニティの老化と死を体現しているキャラクターだ。最強の肉体と最強の知性を持った「軍人」がG.I.ジョーを通じて描かれた理想の男性像であったことは、本連載の第1回で整理した。コワルスキーはその「軍人」として朝鮮戦争に従軍したのだが、その苛烈な戦闘、特に殺人を犯したという罪の記憶を拭い去ることができない。当然のことながら、軍人と戦争は切り離せないものだ。ここでは軍人という理想の男性性が、戦争という暴力とも結びついていることが示されている。
またコワルスキーはフォード社の自動車工でもあり、そのガレージには50年かけて買い揃えたという無数の工具が整然と並んでいる。「自動車」というモチーフが、フロンティアの記憶と結びついたアメリカの象徴であり、かつアメリカにおける男性的な成熟のイメージと結びついていることも、本連載の第3回で確認した。コワルスキーが丹念に整備し磨き上げているグラン・トリノというスポーツカーは、今や成立しなくなってしまったアメリカ的な理想の男性の象徴として配置されている。このグラン・トリノは、本来受け継ぐべきコワルスキーの血縁ではなく、移民であるところのモン族の少年に継承される。この展開は、もはやその肉体同様寿命を迎えつつある「白人男性ヒーローのステレオタイプ」であるコワルスキーの美学を、正統な後継としてアメリカ内部に受け継ぐことは不可能であることを表現しているといえるだろう。

▲1972年式グラン・トリノ。劇中に登場したのと同じモデル、同じカラーリング(出典)
そしてもうひとつ、これまで本連載で触れていない要素が「キリスト教」だ。『グラン・トリノ』においてコワルスキーは、物語序盤において若い神父が取り仕切る教会に対して非常に冷淡な態度を取っている。しかし自らの死期が近いことを察したこともあり、ほとんど自殺に近いギャングとの対決に向かう際に、(おそらくはハードボイルドの実践として本心を語らずにいるであろうものの一応は)神父に懺悔を行うことで、キリスト教的な価値観に対して再接近を試みている。この映画において、キリスト教的な価値観のうち「自己犠牲(self-sacrifice)」の精神にフォーカスが当たっていることには注目しておきたい。
元「軍人」であり「自動車」工でもあるコワルスキーは、「キリスト教」の理念に基づき自己を投げ出し死んでいく。そして移民の少年タオに成熟を託した。ここでは『グラン・トリノ』の物語とその表現するマスキュリニティを、一旦このように整理したい。
『トランスフォーマー』が抱えてしまった矛盾
ここからは、『グラン・トリノ』の整理によって得られた観点から、改めて『トランスフォーマー』について論じていきたい。
『トランスフォーマー』は、基本的には主人公であるサム・ウィトウィッキーの成熟を描いている。物語は高校生のサムが、父親にはじめての自動車を買ってもらうところからはじまる。この自動車が実は異星人「トランスフォーマー」のひとり「バンブルビー」であり、サムは「オートボット(前回紹介した正義の軍勢「サイバトロン」の英語名)」と「ディセプティコン(同じく悪の軍勢「デストロン」の英語名)」の戦いに巻き込まれ、その中で成熟していくことになる。
この第1作は、基本的には前回紹介したような80年代のトランスフォーマーにおける理想の男性性と成熟を忠実に引き継ごうとしている。アメリカ大統領(顔は映らず一瞬だけ登場する)が意図的に矮小化されて描かれる一方で、オートボット司令官であるオプティマス・プライム(「コンボイ」の英語名)は、トランスフォーマーとして最強の肉体を持つだけでなく、高潔な人格と知性を持った理想のリーダーとして描かれる。1984年のトランスフォーマーから設定されていたモットー「自由とは全知的生命体の権利である(Freedom is the right of all sentient beings.)」の引用は、オプティマス・プライムがリベラルな理想の体現者であるという印象を強めるものだ。またウィトウィッキーという姓は前回も紹介したスパイクの設定上の姓の引用であり、バンブルビーはバンブルの英語名である。つまりこの映画は、コンボイ=オプティマス・プライムという圧倒的なリーダーに憧れつつ、未成熟なトランスフォーマーであるバンブル=バンブルビーとの関係性を通じてスパイク=サムが成熟していくという、1984年時点のトランスフォーマーに忠実な構造をなしている。

▲サム・ウィトウィッキー。シャイア・ラブーフが演じる(出典)
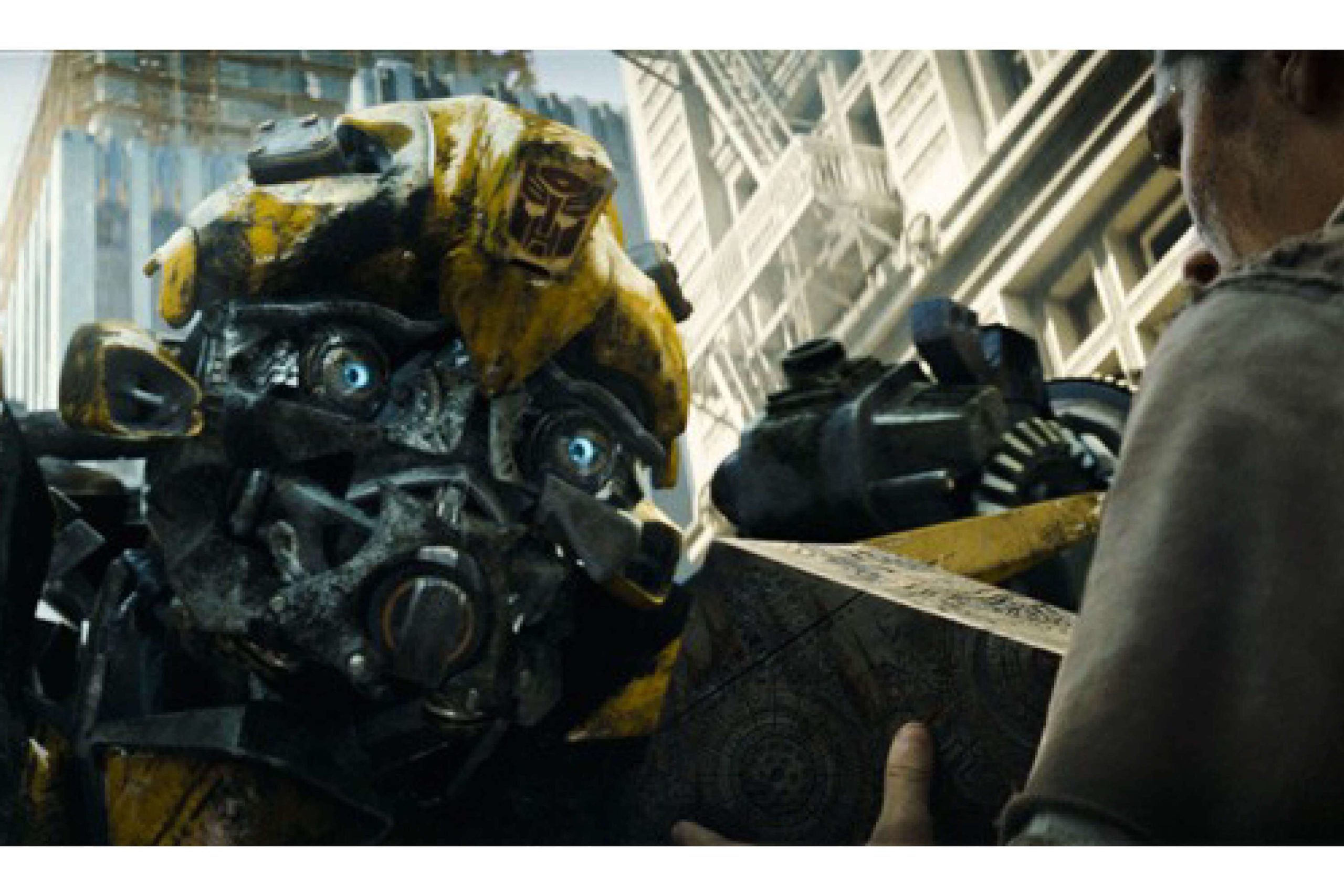
▲サムと友情を育むバンブルビー(出典)
第1作は初期トランスフォーマーが提出した理想の男性性と成熟のイメージをアメリカン・マスキュリニティと結びつけて再提出しており、全体的にそれまでのトランスフォーマーというブランドに対して誠実な作りにしようという意図は十分に感じ取ることができる。しかし結果としてその物語は旧来的なアメリカン・マスキュリニティを肯定する方向に大きく傾いている。
そうなってしまっている理由は幾つかあるのだが、ここでは重要な点をふたつ挙げておきたい。ひとつは軍人の活躍にフォーカスが当たっていること、そしてもうひとつは自己犠牲の精神が重要なものとして描かれていることだ。
基本的には主人公はサムなのだが、もう一人、第二の主人公と言うべき存在がいる。実はこの映画はサムではなく、アメリカ軍人であるウィリアム・レノックス大尉と、彼が率いる部隊の描写からはじまり、映画を通じて彼の率いる部隊の戦闘が、サムの成熟の物語と平行して描かれる構成になっている。レノックス大尉はまさに最強の肉体と最強の知性を持つ理想のアメリカ軍人として振る舞い、サムのロールモデルとなる。この映画は全体的に、アメリカ軍人を理想の男性性の体現者として描くことに躊躇がない。これには映画そのものがアメリカ軍の全面的な協力の下に撮影されているという政治的な事情や、そのフィルモグラフィにおいてアメリカ軍を好意的に描き続けてきたマイケル・ベイの意向が強く反映されているなど、幾つかの要素が影響していると思われる。しかし日本において変身サイボーグが、そしてアメリカにおいてもスーパーヒーローが既に更新して久しいはずの「軍人」という旧来的な男性性を理想像として設定したことは見逃せない。

▲ウィリアム・レノックス大尉とその部隊員(出典)
また「犠牲なくして勝利なし(No sacrifice, no victory.)」というフレーズが、ウィトウィッキー家の家訓として伝えられている設定にも注目したい。物語は、それまで臆病だったサムが自らの命を賭してメガトロンに立ち向かうところでクライマックスを迎える。メガトロンの攻撃によって高層ビルから落下するサムを救助したオプティマス・プライムもまた、自らを犠牲にしてメガトロンを打ち倒すことを誓うのである。劇中でメガトロンは、弱者の側に立つが故にオプティマス・プライムは弱い、自己を犠牲にする故に敗北するのだと宣言してみせる。しかしむしろ自己犠牲の覚悟、その高潔さによって、オプティマス・プライムは勝利する。
これを単純に美しい物語として受け止めることもできるが、ここではもう一歩踏み込んで、その意味について考えてみたい。自己犠牲を厭わないことは、なるほど美しいだろう。しかし問題は、その自己犠牲の先に待っているのが、なんとしても敵を滅ぼす、という暴力であることだ。
もちろん、人類を滅ぼそうとする侵略者であるメガトロンに対して、人類の自由を守るというオプティマス・プライムの思想、そして暴力に対して暴力で対抗するという手段には、それなりの正当性があるだろう。オプティマス・プライムはメガトロンに対して「兄弟」と呼びかけてさえいる。しかし自己を犠牲にしてでも敵を滅殺しなければならないということを映画の中心に持ってくるその美学は、20世紀に世界を覆った戦争の惨禍、さらに遡れば、ネイティブ・アメリカン/インディアンを駆逐して作り上げたフロンティアを思い起こさせるものでもあるはずだ。
実は1984年のトランスフォーマーにおいて、「オートボットがやけに好戦的である」「メガトロンのほうがむしろ理想の上司である」という話が、ファンの間で人気のあるジョークとして語られている。これは日本語版における翻訳の問題もあるのだが、1984年におけるトランスフォーマーがサイバトロンとデストロンの戦いを、かなりフラットな目線から描いていたことにもよるだろう。組織論の違いはあれど、基本的に両軍は、地球という場所で資源を奪い合う、異邦の存在なのだ。
しかし映画版のトランスフォーマーは、こうした視点を失っている。この映画におけるディセプティコンは、意図的に下品に、邪悪に、救いようのない存在として描かれているように見える。それがオートボットの「正義」が無条件には成立しないことを隠蔽するためである、というのはさすがに乱暴かもしれないが、キリスト教的な美学をオートボット側に置くことで、オートボットとディセプティコンが対称の存在でなくなっているとは言えるだろう。
戦争はあくまで外交手段のひとつであり、その意味において、暴力を振るう主体は対称であるはずだ(だからこそテロリズムは非対称戦争と呼ばれる)。しかし一方を「正義」という美学によって無邪気に肯定し、自己犠牲の精神を称揚したことが、かつて多くの兵士・国民を「犠牲」として動員していった大戦の惨禍に繋がったのではないか。
この映画を見るたび、筆者は考える。もし自分がサム・ウィトウィッキーで、この戦争に巻き込まれたとしたら。このオプティマス・プライムには、尊敬の念というよりも――メガトロンと同じくらい、恐怖を感じるのではないだろうか。ここに至って、トランスフォーマーを象徴するオプティマス・プライムというキャラクターは、まさにコーネルの言うような「法の正しい側が単純な一筋の光によって照らし出されるような、古き良き時代を取り戻すことができるといった安易な幻想」というテーマにぶつかっていく存在として深化されたのである。
クリント・イーストウッドとオプティマス・プライムという「双子」
ここまでの議論を踏まえて、改めて『トランスフォーマー』を、主人公サムの物語として整理してみよう。「軍人」「自動車」「キリスト教」という3つの要素とその取り扱いを軸として見ていくと、『トランスフォーマー』の物語は次のように言い換えることができる。レノックス大尉のような「軍人」を手本にして、サムという少年が「自動車」に乗り込み、「キリスト教」的な精神を体現して成熟する。
この意味において、『グラン・トリノ』と『トランスフォーマー』は、ほとんど同時期に公開されたことも含めて、双子と言えるほど似通っている。しかも公開年は『トランスフォーマー』の方が先なのだ。
こうした前提を踏まえると、面長で精悍な白人男性を思わせる映画版オプティマス・プライムの顔のデザインが、クリント・イーストウッドの演じるコワルスキーのようにさえ見えてくる。

▲ウォルト・コワルスキーを演じるクリント・イーストウッド(出典)

▲オプティマス・プライム。写真は『最後の騎士王』版のthreeA製アクション・フィギュア(出典)
このふたつの映画は、どちらもアメリカン・マスキュリニティを「挫折させるふりをして延命させている」作品であるという意味でも相似形を描く。
『グラン・トリノ』は一見コワルスキーの死を描くことでアメリカン・マスキュリニティを批判しているようでありながら、タオという移民の少年にグラン・トリノを譲っていることからわかるように、むしろこうした理想の男性性と成熟のイメージの継承の物語といえる。先述のコーネルの著作の原書は出版されたのが2009年であることから、『グラン・トリノ』の評論はおそらくはタイミングの関係で収録されていない。コーネルがこの映画をどのように論じるかはわからないが、果たしてこの物語が「法の正しい側が単純な一筋の光によって照らし出されるような、古き良き時代を取り戻すことができるといった安易な幻想」に安住していないと言えるのかについては疑問が残るところである。
そして前回確認した通り、トランスフォーマーは、「乗り物」でありながら「異星人」であることによって、旧来的なアメリカン・マスキュリニティへの憧れを挫く、ある意味で崇高な存在であったはずだった。しかしサムの成長物語という本筋からすれば本来必要ないはずのレノックス大尉の活躍を挿入したこと、そしてキリスト教的な自己犠牲の精神を強調することによって、本来トランスフォーマーが更新したはずの旧来的なマスキュリニティは保存され、フィルムの中でトランスフォーマーと同居してしまうことになる。
ラストシーンで、オプティマス・プライムは次のように語る。
“I have witnessed their capacity of courage. And though we are worlds apart, like us, there’s more to them than meets the eye.”
(私は彼らの勇気ある行動力を見た。見かけは違っても我々と同様に、目に見える以上の力を持っている)
ここで語られる「彼ら」とは、無論人類のことだ。「More than meets the eye」というトランスフォーマーのおもちゃの有名なキャッチコピーを引用しながら語られるこのスピーチにおいて「勇気」とされているのは、「自己犠牲を厭わずに敵を打ち倒すこと」であり、本連載の整理に照らせば「軍人」と「キリスト教」の理念を融合したものであるといえる。このスピーチは劇中では、オプティマス・プライムが身体的にはか弱い人間=サムの心の強さを認めたという文脈で行われるポジティブなものだ。しかしここには、むしろ『トランスフォーマー』が囚われた困難が刻まれてもいる。その困難とは、トランスフォーマーを崇高な異星の機械生命体としてではなく、逆にアメリカン・マスキュリニティから逃れられない存在として描いてしまった、描かざるを得なかったことだ。
第2作目から第5作目までのハリウッド版トランスフォーマーは、このことを自己批判していくことで物語を展開していくことになる。しかしそれゆえに、アメリカン・マスキュリニティの重力から離脱した新しいイメージを提出することには失敗し続け、イーストウッドよりさらに深い絶望へと沈んでいくことになるのである。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2017年8月9日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2020年6月29日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。
「”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。



