都市のオルタナティブを追求するプロジェクト「風の谷を創る」に関わる多彩なメンバーたちの横顔を紹介する本連載。今回、ご登場いただくのは「Game Changer Catapult(ゲームチェンジャー・カタパルト)」代表の深田昌則さんです。その経歴やカタパルトへの思い、「農と食」班での挑戦について伺うなかで、「風の谷」が進むべきプロセスが浮き彫りになっていきました。

端的に言うとね。
グローバルプレーヤーとして体感した日本のものづくりの盛衰
──今日は、マサさんと「風の谷」との関わりはもちろんですが、具体的にどういう経歴で、普段、何をやっているのかということも伺いたいんです。みんな、漠然と「カタパルトの偉い人」って思っていますよね。
深田 偉くはないです(笑)。経歴的にはパナソニック(当時は松下電器産業)に入ったのが1989年、平成元年です。
──バブルの真っ盛りだ。
深田 1989年に入社してすぐにカナダに留学をして、戻ってきてからは国内のマーケティングをやっていました。ナショナルショップ向けの特選品フェアや合同展示会などですね。
──ナショナルショップって、今となってはパワーワードですね(笑)。
深田 その後、1994年から海外営業で、業務用のオーディオの仕事をしていました。自分でレンタカー借りて、ハリウッドのレコーディングやマスタリングスタジオに行って、デジタルオーディオテープレコーダーを売るんです。
日本で技術者とともに「これは!」と思うすごいテクノロジーを見つけると、それをハリウッドに持っていく。すると、マイケル・ジャクソンやマドンナのレコーディングやマスタリングをしているエンジニアが、「これ20ビットと24ビットで音がすごく違う!」「すごい!」って驚いてくれて。
──それはめっちゃいいエピソードですね(笑)。
深田 営業なのに、一日中リスニングルームに入り浸って、ずっと音を聞いてました。16ビットのCDを作るための、18ビット、20ビット、24ビットの音の聞き分けとか。だから、あんまりあくせく仕事はしていませんでした (笑)。
あとは映画の仕事にも大変興味があったので、ハリウッドでは俳優が撮影しているとこに「こんにちは」って入っていき、今のスマホの原型になるような小型カメラやメモリーカードを見せて、ネットで紹介してもらったり。ユニバーサルスタジオの中にパナソニックのオフィスがあったので、スタジオ内をうろうろ歩いていて、トラムツアーの客から「日本人がいる!」って指さされてました(笑)。
その後、ヨーロッパ向けのテクニクスの営業をして、2000年からはグローバルマーケティングで海外宣伝責任者になって。このときはLumixとかDIGAとかD-snapとかの市場導入マーケティングをやっていました。
ハリウッドでの仕事は続いていて、アンジェリーナ・ジョリー主演の映画『トゥームレイダー2』に発売前のパナソニックのカメラやメモリーカードを登場させるとか、オリバー・ストーンにテレビコマーシャルに出てもらうとか、我々からコミッションしてショートフィルムを撮影・制作するとか。華やかな時代でしたね。
あとはスポーツマーケティングということで、オリンピックの仕事に関わることになって。IOCとスポンサー契約の交渉をしたり、アテネやトリノでは現場のオペレーションをやっていました。
その後、カナダでコンシューマー関係の責任者をしていたんですけど、薄型テレビやデジタルカメラなどのマーケットがだんだんしんどくなっていきました。パナソニックとして売るものが少なくなりつつあるね、っていう感じになってきて、新規事業や事業開発に携わるようになったんです。
で、日本で新規事業開発の仕事をやるということで2015年から始めたのが、「ゲームチェンジャー・カタパルト(以下GCカタパルト)」。さらに、株式会社BeeEdgeという仕組みを作って事業に出資できるようにしまして……経歴でいうとそんな感じですね。典型的なパナソニックの、組織の中に組み込まれた仕事の仕方というよりは、そもそも好きなことしかしてないんですよ。
──日本のものづくり産業がだんだんしんどくなっていく過程をつぶさに見てきたと思うのですが、そのとき、何を感じていましたか。
深田 どちらかと言うと僕は、国籍というよりブランドを背負って海外でやってきたという意識なんです。グローバルプレーヤーとして仕事をしてきて、特に2010年以降、急に失速していった。だから、その失速の背景をひも解きながら、新規事業で新しいものを作る仕事に変わっていったという感じですね。
大企業をハックして、サラリーマンを解放する
──GCカタパルトって、ベンチャー業界にあまり詳しくない人に説明するには、若干難しいですよね。社内ベンチャーとも違いますよね。
深田 大企業の中でイノベーションを起こす、具体的には「未来のカデン」を作るというプロジェクトです。家電といっても量販店で売っているような製品ではなく、「暮らしの課題を解決する」ことをミッションにする(カタカナの)カデンです。
実は松下幸之助って、前回のパンデミックの直前に創業しているんですよ。創業した1918年3月というのは、ちょうどヨーロッパでスペイン風邪が出始めたころ。図らずもパンデミック直前に創業してしまったわけですが、1920年、パンデミックが終わった後、エレクトロニクスや自動車、航空機、科学などの進化を背景に好景気が続きます。今で言うところのAIやロボティクスといった新しいテックによって社会の課題を解決する、というかたちで上昇気流に乗った。それが、パナソニックのそもそもの出自なんです。
20世紀にはその後、1960年から70年代の高度成長期、1995年以降のドットコムブームなど、上昇気流の機会は何回かありました。パナソニックは高度成長期の上昇気流に乗ることはできましたが、1995年以降はそれができなかった。なぜかというと、やはり我々がいま持っているようなテクノロジーや仕事の仕方だけでは、新しい社会課題をじゅうぶんに解決できないからなんです。GCカタパルトは、もう一回、原点に立ち返り、新しいカデン──未来の暮らしの課題を解決するものを作りたいということで始めたわけです。
なぜ、GCカタパルトのような形にしたのかというと、やっぱり、今の経営方針だけではなかなかそういう発想に至らないというのがわかったから。従業員の中には、やりたいことがあり、それを形にする力のある人たちはいっぱいいる。彼らに権限なり予算なりを渡して、好きなようにやってもらうなかで、将来の事業の種は生まれる。
大企業をハックして、管理型マネジメントから逃れるオルタナティブを作っていくということに、チャレンジしているわけです。

──僕は1978年生まれなので、同世代には何回目かのベンチャーブームに乗った人たちがいっぱいいます。彼らはすごく頑張っているんだけれど、日本のベンチャーの世界に回っているお金の規模自体が小さく、壁にぶつかってしまっている人も多いと思うんです。今の日本に現存する、数少ない前向きなエネルギーが渦巻くその一方で、憧れだけがから回りしている世界になってしまっている側面は確実にある。この世界に大企業がドカッとお金とリソースを落とせば、彼らはもっともっと活躍できるのにって思うんです。
深田 シリコンバレーなどでイノベーションが作られてきたのは、エクイティファイナンスが当たり前になったからです。これまでは事業を起こすときには、銀行からお金を借りて、それを返済してというような仕組みが一般的でした。そうではなくて、まず出資のような形でお金をもらい、ベンチャー企業の事業価値が上がって最終的には出資者にリターンがあるという仕組みができた。
僕は、この仕組みを大企業の中にも入れたいと思っているんです。企業内で儲かっている事業部からお金をもらってきて、「ちょっとこれやってみ」って言ってやって、「これできました」「お前それ何の意味があんねん」といった話だと、なかなか未来は作れません。
だから、ベンチャーキャピタルと一緒になって、パナソニックの外に会社を作って、そこから出資する形にしたんです。パナソニックは短期的には費用ではなく、出資という形でお金を出すことになる。その新規事業が成功すると、3年後なり5年後なり、事業が価値として戻ってくる。
──日本の優秀な人材は、これはよくないことでもあるのだろうけれど、なんだかんだ言ってある程度は大企業に集中していますよね。一人ひとりの能力は高いから、ソフトウェア的には新しい世界に順応している、むしろ先を行っている人もたくさんいる。ところが彼らが所属している組織、ハードウェアの部分がいかんせん古すぎて、身動きがとれなくなっている人がものすごく多い。
彼らがエネルギーを発散する場所を作らないと、この国はおもしろくならないだろうって思っていたんです。だから、GCカタパルトのことを初めて知ったとき、「これはおもしろいものが出てきたな」って直感しました。
深田 企業の中で優秀な人、やりたいことがある人がうまくその力を発揮できていないというのは確かですね。大企業側も新規事業を作りたいとは考えているんです。しかし、日本の管理型マネジメントがまるでイケてない。上司の言うことを聞くことが出世の近道で、それが体に染みついている人ばかりになっているというのが、今の大企業の姿。たとえるなら、動脈硬化を起こしているような状態で、もっとストレッチして身体を動かす訓練をしなきゃいけない。
だとしても、経営幹部にネゴって「予算をください」みたいな話では、破壊力が足りない。だから、GCカタパルトという組織のブランディングをしながら、社員が剥き身で社会の動きに触れられるような機会を作り、最終的な社内のジャッジメントよりも社外のジャッジのほうをレバレッジとして効かせるという仕組みにしたのがGCカタパルトなんです。大企業をハックする、人事制度をハックする、財務の仕組みをハックする、上司部下の関係をハックする、みたいなことをやっているんですよね。
そのハックというのは、働いている人たちのパッションで、ピラミッドを崩していくことです。日本の大企業にたくさんいる優秀層を閉じ込めている檻の鍵を壊してグワーッと開く、サラリーマンを解放していく、そういうイメージです。
──僕の世代って、まだ優秀な奴が「とりあえず大企業に就職」していたんです。いや、たぶん今も残念ながらそう変わってはいないでしょうけど、だからこそ、こいつらの力をもっと生かす社会になるべきだ、という思いは僕にも強くあります。たとえば僕の高校の同級生の中には、こんなに優秀なのに、なんでこんなにくすぶってるんだろう、みたいな奴がいっぱいいる。
深田 大企業の中だけだとどうしても限界があるんですよね。最近、元レノボ・ジャパン社長の留目真伸さんっていう方が取り組んでいる新産業共創スタジオSUNDREDという活動に参加していて、そこは、会社とか組織の枠を乗り越えて、やりたいことを自由に動き回る人の集まりなんです。我々はそういう人たちのことを「インタープレナー」と呼んでいます。アントレプレナーでもイントレプレナーでもなく、インタープレナー。要は、人材というリソースをハックしているんです。
大きな目的を実現するために、サラリーマンという仕組みをハックするという人って、実は増えているんですよね。おそらくこの先、上場企業に勤めながら、別に個人で会社を作って……というのが当たり前の世界が来ます。サラリーマンとして働いて50歳になったらリストラとかいう世界は、やっぱり違うじゃないですか。僕自身もいろいろ仕掛けていこうと思っているところです。
──いいですね。いろいろなところで活動しておもしろいでしょ、というモデルケースはどんどん増えるべきだと思います。
深田 その意味で、つまり、サラリーマンとしての働き方のオルタナティブをきちっと作るという点で、GCカタパルトと「風の谷」は似ているのかもしれません。求められるのは、大企業の部とか課とか、そういった組織における優れた成績作りを目指すのではなく、社会に出ていって、自分で事業を起こして社会のためになることを実現すること。大事なのは未来を作っていくこと。作りたい未来を作るという意味で、「風の谷」と通じると思います。
人生が問われる「風の谷」
──マサさんが「風の谷」に加わったのっていつ頃ですか? 気づいたらずっといるっていうイメージですけど(笑)。
深田 2018年ぐらいです。ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSという広告賞にクリエイティブイノベーション部門というのがあって、その審査員のひとりとして僕も加わったんです。部門の審査委員長が暦本純一先生で、そこに安宅さんも来られて。その関係でACCのイベントで一緒に登壇する機会があって、それが2017年の夏か秋ですね。その後、お話を伺い参加したと思います。
──最初に安宅さんから「風の谷」構想を聞いたときどう思われました?
深田 まさに日本に足りていない未来づくりだと思いました。しかも、落としどころがまったくわからないなかで、大人が真面目に一から議論し着手する活動というところがすごくおもしろかったですね。
一番インパクトが大きかったのは、サラリーマンの仕事のやり方とはまったく正反対だったことですね。決められた時間軸の中で、できそうなことをきちっとやるのがサラリーマンです。そこで一番大事なのは、何ができそうなのかを見極めること。できそうにないことには着手しない、失敗しないというのがサラリーマンの処世術だったりするわけです。でも、「風の谷」はまったく違っていて、そこへ至る道筋はともかく、どういう未来に到達すべきかを延々と議論しますよね。必ずしも筋の良い答えが出なくても、議論していくことによって、なんらかの形でおぼろげに見えてくるっていう作業を繰り返すじゃないですか。
──僕もこれまでの人生で、あそこまで手探りなことはやったことありません。
深田 すごく面食らいましたね。問いの立て方とか、議論の本質の本質の本質を問うみたいなところは、すごくチャレンジング。毎回3時間以上の集まりですが、「お前の人生は?」ということをすごく問われる。そういう経験になっていますね。
しかも周りの人たちは、あたかもそれを普段から考えていますよ、というふうにサラッと言う (笑)。逆に言うと、そこがサラリーマンとして問われてこなかった部分なんですよ。サラリーマンはむしろ、決められた枠の中できちっと受け答えができればOKだったりすることも多い。でも、やっぱりそれでは未来は作れない。「風の谷」は人生を賭けて、物事の本質を見極めながら筋の良い道筋を自ら考えて生み出さなければ、そこに選択肢すらない、というあり方。しかもそれを、ちゃんとした大人たちがやっている。
一方で、参加している学生たちが、それを案外サラッと素直にできちゃうということも衝撃でした。サラリーマンとして組織の中で仕事をしてきた何十年っていうものが、自分の形を固めてしまい、能力を限定してきたんだと痛感しました。
壊すのではなく仕組みや仕掛けを変える
──マサさんが「風の谷」に対してこうあってほしい、ということはありますか。
深田 そうですね。先ほどのサラリーマンを解放するという話に通じるのですが、そもそも人間がどう生きるかを考えたとき、ちゃんと選択肢が用意されていて選べるような社会を作りたいという思いがあるんです。
都市に住むということだけで、家や仕事など選択肢が狭まることってたくさんあるじゃないですか。でもそれらを一旦解放したうえで、じゃあどんなところに住みたいのか、どんな暮らしをしたいのかっていう選択肢がたくさん広がっているのが、「風の谷」みたいな世界かなと思っています。
──選択肢を広げるものとして「風の谷」を位置づけようと考えると、難しい問題があると思います。要は都市の生活との距離感です。昨年秋に地方を視察したとき、僕が一番強く思ったのは、ここに住んでいる人たちは少なくとも今は「風の谷」のようなものを望んでいない、ということです。むしろもっと大きなショッピングモールができて欲しいと考えている人が今は多いんじゃないかと感じたわけです。実際にできてしまえば、興味を持って来てくれるでしょうけど、現時点では大きな溝がある。
これは家電的な問題にも通じます。ふつうに商売をしようと思ったら、大切なのは、すでに存在しているニーズに応えることです。ところが、新しい市場を作るとしたら、先にすごいものを作って欲望を開発しなければいけない。
「発明が欲望を作る」とは暦本純一先生がよくおっしゃる言葉ですが、「風の谷」のプロジェクトも、「風の谷」という空間をまず発明することによって新しい欲望を作る、という形に近い。現時点において「風の谷」のロジックは、日本の土建行政的なものに真っ向から対立する発想だし、人類が培ってきた都市というものに対してのオルタナティブです。やはり、既存のニーズから離れているプロジェクトだと思うんです。
深田 我々が都市と呼んでいるものの正体は、すでにわかってきていますよね。20世紀、阪急電鉄の小林一三がやったように鉄道を中心に開発が進み、その沿線に都市が生まれました。戦後は自動車でアクセスしやすいショッピングモールが中心となり街が生まれた。イオンが日本のふるさとみたいになり、我々の世代は、そういうのを都市と呼んでいるわけです。つまり、「風の谷」が目指すのは、長いスパンでみた都市と田園というよりも、20世紀型の都市文明に対するオルタナティブに近いと思うんです。
そういう意味では、ゴミゴミとした都会に住まずに、文化的な生活ができるオルタナティブは作れるんじゃないかなと思いますし、一から場所を作ったとき、そこにどんな文化が乗るのかということにも興味があります。
──僕、何年か前に、守口にあるパナソニックに行ったことがあるんですよ。働き方改革とメディアみたいなテーマで講演に呼ばれて。
深田 よく宇野さんを呼びましたね(笑)。
──関西には長く住んでいましたが、守口には行ったことがなくて、そのときが初めてでした。そして、愕然としてしまったんです。一言で言うと、イオンモールのような郊外型の大規模店のひしめく平成の郊外の典型例のような風景が広がっていた。
あのオフィスには日本の頭脳と言っても差し支えないような優秀なエンジニアがたぶんいっぱいいて、そんな彼らが、この画一化された風景の中で仕事をしている。これは日本を代表する企業の「城下町」としてどうなんだろう、と思いました。ここからクリエイティブな仕事が生まれるとはどうしても思えなかった。
その後、マサさんと出会って、マサさんみたいな人がGCカタパルトを始めた理由が、すごく腑に落ちたんです。既存のゲームの枠の中でできることは、結局のところ最適化にすぎず、そこからは創造力が生まれないっていう前提があったんだろうなと思ったんです。
深田 むしろ、イオンできて良かったなぐらいです(笑)。ただ、先ほどお話しした、20年前にハリウッドに持っていっていたすごいテクノロジーって、門真や守口にいる技術者が作ったものなんですよ。西三荘駅前の工場っぽいビルとかにも彼らは事務所を構えていて、ふらっと立ち寄ると、「ちょっとこれ聞いてみ」とか言いながら、びっくりするような製品を出してきたんですよ。
──そういった秘密基地みたいなものをどう再生するのかが、GCカタパルトのミッションでもあり、「風の谷」もまた、びっくりするようなものが生まれてくるためのひとつの環境づくりということですよね。そういうところで通じているんですね。
深田 僕にとって「風の谷」の生活というのは、都市から何かを持ち出して、「谷」で新しい使い方をガチャガチャやるっていうイメージに近いんです。
対立ではなくて、現状の社会をハックするということですよね。GCカタパルトも、大企業を壊さず仕組みや仕掛けを変えるものですし。既存の対立構造に収まらない第三の軸だからこそ、トップマネジメントに刺さることができるし、フロントラインで不満が溜まっている若手層に望みを与えることができる。僕はこれが、大企業をハックする形だと思っているんですが、ハックっていうのは壊すことではないんです。うまく利用しながら、ぬるっと前へ進める。いつのまにか自分のやりたいことを実現してしまっているという状態が理想です。
我々みたいな事業会社は、右側でちゃんとモノを作って商売をしながら、左側で未来も作るという、ある意味、対立構造にあるものをいっぺんにやらなければいけないというミッションがあります。日銭を稼ぎながら未来を作る。未来だけ作っていても飯は食えないし、足元だけ見ていると未来はない。両利きの経営みたいな言い方もしますが、そもそも人間ってそうだったよねという話なんですよね。今日食べるお米と、未来のために植えておくお米。それと同じことを、これからどうやるかっていう世代なんだと思います。
ポイントは、理屈をうまく作りながら社会実装させていくことで、その意味では、これから「風の谷」がやらなければいけないことは多い。でも、ワクワクしますよね。
「食」班から「農と食」班への“変貌”
──マサさんのチャンク(グループ)は、「農と食」班ですよね。どうして、食だったんですか?
深田 僕はずっと家電関係をやってきて、フードテックの世界とも関わりがあったんです。スマートキッチンサミットや海外のフードテックベンチャーのイベントなどに登壇したりもしていました。未来の食とその課題はとても大きなテーマだという認識は持っていたし、興味もありました。もちろん、興味のあり方はそこだけではありませんが。
そもそも食は人間の根源ですよね。栄養補給のためのものだけれど、それだけではない。家族を養うとか富を蓄積するといった意味もあるし、さらにそれが文化や教育にもつながる。意味が重層的になっているのが食なんです。
たとえば、我々は食というと、まず食べることで体を維持するという点に注目しがちです。食料安全保障の議論とも通じますが、じゃあ、食はカロリーなのか? というとそれは違う。スノビッシュな人たちがワインや高級レストランの話をして楽しむといった、ガストロノミーやグルメといった世界もあれば、こだわりの健康食の世界もあるわけで。
この両極端のところの間に、文化がたくさん埋まっている。ジャンクフードの世界、外食産業の世界、家電製品を使って作る家庭料理の世界……食にはたくさんの角度がある。この角度を短期間で意味を分析しながら作っていくっていうのは、むちゃくちゃチャレンジングで、正直まだまだ全く前に進めていない感もあります。こうした構造を理解するために、ここ1年半ぐらいかかりました。
そもそも何を食べるべきかという議論が、圧倒的に欠けているんですよね。逡巡してしまうのは、実装していったときに「そうは言ってもおいしいお肉が食べたい」ということがあるので。コオロギ食やソイレントのような、食べるという行為に時間をかけるなんてもったいないという価値観もあって、そういうものまでハックしていくのかっていうところは、まだまだ議論が足りていない。
──そこは僕も関心があるところです。たとえば地球環境への正しさを優先して、とりあえず昆虫食だというような結論になるのでは、ありふれていてつまらない。ほんとうにコオロギ「だからこそ」実現できる「おいしさ」を獲得したときはじめて「風の谷」でやる意味がある。
ここを間違えてしまうと実際はさほどおいしくなくても、美しい景色の中で楽しくバーベキューしながら食べるとおいしく感じたりもするところに逃げてしまいかねない。でも、それは違うと思うんですよね。
深田 それではないよね、という話はしています。エスタブリッシュな方々の食に対する向き合い方に引きずられがちなんですが、やっぱりハックするためには第三の軸を作りたいんです。ガストロノミーとジャンクの空間の間……間というか、違う価値観ですよね。たとえば微生物のDNAをハックして土地の味を作っていくようなものとか。
──僕自身は毎日ゼロカロリーコーラを飲んで、天下一品のラーメンが好きで、一人焼肉にも行くし、高田馬場で一番おいしいのはロースとんかつだと思っている。ある基準で考えたら、ものすごく俗悪な食生活を送っている人間なわけです。もちろんその場所でしか食べられない、土地に根ざした味も大事だけれど、しかしそういう人間「も」否定しない場所であって欲しいと思うんです。
深田 でも、宇野さんはそれを堕落として飲んだり食べたりしているわけではなく、「これは俺のナンバーワン」という判断で選んでいるわけですよね。そういう判断の軸を排除するなという話なんだと思うんです。要は、堕落したものも許せという話ではなく、自分がこだわって「これが良い」と言うものは、それはちゃんと認めるっていう話。そういう軸みたいなものが必要だと思っているんです。
これって、サラリーマンの世界と一緒なんですよ。サラリーマンの世界って、出世街道を行く人と、課長にもなれずのんびり働く人の二分論で語られがちですが、それはすごくもったいない。実は出世には興味がないけれど、世の中を変えてやるっていう人がいるわけです。この第三極をGCカタパルトが作ってきた。
それと同じように、要は高級品と大衆品みたいな話じゃなくて、こだわりだったり、世の中を変えるものだったり、そういう食の軸があると思うんです。
たとえばSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)って、そういう感じなんですよ。有名ミュージシャンや投資家を接待するような高級レストランがある一方で、フードトラックの聖地みたいにもなっているんです。年に5〜6日間だけのイベントですが、それらがぎゅっと集まり、入り乱れて、どっちにしようか選ぶことができる。
どうしてそうなっているかというと、未来を作っていくっていう目標だけはみんな、一致しているからなんです。高級レストランで食べる人も、フードトラックでジャンクを食べる人もみんな、未来を作ろうと言っている。未来は一つじゃないっていう、暗黙の了解がある。実はSXSWはそのへんがすごくおもしろい。
こんなふうに、欲望が多様化する空間であるべきだと思うんです。特に食は欲望と直結しますから。


──第三の軸を立てていくということは、「風の谷」にとっても重要ですよね。
僕の領域の話で言うと、プラットフォームは画一化されていていい、むしろ設計主義的に管理されていて然るべきで、ただ、そこでのコミュニケーションやコンテンツというのは多様であらねばならないというのが、21世紀初頭のシリコンバレーイズムだったはずなんです。それが失敗しているのが、今だと思うんです。
人間の価値観は放っておくと多様化しない。だからこそ、多様化させるための戦略、第三の立場が必要になる。僕の中で「風の谷」というのは、都市のオルタナティブであると同時に、インターネットのオルタナティブなんです。
深田 「農と食」班においても、対立軸にするというよりは、やりたいことを追求している間に、いつのまにかできてしまっている、という仕組みにしたいんです。それが第三の軸のプロセスかなとも思います。
「風の谷」の思想的な理想は食に宿る
──いま、すべての議論がつながった感じがします。古いものづくりの企業は、トップダウンで意思決定がなされ、徹底的に管理をして、ねじや歯車のように働ける従業員が優秀になる、という世界観でやってきた。日本はそれで一回天下をとったけれど、そうではなくなった。むしろ、一人ひとりの創造性が大事で、ボトムアップの力が重要だとなった。それが情報産業なわけです。
工業社会と情報社会、製造業と情報産業という、二つの軸があるとすると、今やろうとしてるのは、この両軸の対立に対しての第三の軸。それは、大企業でもベンチャーでもなく、企業内ベンチャーと呼ぶのが正しいのかわかりませんがGCカタパルトであり、都市と地方の対立でもない「風の谷」でもある。今日の議論って、ずっと相似形で進んでいますよね。
深田 本当にそうだと思っています。もっと言うと、僕は日本のあり方みたいなこともずっと考えていて。たとえば、明治維新のとき、海外から欧米的な帝国主義みたいなものが入ってきたときに、民主主義というOSを使って、日本的な新しい軸を作って成功させていきましたよね。第二次世界大戦後、工業社会が始まるんですが、アメリカが作った合理主義みたいなものの上に日本の伝統を乗せて、任天堂のゲームみたいなものを作ってしまった。
いま、欧米が新しいOSを作り替えているところで、それがうまくできてきたら、日本はそれをハックして応用するのが得意なのかなとも思うんです。たまたま昨日、Clubhouseで落合陽一さんが言っていたんですが、Clubhouseで「無言の部屋」とか「ピカチュウの部屋」とか、むちゃくちゃな使い方を思いつくのは日本人ぐらいだって(笑)。それを聞いて、そうだよなって思ったんですよね。
パナソニックなり松下幸之助なりがやってきたことは、家電をOSにして、別の課題を解決していくということです。もともと冷蔵庫は、電気を使わない木の箱でした。氷を買ってきたり配達してもらったりして、箱に入れて冷やしていたわけですが、手間もかかるしお金もかかると電気で勝手に冷える箱を作った。
要は全然違うソリューション、生活を便利にするソリューションを、家電というフォーマットで行ってきたわけです。最近の例で言うと、美容家電ですよね。エステとか美容師のサービス産業だったものを、ハードウェアに持ってきて、家電的に解決してしまう。
つまり、サービス産業で提供されるものをハードウェアで置き換える、というやり方もあるということです。iPhoneがそれに近いことをやってしまっていますが、車や住宅、ヘルスケアや介護など、手付かずの分野はまだまだあります。ソフトウェア的なものをハードウェアの形に置き換え、定着させて世の中に広げるというのは、これからも可能性があると思います。
林間放牧のように、実は一見非効率なものが、効率が良かった、という話もありますしね。でも、第三の軸というのは、効率か非効率かじゃなくて、その間にいながらも全然違う価値観で、そこにサステナビリティや、中長期的に見たらコストダウンできるみたいな話を位置付けるものだと思います。それが何なのかはまだ探っているところですが、出せたらいいですよね。
──それは「食と農」班、責任重大ですね。「風の谷」全体の持続原理みたいなものを作ることを求められている。「風の谷」の思想的な理想は、結果として、「風の谷」の食というものに宿っていくような気がします。
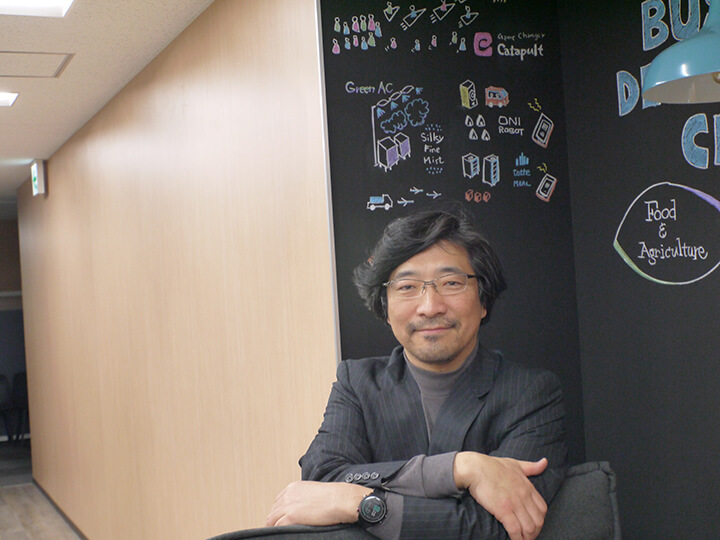
「土的」にいこう
──春になったら「農と食」班はどう展開していくことになっていますか?
深田 実際に農業をやっているところを見に行ったり、話を聞きに行くことができたらいいなと思っています。あともう一つは、先ほどの「微生物」というキーワードもあって。食の良し悪しは、実は微生物で決まるのではないかとも言われているんです。その土地の土壌にはどんな微生物がいるのか、微生物ハンティングもしないといけない。土壌とか菌がヒントになって、第三の軸に近づけるんじゃないかとも思っています。これはぜひ、やりたいです。
──「土」は思想的なモチーフとしても大事だと思います。『風の谷のナウシカ』で、トルメキアは火で、風の谷は風と水だ、ということが出てきますよね。これは、1980年代に反体制運動がエコと合流した「赤から緑へ」という思想の流れを、宮崎駿が作品に取り込んで描いたわけですが、文明と自然、資本主義とその外側という対比なんですよね。でも、僕らが立てなければならないのは、第三の軸。それこそ比喩ですが、土的にいきたいですよね。
専門家の方にも伺いましたが、土って、細かく砕かれた岩石、俗に砂と言われているものと植物の死骸が混ざった混合物っていう、よくわからない、あいまいな定義なわけです。農業は、そんな定義の難しい土というものと、ずっと向き合うものですよね。しかも、それを自分たちで作りながら壊し、壊しながらつくることをずっとやっていく。そこに、僕らの自然観というか、空間に対しての思想的な態度表明の手がかりがある気がします。
深田 その土の良し悪し、肥える肥えないを左右するのが微生物らしいんですよ。どれだけ多様な微生物が入っているかによって、土が変わる。微生物養殖というか、微生物ファーミングみたいな考え方にもつながっていきます。いかにその土地の微生物の多様性を維持するか、それを生かした農業をするかというところが差別化になる。
だから、微生物は一つのキーワードだと考えています。お酒やきのこも全部微生物に直結しますし。たぶん、「風の谷」の食の付加価値の作り方は、微生物の多様性を守った料理みたいなことになるんじゃないかなって、ちょっと未来を想定しています。
──微生物って、否応なくその土地土地で違うものですからね。発見したり創成したりするまでもなく、もとより独立して存在している価値じゃないですか。
深田 しかも、菌や菌糸みたいなものも含め、圧倒的な価値を発揮することがある。たとえばトリュフなんて、旬のそのとき、この一口のためだけにという世界じゃないですか。そういうことを「風の谷」で生み出していくことができたら、「風の谷」の経済は回っていくかもしれません (笑)。
──楽しみですが、「農と食」班は膨大な課題がありますね。
深田 どこから手をつけるのかという順番は、考えないといけないですね。第三の軸を早く位置付けたいんですけど、これがなかなか大変で。フィールドワークをして、その次かなっていう気がします。そうすると少し見えてくると思います。
──今日のテーマともなった、第三の軸をしっかり立てていくっていうのは、マサさんからいただいたキーワードとして、全体デザイン班のほうに持ち帰りたいと思いました。
深田 そもそも、「風の谷文法」が第三の軸そのものなんですよね。つまり、「Aである。ただし、Bでありうることも否定しない」という言い方で、AとBをも許容する。それはおそらくCという価値観を言いたいわけですよね。でも、Cを「Cです」と明示してしまうと、AもBも排除してしまう可能性がある。AもBもあっていいと受け止められるのは、Cという価値観を信じているから。そもそもの立脚点がわかったように思います。
──「風の谷文法」に関しては、僕はちょっと複雑なことを考えています。もちろんあれは、こんな感じの語り口で運動を進めていきたいという態度表明です。ガチガチに教条的にならずに柔軟性を持って、そしてユーモラスに楽しく運動を進めていきたいということを、文体で表現したかった。
でも実はもう一つ、あまり他では言ってないことがあるんです。言語は不完全で、世界には「○○ではない」という形でしか表現できないものが確実にある。ところが、それは悪用されることがとても多い。たとえば、「○○ではない」という言葉で否定ばかりすることで、常に相手の意見にケチをつけて批判する。そしてじゃあお前はどうするんだと訪ねたら、自分の提示する価値は言葉では表現できない、「○○ではない」というかたちでしか言えないのだと逃げてしまう。こうしたふるまいは、世の中にあふれていますよね。
だからやはりどこかで「○○である」って言わないと建設的なコミュニケーションは生まれない。そのほうが絶対に健全なものになる。ただ、それで健全なコミュニケーションにはなるのだけれど、相手に対するマウンティングの欲望などとはまったく関係ないところで、「○○ではない」っていう言葉の積み重ねでしか表現できないものはやはり確実にあるわけです。だから僕は「風の谷文法」にこだわったんです。「○○ではない」っていう否定系を、どうポジティブに使っていくのか。そのチャレンジが、実は「風の谷文法」の裏テーマであり、僕が「風の谷」に参加する裏テーマでもあるんです。
深田 そのお話は本当によくわかります。新規事業の作り方も、「新規事業の作り方はこうです」って言ってしまったら、そこで終わってしまうんです。その作り方通りにやっても、新規事業は生まれません。新規事業と既存事業では作り方はまったく違います。だから、「既存事業の作り方とは圧倒的に違う」ということは言うんですが、「新規事業の作り方はこうです」とは言えない。そういうことって、たくさんありますよね。
リーンスタートアップや産業のアーキテクチャの変革、社会課題・人々のお困りごとの解決など、既存のやり方ではなくて……ということはいっぱいある。それを我々は「アンラーン」と言っています。「アン」は否定形です。実はGCカタパルトのキーワードって、「アンラーン・アンド・ハック」なんですよ。
──それ、素敵ですね! どんなごちそうでも3日続けて食べたら飽きるじゃないですか。だから「食」って、ある種のポジティブな否定の連続でできているようなところがある。ものすごくポジティブに、僕たちは「○○ではない」ものを食べたいと感じながら日々生きているわけですからね。
深田 ぜひ、宇野さんも食班に。今度一緒にフィールドトリップに行きましょう。
──はい、ぜひ!
[了]
この記事は、宇野常寛が聞き手を、鈴木靖子が構成をつとめ、2021年3月8日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。


