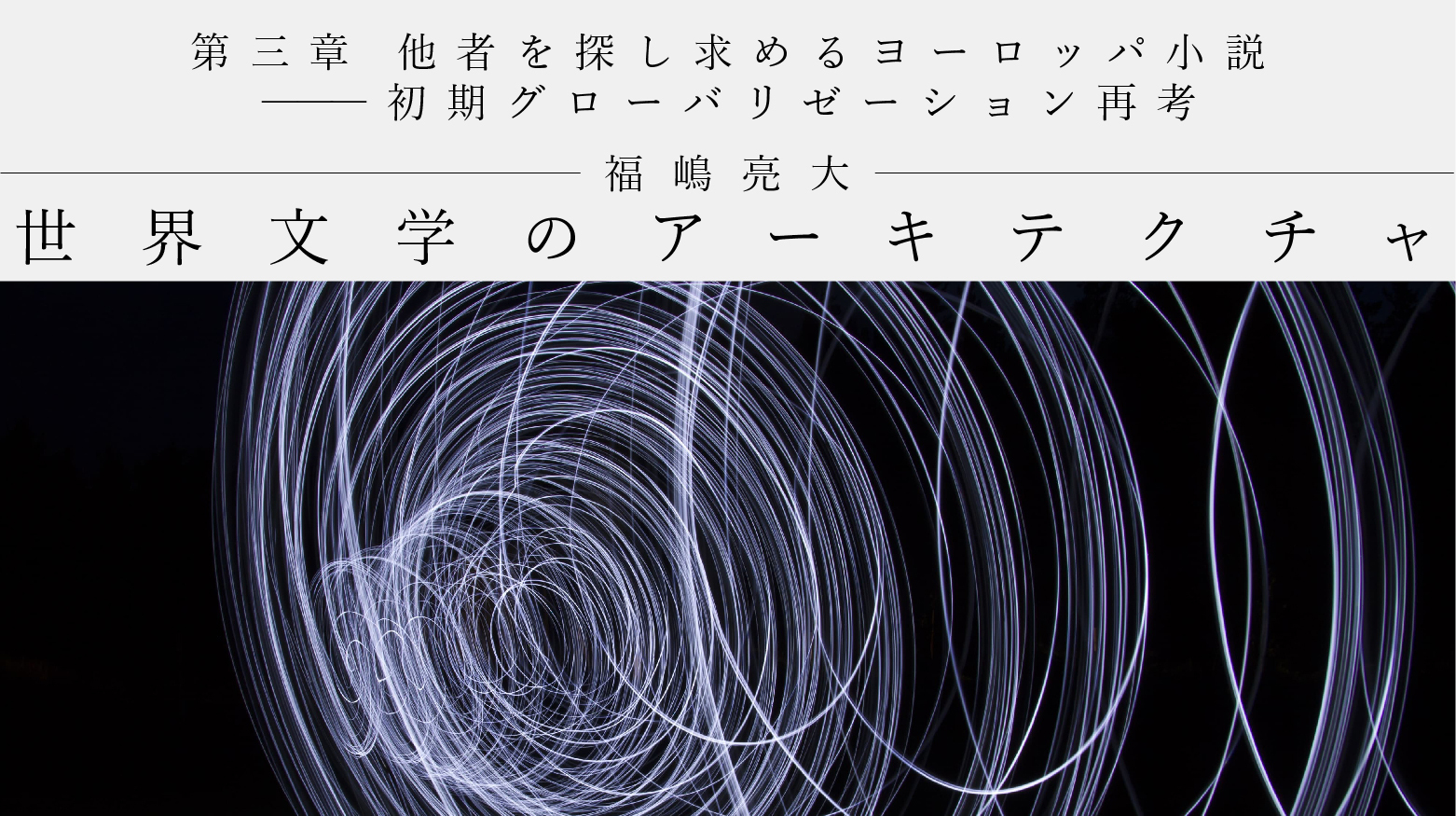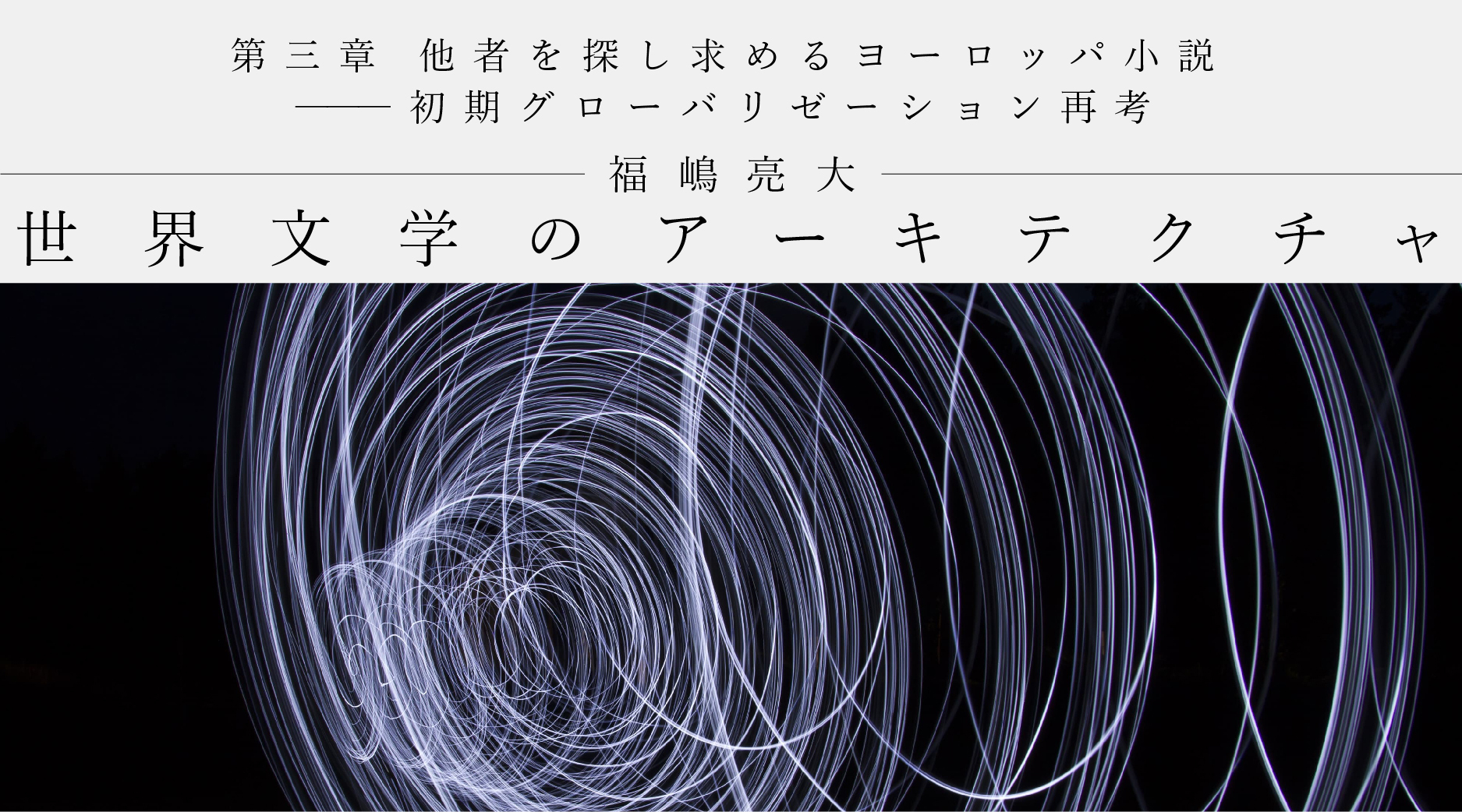批評家・福嶋亮大さんが「世界文学」としての小説とそれを取り巻くコミュニケーション環境を分析していく連載「世界文学のアーキテクチャ」。
一八世紀、初期グローバリゼーションによって「小説」が爆発的に市場に広がったとき、文学作品にどのような変化が起きたのか、『ドン・キホーテ』『ロビンソン・クルーソー』など当時を象徴する作品を分析しながら論じます。
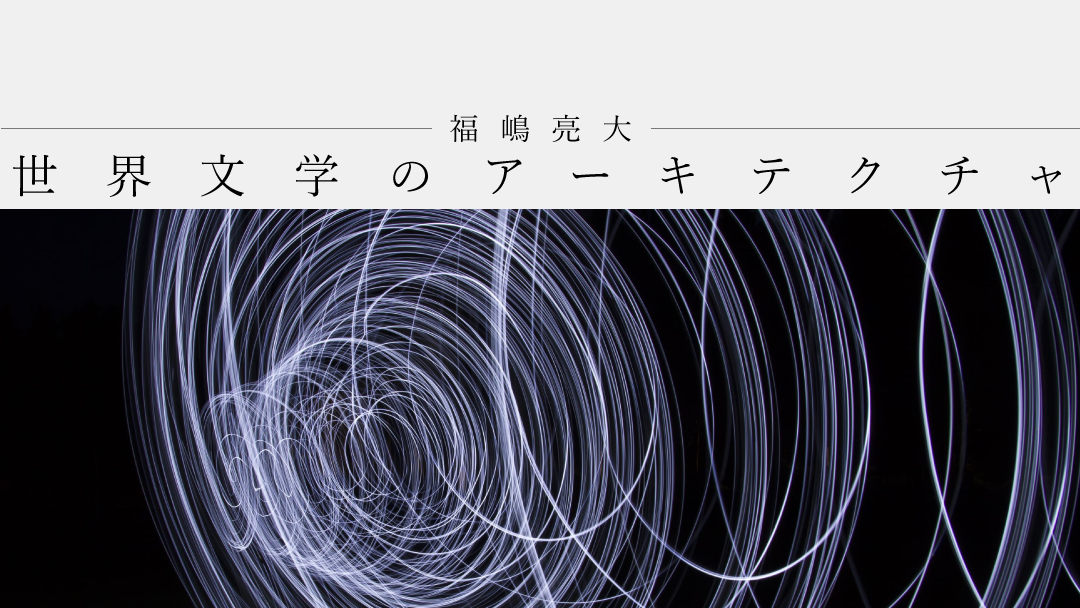
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、ヨーロッパ中心主義をいかに解体するか
世界文学=世界市場の成立は、文芸の諸ジャンルのなかで小説が覇権を握ったことと不可分である。小説は文学史上の新参者であるにもかかわらず、詩や演劇を凌駕し、世界規模の市場を生み出した。いわば小説のパンデミックこそが、近代文学史における最大の出来事なのである。序章で述べたように、それは商品としての小説が勝利したということと等しい。
ただし、このように考えるとき、小説がヨーロッパの固有種であることがしばしば暗黙の前提となっている。世界文学を推進せよというフリーメイソン的な命令を発したゲーテですら、ヨーロッパ文明の源流である古代ギリシアに特権性を与えていた。ゲーテがエッカーマンに対して、来るべき世界文学は何でもありではなく、あくまで「古代ギリシア人の作品には、つねに美しい人間が描かれている」(一八二七年一月三一日)から、それを模範にせねばならないと釘を刺したのは、その証拠である。もともと、ゲーテの美学は一八世紀ドイツの美術史家ヴィンケルマンの『ギリシア芸術模倣論』――古代ギリシア芸術という「源泉」に戻ることを訴え、新古典主義を準備した著作――の影響下にあったが、その尺度は文学にも適用されたのである。
パレスチナ生まれの批評家エドワード・サイードが批判的に論じたように、ヨーロッパ中心主義的なイデオロギーは、ゲーテのみならず二〇世紀の碩学の比較文学者(クルツィウスやアウエルバッハ)にまで及んでいる。サイードは「ヨーロッパと、ヨーロッパのキリスト教的・ラテン的文化圏」を最高位に据えるイデオロギーを解体することに、あくなき執念を燃やし、特にイスラムやアジアへのバイアスのかかった表象(オリエンタリズム)を粘り強く批判した[1]。西洋の帝国主義はたんに軍事力で他者を支配しただけではなく、文学や学問のレベルでも東方の他者を御しやすい記号に変えたとするサイードの批評は、知識=権力のもつ政治性をラディカルに問いただそうとする試みであった。
サイードの仕事の重要性は疑う余地がない。とはいえ、彼とは別のアプローチで、ヨーロッパ中心主義を相対化することも可能ではないか。そもそも、東アジアでは、中国がヨーロッパとは独立した「小説」の文化を数世紀にわたって持続させ、日本や朝鮮半島にまで影響を及ぼしてきた。その歴史の重みは、西洋の内在的批判者であったサイードよりも、ヨーロッパ中心主義者と目されるゲーテのほうが、かえって真剣に受け取っていたと言えるかもしれない。サイードはイスラムに対する西洋諸国(特にイギリス、アメリカ、フランス)の偏見の再生産に鋭い感覚を働かせた反面、中国や日本の文学的伝統はおおむね視野の外に置いた。それに対して、文人政治家のゲーテはむしろ中国(清)の小説にも言及しながら、世界文学の構想を気兼ねなく語ったのである。
さらに、ゲーテは一四世紀ペルシアの詩人ハーフィズに強く触発されて、一二編から成るチクルス(連作)『西東詩集』(一八一九年初版/一八二七年決定版)を刊行したが、それと連動してきわめて綿密な研究を残した。彼はそこでオリエントの「精神」を高く評価している。
オリエントの詩歌の最高の性格は、われわれドイツ人が精神[ガイスト]と呼ぶ、上位にあって人間をみちびく存在のすぐれた特性である。〔…〕精神はとりわけ老年に、あるいは老年に入った世界の時期に属する。オリエントの文学には、総じて世界全体を見わたす眼、アイロニー、資質の自在な行使が見いだされる。[2]
ヘーゲルならば、このような言い方は決してしなかっただろう。ヘーゲルにとって、精神の歴史はヨーロッパで真に完成するのであり、アジア文明は踏み越えられるべき未熟な段階にすぎない。それとは逆に、ゲーテはペルシアの詩にこそ、ヨーロッパの人間中心主義とは異なる「老年」の成熟した精神を認めた。「アラビア人が駱駝や馬に対して心からの親和性をもっていることは、あたかも肉体と霊の間柄にさながらである」と称賛したゲーテが、自身の『西東詩集』でもイエスやムハンマドゆかりの「恩寵を受けた動物」(驢馬、狼、犬、猫)を取り上げていることは、注目に値するだろう[3]。『ファウスト』を筆頭にして、ゲーテの文学には人間ならざるものへの変身の欲望があったが(第一章参照)、彼はそれをアラビアの詩に見出したのである。
もっとも、この野心的な詩集もサイードに言わせれば、オリエンタリズムを「無邪気に利用」したものにすぎない。彼はゲーテの「移住〔ヘジュラ〕」という詩を取り上げて、そこでオリエントが「解放の一形式」に――若々しい精神をよみがえらせる「泉」に――仕立てられたことを批判した[4]。戦争の続く西・南・北の野蛮さに染まっていない「東」を称揚したゲーテは、ペルシアの詩を尊敬するように見えて、実際にはその他者性を除去し、いわば精神のアンチエイジングの機会として横領したのではないか? このサイードの問題提起は広い射程をもつ。なぜなら、他国を勝手に「解放」のシンボルとして祭り上げるイメージ戦略は、過去のオリエンタリズムに限らず、現代でもさまざまな形で反復されているのだから。
それでも、私は以下サイードの見解をたびたび参照しつつも、大筋ではゲーテの(一見するとナイーヴにも思える)世界文学論のプロジェクトの批判的延伸を試みたいと思う。というのも、東西のコンタクト・ゾーンのもつ意味を再考しつつ、アジアの独立性にも十分な注意を払うことは、世界文学論の核心的なテーマだからである。そこで以下の二章では、〈1〉ヨーロッパとその外部世界とのコンタクトを中心として文学史を再記述すること、〈2〉ヨーロッパと並び立つ中国の文学について、その文学史上の意味を再考すること、この二点について考察する。
2、コンタクト・ゾーンの文学
もとより、古代ギリシアに始まる純正のヨーロッパ文化とは、それ自体がフィクションである。そのフィクションへの批判として、ギリシア文化のルーツをエジプトやシリアに認めたマーティン・バナールの『ブラック・アテナ』は名高い。彼の仮説は学界で猛烈なバッシングを受けたが、ギリシアをヨーロッパの不動の源泉とする限り、それ以前のメソポタミアやエジプトのきわめて長大な文明が不当に軽視されることは避けがたい。その点で「ヨーロッパ白人中心主義」を解体し、古代ギリシアをむしろ雑色の混成文化として捉え返そうとするバナールの主張は、今でもその意義を失っていない[5]。
ギリシアの文学史にしても、彼らが「バルバロイ」と呼んだ東方の世界とのコンタクト抜きには語れない。ギリシア演劇のパイオニアであるアイスキュロスの悲劇『ペルシア人』は、ペルシア帝国のクセルクセス大王の傲慢ゆえの敗北をテーマとしている。短気なクセルクセスはギリシアとの戦争で、大勢の兵士をむざむざと失った。取り残された女たちは、王の短慮のもたらした大量絶滅への「嘆き」の声でアジアの大地を満たす。「今やげにアジアの全土/人影もなく嘆きあり」[6]。
ペルシア戦争に従軍した兵士でもあったアイスキュロスは、その硬質でゆるぎない言葉によって、ペルシア人女性への感情移入を強力に組織した。ペルシアの指導者の失敗が、女性たちの嘆きにおいて、アジア全土に被害を与える深刻なカタストロフとして表現される――これはまさに表象と感情の政治である。サイードによれば、アイスキュロスのペルシア表象は、偏見に染まった西洋のオリエンタリズムのプロトタイプになった。そこでは、ペルシアは威嚇的な「他者」であることをやめて、比較的親しみやすい女性の嘆きの声へと縮減された[7]。戦争は他者(オリエント)との敵対性を際立たせる一方、それ自体が巨大なコミュニケーション、つまり敵=他者に乗り移り、かつ勝者の立場から敗者の感情を定型化する機会になったのである。
こうして、ギリシアの劇は自らのライヴァルであった「アジア」および「帝国」を消化吸収する器官として機能した。ただ、公平を期して言えば、ギリシア人がただ東方の帝国を「野蛮」や「悲嘆」のイメージに回収し尽くしたわけでもない。
例えば、ヘロドトスは『歴史』でイランの騎馬民族スキュタイ人について「外国の風習を入れることを極度に嫌う」(巻四・七六)としてその閉鎖性を指摘する一方「世界中でペルシア人ほど外国の風習をとり入れる民族はいない」(巻一・一三五)と評して、享楽的なペルシア人が異国のファッションを貪欲に吸収し、ギリシア由来の少年愛を存分に楽しんでいることを報告していた。ギリシアの植民都市であるハリカルナッソス(現トルコ)生まれのヘロドトス自身がコンタクト・ゾーンの申し子であり、それは彼のペルシアの見方にも影響したと思われる[8]。ヘロドトスの数世紀後、アレクサンドロス大王の東征をきっかけとして、ペルシア人はギリシア文化と融合してヘレニズム文化を生み出したが、それも彼らの並外れた開放性なしにはあり得なかっただろう。
さらに、西洋文化の源流としてヘレニズムと並列されるヘブライズム(ユダヤ・キリスト教の一神教文化)も、アジアとのコンタクト・ゾーンを母胎としている。バビロン(現在のバグダード近郊)に強制移住させられたユダヤの民は、異郷の地で聖書の編集にあたったが、そのプロセスでオリエントの神話が聖書のテクストに侵入することになった。特に、『創世記』の最初の部分(いわゆる「原初史」)における洪水物語(ノアの箱舟の説話)は、メソポタミアの『ギルガメシュ叙事詩』の洪水物語から、その多神教的要素を払拭し、峻厳なヤハウェ信仰の立場からそれを書き改めたものと推測されている。加えて、旧約聖書のコーへレト書(伝道の書)にも『ギルガメシュ叙事詩』とよく似た人生観――人間が死ぬべき「空の空」の存在であり、その運命が動物の運命と何ら変わらないことを率直に認めようとするニヒリスティックな覚悟――が認められる[9]。
生物学的な隠喩を使えば、ヘレニズムにせよヘブライズムにせよ、いわば遺伝子の交叉(クロスオーバー)に似た文化現象と評せるのではないか。はっきりしているのは、ヨーロッパの文化的アイデンティティの古層はすでにアジアに深く浸透されており、その純正さを無理に主張しようとしても、せいぜい偏狭なオリエンタリズムに陥るだけだということである。われわれはむしろ、アイスキュロスの劇もヘロドトスの歴史書もユダヤの聖なるテクストも、アジアの帝国との「接近遭遇」というトラウマ的なショックなしにはあり得なかったことを再確認すべきである(裏返せば、オリエンタリズムとはこのショックを無化しようとする集団心理的な反応として理解できる)。
そして、この接近遭遇ゆえのショックは、七世紀以降アジアに強大なイスラム帝国が築かれたことによって、いっそう増幅された。サイードは次のように鋭く指摘している。
たしかにイスラムは多くの点で、まことに気にさわる挑発的存在であった。それは、地理的にも文化的にも、不安をかき立てるほどにキリスト教世界に近接していた。ユダヤ教的=ヘレニズム的伝統を身につけたのもイスラムなら、キリスト教から独創的なやり方で借用を行ったのも、軍事上、政治上の無類の成功を誇ることができたのもイスラムであった。そればかりではない。イスラムの国々は、聖地の近隣、いや聖地の頂点[イェルサレム]にさえ存在していた。[10]
キリスト教世界にとって、イスラムは自己と遠く隔たった他者ではなく、むしろ多くの点で自己と近似した――しかもしばしば自己よりも優れた――他者なのであり、だからこそその存在が気にさわったのだ。この近さゆえの不安と否認が、今日のパレスチナ問題やヨーロッパ社会のイスラモフォビアにまで及んでいるのは明らかだろう。
そもそも、イスラムの高度に洗練された知識や技芸は、ヨーロッパの思想や文化にも入り込んでいる。十字軍遠征を経て、アリストテレスをはじめ古代ギリシア人の哲学がイスラム経由で中世スコラ哲学に入り込んだことはよく指摘されるが、文学についてもその中枢にある恋愛表現が、イスラムから影響を受けたという有力な説がある。
ドニ・ド・ルージュモンによれば、ヨーロッパ抒情詩の源流である一二世紀のトゥルバドゥールには、アラビアの文学の影響が及んでいる。彼らの詩は結婚を度外視した純潔な魂の讃歌であり、その「永久に満たされることのない」愛ゆえの神秘主義的な飛躍を、高度に洗練されたレトリックで歌い上げた。その母胎となった宮廷風恋愛(コルテツィア)の隠喩は、アラビアのエロティックな詩とよく似ているとされる。その一方、アンリ・ダヴァンソンはより微妙な筆遣いで、この「アラブ仮説」の行き過ぎを戒め、両者の違いを指摘したが(例えばアラビアの愛がしばしば同性愛であったのに対して、ヨーロッパのトゥルバドゥールのそれは異性愛的性格をもつ)、それでもアラビアからの影響を決して否定したわけではない[11]。この観点から言えば、ゲーテの『西東詩集』はヨーロッパ抒情詩のアラビア的古層を、再び視界に浮上させるような仕事と見なせるだろう。
3、『ドン・キホーテ』――痕跡としてのイスラム
このように、ヨーロッパ文学の進化を考えるとき、異質な外の文化とのコンタクトを無視することはできない。それどころか、自己に他者をたえず乗り移らせる霊媒的な力、つまり他者になろうとする変身の意志こそがヨーロッパの核心部にあると見なしても、決して誤りではないだろう。外的なショックを利用して内的な変容を加速させること――このような戦略は近代小説の展開にも見出せる。以下では一七世紀初頭のセルバンテス、および一八世紀のモンテスキューとダニエル・デフォーという三人の代表作を、その範例として並べてみたい。
セルバンテスの『ドン・キホーテ』について特に興味をひくのは、アラビアの歴史家シデ・ハメーテの原作『ドン・キホーテ』をたまたま市場で入手した著者セルバンテスが、スペイン語を解するモーロ人(マグレブやイベリア半島に住むイスラム教徒)にそれを翻訳させたという体裁で書かれていることである。つまり、『ドン・キホーテ』は翻訳文学の仮面をかぶり、アラビア語文学のレプリカとして自己を演出した。セルバンテスは作者でありながら、その作者性そのものをわざと文化的な混成体に仕立てたのである。
そもそも、スペインでは長くキリスト教文化とイスラム教文化が対立しつつ共存していた。イスラム勢力がイベリア半島から撤退したのは一四九二年のグラナダ陥落においてであり、その数百年に及ぶ支配の遺産は、スペインのアイデンティティの根幹に入り込んでいる。スペイン王国を共同統治したフェルナンド二世とイサベル一世は、カトリック信仰と血の純潔をもとにした統一政策を進め、アラビア文化とユダヤ文化をともに排除しようとしたが[12]、セルバンテスはあたかもこの純血主義化したスペインを再び雑種的なコンタクト・ゾーンに投げ返すようにして『ドン・キホーテ』の作者性を設計したと言えるだろう。彼の年下の好敵手であった劇作家ロペ・デ・ベガは、スペインを「交易と利益の世界的大市場」(『セビーリャの砂岸』)と呼んだが[13]、『ドン・キホーテ』そのものが複数の文化の交差する「世界的大市場」に似ていた。
もっとも、セルバンテスは『ドン・キホーテ』のアラビア的起源をかしこまって述べたわけではない。『ドン・キホーテ』にはむしろアラビア人への無遠慮な評価が書き込まれていた。
この物語の信憑性について何か疑義が呈せられるとしたら、もっぱらそれは、作者がアラビア人であることに由来するものであろう。嘘をつくというのはあの民族の本来的な性癖だからである。しかも、彼らはわれわれに激しい敵意を抱いているのであってみれば、同じ嘘でも、作者は事実を誇張するというよりはむしろ書き渋るという傾向にあることが推定されうるし、実際わたしにはそのように思われる。(第一部第九章)
この手の込んだ記述において、セルバンテスはいわばウイルスを仕込まれたプログラムの誤作動として、『ドン・キホーテ』という小説を了解している。『ドン・キホーテ』の起源には、真実をねじまげようとするアラビア人の「敵意」がある。『ドン・キホーテ』に象徴される近代小説とは、まさに異邦の他者によってハイジャックされ、プログラムをたえず書き換えられながら前進する自己言及的なジャンルなのであり、そこに神話のようなハーモニーを期待することはできない[14]。
その後も、セルバンテスはちょくちょく顔をのぞかせては、作品の起源である原作者シデ・ハメーテの執筆態度、特にその細部にまでこだわり抜こうとする書き方を無遠慮に評価する(後篇第四四、四七章)。『ドン・キホーテ』を動かすプログラムの秘密は、設定上は作者でも翻訳者でもないはずのセルバンテスによって次々と暴露された。そこには、作者も含めて何ものも無傷のままでは済まさないという、セルバンテスの強固な批評意識を読み取ることができるだろう。
そもそも、セルバンテスは序文で、自分は「一見したところドン・キホーテの父親のようであっても、実はその継父」であるから、子ども可愛さに目がくらむことはないという趣旨のことを述べていた。この面白い表現は、アラビア的なものを含めて『ドン・キホーテ』が複数の父=起源をもつことを暗示する。セルバンテスはここで、作者と主人公の関係を、情緒的にべったりしたフィリエーション(血縁関係)ではなく、さまざまな知的操作を介在させたアフィリエーション(養子縁組関係)として捉えた。
このようなアフィリエーションの多角化は、地中海がさまざまな交渉や衝突の生じる荒々しいコンタクト・ゾーンであったことと切り離せない。特に、スペイン帝国とオスマン帝国が地中海でたびたび軍事的に衝突していた以上、セルバンテスが語りをねじまげるアラビア人の「激しい敵意」に(どこまで本気かは別にして)言及したことも、さほど不思議ではない。彼自身、スペインとトルコの命運を賭けたレパントの海戦に従軍し、左手を負傷したとされる。ちょうどアイスキュロスの劇がペルシア戦争の戦後文学であったように、『ドン・キホーテ』もスペイン帝国とトルコ帝国(カトリックとイスラム)の戦争の戦後文学であった。
ただ、ここで見逃せないのは、『ドン・キホーテ』の刊行が一五七一年のレパントの海戦から、およそ三〇年も経った後だということである。イタリアに渡って青年兵士となり、オスマン帝国相手に奮戦したセルバンテスは、トルコの海賊に捕まってアルジェの牢獄に収容された後、傷痍軍人としてスペイン社会に帰還する――この一六世紀の地中海人は、しかし無敵艦隊の食糧係や徴税人等の職を転々とするうちに罪に問われ、投獄されてしまう。戦争の英雄から周縁的なアウトサイダーへと転落した彼が、この不遇の時期を辛うじて生き延び、ようやく五〇代半ばに刊行したのが『ドン・キホーテ』なのである[15]。
その間、セルバンテスやロペ・デ・ベガの関与したスペインの無敵艦隊は、一五八八年のアルマダの海戦でイギリスに手痛い敗北を喫し、国威には陰りが生じていた。つまり、帰還兵セルバンテスがベストセラーを刊行するまでに、この作家とスペインはともに自己のアイデンティティを大きく変化させる「危機」の時代にあったと言えるだろう。歴史家のフェルナン・ブローデルは、レパントの海戦が海上におけるトルコの衰退を示すと述べながら、それ以降スペインとトルコがともに地中海を去ったことを強調している。
スペイン陣営とトルコ陣営、地中海で長らく睨み合ってきたこの二つの勢力が、互いに相手から離れていき、それと軌を一にして、かつて一五五〇年から一五八〇年にかけて、この内海の名物であった大国同士の戦争が、いっさい見られなくなっていくのだ。[16]
一六〇一年に『ドン・キホーテ』が刊行されたとき、トルコとスペインはすでに地中海の覇権争いから退却し、大きな戦争の機会はそこから失われていた。アラビア人シデ・ハメーテの原作とされるテクストに、セルバンテスが遠慮なく干渉するのは、アラビアの遺産の大きさとともに、地中海におけるイスラムの軍事的脅威の減退を感じさせる。セルバンテスの継子であるドン・キホーテ主従は、地中海でイスラム教徒と戦争もせず、あるいはロビンソン・クルーソーのように大西洋に乗り出すこともなく、赤く荒涼としたスペインの大地を愛馬ロシナンテとともに遍歴しながら、幻想と現実をらせん状に絡めあわせた。この陸地に根ざした迷宮的なメタフィクションは、イスラムとのコンタクトを、シデ・ハメーテというミステリアスな痕跡として残したのである。
4、『ペルシア人の手紙』――統治の腐敗
さて、『ドン・キホーテ』からおよそ一二〇年後の一七二一年、フランスではモンテスキューの書簡体小説の傑作『ペルシア人の手紙』が刊行されて大評判となる。モンテスキューはそこで、スペイン人の著作一般を酷評しながらも、ただ『ドン・キホーテ』についてだけは「スペイン人の本で唯一の良書」であり「他のあらゆる本の滑稽さを暴いた書物」だと称賛していた(手紙78/以下『ペルシア人の手紙』の引用は講談社学術文庫版[田口卓臣訳]に拠る)。
ここで、『ペルシア人の手紙』を『ドン・キホーテ』の隠れた後継者と見なすことも不可能ではないだろう。セルバンテスがドン・キホーテとサンチョ゠パンサという二人組の旅人を起用したように、モンテスキューは主にユズベクとリカという二人のペルシアの旅人の視点から、パリとペルシアという二つの異質な社会を批評した。『ドン・キホーテ』と同じく『ペルシア人の手紙』にも、社会が信じ込んでいる幻想の「滑稽さを暴く」一面があったのは確かである。モンテスキューは単眼的な観察には与しない。むしろユズベクとリカ、ペルシアとフランスのあいだの視差(パララックス)こそが、この書簡体小説に鋭い批評性を与えた。
貴族ユズベクはペルシアの都市イスファハーンに一夫多妻制のハーレムをもち、そこを黒人の宦官長に管理させる一方、宮廷の専制政治にも嫌気がさし、かつ女たちへの愛も枯渇したために、新たな叡智を求めてリカとともにパリに向かう。つまり、ユズベクは自由を求める知的亡命者のプロトタイプである。しかし、彼がパリの文化を異邦人として観察するうちに、妻の一人ロクサーヌの反逆をきっかけとして、本国のハーレムの運営が破綻し始める。焦ったユズベクは必死に書簡で指示を出すが、数ヶ月の時差があるために女たちの「反乱」を食い止められず、ついにハーレムは崩壊に到る。
ユズベクはペルシアの宮廷では専制を嫌う開明的なタイプであり、フランスをはじめ他の社会についても鋭い観察力を発揮するが、ハーレムの女性たちに対しては、むしろ専制君主としてふるまう。だが、動物のように虐待されてきた女性たちが、自らを解放しようとしたとき、ユズベクの自己矛盾は顕在化し、その統治術は破綻するのである。『ペルシア人の手紙』に「専制の不条理」を認めるツヴェタン・トドロフが的確にまとめたとおり、ユズベクは「他者について明敏であり、自分について盲目な人間の典型なのである」[17]。
その一方、二人のペルシア人の訪れたパリでは消費文化が隆盛を極めていた。コーヒーが大流行し、カフェでニュースを伝えあうパリの様子を見て、知識人のユズベクは「それにしても私が不愉快なのは、こういう才人たちが祖国の役に立とうともせず、子供じみたことに才能を浪費していることだ」(手紙36)と慨嘆する。他方、ユズベクよりも若いリカは、むしろ「好奇心が尋常ではない」パリの住民によって急速にアイドル化され、そのブロマイドまで制作される。
僕はどこへ行っても、自分の肖像画を見つけた。どんな店の中にも、どんな暖炉の上にも、僕の分身が増えていった。それくらい人々は僕を十分に見られなくなることを恐れていた。(手紙30)
こうして、パリでは住民の祖国愛がカフェのおしゃべりのなかで失われる一方、物珍しい異国のアイドルのシミュラークルが増殖する――これは二一世紀の消費社会論にも十分に通用するテーマだと言えるだろう。しかも、その消費社会は、キリスト教の権威をも失墜させている。パリ市民の新しい偶像となったリカの無遠慮な観察によれば「教皇はキリスト教徒の首長だ。人々が習慣ゆえにごまをする古い偶像だ」(手紙29)。
そもそも、当時のフランスは、イギリス人ジョン・ローの投機的な経済政策(いわゆる「システム」)に翻弄されたばかりであった。『ペルシア人の手紙』はローのシステムへの批判として「一〇年ごとに金持ちを貧困に突き落とし、貧乏人を富の絶頂へと一気に羽ばたかせる激変が起きる」(手紙98)フランス社会の大混乱ぶりを、ユズベクの視点から描いたが[18]、そのパリの消費者たちはユズベクのたどった自己崩壊の原因をある程度共有している。つまり、物珍しい他者にばかり気を取られて、自分が破滅に向かっていることにはまるで気づかないのである。
もともと、ボルドー南西(スペインとのコンタクト・ゾーンでもある――モンテスキュー自身にもスペインの富について分析した論説がある)のワイン用ぶどうの栽培業者であった彼には「腐敗」に憑かれたデカダン的思想家としての一面があった。実際、彼の主著『法の精神』には、プラトンのように最善の政体を描こうとする意図はない。それどころか、彼は君主政、貴族政、民主政、そのいずれもが時とともに最悪の「専制」へと堕落してゆくことを強調した。あるいは『ローマ人盛衰原因論』でも、共和国ローマがその内的必然性によって、いかに徳を失って衰退したかが克明に記された。そのため、彼の政治的著作は総じて「原理の腐敗は避けがたいという印象」(阪上孝)を与える[19]。
モンテスキューは社会を改善する特効薬を示さなかった。ただ、ワインの醸造と同じく、立法者=調整者のコントロールのもとで、事物の秩序を保ち、適度なリズムで運動を続けること――それだけが彼にとって社会を平穏に保つ秘訣であった。逆に『ペルシア人の手紙』ではまさにその立法者=調整者が不在のまま、手紙の行き違いが発生するうちに、ユズベクのハーレムとパリの消費社会における統治の腐敗が暴かれてゆく。一六一通の手紙を舞台とする東西文明のコンタクトは、双方の知識社会の退廃をはっきり浮かび上がらせるものとなった。
5、帝国の退廃と勃興
さらに、『ペルシア人の手紙』が特筆に値するのは、フランスとペルシア以外の社会についても鋭い分析が見られることである。ユズベクはペルシアからパリに向かう道中でオスマン・トルコを経由し、こう記している。
トカからスミルナまでは、特筆に値する都市はただの一つもない。私はオスマン帝国の衰弱を目の当たりにして驚いた。この国の病んだ体は、適度の穏やかな養生ではなく荒療治によって持ちこたえていて、そのせいでますます疲弊し、やつれ果てている。(手紙19)
ユズベクは「二世紀も経たないうちに、この帝国はどこかの征服者による凱旋の舞台にあるだろう」と述べる。この予想がかなり正確であったことは、オスマン帝国が長い衰退期を経て『ペルシア人の手紙』のほぼ二〇〇年後の一九二二年に滅亡したことからも分かるだろう。そして、このオスマン帝国の崩壊を主導したのは、政教分離を推し進め、一夫多妻制を廃止した――いわば専制と自由のあいだの自己矛盾を克服するのに成功したユズベクとでも評せるような――トルコ人の将軍ケマル・アタチュルクであった。
そればかりか、ユズベクは帝国という統治モデルそのものの限界にも言及した。モンテスキューは後に『法の精神』で小国主義に基づく共和制論を掲げるが(「その本性からして共和国は小さな領土しかもたない。そうでなければ、それはほとんど存続できないだろう」[20])、それに似た考えは『ペルシア人の手紙』のなかですでに表明されている。
帝国というものは、一本の樹木に喩えることができる。その広がりすぎた枝は、幹から樹液を吸い尽くし、木陰を作ることにしか役立たない。
君主たちに遠隔地征服への情熱を改めさせるにあたって、ポルトガル人とスペイン人の例以上にふさわしいものはない。(手紙121)
ここでモンテスキューは、トルコのようなアジアの古い帝国のみならず、海外に帝国を築いたスペインやポルトガルについても、その拡張戦略の病理を強調した。すでに一六世紀の修道士ラス・カサスは『インディオスの破壊についての簡潔な報告』(一五五二年)で、スペインのコンキスタドールたちが新大陸の植民地で暴虐の限りを尽くしたことを告発していた。彼の『報告』はヨーロッパじゅうに広まりスペインの悪評を高めたが、モンテスキューもペルシア人ユズベクに、スペイン帝国の残虐でおぞましい侵略を厳しく批判させている。
では、モンテスキューにとって、巨大な帝国モデルはただ下り坂にあるばかりであったのか――否。ここで興味深いのは、ユズベクがオスマン帝国の凋落とちょうど対比するようにして、新興国ロシアに言及したことである。「この国[ロシア]の皇帝[ツァー]は、キリスト教諸国でペルシアと重なる利害を持つただ一人の君主だ。なぜなら、皇帝は私たちと同じくトルコ人の敵なのだから」(手紙51)。トルコの衰退を目の当たりにしたペルシア人ユズベクは、ロシアについては、トルコの敵という一点で同じ陣営の仲間と認めている。しかし、その一方で、ロシア皇帝ピョートル一世は、トルコ以上のエネルギーをもつ存在として描き出された。
皇帝は今や自国を見捨てているが、まるで国が彼を抑えきれないかのようだ。彼はヨーロッパに別の属領や新しい王国を探し求めることだろう。(手紙51)
実際、一八世紀初頭に内陸のモスクワから海沿いのペテルブルグに遷都したピョートル(二一世紀のプーチンのお手本でもある)は「バルト海の王」として君臨し、ロシアの海洋志向を鮮明にした[21]。『ペルシア人の手紙』の出た一七二一年は、まさにそのピョートルがロシア帝国の初代皇帝になった年である。モンテスキューはヨーロッパを脅かしてきたアジアのトルコ帝国の衰退を予告する一方、西欧文明を利用してのしあがった帝国ロシアが、いずれその制御不可能なエネルギーによって、ヨーロッパに進出してくる未来を予想していた。しかも、その不気味な未来は、ペルシアの貴族のレンズを通して描かれたのである。
レパントの海戦に参加したセルバンテスは、アラビア人の原作者にまだ「敵意」を認めていた。それに対して、その一世紀以上後の『ペルシア人の手紙』は、トルコやペルシアに代表されるアジアのイスラム帝国が、ロマンティックな表象へと本格的に置き換えられる時代を予告していた。ユズベクやリカは他者に気をとられすぎた観察者であり、フランス人にとっては安全な消費の対象にすぎない。サイードによれば、ヨーロッパ人はイスラムについては「危険の感覚」をもっていたが[22]、『ペルシア人の手紙』ではこのような危機感は消失し、その代わりにロシアが新たな他者として現れるのである。
6、アジアの帝国から未知の新世界へ
われわれはふつう、文学の世界認識は狭小な段階から徐々に拡大していったと漠然と思い込んでいる。しかし、ヨーロッパ文学の歩みは決してそういうものではない。繰り返せば、古代ギリシアのアイスキュロスからして、すでに東方のペルシア帝国とのコンタクトを劇の中枢に据えていた。前章で述べたように、「今・ここ」を超越して、他者に憑依するガリレイ的言語意識も、ヘロドトスの『歴史』をはじめギリシア人の世界認識に早くも出現していた。
標語的に言えば、ヨーロッパ文学史とは他者を探し求める歴史である。ゆえに『ペルシア人の手紙』のなかで、オスマン帝国の退潮が予言され、その代わりに非イスラム的な他者であるロシアが登場することは、きわめて重要である。しかも、その他者に気をとられすぎて、自己が衰亡してゆくというアイロニーまで、モンテスキューはしっかり書き込んでいたのだ。そこから小説史のマクロな展開を読み取るならば、およそこうなるだろう――ヨーロッパの近代小説とはオリエントのイスラム帝国の黄昏とともに生じ、その後は非イスラム的な他者との遭遇を利用しつつ、二〇世紀半ばの世界各地の植民地の独立とともに衰亡したジャンルである、と。
ただ、その場合、ヨーロッパ文学に世界認識=他者認識のビッグバンをもたらしたのが、新興国のロシア以上に、海を隔てた「新世界」についての知見であったことも指摘せねばならない。そのインパクトをいち早く利用したのは、ロンドンのトマス・モアによる『ユートピア』(一五一六年)である。一五世紀末以降「新世界」(アメリカ大陸)を四度旅したと称するイタリア人アメリゴ・ヴェスプッチの航海記が、当時人気を博していた。『ユートピア』はヴェスプッチに随行したとされる架空の船乗りラファエル・ヒュトロダエウスが、その並外れた体験と認識をアントワープ(アントウェルペン)でモアに語ったという体裁で書かれている。
エラスムスは盟友モアの描き出したユートピアを「既知の世界の境界外」に位置する「新世界」と評した。「社会の最善政体」とは何かを考えるプラトン以来の政治学を引き継ぎながら、モアは私有財産制を撤廃し、住民たちが自然状態に従って生きる一種の共産主義社会を構想したが、そのラディカルなヴィジョンはまさに未知の「新世界」の出現に強く触発されている。ヴェスプッチの航海はたんに地理的な発見にとどまらず、「既知の世界」に閉じ込められていたそれまでの哲学的な世界像に、ブレイクスルーをもたらす契機になったのである。
このような文学や思想のグローバリゼーションが一つの頂点に達したのは、一八世紀においてである。非ヨーロッパの「新世界」との出会いを契機として、一八世紀初頭のフランス人は多様なユートピア的想像力を開花させた。その後、モンテスキューの『ペルシア人の手紙』を皮切りに、ヴォルテール、ルソー、ディドロら新興の「哲学者」(フィロゾーフ)たちが続々と小説を手掛けた。そこにも異世界への関心ははっきり示されており、そのエキゾティックな装いのなかに、本格的な文明批評が込められるケースも多かった。想像上のタヒチ人の視点からヨーロッパの性道徳を諷刺したディドロの『ブーガンヴィル航海記補遺』(一七七二年執筆/著者の死後刊行)は、その代表作である[23]。
さらに、ルソーの『新エロイーズ』(一七六一年)の主人公で、田舎者で純朴な家庭教師サン゠プルーも、ジュリとの恋に破れた傷心を抱えて世界周航の旅に乗り出し、南米のブラジル、パタゴニア、メキシコ、ペルー、さらにはアフリカ大陸をめぐるが、そこではいずれも貪婪なヨーロッパ人に略奪された優しくも不幸な現地人の姿が見出される(第四部・書簡三)。つまり、サン゠プルーと同様に深く傷ついた「新世界」の惨状が、文明の横暴の証拠として描かれたのだ。その一方、この傷心旅行にイスラム世界が含まれないのは、『ペルシア人の手紙』と比較して、オリエントの象徴的地位がさらに下落したことを示唆するだろう[24]。
広大な環大西洋的世界――大地震の起こったリスボンからアフリカのモロッコ、南米のスリナムまで――をいわばJ・G・バラードふうの残虐行為展覧会に変えてゆくヴォルテールの傑作『カンディード』(一七五九年)も含めて、『ペルシア人の手紙』より一世代後の小説は、陸でつながったオリエントの帝国から、海を隔てた「新世界」へとその地理的重心をシフトさせた。われわれは、このヨーロッパ文学における他者性の座標の変化に注意を払わねばならない。
7、初期グローバリゼーションと世界像の爆発
歴史家のC・A・ベイリは、国民国家の最盛期以前にあたる「一七世紀・一八世紀のグローバリゼーション」の性質を考えることの重要性を説いている。彼はこの時期の奴隷プランテーションのシステムや新世界の銀のような経済的ネットワークが、すでに世界を連結しつつあったことを強調し、それを「初期グローバリゼーション」と呼んだ[25]。私もこの名称を採用することにしよう。
初期グローバリゼーションを背景として、一八世紀は新世界とのコンタクトの体験を文学と思想に登録した。それはたんに地理的テーマを多様化しただけではなく、人間像や世界像そのものにも劇的な地殻変動を引き起こした。それを「思想の地震」と呼んでも言い過ぎではないだろう。一七五五年のリスボン大地震が、ヴォルテールに『カンディード』を書かせ、後にカントの地理学にも影響を与えたことはよく知られるが、認識論的なレベルでの地震はすでに『ペルシア人の手紙』の段階で予告されていた。
思想史家のダニエル・モルネは、ジョージ・アンソンやクック、ブーガンヴィルの世界周航記をむさぼるように消費した一八世紀フランスの知的傾向を、次のように要約している。
大作家の著作は、真面目なものであれふざけたものであれ、広大な世界を巡り歩くこのような趣味を反映していた。小説、コント、悲劇、市民劇、喜劇、オペラ・コミックには常に中近東、中国、エジプト、ペルー、インド趣味が見られるか、そのような装いをされていた。おそらくは、この異国趣味は作品では往々にして、意匠や変装にすぎなかったであろう。バビロンはパリであり、トルコの僧侶は我々の司祭だった。けれども、異国趣味が本格的であった場合も少なくなかった。パリの住民でも、フランス人でも、ヨーロッパ人でも、文明人でもないように努力がなされたのだ。[26]
グローバルな探検を背景として習慣の自明性を問い直すこと、それによってヨーロッパ人の限界を超えた新しい人間像を描き出すこと――この超‐人間性こそが「啓蒙の世紀」における核心的なテーマとなった。そこにはシリウス星人や土星人の登場するヴォルテールの哲学小説『ミクロメガス』のように、ほとんど『ガリヴァー旅行記』のSF版とでも言うべき諷刺性を発揮した作品もあれば、後のサドのリベルタン小説のように「自然」の名のもとに、人間の怪物性を驚くほどの高解像度で象ってみせた作品群もある。
小説という新しいメディアを活用しながら、人間的なものの臨界点にまで到ろうとするフィロゾーフたちの言論は、革新的な運動であり、それまでのフランスの旧態依然としたイデオロギーを破壊するものであった。ヴォルテールは『哲学書簡』(一七三四年)――フランスの遅れを批判しつつ、イギリスの先進的な政治や文化を称賛してベストセラーとなった――において「本を読む人間でも、その内訳は、小説を読む人間二十人にたいして、哲学を研究する人間はひとりという割合だ。ものを考える人間の数はきわめて少ないし、また、こうしたひとびとは世間を騒がそうとは思いもしない」と嘆いたが[27]、その彼自身が小説によって思想を広めたのである。上品で老成したフランス文化を敵視したドイツのゲーテは、まさにこの反フランス的フランス人である「哲学者」たちの活動に魅了されていた[28]。
むろん、彼らの「小説」は危険視されたが、哲学者はその流通の自由を何とか確保しようとした。特に、厳しい検閲をやめて、出版の自由を守るよう君主に強く訴えたのはディドロである。当時、非合法化された作品については海賊版が横行し、著者の立場はろくに守られなかった。その状況を憂慮したディドロは、フランスが率先して質の良い出版物を刊行する一方、海賊版を摘発して、著者の利益を守ることが社会の利益にもなると主張した。そもそも、彼の考えでは、既成観念に反する危険な書物――その例としてディドロは真っ先に『ペルシア人の手紙』を挙げている――ほど、法の網の目を軽々とくぐり抜けてしまうので、規制は意味をなさない。
閣下、国境にそってずっと兵士を配置なさり、姿を現わすあらゆる危険な書籍を押し戻すために銃剣を装備させてください。そうしたとしても、こうした書籍は、こういう表現をお許しいただきたいのですが、兵士の脚の間を通りぬけ、兵士の頭の上を飛びこえ、われわれに達するでありましょう。[29]
ディドロによれば、商品としての書籍にはいわば足が生えている。ゆえに、どれだけ厳重に国境を封鎖したとしても、それはウイルスのようにフランスに侵入し、国民のあいだに感染を広げるだろう……。ディドロはこの出版物の特性を、むしろ公共の利益に変えるような政治を望んだ。こうした発想は、小説という野生のジャンルの勃興と切り離せない。
8、一八世紀の首都ロンドン
このように、一八世紀の初期グローバリゼーションを背景として、小説の世界像や人間像にはブレイクスルーが生じた。その文化史上の意味を、われわれはもっと真剣に受け取るべきだろう。実際、世界文学研究に進化論的なアプローチを試みるとき、この世紀は特別な地位を占める。
例えば、世界文学論を牽引する批評家のフランコ・モレッティは、一八世紀および二〇世紀が「形式の多様性や語りの実験」において多様であったのに対して、一九世紀は「ふたつのポリフォニックな時代にはさまれたモノディクな時代である」とまとめている。小説の「変異」を爆発させた一八世紀的なポリフォニーは、一九世紀においてむしろ表現の多様性の収束に向かった[30]。ふつう小説の黄金時代と聞くと、バルザックやドストエフスキーら多くの巨匠を生み出した一九世紀が真っ先に想像される。しかし、モレッティによれば、この黄金時代はむしろ小説の書き方が一元化されていった時代なのであり、それを再び多元化しようと試みた実験の時代が二〇世紀ということになる。
もとより、このテーマはフランスだけ見ていても十分には理解できない。なぜなら、一八世紀小説の最大の生産地は何と言ってもイギリスであり、その主人公はしばしばグローバリストであったからである。
フランスの小説が戦闘的な哲学者たちに導かれたのに対して、イギリスの小説はどこか知的アマチュアリズムの自由さを感じさせる。出版業者(リチャードソン)、ジャーナリスト(デフォー)、牧師(スウィフト、スターン)、さらに後には多くの女性たち(ジェーン・オースティン、ブロンテ姉妹等)を含むイギリスの作家の多様な出自には、他国にはない社会的な厚みがあった。リチャードソンに熱狂したディドロ、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』を『エミール』で教育書として読み解いたルソーをはじめ、フランスの哲学者たちはまさにこのイギリスの知識人たちから、強烈なインパクトを受けた。サイードは知識=権力の社会的配置という観点から、英仏の違いをうまく説明している。
イギリスが、ヨーロッパのなかで競争相手もなく一人勝ちの状態で、小説という制度を創出し維持したことは、まったくの偶然ではない。フランスはすくなくとも十九世紀前半においては、小説よりももっと高度に発達した知的制度――アカデミー、大学、研究所、定期刊行物など――を誇り、アーノルド、カーライル、ミル、ジョージ・エリオットといった一群のイギリス人知識人をうらやましがらせることしきりであった。しかし、イギリス側のこの立ち遅れを補償するものとして、驚くべきことに、イギリス小説が、着実に発展し、しだいにゆるぎなき支配的地位を確保するにいたったのである。[31]
フランスほど緊密な知的集権化がされなかったからこそ、イギリス人は小説の野生を積極的に知的制度に組み込んだ――それがイギリス小説の「一人勝ち」の要因だとサイードは見なす。加えて、ここではイギリスにおける商業の強さも考慮に入れるべきだろう。例えば、ヴォルテールは『哲学書簡』で「イギリス国家の偉大さは、まさに商業によって形成された」と断定しながら、ユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒がお互いを対等に遇しあっているロンドンの王立取引所を、どんな裁判所よりも尊い場所だと見なした[32]。彼にとって、万物の商品化を留保なく推し進めるロンドンの取引所こそ、寛容の酵母と言うべき場であった。なぜなら、そこでは宗教も思想も等しく交換可能なものに変わるからである。
ロンドンという知的・商業的センターは、それ自体が初期グローバリゼーションの象徴である。パリが「一九世紀の首都」(ヴァルター・ベンヤミン)だとしたら、ロンドンは一八世紀の首都なのだ。そして、この「首都」の繁栄に根ざした小説家として、ダニエル・デフォーほど興味深い存在はいない。ヴォルテールやディドロが初期グローバリゼーションに触発された哲学者だとしたら、デフォーは初期グローバリゼーションの裏面を表現した小説家にほかならない。
9、『ロビンソン・クルーソー』――他者の中性化
二〇代の気鋭の著述家モンテスキューの『ペルシア人の手紙』が人気を博する二年前の一七一九年、六〇歳を前にしたデフォーの『ロビンソン・クルーソー』が刊行される。フランス人モンテスキューがアジアの古い帝国からヨーロッパを観察したのに対して、イギリス人デフォーはむしろ東方には目もくれず、アフリカ大陸とアメリカ大陸の沿岸部という環大西洋的世界を舞台に選んだ[33]。この場合、クルーソーがデフォーから見ると親世代、つまり純粋な一七世紀人であるのも注目に値する。老作家デフォーは、商業大国イギリスを成立させた「父」の肖像を描いたのである。
周知のように、この長編小説の筋書きは、ドイツ生まれの父をもつイギリスの中産階級出身のクルーソーが、船の難破の後でたった一人カリブの孤島に流れ着き、その地の開発にいそしみ、やがて野蛮人のフライデーと出会った後、イギリスに帰還するというものである。これが特にサイード以降の研究者によって、ヨーロッパの植民地主義の寓話として読まれてきたのは当然である。
もっとも、たいていの読者は、肝心のクルーソーの≪島≫がどこにあるかを気にかけないだろう。というのも、その島はいかなる国にも所属しない無歴史的な空間を装っているからである。ポストコロニアリズム批評の旗手ピーター・ヒュームが指摘するように、デフォーは確かに島がオリノコ河口にあり、そこからトリニダード島が見えると記しているものの、たいていの読者にとって「その島の位置はどうでもよいと思われている」。だからこそ、ヒュームはこの中性化・神話化された島を、歴史的な「カリブ海域に差し戻す」こと、つまり『ロビンソン・クルーソー』の植民地主義的前提を明らかにすることをめざした[34]。
むろん、それは必要な作業である。ただ、私の考えでは、むしろデフォーが島の地理を戦略的にあいまいにして、読者の関心をそこから巧妙に逸らしたことこそが重要である。結論から言えば『ロビンソン・クルーソー』を特徴づけるのは、いわば規則正しい足取りで他者の中性化に向かおうとする一種の思考実験である。われわれはその戦略を確認せねばならない。
そもそも、平凡な中産階級の息子であるクルーソーとはいかなる人物なのか。本書序章で紹介したように、クルーソーは勤勉な経済人(ホモエコノミクス)の例とされるが、そこからはみ出す部分も実は多々ある。というのも、彼を突き動かすのは冷静な「理性」ではなく、ふとした拍子に兆す「悪い心」だからである。クルーソーは自己を律することができないまま、たえず衝動的に行動するが、島に着くまでは何をやっても長続きしない。ギニア湾で貿易に従事した後、ブラジルでタバコとサトウキビのプランテーションを経営するものの、彼の経済的な熱意はすぐに消えてしまう。植民者である彼は、現地の労働者にはまったく目もくれないまま、たった一人で孤独と後悔にさいなまれる。
ぼくは自分の境遇を見つめてはとても深く後悔していた。ときどきあの隣人と話すほかに、会話する相手もない。仕事といえば、ただ自分ひとりで身体を動かすだけだった。まるで、自分のほかにはだれもいない、どこかの無人島に流された男のような生活だ。よくそうつぶやいたものだ。(五七頁/以下『ロビンソン・クルーソー』の引用は河出文庫版[武田将明訳]に拠り、頁数を記す)
ジャーナリストとしてのデフォーは、イギリスの強みが交易のネットワークにあることを強調した。しかし、ブラジルのクルーソーはむしろ企業家としては怠惰であり、実際プランテーションの事業を途中で投げ出しまう。そのことは興味深い逆説を生み出す――彼は確かにイギリス人からグローバリストへと着実に近づいてゆくが、それは彼をますます社交的なネットワークから切り離し、無人島の住人のような孤独な存在に変えてしまうのだ。つまり、他者とのコンタクトが増えるほど、かえってそのネットワークを切断したいという発作的な欲動は高められる。クルーソーを翻弄するその制御不可能な力を、デフォーは「悪い運命」(ill fate)と呼んでいた。
私は先ほど「ヨーロッパ文学史とは他者を探し求める歴史である」と記した。その歴史において、『ペルシア人の手紙』とほぼ同時期の『ロビンソン・クルーソー』は特別な意味をもつ。なぜなら、他者と接触したいという意志がピークに達した一八世紀のグローバリズムの時代において、デフォーの小説はむしろそのことへの懐疑を示しているからである。接続から切断へ――それがこの特異な小説のヴェクトルである。
10、レプリカとしての≪島≫
ここで注目に値するのは、この「悪い運命」が具体的な歴史からの撤退を促したこと、特にクルーソーの≪島≫を中性的・神話的な空間に変えたことである。このプロトコル(手順)にこそ、デフォーの高度な作家的技巧が認められるだろう。
クルーソーの人生には明白なパターンがある。もともと、中間階級の家に閉じ込められていたクルーソーは、そこから衝動的に脱出してギニア貿易商になるが、やがて海上でイスラム教徒の海賊に襲撃され、ムーア人(モーロ人)の捕虜としてサレ(モロッコの都市)に送られる。このイスラムとの接近・遭遇と監禁を経て、ブラジルの農園という擬似的な無人島を経営した後、そこからも脱出し、海難事故によって孤島にたどり着く――つまり、デフォーは物語の中心である島にクルーソーを送り込む前に、すでに三度も「監禁」と「脱出」の予行演習を重ねていた。彼の発見した未知の島は、実は先行する監獄的な島の「レプリカ」なのだ[35]。
さらに、フライデーも決してオリジナルな存在ではない。クルーソーはすでにムーア人のもとから脱出する際に、イスラム教徒の忠実な少年ジューリーの助けを借りており、その後孤島に流れ着いたときにはオウムのポルに人間の言葉を教え込む。このジューリーやポルがフライデーの雛形となっているのは明らかである。孤島のクルーソーは、いきなり未知の他者と遭遇するわけではない。彼が出会ったのはむしろ他者の諸要素のコピー、つまり他者の中性化されたレプリカである。
そもそも、ジューリーやポルに比べても、フライデーという名づけは手抜きである――クルーソーに命を救われたのが金曜日だから、その名前が付けられただけなのだ。むろんキリストが磔刑に処せられた金曜日という意味はあるとはいえ、このぞんざいな命名儀式が象徴するように、フライデーはあくまで他者のレプリカであり、そこからは威嚇的な他者性が除去されている。だが、だからこそフライデーの容貌は、他の新世界の「未開人」とは明らかに区別される。
髪は長く黒く、羊毛みたいに縮れてはいなかった。額はとても高く広がり、目はすごく生き生きして、凛々しい煌めきがあった。肌の色はあまり黒くはなく、褐色だった。でもブラジルやヴァージニア、その他アメリカの現地人みたいな、醜く黄色っぽく不快な褐色ではなかった。茶色っぽいオリーヴの明るい色で、見ていてとても気持ちいいなにかであった。(二八九頁)
クルーソーはフライデーに、黒人であることを自己否定するような美的容貌を認める――ここには黒いのに黒くないというパラドックスが巧妙に仕組まれている。要するに、フライデーは未開性を否定する未開人なのだ。これを反転させて言えば、クルーソーのほうは文明性を否定する文明人である――放蕩息子の彼はいつも自分の境遇に満足できず、すぐに「悪い運命」の力に感染し、理性を失って幻想に憑かれるのだから。クルーソーはフライデーに対して慈愛に満ちた父としてふるまうが、それが可能なのは、この両者がそもそもある種の「未開性」において相互浸透していたためである[36]。
ともあれ、クルーソーの≪島≫は中性化の終点に位置している。島にたどり着く前には、奴隷貿易を暗示する「ギニア」、ポルトガルの植民地である「ブラジル」、異教徒の海賊である「イスラム」という固有名がクルーソーの語りに入り込んでいたが、島に入ると(フライデーが出てくるまでは)それらの植民地主義的な記号は希薄になる。デフォーは地図上の対応物をほとんどもたない島のレプリカ、いわばVR空間のような島を作成し、クルーソーをその島の「王」に据えた。読者が島の所在地を気にしないのは、まさにこの仮想性のためである。
そして、この文明とも野蛮とも決められない中性的なVR空間では、抜き差しならない敵対性は打ち消される。クルーソーは不運なアクシデントに見舞われた遭難者であり、拡大の意図をもった侵略者ではない。ゆえに、彼がフライデーを暴力によってではなく、あくまで聖書の力で「回心」に導くことは重要である。デフォーは聖書の言葉を、クルーソーとフライデーの合一を促すアイテムとして使っていた。それは先行する粗暴な植民者たちとは、明白に異なる態度として描かれている。
現に、モンテスキューと同じく、デフォーも作中でしばしばスペインの植民地政策の暴虐ぶりを批判していた。クルーソーはスペインを念頭に置きながら「カトリック司祭の無慈悲なかぎ爪に捕らわれ、異端審問に引きずりこまれるくらいなら、野蛮人に引き渡されて生きたまま貪り食われるほうがましです」(三四九頁)とまで言っている。つまり、カニバリズムという野蛮の象徴よりも、文明の皮をかぶったカトリック原理主義のほうが、クルーソーの恐怖の対象なのである。そのうちに実際にスペイン人が現れるが、聖書の寛容の精神に立つクルーソー=王は、フライデーとスペイン人を平和的に共存させることに成功する。一見すると植民地主義的に見える『ロビンソン・クルーソー』は、むしろ暴力的な植民地主義への批判を含んでいた。
むろん、ポストコロニアリズム批評の観点からは、このような和解の演出そのものが、植民地主義を受け入れやすくさせる手の込んだ詐術ということになるだろう。それはそのとおりだが、デフォーが≪島≫を戦略的に中性化したこともやはり認めなければならない。そこは歴史的な意味の充満したトポス(場)ではなく、資本主義の帝国のはざまに口を開いたスペース(空白/空間/宇宙)として仕立てられた。だからこそ、その無のスペースは、国籍や宗教を超えたグローバルな和解劇の舞台になり得たのだ。
他者を探し求めるヨーロッパ小説史において、『ロビンソン・クルーソー』が特別な位置を占めるのは、以上の理由によってである。フランスの哲学者たちが「新世界」から新たな人間像を引き出そうとしたのに対して、デフォーはヴァーチャル・リアリティとしての島に他者のレプリカを集わせた。このプロトコルのおかげで、後世の人間たちは島の王クルーソーを非歴史的・神話的な「経済人」のモデルと見なせたのである。
11、諸帝国の時代から諸国家の時代へ
以上のように、一八世紀のフランスやイギリスでは新世界とのコンタクトが文字通りの世界文学の母胎となった。しかし、ここで重要なのは、この初期グローバリゼーションを背景とする世界像の爆発が、一九世紀以降は国民国家のスケールにあわせて規格化されたことである。政治学者のデイヴィッド・アーミテイジの言葉を借りれば、これは「諸帝国の世界から諸国家の世界への転回」を意味している[37]。
この見地から言えば、一八三〇年を一つの大きな分水嶺として捉えることができるだろう。フランスに即せば、それは「ブルジョワの王」であるルイ・フィリップが王政を打倒した七月革命の年である。それをきっかけに従来の土地貴族に代わって、フランスでは中間的なブルジョアが覇権を握ることになった。それとともに、ヨーロッパ各地のナショナリズムも刺激され、保守政治家メッテルニヒの主導した「ウィーン体制」(ヨーロッパの全体の協調を守ろうとするシステム)もひび割れ始めた。
グローバリズムからナショナリズムへの時代の変化を象徴するのが、まさにその一八三〇年に刊行されたフランスのスタンダールの『赤と黒』である。スタンダールはそこで、王政復古時代の退廃したフランス社会を背景として、ナポレオンに憧れる情熱的な青年ジュリアン・ソレルを主人公としたが、サイードが言うように、そこでは国外――とりわけ一八三〇年にフランスに植民地化されたアルジェリア――の状況が隠されている。ヨーロッパ規模の帝国を築こうとしたナポレオンの熱意は、ただ痕跡として残っているだけであり、ソレルの軌跡はもっぱらフランスに限定されている[38]。この点で、スタンダールは一九世紀のナショナリズムの時代に適応した小説家であった。
それでも、一八世紀のグローバリゼーションの意義が一九世紀においてすっかり失われたわけではない。C・A・ベイリはナショナリズムの体制が拡大するなかでも、初期グローバリゼーションの記憶は国際秩序のなかに依然として保持されていたと述べる。
一八一五年頃から、ヨーロッパの国家と西洋の植民地主義は、旧来の世界秩序に対して新しい様式の国際主義を押しつけ始めた。ますます国民国家は、グローバルなネットワークを支配していった。それは、あらゆる国際的ネットワークに対して、より厳格に境界が引かれた領土、言語、宗教的慣行の制度を押しつけた。だが、心に留めておかねばならないのは、旧来のグローバリゼーションの様式が、新しい国際秩序の水面下に根強く残っていたことである。[39]
このベイリの指摘はゲーテの「世界文学論」のもつ反時代的な性格を了解するのにも役立つだろう。ゲーテは一九世紀という国民国家の世紀にありながら、一八世紀のコスモポリタンな遺産、つまりボーダーレスな「旧来のグローバリゼーションの様式」の継承者としてふるまった。彼の世界文学論は未来的な構想に思えるが、その土壌はむしろ過去のヨーロッパにあり、『西東詩集』もそこから芽生えたのである。
私たちは往々にして、ナショナリズムからグローバリゼーションへという進歩主義的な物語を描きがちである。しかし、ベイリが言うように、一八世紀のグローバリゼーションが一九世紀のナショナリズムに先行したのだとしたら、話の順序は逆になる。現に、一九世紀の時勢に静かに抗ったゲーテは、急進化したフランス革命にも、ドイツの政治的なナショナリズムにも与しなかった。彼がヨーロッパ統一に邁進するフランス人のナポレオンを崇拝したり、国民国家の時代に逆行してヨーロッパ全体の「勢力均衡」をめざしたメッテルニヒに共鳴したりしたのも、一八世紀に軸足を置く世界市民的保守主義者としては、むしろ当然のふるまいである[40]。
そして、旧来のグローバリゼーションの様式に根ざすゲーテの「保守性」は、彼の政治的態度にいささか奇妙な性格を与えることにもなった。カール・シュミットが鋭く指摘したように、ドイツの敵であるナポレオンを称賛したゲーテは、他のドイツの教養人と同じく「現実の敵」が誰かを分かっていなかったように思える[41]。シュミットから見れば、世界市民ゲーテは友と敵のあいだの区別をまともにできていない。だが、この政治的センスのなさは、ゲーテがグローバリズムの時代とナショナリズムの時代の「あいだ」にいたことの帰結なのである。
では、一八世紀の遺産を引き継いだゲーテは「新世界」にどう向き合ったのだろうか? この厄介な問いは、しかし第五章に譲ろう。冒頭で予告した通り、われわれはここでそろそろヨーロッパ人の世界像から離れ、東アジアの文学環境に眼を転じることにしたい。
[1]E・W・サイード『文化と帝国主義』(第一巻、大橋洋一訳、みすず書房、一九九八年)一〇二頁。
[2]「西東詩集 注解と論考」『ゲーテ全集』(第一五巻、小栗浩訳、潮出版社、一九八一年)三一〇頁。
[3]同上、三二一頁。
[4]エドワード・W・サイード『オリエンタリズム』(上巻、今沢紀子訳、平凡社ライブラリー、一九九三年)三八二頁。
[5]マーティン・バナール『ブラック・アテナ』(片岡幸彦訳、新評論、二〇〇七年)。私にとって興味深い事例は、プラトン晩年の対話篇『法律』である。プラトンはそこで、すでにエジプトでは何千年もかけて国家の実験がやり尽くされたことを指摘し、それを前提に最善の政体を構想する。われわれはついソクラテスやプラトンを「古代人」と見なしてしまうが、彼ら自身はエジプト以来の長大な文明史の終端に立つ、いわば最もモダンなプランナーとして自己を位置づけていた。
[6]『ギリシア悲劇Ⅰ アイスキュロス』(ちくま文庫、一九八五年)八四頁。アイスキュロスの代表作「縛られたプロメテウス」でも、火を盗んでスキュティアの荒野に拘束されたプロメテウスは「エウロパの地」を去り「アジアの里」に向かうようにイオに告げる。アジアへの進出を力強く語ったアイスキュロスの劇には、ヨーロッパ文学の越境性が先取りされていた。
[7]サイード『オリエンタリズム』五八頁。なお、サイードはなぜか無視しているが、ペルシア(胡)が中国や日本にまで恩恵をもたらした文明の回廊であったことは言うまでもない。西洋にとってのペルシアしか問題にしないサイードの偏屈な態度は、それ自体が西洋中心主義を再生産していないだろうか。
[8]もう一人、トルコと関係する知識人としては、コス島生まれの医者ヒポクラテスがいる。ヒポクラテスを象徴とする医師団は、小アジアの植民都市にも巡行していたため、彼らの著作には異郷の風土や住民の健康状態、その習俗についての詳しい記述がある。諸文化のコンタクト・ゾーンを遍歴したヒポクラテスたちは、いわば最古の人類学者と呼べるのではないか。さらに、このヒポクラテスの名前を冠した後世の架空の書簡体小説(いわゆるヒポクラテス・ロマン)は「笑う人」と呼ばれたデモクリトスを事実上の主役とし、ミハイル・バフチンによってヨーロッパ小説の先行例とされた。詳しくは拙著『感染症としての文学と哲学』(光文社新書、二〇二二年)参照。
[9]『ギルガメシュ叙事詩』(月本昭男訳、岩波書店、一九九六年)における月本の解説参照。
[10]サイード『オリエンタリズム』一七六頁。
[11]ドニ・ド・ルージュモン『愛について』(上巻、鈴木健郎+川村克己訳、平凡社ライブラリー、一九九三年)一三九頁以下、一九〇頁。およびアンリ・ダヴァンソン『トゥルバドゥール』(新倉俊一訳、筑摩書房、一九七二年)一六八頁以下。
[12]カルロス・フエンテス『セルバンテスまたは読みの批判』(水声社、牛島信明訳、一九八二年)四二頁以下。この政治的なカトリック化によって、スペインでは厳しい異端審問の嵐が吹き荒れることになる。ドストエフスキーはまさにこの時期のスペインのセビーリャを舞台にして、『カラマーゾフの兄弟』のイワンを作者とする「大審問官」の説話を記した。
[13]ジャン・カナヴァジオ『セルバンテス』二二五頁。
[14]レヴィ゠ストロースは『神話と意味』(大橋保夫訳、みすず書房、一九九六年)のなかで、一七世紀に神話的思考が退潮し、その代わりに小説が勃興したと述べている。この衰えた神話の機能を代替したのが、一七世紀のフレスコバルディからバッハを経て一九世紀のヴァーグナーに到る音楽であった(六四頁)。これはセルバンテス以降の小説が何を犠牲にしたかを照射する。
なお、『ドン・キホーテ』の作者問題そのものを巧妙に小説に仕立てたのは二〇世紀のボルヘスである。彼の「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」(『伝奇集』所収)の主人公は、セルバンテスに徹底して同一化し、『ドン・キホーテ』の字句にそのまま重ね書きするような分身的な作品を書こうとする。『ドン・キホーテ』の複雑なアフィリエーションの知恵の輪に、ボルヘスはさらに架空の鎖を加えたのである。
[15]牛島信明『反゠ドン・キホーテ論』(弘文堂、一九八九年)五八頁以下。
[16]フェルナン・ブローデル『地中海』(第五巻、浜名優美訳、藤原書店、一九九五年)八九-九〇頁。ブローデルはここで、フェリペ二世がマドリードから海沿いのリスボンに拠点を移したことを、地中海から大西洋にスペインの関心が移ったことの象徴的事件と見なしている。
[17]ツヴェタン・トドロフ『われわれと他者』(小野潮+江口修訳、法政大学出版局、二〇〇一年)五五九、五六七頁。
[18]詳しくは、浅田彰「ローとモンテスキュー」および小西嘉幸「崩壊譚」樋口謹一編『モンテスキュー研究』(白水社、一九八四年)所収参照。
[19]阪上孝「モンテスキューとデカダンス」同上、二六、四三頁。Catherine Volpilhac-Auger, Montesquieu: Let There Be Enlightenment, tr. by, Philip Stewart, Cambridge University Press, 2023, p.3. ジャン・スタロバンスキーが『モンテスキュー』で、『法の精神』をボルドーの赤ワインに、『ペルシア人の手紙』を甘味のあるアルコールの強い白ワインになぞらえているのも面白い(現在もモンテスキューの生家はワイナリーを営んでいる)。
[20]モンテスキュー『法の精神』(井上堯裕訳、中公クラシックス、二〇一六年)一一〇頁。
[21]なお、モンテスキューから一世紀以上後、マルクスはロシア専制の起源を探る『一八世紀の秘密外交史』(石井知章+福本勝清編訳、白水社、二〇二三年)を著したが、そこでもやはりピョートルがロシアを海洋国家に作り替えたことが重視されている。マルクスは資本主義の揚棄をめざすだけでは、いずれロシア的な権威主義の罠にはまり、人類の解放に失敗することを予感していた――皮肉なことに、それはマルクスの思想を横領したソ連のスターリニズムにおいて証明されるのだが。社会を「腐敗」させる専制政治への関心において、マルクスとモンテスキューには共通性がある。
[22]サイード『オリエンタリズム』一七八頁。
[23]中川久定『啓蒙の世紀の光のもとで』(岩波書店、一九九四年)八〇頁。なお、世界周航を果たした実在の探検家ブーガンヴィルは、タヒチ島の青年アオトゥルをフランスに連れて帰り、自ら『世界周航記』(一七七一年)も記したが、その架空の「補遺」としてでっちあげられたのが『ブーガンヴィル航海記補遺』である。つまり、ディドロはブーガンヴィルの経験を勝手に盗み出し、それをデフォルメして文化人類学的な思想書に仕上げた。この奇妙な成り行きにも、自己を他者に盗ませながら語るディドロの特徴が認められる(前章参照)。
[24]ルソー『新エロイーズ』(第三巻、安土正夫訳、岩波文庫、一九六一年)三三頁以下。ドニ・ド・ルージュモンは『新エロイーズ』について、一二世紀のトゥルバドゥール由来の「幸福な憂愁」をベースにしながら、そこに「洗練された敬虔主義」を浸透させた小説と見なす。(前掲書下巻、八七頁)。だとしたら、アラビアの恋愛文学は本来、ルソーの先祖でもあったと言わねばならない。
[25] C・A・ベイリ『近代世界の誕生』(上巻、平田雅博他訳、名古屋大学出版会、二〇一八年)五三頁以下。
[26]ダニエル・モルネ『十八世紀フランス思想』(市川慎一+遠藤真人訳、大修館書店、一九九〇年)九三頁。
[27]ヴォルテール『哲学書簡』(斉藤悦則訳、光文社古典新訳文庫、二〇一七年)一二八頁。
[28]坂井栄八郎『ゲーテとその時代』(朝日出版社、一九九六年)六七頁。
[29]「出版業についての歴史的・政治的書簡」(原好男訳)『ディドロ著作集』(第三巻、法政大学出版局、一九八九年)一五五頁。もともと、出版事業を思想の武器としたのは、ペトラルカやエラスムスをはじめユマニストたちである。その結果、小型化した書物はモバイルな通信装置になり、旧来のゴシック体に代わるローマン体(ユマニスト書体)という新たなフォントも出現した。この出版=思想の伝統は一六世紀末に途切れたが、一八世紀のディドロやヴォルテールらはそれを復活させた。リュシアン・フェーヴル+アンリ゠ジャン・マルタン『書物の出現』(上巻、関根素子他訳、ちくま学芸文庫、一九九八年)第三章および第五章参照。
[30]フランコ・モレッティ『ドラキュラ・ホームズ・ジョイス』(植松みどり他訳、新評論、一九九二年)三三八頁以下。
[31]サイード『文化と帝国主義』一四六頁。
[32]ヴォルテール前掲書、五七頁。ただ、ヴォルテールの取引市場モデルは、寛容の可能性を広げると同時に、あらゆる文化を均質化する危険性も秘めている。この点については、カルロ・ギンズブルグ『糸と痕跡』(上村忠男訳、みすず書房、二〇〇八年)七四頁以下の記述が含蓄に富む。
[33]ただし、デフォーが初めて公刊したテクスト(今は失われた)は、オスマン帝国による一六八三年のウィーン包囲を批判したものだと言われている。その意味で、攻撃的で「野蛮」な他者への関心はデフォーにおいて一貫していた。Srinivas Aravamudan, “Defoe, commerce, and empire” in The Cambridge Companion to Daniel Defoe, ed.by John Richetti, Cambridge University Press, 2008, p.62. ただ、重要なのは、他者の座標が変わったことである。
[34]ピーター・ヒューム『征服の修辞学』(岩尾龍太郎他訳、法政大学出版局、一九九五年)二四八頁。
[35]Michael Seidel, “Robinson Crusoe”, in The Cambridge Companion to Daniel Defoe, p.190ff.
[36]Dennis Todd, Defoe’s America, Cambridge University Press, 2010, p.36ff.
[37]デイヴィッド・アーミテイジ『思想のグローバル・ヒストリー』(平田雅博他訳、法政大学出版局、二〇一五年)二七五頁。
[38]サイード『文化と帝国主義』一九三頁。
[39]ベイリ前掲書、三一四頁。
[40]坂井前掲書、二二九頁以下。一つの国家が存在しなかったドイツにおいては「祖国愛」は国家よりも小さい諸邦(ヴァイマル等)に向けられていたため、かえって世界市民的感情とも結びつきやすかったと坂井は説明している(二三七頁以下)。つまり、ネーションが弱体であったからこそ、ミクロな地方とマクロな世界が比較的容易に結びついたのだ。さらに、このコスモポリタンな保守主義は、ゲーテの次世代のフリードリヒ・シュレーゲルにも見出せる。彼はヨーロッパの超国家的理念を支える「真の帝政」の復活を願い、オーストリア・ハプスブルク家にこの「保守主義革命」の夢を託した。エルンスト・ベーラー『Fr. シュレーゲル』(安田一郎訳、理想社、一九七四年)一二三頁。
[41]カール・シュミット『パルチザンの理論』(新田邦夫訳、ちくま学芸文庫、一九九五年)二一頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年6月7日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年7月6日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。