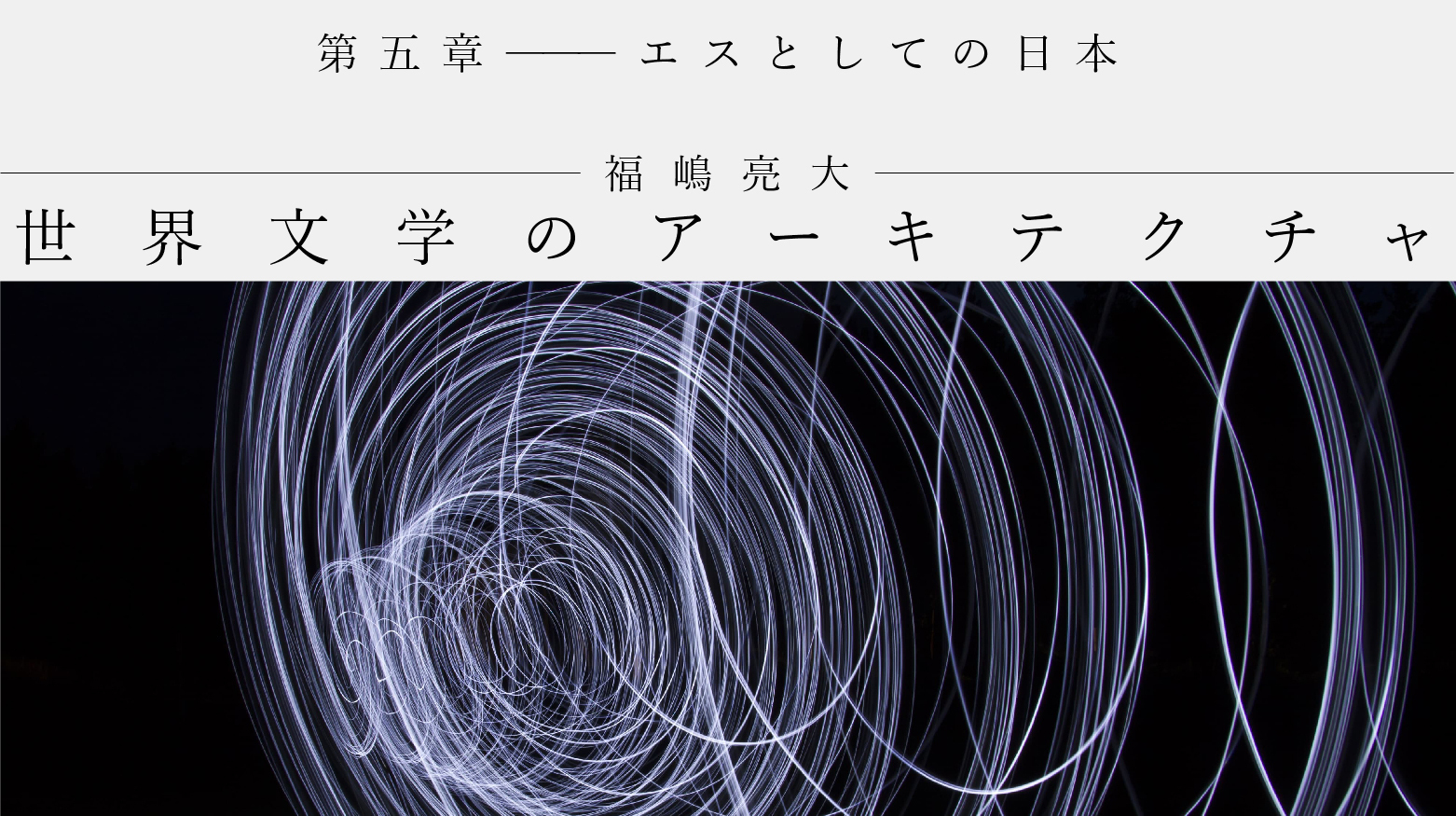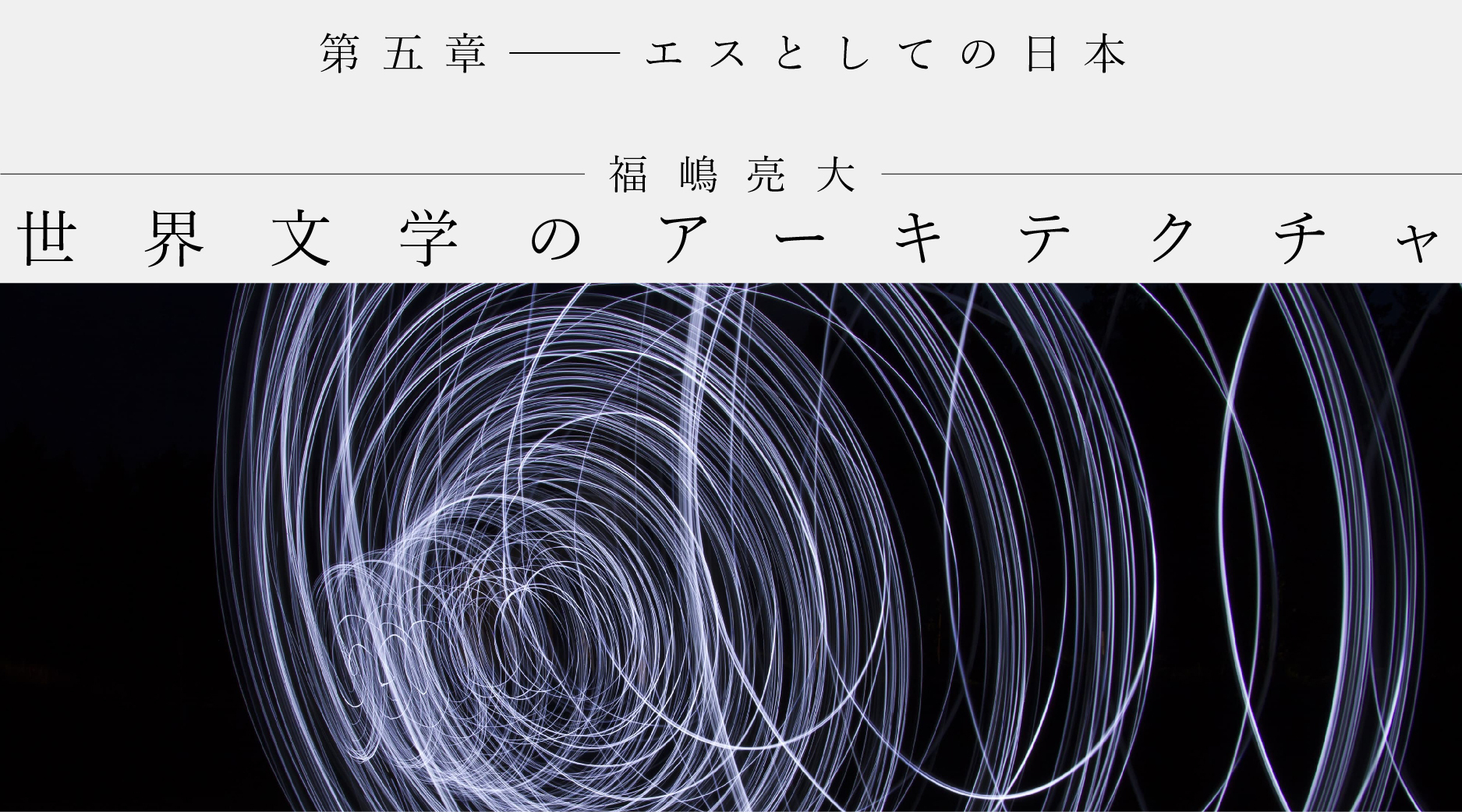批評家・福嶋亮大さんが「世界文学」としての小説とそれを取り巻くコミュニケーション環境を分析していく連載「世界文学のアーキテクチャ」。
今回は日本文学が受けた中国小説からの影響について分析します。あくまでも傍流的立ち位置だったという「小説」が隣国の文化に何をもたらしたのか、18世紀に国学を興した本居宣長の研究から明らかにします。
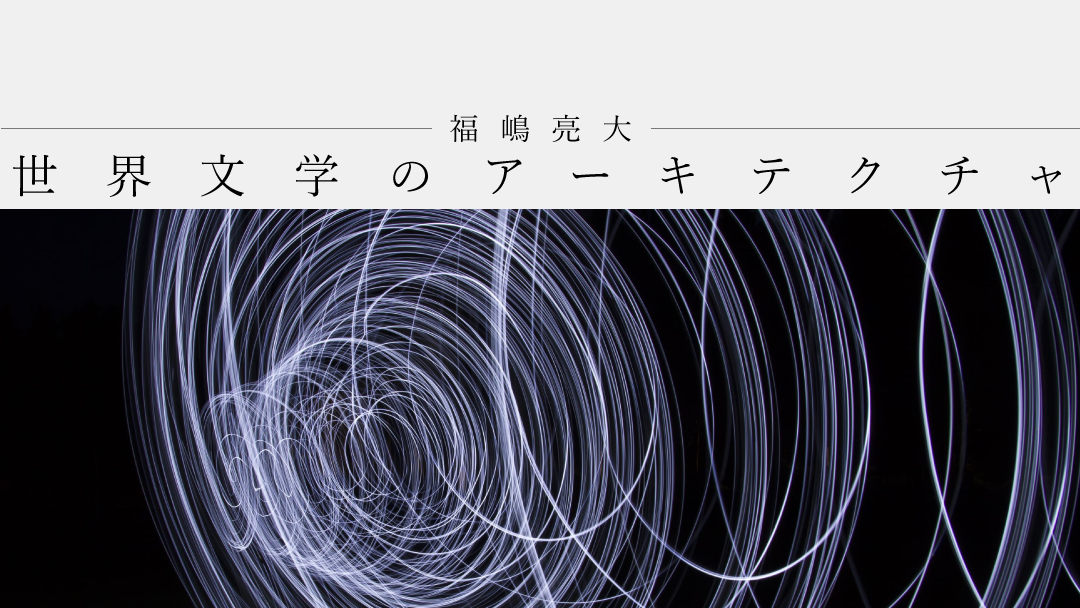
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、エスとしての日本/小説
文芸批評家のテリー・イーグルトンはアイルランドをイギリスの無意識(エス)と見なす立場から、エミリ・ブロンテの『嵐が丘』(一八四七年)のヒースクリフが、わけのわからない言葉を話す薄汚れた黒髪の孤児として登場することに注目した。彼の考えでは、リヴァプールの街角で飢えていたところを拾われたヒースクリフは、一八四〇年代後半に未曽有のジャガイモ飢饉に襲われたアイルランドの難民のアレゴリーである。イーグルトンはこの黒々とした難民的存在のもつ不気味さに、イギリスにとって目を背けたいエスの露呈を認める。
われわれは、エスの領域にあっては自我にとって許容しがたい行為に耽る。それと同じように、十九世紀のアイルランドという場所にあっては、イギリス人たちは、自らの意識的な信念の否定あるいは逆転という形で、自分自身の諸原則を明るみに出してしまうことを余儀なくされたのである。[1]
この見解を応用して言えば、日本にも中国のエスとしての一面がある。つまり、中国から見ると、日本は(イギリス人にとってのヒースクリフのように)意味のわからない言葉を話しながら「許容しがたい行為」に耽り、ついには道徳的な信念を「逆転」させるミステリアスな存在ではなかったか。しかも、一九世紀後半以降の日本は急速に軍事化し、中国に戦争を仕掛けるまでに到ったのだから、その存在はなおさら不気味に映るに違いない。
現代の日本研究者である李永晶は、まさにこの不気味さを「変態」と言い表した。それは性的な「変態」を指すとともに、日本が中国から文化的影響を受けつつ、思いがけない方向に自らを「変異」させてきたことも意味する。中国のコピー(分身)である日本は、ときにオリジナルを凌駕するような文化的変異株を作成した。李によれば、中国人はこの捉えどころのない日本に対して、潜在的な「情結」(コンプレックス)を抱いてきた[2]。私なりに言い換えれば、この固着した感情は、日本が中国の意識を脅かす「エス」であることと等しい。
その一方、中国の内部にも私生児的なサブカルチャーがあったことも見逃せない。それはほかならぬ「小説」である。『水滸伝』にせよ『金瓶梅』にせよ『紅楼夢』にせよ、そこには儒教的な規範意識によって抑圧されたもの(カーニヴァル性、性愛、少女性……)が回帰している。前章で述べたように、李卓吾をシンボルとする明末以降の批評家は、中国のオーソドックスな文化の「変態」であるサブカルチャー=小説に積極的な価値を認めた。
のみならず、このエスとしての中国小説は、同じくエスとしての日本にも多面的な影響を及ぼした。中国小説と早期に接触した思想家として、ここで空海の名を挙げておこう。空海が『聾瞽指帰』(七九七年)の序文で、唐の張文成(張鷟)の小説『遊仙窟』――運命の行き詰まりを感じていた著者が、仙女のいる家に迷い込み、詩の巧みな応酬によって彼女の心をつかんで一夜の性的な交歓にふけるエロティックな小説――に言及していたことは興味深い。
中国に張文成という人がいて、疲れやすめの書物を著した。その言葉は美しい玉をつらぬくようで、その筆力は鸞鳥や鳳凰を高く飛ばすようである。ただし残念ながら、むやみに淫らなことを書きちらして、まったく優雅な言葉[雅詞]がない。その書物にむかって紙面を広げると、魯の賢者柳下恵も嘆きをおこし、文章に注目して字句を味わおうとすれば僧侶も動揺する。(原文は漢文)[3]
『聾瞽指帰』とは空海の思想書『三教指帰』――中国の「賦」をモデルとする対話体の作品であり、儒教・仏教・道教の三教を競わせた末に、仏教の優位性を示す――の原型になったテクストだが、『三教指帰』のヴァージョンでは序文が書き直され、この引用部は削除された。それだけに、この小説論には、どこか過剰で不穏なものが感じられる。空海は確かに『遊仙窟』の「淫らさ」は文章の標準にならないと見なすが、そのような不埒な小説=サブカルチャーが僧侶の心を動揺させるだけの魔力をもつことも、はっきり認めている。小説を批判しつつその幻惑的な美しさにも言及するという両義性が、この序文には忍び込んでいる。
なぜ空海は宗教者でありながら、自身の信条とは無関係のフィクションにわざわざ言及したのか。仏教学者の阿部龍一が指摘するように、それは恐らく、若き空海がエリート的な立身出世コースからドロップアウトした私度僧、つまり律令体制のアウトサイダーであったことと関わるだろう[4]。その濃厚なエロスによって信仰心をかき乱す『遊仙窟』は、あくまで非公式的なサブカルチャーにすぎない。しかし、日本の律令国家を支える政治的・宗教的な言説に飽き足らなかった空海には、そのような異国のサブカルチャーに感応する余地が大いにあった。「文」(エクリチュール)に対する空海の態度は、当時の日本の誰とも似ていない。彼は『三教指帰』のような護教論的著作のみならず、中国の詩学を体系化した『文鏡秘府論』も残しているが、これも後にも先にもほとんど類例のない仕事であった。
象徴的なことに、遣唐使によって持ち帰られた『遊仙窟』は、中国では早くに散逸し、日本でしか現存していない(それを再発見した中国人は『中国小説史略』を書いた魯迅である)。しかも、日本人はこの舶来の『遊仙窟』を神聖視し、その影響は『万葉集』や『源氏物語』のような日本文学の中枢にまで及んだ。中国では抑圧されたエス的なサブカルチャーが、かえって日本では文化の表面に堂々と現れ、空海や紫式部のような優れた知識人をも魅了する――ここには日本の文化体験の原型があると言えるだろう。
2、本居宣長と一八世紀の文化的パラダイム
もとより、このようなエス的なものの表面化は日本に限らず、中国文明の「辺境」の特徴でもある。例えば、二〇世紀後半以降の香港文学には、金庸の武侠小説から、張愛玲のような女性作家の作品、さらに倪匡のSF小説に到るまで、中国文学の主流から排除された異端的要素が満ちている。香港とは「中国の伝統文化の明暗を反転させた自画像」(金文京)なのだ[5]。香港文学は確かに中国の地方文学だが、その辺境性によって中国をあべこべの姿で映し出してきたという意味では、反・中国的な「変態」の文学でもあった。
日本にせよ香港にせよ、しばしば中国大陸では傍流のサブカルチャーこそが主流になり、中国的な信念を反転させた。加えて、日本において特徴的なのは、中国のオーソドックスな文化に対する否定や逆転が、強固な思想にまで仕上げられたことである。それを成し遂げたのが、一七三〇年に松坂で生まれた国学者の本居宣長である。
周知のように、宣長は中国の道徳的な「からごころ」に対して、日本固有の「やまとだましい」や「もののあはれ」の独立性を訴えた。一口に言えば、それは人間の弱さに積極的な価値を与えるものである。例えば、宣長によれば、中国の聖人とは違って、日本の神は平気で不埒なことをする。しかし、それは決して恥ではなく、むしろ日本が中国とは異なり、厳格なルールを作らずともうまく治まっていたことの証明である。今の学者――特に荻生徂徠が想定されている――は秩序回復のために、制度の創設をしきりに訴えるが、それは中国かぶれの悪弊にすぎない(『直毘霊』等参照)。
この「もののあはれ」を言い表すメディアが「歌」である。宣長は初期の歌論『排蘆小船』の冒頭で、歌は政治の助けでも修身のためにでもなく、あくまで「心に思ふこと」を言うものだと断言した。歌とは実利的な目的に関係なく、ただ「人情」をすなおに伝えるものである。しかも、人情とは「はかなく児女のよう」なものであり「男らしく正しくきっとしたること」の対極に位置する。宣長は男性中心的な武士の価値観からすれば未成熟に見える「児女」の感受性こそを、歌にとってより根源的なものと見なした[6]。
ただ、繊細な弱音で奏でられる「もののあはれ」に耳を傾けるには、言葉に接する態度そのものを変更せねばならない。宣長によれば、古代のゆかしい言葉遣いは、近代になってひどく俗化してしまい、すなおな心を表現することが難しくなった。ゆえに、彼は古代の雅言を保存している「歌」こそが、この不用意な近代化へのデトックスになると見なす[7]。この宣長の復古思想は、比喩的に言えば、よく鳴り響くモダン楽器が打ち消してしまうニュアンスや響きを、作曲家の生きた当時のピリオド楽器で回復しようとする近年の古楽運動に似ている。
このような宣長の考え方は、近世社会のコンテクストから孤立したものではなかった。むろん、彼はあくまで『古事記』や『源氏物語』を研究する古典学者であり、同時代の小説を本格的な主題にはしなかったが、その美学は同時代の市民文学と共鳴するところが多い。例えば、当時の時代物の浄瑠璃には「もののあはれを知る」という言葉がしきりに用いられ、一九世紀前半の流行作家である為永春水も、まさに「あはれ」という同じキーワードを用いた。若き宣長自身、京都での遊学中に、人形浄瑠璃や歌舞伎に通いつめていたことが知られている[8]。宣長の古典研究は、繊細なセンティメンタリズムを評価する同時代の芸能と連動していた。
さらに、中国に眼を向けると、宣長がライフワークの『古事記伝』に取り組んだ時期に、曹雪芹が同じくライフワークの『紅楼夢』を書き継いでいたのは、興味深い符合である。『紅楼夢』の主人公である賈宝玉には、まさに男性中心主義的な「からごころ」への強い反発がある。口中に美しい玉を含んで誕生した賈宝玉は「女の子はみな水でできた身体、男はどれも泥でできた身体。女の子になら会っただけでわたしは気がはればれする。だのに男に会うと臭くて胸がむかつくのだ」(第二回)と大胆に言ってのける。この男性嫌いの中性的な主人公にとっては、『水滸伝』ふうのホモソーシャルな絆でも、『金瓶梅』ふうの大人の生々しい性愛でもなく、清潔かつ繊細な少女的共鳴こそが「真」なのである。ここには、宣長によく似た成熟忌避のモチーフがはっきり現れていた。
男性的できりっとした「からごころ」を偽りとし、たとえ未完成・未成熟であったとしても、ありのままの心情を肯定する宣長の美学は、「真」や「情」を高く評価する近世東アジアのパラダイムに属している。それは文学に根ざしながら、人間性の理解そのものを変えようとする思想運動であった。そもそも、宣長が若いころから近世中国の批評にも目を通していたことは、初期の『排蘆小船』で李卓吾に言及したことからも分かる[9]。日本の知的文脈だけで見ていると、宣長の画期性をつかむことはできない。
宣長自身、中国の書物を読むように推奨していた。彼の考えでは、中国人は自国の文献しか読まないエゴイストであり、西洋の学問状況も知らず、そのせいで知的停滞に陥っている(『玉勝間』七の巻)。逆に、≪外≫を知る学問的利点を弁えていた宣長は、あくまで中国との比較によって、日本の特異さを引き出そうとした。その結果、宣長の美学はかえって、李卓吾をシンボルとする中国の先鋭な小説批評と共振したのである。それは中国の旧来のオーソドックスな文化を食い破る、エス的なものどうしの共鳴現象と言い換えてもよい。
3、「大きな物語」への懐疑と言語論的転回
このように、近世の東アジア思想には、文化の本流から外れた「エス」の発見を促す機運があった。ここで改めて思想史のコンテクストを俯瞰しておきたい。
そもそも、一七世紀以降の東アジア思想を特徴づけるのは、その「反理学」の潮流である。宋以降に確立された理学(朱子学)は、世界の根本原理を「理」および「気」の二元論に求め、そこから森羅万象を合理的に説明しようとするメタナラティヴ(大きな物語)であった。それ以前の儒教は、もっぱら形而下の実践のなかに道徳を求めたが、理学はそこに形而上学的・宇宙論的な基礎を与えた。しかし、この思弁的な哲学では説明や対処の難しいことが生じたとき、近世の東アジアではさまざまな反理学的な構想が浮上したのである[10]。
例えば、日本の荻生徂徠は理の限界を「制度」で補うことをめざし、近代的な政治学への道を開きつつ、古文辞学派のリーダーとして中国古典の思想や文学を原文のリズムで読み解くことを試みた。この「中国化」した徂徠の制度論に反発し、より自然生成的な「神の道」を復権させたのが本居宣長である。かたや、中国では明末に陽明学の系譜を継ぐサブカルチャーとしての「小説」が勃興し、形而上学的な「理」よりも、内なる「心」や「情」に真正性を認める文芸批評家たちが現れた。さらに、清に入って、抽象的な「哲学」(理学)から実証的な「文献学」(考証学)への転回が起こったのも、反理学のヴァリエーションの一つである。
特に、一七世紀以降に台頭したいわゆる「清朝考証学」の担い手には、江南地方の商人の出身者が目立った[11]。それは政治の実務や立身出世とは一定の距離を置いて、実証的な学問を自律させようとする在野の運動である。空理空論に陥った哲学では、明の滅亡を食い止められなかったという苦い認識が、その追い風となった。ここで重要なのは、この反哲学としての文献学の運動が、テクスト=言語への接近を促したことである。理学というメタナラティヴへの懐疑は、一種の「言語論的転回」へと到った。
ゆえに、宣長があくまで言語に密着した在野の研究者として、人間の「情」を文芸の中心に据えたことは、日本に限らず一八世紀東アジアを特徴づける現象であった。「理」に代わって「情」や「言」にフォーカスする反哲学の構想は、宣長の文献学において鮮明なコンセプトに仕上げられた。ちょうどピリオド楽器がバッハやモーツァルト等の演奏を変えたように、宣長の研究も『古事記』や『源氏物語』の音色を根本的に変化させた。しかも、幸運なことに、宣長が学者人生を送るうちに、さまざまな書物が格段に入手しやすくなっていった(『玉勝間』二の巻)。このテクストへのアクセシビリティの上昇を利用して、彼は自らを文献学者としての思想家に育てたのである。
もとより、小説にせよ批評にせよ文献学にせよ、それらは言語への鋭いセンスなしにはあり得ない。近世の前衛小説『水滸伝』を批評する金聖嘆も、日本固有の思想を蔵した古代文学として『古事記』を解読する本居宣長も、言語こそを最も確実な現実と見なす思想家=批評家であった。彼らはともに真実の人間性に近づこうとしたが、そのプロジェクトは抽象的な思弁ではなく、あくまでテクストの具体的な研究によって達成されるべきものであった。
4、「呪われた部分」への潜行――上田秋成
この近世の言語論的転回は、日本の小説史にも広範な作用を及ぼしている。興味深いことに、真に人間らしい感情をテクストから探り当てようとする文献学の戦略は、日本の近代小説のプロトタイプと呼ぶべき「読本」(大衆的な草双紙とは異なる、より高度な文学的技巧を駆使した物語作品)とも交差した。特に、一八世紀を代表する読本作家の上田秋成は、文献学・書誌学に取り組んだ名うての学者であり、宣長の学問上のライヴァルでもあった。
代表作の『雨月物語』(一七七六年)をはじめとする秋成の読本の中枢には、不気味な廃墟や陋屋がある。そこでは時間はリニアに進まない。うっかり廃墟に迷い込んだ主人公は、とっくに滅んだはずの死者の霊にとりつかれ、粘りつく情念の渦に巻き込まれる。『雨月物語』の世界ではミステリアスな悪霊こそが時空の支配者となり、生者はその操り人形に変えられてしまう。
しかも、この生死を反転させる廃墟を象るのに、秋成は先行する日本の『源氏物語』や中国小説のテクストを効果的に用いた。なかでも、『雨月物語』に収録された名高い怪談「浅茅が宿」や「蛇性の淫」は、いずれも近世中国の小説集――瞿佑の『剪灯新話』や馮夢龍の『警世通言』――がアイディアの源泉になっている。秋成は文献学者らしく、中国のテクストを日本のテクストにいわば「翻訳」しつつ、それを和文脈ならではの美文に仕上げた。しかも、その洗練された文体は、たんに小綺麗な世界ではなく、むしろおぞましい悪霊や不気味な廃墟を描くためにこそ用いられたのである。
秋成が悪霊や廃墟にアプローチしたのは、日本の根底にある「呪われた部分」――現存の社会秩序を揺るがす過剰なエネルギーの塊――を露出させるというバタイユ的戦略として理解できるだろう。どのような社会にも一種の呪いがかかっており、暗黙のうちに周縁に排除されたものがある。秋成にとって、物語はこのエス的なものに近づく手段であった。『雨月物語』巻頭の「白峰」で言えば、讃岐に配流された恨みを西行に長々と語る崇徳院の亡霊が、まさにエス的な「呪われた部分」として現れる。秋成はこの恐るべき呪いの力を出現させるのに、中国小説のテクニックを巧みに利用した。
さらに、秋成晩年の一八〇八年刊行の『春雨物語』、特にその最後の一編である「樊噲」になると、中国小説のシミュレーションは『雨月物語』以上にはっきりしたものになった。この鮮烈な印象を与えるピカレスク・ロマンでは、快足を誇る大蔵が、ふとしたはずみに殺人を犯してしまった後に「樊噲」(漢の劉邦に仕えた豪傑)を名乗る盗賊となって、日本各地を遍歴する。しかも、その悪行を仲間とともに戦術的に実行するシーンに、秋成はまるで『ミッション:インポッシブル』のような精彩に富むイメージを与えた。
日本を陽気に駆け抜けてゆくアウトサイダー大蔵=樊噲の姿には、明らかに『水滸伝』のカーニヴァル的想像力が引き写されている。彼は酒食を楽しみ、無心に笛を吹き、ときに間抜けな失敗をしでかしたあげく、ついには仏道への「回心」を果たすが、それは『水滸伝』の魯智深や武松を模したものである。荒くれの好漢である魯智深が、いかなる知識人も及ばないほどに純真な人間であり、だからこそ死の前に悟達したように、大蔵=樊噲もさまざまな荒唐無稽な犯罪を経て、やがてその心の純粋さに目覚めてゆく――この回心のドラマには、虚構性によって真実性に近づくという近世的な思想が投影されていたと言えるだろう(前章参照)。
ここから言えるのは、秋成が宣長と同じく、近世東アジアの思想的なパラダイムに属していたことである。彼らはともに、鋭い言語的なセンスを備えた文学者として、人間の「真」の姿に迫ろうとした。ただ、宣長がいわば古楽奏者のように、古代のはかなく繊細な歌=人情を復元したとすれば、秋成はいわばモダン楽器(中国の小説)とピリオド楽器(日本の物語)の利点を組み合わせつつ、市民文化を揺るがす「呪われた部分」への潜行を企てた。それは不穏な一九世紀の到来を予告するものでもあっただろう。
5、中国の文学的知能の相続――曲亭馬琴
繰り返せば、中国小説には文化のエスに潜り込み、その原則を明らかにするという精神分析的な性格があった。特に『水滸伝』は、カーニヴァル的な沸騰状態において規範を解体し、人間たちの秘められた欲望をリリースする。中国小説の変異株(変態)である秋成の物語にも、それに近いことが言えるだろう。そこでは悪霊や悪漢を主人公として、エス的な「呪われた部分」へのアクセスがしきりに試みられていた。
この秋成の手法を別のやり方で引き継いだのが、一七六七年に生まれ、黒船来航を前に亡くなった曲亭馬琴である。日本で最初に商業作家として生計を立て、実に半世紀にわたって第一線で書き続けた馬琴は、明治期を含めても一九世紀日本の最大の小説家と言えるだろう。一八一四年に初輯が刊行され、一八四二年に完結した『南総里見八犬伝』は、彼のマラソン・ランナーのような作家人生を象徴する大作である。
しかも、その汲めども尽きない旺盛な語りの力は、中国由来の小説批評への強い関心と切り離せなかった。馬琴は秋成と同じように、先進的な中国小説といわば「アフィリエーション」(養子縁組)の関係を結んだ。しかも、洗練された美文家であった秋成とは違って、馬琴は脱線を恐れず、テクストにさまざまな学問的知見や批評を盛り込んだ。特に、その小説論は同時代の誰よりも卓越している。彼は『八犬伝』の作家であるだけではなく、日本の「小説批評家の元祖」でもあった[12]。
そもそも、流行作家であった馬琴は、作品を眼で見ても、声に出しても楽しめるように多様な読者サービスに努めた。葛飾北斎らとコンビを組んで上質のイラストを用い、朗読に向いたリズミカルな文体を導入した彼の読本は、文字テクストを視聴覚メディアに変える実験場となった。馬琴の文学が家庭内で女性や子どもたちにまで読み伝えられたのは、まさにその実験の成果である[13]。その一方、より高尚な議論を期待する読者に対しては、馬琴は文芸批評を提供した。
馬琴は宣長および秋成の学問を敬愛しつつも、彼らがやらなかった小説批評という新しい分野にチャレンジした。その際に、彼がモデルにしたのは、金聖嘆や李漁のような近世中国の批評家=思想家たちである。中国小説がそのメタ言説(批評)を含むハイブリッドなテクストであったように、馬琴の読本(稗史)は文芸批評や雑学を、その語りの余白において展開した。彼の最も名高い物語論である「稗史七則」――物語の制作にあたって心得るべき七つの技術をマニュアル化したものであり、金聖嘆や李漁の影響を強く受けている――も、『八犬伝』第九輯中帙附言として記されたものである。物語の仕組みを、当の物語のなかで解き明かすというこのメタゲームは、中国小説との接触なしにはあり得なかった。
さらに、馬琴は自らの批評を読者との双方向のコミュニケーションに仕立てた。彼の熱烈なファンであった殿村篠斎が、まだ完成途上の『八犬伝』について質問や批評を送ってきたとき、著者はそれに快く応じた。この両者のやりとりをまとめたのが『犬夷評判記』である[14]。『八犬伝』を二〇年以上も書き続けるのに並行して、その創作の秘密の一端を解き明かすような自作批評も公にする――ここからは、馬琴が批評というコミュニケーションを戦略的に活用していたことがうかがえるだろう。
こうして、小説と批評を交差させた中国の新しい文学的知能は、一九世紀日本の馬琴によって相続された[15]。しかも、彼は中国小説の単純な形態模写をしたわけではなく、ときに中国にもないような先進的な文芸批評も試みた。特に、われわれの目を引くのは、その文体論である。例えば、馬琴は建部綾足の『本朝水滸伝』が雅語を用いていることを厳しく批判し、中国小説(稗史)を「父母」として小説を書こうとするならば、俗語を用いなければならないと力説した。
稗史野乗の人情を写すには、すべて俗語によらざれば、得なしがたきものなればこそ、唐土にては水滸伝西遊記を初として、宋末元明の作者ども、皆俗語もて綴りたれ、ここをもて人情を旨として綴る草紙物語に、古言はさらなり、正文をもてつづれといはば、羅貫中高東嘉もすべなかるべく、紫式部といふとも、今の世に生れて、古言もて物がたりふみを綴れといはば、必ず筆を投棄すべし。[16]
ふつう日本文学史では、書き言葉を話し言葉に近づけようとする俗語化の試みを、明治期の言文一致運動に求める。しかし、馬琴は早くも一九世紀前半に、「人情を写す」には俗語の力が不可欠であり、それは『水滸伝』や『西遊記』はもとより、日本の『源氏物語』も変わらないときっぱり述べていた[17]。このような方法論的な自覚は、中国で大量の白話小説が刊行され、文学環境をラディカルに変化させたことに裏打ちされている。
馬琴にとって、先進的な中国小説のプログラムを日本語の環境でいかに利用するかは、一貫したテーマとなった。それは俗語化だけではない。彼は『八犬伝』以前に大きな人気を博した『椿説弓張月』(一八〇七~一一年)において、すでに中国小説の趣向を借りている。『椿説弓張月』は鎌倉時代の『保元物語』を下敷きとしつつ、弓の名手である亡命軍人・源為朝をその悲劇の運命から救済しようとする架空の物語である。保元の乱で敗北し、伊豆大島に流された馬琴版の為朝は優れた統治者となるが、その後朝廷に追われて琉球にまで落ち延び、そこで独立王国の父祖となる。この後半部のアイディアが一七世紀中国の陳忱の小説『水滸後伝』から得られたことは、つとに指摘されてきた。
もともと、『水滸伝』を部分訳し、『水滸伝』の好漢のジェンダーを反転させた『傾城水滸伝』をも世に送り出した馬琴は、陳忱の『水滸後伝』にも強い批評的関心を寄せていた。ゆえに、この小説が『椿説弓張月』の設計に利用されたのも不思議ではない。では、『水滸後伝』とはいかなる小説なのか。少し回り道になるが、簡単に紹介しておこう。
6、遺民=亡霊のユートピア的想像力
一六世紀の中国はドラマティックな出版革命を経験したが、それから一世紀も経たない一六四四年に、漢民族王朝の明は満州族に攻略されて滅亡する。このトラウマ的なショックを強く受け取ったのが、明の「遺民」たちである。彼らは新しい異民族王朝(清)に仕えるのを潔しとせず、前王朝の記憶を保ち続けた。一七世紀中国の文学や美術を考えるのに、遺民という亡霊的な存在を欠かすことはできない。
この遺民の志をもつ知識人の一人であった陳忱は、梁山泊の水軍を率いた李俊が後年シャムに逃れて王になったという『水滸伝』の一文をふくらませて、『水滸後伝』という新たな小説に仕上げた。そこでは、李俊をはじめ梁山泊のサバイバーたちが、腐敗した宋王朝――やがて女真族の金に蹂躙される――から逃走し、シャムに理想の政権を樹立するまでの物語が語られる。この亡命者たちの活躍には明らかに、異民族に蹂躙された明の遺民の苦境および願望が投影されていた。
著作権の概念のなかった当時、小説は一種のオープンソースとして用いられた。都市の盛り場でのパフォーマンスを母胎とする『水滸伝』や『三国志演義』はもとより、その『水滸伝』のエピソードをもとにした『金瓶梅』、さらには『水滸伝』の続書(続編)である『水滸後伝』は、いずれも間テクスト的なネットワークから派生したものである。ゆえに、これらの中国小説は、単独の作者の所有物としては理解できない(なお、二一世紀の中国においても、劉慈欣のベストセラーSF小説『三体』の「続書」が、インターネット上のファンによって書かれた――これは、近世的な伝統がネットワーク社会で復活したことを意味する)。
そのことと一見して矛盾するようだが、ここで面白いのは、この匿名的なオープンソースからときに固有の「作家性」が産出されたことである。この現象はしばしば、続書において認められる。現に、『水滸伝』や『西遊記』の著者の実態があいまいであるのに対して、その続書である陳忱の『水滸後伝』や董説の『西遊補』には、作者の遺民=亡霊としての境遇が投影された。オリジナルよりも二次創作において作家性がより鮮明になるという逆転現象が、ここには生じていた。
特に、一六六〇年代――ちょうど明の遺臣である鄭成功が、オランダ人から台湾を奪取しようとした時期にあたる――に書かれたと思しき『水滸後伝』には、遺民=亡霊の立場からの政治批評という一面がある。そこでは、オリジナルの『水滸伝』に引き続き、奸臣に牛耳られた宋王朝の衰退のシミュレーションが試みられ、政治家や僧侶の堕落が次々とあばかれてゆく。国家の中枢がすでにすっかり腐敗しきっていたところに、強力な異民族が襲来し、ついに宋は滅亡のときを迎える……。陳忱がここに、明の滅亡というトラウマ的体験を重ねていたのは明白である。
この致命的な内憂外患のなかで、『水滸後伝』の好漢たちには中国の「文化防衛」という役割が与えられた。シャムに亡命した彼らは、その地の奸臣と敵対するのみならず、何と「関白」の率いる日本軍とも交戦し、魔術によってその全員を凍死させる。粗野でずるがしこい異民族に対して、それを遥かに上回る中国人の叡智が誇示されるのだ。ここには、漢民族王朝の宋の自滅に対する一種の償い(redemption)という意味がある。
もともと、あらゆる社会的職種が戦争に差し向けられるオリジナルの『水滸伝』は、一種の総動員体制のような様相を呈していた。『水滸後伝』は好漢たちに再び動員をかけて、海外のシャムでユートピア建設に乗り出すが、物語が進むにつれて原作のカーニヴァル性はどんどん希薄になってゆく。かつての荒くれのピカロ――悪漢にして好漢――たちは、最終回に到ってついに礼楽の担い手となり、優雅な詩会を開催するまでになった(第四〇回)。こうして、李俊の統治するシャムは、中華文明のミニチュアとして再構築された。
ただし、ここには、無力な遺民=亡霊の文学ならではのアイロニーがある。というのも、李俊たちの「文明化」とその全面勝利は、あくまで限界を刻印されていたからである[18]。現に、この詩会の後に、宋江や燕青らの登場する芝居(水滸戯)が上演され、李俊らがそれを楽しむというメタフィクション的な場面が続くが、これは『水滸後伝』の虚構性に対するアイロニカルな自己言及である。李俊たちがシャムにユートピアを築いたところで、それはせいぜい上演された虚構にすぎない。ゆえに、トラウマ的な破局の歴史は何も変わらない。『水滸後伝』の末尾では、やがて南宋の滅亡が訪れることが仄めかされる。
そして、一八世紀に入ると、このようなアイロニーを含んだ文明の再建は、シャム(想像上の外国)ではなく中国の内部に向かった。『水滸後伝』のおよそ一世紀後の『紅楼夢』では、ジェンダー表象にも巧みな操作が加えられた。陳忱が『水滸伝』のエネルギーを呼び覚まして、男性優位のホモソーシャルな国家を海外に再建したのに対して、没落した名家の出身である曹雪芹は、むしろ反国家的な女性優位のユートピア(大観園)を国内に設計してみせるが、それも結局は崩壊する。この二つの小説はまさに好一対のユートピア小説であり、その夢はいずれ現実に屈することが示唆されていた。
7、『椿説弓張月』と≪未開≫の発見
では、一九世紀人である曲亭馬琴の文学はどうか。曹雪芹のおよそ五〇歳下の彼にとっては、極度に洗練された『紅楼夢』ふうの戯れよりも、むしろそれ以前の『水滸後伝』のようなダイナミックな国家建設のプロセスのほうが、その作家的資質からしても魅力的であったと思われる。
そもそも、馬琴は江戸の読本文化の申し子でありながら、その自閉的な洗練から逃れようとする意志をもっていた。彼のパワフルな想像力は、江戸を飛び出し地方を旅行することによって培われた[19]。馬琴には、自己を自己ならざるものへと変容させようとする超越の志向があった。彼はオープンソースとしての中国小説にしきりにアクセスし、そのアイディアや方法論を深く研究した作家であったが、それもロマンティックな自己超越のなせる業である。
繰り返せば、近世の中国小説は、歴史書のくびきを脱して「真実性」と「虚構性」を追求するプログラムを開発した。秋成はこの新しい知能を利用して、日本の「呪われた部分」を暴くというバタイユ的な戦略を進めたが、それは馬琴にも共通する。馬琴は政治的秩序の深層に、不気味な「呪い」という負のレイヤーを見出した。例えば、『椿説弓張月』では為朝の遺民=敗者の情念が琉球の国家建設を準備し、『八犬伝』では悪女・玉梓のかけた呪いが、めぐりめぐって「八犬士」を生み出すことになる。もともと、日本の物語は『平家物語』を筆頭として、敗者に感情移入する傾向が強い。馬琴はこの日本的抒情のパターンを利用しつつ、江戸=都市の外部へと突き抜けようとした。
例えば、伊豆大島に渡った為朝は、ちょうど『水滸後伝』の李俊がそうしたように、近隣の島々を巡歴するが、その途上で女性しか住まない女護島に渡る。島の一人の女性から、女護島の最初の住人が徐福の従者であったこと、それが女人だけで暮らす奇妙なならわしのもとになったことを説明された後、為朝には次のような考えが生じる。
為朝は、なるほど、巷談街説[街のゴシップ]も一概にそしることはできないものだと、はたと膝を打った。今この女の語るところは、世の伝説と、当たらずとも遠からずではないか。人はさまざまな世を経るものであるな。都会の繁華な地に生まれたものは、自ら耕さずに飯を食らい、織らずに服を着るから、田舎人の辛苦に同情がない。このような恵まれた環境があるのに、驕って満足せず、貪って飽きることを知らないので、最後には神仏に見放されて、子孫が途絶えてしまうものが多い。私は伊豆の島々を巡覧して、たとえようもない、もののあわれの感を催したが、そこにはこの[苦労の多いならわしを信じ込んだ]島すらあるのだ。今、彼らを教化して、男女を一つところに住ませて、この島を伊豆七島のうちに加えたら、後の世に裨益することだろう。(後篇巻之一)〔『椿説弓張月・上 日本古典文学大系60』[後藤丹治校注、岩波書店]に基づく拙訳〕
ここには、複数のテーマが慌ただしく語られている。為朝はまず①徐福伝説のような荒唐無稽な伝説も何らかの歴史的な真実を語っているという、いわば民俗学者のような認識を語る。そして②未開の島々の風習に、いわば文学者として「もののあはれ」の感を催している。続けて③この純朴な未開性と対比して、都会人の驕慢ぶりをいわば文明批評家として厳しく指弾する。にもかかわらず、彼は最後に④この島の迷信は正しい知識によって克服されるべきだと信じる植民地主義者として現れる。実際、為朝はまさにこのインフォーマントの女性と進んで結婚し、島の迷信を打破したのである。
こうして、馬琴は為朝に乗り移りながら、都会の虚飾の代わりに、素朴な未開性を前面に押し立てた。これは宣長の思想をアップデートしたものである――というのも、宣長が『古事記』や『源氏物語』のような過去の王朝のテクストに「もののあはれ」を認めたとすれば、馬琴はローカルな≪島≫の風習にこそそれを認めたのだから。むろん、馬琴の読本も、徐福伝説をはじめ膨大なテクストを参照しているが、彼の画期性はテクストを現実にあり得る風土や人間と結びつけたことにあった。一九世紀の馬琴は一八世紀の宣長と違って、人間の「真」を洗練されたテクストではなく、ごつごつとした≪未開≫の環境のなかに見出し、しかもそれを植民地主義者のように掌握しようとした。
そのため、馬琴は琉球あるいは伊豆大島の環境を了解することに、並々ならぬ知的情熱を注いだ。『水滸後伝』のシャムが中華文明のミニチュアにすぎなかったのに対して、『椿説弓張月』の伊豆や琉球は、その住民のもつ神話や歴史のみならず、地理、物産、習俗、音楽等に及ぶ百科全書的なデータで肉づけされている。ここにはエキゾティックな趣味だけではなく、まさに民俗学者のような視点がある。馬琴は野性を保存した≪島≫に、都会ではすでに失われた古い日本の亡霊を読み取ろうとした。これは『水滸後伝』とはまったく逆のヴェクトルである。
しかも、馬琴の想像力はそこから、人間ならざるものとのエス的な融合にまで進んだ。現に、『椿説弓張月』の為朝にせよ『南総里見八犬伝』の八犬士にせよ、彼らは動物と感情的に交わる能力(物類相感)から、人間離れした神的なエネルギーを引き出していた。この二つの大作はともに、ローカルな風土に根ざしながら、国家建設の物語をパワフルに立ち上げてゆくが、その根底には動物と神を等置するアニミズムがある[20]。馬琴は世界の深層にアニミズム的な野性を認め、それを国家の起源として描いたのだ。
これは日本文学の刷新と呼ぶにふさわしい。一八世紀の本居宣長の美学では、このような≪未開≫のもつ破天荒なエネルギーは到底得られなかっただろう。かたや、上田秋成の「呪い」や「悪霊」の文学は、一見して馬琴とよく似ているものの、それは建設的な力ではなく解体的な力を引き出すものであった。馬琴が一八世紀の思想を引き継ぎつつ、それを新たなステージに押し上げたことは歴然としている。
8、琉球というコンタクト・ゾーン――馬琴・ペリー・ゴンチャロフ
牡丹の痣を共有していた八犬士たちが、まさにそのスティグマを手引きとして結集するように、馬琴自身も≪未開≫の痕跡を発見し、それをつなぎあわせることに取り組んだ。アニミズム的な野性の発見によって、日本を日本ならざるものへと変身させること。あるいは、日本ならざる未開の島から真実の心を引き出すこと――このような飽くなき超越の意志が、馬琴を卓越した「思想家」にしたのは疑い得ない。
ただし、一九世紀のグローバル政治の圧力は、馬琴の超越のプロジェクトを上回る勢いで日本に迫っていた。現に、『八犬伝』の完結した一八四二年には、中国はイギリスとのアヘン戦争に敗北し、その後は列強に国土を侵食されるという国難の時期に入っていた。この不穏な世紀を予告するように、馬琴は琉球という≪新世界≫への植民地主義的な進出を語ったが、その後の日本を揺るがしたのは、さらにその遥か彼方にある世界、すなわちロシアとアメリカという≪新世界≫であった。
ロシアはすでに一八世紀から、海上で日本の船と接触を繰り返し、徳川幕府に通商を要求していた。それは日本の政治家や学者にとって、新たな国難の到来を示すものであった。特に、ロシアの南下政策に強い関心を抱いていた水戸学者の会沢正志斎は、一八二五年の『新論』――その「国体」論および「尊皇攘夷」論によって幕末の志士を強く触発した――というパンフレットで、イギリスと並んでロシアの脅威をしきりに語った[21]。馬琴が主に房総半島を舞台にする『八犬伝』という戦争文学の執筆に取り組む一方で、水戸の会沢は対外戦争を予感しながら、危機の時代のイデオロギーを組み立てたのである。
その一方、日本へのアメリカの接近は必ずしも予測されてはいなかった。現に、国防の必要性を訴える会沢の『新論』でも、アメリカの脅威には触れられていない。しかし、日本を開国させたのは実際にはアメリカであった。当時の日本がヨーロッパ的洗練ではなく、エネルギッシュなアメリカ的野性に遭遇したことは、明治以降の国家の進路にも、少なからぬ影響を与えたと思われる。
しかも、「新しい国であるアメリカが古い日本を開国させる」というミッションに燃えるマシュー・ペリー提督とその大船団は、直線的に日本列島に向かったわけではなく、シンガポール、香港、マカオ、そして琉球を経由して、さまざまな外交上の成果をあげた。つまり、ペリーの遠征は日本を含めて、アジアへの進出の足場を築くものであった。現に、ペリーの提出した大部の報告書『アメリカ艦隊の中国海域及び日本への遠征記――一八五二~四年』では、現地の人間や地理についてのきわめて詳細な情報が記されている。
馬琴は『椿説弓張月』において、民俗学者のように琉球を観察したが、それはあくまでテクストに基づくものであった。逆に、ペリーの艦隊は琉球王国を実に四回も訪問した。ペリーの一行には画家や植物学者も随行しており、彼らの力によって、琉球の地質や植生、言語をはじめ、あらゆる観点から琉球がリサーチされている[22]。しかも、琉球のみならず浦賀、下田、箱館の状況まで含むペリーの調査の精度と広がりは、馬琴の文学とは比べ物にならない。日本の卓越した物語作家よりも、アメリカ人のペリーのほうがより日本の地方に精通していたところに、彼我の情報格差が凝縮されていた。
このペリーの報告書と好一対の関係にあるのが、ロシアの小説家イワン・ゴンチャロフの旅行記『フリゲート艦パルラダ号』である。代表作の『オブローモフ』(一八五九年)を書く以前、ゴンチャロフは一八五〇年代に日本との通商を求めるプチャーチン提督に随行し、ロンドンから南アフリカのケープタウンを経て日本、さらにはシベリアまで訪れた。それら諸地域の様子をつぶさに記した『フリゲート艦パルラダ号』はロシア国内でベストセラーとなった。
日本に迫るロシアのプチャーチン艦隊の動向を察知したペリーは、予定を急遽早めて浦賀に向かった(上海の近辺でプチャーチンとペリーはニアミスしている)。もしロシア側のプチャーチンが日本に先着していれば、その後の歴史の進路は大きく変わった可能性もあるが、今はゴンチャロフによる琉球の描き方についてだけ触れておこう[23]。すでに琉球にはペリー率いるアメリカ人が先んじて到着し、「メルヴィル港」と称する港にまで目星をつけていた。ゴンチャロフはその野心的なアメリカ人の姿を書きとめる一方、琉球人の生活には原始的な「古風純朴さ」を見出している。
これは、バイブルやホメロス描くところの古代世界がわずかに無事に残っている唯一の場所なのである。これは野蛮人ではなく、羊を飼って生計を立てている牧人たちであり、宗教や、人間の義務や、善行を完全にして高度に理解している、古風純朴の人々なのである。ここへ来てバイブルや、オデュッセイアに出てくる地方や、住居や、手厚いもてなしや、原始的な静けさや、素朴な生活の記述を確かめられるがよい。ここでは二千年前と同様に、何の変化もなく人が暮らしているのだという思いがして一驚されるであろう。[24]
馬琴が伊豆や琉球に、都会に汚染されていない未開の人心や物産を見出したように、ゴンチャロフもそこに聖書やホメロスの叙事詩の時代を認めた。彼らはそれぞれ、琉球に古代の美風を投影した。しかも、そのゆったりとした古代の世界は、加速する植民地主義の力で「発見」されたのである。
アメリカ人とロシア人を遭遇させた琉球は、まさに一九世紀世界の縮図と言うべきコンタクト・ゾーンとなった。そこを物語の舞台に選んだ馬琴は、図らずもグローバルな植民地主義の政治の核心に近づいていた。もし馬琴がアメリカやロシアに生まれていれば、ゴンチャロフにも劣らないトラベローグ(旅行文学)の書き手になっただろう。しかし、現実には一九世紀半ば以降、馬琴の想像力を超えるスピードで事態は進んだ。馬琴の死後、日本はまさにヨーロッパともアジアとも異なる≪新世界≫の新しい力に導かれて、世界史のステージに登壇させられたのである。
では、この≪新世界≫は世界文学史においていかなる位置を占めるのか。それを次章の課題としよう。
[1]テリー・イーグルトン『表象のアイルランド』(鈴木聡訳、紀伊国屋書店、一九九七年)二七頁。アイルランドと日本を仮想的につなぐ存在として、漱石が挙げられる。一九〇〇年から二年間イギリスに留学した漱石は、社交のゲームに興じる拝金主義的なイギリス紳士に幻滅し、いっそスコットランドやアイルランドに行こうと考えたものの、それは英語の勉強に不適当と見なして断念する(『文学論』序参照)。折しも二〇世紀初頭のアイルランドのダブリンでは、漱石と同世代のウィリアム・バトラー・イェイツが、盟友のシングらとともにアイルランド演劇運動を牽引していた。漱石がもしダブリンに赴いていれば、イェイツはもとより、学生時代のジェイムズ・ジョイスとすれ違った可能性もゼロではない。ユーラシアの両端に生まれた「エス」的作家どうしの遭遇を想像するのも一興だろう。
面白いことに、漱石がスコットランド生まれの経験論哲学者デイヴィッド・ヒュームに関心を寄せたのに対して、晩年のイェイツは、唯心論的な観念論を掲げたアイルランド生まれのジョージ・バークリーに傾斜した。岩田美喜『ライオンとハムレット』(松柏社、二〇〇二年)一五二頁以下。超越的な理性の支えをもたないヒューム的経験やバークリー的観念を、より本源的なものと見なすこと――これもエス的な辺境文化の特徴と言えるだろう。
[2]李永晶『変異 日本二千年』(広西師範大学出版社、二〇二一年)一〇頁。
[3]「聾瞽指帰」(村岡空訳)『弘法大師空海全集』(第六巻、筑摩書房、一九八四年)一二六頁。空海は続けて、日本の作家「日雄」による『睡覚記』に言及している。これは現存しないが『遊仙窟』に似た小説であっただろうと推測される。
[4]Ryuichi Abe, The Weaving of Mantra: Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse, Columbia University Press, 1999, p.99.なお、『遊仙窟』の影響は、折口信夫が一九四〇年代という戦時下の小説『死者の書』でも問題にしている。折口は大伴家持の口を借りて、エロティックな『遊仙窟』が日本人の感受性をハッキングし、その精神を植民地化してしまったという認識を語った。詳しくは、拙著『百年の批評』(青土社)に収めた『死者の書』論参照。
[5]金文京「香港文学瞥見」可児弘明編『香港および香港問題の研究』(東方書店、一九九一年)二二三頁。
[6]本居宣長『排蘆小船・石上私淑言』(岩波文庫、二〇〇三年)一一、六三頁。
[7]同上、七三頁。
[8]日野龍夫『宣長・秋成・蕪村』(ぺりかん社、二〇〇五年)一五三頁以下。
[9]本居宣長前掲書、一三頁。なお、宣長の学問の方法にも、中国の文献学との類似性が認められる。吉川幸次郎『本居宣長』(筑摩書房、一九七七年)参照。
[10]近年では台湾の思想史家・楊儒賓の『異議的意義』(台大出版中心、二〇一二年)が、伊藤仁斎や荻生徂徠の思想を、近世東アジアの反理学的パラダイムのなかに位置づけている。
[11]ベンジャミン・エルマン『哲学から文献学へ』(馬淵昌也他訳、知泉社、二〇一四年)。
[12]森潤三郎「曲亭馬琴翁と和漢小説の批評」日本文学研究資料叢書『馬琴』(有精堂、一九七四年)三六頁。
[13]馬琴文学の酵母となったオーラル・コミュニケーション(音読)の環境は、明治期以降もしばらく持続した。詳しくは、前田愛「音読から黙読へ」『近代読者の成立』(岩波現代文庫、二〇〇一年)所収参照。
[14]高田衛『完本 八犬伝の世界』(ちくま学芸文庫、二〇〇五年)九六頁。
[15]David L. Rolston, Traditional Chinese Fiction and Fiction Commentary: Reading and Writing Between the Lines, Stanford University Press, 1997.
[16]「本朝水滸伝を読む並批評」『曲亭遺稿』(国書刊行会)三一九頁。
[17]馬琴による俗語化の推奨は、宣長とも好対照をなしている。『排蘆小船』の宣長は、古代の美風を保存した雅語を評価し、俗語化を堕落と見なした。ここには、歌の批評家・宣長と小説の批評家・馬琴の違いがはっきり現れている。
[18]Ellen Widmer, The Margins of Utopia: Shui-hu hou-chuan and the Literature of Ming Loyalism, Harvard University Press, 1987, p.150.
[19]水野稔「馬琴の文学と風土」前掲『馬琴』。
[20]高田前掲書、七八頁以下。
[21]会沢の『新論』のもつ「動員のイデオロギー」としての性質については、片山杜秀『尊皇攘夷』(新潮社、二〇二一年)および片山杜秀+福嶋亮大「水戸学のアクチュアリティ」『新潮』(二〇二一年、一〇月号)参照。
[22]M・C・ペリー『ペリー提督日本遠征記』(下巻、宮崎壽子訳、角川ソフィア文庫、二〇一四年)。
[23]なお、すでにイギリス海軍の軍人バジル・ホール(有名な日本研究者バジル・ホール・チェンバレンの祖父)が、ヨーロッパでベストセラーとなった『朝鮮・琉球航海記』(一八一八年)のなかで、朝鮮および琉球について詳しい記録を残していた。さらに、ホールが琉球訪問の後でセント・ヘレナ島に流されていたナポレオンと会見し、彼に琉球の平和ぶりを報告したことも、グローバル・ヒストリーの観点からは興味深い。ただし、ゴンチャロフもペリーも、ホールの記述はあまり評価していない。
[24]イワン・A・ゴンチャローフ『ゴンチャローフ日本渡航記』(高野明+島田陽訳、講談社学術文庫、二〇〇八年)三七九頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年8月1日、8月8日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年9月21日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。