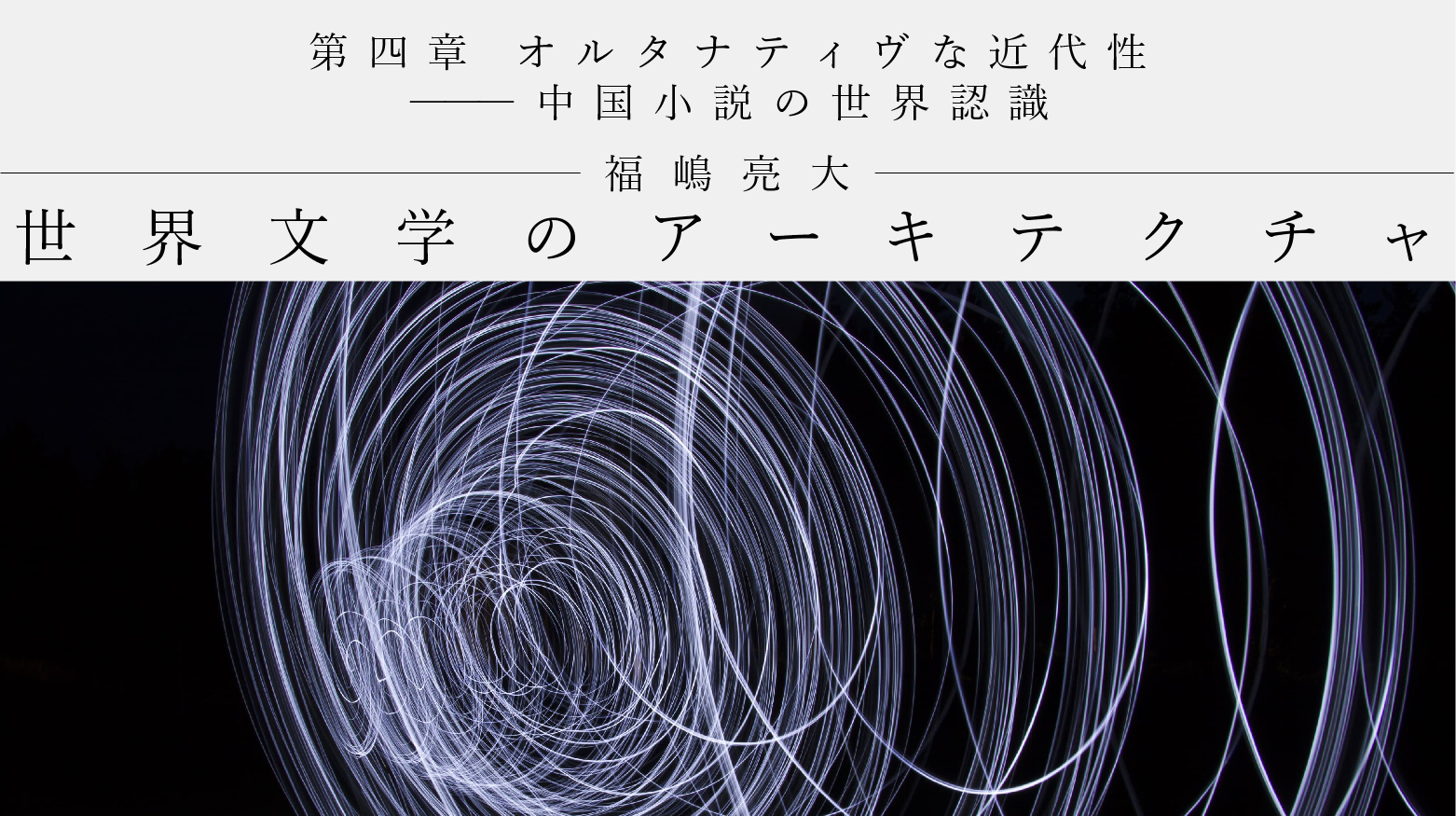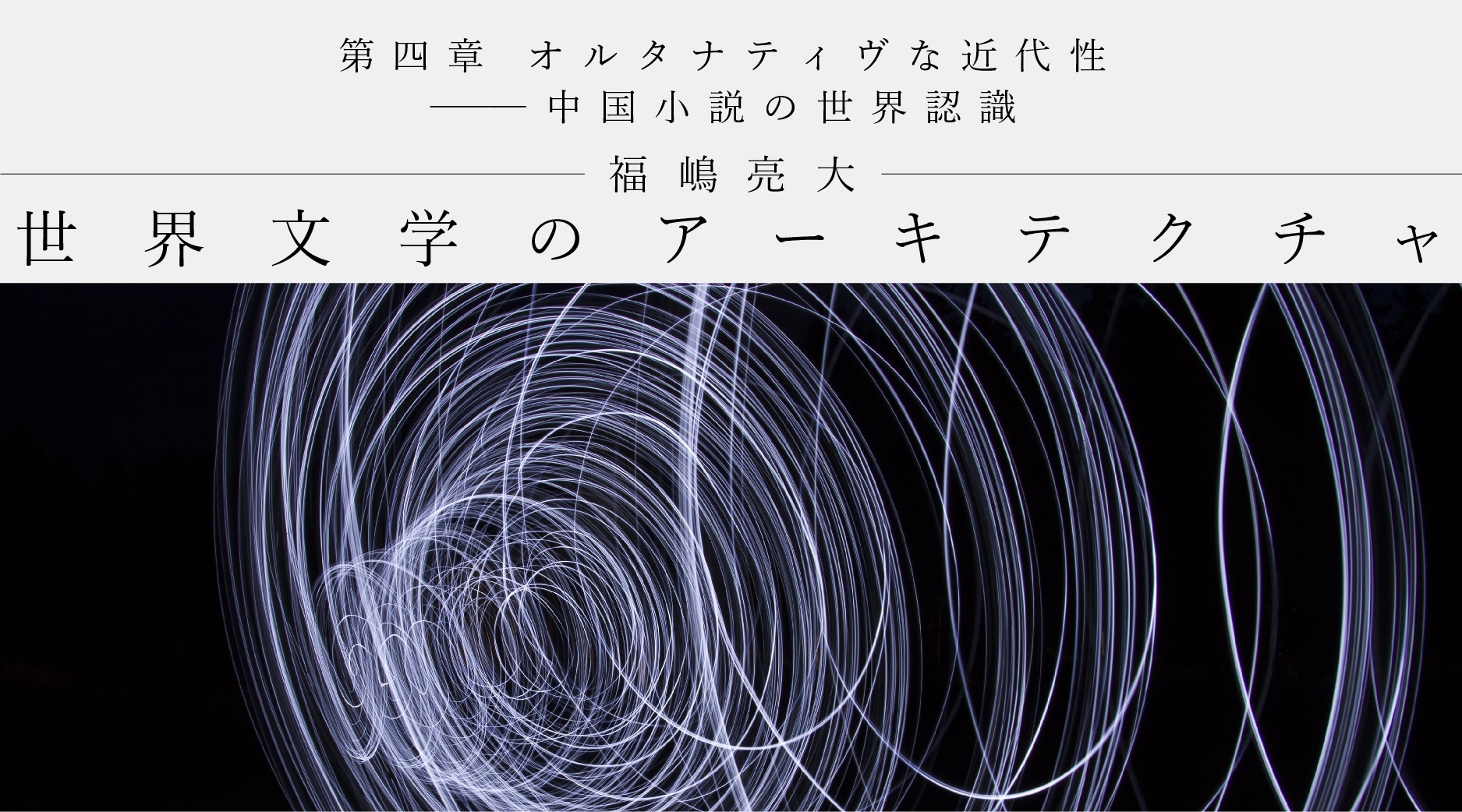批評家・福嶋亮大さんが「世界文学」としての小説とそれを取り巻くコミュニケーション環境を分析していく連載「世界文学のアーキテクチャ」。
近代以降に一般化した「小説」との差異を指摘しつつ、『水滸伝』や『三国志演義』といった作品がどのように読み解かれたのかを通じて、近世の中国文学とその批評のあり方について分析します。
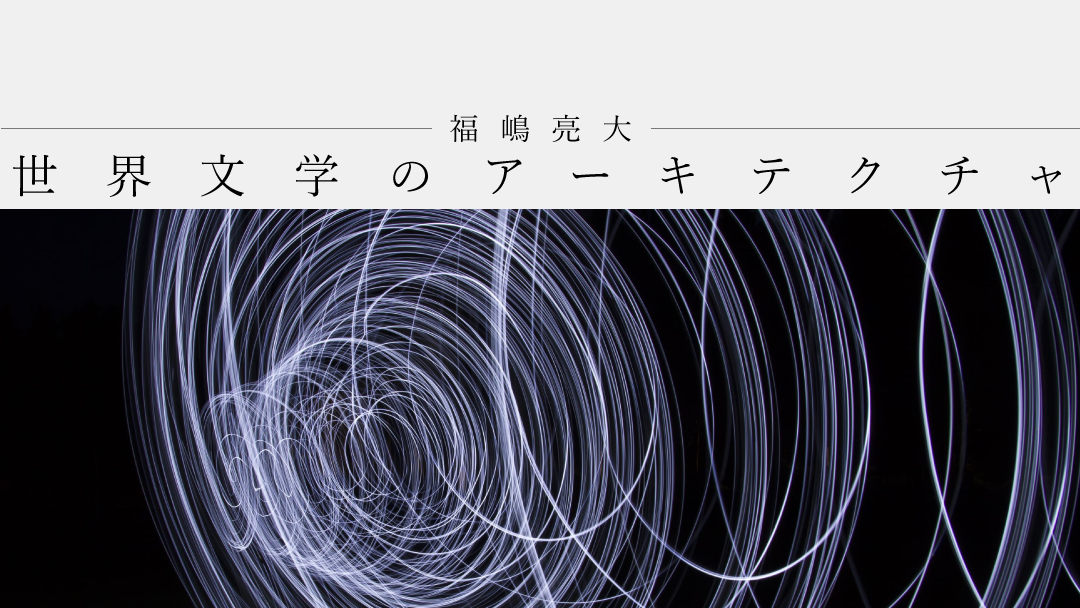
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、二つの文学ウイルス
本章およびその補遺では、主に近世(early modern)の小説を中心として、中国文学および日本文学のあり方に照明を当てるが、それに先立って、中国小説の文化史的な位置づけを検討したい。少し回り道しながら考えていこう。
夏目漱石の『文学論』(一九〇七年)の序は、英文科出身の彼が英語の研究を命ぜられ、二〇世紀初頭のイギリスに留学したときの回想に始まる。彼はそこで文学を「社会学的心理学的」に研究するという巨大なテーマに取り組み、ついに神経衰弱に陥った。ここで重要なのは、彼をこの無謀な研究に駆り立てたのが「漢文学」および「英文学」との遭遇であったことである。
余は少時好んで漢籍を学びたり。これを学ぶ事短かきにも関らず、文学はかくの如き者なりとの定義を漠然と冥々裏に左国史漢より得たり。ひそかに思ふに英文学もかくの如きものなるべし、かくの如きものならば生涯を挙げてこれを学ぶも、あながちに悔ゆることなかるべしと。
こうして、二つの文学の共通性を信じて、英文学研究に生涯をささげようとした漱石は、しかしいくら読書しても英文学を味わい得たという境地に到れず、大学の卒業時には「何となく英文学に欺かれたるが如き不安の念」に駆られる。この不安が漱石を次の有名な見解へと導いた。「漢学に所謂文学と英語に所謂文学とは到底同定義の下に一括し得べからざる異種類のものたらざるべからず」。つまり、漱石は漢文学と英文学をいったん「文学」の名のもとに同一化したが、それがかえって両者の差異を際立たせたのである。
私は前章で、小説の流行をパンデミックにたとえた。そのメタファーを再び用いて言えば、すでに漢文学ウイルスに感染していた漱石は、英文学ウイルスに遭遇し、しかもその特有の「症状」に強い違和感を覚えていたと言えるだろう。この二つの文学は同種に思えるが、いわばインフルエンザウイルスとコロナウイルスが似て非なるものであるように、それが読者の引き起こす反応は異なっていた。少なくとも、鋭敏な漱石はどうしてもその差異を看過できなかったのである。
同時代人の森鷗外は、ゲーテをはじめヨーロッパ文学の翻訳に熱心に取り組んだ。ゲーテが『西東詩集』でペルシア詩人の「精神」をドイツ語に変換したように、鷗外もヨーロッパ文学のエッセンスを日本語の表現に導入しようとした。特に、オムニバス形式で各国の短編小説を翻訳・収録した鷗外の『諸国物語』は、まさに世界文学の地図製作者の面目躍如という感がある。むろん、ドイツに留学した鷗外も漱石と同じく、二つの文学の差異を肌身で感じていたに違いない。それでも、彼はゲーテの翻訳者にふさわしく、世界文学を受容し得るだけの表現力や柔軟性をもつ日本語のプラットフォームを、入念に組織したのである。
それに対して、漱石は卓越した語学力をもっていたにもかかわらず、年上の鷗外や二葉亭四迷と違って、その能力を翻訳に向けることはなかった。彼がやろうとしたのは、いわば系統の異なる二つの文学ウイルスを生み出した共通の仕組みを、科学的なアプローチで解き明かすことである。F(認識的要素)とf(情緒的要素)の組み合わせであらゆる文学を説明しようとする漱石の力業は、そこから生み出された。
ただ、現代のわれわれのもつ文学イメージからすると、いささか奇妙に思えることがある。それは、漱石が「文学はかくの如き者なりとの定義」を得たのが「左国史漢」、つまり『春秋左氏伝』『国語』『史記』『漢書』という歴史書からであったという事実である。彼自身優れた漢詩人であったにもかかわらず、漱石はこの序文で詩人にまったく言及していない。『文学論』の本文では、イギリスと中国の詩が多く作例として挙げられるのだから、序文の態度はなおさら奇異に感じられる[1]。
しかし、中国文学の基礎を歴史書に求めるのは、決しておかしいことではない。それは中国文学の特性に関わっている。かつて吉川幸次郎は、近世に白話小説が流布するまで、中国文学の担い手たちが一貫して、虚構よりも事実を尊重してきたことに本質的な意味を認めた。
非虚構の素材の尊重、言語表現の特別な尊重が、この文学史の二大特長と考えられる。二つはともに、この文明に普遍な方向である即物性によって説明されるであろう。歴史事実、日常の経験は、空想による事象よりも、より確実な存在である。表現された言語は表現する心象よりも、より確実に把握される。この国の哲学も、ひとしく即物的であり、神、超自然への関心を抑制し、地上の人間そのものへ視線を集中したが、おなじ精神が、文学をも支配したのである。[2]
このような「即物性」を凝縮したのが、「地上の人間」の諸相を記録した歴史書というジャンルである。左国史漢に文学を代表させたとき、漱石は中国文学の急所を浮かび上がらせていたと言えるだろう。
2、詩と小説――その評価の違い
そもそも、事実の記録と伝承は、中国では歴史書に限らず文学的なエクリチュール全般――今はこういう大雑把な言い方をしておく――で要求されたものである。ホメロスの叙事詩が百科全書的な教育装置であったとするエリック・ハヴロックの説(第二章参照)は、ギリシアのみならず中国の文芸にも適用できる。例えば、詩を学ぶ効用について、孔子は次のように説明した。
子曰く、小子何ぞかの詩を学ぶこと莫きや。詩は以て興すべく、以て観るべく、以て群すべく、以て怨むべし。邇くは父に事え、遠くは君に事え、多く鳥獣草木の名を識る。(『論語』陽貨)
孔子の詩学によれば、詩は心を奮い立たせ(興)、ものを観る仕方を教え(観)、共同生活を営ませ(群)、うらみごとの感情もうまく吐露させる(怨)。のみならず、詩の学習者は父や君主に適切な仕方で仕え、鳥獣草木の知識を得ることもできる――つまり、詩は共同生活に必要な基礎教養や倫理を教える百科全書として、孔子には理解されていた。しかも、この百科全書はたんに自然の名称のみならず、自然の根源的な生命力(古代ギリシアで言う「ピュシス」)をも伝達する。「詩三百、一言以て之を蔽う、曰く思い邪なし」(『論語』為政)と力強く言い切った孔子は、邪念のないまっすぐでふくよかな生命力こそを、詩という教科書の核心と見なしていた。
現に、古代の歌謡を集めた『詩経』における自然物は、しばしば「徳」の文字を伴って歌われる[3]。徳とは英語のvirtueと同じく、万物そのものに内在し、人間や自然を動かす霊的な「力」を言い表した言葉である。ゆえに、詩を共有することは、たんなる知識の獲得にとどまらず、自然や人間のもつ根源的な生命力にアクセスする行為に等しかった。詩が共同体の基礎教養となったのも、この万物のもつ「徳」の力を了解するのに、詩が欠かせなかったためである。
孔子やその門弟は、しばしば『詩経』を倫理的生活のメタファーとして用いた。一例をあげると、孔子が「貧しくても学問を楽しみ、豊かでも礼を好むほうがよいだろう」と述べたところ、弟子の子貢が「『詩経』に「切するがごとく、磋するがごとく、琢するがごとく、磨するがごとく」とあるのがそれでしょうか」と答えて、孔子が絶賛したというエピソードがある(『論語』学而)。切磋琢磨とはもともと骨、象牙、玉、石の加工法を指す言葉だが、師弟はそれを修養のテクノロジーとして読み替えている。詩は自然と人為をメタファーでつなぐ、一種の翻訳装置であったと言えるだろう。
では、小説はどうだろうか。詩が歴代の知識人(士大夫)に高く評価されてきたのに対して、小説は総じて劣位に置かれてきた。ここで重要なのは、小説が文化と非文化のボーダーラインにあったことである。中国の小説の起源を考えるとき、紀元一世紀の歴史家・班固の『漢書』芸文志――漢代の書籍目録であり、古代学術史の基礎文献でもある――の次の記載は必ず参照されるが、そこにはすでに小説の位置づけの難しさが示されていた。
小説家の流れは稗官に由来するのだろう。街談巷語(大通りや路地の話)、道聴塗説(道端で聞いたことを道端の他人に受け売りで話すこと)をこととする人間の造ったものである。
班固はここで孔子の批評を念頭に置いている。孔子は「道聴塗説は、徳を之れ捨つるなり」(『論語』陽貨)と弟子に厳しく注意した。他人の言葉をすぐに受け売りしたり、街角のゴシップを不用意に垂れ流したりするのは、彼には徳を台無しにする悪行として映ったのである。これは、彼が詩を徳の向上と結びつけたこととちょうど対照的である。孔子の文芸批評は、詩を共同体の教師として評価しながら、後に「小説」の淵源となったゴシップの流通(道聴塗説)を批判するという両面戦略を示していた。
ならば、班固はこの孔子の考え方に従って「小説」には社会的価値がないと断定しているのだろうか。その答えはイエス・アンド・ノーである。この文章は確かに、国家の高級官僚の立場から、ストリートで交わされる不正確な言葉を見下している(実際、班固が具体的に「小説」の書名を挙げるとき、そこにはしばしば「内容が浅薄である」という短いコメントも付けられた)。しかし、ここで重要なのは、班固がその直後に次の孔子(実際には弟子の子夏)の言葉を引用したことである。
小道といえども、必ず観るべき者あり。遠きを致すには泥まんことを恐る。是を以て君子は為さざるなり。(『論語』子張)
つまらないことにも必ず見るべきものはある、ただ遠大なことをやろうとする君子はその小さなことにのめりこむのを恐れるから、それには手を出さない――班固はこの『論語』の考え方を「小道」を語る「小説」の批評に応用した。彼が認めたのは、街角のゴシップが、まともな人間には相手にされないとはいえ、社会の観察者にとっては一定の意義をもつということである。しかも、このサブカルチャーとしての「小説」が君子をものめりこませる怪しげな魅力を備えていることも、班固は認識していた。
3、言説の分類を混乱させる小説
詩が自然や国家と深く共鳴しながら、共同体を教え導く装置であるのに対して、小説は都市のストリートで交わされる雑多な会話のレポートである。国家の繁栄の秘訣を壮麗な「賦」のスタイルで探り当てた詩人思想家の班固にとって、小説はあくまで非公式的でジャンクな言説にすぎなかった。だが、彼はそれをむげに退けたわけでもない。この両義的な態度にこそ、中国の小説を考える鍵がある。
ここで注目に値するのは、班固がわざわざ「小説家」という部門を用意したことである。彼は「小説家」を、儒家・道家・墨家・陰陽家・法家・名家・縦横家・雑家・農家を含む「諸子略」のリストの最後に位置づけた。これは思想書(子書)を集めたカテゴリなので、班固にとって小説家のポジションは、十の思想家の末端にあったということになる。むろん、国家公認の思想である儒教のテクストとは比較にならないとはいえ、街角のルポルタージュとしての小説家のテクストにも、彼はひとまず思想書の資格を認めたのだ[4]。
そもそも、ロラン・バルトが述べたように、語りには遍在性がある。「物語をもたない民族は、どこにも存在せず、また決して存在しなかった。〔…〕物語は、人生と同じように、民族を越え、歴史を越え、文化を越えて存在するのである」[5]。語りはありふれている。それは人間と同じく、世界じゅうに存在し、どこからでも発せられ、いつしか異なる時空へと侵入してゆく――このような性質が「街談巷語」と「道聴塗説」という中国のプロト小説の成立条件になったことは間違いない。班固の画期性は、このあまりにもありふれた語りを収集した無名の「小説家」を、思想家の列に加えたことにある。
もとより、一世紀の班固の言う「小説」の内実は、その後の「小説」と比べれば、ずいぶん貧弱である。彼はすでに小説の萌芽をつかんでいたが、それが千年以上かけて大きな文化にまで展開してゆくとは想像しなかっただろう。中国文学の進化史を考えるとき、小説というカテゴリそのものが、時間をかけて成長していったことを見逃すわけにはいかない。
その「進化」の鍵を握ったのが、まさに「左国史漢」に代表される中国の歴史書であった。六朝期のいわゆる「志怪」(怪をしるす)や唐代のいわゆる「伝奇」(奇を伝える)――文学史では「古小説」と呼ばれる――は、実際に起こったことのドキュメントという体裁を備えている。なかでも、唐代伝奇は九世紀初頭の李公佐による『謝小蛾伝』や『南柯太守伝』、白行簡(白居易の弟)の名編『李娃伝』をはじめとして、しばしば史書の「列伝」をモデルとして書かれた(なお、李公佐は各地を遍歴した官僚であり、その小説にはトラベル・ライティングの要素もある――特に『謝小蛾伝』には彼自身が訪問者として登場し、探偵の役割を担った)。まったくの絵空事として小説を書くという反事実的な態度は、当時は優勢にならなかった。
さらに、中国小説の黄金期と呼ぶべき明清時代においても、史実をもとにした『三国志演義』はもとより、『水滸伝』、『西遊記』、『儒林外史』等にはいずれも「伝」や「記」や「外史」のように、歴史的な事実の伝承というスタイルが保たれている。当時の文芸批評家にとっても、小説を司馬遷の『史記』になぞらえるのは定番のやり方であった。例えば、『水滸伝』の批評家として名高い一七世紀の金聖嘆は「水滸の方法は史記から来た」と述べて、『水滸伝』を『史記』に並び立つテクストとして正典化したのである。
さらに、二〇世紀になっても、歴史書の記憶は亡霊のように小説につきまとった。例えば、魯迅の『阿Q正伝』――新聞の補助的なメディアである副刊で連載された――は、歴史書のパロディとして書かれている。その冒頭で、おしゃべりな語り手は「列伝、自伝、内伝、外伝、別伝、家伝、小伝」と伝記のタイトルをあれこれと列挙した挙句に、いずれも阿Qというつまらない人物の伝記にはふさわしくないと考えて、ついに「正伝」――「閑話休題、言帰正伝(それはさておき、本題に戻ります)」という小説家の決まり文句から借用されたもの――という新しいタイトルを提唱する。小説史研究のパイオニアとして『中国小説史略』という名著を書いた魯迅は、ここで中国小説の歴史そのものにユーモラスに干渉したと言えるだろう。
中国の小説は既存の言説の分類体系をたえずすり抜けてゆく、文字通りマージナルなテクストであった。それは思想書のマージン(周縁/余白)にあるがゆえに、公認の思想の外にしばしば漏れ出してゆく一方、歴史書の伝統をハイジャックして、まるで歴史を語るようにして架空の物語を語った。思想書であって思想書でなく、歴史書であって歴史書でないという不思議なパラドックスが、小説を諸言説のはざまにある特異なジャンルに仕立てたのだ。
4、散文の二つの方向性
街路や宮廷をはじめ社会のあらゆる場所を培養土とし、公認の言説を擬態しながら、ミクロな変異を続けること――このウイルス的挙動こそが中国小説のダイナミズムの核心にある。小説は思想書や歴史書の伝統に寄生し、そのさまざまな表現の技術を自らに転写した。ゆえに、われわれは小説を一種のパラジット(寄生者)として理解すべきだろう。もともと取るに足らない非公式的な言説であった小説は、正統的な散文の技術を盗みながら、その性能を高めていったのである。
ここで、中国の散文の伝統について簡単に整理しておこう。古代の散文には、大別すると「記言」(議論の文)と「記事」(叙事の文)という二つの方向性があった[6]。つまり、君主や学者の言行を記録すること、過去に起こった出来事を述べ伝えることが、散文の主要な仕事となった。このうち前者からは思想書が生み出され、後者からは歴史書が派生する。
もとより、この二つは截然と区別できるわけではない。現に、漱石の挙げた歴史書の『春秋左氏伝』――『春秋』の注釈書であり、豊富な物語的要素を備えた著作――や『国語』には、この両者が混在している。例えば『左伝』は過去のさまざまな事件の顛末を述べてゆくが、その事件の進行はしばしば精彩に富んだ対話によって再現され、それが肉厚のリアリティを生んだ。漱石は『文学論』で『左伝』における楚と晋の戦争シーンを取り上げ、その場にいる作中人物の対話によって戦況を伝える「間隔法」が、イギリスのウォルター・スコットの歴史小説『アイヴァンホー』と符合すると述べている(第四編第八章)。『左伝』にはホメロスの『イリアス』のような戦争文学としての一面があるが、そのリアリティは全知全能の客観的なナレーションによってではなく、むしろプレイヤーたちの臨場感あふれる対話によって確立された。
『左伝』や『史記』のような「叙事の文」には、抽象的な思弁よりも具体的な事実を重んじる中国文学の「即物性」が凝縮されている。しかも、その記述は、血沸き肉躍る戦時のスペクタクルの再現よりも、その戦争について政治家や軍人がどのような観察や対話をやったかという知性的・戦略的なテーマにこそ重点が置かれた。政治や軍事にまつわる具体的なシチュエーションから引き出された数々の対話や教訓――それもまた広義の「思想」と呼ぶに値するだろう。戦争の活劇的なシーン以上に、プレイヤーたちの対話を重んじる歴史書の手法は、後の『三国志演義』や『水滸伝』のような叙事的な小説にも受け継がれている[7]。
その一方、「叙事の文」と並び立つ「議論の文」の系統においても、思想と歴史は厳密に区別されない。「議論の文」のなかで、特に小説の発生を考えるときに重要なのは、思想家たちによる「譬論」、つまり物語をたとえに用いながら議論を進める言説方式である[8]。
古代中国ではさまざまな思想家(いわゆる諸子百家)が諸国家を渡り歩きながら思想を売り込んだが、そのような流動性は散文の形態にも大きな作用を及ぼした。特に、戦国時代の中期になると、彼らの著作にメタファーを用いた論弁術が現れるようになる。それまでの思想書、例えば孔子の随想集である『論語』は、ミクロな倫理とマクロな政治を気ままに横断する教育的な語録であった。しかし、思想家たちが競い合う「百家争鳴」の時代は、そのような断片的な語録のスタイルにはとどまらず、より長大で手の込んだ説得のレトリックの開発を促したのである。
この流れは、法家思想の代表作である『韓非子』によく示されている。そこでは、議論の補強材料としてしばしば故事が語られる。印象深い逸話をメタファーとしながら、韓非子はそこからときに政治的な教訓を引き出し、ときに自らの思想の優位性を証明する。相手の意表をつく「たとえ話」によって、為政者の説得を試みるレトリックの技術が、韓非子の思想に豊かな物語性を与えることになった(そのうち最も有名なのは、儒家を批判するために持ち出された「矛盾」の語源となったエピソードである)。政治思想書である『韓非子』が、同時に歴史や物語を伝える叙事的な機能も含んでいたこと――ここにもやはり、歴史書と思想書の交差が認められる。
繰り返せば、この「叙事」と「議論」という散文の二つの仕事は、小説という野生のジャンルにも継承された。ただ、もともと街路に根ざした小説の本領は、マクロな歴史的事件を大上段から語ることよりも、むしろ政治や歴史の背後に回り込み、そこからミクロな逸話を拾い出すことにあったと言えるだろう。
現に、小説の語りはしばしば、為政者にまつわる週刊誌的なゴシップへと傾いた。例えば、三世紀の魏の文帝・曹丕を著者の名に冠する『列異伝』は、その後の志怪小説の先駆けと考えられる作品である。これは曹丕自身が編纂したわけでは恐らくないにせよ、そこに記されたゴシップや怪談は、当時の上流社会における「怪」の好みを示唆したものである。さらに、忌憚のない人物評やうまい言葉遣い、ユニークな逸話を集めた『世説新語』(五世紀の劉義慶の著作)は、当時の文学サロンにおいて、臨機応変に言語を操りながら有名人を的確に評する技術が、一種の「思想」になっていたことを物語る。
九世紀(中唐)になると、このようなゴシップや伝承が本格的にオーソライズされ、それを記録した知識人の「作者」も続々と現れるようになった。その反面、それらのゴシップ的な小説はノンフィクションの形態をとりながら、ときに荒唐無稽であり、ときに先賢をあざわらうような諧謔性を含んでいたため、小説のとめどない増殖は時代の病としても受け取られた[9]。小説の表現がそれまでの言説では捉えがたい領域にまで及んだのは、まさにこの変異の可能性に富んだウイルス的性質ゆえである。
現に、唐の伝奇小説の画期性は、フィクションとノンフィクション、事実と反事実のあいだで戯れる技術を発明したことにある。例えば、白行簡の『三夢記』や『南柯太守伝』は、夢をテーマとして「不確定性の詩学」の道を切り開いた[10]。例えば、『南柯太守伝』は「列伝」のスタイルを踏襲しているが、長大な歴史的事実であるかのように語られた内容は、実はすべて主人公の見た一場の夢であったことが明かされる。白行簡をはじめ唐の知識人作家たちは、歴史書のシミュレーションをやりつつも、その内容が事実か否かを厳密に確定しない保留の技術を培った。われわれはそこに、高度に洗練された小説的戦略を認めることができる。
5、一六世紀のコミュニケーション革命
以上のように、中国の「小説」はその周縁性ゆえに、オーソドックスな文化的分類体系を攪乱してきた。この文化のへりにあった小説が大きな飛躍を遂げたのが、明清時代――アメリカの学術界では「後期帝国中国」(Late Imperial China)とも呼ばれる――である。その背景には、出版物の爆発的増大という劇的なコミュニケーション革命があった。
印刷術そのものはすでに八世紀には存在していたが、それが出版という業態へと進むには相当の時間がかかった。唐までは、書物に記された知識は、手書きの書写本(鈔本)として一部の貴族に独占され、ごく狭い範囲で流通するだけであった[11]。例外は、仏教が布教のために印刷術を利用したことである。韓国で発見された「大陀羅尼経」や日本の「百万頭陀羅尼」が最初期の印刷物とされることからも分かるように、印刷の歴史は仏教と深い関係がある。中国文学者の大木康は「印刷術はほぼまちがいなく仏教の世界、あるいは少なくとも仏教にごく近いところで発明されたといってよいのではないかと思う」と述べている[12]。
唐の滅亡後、それまで社会から隔離されていた書物は、貴族階級の没落によって広く開放され始めた。それが中国出版史の事実上のファースト・ステップとなる。宋代(特に南宋)に入ると、出版業はめざましい広がりを見せて、書物の供給ルートが形成された。旺盛な知識欲をもった宋の知識人は、儒教以外の異端的な思想書(『韓非子』等)も含む多様な書物を望んだ。その結果、当時の著名な詩人・蘇軾(蘇東坡)に無断で、彼の詩集を刊行するようなケースすら生じたのである。しかも、この海賊版の詩集に朝廷を誹謗する箇所があったとされて、蘇軾はあやうく処刑されかける。これは営利出版がそのまま政治的な事件になり得ることを、よく示すエピソードだと言えるだろう。
しかし、当時の士大夫は書物があまりに広く開放されることを警戒し、営利出版の発展には無意識のうちにブレーキをかけた。そのため、出版がその潜在力を解き放てずにいるうちに、モンゴル族の支配する元の時代になり、出版物の多様性や品質は低下してしまう。いったん冬の時代に入った出版業は、なかなかそのトンネルから抜け出せなかった。それは元が滅んで、漢民族の明になっても変わらない。「出版の俗化と単調化は、漢族王朝が復活して明代となっても、とどまるどころか一層はなはだしく進行し、加えて量的にも衰退の様相を呈した」(井上進)[13]。
この質量ともに低調な状況が一変したのが、一六世紀半ば以降の明末の万暦年間のことである。この時期に出版文化は空前の活況を呈し、多くの印刷物が巷にあふれた。書物はもはや一部の知識人の独占物ではなくなり、各都市に広く流通するようになった。ちょうど一六世紀以降のヨーロッパでユマニストたちが出版と思想を結びつけ、新しいフォントであるローマン体やイタリック体が普及したように(前章参照)、だいたい同時期の中国でも、版木を彫るときに分業しやすい幾何学的な明朝体のフォントが誕生し、書物の拡大に大いに寄与した。
大木康は当時の「出版革命」の帰結として、書物の形態が大量生産に向いた線装本に変わり、明朝体が生まれ、図像入りの書物が氾濫するようになったことに加えて、小説の刊行点数が爆発的に増加したことを挙げている。それに伴って、出版や批評に積極的にコミットする「出版文化人」(陳継儒、李卓吾、馮夢龍、李漁ら)が台頭し始めた[14]。出版と小説を積極的に活用しながらときに社会の規範に挑戦した彼らを、中国版のユマニストと見なしても、さほど言い過ぎではないだろう。
すでに『三国志演義』や『水滸伝』は元末明初(一四世紀)の時点で、ある程度作品としてまとまりつつあったが、出版革命の起こった一六世紀以降、出版物として社会に定着する。例えば、『水滸伝』の刊本には複数の系統があるが、そのうち代表的な『李卓吾先生批評忠義水滸伝』(杭州の容与堂刊)は一七世紀初頭に刊行された。それとほぼ同時期の一六一〇年に、『水滸伝』の一つのエピソードを長編にふくらませた『金瓶梅』が出る。『三国志演義』の代表的な刊本である『李卓吾先生批評三国志』もだいたい同時期の刊行物である。
この『水滸伝』や『三国志』を筆頭に、当時の小説はしばしば出版文化人のコメント入りで刊行された。ここから分かるのは、著名な批評家のコメントが作品の付加価値を高めたこと、そして小説が批評=思想の新しい動向と密接に関わっていたことである。これらの小説はたんなる暇つぶしにはとどまらず、出版革命を背景とする先端的な思想運動のシンボルにもなった。
これらの小説の作者は名義上、羅貫中や施耐庵とされているが、彼らの実態は漠然としていて、ほとんど何も分からない。それに比べて、一六世紀後半を生きた李卓吾は、出版界では名高い思想家であった。そのため、彼の名義を借りて、実際には別人が批評を書くケースも多かった(例えば、『李卓吾先生批評忠義水滸伝』の批評家は、李卓吾ではなく葉昼という説が有力である)。後述するように、このパイオニアとしての李卓吾の思想に触発されて、『三国志演義』の改訂版を出した毛宗崗や『水滸伝』に独創的なコメントを付した金聖嘆のような一七世紀(明末清初)の批評家が、この批評=思想の運動を継承することになる。
6、オルタナティヴな近代性
もとより、中国小説の進化は単線的なものではない。明清時代の小説の母胎になったのは、都市の盛り場で活躍した講釈師の種本をもとにした「話本」である。庶民を楽しませるパフォーマンスが印刷文化に入り込み、さまざまな物語が合成されて『三国志演義』や『水滸伝』のような小説が形成された。このような経緯ゆえに、白話小説は書かれたテクストとして確立された後も、おおむね講釈師の口調をまねるような文体で書かれた。
その一方で、清代に「四大奇書」――このネーミングは書店が販促のために設定したものだが――と総称された『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』の表現は、たんなる通俗的な娯楽の域をはるかに超えている。それは出版革命のなかで、小説の作者および読者に本格的な「文人化」が生じ、知識人の教養や趣味が小説に色濃く反映されるようになったためである。民衆の即物的なサブカルチャーと知識人の頭脳的なハイカルチャーが交差したとき、中国の小説は稀にみる豊饒さを獲得した。
この文化間の交差をよく示すのが、『三国志演義』のテクストである。金文京が指摘するように、『三国志演義』は当時のベストセラー小説であったため、各書店が先を争って、独自のアレンジを加えた刊本を世に送り出した。そこには大別して、知識人読者を想定した高級な「江南系」のテクストと通俗的な要素の多い「福建系」のテクストがあり、それぞれが読者を獲得しようと競い合っていた(前出の『李卓吾先生批評三国志』はむろん江南系である)。このうちより多く普及していた福建系の刊本は、海外にも珍品として流出し、今でもスペイン、日本、ドイツ、イギリスの図書館に所蔵されている[15]。さまざまなヴァージョンのテクストを増殖させるこの「出版戦争」一つとっても、当時の小説がいかにハイブリッドな産物であったかがうかがえるだろう。
いずれにせよ、当時の「小説」にすでに高度な思想性や反省意識が込められていた以上、われわれはそれをたんに近代以前の未成熟な文学ジャンルとして片づけることはできない。そもそも、一七世紀初頭は中国文学のみならず世界文学史上の分水嶺と呼ぶべき重要な時代である。『水滸伝』の容与堂本や『金瓶梅』が刊行されたのは、ちょうどスペインでセルバンテスの『ドン・キホーテ』がベストセラーになり、イギリスでシェイクスピアの新作が上演されていた時期に重なっていた。つまり、ヨーロッパでも中国でも、ほぼ同じタイミングで文学史上のブレイクスルーが起こったのである。
ふつうの文学史は、中国や日本に関しては、一九世紀以降の西洋文学との出会いを「近代化」の指標として位置づける。そうすると、それ以前の近世は未成熟な「前近代」の段階として処理されざるを得ない。しかし、ひとたび西洋中心主義的な史観を脱して、≪世界文学≫の視野から考えるならば、むしろスペインでもイギリスでも中国でも、だいたい同じ時期に「小説」が勃興したことの重要性が了解されるだろう[16]。
しかも、爆発的に増加した中国の出版物は、国外にもまるでウイルスのように流出した。日本や朝鮮はもとより、ヨーロッパにも中国の小説は入り込んだ。『三国志演義』の福建系テクストが航海の土産としてヨーロッパに持ち帰られただけではなく、一八世紀初めのイギリスでは明末清初(一七世紀)の『好逑伝』が英訳され、その英語版をもとにしたヨーロッパ各国の翻訳版も大いに好評を博した。一九世紀のゲーテが≪世界文学≫の到来を予感したのも、清の小説を読んだことがきっかけであった(第一章参照)。つまり、一六世紀中国の出版革命はたんに中国小説の進化の起爆剤になっただけではなく、≪世界文学≫というアイディアの成立にも不可欠であった[17]。
われわれは≪世界文学≫という座標の採用によって、「近代」をより広い時間的・空間的な幅をもって捉えることができる。近代をヨーロッパ小説に限定することをやめれば、文学の進化史における複数の近代化のルートが浮かび上がってくる。中国小説が重要なのは、まさにそれがオルタナティヴな近代の可能性を指し示しているからである。
7、『水滸伝』の政治学と倫理学
中国小説のモダニティを考えるとき、その里程標と呼ぶべき作品は、宋代を舞台とした第一級のピカレスク・ロマン『水滸伝』である。数ある小説のなかでも、『水滸伝』は早くから別格の存在として扱われてきた。
繰り返せば、『水滸伝』は一種の集団制作であり、かつ長期にわたって形成されてきた小説である。ただ、その伝承のプロセスにおいて『水滸伝』の本文テクストは総じて尊重され、不用意な修正を受けることは少なく、むしろ慎重な校訂作業を施されて刊行された。むろん、この小説の後半部が精彩を欠くことを理由に、テクストを大胆に「腰斬」して前半の七〇回だけにして刊行し直した一七世紀の金聖嘆のような批評家はいるが、そのケースが突出して目立つほどに、『水滸伝』はいわば小説の聖典として大切に伝承されてきた[18]。
スペインのピカレスク・ロマンが近代の一人称小説の先触れとなったように(第二章参照)、市民社会とその外部のボーダーラインにいる「好漢」が活躍する中国の『水滸伝』も、中国小説に最大のブレイクスルーをもたらした。自ら望むことなく犯罪者になってしまった好漢たちは、国家の論理に盾突くアウトサイダーとして生き延びる。その結果、それまでの士大夫の文化において逸せられてきた社会的階層が、『水滸伝』ではかつてない輝きを帯び始めた。
ここで特筆すべきは、その職業の多様性である。もとは胥吏(政府と民衆を仲立ちする事務職)であった宋江が、梁山泊の並み居る好漢たちのリーダーになる一方、泥棒、軍人、名家の若旦那、漁師、鍛冶屋、印鑑職人、書道家、居酒屋のおかみ、力士、薬売りなどの多様な職業人が『水滸伝』のダイナミズムの源泉となった。このような百科全書的な書き方は、それ以前には『史記』を除いて他になかったし、それ以降もほとんどない。『三国志演義』が古代国家の英雄たちが競い合う歴史小説だとしたら、『水滸伝』は近世市民の生活に根ざしながら、国家というシステムそのものとの対立を描き出す、前例のないレジスタンス小説であった。
面白いことに、『水滸伝』の多様な職業人たちは、アウトサイダーの世界(江湖)との接触によって、神話的な存在に生まれ変わる。好漢たちには『三国志演義』の関羽や諸葛亮をはじめ、しばしば先行する英雄たちにちなんだ綽名がつけられたが、これは『水滸伝』の人間たちが物質の世界と神話の世界にまたがっていることを意味する。つまり、普段はこれといって特徴のない小役人や村のインテリが、犯罪をきっかけとして、過去の英雄のイメージを記号としてまとった好漢に変身する――しかも、その輝かしい神話の世界は、兄弟的な絆によって固く結ばれていた。
劉備、関羽、張飛が義兄弟の契りをかわす「桃園結義」で開幕する『三国志演義』も含めて、近世中国の小説にはしばしば、国家の垂直的な君臣関係とは異なる、水平的・兄弟的な「侠」の倫理が刻印されていた。弟の関羽が呉の孫権に討たれたとき、劉備があらゆる合理性をなげうって敵討ちを優先させたのは、まさにその倫理のなせる業である。『水滸伝』はこの「侠」の価値観をデフォルメし、好漢たちの義兄弟の関係を百八人にまで増幅させた。彼らが集う梁山泊は、国家とは異なる倫理システムのもとで築かれたユートピアなのである。
しかし、『水滸伝』の後半になると、梁山泊の好漢たちは朝廷に帰順し、むしろ国家の忠実な尖兵として生き始める。このアウトサイダーからインサイダーへの変身は、梁山泊の軍団をやがて崩壊に向かわせることになった。特に、強大な反乱者である方臘の征伐において、多くの好漢は戦死し、彼らのアウトサイダーとしての輝きは衰滅してゆく。水平的・兄弟的な「侠」が垂直的・国家的な「忠」に組み込まれたとき、それは悲劇に行きつかざるを得なかった。この二つの倫理のクラッシュを描き出した『水滸伝』は、政治学や倫理学の書物としての性格をもつ[19]。
そもそも、金文京が強調するように、近世の中国小説には知識人の「世界認識」が託されている[20]。例えば、『三国志演義』の冒頭には「そもそも天下の大勢は、分かれて久しくなれば必ず合一し、合一して久しくなれば必ず分かれる[分久必合、合久必分]のが常である」という認識が記される。英雄たちの行動は、この循環論的な歴史哲学のデモンストレーションとして展開された。なかでも、小説後半の事実上の主人公となる諸葛亮は、この哲学を体現する政治家と見なせるだろう。実際、彼が劉備に説いた「天下三分の計」は、まさに「分」の状態を生き延びるための地政学的な均衡理論にほかならない。
それと同じく、『水滸伝』の政治や倫理も「分」の一歩手前の不穏な時代の世界認識になっている。この点で、中国小説には危機の時代の思想書としての一面があった。
8、カーニヴァル的な白話文体の成立
繰り返せば、近世の中国小説は、文人的なハイカルチャーと通俗的なサブカルチャーを融合させた文化革命の産物である。それは従来『史記』のような史書が担っていた役割を肩代わりしつつ、複製技術(出版)の力によって、いっそう幅広い読者を魅了した。このハイブリッドな性格ゆえに、それまでの知識人の文学では逸せられてきた市民生活が、そこでは生き生きとした筆致で再現された。特に、『水滸伝』の主役は、その分厚い物質的世界にあると言っても過言ではない。
好漢たちは大酒を飲み、実においしそうに大皿の肉を食らう。その旺盛な食欲が、『水滸伝』のエピソードを推進するエンジンになっていることは明らかである。さらに、彼らが「人肉」を食らったり人間の肝臓をささげたりするカニバリズムのモチーフも、読者には忘れがたい印象を与えるだろう。『水滸伝』的人間たちは誰もが物質の世界に深く関わっており、ときには自らが物質そのものに変貌する。例えば、好漢の魯達――後に出家して魯智深を名乗る――が、悪徳の肉屋を凝らしめるつもりがうっかり殴り殺してしまう有名な場面は、次のように派手な祝祭として描き出された。
ぽかりと一発、ちょうど鼻の上を殴りますと、殴られて真赤な血が吹き出し、鼻は横っちょへひんまがり、まるで味噌醤油屋の店開き、しょっぱいの、酸いの、ひりひり辛いの、一時にどっと溢れ出しました。肉屋はもがき起きる力もなく、かの庖丁もそばにほうり出したまま、口でただ、
「よくもやったな。」
とわめくばかり。魯達、どなりつけ、
「こん畜生、まだ口ごたえする気か」
と拳骨ふりあげ、瞼のあたり、眉尻へ一発、打たれて目のふち裂けほころび、目の玉飛び出し、まるで呉服屋の店開き、赤いの、黒いの、猩猩緋、一時にどっと溢れ出しました。両側の見物たちは、魯隊長が恐ろしくて、仲裁にはいろうとする者はだれもありません。(第三回/以下『水滸伝』の引用は岩波文庫版[吉川幸次郎・清水茂訳]に拠る)
庖丁で赤身や脂身の肉を刻んだばかりの肉屋の主人が、ここではあっという間に、味噌、醤油、呉服に似た物質に変身させられる――この残酷ではあるが、底抜けに明るい場面は、ミハイル・バフチンがフランソワ・ラブレーの『ガルガンチュア』や『パンタグリュエル』に即して述べた「カーニヴァル小説」の特性を思い出させる。
バフチンによれば、ラブレーの小説は民衆的なカーニヴァルの伝統とつながっている。そこには身体をバラバラにするような解剖学的記述が連発され、ときにそれは料理のモチーフにも通じていくが、そのグロテスクな記述は死や停滞ではなく、むしろ世界の「成長」や「増殖」を促し、そこに新たな活力を与える。ラブレーは「世界の陽気な物質」としての身体=肉を、民衆的な祝祭の枠組みを借りながらたえず創造し続けた[21]。バフチンはこのようなカーニヴァル小説を、世界の多産性に鮮烈な光を当てるための技法として捉えたのである。
このラブレー的な陽気さは、『水滸伝』の前半部の端々に認められる。『水滸伝』はたんに好漢たちの食をリアリスティックに再現しただけではなく、世界を別のものに生まれ変わらせる物質的な「力」を発明した(ここに古代の「興」の詩学を重ねあわせることも、あながち不可能ではないだろう)。魯智深の拳骨のシーンは、物質を勢いよく噴出させ、見物人たちを圧倒する陽気なカーニヴァルなのである。『水滸伝』では、肉や酒を売り買いする都市の日常生活が、世界と人間をたえず生まれ変わらせる契機になった。ここには、国家の押しつけるモラルよりも、物質の世界に根ざした民衆のアモラル(非道徳)な力を評価するという倫理の方向性がはっきり示されている。
さらに、この停滞や疲労を知らないダイナミックな祝祭性が、迅速に進む文体によって支えられていることも見逃せない。例えば、武松が虎と対決する場面は、その活気溢れるスピーディな実況中継によって名高い。
虎の方はひもじくもあり、のどが渇いてもいます。二つの足で地面をかくと、身体ごと上へ跳びあがり、空中から跳びかかってきます。武松、びっくりした拍子に、酒はすっかり冷汗となって出てしまいました。いえばおそいが、動作ははやく、武松、虎が跳びかかって来るのを見て、ひらりと身をかわし、虎のうしろにまわりました。虎というものは、うしろに人をまわるのが何よりの苦手、つと前足で地面をおさえ、腰をずっとはねあげて来ますのを、武松ひらりと身をかわし、かたえにのがれました。虎、はねあげそこねたと見るや、おうっと一声、まるで中空に雷が鳴ったよう、かの岡さえもゆれ動く中を、鉄棒にも似た虎の尾をさかさまに立て、さっとひとなぎするのを、武松又もやかたえにかわします。(第二三回)
武松の迅速な行動を評した「説時遅、那時快(語れば遅いが、動きは早い)」(第二三回、第二九回)という名文句は、まさに『水滸伝』の文体の特徴をつかんでいる。ナレーターの語りでは追いつけないほどの速度で好漢たちが動き出し、まるで読者の眼前に迫ってくるかのような文体――現代ふうに言えば、それはテクストからキャラクターが飛び出してくる一種のVR体験のようなものに近かっただろう。
このように、魯智深や武松のアクションには『水滸伝』のカーニヴァル的な性格が濃縮されているが、それは『水滸伝』を特徴づける口語的な文体、つまり「白話文」と切り離せない(なお、白話文は言文一致文と同じではない――白話とはあくまで口語を洗練させた人工的な書き言葉であり、だからこそ異なる方言を話す諸地域にまで流通したのである)。『水滸伝』のスピーディな展開は、白話文のぶしつけな即物性なしにはあり得なかった。
もとより、口語を文章語としてうまく仕立てるのは、並大抵のことではない。『三国志演義』は伝統的な文言文をベースとするため、それを読み書くときの障害はさほど大きくなかった。それに対して、白話文はまだ書き方が確定しておらず、それを知識人が満足できる水準に引き上げるのは難事業であった。にもかかわらず、『水滸伝』はこの新興の白話文をいきなり高度な文体に飛躍させ、それまでの文言文では到底書けない祝祭的・物質的な世界を象ってみせた。内容的にも文体的にも大きな革新をもたらした『水滸伝』が、多くの前衛的な文人に愛好されたのは不思議ではない。
9、批評の新しいプログラム――真実・虚構・生成
白話文という新しいスタイルを高度な表現にまで高めた『水滸伝』は、まさにそのことによって「思想書」としての一面をもった。『水滸伝』をどう読むかという問題こそが、中国の文芸批評と思想を飛躍させたと言っても過言ではない。かつて班固が記録したストリートの散発的な「小説」とは違って、一六世紀明末の小説は強力な思想的磁場のなかにあった。
先述したように、当時の小説批評においては、出版文化人として活躍するものの、迫害されて獄中自殺した明末の李卓吾(李贄)がシンボリックな存在となったが、彼の思想は陽明学左派の泰州学派に属する。王陽明をパイオニアとする陽明学は「心学」と呼ばれる通り、外部の規範や道徳よりも、内なる心こそをより本源的なものと見なす、中国では異例のアヴァンギャルドな思想であった。
王陽明の死の二年前、一五二七年に福建の泉州で生まれた李卓吾(一説にはイスラム教徒の家系と言われる)はこの思想運動を引き継いで、旧来の絶対化された経書(聖人の考えを記したとされる正統的なテクスト)についても「六経はみな史なり」として歴史的限界をもつと見なし、むしろ自らの心の赴くままに多様な書物を読みふけった[22]。一六世紀の福建が小説の一大生産地であったことも、この自由な読書生活を後押ししただろう。陽明学という思想運動は、出版革命を背景としながら、知識人の書物との関わり方を大きく変えたのである。
現に、この李卓吾の名義を小説のブランディングに用いた文芸批評家たちは、内なるピュアな心(李の言う「童心」)の真実をことのほか重んじた。「真」は『水滸伝』をはじめ、当時の小説の批評を導くキーワードとなった。例えば、『李卓吾先生批評忠義水滸伝』のコメンテーター(葉昼か)の評によれば、『水滸伝』はもとよりフィクションではあるが、その描写は「真情」から出たもので、天地とともに生じたようなものであり、その文章の最大の長所は人間的感情への肉薄にある――ここには『水滸伝』を英雄物語としてではなく、むしろ真実味のある人情小説として読み解こうとする方向性が鮮明にされていた[23]。
さらに、このコメンテーターは、魯智深や武松ら多くの好漢たちの描かれ方が「同じであって同じではない」ことに注目する。彼らはみなせっかちで、気性の荒いキャラクターだが、その個性がきっちり描き分けられているため印象が混ざりあうことがなく「眼前」にいるかと錯覚するぐらいに真に迫っている[24]――この指摘から分かるのは、『水滸伝』がまさに人物や風景が鮮明にポップアップするVR的なテクストとして受容されたことである。
しかも、ここで面白いのは、この真実性の追求が虚構性の評価と両立したことである。つまり、必ずしも歴史的事実に拠らないフィクションが、かえって人間の「真」を浮かび上がらせるという新しい逆説が出てきたのである。そこには当然、出版革命を経た複製技術時代の到来が大きく関わっているだろう。さまざまな種類の書物が巷に溢れるようになったとき、テクストの批評基準も否応なく変わらざるを得なかった。
この「歴史性から虚構性へ」あるいは「歴史性から真実性へ」という大きな変化を体現するのが、一七世紀最大の文芸批評家・金聖嘆である。一六〇八年に生まれた彼は『水滸伝』を筆頭とする白話小説や戯曲を、過去の古典と並ぶ傑作として「正典化」した。この新たな価値判断の背景にあったのが「史記は文をもって事を伝え[以文伝事]、水滸は文によって事を生ず[因文生事]」という有名な見解である。金聖嘆はたびたび『水滸伝』を『史記』になぞらえたが、その両者の違いも言い当てようとした。彼の考えでは、『史記』の文が歴史的事実を伝達するのに対して、『水滸伝』の文はフィクションを新たに生成する力をもつ――ちょうど二一世紀の生成AIが高度に自律した言説を作り出すように。金聖嘆ら批評家たちは、いわば『水滸伝』にそれまでのテクストとは異質の知能を見出し、その魔術の秘密を探ろうとしたのである。
このような批評の出現は、虚構がそれ自体として評価されるようになったことを意味する。しかも、それは『水滸伝』が「真」に迫る小説であったことと何ら矛盾しなかった。金聖嘆にとって『水滸伝』の長所は、非現実的な怪異現象を語らず、あくまで人間世界の真実に接近したことにあった。彼は『西遊記』があまりにも空想的で荒唐無稽であり、『三国志演義』があまりにも歴史に拠りすぎているのに対して、『水滸伝』はこの両者の中間で最良のバランスをとっていると評価した[25]。ここからは、真実性と虚構性の両立が批評の新たなプログラムとなったことが分かるだろう。
もとより、中国の小説が完全に「歴史離れ」することはほとんどなかった。例えば、『三国志演義』の代表的な批評家である毛宗崗は、金聖嘆に反して、むしろ「歴史化」の方向へと舵を切った[26]。彼の考えでは『三国志演義』は総じて史実に忠実であり、だからこそ『水滸伝』よりも高く評価されるべき小説であった。いずれにせよ、ここで重要なのは、さまざまなタイプの批評に対応できるほどに、当時の小説のメニューが多様化していたことである。歴史をどう捉えるべきか、虚構をどう評価するべきかというテーマは、小説の世界認識に即して展開されていた。
10、家庭小説の系統――『金瓶梅』から『紅楼夢』へ
ところで、中国小説の世界認識のあり方を考えるとき、『水滸伝』や『三国志演義』のような軍事的・外向的な小説に加えて、日常生活のエロスをとめどなく増幅させてゆく『金瓶梅』や『紅楼夢』のような家庭的・内向的な小説があったことが重要である。ただ、こちらの系統の小説は後の章でも扱うので、今は概略的な説明にとどめよう。
『金瓶梅』は一人の作者によって書かれた、中国で最初の長編小説である。『水滸伝』や『三国志演義』が長期にわたって徐々に形成された集団的な制作物であったのに対して、『金瓶梅』は最初から最後まで、蘭陵笑笑生を名乗る一人の作者――その正体は定かではない――の意向が貫徹されており、文学史上の意義はきわめて大きい。
そうは言っても、『金瓶梅』が完全にオリジナルの作品というわけではない。それどころか、それは『水滸伝』の有名なエピソードを百回本の規模に膨らませた小説、現代ふうの言い方をすれば『水滸伝』の長大な「二次創作」である。『水滸伝』では武松が兄嫁の潘金蓮および彼女と密通したプレイボーイの西門慶を討ち果たして、二人に謀殺された兄の仇をとる。それに対して、『金瓶梅』ではむしろこの悪役にされた西門慶の家庭を舞台として、潘金蓮、李瓶児、龐春梅という三人をはじめとする、女性たちとの性生活が描かれた。
もっとも、それをポルノ小説として片づけるのは正しくない。むろん、『金瓶梅』に性的な要素は不可欠であるとはいえ、それはあくまで一部であり、小説の多くは、日々の衣食住や接待、折々の行事等を、驚くほどの高精細度で象った記述で占められている。『金瓶梅』とはある意味で、人間以上に物質が主役となった小説である。『三国志演義』の英雄たちがもっぱら軍事的な戦略で動くのに対して、『金瓶梅』の市民たちは物質的な戦略によって自らの優位性を築こうとするのだ。
中国文学者のマーティン・ホアンが指摘するように、『金瓶梅』では寝室でのスキルやディーラーとしての能力がものを言う。これほど物質性や経済に密着した中国小説は、ほとんど類例がない。しかも、衝立やブラインドのような小道具を配した『金瓶梅』の文体は、プライヴェートな家庭生活をのぞき見するような錯覚を生み出した[27]。もともと『水滸伝』にも食を中心とするカーニヴァル的な物質性が描かれていたが、『金瓶梅』は『水滸伝』の陽気な物質性を、より家庭的な次元に置き直し、そこにまといつく欲望のありさまをくまなく照らし出した。『水滸伝』が梁山泊という目的地に向けて積分的に書かれたのに対して、『金瓶梅』はミクロな家庭生活を微分的に解き明かしたのである。
しかも、この恐るべき小説には、物質生活の爛熟のもたらす快楽と退廃は底なしであり、救済の可能性はどこにもないというメッセージが隠れている。西門慶たちは確かに性生活を享楽しているが、その快楽の世界は決して幸福にはつながらず、最後には破局を迎える。この暗い結末は、すでに『水滸伝』でも描かれた、国家(宋)の末期的な光景にも接続されていた(第七十回)。腐敗した高官に牛耳られた宋の政治は、もはや修復不可能であり、やがて女真族の金に蹂躙されることが確定している。『金瓶梅』においてはミクロな家庭もマクロな国家も、ともに未来の地獄を避けることはできない。
この『金瓶梅』のデカダン的な家族小説としてのプログラムを一世紀以上後に引き継いだのが、一八世紀(清)の作家・曹雪芹の『紅楼夢』である。フランスのルソーやディドロと同世代人である曹雪芹(一七一五年頃生まれ)は、多くの女性たちが取り仕切る大観園を舞台として、父権的な中国社会のパロディをやったと言えるだろう。
『金瓶梅』が市民的な家族生活のディテールに着眼したのに対して、『紅楼夢』は貴族の大邸宅である「大観園」を舞台として、思春期の中性的な男性・賈宝玉と少女たちとの戯れを延々と描き続けたが、これは明らかに時代錯誤的な設定である。この時期の中国の漢人社会では、すでに大家族のモデルは実態にあわなくなっており、家族を束ねる「礼」も形骸化しつつあった[28]。曹雪芹はこの大家族の理想の終わりを予感しながら、むしろそれを「虚構」として温存する道を選んだ。
繰り返せば、真実性と虚構性の追求というプログラムは、一七世紀の金聖嘆においてすでに高まっていたが、一八世紀の『紅楼夢』はその思想運動のピークと呼べる小説である。甄士隠(真事隠と同音)と賈雨村(仮語存と同音)の交友から始まるその物語は、虚構(仮語)のなかに真実が隠れるという『紅楼夢』のアレゴリーの説明となっている。その後も、真(まこと)と仮(うそ)のあいだの戯れは作中で何度も繰り返された。序盤で賈宝玉が訪れる「太虚幻境」(神仙のユートピア)のゲートには、すでに次の謎かけ的な聯が記されていた。
仮の真となる時、真もまた仮
無の有となる処、有もまた無
(第五回/以下『紅楼夢』の引用は平凡社ライブラリー版[伊藤漱平訳]に拠る)
真実が虚構であり、虚構が真実であるというこのメッセージには『紅楼夢』の思想が凝縮されている。と同時に、それは明末以来の小説批評への絶妙の応答にもなっていた。李卓吾以降の批評家たちにとって、小説の使命は、虚構性を利用して真実性を追求することであった。曹雪芹はまさにこの二つのヴェクトルを戯れさせながら、『紅楼夢』を書いたのである。
ゆえに、『紅楼夢』のなかで、歴史書をモデルとする小説への批判があるのも不思議ではない。実際、その第一回では、すでに陳腐化してしまった才子佳人小説と並んで、歴史書のような小説が批判の槍玉にあげられている。歴史的な事実に縛られた伝統的なスタイルを超えて、人間的感情の真実を浮かび上がらせること――それが『紅楼夢』の戦略であり、その拠点となった大観園は、粋を凝らした中華文明のテーマパークのような様相を呈していた。
ロココ的な繊細優美な虚構のユートピアとしての大観園――しかし、『紅楼夢』の著者はそれを破綻させずにはいなかった。社会的現実から隔離された大観園というテーマパークは、ついに経済的苦境に陥って消滅に到り、賈宝玉のモラトリアム生活も終わりを告げる。仮と真の戯れはいずれ衰滅する――このことは『紅楼夢』の設計した虚構(仮)の空間そのものの限界を指し示していた。
11、東西文学の「大分岐」
私はここまで漱石の『文学論』を起点として、中国小説の進化史についての簡単なデッサンを試みてきた。歴史書とも思想書ともつかないあいまいなジャンルであった小説から、明清時代になるとやがて作品どうしの内的な対話が生じる――すなわち、『水滸伝』は『三国志演義』に潜在していた男性たちの「侠」の倫理を、肉や酒を伴う陽気なカーニヴァル小説において再創造した。『金瓶梅』がその『水滸伝』の物質生活をドメスティックな家庭生活の次元に置き直したとすれば、『紅楼夢』は『金瓶梅』の欲望のドラマを、より貴族的で洗練されたユートピア小説へと転換させた。このような活発な相互批評性は、当時の小説が先端的な思想運動であったことを物語っている。
ならば、この豊饒な中国小説の文化が、その後ヨーロッパ小説に圧倒されてしまったのはなぜなのか。この問いに答えるのは一筋縄ではいかないが、その理由の一つとして、一八世紀に起こった変化を見逃すことはできない。
第一章で述べたように、ケネス・ポメランツは一七五〇年頃の「大分岐」を境にして、ヨーロッパ経済が東アジアの経済を凌駕し始めると論じた。この歴史観は小説の進化を考えるのにも有益である。『紅楼夢』はだいたい一七五〇年代に書き継がれ、三〇年ほど手書きの写本として流通した後、曹雪芹死後の一七九一年にようやく出版物として刊行されたという、異例の展開をたどった小説である。このプロセスはまさにグローバルな「大分岐」が進みつつあった時代、つまり中国の版図が乾隆帝のもとでピークに達するものの、その後は成長が飽和し始める時代と重なっている。
中国はヨーロッパのような広大な海外植民地をもたなかった。ポメランツの考えでは、それがヨーロッパとの格差を広げる要因となった。このような社会状況の違いは、小説の内容にも反映されている。同世代のディドロが『ブーガンヴィル航海記補遺』で南太平洋のタヒチ島からヨーロッパ文明を批判的に照射したのと違って、曹雪芹はあくまで中国大陸に内在し、そこに中華文明の想像上のテーマパークを作った。『紅楼夢』はそれまでの中国小説の進化の総決算であり、かつその進化の飽和を暗示する小説なのである。
ゆえに、一八世紀ヨーロッパの初期グローバリゼーションが「新世界」の探索を背景としながら、他者を探し求めるジャンルとして小説を再創造したことは、決定的な意味をもつと言わねばならない。それを下地として、一九世紀のヨーロッパ、アメリカ、ロシアでは小説の黄金時代が訪れ、小説の世界的なパンデミックが促された。逆に、ユートピア的想像力を総じてドメスティックな次元にとどめた中国からは、一八世紀の『紅楼夢』に質的に匹敵するだけの白話小説は出てこなかった。中国の作家たちはおおむね「新世界」を内部に求めるしかなかった。この抑え込まれた想像力が再び解放されるには、二〇世紀初頭(清末)まで待たねばならない。
漱石の『文学論』は、このような小説の進化史の果てに書かれた理論書である。もし『紅楼夢』を凌駕するような小説が一九世紀の中国で書かれていれば――あるいは虚構の自律性をいっそう強く推進する批評家が出ていれば――、漱石の書き方は恐らく根本的に変わり、中国文学を「左国史漢」という歴史書のモデルで代表させることもなかっただろう。その意味で、中国小説への言及を欠いた彼の『文学論』は、東西文学の「大分岐」の帰結なのである。
[1]さらに、漱石自身の長編小説ももっぱら「二〇世紀」(これは漱石文学のキーワードである)の日本を舞台にし、歴史小説は一つもない。のみならず、彼の時間感覚は「百年待っていて下さい」(『夢十夜』)という言葉に象徴されるように、しばしば運命論的=超歴史的な位相へと飛躍した。『渋江抽斎』をはじめ史伝を手掛け、「歴史其儘と歴史離れ」という方法論的な評論も残した鷗外と比べると、もっぱらコンテンポラリーな現実に照準しながら、しばしば時間を神秘化した漱石の特性は、いっそうはっきりするだろう。
[2]吉川幸次郎『中国文学入門』(講談社学術文庫、一九七六年)八四-五頁。
[3]目加田誠『詩経』(講談社学術文庫、一九九一年)二五一頁以下。アリストテレス以来の西洋哲学が再現的な「ミメーシス」(模倣)を重視したのに対して、中国ではむしろ人間や天地を強く動かす「興」を詩論の中心に据えた。この点は羅青『興之美学』(初文出版社、二〇一八年)で詳述されている。「力をも入れずしてあめつちを動かし」という日本の『古今集』仮名序の汎心論的な詩学も、中国の「興」の詩学と無関係ではない。
[4]Sheldon Hsiao-Peng Lu, From Historicity to Fictionality, Stanford University Press, 1994, p.42-3. その後、唐代に編纂された『隋書』経籍志にも「小説家」という部門は引き継がれた。
[5]ロラン・バルト『物語の構造分析』(花輪光訳、みすず書房、一九七九年)二頁。
[6]小川環樹「中国散文の諸相」『小川環樹著作集』(第一巻、筑摩書房、一九九七年)所収参照。さらに、陳平原『中国散文小説史』(上海人民出版社、二〇〇四年)もやはり「記事」と「記言」の系統を整理しつつ、中国の散文の変容がいかに小説の展開と結びついたかを、詳しく跡づけている。
[7]夏志清『中国古典小説』(何欣他訳、聯合文学出版社、二〇一六年)が指摘するように、『三国志演義』における人間の描写は戦前に集中していて、戦争そのものにではない。赤壁の戦いはまさにその典型であり、戦前の細かい駆け引きや計略こそがむしろストーリーの核心なのである(一〇八頁)。
[8]陳洪『中国早期小説生成史論』(中華書局、二〇一九年)一〇八頁以下。
[9]Sarah M. Allen, Shifting Stories: History, Gossip, and Lore in Narratives from Tang Dynasty China, Harvard University Asia Center, 2014, p.1.
[10]Lu, op.cit., p.116.
[11]なお、手書きによる伝承は、テクストの変容を不可避的に生じさせる。例えば、四~五世紀の詩人陶淵明の詩には多くの異本が存在し、どれが正しいテクストかを定めるのは困難をきわめた。だからこそ、異本の海をかきわけて「真正の陶淵明」を求める欲望が、後世の文人たちにおいて加速した。「真」への渇望は、伝達のエラーの多さとコインの裏表なのである。田暁菲『塵几録』(中華書局、二〇〇七年)一五頁以下。
さらに、メディア論的な見地から重要なのは、八世紀の盛唐の詩人である。例えば、李白は広く愛唱された流行詩人であったため、その詩には陶淵明と同じく多くの異本が存在する。逆に、李白の後輩である杜甫(陶淵明の詩集をテーマとする文芸批評的な詩も残している)は、自作の詩の「定本」を作ろうとした最初の詩人であった。鈴木修次『唐詩』(NHK出版、一九七六年)三〇頁以下。
[12]大木康『中国明末のメディア革命』(刀水書房、二〇〇九年)一九頁。
[13]井上進『中国出版文化史』(名古屋大学出版会、二〇〇二年)一五三、一七八‐九頁。
[14]大木前掲書、三三頁以下。
[15]金文京『三国志演義の世界』(増補版、東方書店、二〇一〇年)二一九頁以下。今でも『三国志』は漫画やゲームになっているが、それも受容層に合わせた「異本」の増殖の例と言えるだろう。
[16]むろん、シェイクスピアは劇作家であって小説家ではない。しかし、彼の作品が特にドイツ・ロマン派の批評において、舞台から独立したテクストとして受容されてきたことも確かである。その点で、シェイクスピアにはプロト近代小説としての一面がある。
[17]その一方、この出版革命の弊害を指摘するヨーロッパ人もいた。東アジアでのキリスト教伝道に尽力した一九世紀のイギリス人宣教師ウォルター・ヘンリー・メドハーストは、大量の印刷物のせいで、中国人の思想が「ステレオタイプ」になり、社会を「永遠の停滞」に落ち込ませたと厳しく批判した。レイモンド・ドーソン『ヨーロッパの中国文明観』(田中正美他訳、大修館書店、一九七一年)一〇八頁以下。このような社会の平均化や停滞が懸念されるほどに、中国では多くの印刷物が溢れていたのである。
[18]小松謙『水滸伝と金瓶梅の研究』(汲古書院、二〇二〇年)八〇頁。なお、『水滸伝』の後半部は後世に付与されたパートなので、金聖嘆による「腰斬」はたんなる恣意的な改変ではなく、むしろアップデートされ続けてきた『水滸伝』をもとのヴァージョンに戻す修復作業とも考えられる。この点は、小松謙『「四大奇書」の研究』(汲古書院、二〇一〇年)二三二頁以下が詳しい。
[19]よく知られるのは、毛沢東による『水滸伝』批判である。彼はしばしば演説のなかで『水滸伝』を引用し、好漢たちが朝廷に帰順したことを敗北主義・修正主義と見なしつつ、革命家はその道をとってはならないと釘をさしていた。彼の主要な著作『矛盾論』でもそうだが、毛は徹底して、政治的有用性の観点から『水滸伝』を読み解いていた。
最近の例で言えば、カール・シュミットやレオ・シュトラウスを中国に導入した思想史家の劉小楓が『≪水滸伝≫与中国古典政治哲学』(四川人民出版社、二〇二〇年)という論文集を編集し、そこで『水滸伝』を政治哲学と接合することを試みた。そこでもやはり「国家の敵」を経て「国家の友」になるという『水滸伝』の弁証法的展開の意味が問われている(七三頁)。
[20]金文京+福嶋亮大「世界認識としての「三国志」」『ユリイカ』(二〇一九年六月号)。
[21]ミハイル・バフチン『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』(杉里直人訳、水声社、二〇〇七年)二四八頁以下。
[22]井上前掲書、二八九頁以下。
[23]葉朗『中国美学史大綱』(上海人民出版社、一九八五年)三六六頁。
[24]同上、三八八頁。
[25]Lu, op.cit, p.138.
[26]金前掲書、一三五頁。
[27]Martin W. Huang, Desire and Fictional Narrative in Late Imperial China, Harvard University Asia Center, 2001, p. 59, 93.
[28]余英時『紅楼夢的両個世界』(聯経出版事業公司、一九七八年)二三九頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年7月7日、7月12日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年8月24日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。