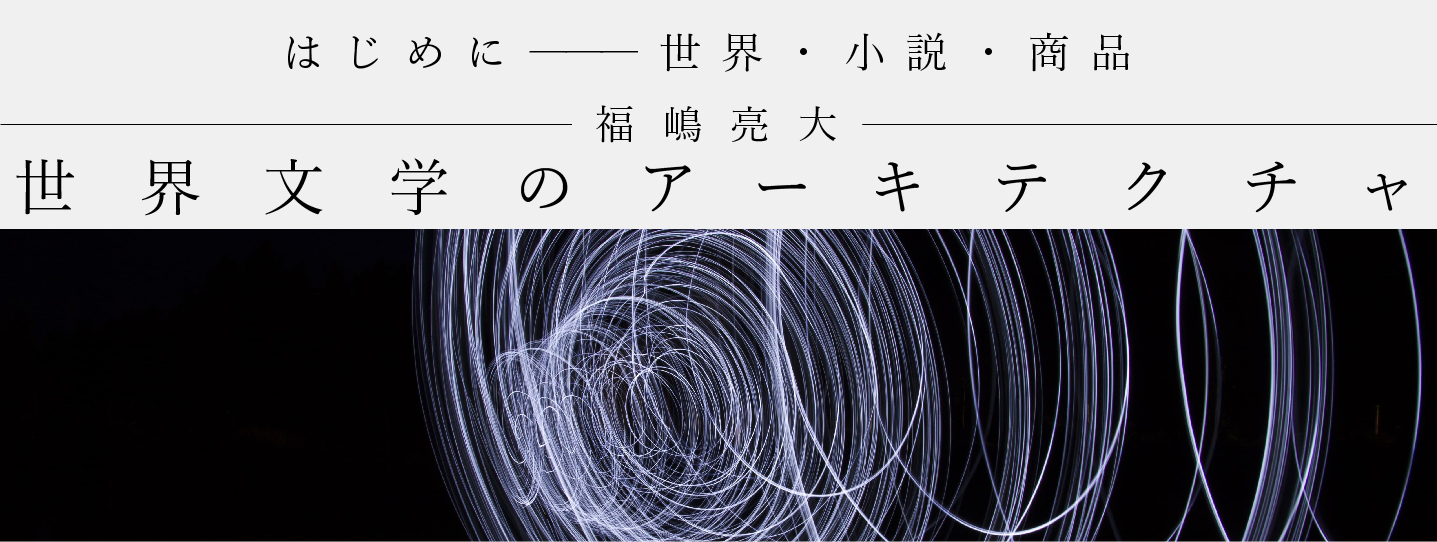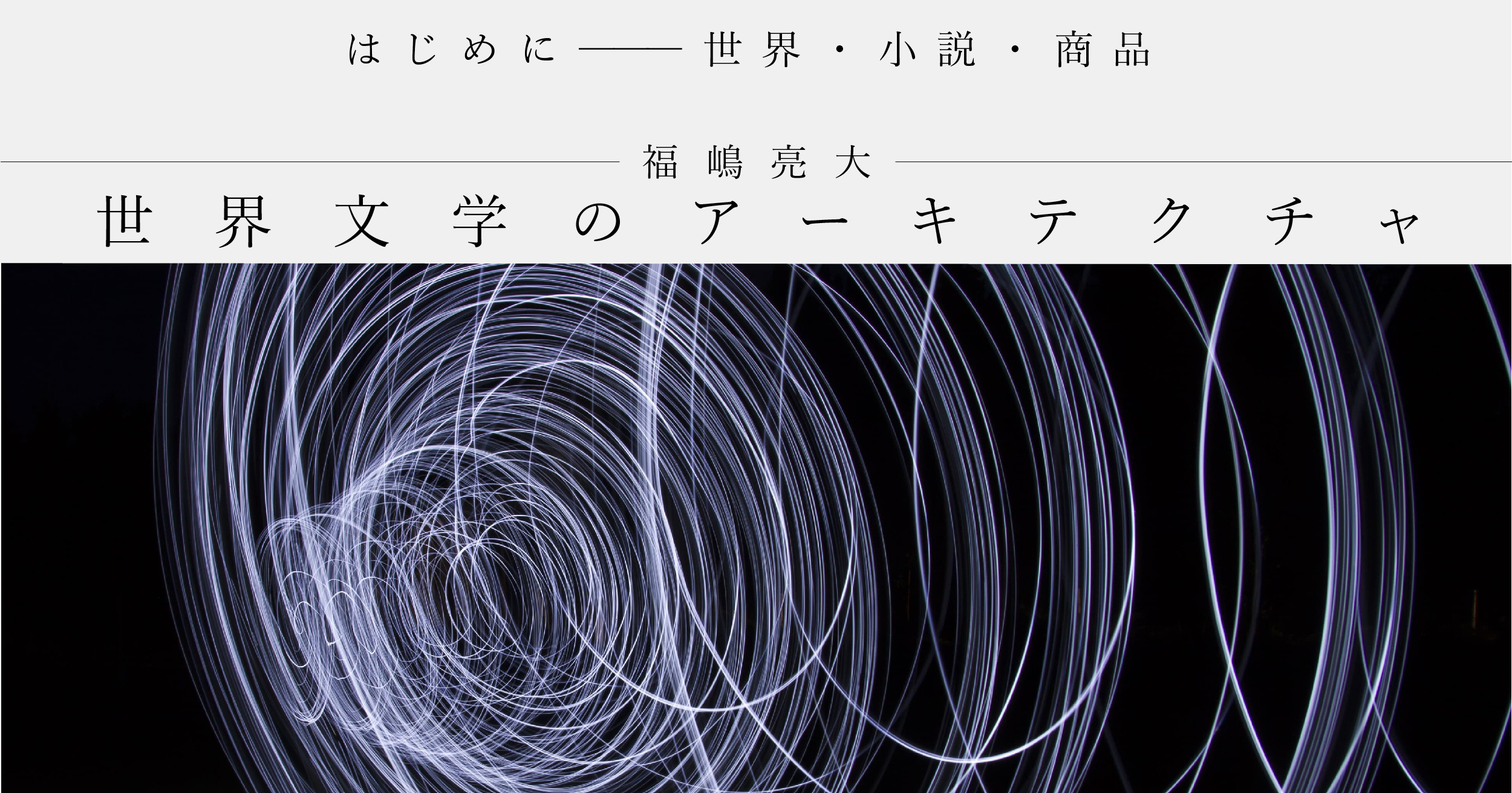批評家・福嶋亮大さんによる「世界文学のアーキテクチャ」。近年のグローバルな文学作品研究において、「世界文学」の概念が用いられるようになりました。もともとは産業革命期の19世紀に誕生したこのワードを手がかりに「小説」と「資本主義」の構造的な類似を分析しながら、「世界文学」としての小説が持つ特徴を理論化していきます。
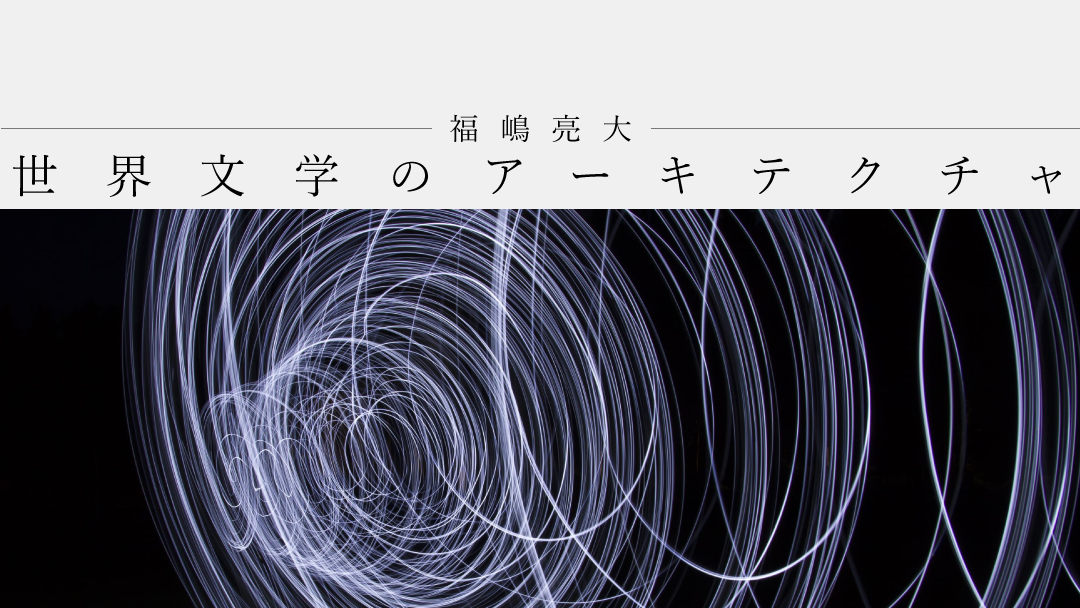
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
私はこの間PLANETS刊の雑誌『モノノメ』に世界文学論を連載してきましたが、それはもともと第一部の理論パートおよび第二部の歴史パートという二部構成を想定していました。ただ、書き進めるうちに、世界文学を理論的対象とするには、まず小説の歴史的な歩みを明確に描き出さねばならないということに気づきました。そこで編集部にお願いして、当初の第二部のプランだけを独立させて、新たなウェブ連載「世界文学のアーキテクチャ」として仕切り直すことにしたのです。そのような経緯があることを初めにお断りしておきます。
1、アーキテクチャとしての世界文学
二一世紀に入ってから、一八二〇年代のドイツでゲーテが語った「世界文学」(Weltliteratur)という概念が、しばしば文学研究の議論の俎上にのぼるようになった。グローバル化に伴って、各国の文学作品がその流通の領域を自国の外へと広げつつある今、西洋偏重の文学史観への反省を含んだ、より包括的な文学理解が要求されているのは確かである。「世界文学」はその要請に応えるために呼び出された一種のパスワードだと言えるだろう。
もっとも、世界文学がいささか捉えどころのない、漠然とした言葉であるのも確かである。われわれはそこから何を引き出すことができるだろうか。例えば、アメリカの比較文学者デイヴィッド・ダムロッシュは『世界文学とは何か?』という著作のなかで、世界文学を文学全体の「ある一つの部分集合」と見なす立場から、次のような考えを示している。
私の考えでは、世界文学とは翻訳であれ原語であれ(ヴェルギリウスはヨーロッパではずっとラテン語で読まれてきた)発祥文化を越えて流通する文学作品をすべて包含する[1]。
ダムロッシュによれば、ある作品が発祥地を超えて異郷で「アクティヴに」存在するとき、その作品は「世界文学」としての資格をもつ。これは植物学的な「移植」(transplant)のモデルに近い。原産地から別の環境に持ち込まれることによって、いっそう繁殖力を増した文学――それがダムロッシュの言う「世界文学」である。彼はこのような生育環境の変更に、きわめて積極的な意味を与えている。「世界文学の領域へ入った作品は、真正さや本質を失うどころか、むしろより多くの点で豊かになりうる。このプロセスを追うためには、特定の状況において作品がどのような変容を遂げるのかをじっくりと見なければならない」[2]。
ダムロッシュはここで、世界文学という概念を、さまざまな国家から移植された文学作品たちで賑わう一種のプラットフォームとして捉えている。このプラットフォームにおいてさまざまな偶発的な「読み」の機会にさらされるとき、作品には思いがけない照明が当てられるだろう。ダムロッシュにとって、世界文学とは各国文学のたんなる総和ではない。世界文学に《なる》ことは、作品を既存の理解の文脈から離陸させ、そこに新たな「実りある生」を芽生えさせる出来事なのである。
このような見解はそれなりに説得力をもつ。文学作品は確かに旅によって自らを転生させるのであり、この旅する文学に「世界文学」という別名を与えることは不自然ではない。この旅には内在的な終わりがないため、世界文学へのエントリーによって、作品にはいわば長い余生の可能性が与えられることになるだろう。さらに、各国の古代文学から現代文学までが「世界文学」という理念的なプラットフォームに登録されれば、作品どうしの関連性や結びつきが変わり、文学の評価をめぐるコミュニケーションにもおのずと変動が生じる。第一章で詳述するように、そもそもゲーテの世界文学論こそが、まさに文学の評価者・翻訳者・伝達者の増大というコミュニケーション革命を前提としていたのである。
もっとも、ダムロッシュが世界文学を評価するとき、しばしば具体性を欠いた、広告的な表現をしがちであることも否めない。例えば「アクティヴに存在する」とか「豊か」であるとか「実りある」というのが、どういう状況を指すのかは判然としない。文学作品の異郷への移植が、その作品の新たな読みの発見につながり得るのは確かだとしても、それを指摘するだけではきわめて平板な言説に留まってしまう。したがって、もしわれわれが「世界文学」という概念の復権を目指すのであれば、まずはその概念の根幹に何があるのかを問わねばならない。
私はここでとりあえず、世界文学という概念を「アーキテクチャ」の隠喩によって捉えたいと思う。英語のarchitectureはもともと「建築」を意味するが、それがコンピュータ科学においては基本的な「設計思想」(一定の手順に基づくデータの処理装置をいかに配置するか、コンピュータのどの部分を最適化するか等)を指す言葉として転用され、その用法が今ではインターネットにまで波及している[3]。いずれの用法においても、さまざまなテクネー(技術)に先立つテクネー、つまりアルケー(始原)のテクネーの力が「アーキテクチャ」として総称されていることに変わりはない。
この概念を世界文学に当てはめてみよう。そうすると、世界文学というアーキテクチャは、たんに各国の作品を陳列する見本市ではなく、むしろ数世紀をかけて形作られてきた設計思想の集積として理解することができるだろう。コンピュータがデータを特定のやり方で処理するように、文学も複雑な心的事象や社会的事象を言語に変換するためのさまざまなプログラムを開発してきた。世界文学の時代の到来とは、これらのプログラムを搭載したアーキテクチャが地球規模で共有されるようになった状況を指している。では、個々の作品を操縦するアーキテクチャは、いかなる歴史をたどって生み出され、成長してきたのだろうか。
もとより、世界文学というアーキテクチャの仕様書があらかじめ作家たちに与えられていたわけではない。しかし、事後的に観測すると、作家たちの仕事を導くプログラムが、各時代においてある程度共有されていたことが浮かび上がってくる。しかも、これらのプログラムはそれぞれの歴史的な軌道のなかで、固有の進化や変遷を遂げてきたのであり、その進化のプロセスは今も終わったわけではない。この点で、世界文学というアーキテクチャは、いわば未完のオープン・システムとして捉えることができるだろう。私がやろうとするのは、このアーキテクチャの進化史を捉えるための理解の通路を作ることである。
2、精神の商品化
本書の狙いは「世界文学」をパスワードとしながら、文学言語を成り立たせる諸々のプログラムを中心として、文学の設計思想の進化史を描き出すことにある。それに先立って、議論の前提として、二つの論点にあらかじめ言及しておきたい。第一の論点は、世界文学が商品経済と連動していたことである。第二の論点は、一八世紀以降の世界文学の中心が小説によって占められたことである。
第一の論点から述べよう。ゲーテが一八二〇年代に世界文学を唱えたとき、世界規模の交通の拡大がすでに彼の視界に入っていた。ゲーテに傾倒していた一八七五年生まれのトーマス・マンは、一九三二年の講演でそのことを的確に指摘していた。
ゲーテの世界文学の提唱のなかには、疑いもなく多くの先取りがありました。そして、彼の死後の百年間の発展、交通の発達、それがもたらした交易の迅速化、大戦によってさえも、停滞させられるよりもむしろ促進されたヨーロッパの、いや世界の緊密化、これらすべてが、ゲーテが今はその時代だと感じた時代を、いよいよ真に現実のものとするためには必須のものであったのでした。[4]
ゲーテの言う世界文学は「交易の迅速化」や「世界の緊密化」と密接につながっている。マンも注目するように、ゲーテ自身、国境を超えた文化の相互浸透を「観念と感情の自由貿易」と言い表していた[5]。このような言い方は、すでにゲーテの段階で、経済的なモデルによって文化の流通が説明できるようになっていたこと、つまり精神の世界と商品の世界が多くの点で重なりつつあったことを示唆している。マンは二つの世界戦争の狭間にあって、この二つの世界がいっそう不可分なものになったと認識していた。
さらに、マンと同世代のフランス人作家ポール・ヴァレリーもまた、やはり大戦間期の一九三九年の論説で「精神の経済」に言及した。ヴァレリーの考えでは、あらゆる「精神的な事象」(科学、芸術、哲学)は今や経済的なものと隣接している。
私が株式取引所の用語を借りて話していることはお分かりだろう。精神的な事象に関して使うのは奇妙にも思われるかもしれない。しかし、他によりよい言葉がないし、多分、この種の関係を表現するのに、捜しても他に適当な言葉はなさそうである。というのは、精神の経済も物質の経済も、人がそれを考えるとき、単純な価値評価のせめぎあいとして考えるのが最も分かり易いからである。
一つの文明は一つの資本である。その増大のために数世紀にわたる努力が必要なのは、ある種の資本を増大させるのと同様で、複利法で増資していくのである。[6]
ヴァレリーにとって、精神の挙動を言い表すのに、経済以上に適格なメタファーはない。これは見かけ以上に大胆な考え方である。彼によれば、精神は宗教的にでも政治的にでも家族的にでも法的にでもなく、あくまで経済的に――つまり商品のように――存在しており、だからこそ生産、消費、交換、増資、流通等のメタファーによって説明することができる。ヴァレリーの考察は、ゲーテの予告した「世界文学」の時代、つまり観念や感情が交易の対象になる時代を、あらゆる精神的現象の地盤として位置づけるものであった(なお、ヴァレリーにはゲーテの『ファウスト』を改作した『我がファウスト』という戯曲もある)。それは、同時期のトーマス・マンの考え方とも明らかに響きあっている。
むろん、このような精神の経済モデルには、いささか単純化のきらいもある。文学一つとっても、そこに経済的次元に還元できないものがあるのは明らかだろう。この問題は小説(散文)以上に詩において、よりいっそうはっきりする。というのも、詩は精神の商品化の傾向に対して、強い抵抗を示す文学ジャンルとしてしばしば評価されてきたからである。
例えば、一八八八年生まれのモダニズム詩人T・S・エリオットは「国民間の精神的な交わり」がなされるには、かえって翻訳困難な詩が必須だと見なした。詩は安易な交換=翻訳を拒絶するからこそ、国民間のより深遠なコミュニケーションの可能性を読者に自覚させることができる。「一言語で言えるだけで翻訳できないすべてのものに、詩はいつも気づかせてくれます」。エリオットの考えでは、ヨーロッパ文学は自給自足ではなく、あくまで「ギブ・アンド・テイク」の関係によって成り立ってきた[7]。その関係を良好なものとするには、他言語を自由に翻訳できるという自惚れよりも、むしろ交換=翻訳を妨げる障害への鋭い感覚こそが必要なのである。
もっとも、エリオットの見解は、文学が商品化の圧力にさらされていることをすでに前提としている。資本主義経済から隔離された文学的な聖域は、もはやあてにできない。だからこそ、エリオットは詩を聖なる祭壇に祭り上げるのではなく、むしろ交換の限界を意識させる文学的実験へと差し向けたのである。ゲーテの言う「世界文学の時代」において、精神はますます商品と似てくる。現代のわれわれもその条件から逃れることはできない。
3、資本主義を引き写す小説
この精神の商品化とも関わることだが、ここでもう一点確認したいのは「世界文学」の中枢がもっぱら小説に占められたことである。むろん、世界文学には詩や演劇も含まれる。しかし、文学の「世界化」は小説の力なしにはあり得なかった。疫学的な隠喩を使うならば、小説は主としてヨーロッパに起源をもち、一八世紀から一九世紀にかけて世界的なパンデミックを引き起こしたウイルス的存在になぞらえられる(詳しくは第三章参照)。世界文学というアーキテクチャは、ウイルスとしての小説をその主要な構成要素とした。
興味深いことに、小説の挙動は資本主義の挙動と近似的である。例えば、世界システム論の提唱者であるイマニュエル・ウォーラーステインは、資本主義を「万物の商品化」のプロセスとして捉えている。
史的システムとしての資本主義は、それまでは「市場」を経由せずに展開されてきた各過程――交換過程のみならず、生産過程、投資過程をも含めて――の広範な商品化を意味していたのである。いっそうの資本蓄積を追求しようとした資本家たちは、経済生活のあらゆる分野において、いっそう多くのこうした社会過程を商品化してしまうことになった。[8]
ウォーラーステインの考えでは、資本主義はその固有の歴史において「社会過程の広範な商品化」のプロセスを継続してきた。その結果として、空気や水はもとより、ゲノムや感情のような不可侵と思われる対象ですら、市場で流通する商品となる。資本主義の浸透によって、われわれは世界の全体を商品の形態において捉えるようになった。資本主義社会の人間は、他の人間を、取引可能な商品の担い手として認識するようになるだろう。
資本主義のもたらした広範な商品化に似たプロセスは、小説のプログラムにも内包されている。すなわち、小説を書き進めると、そこにはしばしば交換過程、生産過程、投資過程に似たプロセスが発生することになる。
例えば、一八世紀には多くの書簡体小説が書かれたが、それはまさに手紙のやりとりという私的なコミュニケーション、つまり外部からは本来うかがい知れない秘密めいた交換過程を再現したものであった。例えば、一七六一年に刊行され、当時屈指のベストセラーとなったジャン・ジャック・ルソーの『新エロイーズ』では、令嬢ジュリとその家庭教師で平民のサン゠プルー、およびその周囲のひとびとの手紙の交換が、感情のテレパシー的な共鳴現象へと発展する。
この『新エロイーズ』のおよそ半世紀前に、イギリスではダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(一七一九年)が刊行されていた。その主人公クルーソーはいわゆる「経済人」(ホモ・エコノミクス)のモデルとして、マルクスやマックス・ヴェーバーのような後世の理論家たちに注目されてきた。つまり、この小説はしばしば資本主義の精神の基本的なモデルとして読まれてきたのである。
そもそも、クルーソーの経歴は商品の世界と密接に関わっている。イギリス・ヨーク市の貿易商の三男で、さまざまな浮ついた考えで頭をいっぱいにしていた放蕩息子の彼は、アフリカ沿岸とりわけギニアを相手にする貿易商として活動する。その後、ブラジルに四年間居住して農場経営を覚えたクルーソーに、再び海にまつわる転機が訪れる――黒人奴隷の調達をするために、アフリカへ向かうというプランが浮上するのだ。しかし、クルーソーを乗せた船は、ブラジルからアフリカへ向かう航海の途中で遭難する。たった一人カリブ海の孤島に流れ着いた彼は、現地民のフライデーを従えて島の開発を勤勉に進め、十分な生産性を備えた植民地に作り変えていった。
このように、いわば環大西洋的存在としてのクルーソーは、交換過程と生産過程をともに活気づける。生産者にして商人でもある彼にとって、大西洋を取り囲む大陸は、商品――黒人奴隷も含む――の循環する市場であり、カリブに浮かぶ島は原材料を衣食住の資源に変える労働の場であった。
さらに、『ロビンソン・クルーソー』のおよそ百年前の一六一五年に、スペインのミゲル・デ・セルバンテスは自作の『ドン・キホーテ』の後篇を刊行した。よく知られるように、後篇は一種のメタフィクションとして書かれており、ドン・キホーテとサンチョ・パンサの二人組が活躍する前篇が書物となって流通している状況を、物語の筋に組み入れている。
ドン・キホーテは学士を立ちあがらせると、こう言った――
「すると、わしのことを描いた物語があり、それを著したのがモーロの賢者であるというのは本当でござるか?」
「本当なんてもんじゃありませんよ」と、サンソンが答えた、「わたくしの睨むところ、その本はこれまでに一万二千部のうえ印刷されているはずですからね。嘘だと思うなら、本が出版されているポルトガル、バルセローナ、そしてバレンシアに訊いてみればすぐに分かることです。しかも現在、アントワープでも印刷中だという噂があります。ですからわたくしには、今後この本が翻訳されないような国も言葉もなかろうと思われるんですよ。」[9]
実際、一六〇五年に刊行された『ドン・キホーテ』はあまりに評判になったため、海賊版が出現していた。セルバンテスはその状況を逆手にとって、後篇を『ドン・キホーテ』という書物への自己言及を含んだメタフィクションに仕上げた。これは投資過程によく似ている。つまり、元手となる資本が利潤を生み出し、自らを増殖させるように、『ドン・キホーテ』の後篇は『ドン・キホーテ』そのものの自乗として書かれた。しかも、そこには来たるべき翻訳の時代がはっきり予告されていたのである。
このように、資本主義の原理は小説の原理と相似形をなしている。資本主義が万物の商品化をエンジンとするように、交換過程、生産過程、投資過程等を再現する小説は、万物の小説化に駆り立てられている。小説はいわば資本主義のプログラムを引き写すようにして、自らの領土を拡大した。人間に把握できる限りの事象は、何であれ小説の素材になり得るし、かつその流通や翻訳の広がりにも内在的な制約がない――それこそがnovel(新奇な)という名を与えられた小説の根本原理である。
4、感覚的にして超感覚的なもの
ところで、私はここまで無造作に「商品」という言葉を使ってきた。しかし、小説がそうであるように、商品という存在そのものに謎めいたところがある。例えば、マルクスは『資本論』の「商品の物神的性格とその秘密」を論じた名高い文章において、商品とは一見して「平凡」でありながら、実際には神秘に満ちたものだと主張した。
例えば材木の形態は、もしこれで一脚の机を作るならば、変化する。それにもかかわらず、机が木であり、普通の感覚的な物であることに変わりない。しかしながら、机が商品として現われるとなると、感覚的にして超感覚的な物に転化する。机はもはやその脚で床の上に立つのみでなく、他のすべての商品にたいして頭で立つ。[10]
マルクスはこの文章のしばらく後で、経済学者の愛好する物語としてロビンソン・クルーソーに言及している。マルクスによれば「時計、台帳、インクおよびペンを難破船から救い出したわがロビンソンは、よきイギリス人として、まもなく自分自身について記帳しはじめる。〔…〕ロビンソンと彼の自分で作り出した富をなしている物との間の一切の関係は、ここではきわめて単純であり、明白」である[11]。島のロビンソン・クルーソーは個人的に衣食住の必要性を満たすために生産する。マルクスが言うように、これは単純明快である。しかし、その生産物が社会的に流通する商品となった途端、まさに「感覚的にして超感覚的なもの」へと変身するのだ。
この興味深い問題については後続の章で改めて取り上げるが、ここで一つだけ言っておきたいのは、文学(精神)と商品が接近する世界文学の時代においては、この「感覚的にして超感覚的」という二重性が文学それ自体の特性になってゆくということである。この商品と同じ二重性をもつ小説をどのように動かすか――私の考えでは、それこそが、世界文学というアーキテクチャに課せられた根本的なテーマである。私はそのことを以下の分析によって示そうと思うが、あまり先を急がず、まずはゲーテの世界文学論のコンテクストを再考するところから始めたい。
[1] デイヴィッド・ダムロッシュ『世界文学とは何か?』(秋草俊一郎他訳、国書刊行会、二〇一一年)一五頁。
[2] 同右、一八頁。
[3]アーキテクチャの概念をインターネットに本格的に応用したのは法学者のローレンス・レッシグであり、日本では情報社会学者の濱野智史が『アーキテクチャの生態系』(ちくま文庫、二〇一五年)でそれを継承した。レッシグの言うアーキテクチャとは、人間の行動や集団の秩序を情報環境上でコントロールする仕組みを指すが、濱野は生態学的なモデルを採用して、このアーキテクチャがいかに動態的に「進化」してきたかを分析した。本書はこの濱野の試みを世界文学論に応用しながら、文学の表現をコントロールするプログラムの集積をアーキテクチャと呼び、その進化史の一端を解明しようと試みたものである。
[4]トーマス・マン『ゲーテを語る』(山崎章甫訳、岩波文庫、一九九三年)六〇頁。
[5]同右、六一頁。
[6]ポール・ヴァレリー「精神の自由」『精神の危機』(恒川邦夫訳、岩波文庫、二〇一〇年)二二六‐八頁。この論考についてはパスカル・カザノヴァ『世界文学空間』(岩切正一郎訳、藤原書店、二〇〇二年)も言及している(三〇頁以下)。
なお、ヴァレリーがこの精神=経済のモデルから、一個の抽象的人格を生み出していたことも注目に値する。彼の思索的な小説『ムッシュー・テスト』(清水徹訳、岩波文庫、二〇〇四年)の主人公エドモン・テスト――ヴァレリーの知的分身でもある――は、ささやかな株取引で生計を立てながら、その純粋な精神の力によって「存在する一切をただ自分のためだけに変形し、自分のまえに何が差し出されようと、それを手術してしまう」(二五頁)。このオペレーションの力は、物理的な世界を飛び越えて、社会を数値の行列に置き換えるところにまで到達する。「八億一千七万五千五百五十……わたしは計算を追わず、ただこの未聞の音楽に耳を傾けていた。彼はわたしに株式市場の変動のありさまを伝えていたのだが、数詞の長い行列はまるで一篇の詩のようにわたしを捉えた」(三五‐六頁)。ヴァレリーの言う精神=経済のエレメントは、物質的な商品以上に、数値化された金融商品に似ており、それゆえにたえず激しい価値(評価)の変動にさらされている。この人間も事物も絶滅した精神=経済に、ヴァレリーは前代未聞の詩=音楽を認めた。
[7]「詩の社会的機能」(山田祥一訳)『エリオット全集3』(改訂版、中央公論社、一九七一年)二四九頁。
[8]イマニュエル・ウォーラーステイン『史的システムとしての資本主義』(川北稔訳、岩波文庫、二〇二二年)二三頁。
[9]セルバンテス『ドン・キホーテ 後篇(一)』(牛島信明訳、岩波文庫、二〇〇一年)六〇頁。なお、牛島信明の訳注によれば、『ドン・キホーテ』は早くも一六一二年にロンドンで英訳が、一六一四年にパリで仏訳が刊行されていた(四三二頁)。
[10]マルクス『資本論(一)』(向坂逸郎訳、岩波文庫、一九六九年)一二九‐一三〇頁。
[11]同右、一三八頁。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年3月28日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年4月27日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。