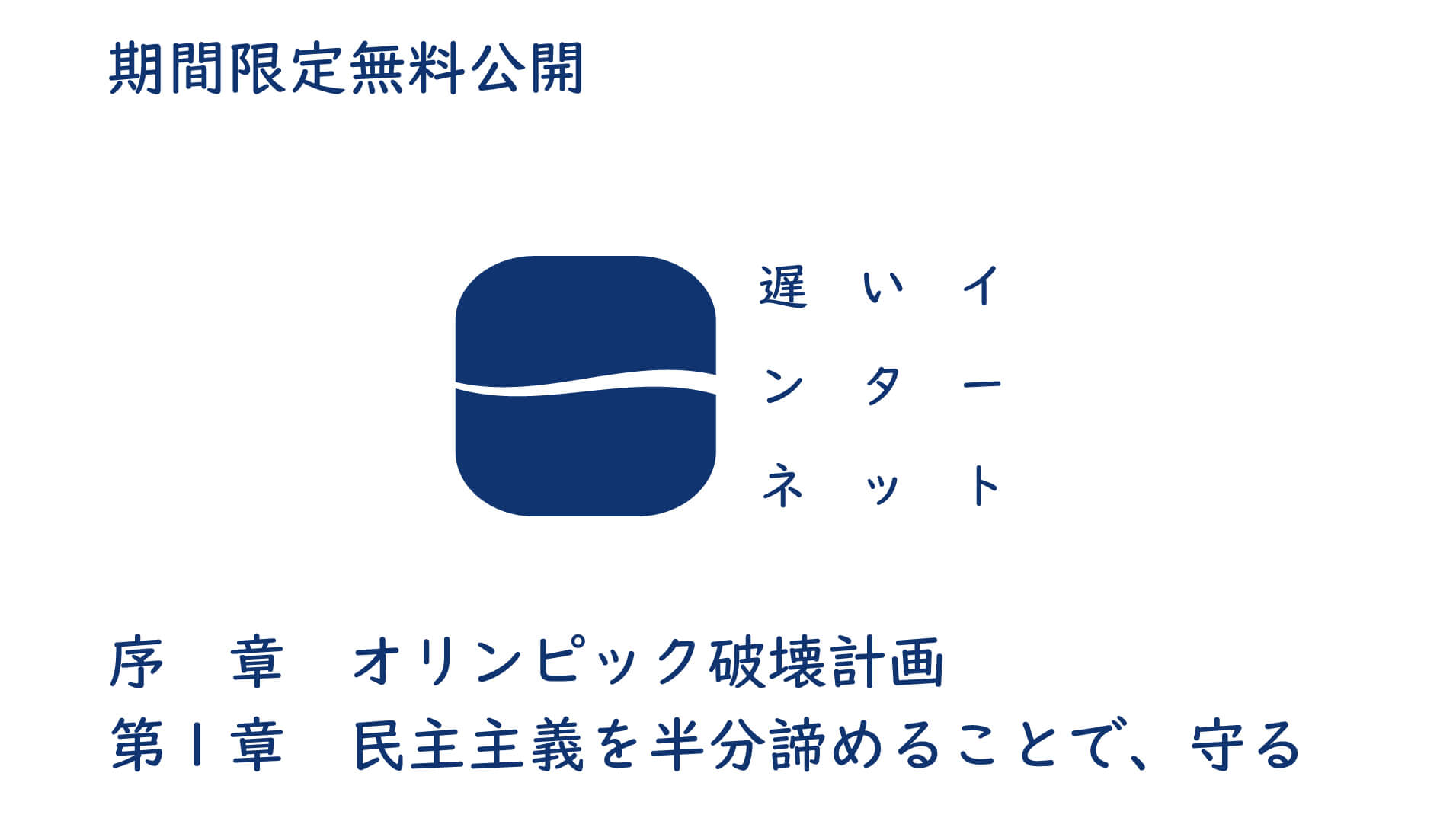期間限定で『遅いインターネット』(幻冬舎)の序章と第1章を無料公開します。
いまの、インターネットは「速すぎる」。そして、そのために人間を「考えさせない」装置になっている。
いま、世界中で起きていることがそれを証明しているように思えます。
では、なぜ僕たちはこの「速すぎる」インターネットを手放せないのか。どうすればインターネットを、情報技術をもっと建設的に使えるのか。
この本で僕はいろいろな角度から考えました。
延期が決定された2020年の東京五輪、平成という「失われた30年」、トランプ大統領の出現とブレグジット、ポピュリズムとグローバル資本主義、GoogleとFacebook、YouTubeとNetflix、吉本隆明と糸井重里……一見、ばらばらのキーワードが、最後には僕の提唱する「遅い」インターネットに帰結します。
世界中が「速いインターネット」に侵食されつつあるいまだからこそ、ゆっくり自宅で読んでみてください。
序章 オリンピック破壊計画
TOKYO2020
走ることが好きで、週に二、三度は朝に都内を走っている。
自宅のある高田馬場から走り出して、明治通りを新宿方面に走る。そして首都高にぶつかったところで左折するのがいつものランニングコースだ。そして自宅からちょうど5キロほど走ったあたりで、右手に新国立競技場が見えてくる。新宿御苑と神宮外苑のあいだにあたるこの付近は緑が多い。そして静かな高架下の日陰を走っていると反対側に突然巨大な建造物たちが次々と現れることになる。その一番奥にそびえているのが、完成したばかりの新国立競技場だ。
僕はしばらく前からこのいわくつきの競技場の建設現場を走りながら眺めることを密かな楽しみにしていた。巨大な建造物が通りかかるたびに少しずつ、しかし確実に完成に近づいていくことに他人事ながらちょっとした満足感を覚えていた。だけどその一方で、いつも考えることがある。こんなものは壊れてしまえばいいのに、と。工事現場の前を通り過ぎながら、僕はいつも完成間近の新国立競技場が爆煙を上げて、燃え上がるさまを想像していた。和のテイストを部分的に取り入れて、木材をたっぷりと用いたこの建物はきっとよく燃えるだろう。真っ青な夏の空の下、黒い煙を上げて燃え盛る競技場の上をカラスのように真っ黒な戦闘ヘリコプターが飛び去っていく場面を、いつも思い浮かべていた。
気がつけば、2020年の東京オリンピックまであと1年足らずに迫ってしまった。
この間に、天皇が譲位して元号も平成から令和へと変わった。あたらしい時代がここからはじまったかのように、目を輝かせて語る人も多い。だけど、実際のところはこの国は何も変わってはいない。平成は終わっても、「失われた30年」が終わったわけではない。もちろん、それを終わらせるためにこそ、まずは気持ちをいったんリセットしたいと考えるのはよく分かる。でも、気分だけが先走って実体が伴っていないことを、本当は多くの人が感じているはずだ。僕が改元にも、2020年のオリンピックにも空疎さを感じているのはそのためだ。ただ、この後ろ向きのモードをリセットしたい、という気持ちだけが空回りしてしまっているように思えるのだ。
そもそも、この2020年の東京オリンピックは何のために行われるのだろうか。オリンピックはそれ自体が目的である──「参加することに意義がある」というオリンピックの創始者(クーベルタン)の言葉にあるように──と考える人もいるだろう。
だけど、現実はもっと生々しいものだ。現代の規模的に肥大したオリンピックは、国家を挙げた一大事業だ。オリンピックはある時期から参加国と競技種目の増加に伴ってそれ自体ではどう考えても採算の取れないものに、いや、それどころか開催国、開催都市の財政に致命的なダメージを与えかねないものになっている。
それはオリンピック開催の経済効果をもってしても賄えないもので、たとえば1976年のモントリオールオリンピックでは競技場の整備などが市や州の財政を圧迫し、その結果、住民たちはその後に約30年にも亘って、不動産税やたばこ税の高騰に苦しむことになった。この問題を解決すべく1984年のロサンゼルスオリンピックで大胆に導入されたのが、テレビの放映権料でマネタイズするというビジネスモデルだ。その結果として、いまや一部の競技のルールや開催時刻はテレビの生中継に最適化されるかたちで改変されているというから驚きだ。そう、現代のオリンピックは何よりまずテレビショーなのだ。そして、この莫大なテレビの放映権料をもってしてもなお、年々規模が巨大化する現代のオリンピックは基本的に開催都市にとっては不採算な事業になっている。
それでもオリンピックを世界中の都市が誘致するのはそれが絶大なナショナリズムを発揮させる装置だからだ。国家がそのアイデンティティの再構築を要求されるとき、オリンピックの開催は非常に有効な手段として信じられている。そしてそれゆえに、オリンピックはしばしば、国家がその中核となる都市開発計画を円滑に進行し、市民に理解を得るための物語として利用される。そうすることで、この不採算な巨大事業はナショナリズムの触媒となると同時に、都市を対象とした未来への投資として位置づけられる。たとえば、2012年のロンドンオリンピックは移民や低所得者の集まる東地区の大規模再開発を前提に誘致されたものだ。オリンピックとは、ある街と国が次の世代に手渡したい未来の社会の青写真があってはじめて誘致されるべきものなのだ。
次世代への投資を動機づける「物語」としてのオリンピック──その見本と言える成功例が1964年の最初の東京オリンピックだった。首都高速道路も東海道新幹線も、半世紀以上前にこの東京オリンピックに向けた都市改造として整備されたものだ。そう、1964年の東京オリンピックは、敗戦の復興から高度成長へと飛躍する当時の日本の国威発揚であると同時に、急速に発展する国内産業を下支えする都市改造とインフラストラクチャーの総合整備計画でもあったのだ。そこには、半世紀規模の大計画が、この国の近未来を見据えた青写真がたしかに存在した。
だが、来るべき2020年の東京オリンピックはどうだろうか。そこには基本的に何も、ない。そこに存在するのはせいぜい、もう一度東京にオリンピックがやってくれば、誰もが上を向いていた「あのころ」に戻れるのではないかというぼんやりとした(そしてまったく無根拠な)期待だけだ。実際に2020年の東京オリンピックに、1964年に存在したような半世紀先を見据えた都市改造や国土開発の青写真はまったく存在しない。消去法で選ばれてしまったこの2020年のオリンピックに対して、この国の人々はまったくビジョンをもっていないのだ。自治体間の予算の押し付け合いと、開催準備の混乱が体現する「うっかり呼んでしまったオリンピックのダメージコントロール」が、来るべき2020年の東京オリンピックの実体だ。
そう、僕たちは2020年にオリンピックを迎えるべきではなかったのだ。少なくとも、このあと半世紀の都市計画の青写真と社会そのもののグランドデザインなしに誘致すべきではなかったのだ。いや、むしろこの国の現状を考えるのなら、これらをしっかりと備えた上でオリンピックを誘致して、そしてやりきることで本当の意味で平成を、失われた30年を終わらせるべきだったのかもしれないが、現実に進行しているのはその真逆のことだ。
ただ、誤解しないでほしい。だからと言って僕はいまさらオリンピックを返上すべきだと述べる気はない。実効性をもたない反対論を唱えて席を確保するような仕事にはそもそも興味が、ない。むしろその逆でこの無策でそれゆえに空虚なオリンピックは、反面教師として僕たちにこれから為すべきことを教えてくれるように思えるのだ。だから僕はただ文句をつけるだけではなく、ポジティブな「対案」を示すことにこだわった。
僕の雑誌『PLANETS vol.9』(2015年1月発売)のテーマは2020年の東京オリンピックだった。
僕ははっきり言ってしまえばこのオリンピック招致には反対で、そして反対しているからこそ単に批判するのではなく僕たちなりの「対案」を残そうとした。少しでも未来に残すものが多いオリンピックにするべきだと考えて、仲間たちと僕たちの理想の「2020年東京オリンピック」の企画案を発表した。
このとき僕が考えていたのは、言ってみればオリンピックをテレビの中の他人の物語を「見る」だけのものではなく、インターネットの時代に相応しく自分の物語として「参加する」ものにすることだった。画面の中のアスリートに感動し、みんなでひとつの同じ夢を見るのではなく、ひとりひとりが参加し、それぞれの、ばらばらの自分の物語を見つけるものにできないか。そしてそうすることで、この国の社会に決定的に欠けている多様性をインストールする。そんな社会提案になっていればよいと考えた。
開会式は過去の栄光を自慢するものではなく、こんな未来を手にしたいという理想を込めるものにしたい。近代スポーツにつきまとう五体満足主義的な身体観をもっと多様なものにアップデートしたい。この東京という街を、21世紀を代表するメガシティとして世界にビジョンを示すものにしたい。そうした様々なアイデアを詰め込んだ一冊になった。
たとえばチームラボの猪子寿之が単に「見る」だけでなく、情報技術を駆使して市民も参加できる開会式や競技中継のプランを考えた。あるいは乙武匡洋のオリンピック/パラリンピックの融合案を実現するために、ゲーム研究者を中心に新しい競技の開発を試みた。あるいは建築家や社会学者たちでチームを組んで、こうした多様性を受容し育むことのできるハードウェアをコンセプトに東京の再開発計画をまとめ上げた。それが僕らの「オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト」だった。
個人的にはとても手応えのある一冊になったと思う。しかし、この本は一部のメディアや関連業界に少し反響があっただけで、社会に大きな波を起こすことはできなかった。そもそも、この本が発売された2015年1月の時点では2020年の東京オリンピックそのものの社会的な関心は驚くほど低かった。
だが発売からしばらくあとに、新国立競技場建設の膨大な予算とエンブレムの盗用疑惑によってオリンピックは社会的な関心を集めることになった。どこかに自分より甘い汁を吸っている人間がいるに違いないのだという被害者意識によって駆動されて、瞬く間に誰もが誰かを叩くことに夢中になっていった。このとき僕は誰もが「……ではない」という言葉(批判)を欲しがり、「……である」という言葉(対案)を望んでいないことを痛感した。否定の言葉だけが人間と人間をつなぐことができる。それがこの社会の身も蓋もない現実だった。
そして、あれから5年、平成が終わり、令和という時代がはじまった。しかし、この国の本質は何も変わっていない。問題は何も解決していないのだ。
その象徴があの新国立競技場だ。長期的な都市開発のグランドデザインをもたないまま、メインスタジアムとしてザハ・ハディドの設計による国立競技場の建て替えを決定し、その膨大な予算額が世論の批判を集めて葬り去られ、「多少の」予算の圧縮を実現することで隈研吾の極めて無難な設計が採用されて建て替えが実行される。もちろん、この建て替えを中心とした再開発で東京という街が生まれ変わることもないし、これから必要な都市機能が整備されることもない。まず長期的な思考の欠如による根本的に安易で、空回りしていて、その上実現すら危ういどうしようもない(無)計画が前提として存在して、その杜撰な計画がその場その場でのちょっとした空気に左右されて、「修正」されていく。そしてそのすったもんだの中で根本的な問題設定の間違いは正されないまま放置されるのだ。
平成という「失敗したプロジェクト」
そしてなし崩し的に「平成」と呼ばれた時代が終わり、「令和」という新しい時代が幕を開けた。しかし、この国の実体は何も変わっていない。新国立競技場のデザインを変えても、青写真をもたない東京オリンピックの実体が何も変わらないように。
そもそも「平成」とは何だったのか。それはどのような時代だったのか。2年ほど前に、新聞のインタビューに僕はこう答えた。
平成とは「失敗したプロジェクト」である、と。
そのプロジェクトとは何か。それは「政治」と「経済」、ふたつの「改革」のプロジェクトだ。「平成」とは政治改革(二大政党制による政権交代の実現)と、経済改革(20世紀的工業社会から21世紀的情報社会への転換)という二大プロジェクトに失敗した時代である。これが、僕の結論だ。
平成の政治改革とは自由民主党による事実上の一党独裁と、社会党をはじめとする諸野党による対立を装った補完によって形成されてきた55年体制という共犯関係を打破し、中道的な二大政党制に移行することで議会制民主主義を機能させることを目的としたプロジェクトだった。
そのために試みられたのが、思想的、政策的には呉越同舟である自民党を主に経済政策によって二分し、野党を解体して組み込みながら中道的な二大政党に再編することだった。それが1993年の細川護熙内閣にはじまる平成の「政治改革」だ。その後の「第三極」ブームも、地域改革政党のブームも、源流はここにある。
しかしこの日本に機能する「民主主義」を導入しようとする運動は(そのプレイヤーを二転も三転もさせながら展開した運動は)、数多くの茶番劇を経ていま、完全に失敗に終わっている。
気がつけばこの国の自民党による一党支配はより盤石になり、政権交代の可能性は皆無に等しい。今日における諸野党の役割は政権交代の可能性を模索することではなく、「55年体制」下の諸野党がそうであったように自民党への批判票の受け皿となることに回帰している。
2012年末の民主党政権の自壊と第二次安倍政権の成立によって、この国の「政治改革の 30年」は、平成最大のプロジェクトは完全に失敗に終わったのだ。
では経済はどうか。平成の30年で、この国の経済は相対的に大きく後退している。「平成」がはじまったころ、日本はアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国だった。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉が時代を象徴するフレーズとして世界中に共有され、20世紀後半の重工業社会でもっとも成功したモデルとして日本的経営が評価されていた。
しかし、今日ではどうだろうか。端的に述べれば日本はかつての成功体験に引きずられ、 20世紀的な工業社会から脱皮できないでいる。その結果21世紀的な情報産業は発達せず、東京はシリコンバレーや中国沿岸部といった、世界経済を引牽する都市群に完全に置いていかれてしまっている。
そして国という単位でも日本は隣国の中国の圧倒的な成長を前に為す術もなくあっさりと追い抜かれ、それどころか人口3分の2のドイツに追いつかれようとしている。経済的な豊かさの国際指標とされる1人あたりのGDPにおいてこの国は恐るべきことに世界第18位までに転落しているのだ。
かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と讃えられた日本的な経営は、いまや個人の個性を抑圧し、才能を潰し、組織の歯車にすることで、情報産業を支えるイノベーションを疎外するための仕組みでしかない。そしていまでもこの国では成果ではなくメンバーシップに対して報酬が支払われる制度が生き残っている。会社への忠誠心を測る基準として残業時間が評価され、「打ち合わせ」という名の上司や取引先への愚痴大会が稼働時間の大半を占め、その不毛で陰湿なコミュニケーションがそのまま夜の「飲み会」に反映される。こうしたコミュニケーションのためのコミュニケーションを反復する中で、人間は「個」を失い、独創的な思考を失い、組織の歯車となっていく。もちろん、20世紀の工業社会ではこうして規格が統一され、寸分の狂いもない(誰もが同じ思考をする)ネジや歯車のような人間を集めたほうが有効な局面もあったに違いない。しかし、今日においてこうした個を失い、想像力を失った人間は何も生み出すことができない。むしろ出る杭を打ちたくなる同調圧力をもたらし、イノベーションを疎外する要因にしかならないことは誰の目にも明らかだ。
しかし過去の成功体験に引きずられた旧い日本人たちはそのことを認めようとしない。その結果フィンテックもシェアリングエコノミーもいまだ普及の兆しすらなく、この国は1周遅れの国になりつつある。多くの現役世代が実感しているように、この国は技術的にも社会的にも周回遅れになっているのだ。いまだに通帳と判子が幅を利かせ、実店舗に足を運ぶことを要求される金融取引、既存の業界の雇用を守るという大義名分で規制されるライドシェア……これでは絶対に諸外国と戦えないと絶望したビジネスマンは数知れないはずだ。
そしてこうした経済の体質は、本来は政治主導で改善されていくべきだった。いや、正確にはグローバルな経済の変革の波とうまく付き合っていく(流れに乗らなければ機を逸するものについては船頭となり、うっかり流されてはいけないものは防波堤になる)ために政治が機能すべきだった。しかし、現実の政治はこうした波に鈍感さを発揮したまま、単に静観することしかできなかった。それどころか、現実の変化を認めたくない人々の側に立って、リスクを取って波に乗ろうとする人の足を引っ張ることに加担することすらあった。この状況に終止符を打つこともまた、平成の政治「改革」の大きな目標だったはずだ。
もちろん経済規模や生産性だけが、社会の質を決定すると考えるのはあまりに安易だし、僕は当時の「改革」だけが「正解」であったとも考えない。だが、この経済的な失敗がこの国を決定的に後ろ向きな「つまらない国」にしてしまっていることも間違いない。
いま、世界をもっとも強い力で更新しているのは経済だ。マルクス主義は20世紀の末に完全に失敗したが、いま、資本主義の内部から国家を超えた社会変革の可能性が芽吹いている。革命や政治運動で時の政府を打倒してもローカルな国民国家しか変わらない。しかし、グローバルな市場に情報技術を用いたイノベイティブな商品サービスを投入することで、世界中の人間の社会を、生活を一瞬で変えることができる。いま、世界中の人々がこの可能性に賭けている。いや、それどころか日本が出遅れているあいだに、このシリコンバレーの情報産業を中心に展開したグローバル資本主義のもたらす副作用に対する反省のターンに世界は既に入っている。
グローバルな市場と情報技術が、世界をひとつに結ぼうとすればするほど、この波に乗り遅れた人々──主にかつての先進国に暮らす、20世紀の工業社会の構造下で旧後進国を搾取していた人々──が既得権益を失う恐れから再び「壁を作れ」と声を上げ、国民国家に回帰している(トランプ/ブレグジット)。このグローバルな市場とローカルな国家の対立構造 ──同時にこれは相対的にリベラルで多様性を擁護する市場(非民主主義)と、排他的で保守的な国家(民主主義)とのねじれた対立構造でもある──の解消こそが、今日の世界的な課題であることは明らかだ。
つまるところ、いま求められているのはグローバル資本主義と、その背景にある情報技術の批判的な発展だ。しかし、1周遅れのこの国ではそもそもグローバル化も、社会の情報化もそのものが受容されていない。20世紀的な工業社会から、21世紀的な情報社会への転換に失敗し、グローバル化に対しても相対的に門戸を閉ざしている。このような1周遅れの状況で、オールドタイプの知識人やオールドメディアのジャーナリストたちが、欧米のグローバル資本主義やシリコンバレー的な技術主義に対する批判の潮流を歓迎し、1周遅れの自分たちの正当化に用いるという、絶望的な状況がこの国を覆っている。
あえて背を向け、選択しないこととそもそも選択肢が存在しないことはまったく違う。この国は、あたらしい世界に触れることすらできていない。だから旧いものを選ぶしかない。自分が無知であることすら知らない人はあたらしいものにアレルギー反応を示し、世界を変えることに貢献できるほどは賢くない人は(最初から選択肢などないことからは都合よく目をそらして)あえて旧い世界に留まることが賢いのだと自分に言い聞かせる。しかしどちらも問題外だ。移民にもシェアリングエコノミーにもフィンテックにも「あえて」背を向ける選択はもちろん検討されるべきだが、それはそれらの可能性を批判的かつ建設的に検証し尽くしたあとでなければ意味はない。空回りする逆張りほど空しいものはない。
平成という失われた30年は、やはり「失敗したプロジェクト」だったのだ。
「動員の革命」はなぜ失敗したか
ではこの「平成」という「改革」のプロジェクトはなぜ失敗したのだろうか。
小沢一郎、小泉純一郎、橋下徹、小池百合子──その所属勢力こそ異なるが、平成という時代はカリスマ的なリーダーがテレビポピュリズムを用いて、55年体制的な戦後政治を打破しようとした時代だった。しかし誰ひとりとしてその志を貫徹できなかった。それは彼らの選んだテレビポピュリズムという手法の限界でもあった。
ポピュリズムはその性質上持続可能性が低い。最初の選挙ではメディアの操作に成功し、ワイドショーの「潮目」を読み「風」を吹かせたとしても、その次、さらにその次までそれを持続させることのできるケースはほとんどない。あの天才・小泉純一郎ですら、5年で「勝ち逃げ」することが精一杯だった。これは都市の無党派層のうち、それもテレビの報道番組やワイドショーでの印象で投票先を決定するリテラシーの低い大衆を動員することで既存政党の組織票に対抗するという戦略そのものの限界に他ならない。その帰着が2012年末の第二次安倍晋三政権の成立にはじまる「55年体制」への事実上の回帰だ。平成というポピュリズムの時代はこの国の民主主義の成熟を促すどころか、ただ政治漂流の苦い記憶だけを残す結果に終わったのだ。
このテレビポピュリズムを克超する可能性として一瞬だけ注目を集めたのが、インターネットを通じた政治運動だ。2010年から2012年にかけて発生した「アラブの春」、2011年のオキュパイ・ウォールストリート運動など、この時期、世界的にソーシャルメディアによる市民運動への動員が注目を集めていた。この国でも東日本大震災の直後に反原発デモがTwitterの普及とその動員力を背景に拡大し、「ウェブで政治を動かす」「動員の革命」が政治を変えると、本気で議論されていたことがあった。そして結論から述べれば、「動員の革命」という発想は安易だった。「動員の革命」を主張するアジテーターたちは述べた。テレビをはじめとする旧来のマスメディアとは異なり、現代のソーシャルメディアはユーザーひとりひとりが「発信」することで社会に一石を投じることができる。この一石を投じる行為は人々をただ情況を見ているだけの観客から介入する当事者に変える。この延長にいま盛り上がりを見せるソーシャルメディアの動員を用いたデモがある。この世界的なムーブメントによって民主主義はあたらしいステージを迎えるのだ、と。しかし、現実に起こったことはその逆だった。広く知られるように「アラブの春」で軍事政権を打倒した国の多くが政情の不安定化を経て、IS(イスラム国)などに代表されるカルト勢力の台頭とそれに伴う内戦に陥った。日本の反原発デモも大きな成果を挙げることなく支持を失い、今日の社会のリベラルな政治勢力の衰退の遠因となった。今日において明白なのはソーシャルメディアによる「動員の革命」とは、ポピュリズムの一形態に過ぎないということだ。その動員力はテレビのそれよりも弱い。しかし、よりアクティブで熱狂的な参加者がそこには集う。この局所的な熱量の高さ、瞬間最大風速の強さは、それがより一過性の狂躁であることを意味していた。それはテレビのそれよりも、より短期で、そして熱量の高い分冷めやすく、思慮を欠いたポピュリズムに過ぎなかったのだ。テレビポピュリズムにインターネットポピュリズムで対抗するという「動員の革命」はこうして敗北していった。いや、それどころか平成というポピュリズムの時代を下支えし、強化したのだ。
そう、気づいたときは既に手遅れだった。それも、決定的に。 いまこの国のインターネットは、ワイドショー/Twitterのタイムラインの潮目で善悪を判断する無党派層(愚民)と、20世紀的なイデオロギーに回帰し、ときにヘイトスピーチやフェイクニュースを拡散することで精神安定を図る左右の党派層(カルト)に二分されている。
まず前者はインターネットを、まるでワイドショーのコメンテーターのように週に一度、目立ちすぎた人間や失敗した人間をあげつらい、集団で石を投げつけることで自分たちはまともな、マジョリティの側であると安心するための道具に使っている。
対して後者は答えの見えない世界の複雑性から目を背け、世界を善悪で二分することで単純化し、不安から逃れようとしている。彼ら彼女らはときにヘイトスピーチやフェイクニュースを拡散することを正義と信じて疑わず、そのことでその安定した世界観を強化している。
そして今日のTwitterを中心に活動するインターネット言論人たちがこれらの卑しい読者たちを牽引している。
彼らは週に一度週刊誌やテレビワイドショーが生贄を定めるたびに、どれだけその生贄に対し器用に石を投げつけることができるかを競う大喜利的なゲームに参加する。そしてタイムラインの潮目を読んで、もっとも歓心を買った人間が高い点数を獲得する。これはかつて「動員の革命」を唱えた彼らがもっとも敵視していたテレビワイドショー文化の劣化コピー以外の何ものでもない。口ではテレビのメジャー文化を旧態依然としたマスメディアによる全体主義と罵りながらも、その実インターネットをテレビワイドショーのようにしか使えない彼らに、僕は軽蔑以上のものを感じない。
あるいは彼らは、人々はもはや考えないためにこそインターネットを用いることを前提に読者が欲しがっている言葉を、最初から結論が分かっている議論をまるでサプリメントのように配信する。そしてサプリメントを受け取った読者はいまの自分は間違っていないのだと安心する。自分は善の側に立っていることを確認し、反対側の悪を非難すれば自分は救われると信じることができる。
これがインターネットポピュリズムで政治を動かすと宣言した「動員の革命」の現在形なのだ。そしてその実体は平成のポピュリズムの超克ではなく、その補完以外の何ものでもなかった。元号が変わっても、平成というポピュリズムの時代は終わる予感すらない。
走りながら考える
2016年8月21日の午後8時(現地時間)──リオデジャネイロで開催されていた夏季オリンピックの閉会式が全世界に中継された。4年後の2020年の開催都市は、東京。二度目のオリンピックを迎えるこの地球の裏側の都市へ、五輪旗の引き継ぎ式が行われた。
引き継ぎ式は大手広告代理店を中心に編成されたチームによって演出され、そしてその中でも注目を集めたのが式典の最後を飾った安倍晋三首相の登場につながる映像パートだった。北島康介、高橋尚子といったかつてのオリンピックで活躍したアスリートたちに交じって、キャプテン翼、ドラえもん、ハローキティ、パックマンといった戦後マンガ、アニメ、ゲームのキャラクターたちが競演し、「規律と調和」「おもてなし」といった「日本の精神」がアピールされていった。
そして、リムジンに乗って登場した安倍はこのままでは閉会式に間に合わないことを悟ると、車中で〈スーパーマリオ〉シリーズのマリオに変身する。渋谷の駅前に現れたドラえもんが、四次元ポケットから土管を取り出してスクランブル交差点に設置、安倍は土管の中に潜りワープを開始する。地球の裏側、リオデジャネイロへ向けて。すると、中継画面は会場のライブ映像に切り替わる。ステージの中央にいつの間にか設置されていた土管からマリオに扮した安倍本人が登場する──。
少なくとも国内からは賞賛の声が相次いだこのクロージングのパフォーマンスを目にしたとき、僕は強く思った。このクロージングの演出はたしかに過不足がない。そこにはものづくりとサブカルチャーの大国として進んできたこの国の戦後の姿が、内外の視線を織り交ぜてある程度適切に記述されているのは間違いないだろう。しかし、同時に強く感じた。ここにはなにひとつ未来がない、と。そこには、これからこの国はこうありたい、という部分がすっぽり抜け落ちていた。かつての、1964年の東京オリンピックは経済大国化という夢の結晶だった。復興から高度成長へ、そして経済大国へ。首都高速道路、東海道新幹線、カラーテレビ──官民のインフラ整備が象徴するように、あのオリンピックは来るべき未来のビジョンと密接に結びついていた。しかし……
この優秀な、と言ってよい、一見過不足のないクロージングに対して僕が物足りなさを感じるとすればそれは、未来のなさ、だ。戦後という時代の成果物と、そこに息づく「日本的な」精神を歴代のトップアスリートに交じって戦後サブカルチャーのキャラクターたちがアピールし、そして時の首相がマリオとして現れる。そこには既に失われた時代の栄光を振り返る力はあっても、未来を構想する力はまったく、ない。僕にはあのクロージングが、同時にもはや日本は過去にしか語るべきもののない国になってしまったことを告白しているように思えたのだ。
僕はあの新国立競技場を目にするたびに、思い出すある映画の台詞(せりふ)がある。「戦線から遠のくと、楽観主義が現実にとって代わる。そして最高意思決定の段階では現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けているときは特にそうだ」。何を言っているんだ、戦争なんてまだはじまっていないじゃないか。そう考える人も多いだろう。けれど、違う。戦争はもうとっくにはじまっているのだ。平成と呼ばれた「失われた30年」がはじまったあのときから、いや、そのはるか以前から戦争ははじまっていたのだ。ただそのことに、僕たちが気づくのが遅すぎた。そして、僕たちはいま戦争に負けていることから目をそらすための楽観主義に陥っている。
あの新国立競技場は、かつての戦艦大和のようなものだ。もはや時代遅れの無用の長物でありながらなけなしの、しかし膨大な資源と人員と予算を投じて建造された帝国海軍の象徴としての巨大戦艦は事実上なにひとつ戦果を上げることなく、沖縄の海に沈んでいった。あの決定的な敗戦から70年と少し。この国の人々は再び大和を建造してしまったのだ。
そう、問題は競技場のデザインや建築費用ではない。そもそも東京という街をこれから半世紀どうするのかというビジョンが存在しないことが問題なのだ。競技場の建て替えはもちろん、あらゆる再開発はそこから逆算されなければいけないはずだった。しかし、残念だけれど僕たちはこうした青写真を、未来への展望を一切もたずに2020年の夏を迎えようとしている。そして、それが巨大な茶番であることから誰もが目をそらそうとしている。だから僕はあの新しい国立競技場を目にするたびに思うのだ。こんなものは壊れてしまえばいいのに、と。
前述した僕と仲間たちが提案した2020年東京オリンピックの対案──『PLANETS vol.9』の「オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト」──にはちょっとした仕掛けのようなものが仕込んであった。この本はA(Alternative=実施対案)、B(Blueprint=都市計画の青写真)、C(Culture=文化施策)という三つの計画から成る理想の東京オリンピックの企画書だった。しかし実は巻末に四つ目の計画「D」が存在する。この「D」とは「Destroy」つまり「破壊」のDだ。「オリンピック破壊計画」と題したそれは、体裁としては想定される東京オリンピックへのテロ対策を考えたものだったが、事実上は破壊計画のシミュレーションだった。僕はずっと、このオリンピックは破壊されるべきなのだと、考えているのだ。
もちろん、本当に新国立競技場を破壊しても意味がない。本当に世界を変えたいのなら、むしろ僕たちはあの巨大建築が象徴するものを、この社会を覆う見えない壁のようなものを破壊しなければいけない。オリンピックも新国立競技場も象徴に過ぎない。これらはこの平成という失われた30年で事実上二流国に転落し、そしてその現実から目をそらし続けるこの国の、表面だけを辛うじて取り繕ったハリボテのようなこの国の象徴に過ぎない。だから僕たちが破壊しなければならないのは、この2回目の(茶番としての)オリンピックそのものではない。こうした茶番を反復して再生産する目に見えない力の源を、僕らの思考を現実から遮断する目に見えない壁を僕たちは破壊しなければいけないのだ。
以前の僕はこの茶番を、2020年の東京で行われることを少しでも茶番ではないものにするための対案を出すことを考えていた。しかし、いまの僕は少し違う。どちらかと言えばこの茶番が反復される構造を破壊することを、そして別のものに作りかえることを考えている。そしてそのためにまずオリンピックという他人の物語を語るよりも、自分の物語を自分で走ることのほうに関心がある。
だからこれは、走りながら考える本だ。ゴールは決められていない。たぶん栄養剤のようにこの本を読み通すことで力が湧いてくることもなければ、安定剤のようにいまの自分はそれでよいのだと安心することもないと思う。いま書店に並んでいる本は大抵このどちらかだ。しかしこの本を読むと、どちらかと言えば、スッキリしない、モヤモヤとしたものが残るはずだ。けれど、こうしたモヤモヤとしたものが身体に沈殿するからこそ、それを吐き出すために人は走り出す。そう、この本は一緒に走りながら考えてもらうための一冊だ。あらかじめ分かっていることを確認して安心するための本ではなく、手探りで、迷いながら考える本だ。そしてこの国を、いやこの世界を覆う目に見えない壁を破壊する言葉を手に入れること。それがこの本の目的だ。
では、そろそろ走りはじめよう。繰り返すが、ゴールは存在しない。これは一緒に考えながら、一緒に走る本だ。答えを用意して、活力や安心を与えるための本ではなく、問いを共有して一緒に迷い、試行錯誤するための本だ。ゴールテープを切ってタイムに満足する気持ちよさは提供できないけれど、走ることそれ自体の気持ちよさはきっと共有してもらえると思う。
第1章 民主主義を半分諦めることで、守る
2016年の「敗北」
では、思考の皮切りに少しだけ時間を遡ろう。
まず僕たちはあの3年前の、2016年11月8日のことを思い出すべきだ。あの日は世界を駆動していたひとつの理想が決定的に躓き、そして敗北した日だった。
その日行われたアメリカ大統領選挙によって第45代大統領に選ばれたのは、大方の予想(あるいは希望的な観測)を覆してヒラリー・クリントンではなくドナルド・トランプだった。
開票が行われたのは(日本時間では)翌日の水曜日で、勝敗が決したとき僕は非常勤で1コマだけ講義を担当している大学の教壇に立っていた。授業の準備をしている午前中は、まだ多くの人が(そして僕も)ヒラリーの勝利を前提にしていた。開票状況は既にトランプの勝利を証明しつつあったのだけど、人々はそれを認めたくなかったのだと思う。そして、講義を終えたころには趨勢が決していた。
講義が終わっても帰らない学生たちは僕に尋ねた。なぜ、ヒラリーはトランプに敗れたのか、と。僕は答えた。それは、グローバリゼーションへのアレルギー反応なのだ、と。この四半世紀でアメリカとベトナムの格差は圧倒的に縮まっているが、シリコンバレーの起業家とラストベルトの自動車工の格差は逆に広がっている。だから、ラストベルトの自動車工は「壁を作れ」と反グローバリゼーションを掲げるナショナリストを、つまりトランプを支持したのだ、と。
だけど僕は学生たちに一通り解説しながら、それだけでは足りないものを感じていた。
グローバルな市場とローカルな国家の対立──この構造は、21世紀初頭から世界中の哲学者や経済学者、あるいは歴史学者によって繰り返し指摘されていることだ。だが、2016年に人類が突きつけられたのは、このパワーバランスが想定されていたものとはいささか異なるかたちに、それも急激に変化しつつある現実だった。たとえば、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートが2000年に出版した『〈帝国〉』では国民国家のコントロールを超えたグローバルな単一市場に君臨する超国家的な存在を「帝国」と形容している。この「帝国」は今日においては「GAFA」(Google, Apple, Facebook, Amazon)などのグローバルな情報産業の支配的な状態を強く想起させる。ネグリ=ハートの「帝国」という言葉の選択は、ローカルな国家に対するグローバルな市場の側の勝利を前提としたものだ。ネグリとハートは述べる。私たちがいま、不可避の支配力としてその存在を正しく認識し、抵抗しなければならないのはグローバルな資本主義市場が形成する皇帝も独裁者もいない(しかし、確実に存在し私たちの生を決定する)あたらしい「帝国」なのだ、と。しかし実際にこの日起こったのは、むしろこのあたらしい帝国の支配がその震源地で否定されたことではないか。
あるいはなぜバーニー・サンダースではなく、トランプなのかという問いを立ててみてもよい。もしヒラリーの敗北の原動力が、グローバリゼーションが再生産する国内格差だけに起因するのであれば、ヒラリーを制するのは民主党予備選挙で彼女と争い、よりラディカルな再分配を訴えていたサンダースであるべきだったのではないか。
僕たちがこの選挙の結果に、ドナルド・トランプの台頭に感じる不気味さは、背中のあたりがむず痒くなるような感覚は、もっと言ってしまえばある種の後ろめたさのようなものはどこから生まれるのか。むしろ自分が言葉にしなければならないのは、その不気味さについてではないか。そう感じていた。
そんなモヤモヤした感情を引きずりながら仕事場に戻って、ふとFacebookを開くとそこには仕事仲間たちがトランプの当選を嘆く投稿が並んでいた。投稿しているのは概ね、六本木や渋谷の情報産業に関わる起業家や投資家やエンジニアたちで、彼らの投稿はどれもとても似通っていた。曰く、自分のシリコンバレーの、ニューヨークの友人たちがこの結果を嘆いている。しかし絶望する必要はない。僕たちは国民国家などという旧い枠組みに囚われないあたらしい世界を既に生きている。僕たちのようなグローバルな市場のプレイヤーにもはや国境など関係ない。アメリカがトランプの支配によって自由を失ってしまうのなら、ロンドンに、パリに、シンガポールに、そして東京に来ればいいだけの話じゃないか、と。
僕は彼らの投稿を一読して、頭を抱えた。彼らの主張は概ね、正しい。しかし正しいからこそ、彼らは決定的なことを揃いも揃って見落としている。自分たちは既にあたらしい「境界のない世界」の住人であり、旧い「境界のある世界」のルールなどもはや関係ないのだと語る彼らのこの「語り口」こそが、トランプを生んだのだ。そのことに彼らはまるで気がついていない。彼らの「語り口」とその背後に渦巻くものこそが、トランプが述べるものとは別の、そしてより決定的な「壁」を再生産してしまっているのだ。そして、ここに僕が言葉にしなければいけないこと──トランプを大統領に押し上げてしまったものの本質──があるのだと思った。
世界はいまたしかに「境界のない世界」に近づきつつある。そして、いまだに世界に多く残された旧い「境界のある世界」の住人たちは、この時代の流れにアレルギー反応を示しつつある。実際に、この2016年はあたらしい「境界のない世界」へのアレルギー反応が噴出した1年だった。アメリカ大統領ドナルド・トランプの誕生、そして同じ2016年に行われたイギリスのEU離脱を支持する結果となった国民投票(ブレグジット)。2016年は冷戦終結後から一貫して進行してきたグローバリゼーションに、そしてそれと並走して進行してきた人類社会の情報化に対するアレルギー反応の時代に世界が突入したことを宣言する1年になったのだ。
ドナルド・トランプは声高らかに宣言する。「壁を作れ」と。この「壁」とは直接的には国民国家間に引かれた国境のことであり、比喩的にはグローバリゼーションの進行が世界を市場というひとつのゲームボードに統一しようとする流れに対する防波堤のことだ。そして彼が「壁」を作れと叫ぶのは、現実には既にそこからは境界が少なくとも経済のレベルでは徐々に、しかし確実に取り払われているからだ。
そう、既にかつて存在した壁は取り払われてしまっている。だからこそ壁を再建せよと叫ぶ声が響くのだ。そして壁を作れと号令をかける人間ではなくむしろ壁などもはや自分たちには関係ないと豪語する人々があたらしい精神的な「壁」を無意識のうちに作り上げてしまっているのだ。
冷戦終結から約四半世紀のあいだに20世紀的な国民国家の集合(インターナショナル)から、世界単一の市場経済(グローバル)へ世界地図を描く図法は変化し、このあたらしい「境界のない世界」は急速に拡大していった。今日の世界においては革命で時の政権を倒しても、ローカルな国民国家の法制度を変えることが関の山だが、情報産業にイノベイティブな商品やサービスを投入することができれば一瞬で世界中の人間の生活そのものを変えることができる。21世紀とはグローバルな市場というゲームボードによって世界がひとつの平面に統一された時代であり、その主役は国境を越えて活躍するグローバルな情報産業のプレイヤーたちに他ならない。たしかにこのあたらしい「境界のない世界」を生きる彼らにとって、もはや生まれ出た土地が所属する国民国家は、個人の属性を示す無数のタグのひとつに過ぎないだろう。
だがその一方でこの世界に生きる大半の人々はこのあたらしい「境界のない世界」に投げ込まれてしまったことに気づいていない。より正確にはいつの間にかあたらしい世界の中に投げ込まれてしまったことに気づきはじめているために、脅え、戸惑っている。彼らの心はいまだに20世紀的な、旧い「境界のある世界」に取り残されている。彼らはまだまだ精神的にも、経済的にもローカルな国民国家という枠組みの保護を必要としているのだ。
イギリスのジャーナリストであるディヴィッド・グッドハートは前者を「Anywhere」な人々、後者を「Somewhere」な人々と名付けた。「境界のない世界」を生きる人々は「Anywhere」に、つまり「どこでも」生きることができる。あの日彼らが口を揃えてアメリカがトランプに支配されるのならば、ロンドンに、パリに、東京に来ればよいと述べたことがその世界観を象徴している。対して「境界のある世界」にその心を置いてきてしまった人々は、「Somewhere」つまり「どこか」を定めないと生きていけないのだ。
このあたらしい「境界のない世界」に生きる「Anywhere」な人々の文化のルーツは1960年代から70年代にかけてアメリカ西海岸を中心に展開されたヒッピーカルチャーにある。それは今日の情報産業が牽引するグローバル資本主義の源流を遡れば明らかだ。
60年代末の世界的な学生反乱とその挫折──アメリカのベトナム反戦運動、フランスの五月革命、そして日本の全共闘運動とその挫折──は、そしてその後の資本主義の勝利による(相対的に)安定した民主主義社会と豊かな消費社会の実現は、ベビーブーマー以降の世代のユースカルチャーのモードを政治的なアプローチ(革命)で「世界を変える」ことから、文化的なアプローチで世界の見え方を、つまり「内面を変える」ことに移行させた。
アメリカにおけるこの変化の中心地となった西海岸では革命という名の最後のフロンティアを失った代償として、様々なアプローチが試みられた。エコ思想、オリエンタリズム的な禅の受容、ニューエイジ的な精神世界への接近、ドラッグ・カルチャー──こうした試行錯誤のひとつがコンピューターの発展がもたらしたサイバースペースの追求だった。この時点で、コンピューターの作り出すあたらしい世界はあくまで人間の内面に変化をもたらすための虚構であり、世界を変えるために現実に作用するものではなかった。しかし20世紀末にこのモードに終わりが訪れる。冷戦終結によるグローバルな市場の拡大と、インターネットを中心とした情報技術の進化は、再び若者たちに世界を変える可能性を信じさせはじめたのだ。ただし、今度は政治的アプローチではなく経済的なアプローチで。そして21世紀の今日において、政治はローカルなものであるのに対し経済はグローバルな存在だ。バラク・オバマとスティーブ・ジョブズのどちらの名前が1世紀後の世界史の教科書に大きく印字されるか、もはや議論の余地はないはずだ。彼ら「Anywhere」な人々は、グローバル資本主義によって出現した「境界のない世界」に情報技術を用いて自由にコミットし、そして変えていけると信じているのだ。
カウンターカルチャーの時代のヒッピーたちの育んだカリフォルニアのリベラルで反権威的な気風は90年代にパワーエリートたちの牽引したグローバル資本主義と結びつき、今日の若いビジネスマンたちに顕著な市場にイノベイティブな商品やサービスを投下することによる世界変革を志向する態度として受け継がれた。今日のシリコンバレーの文化を決定づけたこの傾向は「ヒッピーとヤッピーの野合」としてヨーロッパの社会学者たちに「カリフォルニアン・イデオロギー」と名付けられ批判を受けた。しかし今日においてはこのカリフォルニアン・イデオロギーこそがもっとも強い力で世界を変革してしまっている。今日においてカリフォルニアン・イデオロギーとは、シリコンバレーの起業家たちへの「悪口」を超えてむしろ世界中に出現している「Anywhere」な人々の世界観を表現するのに相応(ふさわ)しい言葉になっていると言えるだろう。そしていま、この思想に対するアレルギー反応が世界中で噴出しているのだ。
この「ヒッピーとヤッピーの野合」であるカリフォルニアン・イデオロギーを内面化した現代的なクリエイティブクラス、つまり「Anywhere」な人々は相対的にリベラルで多様性を擁護する傾向がある。「境界のない世界」に適応した人間にとって、「壁」は美学(ヒッピーの遺伝子)的にも経済(ヤッピーの遺伝子)的にも不要なものだからだ。そしてこれに反発する、没落した中産階級を中心とする「Somewhere」な人々は保守的で排他的な傾向をもつ。「境界のない世界」に適応できない人間は壁の再生を望むからだ。20世紀の左翼的な知性は、国民国家と資本主義をセットで批判することに集中していたが、もはや両者の支持層は大きく隔たりつつあるのだ。
その結果として世界はいま、まるでグローバル資本主義のプレイヤーであるあたらしい「境界のない世界」の「Anywhere」な住人たちと、ローカルな国民国家の市民として生きる旧い「境界のある」「Somewhere」な世界の住人に二分されているかのように見えている。だがそれは錯覚だ。実のところ既に境界は半ば(つまり経済のレベルでは)取り払われている。そしてだからこそ壁を求める人々が増殖している。不可避に拡大する「境界のない世界」に強く適応したのが「Anywhere」な人々であり、弱くしか適応できない人々は「Somewhere」な人々として見えているだけだ。21世紀の今日の世界で相対的に没落しつつあるのは戦後に形成された西側諸国の中流層たちだ。彼らの安定は旧第三世界からの搾取の産物であった。だが「境界のない世界」はこの構造を破壊しつつある。だからこそ彼ら(「Somewhere」な人々)は「壁を作れ」と訴えるトランプを支持し、「線を引き直す」ブレグジットを選択することで、あたらしい「境界のない世界」に対抗しようとしているのだ。
それはあたらしい「境界のない世界」の住人たち(「Anywhere」な人々)からすれば愚かな選択なのかもしれない。たとえば彼らはしたり顔でこう述べるだろう。「壁」を作ることで、ほんとうにラストベルトの自動車工たちの生活が上向くという保証はどこにもない。むしろあたらしい「境界のない世界」に開かれることではじめて現代における経済成長は可能となり、増えたパイを分け与える余地も生まれるのではないか、と。いま必要なのは、むしろあたらしい「境界のない世界」のもたらす圧倒的な成長とそれに対応したあたらしい再分配の仕組みなのだ、と。
だが、おそらくこのような彼らの「賢く」「正しい」言説は機能しない。それどころか、彼らのこの「語り口」こそが民主主義というゲームにおけるトランプ的なものの勝利を約束しているのだ。
ここで語られているのはあたらしい「境界のない世界」を生きる彼らが、旧い「境界のある世界」に取り残された人々に施しを与えるという筋書きだ。
このときあたらしい世界の「Anywhere」な住人たち(グローバルな資本主義のプレイヤー)は、無意識のうちにこう述べてしまっている。君たち「Somewhere」な人々(ローカルな民主主義のプレイヤー)はもはや世界に素手で触れることはできないのだ、と。世界に革新をもたらし、人類を前に進め、パイそのものを増やすことができるのは自分たちのあたらしいビジネスとテクノロジーであり、民主主義によって国家を操縦し、適切な再分配を求めることは(必要なことかもしれないが)副次的な問題に過ぎないのだ、と。あたらしい世界、「境界のない世界」に生きる自分たちはもはや民主主義のような旧い世界のシステムを必要としていないのだと。この主張が、民主主義というゲーム上で支持されることが果たしてあり得るだろうか?
そう、あたらしい「境界のない世界」の住人たちは、旧い「境界のある世界」の住人たちに、政治の、具体的には民主主義の場においては敗北する他ないのだ。なぜならば、あたらしい世界のアイデンティティは最初から政治を、民主主義を必要としていないからだ。現代の世界の構造上では、民主主義はこのあたらしい「境界のない世界」を原理的に肯定できないのだ。
ここにヒラリーとトランプの明暗を分けたものがある。トランプにラストベルトの自動車工の支持を集めたのは、むしろヒラリー(的なもの)の語り口が、あるいはあの日僕の Facebookのウォールに並んだ僕の友人たちの語り口が象徴する精神的な「壁」の存在なのだ。
もちろん、グローバル資本主義と情報技術が実現しつつある「境界のない世界」を、トランプとは正反対の思想から批判する立場もあり得るだろう。むしろ本書を手にする人のうち何割かは確実にこうした作法としての「左翼的な」態度を身につけているはずだ。しかし、「境界のない世界」の拡大を本書は前提として肯定する。実際にこのあたらしい世界の拡大は事実として格差と貧困をこの世界から大きく縮減している。そして世界からは貧困に、不衛生に、不十分な教育に苦しむ人々の絶対数も割合も急速に減っている。だとすると残された問題は、シリコンバレーの起業家とラストベルトの自動車工のあいだに再生産されつつあるあたらしい「壁」をどう乗り越えるのかという問題に他ならない。そしてこのあたらしい壁を乗り越える想像力の手掛かりをここでは考えてみたい。
あるいはピーター・ティールのようにもはや自由と民主主義は両立しない、という認識に立つ人々も実のところ少なくはないだろう。リベラルな気風を強くもつシリコンバレーの起業家たちの中にも少数派とはいえトランプを支持するプレイヤーが現れている。そしてティールはその代表者だ。ペイパル・マフィアの代表的人物としてシリコンバレーを牽引してきたティールのトランプへの接近についてはそのインパクトの大きさから様々な見解が述べられているが、その内容は概ね二通りに大別できる。ひとつは宇宙開発をはじめとする自身の起業家としての野心を実現するために政治への接近を必要としたティールが「逆張り」を行いこの危険な賭けに勝利したというもので、もうひとつはそもそもシリコンバレーのもつリバタリアニズムの遺伝子と保守主義の親和性を指摘するものだ。リバタリアニズムのルーツには国家からの独立と自助を美徳とする建国以来の「アメリカ的なもの」の精神が存在する。ティールらの掲げるサイバーリバタリアニズムとは、端的に述べれば情報技術によって国家からの完全な自立を志向する思想だが、アメリカとはこの(社会的な)反国家の精神こそが国家への(文化的な)回帰に結びつくという転倒したイデオロギーをその建国の理念として国民的なアイデンティティの基礎に置く社会なのだ。実際にかねてよりティールの文化的な保守性はたびたび指摘されており、そのトランプへの接近は必然的なものであると考えることができる。
またティールらの思想と活動は、加速主義と呼ばれる思想運動を生んでいる。「情報産業によって加速するグローバル資本主義(テクノキャピタリズム)の徹底による資本主義それ自体の超克」を訴えるこの運動はティールらの影響下にあるカルトの一派と目されており、トランプの支持層のひとつである新興の右派層(オルタナ右翼)に強い影響を与えている。リベラリズム、多文化主義など今日の民主主義社会のコンセンサスに対し懐疑的な態度を取る(ことで求心力を保つ)ことにその特徴があり、その結果としてデジタル・レーニン主義やネオ・ダーウィニズム的な優生思想などを評価する傾向をもつ。
かつてシリコンバレーを中心としたテクノキャピタリズムがヒッピーとヤッピーの野合(カリフォルニアン・イデオロギー)として批判されたことは前述した通りだが、こうしたカルトの台頭はサイバーリバタリアンとデジタル・レーニン主義の野合をもたらすのかもしれない。
「壁」としての民主主義
そしてこうした状況を俯瞰した上で、本書ではもう一度民主主義について考え直してみたい。たしかにあたらしい「境界のない世界」の住人たちが述べるように、この問題はあたらしい(境界のない)世界が拡大して、旧い(境界のある)世界を飲み込むことでしか解決しない。しかし残念ながら、前述したように今日の民主主義においてこの立場が支持されることはあり得ない。
そう、問題を履き違えてはいけない。問題はなぜヒラリーはトランプに敗れたのか、なぜブレグジットは成立してしまったのか、ではない。民主主義というゲームは原理的にあたらしい「境界のない世界」を支持できない。ここに問題の本質がある。
あたらしい「境界のない世界」を受け入れた「Anywhere」な人々はついこう考えてしまう。旧い「境界のある世界」の「Somewhere」な住人たちを説得するべきだと。「壁」を作ることも、EUから離脱することも、あなたたちの生活を救済することには必ずしもつながらない、むしろ逆効果をもたらすことすら考えられるのだ、と。しかしおそらくこの言葉は届かない。なぜならば、これは問題の本質を履き違えた言葉だからだ。賢く、意識の高いあたらしい「境界のない世界」の「Anywhere」な住人たちは、トランプの嘘を暴けば旧い「境界のある世界」の「Somewhere」な住人たちは、自分たちの側につくと考えがちだ。しかし問題の本質は別にある。トランプのアジテーションに嘘と誇張が多いことなど、実のところ誰にでも分かることだ。問題の本質は、にもかかわらず多くの人々が彼を支持していることなのだ。むしろ、こう考えたほうがいいだろう。彼らはトランプのアジテーションを「信じたい」のだ。彼らはトランプが真実を語るから支持しているのではなく、魅力的な嘘を語るからこそ支持しているのだ。
彼らは信じているのではなく、信じたいのだ。フェイクニュースをロクに検証もせずに拡散する知人に対して説得を試みるとき、大抵の場合は論理的にその矛盾を指摘し、証拠を挙げてそれが虚偽であることを説明することは効果を上げない。大抵の場合、彼らはかたくなにそれが虚偽であることを認めようとしない。仮に認めたとしてもこう反論する。「たしかにこの情報は解釈によっては間違っているかもしれない。しかし(たとえ虚偽であったとしても)この立場の意見を拡散することは社会にとって意味があることではないか」と。あるいは「この情報は間違っているかもしれないが、真面目にこの意見を拡散している自分の気持ちを否定しないでほしい」と。
誤解しないでほしいが、僕はフェイクニュースの検証や、陰謀論と歴史修正主義の批判が不必要だと述べているのではない。前提としてその努力は不可欠だ。しかしそれだけでは足りないことを指摘しているのだ。フェイクニュースに騙されないように、フィルターバブルに陥らないように、メディアリテラシーを粘り強く啓蒙すべきである。僕も他の仕事ではこうした運動を微力ながら支援してもいる。しかし、それだけでは補えないものがある。フェイクニュースを人々が信じるのは、それが正確な情報だと判断するからではなく、それを信じたいからだ。フィルターバブルに安住するのは、それに気づかないからではなくそれが心地よいからだ。ほんとうに問題とすべきは、フェイクニュースの偽りとフィルターバブルの陥穽(だけ)ではない。むしろそれを望んでしまう欲望のほうなのだ。だから僕たちがアプローチしなければいけないのは、彼らの「信じたい」欲望のメカニズムなのだ。
あたらしい(境界のない)世界を生きる「Anywhere」な人々と旧い(境界のある)世界を生きる「Somewhere」な人々とを決定的に分断しているものはなんだろうか。収入の多寡、教育程度、携わる産業の新旧──どれも正しいが、本質的ではない。彼我を隔てるものでもっとも決定的なもの。それは、世界に素手で触れているという感覚だ。
ローカルな国家よりも、グローバルな市場が上位にある今日において、このあたらしい(境界のない)世界に対応した「Anywhere」な人々──比喩的に述べればシリコンバレーの起業家たち──は世界に素手で触れている感覚とともに生きている。自分たちの仕事が、市場を通じて世界を変える可能性を信じて生きることができる。
対して、旧い(境界のある)世界の「Somewhere」な人々はどうだろうか。20世紀的な工業社会を生きる労働者階級が、グローバルな市場のプレイヤーであるという自覚をもつことは、世界に素手で触れている感覚をもつことは難しい。資本主義下における個人の経済的な価値とは、正確にはその人の社会的な評価に応じて金融機関や投資家から調達できる(借金できる)額のことに他ならないが、旧い世界を生きる労働者たちは雇用主からの報酬以外に資金調達の手段を知らない(国内で言えば、住宅ローンを組むときだけ、彼らは資本主義の本質に触れることになる)。その意味で彼らは資本主義を生きてすらいないのだ。
もしかしたらこう思う読者がいるかもしれない。世界に素手で触れることなんて、そもそも幻想ではないかと。もちろん、その通りだ。その指摘は正しいが、同時にこの議論の前提を理解していないことを証明してしまっている。僕は最初から幻想の話をしているのだ。あくまで人間が生きるためにいかなる幻想を必要としてしまうのかという話をしているのだ。 ある時期までは、(そして人類社会のある部分ではこうしているいまも)確実に人間が世界に素手で触れているという実感を得るために機能していた最大の幻想こそが僕らの民主主義だ。かのウィンストン・チャーチルはこう述べた。「実際のところ、民主主義は最悪の政治形態と言うことができる。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが」と──チャーチルはここで、おそらくは機能面から民主主義を(アイロニカルに)肯定したはずだ。だが民主主義はむしろ、人々の心の拠り所として必要だったのだ。世界に素手で触れているという実感を与えるために、必要だったのだ。
ついこのあいだまで、今日のグローバルな経済とローカルな政治という関係がまだ成立せず、インターナショナルな政治にローカルな経済が従属していた時代まで、世界に素手で触れているという実感はむしろ政治的なアプローチの専売特許だった。だからこそ、20世紀の若者たちは革命に、反戦運動に、あるいはナショナリズムに夢中になったのだ。民主主義とは、このあいだ少なくともこれまで試みられてきたあらゆる制度よりも確実に、誰にでも世界に素手で触れられる実感を与えてくれるものだった。そして、少なくとも世界の半分ではこうしているいまもそうあり続けてしまっている。この1票で、世界が変わると信じられること。僕の考えでは民主主義の最大の価値はここにある。だが、皮肉なことだがこの強力な機能のために、いま、民主主義は巨大な暗礁に乗り上げてしまっている。
20世紀的なインターナショナルな政治とローカルな経済の関係が、21世紀的なグローバルな経済とローカルな政治に逆転したときに、政治をコントロールする民主主義は世界を素手で触れることのできない人々の拠り所になっていったのだ。20世紀的な旧い(境界のある)世界に取り残されていると感じている大半の「Somewhere」な人々にとって、グローバルな市場を通じて世界に素手で触れることはとても難しい。しかし、この1票を投じてローカルな政治を変えられると信じることはできる。そして、そうすることで──それが世界に素手で触れることだと信じることで──まだ経済ではなく政治が、市場ではなく国家が世界の頂点だった旧い世界が終わりを告げていないことを信じることができる。かくして、民主主義のグローバル資本主義に対する抵抗としてトランプは当選し、ブレグジットは成立した。おそらくドナルド・トランプは他の誰よりも、自分がどのような力に支えられている存在かを理解していたのだ。だからこそ、彼はフェイクニュースを駆使し、人々が陥るフィルターバブルを活用したのだ。
嫌な話をしたいと思う。2016年の11月8日から9日にかけて、僕のFacebookのウォールでトランプの当選を嘆いてみせたグローバルな市場のプレイヤーたちと、こうしているいまもTwitterのタイムラインに溢れかえっているヘイトスピーカーや、歴史修正主義者たちで、投票行為に積極的なのはどちらだろうか。答えは書くまでもないだろう。いま、民主主義にコミットするインセンティブがあるのは主に時代に取り残された「Somewhere」な人々であり、より排外的でナショナリスティックな人であるほど、その動機は強くなってしまうのだ。
かつて村上春樹はこう述べていた。
〈僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。(中略)いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる〉
この「囲い込み」を人間が必要としてしまうのはなぜか。それはいま多くの人々が世界との番蝶を失い、世界に素手で触れる感覚を失ってしまっているからだ。そのため世界を「囲い込み」で限定し、自分の手が届くものにダウンサイズしようとしているのだ。
僕は本章の冒頭で、なぜサンダースではなく、トランプなのかと問題提起した。そしてその答えは明白だ。それはサンダースよりもトランプが、人々に強い「囲い込み」を与え、そのことで世界に素手で触れている感覚を与えているからだ。トランプが「壁を作れ」と述べその手段として排外主義的なナショナリズムを選択しているから「こそ」なのだ。それも、僕らの民主主義を用いて。インターネット時代の民主主義こそがいま、世界を否定の言葉で埋め尽くし、そして分断しようとしているのだ。
ここでふたつの問題は重なり合う。2020年の東京オリンピックが象徴する平成という「失敗したプロジェクト」と、2016年のトランプ/ブレグジットが代表するグローバル資本主義に対するアレルギー反応の勝利は、ともに情報社会下の民主主義の機能不全に起因する。今日の世界において残念ながら民主主義という名の宗教は、人々に世界に素手で触れているという実感を与える装置は、新旧の世界の分断を加速する装置にしかなっていない。この現実を受け入れた上で、どうこの暗礁から脱出するのか。それがいま問われていることなのだ。
こうして民主主義は、ポピュリズムで平成という「失敗したプロジェクト」を演出し、そしてトランプに支持を与えた。これが「目に見えない壁」の正体だ。そして民主主義以外の政治形態の選択肢を事実上もたない僕たちの社会は、いま、暗礁に乗り上げている。
誤解しないでほしいが僕は、日本やアメリカ、EU諸国の暗礁に乗り上げた民主主義が中国やシンガポールの開発独裁的な制度に対し劣っていると述べているのではない。前提として、それでも民主主義はもっとも相対的にリスクの低い政治制度だ。しかし、今日においては、その相対的な優位の程度は下方修正する必要があることを認識した上で民主主義を改良する必要がある。これまで、7回コールドで圧勝することを前提に考えることのできたゲームは、9回裏までの継投を視野に入れなければならなくなっているのだ。
僕たちはいま、自分たちが生み出した民主主義というシステムによって報復されようとしているのだ。僕たちは既に国家よりも市場が、政治よりも経済が広範囲に、不可逆に、決定的に人々の生を支配するあたらしい世界に生きている。しかし、僕らは民主主義という政治的なアプローチを超える意思決定のシステムをもっていない。それは言い換えれば、僕たちはどのようにして世界に素手で触れるべきなのかという問いが再浮上していることを意味する。いや、この問いは厳密な記述ではないだろう。僕たちはどのようにして世界に素手で触れるという幻想を機能させるべきなのか。それも、現代の情報環境と世界経済を前提に、どう再構築されるべきなのだろうか、という問いに直面しているのだ。
民主主義を半分諦めることで、守る
では、どうするのか。「民主主義を半分諦めることで、守る」というのが僕の解答だ。民主主義はインターネットはおろか、放送技術が生まれる前に発案されたものだ。インターネットポピュリズムに少なくとも既存の民主主義は耐えられない。この現実を、僕たちは受け止めるべきだ。
もはや民主主義は自由と平等の味方ではない。これは歴史を振り返ればそれほど珍しい現象ではない。ナチスを民主主義が産み落としたように、民主主義は常に民意の暴走が自分たちの自由と平等を脅かすリスクと隣合わせの制度だ。だが戦後の西側諸国の半世紀に亘る安定期は、人類にそのことを忘却させてしまったように思える。この時期の西側諸国の政治的、経済的安定は端的に冷戦下のパクス・アメリカーナの産物としての側面が大きい。それはマーシャル・プランの成果であり、民主主義の勝利ではない。この現実を人類はまず受け止めるべきだろう。そして冷戦終結から30年を経つつある今日のグローバル化した世界下における民主主義は情報技術に支援されこれからその本来の顔を取り戻すことになる。いや、既に取り戻していると言える。これからはほとんどの場面で、民主主義は自由と平等の最大の敵として立ちふさがることになる。今日において僕たちは軍国主義や共産主義と同程度(よりはやや低い程度)に、民主主義の暴走によって自由と平等がトップダウンではなくボトムアップにより抑圧されるリスクを管理していかなければいけない。だがいま述べたようにそれでも、他制度よりは相対的に民主主義はまだ暴走のリスクが低い。だからこそ「熟議を重視するべきだ」といった類の事実上無内容な精神論ではない、暴走リスクを減らすためのあたらしい知恵が必要なのだ。
もちろん前提として、究極的な結論としてはあたらしい「境界のない世界」を拡大し、旧い「境界のある世界」を飲み込むしかない。そうすることで、「Somewhere」な人々を「Anywhere」な人々に徐々に変化させていくしかない。しかし現時点では世界のどこでも働ける「Anywhere」な人々は一握りの成功者だ。したがって彼らのような自由を中流以下の人々が獲得できるようにするしかない。そうすることで、「Somewhere」な人々が承認欲求のはけ口として政治を利用するインセンティブを下げるしかない。だが、そうなるには(特にこの日本では)途方もない時間がかかるだろう。その途方もない時間を1年でも、1ヶ月でも縮める努力は最大限に行うことを前提とした上で僕たちは民主主義を(半分諦めることで)守り、そしてそのことで民主主義「から」自由と平等を守る他ないのだ。
民主主義と立憲主義のパワーバランスを是正する
そこで本書では三つの提案を処方箋として示したい。そのうちふたつは、既に議論されているものを紹介する。本題は最後のひとつ、つまり三つ目の提案だ。
まず第一の提案は民主主義と立憲主義のパワーバランスを、後者に傾けることだ。
立憲主義とは統治権力を憲法によって制御するという思想で、そのために民主主義としばしば対立関係に陥る。なぜならばたとえそれがどれほど民主的に設定されたものであったとしても、過去に定められた憲法を現在の民意が支持するとは限らないからだ。したがってあらゆる民主主義は憲法改正の手続きを憲法自体に組み込むことになる。言い換えればそれが民主的な憲法の条件で、ここで民主主義と立憲主義のパワーバランスが設定されることになる。そしてポピュリズムによる民主主義の暴走リスクを高く見積もらざるを得ない今日においては、このパワーバランスを立憲主義側に傾ける必要がある。もはや僕たちは民主主義で決定できる範囲をもっと狭くするべきなのだ。これから民主主義は、もたざる者の負の感情の発散装置になるしかないことを前提として、運用するしかない。民主主義を守るために、その決定権を狭めること。これしかない。これからは基本的人権など民主主義の根幹に関わる部分は立憲主義的な立場を強化することで、(奇妙な表現になるが)民主主義の暴走から守る他ないのだ。
たとえばこの日本では三権のうち司法の相対的な弱さが指摘されている。違憲立法審査権は有名無実化しており、法律に対してもその他の命令や規則に対しても最高裁判所が違憲判決を下すことは驚くほど少ない。その背景には最高裁判所の人事権を内閣が握るという不十分な三権分立の問題がある。またそもそも最高裁判所が一般事件の上告を処理することを重視した制度設計になっていることも問題だ。日本の最高裁判所は、47都道府県すべての地域をカバーし、民事、刑事を問わずすべての事件を担当するために事実上各高等裁判所からの上告の処理にそのリソースはほぼすべて宛てがわれることになる。また日本ではアメリカ・イギリス等と同様に付随的審査制と呼ばれる制度が採用されている。これは何らかの事件に対する裁判の判決に内抱するかたちで違憲審査を行う制度で、個人の権利保護に力点を置いたものだ。しかし、民主主義によって支持を受けた時の政権による立憲主義の有名無実化のリスクを軽減するためには、ドイツやイタリア等が採用する抽象的違憲審査制に現状の制度を近づけることが効果的だ。これによって憲法裁判所を設置し、法律や命令が合憲か否かを直接問うことが可能になる。これはあくまで一案だが、こうした司法の独立と強化による立憲主義の強化へ舵を切ることが必要となるだろう。
だが仮にこうした民主主義と立憲主義のパワーバランスの調整が実現したとしても、それが対症療法的なものでしかないことは忘れてはならない。繰り返すがこれから民主主義による国民国家のコントロールは基本的に自由と平等に背を向ける傾向を強めていく。生存権や表現の自由、男女平等といった基本的な人権については国際連合をはじめとする超国家的な枠組みの権限を強化すること、あるいはグローバルな市場の強力なプレイヤーたちが個人の自由な経済活動を要求する立場から国民国家の暴走を牽制することがより重要になる。今日においては、内部と外部からローカルな国民国家の民主主義の決定権を抑制することが必要なのだ。
「政治」を「日常」に取り戻す
民主主義を半分諦めることで、守る。その第二の提案は情報技術を用いてあたらしい政治参加の回路を構築することだ。
情報技術による政治のアップデートというと、一昔前はインターネットを用いた直接民主制のことを示していた。そしてその背景にソーシャルメディアを用いた社会運動の世界的な盛り上がりがあった。世界的にはアラブの春、日本的には反原発デモがこれに当たる。しかしどちらも無残な結果に終わったことは記憶にあたらしい。アラブの春は結果的に当該国の政情の不安定化とその帰結としてのISに代表されるカルト勢力の台頭をもたらしたし、反原発デモは既存の左翼勢力に小規模かつ一時的な復権を与えただけだった。
そして2016年の「敗北」を経た今日においてはそれどころか、フェイクニュースや陰謀論がソーシャルメディアでは定着してしまい、むしろ民主主義の破壊者と見なされている。
では、どうするのか。解答は民主主義の「回路」をあたらしく作ることだ。
本書を手に取る大半の人々が、民主主義といえば選挙による代表者の選出や国民投票による意思決定のことを思い浮かべるだろう。あるいはデモを中心とした社会運動のことを想起するはずだ。だが民主主義の回路とはほんとうにこのふたつだけなのだろうか。
東日本大震災後にいよいよ明らかになったのは、この国の民主主義は使い物にならない、ということだ。市民運動は旧態依然とした左翼の文化が残り続け「意識の高すぎる市民」たちの自分探しの域を出ず、選挙は相変わらず「意識の低すぎる大衆」たちを対象にしたどぶ板選挙が支配戦略として定着している。しかし、インターネットと民主主義はここにあたらしい政治参加への回路を構築する可能性を秘めている。
そもそも人間とはすべての選択を自己決定できる能動的な主体=市民でもなければ、すべてを運命に流されていく受動的な主体=大衆でもなく、常にその中間をさまよっている。
言い換えれば、20世紀的な想像力の限界はここにあったのだ。20世紀は「映像の世紀」だと呼ばれているが、この「映像」という制度は現代から考えると旧い人間観に立脚したものだと言える。
たとえば「映画」はとても能動的な観客を想定したメディアだ。対してテレビはとても受動的な視聴者を想定したメディアである。これは先ほどの比喩に当てはめるのなら映画は市民、テレビは大衆を対象にしたメディアだと言える。
しかしインターネットは違う。インターネットはユーザーの使用法で映画よりも能動的にコミットする(自分で発信する)こともできれば、テレビよりも受動的にコミットする(通知だけを受け取る)こともできる。もちろん、その中間のコミットも可能だ。
インターネットは、はじめて人間そのもの、常に「市民」と「大衆」の中間をさまよい続ける「人間」という存在に適応したメディアだと言える。にもかかわらず、2010年代の人類はインターネットを「大衆」を動員するために用いた。ここに過ちがあったのだ。
同じことが、たとえば政治制度にも言える。多くの民主国家では現在、二院制が敷かれている。上院と下院、参議院と衆議院。これは要するに「市民」を対象とした熟議と「大衆」を対象としたポピュリズムでバランスを取る、という発想だ。
ここから分かるのは、20世紀までの人類は技術的に人間の、極端なふたつの側面、つまり「市民」か「大衆」かを想定した制度しか作ることができなかった、ということだ。そして技術的限界から「仕方なく」その両者を並置させてバランスを取っていたのだ。しかしインターネットは、いやインターネットを下支えする情報技術の発達はこの二項対立を崩す可能性を秘めている。しかし、人類はその用い方をこの四半世紀のあいだ間違え続けたのだ。
たとえば、団塊ジュニア世代を中心としたこの国のインターネットのオピニオン・リーダーたちは東日本大震災後に第二のテレビとして、ポピュリズムの器としてインターネット(具体的にはTwitter)を用いようとした結果、敗北していった。ボトムアップのインターネットポピュリズムはトップダウンのテレビポピュリズムを緩和するどころか下支えする。それは今日の日本社会を観察すれば明白だ。
あるいは、震災直後に「国会をインターネット生中継して視聴者からのコメントを可視化すれば民主主義が発達する」という主張が少しだけ話題になったが、それがまったく実効性を欠いた机上の空論に過ぎなかったことはもはや明白だ。これは熟議=国会と、ポピュリズム=インターネット生中継とのあいだでバランスを取る、という発想に基づいたものだが、残念ながらこれでは20世紀以前の社会観から何も発展していない。熟議とポピュリズム、市民と大衆、ストックとフローでバランスを取る、という発想自体が過去のものであり、この発想から逃れられない限り人間は情報技術を使いこなせないのだ。いま必要なものはその中間のものへのアクセスであり、今日の情報技術の真価はそこにこそある。
したがってこのとき情報技術を用いる対象は「市民」であっても「大衆」であってもならない。必要なのは市民を動員してデモに連れ出すことでも、大衆を動員して選挙に連れ出すことでもない。人間を(意識の高すぎる)市民化すること、あるいは(意識の低すぎる)大衆化することもなく、人間本来の姿のまま政治参加を促す回路だ。
市民が街頭のデモに参加するとき、あるいは大衆が投票所に足を運びテレビの開票速報を見守るとき、彼ら彼女らは非日常的な体験の中にいる。普段の労働や学習を中心とした日常の生活から切断された非日常に動員されている。そしてそのことで、人間本来の姿を失い(意識の高すぎる)市民/(意識の低すぎる)大衆に加工されてしまっている。街頭のデモに参加し、シュプレヒコールを叫ぶ「市民」たちは、このときたしかに世界に素手で触れている感覚を得ている。それはデモに「動員」されて、等身大の自分を一時的に忘却して、イデオロギーと自己同一化することで得られる幻想だ。あるいは選挙という祝祭をテレビショーとして消費する「大衆」たちもまた、この瞬間は世界に素手で触れていると錯覚することができるだろう。ついでにお気に入りのコメンテーターの話したことをコピー・アンド・ペーストしてTwitterに投稿して何かを主張した気になれば完璧だ。いずれにせよ彼ら彼女らはこのとき非日常に「動員」されている。デモは意識の高すぎる「市民」を、選挙は低すぎる「大衆」を非日常に「動員」するシステムなのだ。
民主主義をデモ/選挙といった非日常への動員から解放する。そのことによって、ポピュリズムの影響力を相対的に下げる。いまや自由と平等の敵となりつつある民主主義の暴走リスクを下げることが、必要なのだ。
では、どうするべきか。処方箋はふたつある。ひとつ目は自民党や公明党や共産党といった55年体制下から続く既存政党の組織票にメディアを用いたポピュリズムで対抗する、という発想それ自体に限界があったことを認めることだ。歴史の教える通り、ポピュリズムはその定義上無党派の浮動票に対するアピールでしかない。そのため、強固な組織票をもつ勢力に長期的には敗北してしまう。ならば、「こちら」も組織票をもてばよい。
そのためにまず個人と国家の中間に、家族でも地域社会でもましてや戦後的企業のムラ社会でもない、現代的な連帯のモデルを実現する。もちろん、いまさら「インターネットを通じた町おこしで地域共同体を再生」といった類の与太話をここに書き連ねようとは考えていない。
平成の改革勢力の本来の支持基盤は、都市部の比較的若いホワイトカラー層であった。しかし、彼らは同時に特定の支持政党をもたない無党派層でもあり、その多様なワーク/ライフスタイルから組織化も難しいと言われていた。そのため、平成の改革勢力たちはテレビポピュリズムに依存し、その動員対象を必要以上に拡大せざるを得なかったのだ、と。
しかし、今日ではどうだろうか。55年体制の焉終か(しゆうえん)ら30年を経たいま、この前提は大きく変化している。正社員の夫と、専業主婦の妻とその子供からなる家庭が郊外の持ち家に住む、というスタイルは若い現役世代では過去のものになりつつある。多様化したワークスタイルをもつ共働きの家庭が(それゆえに)都心の賃貸に住み子育てに勤(いそ)しむ。新聞/テレビではなくインターネットを情報源にし、駅前のデパートよりもAmazonと楽天で買い物をする。彼らは明らかに「生活」の次元で昭和の日本人たちとは異なる世界に生きている。彼らは、戦後的な社会装置と文化から逸脱した存在だ。労働組合から医師会や農協といった戦後政治を支えた団体組織から、彼らは組織的にもそしてそもそものワーク/ライフスタイル的にも逸脱している。たとえば今日においては平成の改革勢力の流れを継承する人々がこれらのあたらしい日本人たちの組織化を精力的に行ってその支持基盤を固めることも不可能ではないはずだ。そして、一見ばらばらの彼らをつなぐ道具として、地域コミュニティからテーマコミュニティへと中間的な共同体の性質が移動せざるを得ないこの時代における連帯のための道具として、はじめてインターネットは希望になり得るはずだ。これまでのやり方ではつなげなかったものたちをつなげるのが本来のインターネット、なのだから。
インターネットはいま、肥大したソーシャルネットワークから離脱したつながりを求めつつある。良質な情報はサブスクリプションの有料サービスに、信頼性の高いコミュニティはオンラインサロンに閉じる動きが活発だ。これを本来のインターネットの精神に対する反動だと断じることもできるかもしれない。インターネットとは、世界中のどこからでもアクセスできるその開放性こそに本質の一端があったことは間違いないからだ。だが、逆にこう考えることもできる。インターネットが人間の吐き出した言葉と言葉をつなげるというのは、あくまで技術的な制約がもたらした初期の現象であり、そのもっとも本質的な役割は血縁や地縁や職業集団を超えて人間関係を結び直すことにある、と。インターネットは適度に閉じることを覚えたいま、むしろ本来の顔を取り戻しつつあるのかもしれない。こうしたコミュニティの再編は言論の流通による世論形成よりもより深いレベルで政治を変えるポテンシャルを秘めている。
そしてふたつ目はこうして生まれたあたらしい日本人たちの団体によるロビイングや陳情を中心とした政治活動だ。そもそも、戦後日本の政治は「意識の低すぎる」選挙と、「意識の高すぎる」デモとが両方空回りすることで暗礁に乗り上げてきた。そして良くも悪くも、機能していたのがこうした団体による個別のコミュニケーションだったはずだ。ときに談合と縁故資本主義の温床となりがちなこうしたコミュニケーションをフェアでオープンなゲームに改革すること。その上で、あたらしい日本人たちの要求を、彼らの団体がこのゲームの上で実現させてゆくこと。この選挙とデモの中間に、社会を変える手掛かりがある。
その具体的な手段としてここでは情報技術を用いたあたらしい政治参加の回路の構築を提案したい。国内において広く認知されているとは言い難いが、2011年前後の失敗を踏まえた上で活動している市民運動や社会起業家の試みが内外に拡大している。そしてこれらの共通点は選挙という非日常的なお祭りではなく、日常の生活の中に政治参加への回路を設定するという発想だ。
その代表例がクラウドローだ。近年、市民が情報技術を活用して社会の課題を解決するシビックテック(civic、つまり市民とtech、つまりテクノロジーをかけ合わせた造語)と呼ばれる運動が現れている。クラウドローはその手段のひとつで、インターネットによって市民が法律や条例などの公的なルールの設定に参加するサービス群のことをさす。
たとえば台湾では「vTaiwan」というプラットフォームが注目を浴びている。これはオンラインとオフラインにまたがる官民連携のルール形成を目的としたプラットフォームだ。台湾は少なくともアジアにおいては、もっとも意欲的に民主主義の情報技術によるアップデートに取り組んできた(事実上の)国家だ。2010年代前半のインターネットの普及を背景にした市民運動の世界的な同時多発は、台湾を舞台にも展開している。当時の台湾政府は2008年に馬英九が総統となり国民党が政権復帰すると中国との政治的、経済的接近に舵を切り独立派の市民からの反発を呼んでいた。そして2014年、中台間でのサービス業開放によって経済統合を進める「サービス貿易協定」が強行採決されると学生たちが立法院(台湾の国会)に突入した。市民の強い支持を背景に占拠は24日間にも及び、馬英九政権は協定内容の大幅見直しを余儀なくされた。このとき議場に飾られたひまわりの花から「ひまわり革命」と呼ばれているこの運動は、思わぬ副産物を産み落としている。それが「vTaiwan」だ。馬英九政権は市民運動の中核となった学生勢力との対話のチャンネルを模索し、それに台湾市民のテックコミュニティ(g0v(ガブゼロ))が応えるかたちで「vTaiwan」は生まれた。
現在(2019年12月)の蔡英文が率いる民進党政権は、著名なプログラマーであり、オープンガバメントの推進運動などを通して社会運動家としても知られる唐鳳を弱冠35歳の若さにもかかわらずデジタル総括政務委員に就任させた。シビックテックの推進は「ひまわり革命」から蔡英文政権の成立へと至る台湾のあたらしい民主主義のひとつの象徴なのだ。こうした背景のもと、このvTaiwanを用いて、台湾ではライドシェアサービス(ウーバー)の参入と既存のタクシー業者との調整や、リベンジポルノに対する罰則の規定、市街地におけるドローン活用を推進するための適切な規制などが市民間の協議によって提案され、行政に採用されている。
vTaiwanには様々なオープンソースが用いられているが、そのうちのひとつ「ポリス」は、ユーザーが自由に意見を述べることができるその一方で、あるユーザーが他のユーザーの意見にコメントをつけることはできない。あくまで賛成/反対の票を投じることができるだけだ。そして議論が進行すると参加したユーザー全員の意見がオピニオンマップとして表示される。そこで、問題の対立点がどこにあるのかが可視化される。こうして感情的な論争や議論の綜錯を回避し専門家の意見が集約され具体的な提案が作成されていく。ここにはボトムアップの意思決定は存在するが、多数決の生むポピュリズムは存在しない。
このvTaiwanにおけるルールメイキングで要求されるのは、それぞれの課題に関係する分野での高い専門性だ。もちろんここで扱われている課題について意見を述べることは誰でもできる。しかし、行政の担当部署と同等か、多くの場合それ以上の専門的な知見がなければ実用的なルールメイキングは不可能だ。vTaiwanに参加しているのは主に現地のシビックテックの団体のメンバーだが、彼ら彼女らはそれぞれの職業で培われた専門性を発揮し、適切なルールを策定し行政に提案を行っている。
こうしてルールメイキングに関わるメンバーがその業生で得られた知見を活かし、公的なルールメイキングに関与していることがvTaiwanを考える上で重要なポイントだ。
前述したように既存の民主主義は人間を公的な存在(市民)と捉えるか、私的な存在(大衆)として捉えるかしかできていない。
だが実際に人間はその社会生活のほとんどを働くことで、市場のプレイヤーとして生きている。しかし既存の民主主義ではその人間の社会生活の大部分を占める職業人として政治に関与することは(代議士、行政府の職員、ジャーナリストといった政治そのものを仕事にする人々を除けば)できない。しかし現在の情報技術はそれを限定的なかたちでありながらも可能にしはじめているのだ。これらのクラウドローにおいて、人間は「市民」でも「大衆」でもなく、その中間体、具体的には職業人としてその専門的な知見を活かし政治に関与するのだ。
たとえばあるインターネットビジネスを手掛ける企業に勤める人物を想定しよう。この人物はこれまで多くのシェアリングエコノミーのサービス、とりわけクラウドソーシングサービスに深く関わり、多くの知見をもっている。そんな彼/彼女がクラウドローでライドシェアの国内導入について、適切な規制を定めるルールメイキングに参加する。このとき彼/彼女の日常の延長線上に政治は存在する。
市民/大衆を非日常(化された政治)に動員することで成立する今日の民主主義に対し、シビックテックの試みはあくまで日常に留まったまま個人と政治を接続する。そしてこうしたあたらしい回路を導入し、その決定力を保証することで非日常への動員=ポピュリズムの暴走リスクが高まらざるを得ない既存の民主主義の決定力を相対的に低下させることができる。非日常に動員された市民/大衆のポピュリズムから、日常を生きる職業人の手に政治を取り戻すのだ。
もちろん第一の提案がそうであるようにこの提案も万能薬ではない(そんなものは当然どこにも存在しない)。たとえばvTaiwanをはじめとするクラウドローの多くが直面しているのが、その法的な根拠の薄弱さだ。これらのサービスは産声を上げたばかりの回路であるがゆえに、既存の法体系にどのように組み込まれるべきかの議論もはじまったばかりだ。 vTaiwanの場合、そこで策定された提案は行政に対して一切の法的な強制力はもたない。現状vTaiwanが影響力を行使しているのは、蔡英文政権の進める行政の情報化の一環として、ライドシェアやドローンといった情報技術に強く関係し、かつ専門性の高い課題についてはシビックテックを活用しルールメイキングを試みるという方針が取られているからに過ぎない。
vTaiwan以外にもDecide Madrid(スペイン)、Better Reykjavík(アイスランド)などがクラウドローの成功例として知られている。そしてこれら世界中で勃興しつつあるクラウドローでは労働、教育、社会保障など、より広範な課題に対するルールメイキングが期待されている。そして関与のステージも狭義のルールメイキング(条例や法律の素案作成)のみならず前調査から政策評価まで多岐に及ぶことが期待されている。こうしたクラウドロー的なルールメイキングを民主主義の意思決定のシステムに法的にどのように埋め込むのかが今後問われることになるだろう。
またクラウドローの開放性と規模の問題についても留意が必要だろう。たとえば台湾では、シビックテックによるvTaiwanと並行して政府の主導するJoinと呼ばれるサービスが運営されている。これは市民がオンライン上で陳情を実施し、討論するためのプラットフォームだ。
このvTaiwanとJoinはどこが違うのか。ひとつは前述した通りそれが民間のものか政府のものか、運営主体の違いだ。そしてもうひとつはその規模だ。2018年の段階で vTaiwanの参加者は20万人であり、Joinの参加者は500万人だ。台湾の人口は約2300万人なので、Joinの規模の大きさが分かるだろう。しかしクラウドローにおいてコミュニティの規模はメンバーの専門性とトレードオフの関係にある。Joinのアドバンテージは、参加者の専門性の低さが結果的により広範な市民生活の課題(病院、公園などの整備、犯罪防止の取り組み)を取り上げることを可能にしていること、vTaiwanと同じようにその提案に法的な強制力こそないものの、官製のサービスでありかつ数千人規模の陳情の実現が容易であるために政府への圧力が働き易いことが挙げられる。だがその反面Joinでは vTaiwanのように高度に専門的な議論とルールメイキングは難しい。そしてメンバーの専門性の低さは人間の「働く」という日常の回路と政治を接続するクラウドローのアドバンテージを自ら放棄し、インターネットポピュリズムの一形態に接近してしまっていることが挙げられる。いずれにせよ、重要なのはもはや民主主義が自由と平等に資する可能性が極めて低くなったいま、ポピュリズムのリスクを相対的に低減できる意思決定の回路を導入することだ。もちろんそれはトップダウンのデジタル・レーニン主義ではなくボトムアップのものでなければならない。そのためには非日常から日常へ、市民/大衆の動員から職業人の参加へと民主主義の重心を移動させる必要がある。シビックテックによるクラウドローは、このような背景から誕生したひとつの暫定解である。
インターネットの問題はインターネットで
さて、このふたつの提案が十分に実現されていない現在において民主主義という回路を通じて、世の中が肯定的に変化すると信じることは難しい。もちろん、少しでもマシな状況に加担するために、僕も投票には行くだろう。場合によっては支持者や支持政党の応援のために筆を執るかもしれない。しかし、その一方で、僕たちはいよいよ「民主主義を半分諦めることで、守る」段階を迎えたことを受け入れるべきなのだ。そしてポピュリズムという誘惑を捨てることを主張する僕は、もはや民主主義は暗礁に乗り上げたシステムであるのだというニヒリズムも一緒に捨てている。これは、そのための本でもある。そしてそのためにこそもう一度インターネットの問題について考えてみたい。インターネットは平成の最大の希望であり、そして最大の失望だった。だからこそ、平成という「失われた30年」を超えるために、その轍(てつ)を踏まないためにこそ、僕たちはインターネットの問題を正面から捉え直す他ないのだ。ここを、避けては通れない。
そして第三の提案はメディアによる介入で僕たち人間と情報との関係を変えていくことだ。端的に述べれば「よいメディア」を作ることだ。そしてこのあたらしいメディアにはいまこそインターネットを用いるべきだと考えている。きっと多くの読者が(最後まで読むこともなく)この結論をあざ笑うだろう。いまさらインターネット? なぜ、いまインターネット? インターネットへの過大評価こそが、今日の暗礁に乗り上げた民主主義を生んだのではないか? もちろん、まったくもってそう思う。実際にこの本のここまでを注意深く読み返してもらえれば、その前提は当然共有されていることはよく分かるはずだ。そしてこうした批判は織り込んだ上で、僕はそれでもインターネットを用いたアプローチが必要だと述べているのだ。
書名から明らかなことだ、もったいぶる必要もない。先に結論を述べてしまおう。
いま必要なのはもっと「遅い」インターネットだ。それが、本書の結論だ。
今回の公開はここまでです。このあと、第2章では「モノからコトへ」「他人の物語から自分の物語へ」をキーワードに、現代のグローバルな情報環境について分析し、整理します。そして第三章では、少し寄り道してーー最後まで読むとそれが寄り道ではないとわかると思うけれどーー吉本隆明という思想家の仕事を参照することでなぜ、人間はインターネットの「速さ」に負けてしまうのか、その問題の本質はどこにあるのかを解き明かします。そのうえで、最後の4章はでは、僕(宇野)はどうするのかというマニフェストを公開します。
続きが気になった人は、ぜひ本を手にとってください。きっと、世界の見え方が変わるはずです。
【目次】
序章 オリンピック破壊計画
TOKYO2020
平成という「失敗したプロジェクト」
「動員の革命」はなぜ失敗したか
走りながら考える
第1章 民主主義を半分諦めることで、守る
2016年の「敗北」
「壁」としての民主主義
民主主義を半分諦めることで、守る
民主主義と立憲主義のパワーバランスを是正する
「政治」を「日常」に取り戻す
インターネットの問題はインターネットで
第2章 拡張現実の時代
エンドゲームと歌舞伎町のピカチュウ
「他人の物語」から「自分の物語」へ
「他人の物語」と映像の世紀
「自分の物語」とネットワークの世紀
『Ingress』から『ポケモンGO』へ
ジョン・ハンケと「思想としての」Google
仮想現実から拡張現実へ
拡張現実の時代
個人と世界をつなぐもの
物語への回帰
「大きな物語」から「大きなゲーム」へ
文化の四象限
第3章 21世紀の共同幻想論
いま、吉本隆明を読み直す
21世紀の共同幻想論
大衆の原像「から」自立せよ
「消費」という自己幻想
吉本隆明から糸井重里へ
「政治的なもの」からの報復
「母性のディストピア」化する情報社会
第4章 遅いインターネット
「遅いインターネット」宣言
「速度」をめぐって
スロージャーナリズムと「遅いインターネット」
ほんとうのインターネットの話をしよう
走り続ける批評
端的に言うとね。