さまざまな分野の知恵とテクノロジーを組み合わせて、人間が自然と共に生きるあたらしいかたちを模索するプロジェクト「風の谷を創る」。この連載ではこのプロジェクトに関わる多彩なメンバーたちの横顔を紹介していきます。今回は長年出版社でさまざまな編集に携わってきた岩佐文夫さんに、これまでのお仕事について、そして「風の谷」のこれまでの活動について伺いました。「編集者」から見た「風の谷」は一体どんな運動なのでしょうか?
「風の谷を創る」のこれまでの連載記事は、こちらにまとまっています。よかったら、読んでみてください。
端的に言うとね。
社会に影響を与える「編集」との出会い
──岩佐さんにこうやってお話を伺うのは実は2度目なんですが、今日はより詳しく、岩佐さんのご経歴から「風の谷」の今後についてまで伺っていきたいと思います。改めて、よろしくお願いします。
岩佐 こちらこそ、よろしくお願いします。宇野さんのネットテレビ番組で1度目にお話ししたときにも言ったんですが、安宅(和人)さんが「編集者として岩佐さんと宇野さんは似てる」っておっしゃってたんですよ。へーと思って、それから僕は宇野さんに興味を持ったんですね。
──それ、どの辺が似てると思ったのか気になりますよね。岩佐さんは編集者として長年ご活動されてきていると思うのですが、そもそもこういった仕事に携わるきっかけはなんだったのでしょうか。
岩佐 単なる偶然ですね。恥ずかしながらメディアや書籍の編集の仕事を自分で選んだわけではないんです。
──そうなんですか? それ、かなり意外な気もします。
岩佐 実は小学校3年生までひらがなが書けなかったくらい、国語とは無縁で。大学に入るまでほとんど本を読んでこなかったタイプの人間です。就職活動もまったくできなくて、いろんなご縁でやっと入れていただいたのが、日本生産性本部という財団法人でした。僕は密かに海外技術協力をやりたいと思っていたんです。
でも、たまたま最初に配属されたのが出版部でした。小さなセクションだったんですが、配属が決まったときには人事の人に「どうやったら海外技術協力部に異動できるんですか?」なんてずっと聞いていたくらい、出版やメディアの仕事には関心がありませんでしたね(笑)。
──出版部ではどんな書籍をつくられていたんでしょうか。
岩佐 企業の人事や組織マネジメントにまつわる本をつくっていました。ビジネス書の中でも比較的専門的な分野のものが多かったです。それだけやっていてもつまらないなと思って、そのうち自分で新しい著者を開拓するようになりました。30代前半は、いわゆるビジネス書の王道に近いものを出そうという試みを自分でやっていました。
当時は「マルチメディア」という言葉が出てきた頃で、書店には一斉にマルチメディアについての本が並んでいた時代でした。インターネットが出てくる直前のことですが、僕はこれにすごくショックを受けたんですね。そこで「こうやって新しい、これからの時代をつくるような本をつくりたい」と思って、その方面の著者を開拓するようになりました。そのときに知り合ったのが、当時の日本総合研究所の部長だった、田坂広志さんでした。
アメリカではすでにインターネットがインフラになって、社内のイントラネットがこれから組織に導入されるということで、かなりブームになっていました。ただ、こういう本を書ける人をすごく探したんですが、日本ではほとんど事例がなくて、導入したという一部の企業の方に聞いても「こういうことは日本企業はできないよ」と否定的な見方をされていたんです。だから、かなり早い段階で田坂さんと知り合って、執筆をお願いして、本を書いてもらえたのは、僕の一つの成功体験です。
自分がつくった本が本屋に並ぶのはかなり恥ずかしいんですが、同時にすごく嬉しいんですよね。読んだ感想が来たり、雑誌に取り上げられて話題になったり、著者にいろんな声がかかるようになったりすると、20代の若造ながら、こうやって社会に影響力を与えられる仕事なんだな、とすごく実感したんですよ。
──それはメディアの裏方の仕事の醍醐味ですよね。そこからダイヤモンド社に移られたのには、どんな経緯があったんでしょうか?
岩佐 書籍編集をしていた当時、本を書いたことがない人を発掘するということに喜びを感じていて仕事がとにかく楽しかった。自分が発掘した著者が、いろんな出版社から本を出すようになる。そういうことがすごく楽しかったんですね。人に恵まれたというのも大きいと思います。
ただ、ちょうどそういうときに「そろそろ異動だね」という話になったんです。よく考えると、14年くらい同じ部署にいるやつも珍しかったんですよね。これからは管理職だ、となったときに「ちょっと待てよ。僕がこの会社で今やっている仕事よりやりたいことはあるかな?」と冷静に考えたら、もう当初の海外技術協力への熱が冷めていることに気づいたんです。
そうして自分がこの会社で同じ仕事をずっとやるのはかなり狭き門だなと思って、「会社辞めます」と宣言をしました。当時は36歳で、年齢が微妙で転職が難しいだろうなと思っていたんですが、いくつかの出版社が声をかけてくれて、その中で一番早く動いてくれたのがダイヤモンド社でした。
本を書いたことがない人の本をつくる 書籍編集の面白さ
──ダイヤモンド社でのキャリアについてもお伺いしていきたいのですが、最初から「ハーバード・ビジネス・レビュー」の編集を担当されていたんでしょうか?
岩佐 17年いましたが、雑誌、書籍、雑誌の順番で編集をしていました。最初は雑誌「ハーバード・ビジネス・レビュー」の編集者です。ちょうど2000年のことで「ハーバード・ビジネス・レビュー」が月刊化されるタイミングで、編集者を探していました。僕はそれまでずっと書籍しか担当していなかったので、雑誌に対してすごく興味があったんです。
当時は日本で言うとグロービスなんかが開校して、MBAやビジネススクールという言葉が注目され始めた頃でした。あとは、いわゆるマッキンゼー、BCGといった外資系コンサルティングファームが就職先としても注目を集め始めていました。当時月刊化したのも、そういう流れからでした。
──実際、雑誌の仕事を担当されてどうでしたか?
岩佐 誰が悪いという話ではまったくないんですが、雑誌はやはり、編集長のものだということを実感しましたね(笑)。それに対して、やはり書籍だと自分の担当本で、自分が編集長になれるじゃないですか。もっと自由に本をつくりたいと思うようになったんです。
もうひとつは、雑誌って読者層が変わらないんですよ。毎月同じ読者層を相手にする感じで、いわば雑誌に期待されていることも明確です。書籍だと一冊ごとに読者を変えることもできるんです。そんな窮屈さも感じていて、書籍編集に移らせてもらうことにしました。
──ということは、書籍の編集を担当されていたのは、2000年代半ばからでしょうか。当時はどのような書籍をつくっていたんでしょうか。
岩佐 2004年から2012年ですね。まず、依然と同様、本を書いたことがなかったり、あまり注目されていない人に書いてもらうことにフォーカスしていました。そんな中で現在、経営競争基盤の冨山和彦さん、立命館APU学長の出口治明さん、元マッキンゼーの採用マネジャーだった伊賀泰代さん。それから、今、資生堂の社長をやられている魚谷雅彦さんなどに書いてもらうことができました。
あとは、せっかくダイヤモンド社にいるから、経営学の王道の本をつくろうと思っていました。ジェイ・B・バーニーという人の『企業戦略論』という上中下巻は、15年以上前の本ですが、今でも増刷しているようで嬉しいですね。
──そういった著者の方々は、どのような基準で選ばれているんでしょうか?
岩佐 本物でかつ異端児が好きです。たとえば冨山さんの書籍は、『会社は頭から腐る』というタイトルなんですが、冨山さんは一貫して大企業の変革と新たに求められるリーダー像を主張されていました。正面切って誰も言わないことを、王道の論理で論破される。すごくすがすがしい異端さがありました。出口さんは60歳を越えてからライフネット生命を起業されました。ネット生保の草分けですが、当時の保険業界の課題を伺っていると、ネット生保に行き着く必然性が王道に思えました。何より、田坂さんもそうですが、冨山さん、出口さんとも人柄が圧倒的に素晴らしく、面白い人に会ったら、人に話したくなるじゃないですか。基本はその延長ですね。
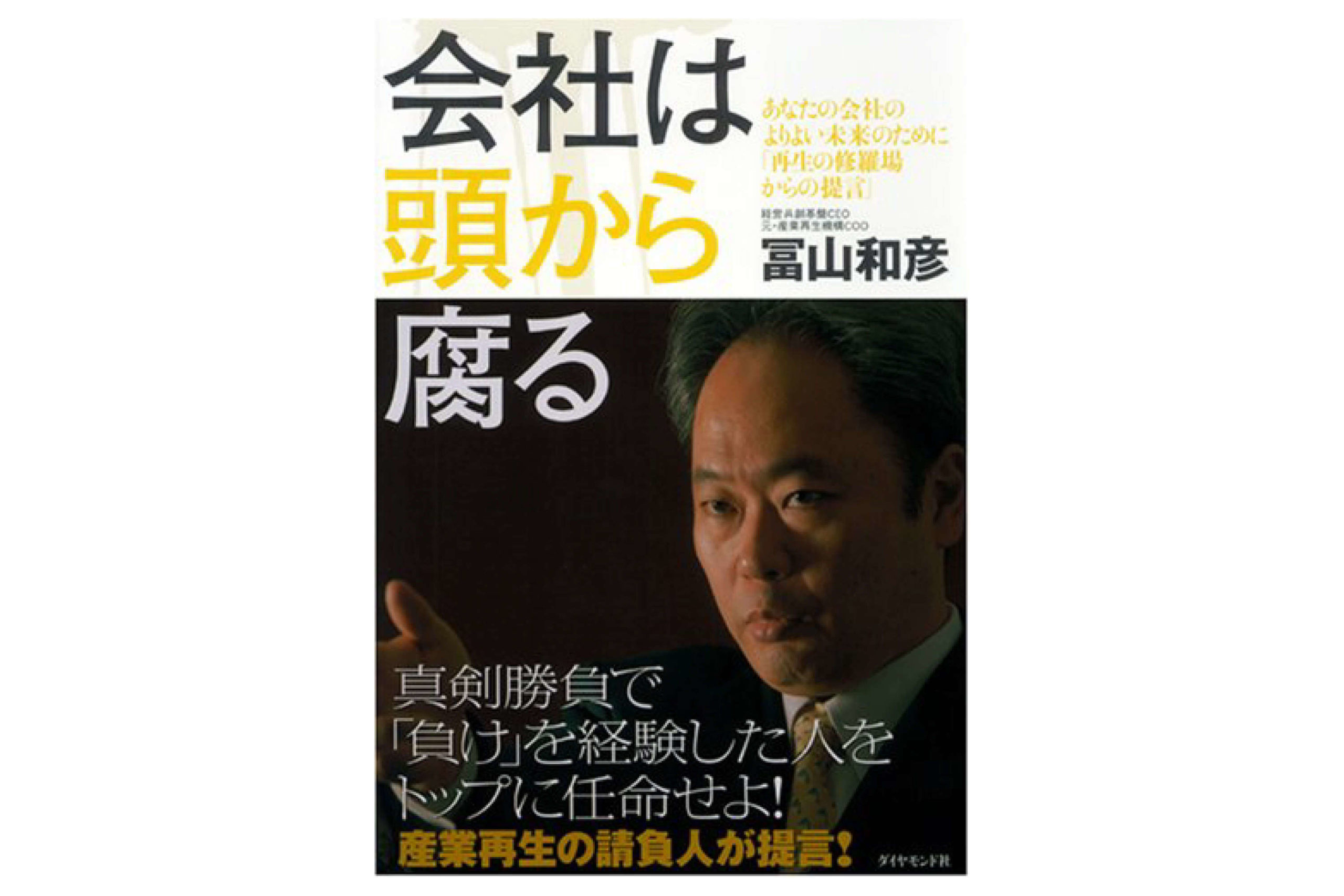
──そういった人脈はどのようにつくられているんでしょうか? もちろん、企業秘密かもしれませんが……。
岩佐 特別なことはしていません。そういう意識を持っていることは大きいと思いますね。あと本を書いたことのない人の本を出すのはリスクも大きいです。でも、宇野さんはわかると思うんですが、情報は出せば出すほど集まってくるじゃないですか。「あいつは本を書いたことがない人が好きだ」という評判が定着したら、「実績ないんだけど面白い人がいる」って言って、いろんな方から紹介してもらえるようになる。冨山さんや出口さんとの出会いも、最初はそういう知人からの紹介でした。
もう一つ心がけていたのは、1回会って面白いと思ったときに、2回目に会うチャンスをつくるということです。相手にも自分が興味を持ったことをきちんと伝えます。その上で、「今度また時間もらえませんか」と伝えて、より深く話を聞く機会を狙います。一緒に食事をしたり、お酒飲んだりを繰り返して仲良くなるということは一切しません。むしろストレートで不器用かもしれないけど、一緒に小さなことをやって、手ごたえをつかんでから大きなことをお願いするという感じですね。「次も会いたい」と伝えることも、そういう「小さいこと」の一つだと思います。
そういう意味で言うと、処女作を手掛けるというのは、本人のモチベーションが高いので、色々な面で心配が少ないことも多いですよね。たとえばすでに10冊書いている人に11冊目を依頼するのと、1冊目を依頼するのでは、心の持ち方が全然違うじゃないですか。だからこそ、「なぜあなたが本を書く必要があるのか」と説得するときは、自分でも気恥ずかしいような言葉を並べて喋っていたと思います。
東海岸から西海岸へ ──「ハーバード・ビジネス・レビュー」編集長として
──書籍から雑誌に戻られて担当されたのは「ハーバード・ビジネス・レビュー」の編集長ですよね。そのときはどういうことを意識されていたんでしょうか? 先ほど「雑誌は編集長のもの」とおっしゃっていましたが……。
岩佐 まさか自分が編集長をやると思っていなかったので、「編集長をやってほしい」と言われたときに「これくらい大きな条件のんでくれ」って偉そうに4つくらい条件を出したんです。そうしたら担当役員が「社長と相談する」とか言って、1週間後には「社長OKだからやるよね?」とか言われて(笑)。会社も本気なんだな、と思って腹を括りました。
編集部では「みんなが編集長になったつもりでやってほしい」という思いは伝えていました。「自分が編集長だったらどうする?」という視点で考えてもらいたかった。そして「雑誌は編集長のものだ」と言わせず、みんなが楽しめる、自分事になれるような雑誌にしたいと。まあ、実際どうだったかはちょっと……(笑)。やっぱりどうしても編集長のものになってしまいますよね。
酔っ払ったとき、誰かに「岩佐さんはよく話を聞いてくれるけど、最終的には岩佐さんの考えている方に全部もっていきますよね」って言われたこともありました(笑)。たしかに、僕が一晩一人で考えてひっくり返して「ごめん」っていう場面もありましたし……(笑)。
──なるほど(笑)。僕も自分の好きなようにつくらないと気が済まないから、耳が痛いですね。内容面ではどんなことを意識されていましたか?
岩佐 「ハーバード・ビジネス・レビュー」は、アメリカ東海岸ボストンのハーバード・ビジネス・スクールの雑誌です。20 世紀のアメリカ経済を牽引した東海岸を代表するような雑誌で歴史も90年以上あります。それこそ20世紀の東海岸のビジネスパーソンは、スーツにネクタイ姿が当たり前のカルチャーです。でもシリコンバレーが勃興し、IT産業やネット企業がオールドエコノミーにとって変わるようになりました。西海岸にはこれからの経済を引っ張っていく勢いが充満していて、そのカルチャーはTシャツです。このビジネスの知見を培ってきた東海岸とこれからの経済を担う西海岸の台頭。こういう時代に、東海岸発祥の「ハーバード・ビジネス・レビュー」は、東海岸と西海岸をつなぐ雑誌になりたいと思いました。日本で言うと、丸の内と六本木・渋谷を繋ぐ感覚です。既存の大企業には、スタートアップやネット企業の勢いやポテンシャルを伝えたいし、スタートアップには大企業が培ってきた経営論を伝えたい。そんな存在になりたいと思いました。
──読者の反応はどうでしたか?
岩佐 もちろん賛否両論で、軽くなったという人もいました。ただ、大企業の役員などのシニアの読者が多少減っても、30代くらいのベンチャー系・スタートアップ系で働いているタイプの読者層を増やしたいという思いがあったので、そうした新進の企業を取り上げたことで喜んでくれた読者の反響がある一方で、「なんでこんなやつを載せるんだ」というクレームももらったことがありました。
たとえば「ハイクオリティの経済誌で経済界の重鎮が登場してきた中でホリエモンが出てくるのはアリなのか?」という議論もあったし、コーポレートガバナンスの特集で糸井重里さんに出ていただくときには「糸井重里さんは資本市場の専門家なの?」という議論もありました。当時のバックナンバーを見ると、それが顕著に現れていると思います。
そういった方針転換のなかでも、特にビジネスの大きさよりも、ゼロからイチを生み出す価値の発掘を中心に置くようになりましたね。たとえば今は1000億のビジネスを1100億円に伸ばすよりも、ゼロから5億円のビジネスをつくるということのほうがすごいじゃないですか。僕自身、そういう「新たに生む」ことに大きな価値を感じるようになりました。
それにともなって、アメリカ本社の翻訳記事の割合を少なくして、オリジナル記事を増やすということもしました。海外の記事の方がいいというオーソドックスな考え方もあるんですが、世界最先端の記事と日本の新進気鋭の企業の話を混ぜたり。日本企業の中にもグローバルで見ても価値ある企業もあると思っていたし、読者には文化や規模の違いを言い訳にしないで読んでもらいたいと思いました。
──5年間の中で「これは手ごたえがあった」という号を具体的に挙げるとしたら、どの号になりますか。
岩佐 三つ挙げるとすれば、一つは人工知能を特集した号ですね。これは2015年11月号という比較的早い時期に出したんですが、工学者の松尾豊先生や安宅和人さんに出ていただきました。
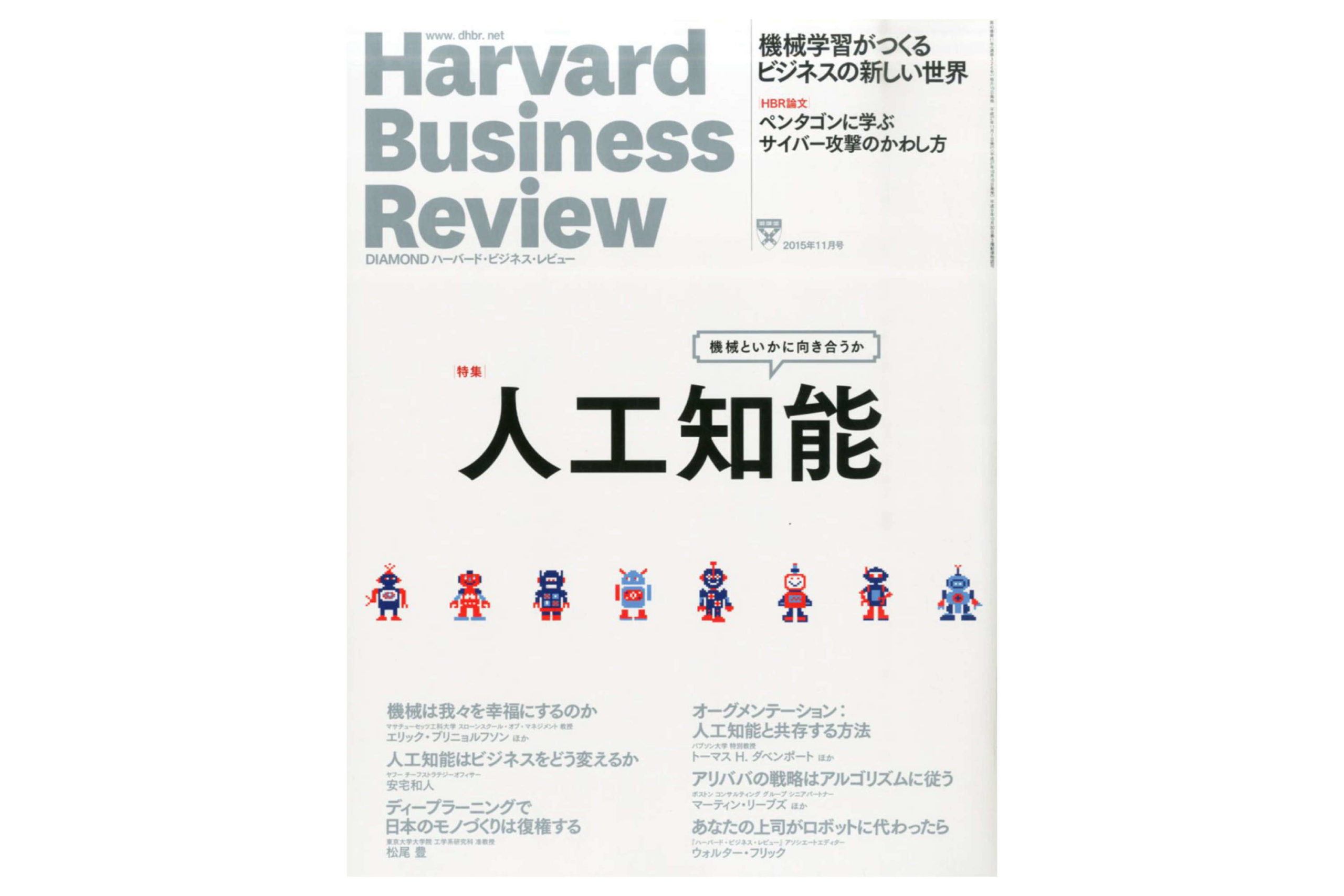
▲DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2015年 11月号
僕はあの号をつくったことで、人工知能が人の仕事を奪うという脅威論はまったく信じなくなりましたね。もちろん僕は技術者でもエンジニアでもありませんが、AIというものが社会にとってどういう存在であるか、その確固たるベースが自分の中でできました。
AIというテクノロジーとビジネスをつなげる話を誰かに書いてもらおうと思ったときに安宅さんが頭に浮かびました。安宅さんも個別には語っていたのですが、AIについて経営に与えるインパクトというテーマで書くのはあれが初めてだったと思います。この号の安宅さんの論考から、日本でのAI議論も方向が変わり、脅威論から活用論にシフトしていきました。その意味では、非常に意義のある号でした。
二つ目に挙げるとすれば、2016年の11月号の40周年記念号ですね。これは「これからの未来をつくる40歳以下の経営者を20人紹介する」という特集でした。

▲DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2016年11月号
それまでの実績ではなく、これからの未来をつくる人を選考基準にしたんですが、様々な経営者に集まってもらって選考委員会をつくったりして、かなり苦労しましたね。それこそ「なんでこんな人載せるんだ」という批判もありつつ、10年経って振り返ったときに、「ハーバード・ビジネス・レビューってすごいね。10年前からこの人たちに注目していたんだ」という号にしよう、と意気込んでつくりました。
三つ目は僕が編集長を担当した最後の号です。辞めるとは言っていなかったんですが、もう僕が強引に特集を決めました。テーマは「知性」です。
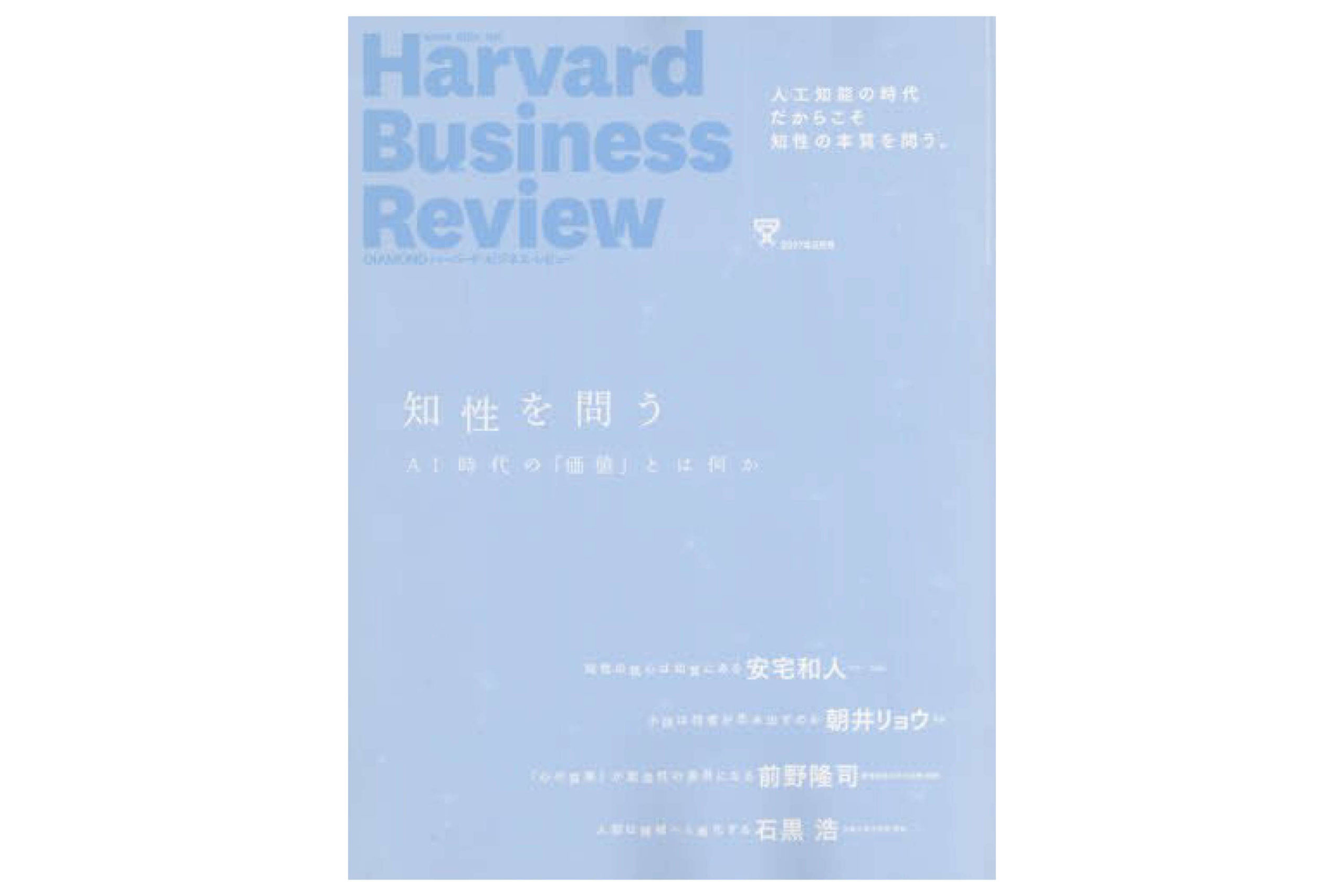
▲DIAMONDハーバードビジネスレビュー 2017年5月号
これは、前の年の暮れに『サピエンス全史』を読んで、人工知能の時代は人間の知性が問われる時代だと直感で感じました。それと人工知能の特集号での安宅さんの論考の中に、「人間の知性の本質は知覚である」ということが書かれていて、これをもっと詳しく紹介したいと思いました。「知性」特集号では安宅さんの他にアンドロイド研究でも知られる石黒浩さん、そして作家の朝井リョウさんへのインタビューを掲載しました。特に安宅さんの知覚の話が、朝井リョウさんが創作で意識されている小説の醍醐味の話と見事に繋がって、自分なりには知性を再定義する特集を組めたと思っています。
「肩書きのない編集者」としての2年間
──そこから編集長を退任されて、退社もされたんですよね。そのあたりはどのような経緯があったんでしょうか。
岩佐 編集長になるときに提示した条件の一つが、3年限定でした。でも3年経っても何もできていなかったので、あと2年で都合5年間で辞める、と会社にも自分にも言いました。そもそも僕、怠惰なんですよ。
──あまりそんなイメージはありませんが……。
岩佐 ダメ人間なんです。宇野さんもよく自分をダメだって言っていますが、僕はもっとダメなんです。だから、終わりを決めると良い仕事ができるというのが一つ。二つ目は、編集長になるといい思いをいっぱいできるじゃないですか。周りからもちやほやされるし、それに慣れるといかん、と思ったんです。三つ目は、これはやってから思ったことですが、すごく学びの多い、いい経験をさせてもらえたので、自分が独占してはいけなくて、人に譲りたいという気持ちはすごく強くなりました。やはり、若い人にこの経験をさせたいと。
──そして、会社まで辞めたんですよね。
岩佐 宇野さんはわかると思うんですが、編集者にとって一番楽しいのって編集長じゃないですか。企業の場合、すごく評価されても、その次のポジションはもう役員なんです。正直、僕には絶対に楽しめないと思っていて。あとは元編集長が残っていても、みんなやりづらいだろうな、と。もう自分の編集者人生を悔いなく全うしようと思って、会社も辞めることにしました。
──わかります。僕の知っている編集者も、出世して管理職をさせられるのがつまらなくて転職して現場に戻ったり、業界を去ってしまった人がいます。岩佐さんの場合、独立を選ばれたわけですが、その後のビジョンのようなものはあったんでしょうか。
岩佐 まったくありませんでした。編集長時代はそれに集中したかったので、次に何やろうかなんて絶対考えたくないと思っていたんですよね。考えたらいくらでも出てくると思ってもいたし、ゼロベースで考えたいとも思って、考えずに辞めました。
僕はもともと若い頃から、フリーランスや自分で事業を立ち上げた人に対して憧れがありました。会社員はコロナだろうが給料が入るわけじゃないですか。休みたいと思ったら休めるわけだし、何も考えなくてもボーナスも入ってくる。だからこそ、自分で本当に稼いでる人たちはすごいな、と。それはカメラマンやイラストレーターさん、ライターさんなどの専門職の人たちを見ていて、20代の頃から思っていたんですよね。自分が組織から離れて、「何もない岩佐」になったらどうなるのかを試してみたかった。
恥ずかしい話ですが、「元ハーバードビジネス編集長の」と言われることはまだまだ多いですね。そういうこと肩書きをくれたダイヤモンド社にはすごく感謝しています。一方で、直に社会と接していると実感することは多々あります。冠がなくなったことで、自分が社会の中で居場所がなくなるという焦りのような感覚は、意外とありませんでした。
──フリーになってからこれまではどんな仕事をされてきたんでしょうか?
岩佐 1年目はラオスとベトナムに行きました。サラリーマンを辞めたということはどこに住んでもいいんだ、ということに気づいて、これまで憧れていた「海外に住む」を実践しようと思ったんです。同時に、英治出版からフェローという肩書きで会社に関わってくれないか、というお話をいただきました。ソニーコンピュータサイエンス研究所がちょうど30周年を迎えるときに、30周年記念事業のプロデューサーをやってほしい、というお話をいただいたのも、会社を辞めてから1年目でしたね。
2年目は、ある会社の事業構築に関わったり、総合商社のエネルギー事業部の新規事業開発のお仕事をしたり、オウンドメディアをつくるというプロジェクトもいくつかやりましたね。あとは会社の経営者のメンターやアドバイザー的的な仕事を5〜6社くらい。それ以外だと、時々本やコンテンツづくりにも関わっています。
──最近で言えばなんと言っても『シン・ニホン』ですよね。今後フリーランスとして取り組んでいきたいことはありますか?
岩佐 究極的にいうと、自分の頭で考える人を増やしたいと思っています。単に知識を吸収するだけでなく、自分で考えて新しいアイデアを出す人を増やしたい。また、そういう人を生み出す社会をつくりたい。それぞれの人が自ら考えて行動すれば、社会の同調圧力も弱まるだろうし、組織の論理で個人の想いが封印されることもなくなるだろうし、環境問題などのビッグイシューについても多くの知恵が集まると思うんです。そんな方向へシフトする事業を生み出したいと思っています。個人的にはまだまだ自分の領域を広げていきたい。過去の経験でこなせる仕事ではなく、コンセプトをつくったり見えないものを言語化する力を生かして、不慣れだけど自分なりの仮説を立てて取り組む仕事をしていきたいと思っています。
「風の谷」は総合誌であり、運動論である
──徐々に「風の谷」の話もお伺いしていこうと思うんですが、そもそも安宅さんとは、「ハーバード・ビジネス・レビュー」の時にお知り合いになったんでしょうか。
岩佐 はい、そうです。2013年ごろかな。編集部員の一人が安宅さんに会って興奮して帰ってきて「すごく面白い人がいる。岩佐さん、早く会ったほうがいい」と言われて。以前から名前は伺っていたんですが会う機会もなかったので、そこまで言うならと思って、なにかにかこつけて安宅さんに会いに行ったんです。
もちろん『イシューからはじめよ』は読んでいましたが、実際に会ったらあの明るさに魅了されました。質問したことにもロジックとご自身の見立てで明確に答えられる。とにかく一回一緒に仕事したいと思い、その場で原稿をお願いしました。そうしたらその仕事がやっぱり超マニアックに取り組んでくれて、「安宅さん、こういう仕事をするのか!」と衝撃を受けました。
それ以来、僕にとっては特別な人の一人には間違いありません。1回誌面に出てもらった人には、その後2年間は出てもらわないという内規をつくったんですが、安宅さんに関しては僕自身がそれを破って、例外で3回も出てもらったくらい(笑)。会社を辞めた後は編集者と著者という関係よりも広がった関係でお付き合いするようになりました。それで安宅さんが例の鎌倉(コクリ!プロジェクト)から帰ってきた後に、「岩佐さん、風の谷を一緒にやりませんか」と誘ってもらったんです。
──岩佐さんにはこの2年半、「風の谷」がどう見えていましたか。
岩佐 プロジェクトとしての「目指すこと」は明確だけど、実際の目的地やそこにいく道がわからなかったのが、だんだん見えてきたという感じです。人に話すときにも、昔はポカーンとされたけど、今は理解してくれて興味を持ってくれる人が増えた気がします。だからこそ今はたくさんの人が集まってきていますよね。
プロジェクトの進め方として非常にユニークだと思います。最初にビジョンだけある。そのビジョンもきちんと言語化されていないけど、空気のようにあることだけ確認できる状態でスタートしたんです。そこで集まった人は多様で、それぞれの意思で参加していて、参加するからといっても明確な責任や役割が発生するわけではありません。それが、回を重ねることによって、目指すことが言語化されてきて、一人ひとりの責任や役割も、組織的に決まるというより、それぞれの人が自分で定めるかのように決まっていく。プロジェクトチームの境界線も絶えず揺らぎながら決まっていくというスタイルです。
組織としての「風の谷」に関しては決まり事がほぼないに等しいですよね。それぞれの人が役割を外的要因で担うのではなく、自分からつくり出して担っていく。そしてその集合体として、組織としての「風の谷」が機能して動く。
やはり、まったくジャンルの違う人たちが集まってきているのが面白いです。建築をやってる人やコンサルをやってる人もいれば、官僚の方、観光業の方、地方で活躍している人や僕みたいな編集者もいる。それぞれ自分のやってきたことの中で持ち続けてきた問題意識が「風の谷」という場で一つになる。「風の谷」がなければ絶対一緒に議論しなかったであろうことや、一緒に共感することもなかったであろうことに共感できたりする。
──僕は以前から、「風の谷」って総合誌のようだと思っているんです。明確なテーマがあるのだけど、まるで総合誌のように、科学、経済、政治、文化と何から何まで入ってくるじゃないですか。
岩佐 いいこと言いますね! テーマがある総合誌。だからこそ、そこに入っているというだけで、まったく違うキャリアの人と共感できるし、違いが違いのまま生かせるんですよね。
──2年半を振り返って印象的だったことはありますか?
岩佐 ビジョンのすごさをつくづく感じていますね。明確なご褒美はないのに、日々楽しい。2年半走り続けてて、そのスピードが落ちてない。これはやはりビジョンの強さがあってこそだと痛感しています。
チームのあり方が、非常に利他的であり利己的であるところも面白いと思っています。風の谷のビジョンは社会にとって非常に価値のあるものだとメンバーの誰もが信じています。その一方で、誰もが個人の想いとして「面白い」と思っている。社会運動という意味では利他的だけど、風の谷の集まりを通じて、一人ひとりが自分の奥底にある欲望とか情念を具現化するような、一種の利己的な面白さを味わっている。これは世の中のためというものだけを掲げているよりも、はるかにリアリティのある、健全な活動だと思っています。
新型コロナウイルスで中止となった小田原でのイベントで「200の言葉」というのを、ランドスケープデザイナーの熊谷玄さんがつくりましたが、あれはこの2年半の活動を集約したものだと思いました。端的な一つひとつの言葉がそれぞれ10の問いと100の妄想が浮かんできそうな言葉の数々でした。あの言葉はこれまでの2年半の議論から出てきたものですが、僕らはすごい気づきとコンセプトを生み出してきたんだと感慨深かったです。
──これまでの活動の中で言うと、「風の谷憲章」を岩佐さんと僕でまとめたことも、プロジェクトの性格を固める上で、かなり大きな役割を占めていたと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか?
岩佐 そうですね。僕はテクノロジーの実装に対してほとんどパワーを出せないって思っているので、物事の抽象と具象をつないだり、言語化することで貢献したいと思っていました。今思い出してみると、あの憲章を書くのにはそれほど時間がかかってないんですよね。用賀のドトールコーヒーで書いて、2時間もかかっていないかもしれないです。「ただし」という言葉はその前の議論から出ていたな、と思い出して、この言葉を使ったらすごい表現できそうだなと思って、議論の雰囲気を思い出しながら一気に書きあげました。それを宇野さんと一緒にリファインして。結果的に今でも大きく変わっていませんが、書いた当時は、叩き台くらいの気持ちだったし、何よりスラスラ書けました。
──岩佐さんの初稿を見たときに、これまで僕らはかなり手探りでとりとめのない議論をしているつもりだったけれど、実は思った以上にコンセプチュアルな運動になっていたんだな、と思ったんですよ。
最初の頃に憲章をつくってしっかりと議論ができたことは、今の活動にかなり良い方向に働いていると思っています。都市のオルタナティブをつくるんだけど、既存の政治体制や資本主義そのものに対して、ある種の左翼的なカウンターとして否定していくのとは違うんだと。あるいは西海岸的なヒッピーカルチャーの流れを汲んだ自然回帰や、コミュニティ賛美の町おこしみたいなものとは距離を置いていこう、ということですね。憲章をつくる頃は、いくつかのコアになるような議論が固まっていったところだったんですよね。
あと、憲章についていうと、あのそれぞれの条文の末尾に常に「ただし、◯◯でもよい」という留保をかけ続けることで運動としての柔軟性を示す「風の谷話法」を考えられたのが大きかったと思っています。ああいったユーモアを大事にしようという合意があの時点でできたことが、運動のスタンスにいい影響を与えていったと思います。
岩佐 同感です。思い起こせば、ぐちゃぐちゃしていたけど、当時、本質的なことをきちんと議論できていたということですね。その議論の言葉が全部、憲章には入っていて、議論を聞いていてアウトプットのイメージが見えていたからこそ、すぐに書けたんですよね。
今読み返してみても、あの文章から学ぶことはたくさんあります。たとえば、「良いコミュニティじゃなくて良い場所をつくる」という一文だけで、自分がなぜ東京に住んでいるのかを改めて考えるわけです。
あたらしい「社会」関係を築いていくために
──岩佐さんはこの先「風の谷」でどのようなことをやりたいと考えていますか。
岩佐 これまでにない「社会」の様相を実現したいですね。人が集まると社会ができて、文明の発展とともに都市が形成されていった。これは歴史の必然であり、人類が生存と幸福を追求して出来上がってきた一つの形です。ですが、答えはそれだけではないはずです。しかも通信やデータ解析、それからセンサリングの技術がこれだけ発展する世界においては、従来の都市に変わる「人が暮らす社会」が構築されるのは突飛なことではありません。答えは決して奇抜な発想から生まれるものではなく、人の自然な姿の幸福や地球のあるべき姿をプリミティブに問い直すことから、自ずと目指すべき社会像が見えてくると思います。それが今のテクノロジーを使うことで実現可能になる。姿を見せたら、人が奇抜なものとして見られるのではなく、「そういえば、それが自然だよね」という見られ方をする。
特にソーシャルディスタンスが求められる世界にあって、人が心理的に人と近いと思える快適な空間が構築できればと思っています。
──そもそも「風の谷を創る」という運動自体が、ジャンルの垣根を越えて利益も共有してない人が手弁当で集まっていますから、ここが新しい社会や関係性の新しいモデルになっていくということには、すごく説得力がありますね。
岩佐 おっしゃる通り。僕ら「風の谷」のメンバーが共有しているのは、特定の地域社会でもないし、ミッションを持った組織でもない。このビジョンに惹かれた人たちです。多様性とは、一人ひとりの個性を受け入れていくことだと思いますが、ビジョンへの共感があるからこそそれができるんです。みんなが自由に人のことを気にせず、ただ多様であって、それが社会として調和が取れている。こういうモデルは、実は世の中にそんなに多くないんですよね。それはもちろん、血縁や封建的な地域社会といった旧来のものとは違ったプリンシプルで成り立つ社会です。
──今日の話を聞いていて、「風の谷」は僕らがかつて雑誌というものに求めていたものを、どう実空間で実装するかということでもあるのだと思いました。ある時期まで、雑誌とは都市文化であり、都市とは雑誌的なものであったことは間違いない。都市とは要するにばらばらの個人が密集して暮らして、別に一体感は生まれないのだけれどそこで起きたコミュニケーションから生まれたもの、具体的には町並みや文化がその都市の「らしさ」として共有されていくわけです。雑誌は編集者がそれを意図的に仕掛けるもので、一見ばらばらの記事を集めて、その組み合わせで、その雑誌「らしさ」をつくり出そうとする。
ところがいつの間にか僕らが生きている都市は、雑誌的なものではありえなくなってしまっていた。いま都市は、ちょっと油断すると均質化してしまうようになってしまった。自分は文化的で個性的だと思っている人ほど、似たような飲み屋やカフェに似たような服装で現れて似たような話をしている。そしてその背景には実空間と離れたところで、人間の精神を均質化するSNSというムラに人間は強く依存するようになった。つまり、インターネットでは相互監視のネットワークになってしまっていて、その結果、均質化している。この傾向が実空間に侵入して、逆に多様性を重んじる空間や、個人が自由に振る舞える空間がなくなっている気がするんです。
そうして都市的なものを効率化するはずだった消費文化や情報技術が浸透していった結果、皮肉にも都市空間は同質的な価値観別にクラスタリングされて、他者とは出会えない空間へと変質してしまった。つまり「雑誌的」なものではなくなってきているんだと思うんですよね。それをどうリアル空間に取り戻すかというのが、実は編集者にとっての「風の谷」なんじゃないかということに気がつきました。
岩佐 そうですね。結局、雑誌はコンテンツの集まり以前に、世界観の表現じゃないですか。世界観はある種の主観ですよね。今、都市の世界観が崩れているということは、Googleのような、客観的な情報を手に入れやすい手段があるがゆえに、世界観がなくても人と人がつながってしまうことの現れだと思います。そして世界観も均質化している。そういう意味では、いまこそ多様な世界観をどうつくるかを考える時だと思う。
たとえば、世界観のしっかりしている雑誌は、たとえば10人いたら9人は自分には関係ないものなんです。すべての人を満足させようとする雑誌は誰にも刺さらない。その一方で、閉鎖的な空間ではなくて、誰もが覗きにくることもできる入口もある。この半透明な境界があって開かれているので、一定の世界観を維持しながら、特定のイデオロギーを掲げる排他的な空間にならない。こういう世界観が明確にあって、かつオープンなコミュニティを構築できればと思っています。
──安宅さんが「風の谷」は「運動論をつくる運動」だと言っていますが、それは1980年代のエコロジー運動や1990年代のスローフード運動を念頭に置いて言っているんだと思うんです。要するにああいった運動の脆弱さや閉鎖性を乗りこえないといけない、ということだと思います。それって究極的には、この運動論を身に付ければ誰でも「風の谷」を世界中につくれるということじゃないかとも思うんです。実際、憲章にも明記したように「風の谷」の在り方は一つじゃなくていいという話をずっとしてるわけですが、僕らが究極的につくるのは「谷」そのものであると同時に、こうすれば自分たちの「谷」をつくれるという、ある種のメタルールだと思うんです。
岩佐 そのうえ、従来の運動論は解決しようとする課題が明確であるのに対して、僕らがやろうとしている「風の谷」には明確な課題がありません。「こういう世界があればいいね」というビジョン設定型の運動論ですよね。ここも新しいと思うんです。そういう意味では運動論として形が見えてきたら、すごいモデルになるのではないでしょうか。
──最初の2年間は憲章が象徴しているように、コンセプト固めと基礎研究のためのベースづくりの期間だったと思うんですが、このコロナ禍を通じてフェイズも変わっていくように思います。
岩佐 コロナ禍によって、逆に僕らのコンセプトが明確になり具体的なイメージが進んだ部分もあります。安宅さんの妄想から生まれたプロジェクトに、社会の要請が近づいてきた。プロジェクトはますます加速すると思いますし、言語化を超えた「形」はどんどん見えてくると思います。
──そうですね。岩佐さん、今日は貴重なお話ありがとうございました。
[了]
この記事は、宇野常寛が聞き手を、石堂実花が構成をつとめ、2020年7月20日に公開しました。Banner photo by 岡田久輝
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。




