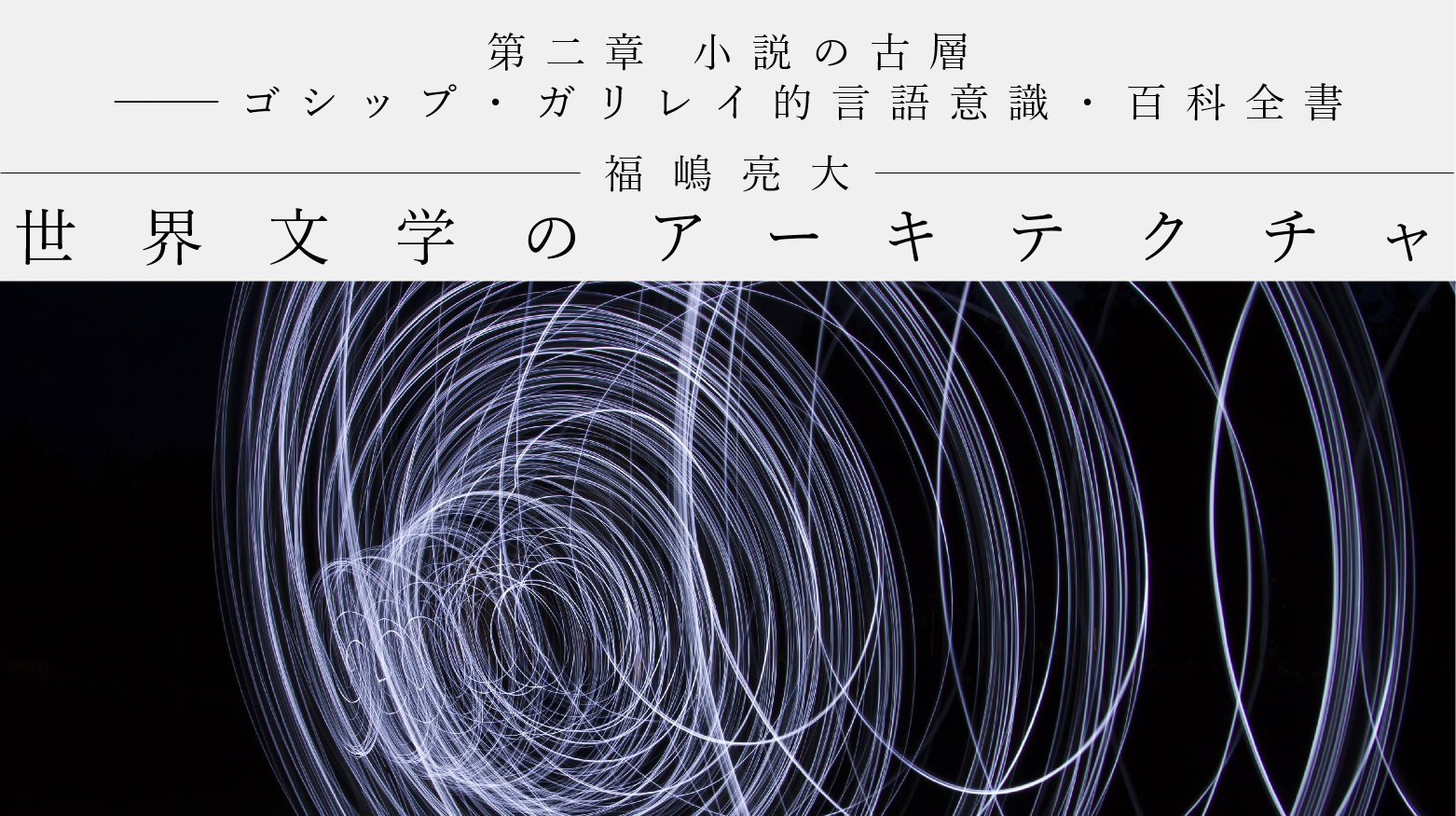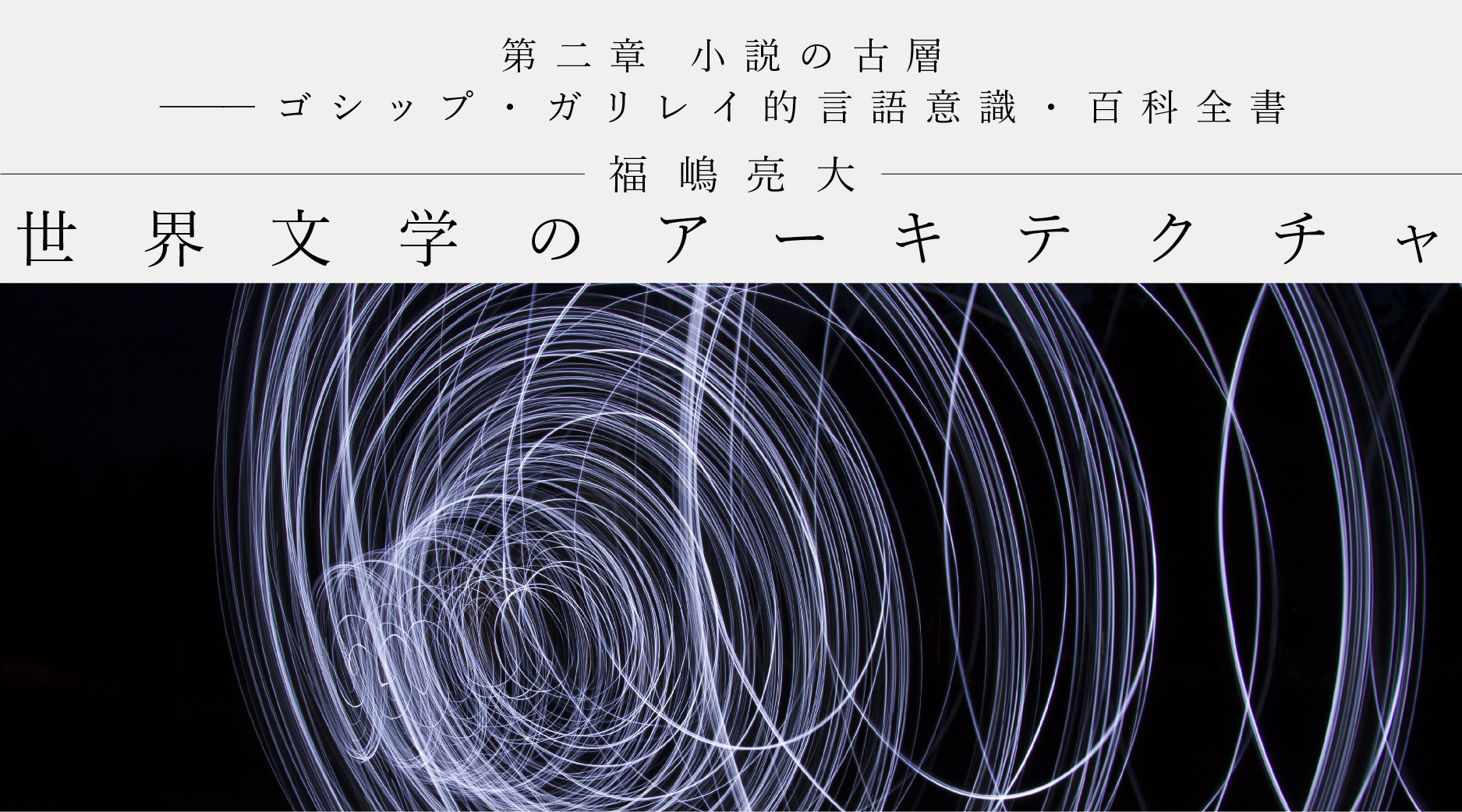批評家・福嶋亮大さんが「世界文学」としての小説とそれを取り巻くコミュニケーション環境を分析していく連載「世界文学のアーキテクチャ」。
小説の「起源」を探るべく、人類が言語以前から持ち続けていたコミュニケーション様式を振り返りつつ、言語と小説の進化史について考察します。
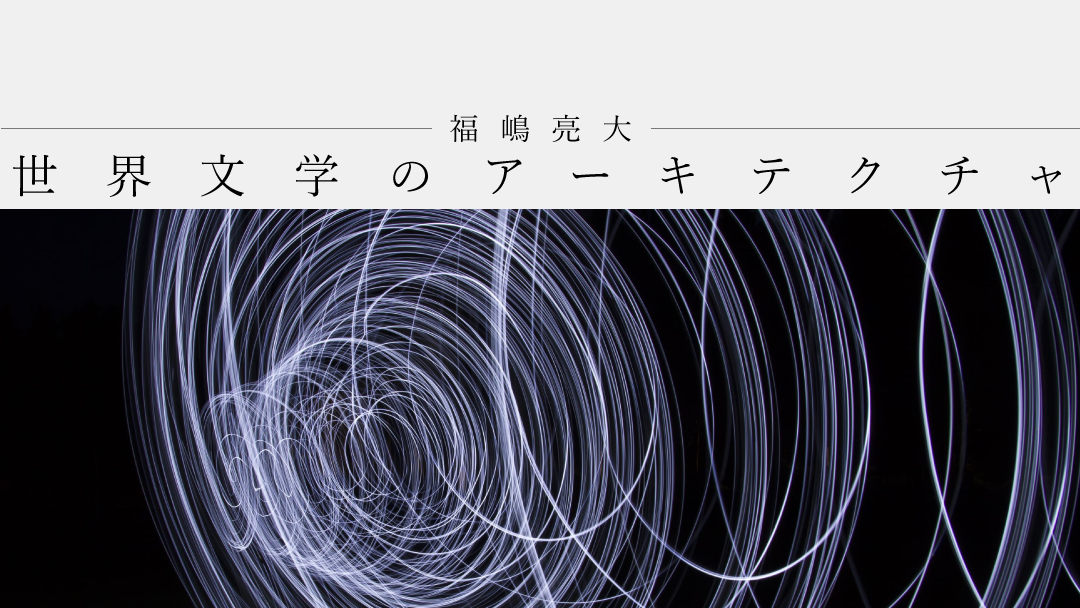
「遅いインターネット」はPLANETS CLUBの皆様のご支援によって、閲覧数を一切気にせず、いま本当に必要なこと、面白いと思えることを記事にすることができています。PLANETS CLUBでは、宇野常寛が直接指導する「宇野ゼミ」、月イチ開催の読書会など、たくさんの学びの場を用意しています。記事を読んでおもしろいと思ったらぜひ入会してみてください。(詳細はこちらのバナーをクリック↓)
端的に言うとね。
1、ゴシップの人類学的意味
小説の起源をいつ、どこに求めるかは難題である。ただ、人類史的な視点から言えば、ストーリーを語ろうとするコミュニケーションの意欲が人類に備わっていることが、あらゆる小説の必要条件であることは確かに思える。もし人間が「語る動物」でなければ、小説が生まれることもなかっただろう。
その一方、語る動物であるからといって必ず小説を生み出すわけでもない。どんな共同体にも物語はあるが、それが小説という形態をとるようになったのは、比較的最近の現象にすぎない。小説とは語りのコミュニケーションの大海に浮かぶ島嶼のようなものであり、ゆえに≪世界文学≫の進化を考えるには、まずは語りの条件を明らかにする必要がある。この点については、文学研究の外部に手がかりを求めるのがよい。
例えば、人類学者のロビン・ダンバーは、人間の言語的なコミュニケーションを猿の毛づくろいと類比している。霊長類の社会は多くの時間を毛づくろいに費やすことによって、集団的な結束や帰属感を高めてきた。しかし、群れが大きくなれば、毛づくろいに費やせる時間は限られ、社会の結合が保てなくなる。ダンバーの考えでは、この限界を突破するためにこそ、言語が必要とされた。対面の毛づくろいにかかる膨大な時間を省略しながら、それでも巨大な群れを維持するために、いわば音声的な毛づくろいとしての言語的コミュニケーション、とりわけゴシップ的な話題が求められた。ダンバーは大胆にも、人間に噂話をさせるためにこそ言語が進化したと結論づける[1]。
実際、ダンバーが言うように、人間の会話は知的・専門的な内容を含んでいたとしても、すぐに卑近な人間関係の話題へと転じてしまう。われわれは既知の人間も見知らぬ人間も遠慮なくゴシップの話題にのせながら、集団の結合を確保し、集団における自らの位置をもたえず確かめている。このような社会生活のあり方はインターネット時代になっても変わらないし、むしろ顕在化している。ネットのユーザーは誰某がこんな悪事を働いたとか、誰某と誰某が決裂したとか、その種のくだらない週刊誌的なゴシップに飢えている。このような性向は、人間の言語がそもそもそのような噂話の交換のために進化したことに基づく。
ゴシップはもっぱら人間の評価に関わるが、より広く言えば、人類はたえず環境の評価(アセスメント)をやるように仕向けられている。例えば、あの果実は食べられるのか、彼とは友人になれそうか、あの部族は敵対的か、明日の天候はどうなるか、狩猟にどれだけの労力が必要か――われわれの先祖はたえずそのような評価を下し、それを仲間に語りながら生存してきた。今日の大衆社会のゴシップは、そのような環境の評価を見ず知らずの他人にまで拡大したものである。
もとより、ゴシップの多くは有名人の評判の低下を狙っている。やっかみや嫉妬によって加速する大衆社会のゴシップは、たいてい下劣であさましい。にもかかわらず、ダンバーが示すように、われわれの噂話は恐らくその根底においては共同生活に資するもの、つまり協力的=利他的なコミュニケーションを促すものである。ひとが噂話に熱中するのは、それによって何らかの利益を他者と分かちあおうとするからである。
霊長類学者のマイケル・トマセロによれば、人間の幼児のやる指さしは、早くも情報のシェアの意欲を示している。幼児は大人たちが指さしに何とか反応しようとすることを知っており、だからこそしきりに対象を指示し、大人とその情報を共有しようとする。言葉を話す前から、手ぶりや身ぶりで外界を指示し、いわば大人を教育しようとする幼児のコミュニケーションは、他の霊長類と比較しても際立った特性を示している[2]。トマセロはこの前言語的なふるまいこそが、言語の進化の基礎にあると考えた。彼によれば、共同体に有益な情報を伝え、他者と「協力」するという「生活形式」(ヴィトゲンシュタイン)に深く依存して、言語は進化したのである。
逆に、言語がもっぱら「競争的」に、つまり他者を攻撃するために用いられるとしたらどうか、と想像してみるのも面白い。トマセロの考えでは、そのとき、言語の形式はわれわれの想像を絶したものになる。
さらに注意を引くのは、もしも協力でなく競争というコンテクストで進化していたなら、人間の「言語」はどんな風になっていただろうか――それを「言語」と呼びたいなら、の話だが――と想像してみることである。この場合、共同注意も共通基盤もないことになるから、指示するための行為を人間のようなやり方では行えなくなる。とくに視点や、その場に存在しない指示対象に関してはまず無理である。お互いに協力的であるという想定の下での伝達意図は存在しないし、それゆえどうしてある人が自分とコミュニケーションをしようとしているのかを一生懸命に見つけようとする理由もない――またコミュニケーションの規範もない。慣習とは人々が協力に基づく理解と関心を共有している場合にしか生じないものだから、慣習もないことになる。[3]
この空想上の「競争的」な言語は、今の言語とは似ても似つかないものになるだろう。トマセロによれば、それはフィクションも生み出せないし、協働の道具にもならない。そこからは慣習も発生せず、他者の意図を読み取ろうとする動機も生じない。この競争的な言語でもコミュニケーションは可能かもしれないが、それは協力的な言語によるコミュニケーションに比べれば、ひどく貧弱なものとなるに違いない。
2、語り――時空の放浪
このように、言語は気まぐれに進化したわけではなく、協力的なコミュニケーションというコンテクストに沿って、あらかじめ進化のレールを敷かれていた。カントが「非社交的社交性」という素晴らしい概念で説明したように、人類は好むと好まざるとにかかわらず、協力的な社会生活を営むように仕向けられている。人間が「社会を求めかつ社会から逃れようとする、その矛盾した傾向」に囚われていることを、カントは見事に示した[4]。われわれが自発的に思いやりをもとうとするそのずっと手前の、われわれが意識できない次元で決まっている「生活形式」が、利他性や社交性の源泉である。ダンバーやトマセロに従うならば、言語もまたこの生活形式の所産ということになるだろう。
だとしても、この「生活形式」はあくまで人類の言語的コミュニケーションの前提であって、その進化の目的地ではない。この形式から、文学はいったいどのような進化を遂げ、いかにして≪世界文学≫というグローバルな流通の場を獲得したのか――これが次の重要なテーマとなる。
それを考えるには、まずすべての文学が「語り」の能力によって規定されていることに注意せねばならない。近年、ダーウィンの進化論を応用した文学論を構想しているブライアン・ボイドは、語りの特性を次のように説明している。
語りは、ほかのいかなる場所ないし時間にも言及しうるものであるために、「今、ここ」から高度に独立した状態を保っている。〔…〕わたしたちは率直な情報を見返りとして求める場合には率直な情報を開示する十分な理由があるけれども、情報を戦略的に開示し、隠蔽し、ゆがめ、あるいは一見真実に見えるストーリーを作り出すことさえする。語りはいつも、少なくとも戦略の痕跡を帯びている。わたしたちは誰の関心を、いつ、どのように引くべきかを判断しなければならないし、受容者の関心を最大化し、受容者の努力や抵抗を最小化しようとする。[5]
語りはさまざまな時間や空間にアクセスし、そこで起こった/起こり得る/起こったかもしれない出来事について、他者を聞き手として評価を下す。われわれの日常会話でも、あれこれ語りあううちに、その話題となっている時や場所はランダムに変化してゆくだろう。「今・ここ」に縛りつけられた身体的な行為(食べること、眠ること、歩くこと……)とは異なり、語ることはいわば時空の放浪を含んでいる。
このような語りの性能は、すでに古代ギリシアの歴史家ヘロドトスにおいてはっきり自覚されていた。彼は『歴史』でエジプトの祭りの起源に関わる荒唐無稽なエピソードを紹介した後「このようなエジプト人の話は、そのようなことが信じられる人はそのまま受け入れればよかろう。本書を通じて私のとっている建前は、それぞれ人の語るところを私の聞いたままに記すことにあるのである」(巻二・一二三/以下『歴史』の引用は松平千秋訳[岩波文庫]に拠る)というきわめて印象深い言葉を書き残している。ヘロドトスにとって、歴史とは、ある出来事を伝える語りを再話すること、つまり《語りの語り》なのであり、それが信用に値するかは二の次であった。
ゆえに、たとえオカルト的な伝承であったとしても、ヘロドトスはその客観性の乏しさを知りながら記録に残した。それは裏返せば、絶対的に信頼できる歴史はないということと等しい。そもそも、ギリシアとペルシアの戦争の始まった原因すら、お互いの「語り」が異なっていることを、ヘロドトスは弁えていた。
むろん、ヘロドトスはたんに「聞く」だけの著述家ではない。『歴史』を読めば、彼が自分の足で精力的に各地を訪れて、噂の真相を探ろうとする一方、その収集が及ばない範囲については伝聞情報をうまく用いていたことが分かる。ヘロドトスは当時屈指のフィールドワーカーであり、かつ他者の「語り」のコレクターでもあった。ヘロドトスの次世代にあたる歴史家トゥキュディデス――ペロポネソス戦争に従軍し、アテナイを襲った悲惨な悪疫についても精細な記録を残した――は、災厄の因果関係を究明し、それを後世の教訓にしようとした。ゆえに、そこではあまりに突飛な話は出てこない。それに対して、ヘロドトスはものごとの因果関係を厳密に見定めるよりは、むしろ真偽も定かではないさまざまな語りのコレクションを築いたのである。
このようなメタナラティヴの性質は、ヘロドトスの記述にどこか気まぐれな性格を与えている。そもそも『歴史』の本来のテーマは、東方のペルシア人の侵略に抗したギリシアの防衛戦争にあったが、ヘロドトスの語りはこの本筋からたびたび脱線する。そこには、アジアを征服したスキュタイ人の習慣についての文化人類学的な記述、エジプトの祭祀をめぐるゴシップ的なエピソード、アゾフ海(現在のウクライナとロシアに接する黒海の内海)の地理の紹介という具合に、驚くほど広域にわたる情報が盛り込まれていた[6]。他者の語りを語るという彼のメタナラティヴは、フィールドワークの限界を突破して、ほとんどユーラシア的な広がりを『歴史』に与えたと言えるだろう。
ブライアン・ボイドが述べたように、語りは「今・ここ」から高度に独立しているため、いつでも無軌道なものに変じる可能性を秘めている。しかし、ヘロドトスのような歴史家はこの語りのアナーキーな性格を逆用して、認識の時空を大胆に広げた。このような戦略的な語り手は、古代の歴史家には限られない。というのも、はるか後、二〇世紀の実験的なモダニスト作家(ジョイス、ウルフ、フォークナー等)や技巧的なメタフィクション作家(ナボコフ、ボルヘス等)も、時空の放浪という語りの性質を最大限に利用していたからである。
3、神話と「世界以前のもの」
繰り返せば、語りは協力的なコンテクストのもとで、環境や人間の評価をシェアするように方向づけられている。ゴシップはその典型的な用法である。しかも、その語られる対象は「今・ここ」からの高度な独立性をもつので、語りのアンテナの発する電波は、死者も含めて、はるかに遠い時空の存在にまで届く。このような性能が、文学の進化の前提条件となったことは間違いない。
ただ、ここで新たな問題が浮上する――それは、このアナーキーな語りだけでは、文学的な生産をやるには不十分だということである。日常会話のなかでは、たいていさまざまな話題がランダムに浮かんでは消えてゆく。環境や他者の評価も頻繁に揺れ動き、しかもそのような会話をしたことそのものがすぐに忘れられる。この不安定な語りから創造性を引き出すには、別の戦略が要求されるだろう。
ブライアン・ボイドも文学の進化論を考える立場から、まさに語りの戦略性を問題にした。彼が試みたのは「盲目的な変異と選択の保持」に基づくダーウィン・マシンの原理を、文化や芸術一般にも当てはめることである。ダーウィン・マシンは「前もって正しい答え」を知っているわけではないが、気まぐれな変異によって「複数の可能性」を生み出し、そのつど環境によるテストを経て、特定の変異体を選択的に「保持」する。「選択的保持なくして、単なるランダム性だけではどんどん強力になる創造性を生み出すことはできない」[7]。
文学もまた、いわばウイルスのように、ランダムな変異(可能性の増大)と選択的保持(可能性の縮減)をたえず実行し続ける一種のダーウィン・マシンになぞらえることができる。そして、文学のランダムな変異を促すのが、語りのもつゴシップ的なうつろいやすさであることも確かだろう。では、文学において「選択的保持」を可能にするものは何か。言い換えれば、語りの気まぐれな変異を抑制し、その評価のコミュニケーションを組織的に定着させる戦略とは何であったのか。
その戦略のうち代表的なものとして、ここでは「神話」を挙げることができる。神話とは、人間の計算や管理を超えた力を伝承する共同体の記憶システムである。繰り返せば、日々の雑談においては、ものごとの評価は安定しない。それに対して、ものごとの由来をその起源から解き明かし、その説明を共同体の成員のあいだでシェアすることを企てる神話においては、評価のランダムな揺らぎは抑制されるだろう。
著名な聖書学者ルドルフ・ブルトマンが述べたように「神話は、超越的な実在に、内在的な、此岸的な客観性を与えるものであるといってもよいだろう。神話は、世界的でないものに、世界的な客観性を与えるのである」[8]。つまり、神話とは世界外の力(=超越的なもの)を世界内の言語(=内在的なもの)に翻訳するシステムである。今の世界ができあがる以前の段階、つまり世界以前のミステリアスな領域に、神話はアクセスしようと試みる。それによって、現在の世界が「世界的でないもの」、つまりこの世界に属さない何ものかに由来することが示されるのだ。
レヴィ゠ストロースも同じように、神話とは「事物がなぜ現在の姿であるか」を説明するものだと述べている。しかも、神話の語る太古の世界は、たんに時期的に古いというわけではなく、そもそも現在とは摂理を異にする時代(例えば、動物と人間の境界がない時代)であるため、過去と現在のあいだには断層がある。神話の役割は、この決定的に「分離」してしまった世界どうしをブリッジすること、レヴィ゠ストロースふうに言えば二つの不連続な世界を調停することにある[9]。
ブルトマンおよびレヴィ゠ストロースを引き継いで言えば、神話が語るのは、この世界が世界以前の何ものかの力に基づくという認識である。神話における太古の世界は、今の世界の摂理には属さず、しかもそれこそが現存する事物の「起源」として位置づけられる。われわれの世界に先立ち、かつ世界そのものを形作る原初の力に対して、神話は客観的な説明を与えようとした。それは、語りのもつ無軌道な性格を抑制する。つまり、この世界についてのあれやこれやの語り=評価をランダムに増殖させる代わりに、世界以前のもの(世界外のもの)を基準として語り=評価に一定の方向性を与えること――、それが神話の機能であった。
してみると、神話は広義の「教育」を施す装置として了解することができる。古代ギリシアにおいて、神話的=教育的な想像力はホメロスの叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』やヘシオドスの『神統記』のようなきわめて高度な作品として結晶化した。ヘロドトスはおよそ四〇〇年前のホメロスやヘシオドスについて「ギリシア人のために神の系譜をたて、神々の称号を定め、その機能を配分し、神々の姿を描いてみせてくれたのはこの二人なのである」(巻二・五三)と称えている。つまり、それまで大いに混乱していた神の名称や役割を整理し、ものごとの来歴をギリシア人に了解できるようにしたところに、ホメロスやヘシオドスの功績があった。
特に、トロイア戦争を背景として、膨大な神々と英雄を登場させたホメロスについて、メディア論の先駆者であるエリック・ハヴロックは「物語作家であると同時に、部族的なエンサイクロペディアの編集者でもある」と述べている。ホメロスをはじめ詩人たちは、多くの技術的なノウハウをもち、その知識を口承で伝え、共同体のなかに保存する役目を背負っていた。ハヴロックの大胆な説によれば、ホメロスの叙事詩は、文字によるコミュニケーションが優勢になる前の、ギリシア人の記憶と学習のシステム、すなわち「有能な市民がその教養の核心として学ばねばならない倫理学と政治学と歴史学と技術の一種のエンサイクロペディア」として理解できる[10]。
ハヴロックが正しいとしたら、現代人にとってのウィキペディアと同じく、古代ギリシア人はホメロスの叙事詩を、基礎的な教養や知識を学ぶためのアーカイヴとして受容していたことになる。それはホメロスの文体を考える鍵にもなるだろう。例えば、ゲーテの世界文学論の継承者である批評家のエーリッヒ・アウエルバッハはかつて、旧約聖書の登場人物に重層的・神秘的な「背景」があるのに対して、ホメロスの英雄たちには「前景」しかないと批判的に述べたことがある。ホメロスの文体はくまなく均一に照明が当てられており、過去や未来に通じる「奥行き」がなく、ひたすら明白な「現在」の連続に支配されている[11]。ただ、この明朗でフラットな文体は、共同体のエンサイクロペディアとしての役割を果たすのには有効であったに違いない。
4、神話への批判
このように、共同体の教師と言うべき神話は、多くのランダムな事象に満ちた世界を整合的に評価し、それを共有するシステムである。ただ、この評価=教育システムへの疑義も、すでに古代ギリシア人によって提出されていた。ここで重要なのは、とりわけ哲学と小説のなかに神話への批判が含まれていたことである。
ホメロスの叙事詩は確かに、感覚的なものや具体的なものに満たされている。それは世界の「多」なる事物を、まさに百科全書的に整理し網羅しようとする企てであった。それに対して、哲学者のプラトンは、そのような感覚的・具体的なものはハプニングだらけの見かけの世界――それは「生成と消滅」を繰り返すかりそめのものにすぎない――の事象であり、存在の真実は別の世界にあると見なした。それがイデアの世界である。エリック・ハヴロックの考えでは、プラトンの提出したイデア論は、ホメロス流の教育(パイデイア)の弱点を克服し、「抽象的客観」としてのイデアの世界にひとびとを覚醒させることを狙いとしていた[12]。つまり、プラトン的哲学者はホメロス的詩人に代わる新たな教育者であり、イデア論はその教育システムの中枢にあった。
さらに、ホメロス的エンサイクロペディアは、血塗られた暴虐な記録の宝庫でもある。『イリアス』では英雄どうしがお互いにいがみあい、相手の愛人を奪い取り、戦場においては人間のみならず神々ですら容赦なく傷つけられる。ホメロスの作成した神々の詳細なリストは、そのまま暴力や略奪行為のリストでもあった。このいわば満身創痍の叙事詩が、共同体の正しい教師になり得るのか――このような疑念はプラトンの哲学に限らず、ギリシア人の言説にたびたび現れる。
例えば、二世紀のギリシア語作家ルキアノスの小説『メニッポスまたは死霊の教え』は、語り手のメニッポスによる霊界めぐりの顛末を語る小説だが、その動機を語る部分に、ホメロスやヘシオドスの神話についての興味深いコメントがある。
僕は、子供でいた間は、ホメロスやヘシオドスの作品で、半神のみならずまさに神々までが、戦争やいさかい、さらには密通、暴力沙汰、略奪、訴訟、父親の追放、兄弟姉妹との結婚を行なっていると叙述されるのを聴かされると、それはすべて善いことなのだと思い、ひとかたならずそれに心を動かされもした。だが、大人の仲間入りをしてからは、法律では反対に、密通も、いさかいも、略奪もしてはならないといった、詩人たちの話とは逆のことが命じられているのを耳にするようになった。それで僕は大きな懐疑に陥り、自分で自分を落ち着かせることができなくなった。[13]
ここでルキアノスが示すのは、ホメロスの語る神々の乱脈ぶりが、道徳上の混乱を招いていたことである。しかし、ホメロスに一度は心動かされたルキアノスは、神話批判の合唱に加わるよりも、むしろ神々の不徳ぶりをもっと際立たせ、混乱をいっそう助長させることを選ぶ。例えば、彼の代表作『神々の対話』は、ギリシアの神々をどんどん登場させては、その言動を笑いの対象に変えてゆく――例えば、性的に放埓なゼウスはなんと自ら「妊娠」してしまうのだ。要するに、ルキアノスはここで神話を面白おかしいゴシップの集積に変えたのである。
繰り返せば、ホメロスやヘシオドスの神話は、世界の「多」なる事物や技術を正しく評価し、それらを記憶するためのエンサイクロペディアを組織した。ルキアノスの小説も同じく「多」なるものを取り込んではいるが、そこには神を滑稽なジョークに変えるという操作が施されている。ルキアノスの対話はきわめて精彩に富んでいるが、それは自由闊達な――ということは無軌道でもある――「語り」の特性によるところが大きい。小説家ルキアノスはホメロスの神話を脱構築するにあたり、ゴシップ的な語りの力を躊躇なく導入した。その力に乗じて、彼の小説の時空は海の怪物の口中から月世界にまで、大胆に広がっていったのである。
5、バフチンとガリレイ的言語意識
もとより、小説の起源を厳密に定めようとする試みは、たいてい挫折するだろう。それでも、小説の小説性とでも言うべきものが何であり、それがどう歴史的に受け継がれたかを考えることには大いに意味がある。ホメロスをルキアノスが脱構築するプロセスには、すでにこの小説性の萌芽が認められる。
二〇世紀ロシアの文芸理論家ミハイル・バフチンは、まさにこの「小説性」の究明という巨大なテーマに挑戦した。ただし、彼の考える小説性は日常言語と隔絶しているわけではない。彼にとって、文学の言葉とは日常のコミュニケーションと別ではなく、むしろその特性を拡大したものである(この点で、彼は詩的言語の独立性を主張するフォルマリストたちとは袂を分かつ)。ゆえに、バフチンはまず日常会話の特性をつかむところから始める。
次のように言っても過言ではない――人がその日常において最も多く口にするのは、他の人々が語ることがらである、と。すなわち、人はもっぱら他者の言葉や意見・主張・報道を伝え、思いおこし、考量し、論議し、それに憤慨し、あるいは賛成し、異議を唱えたり、またそれを引用したりしているのだ。〔…〕世論やゴシップ、悪評、陰口などにおいて「皆がそう言っている」とか「彼はそう言った」とかいう言葉が占める比重には、測り知れないものがある。
どのような会話も他者の言葉の伝達と解釈に満ちている。会話のいたるところに、様々な〈引用〉――ある人間が語ったことばの、「と言われている」ことあるいは「誰もが言っている」ことの、自分の話し相手の言葉や、以前に語った自分自身の言葉の、新聞の、法令の、文書等々の引用――がなされている。大部分の情報や見解は、普通、直接的な形式で自分自身のそれとして伝えられるのではなく、不特定の一般的な典拠――「聞いたところによれば」「とみられている」「と考えられている」等々――を引き合いに出して伝えられる。[14]
引用と聞くと、われわれは特殊な文化的技法だと思いがちだが、それは誤りである。それどころか、われわれのコミュニケーションのほとんどの部分が、他者の言葉を引き合いに出し、他者をあれこれと評価することで成り立っていることは、日常生活を顧みればすぐに了解されるだろう(私のこの文章も例外ではない)。しかも、この「われわれ」の範囲は決して大人だけではない。幼児のコミュニケーションを観察すれば、彼らが引用の技法――「保育園の先生がさっきこう言ったよ」――を驚くほど巧みに使いこなしていることに気づくだろう。仏典の冒頭に置かれる「如是我聞」(かくのごとく我聞けり)という決まり文句は、コミュニケーションの本質そのものをずばりと言い当てている。
ここで重要なのは、バフチンの小説観が、意外にも前出のロビン・ダンバーやマイケル・トマセロの見解とも符合することである。彼らによれば、言語は他者との協働という、意識以前の「生活形式」において進化してきた。バフチンもまさにこの他者を志向する生活形式から、小説の言葉を再考しようとした。しかも、それは文学のみならず政治的な問題とも無関係ではあり得ない。特に「誰某がこう言った」という情報に基づくゴシップや悪評は、バフチンの生きたソ連社会ではときに生死に直結するような重要性をもっただろう。
われわれの語りは、たえず他者に憑依されながら、前もって決められた軌道もないまま進んでゆく――それを説明するにあたって、面白いことに、バフチンは「プトレマイオス的言語意識」と「ガリレイ的言語意識」を区別した。古代ローマの天文学者プトレマイオスが地球を不動の中心とする天動説を集大成したのに対して、ガリレオ・ガリレイの地動説は逆に地球のほうが動くと見なし、プトレマイオス的な自己中心性を破棄した。バフチンによれば、それと同じことが小説にも言える。「小説とはただひとつの言語の絶対性を拒否したガリレイ的言語意識の表現である」[15]。
ガリレイ的言語意識とは、語りが中心性をもたず、たえず他なるものに変じてゆくことへの自覚を指す。「言語は諸々の志向に全面的に自己を奪われ、貫かれ、隅々までアクセントを付与されている」[16]。散文の語りはいわば惑星的な軌道を描きながら、たえず他者の言葉の軌道と交わり続ける。ゆえに、語れば語るほど、そこからはしばしば中心性が失われ、多くの他者たちの言葉が乗り移ってくることになるだろう。バフチンはこの他者たちに憑依された言葉を「オーケストラ」のように操縦することを、小説の仕事と見なした。
6、ルキアノスに始まる小説史
小説の語りは惑星のように、他なるもののあいだを移動し続ける――このような文学的地動説を基礎として、バフチンは小説の「前史」についての研究に取り組んだ。その際に、彼が重視したのが、ルキアノスの対話体小説やそれと類似するメニッペアン・サタイア(メニッポス的諷刺)というカテゴリーである。
先述したように、ルキアノスは自らの小説(『メニッポスまたは死霊の教え』や『イカロメニッポス』)にたびたびメニッポスを登場させた。メニッポス本人の作品はすでに散逸して残っていないため、彼がルキアノスにどの程度の影響を及ぼしたのかは分からないが、いずれにせよルキアノスにとって、メニッポスの小説が重要な先例になったことは確かである。ペトロニウスの『サテュルコン』も含めて、バフチンはこれらの古代の滑稽な「笑い」の文学を、ヨーロッパ小説の古層と見なした[17]。これはきわめて重要な見解である。
実際、ルキアノスふうの諷刺文学の系譜は、その後のヨーロッパの文芸の生みの親となった。ルキアノスをラテン語に翻訳し再生させたのは、ルネッサンス期のユマニスム(人文主義)――ギリシア・ローマの文献研究をもとにするキリスト教の再構築運動――を代表するエラスムスとトマス・モアである。ルターの宗教改革に先駆ける彼らの仕事は、キリスト教神学のみならず古典小説の再興にも大いに貢献した。エラスムスの『痴愚神礼賛』や『対話集』にせよ、モアの『ユートピア』にせよ、それらの諷刺の技術はルキアノスの直系である。エラスムスは空理空論にふける神学者のくだらなさをゴシップ的に描き、モアは羊を囲い込んで農民を搾取するトポス(場所)を批判して、ユートピア(無場所)のヴィジョンを示した。それらは、ものごとの評価を変え、時空を飛び移る語りの力を存分に発揮したものである。
さらに、エラスムスらの次世代にあたる一六世紀フランス・ルネッサンスの大作家フランソワ・ラブレーも、ルキアノスを高く評価していた。ルキアノスの『本当の話』に倣うようにして、ラブレーは巨人パンタグリュエルの口のなかで、農夫がキャベツを育てるという名場面を描いた[18]。ひたすら食べ、旺盛に語る巨大な口に、ついには語り手自身が棲みついて珍妙なユートピアを築いてしまう――この「語るもの」と「語られるもの」をもつれさせる螺旋状の動きは、語りが語り手自身を吞み込みながら進むさまを、実にユーモラスに示していた。
改めて言えば、バフチンは日常言語の分析から出発しつつ、古代のメニッポスやルキアノスを源流とする小説史を再構成した。この小説史の核には、自己を脱中心化し、他者に憑依するガリレイ的言語意識がある。バフチンはラブレーをはじめスペインのセルバンテスやイギリスのローレンス・スターン、さらに一九世紀のドストエフスキーを高く評価したが、それも彼らがガリレイ的言語意識を踏み台として「カーニヴァル」や「ポリフォニー」のような創造的な表現へと到ったからである。
7、ディドロにおける無限の語り
むろん、以上のようなテーマを「小説」に限定する必要はない――他者の語りを語ったヘロドトスの『歴史』からして、すでにガリレイ的言語意識に導かれていたのは明らかなのだから。それでも、小説が特異なのは、ガリレイ的言語意識のもつ無軌道性や他者志向性がポジティヴなものとして、大規模に利用されたためである。
では、このいささか謎めいたジャンルは、文学の進化にどのような影響をもたらしたのだろうか。そもそも、ガリレイ的言語意識には明確な始まりもないし、内在的な終わりもない。つまり、語りとは他者の言葉を引用し、他者を憑依させながら、その気になれば果てしなく続けられるものである。そのため、小説というジャンルには語りの自己目的化というプログラムが内在しており、何を語るかよりも、語るという行為そのものが作品を支配することも少なくない。このような傾向は、一八世紀のローレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』やフランスの哲学者ディドロの思想小説において露出してくる。
特にディドロの小説はしばしば、二人の登場人物のいつ終わるとも知れない漫才の一部を録音したように思えるときがある(『ラモーの甥』、『運命論者ジャックとその主人』、『これは作り話ではない』等)。二人の言葉はときに浸透しあい、ときに反射しあい、ときに反発しあいながら、二人で一人という撚糸のような語りのパフォーマンスを生み出す。このパフォーマンスは決して直線的には進まない――すなわち、一方の語りが他方の語りを中断させることもあれば[19]、両者の語りが脱線に脱線を重ねて、あらぬ方向へと進んでしまうこともある。何にしても、両者の対話には始まりも終わりもない。それは、無限に続く語りの有限の記録なのである。
そのため、ディドロの小説を読むと、それがより広大な思想の一部を切り取ったものという印象を与える。例えば、『運命論者ジャックとその主人』のような実験的な長編小説でも、その前後にはもっと膨大な語りがあり、本編はあくまで部分的なノートにすぎないのではないかと感じられる。その脱線の多い語りは、的を外し続けることこそを目的にするという、不思議なパラドックスに導かれている。ゆえに、語れば語るほど、多くの「とりちがえ」が発生するのであり、しかもそのことを二人の登場人物自らが自覚している。
ジャック――ねえ、旦那さま、人生というのはとりちがえの連続ですね。恋愛のとりちがえ、友情のとりちがえ、それから政治も、財政も、教会も、司法も、商業も、妻も、夫も、世の中とりちがえだらけです……
主人――おい!もうとりちがえの話は十分だ。だいたい、歴史の事実が問題になっている時に、道徳の話を始めること自体がひどいとりちがえじゃないか。お前の隊長の話はどうなった?[20]
この軽妙な会話からも分かるように、ディドロは自己を脱中心化する「ガリレイ的言語意識」を小説のすみずみにまで浸透させた。この他者への憑依は、彼の一貫した戦略でもある。批評家のジャン・スタロバンスキーが鋭く評したように「ディドロにとって、自分自身の名で語るのがためらわれることは、他者の口から語られる。あたかも、ディドロの中にある最も辛辣な存在が盗まれたかのように」[21]。憑かれたように語るディドロの語り手は、自己をたえず「外」に送り出し、他者に自己を盗ませ続ける――それこそが、ディドロが自己の思想を伝えるやり方なのである。
そのこととちょうどコインの裏表だが、ここで興味深いのは、ディドロが「語りのフレーム」に対する高度な意識も備えていたことである[22]。例えば、彼の代表的な文学論「リチャードソン頌」には、イギリスの作家リチャードソンの長大な書簡体小説『クラリッサ』(一七四八年)の最大の見せ場――ヒロインであるクラリッサの葬儀のシーン――を読んだ友人の反応が記されている。
この友人はぼくの知る限りもっとも感じやすい人間の一人で、しかもリチャードソンの熱狂的賛美者だった。ぼくに勝るとも劣らないほどだ。友人はノートを奪うと、片隅に行って読みはじめた。ぼくは様子をうかがった。まず、涙を流し、まもなく読むのを中断してむせび泣いた。やおら立ちあがると、あてもなくうろつき、絶望した男のような叫びを発した。それから、ハーロー家の人びと全員にこのうえなく厳しい非難を浴びせかけた。
これは実はディドロ自身の反応と推測されているが、彼はそれをわざと友人の話として語ったのである(ここにも自己を他者に盗ませるディドロ的戦略がある)。感じやすいディドロは、作家リチャードソンのキャラクターの幻影にすっかり心を盗まれて、人格ごと作中世界にトリップしてしまう。「ぼくはリチャードソンを読みながら、よくこういったものだ。クラリッサになれるなら命と引き替えてもいい。だが、ラヴレイス[クラリッサを奪おうとする下劣な悪役]になるくらいなら死んだ方がましだ」。
リチャードソンの小説は、冗漫にも思えるこまごまとした部分の連続で成り立っている。しかし、ディドロの考えでは、リチャードソンはその冗漫なディテールから「情念に語らせる」力を発生させ、それを強力な「イリュージョン」に変えた[23]。そして、こまごまとした情念の幻影が延々と続いていくリチャードソンの小説に、有限の「フレーム」を与えるもの――それこそが語りの外にいる観者(beholder)の強烈な感情移入なのである。とめどなく続く『クラリッサ』の語りは、とめどなく流れ続ける読者の涙によって、はじめて輪郭を与えられる。
こうして見ていくと、ディドロが小説を手掛けたのは決してたんなる余興ではなかったことが分かる。彼にとっては、哲学的思索を小説のアナーキーな語り――気まぐれな話題転換を許し(=無軌道性)、いつまでも続けることができ(=未完結性)、「今・ここ」の時空を超え(=超越性)、情念のイリュージョンを発生させるもの(=情動性)――の場に強く感情移入させることそのものが、新しい哲学的実践であった。この実践は、哲学者である「私」と奇矯で道化的な「彼」の語りを撚り合わせた傑作『ラモーの甥』において最も先鋭に示されている。
8、ボッカッチョと語りのコレクション
さて、小説が他者の言葉の集積であり、それゆえに永遠に未完結のものだとしたら、小説そのものがどこか語られた事象の収集というプロジェクトに似てくるのも不思議ではない。もともと、ダランベールとともに『百科全書』の責任編集を務めたディドロは、例外も手加減もなくありとあらゆるものを収集し検討し尽くすことを、エンサイクロペディア(もとは「知識の連鎖」の意)の哲学的な使命としたが[24]、このタブーなき百科全書的網羅性は彼自身の小説にも当てはまるだろう。
しかも、語りの百科全書としての小説は、実はディドロのずっと前からすでに試みられてきた。その最大の成功例の一つとして、一四世紀半ばに出たボッカッチョの『デカメロン』が挙げられる。
よく知られるように、『デカメロン』はペストの蔓延するフィレンツェから避難した男女十名が、十日にわたって百の物語を語り続ける小説である。この百という数字そのものはダンテの『神曲』の構造を踏襲したものだが、フィレンツェの政治家ダンテがあくまで厳格なカトリックであったのに対して、商人出身のボッカッチョはキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の交差点にあり、百の物語を次々とリレーさせながら、公式的な道徳から軽やかに逸脱していく。ちょうどルキアノスの小説が先行するホメロスの神話を脱構築したように、ボッカッチョの『デカメロン』は先行するダンテの『神曲』を脱構築したと言ってもよい。
『デカメロン』ではヨーロッパはもとより、イスラム圏からエジプトに及ぶ広範囲の事件がテーマとなった。ボッカッチョがいかにしてこれらの物語を知り得たかは昔からの難問だが、地中海沿岸に集う商人や十字軍兵士、巡礼者が各地から運んでくる逸話――それは口承のケースもあれば書き物のケースもあった――が、恐らくその素材になったのだろう[25]。一四世紀イタリアの商品経済を背景として、『デカメロン』の語り手たちは時空を遠慮なく飛び越えながら、ときに愉快で、ときに残酷なゴシップを持ち寄る。しかも、柔らかな風が吹き込み、笑いさざめく男女の集うその清浄な庭園の隣には、恐るべきペストの地獄が広がっていたのだ。バフチンはまさにこの『デカメロン』の転調の妙に注目し、次のように記した。
ペストのせいで、人は人生や世界について別の言葉を発する権利、人生や世界に別の角度からアプローチする権利を獲得する。すべての約束事が意味を失うだけでなく、掟という掟は、「神の定めも人間の定めも沈黙してしまっている」のだ。[26]
善悪の規準そのものを壊してしまうペストは、世間の虚飾をはぎ取り、人間と世界について「率直」に語る権利を語り手たちに与える。ボッカッチョはタブーを解除された庭園で、社会の約束事に覆い隠されてきた人間のエネルギーを浮上させた。繰り返せば、語りとは環境を評価し、それを共有する方法である。ボッカッチョはペストという枠のなかで、その評価の仕方を無遠慮で手加減のないものに変えた。バフチンはそれを、人間や世界について「別の言葉を発する権利」という印象深い言葉で呼んだのである。
してみると、ボッカッチョがその後の小説家の規範となったのも不思議ではない。ボッカッチョはノヴェラ(novella)、つまり中心的な題材の周りに組織された物語のパイオニアであり、特にスペインがこのジャンルを早くから輸入した。例えば、『ドン・キホーテ』のセルバンテスも「われらがスペインのボッカッチョ」と賛美されたのである[27]。そもそも、セルバンテス自身、若いときに兵士としてイタリアに渡った経験から、その地の文芸に通じていた。彼のイタリア経験は、『ドン・キホーテ』とも気脈を通じる彼のコミカルな傑作「ガラスの学士」からもうかがい知ることができる。
9、近代小説の源流としてのピカレスク・ロマン
ただ、ボッカッチョは物語の見事なコレクションを構築したとはいえ、それが近代小説に発展するにはさらなるブレイクスルーが必要であった。ボッカッチョの限界を超える文学的革新を最初に達成したのは、やはりスペインの小説であった。
特に一四九九年に出たフェルナンド・デ・ロハスの傑作『セレスティーナ』に続いて、スペインの黄金世紀に書かれた一連のピカレスク・ロマン(悪漢小説)の達成は、小説史において決して見過ごすことのできない重要性をもつ。作者不詳の『ラサリリョ・デ・トルメスの生涯』に始まり、セルバンテスの同時代人であるマテオ・アレマンの『グズマン・デ・アルファラーチェの生涯』、フランシスコ・デ・ケベードの『ブスコンの生涯』等がその代表格として挙げられる。この伝統は『ドン・キホーテ』の母胎にもなった。
近代小説の源流としてのピカレスク・ロマンについては後の章で論じるが、その画期性が一人称の「視点」の発明にあったことはここで述べておきたい[28]。ボッカッチョが十人の登場人物に分担させた語りを、ピカレスク・ロマンは一人の下層の語り手に集約させた。それによって、統一的な視点から多様な社会階層を巡歴し、物語を収集し続けるという、新しいアーカイヴ化の技術が編み出されたのである。バフチンもまた、ピカレスク・ロマンの達成を高く評価した。
近代ヨーロッパ小説のゆりかごを揺らしていたのは悪漢、道化、愚者であって、彼らはその襁褓の中に自分の帽子を玩具と共に残してきたのだ。
彼[ピカレスク・ロマンの主人公]は何に対しても不誠実であり、誰をも裏切る。しかし、まさにそのことによって、彼は自己に対する、自己の反パトス的、懐疑的な志向に対する忠実を守るのである。[29]
小説の進化史を考えるのに、これはきわめて重要な見解である。悪漢、道化、愚者という三つのカテゴリーは、社会環境を率直に評価し、さまざまな語りをタブーなく集めるという態度を小説に定着させた。彼らは「愚かさ」を武器にして、社会的に公認された「知」が見過ごしている下層の世界に臆せず入りこみ、多くの物語に接触する。しかも、ボッカッチョの『デカメロン』と違って、そこではいわばオーケストラの指揮者のような一人称の語り手――世評にではなく自己の欲望に忠誠を誓う語り手――が生成された。バフチンがピカレスク・ロマンを近代小説の起源と見なしたのは、まさにこの多声的な一人称の発明ゆえである。
*
ここまでのポイントをまとめておこう。〈1〉言語の進化の前提には、他者志向的な「生活形式」があり、とりわけ他者についての評価をシェアするゴシップが進化のエンジンとなった。〈2〉この特性に沿って生成された古代の小説は、ルキアノスの作品をはじめとして、神話の脱構築(ゴシップ化)に差し向けられた。〈3〉その一方、語りは「今・ここ」の制限から自由であり、死者も含めた他者に憑依されている。〈4〉この語りのもつ「ガリレイ的言語意識」を起点として、始まりも終わりもない語りの無限性を際立たせたディドロやスターンの小説、気ままに増殖してゆく各地のゴシップをアーカイヴ化したボッカッチョの『デカメロン』、物語のアーカイヴを統合する一人称の語り手を生成した一連のピカレスク・ロマン等が発生することになる。
もとより、ここまで取り上げてきたのは、小説の進化史のほんの一端にすぎないが、言語の「生活形式」に沿うようにして、小説の実験が企てられてきたことは確認できたはずである。神話というジャンルに代わって小説というジャンルが近代社会で優勢を築くなか、言語的なダーウィン・マシンを動かす「変異と選択」のパターンも、いっそう多様なものになった。その反面、ボッカッチョやディドロらが示すように、小説の編み出した語りの力はいつでも逸脱的なものにもなり得る。語りはそのアナーキーさゆえに、社会の価値基準を侵犯する可能性を帯びている。
ここで、かつて森鷗外が一九〇九年のエッセイ「追儺」に記した有名な言葉を思い出すのがよいだろう。
此頃囚われた、放たれたという語が流行するが、一体小説はこういうものをこういう風に書くべきであるというのは、ひどく囚われた思想ではあるまいか。僕は僕の夜の思想を以て、小説というものは何をどんな風に書いても好いものだという断案を下す。[30]
鷗外は「小説というものは何をどんな風に書いても好い」と断言する。これは第三者的な立場から語られた見解ではない。「追儺」と同年に出た『ヰタ・セクスアリス』で発禁処分を受けた鷗外にとって、この「夜の思想」を守り抜くことは何よりも難しく切実な課題であっただろう(なお、この文章が書かれたのは大逆事件の前年でもある)。
と同時に、現代のわれわれが「表現の自由」をいわば一点の曇りもない昼の思想と見なすのと違って、鷗外がそれをむしろあてにならない「夜の思想」として――いわば追儺の豆まきで追い払われる疫鬼のようなものとして――捉えていたことも見逃せない。「小説というものは何をどんな風に書いても好い」という思想には、そもそも破壊的な性格がある。実際、ゴシップがそうであるように、小説も社会規範を侵犯して、その価値を低落させるという暴力性をもつ[31]。鷗外はその危険性をよく理解していた。「ガリレイ的言語意識」に導かれた小説の言葉は「夜の思想」の陰りをいつも伴っている。
[1]ロビン・ダンバー『ことばの起源』(松浦俊輔他訳、青土社、二〇一六年)一一三頁。
[2]マイケル・トマセロ『コミュニケーションの起源を探る』(松井智子+岩田彩志訳、勁草書房、二〇一三年)一〇五頁。
[3]同右、三〇六頁。
[4]ツヴェタン・トドロフ『共同生活』(大谷尚文訳、法政大学出版局、一九九九年)一二頁。
[5]ブライアン・ボイド『ストーリーの起源』(小沢茂訳、国文社、二〇一八年)一五七頁。
[6]ドーヴァー「ホメロス以後のギリシア文学」ロイド゠ジョーンズ編『ギリシア人』(三浦一郎訳、岩波書店、一九八一年)参照。
[7]ボイド前掲書、一一五頁。
[8]ブルトマン『キリストと神話』(山岡喜久男他訳、新教出版社、一九六〇年)一九頁。
[9]クロード・レヴィ゠ストロース『構造・神話・労働』(大橋保夫編、みすず書房、一九七九年)六四頁以下。
[10]エリック・A・ハヴロック『プラトン序説』(村岡晋一訳、新書館、一九九七年)四六、一〇三頁。『ギリシア人の神話と思想』(上村くにこ他訳、国文社、二〇一二年)のジャン゠ピエール・ヴェルナンも同様に、世界の「起源」を明確にしたホメロスやヘシオドスを、神々の系譜の作成者であり、共同体の記憶システムの構築者であると見なしている(一六一頁以下)。
[11]E・アウエルバッハ『ミメーシス』(上巻、篠田一士他訳、ちくま学芸文庫、一九九四年)第一章参照。
[12]ハヴロック前掲書、第一二章参照。
[13]ルキアノス「メニッポスまたは死霊の教え」『偽預言者アレクサンドロス』(内田次信他訳、京都大学学術出版会、二〇一三年)九四頁。
[14]ミハイル・バフチン『小説の言葉』(伊東一郎訳、平凡社ライブラリー、一九九六年)一五三‐四頁。
[15]同右、二〇二頁。ガリレオ・ガリレイ自身、卓越した文学的天分を備えた著述家であったことは、彼の主著『天文対話』の自在な語り口からもうかがえる。
[16]同右、六七頁。
[17]「叙事詩と小説」(杉里直人訳)『ミハイル・バフチン全著作』(第五巻、水声社、二〇〇一年)四九六頁以下。なお、メニッポスやルキアノスの系譜を遡ると、ギリシアの哲学運動の一派であるキュニコス派(ディオゲネスをその祖とする)に行き着く。もともと「犬」という言葉に由来するキュニコス派は、世論を気にする態度を捨てて、言葉以上に実践を重んじつつ、頭陀袋(完全な自足を象徴するもの)や杖を持ち歩く特徴的なファッションに身を包み、自発的に「貧しさ」を選び取った。シニカル(犬儒的)とは元来、ストリートにおける貧困の哲学の特徴であったと言えるだろう。
ここで面白いのは、福音書に記されたイエスの言動がキュニコス派と似ているという学説である。聖書学者のジャン・ドミニク・クロッサンは『イエス――あるユダヤ人貧農の革命的生涯』(太田修司訳、新教出版社、一九九八年)で「おそらくイエスの活動は、貧農によるユダヤ的キュニコス主義のように見えたことであろう」と推測している(一九九頁)。だとすると、キュニコス派を蝶番として、聖書と小説という二つのユニークな伝統を結びつけることも可能かもしれない。
[18]ルキアノスとラブレーのつながりについては、E・アウエルバッハ『ミメーシス』(下巻)三三頁以下参照。
[19]ディドロの語りの特性については、田口卓臣『ディドロ 限界の思考』(風間書房、二〇〇九年)参照。
[20]ドニ・ディドロ『運命論者ジャックとその主人』(白水社、王寺賢太+田口卓臣訳、二〇〇六年)七〇頁。
[21]ジャン・スタロバンスキー「ディドロと他者の言葉」(小関武史訳)『ディドロ著作集』(第四巻、法政大学出版局、二〇一三年)四七八頁。
[22]Jay Caplan, Framed Narratives: Diderot’s Genealogy of the Beholder, University of Minnesota Press, 1985.
[23]以上「リチャードソン頌」(小場瀬卓三+鷲見洋一訳)前掲『ディドロ著作集』五三、五五、五六、六三頁より引用。
[24]「百科全書」(小場瀬卓三訳)『ディドロ著作集』(第二巻、法政大学出版局、一九八〇年)一三八頁以下。ディドロはここで、強い自負心とともに「『百科全書』は哲学者の世紀以外にはありえない企画」だと記している。一八世紀という哲学者の世紀は、『百科全書』や思想小説のような、それまでとは異なる哲学の手法が編み出された時代でもあった。
[25]アンリ・オヴェット『評伝ボッカッチョ』(大久保昭男訳、新評論、一九九四年)二二〇頁以下。
[26]ミハイル・バフチン『フランソワ・ラブレーの』(水声社)三五〇頁。
[27]ジャン・カナヴァジオ『セルバンテス』(円子千代訳、法政大学出版局)三五八頁以下。
[28]Francisco Rico, The Spanish picaresque novel and the point of view, tr. by Charles Davis, Cambridge University Press, 1984.
[29]バフチン『小説の言葉』二六二、二六六頁。
[30]「追儺」『鷗外近代小説集』(第二巻、岩波書店、二〇一二年)一四〇-一頁。表記は現代仮名遣いに改めた。
[31]イギリスのポストモダン作家サルマン・ラシュディの『悪魔の詩』はその一例である。ラシュディが小説の名のもとに遂行したのは、クルアーンというイスラムの聖なるテクスト、つまり「起源のテクスト」をタブーなく書き換えてしまうことであった。この強烈なハッキングのもつ意味については、チュニジア生まれのフェティ・ベンスラマの好著『物騒なフィクション』(西谷修訳、筑摩書房、一九九四年)を参照されたい。
さらに、このような侵犯の性格はあくまで小説の一面にすぎない。D・A・ミラーが『小説と警察』(村山敏勝訳、国文社、一九九六年)で指摘したように、小説は「無法者」のように見えて、実際には「警察」のように機能することも多い。小説が「何をどんな風に書いても好い」のは確かだが、それはいつでも偏見の強化や権威づけに転じるのである。
(続く)
この記事は、PLANETSのメルマガで2023年5月16日に配信した同名連載をリニューアルしたものです。あらためて、2023年6月9日に公開しました。
これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。